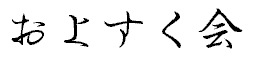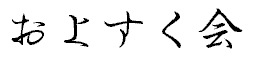
平成19年以前の読書会の報告です
平成19年12月19日 例会報告 浜岡はるみ
末摘花
常陸の宮の姫君 P-19
1)かどある者 ⇒才と角:良い意味と悪い意味 かどかどし⇒(才才し)才気がある、(角角し)気が強い、とげとげしい
2)耳なる ⇒聴きなれる 3)曇りがち ⇒お天気 4)いとひ顔 ⇒嫌う 5)もこそ ⇒そうなっては困る
6)いま⇒そのうち今度 7)御格子参りなむ ⇒御格子を降ろしましょう 8)そそのかす ⇒早くするようにせきたてる(良い事だからと)勧める 9)なかなか ⇒中途半端だ、不十分である 10)け近し⇒(け)は接頭語 11)心にくし ⇒心ひかれる 相手に教養があり、優れていると感じられた時に抱く羨望の気持ちを表し、また動きや状態が明らかでない時、もっと知りたいと特別強い関心を抱く状態をもいう。奥ゆかしい 12)いでや ⇒さあどんなでしょう(曖昧にする言葉)
13)かすかなるありさま ⇒みすぼらしいさま 14)思ひ消えて ⇒心細そうにしおれて 15)心苦しげに ⇒痛々しい、気の毒で 16)際 ⇒身分 17)人の御ほど ⇒身分 18)けしき ⇒意中 19)また契りたまへるかた ⇒別の所に約束した所
20)上 ⇒帝 21)まめ ⇒まじめ 22)もて ⇒接頭語で動詞の意味を強める 23)異人(ことひと) ⇒他の人、別人
24)咎(とが) ⇒欠点 25)あだあだし ⇒誠実でない、浮気である
命婦は才気ある娘です。【琴の音がどんなにか良く響くだろうという夜に貴女様の琴の音が聴きたく参りました。日ごろはあわただしく拝聴出来ず残念なので】と言って姫にお琴を奏でさせたものの、お琴の達人の源氏にじっくり聴かせると、姫のレベルが知られてしまうと考え、口実を言ってお琴を止めさせます。物足りない源氏はもっと姫の様子を知りたがり、【ねたう】くやしがりますが、それを、姫の様子を【かすかなるありさま】【思ひ消えて】【心苦しげに】等の言葉で断ります。しかし心の中では源氏が姫に興味を持ってくれた事を嬉しく、安心します。源氏は、自分も姫も急に親しく仲良くなれる身分ではないと納得し、「これから約束した所に行くので、姫に自分の意中をほのめかせ」と言ってそっと帰ろうとします。後から命婦が、「いつも源氏が真面目すぎて困るとおっしゃる帝があなた様のこの様な、しのび姿をご覧になられたら何とおっしゃるでしょうね」ときつい嫌味を。源氏は負けずに、振り返って、戻って来て笑いながら「浮気っぽいあんたになんか言われたくないよ」と。日頃自分の事を恋多き女、色好める女と源氏に言われている事を恥ずかしいと、黙ってしまう命婦です。
【イメージ】
【乳母子】であり、【わかむどほり】の二人のやり取りが微笑ましく、映画を観ているようです。源氏がこんなに親しく心を開いた女の人はかつてなかったと思います。女と思っていないのでしょうね。命婦の言葉に振り返って、笑いながら戻って来て言い返した源氏の姿がリアルに、若くて、いい男(私の場合特定の)を想像させてくれ、ニコニコしてしまいました。命婦は若い女の子です。黙ってしまった彼女の【はずかし】の心が良く感じられました。
今回は忘年会の時間が迫っていたため時間が短く、しかしその中で倉橋さんの朗読はプロ並でした。素晴らしい!読みの練習をした方が良いと反省しました。
6年目に入る2008年【およすく会】の益々の発展を祈願して2007年最後の報告と致します。
皆様良い年をお迎え下さい。
平成19年11月21日 例会報告 浜岡はるみ
末摘花
夕顔の面影 P-6
1)思へども ⇒元歌「思へども身をし分けねば目に見えぬ心の君にたぐへていでやる」
2)なほ飽かざりし ⇒元歌「あかざりし袖の中にや入りにけむ我が魂(たま)のなき心地する
【目に見えぬ】【魂】⇒夕顔の思い出 3)年月経れど ⇒翌年になっても 4)けしきばむ ⇒気取る 体裁をつくる
5)いどましさ ⇒張り合う 競争 6)ことことし⇒ ものものしい たいした身分がない 7)てしがな ⇒希望
8)ゆゑづく ⇒いわけありげにする 9)くづほれる ⇒衰弱する くづれ落ちする 10)なおなおしき⇒平凡でつまらない
11)ねとし ⇒しゃくである いまいましい
時間を引き戻しましょう。8月に夕顔を亡くした悲しみは年が明けても癒える事無く、季節は既に春になっています。若紫に会うのはもう少し先の事。源氏の心の空洞は埋まらず、夕顔のような可愛く、人なつこく、気兼ねがいらない、親しみやすい女人は周りには皆無で【ここもかしこもうちとけぬ限りのけしきばみ心深きかたの御いどましさ】それでも懲りずに、夕顔の様な女人を求めて隅から隅までアンテナを張って、これと思う女に一行ちょっと気を引く便りを書くと、殆どの女はなびいて来ます。全く当たり前の【目馴れた】事。強情でなびかない、堅物で異性に疎い女もそれを貫ききれず【過ぐしはてず】、強情のままではいれず【くづほれて】平凡でつまらない【なおなおしき】女になってしまって、言い寄るのを止める事も多々ありました。(なんせ源氏ですからね。)あの空蝉を折々に思い出し、いまいましく、しゃくだと思い、軒端の萩には、風の便りを聞いた時など驚かす便りをする事も。あの夜の火影に浮かんだ二人を又見たいと思う。源氏は全ての女達を忘れない人です。
【イメージ】
夕顔の面影を追い求める源氏の前には、気取って、堅苦しく、競争心で溢れたつまらない女しかいない。彼になびかない女は殆どいないのに、夕顔に似た【ことことしきおぼえはなく、らうたげならむ、つつましき】女はいない。もう一度会いたい、話したい渇望と空しい現実が【ここもかしこも・・・】の苛立ちに良く現れています。空蝉と軒端の萩の碁打ちのシーンが私達にも浮かんできました。火影の【乱れ】の文字がイメージをより鮮やかに浮かび上がらせます。歌の様な書き出しで始まるこの巻は、とても解りやすい様に感じたのは気のせいでしょうか?
それとも私の読解力の向上?
大輔の命婦 P-10
1)さしつぎ ⇒すぐ次に位置する者 2)わかむどほり(ばら) ⇒皇室の血筋を引く女性から生まれる事。またその人
3)色好む ⇒恋愛の情趣を解する事であり、情事を求める事ではない 4)かなし ⇒胸が詰るほど情愛を感じる
5)三つの友 ⇒P-13 白氏文集より詩、琴、酒 6)よしづく ⇒風雅のたしなみをもつ、造詣が深い
7)手づかい ⇒上手 8)けしき+ばます ⇒もったいぶった態度 9)のどやか(長閑やか)⇒時間的にゆとりのある
左衛門の乳母という惟光の母に次ぐ源氏の乳母の娘で、大輔の命婦という皇室の血を引く色を好む娘がおり、源氏の召使いとして働いております。その娘が源氏に、故常陸の親王の姫について、ついでの折に話します。父の亡き後心細く残され、隠れるように寂しく暮らしており、琴を心の友としている。と【あわれのことや】琴の名手は琴に反応します。亡き父上が琴の名手であったゆえ娘も当然上手であり風雅への造詣も深かろう。と【われに聞かせよ・・・】困ったのは大輔の命婦。【さやうにきこしめすばかりには・・・改めてわざわざお聞きになる様なものではありません】と否定するも、自分の気を引くために謙虚に言ったと誤解した源氏【いたうけしきばましや・・・勿体つけないで、朧月夜に忍んで行くのでその姫の家に行きなさい】と。命婦は面倒な事になったと思いつつも、春は宮中の行事も少なくのんびりしているので、退屈しのぎに訪ねて行きました。姫とは同じ皇室の血を引く【わかむどほり】として親しい間柄です。が、何故か源氏には姫の事を【心ばへ容貌など深きかたはえ知りはべらず・・・】と申しました。どうして?
【イメージ】
大輔の命婦という、とても面白い娘が登場します。積極的に色を好むため世間が広いと思われます。女探しには最適の人材です。【わかむどほり】の関係からか源氏とも親しく話が出来る娘です。何時もの事ですが源氏は本当に、せっかちな性格です。姫君像がどんどん膨らんで、居ても立ってもいられない。
常陸の宮の姫君P-14
1)しるく ⇒本当に ぴったり言葉通りに 2)十六夜の月 ⇒日没の後ためらう様に出てくる月 3)一声⇒ 姫の琴の音
4)百敷 ⇒宮中 5)ねたかる ⇒しゃく 6)うちつけ ⇒無礼 ぶしつけだ 7)やすらふ ⇒ためらう
言葉通り源氏は十六夜の月の夜に訪ねて来ます。命婦の【いと、かたはらいたきわざかな・・・困ります。琴の
音が澄む様な夜でもありませんのに】と迷惑顔。それに対し、【なほあなたにわたりて・・・そうはいってもやはり来たのだから主人のところに行って姫の琴の音をちょっとだけ聞かせよ。このまま帰るなんてしゃくではないか】
命婦は源氏を客間ではない普通の部屋に案内した事を後ろめたく思いつつ、しぶしぶ姫の居る寝殿へ。姫は格子も降ろさず梅の香を楽しみながらボーっとしています。そこで【御琴の音いかに・・・琴の音がどんなにか良く響くだろうという夜に貴女様の琴の音が聴きたく参りました。日ごろはあわただしく拝聴出来ず残念なので】と。【聞き知る人こそあなれ・・・琴の音を解ってくれる人がいるのですね。宮中に出入りする人に聴かせるほどのものではありません】と言いつつ、姫はまんざらでもない様子で、ほのかに琴を掻き鳴らします。その音は源氏には趣がある様に聴こえ、名手ではないが、不快な聴き難い音ではありませんでした。あの常陸宮が古いしきたりを守りながら、窮屈に、娘を大切に、大切に育てたであろう。が、今や屋敷は荒れ果て娘は一人思い悩んでいるであろう。こんな所に昔物語の様に思いがけない美しい女が住んでいるのだろう。など想像しつつ、言い寄って見たいと思いながら、それにしても突然の訪問は無礼でぶしつけだと恥じて躊躇するのでした。
【イメージ】
お琴のほのかな音を聴いた源氏の中のイメージは今や、貴公子が愛する美しい姫の姿にまで膨らんでいます。命婦の対応の妙が面白い。源氏を迎えた時の対応と姫への対応の比が世慣れた人柄を思わせます。喜劇的です。どんな姫君なのか。先を読むのが楽しみです。
【まとめ】
末摘花の一回目が始まりました。夕顔の死から年を越した次の春です。今までの中で一番読みやすく感じました。軽い書き方に思われました。歌で始まったからでしょうか。夕顔を亡くした悲しみが癒えないうちに他の女を捜す事に抵抗を感じていました。が、解りました。泣けるほど解りました。それ程会いたいのです。もう一度会いたいのです。必死に探しているのです。夕顔を・・・・。
大輔の命婦の人柄が楽しみです。【わかむどほり】の人脈は色々な線で繋がっているのですね。【・・通り商店街】
みたいで覚え易いです。
あと1回で2007年の【およすく会】は終りです。12月の例会後は忘年会です。
来年は4月18~20日の嵯峨野への旅も企画されました。
今年一年間の感動、先生への質問、旅の計画等々盛り上げて楽しい忘年会にいたしましょう。
平成16年9月15日 例会報告 空蝉第2回 沈光子
源氏は小君にわがままを言って、女宮に会うために再び紀伊の守邸へ忍び込んでいます。
紀伊の守が伊予へ赴任した留守に乗じてうまくことを運ぼうとしています。
碁打ち
紀之守邸は主が留守のため、女房たちに中の品らしい隙・気の緩みがある。
源氏が身をひそめた東庇の格子は開けたままになっている。女宮は、昼から訪れている
西の方(紀伊の守の妹・女宮には義理の娘になる)と碁をさしているという。盗み見よう
として、源氏は開け放たれている格子に近づいてく。
格子の際に立てられているはずの屏風も端の方が畳まれており、上の品の家ではありえ
ないことだが、暑いからと身を隠すべき几帳も垂れ上げてあって、源氏の潜んでいる東庇
の格子のところから、奥まで見通せた。明かりが人の近くにともされており、まず寝殿の
中央の中柱の側に、横を向いた恋しい女宮が眼に入った。濃い赤紫の綾の一単衣がさねを
着ているようだ。はっきりはしないけれど何か羽織っており、(彼女は)髪が豊かではな
いのか頭が小さく、小柄でどうということのない容貌をしていた。女宮は差し向かいにい
る義理の娘へも顔を見せない(慎重な慎み深い)振る舞いをしている。痩せた指先がほん
の少し袖口からのぞいていた。
東向きに座った西の方(女宮からは義理の娘になる)はといえば、源氏からは丸見えだ
った。白い薄ものの単衣、淡い藍の小袿のようなものをしどけなく羽織って、紅のはかま
の紐を結んだ際まで胸をはだけるように、無造作に着崩している。色白で美しく、身体つ
きはぴちぴちと丸みがあり、すらりと上背もあって、豊かな髪は長くはないが二つに分け
て顔から肩にかかるのが美しく、総じて容貌に不足ない美しい人に見える。親はこの娘を
世に比類ないと自慢に思っているだろうと興味をそそられる。(この女に)しとやかさを
添えてやりたい、と(源氏は)ふっと思ったりした。この女は才気があって、碁の勝敗へ
きびきびと反応して騒々しい。女宮がしとやかにゆったりと
「お待ちなさいよ、そこはいっしょでしょう。こちらにあなたの勝ち目がありますよ」
などど言っても
「いいえ、今度は負けました。隅のあちこち数えなくては」
と指を折り、
「十、二十、三十、四十」
などど点数を数える様子に、(源氏は)伊予の湯桁の数を数える姿を連想してしまう。
(西の方の父親の赴任先の伊予と、伊予の湯の湯船はたくさんあるのをかけている)
西の方はくったくなくさばさばとして魅力的だが、そうぞうしく優雅さが足りない。
かたちくらべ
女宮はといえば、(西の方とちがって、そこまでしなくたってと思うほど大げさに)
口元をおおって(義理の娘へも)はっきりと顔を見せない。(だが)眼を凝らしてじっ
と見つめていると、しだいに容貌がはっきりしてくる。
眼がはれぼったいようだ、鼻もすっきり筋が通っているというでもない、老けてみ
える。艶やかに美しいところなども見えず、一つ一つ上げてみれば、どちらかと言え
ば醜い方なのに、(上の品の)身だしなみを取り繕って、晴れやかな容貌の西の方より
たしなみがあるので、(容姿は不足でも)誰しも眼が引き付けられてしまうだろう。
p99
(西の方が)若々しく華やかな愛嬌で機嫌よさそうにくつろいで、笑い崩れたりし
ているのも、それはそれで魅力的である。我ながら(西の方にも心が動くのが)軽々
しいとは思うものの、お堅い一方というのではない(源氏の)心は、西の方へも捨て
がたい魅力に思ってしまう。
これまで(上の品の)女たちは、打ち解けて心通わせることがなく、取り繕い、他
人行儀で(そばめーそっぽを向く)あった。このように天真爛漫・素直でくったくな
い女の様子を垣間見ることなど、なかった。盗み見られていると知らない(女たちを)
で、くっきりと見てしまうのは気の毒だ、もっと見ていたいけれど、小君が(のぞき
見しているのをみられるのも恥ずかしいことだ)来るような気がして、源氏はその場
を離れた。
小君の手配で紀伊の守邸へうまく忍び込んだ源氏は、上の品では考えられない偶然が重
なって、碁打ちをしている二人の女を盗み見します。暑い夏とは言え、中の品の紀伊の守
の留守宅は女房たちの用心が緩んでいて、外からの眼を遮る戸や屏風、几帳までがまくり
上げられていました。
髪が豊かでなく、身体は小さく貧弱。鼻筋もすっきりとしたところがなくパッとしない
と、源氏は恋焦がれている女宮の容貌について「ちひさき人の 痩せ痩せにて 鼻なども
あざやかなるところなうねびれて にほはしきところも見えず」「あざやかなるところな
うねぎれて」と 彼女はいがいと老けてるよ、なんて容赦の無い冷静な観察をします。
眼を転じて、碁打ちの相手をしている西の方へも観察の眼を向けます。
ピチピチした姿態、腰紐あたりまで緩めた胸元からのぞく若々しさ。色白で体格がよく、
髪も豊か、くったくのないあっけらかんとした喋り口。才気も感じられ明るい性格に好感
を持つ。少し品がないものの、捨てたもんじゃない。
「つぶつぶと肥えて まみ口いとあざやかに すべていとねじけたるところなく」
「なほ静かなるけをそへばや」(上品な気配を持たせたい)
向かいあって碁を打つ二人の女をかわるがわる観察する描写が生き生きしていますね。
かたちくらべ で恋しい女へのヒイキ目の観察がないのは、源氏が女宮の容姿に魅力を感
じていたのではなく、中の品の後妻という身分でありながも、かつて身につけた上の品の
居ずまいやたしなみ・教養と高貴な精神を持って毅然と生きていることに引かれているか
らでしょう。
それにしても女を観察する眼は冷静かつ鋭い。紫式部は、若々しく華やかな美しい西の
方と、容姿は劣るが上の品の教養を身につけた女宮と、対照的な二人の女に碁打ちをさせ
て、源氏に覗き見させました。二人の女の美しさと欠点は、向き合っている対照的な相手
によって照射されています。欠けているものを向かい合う相手が持っている、というこの
二人の配置は見事ですね。
夜を迎え、女たちが衣擦れの音をさせながら引き上げていくと、 華やかでにぎやかだ
った碁打ちの場面から、寝所のシンとした静けさに展じていきます。
平成16年8月18日 例会報告 空蝉第1回 浜岡はるみ
帚木の巻は突然終わり空蝉になったわけですが、時間は同じなのに何故タイトルが変わるか?
それは、新しい登場人物として、女君の名である空蝉と彼女の義理の娘が登場するからだそうです。
帚木の巻最後の言葉・・・とぞ。が巻の終わりを表わしています。
それぞれの夜
源氏の深い挫折感からスタートです。
【源氏は】寝られないままに、「私はこのように人に憎まれるのに慣れていない(ならはぬ)のに、今夜初めて情けない・つらい(憂しと)男女の中(世)を思い知り、人に合わせる顔がなく(はづかし)死んでしまいたい(ながらふまじくこそ)と思うよ」などと言うと、【小君は、源氏が可愛そうで】涙まで流して横たわっています。源氏はそんな小君を大変いとおしく(いとらうたし)思う。思わずそっと触れた小君の細く小さい手、あまり長くない髪に逢瀬の夜握った女君の華奢な手と少ない髪の手さぐりの感覚が姉に良く似ているのも(さまかよいたるも)、気のせいか(思いなしにや)とまた女君を恋しく思う。女君が嫌がっているのに強引に(あながちに)引っかかって(かかずらう)つきまとって(たどり)寄ったが、体裁が悪く(人わろし)、心の底から(まめやかに)目を覚まさせる程(めざまし)の挫折感で眠れないまますごし、何時ものように(例のようにも)、【小君に】言いつけたりそばに置かず(のたまひまつはさず)、真夜中にひっそりと(夜深う)一人で紀伊の守低を出て行く源氏を小君(この子)はいとおしく、淋しく(そうぞうし)と思うのでした。
拒否される事の無かった今迄の人生の中で始めて経験した挫折感と体裁の悪さに自己嫌悪に陥り真夜中に紀伊の守邸を後にする源氏の苦しさが語られています。今回の話題として
1)ホモセクシュアル
この源氏と小君の関係を男同士の性的な関係に観る読み手(翻訳者)がいるそうです。そういう視点で読むと思わず触
れた手と髪のシーンがそれなんでしょうか。自己嫌悪で深夜に一人で帰って行く男にそんな気持ちはないと思いますし、小
君は源氏にとっては弟のような存在であると思います。またそんな話だったらこんなに長い年月読み続けられては来なかっ
たでしょう。
2)人わろし
周囲の人を気にする事、人に悪く思われる事で大変重要な言葉です。
諏訪さんから、日本は大陸や色々な国から流れて来た人々が作ったいくつもコミュニティーから構成されていた。その組
織を上手く運営するために常に周りを意識した関係作りが必要であったためそれが習慣・文化となったのではないかとい
うお話があり。
3)階級制
源氏が帝の子供で、女君が中の品の女という位置関係でしたら、絶対紀伊の守に妻を差し出すよう命令出来る様に思
います。時代劇の悪代官はたいてい可愛い百姓娘を自分の物にしてしまいます。しかし、平安の男と女の歌を交わし合
う対等な関係にはその様な権力の横行はないようです。深夜にひっそり出て行く源氏の姿は痛々しいです。
4)美人
女君の髪は少ないのですが、これはあまり美人でないという表現だそ
それぞれの夜 その2
女君の心の葛藤
女も言い表せない位(なみなみならず)、源氏ともあろう方を突っぱね大恥をかかせた自分に対して平静ではいられないのに、【源氏】からは何の連絡もぷっつりなくなって(絶えてなし)しまいました。かたはら ⇒ そばにいる人 いたし ⇒ 心苦しい
懲りておしまいになられたのであろうと思う。このまま(やがて)知らん顔して(つれなくて)【恋】が終わって(止みたまい)しまったら【源氏は】さぞかしつらいだろう。ましかば・・・まし ⇒ 反実仮想
かといって強引に(しひて)嫌な(いとほしき)【源氏の】振る舞いが続くのも自分にとってはもっと嫌な(うたて⇒うたた)事だ。適当な時に(よきほどに)終わりに(閉じめ)しよう。 てむ ⇒ 強い意志
とは思うものの(から⇒逆説)心の迷い(ただならず)で、物思いがち(ながめがち)な女君であった。
三度挑戦(みたびちょうせん)
この題は、先生がつけたそうです!
源氏は自分に対してとった女君の振る舞いが不愉快でたまらない(心づきなし)と思いながらもこのまま引き下がる気にならない(かくてはえ/止むまじう御心にかかり)。面目をつぶされ(人わろく)自分が情けなくにっちもさっちも行かない位苦しんで(わびて)、小君に「とても辛く、腹立たしく(うれたう)、【女君を】強いて忘れようと思うけれど(しひて思ひかえせど)心はそうはいかない(心にも従わず)から苦しいんだ。良い時を見て【女君に】会えるよう(対面すべく)どうにかしなさい(たばかれ)。」と【小君に】ずっと言い続ける(のたまい・わたる ⇒わたるはその状態が続く事 【その事は小君にとっては】わづらわしいけれども、こんな恋の橋渡し(かかるかた)でも【自分を】傍に置いて下さる(のたまひまつはす)事は嬉しく思われた。幼いながらどんな時が良いかと待ち続けていた。(待ち・わたる⇒状態が続く)そこへ紀伊の守が国に下り(お供の男たちが大勢いなくなり)、女だけ(女どち)で警護の手が薄く気の緩んだ(のどやかなる)【屋敷へ】
夕闇の道(暗くなって月が出る前)の足元が暗い(たどたどしげなる)頃にまぎれて我が(小君)車にて【屋敷へ】お連れ致します【という小君に源氏は】この子も幼くどうなるのか心配と。でもそのようにのんびり(のどむ)待っていられない気持ちなので、目立たない姿(さりげなき姿)で門限の前(門など点さぬ⇒門に棒を点す)にと急ぎ紀伊の守邸をめざします。
逢魔が時(おうまがどき)⇒日没後月が出るまでの時間で、魔物が出没する時間。香田さんから
またまた来ました紀伊の守邸
人の居ない門(人見ぬかた)から【車を】引き入れて、【源氏を】降ろしました。子供(童⇒元服前の髪型)なので夜勤の番人(宿直人)なども特別念入りに調べ(ことに見入れ)たり、お愛想(追従)する事もせず、心配なく入れました。東の妻戸に【源氏を】立たせ、自分【小君】は南の隅の間から格子を叩いて大声で叫んで(ののしりて)【自分に人の注意を向けさせ源氏が見つからないよう】中に入ります。御達(女御達)が「丸見えですよ(あらわなり)」と言った。「何故こんなに暑いのにこの格子は降ろされているんだ?」と【大人びた口調で女御に】聞くと、「昼から別棟の主人の家族(女君の義理の娘)⇒(西の御方)がおいでになって碁を打っています。」と言う。⇒ 女の客が来ているので格子を降ろしている。
それを聞いて【源氏は】向かいに座っている(ゐ)【女達】を見たいと(ばや⇒希望)思い、するりと(やおら)そして一歩一歩そろりそろりと簾の間に入りました。
歩む ⇒ そろりそろり 一歩一歩
ありく ⇒ あちこち探し歩く
子供だと思って心配していた小君の言動に源氏は逞しさを感じたのではないでしょうか。女達だけののんびりした屋敷の中の様子が目に浮かびます。暑い夏の逢魔が時のお話は、いよいよ面白くなりそうです
平成16年7月21日 例会報告 帚木第十七回 沈光子
源氏は女君に会うために 方たがえを口実にして再び紀伊の守邸を訪れています。
女君のもとへ忍んでいく心づもりの源氏は、従者たちを下がらせて、小君に手紙を持たせたのですが、女君の居所がわかりません。あちこち邸内を探し回って渡殿へまで来てや
っと女君を探しあてました。小君は大好きな源氏を拒んで身を隠した冷たい態度の君があきれるほど情がない人に思え
「こんなことでは源氏の君に頼みがいのない使いと思われてしまうではありませんか」
と泣き出しそうになって言うと
「このような使いをするなんて考えは持つものではありません。まだ子供がこのように恋の取次ぎをするなんていけないことです」
ときつくたしなめられまます。
「気分が悪いので女房たちを側に置いて腰なんかを揉ませていた、と伝えなさい。
おまえがウロウロしていると皆に怪しまれます」
と取り付くひまもなく小君へあたり散らすように言うものの、内心では、このように受領の後妻なんていう世間で言われるような身でなく、親がいた頃の(上の品の入内を志していた高貴な身分の家らしい)風情が残っていた邸内へ源氏を迎えるのなら、たまに訪れてくる源氏をお持ち申し上げるのなら、どんなに素晴らしいだろう。源氏の心を知りなが無視している自分を、源氏はどんなにか身の程しらずで無粋なことに思われるだろうかと、我ながら胸が痛くて、自分で源氏との恋をあきらめようと決めたものの、思い乱れるのでした。いずれにしても宿命に弄ばれて、身もふたもない情緒を解さないつまらない女だと思われて、この恋を封じるのだ、と女君は思い定めたのでした。
箒木の心
源氏は、小君はどのようにして女君へ(手紙を届ける)策を使うだろうか、とまだ幼い小君を頼りなく思いながらも、ただ待つしかなくて、臥していらっしゃったのですが、不首尾だったと報告され、あきれるくらいめったにないほどに源氏を拒む女君の仕打ちに、途方にくれてしまい
「自分が恥ずかしくてならないよ」とおいたわしいご様子でした。言葉もなく苦しげで、女君から拒絶される苦しみから、辛い、とお思いなのでした。
「箒木の心を知らでそのはらの
道にあやなくまどひぬるかな」
遠くからは見えているのに近づくとみえなくなるといわれている 園原に伝わる伝
説の箒木にたとえて、女君への思いを託した手紙を小君に持たせます。今夜の気持ちはどう言っていいかわからないよと。女君もさすがに眠ることもできず
「数ならぬふせ屋におふる名の憂さに
あるにもあらず消ゆる箒木」
と、苦しい胸の内を詠んで返歌します。(ふせ屋は貧しい家と園原とともに箒木が
あるといわれる地名とのかけ言葉・解説参照)
小君は苦しんでいる源氏がいたわしくて、眠れずにフラフラ歩き回るので、源氏付
きの童子が何事かと怪しまれてしまいそうで、困ったもんだと女君は思うのでした。
いつものように従者たちが眠り呆けていますが、源氏ひとり眠れず、これまで経験したことがないほど強い抵抗にあい、恋心を拒み通す彼女への思いが壁のように立ちふさがり、うらめしいと思いながらも、思うようにならない人だからこそ心惹かれているのだとも思い、しかし余りに辛くて、もうどうでもいい(さばれ→さばあれ→どうでもいい)と思ったりも
するのですが、どうにも引くに引けない恋心でした。
「女君が隠れているところへ連れていってくれ」
と小君へ駄々を言えば「むさくるしくごたごたした部屋にこもっていて、それに女房もたくさんいますので恐れ多くて」
と
答えます。小君は源氏があわれでなりません。
「じゃぁもういいよ。小君だけでも私につれなくしないでおくれ」
とおっしゃって、お側近くに寝かせるのでした。若くて美しい源氏のそばにいるのがうれしいと思う小君の方が、冷たく無情な女君よりは可愛いと思うのでした。
源氏の苦しい胸のうちそして逡巡、女君の辛い境遇ゆえの無粋な選択が、流れるような切れ目ない文章で語られていますね。源氏は恋多き男ですが、どの恋にも誠心誠意でぶつかっていくようです。まして箒木は、雨夜の品ださめで聴いて興味をそそられた、中の品の女との初めての恋です。上の品の女とは違って、自己を主張し、個性を持って源氏に立ち向かう恋の舞台で、源氏へ対等な恋の相手として、彼を翻弄しています。源氏は上の品の女との恋では出会わなかった体験に、面食らうことばかりです。
一方、女君は父親が生きていた頃とは比べようもない身分の自分を恥じています。
上の品の女としての教養や美意識を身につけているので、現実の自分の身の程をわきまえているのです。彼女が上の品の生活を知らなければ、あるいは源氏の恋を有頂天になって受け入れたかもしれない。しかし彼女がかつて身に着けた上の品の教養や美意識が、それを許さない。源氏も女君も辛い恋に身も心もさいなまれていきました。
文章が切れ目なくつづくので、古文に弱い者は泣かされますが、幾らか敬語によっ
て主語を読み取れるようになると、この長文が物語の優雅さをかもしていることに気づか
されます。清少納言のような文体では、この優雅さは出ませんよね。
この時代の美意識とうものが物語の奥行きをつくっているように思いました。従者が眠り呆ける場面では、肉体を酷使している身分の者の寝姿へ「いぎたなし」という表現を使っています。これは源氏の美意識であるとともに作者の紫式部の美意識でもあるでしょう。あくびしたり、居眠りしたり、なんてとんでもないことなのでしょうね。現代では総理大臣でさえ国会開催中に居眠りしてますがねぇ。そういうのをテレビ放映するっていうのも「いぎ
たなし」なのでしょう。
源氏と女君との間を行ったりきたりさせて、式部は小君を非常にうまく使っています。
女君が
「かくけしからぬ心ばえは、つかふものかは。幼き人のかかること言ひ伝ふるは、いみじく忌むなるものを」
と当り散らすのも、源氏の使いが弟の小君だからでしょう。そして小君相手に源氏が「よし、あこだに、な捨てそ」
なんて、すねてみせます。女君も源氏も小君にだけは普段に似ず、心のままにすねたり、当たったりしています。小君を登場させたことで、恋の当事者たちは的確に過不足な
く生き生きと描かれたように思えます。小君が源氏からも女君からも、生身の思いを
ぶつけられて、戸惑い恐縮し、そういう時の小君の愛らしさが読者の微笑を誘います。
小君は式部からみても愛らしく賢げな少年なのでしょう。
巷に言われている「源氏物語はレイプ物語」という風聞は、原文を読む限り的外れ
ではないか、という話がでました。原文は、源氏の恋に殉ずる純情と苦悩を描ききっており、女君も意思と個性をもった人間として登場しています。
しかし式部は博識ですね、漢学者の娘ですからと、先生からの補足がありました。
箒木があるという地方の伝説にも通じているんですね。
ということはつまり、読者もそういう知識を共有していけるらしいのが、当時の文字を持
つ人々の教養の深さが偲ばれます。
皆さま、ひっそりと胸に手を当てて越し方を振り返りますと、源氏と女君の苦しい
恋物語は、どこか仕舞い込んでいる失恋の痛手に思い当たりません?
時空を超える式部の人間洞察に脱帽!
平成16年6月16日 例会報告 帚木第十六回 朴文順
にわかの文 後半)
またの日、小君召したれば、(源氏のもとへ)参るとて(姉の)御返り乞ふ(女君が)「かかる御文見るべき人もなしと聞こえよ」とのたまえば、(小君は)うち笑みて、「(源氏が)違ふべくものたまはざりしものを、いかがさは申さむ」と言ふに、(女君は)心やましく(=相手に傷つけられたように思う)、残りなくのたまはせ知らせてけると思ふに、つらきこと限りなし。「いで(さあ、まあ)、およすけたることは言はぬぞよき。さは(だから)、な参りたまひそ」と、むつかられて、「召すには、いかでか」とて参りぬ。紀伊の守、すき心(若い女に目がない感じ)に、この継母のありさまを、あたらしき(もったいない、惜しい)ものに思ひて、追従しありけば、この子をもてかしづきて、率てありく。
源氏の文を渡し、源氏のもとへ参上しなくてはならないので、姉に返事を求めると「このような手紙をみるひとはここにはいない(=人違い)、と源氏に申し上げなさい」と姉が言うので、小君はなに言ってるの、源氏が嘘をおっしゃるわけはないのに、どうやってそう申し上げればいいの、と姉がごまかしているのを無邪気にわらいます。その小君の応えをきいて、女君は源氏は小君にすべてを話してしまったのだと思い、不機嫌に弟にあたってしまう。「そんな大人びたことは言うものではないです。源氏のもとへは参上するな」そう姉に言われても源氏に呼ばれていかないわけにはいきません。一方若い継母に関心を寄せる紀伊の守も機嫌をとってこの小君を連れ歩いたりします。
()で補った言動の主体は動詞の尊敬語の形態でわかります。「参る」は謙譲語なので源氏のもとへ行く、ということ。「聞こえよ」というのは「申し上げなさい」ということだから女君が小君に、「たまはる」は「言う」の尊敬語なので主体は源氏、といった感じです。
あたらし(可惜し)・・・一説にアタラ=当ると同根で、相当する、値打ちがあるものを、と感嘆することから、もったいないという意になったそうです。平安時代にはすでに「新し」と混同していたようです。
使者小君
君(源氏)、(小君を)召し寄せて、「昨日待ち暮らししを、なほあひ思ふ(=恋人に対して使う)まじきなめり」と怨じたまへば、(小君)顔うち赤めてゐ(=座る。じっとしている)たり。(源氏が)「いづら(=どれどれ)」とのたまふに、(小君は)しかしかと申すに、「いふかいな(言う甲斐のない)のことや。あさまし(驚きあきれる)」とて、またも(女君への文を)賜へり。「あこ(吾子。我が子だけでなく、かわいがっている幼いものに対して親愛の情をこめてよぶ)は知らじな。その伊予の翁よりは、先に見し人ぞ。されど、(自分=源氏は)たのもしげなく、頚細しとて、(女君は)ふつつかなる後見まうけて、かくあなづり(=侮り)たまふなめり。さりとも、あこはわが子にてをあれよ。このたのもし人(=伊予の介)は、ゆくさき短かりなむ」とのたまへば、さもやありけむ、いみじかりけることかな、と思へる、(と思っている小君のことを源氏は)をかしとおぼす。この子をまつはしたまひて、内裏にも率て参りなどしたまふ。わが御匣殿(源氏の屋敷、二条院の衣装係)にのたまひて、装束などもせさせ、まことに親めきてあつかひたまふ。
召す、怨じたまふ、のたまふ、賜へりは尊敬語なので主体は源氏。ゐたりは尊敬語ではないので小君、申すは謙譲語なので小君、ということがわかります。と思へる、おかしとおぼす。の部分も「そうかもしれない。大変なことだな」と小君が思っているのを源氏はかわいいと思っている、という構造が敬語の使い分けでわかります。
源氏は返事を待ちわび、しかも不首尾に終わってしまうのですが、またも手紙を書きます。そして小君にちょっとした嘘をついて、完全に小君を味方につけてしまいます。実は自分は伊予の介よりも前に女君と恋人関係になったのに、自分が頼りなげであったので、女君は伊予の介という後見をつくってわたしを馬鹿にしている。それでもおまえは私の子(のように大事な子)でいなさいよ。伊予の介は老い先も短いかもしれない、といって小君のために衣装なども作らせて親のようにかわいがっている。
見る、ということは現在では男女が誰でも殆ど自由に見るわけですが、当時異性を直接見る、会うというのは寝所でしかありえないわけですから、「見る」=恋人の関係になることを指します。
頚細しとは源氏が自分の頼りなさをいうところですが、同時にその容貌が華奢で美しいということにも自信をもっていることがあらわれています。対になる伊予の介のことを「ふつつか」と言っています。ふつつか(=不束)とは現在ではつたないこと、行き届かない、という意味で使われることが多いですが、もともと植物などが太くしっかりした様子、人の形容に使えばごつごつして不恰好なこと、不体裁なこと、風情がないことなどを意味します。束(つか)には「束の間」のように、ちょっと、わずかという意味がありますから、それを否定しているのでこのような意味になるのかと納得。「ふつつか」がもともと外見を指すということははじめて知りました。
御文はつねにあり。されど、この子(=小君)もいと幼し、心よりほかに散り(=落とす)もせば、軽々しき名さへとりそへむ、身のおぼえ(自分が世間からどう思われているか、評価されているか、ということ。=受領の妻)をとつきなか(つりあいがとれない)るべく思へば、めでたきことも(源氏のような人に愛されるということ)わが身からこそと思ひて、うちとけたる御答へも聞こえず。(源氏の)ほのかなりし御けはひありさまは、げになべてにやは(反語。通り一遍では全然ない→素晴らしい)と、思ひいできこえぬにはあらねど、をかしきさま(自分の恋心、ときめき)を見えたてまつりても、何にかはなるべき、など思ひかえすなりけり。君(=源氏)はおぼしおこたる(=考えがゆるむ、粗略になる)時の間もなく、心苦しくも恋しくもおぼしいづ。思へりしけしきなどのいとほしさも、はるけむかたなくおぼしわたる(~しつづける。ずっとしている)。軽々しくはひまぎれ(こっそり隠れて)、(源氏が女君のところへ)立ち寄りたまはむも、人目しげからむ(人目の多い)所に、便なき(=不都合な、けしからぬ)ふるまひやあらはれむと、人(=女)のためもいとほし(=可哀想)くと、おぼしわづらふ。
女君も源氏も思い悩んでいます。思ひいできこえぬにはあらねど、「思い出さないわけではないけれども」と心の逡巡が文章によく表れているように思います。一方源氏は「はるけむかたなくおぼしわた」っている。女君は源氏ほどの人に愛されてうれしくないわけはないのですが、何よりも自分の今の立場、身分を考えると源氏の想いに応えて自分の素直な気持ちを届けることは出来かねます。なんといっても自分は受領の妻。父が生きてた頃は入内も検討されていたほどの上の品の女だったのですが、いまでは夫の伊予の介の後見がなければ生きてはいかれないほどに零落してしまった身分です。最初から中の品の女であればもしかすると源氏の求愛にただ歓喜するだけだったかもしれませんが、上の品のプライドをもったまま、中の品の女として生きなければならない現実に、いやでも源氏との釣り合いのとれないこと(つきなし)が気にかかります。源氏は源氏で、拒絶されればされる程、女君に心を寄せるのですが、中の品の人妻である女君の立場を考えると軽軽しく噂になるようなこともできず思い悩みます。それでもふたりとも一度だけの逢瀬のことが忘れられずにいるようで、このまま二度と会わずに終わるということもなさそうで、今後の展開が気になります。
手引き(P68~)
例の、内裏に日数経たまふころ、さるべきかたの忌み待ちいでたまふ。にはかに(=急に)(左大臣邸に)まかで(退出)たまふまねして、道のほど(=途中)より(紀伊の守邸に)おはしましたり。紀伊の守おどろきて、遣水の面目とかしこまりよろこぶ。小君には、昼より、かくなむ思ひよれる(=考える)と、のたまひ契れり(しめしあわす)。(源氏は小君を)明け暮れまつはし馴らしたまひければ、今宵もまづ召し出でたり。女も、さる御消息ありけるに、おぼしたばかり(=計画をたてる)つらむほどは、浅くしも思ひなされねど、さりとて、うちとけ、人げなき(=ものの数に入らない。一人前ではない。厳格な身分制度のあった時代のことなので、ある一定以上の身分の人間でなければ人の数には入らない、という考え方から)ありさまを見えたてまつりても、あぢきなく、夢のやうにて過ぎにし嘆きをまたや加へむ、と思ひ乱れて、なほ(=やはり)さて待ちつけきこえさせむことのまばゆ(相手があまりに光り輝いているのでこちらがいたたまれなくなる)ければ、小君が出でて去ぬるほどに、「いと(源氏の場所と)けぢかければ、かたはらいたし。なやまし(=気分がわるい)ければ、忍びて(女房などに)うちたたかせ(=腰など揉んでもらう)などせむに、ほど離れてを」とて、渡殿(母屋の外の廊下のようなところ)に、中将といひし(女房)が局したる隠れに(目的の「に」)うつろひぬ(完了の助動詞)。
源氏は女君に会う機会は方違えしかないと思い至り、内裏で方違えの時を待ちます。さてその時がやってきて、左大臣邸に退出すると見せかけて急に紀伊の守邸を訪れると、紀伊の守は源氏が自分の邸内に中川から引き入れた遣水を気に入ってくれたのだと思って喜びます。「紀伊の守おどろきて~」は他の部分とはトーンが異なり、生まれた時から中の品であった紀伊の守の無邪気な喜びようが滑稽であると同時に女君の惑いの切なさが際立つように思われる一文です。小君にはこの訪れを前もって知らせていたのですが、女君もそれを知っており、源氏がこのようにしてまで、自分のところに来てくれる情を考えもしますが、そうはいってもやはり自分は中の品の女、釣り合いのとれない身分で逢瀬を重ねても、夢のようにすごすひとときがおわったあとの現実の世界での嘆きが増すだけだと思い悩みます。そこで小君が出て行った隙に、体調が悪いので、という理由をつくって渡殿にある例の中将の女房の部屋に隠れます。
「夢のやうにて過ぎにし嘆き」というのは現代の私たちでは想像できない、身分社会の悲しさやせつなさなのだと思いますが、身をもってその身分の違いを経験している女君の嘆きはいかばかりか・・・という気がします。源氏との逢瀬は夢のようで、それは現実(中野品の受領の妻)に戻ってしまえば、いっそ知らなかった方が幸せだったほどの嘆きなのでしょう。源氏に夢中になるというのは文字通り夢の中のできごとなのかもしれません。
かたはら(傍ら・側・片端ら)いたし・・・(傍らの人が自分をどう見るだろうかと意識して)気がひける。気恥ずかしい。気が咎める。片腹痛し、とするのは中世以降の当て字で、おかしさの余り片腹が痛い、ばかばかしいという意味にもなったようです。
うつろふは文字通り移る、移動することを表しますが、同時に心の惑いを読み取ってもよいのではないでしょうか。ここが「うつろひけり(中将の部屋に行った)」と物事の事実を単に描写するのではなくて、「うつろひぬ」と完了の助動詞になっていることで、さまざまな想いを抱きながらも、移ってしまった、と読者に女君の心情も考えさせ、「うつろふ」のもうひとつの意味、「心が動く」を連想させて見事だと思いました。
今回古語辞典をなんどかひいてみたのですが、学生時代に辞書を繰るあの辛さは微塵も感じず、とてもたのしく納得できる時間でした。かなで意味がとりづらい場合も、ほとんどの場合漢字が添えてあるので、漢和辞典も同時にひいてみてその意味の多様さに驚きました。「束の間」なんてよく使う言葉ですが、なるほどいわれてみると「束」に「わずか、少し」なんていう意味があるんだなー、とか・・・。源氏を古語で読み始めてから近松や馬琴などの近世文学がわりとすらすら読めるようになったのもこの講義のおかげです。
平成16年5月19日 例会報告 帚木 十五回 沈光子
心のこり
夜明けと共に起き出してきた人々の気配であたりがざわついてきました。迎えに来た中将へ女君を返して戸を閉めたものの、源氏は二度と逢うことがかなわない人への思いで、戸が越えがたい関所(ひこ星に恋はまされぬ天の川 隔つる関に今はやめてよ)のように感じるのでした。
直衣を着て身支度を整えた源氏は、客間の格子(南の高欄)によりかかり、恋の余韻に全身を預けてもの思いにふけります(しばしうちながめたまふ)。
つい立の上からチラッと見える憧れの人を、ワクワクドキドキしながらのぞき見する女房たちは、源氏の魅力が我が身にもしみるように思うのでした。(こういうがさつさは中の品の屋敷らしい雰囲気をよく表していますねぇ。冬ソナのヨン様に群がるファン心理そのものだわ)
月はまだ空にあり、しだいに光を納めていくものの、輪郭はまだくっきり見えていて、中々風情のある曙の景色でした。どうということのない空の様子が、見る人の心によってどのようにでも、激しい衝撃を与えるようにも映ります。
女君は自分との恋に胸を痛めているに違いない。手紙を交わすことさえままならない人へ後ろ髪を引かれながら、源氏は去ったのでした。
したごころ
左大臣邸へ戻っても、すぐには眠ることができません。再び逢うことがかなわず、ましてや女君の立場では、どんなに思い悩んでいることかと思いやる源氏は、苦しく切ないのでした。
女君は美人というのではないけれど、感じがよくてたしなみをわきまえた正に中の品でなければ出会えない人で、経験を豊かに持った左馬頭が雨の晩に言ったことは、本当だったなぁとガテンがいったのでした。
ここしばらくは本宅を気づかって左大臣邸にいる源氏です。でも女君へ音沙汰なし(いとかき絶えて)でいる状態なので、女君の心中が心にかかって苦しくてならず、紀伊の守をお呼びになりました。
P56
「先日逢った中納言の子(女君の弟)を私へ預けてくれないかい。可愛らしげに見えたし、そば近くへ置こうと思うんだ。天上童に私が帝へ推薦して上げよう」
と言うと紀伊の守は
「ありがたいことですが、姉君へ相談してみましょう」
と女君を引き合いに出したので、源氏はドキッと胸が騒いでしまう。
「その方はあなたの(朝臣)の弟を産んでいますか」
「そういうことはありません。この二年ほどまえに後妻として(父に)連れ添っていますが、入内も決まっていたのに(女君の)父親が亡くなって思いがけない身分になってしまい、満足していない(心ゆかぬ)ように訊いています」
「かわいそうなことだね。その姫君は評判の人でしたね。(よろしく聞こえし人ぞかし)ほんとうに美人ですか?」
と訊くと
「それほど悪くないようです。世間でよく言うように生さぬ仲ですので、よそよそしくしていますので」
と答えます。
にわかの文
5日6日すぎて、女君の弟を連れて紀伊の守が参上しました。小柄で育ちのよさがにじみでて優雅、身分ある貴族らしい風采でした。源氏は側近くへ招き入れて、打ちとけて話かけました。
女君の弟は子ども心に、あこがれの人に接して光栄で嬉しそうでした。
源氏は女君のことをくわしく訊くのでした。答えるべきことは答える弟が、下心のある源氏には恥かしくなるほどきちんとしていて慎み深く(はずかしげにしずまりたれば)、女君のことを切り出しにくいのでした。
けれど彼女とのことをじょうずにそれなりに(適当に煙幕をはって)話してきかせました。
弟は子ども心に、そんなことがあったのか、とぼんやり理解するようでしたが、まだ幼くて深い詮索もせず、源氏からの手紙を姉君へ届けに持って来たのでした。(女-恋の相手へはただ女とだけ書かれる)
女君は余りのことに涙を浮かべてしまう。弟が源氏との仲を知ってしまうなんて体裁悪く (はしたなくて)、そうかといって源氏の手紙なので無視することなんて出来ず、顔を隠すように広げました。(女君は横になっている状態)
メンメンとつづられた手紙には
眠ることができないので、夢の中であなたに会うこともできません
眠る夜もなくて と詞書まで添えられていました。
その上、筆跡はすばらしくみとれるほどで、女君はにじんでくる涙で何も見えなくなっていき、宿世に翻弄される我が身を思い、臥してしまいます。
(夢をあう-夢が現実になって再会を果たす 目さえあわでは-瞼が合わさることなくで眠れない)。
心のこり では式部の自然観が現れている と解説がありました。月を描いた景色、自然と登場人物の心理を重ねる描写になっています。
日本文学の常套手段がすでに紫式部によって確立されていたというのは、驚き。自然描写と人間心理が表裏一体というのは、歳を重ねるほど感じ入る普遍性。そこを式部はきっちり押さえて描いている、驚きモモノキです。
源氏が千年の歳月を読み継がれてきた理由は、ここにもあるんですね。
したごころ でみせた源氏のしたたかさには驚かされました。恋にはウブで純情な源氏が、紀伊の守とは、女君への思いを探って、腹の探りあい、丁々発止でした。老練とも言える一七歳の源氏の巧みさです。こういうバランスの悪さというか、恋にはとりわけ純という処が、ファンにはたまらないのね。何もヨン様だけばかりが男じゃないんだってば!
会話体で押していく書き方は、源氏の中ではこの場面だけだそうで、臨場感があふれています。
弟が女君へ手紙をもっていくくだり、女君が臥せっていた に先生が姉上の失恋を思い出し「布団を被って寝ていたのよねぇ」としみじみ言ってました。
「ああいうときは寝るきゃないのよねぇ」には、一同思い当たる節があるようで深くうなづいておりましたなぁ。
源氏は女君との再会を果たすべくどのような策に出るのでしょう。次回が楽しみですね。
有明の月 諏訪淳嗣
何なのだろう。やはり 気になる。 そんな独り言。
P52
-----------------
月は有明にて
光 をさまれるものから かほけざやかにみえて
なかなか をかしき あけぼのなり
ただ 見る人から 艶にもすごくも見ゆるなりけり。
-----------------
この一文を声を出して読んでいて、
その情景・心情が私の心にふっとによみがえってきた。
暗黒の天空に白く輝く満月を見たとき・思い出したとき とは違う。
なかにし礼原作のテレビドラマ「赤い月」のラストシーンの月が
目の前に浮かんだ。あのときに感じたものは何なのだろう。
満州の黄砂によって、赤く輝く月。そして白くフェードアウトして行く月。
白い世界に消えてゆく月だが、はっきりと 月が 見えていた。
この月を 見たときは、
会社で倒れた義父が、付き添いの甲斐なく他界したとき、
病院から出て 出逢ったときの月だ。 静かだった。
悲しくもなく、悔しくもなく、ただ あかるさを感じる天空に
かほけざやかにみえて 見えていていた。
また、思い出した。沈さんと息子さんが……。
そうだ。息子たちが生まれてくるときにも……。
有明の月が ”光 をさまれるものから かほけざやかにみえて”
あの月を私は何を感じて見つめていたのだろう、言葉ではまだ言い表せない。
しいて云えば私には なにもない しずかな世界 だった。
平成16年4月21日 例会報告 帚木 十四回 沈光子さん
口説き上手
高貴な香が鼻をつき、女君を連れている男が源氏だと察した中将ですが、相手が源氏ではどうにもできずに、オロオロついていきます。源氏は障子を閉めて「朝、迎えにいらっしゃい」と言う。
女君は中将に知られたしまったことで、いっそう耐え難く動揺して汗びっしょり、本当に気分が悪そうでした。
源氏はここ一番とばかりに流れるように口説き文句を並べます。あまりに饒舌なので、まあいったいどこからそんな言葉が出てくるのかしらん、なんて作者におちょくられるほどです。(例のいづこより……ことの葉にかあらん)
あはれしらるばかり なさけなさけしくのたまひつくすべかんめれ (女が自分を哀れと思ってくれるように情愛深く聴こえる言葉を囁き続けています)
女君は 数ならぬ身(身分の低い身)の自分だからこのように見下しているんでしょ。心なんかこもっているはずないわ。と突き放します。(おぼしくたける御心ばへのほども……思うたまへざらむ)
低い身分ですけど私は身の丈に合った生き方をしているんですから、ちょっかい出さないでよ。と身もフタもない言い方で、源氏をきっぱり拒みます。(いとかようなる際は、際とこそはべれ とて かくおしたちたまへるを)おしたちは強引という意味です。
女に振られたことがないドンファンの源氏は虚を突かれて冷静さを失っていきます。
つらそうに思い沈んでいる女君(深くなさけなくうしいと思い入りたる)へ気が引けるほどでした。(心はずかしきけはひ)
源氏は必死になって「僕は身分違いなんてこと知らないんだもん。(身分の高い彼にはとうてい想像できない)世間一般の浮気者たちといっしょにして軽蔑しないでよ。(おしなべたるつらに思ひなしたまへるなむ、うたてありける)
世間で言われているような 無理強いして恋をものにするような男なんかじゃないんですから(あながちなる好き心はさらにならはぬを、さるべきにや)と、身分違いを盾にあくまでも拒もうとする女君を口説きつづけます。
「軽蔑するのももっともなことだけど、あなたへの恋心は僕にもどうにもならないほどなんですよ。(げにかくあはめられたてまつるもことわりなる心まどひを、みづからもあやしきまでなむ)なんて、いつもの源氏らしくなく真剣にしどろもどろに言うのです。(まめだちて、よろずにのたまへど)
P43
源氏の真剣なようすに心引かれていく女君は切なく、拒みつづけて強情をはれば無粋な女だと思われてしまうだろうと思うものの、身分違いの相手との恋の先が見えてしまう。源氏の強引なやり方をひどいと思うものの、心ひかれていく自分を抑えられない。身分違いの分を知る自分は、心とは裏腹に源氏につれない態度をするしかない、とばかりに切ない女君です。
源氏には女君の心の揺れがわかり、かといって無理強いはできないし、彼女には気の毒だけど、でもこの女君がいるのを知っていて逢わずにいたら、どんなにか心残りだったろうか、と思います。
p45
頑なな女君へなすすべもなく、なだめる言葉も出ない源氏です。しかし源氏はますます女君に引かれていきます。
「ねえ、そんなに嫌わないでよ。僕たちはきっと思いがけない縁があるんですよ。宿縁なんです。世間知らずのおぼこ娘みたいなダダをこねないでよ。僕だってつらいじゃありませんか」なんて言う。
いつしかドンファンならぬ素直な純情源氏になっていきます。しも という強めの言葉が二度使われていて、源氏の素直な真摯な対応ぶりが強調されています。
「こんな受領の後妻なんかになっていない 情けない身になる前の昔の自分だったら、身分不相応でもまた逢えるとうのぼれることもできるけど、今夜だけのひとときの浮寝でしかないと思うと、アアほんとに哀しいわ。でもしかたないわねOKよ。ねぇ、今夜のことは決して他言しないでね」と女君が折れます。筆者が同情するほどの女君の気持でした。源氏は心を込め慰めの言葉を尽くしたのでした。
夫の面影
一番鶏がなきました。「ああ、寝坊しちゃったよ。車出さなきゃ」なんて起きだした人々の気配がしてきます。紀伊守も「女たちの方違えじゃないんですからこんな暗いのに行かなくてもいいじゃありませんか」と気遣いをみせている様子。
源氏は、こんな偶然で女君に逢うなんてことは二度とない、不可能だよと思う。あの様子じゃわざわざ手紙なんかくれるなんてこともなさそうだし、無理だろうなぁ(さしはへてはいかでか、……いとわりなき)と思うと辛い。
中将も迎えにきて、いったんは女君を帰そうとするけれど、また引き止めてしまう。
「これっきり、これっきり、これっきりですかぁ。手紙も出せないの?(いかでか聞こゆべき)
こんなに苦しい恋心はこれまで経験したことないよ、これはめったにないことですよ」と源氏が泣くのも艶っぽく見えます。(蛇足ですが、エエ男はよく泣くねぇ。たとえば韓国ドラマのヒロイン。心のままに生きてますなぁ)
あわただしく源氏は詠みます。
つれなきを恨みもし果てぬしののめに(東雲がしらんでくる)
とりあえぬまで(鶏と、とりあえずをかけて短い時間をあらわす)おどろかすらむ
p50
女君は自分の身のほどを思うと、気恥ずかしく(いとつきなくまばゆきこころちして)昨夜の激情にかられたひと時の余韻も急速に醒めていく。
いつもはくそまじめで気に入らない(すくすくしく心づきなし)うんざり(思ひあなづる はおもいやられる)の伊予の方を思い出して、ひょっとして夫が私のことを夢にでもみて何かあったんじゃなかなんて気づいたらと思うと身がすくみます。(女君には幼い弟がいるし、それに後ろだてもなく帰る家がないんです。夫はそれを承知で後妻に望んでくれたのよね、爺さんだけどいい人なの。追い出されたら大変)
女君の気持は現実に戻っていますが、返歌をします。
身の憂さをなげくにあかで(たりない)あくる夜は
とり重ねてぞ音もなかれる
(こちらも鶏ととりかさねが 重なってます。鶏も啼いてます、私も泣いてます)
みるみるうちに(ことと)明るくなっていき、源氏はようよう未練をたちきって障子口まで女君を見送ります。女君はといえば、みるみる気持が現実に戻っていくのでした。
先生の解説を参考にしていただいて十分に補足してください。
この日は晴美節も飛び出し、いつもながら経験豊富な生徒にとっても濃密な講義となりました。
源氏は 雨夜の品定め で聴くともなく聴いていた中の品の女への興味に引かれて女君と逢うわけですが、これまでの上の品の女たちからは経験しなかったことづくしでした。身分の高い女は自分という者を顕かにするようなことはしませんが(はしたないのでしょう)、身体ごとぶつかって来るような女君の自我のまえで、源氏はたじたじでした。そして自分も真剣に相手へ全身全霊を傾けていきます。雨夜からの小説的複線がみごとに展開されていきます。
この時代の恋愛を現代の価値観で測るのは無理でしょう。当時の仏教に支えられた無常観・一期一会を大切にする価値観は現代とは比べるべくもなさそうです。それに寿命がいまの半分と思うと、人生の密度が異なるように思います。それに女系の社会システムも大きいでしょう。現代より遥かに大らかで素直な人々の人生観だと思えます。
物語の流れるようなそしてテンポの速さは、そういうことと無縁でないように思えますです。
この時代の女の自我を描くことができるのは、式部もまた強い自我をもって生きた女だったからでしょうね。初々しい源氏はこの恋で初めて経験することが多かったですね。
なにより驚かされたのは、ロマンチストの男心と現実的な女の恋情を描き分けていたことです。これは驚愕に値します。源氏物語が長きに渡って読み継がれてきたのは、この普遍的な人間への洞察ゆえでしょう。歳を経てますます味わいを増す読みができる、常に旬でありつづける源氏物語は、いよいよ恋の遍歴を重ねて佳境へ向かうようですね。
平成16年3月17日 例会報告 帚木第十三回 朴文順さん
しのび込み(P30~)
君(=源氏)はとけ(とく・・うちとける、安心する)ても寝られたまはず、いたづら臥し(=寂しい独り寝)とおぼさるるに、御目さめて、この北の障子のあなた(=あちら、むこう)に人のけはひするを、こなたや、かくいふ人(=昼間話題にした姫君)の隠れたるかたならむ、あはれや、と御心とどめて、やをら起きて立ち聞きたまへば、ありつる(つる=完了の助動詞。先ほどいた)子の声にて、「ものけたまはる(=「もの承る」→「もしもし」)。いづくにおはしますぞ」と、かれたる声(枯れた声。声をひそめている様子)のをかしき(=かわいらしい)にて言へば、「ここにぞ臥したる。客人(=源氏)は寝たまひぬるか。いかに近からむ(推量の助動詞)と思ひつる(助動詞:完了)を、されどけどほ(けどほし=遠い)かりけり」と言ふ。寝たりける声のしどけなき(くつろいだ、うちとけた感じ)、いとよく似かよひたれば、いもうと(男からみた女きょうだい。この場合は「姉」)と聞きたまひつ。「廂にぞ大殿籠りぬる。音に聞きつる(噂にきいた、評判どおりの)御ありさまを見たてまつりつる(助動詞:完了「さっき見た」)、げにこそ(=本当に)めでたかりけれ。」とみそか(=ひそかに、声をひそめて)に言ふ。「昼ならましかば、のぞきて見たてまつりてまし(「~ましかば~まし」「もし~だったら~したかったのに(できなかった)」仮想の副詞)」と、ねぶたげ(=眠そうに)に言ひて、(夜具に)顔ひき入れつる声す。(源氏は)ねたう(ねたし。「くやしい、癪だ」)、心とどめても問ひ聞けかし(もっとちゃんと自分のことを聞いてくれ)とあぢきなく(=つまらなく)おぼす。(弟が)「まろ(=私)は端に寝はべらむ。あなくるし(「ああ疲れた)」とて、(寝所を整えるために)火かかげなどすべし(助動詞:推量。源氏の視点。実際にその場面を見ているわけではないが気配でそうだろう、と思って)。女君は、ただこの障子口すぢかひ(=斜かい)たるほどにぞ臥したるべき(助動詞:推量)。(姉が)「中将の君(=この姫君に仕えているいちばん身近な女房。)はいづくにぞ。人気遠きここちして、もの恐ろし」と言ふなれば、長押(=母屋と廂の間区切る横木。仕えの女房たちは廂に寝ている)の下に、人々(=女房たち)臥して答へすなり。「(中将の君は)下に湯におりて、『ただ今参らむ(=すぐ戻る)』とはべる」と言ふ。
さて、昼間紀伊の守と話したことを思い出したりして、例の姉弟(まあ、姉でしょうが)のことが気にかかり、眠れない源氏。暗闇の寝所で衣ずれの音などが障子(襖)のむこうから聞こえて、これがあの姉の気配だろうか、とやおら起きて聞き耳をたてます。ものごし優雅な源氏が暗闇のなかで「やをら」起きる、というのがおもしろいです。その姉弟の会話を聞くと、弟は源氏をみて、その素晴らしさを姉に語るというのに、姉は眠気のほうが勝って「昼間だったら覗いて見てみたかったんだけど~」と欠伸まじりとも思える興味のあまりなさそうな感じで答えるのにたいして、源氏は「ねたし」と感じます。
襖で区切られて、更に寝所の様子というのは姉弟のやりとりからもわかるように暗い。そうするとここでもまた源氏の視点に立つと助動詞が効いてきます。会話やかすかな物音から襖の向こう側を推量しています。
姫君は方違へでやってきたひと(義理の息子)の家にいるだけでなく、今日は源氏というお客までとなりにやってきているので、いつも一番身近に仕えている中将の君(女房の名前は父の役職からとることが多い)がいないことで落ち着かないのか、居場所を女房たちに問うと、ここがまた「中の品」らしいところというか、「お風呂に行っていてすぐもどるそうです~」と寝ながら応えるだけで、誰も姫の相手はしません。
風呂は寝殿の後ろ(北側)にあって、当時は蒸し風呂だったそうです。また、現在のように頻繁に風呂に入れるわけではないので、このような場面はめずらしいそうです。
皆しづまりたるけはいなれば、かけがねをこころみ(ためしに)に引きあげたまへれば、あなた(むこう)よりは鎖さざりけり。几帳を障子口には立てて、火はほの暗きに見たまへば、唐櫃だつ物(調度品の類。「だつ」を使うことで部屋の暗さがわかります)どもを置きたれば、みだりがはしきなかを、分け入りたまへれば、(姫君が)ただひとりいとささやかにて臥したり。(姫君は)なまわづらはしけれど、(源氏が)上なる衣押しやるまで、求めつる人(=中将の君)と思へり。「中将召しつればなむ、人知れぬ思ひのしるしあるここちして」と(源氏が)のたまふを、ともかくも思ひわかれず、もの(=物の怪の「もの」でしょうか。超自然の恐ろしいもの)におそはるるここちして、「や」とおびゆれ(=おびえる)ど、顔に衣のさはりて、音にも立てず。
「上の品」であればまわりの者がついうっかり、なんてことはないのでしょう、当然閉まっている鍵なのですが、ためしに源氏が自分の側の鍵を上げてみると、向こうからはかかっていない。この対比も品の違いを際立たせています。鍵が両側についていて、源氏の方(上の品)はかかっていて、姫君の方(中の品)はかけ忘れています。突然きまった源氏の来訪にそれまで一部屋を使っていたので、調度品の類が雑然と置かれている中を源氏は分け入って進みます。すると、姫君が「いとささやかに」横たわっています。当時は夜具というのは自分の着物を上からかけているだけなので、身体の大きさも暗い中でもわかるのでしょう。「ささやか」という言葉には物理的に華奢なかんじというだけでなく、昼間の話や桐壺帝からの話をきいて「あはれ」と思っている源氏の視点もはいっているように感じました。人の気配を感じたのか寝入りばなの姫君は「なんとなくわずらわしいな」と感じますが、源氏が夜具にしている着物をひきあげるまで、風呂にいっていた中将の君だとばかり思っていました。「中将を呼んだので(こうして来たのです)、人知れずお慕いしていたかいがあって(うれしい)」と、(近衛の中将である)源氏が言います。姫君はこの部屋に男がいることに動転してしまいとっさには状況を判断することが出来ず、物の怪かと怯えて思わず声が出てしまいますが、衣が顔に触れて音になりません。
「中将の君」は女房の名ですが、近衛の中将という役職を持つ源氏もまた「中将の君」で、この源氏の言葉は非常に印象的です。
ちひさやかなる人(P36~)
「うちつけに(=突然で)、深からぬ心(=でき心、いいかげんな気持ち)のほどと見たまふらむ、ことわり(=当然)なれど、年ごろ(=長い年月)思ひわたる(=ずっと~し続ける)心のうちも、聞こえ知らせむとてなむ。かかるをり(=このような機会)を待ちいでたるも、さらに浅くはあらじと思ひなしたまへ」と、(源氏は)いとやはらかにのたまひて、鬼神もあらだつまじき(源氏の)けはひなれば、はしたなく(=体裁が悪い)、「ここに、人」とも、えののしらず(「え~ず」で「~できない」。「ののしる」は「大声を出す、騒ぐ」)。ここちはた(気持ちではまた)、わびしく(=情けなく)、あるまじき(=あってはならない)ことと思へば、あさましく(=驚き、あきれる)、(姫君は)「人違へにこそはべるめれ」と言ふも息の下(=せいいっぱい、やっとのこと)なり。(姫君の)消えまどへるけしき(=とり乱す様子)、(源氏は)いと心苦しくらうたげ(=かわいい)なれば、をかしと見たまひて、(源氏は)「違ふべくもあらぬ心のしるべを、思はずにもおぼめ(=知っていながら知らない振りをする)いたまふかな。すきがましき(=けしからん)さまには、よに(=決して)見たてまつらじ。思ふことすこし聞こゆべきぞ」とて、(姫君が)いとちひさやかなれば、かき抱きて、障子のもと出でたまふにぞ、求めつる中将だつ(源氏からみて、なので「だつ=らしい」)人来あひたる。(源氏は)「やや」とのたまふに、(中将の君は)あやしくて、探り寄りたるにぞ、いみじくにほひみちて、顔にもくゆりかかるここちするに、思ひ寄りぬ(=察しがつく)。あさましう、こはいかなることぞと思ひまどはるれど、聞こえむ(=申し上げる)かたなし(=術がない)。なみなみの人ならばこそ、あららかに(=荒々しく)も引きかなぐらめ、それだに人のあまた知らむは、いかがあらむ。(中将の君は)心も騒ぎて、したひ来たれど、(源氏は)動もなくて、奥なる御座に入りたまひぬ。
寝入りばなに突然男が現れて怯えている女に対して「突然なので、いい加減な気持ちと思われても仕方がないが、ずっと恋焦がれていたわたしの気持ちも聞いてください」と、口説き始めます。そのものいいがあまりに「やはらか」で、鬼さえも手荒く振舞えなくなってしまう様子なので、女も声を出して人を呼ぶこともできない。けれど気持ちでは、当然自分のことをひとの妻だと知っていながらこのような事態になることはあってはならないと思いやっとのことで「人違いでしょう」と言うが、その必死に抵抗しようとする様子も源氏にはかわいらしく見えていとおしく、姫の「人違い」という言葉を受けて「間違えるはずもない私の恋心を知って知らぬ振りをするのですね。」と答える機敏さが光ります。「すきがましきこと」を「好色」と訳してしまうと違和感があります。「襲いに来たわけでも、ひどいめにあわせるわけでもない、まず私のあなたに対する恋心をきいてください。」というような感じでしょうか。これは源氏が単に口説き文句の常套句として使っているだけではなく、いちど関係を持った女性はとことん面倒をみる、という源氏の態度からも納得できるような気がします。
そして小さい姫君を抱いてそのまま自分の寝所に移ろうとしたその時、姫君が本当に求めていた「中将の君」らしき女房が現れます。源氏は「やや」と声をかけますが何しろ暗い寝所なので声を頼りに探り当てると、その姿を見るよりも高貴な香りが満ちて、これは、と思い当たります。男に姫君が連れ去られようとしている。でもその相手が源氏ともなると何も言えない。そのへんの男であれば「姫君になにを」とでも言ってて荒々しく引き離すのだが。ただそういう場合に未然にことが防げたとしても、騒ぎ立てることで大勢の人がそんなことを知ってしまったらどうなるだろう、と動転してしまいとにかく源氏の方について来たが、源氏はと言えば「動もなくて」奥の自分の寝所に入っていく。「動もなくて」を「平然と」訳してしまうと源氏がとても悪い人のような印象になってしまいます。身のこなしの優雅さやうろたえる「中将の君」との対比として捉えたほうがよいのではないでしょうか。
「しのび込み」の場面からずっと寝所の暗さは強調され続けているので、読者にも薄暗い寝所の情景は映像的にうえつけられています。そんな中でふっと薫る源氏の香り。いままで視覚的に語られる源氏の美しさでしたが、ここで嗅覚にもうったえてきます。映像をもってしても表現し尽くすことのできない、「源氏物語」の優れた点のひとつではないでしょうか。香の歴史については詳しくないので当時それがあったのかわかりませんが、竜涎香(雄鯨の腸内で醗酵したイカの嘴が浜辺に流れ着いたものを使ってつくる貴重で高価なお香)なんかだったんでしょうか・・・。物資的に限定された世界で、だからこそ極められた世界というのは現在より豊かだったと言えるかもしません。
平成16年2月18日 例会報告 帚木第十二回 朴文順さん
中の品の家(後半P18~)
思ひあがれる(=気位が高い、心に誇りをもった。現在の「思いあがる」のような悪い意味はない)けしき(=様子)に聞きおきたまへるむすめなれば、ゆかしくて、耳とどめ(聞き耳をたてる)たまへるに、この西面(源氏は同じ母屋を仕切った東面にいます)にぞ人のけはひする。(女たちの)衣のおとなひはらはらとして、若き声などもにくからず(=感じがよい)。さすがに(=それでも)忍びて、笑ひなどするけはひ(=様子)、ことさらび(=「ことさら」+「ぶる」で動詞。わざとらしく思わせる、感じさせる。)たり。格子をあげたりけれど、(紀伊の)守、心なし(=無用心、思慮が足りない)と、むつかり(=不平を言う、不満に思っている。現在でも幼児に対して使いますが、大の大人がむつかるのですから「ああ、無用心だなあぶないあぶない」など言いながら部屋を見回っている感じでしょうか)て、(格子を)おろしつれば、火ともしたる透影(=正確な意味はわかりませんが「あかり」)、障子(=襖)の上より漏りたるに、やをら寄りたまひて、(源氏は)見ゆやとおぼせど隙もなければ、しばし(女たちの会話を)聞きたまふに、この近き母屋につどひゐ(ゐる←居る。P16の「のぞきゐて(渡殿に座り込んで覗いている)」とおなじ用法)たるなるべし(助動詞:推量)、うちささめき言ふことどもを聞きたまへば、わが御うへ(=自分のこと)なるべし(助動詞:推量)。
ことさらびたり・・・それなりに高貴らしく振舞ってはいるものの、左大臣邸つきの女房たちとくらべてしまうとやはり女房も「中の品」だと源氏は感じているようです。
わが御うへ・・・「わが」とは源氏が自分のことを言っているので、自分のうへ(こと)御をつけるのは不自然に思われますが、敬語は客観的、絶対的なので、こうなるそうです。
●助動詞●古文は現代からみると極端に省略された文章ですが、動作の主体が敬語によってわかるように、場面の情景は助動詞でわかるようです。
「格子あげたり(継続)けれど~おろしつ(完了)れば」は、いつからかあがっていた格子だが、源氏を迎え入れるために紀伊の守が邸内を見回っていたときにあがった格子をみつけて「これは無用心」と思いおろしたので源氏が到着し東面の部屋に入ったときにはすでに格子はおろされた状態だった。これだけのことを助動詞の使い分けで省略できるので流れるような文章になるということでしょうか。
中の品の家(後半P18~)
思ひあがれる(=気位が高い、心に誇りをもった。現在の「思いあがる」のような悪い意味はない)けしき(=様子)に聞きおきたまへるむすめなれば、ゆかしくて、耳とどめ(聞き耳をたてる)たまへるに、この西面(源氏は同じ母屋を仕切った東面にいます)にぞ人のけはひする。(女たちの)衣のおとなひはらはらとして、若き声などもにくからず(=感じがよい)。さすがに(=それでも)忍びて、笑ひなどするけはひ(=様子)、ことさらび(=「ことさら」+「ぶる」で動詞。わざとらしく思わせる、感じさせる。)たり。格子をあげたりけれど、(紀伊の)守、心なし(=無用心、思慮が足りない)と、むつかり(=不平を言う、不満に思っている。現在でも幼児に対して使いますが、大の大人がむつかるのですから「ああ、無用心だなあぶないあぶない」など言いながら部屋を見回っている感じでしょうか)て、(格子を)おろしつれば、火ともしたる透影(=正確な意味はわかりませんが「あかり」)、障子(=襖)の上より漏りたるに、やをら寄りたまひて、(源氏は)見ゆやとおぼせど隙もなければ、しばし(女たちの会話を)聞きたまふに、この近き母屋につどひゐ(ゐる←居る。P16の「のぞきゐて(渡殿に座り込んで覗いている)」とおなじ用法)たるなるべし(助動詞:推量)、うちささめき言ふことどもを聞きたまへば、わが御うへ(=自分のこと)なるべし(助動詞:推量)。
ことさらびたり・・・それなりに高貴らしく振舞ってはいるものの、左大臣邸つきの女房たちとくらべてしまうとやはり女房も「中の品」だと源氏は感じているようです。
わが御うへ・・・「わが」とは源氏が自分のことを言っているので、自分のうへ(こと)御をつけるのは不自然に思われますが、敬語は客観的、絶対的なので、こうなるそうです。
●助動詞●古文は現代からみると極端に省略された文章ですが、動作の主体が敬語によってわかるように、場面の情景は助動詞でわかるようです。
「格子あげたり(継続)けれど~おろしつ(完了)れば」は、いつからかあがっていた格子だが、源氏を迎え入れるために紀伊の守が邸内を見回っていたときにあがった格子をみつけて「これは無用心」と思いおろしたので源氏が到着し東面の部屋に入ったときにはすでに格子はおろされた状態だった。これだけのことを助動詞の使い分けで省略できるので流れるような文章になるということでしょうか。
噂話 (P20)
「いといたう(「いと」+「いたう」=ものすごく)まめだち(「まめ(真面目)」+「だつ」=真面目くさく振舞う)て、まだき(=まだその時期ではないのにもう、はやくから)に、やむごとなきよすが(=高貴な妻→葵の上)、さだまりたまへるこそ、さうざうし(=物足りないと思う)かめれ(伝聞推定「だろう」)。されど、さるべき(=しかるべき)隅(奥まった場所、秘密という意味から転じて女、女のところ。)には、よくこそ(巧く上手に)隠れありきたまふなれ(伝聞推定)」など(襖で隔てた西面にいる女房たちが)言ふにも、(源氏は)おぼすことのみ心にかかりたまへば、まづ胸つぶれて、かやうのついでにも、人の言ひ漏らさむを、聞きつけたらむ時、などおぼえたまふ。ことなることなければ、聞きさし(さす=やめる)たまひつ。式部卿(桃園式部卿)の宮の姫君(源氏の従兄弟)に、朝顔奉りたまひし歌などを、すこしほほゆがめて(間違う、事実と異なる)語るも聞こゆ。くつろぎがましく、歌誦じかちにもあるかな、なほ(=やはり)見劣りはしなむかし、とおぼす。(紀伊の)守、出て来て、燈籠かけそへ、火明くかかげなどして、御くだもの(=酒菜。菓子や木の実など軽いつまみ)ばかり参れり。「とばり帳(=寝台)もいかにぞは。さるかた(=女)の心もなくては、めざましき饗ならむ」と(源氏が)のたまへば、「何(=どんな女)よけむとも、えうけたまはらず」と、かしこまりてさぶらふ。端つかた(=端の方)の御座に仮なるやうにて大殿籠れ(高貴な人々が「眠る、やすむ」の意)ば、人々もしづまりぬ。
隅(くま)・・・「くま」と読むと目の下の隅や隈取を連想しますが、「すみ」と読めば奥まった場所、日の届かないところ、影、秘密というイメージです。どうして男のことは指さないのかな、と思ったんですが、当時は女性は家の中から動けず、男性が女性の「ところ」へと通っていったので、影の場所を指す「隅」が「女=女のところ」になったのではないでしょうか。いま、まとめながら、女性は男性のように簡単に出歩くことのできなかった分、住処と一体化している、あるいはそう見られているのではないかと感じました。
おぼすことのみ心にかかりたまへば・・・女房たちが少し下世話なかんじで源氏の女性関係についての噂話(もちろん源氏に近い筋からの直接の情報ではなく伝聞の伝聞のような話。)をしているのだけれど、源氏が気にかかることは「おぼすことのみ」=藤壺とのこと。まづ心つぶれて(動揺して)、こんな際に女房たちの間であのことが話題にのぼったら、と気が気でない。読者はまだ「おぼすこと」がなんなのか知らされていないが、「桐壺」の最後で、新築した自分の家をみて「かかる所に、思ふやうならむ人をすゑて住まばやとのみ、嘆かしうおぼしわたり」(P122)とあり、その後の「帚木」の最初の場面までに五年間の空白があることから、その間に藤壺とのあいだになにかが起こったということを想像させるようになっています。「おぼすこと」は「帚木」の恋文のくだり(P135~)の源氏の態度からも想像されます。
くつろぎ(余裕がある様子)がまし(気取る)く、歌誦じかち(~じがち=なにかと歌をよみたがる)にもあるかな・・・源氏は、噂話に興じる中の品の女房たちの様子を聞き、やはり上の品の女房たちとくらべて見劣りすると感じている。
「とばり帳もいかにぞは」・・・こゆるぎの紀伊の守が世話を焼いている様子をからかおうと、冗談で「女の用意は・・・」ときくと「どんな女がよいのかわからないもので」と真面目にかしこまって答える紀伊の守の様子です。
姉弟 (P24~)
主人の子ども、をかし(こどもに対して使う場合は「かわいらしい」)げにてあり。童(=殿上童、殿上の間で公卿の雑用をつとめる子供)なる、殿上のほどに御覧じ馴れたるもあり。伊予の介の子もあり。あまた(の子どもたちが)あるなかに、いとけはひあてはかにて十二三ばかりなるものあり。いづれかいづれ(どの子がどんな子か)、など問ひたまふに、(けはひあてはかな一二三歳くらいの子をさして)「これは、故衛門の督の末の子にて、(衛門の督が)いとかなしく(=胸がつまほどかわいがる)しはべりけるを、をさなきほど(=時、頃)に後れ(=衛門の督に先立たれ)はべりて、姉なる人のよすがに、かくてはべるなり(=このようにしている)。才(=男子の学問。漢学)などもつきはべりぬべく(推量)、けしうははべらぬ(=悪くないかなりのものだ)を、殿上なども思うたまへかけながら、すがすがし(清清し=物事がすらすらと運ぶ)うはえまじらひ(交じらい→人と交じらう→宮仕えをする)はべらざめる」と(紀伊の守が)申す。「あはれのことや。この姉君や、まうと(=目下の者に対する二人称)の後の親」「さなむはべる」と(紀伊の守が)申すに、(源氏は)「似げなき親をも、まうけたりけるかな。上(=桐壺帝)にもきこしめしおきて『宮仕へにいだし(過去)立てむと(衛門の督が)漏らし(過去)奏せし(過去)、いかになりにけむ』と、(帝が)いつぞやのたまはせし。世(=男女の仲)こそ定めなきものなれ」と、いとおよすけ(大人びて)のたまふ。
この部分はすこし時間が遡ります。ことわりがないので、戸惑ってしまいますが、フラッシュバックの技法でしょうか。このまえの部分が「仮なるやうにて大殿籠れば、人々しづまりぬ」ですから、源氏がちょっと横になって、隣にいるであろう受領の妻についてのエピソードを思い出しているようにも感じられて非常に映像的な場面です。方違へで紀伊の守邸にやってきてまもなく、宴会をおこなっている場面です。
受領というそれほどの身分のものではない「中の品」の妻がなぜ「思いあがれるけしき」なのか、ここでわかります。父の衛門の督が生きていればこの兄弟も身分にふさわしい暮らし方をしていたのに、という部分です。
余談ですが、東芝に「atehaca(アテハカ)」という家電のシリーズ(電子レンジやポット。いろんなものを削ぎおとしたシンプルなデザインのものです。)がありまして、北欧の方の言葉かしら?どんな意味だろう・・・と思っていたんですが、今回の部分を読んで、古語の「あてはか」からとった名前だったんだと気付き調べてみたらやっぱりそうでした。http://www.atehaca.com 「あてはか」とは、先生の解説でも「上品でみやびやかなさま、気品が自然に身に備わった」とありますが、このHPには One's personality,appearance and attitude is elegantly beautiful.Being graceful とあります。現在の日本語でも英語でもこれだけの言葉を費やさなくてはいけない意味をあらわす単語が一語であったんですね。この言葉が消滅してしまったということはつまり「あてはか」な人がいなくなったから、なのでしょうか。「あですがた」や「あでやか」という言葉はありますが現在の「あで」は「艶」ですから「貴」の意味は含まれないようです。
(紀伊の守がこたえて)「不意(誰も予想しない、というニュアンスです)にかくてものしはべるなり。世の中といふもの、さのみこそ今も昔も定まりたることはべらね。中についても(=なかでも)女の宿世は浮びたるなむ、あはれにはべる」など聞こえさす。(源氏は)「伊予の介は、(女を)かしづくや。君と思ふらむな(主人とおもっているだろうな)」(紀伊の守は)「いかがは(もちろんです)。私の主とこそは思ひてはべるめるを、すきずきしきことと、なにがしよりはじめて、うけひき(=同意する)はべらずなむ」と申す。「さりとも、まうとたちのつきづきしく(=につかわしく)今めきたらむに、(女を)おろし(=ひきわたす。)たてむやは。かの介(=伊予の介)は、いとよしありてけしきばめるをや」など、物語したまひて「(その女はいま)いづかたにぞ」「皆下屋(別棟の召使たちが住むところ)におろし(=下がらせ)はべりぬるを、えやまかりおりあへ(あふ=全部やり切る)ざらむ」と聞こゆ。酔いすすみて、皆人々簀子に臥しつつ、しづまりぬ。
宴会が始まった頃は「こゆるぎ」にかけまわる中の品の紀伊の守と「のどやかにながめたまふ」上の品の源氏という対称的な二人でしたが、ここではともに「若く美しい継母をもった男性」として描かれています。もちろん源氏のほうが機転がきいたうけこたえをしていますが、源氏の、父である帝に対する思いを紀伊の守を使って表現しているようにも感じました。また、結局「父を裏切らない紀伊の守」と「父を裏切る源氏」という対照もあり、ここでは継母に恋焦がれる息子ですが、皮肉なことにずっと後に「息子に裏切られる源氏」という展開が待っているのですから、すべての物語を読み終えてもういちど読み返すときにこういった場面で読者がひっかかるような仕掛けがあるんだなと思うと、源氏が千年読み継がれてきた理由がよくわかります。
平成16年1月21日 例会報告 帚木第十一回 朴文順さん
源氏と女房たち
からうして、今日は日のけしきもなほれり。→昨晩まではどんな様子だったかというと帚木のP131、なが雨晴れまなきころ・・・ 物語は続いています。
かくのみさぶらひたまふ→同じく1巻目のP131、いとど長居さぶらひたまふの部分に照応します。源氏が(藤壺がいる)内裏にできるだけいたい、けれどもそういうわけにもいかない。大殿(左大臣)が気の毒だとは思っているので、ひさしぶりに妻の実家を訪れます。
(左大臣邸の)おほかたのけしき、人(正妻=葵の上)のけはいもけざやかにけ高く、(源氏がなかなか訪れないからといって)乱れたるところまじらず、
(妻の)あまりうるはしき(=あまりに隙のない整いすぎた美しさ)様子にうちとけることもなくさうざうしくて
中納言の君、中務などやうの、おしなべたらぬ若人(いずれも左大臣家の女房)を相手に冗談などを言って過ごします。
暑さに乱れたまへる御ありさま・・・源氏が暑さに服をすこしだらしなく着崩している様子。もちろん皆きちっとした服装をしているわけですが源氏なので女房たちも見るかひあり と思うのでしょう。
「あなかま」・・・うるさい、静かに、という意味ですが、現代で言えばひとさし指を口にあてて「しっ!」というような感じでしょうか。几帳のむこうの左大臣に聞こえないように言ったはずです。
女房は左大臣家つきの女房なのでもちろん葵の上に忠心をもっているのですが、その前にそれぞれがひとりの女性です。あの弘徽殿ですら、恋敵の桐壺はにくくても息子の源氏(それも成人前の少年)のあまりの美しさに女性として色気を感じたのですから、若い女房がこうして自分たちのまえでリラックスしてうちとけている成人した源氏の魅力にとりつかれないわけはなくのではないでしょうか。
女房たちの様子が生き生きと描かれているのに対して葵の上のことが描かれていても人物としてというよりは形容が「左大臣家」と並列されて「けざやかにけ高く」と、左大臣家そのものの描写のようです。左大臣家で当の左大臣や兄の頭中将より誰よりもその「家」を感じさせるのは葵の上のような気がします。感情がよみとれる部分がほとんどなく、だからこそかえってみえない彼女の心の動きが気になり、想像してしまいます。
葵の上は、今後(人間違えをしてしまって、という場面もありますが)源氏がおのずから関係をもつ女性たちとはちがって唯一最初から与えられた政略結婚というかたちで婚姻関係を結んだ女性です。もし、彼女とうまくいっていたら(正妻にたいして「さうざうし」という感情を持たなければ)「源氏物語」は成立しなかったのでは、と思うと本当に物語の構成の精巧さにあらためて感心させられます。
葵の上にたいして思い入れがあるので、感想がつい長くなってしまいました。この後「方違へ」「中の品の家」と続きますが、今日はとりあえず。明日は校了前の休日出勤です・・・。
方違へ
さかし(=そのとおり)
二条の院(=源氏の私邸)も同じ筋(=内裏からみて左大臣邸とおなじ方角)にて、・・・なやましきに(なやむ=病気、からだが疲れている、で現在の「悩む」とは違う)
「いとあしきことなり」解説にもあるとおり、相当強い語気で、女房が上のものにはふつうは使わないのですが、とにかく寝てしまおうとしている源氏になんとか方違えしてもらいたいようです。
紀伊の守(=従五位の受領で、左大臣の家来筋)
中川のわたりなる(=にある)家 この家は紫式部が実際に住んでいた家をモデルにしているのではないかと言われているそうです。
牛ながら(=牛をつないだまま)、(門内に)ひき入れつべからむ所を。・・・目上の者の家を訪れるときは家のまえで車を降りなければなりませんが、家臣の家であれば牛車のまま中まで入れる。
忍び忍びの御方違へ所(=女のところ)は、あまたありぬべけれど、(左大臣のところへは)久しくほど経て渡りたまへるに、方塞げて、ひき違へほかざまへ(=全く違うほかの女のところ)と(左大臣が)おぼさむは、いとほしき(=気の毒)なるべし。
紀伊の守に御せ言(=命令)賜へば、(紀伊の守は)うけたまはりながら、(源氏の御前を)しりぞきて、
伊予の守の朝臣(=紀伊の守の父)の家につつしむこと(=忌みごと)はべりて、女房なむまかり移れるころにて(女房たちまで連れて皆で来ている)、(自分の家は)狭き所にはべれば、なめげ(なめし=失礼、無礼)なることやはべらむ
下に(=陰で、ひそかに)嘆くを(源氏は)聞きたまひて、
その人近からむ(=近くに人がいる気配)なむ・・・・ただその几帳のうしろに(泊りたい)
「げによろしき御座所にも」・・・源氏の冗談に対して女房はそれを制するのでなくさらに輪をかけるような受け応えをして場を盛り立てます。さすが左大臣家の女房、という感じです。
中の品の話は昨晩さんざん聞かされていたこともあり、興味が湧いた源氏は、先ほどまで疲れて眠かったというのにいそいそと大臣にも挨拶せず(大臣にも聞こえたまはず)親しいものだけ=むつましき限り)を連れて紀伊の守邸へでかけます。
中神・・・陰陽道で説く神。60日を周期として、その間16日は天上にあるが、ほかは5,6日ずつ八方に遊行する。この神のいる方向を「方塞がり(かたふたがり)」として忌み、「方違へ」をする。
そんな具合ですから京ではしょっちゅうぐるぐるみな回遊していたようです。方違えの風習は現代にも残っている(結婚のときなど?)ようですが、残念ながら私にはよくわかりません。風水などで「方角が悪い」とか言いますし、おみくじや占いでも吉の方角、凶の方角などありますが、ご存知の方教えてください。
主語を補いながら書いていくと、原文は敬語の使い分けで主体が誰であるのか自ずからわかるようになっていて、結果として流れるような美しい文体になっているのだな、と思いました。学生時代はこれで悩まされ、原文を味わう余裕がなかったように思います。
中の品の家
(紀伊の守は)にはかにとわぶ(=思い煩う、困り果てる)れど、人(源氏も供の者も)も聞き入れず。
寝殿の東面払ひあけさせて(=すっかり開けさせる)、かりそめの御しつらひしたり。水の心ばへ(中川の水を邸内に引き入れていること)など、さるかたに(それなりに)をかしくしたり。田舎家だつ柴垣して、前栽など心とめて植ゑたり。
風涼しくて、そこはかとなき虫の声々聞こえ、蛍しげく飛びまがひて、をかしきほどなり。
人々(供人たち)、渡殿より出でたる泉にのぞきゐて(=座り込んでのぞいて)、酒飲む。
主人(=紀伊の守)もさかな(=酒菜。当時は酒の肴はだいたい木の実や果物を指したそうです)求むと、こゆるぎの急ぎありくほど、君(=源氏)はのどやかにながめたまひて、かの中の品に取り出でて言ひし、このなみ(=この程度)ならむかしとおぼしいづ。
中の品の家には行ったことのない源氏は昨晩のいろいろな話から想像していたものの、実際の家を見てみると、まあまあ、なかなか趣向をこらした様子ではある、というのが「さるかたに」にあらわれています。でもまあやっぱりどこか田舎くささを感じてもいるようです。
紀伊の守が急な来客の対応に追われている様を、(身体を揺り動かしながら歩いていることから)「ゆるぎありく」→こゆるぎ、という本来「磯」にかかる枕詞を「磯(いそ)」=「急(いそ)」にかけています。
こゆるぎに急ぐ中の品の紀伊の守に対して、上の品の源氏はというと、のどやかにながめたまひて、ですから一文の中でみごとに対照があらわされています。
「こゆるぎ」がでてくる歌には次のようなものがあります。こゆるぎは身体を揺り動かす、というほかに心の動揺の意味もあるようです。右近の作品は女性らしくて好きです。
わかめ刈る春やこるらむこゆるぎの磯のあま人波にまじれり(源兼澄・万葉集)
とふことを待つに月日はこゆるぎの磯にや出でて今はうらみん(右近・後選1049)
1月21日に進んだのはここまでです。
「葵の上」に思い入れがあるといっても、わたしも読んだのは与謝野晶子訳の「桐壺」の章のみです。読んだのが小学生のときで、子供が想像していた結婚像とあまりにちがったのがショックで、その心情を語られない女性に非常に興味が湧いたのがそもそものきっかけでした。「白鳥の湖」の悪魔の娘(オディール?)や「白雪姫」の継母など、通常「悪役」とされるひとたちに興味をもつ性質なので。単純な勧善懲悪って都合がよすぎてリアリティに欠けると思うんです。ほかの女性について知っているのは漫画「あさきゆめみし」や橋本治訳(高校生の頃はやったんです)の源氏からです。その後原文でよむのは試験や受験対策で常に「主語は誰か?」「空欄を埋めよ」だったんで、原文をじっくり味わう余裕もなく過ごしてきました。なので、わたしも毎回はじめて知ることばかりです。これからもどうぞよろしくお願い致します。
朴文順
12月17日 例会報告 帚木第十回 浜岡はるみさんと沈光子さん
蒜食いの女 その一
1)蒜 ⇒にんにく 野蒜 ⇒野の蒜
2)けしきある ⇒変わっていて面白い
3)なでふ ⇒なじょう :なんていうかどうという事もない
4)文章生 ⇒当時の官僚コースの学生。身分のない者が官吏になるためのコース
5)かしこき女 ⇒漢文の出来る女
6)公事 ⇒宴会の時の詩作
7)才(ざえ) ⇒漢学
8)『わがふたつの途歌ふを聴け』⇒これは、白居易の『白氏文集』の中の『議婚』という歌の一部
『議婚』
主人会良媒 主人良媒を会す
置酒満玉壺 置酒して玉壺(ぎょくこ)に満つ
四座且勿飲 四座飲むなかれ
聴我歌両途 我がふたつのみち歌うを聴け
富家女易嫁 富家のむすめは、嫁(か)しやすく
嫁早軽甚夫 嫁すること早くしてその夫を軽んず
貧家女難嫁 貧家のむすめ嫁(か)し難たく
嫁晩考於姑 嫁する事遅くして姑の考なり
聞君欲娶婦 聞く君婦をめとらんと欲すと
娶婦意如何 婦をめとる如何(いかん) ?
9)いときよげ ⇒美しい字
10)消息文 ⇒恋文
11)仮名(かんな) ⇒真名(まな):漢字
12)むべむべしく ⇒格式ばった、漢文調
13)腰折文 ⇒下手糞な歌:漢文調の続きの良くない歌
14)なつかしき妻子 ⇒日常語ではない表現:漢文調に面白おかしく表現した
15)無才の人 ⇒私の事
16)なまわろならむ ⇒なまわろし:どことなくみっともない(振る舞い)
17)すかい ⇒すかす:騙す、その気にさせる
18)をこずき ⇒おこ+づく:馬鹿みたいに →加山雄三みたい?という意見あり
式部は、源氏や中将に比べれば相当下位になる訳で、変わった面白い話をしなくてはいけない訳です。せかされて彼は、官僚コースの学生として学んでいた頃知り合った、漢文の出来る博学な女の話を始めます。その女は、ある博士の娘で、博士には娘たちが多くいて、博士の家に生徒として通っているとき、その一人に言い寄ったところ、親の博士が聞きつけて、さかづきを持って出てきて白居易の歌を出して、娘を嫁にしてくれるよう迫られ、そんなに気はないのにずるずると付き合っていきました。女は、式部のために漢文の歌作りから様々な宮廷に勤めるための知識を教え、恋文にも仮名を使わず、漢字で格式ばった表現で美しい字で書いてきました。当時漢字は男のもの、仮名は女のものという暗黙の決まりがあったにもかかわらず、彼女は男の教育のために漢文で書いてきたんだと思いますが、相当な博学の女でありました。劣等感もあり、段々足が遠のいていく式部でありました。中将が興味を示し、更に話をさせようとします。
蒜食いの女 その二
1)心やまし ⇒嫌な感じ
2)物越し ⇒几張とか屏風が間にある
3)ふすぶる ⇒(女が)嫉妬する
4)またよきふし ⇒(別れるには)またよきふし
5)さかし人 ⇒女
6)はやりか ⇒せわしない、気が高ぶっている →久し振りに来たので喜んでいる
7)風病 ⇒神経痛という説
8)極熱の薬草 ⇒熱さましの薬
9)雑事等 ⇒着物等のお世話をする事
10)あわれに ⇒愛する人の心に届く様に →しかし、『むべむべしい』
11)さうざうしい ⇒物足りない、淋しい、あるべき物がない
12)何とかは ⇒(あまりの事に)何も答えられない
13)高やかに ⇒声高に
14)逃げ目 ⇒逃げる時の目つき
15)ささがに ⇒蜘蛛 →ささ:小さい 蟹
16)ひるま ⇒昼と蒜の間(にんにくの臭う間)
17)あやなさ ⇒納得いかない、筋が通らない
18)ことづけ ⇒口実 →自分を追い返して他の男と会うんだろう
19)し ⇒強め →夜を強める
20)なにか ⇒反語
21)まばゆからまし⇒恥ずかしくない
22)口 ⇒(和歌を返す)読み
23)疾く ⇒速い
24)しずしず ⇒式部の表情 →おもしろく、三枚目にとぼけて
25)むくつけき ⇒ぞっとする
26)爪弾き ⇒非難する
27)いわんかたなし⇒どうしようもない
28)あはめ ⇒けなして
長い間通わなかった式部がある日ついでに立ち寄ったところ、女は下熱剤としてにんにくを食べていました。当時、上流の人たちが病気を治したい場合は、祈祷師に頼むのが普通で、決してにんにくなぞ食べないそうです。彼女は貧しい暮らしをしていた訳です。
女は、むべむべしさが身についてしまっていて、男が来た事を飛び上がる程に喜んでいるのですが、にんにくの臭さに狼狽し声高く、この臭いがなくなった時に来てくださいと漢文風に堅苦しく言います。式部には理解できない女の振る舞いに、『蜘蛛も巣を張ろうという夕暮れなのに昼間(にんにくの臭う間)に来いとは納得いかない。自分を体よく追い返して他の男と会うんだろう』と捨て台詞。返して女は、『毎夜隔てないで会う仲だったらひるま(昼と蒜の臭い)会っても恥ずかしくないのに』と言い返しました。さすがに返歌は速かったと、中将たちにとぼけた言い方をする式部。病気ににんにくを食す事といい、漢文に秀でた女の事といい上流社会の男達には想像出来ない世界で、鬼と話した方がまだましだとまで言います。階級のギャップを感じる話です。恋する女のけなげさが感じられました。
この話に似た落語があった様な気がしますが、江戸時代ですよね。向田邦子の短編『花の名前』も思い出しました。ささ蟹って言うのが蜘蛛というのは、とってもヴィジュアル的な表現だと思いました。
年越してしまいましたが、『女性論の果てに』は出来たらまた後で。出来なかったらごめんなさい。
以上浜岡でした。
以下から沈光子さん
この巻きではつそれにしても、くづく階級社会の文化ギャップを教えられましたね。
蒜食いの女 は貧しい学者の娘。
父親にしてみれば貧乏人の娘沢山で、ひとりでも早く片付けたいところ。
娘に興を示す男がいれば、それ! と押し付けんばかりに縁づなくちゃ、後がつかえてる。娘にまんざらでもない男が現れて、ヤレヤレ、一丁上がり、と胸をなでおろしたでしょう。
娘は門前の小僧習わぬ経を読む で男の学問ばかりしっかり身についていて、恋の手習いの方にはトント縁がないのね。男をからめとる肝心の手練手くだが身についていないの。
恋の語らいでも、口に出るのは堅苦しい漢文調。
男にしてみれば興醒めなことこの上ない。
でもそこはお互いにまだ初心な頃の、それも下々の階級のことですから、なんとかそれなりに過ごしていたんだわ。
女に逃げ腰になっても、これからの出世に彼女の漢学の知識は必要不可欠。
やんごとなき生まれの公達たちと違って、試験に受かっていくことでしか階段を上っていけないのですもの。
上が上の公達たちにはとうてい理解できない下の階級の者たちの暮らしぶりを、藤式部は自分を笑い者にしながら、座をしらけさせまいとして語ったのね。
さすが宮仕えで鍛えられた苦労人の藤式部。自分の求められているもの、己の分を知る男なわけ。
それなのに、そんなバカな話(晴美ノート参照・極熱の治療に蒜を食う)があるもんか と信じようとしないのね。信じられないくらい、下々の生活を知らないわけ。
香を選りすぐり、焚き染め、気を持たせた恋の歌を詠んでみせる女 しか知らない彼らには、蒜の臭いをさせながら、衝立超しに男と会う女なんて 鬼の方がまし、なんていう感覚なのよ。
「さわりがあるので」とことづけて帰すこともできるのに、男に会いたい一心の女の純情が、裏目に出てしまっているのが哀しくも可笑しいね。
藤式部もほうほうのていで逃げ出すんだけど、可笑しさの中にも彼の温い人柄が感じられます。
藤式部はすまして「すこしよろしからむことを申せ」と責められても「これよりめづらしことはさぶらいなむや」とすましています。
これ、上が上の公達たちへのささやかなレジスタンスよね。
女性論の果てに
女が思いやりのない文などよこして男を困らせる「わろもの」事例がでてきます。
知ったかぶりで才のあるところを見せびらかすように、相手の状況もわきまえずにありったけの知識をひれかしているのは興覚めなもんだ、と左馬頭が女の教養について語り、女性談義の落ちをつけます。
どんなたくみな歌であれ、「つきなきいとなみ」場違いで時をわきまえないのには閉口させられますなぁ、などと気がきかない女を嘆いています。
当時は女から歌をもらえば何がなんでも返歌しなければ無粋な男にされてしまうんですから、心ここにあらずのまま返歌するのもうっとうしい。
官吏として大事を前にして頭がいっぱいの折に、風流ぶったすばらしい歌が届いても「なかなか心後れて見ゆ」と左馬頭はいいます。
左馬頭の理想の女像についての本音・結論が語られます。
それを聴きながら源氏はただ一人の女性への思いに「足らずまたさし過ぐべくなむあべかりける と言うにも 君はひとりの御ありさまを、心のうちに思いつづけたまふ。これに、足らず、またさし過ぎたることなくものしたまいひけるかな」と比べようもないあこがれの藤壷への恋慕にひたっているのです。
話は果てもなくつづき、ついに夜を徹し朝を迎えてしまいました。
男は女の話を、女は男の話を、語りついでいけば夜を徹してしまうのは、今も昔も同じ。
みなさま、何を隠そう私め、この歳になって超し方を振り返りますと、破れた恋のひとつや二つ、手痛い思い出の三つや四つ、悔しい思いの五つや六つ、いえいえ涙をしぼった晩は数え切れないほどありますです、ハイ
11月19日 例会報告 帚木第九回 浜岡はるみさん
常夏 :ナデシコの栽培品種。花と葉の色がともに濃く、一年じゅう花が咲く。
四人の話は続きます。中将が、『痴れ者:愚か者・ばか者の話をしよう。』と始めます。
この、痴れ者とは中将自身を指すか常夏の女を指すか二つの説が五分五分にあるそうです。
田中先生は女の方をとるそうですが、貴女はこの章の終わりにどちらを選びますか?
それ程に今回の常夏の女は、男と女の考える内容のギャップが激しく理解するのが難しい章でした。
しかし、田中先生の解説はその難しさを充分理解させてくれます。解説は、そちらをお読み下さい。
関係の説明をします。
中将 :紫の上の弟で、源氏とは義兄弟になります。彼は所謂おぼっちゃまである訳です。
常夏の女:貴族ではあるのですが、落ちぶれて親も亡くなり中将との間に女の子がいます。
北の方 :第一夫人は年上で、高貴な家の娘で、中将が常夏の女と関係する事を極端に嫌っている様です。
P-221
1)いと忍びて ⇒:北の方には絶対内緒で
2)見つ ⇒:会う
3)たえだえに ⇒:時々
4)うち頼める ⇒:夫として頼りにする
5)たまさかなる ⇒:時々、たまに
6)もてつく ⇒:とりつくろう、装う
7)頼めわたる ⇒:頼みに思わせ続ける
8)ありきかし ⇒:あったなーと思い出している
9)ろうたげ ⇒:いじらしい げ:客観的な見方
妻について:一番最初の妻は、源氏の結婚に出てきましたが、ある程度の地位のある家の女で年上ですが、その後の妻たちは、
三日通うと妻にしても良い事になっていたそうです。
P-223~224
1)のどけき ⇒:のどかで心配のない
2)おだしく ⇒:ゆったりと穏やか
3)この見たまふる⇒:北の方
4)情けなく ⇒:容赦なく
5)うたて ⇒:嫌がらせ
6)かすめ ⇒:におわす、ほのめかす
7)むげに ⇒:すっかり
8)思いしおれて ⇒:気が滅入って
9)撫子 ⇒:なでるように大切に扱う→子供でおそらく女 覚えていますか?小萩→男の子
中将の鈍感さ:『いさや、ことなることもなかりきや』ですって。若いって事は鈍さと鋭さが共存しているんですね。本人は自分の鈍感さ
を全く自覚していない。最近の日本の若い男の子たちにも見られる現象です。要するに想像力の欠如。
P-226
1)うら ⇒:心、見えないもの
2)もの思い顔 ⇒:憂わし気な顔
3)きほへる ⇒:競争する 虫の音と競ってしくしく泣く
4)常夏 ⇒:撫子の異称・別名 女の事
5)大和撫子⇔唐撫子
6)ちりをだに ⇒:古今集 おおちこうちのみつね の歌に
塵をだに据ゑじとぞ思ふ咲きしより妹とわが寝る常(床)夏の花
7)うち払う ⇒:塵を払う⇒中将を否定する意味と ⇒:涙にくれている意味
8)常夏 ⇒:私
9)あともなく こそ しか ⇒:強調して、中将のショック状態を表している
中将は女に嫌われてしまった事すら気がつきません。自分が薄情者と思われたくないという自己愛。一方女は、北の方の嫌がらせを受けながら関係を続ける事に対する自己嫌悪の形の自己愛。中将は女に去られて初めて面と向かって付き合ってこなかった自分を後悔する訳です。家をあともなく空にする事は、家人多勢を引き連れて消え去るわけですから、ものすごいエネルギーを要します。常夏の女の怖いまでのプライドと強さを感じて、ぞっとします。私だったら、しょうがないなって居座ってしまいます。
常夏って床との掛詞以外に、一年中咲くっていう事から、いつでも変わらない女っていう意味が含まれているのでしょうか?田中先生。
P228~229に常夏すなわち夕顔の性格が書かれています。夕顔の章が楽しみですね。
常夏の女 その二へつづく
常夏の女 その二 2003.11.19
P-229
1)はかなき世 ⇒:心細い身の上
2)ましかば まし ⇒:仮定 反実仮想
3)あくがら ⇒:フラフラと浮かび出る
4)こよなき ⇒:こんなに
5)さるもの ⇒:妻
6)尋ねる ⇒:住所が解らずあちこち捜す
7)これこそ ⇒:この女こそ
8)つれなくて ⇒:女がつれなくて
9)やうやう ⇒:次第に
10)かれはた ⇒:あの人はまた
11)たもつまじく ⇒:関係を持つ
中将は、自分を捨てて行った常夏の女について現実を見ようとしない、見たくないんです。女が自分の庇護を拒んだ深い訳までは解りません。落ちぶれて今でも中将を思い続けている哀れな女にするっきゃない男としてのプライドなんでしょう。でも幼い女の子を心配する親心はしっかりあるようです。この辺は沈さんに書いてもらったら、とっても面白い所だと思います。お願いします。
P-232
1)さしあたりて見む ⇒:一緒に暮らす
2)よくせずは ⇒:悪くすると
3)あきたし ⇒:うんざりする、飽きる
4)すきたる ⇒:浮気っぽい
5)この心もとなき ⇒:私の頼りない女
6)疑い ⇒:男がいたという疑い
7)添う ⇒:男に走ったと言う事を添え
8)くさはひ ⇒:非難すべき点のある
9)法気づき ⇒:抹香臭い
10)くすし ⇒:薬臭い
今までの指喰いの女、木枯らしの女、常夏の女を中将がまとめています。
先生の解説の中の、『常夏の女が、どこにでもいそうな陳腐な女に変わってしまっていた。』という文章が、中将と常夏の女の心のギャップを表していると思いました。そして、痴者について、最初は中将が自分を卑下していると思っていたんですが、最後になって女の事を言っていたんだと解りました。ちょっとひどいなと思いました。ここも沈さんに書いて欲しい所です。
その二は、スピードアップして終わったので追いつかない感がありました。文の奥に隠れた言葉がとても難しかったです。
いろいろな方のご意見を聞きたい章です。聞かせて下さい。
10月15日 例会報告 帚木第八回 沈光子さん
「木枯らしの女 」 が終わり、次回は 「常夏(なでしこ)の女 その一 」 221ページからです。
木枯らしの女 の情景描写、美しかつたですね。
左馬頭は指喰いの女の嫉妬に悩まされながらも、つまみ喰いが止みませんでしたね。
女を頼みにしているのに、とまりにと思うには少し物足りない気がして、浮気が止まなかった。
でも亡くしてみて初めて、彼女がいたればこその我ががままだったと気づいたのね。
左馬頭は、木枯らしの女を冷静に観察していますね。
同時に 指喰いの女が 自分にとってどれほど大切な女だったか、また自分のような者をどれほど大切に思ってくれていたかを、思い知ったのよね。
若気の至りを悔やむ左馬頭の気持ちが、何事にも派手派手しい木枯らしの女を冷静に観ていることで推察されます。
左馬頭に見られているとも知らない木枯らしの女は、通ってきた眼の前の男へありったけの才を総動員して、丁々発止と恋芝居を演じきっているし、また彼女はそれが身についているのね。
俺のときも女はこんなふうだったよなぁ。左馬頭はきっとそう思ってシラケタわね。
でもあの時は、それがとても魅力的にみえたし、俺はそれにふさわしいエエ男なんや、なんて身のほど知らずにのぼせ上がって、恋多き女にうつつを抜かした。
指喰いの女の嫉妬につれない態度で報い、喧嘩が絶えなかった。
あげくに一途な思いを寄せてくれていた大切な彼女を失ってしまった、って覚めた眼で観てるね。
だから情景がいっそう凛として読者に響いてきた。
悲ししかな、人間ってさぁ、無くしてみなけりゃわからない、ってことあるよね。
あってあたりまえのものは、ちっともありがたくないのよね。でも無くして初めてわかる関わりの深さ。
これって胸に覚えがある人、多いんじゃないかしらん。
左馬頭だけじゃないね、悲しいかな人は無くしながら成長していくのかも。
哀切を知るこの年齢になるまでには、私も大切なものずいぶんと無くしてきたんだわ。
木枯らしの女の屋敷の庭が月明かりに映えている様が、叙情的に描かれていて想像をかきたてます。
池には月が映っているかも、みたいな解説がありましたが、池は薄明かりの中で、ボウウトそれらしい姿を浮かび上がらせているだけだと思う。
吹き抜ける風が、燻し銀のようにな池の面に走っていく。一瞬、波頭が月明かりできらめく。
池に月が映えると派手派手すぎる。左馬頭の心情に合わない感じがするなぁ。
左馬頭は最後におっさんらしく教訓をたれましたが、源氏は彼の蛇足に成熟した男のするどい一言を述べましたなぁ。左馬頭より七才も下なのに、育ちの良さはこういうふうに出るものなの?
にくらたしいほど格好いいのね、源氏は。
ああ、早く源氏が女に翻弄されるところへ読みつきたいなぁ。出来すぎの源氏なんて、手が届かないもん。人間の苦しみを幾重にも孕んでいく源氏にたどりつきたいなぁ。
浜岡はるみさん
木枯らしの女 その一
左馬頭の話は続きます。
1)うち読み :歌を詠む教養
2)手つき :書の才能
3)口つき :歌を即興で吟じて読む
4)さがなもの :本来は、たちの悪い、手に負えない。指喰い女に対する親しみの表現
5)艶 :異性を意識する振る舞い
①あでやか ②優美 ③なまめかしい
6)ありけらし :過去の推量で、あったようだ
7)神無月 :旧暦の11月 今の暦では初冬
旧暦 春1~3月 夏4~6月 秋7~9月 冬10~12月
8)うつろいわたる:霜で変色した菊が辺り一杯にわたって
9)きほへる :競う
10)紅葉の乱れ:枯葉が舞っている
【まとめ】
指喰い女が居た頃には、何にでも有能なその女は左馬頭の中で輝いていたけれど、指悔いが居なくなってみると自分には(まばゆすぎる)存在となっていき、指喰い女を思う気持ちもあり、段々足が遠いていきました。そんな中でその女には誰か通って来る男が現れたようです。
神無月のころほひ・・・・からは、映像を見ている様な素晴らしい文章です。内容は、本で読んでください。
今回は、何と言っても【月】です。
まず浮かぶ景色です。
初冬の冴え冴えとした明るく白い月の下、池に映る月、霜で色褪せた一面の菊と、風と競うように舞う枯れた紅葉の枯葉を映す月の光。私たちは、また漆黒の闇の中の月について話しました。思い出されるのは、【桐壺】の中の(夕月夜の訪問)の月です。この月は、もう少し早い秋でしたね。月影ばかりぞ、八重葎にもさはらずさし入りたる。
私は、改め古代の月を思いました。百人一首の中にも沢山の月があります。何の気なしに読んでいたあの月たちをもう一度思い直してみたいと思いました。そして、竹中さんが犬の散歩で早朝に見る(ありあけの月)のお話をしてくれました。雪の夜の月も又話題になりました。子供の頃、月を見ながら歩いて、自分が止まると月も止まったあの月は、本当に美しかった事を思い出しました。東京の月は周りが明るすぎて可愛そうと思ったのは、上京したばかりに思った事でした。意識して月を観る暮らしをして見ませんか?あまりに多くの光たちに、負けそうになっている今の月を観てあげようではありませんか?
次は音楽です。
横笛の冴え渡る音、次いで和琴の美しい調べ。和琴は本当に美しい音を出します。雅楽演奏会で知りました。
最初は、6弦琴を奏で、その後13弦の琴に変えて演奏するなんて、なんていう才能でしょう。ちょっとやり過ぎですけどね。
でも、香田さんが言った様に、男が来ないんだから、とやかく言う筋合いではないとは思います。女は一生懸命なんですから。
木枯らしの女 その二
左馬頭の、(艶にあえかなるすきずきしさ)を持つ女へのあまりに美しいイメージに、再度紫式部の文才を感嘆しました。
折らば落ちぬべき萩の露 拾はば消えなむと見ゆる玉笹の上の霰 ですよ~。
この頃雨の日の草の上の露の玉の美しさに気がつき感動しています。露を沢山休ませる草とそうでない草があった事も。
なまめかしく、消え入りそうな艶っぽい色気に対して若い心は無防備ですよね。それが自然ってもんでしょう。
最後に久しぶりに源氏が出てきました。
次回は、常夏の女 その一からです。
源氏物語の中では、重要な章です。皆様お出かけ下さい。
ちなみに、常夏とは、撫子の一品種との事です。ハワイの女ではありません。念のため。
以上【月】に感動した浜岡でした。追加、訂正、ご意見お寄せ下さい
9月17日 例会報告 帚木第七回 香田直子さん
例の「指食い事件」があって、しばらくたった頃です。
賀茂神社のお祭りの雅楽練習が夜遅くまであった日、さてどこに帰ろうと─
能天気な左馬頭は思いを巡らすの。
外は雪がチラホラ、職場に帰って寝るのも辛いし、面倒な女の所にもいきたくないし……
そこで、もうそろそろ「指食い女」の恨みも解けているに違いないと、
のこのこと帰るの。帰ってみると、外の寒さを慮ってか、着物を温めて
今夜こそ帰って来るだろうと待ちかねたようになってるのね。
「わぁーい!やっぱり待っててくれたんだ」と喜びも束の間……
肝心要の彼女の姿がない。いつものおつきの女房共がいるだけなの。
彼女は親の家に「ひきこもり」をしているのです。
何の言付けもなく、彼は「嫌われちゃったのかなぁ─」とか、
「他にオトコでも出来たんかな?」なんぞと、うだうだ悩んだりもするのね。
だけど、中々吹っ切れない左馬頭は「やり直そうよぉ!」ってしつこく迫ったり
してみるのだけど、彼女としてはいくら大好きな彼であっても、
自分だけのオトコじゃなきゃイヤな訳で、なのにお馬鹿さんの彼氏は
彼女の本当の気持ちが理解出来ないのですよ。
で、そうこうしてるうちに、彼女は苦しみ抜いて死んじゃうの。
そして、『結婚するならあの女がよかったのになぁ……』なんぞと、
左馬頭は暗~くなったりしてね。
それに気を使った中将は話を明るい方へ持って行こうとする。
彦星と織姫の長き契りにあやかりたいもの……
「結婚相手を見つけるのはやっぱり大変なことで、
結論なんて、簡単にはでないんだよ」 ってまとめましたとさ。
あの頃のオンナ達は、糸を紡ぎ、染め、織り、縫い……
愛(いと)しいオトコの為に頑張ってたのよねぇ。
ちよっとだけウラヤマシイなぁ─なんて思う今日この頃のワタクシの
いい加減な解釈でした。どうぞ皆さま鵜呑みになさいませんように
御忠告申し上げます。
なおこ様 浜岡はるみ
ほんに、何と自分勝手な男たちなんでしょう。未成熟がそのまま許されるのは、今とあまり変わっていないかも。
でも、それが男の一つの魅力でもあるのですが。彼らも暮らしのために、後見の女たちは必要なんですし。
例えば、指喰い、木枯らしの女を同時に相手にしてたら、その女の性格を理解し、
その幸せが何たるかを想像するのが賢い男ってもんでしょう。
女は成長していきます。変わっていきます。それを可能にするのは男の力でもあると思います。
左馬頭は、若かったんで、複雑な男女間の関係を上手くやるのはまだまだだったんですが
そうこうして、彼も大人になっていったんでしょう。
8月13日例 会報告 帚木第六回 浜岡はるみさん
指喰いの女 その一
左馬頭の、まだとっても若かった時のお話です。
はやう、まだいと下?に・・・・からです。
1)下? :勤めてからの年月が短く、その社会で地位の低い人。〔狭義では、年功を経ない僧を指す〕
⇔じょうろう(ジヤウラフ)【上?】
年功を積んだ上位の僧または、上位の△女官(御殿(ゴテン)女中)を指した語。
〔広義では、身分の高い婦人を指す。「女郎」は、この変化〕 ⇔下?(ゲロウ)
2)あはれと⇒心を動かす程忘れられない
3)すき心 ⇒女に対する好奇心
4)『とまり』と『よるべ』:
『とまり』⇒留まる、添い遂げる
『よるべ』⇒頼みとする妻ではあるが・・・・
5)さうざうしい ⇒あるべきものがなくて寂しい
6)まぎれ ⇒他のもの(女)に興味を示す
7)もの怨じ ⇒嫉妬
8)おいらか ⇒おおらか、おっとり
9)数ならぬ ⇒人の数に入らない、一人前でない
10) 見も放たで ⇒見放さず⇒女の方が身分が上
11) なき手をいだし ⇒無い知恵を絞り
12) くちおしい ⇒取柄の無い
13) みさを ⇒我慢、辛抱して
14) けしう ⇒否定の褒め言葉
15) 憎きかた ⇒嫉妬深さ
16) 心をさむ ⇒納得いく
【まとめ】
左馬頭がまだとっても若かったとき、今でも忘れられない女がいました。彼女は彼より身分が上で、おそらく年上の
様に思われます。若い男は自信があるんです。他にまだまだ良い女がいると思うのです。そんな訳で、彼はその女
を、頼みとはしながらも、他の女たちへの思いを絶ち切れず、いつも女の嫉妬に悩んでいました。
この女は、優れた妻とはいえないけれど、この人のためならと無い知恵を絞って、一生懸命男に尽くし、見栄えの
悪さも化粧して、男にうとまれないよう勤め、男が満足出来る合格妻であったのですが、唯一情深さ故の嫉妬深さが
男にとって最悪であったのです。
指喰いの女 その二
そのかみ・・・・・
1)かみ ⇒当時
2)おじたる ⇒(自分を)恐れている
3)かた ⇒嫉妬
4)さがなさ ⇒口うるささ
5)絶えてまた見じ ⇒もう決して会わない
6)なのめ ⇒いい加減に
7)思ひなりて ⇒考えを変えて
8)われたけく ⇒得意満面(自己の未熟さは意識している)
9)言いそし ⇒まくしたてる
【まとめ】
その当時と左馬頭は回想している。
その女の従順さを深く信じていた彼は、強行な態度で今の関係を脅かすと女が嫉妬する心を改めるであろうと考えて心なら
ぬ芝居を打ったんです。未熟ゆえに、われたけく、ちょっと子供っぽい高めの声で。と思うのですが。
すこしうち笑いて・・・
1)みだてなく ⇒見栄えがしない
2)人数なる ⇒一人前になる
3)あいな頼み ⇒あてにならない望み
4)かたみに ⇒お互いに
5)そむき ⇒別れる
6)きざみ ⇒時
7)ねたげ ⇒妬ましいほど冷静に
【まとめ】
ふふん・・行ってくれるわね。って感じで女が言います。
あらゆることに見栄えのしないあんたが一人前になるのを楽しみに、心変わりを我慢して耐えてきたけれど、当てにならない
望みだったわ。お互いに別れる時が来たようね。と、妬ましい程冷静に言われ、左馬頭は逆上して憎たらしい事ごとを更に
言い放ったその時、女は男の指ひとつ(どの指でしょうか?人差し指ではという意見)を喰いました。女の愛情です・
ねたげとかにくげとか今風の表現が出てきて面白いですね。
おどろおどろしく・・・・
1)かこち ⇒嘆く
2)まじらひ ⇒宮仕え
3)いとどしく ⇒いよいよもって
4)人めく ⇒人になる
5)世をそむき ⇒出家する身になって
6)言ひおどし ⇒言いがかりをつけて
7)あくがる ⇒魂が肉体から出てフラフラする
8)ありく ⇒あちこち移動
【まとめ】
何故だ?痛さとショックで、『こんな傷者になったら、宮仕えだって出来ないし、一人前にもなれないし、出家するしかないか
もしれないじゃないか!』などと言って、『さらば今日こそは限りなめれ!』と言いました。
不思議なのですが、最後にあんたの嫌いなところは、たった一つだけだったよっていう歌を詠んで別れました。。
そうはしたものの左馬頭は、女は今迄とおんなじで変わらないだろうと、たかをくくって、フラフラあちこちして、女から逃げてい
ましす。
以上が8月の報告です。
嫉妬深さは、愛情の一面だっていう事が解るまでは、まだまだの左馬頭です。
年上の女の若い男に対する心の微妙さが、良く解るお話ですね
[
7月16日例会報告 帚木第五回 工藤さん(新人)
今回の女の心変わり、法の師左馬頭、も、面白かったですね。
何事も基本が大事というようなことを、考えさせられました。絵について、唐絵と大和絵についての日本人の
受け取り方の違いなど、また、目からうろこが落ちるような発見がありました。古語の、なつかしき という言葉が
近づいていきたくなるような優しい感じという意味ということが、なるほどーっという感じでした。
というのは、今、私が懐かしいという言葉を使うときに、思い出がよみがえって懐かしいと言うときと、
なんか懐かしい感じがするという郷愁について言うときと、両方あり、なんとなく、自分で不思議だったのですが
もともとの意味がこういうことで、現代の意味になったのかな、などと思い、懐かしいという言葉が自分の中で明確になりました。
唐絵はうるわしだけれども、なつかしくはないということですね、と先生がおっしゃってましたが、
なつかし、の感覚が大事なのかな、と思いました。
前回の甘えた妻の話、私も、本当に甘えた妻なところがあります。妻としてというより、私は仕事のことを
思いました。自分が、会社で何をやりたいのか、要求もせず、勉強もせず、嫌なことがあるとすぐに会社を休んで
そういうことで、周りに、訴えようとしたり、本当に甘えていました。ちょうど、こんなことでは、だめだ、と
心を入れ替えたところだったので甘えた妻、身にしみました。やはり、逃げてはいけないのですよね。
特に、仏もなかなか心ぎたなしとみたまひつべし。
というところがぐさっときました。社会の厳しさは、今も昔も本当に変わらないと思いました。
5月21日例会報告 帚木第三回 沈さん
「葎の門」153頁から始まりました。
(先生が当時の官位の表と瀬戸内源氏の訳のコピーを用意して下さいました。)
左馬頭は若い貴公子たちにこと知り顔に、上調子な女の品定め話に気づいて
話題を変えます。
何といっても新鮮に感じるのは、葎(つる草)におおわれた落ちぶれた家の奥に人
知れず世間から忘れられたようにひっそりと住でいる、可愛らしく美しい人が閉じ
込められたようにいたりすのは、新鮮で、意外で、好き者の心をそそりますなぁ。
没落した老いた父や世をすねた兄なんかがいて、でも家の奥には気位を高く保っ
て暮らしている女がいたりするもんだよ。意外な場所にちよっとした振る舞いにも、
凛とした品格がある女がいるなんてのは、めっけもんでなぁ。
みたいなことを年長らしく、したり顔で話しています。
ここの箇所の「思いあがり」は 気位たかく保っている という意味で、現代とは異
なり、褒め言葉だそうです。
源氏の姿が語られ、育ちの良さが、崩れる一歩手前の、容姿・出自に恵まれた
源氏の、くつろいでいながらもその姿はため息が出るほど美しく、シャレぶりなんか
を描いています。ため息は作者の式部のものでしょうね。エエ男はどんな格好して
もええ男! ほれてますなぁ、式部は源氏に。
実際に源氏はたいそうおしゃれだそうです。女のところへ通うときなんかはとっても
おしゃれなんだって、先生が補足してらした。
「家の主人」(いえのあるじ) 「妻の条件」まで進みした。
坂斉さんが「妻の条件」を読んだのが、何かちょと面白かった。
男に媚びたりせず、「そういう自分は許せなかった」なんて独身談義などが、思わ
ず零れ落ちたという感じで坂斉さんが言葉少なに出たのも、「およすく会ならでは
だね。隣の高見沢さんが「そうなのよ私たち」、という感じで笑ってましたなぁ。
先生は経験からでしょうが「男は馬鹿だから、かわい気に芝居する女に引っか
かるんだわ」なんて男談義を挟んだりしたので、一同深くうなずき、はるみさんが
出席していたら、もっともっと盛り上がっただろうなぁ、って皆おもっていたんじゃない
かなぁ。
女のはかなげな芝居もばれてしまえば、興醒めで、そこのところは年長者らしく
左馬頭は過去の手痛い失敗からか、強調していた。
次回は「167ページ」からです。7月までシルバーセンターの和室がとれています。
人数も増えたことだし、今回のお部屋(1900円)でもいいんじゃない、という意見
多かったので、椅子の部屋ですし、トイレは近いし、狭からず広からずでいいねぇ
ということで、8月からはここを押さえたいと思っています。
はるみ節が聴けないのは淋しいよ。新人も入りましたし、来月も新人が来ます。
次回は元気なはるみさんにお会いできるのを楽しみにしています。元気なお姿も
さることながら、はるみ節がないとあるとでは、大違い。誰でも一人でも欠けると
淋しいね。
4月16日例会報告 帚木第二回 諏訪
今月はイメージで読む源氏物語<桐壺帚木>の巻P139の”中将の幻滅”からはじまりました。
参加者は、天田・今福・香田・沈・高見沢・諏訪
竹中・永田・浜岡・吉田さんにはじめての”くどう”さんの11名でした。
”雨夜の品定め( よき → よろしき → わろし → あし )”
高貴で若い男たちのとまどいの経験理論描写。
否定語・反語に 、二重否定など 振り回されました。
そして女の評価ポイント ”かど(才) と かたかど”
人生経験豊富な熟女たちの休憩時間での会話。
自分たちの人生の経験と照らしてうるさいこと。そして……。
なにやら うなづいた後のみなさんの結論は”男は子供だ” だった。
女性はすぐに母親をやりたがるものだなと再認識しました。
”かたはらいたきこと多かり”
「えっ! かたはらいたしとはそういう意味なの。 片腹じゃないの」
--- うさぎのおいしい山 や ウスが棲む…… 追われて見た赤とんぼ ---
沈光子の報告
「中将の幻滅」から始まりましたが、難しかったですね。
1行目から「女の、これはしもと難つくまじきはかたくもあるかな…」ですもんね。
「…しも」が強調の言葉だんて、知りませんでしたね。
「なん」も強めの言葉だし、いろいろ強調することが多い、中将の女への幻滅を説くには、ぜひ黄泉がえって「およすく会」の女に一度会うことですなぁ。
予習というほどではありませんが、「かたかど」という語彙に悩まされ、????
で先生の講義を楽しみにしていました。
それにこの章は高校生のとき「雨夜の品さだめ」として印象に残っているところです。
高校生の頃には、さわりの部分だけの授業だと思うけど、その後、すぐ夕顔にとんだので、”勝手なことを言いやがって」という印象がいまでも鮮明にのこっています。
それなのに長じて私ったら「かたかど」の下の品の男をつかんでしまい、自分はそれに似合いの下の品の女と、いじけています。
私のことはどうでもよろしい。
源氏は最上の品に囲まれて育っているし、桐壺の幻影を抱いたマザコンの君だから、なんだかんだ言ってもこれから女で苦労するのが、楽しみですねぇ。
女がわからない男には心の平安は訪れないんだから。
「三つの品」1454頁」「耳たたずかしの中の言葉「耳たたずかし」、これ現代でも使えそう。わたしの常套句にしようと思ってます。都合の悪いことはすべて「耳たたずかし」と聞き流す術は、使えます。精神衛生上、この上なく便利。医者いらずになるわ(精神科医)。
3月19日例会報告ー<帚木>第一回
浜岡はるみ
*【ははきぎ】とは、帚草の事だそうです。
5年間の空白の後、源氏は既に17歳になっています。
藤壺への思いは断ちがたく新妻への思いやりの余裕なぞ全く無いようです。
左大臣家の頭中将が、はっきりした形で(P-118の蔵人の少将と同じ人)登場しました。
源氏と中将との微妙な関係が、言葉のそこここに見られます。
今回は【恋文】の文章の、つれづれと・・・が感動的でした。大殿油は、おそらく菜種油を燃やしているぼんやりした光でしょう。
影絵の様に二人の男たちの影が映り、外は雨がしとしと降っている宵を想像出来ます。
恋文は当時の女性にとって自分を表現する大変重要なもので、内容はもとより紙の色や香り、
結び付ける季節の木や花の選択等々大変手の込んだものの様で、若い時からあまりそういう事が上手で
ない私には羨ましいです。
香田なおこ
「忍びたまひけるかくろへごと」
「なよびかにをかしきこと」
「すきがましきあだ人」
「つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵」
なんて綺麗なんでしょう!
改めて古語の美しさ、柔らかさ、優しさ、たおやかさに
感じ入りました。
内容よりも、古語に惹かれてしまいます。
1月15日の源氏読書会断片
* 『イメージで読む源氏物語1桐壷』も終わり近く、<少年源氏の恋>の場面
藤壷に恋をした源氏の気持ちが「常に参らまほしく、なずさひ見たてまつらばや」と書かれている
ことに感じたなおこさん、叫ぶ『私は23年間恋をしてました』。
* <妃と御子>の場面では皆さん「弘き殿の女御、またこの宮とも御仲そばそばしきゆぇ、うち
そへて、もとよりの憎さの立ちいでて、ものしとおぼしたり」(”ものし”は不快の感情を表す)の
文に感じたようで、例のごとく、はるみさんが『弘き殿は鋭い』とつぶやく。『ねたみっぽいひとだ』
きっと職場で弘き殿的いじめにあってるのだろう。弘き殿が出てくると妙に活気づく。母上の介護中を
ぬけだして車でかけつけてくれた久美子さんまでが、『わたし弘き殿のような姑になりたくないもん』
とおっしゃる。現文学少女のぱくちゃんが『私小学校のとき桐壺よんで葵の上に共感してしまった』と
言ったのでびっくり。
すると近寄りがたい美女ライターのさかちゃんが『<光君と聞こゆ><かかやく日の君と聞こゆ>の
”聞こゆ”にほんとうはよくわからないがーーーというパラドックスを感じる』と言う。さすが。
[読書会一覧に戻る]
平成17年8月17日 例会報告 浜岡はるみ
なにがしの院~語らい
この場所は、河原院と言われ、源融(とおる)邸であった場所と言われています。図説9ページ平城京条坊図の17になります。
源融という人は、左大臣で源氏のモデルになった人だそうです。
(822~895)平安時代前期の歌人・政治家
父は嵯峨天皇。河原左大臣と呼ばれた。風流人として知られ、河原院と呼ばれる豪邸には多くの風流人士が集まった。
百人一首【みちのくのしのぶもぢずり誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに】は彼の作品。
豪邸といわれる位広い邸宅で、普通の家の4倍の広さです。
夜明け前の霧が深い中を二人を乗せた車はその豪邸に着きます。
うっそうとした木立が暗くおおいかぶさり、荒れた門にはしのぶ草が茂っている。
源氏は、思わず女を連れ出してしまった事への不安と期待で胸が高鳴っています。
【しののめ】とは、夜明け前の明るさを感じさせるがまだ暗い、まさしく源氏の気持ちを表しています。
【ならひたまへりや】と女に聞く事は、冷静な状態ではありえない失礼な発言ですが、今の源氏は気がつかない。それ程舞い上がっています。自分の過去を問われて女は恥らい、男を信じてきた自分がこれからどうなるか先が見えない身の上の心細さと不安な心を【影や絶えなむ】と歌います。女は恐ろしがっています。でも源氏は女が狭苦しい、ごちゃごちゃした場所から人気もないうっそうとした豪邸に来た事を恐れているとおもしろがっています。二人の気持ちは離れています。
右近は、昔の華やいだ時代を思い出しています。そして、管理人の著しく恐縮する態度、この屋敷が皇室の院と知っていた事から、男が源氏であると確信しました。【この御ありさま知り果てぬ】です。
管理人は、あせっています。源氏の来訪を接待するには人手が少な過ぎるのです。でも、源氏は隠処を求めて来たのですから人を呼ぶ事を禁じます。ただひたすら女との語らいを求めます。
【息長川】万葉集の歌
【鳰鳥の息長川は絶えぬとも君に語らふこと尽きめやも】鳰鳥は息長川の枕詞で、鳰鳥とは、かいつぶりの事。息が長い鳥です。
語らい
日が高く上がる頃に起きました。今日はずる休みでしょうか?今迄上げた事もない源氏が上げた格子の向こうには、荒れ果てた庭が広がり、池も水草に覆われて薄気味わるい所になっていました。ここで今福さんから、平泉にある毛越寺(もうつじ:昔は中尊寺より大きい寺)の平安時代末様式の庭園の事、坂齋さんが平安神宮の神泉苑について話されました。
源氏はまだ顔を隠したままで、二人が初めて出会った、あのたそがれどきの事を歌にして交わします。
ここで、【心あてにそれかとそ見る白露の光そへたる夕顔の花】ページ146の扇の歌を思い出しましょう。
何と二人とも覚えているんです!それで、【露の光やいかに】と言って顔をみせます。自信のある露の光ですね。普通は出来ない!
女が返す歌が【光ありと見し夕顔のうは露はたそがれどきのそら目なりけり】。素直に認めない可愛さです。
でもなんと賢い人達でしょう。私は昔自分が詠んだ歌の一字一句なんておぼえてられない!!!直子さんは?
ところで、後見とはチラッと見ることですが、最近の若い人達は【ちら見】っていうそうです。
ついでに、ページ214の【すごげ】っていうのも今風ですね。
源氏は女の素性に迫まりますが、【海士の子なれば】と頑なに拒みます。
海士に対して【われから】は、海藻などに付着する節足動物の一種で、乾くと殻が割れることからこういう。
和歌では【我から】とかけて用いる。と言う事で知識も深いのです。
語り手の【あいだれたり】は源氏ともあろう者が身分を明かしたのに、素直に身を明かさぬ女は甘え過ぎだと批判的。
ですが、二人は語らい、時間と空間はもう二人だけのものです。(ここにハートマークをずらずら入れたいのですー・・・・)
夕顔の実像について、従来の男の言うままに従うというイメージとは全く違う、自分をしっかり持った自立した女であるという高見沢さんの意見で一致。女から見ても、いとおしいと思える夕顔です。
感想 その1 ソウル在住 沈光子
はるみさん、今月もいろいろ調べましたね。
「源隔」のこと、はるみ講義録で初めて知ったわ。
もちろん、胸キュンの恋のは 覚えありあり 一度や二度の恋じゃないけど。
夕顔は娼婦だ なんて解釈があるんだそうですね。
そういう説を影響力ある人気作家が得々と言うなんて、原文を読んでいないことがバレバレね。
はるみさんの爪の垢でも煎じて呑ましてやりたいわ。ちょっとは真面目に原文を読めよ!ってね。
夕顔と源氏の恋は、それまでの才をきらめかせるようなやり取りではなくて、知的で初々しいわ。
「正しい恋」という感じ。源氏も夕顔も 「青春してる!」
平成17年7月20日 例会報告 浜岡はるみ
板屋の物音~ためらい
八月十五日は、はづきじゅうごや で仲秋の名月の頃です。十六日頃は、十六夜(いざよい)月でもうひんやりと肌寒い頃。
隈なき月影が、板張りの貧しい家々を映し出しています。
源氏が普段は決して聞くことのない庶民の暁時の音の世界。あまりの騒々しさに鶏の声すら聞こえない。
1)隣の家々の賎の男達の心細い暮らしの愚痴話 ⇒通訳がいないとはっきり理解出来ない庶民の言葉でしょう。
2)確の音(恐らく石臼の様な音)連想される【ごほごほ】は雷の音。何時頃から【ごろごろ】になったんでしょうね。
3)砧の音(唐の白居易の詩文集【白氏文集】にある、悲しげな音)
4)空飛ぶ雁の声
5)虫の声々
6)耳元に挿した様にけたたましく響く蟋蟀(こおろぎ)の羽音
⇒こおろぎを変換すると難しい蟋蟀が出てきます。昔はキリギリスと呼ばれていたんですね。
7)御嶽精進する翁の立ったり座ったりが辛そうな声
⇒立ったり座ったりして額を地面に押し付けてお祈りするそうです。
⇒南無当来導師とは弥勒菩薩に帰依する祈りを表します。
こんな騒々しい音に囲まれていては、ゆったり恋を囁く事もかないません。
音は、一度気になると本当に気になります。こおろぎの羽音は本当にうるさいです。
日頃とってもひろーいお屋敷に住んでいる源氏に虫の声はとーくから聞こえるものなんです。まして賎の男達や翁の声をや。
源氏の17歳とは思えない、
月の煌々とした光に照らし出される呉竹、前栽の露に、御嶽精進する翁に対する無常観。
砧の音、長生殿の例(玄宗皇帝と楊貴妃の話)、※翼を交わせる(情愛の細やかな夫婦の例)等の広い知識
※【翼を交わせる】は、桐壺にも出てきたと田中先生がおっしゃったので探しました。
P-76に、翼をならべ、枝をかはさむと契らせたまひし・・・・がありました。
【長恨歌】の中の【比翼の鳥】と【連理の枝】を連想させ、桐壺帝が死んでしまった更衣との死後の世界でも永遠に変わらない愛を
思う場面に書かれていました。
そして、女に対する深い深い思い。女は死ぬまで愛する人から【らうたき人】と呼ばれたいですね。
今度も又作者の素晴らしい才能を思い知りました。
1200年前に書かかれたとは思えない人間洞察。その場その場に描かれたイメージは、まさしく芝居の脚本で
例会まとめ2 沈 光子
p199 板屋の物音
葉月(陰暦8月)の十五夜の月明かりが隙間だらけの板屋へ差し込んで
(部屋の)隅々まで照らしています。住んだことのないような(粗末な)
住まいも(源氏には)ものめずらしい。暁が近いようだ。隣の家々から
目覚めた(あやしき-身分が低い)男たちの声高な(互いに家の壁ごし
に喋る)話が聞こえました。
「ああ寒いなぁ。今年は不作でなりわいもうまくいくいかなくて、自
信がなくなった。田舎へ行くなんて考えられないし、心細いなぁ。北隣
さん、聞いているかい?」
などと言い交わしているのも聴こえます。ささやかなその日暮らしを
支えるために朝はやく起き、ざわざわと 一日の始まりを始める音など
もま近く聞こえるのを、女は恥ずかしがっていました。体裁を繕う女だ
ったら、消え入りたいほどきまりの悪い住まいでしたよ。
でも女はおっとりしていました。恨めしさも、悲しさも、きまり悪さ
も、気にするふうがなく、彼女自身には貴品があって、(これ以上ないほ
ど無粋で失礼な)近所のあけすけな会話の内容も、ピンとこず、わから
ぬようなのが(源氏には)かえって、顔を赤くされるより罪がないよう
に見えました。
ごほごほと雷よりすごい音をさせる唐臼の音が、すぐ寝床のそばで鳴
るように聞こえ、(源氏は)これには閉口しました。(けれどもこの音が)
何の音とは(源氏だって)わからないのです。なんだかわからない不快
な音だ と聴くだけでした。そのほかにもまだ多くの騒がしい雑音が聞
こえました。
p204 ろうたき人
白い麻布を打つ砧のかすかな音もあちこちから聞こえ、空を行く雁の
声もした。秋の物悲しさがしみじみと感じられた。(一転して、美文調)
庭に近い室であったから、引き戸を開けて二人で外をながめるのであっ
た。ささやかな庭にしゃれた姿の竹が立っていて、植木の露はこんなと
ころでも(二条の院の前栽に変劣らず)きらめき輝いている。
虫の声も折り重なって聴こえる。壁の中で鳴くといわれている(ほど
に身近な)蟋蟀でさえも(端がどこかわからないほど広いところに住ん
でいる源氏は)かすかにしか聴いてこなかった耳に、ここではどの虫も
耳に刺し当てたように聴こえ、これはこれで風変わりな情趣だと(源氏
が)思うのも、(夕顔を)一途に思う心が深いからで、どんな欠点でも大
目にみて悪くは思わないのでしょう。
白い袷、柔らかい淡紫を重ねて、華やかではないが、可愛らしくほっ
そりとした女で、きわだってよいというところはないものの、繊細な感
じのする人で、ものを言う様子が可憐で(源氏の思いは)募るのだった。
p206
(当世ふうに)恋の駆け引きをする才気を少しこの人に添えたら(も
っといいのに)と見ながらも、もっとこの人を知りたくて、
「さあ出かけましょう。この近くの心やすい家へ行ってゆっくりしま
しょう。こんな所へ通いたくないんだよ」
と言うと、
「どうして急に、おっしゃるの」
とおおように言って、おっとり女は座っていた。変わらぬ恋を死後の
世界まで続けようと(源氏が夫婦の誓いを)当てにさせると、少しも疑
わずに信じてくれるウブなところは、結婚した経験のある女とは思えな
いほど可憐で、(源氏は)もう誰彼の思わく・世間の体面をはばかること
がなくなり、右近に随身を呼ばせて車を庭へ入れることを命じた。この
家の女房たちも、男が女主人への思いがなみなみならないことと分かっ
ていたので、戸惑いながらも信頼してしまうのでした。
p209 ためらい
明け方近くなってきました。鶏の声は聞こえず、現世利益の御岳教の
信心だろう、(板壁ごしに)老人らしい祈祷の声がし、立ったり座ったり
の気配がする。立ち居が苦しそうである。源氏は(他人ごとととは言え)
身にしむように思え、朝露と同じようにいつ死んでもいいような老いた
人が、この世に何の慾を持って祈祷などするのだろう、と聞いていまし
た。
「南無当来の導師」
と阿弥陀如来を呼びかけています。
「あれを聞いてごらん。現世利益だけが目的じゃないよ(来世への祈
り)」
と(源氏は)共感されて、
優婆塞(修行僧)が行なふ道をしるべに
来世もという深い契りを違えないでね
と一首吟じました。玄宗と楊貴妃の七月七日の長生殿の誓い「比翼の鳥
にならん」は実現されなったけれど、五十六億七千万年後の弥勒菩薩出
現の世までも変わらぬ誓いを(源氏は)したのです。この約束は余りに
大げさですよね(式部の言葉)。
前の世の契りがわかる身の上だから
行く末かのことなんかは頼みがたいわ
と(源氏の深い心にこたえずに)女は返歌しました。(恋にのめりこん
で舞い上がっている源氏とちがい 女は自分を冷静に見詰めている)
女の歌を詠む才に見るように、(女の内側は)実のところ心細いんです
ね(作者の言葉)
いざよいの月(入るのをためらうような)夜に出れば フイッと飛ん
でいって帰らないことがあるということを思い、(女が)出かけるのを躊
躇しているうちに、月も入ってしまい、東の空が白んできました。
人目にたたぬ間にと(源氏は)出かけるのを急ぎ、女の身体を(源氏
が)軽々と抱き抱えて車に乗せると、右近が同乗しました。
光源氏・十七歳、駆け引きもない、「好き」というだけで胸が苦しくなる
恋に殉じています。
上の品の女、中の品の女たちとの恋で、才を競い、またその才が人柄
でもあった時代の源氏。着るものから、香や佇まい、和紙一枚にいたる
まで‥歌からあきらかになる教養も隠しようがありません。
どの恋も真剣で一途でしたが、そして恋が源氏を成長させてもきました
が、ここで初めて彼は駆け引きのない「恋」にのめり込んでいきます。
十五夜の月明かりの中でスポットを浴びているような夕顔との恋が描
かれていました。高見澤さんから、舞台化され得ない「永遠のイメージ
舞台」という感想があり、フーッと深いため息の中でみなさんうなづい
ておりましたです。
あばたもエクボ。どこもかしこも大好き、少しでも長く一緒にいたい・
離れたくなーい夕顔との恋。
六条の女君をさしおいて、板屋の物音なんかものともせずに源氏は夕
顔へのめり込んでいきました。
「あてはかにこめかしく」感じられる夕顔は、上品でおっとりして男に
はあどけなくさえ見える女性。千年後の現代だってこういう女に男はゾ
ッコンでしょう。またここで当時の庶民が登場しています。天皇から上
の品中の品、下の品、そしてここで夕顔を通して庶民の暮しを源氏に垣
間見させています。
式部だって庶民の暮しに明るいわけではないでしょう。でもこういう登場
のさせ方を背景にして、源氏物語の世界に厚みを持たせました。
「板屋の物音」でこれでもかというほど庶民の暮しを源氏へ見せ、一転
「らうたき人」で、これでもかという美文調に展開してましたね。
式部が下の品の庶民の暮しを描くという意外性、深い教養人の式部が
ここで一気に軌道修正という感じが、可笑しかったです。
さあ、この恋の顛末やいかに。
いさよう月にゆくいりなく あくがれむことを、女は思ひやすらい、
とかくのたまふほど、にはかに雲がくれて‥‥ が後の展開に利いてく
るみたいです。
平成17年6月15日 例会報告 浜岡はるみ
どんどん夕顔との恋の深みに溺れていく自分を抑えられない源氏です。
「今朝のほど昼間の隔てもおぼつかなくなど」・・・です。
恋する男と女にとって会えない時間は何と長いのでしょう。
夕顔の源氏のイメージは、
「いとあさましくやはらかにおほどきて、もの深く重きかたはおくれて、ひたぶるに若びたる」
驚くほどに素直で穏やかで、おっとりしていて、思慮深さは今ひとつで、一途に子供っぽく若々しく見える・・です。
女から見ても引かれる様な不思議な人。
やつしの恋
変化 ⇒動物などが姿を変えたもの。 ⇒それで「いづれか狐」なんですね。
身をやつす ⇒上の身分の者が下の身分の者に身を変える。
狩の御衣 ⇒図説P-23 狩衣は、袖口に括り紐があって袖を絞れる。 直衣には紐がない。
わざとらしい程みすぼらしい衣服、いつも皆が寝静まった夜中に訪れ、顔もろくに見せようとしない。まるで昔聞いた、ものの変化の様な素性が知れない、気味悪い男と思うものの、その気配や手触りで身分の高い高貴な人である事がはっきり解る夕顔は、昔高貴なお方(頭中将)を知っていたんでしたね。
惟光の仕業ではないかと疑う夕顔に、知らぬ振りを装う惟光は必死です。源氏とのこの深い結びつきの強さは、二人が乳母児である事から来ています。
源氏は、女が突然何処かへ消えてしまう不安を「いづかたにもいづかたにも」と生々しく思い。世間がどう言おうと二条の院に迎えようとか、女に「染み」きった悶々とした日々が良く現れていますね。睡眠不足で大変だったと思います。
いづれか狐
真夜中、女の家の寝所での二人の語らい
源氏は、女に「聞こえけむ」という敬語を使い、彼女を身分の低い女とは見ていません。
「げに、いづれか狐なるらむな」の「な」は親しみのある音です。「ただはかられたまへかし」は、騙されてしまいなさいよ。打ち解けている源氏の様子がとっても良く解る会話です。
源氏はこの女が頭中将が語った常夏の女と疑っています。面白いのは、通いが途絶えがち「かれがれ(離れ離れ)」になって、他の女に心が移ってしまった方がこの女をもっと客観的に見られ、愛おしさが増すだろう。ですって!!
この思いは頭中将が常夏の女に対する結果としての思いと全く同じではありませんか!!!
何時の世も男は従順な女が好きなんですね。
余談ですが、
穏やかな、おっとりした、時に子供っぽい。そんな女の人が身近にいました!!
天田さんです!!(失礼)。
女から見ても引かれる様な不思議な人。
本当にイメージは一致しています。皆様はどう思われますか?
浜岡でした。
平成17年5月18日 例会報告 浜岡はるみ
夕顔⇒常夏の女
昨年11月・12月の常夏の女を読み返しました。
男(中将)と女(夕顔)の心のすれ違い
中将が、「なにがしは、痴者の物語をせむ」と始めたあの雨の夜を思い出しましょう。
あの時先生は、この痴者とは女の事と言われました。今読み返すと、確かに彼は女の事を痴者と言っていた事が解りました。
彼が涙ぐみつつ話した常夏の女は、その子供を気遣う気持ちはあるものの、彼にとって最終的に「痴者」という事で解決されています。
女(夕顔)が自分の窮地を撫子の花に添えて中将に届けた歌
山がつの垣ほ荒るともをりをりにあはれはかけよ撫子の露
そして最後に男(中将)に返した歌
うち払う袖も露けき常夏にあらし吹きそふ秋もきにけり
今読むと、女(夕顔)の悲しさ、苦しさ、情けなさが痛く感じられます。
前回夕顔の女房が賢く、優れているという話がありました。この強い絆は、中将との別れの後、主従が一緒に乗り越えてきた道の厳しさから培われたのだという事が解りました。なんせ⇒「あともなくこそかき消ちて失せにしか。」 だったんですから。
P-183の
「このほどのこと、くだくだしければ、例の、もらしつ。」
この短い文章の中に、惟光が源氏を夕顔宅に通わせる迄の、ものすごく大変な道のりが隠されていて、一つの物語が出来る程で、
「しひておはしまさせそめてけり。」の【しひて】に彼の大変さが現れています。本当に大変だったんですね。あまりに真面目で、こっけいでもありますが。源氏の方は、変装したり、馬に乗ったり冒険とスリルを楽しんでいる様です。源氏物語絵巻にこのシーンがあったら面白いのに。
改めて、仮名で(女性を対象に)書かれ、時代を超えて読まれ、語り継がれた源氏物語の面白さが解って来ました。田中先生に感謝します。
最後に、やっと買った古語辞典で【きぬぎぬ(後朝)】を調べました
・きぬぎぬ【衣衣・後朝】
二人の衣服を重ねかけて共に寝た男女が翌朝それぞれの衣服を着て別れること。また、共寝をした翌朝の別れ。また、その朝。
やっぱり辞書は必要ですね。
感想
ゆふがほの闇に焦がれし戀一途 なを
隣家と頭中将 例会報告 沈 光子
そうそう、惟光が(源氏の君から)言い付かっている(隣家の)偵察は、すっかり事情がわかるようになっています。
「おんな主人のことはまったくわかりません。世間から隠れ忍んでいるようですが、折々、南の半蔀のある住まいへ渡ってくるようなんです。車の音がすれば、若い女房たちがのぞきみるのですが、女主人らしい方も、こっそりお渡りになるようです。
(女主人の)お顔立ちは悪くなさそうです。
ある日、前駆がして、童女が慌しく
『右近さん、見てみて。中将殿がいま通っていくわ』
なんて言えば、風格のある女房が出てきて
『シッ、静かになさい』
と手で制する
『どうして(中将殿だと)わかったの。見てみましょう』
といって(右近さんが)渡ってくる。簡単に板を渡して行ったり来たりする渡しの橋で、右近さんは急ぐあまりに、衣の裾を引っ掛けて、よろけ、転げ落ちそうになりました。
『悪いのは慌てたわたしじゃなくて、この危ない打橋をつくった葛城の神だわ』
と文句をいって、のぞきの好奇心も醒めてしまったようでしたよ。
中将殿は御直衣姿で随身も引き連れていました。ああ、あの人、この人、と(顔見知りを)数えて、小舎人童を見つけて(やっぱり)中将殿の車に間違いないと、言っていました
とお伝えすれば
「その車を見届けたかったなぁ」(自分なら一目でわかるものを)
と源氏がおっしゃって、もしかしたら(あの雨夜の品さだめの折に頭中将が話していた忘れられない女ではないのか、と思い当たるようでした。
(源氏のお顔つきをみて)惟光は(源氏の君が隣家の女主人のことを)もっと知りたがっているようだと思い
「私めも(自分の)恋をしかけておきました。隣家の様子も隈なく見ています。
(女主人を)仲間の女房にように見せかけてとぼけておりますが、私は騙されたふりをして動き回っています。隠しおおせていると思っているのに、御使えしている女童が口をすべらせ(女主人に対して)敬語を使ってしまいそうになるのをごまかしたりしております」
などと(源氏へ報告して)隣家のようすを思い出してはおかしそうに笑うのでした。
「尼君のお見舞いにいった折に隣家をのぞかせておくれでないか」と源氏はねだるのでした。
下の品への冒険
たとえ仮住まいとはいえ、住居の程度を思うと、これこそ頭の中将が軽く見た下の品だろう、その中に意外な女がいれば思いのほかをかしきことがあるかも、などと思う源氏の君でした。
惟光は主人の源氏の心に沿うべく(隣家偵察)任務に熱心であるが、また自分の好き心からも、手をつくし、あらん限り歩きまわって、ようよう源氏の君は隣家へ通うこととなったのですが、その顛末はくだくだしくは言うまい。(書き手のことば)
隣家の女主人は誰とも詮索しないで源氏を受け入れ、源氏もまた名乗ることなく、むやみと身をやつして(身分を隠し)、とは言ってもいつもと違い、身を入れて熱心に(車にも乗らずに)徒歩で通うのは、並々ならぬ思い入れがあるからのようです。(惟光はその情熱にけおされて)自分の馬に源氏の君をお乗せして、歩いてお供しました。
「隣家の私の通う女にこの徒歩姿をみられたら、恰好悪いなぁ」
とこぼす惟光ですが、(源氏の君は)慎重にことを運び、乳母を見舞ったあの日、夕顔を教えてくれた随身だけ、そして源氏の君の顔を余り知らないような童ひとりをお供にお連れになったのでした。
もし気づかれたら、と(用心して)女の家の隣・惟光の家へ中宿りに寄ることもなさいませんでした。
隣家の女主人も通ってくる男の身のやつしように不安がり、(後朝の使い-源氏からの歌を届けにきた)御使いを暁の道をそっとつけて、それとなく素性を探ろうとするのを、うまくかわしてしまいます。
さすがに哀れでもあり、そうかといって会わずにはいられない、(上の品の自分が下の品の)女にのめりこんでいけば、とんでもないこと、世間に背く軽々しいことだと、思いながらも足しげく通ってしまうのでした。
思いつめる性格の上の品の女、六条へ足が遠のき、源氏は夕顔にのめりこんでいきます。
好奇心旺盛な若い源氏です。夕顔はそれまでの女たちとは異なる魅力にあふれているようです。
あのつれなく袖にした中の品の女・空蝉のように、頑ななところはありません。六条の女君のような身分の誇りが鼻につくようなこともありません。求められれば、どこの誰ともわからないのに、すんなりと受け入れてくれた女でした。
源氏に限らず、男というものは千年まえからこういう女に弱いんだわ。
平成17年4月20日 例会報告 浜岡はるみ
伊予の介と対面す
空蝉を忘れられないでいる源氏の前に、伊予の介が報告に現れます。
彼の妻が忘れられず、苦しんでいる自分、娘とも一夜を契った自分に対して、まじめに実直に報告する伊予の介(大人)を前に自分の不謹慎、後ろめたさを自覚します。
空蝉のつれなさは、しゃくだけれど、伊予の介を思うと良かったと思う17歳の若者である源氏。
旅で日焼けした逞しい首の太い伊予の介と色白く首の細い二人は対照的な絵です。
伊予の介は、妻空蝉を連れて任地に下ると言います。その言葉に激しく動揺し、もう一度会いたいと思う。小君に相談するけれど、もちろん空蝉は会わない。会わないけれど、
心では源氏を慕い忘れてはいない。お互いの心は通じあっていた。
伊予の介は、娘は後見人をつけて置いていくというが、源氏の心は彼女へは動かない。
六条の女君
秋になります。当時は8月8日が立秋。【秋にもなりぬ】の【も】は時間の速さを思わせます。源氏の悶々とした心が継続しています。
とても難しい所で、主語が次々変わります。大殿とは葵上の事。
【源氏が】大殿に絶えま置きつつ、【大殿が】うらめしくのみ・・・【六条の女君の】とけがたかりし・・・【源氏に】おもむききこえ・・・
【語り手が】いとほしかし・・・【六条の女君に】いたくそそのかされ・・・【源氏は】ねぶたげ・・・【六条の女君は】御頭もたげ
六条の女君の女の悲しさが良く現れています。彼女は、前の皇太子の妃であり、非常に高い身分で源氏が敬語を使う程の人です。
しかし、自分が心を許さなかった頃頻繁に通った頃に比べ、最近ではすっかり熱が冷めて訪れる回数が減っている源氏に、改めて二人の年の差(女君24歳・源氏17歳)や世間体を感じ、
彼が訪れぬ夜(夜がれ)には寝られず、【寝覚め寝覚め】ています。リアルな表現ではありませんか。たまの訪れの翌朝には、返したくないのに緊張し焦って帰りをせかせてしまう悲しさ。
前栽の花の咲き乱れる中に立つ源氏を眺め【たぐひなし】と思ったのは語り手ではなく、女君なのではないでしょうか。
中将の君の紫苑色(秋の色)と朝顔の花
源氏は帰りしなに高欄で、六条の女君と別れたばかりなのに、その女房のあまりの美しさに誘惑しようと、歌を送り女房の手を取ったのですが、素早く彼女は源氏の主人へのつれなさをなじる
歌を返します。六条の女君の女房の質の高さを表しています。主人の質は女房の質でありました。更には可愛い(小君の様な)小姓が指貫の裾を朝の露で濡らして源氏に朝顔を折って差
し上げた、絵のような晩夏の朝のシーンです。朝顔は紫苑色だったのでしょうか。
感想
竹中久美子
先日 NHKで「よみがえる絵巻」 十六帖関屋 の画面から。
先生が空蝉の講義の時に 「この後にもあるのよ」言われた事が判りました。
夫のいる女に恋をしてなのめならぬ思いをした源氏
分をわきまえて苦悩する空蝉
のほほんとした、軒端の荻
夫の伊予の介の登場
4人の思いおもいが難解な古語から情景が浮かび上がって来るのも先生の講義のお陰
です。
十六帖 関屋 逢坂で源氏の牛車の行列と空蝉を乗せた車と行き会場面 秋紅葉の彩
りも悲しく
空蝉の切ない歌がありますね。「もののあわれ」ですね。
この巻までも 参加できますよう願っています。
18日は惟光の報告であらたな展開・・・楽しみなのに
(この日は欠席)孫達の帰国で午後から空港に行かねばなりません。体が2
つ欲しい心境で・・残念な、竹中です
香田直子
平安の戀
「後朝のけだるさ春のしどけなさ なを」 →六条の宮
これだけじゃあ、あんまりですよね。
「秘め事は秘め事のまま春愁ふ」 →伊予の介に対して
「朝顔や羅に隠すこころうち」 →女房の女心
平成17年3月16日 例会報告 沈光子
p152 まだ見ぬ御さまなれど、いといとしるく思ひあてられたまへる御そば目を
見過ぐさで、
さしおどろかしけるを、いらへたまはでほどければ、なまはしたなきに、かくわざと
めかしければ
(ここは時間的に、源氏が乳母の家の前から隣家をうかがう場面へ戻っています。
こ
の部分は隣家の女側の視点) (簾ごしにだったので)源氏の姿を見たわけではない
が、はっきりと(しるくー区別・はっきりしている に強めの いと がついてい
る)見当がつく横顔(そば目―横顔)
を(女たちは)見過ごさなかった。(女から先に寄越した手紙が源氏を)驚かしてし
まっ
たが、返事がないまま時間が過ぎて、バツが悪い思いをしているところへ(随身が使
者として)いかにもかしこまって訪れた
あまえて、いかに聞こえむ、など、言いしろふべかめれど、めざましと思ひて、随身
は参りぬ。
(随身の視点) 隣家の者は身の程しらずにもいい気になって(あまえてー現代
と同じ意味で用いられている)(随身が持ってきた源氏の返歌に)どうしようお返事
しなくちゃなどと騒がしくするので、(生真面目な随身は)不愉快になり(めざましー
興ざめ・面白くない)(返歌を待たずに)戻ってきてしまった。
御前駆の松明ほのかにて、いと忍びて出でたまふ。半蔀はおろしてけり。隙々より見
ゆる火の光、蛍よりけにほのかにあはれなり。 (源氏の乗った輿の前をいく)
前駆が持つタイマツのほのかな明かり、ひっそり帰って
いく。(吊り上げてあった)半蔀が下りている。半蔀から透ける隣家の明かりが蛍の
光よりもはかなくもれているのも(暮しぶりがしのばれるようで)心引かれるのであ
る。
御心ざしの所には、木立前栽など、なべての所に似ず、いとのどかに心にくく住み
なしたまへり。うちとけぬ御ありさまなどの、けしき異なるに、ありつる垣根思ほし
いでらるべきもあらずかし。翌朝、すこし寝過ぐしたまひて、日さし出づるほどに出
でたまふ。朝
明の姿は、げに人のめできこえむもことわりなる御さまなりけり。今日もこの蔀の前
渡りしたまふ。来しかたも過ぎたまひむわたりなれど、ただはかなき一ふしに御心と
まりて、
いかなる人の住処ならむとは、往来に御目とまりたまひけり。 目指すところ
(心ざすー心指す)は(庭の)木立や前栽など、よくある屋敷に似ず、ひ
じょうに奥ゆかしく(心にくくー奥ゆかしく)上品に暮している。誇り高くうちとけ
ない(女の)様子など、普通でない格段の気品があるので(けしき異なる)、乳母の
隣家の垣根(咲いていた夕顔)をまさか思い出すなんてことはないでしょうねぇ。
(語り手の言葉)(女の屋敷で過ごした)翌朝、少し寝過ごされて、日が出そうな頃
にお帰りに出てこられた。朝明の姿(女のもとから朝かえっていく姿)は世間の人に
騒がれるのも無理のない(美しい)ものでした。今朝もあの蔀の前を通った。これま
で何度も通り過ぎていらした路でしたが、ちょっとしたやり取り(はかなき一ふしー
手紙をやりとりしたこと)(乳母の隣家)に心引かれて、
往来のたびにどのような女が住むのであろうかと、目が留まってしまうのでした。
惟光、隣家をさぐる
惟光、日頃ありて参れり。「わづらひはべる人、なほ弱げにはべれば、とかく見た
めへあつかひてなむ」など聞こえて、近く参り寄りて聞こゆ。「仰せられしのちなむ、
隣のこと尻手はべる者呼びて、問はせはべりしかど、はかばかしくも申しはべらず。
いと忍び手五月のころほひよりものしたまふ人なむあるべけれど、その人とは、さら
に家のうちの人だに知らせず、となむ申す。時々中垣のかいま見しはべるに、げに若
き女どもの透き影見えはべり。褶だつもの、かことばかり引きかけて、かしづく人は
べるなめり。昨日、夕日のなごりなくさし入りてはべりしに、文書くとてゐてはべり
し人の、顔こそいとよくはべりしか。もの思へるけはひして、ある人々も忍びてうち
泣くさまなどなむ、しるく見えはべる」と聞こゆ。君うちゑみたまひて、知らばやと
思ほしたり。
惟光が数日後(日頃―日が積み重なる 月頃―月が積み重なる)に参上した。「病
気で臥せっている人ははかばかしくありませんので、看病しております。(見たまえ
あつかうー看病する)などと報告してから、(源氏の)近くへ寄って言いました。
「仰せがあってから隣を知る者を呼んで訊いたのですが、要領を得ません。ひっそり
と五月頃に隣家へきた人がいるのですが、素性(その人)は家主にさえ(家のうちの
人だに)
知らせないようにしていると申しております。時々垣根からのぞき見ておりますが、
いかにも若い女たちがいるらしい透き影が見えます。(女の中には)褶らしきものを
申しわけ程度ではありますが(かことばかりー申しわけ程度)(身に着けているので)
使える主人がいるようです。昨日、夕陽がいっぱい差し込んでいたので(なごりなく
さし入りてはべりしに)手紙を書いていた女の顔はとても美しかったです。もの思い
にふけっているように見え、そこにいる女たちも(ある人々も)忍び泣く様子、
はっきりと(しるく)見えました」と言う。源氏は微笑み、もっと知りたいと思うの
でした。
おぼえこそ重かるべき御身のほどなれど、御よはいのほど、人のなびきめできこえた
るさまなど思ふには、すきたまはざらむも、なさけなくそうぞうしかるべしかし、人
のうけひかぬほどにてだに、なおほさりぬべきあたりのことは、このましゅうおぼゆ
るものを、と
思ひをり。「もし見たまへ得ることもやはべると、はかなきついでつくり出でて、消
息などつかはしたりき。書き馴れたる手して、口疾く返りことなどしはべりき。いと
くちおしうはあらぬ若人どもなむはべるめる」と聞こゆれば、「なほ言い寄れ、尋ね
寄らでは、そうぞうしかりなむ」とのたまふ。かの下が下と、人の思ひ捨てし住ひな
れど、そのなかにも、思ひのほかにくちをしからぬを見つけたらばと、めづらしく思
ほすなりけり。
世間の評判が(おぼえこそ)大きいお方だけれど、まだお若く、人々がちやほやす
ることを思えば(めできこえーちやほや)(源氏がただの)堅物だったらさぞかし物
足らなく感じることだろう(すきまはざらむもー堅物の態度だったら)。世間が相手
にしないような恋をする資格がないように思われる(ひとのうけひかぬほどにー相手
にしないような)男でも、こと恋愛に関しては好奇心に駆られるものだ(さりぬべき
あたりーさありぬあたり→女のことに関して)、と惟光は思うのでした。「素性がわ
かるやも知れないと、ちょっとした機会をつくって、手紙をやりましたら書き馴れた
達者な文字で素早く(口疾く返りことー詠み口がはやい)返歌がきました。それほど
悪くはないそこそこの若い女房たちがいるようです」(と惟光が申し上げると)「ど
しどし手紙を書いてやってくれ。(主の素性が)わからないのでは物足りないじゃな
いか(そうぞうしー物足りない)」とおっしゃる。(雨夜の品さだめで中将が言って
いたように)下の下の品の、問題にもしなかったような(人の思ひ捨てし住まい)意
外なところなんかで意外に趣きある人を(くちをしからぬー
くちおしくない→満足する)みつけたら、新鮮でワクワク(めづらしくー新鮮)する
だろうなぁ、と思われるのでした。
P152冒頭部分、源氏が乳母の家の門前で輿の中にいたときへ時間が戻り、隣家
の女たちの視点で語られ、すぐに隣家へ返歌を届けにきた堅物の随身の視点に変わり、
そして台本のト書きのような客観描写になります。 わずか5行の文章から時間処理・
視点の変化を読解するのは難しいですねぇ。正直なところ解説抜きでは理解できませ
んでした。はるみさんが「芝居の脚本のよう」と言っていましたがホント台本のよう
です。
松明を先頭にした輿の中から源氏が隣家からほのかにもれる灯りをみながら帰ってい
くのを、客席から観ているような感じです。蛍よりはかなげな隣家の灯火という描写
が、乳母の隣家の女性「夕顔」との恋の行方を暗示しているようです。
この頃、足しげく通っていた六条の屋敷の様子が、夕顔の家と比べるように描写さ
れています。若い源氏にとって、六条の女性はすばらしいけれども、きゅうくつで気
のぬけない恋人だったかもしれません。
さて人がほめそやすという源氏の「朝明の姿」というのが出てきました。 「朝帰
り」なんて陳腐で使い古された言葉がかもす隠微なものは微塵もないそうです。
先生が「くれぐれも誤解のないように」、と念を押しておりましたです。朝もやの中
を恋人に後ろ髪を引かれる憂いに包まれて帰っていく、ただただ美しい源氏の君の
「朝明の姿」を、しかしですねぇ、想像したくても下の品の人生と色恋の経験不足の
まま齢を重ねた者には難しいですなぁ。
何事にも堅苦しい随身とあけすけな夕顔の女房たちの対比。源氏の性格や好みを知
り尽くした惟光が、隣家の様子を源氏へ報告する内容も、的確にポイントを抑えてい
ます。
惟光は政ごとでも恋でも、いい仕事してるんでしょうねぇ。
まだまだ感想はありますが、「およすく会」のメンバーそれぞれが引き続き「一言
感想の書き込み」することになりました。(いつ誰が決めたって? 3月の例会後の
席でそのように決まりました。長いものは時間をとられて困るけど、一言ならという
多数意見により決定です)多数って誰とだれでしょう? 皆様、バトンタッチ!
平成17年2月16日 例会報告 浜岡はるみ
夕顔 その2 P-139
病気見舞い
1) 阿闍梨 ⇒弟子を教える高層
2) 参河の守 ⇒頭領 遠方から来た人
3) わたりつどう ⇒寄り集まる
4)かくおわします ⇒源氏が思いがけずに訪れた
5)またなきこと ⇒予想もしていない
6) かしこまる ⇒恐縮する
7) たゆたふ ⇒躊躇する
8) 忌むこと ⇒仏の道、戒律
9) 日頃 ⇒長い間
10) おこたり ⇒病気が治る
11) 嘆きわたる ⇒ずっと心配していた
12) 世を離るるさま ⇒出家姿
13) 命長くて ⇒長生きして
14) 位高くなど ⇒偉くなる、出世する
15) さてこそ ⇒そうしてこそ
16) 九品の上 ⇒図説国語P-406 上品上生
九品(くほん)⇒仏教の極楽浄土での9の階級
上品上生(じょうぼんじょうしょう)、上品中生(同ちゅうしょう)、
上品下生(同げしょう)
中品上生(ちゅうぼんじょうしょう)、中品中生(同ちゅうしょう)、
中品下生(同げしょう)
下品上生(げぼんじょうしょう)、下品中生(同ちゅうしょう)、下品
下生(同げしょう)
17) 生まれたまわめ ⇒生まれ変われますよ
18) うらみ ⇒執着、こだわり
【まとめ】源氏の乳母すなわち惟光の母への見舞いの場で乳母の病状はかなり
重い。
まず、あの世とこの世について。この世とあの世がはっきりしていて、出家
はその間を渡るための修行に入る意味を持つ。
乳母は既に尼僧の姿になっている ⇒仏の世界に非常に近く入って修行して
いる ⇒重病である
大勢の身内たちが遠方から寄り集まり、重苦しい雰囲気の中に、源氏の君
が思いがけず現れその場が明るく輝きます。
予想もしない出来事に皆恐縮し、重病の尼君も起き上がり、「源氏の君にお会
いしたく、尼になるのも躊躇した自分であったが、この様にお会い出来たのは、
仏の道を守ったお陰で、お会い出来た今はただ阿弥陀仏のお迎えの光を心清く
待つばかりです。」と弱弱しく泣きます。それに対し、17歳の若者とは思え
ない源氏のお見舞いの言葉は、「長い間病気がちで思わしくないと聞きずっと
心配していました。この様な尼姿にお会いするとはあわれで残念でたまりませ
ん。長生きして、私がもっと偉くなっていくのを見て欲しいです。そうしてこ
そ極楽浄土で上品上生の位に生まれ変われますよ。この世にこだわりを残す事
は悪い事だと聞きます。」と源氏も涙ぐんで乳母を励まします。
乳母の年齢は? おそらく30~40歳
いよいよ重態になったらお寺へ連れて行き、仏の傍に置く。
P-142 かたほなる~
1) かたほ ⇒不出来、不完全
2) まほ ⇒優秀
3) 面だたしう ⇒面目が立つ、晴れがましい
4) なづさう ⇒なついて
5) すずろに ⇒自分がコントロール出来ずに、はしたなく振舞って(一言言っては泣き、
又一言言っては泣く状態)
6) そむきぬる ⇒(この世)を捨てる
7) ひそみ ⇒ゆがむ ⇒べそをかく
8) つきじろい ⇒互いにつつき合う
9) 目くわす ⇒目配せする
【まとめ】見舞いの場での乳母の表情とそれを見つめる子供達の表情
語り手が、今の乳母の気持ちを説明して、
不出来な子であっても、乳母というものは呆れる程優秀な子とみなすもの。ま
して源氏のような完璧な人を育てた晴れがましさと源氏が自分になついて育て
た昔が肥大化し、わが身が哀れに、もったいなく、かたじけなく思え、自分を
コントロールする事も出来ない位高揚し、べそをかいた様に源氏の前で泣く母
を見て、子供達は、母がまだこの世に未練があってこのように泣いていると、
はしたなく感じ、なりふりかまわぬ母を非難し、お互いをつつきあったり目配
せしあったりする。
このシーンは、特に映像的で映画を見ている様ではありませんか。
P-143 君はいとあわれと~
1) いはけ ⇒幼い の稚児的表現
2) 思ふべき ⇒母、祖母
3) うち捨てて ⇒死に別れる
4) なごり ⇒その後は
5) はぐくむ人 ⇒育ててくれた人
6) 思いむつぶる ⇒安心出来る
7) またなくなん ⇒他にいない
8) 人となりて ⇒成人した後は
9) 限りあれば ⇒自由な身でなくなり
10) 朝夕にしも ⇒一緒に暮らしていても
11) とぶらい ⇒訪れる
12) さらぬ別れ ⇒避けることが出来ない別れ 死に別れ
13) なくもがな ⇒あって欲しくない
14) おしのごい ⇒涙をぬぐう
15) げによに ⇒まったく実際
16) おしのべたらぬ ⇒並々ならぬ
17) 身宿世 ⇒幸運な人生
18) もどかし ⇒非難がましい気持ちで
【まとめ】源氏の乳母への思いやりの気持ちとそれを聞いた子供達
源氏はそんな取り乱した尼君に同情し話し掛けます。
「幼い時に、母や祖母に死に別れた後の私を育ててくれた人達は沢山いたけ
れど安心出来た人は貴女以外にはいませんでした。成人した後は自由になれる
時が少なく一緒に暮らしていてもお会いする事も出来なくなっていました。心
のままにお伺いした事はなかったけれど、長くお会いしないと心細く感じてい
たのに、死に別れなどはしたくはございません。」と涙ぐみながら話します。
涙で濡れた袖に焚かれた源氏の香が狭い部屋に満ちて、(香は濡れると良く臭
い立つ)、その香の流れの先に先程まで母親を非難がましく見ていた子供達が見
えてきます。全くこの様な立派な源氏を育てた母は幸運な人生であったと、改
めて母の胸中を思い涙ぐみます。
此処も映像的ですね。香りが子供達の方に漂い新たなシーンを導きます。
夕顔 その2 P-146
扇の歌
1) 修法 ⇒病気平癒を祈り加持祈祷で、ごまを焚く
2) またまた ⇒やれる事は何でも
3) 掟て ⇒命じる
4)紙燭 ⇒図説国語P-18 簡単な紙の蝋燭
5)もてならす ⇒使いならす
6) おかしう ⇒美しい字で
7) すさび書き ⇒きちっとした文字でなく、流れる様にきままに書く
8) 心あてに ⇒推測すれば
9) それ ⇒源氏の君
10) 白露の光 ⇒光源氏の事
11) そこはかとなく書きまぎらはしたる ⇒誰が書いたか解らない様に筆跡を変えて
12) あてはか ⇒気品がある
13) ゆゑづく ⇒奥ゆかしい
14) 思いのほか ⇒身分の低そうな小家の
15) おかしう ⇒気が利いて風流な感じで惹かれる
16) 問い聞きたりや ⇒聞いたことがあるのでは?
17) 思うたまへあつかい ⇒思って必死で看病していた
18) え ⇒不可能
19) はしたなやか ⇒そっけなく、体裁悪く、つれなく
20) 憎しとこそ ⇒けしからん
21) 思いたれな ⇒思っているんでしょう
22) ゆゑ ⇒理由、訳
23) 宿守 ⇒隣家の管理人
【まとめ】乳母の見舞いを終えた源氏は、さっきの扇を思い出し、暗い中紙蝋
燭をかざして眺め、隣家の住人を惟光に尋ねる
乳母の病気平癒のための祈祷等とても17歳とは思えない指図などをてきぱ
きして外に出た源氏がふと思いついたのが、先程女童子が渡した扇。惟光に紙
蝋燭を持たせて扇を眺めると、使い慣らされた移り香の人を引き付ける深い香
りの扇には、風流に、流れる様に書かれた歌が。「当て推量ですが貴方様はもし
や夕闇に白い、夕顔にも光を添える光源氏様?」誰が書いたか解らない様に筆
跡を変えて流れる様に書かれている文字にも奥ゆかしく気品があり、身分が低
そうな子家の女に引かれていく源氏。そこで惟光に「この西の家はどんな人が
住むか聞いた事があるか?」と尋ねれば、惟光は、「又始まった。例のごとき女
の事かいな」と、心には思ったがそうは言わず、「この5,6日は此処には居た
ものの、病人を必死で看病していたので隣のことなど聞いておりません。」とそ
っけなく答えると、惟光の心の中を読んで、「私の事をけしからんと思っている
んだろう?でもこの扇の持ち主は私を光源氏と知って歌を詠みかけてきている
んだよ。私に何か言いたい事があるに違いない。この辺りに詳しい者を探して
聞きなさい。」と言えば、惟光は隣家に入って管理人の男の子を呼んで聞いた。
P-149 揚名の介なる~
1) 揚名の介 ⇒身分、お金、収入もない名ばかりの地方次官 裕福な者がお金を納めてな
る名誉職
2) こと好み ⇒派手好み
3) はらから ⇒兄弟姉妹
4) 来通う ⇒良く通って来る
5) ななり ⇒どうもそうらしい 推量
6) したり顔 ⇒得意げに
7) めざまし ⇒興ざめ 身分が高い者が低い者にいう 桐壺の更衣の事 ⇒いとめざま
しからぬ際には・・・
8) 際 ⇒身分
9) さして ⇒自分を指して
10) 憎からず ⇒可愛く
11) 過しがたき ⇒気になる 放っておけない
12) 例の ⇒いつものように
13) このかた ⇒この方面
14) 重からぬ ⇒軽々しい、慎重でない
15) 心 ⇒性質、癖
16) あらぬさま ⇒別の書体で
17) 見め ⇒見なさい 命令
18) ありつる ⇒先ほどの
【まとめ】燐家の内容が少し解り、相手は宮仕え人と推測し、がっかりしつつ
も書体を変えて畳紙に返歌を書いて届けさせる
惟光が、「揚名の介という人の家で、男は田舎に帰っていて、妻というのは若
く派手好みで、兄弟が宮仕え人でよく出入りしているとの事ですが下人の宿守
の言う事は当てにはなりません」と言う。ははん。と思う源氏。それならばそ
の宮仕え人に違いない。得意気に歌を詠んで来た訳だ。相手はまともに付き合
う品の相手ではないとがっかりしたのですが・・・
自分を指して名を聞いてきた可愛らしさは放ってはおけない。此処で語り手が
登場して、いつものようにこの方面では軽々しい性質ですが。と言う。畳紙に
書体を変えて書いた歌、「もっと近寄って私が光源氏かどうかはっきり見たら
如何?貴女がほのぼの見た私の夕顔のような花を」を先程の随身に持たせる。
一般的に女から男に歌を詠む事は少ない。
反歌の文化レベルの高い事!!
それかとも見め ⇔ それかとぞ見る
花の夕顔 ⇔ 夕顔の花
たそがれ:誰そ彼 夕暮れ時で誰が彼か判別出来ない位の暗さ 逢魔が刻
との違いは、たそがれのほうがちょっと明るい。
平成17年1月19日 例会報告 沈光子
夕 顔
夕顔の小家
六条あたりをさかんに忍び歩きしていた頃のこと、(源氏が)内裏から(仕事を終えて)お帰りになる途中、女の所へ行くにはまだ早い時刻なので、中宿(時間つぶし・小休止)に、重病で尼になって(仏の加護を求めて)いる大弐の乳母を見舞いたいと思い、五条あたりに家があるらしいので、探しさがして尋ねておいでになりました。
御車を入れる正門が閉まっていたので、従者へ言って惟光(源氏と乳兄弟でここは惟光の実家)をお召しになり、(惟光を)お待ちになる間、雑然とした五条の下町の様子を(車の中から)ご覧になると、乳母の家の隣に、新しく編み直した檜垣をめぐらし、上部半蔀(格子)をずっと四・五間ほど上げ、簾も真新しくして白いのが(下がっていて)涼しげで、その簾ごしに美しい額つきの(美しい顔つきの女たち)がこぞってこちらを見ているのが、(御車の簾ごしに)透けて見えた。
(簾ごしに見える女たちが)動き回る(上半身の)動きから(見えていない)下半身を想像してみると、(源氏の目線と家の構造の関係で)むやみに背が高いように見える。いったいどんな女たちなのだろうかと、風変わりに感じられた。(今日は忍び歩きの予定もあり)御車もつつましいものにしているし、前駆けの先触れもさせないで来たので、(自分が)誰とも知られることはないだろうと、気楽な思いで御車からもっとよく(この家の中を)見ようとした。
門は蔀というものであろうか、(庇のように)押し上げてあり、一目で(家中)総て見えてしまうほどの構えの住まいなので、(初めてみる)貧しげな住まいをあわれに思ったが
世の中はいづれかさして わがならむ
息とまるをぞ宿と定むる
(と古歌に詠まれた歌は本当だなぁ、行き着いたところを住まいとすればいい、世の中どこも仮の宿なのだから)玉の台(お屋敷)だって同じことだと思う。
P135
きりかけ(目隠しの板塀)らしいところへ、青々とした蔓が伸びのびと這っており、白い花がニッコリ微笑むように咲いている。
うちわたす遠方人にもの申す
われそのそこに白く咲けるは何の花ぞも
(源氏が)古歌を呟くと、警護の御随身が(さっと)膝まづいて
「あの白い花を夕顔と申します。花の名は人並ですが、このような卑しくみすぼらしい垣根なんかに咲くのでございます」
と申し上げる。
本当にその言葉どうり貧しげな小さな家ばかり並ぶあちこちに、今にも壊れ崩れそうな軒のつまなどに、(蔓が)這って(花が咲いて)いる。
「貧者を彩るという気の毒な花のさだめだね。一房手折ってきなさい」
と(源氏が)おっしゃると、押し上げてある蔀の門から入って(従者は花を)手折った。
P137
ちょっとしゃれた造りの遣戸口から、黄の生絹の単袴を粋に着た愛らしい女童(メノワラワ)が出てきて、従者を招いた。
強く香をたきしめた白い扇を差し出し
「この扇へ載せて差し上げなさい。枝もなくて不恰好な花ですから」
と言って渡したそのとき、乳母の家の門が開いて惟光の朝臣が出てきたので、(夕顔を載せた扇は)惟光から源氏へ手渡された。(惟光の身分の方が先の従者より身分が高いので、ちょうど折りよく? 出てきた惟光が源氏へ扇を手渡した)
「鍵の置いたところを忘れてしまって、たいへん失礼いたしました。ものの区別もつかない(下の品)者たちの住むこの辺り、雑然としたむさくるしいところへお待たせしてしまいました」と恐縮して申し上げた。
御車を邸内へ引き入れて(源氏は)お降りになられた。
今年初めての例会は待ちに待った「夕顔の巻き」に入りました。遠いむかしに古文の授業で少しはかじったはずですが、イヤハヤ、夕顔の冒頭から圧倒されてしまいました。
「夕顔」ってこんなに美しい場面から始まったったんだったっけ?
上の品の女しか知らない源氏の君は中の品の女・空蝉に出会い、その魅力にのめり込みました。中の品の人々や暮らしぶり、身分を超えた苦しい恋そして女から拒絶される経験によって人間的な成長をしています。
さて、空蝉との恋に傷ついてばかりはいられません。六条あたりをしばしば訪れているらしい17歳の源氏は、この頃また新たな恋をしているのでしょう。
内裏から下がった源氏は女のところへ行く時刻まで、病に臥せっている乳母を見舞おうとして五条へやってきました。この時代は病についた人が尼になるのは「病状が重く、仏のご加護を得るためです」と先生から補足があり、乳母が快復が難しい病床にあるということがわかりました。
五条あたりと見当をつけて乳母の家を探し尋ねてきた源氏は、乳母の家の正門が開くのを待つ間に、貧者の家々などが雑多に建ちまざった下町を、仔細に眺めます。話に聴いたことはあっても、なにもかもが初めて目にする下の品の暮らし。六条あたりに盛んに通っていたとは言っても、暗くなってから通い、陽が登るまえに女の家から帰っていくので、これまでは見えていなかったのでしょう。
好奇心いっぱいの源氏は乳母の家の隣家に目を留めます。乳母の家に比べればはるかに見劣りする貧者の構えながら、こざっぱりした暮らし向きが窺える佇まいに眼が留まったのでしょう。真新しく編み直した檜垣や新しくした簾が、上の品の源氏の君にもくっきりと涼しげに見えます。
暑さをしのぐために半蔀の上部をずっと引き上げているこの家の中からも、車を止めている源氏の御車を見ている女たちの姿が簾ごしに透けて見えます。
「額つき」が美しいという女性への表現は、当時の女性たちが扇や着物の袖などで顔をおおって見せないところから、顔の中で唯一他人の目にさらされる額の美しさが、容姿の決め手になったからだそうです。額つきが美しいというのが「美人」の条件だとか。現代でも風邪や花粉の季節になると、マスク美男・マスク美女が増えるのにどこか似てますなぁ。
源氏は家の中をもっとよく見ようとして目をこらし、一瞥できる慎ましい住まいに驚きますが、所詮この世は仮なのだからという当時の無常観で、御殿であろうと同じことだと思ったりします。(早くに母を亡くした源氏は母親の実家という後ろ盾がなく、苦労人なのよ、と先生が補足)17歳の源氏の好奇心・素直な感性や無常観。だからこそ心にかなう女性を求める思いもひとかたなぬものがあったのでしょう。
まっ昼間でもなく、かといって宵までには少し間のある時間、乳母の屋敷隣りのつつましくこざっぱりとした佇まい。青々とした蔓と「おのれひとり笑みの眉ひらけたる白い花」。
垣根をはさんだ好奇心いっぱいの互いの視線が簾ごしに交錯しています。
源氏がお車の中で呟いた一言を聞き漏らさずに、膝まづいて応えた従者の教養。黄色の単袴を着た女童の髪が肩にかかる立ち姿の美しさ。主の香を強くたきしめた扇。手折られた夕顔。なにもかもが一服の絵のようでため息がでる場面です。
吉田さんから女童の着ていた「生絹」は、繭糸を構成する蛋白質を除去していないものとの解説がありました。袴なのでゴワッ・パリッとしたシルクなのでしょう。また蒔絵のモチーフにこの場面が多く描かれていることに、改めて気づいた驚きなどが語られました。
乳母の屋敷の正門が開くまでの短い時間を描いた異空間のような夕顔の冒頭の、一字一句をうかうかと読みとばしてしまうと、夕顔の巻の世界を贅沢に味わうことはできませんでしたね。
夕顔冒頭の幻想的な時間と場面から、乳母の家へ入る展開の役回りとして、現実的で無粋な惟光が登場し、源氏へ扇を差し出します。
式部の筆のさえ、おみごと!
吉田さんからの補足
「黄なる生絹(すずし)の単(ひとえ)袴」について、簡単にふれておきます。
生絹(すずし)を辞書で見たら、以下のようでした。
「軽くて薄い絹織物。精練しないのが特徴。」
精練は、お話ししましたように、
絹の繊維の周りのたんぱく質をアルカリ性の溶液で溶かして、表面をやわらかくして光沢を出す工程です。
精練すると、絹にトロ味がでて、つややかになります。
精練しない糸を織った布には、張りがあり、シャキシャキした風合いになります。
袴は、布にはりがないときれいな形がでないのでよく未精錬の糸を使います。
また、精錬しない糸の自然の色は、黄色味のあるベージュなので、
ここでいう「黄なる」というのは、黄色に染められたものではなく、染織していない自然の色を言っている可能性があります。
なお、単(ひとえ)の袴は、夏のいでたちです。
以上から、豪奢な袴ではなく、比較的質素で控えめな、さらりとした袴のイメージが浮かびあがります
12月15日 例会報告 空蝉最終回 朴文順
しのぶの薄衣(P121)
(源氏は)小君(を)、御車の後にて、二条の院におはしましぬ。ありさまのたまひて、をさなかりけりと、あはめ(=なじる)たまひて、かの人(=空蝉)の心を、爪弾きをしつつうらみたまふ。(小君は源氏が)いとほしうて、ものもえ聞こえず。(源氏が)「いと深う憎みたまふべかめれば、身も憂く思ひ果てぬ。などか、よそにても、なつかしきいらへばかりはしたまふまじき。伊予の介に劣りける身こそ」など、心づきなしと思ひてのたまふ。ありつる小袿を、さすがに御衣の下に引き入れて、大殿籠れり。小君を御前に臥せて、よろづにうらみ、かつはかたらひたまふ。「あこは、らうたけれど、つらきゆかりにこそえ果つまじけれ」と、まめやかに(=真面目な顔で)のたまふを、(小君は)いとわびしと思ひたり。(源氏は)しばしうち休みたまへど、寝られたまはず。御硯急ぎ召して、さしはへたる(指し延へ=わざわざ用意する)御文にはあらで、畳紙(=懐紙)に、手習のやうに書きすさびたまふ。
うつせみの身をかへてける木のもとに なほ人がらのなつかしきかな
と書きたまへるを、(小君は)懐に引き入れて持たり。かの人もいかに思ふらむと、いとほしけれど、かたがた思ほしかへして、御ことづけもなし。かの薄衣は、小袿のいとなつかしき人香に染めるを、身近くならして、見ゐたまへり、
源氏は小君を車の後ろに乗せて二条院(自邸)に帰った。そこで先ほどの経緯を小君に説明して、おまえは子供だなあと(不首尾を)なじり、空蝉のことを非難しうらめしく思う。そんな様子をみて小君は源氏がかわいそうで、何も言うことが出来ない。「(空蝉が自分のことを)大層憎んでいるようで、この身が疎ましい。どうして、(男女の仲でなくとも)他人としてでもよいからやさしい返事をしてくれないのだろうか。私は伊予の介にも及ばないのだろうか」と不愉快に思って言う。(持ち帰った)あの薄衣を、それなのに、自分の衣の下に抱いて眠る。小君を傍らに臥せさせていろいろと恨み言を言ったり語らったりする。「おまえはかわいいけれども、あのつらい人(空蝉)の縁の人だから、さいごまで仲良く過ごすということはできないな」と真面目な顔をして言うのを小君はとてもせつないと思う。源氏は少し休むのだが寝付けず硯を持ってくるように言いつけて、わざわざ用意する紙ではなくて、懐紙に手習いのように気分に任せて書き付ける。蝉が身を変えてしまった木の下にはもぬけの殻が残るように、やはりあの女の人柄がなつかしくいとおしい。と書くのを小君はさっと懐にしまう 。人違いで一夜を過ごしてしまったもう一方の女もどうしているか気にかかるけれども、いろいろ思い返して何も連絡を取らない。例の薄衣の小袿にはたいそう懐かしいあの人の香りが沁みこんでいる。それを肌身離さずもってじっと見ている。
ここは主体が源氏/小君と入れ替わりが激しいのですが、「おはす」「のたまふ」「たまふ」「大殿籠る」「召す」などの尊敬語で主体が自ずとわかるので、流れるようなテンポの文章にもついていけます。
あこ=吾子で「わが子」やわが子のようにかわいがっているものに対する呼び名。源氏は小君に出会ったころから、とてもかわいがってこのようによんでいます。
最後の身近くならして、見ゐたまへりの部分の「ゐる」は「~しつづける」という語ですが、たんに「見たまへり」ではなくて「見ゐたまへり」となると源氏の女君への思い入れが感じられます。
うつせみの心(P125)
小君、かしこ(=紀伊の守邸)にいきたれば、姉君待ちつけて、いみじくのたまふ。「あさましかりしに、とかう(=とかく)まぎらはしても、人の思ひけむことさりどころなきに、いとわりなむなき。いとかう心をさなきをかつ(且つ、一方)はいかに思ほすらむ」とて、はづかしめたまふ。(小君は)左右に苦しう思へど、かの御手習取り出でたり。(女君は)さすがに、取りて見たまふ。かのもぬけを、いかに、伊勢をの海士のしほなれてや(★)、など思ふもただならず、いとよろづに乱れて、西の君も、ものはづかしきここちしてわたりたまひにけり。また知る人もなきことなれば、人知れずうちながめてゐたり。小君のわたりありくにつけても、胸のみふたがれど、御消息もなし。あさましと思ひうるかたもなくて、されたる(=戯。大人びた、ませた)心に、ものあはれなるべし。つれなき人も、さこそしづむれ、いとあさはかにもあらぬ御けしきを、ありしながらのわが身ならばと、取りかへすものならねど、忍びがたければ、この御畳紙の片つ方に、
うつせみの羽に置く露の木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな
小君が紀伊の守邸に行くと、姉が待ちつけていて大層しかりつける。「とんでもないことだと考え付くこともなくて、物事はいろいろうまくごまかせても、他人が疑う心からは逃れようがない、本当に困った人だこと。こんなに子どもで思慮がないのを源氏はどうお思いになるでしょう」と一方的に責め立てる。小君は源氏と姉に挟まれて苦しく思うが、源氏の書いたあの文を取り出すと、そうは言っても姉君もそれを取って見る。あの自分が残した衣を伊勢をの海士の脱ぎ捨てた衣のように思っているのだろうかと思うだけでも平静でいられず、たいそう心乱れた。一方人違いされた西の君も、なんとなく恥ずかしい気持ちがして女君の寝所から自分のところへ帰った。源氏とのことは知る人もいないので、ひとりものおもいにふけっていた。小君が邸内をうろついているのを見ては、胸が塞がれるが、手紙も来ない。とんでもない人違いだったということには気づくはずもなく、捨てられたのかもなど思いあわれである。空蝉も冷静に振舞っているようには見えるが、決して浅い気持ちではない源氏の様子を思い(伊予の介と結婚する前の、父も元気な頃の)昔の話であれば、と思っても取り返すことの出 来ない過去であり、どうにもならず源氏の歌を書いた懐紙の隅に
うつせみの羽に置かれた露が木の葉に隠れて見えないように、私も人目に隠れて泣いています。と綴った。
★この部分は鈴鹿山伊勢をの海士のすて衣汐馴れたりと人やみるらむ (鈴鹿山というのは伊勢にかかる枕詞で、意味は「伊勢の男の海士が脱ぎ捨てた衣は汗で濡れている、とあなた(恋人)は思うのでしょうか」)という歌がもとになります。ちょっと調べてみました。「後撰和歌集」の伊尹朝臣作のこの歌には題名があって「女の許にきぬをぬぎ置きてとりに遣はすとて」とありますから、女の処を去るときに自分の衣を置いてきてしまった男がそれをとりに使いを出すのに持たせた手紙なのでしょう。ちょっと唐突なような気がしたのですが、ちゃんと恋の歌なんですね。自分の脱ぎ捨てた衣を源氏が持っていると知って、この歌がぱっと思い浮かぶような教養のある女性が、後見がなくておちていった悲しさが感じられます。
さすがに、取りて見たまふ。の「さすが」は帰ってくる小君を待ち構えて叱責するもののやはり源氏への想いが隠し切れないせつない空蝉の心情がよくあらわれています。
西の君もまさかこの恋が人違いだったとは露もしらず、源氏のことを想っているのが人知れずうちながめてゐたりの「ゐ(る)」に表れているように感じました。
「空蝉」の章はこの和歌で終わるのですが、終わりの「かな」という感嘆の助詞が章全体に響き渡っているようです。
朴文順
11月17日 例会報告 空蝉第4回 朴文順
人違へ
君(=源氏)は(寝所に)入りたまひて、(女が)ただひとり臥したるを心やすく
(=安心する)おぼす。床の下に二人ばかりぞ臥したる。衣をおしやりて寄りたまへ
るに、ありしけはひよりは、ものものし(=どっしりした感じ、大柄な)くおぼゆれ
ど、おもほしも寄らずかし。いぎたなき(寝汚し…睡眠を貪る、めざとくない)さま
などぞ、あやしくかはりて、やうやう(=だんだん、次第に)見あらはし(=正体が
わかる)たまひて、あさまし(=驚きあきれる)く心やまし(=相手の言動で傷つ
く)けれど、人違へとたどりて見えむも、をこ(=愚か)がましく、あやしと思ふべ
し、本意の人(=空蝉)をたづね寄らむも、かばかりのがるる心あめれば、かひな
う、(空蝉が自分(源氏)のことを)をこにこそ思はめとおぼす。(先ほど覗き見し
た)かのをかしかりつる火影(の女)ならば、いかがはせむ(=どうしようか→構わ
ないだろう)におぼしなる(「おぼす」+「なる」なので~という気持ちになった、
気持ちを転換させた)も、わろき御心浅さなめりかし。
(女は)やうやう目さめて、いとおぼえずあさましきに、あきれたるけしきにて、
何の心深くいとほしき(=相手にいとおしい、と思わせる)用意(=気配り、心遣
い)もなし。世の中(=男女の仲)をまだ思ひ知らぬほどより(=にしては、~の割
に)は、さればみ(=ふざける、戯れる)たるかたにて、あえかにも思ひまどわず。
われとも知らせじ(=自分が源氏であるということは知らせまい)と思ほせど、いか
にしてかかることぞと、のちに思ひめぐらさむも、わがためにはことにもあらねど、
あのつらき人(=空蝉)の、あながちに(=無理に)名をつつむも、さすがにいとほ
しければ、たびたびの御方違へにことづけ(=口実にする)たまひしさまを、いとよ
う言ひなしたまふ。たどらむ人(=気のまわる人)は心得つ(=見抜く、わかる)べ
けれど、まだいと若き心地に、さこそさしすぎたるやうなれど、えしも思ひ分かず。
憎しとはなけれど、御心とまるべきゆゑもなきここちして、なほかのうれたき(=い
まいましい)人の心をいみじくおぼす。いづくにはひまぎれ(はふ+まぎれる…逃げ
込む)て、かたくなしと思ひゐたらむ、かく執念き(=強情な)人はありがたきもの
をとおぼすにしも(=強調)、あやにくに(=おかしなことに)まぎれがたう思ひい
でられたまふ。
空蝉が源氏の気配を感じて出て行ったとは知らず、源氏は寝所に忍び込みます。床の
下にはおつきの女房が二人寝ているのですが何も気づきません。衣を押しのけて近寄
るとかつての空蝉の気配とは違いずいぶんどっしりしているし、こんなふうに近寄っ
てもまだ眠りから目を覚まさないような女のはずはない、とだんだんこれは違う女だ
ということに気づきます。空蝉がまたしても逃げてしまったことに驚き傷つきます
が、こんなにまでして逃げる女を捜し求めても無駄だろうし、愚かな男だと思われる
だろう。ここに寝ている女が先ほど垣間見た空蝉の義理の娘であれば、それも構わな
い、という気持ちになっている源氏を作者が「けしからぬ軽々さだ」と言っていま
す。女はだんだん目が覚めて隣に男がいるので呆然としているが、男女の仲にはまだ
不慣れなような割には、変に男に慣れているようでもあり、恥らうこともなく、源氏
が愛おしいと思うような態度では全然ない。このような女に自分が源氏であるという
ことは教えないでおこうとは思うがどうしてこのような事態になったのかと後になっ
て女が思うとき、自分のことはさておき、空蝉にまで考えが及んでしまっては、可哀
相なので「方違えを口実にしてあなたに愛に来たのだ」とうまく取り繕って言い含め
た。気の回る人はことの真実を見抜いてしまうだろうが、源氏がみるにこの女はまだ
幼く、でしゃばっているようでも少しも物事をわかっていない。この女が憎いという
わけではないが気持ちが惹かれる理由もない気がして、やはりあのいまいましい空蝉
のことを想ってしまう。どこぞに逃げ隠れてしまい、源氏のことを愚かでみっともな
い男だとあざ笑っているのだろうか、このように強情な人はめったにいないと思うに
つけても、おかしなことにほかの人に気持ちが動くことがない。
目当ての空蝉には逃げられてしまい、悔しい、うらめしいと思いながらも目の前にい
る中の品の女と比べて逃げる女が気にかかってしかたがない源氏ですが、気持ちが入
り乱れながらもこの空蝉の義理の娘にも手を出してしまう源氏を作者は「けしから
ん、軽々しいさだこと」と揶揄しているのがおもしろいです。
------------
西の御方と
この人の、なま心なく(=屈託がない)若やかなるけはひもあはれなれば、さすがに
(=そうは言っても)情々しく(=情愛深く)契りおかせたまふ。「人知りたること
(=公認の仲)よりも、かやうなるは、あはれも添ふこととなむ、昔人も言ひける。
あひ思ひたまへよ(あなたも私のことを思ってくださいよ)。つつむこと(=人目を
憚ること)なきにしもあらねば、身ながら(=我ながら)心にもえまかすまじくなむ
ありける。また、さるべき人々(あなたの家族、周りの人)も許されじかしと、かね
て胸いたくなむ。忘れで(私のことを)待ちたまへよ。」など、なほなほしく(=陳
腐な、平凡な)かたらひたまふ。(女が)「人の思ひはべらむことのはづかしきにな
む、え聞こえさすまじき」と、うらもなく言ふ。「なべて、人に知らせばこそあら
め、このちひさき上人(=小君)に伝へて聞こえむ。けしきなく(=何事もないよう
に)もてなしたまへ」など言ひおきて、かの脱ぎすべてしたると見ゆる薄衣を取りて
出でたまひぬ。
小君近う臥したるを起こしたまへば、(小君は源氏が気がかりでいたのだが)うし
ろめたう思ひつつ寝ければ、ふとおどろきぬ(=目を覚ます)。戸をやをら押しあく
るに、老いたる御達の声にて、「あれは誰そ」と、おどろおどろしく問ふ。わづらは
しくて、「まろぞ」といらふ。「夜中に、こはなぞありか(ありく=歩き回る)せた
まふ」とさかしがり(=世話好きがって)て外ざまへ来。いと憎くて(=癪に障っ
て)、「あらず(=なんでもない)。ここもと(=ちょっとその辺)へ出づるぞ」と
て、君を押し出でたてまつるに、暁近き月、隈なくさし出でて、ふと人の影見えけれ
ば、「またおはするは誰そ」と問ふ。「民部のおもとなめり。けしうはあらぬ(=か
なりのものだねえ)おもとのたけだち(=背丈)かな」と言ふ。たけ高き人の常に笑
はるるを言ふなりけり。老人、これ(=民部の御達)を連ねてありきけると思ひて、
「今、ただ今、立ちならびたまひなむ」と言ふ言ふ、われもこの戸より出でて来。わ
びし(=困る、閉口する)けれど、えはた押しかへさで、渡殿の口にかひ添ひて、隠
れ立ちたまへれば、このおもとさし寄りて、「おもとは、今宵は上(=主人空蝉のと
ころ)にやさぶらひたまひつる。(私は)一昨日より腹を病みて、いとわりなけ(=
大層耐え難い)れば、下(=召使の休む処)にはべりつるを、人少ななりとて召しし
かば、昨夜まうのぼり(=参上る…参上する)しかど、なほ(=やはり)へ堪ふまじ
くなむ」と、うれふ(=愚痴る)。いらへも聞かで、「あな腹々。今聞こえむ(=ま
た後で)」とて過ぎぬるに、からうして(=やっとのことで)出でたまふ。なほかか
るありきはかろがろしくあやふかりけりと、いよいよおぼし懲りぬべし。
この女の屈託もなく若い様子もあわれで、そうは言っても情け深く交わる。契りの後
で「公認の仲よりもこのように忍ぶ仲の方が情感も増す、と昔の人も言っています。
あなたも私のことを想ってくださいよ。人目を憚ることがないわけでもないので、我
ながら自分の気持ちだけにまかせることができない。またあなたの家族にも許しては
くれないだろうと前から胸を痛めていました。けれど私のことを忘れないで待ってい
てください」と陳腐な繰言をいう源氏に女は「他人がどう思うかと考えると恥ずかし
くてしかたない。こちらから手紙を書くということはできません」 と、源氏の言葉
をすっかり信じて無邪気に応える。「色んな人に知らせるというのは困るが小君に手
紙を言付けてあとは何事もなかったようにしていなさい」 と言って源氏は空蝉の残
したと思われる衣を持って部屋を出て行く。小君が近くで休んでいたのを起こすと、
源氏が気がかりでいながら寝てしまった小君は目を覚ます。戸を開けると、老いた女
房の声で「そこにいるのは誰だ」と、騒がしく尋ねる。小君は面倒臭くて「私だ」と
答えると、「こんな夜中に何故うろつきまわっているのか」と世話好きがって外へ出
てくる。小君は癪にさわって「何でもないよ。ちょっとその辺に出るだけだ」と言っ
て源氏を押し出すと月の光がくまなく射して人影が顕わになったので女房は「またそ
こにいるのは誰じゃ」と聞く。答えを待つ前に女房は「民部のおもとだね。あなたの
背丈はかなりなもんだこと」と言う。背が高い女性をからかっている。この女房は小
君が民部の女房を連れ立っているのだと勝手に思いまだ背の低い小君にむかって「も
うすぐ、すぐ、あなたもこれくらい大きくなるわよ」と言いながら戸の外に出てく
る。小君は閉口してしまうが、押し返すこともできないで、源氏は渡殿の口にぴった
りと張り付いて隠れていると、この女房は寄ってきて「おもとは今晩はご主人(空
蝉)のところにおつとめだったんですね。私は一昨日からお腹が痛くて大層耐えがた
かったので下に下がっていたのを、人が少ないというので昨夜参上したのでけれどや
はり耐えられないの」と愚痴る。そして返事も聞かずに「ああお腹が。また後でね」
と言って去っていったのでやっとのことで出ることができた。やはりこのようなそぞ
ろ歩きは軽率で危ないと身に沁みて思い懲りたにちがいない。
なほなほしくという言い方に全ての事情を知っている作者の揶揄が感じられます。
かの脱ぎすべてしたると見ゆる薄衣を取りて出でたまひぬ。という源氏の行為は前回
の部分の(空蝉が)生絹なる単を一つ着て、すべり出でにけり。という部分と呼応す
ると思うのですが、源氏が他の女との情事のあと、やはり想いをつのらせている本意
の空蝉が残していった抜け殻をもって部屋を出て行くその場面が目に浮かびとても美
しいシーンであると同時に、「空蝉」という名前の意味を本当に考えさせられまし
た。そもそも「うつせみ」という言葉は「現身」からきているので、奈良時代までの
意味としては「この世の人、世間。世間の人」ということでしかなかったのですが、
蝉の抜け殻という「空蝉」という意味が転じて「はかなさ」になったようです。この
場面ではまさに空蝉が残していった衣がはかない命の蝉の抜け殻として表現されてい
るようにも感じられ数多登場する女性のそれぞれのネーミングにも感心させられまし
た。
朴文順
10月20日 例会報告 空蝉第3回 沈光子
小君、たばかる
源氏は(覗いていた場所から)渡殿の戸口へ戻って(小君を)じっと待った。小君は源
氏をこんなところで待たせたのを申しわけなく思い
「たまたま(例ならぬ人―いつもは居ない人→西の方)訪問者がいて、近づくこともでき
ませんでした」
と言えば
「今宵もまたつれなく(あなたーあっち)帰そうっていうのかい。あんまりだよ、辛いじ
ゃないか」
と、(二人の女を盗みみていたことはおくびにも出さずに)源氏は小君へあたってみせ
る。
「いいえそんなつもりはありません。(などてかー反語・否定)(西の方が)あちらへお帰
りになったら、お二人の仲立ちをいたします(たばかりはべりなぬー男女の逢引の算段を
する)」
と小君はきっぱりとこたえる。小君ならうまくやるだろう、子供だが人の様子など落ち
着いて観察・判断できる奴だと源氏は改めて思う。碁が打ち終わったのか、衣のすれる音
(うちそよめくーちょっと着物がすれる音)がし、人々があちこち散っていく(あかるる
けはい
ー散りじりに別れる)気配がする。
「小君はどこにいらっしゃるの。この御格子を閉めてしまいましょう」
と、さっき小君が叩いて開けさせた戸をガタガタさせている。
p104
「寝静まったみたいだ。入ってうまくやってくれよ」
と源氏がおっしゃる。小君は、女君の気性が融通の利かない真面目一方なので、逢引の
算段を相談することもできず、女房たちが下がっていなくなったら源氏を案内しようと、
思う。
「紀伊の守の妹もこちらにいるのか。覗き見させてくれよ」
なんて源氏がおっしゃるので
「そんなことできませんよ。格子には几帳が添え立ててあります、見えるはずないじゃあ
りませんか」(小君は応え)
そのとおり、と思うものの源氏は可笑しくてならない。すでに盗み見てしまったとは言
うまい、自分のために奔走してくれているのだから、(小君をからかってみただけ)と思
う。
夜がふけていき、供も連れずに留守を狙って忍び入る心もとなさを、(まだ若い)源氏
は小君へもらしたのだった。
もぬけ
小君は、今度は妻戸を叩いて開けさせて入った。みな寝てしまったのか、しずかだ。
「この障子口で僕は寝ましょう。風通しをよくしてよ(戸を閉め切らないでね)」
小君はそう言って、薄縁をひいて身体を横たえた。女房たちの多くは東の廂の間に寝て
いるらしい。先刻、妻戸を開けてくれた童も東の廂の間へ横たわって寝てしまったので、
しばらく寝たふりをしていた小君は、灯りがもれてくる方向へ屏風を広げて(明かりを)
遮ぎり、暗くなったところで源氏を導いた。源氏は、どうなることか(いかにぞ)またバ
カを見るのではないか(をこまがしきー愚かバカ→悪い予感で心配)と思い、気後れもし
て(つつましけれど←人に気づかれはしないだろうか)導かれるままに、母屋の几帳を引
き上げて、そっとそーと入ろうとするものの、静まった夜に、お召し物の衣擦れの音はま
さしく「源氏ここにあり」とはっきりさせる印なのであった。(いとしるかりけりーはっ
きりするのだった)
p107
女宮は、(音沙汰のない源氏が自分のことを)忘れてくれたようなので、嬉しいことと
強いて思い込もうとするのだが(思ひなせどー強いて思うのだが)、あの夢のような源氏
とのひと時を忘れられない。ぐっすりと寝ることができず(心解けたる寝だにー心からぐ
っすりと)、昼はもの思いでぼんやりし、夜は眠れずに悶々としているので、春ならぬ木
の芽(この眼)も、休まることがない。
(夜は寝覚め 昼はながめにくらされて 春は木の芽もいとなかりける
一条摂政御集)
恋に身をやつして憔悴している女宮だが、その一方で碁打ちの相手をしていた西の方は、
「今夜はこっちに泊まるわ」
とにぎやかにくったくないお喋りをして、眠ってしまった。若い西の方は無邪気にぐっ
すりと寝ている。
かすかな衣擦れ、高貴な香を感じた女宮は、顔を上げ、薄衣のかかった几帳の隙間、
そこは暗いが、女宮が感じる密かな気配は、まちがいなく源氏のお召し物の衣擦れ、
高貴な香だった。
女宮は反射的にすばやく起き上がり、生絹の単衣を羽織って寝所を抜け出たのだった。
女宮は源氏との夢のようなひと時が忘れられずに、夜は眠れず、昼はぼんやりと過ごし
て恋情に苛まれる日々を送っていました。源氏を頑なに拒みつづけながらも、恋の炎は鎮
まることがないのでした。恋の炎に身をやつした覚えなどは多々ある「およすく会」の皆
さまがた、「身を焦がす」とはまさにこの女宮の状態を言うのだわ、と古傷を思い出して、
女宮もどきの切なさで久々に胸の奥底を痛めた描写でしたね。
恋に身もだえする女宮だからこそ、源氏が忍んで来た気配をいち早く察知したのです。
紫式部は前の場面で中の品の女房たちの衣擦れの音を源氏に聴かせておいて、ここで源氏
の最高級品の衣のかすかな衣擦れの気配を、女宮に気づかせます。
恋する女宮がハッとして顔を上げる場面、恋焦がれている女だからこそわかるかすかな
気配を、女宮のうつむいた顔を上げさせて、みごとに描いています。
源氏はごわごわの絹を着ていたのではありませんし、源氏ならではの香は、蚊取り線香
なみにドーンと鼻をへし折るような匂いではないんですね。微かな気配、かすかな香り、
灯りの届かない暗がりに眼を凝らして、女宮はピンと来てシャンとすばやく寝所を抜け出
したんだわぁ。
寝静まった寝所の中に描かれた、激しく恋する女の研ぎ澄まされた五感。あでやかな西
の方
を登場させた碁打ち場面から展開させる、鎮まりの中の、緊張・ドラマ性。どれもこれも
計算し
つくされた小説展開です。
小説的計算だけでここまで周到に描けるでしょうか? 式部は天才的な文学的感性で登
場人物を動かしたのでしょうか?
女宮がハット顔をあげて源氏の気配を感じる「衣擦れ」と前の場面での碁打ちが終わっ
て女たちが動き散る気配をかもす「衣擦れ」のみごとな対比に脱帽しましたです。先生が
「なんかこの場面が大好きなの」とおっしゃっていましたが、納得!
紀伊の守の妹を盗み見したいから渡りをつけてよ、なんていって小君をからかったり、
もっと女を見ていたいけれど、小君に見られたら恥ずかしいと後ろ髪引かれる思いで好奇
心を押さえたり、源氏の茶目っ気や人柄、若々しさがコミカルに描かれていていましたね。
源氏って 仰ぎ見るくらいステキ だけじゃなくて カワユイ って 感じがしました。
女宮が寝所を抜け出たことを知らない源氏が近づいてきます。次回が楽しみですねぇ。
平成16年9月15日 例会報告 空蝉第2回 沈光子
源氏は小君にわがままを言って、女宮に会うために再び紀伊の守邸へ忍び込んでいます。
紀伊の守が伊予へ赴任した留守に乗じてうまくことを運ぼうとしています。
碁打ち
紀之守邸は主が留守のため、女房たちに中の品らしい隙・気の緩みがある。
源氏が身をひそめた東庇の格子は開けたままになっている。女宮は、昼から訪れている
西の方(紀伊の守の妹・女宮には義理の娘になる)と碁をさしているという。盗み見よう
として、源氏は開け放たれている格子に近づいてく。
格子の際に立てられているはずの屏風も端の方が畳まれており、上の品の家ではありえ
ないことだが、暑いからと身を隠すべき几帳も垂れ上げてあって、源氏の潜んでいる東庇
の格子のところから、奥まで見通せた。明かりが人の近くにともされており、まず寝殿の
中央の中柱の側に、横を向いた恋しい女宮が眼に入った。濃い赤紫の綾の一単衣がさねを
着ているようだ。はっきりはしないけれど何か羽織っており、(彼女は)髪が豊かではな
いのか頭が小さく、小柄でどうということのない容貌をしていた。女宮は差し向かいにい
る義理の娘へも顔を見せない(慎重な慎み深い)振る舞いをしている。痩せた指先がほん
の少し袖口からのぞいていた。
東向きに座った西の方(女宮からは義理の娘になる)はといえば、源氏からは丸見えだ
った。白い薄ものの単衣、淡い藍の小袿のようなものをしどけなく羽織って、紅のはかま
の紐を結んだ際まで胸をはだけるように、無造作に着崩している。色白で美しく、身体つ
きはぴちぴちと丸みがあり、すらりと上背もあって、豊かな髪は長くはないが二つに分け
て顔から肩にかかるのが美しく、総じて容貌に不足ない美しい人に見える。親はこの娘を
世に比類ないと自慢に思っているだろうと興味をそそられる。(この女に)しとやかさを
添えてやりたい、と(源氏は)ふっと思ったりした。この女は才気があって、碁の勝敗へ
きびきびと反応して騒々しい。女宮がしとやかにゆったりと
「お待ちなさいよ、そこはいっしょでしょう。こちらにあなたの勝ち目がありますよ」
などど言っても
「いいえ、今度は負けました。隅のあちこち数えなくては」
と指を折り、
「十、二十、三十、四十」
などど点数を数える様子に、(源氏は)伊予の湯桁の数を数える姿を連想してしまう。
(西の方の父親の赴任先の伊予と、伊予の湯の湯船はたくさんあるのをかけている)
西の方はくったくなくさばさばとして魅力的だが、そうぞうしく優雅さが足りない。
かたちくらべ
女宮はといえば、(西の方とちがって、そこまでしなくたってと思うほど大げさに)
口元をおおって(義理の娘へも)はっきりと顔を見せない。(だが)眼を凝らしてじっ
と見つめていると、しだいに容貌がはっきりしてくる。
眼がはれぼったいようだ、鼻もすっきり筋が通っているというでもない、老けてみ
える。艶やかに美しいところなども見えず、一つ一つ上げてみれば、どちらかと言え
ば醜い方なのに、(上の品の)身だしなみを取り繕って、晴れやかな容貌の西の方より
たしなみがあるので、(容姿は不足でも)誰しも眼が引き付けられてしまうだろう。
p99
(西の方が)若々しく華やかな愛嬌で機嫌よさそうにくつろいで、笑い崩れたりし
ているのも、それはそれで魅力的である。我ながら(西の方にも心が動くのが)軽々
しいとは思うものの、お堅い一方というのではない(源氏の)心は、西の方へも捨て
がたい魅力に思ってしまう。
これまで(上の品の)女たちは、打ち解けて心通わせることがなく、取り繕い、他
人行儀で(そばめーそっぽを向く)あった。このように天真爛漫・素直でくったくな
い女の様子を垣間見ることなど、なかった。盗み見られていると知らない(女たちを)
で、くっきりと見てしまうのは気の毒だ、もっと見ていたいけれど、小君が(のぞき
見しているのをみられるのも恥ずかしいことだ)来るような気がして、源氏はその場
を離れた。
小君の手配で紀伊の守邸へうまく忍び込んだ源氏は、上の品では考えられない偶然が重
なって、碁打ちをしている二人の女を盗み見します。暑い夏とは言え、中の品の紀伊の守
の留守宅は女房たちの用心が緩んでいて、外からの眼を遮る戸や屏風、几帳までがまくり
上げられていました。
髪が豊かでなく、身体は小さく貧弱。鼻筋もすっきりとしたところがなくパッとしない
と、源氏は恋焦がれている女宮の容貌について「ちひさき人の 痩せ痩せにて 鼻なども
あざやかなるところなうねびれて にほはしきところも見えず」「あざやかなるところな
うねぎれて」と 彼女はいがいと老けてるよ、なんて容赦の無い冷静な観察をします。
眼を転じて、碁打ちの相手をしている西の方へも観察の眼を向けます。
ピチピチした姿態、腰紐あたりまで緩めた胸元からのぞく若々しさ。色白で体格がよく、
髪も豊か、くったくのないあっけらかんとした喋り口。才気も感じられ明るい性格に好感
を持つ。少し品がないものの、捨てたもんじゃない。
「つぶつぶと肥えて まみ口いとあざやかに すべていとねじけたるところなく」
「なほ静かなるけをそへばや」(上品な気配を持たせたい)
向かいあって碁を打つ二人の女をかわるがわる観察する描写が生き生きしていますね。
かたちくらべ で恋しい女へのヒイキ目の観察がないのは、源氏が女宮の容姿に魅力を感
じていたのではなく、中の品の後妻という身分でありながも、かつて身につけた上の品の
居ずまいやたしなみ・教養と高貴な精神を持って毅然と生きていることに引かれているか
らでしょう。
それにしても女を観察する眼は冷静かつ鋭い。紫式部は、若々しく華やかな美しい西の
方と、容姿は劣るが上の品の教養を身につけた女宮と、対照的な二人の女に碁打ちをさせ
て、源氏に覗き見させました。二人の女の美しさと欠点は、向き合っている対照的な相手
によって照射されています。欠けているものを向かい合う相手が持っている、というこの
二人の配置は見事ですね。
夜を迎え、女たちが衣擦れの音をさせながら引き上げていくと、 華やかでにぎやかだ
った碁打ちの場面から、寝所のシンとした静けさに展じていきます。
平成16年8月18日 例会報告 空蝉第1回 浜岡はるみ
帚木の巻は突然終わり空蝉になったわけですが、時間は同じなのに何故タイトルが変わるか?
それは、新しい登場人物として、女君の名である空蝉と彼女の義理の娘が登場するからだそうです。
帚木の巻最後の言葉・・・とぞ。が巻の終わりを表わしています。
それぞれの夜
源氏の深い挫折感からスタートです。
【源氏は】寝られないままに、「私はこのように人に憎まれるのに慣れていない(ならはぬ)のに、今夜初めて情けない・つらい(憂しと)男女の中(世)を思い知り、人に合わせる顔がなく(はづかし)死んでしまいたい(ながらふまじくこそ)と思うよ」などと言うと、【小君は、源氏が可愛そうで】涙まで流して横たわっています。源氏はそんな小君を大変いとおしく(いとらうたし)思う。思わずそっと触れた小君の細く小さい手、あまり長くない髪に逢瀬の夜握った女君の華奢な手と少ない髪の手さぐりの感覚が姉に良く似ているのも(さまかよいたるも)、気のせいか(思いなしにや)とまた女君を恋しく思う。女君が嫌がっているのに強引に(あながちに)引っかかって(かかずらう)つきまとって(たどり)寄ったが、体裁が悪く(人わろし)、心の底から(まめやかに)目を覚まさせる程(めざまし)の挫折感で眠れないまますごし、何時ものように(例のようにも)、【小君に】言いつけたりそばに置かず(のたまひまつはさず)、真夜中にひっそりと(夜深う)一人で紀伊の守低を出て行く源氏を小君(この子)はいとおしく、淋しく(そうぞうし)と思うのでした。
拒否される事の無かった今迄の人生の中で始めて経験した挫折感と体裁の悪さに自己嫌悪に陥り真夜中に紀伊の守邸を後にする源氏の苦しさが語られています。今回の話題として
1)ホモセクシュアル
この源氏と小君の関係を男同士の性的な関係に観る読み手(翻訳者)がいるそうです。そういう視点で読むと思わず触
れた手と髪のシーンがそれなんでしょうか。自己嫌悪で深夜に一人で帰って行く男にそんな気持ちはないと思いますし、小
君は源氏にとっては弟のような存在であると思います。またそんな話だったらこんなに長い年月読み続けられては来なかっ
たでしょう。
2)人わろし
周囲の人を気にする事、人に悪く思われる事で大変重要な言葉です。
諏訪さんから、日本は大陸や色々な国から流れて来た人々が作ったいくつもコミュニティーから構成されていた。その組
織を上手く運営するために常に周りを意識した関係作りが必要であったためそれが習慣・文化となったのではないかとい
うお話があり。
3)階級制
源氏が帝の子供で、女君が中の品の女という位置関係でしたら、絶対紀伊の守に妻を差し出すよう命令出来る様に思
います。時代劇の悪代官はたいてい可愛い百姓娘を自分の物にしてしまいます。しかし、平安の男と女の歌を交わし合
う対等な関係にはその様な権力の横行はないようです。深夜にひっそり出て行く源氏の姿は痛々しいです。
4)美人
女君の髪は少ないのですが、これはあまり美人でないという表現だそ
それぞれの夜 その2
女君の心の葛藤
女も言い表せない位(なみなみならず)、源氏ともあろう方を突っぱね大恥をかかせた自分に対して平静ではいられないのに、【源氏】からは何の連絡もぷっつりなくなって(絶えてなし)しまいました。かたはら ⇒ そばにいる人 いたし ⇒ 心苦しい
懲りておしまいになられたのであろうと思う。このまま(やがて)知らん顔して(つれなくて)【恋】が終わって(止みたまい)しまったら【源氏は】さぞかしつらいだろう。ましかば・・・まし ⇒ 反実仮想
かといって強引に(しひて)嫌な(いとほしき)【源氏の】振る舞いが続くのも自分にとってはもっと嫌な(うたて⇒うたた)事だ。適当な時に(よきほどに)終わりに(閉じめ)しよう。 てむ ⇒ 強い意志
とは思うものの(から⇒逆説)心の迷い(ただならず)で、物思いがち(ながめがち)な女君であった。
三度挑戦(みたびちょうせん)
この題は、先生がつけたそうです!
源氏は自分に対してとった女君の振る舞いが不愉快でたまらない(心づきなし)と思いながらもこのまま引き下がる気にならない(かくてはえ/止むまじう御心にかかり)。面目をつぶされ(人わろく)自分が情けなくにっちもさっちも行かない位苦しんで(わびて)、小君に「とても辛く、腹立たしく(うれたう)、【女君を】強いて忘れようと思うけれど(しひて思ひかえせど)心はそうはいかない(心にも従わず)から苦しいんだ。良い時を見て【女君に】会えるよう(対面すべく)どうにかしなさい(たばかれ)。」と【小君に】ずっと言い続ける(のたまい・わたる ⇒わたるはその状態が続く事 【その事は小君にとっては】わづらわしいけれども、こんな恋の橋渡し(かかるかた)でも【自分を】傍に置いて下さる(のたまひまつはす)事は嬉しく思われた。幼いながらどんな時が良いかと待ち続けていた。(待ち・わたる⇒状態が続く)そこへ紀伊の守が国に下り(お供の男たちが大勢いなくなり)、女だけ(女どち)で警護の手が薄く気の緩んだ(のどやかなる)【屋敷へ】
夕闇の道(暗くなって月が出る前)の足元が暗い(たどたどしげなる)頃にまぎれて我が(小君)車にて【屋敷へ】お連れ致します【という小君に源氏は】この子も幼くどうなるのか心配と。でもそのようにのんびり(のどむ)待っていられない気持ちなので、目立たない姿(さりげなき姿)で門限の前(門など点さぬ⇒門に棒を点す)にと急ぎ紀伊の守邸をめざします。
逢魔が時(おうまがどき)⇒日没後月が出るまでの時間で、魔物が出没する時間。香田さんから
またまた来ました紀伊の守邸
人の居ない門(人見ぬかた)から【車を】引き入れて、【源氏を】降ろしました。子供(童⇒元服前の髪型)なので夜勤の番人(宿直人)なども特別念入りに調べ(ことに見入れ)たり、お愛想(追従)する事もせず、心配なく入れました。東の妻戸に【源氏を】立たせ、自分【小君】は南の隅の間から格子を叩いて大声で叫んで(ののしりて)【自分に人の注意を向けさせ源氏が見つからないよう】中に入ります。御達(女御達)が「丸見えですよ(あらわなり)」と言った。「何故こんなに暑いのにこの格子は降ろされているんだ?」と【大人びた口調で女御に】聞くと、「昼から別棟の主人の家族(女君の義理の娘)⇒(西の御方)がおいでになって碁を打っています。」と言う。⇒ 女の客が来ているので格子を降ろしている。
それを聞いて【源氏は】向かいに座っている(ゐ)【女達】を見たいと(ばや⇒希望)思い、するりと(やおら)そして一歩一歩そろりそろりと簾の間に入りました。
歩む ⇒ そろりそろり 一歩一歩
ありく ⇒ あちこち探し歩く
子供だと思って心配していた小君の言動に源氏は逞しさを感じたのではないでしょうか。女達だけののんびりした屋敷の中の様子が目に浮かびます。暑い夏の逢魔が時のお話は、いよいよ面白くなりそうです
平成16年7月21日 例会報告 帚木第十七回 沈光子
源氏は女君に会うために 方たがえを口実にして再び紀伊の守邸を訪れています。
女君のもとへ忍んでいく心づもりの源氏は、従者たちを下がらせて、小君に手紙を持たせたのですが、女君の居所がわかりません。あちこち邸内を探し回って渡殿へまで来てや
っと女君を探しあてました。小君は大好きな源氏を拒んで身を隠した冷たい態度の君があきれるほど情がない人に思え
「こんなことでは源氏の君に頼みがいのない使いと思われてしまうではありませんか」
と泣き出しそうになって言うと
「このような使いをするなんて考えは持つものではありません。まだ子供がこのように恋の取次ぎをするなんていけないことです」
ときつくたしなめられまます。
「気分が悪いので女房たちを側に置いて腰なんかを揉ませていた、と伝えなさい。
おまえがウロウロしていると皆に怪しまれます」
と取り付くひまもなく小君へあたり散らすように言うものの、内心では、このように受領の後妻なんていう世間で言われるような身でなく、親がいた頃の(上の品の入内を志していた高貴な身分の家らしい)風情が残っていた邸内へ源氏を迎えるのなら、たまに訪れてくる源氏をお持ち申し上げるのなら、どんなに素晴らしいだろう。源氏の心を知りなが無視している自分を、源氏はどんなにか身の程しらずで無粋なことに思われるだろうかと、我ながら胸が痛くて、自分で源氏との恋をあきらめようと決めたものの、思い乱れるのでした。いずれにしても宿命に弄ばれて、身もふたもない情緒を解さないつまらない女だと思われて、この恋を封じるのだ、と女君は思い定めたのでした。
箒木の心
源氏は、小君はどのようにして女君へ(手紙を届ける)策を使うだろうか、とまだ幼い小君を頼りなく思いながらも、ただ待つしかなくて、臥していらっしゃったのですが、不首尾だったと報告され、あきれるくらいめったにないほどに源氏を拒む女君の仕打ちに、途方にくれてしまい
「自分が恥ずかしくてならないよ」とおいたわしいご様子でした。言葉もなく苦しげで、女君から拒絶される苦しみから、辛い、とお思いなのでした。
「箒木の心を知らでそのはらの
道にあやなくまどひぬるかな」
遠くからは見えているのに近づくとみえなくなるといわれている 園原に伝わる伝
説の箒木にたとえて、女君への思いを託した手紙を小君に持たせます。今夜の気持ちはどう言っていいかわからないよと。女君もさすがに眠ることもできず
「数ならぬふせ屋におふる名の憂さに
あるにもあらず消ゆる箒木」
と、苦しい胸の内を詠んで返歌します。(ふせ屋は貧しい家と園原とともに箒木が
あるといわれる地名とのかけ言葉・解説参照)
小君は苦しんでいる源氏がいたわしくて、眠れずにフラフラ歩き回るので、源氏付
きの童子が何事かと怪しまれてしまいそうで、困ったもんだと女君は思うのでした。
いつものように従者たちが眠り呆けていますが、源氏ひとり眠れず、これまで経験したことがないほど強い抵抗にあい、恋心を拒み通す彼女への思いが壁のように立ちふさがり、うらめしいと思いながらも、思うようにならない人だからこそ心惹かれているのだとも思い、しかし余りに辛くて、もうどうでもいい(さばれ→さばあれ→どうでもいい)と思ったりも
するのですが、どうにも引くに引けない恋心でした。
「女君が隠れているところへ連れていってくれ」
と小君へ駄々を言えば「むさくるしくごたごたした部屋にこもっていて、それに女房もたくさんいますので恐れ多くて」
と
答えます。小君は源氏があわれでなりません。
「じゃぁもういいよ。小君だけでも私につれなくしないでおくれ」
とおっしゃって、お側近くに寝かせるのでした。若くて美しい源氏のそばにいるのがうれしいと思う小君の方が、冷たく無情な女君よりは可愛いと思うのでした。
源氏の苦しい胸のうちそして逡巡、女君の辛い境遇ゆえの無粋な選択が、流れるような切れ目ない文章で語られていますね。源氏は恋多き男ですが、どの恋にも誠心誠意でぶつかっていくようです。まして箒木は、雨夜の品ださめで聴いて興味をそそられた、中の品の女との初めての恋です。上の品の女とは違って、自己を主張し、個性を持って源氏に立ち向かう恋の舞台で、源氏へ対等な恋の相手として、彼を翻弄しています。源氏は上の品の女との恋では出会わなかった体験に、面食らうことばかりです。
一方、女君は父親が生きていた頃とは比べようもない身分の自分を恥じています。
上の品の女としての教養や美意識を身につけているので、現実の自分の身の程をわきまえているのです。彼女が上の品の生活を知らなければ、あるいは源氏の恋を有頂天になって受け入れたかもしれない。しかし彼女がかつて身に着けた上の品の教養や美意識が、それを許さない。源氏も女君も辛い恋に身も心もさいなまれていきました。
文章が切れ目なくつづくので、古文に弱い者は泣かされますが、幾らか敬語によっ
て主語を読み取れるようになると、この長文が物語の優雅さをかもしていることに気づか
されます。清少納言のような文体では、この優雅さは出ませんよね。
この時代の美意識とうものが物語の奥行きをつくっているように思いました。従者が眠り呆ける場面では、肉体を酷使している身分の者の寝姿へ「いぎたなし」という表現を使っています。これは源氏の美意識であるとともに作者の紫式部の美意識でもあるでしょう。あくびしたり、居眠りしたり、なんてとんでもないことなのでしょうね。現代では総理大臣でさえ国会開催中に居眠りしてますがねぇ。そういうのをテレビ放映するっていうのも「いぎ
たなし」なのでしょう。
源氏と女君との間を行ったりきたりさせて、式部は小君を非常にうまく使っています。
女君が
「かくけしからぬ心ばえは、つかふものかは。幼き人のかかること言ひ伝ふるは、いみじく忌むなるものを」
と当り散らすのも、源氏の使いが弟の小君だからでしょう。そして小君相手に源氏が「よし、あこだに、な捨てそ」
なんて、すねてみせます。女君も源氏も小君にだけは普段に似ず、心のままにすねたり、当たったりしています。小君を登場させたことで、恋の当事者たちは的確に過不足な
く生き生きと描かれたように思えます。小君が源氏からも女君からも、生身の思いを
ぶつけられて、戸惑い恐縮し、そういう時の小君の愛らしさが読者の微笑を誘います。
小君は式部からみても愛らしく賢げな少年なのでしょう。
巷に言われている「源氏物語はレイプ物語」という風聞は、原文を読む限り的外れ
ではないか、という話がでました。原文は、源氏の恋に殉ずる純情と苦悩を描ききっており、女君も意思と個性をもった人間として登場しています。
しかし式部は博識ですね、漢学者の娘ですからと、先生からの補足がありました。
箒木があるという地方の伝説にも通じているんですね。
ということはつまり、読者もそういう知識を共有していけるらしいのが、当時の文字を持
つ人々の教養の深さが偲ばれます。
皆さま、ひっそりと胸に手を当てて越し方を振り返りますと、源氏と女君の苦しい
恋物語は、どこか仕舞い込んでいる失恋の痛手に思い当たりません?
時空を超える式部の人間洞察に脱帽!
平成16年6月16日 例会報告 帚木第十六回 朴文順
にわかの文 後半)
またの日、小君召したれば、(源氏のもとへ)参るとて(姉の)御返り乞ふ(女君が)「かかる御文見るべき人もなしと聞こえよ」とのたまえば、(小君は)うち笑みて、「(源氏が)違ふべくものたまはざりしものを、いかがさは申さむ」と言ふに、(女君は)心やましく(=相手に傷つけられたように思う)、残りなくのたまはせ知らせてけると思ふに、つらきこと限りなし。「いで(さあ、まあ)、およすけたることは言はぬぞよき。さは(だから)、な参りたまひそ」と、むつかられて、「召すには、いかでか」とて参りぬ。紀伊の守、すき心(若い女に目がない感じ)に、この継母のありさまを、あたらしき(もったいない、惜しい)ものに思ひて、追従しありけば、この子をもてかしづきて、率てありく。
源氏の文を渡し、源氏のもとへ参上しなくてはならないので、姉に返事を求めると「このような手紙をみるひとはここにはいない(=人違い)、と源氏に申し上げなさい」と姉が言うので、小君はなに言ってるの、源氏が嘘をおっしゃるわけはないのに、どうやってそう申し上げればいいの、と姉がごまかしているのを無邪気にわらいます。その小君の応えをきいて、女君は源氏は小君にすべてを話してしまったのだと思い、不機嫌に弟にあたってしまう。「そんな大人びたことは言うものではないです。源氏のもとへは参上するな」そう姉に言われても源氏に呼ばれていかないわけにはいきません。一方若い継母に関心を寄せる紀伊の守も機嫌をとってこの小君を連れ歩いたりします。
()で補った言動の主体は動詞の尊敬語の形態でわかります。「参る」は謙譲語なので源氏のもとへ行く、ということ。「聞こえよ」というのは「申し上げなさい」ということだから女君が小君に、「たまはる」は「言う」の尊敬語なので主体は源氏、といった感じです。
あたらし(可惜し)・・・一説にアタラ=当ると同根で、相当する、値打ちがあるものを、と感嘆することから、もったいないという意になったそうです。平安時代にはすでに「新し」と混同していたようです。
使者小君
君(源氏)、(小君を)召し寄せて、「昨日待ち暮らししを、なほあひ思ふ(=恋人に対して使う)まじきなめり」と怨じたまへば、(小君)顔うち赤めてゐ(=座る。じっとしている)たり。(源氏が)「いづら(=どれどれ)」とのたまふに、(小君は)しかしかと申すに、「いふかいな(言う甲斐のない)のことや。あさまし(驚きあきれる)」とて、またも(女君への文を)賜へり。「あこ(吾子。我が子だけでなく、かわいがっている幼いものに対して親愛の情をこめてよぶ)は知らじな。その伊予の翁よりは、先に見し人ぞ。されど、(自分=源氏は)たのもしげなく、頚細しとて、(女君は)ふつつかなる後見まうけて、かくあなづり(=侮り)たまふなめり。さりとも、あこはわが子にてをあれよ。このたのもし人(=伊予の介)は、ゆくさき短かりなむ」とのたまへば、さもやありけむ、いみじかりけることかな、と思へる、(と思っている小君のことを源氏は)をかしとおぼす。この子をまつはしたまひて、内裏にも率て参りなどしたまふ。わが御匣殿(源氏の屋敷、二条院の衣装係)にのたまひて、装束などもせさせ、まことに親めきてあつかひたまふ。
召す、怨じたまふ、のたまふ、賜へりは尊敬語なので主体は源氏。ゐたりは尊敬語ではないので小君、申すは謙譲語なので小君、ということがわかります。と思へる、おかしとおぼす。の部分も「そうかもしれない。大変なことだな」と小君が思っているのを源氏はかわいいと思っている、という構造が敬語の使い分けでわかります。
源氏は返事を待ちわび、しかも不首尾に終わってしまうのですが、またも手紙を書きます。そして小君にちょっとした嘘をついて、完全に小君を味方につけてしまいます。実は自分は伊予の介よりも前に女君と恋人関係になったのに、自分が頼りなげであったので、女君は伊予の介という後見をつくってわたしを馬鹿にしている。それでもおまえは私の子(のように大事な子)でいなさいよ。伊予の介は老い先も短いかもしれない、といって小君のために衣装なども作らせて親のようにかわいがっている。
見る、ということは現在では男女が誰でも殆ど自由に見るわけですが、当時異性を直接見る、会うというのは寝所でしかありえないわけですから、「見る」=恋人の関係になることを指します。
頚細しとは源氏が自分の頼りなさをいうところですが、同時にその容貌が華奢で美しいということにも自信をもっていることがあらわれています。対になる伊予の介のことを「ふつつか」と言っています。ふつつか(=不束)とは現在ではつたないこと、行き届かない、という意味で使われることが多いですが、もともと植物などが太くしっかりした様子、人の形容に使えばごつごつして不恰好なこと、不体裁なこと、風情がないことなどを意味します。束(つか)には「束の間」のように、ちょっと、わずかという意味がありますから、それを否定しているのでこのような意味になるのかと納得。「ふつつか」がもともと外見を指すということははじめて知りました。
御文はつねにあり。されど、この子(=小君)もいと幼し、心よりほかに散り(=落とす)もせば、軽々しき名さへとりそへむ、身のおぼえ(自分が世間からどう思われているか、評価されているか、ということ。=受領の妻)をとつきなか(つりあいがとれない)るべく思へば、めでたきことも(源氏のような人に愛されるということ)わが身からこそと思ひて、うちとけたる御答へも聞こえず。(源氏の)ほのかなりし御けはひありさまは、げになべてにやは(反語。通り一遍では全然ない→素晴らしい)と、思ひいできこえぬにはあらねど、をかしきさま(自分の恋心、ときめき)を見えたてまつりても、何にかはなるべき、など思ひかえすなりけり。君(=源氏)はおぼしおこたる(=考えがゆるむ、粗略になる)時の間もなく、心苦しくも恋しくもおぼしいづ。思へりしけしきなどのいとほしさも、はるけむかたなくおぼしわたる(~しつづける。ずっとしている)。軽々しくはひまぎれ(こっそり隠れて)、(源氏が女君のところへ)立ち寄りたまはむも、人目しげからむ(人目の多い)所に、便なき(=不都合な、けしからぬ)ふるまひやあらはれむと、人(=女)のためもいとほし(=可哀想)くと、おぼしわづらふ。
女君も源氏も思い悩んでいます。思ひいできこえぬにはあらねど、「思い出さないわけではないけれども」と心の逡巡が文章によく表れているように思います。一方源氏は「はるけむかたなくおぼしわた」っている。女君は源氏ほどの人に愛されてうれしくないわけはないのですが、何よりも自分の今の立場、身分を考えると源氏の想いに応えて自分の素直な気持ちを届けることは出来かねます。なんといっても自分は受領の妻。父が生きてた頃は入内も検討されていたほどの上の品の女だったのですが、いまでは夫の伊予の介の後見がなければ生きてはいかれないほどに零落してしまった身分です。最初から中の品の女であればもしかすると源氏の求愛にただ歓喜するだけだったかもしれませんが、上の品のプライドをもったまま、中の品の女として生きなければならない現実に、いやでも源氏との釣り合いのとれないこと(つきなし)が気にかかります。源氏は源氏で、拒絶されればされる程、女君に心を寄せるのですが、中の品の人妻である女君の立場を考えると軽軽しく噂になるようなこともできず思い悩みます。それでもふたりとも一度だけの逢瀬のことが忘れられずにいるようで、このまま二度と会わずに終わるということもなさそうで、今後の展開が気になります。
手引き(P68~)
例の、内裏に日数経たまふころ、さるべきかたの忌み待ちいでたまふ。にはかに(=急に)(左大臣邸に)まかで(退出)たまふまねして、道のほど(=途中)より(紀伊の守邸に)おはしましたり。紀伊の守おどろきて、遣水の面目とかしこまりよろこぶ。小君には、昼より、かくなむ思ひよれる(=考える)と、のたまひ契れり(しめしあわす)。(源氏は小君を)明け暮れまつはし馴らしたまひければ、今宵もまづ召し出でたり。女も、さる御消息ありけるに、おぼしたばかり(=計画をたてる)つらむほどは、浅くしも思ひなされねど、さりとて、うちとけ、人げなき(=ものの数に入らない。一人前ではない。厳格な身分制度のあった時代のことなので、ある一定以上の身分の人間でなければ人の数には入らない、という考え方から)ありさまを見えたてまつりても、あぢきなく、夢のやうにて過ぎにし嘆きをまたや加へむ、と思ひ乱れて、なほ(=やはり)さて待ちつけきこえさせむことのまばゆ(相手があまりに光り輝いているのでこちらがいたたまれなくなる)ければ、小君が出でて去ぬるほどに、「いと(源氏の場所と)けぢかければ、かたはらいたし。なやまし(=気分がわるい)ければ、忍びて(女房などに)うちたたかせ(=腰など揉んでもらう)などせむに、ほど離れてを」とて、渡殿(母屋の外の廊下のようなところ)に、中将といひし(女房)が局したる隠れに(目的の「に」)うつろひぬ(完了の助動詞)。
源氏は女君に会う機会は方違えしかないと思い至り、内裏で方違えの時を待ちます。さてその時がやってきて、左大臣邸に退出すると見せかけて急に紀伊の守邸を訪れると、紀伊の守は源氏が自分の邸内に中川から引き入れた遣水を気に入ってくれたのだと思って喜びます。「紀伊の守おどろきて~」は他の部分とはトーンが異なり、生まれた時から中の品であった紀伊の守の無邪気な喜びようが滑稽であると同時に女君の惑いの切なさが際立つように思われる一文です。小君にはこの訪れを前もって知らせていたのですが、女君もそれを知っており、源氏がこのようにしてまで、自分のところに来てくれる情を考えもしますが、そうはいってもやはり自分は中の品の女、釣り合いのとれない身分で逢瀬を重ねても、夢のようにすごすひとときがおわったあとの現実の世界での嘆きが増すだけだと思い悩みます。そこで小君が出て行った隙に、体調が悪いので、という理由をつくって渡殿にある例の中将の女房の部屋に隠れます。
「夢のやうにて過ぎにし嘆き」というのは現代の私たちでは想像できない、身分社会の悲しさやせつなさなのだと思いますが、身をもってその身分の違いを経験している女君の嘆きはいかばかりか・・・という気がします。源氏との逢瀬は夢のようで、それは現実(中野品の受領の妻)に戻ってしまえば、いっそ知らなかった方が幸せだったほどの嘆きなのでしょう。源氏に夢中になるというのは文字通り夢の中のできごとなのかもしれません。
かたはら(傍ら・側・片端ら)いたし・・・(傍らの人が自分をどう見るだろうかと意識して)気がひける。気恥ずかしい。気が咎める。片腹痛し、とするのは中世以降の当て字で、おかしさの余り片腹が痛い、ばかばかしいという意味にもなったようです。
うつろふは文字通り移る、移動することを表しますが、同時に心の惑いを読み取ってもよいのではないでしょうか。ここが「うつろひけり(中将の部屋に行った)」と物事の事実を単に描写するのではなくて、「うつろひぬ」と完了の助動詞になっていることで、さまざまな想いを抱きながらも、移ってしまった、と読者に女君の心情も考えさせ、「うつろふ」のもうひとつの意味、「心が動く」を連想させて見事だと思いました。
今回古語辞典をなんどかひいてみたのですが、学生時代に辞書を繰るあの辛さは微塵も感じず、とてもたのしく納得できる時間でした。かなで意味がとりづらい場合も、ほとんどの場合漢字が添えてあるので、漢和辞典も同時にひいてみてその意味の多様さに驚きました。「束の間」なんてよく使う言葉ですが、なるほどいわれてみると「束」に「わずか、少し」なんていう意味があるんだなー、とか・・・。源氏を古語で読み始めてから近松や馬琴などの近世文学がわりとすらすら読めるようになったのもこの講義のおかげです。
平成16年5月19日 例会報告 帚木 十五回 沈光子
心のこり
夜明けと共に起き出してきた人々の気配であたりがざわついてきました。迎えに来た中将へ女君を返して戸を閉めたものの、源氏は二度と逢うことがかなわない人への思いで、戸が越えがたい関所(ひこ星に恋はまされぬ天の川 隔つる関に今はやめてよ)のように感じるのでした。
直衣を着て身支度を整えた源氏は、客間の格子(南の高欄)によりかかり、恋の余韻に全身を預けてもの思いにふけります(しばしうちながめたまふ)。
つい立の上からチラッと見える憧れの人を、ワクワクドキドキしながらのぞき見する女房たちは、源氏の魅力が我が身にもしみるように思うのでした。(こういうがさつさは中の品の屋敷らしい雰囲気をよく表していますねぇ。冬ソナのヨン様に群がるファン心理そのものだわ)
月はまだ空にあり、しだいに光を納めていくものの、輪郭はまだくっきり見えていて、中々風情のある曙の景色でした。どうということのない空の様子が、見る人の心によってどのようにでも、激しい衝撃を与えるようにも映ります。
女君は自分との恋に胸を痛めているに違いない。手紙を交わすことさえままならない人へ後ろ髪を引かれながら、源氏は去ったのでした。
したごころ
左大臣邸へ戻っても、すぐには眠ることができません。再び逢うことがかなわず、ましてや女君の立場では、どんなに思い悩んでいることかと思いやる源氏は、苦しく切ないのでした。
女君は美人というのではないけれど、感じがよくてたしなみをわきまえた正に中の品でなければ出会えない人で、経験を豊かに持った左馬頭が雨の晩に言ったことは、本当だったなぁとガテンがいったのでした。
ここしばらくは本宅を気づかって左大臣邸にいる源氏です。でも女君へ音沙汰なし(いとかき絶えて)でいる状態なので、女君の心中が心にかかって苦しくてならず、紀伊の守をお呼びになりました。
P56
「先日逢った中納言の子(女君の弟)を私へ預けてくれないかい。可愛らしげに見えたし、そば近くへ置こうと思うんだ。天上童に私が帝へ推薦して上げよう」
と言うと紀伊の守は
「ありがたいことですが、姉君へ相談してみましょう」
と女君を引き合いに出したので、源氏はドキッと胸が騒いでしまう。
「その方はあなたの(朝臣)の弟を産んでいますか」
「そういうことはありません。この二年ほどまえに後妻として(父に)連れ添っていますが、入内も決まっていたのに(女君の)父親が亡くなって思いがけない身分になってしまい、満足していない(心ゆかぬ)ように訊いています」
「かわいそうなことだね。その姫君は評判の人でしたね。(よろしく聞こえし人ぞかし)ほんとうに美人ですか?」
と訊くと
「それほど悪くないようです。世間でよく言うように生さぬ仲ですので、よそよそしくしていますので」
と答えます。
にわかの文
5日6日すぎて、女君の弟を連れて紀伊の守が参上しました。小柄で育ちのよさがにじみでて優雅、身分ある貴族らしい風采でした。源氏は側近くへ招き入れて、打ちとけて話かけました。
女君の弟は子ども心に、あこがれの人に接して光栄で嬉しそうでした。
源氏は女君のことをくわしく訊くのでした。答えるべきことは答える弟が、下心のある源氏には恥かしくなるほどきちんとしていて慎み深く(はずかしげにしずまりたれば)、女君のことを切り出しにくいのでした。
けれど彼女とのことをじょうずにそれなりに(適当に煙幕をはって)話してきかせました。
弟は子ども心に、そんなことがあったのか、とぼんやり理解するようでしたが、まだ幼くて深い詮索もせず、源氏からの手紙を姉君へ届けに持って来たのでした。(女-恋の相手へはただ女とだけ書かれる)
女君は余りのことに涙を浮かべてしまう。弟が源氏との仲を知ってしまうなんて体裁悪く (はしたなくて)、そうかといって源氏の手紙なので無視することなんて出来ず、顔を隠すように広げました。(女君は横になっている状態)
メンメンとつづられた手紙には
眠ることができないので、夢の中であなたに会うこともできません
眠る夜もなくて と詞書まで添えられていました。
その上、筆跡はすばらしくみとれるほどで、女君はにじんでくる涙で何も見えなくなっていき、宿世に翻弄される我が身を思い、臥してしまいます。
(夢をあう-夢が現実になって再会を果たす 目さえあわでは-瞼が合わさることなくで眠れない)。
心のこり では式部の自然観が現れている と解説がありました。月を描いた景色、自然と登場人物の心理を重ねる描写になっています。
日本文学の常套手段がすでに紫式部によって確立されていたというのは、驚き。自然描写と人間心理が表裏一体というのは、歳を重ねるほど感じ入る普遍性。そこを式部はきっちり押さえて描いている、驚きモモノキです。
源氏が千年の歳月を読み継がれてきた理由は、ここにもあるんですね。
したごころ でみせた源氏のしたたかさには驚かされました。恋にはウブで純情な源氏が、紀伊の守とは、女君への思いを探って、腹の探りあい、丁々発止でした。老練とも言える一七歳の源氏の巧みさです。こういうバランスの悪さというか、恋にはとりわけ純という処が、ファンにはたまらないのね。何もヨン様だけばかりが男じゃないんだってば!
会話体で押していく書き方は、源氏の中ではこの場面だけだそうで、臨場感があふれています。
弟が女君へ手紙をもっていくくだり、女君が臥せっていた に先生が姉上の失恋を思い出し「布団を被って寝ていたのよねぇ」としみじみ言ってました。
「ああいうときは寝るきゃないのよねぇ」には、一同思い当たる節があるようで深くうなづいておりましたなぁ。
源氏は女君との再会を果たすべくどのような策に出るのでしょう。次回が楽しみですね。
有明の月 諏訪淳嗣
何なのだろう。やはり 気になる。 そんな独り言。
P52
-----------------
月は有明にて
光 をさまれるものから かほけざやかにみえて
なかなか をかしき あけぼのなり
ただ 見る人から 艶にもすごくも見ゆるなりけり。
-----------------
この一文を声を出して読んでいて、
その情景・心情が私の心にふっとによみがえってきた。
暗黒の天空に白く輝く満月を見たとき・思い出したとき とは違う。
なかにし礼原作のテレビドラマ「赤い月」のラストシーンの月が
目の前に浮かんだ。あのときに感じたものは何なのだろう。
満州の黄砂によって、赤く輝く月。そして白くフェードアウトして行く月。
白い世界に消えてゆく月だが、はっきりと 月が 見えていた。
この月を 見たときは、
会社で倒れた義父が、付き添いの甲斐なく他界したとき、
病院から出て 出逢ったときの月だ。 静かだった。
悲しくもなく、悔しくもなく、ただ あかるさを感じる天空に
かほけざやかにみえて 見えていていた。
また、思い出した。沈さんと息子さんが……。
そうだ。息子たちが生まれてくるときにも……。
有明の月が ”光 をさまれるものから かほけざやかにみえて”
あの月を私は何を感じて見つめていたのだろう、言葉ではまだ言い表せない。
しいて云えば私には なにもない しずかな世界 だった。
平成16年4月21日 例会報告 帚木 十四回 沈光子さん
口説き上手
高貴な香が鼻をつき、女君を連れている男が源氏だと察した中将ですが、相手が源氏ではどうにもできずに、オロオロついていきます。源氏は障子を閉めて「朝、迎えにいらっしゃい」と言う。
女君は中将に知られたしまったことで、いっそう耐え難く動揺して汗びっしょり、本当に気分が悪そうでした。
源氏はここ一番とばかりに流れるように口説き文句を並べます。あまりに饒舌なので、まあいったいどこからそんな言葉が出てくるのかしらん、なんて作者におちょくられるほどです。(例のいづこより……ことの葉にかあらん)
あはれしらるばかり なさけなさけしくのたまひつくすべかんめれ (女が自分を哀れと思ってくれるように情愛深く聴こえる言葉を囁き続けています)
女君は 数ならぬ身(身分の低い身)の自分だからこのように見下しているんでしょ。心なんかこもっているはずないわ。と突き放します。(おぼしくたける御心ばへのほども……思うたまへざらむ)
低い身分ですけど私は身の丈に合った生き方をしているんですから、ちょっかい出さないでよ。と身もフタもない言い方で、源氏をきっぱり拒みます。(いとかようなる際は、際とこそはべれ とて かくおしたちたまへるを)おしたちは強引という意味です。
女に振られたことがないドンファンの源氏は虚を突かれて冷静さを失っていきます。
つらそうに思い沈んでいる女君(深くなさけなくうしいと思い入りたる)へ気が引けるほどでした。(心はずかしきけはひ)
源氏は必死になって「僕は身分違いなんてこと知らないんだもん。(身分の高い彼にはとうてい想像できない)世間一般の浮気者たちといっしょにして軽蔑しないでよ。(おしなべたるつらに思ひなしたまへるなむ、うたてありける)
世間で言われているような 無理強いして恋をものにするような男なんかじゃないんですから(あながちなる好き心はさらにならはぬを、さるべきにや)と、身分違いを盾にあくまでも拒もうとする女君を口説きつづけます。
「軽蔑するのももっともなことだけど、あなたへの恋心は僕にもどうにもならないほどなんですよ。(げにかくあはめられたてまつるもことわりなる心まどひを、みづからもあやしきまでなむ)なんて、いつもの源氏らしくなく真剣にしどろもどろに言うのです。(まめだちて、よろずにのたまへど)
P43
源氏の真剣なようすに心引かれていく女君は切なく、拒みつづけて強情をはれば無粋な女だと思われてしまうだろうと思うものの、身分違いの相手との恋の先が見えてしまう。源氏の強引なやり方をひどいと思うものの、心ひかれていく自分を抑えられない。身分違いの分を知る自分は、心とは裏腹に源氏につれない態度をするしかない、とばかりに切ない女君です。
源氏には女君の心の揺れがわかり、かといって無理強いはできないし、彼女には気の毒だけど、でもこの女君がいるのを知っていて逢わずにいたら、どんなにか心残りだったろうか、と思います。
p45
頑なな女君へなすすべもなく、なだめる言葉も出ない源氏です。しかし源氏はますます女君に引かれていきます。
「ねえ、そんなに嫌わないでよ。僕たちはきっと思いがけない縁があるんですよ。宿縁なんです。世間知らずのおぼこ娘みたいなダダをこねないでよ。僕だってつらいじゃありませんか」なんて言う。
いつしかドンファンならぬ素直な純情源氏になっていきます。しも という強めの言葉が二度使われていて、源氏の素直な真摯な対応ぶりが強調されています。
「こんな受領の後妻なんかになっていない 情けない身になる前の昔の自分だったら、身分不相応でもまた逢えるとうのぼれることもできるけど、今夜だけのひとときの浮寝でしかないと思うと、アアほんとに哀しいわ。でもしかたないわねOKよ。ねぇ、今夜のことは決して他言しないでね」と女君が折れます。筆者が同情するほどの女君の気持でした。源氏は心を込め慰めの言葉を尽くしたのでした。
夫の面影
一番鶏がなきました。「ああ、寝坊しちゃったよ。車出さなきゃ」なんて起きだした人々の気配がしてきます。紀伊守も「女たちの方違えじゃないんですからこんな暗いのに行かなくてもいいじゃありませんか」と気遣いをみせている様子。
源氏は、こんな偶然で女君に逢うなんてことは二度とない、不可能だよと思う。あの様子じゃわざわざ手紙なんかくれるなんてこともなさそうだし、無理だろうなぁ(さしはへてはいかでか、……いとわりなき)と思うと辛い。
中将も迎えにきて、いったんは女君を帰そうとするけれど、また引き止めてしまう。
「これっきり、これっきり、これっきりですかぁ。手紙も出せないの?(いかでか聞こゆべき)
こんなに苦しい恋心はこれまで経験したことないよ、これはめったにないことですよ」と源氏が泣くのも艶っぽく見えます。(蛇足ですが、エエ男はよく泣くねぇ。たとえば韓国ドラマのヒロイン。心のままに生きてますなぁ)
あわただしく源氏は詠みます。
つれなきを恨みもし果てぬしののめに(東雲がしらんでくる)
とりあえぬまで(鶏と、とりあえずをかけて短い時間をあらわす)おどろかすらむ
p50
女君は自分の身のほどを思うと、気恥ずかしく(いとつきなくまばゆきこころちして)昨夜の激情にかられたひと時の余韻も急速に醒めていく。
いつもはくそまじめで気に入らない(すくすくしく心づきなし)うんざり(思ひあなづる はおもいやられる)の伊予の方を思い出して、ひょっとして夫が私のことを夢にでもみて何かあったんじゃなかなんて気づいたらと思うと身がすくみます。(女君には幼い弟がいるし、それに後ろだてもなく帰る家がないんです。夫はそれを承知で後妻に望んでくれたのよね、爺さんだけどいい人なの。追い出されたら大変)
女君の気持は現実に戻っていますが、返歌をします。
身の憂さをなげくにあかで(たりない)あくる夜は
とり重ねてぞ音もなかれる
(こちらも鶏ととりかさねが 重なってます。鶏も啼いてます、私も泣いてます)
みるみるうちに(ことと)明るくなっていき、源氏はようよう未練をたちきって障子口まで女君を見送ります。女君はといえば、みるみる気持が現実に戻っていくのでした。
先生の解説を参考にしていただいて十分に補足してください。
この日は晴美節も飛び出し、いつもながら経験豊富な生徒にとっても濃密な講義となりました。
源氏は 雨夜の品定め で聴くともなく聴いていた中の品の女への興味に引かれて女君と逢うわけですが、これまでの上の品の女たちからは経験しなかったことづくしでした。身分の高い女は自分という者を顕かにするようなことはしませんが(はしたないのでしょう)、身体ごとぶつかって来るような女君の自我のまえで、源氏はたじたじでした。そして自分も真剣に相手へ全身全霊を傾けていきます。雨夜からの小説的複線がみごとに展開されていきます。
この時代の恋愛を現代の価値観で測るのは無理でしょう。当時の仏教に支えられた無常観・一期一会を大切にする価値観は現代とは比べるべくもなさそうです。それに寿命がいまの半分と思うと、人生の密度が異なるように思います。それに女系の社会システムも大きいでしょう。現代より遥かに大らかで素直な人々の人生観だと思えます。
物語の流れるようなそしてテンポの速さは、そういうことと無縁でないように思えますです。
この時代の女の自我を描くことができるのは、式部もまた強い自我をもって生きた女だったからでしょうね。初々しい源氏はこの恋で初めて経験することが多かったですね。
なにより驚かされたのは、ロマンチストの男心と現実的な女の恋情を描き分けていたことです。これは驚愕に値します。源氏物語が長きに渡って読み継がれてきたのは、この普遍的な人間への洞察ゆえでしょう。歳を経てますます味わいを増す読みができる、常に旬でありつづける源氏物語は、いよいよ恋の遍歴を重ねて佳境へ向かうようですね。
平成16年3月17日 例会報告 帚木第十三回 朴文順さん
しのび込み(P30~)
君(=源氏)はとけ(とく・・うちとける、安心する)ても寝られたまはず、いたづら臥し(=寂しい独り寝)とおぼさるるに、御目さめて、この北の障子のあなた(=あちら、むこう)に人のけはひするを、こなたや、かくいふ人(=昼間話題にした姫君)の隠れたるかたならむ、あはれや、と御心とどめて、やをら起きて立ち聞きたまへば、ありつる(つる=完了の助動詞。先ほどいた)子の声にて、「ものけたまはる(=「もの承る」→「もしもし」)。いづくにおはしますぞ」と、かれたる声(枯れた声。声をひそめている様子)のをかしき(=かわいらしい)にて言へば、「ここにぞ臥したる。客人(=源氏)は寝たまひぬるか。いかに近からむ(推量の助動詞)と思ひつる(助動詞:完了)を、されどけどほ(けどほし=遠い)かりけり」と言ふ。寝たりける声のしどけなき(くつろいだ、うちとけた感じ)、いとよく似かよひたれば、いもうと(男からみた女きょうだい。この場合は「姉」)と聞きたまひつ。「廂にぞ大殿籠りぬる。音に聞きつる(噂にきいた、評判どおりの)御ありさまを見たてまつりつる(助動詞:完了「さっき見た」)、げにこそ(=本当に)めでたかりけれ。」とみそか(=ひそかに、声をひそめて)に言ふ。「昼ならましかば、のぞきて見たてまつりてまし(「~ましかば~まし」「もし~だったら~したかったのに(できなかった)」仮想の副詞)」と、ねぶたげ(=眠そうに)に言ひて、(夜具に)顔ひき入れつる声す。(源氏は)ねたう(ねたし。「くやしい、癪だ」)、心とどめても問ひ聞けかし(もっとちゃんと自分のことを聞いてくれ)とあぢきなく(=つまらなく)おぼす。(弟が)「まろ(=私)は端に寝はべらむ。あなくるし(「ああ疲れた)」とて、(寝所を整えるために)火かかげなどすべし(助動詞:推量。源氏の視点。実際にその場面を見ているわけではないが気配でそうだろう、と思って)。女君は、ただこの障子口すぢかひ(=斜かい)たるほどにぞ臥したるべき(助動詞:推量)。(姉が)「中将の君(=この姫君に仕えているいちばん身近な女房。)はいづくにぞ。人気遠きここちして、もの恐ろし」と言ふなれば、長押(=母屋と廂の間区切る横木。仕えの女房たちは廂に寝ている)の下に、人々(=女房たち)臥して答へすなり。「(中将の君は)下に湯におりて、『ただ今参らむ(=すぐ戻る)』とはべる」と言ふ。
さて、昼間紀伊の守と話したことを思い出したりして、例の姉弟(まあ、姉でしょうが)のことが気にかかり、眠れない源氏。暗闇の寝所で衣ずれの音などが障子(襖)のむこうから聞こえて、これがあの姉の気配だろうか、とやおら起きて聞き耳をたてます。ものごし優雅な源氏が暗闇のなかで「やをら」起きる、というのがおもしろいです。その姉弟の会話を聞くと、弟は源氏をみて、その素晴らしさを姉に語るというのに、姉は眠気のほうが勝って「昼間だったら覗いて見てみたかったんだけど~」と欠伸まじりとも思える興味のあまりなさそうな感じで答えるのにたいして、源氏は「ねたし」と感じます。
襖で区切られて、更に寝所の様子というのは姉弟のやりとりからもわかるように暗い。そうするとここでもまた源氏の視点に立つと助動詞が効いてきます。会話やかすかな物音から襖の向こう側を推量しています。
姫君は方違へでやってきたひと(義理の息子)の家にいるだけでなく、今日は源氏というお客までとなりにやってきているので、いつも一番身近に仕えている中将の君(女房の名前は父の役職からとることが多い)がいないことで落ち着かないのか、居場所を女房たちに問うと、ここがまた「中の品」らしいところというか、「お風呂に行っていてすぐもどるそうです~」と寝ながら応えるだけで、誰も姫の相手はしません。
風呂は寝殿の後ろ(北側)にあって、当時は蒸し風呂だったそうです。また、現在のように頻繁に風呂に入れるわけではないので、このような場面はめずらしいそうです。
皆しづまりたるけはいなれば、かけがねをこころみ(ためしに)に引きあげたまへれば、あなた(むこう)よりは鎖さざりけり。几帳を障子口には立てて、火はほの暗きに見たまへば、唐櫃だつ物(調度品の類。「だつ」を使うことで部屋の暗さがわかります)どもを置きたれば、みだりがはしきなかを、分け入りたまへれば、(姫君が)ただひとりいとささやかにて臥したり。(姫君は)なまわづらはしけれど、(源氏が)上なる衣押しやるまで、求めつる人(=中将の君)と思へり。「中将召しつればなむ、人知れぬ思ひのしるしあるここちして」と(源氏が)のたまふを、ともかくも思ひわかれず、もの(=物の怪の「もの」でしょうか。超自然の恐ろしいもの)におそはるるここちして、「や」とおびゆれ(=おびえる)ど、顔に衣のさはりて、音にも立てず。
「上の品」であればまわりの者がついうっかり、なんてことはないのでしょう、当然閉まっている鍵なのですが、ためしに源氏が自分の側の鍵を上げてみると、向こうからはかかっていない。この対比も品の違いを際立たせています。鍵が両側についていて、源氏の方(上の品)はかかっていて、姫君の方(中の品)はかけ忘れています。突然きまった源氏の来訪にそれまで一部屋を使っていたので、調度品の類が雑然と置かれている中を源氏は分け入って進みます。すると、姫君が「いとささやかに」横たわっています。当時は夜具というのは自分の着物を上からかけているだけなので、身体の大きさも暗い中でもわかるのでしょう。「ささやか」という言葉には物理的に華奢なかんじというだけでなく、昼間の話や桐壺帝からの話をきいて「あはれ」と思っている源氏の視点もはいっているように感じました。人の気配を感じたのか寝入りばなの姫君は「なんとなくわずらわしいな」と感じますが、源氏が夜具にしている着物をひきあげるまで、風呂にいっていた中将の君だとばかり思っていました。「中将を呼んだので(こうして来たのです)、人知れずお慕いしていたかいがあって(うれしい)」と、(近衛の中将である)源氏が言います。姫君はこの部屋に男がいることに動転してしまいとっさには状況を判断することが出来ず、物の怪かと怯えて思わず声が出てしまいますが、衣が顔に触れて音になりません。
「中将の君」は女房の名ですが、近衛の中将という役職を持つ源氏もまた「中将の君」で、この源氏の言葉は非常に印象的です。
ちひさやかなる人(P36~)
「うちつけに(=突然で)、深からぬ心(=でき心、いいかげんな気持ち)のほどと見たまふらむ、ことわり(=当然)なれど、年ごろ(=長い年月)思ひわたる(=ずっと~し続ける)心のうちも、聞こえ知らせむとてなむ。かかるをり(=このような機会)を待ちいでたるも、さらに浅くはあらじと思ひなしたまへ」と、(源氏は)いとやはらかにのたまひて、鬼神もあらだつまじき(源氏の)けはひなれば、はしたなく(=体裁が悪い)、「ここに、人」とも、えののしらず(「え~ず」で「~できない」。「ののしる」は「大声を出す、騒ぐ」)。ここちはた(気持ちではまた)、わびしく(=情けなく)、あるまじき(=あってはならない)ことと思へば、あさましく(=驚き、あきれる)、(姫君は)「人違へにこそはべるめれ」と言ふも息の下(=せいいっぱい、やっとのこと)なり。(姫君の)消えまどへるけしき(=とり乱す様子)、(源氏は)いと心苦しくらうたげ(=かわいい)なれば、をかしと見たまひて、(源氏は)「違ふべくもあらぬ心のしるべを、思はずにもおぼめ(=知っていながら知らない振りをする)いたまふかな。すきがましき(=けしからん)さまには、よに(=決して)見たてまつらじ。思ふことすこし聞こゆべきぞ」とて、(姫君が)いとちひさやかなれば、かき抱きて、障子のもと出でたまふにぞ、求めつる中将だつ(源氏からみて、なので「だつ=らしい」)人来あひたる。(源氏は)「やや」とのたまふに、(中将の君は)あやしくて、探り寄りたるにぞ、いみじくにほひみちて、顔にもくゆりかかるここちするに、思ひ寄りぬ(=察しがつく)。あさましう、こはいかなることぞと思ひまどはるれど、聞こえむ(=申し上げる)かたなし(=術がない)。なみなみの人ならばこそ、あららかに(=荒々しく)も引きかなぐらめ、それだに人のあまた知らむは、いかがあらむ。(中将の君は)心も騒ぎて、したひ来たれど、(源氏は)動もなくて、奥なる御座に入りたまひぬ。
寝入りばなに突然男が現れて怯えている女に対して「突然なので、いい加減な気持ちと思われても仕方がないが、ずっと恋焦がれていたわたしの気持ちも聞いてください」と、口説き始めます。そのものいいがあまりに「やはらか」で、鬼さえも手荒く振舞えなくなってしまう様子なので、女も声を出して人を呼ぶこともできない。けれど気持ちでは、当然自分のことをひとの妻だと知っていながらこのような事態になることはあってはならないと思いやっとのことで「人違いでしょう」と言うが、その必死に抵抗しようとする様子も源氏にはかわいらしく見えていとおしく、姫の「人違い」という言葉を受けて「間違えるはずもない私の恋心を知って知らぬ振りをするのですね。」と答える機敏さが光ります。「すきがましきこと」を「好色」と訳してしまうと違和感があります。「襲いに来たわけでも、ひどいめにあわせるわけでもない、まず私のあなたに対する恋心をきいてください。」というような感じでしょうか。これは源氏が単に口説き文句の常套句として使っているだけではなく、いちど関係を持った女性はとことん面倒をみる、という源氏の態度からも納得できるような気がします。
そして小さい姫君を抱いてそのまま自分の寝所に移ろうとしたその時、姫君が本当に求めていた「中将の君」らしき女房が現れます。源氏は「やや」と声をかけますが何しろ暗い寝所なので声を頼りに探り当てると、その姿を見るよりも高貴な香りが満ちて、これは、と思い当たります。男に姫君が連れ去られようとしている。でもその相手が源氏ともなると何も言えない。そのへんの男であれば「姫君になにを」とでも言ってて荒々しく引き離すのだが。ただそういう場合に未然にことが防げたとしても、騒ぎ立てることで大勢の人がそんなことを知ってしまったらどうなるだろう、と動転してしまいとにかく源氏の方について来たが、源氏はと言えば「動もなくて」奥の自分の寝所に入っていく。「動もなくて」を「平然と」訳してしまうと源氏がとても悪い人のような印象になってしまいます。身のこなしの優雅さやうろたえる「中将の君」との対比として捉えたほうがよいのではないでしょうか。
「しのび込み」の場面からずっと寝所の暗さは強調され続けているので、読者にも薄暗い寝所の情景は映像的にうえつけられています。そんな中でふっと薫る源氏の香り。いままで視覚的に語られる源氏の美しさでしたが、ここで嗅覚にもうったえてきます。映像をもってしても表現し尽くすことのできない、「源氏物語」の優れた点のひとつではないでしょうか。香の歴史については詳しくないので当時それがあったのかわかりませんが、竜涎香(雄鯨の腸内で醗酵したイカの嘴が浜辺に流れ着いたものを使ってつくる貴重で高価なお香)なんかだったんでしょうか・・・。物資的に限定された世界で、だからこそ極められた世界というのは現在より豊かだったと言えるかもしません。
平成16年2月18日 例会報告 帚木第十二回 朴文順さん
中の品の家(後半P18~)
思ひあがれる(=気位が高い、心に誇りをもった。現在の「思いあがる」のような悪い意味はない)けしき(=様子)に聞きおきたまへるむすめなれば、ゆかしくて、耳とどめ(聞き耳をたてる)たまへるに、この西面(源氏は同じ母屋を仕切った東面にいます)にぞ人のけはひする。(女たちの)衣のおとなひはらはらとして、若き声などもにくからず(=感じがよい)。さすがに(=それでも)忍びて、笑ひなどするけはひ(=様子)、ことさらび(=「ことさら」+「ぶる」で動詞。わざとらしく思わせる、感じさせる。)たり。格子をあげたりけれど、(紀伊の)守、心なし(=無用心、思慮が足りない)と、むつかり(=不平を言う、不満に思っている。現在でも幼児に対して使いますが、大の大人がむつかるのですから「ああ、無用心だなあぶないあぶない」など言いながら部屋を見回っている感じでしょうか)て、(格子を)おろしつれば、火ともしたる透影(=正確な意味はわかりませんが「あかり」)、障子(=襖)の上より漏りたるに、やをら寄りたまひて、(源氏は)見ゆやとおぼせど隙もなければ、しばし(女たちの会話を)聞きたまふに、この近き母屋につどひゐ(ゐる←居る。P16の「のぞきゐて(渡殿に座り込んで覗いている)」とおなじ用法)たるなるべし(助動詞:推量)、うちささめき言ふことどもを聞きたまへば、わが御うへ(=自分のこと)なるべし(助動詞:推量)。
ことさらびたり・・・それなりに高貴らしく振舞ってはいるものの、左大臣邸つきの女房たちとくらべてしまうとやはり女房も「中の品」だと源氏は感じているようです。
わが御うへ・・・「わが」とは源氏が自分のことを言っているので、自分のうへ(こと)御をつけるのは不自然に思われますが、敬語は客観的、絶対的なので、こうなるそうです。
●助動詞●古文は現代からみると極端に省略された文章ですが、動作の主体が敬語によってわかるように、場面の情景は助動詞でわかるようです。
「格子あげたり(継続)けれど~おろしつ(完了)れば」は、いつからかあがっていた格子だが、源氏を迎え入れるために紀伊の守が邸内を見回っていたときにあがった格子をみつけて「これは無用心」と思いおろしたので源氏が到着し東面の部屋に入ったときにはすでに格子はおろされた状態だった。これだけのことを助動詞の使い分けで省略できるので流れるような文章になるということでしょうか。
中の品の家(後半P18~)
思ひあがれる(=気位が高い、心に誇りをもった。現在の「思いあがる」のような悪い意味はない)けしき(=様子)に聞きおきたまへるむすめなれば、ゆかしくて、耳とどめ(聞き耳をたてる)たまへるに、この西面(源氏は同じ母屋を仕切った東面にいます)にぞ人のけはひする。(女たちの)衣のおとなひはらはらとして、若き声などもにくからず(=感じがよい)。さすがに(=それでも)忍びて、笑ひなどするけはひ(=様子)、ことさらび(=「ことさら」+「ぶる」で動詞。わざとらしく思わせる、感じさせる。)たり。格子をあげたりけれど、(紀伊の)守、心なし(=無用心、思慮が足りない)と、むつかり(=不平を言う、不満に思っている。現在でも幼児に対して使いますが、大の大人がむつかるのですから「ああ、無用心だなあぶないあぶない」など言いながら部屋を見回っている感じでしょうか)て、(格子を)おろしつれば、火ともしたる透影(=正確な意味はわかりませんが「あかり」)、障子(=襖)の上より漏りたるに、やをら寄りたまひて、(源氏は)見ゆやとおぼせど隙もなければ、しばし(女たちの会話を)聞きたまふに、この近き母屋につどひゐ(ゐる←居る。P16の「のぞきゐて(渡殿に座り込んで覗いている)」とおなじ用法)たるなるべし(助動詞:推量)、うちささめき言ふことどもを聞きたまへば、わが御うへ(=自分のこと)なるべし(助動詞:推量)。
ことさらびたり・・・それなりに高貴らしく振舞ってはいるものの、左大臣邸つきの女房たちとくらべてしまうとやはり女房も「中の品」だと源氏は感じているようです。
わが御うへ・・・「わが」とは源氏が自分のことを言っているので、自分のうへ(こと)御をつけるのは不自然に思われますが、敬語は客観的、絶対的なので、こうなるそうです。
●助動詞●古文は現代からみると極端に省略された文章ですが、動作の主体が敬語によってわかるように、場面の情景は助動詞でわかるようです。
「格子あげたり(継続)けれど~おろしつ(完了)れば」は、いつからかあがっていた格子だが、源氏を迎え入れるために紀伊の守が邸内を見回っていたときにあがった格子をみつけて「これは無用心」と思いおろしたので源氏が到着し東面の部屋に入ったときにはすでに格子はおろされた状態だった。これだけのことを助動詞の使い分けで省略できるので流れるような文章になるということでしょうか。
噂話 (P20)
「いといたう(「いと」+「いたう」=ものすごく)まめだち(「まめ(真面目)」+「だつ」=真面目くさく振舞う)て、まだき(=まだその時期ではないのにもう、はやくから)に、やむごとなきよすが(=高貴な妻→葵の上)、さだまりたまへるこそ、さうざうし(=物足りないと思う)かめれ(伝聞推定「だろう」)。されど、さるべき(=しかるべき)隅(奥まった場所、秘密という意味から転じて女、女のところ。)には、よくこそ(巧く上手に)隠れありきたまふなれ(伝聞推定)」など(襖で隔てた西面にいる女房たちが)言ふにも、(源氏は)おぼすことのみ心にかかりたまへば、まづ胸つぶれて、かやうのついでにも、人の言ひ漏らさむを、聞きつけたらむ時、などおぼえたまふ。ことなることなければ、聞きさし(さす=やめる)たまひつ。式部卿(桃園式部卿)の宮の姫君(源氏の従兄弟)に、朝顔奉りたまひし歌などを、すこしほほゆがめて(間違う、事実と異なる)語るも聞こゆ。くつろぎがましく、歌誦じかちにもあるかな、なほ(=やはり)見劣りはしなむかし、とおぼす。(紀伊の)守、出て来て、燈籠かけそへ、火明くかかげなどして、御くだもの(=酒菜。菓子や木の実など軽いつまみ)ばかり参れり。「とばり帳(=寝台)もいかにぞは。さるかた(=女)の心もなくては、めざましき饗ならむ」と(源氏が)のたまへば、「何(=どんな女)よけむとも、えうけたまはらず」と、かしこまりてさぶらふ。端つかた(=端の方)の御座に仮なるやうにて大殿籠れ(高貴な人々が「眠る、やすむ」の意)ば、人々もしづまりぬ。
隅(くま)・・・「くま」と読むと目の下の隅や隈取を連想しますが、「すみ」と読めば奥まった場所、日の届かないところ、影、秘密というイメージです。どうして男のことは指さないのかな、と思ったんですが、当時は女性は家の中から動けず、男性が女性の「ところ」へと通っていったので、影の場所を指す「隅」が「女=女のところ」になったのではないでしょうか。いま、まとめながら、女性は男性のように簡単に出歩くことのできなかった分、住処と一体化している、あるいはそう見られているのではないかと感じました。
おぼすことのみ心にかかりたまへば・・・女房たちが少し下世話なかんじで源氏の女性関係についての噂話(もちろん源氏に近い筋からの直接の情報ではなく伝聞の伝聞のような話。)をしているのだけれど、源氏が気にかかることは「おぼすことのみ」=藤壺とのこと。まづ心つぶれて(動揺して)、こんな際に女房たちの間であのことが話題にのぼったら、と気が気でない。読者はまだ「おぼすこと」がなんなのか知らされていないが、「桐壺」の最後で、新築した自分の家をみて「かかる所に、思ふやうならむ人をすゑて住まばやとのみ、嘆かしうおぼしわたり」(P122)とあり、その後の「帚木」の最初の場面までに五年間の空白があることから、その間に藤壺とのあいだになにかが起こったということを想像させるようになっています。「おぼすこと」は「帚木」の恋文のくだり(P135~)の源氏の態度からも想像されます。
くつろぎ(余裕がある様子)がまし(気取る)く、歌誦じかち(~じがち=なにかと歌をよみたがる)にもあるかな・・・源氏は、噂話に興じる中の品の女房たちの様子を聞き、やはり上の品の女房たちとくらべて見劣りすると感じている。
「とばり帳もいかにぞは」・・・こゆるぎの紀伊の守が世話を焼いている様子をからかおうと、冗談で「女の用意は・・・」ときくと「どんな女がよいのかわからないもので」と真面目にかしこまって答える紀伊の守の様子です。
姉弟 (P24~)
主人の子ども、をかし(こどもに対して使う場合は「かわいらしい」)げにてあり。童(=殿上童、殿上の間で公卿の雑用をつとめる子供)なる、殿上のほどに御覧じ馴れたるもあり。伊予の介の子もあり。あまた(の子どもたちが)あるなかに、いとけはひあてはかにて十二三ばかりなるものあり。いづれかいづれ(どの子がどんな子か)、など問ひたまふに、(けはひあてはかな一二三歳くらいの子をさして)「これは、故衛門の督の末の子にて、(衛門の督が)いとかなしく(=胸がつまほどかわいがる)しはべりけるを、をさなきほど(=時、頃)に後れ(=衛門の督に先立たれ)はべりて、姉なる人のよすがに、かくてはべるなり(=このようにしている)。才(=男子の学問。漢学)などもつきはべりぬべく(推量)、けしうははべらぬ(=悪くないかなりのものだ)を、殿上なども思うたまへかけながら、すがすがし(清清し=物事がすらすらと運ぶ)うはえまじらひ(交じらい→人と交じらう→宮仕えをする)はべらざめる」と(紀伊の守が)申す。「あはれのことや。この姉君や、まうと(=目下の者に対する二人称)の後の親」「さなむはべる」と(紀伊の守が)申すに、(源氏は)「似げなき親をも、まうけたりけるかな。上(=桐壺帝)にもきこしめしおきて『宮仕へにいだし(過去)立てむと(衛門の督が)漏らし(過去)奏せし(過去)、いかになりにけむ』と、(帝が)いつぞやのたまはせし。世(=男女の仲)こそ定めなきものなれ」と、いとおよすけ(大人びて)のたまふ。
この部分はすこし時間が遡ります。ことわりがないので、戸惑ってしまいますが、フラッシュバックの技法でしょうか。このまえの部分が「仮なるやうにて大殿籠れば、人々しづまりぬ」ですから、源氏がちょっと横になって、隣にいるであろう受領の妻についてのエピソードを思い出しているようにも感じられて非常に映像的な場面です。方違へで紀伊の守邸にやってきてまもなく、宴会をおこなっている場面です。
受領というそれほどの身分のものではない「中の品」の妻がなぜ「思いあがれるけしき」なのか、ここでわかります。父の衛門の督が生きていればこの兄弟も身分にふさわしい暮らし方をしていたのに、という部分です。
余談ですが、東芝に「atehaca(アテハカ)」という家電のシリーズ(電子レンジやポット。いろんなものを削ぎおとしたシンプルなデザインのものです。)がありまして、北欧の方の言葉かしら?どんな意味だろう・・・と思っていたんですが、今回の部分を読んで、古語の「あてはか」からとった名前だったんだと気付き調べてみたらやっぱりそうでした。http://www.atehaca.com 「あてはか」とは、先生の解説でも「上品でみやびやかなさま、気品が自然に身に備わった」とありますが、このHPには One's personality,appearance and attitude is elegantly beautiful.Being graceful とあります。現在の日本語でも英語でもこれだけの言葉を費やさなくてはいけない意味をあらわす単語が一語であったんですね。この言葉が消滅してしまったということはつまり「あてはか」な人がいなくなったから、なのでしょうか。「あですがた」や「あでやか」という言葉はありますが現在の「あで」は「艶」ですから「貴」の意味は含まれないようです。
(紀伊の守がこたえて)「不意(誰も予想しない、というニュアンスです)にかくてものしはべるなり。世の中といふもの、さのみこそ今も昔も定まりたることはべらね。中についても(=なかでも)女の宿世は浮びたるなむ、あはれにはべる」など聞こえさす。(源氏は)「伊予の介は、(女を)かしづくや。君と思ふらむな(主人とおもっているだろうな)」(紀伊の守は)「いかがは(もちろんです)。私の主とこそは思ひてはべるめるを、すきずきしきことと、なにがしよりはじめて、うけひき(=同意する)はべらずなむ」と申す。「さりとも、まうとたちのつきづきしく(=につかわしく)今めきたらむに、(女を)おろし(=ひきわたす。)たてむやは。かの介(=伊予の介)は、いとよしありてけしきばめるをや」など、物語したまひて「(その女はいま)いづかたにぞ」「皆下屋(別棟の召使たちが住むところ)におろし(=下がらせ)はべりぬるを、えやまかりおりあへ(あふ=全部やり切る)ざらむ」と聞こゆ。酔いすすみて、皆人々簀子に臥しつつ、しづまりぬ。
宴会が始まった頃は「こゆるぎ」にかけまわる中の品の紀伊の守と「のどやかにながめたまふ」上の品の源氏という対称的な二人でしたが、ここではともに「若く美しい継母をもった男性」として描かれています。もちろん源氏のほうが機転がきいたうけこたえをしていますが、源氏の、父である帝に対する思いを紀伊の守を使って表現しているようにも感じました。また、結局「父を裏切らない紀伊の守」と「父を裏切る源氏」という対照もあり、ここでは継母に恋焦がれる息子ですが、皮肉なことにずっと後に「息子に裏切られる源氏」という展開が待っているのですから、すべての物語を読み終えてもういちど読み返すときにこういった場面で読者がひっかかるような仕掛けがあるんだなと思うと、源氏が千年読み継がれてきた理由がよくわかります。
平成16年1月21日 例会報告 帚木第十一回 朴文順さん
源氏と女房たち
からうして、今日は日のけしきもなほれり。→昨晩まではどんな様子だったかというと帚木のP131、なが雨晴れまなきころ・・・ 物語は続いています。
かくのみさぶらひたまふ→同じく1巻目のP131、いとど長居さぶらひたまふの部分に照応します。源氏が(藤壺がいる)内裏にできるだけいたい、けれどもそういうわけにもいかない。大殿(左大臣)が気の毒だとは思っているので、ひさしぶりに妻の実家を訪れます。
(左大臣邸の)おほかたのけしき、人(正妻=葵の上)のけはいもけざやかにけ高く、(源氏がなかなか訪れないからといって)乱れたるところまじらず、
(妻の)あまりうるはしき(=あまりに隙のない整いすぎた美しさ)様子にうちとけることもなくさうざうしくて
中納言の君、中務などやうの、おしなべたらぬ若人(いずれも左大臣家の女房)を相手に冗談などを言って過ごします。
暑さに乱れたまへる御ありさま・・・源氏が暑さに服をすこしだらしなく着崩している様子。もちろん皆きちっとした服装をしているわけですが源氏なので女房たちも見るかひあり と思うのでしょう。
「あなかま」・・・うるさい、静かに、という意味ですが、現代で言えばひとさし指を口にあてて「しっ!」というような感じでしょうか。几帳のむこうの左大臣に聞こえないように言ったはずです。
女房は左大臣家つきの女房なのでもちろん葵の上に忠心をもっているのですが、その前にそれぞれがひとりの女性です。あの弘徽殿ですら、恋敵の桐壺はにくくても息子の源氏(それも成人前の少年)のあまりの美しさに女性として色気を感じたのですから、若い女房がこうして自分たちのまえでリラックスしてうちとけている成人した源氏の魅力にとりつかれないわけはなくのではないでしょうか。
女房たちの様子が生き生きと描かれているのに対して葵の上のことが描かれていても人物としてというよりは形容が「左大臣家」と並列されて「けざやかにけ高く」と、左大臣家そのものの描写のようです。左大臣家で当の左大臣や兄の頭中将より誰よりもその「家」を感じさせるのは葵の上のような気がします。感情がよみとれる部分がほとんどなく、だからこそかえってみえない彼女の心の動きが気になり、想像してしまいます。
葵の上は、今後(人間違えをしてしまって、という場面もありますが)源氏がおのずから関係をもつ女性たちとはちがって唯一最初から与えられた政略結婚というかたちで婚姻関係を結んだ女性です。もし、彼女とうまくいっていたら(正妻にたいして「さうざうし」という感情を持たなければ)「源氏物語」は成立しなかったのでは、と思うと本当に物語の構成の精巧さにあらためて感心させられます。
葵の上にたいして思い入れがあるので、感想がつい長くなってしまいました。この後「方違へ」「中の品の家」と続きますが、今日はとりあえず。明日は校了前の休日出勤です・・・。
方違へ
さかし(=そのとおり)
二条の院(=源氏の私邸)も同じ筋(=内裏からみて左大臣邸とおなじ方角)にて、・・・なやましきに(なやむ=病気、からだが疲れている、で現在の「悩む」とは違う)
「いとあしきことなり」解説にもあるとおり、相当強い語気で、女房が上のものにはふつうは使わないのですが、とにかく寝てしまおうとしている源氏になんとか方違えしてもらいたいようです。
紀伊の守(=従五位の受領で、左大臣の家来筋)
中川のわたりなる(=にある)家 この家は紫式部が実際に住んでいた家をモデルにしているのではないかと言われているそうです。
牛ながら(=牛をつないだまま)、(門内に)ひき入れつべからむ所を。・・・目上の者の家を訪れるときは家のまえで車を降りなければなりませんが、家臣の家であれば牛車のまま中まで入れる。
忍び忍びの御方違へ所(=女のところ)は、あまたありぬべけれど、(左大臣のところへは)久しくほど経て渡りたまへるに、方塞げて、ひき違へほかざまへ(=全く違うほかの女のところ)と(左大臣が)おぼさむは、いとほしき(=気の毒)なるべし。
紀伊の守に御せ言(=命令)賜へば、(紀伊の守は)うけたまはりながら、(源氏の御前を)しりぞきて、
伊予の守の朝臣(=紀伊の守の父)の家につつしむこと(=忌みごと)はべりて、女房なむまかり移れるころにて(女房たちまで連れて皆で来ている)、(自分の家は)狭き所にはべれば、なめげ(なめし=失礼、無礼)なることやはべらむ
下に(=陰で、ひそかに)嘆くを(源氏は)聞きたまひて、
その人近からむ(=近くに人がいる気配)なむ・・・・ただその几帳のうしろに(泊りたい)
「げによろしき御座所にも」・・・源氏の冗談に対して女房はそれを制するのでなくさらに輪をかけるような受け応えをして場を盛り立てます。さすが左大臣家の女房、という感じです。
中の品の話は昨晩さんざん聞かされていたこともあり、興味が湧いた源氏は、先ほどまで疲れて眠かったというのにいそいそと大臣にも挨拶せず(大臣にも聞こえたまはず)親しいものだけ=むつましき限り)を連れて紀伊の守邸へでかけます。
中神・・・陰陽道で説く神。60日を周期として、その間16日は天上にあるが、ほかは5,6日ずつ八方に遊行する。この神のいる方向を「方塞がり(かたふたがり)」として忌み、「方違へ」をする。
そんな具合ですから京ではしょっちゅうぐるぐるみな回遊していたようです。方違えの風習は現代にも残っている(結婚のときなど?)ようですが、残念ながら私にはよくわかりません。風水などで「方角が悪い」とか言いますし、おみくじや占いでも吉の方角、凶の方角などありますが、ご存知の方教えてください。
主語を補いながら書いていくと、原文は敬語の使い分けで主体が誰であるのか自ずからわかるようになっていて、結果として流れるような美しい文体になっているのだな、と思いました。学生時代はこれで悩まされ、原文を味わう余裕がなかったように思います。
中の品の家
(紀伊の守は)にはかにとわぶ(=思い煩う、困り果てる)れど、人(源氏も供の者も)も聞き入れず。
寝殿の東面払ひあけさせて(=すっかり開けさせる)、かりそめの御しつらひしたり。水の心ばへ(中川の水を邸内に引き入れていること)など、さるかたに(それなりに)をかしくしたり。田舎家だつ柴垣して、前栽など心とめて植ゑたり。
風涼しくて、そこはかとなき虫の声々聞こえ、蛍しげく飛びまがひて、をかしきほどなり。
人々(供人たち)、渡殿より出でたる泉にのぞきゐて(=座り込んでのぞいて)、酒飲む。
主人(=紀伊の守)もさかな(=酒菜。当時は酒の肴はだいたい木の実や果物を指したそうです)求むと、こゆるぎの急ぎありくほど、君(=源氏)はのどやかにながめたまひて、かの中の品に取り出でて言ひし、このなみ(=この程度)ならむかしとおぼしいづ。
中の品の家には行ったことのない源氏は昨晩のいろいろな話から想像していたものの、実際の家を見てみると、まあまあ、なかなか趣向をこらした様子ではある、というのが「さるかたに」にあらわれています。でもまあやっぱりどこか田舎くささを感じてもいるようです。
紀伊の守が急な来客の対応に追われている様を、(身体を揺り動かしながら歩いていることから)「ゆるぎありく」→こゆるぎ、という本来「磯」にかかる枕詞を「磯(いそ)」=「急(いそ)」にかけています。
こゆるぎに急ぐ中の品の紀伊の守に対して、上の品の源氏はというと、のどやかにながめたまひて、ですから一文の中でみごとに対照があらわされています。
「こゆるぎ」がでてくる歌には次のようなものがあります。こゆるぎは身体を揺り動かす、というほかに心の動揺の意味もあるようです。右近の作品は女性らしくて好きです。
わかめ刈る春やこるらむこゆるぎの磯のあま人波にまじれり(源兼澄・万葉集)
とふことを待つに月日はこゆるぎの磯にや出でて今はうらみん(右近・後選1049)
1月21日に進んだのはここまでです。
「葵の上」に思い入れがあるといっても、わたしも読んだのは与謝野晶子訳の「桐壺」の章のみです。読んだのが小学生のときで、子供が想像していた結婚像とあまりにちがったのがショックで、その心情を語られない女性に非常に興味が湧いたのがそもそものきっかけでした。「白鳥の湖」の悪魔の娘(オディール?)や「白雪姫」の継母など、通常「悪役」とされるひとたちに興味をもつ性質なので。単純な勧善懲悪って都合がよすぎてリアリティに欠けると思うんです。ほかの女性について知っているのは漫画「あさきゆめみし」や橋本治訳(高校生の頃はやったんです)の源氏からです。その後原文でよむのは試験や受験対策で常に「主語は誰か?」「空欄を埋めよ」だったんで、原文をじっくり味わう余裕もなく過ごしてきました。なので、わたしも毎回はじめて知ることばかりです。これからもどうぞよろしくお願い致します。
朴文順
12月17日 例会報告 帚木第十回 浜岡はるみさんと沈光子さん
蒜食いの女 その一
1)蒜 ⇒にんにく 野蒜 ⇒野の蒜
2)けしきある ⇒変わっていて面白い
3)なでふ ⇒なじょう :なんていうかどうという事もない
4)文章生 ⇒当時の官僚コースの学生。身分のない者が官吏になるためのコース
5)かしこき女 ⇒漢文の出来る女
6)公事 ⇒宴会の時の詩作
7)才(ざえ) ⇒漢学
8)『わがふたつの途歌ふを聴け』⇒これは、白居易の『白氏文集』の中の『議婚』という歌の一部
『議婚』
主人会良媒 主人良媒を会す
置酒満玉壺 置酒して玉壺(ぎょくこ)に満つ
四座且勿飲 四座飲むなかれ
聴我歌両途 我がふたつのみち歌うを聴け
富家女易嫁 富家のむすめは、嫁(か)しやすく
嫁早軽甚夫 嫁すること早くしてその夫を軽んず
貧家女難嫁 貧家のむすめ嫁(か)し難たく
嫁晩考於姑 嫁する事遅くして姑の考なり
聞君欲娶婦 聞く君婦をめとらんと欲すと
娶婦意如何 婦をめとる如何(いかん) ?
9)いときよげ ⇒美しい字
10)消息文 ⇒恋文
11)仮名(かんな) ⇒真名(まな):漢字
12)むべむべしく ⇒格式ばった、漢文調
13)腰折文 ⇒下手糞な歌:漢文調の続きの良くない歌
14)なつかしき妻子 ⇒日常語ではない表現:漢文調に面白おかしく表現した
15)無才の人 ⇒私の事
16)なまわろならむ ⇒なまわろし:どことなくみっともない(振る舞い)
17)すかい ⇒すかす:騙す、その気にさせる
18)をこずき ⇒おこ+づく:馬鹿みたいに →加山雄三みたい?という意見あり
式部は、源氏や中将に比べれば相当下位になる訳で、変わった面白い話をしなくてはいけない訳です。せかされて彼は、官僚コースの学生として学んでいた頃知り合った、漢文の出来る博学な女の話を始めます。その女は、ある博士の娘で、博士には娘たちが多くいて、博士の家に生徒として通っているとき、その一人に言い寄ったところ、親の博士が聞きつけて、さかづきを持って出てきて白居易の歌を出して、娘を嫁にしてくれるよう迫られ、そんなに気はないのにずるずると付き合っていきました。女は、式部のために漢文の歌作りから様々な宮廷に勤めるための知識を教え、恋文にも仮名を使わず、漢字で格式ばった表現で美しい字で書いてきました。当時漢字は男のもの、仮名は女のものという暗黙の決まりがあったにもかかわらず、彼女は男の教育のために漢文で書いてきたんだと思いますが、相当な博学の女でありました。劣等感もあり、段々足が遠のいていく式部でありました。中将が興味を示し、更に話をさせようとします。
蒜食いの女 その二
1)心やまし ⇒嫌な感じ
2)物越し ⇒几張とか屏風が間にある
3)ふすぶる ⇒(女が)嫉妬する
4)またよきふし ⇒(別れるには)またよきふし
5)さかし人 ⇒女
6)はやりか ⇒せわしない、気が高ぶっている →久し振りに来たので喜んでいる
7)風病 ⇒神経痛という説
8)極熱の薬草 ⇒熱さましの薬
9)雑事等 ⇒着物等のお世話をする事
10)あわれに ⇒愛する人の心に届く様に →しかし、『むべむべしい』
11)さうざうしい ⇒物足りない、淋しい、あるべき物がない
12)何とかは ⇒(あまりの事に)何も答えられない
13)高やかに ⇒声高に
14)逃げ目 ⇒逃げる時の目つき
15)ささがに ⇒蜘蛛 →ささ:小さい 蟹
16)ひるま ⇒昼と蒜の間(にんにくの臭う間)
17)あやなさ ⇒納得いかない、筋が通らない
18)ことづけ ⇒口実 →自分を追い返して他の男と会うんだろう
19)し ⇒強め →夜を強める
20)なにか ⇒反語
21)まばゆからまし⇒恥ずかしくない
22)口 ⇒(和歌を返す)読み
23)疾く ⇒速い
24)しずしず ⇒式部の表情 →おもしろく、三枚目にとぼけて
25)むくつけき ⇒ぞっとする
26)爪弾き ⇒非難する
27)いわんかたなし⇒どうしようもない
28)あはめ ⇒けなして
長い間通わなかった式部がある日ついでに立ち寄ったところ、女は下熱剤としてにんにくを食べていました。当時、上流の人たちが病気を治したい場合は、祈祷師に頼むのが普通で、決してにんにくなぞ食べないそうです。彼女は貧しい暮らしをしていた訳です。
女は、むべむべしさが身についてしまっていて、男が来た事を飛び上がる程に喜んでいるのですが、にんにくの臭さに狼狽し声高く、この臭いがなくなった時に来てくださいと漢文風に堅苦しく言います。式部には理解できない女の振る舞いに、『蜘蛛も巣を張ろうという夕暮れなのに昼間(にんにくの臭う間)に来いとは納得いかない。自分を体よく追い返して他の男と会うんだろう』と捨て台詞。返して女は、『毎夜隔てないで会う仲だったらひるま(昼と蒜の臭い)会っても恥ずかしくないのに』と言い返しました。さすがに返歌は速かったと、中将たちにとぼけた言い方をする式部。病気ににんにくを食す事といい、漢文に秀でた女の事といい上流社会の男達には想像出来ない世界で、鬼と話した方がまだましだとまで言います。階級のギャップを感じる話です。恋する女のけなげさが感じられました。
この話に似た落語があった様な気がしますが、江戸時代ですよね。向田邦子の短編『花の名前』も思い出しました。ささ蟹って言うのが蜘蛛というのは、とってもヴィジュアル的な表現だと思いました。
年越してしまいましたが、『女性論の果てに』は出来たらまた後で。出来なかったらごめんなさい。
以上浜岡でした。
以下から沈光子さん
この巻きではつそれにしても、くづく階級社会の文化ギャップを教えられましたね。
蒜食いの女 は貧しい学者の娘。
父親にしてみれば貧乏人の娘沢山で、ひとりでも早く片付けたいところ。
娘に興を示す男がいれば、それ! と押し付けんばかりに縁づなくちゃ、後がつかえてる。娘にまんざらでもない男が現れて、ヤレヤレ、一丁上がり、と胸をなでおろしたでしょう。
娘は門前の小僧習わぬ経を読む で男の学問ばかりしっかり身についていて、恋の手習いの方にはトント縁がないのね。男をからめとる肝心の手練手くだが身についていないの。
恋の語らいでも、口に出るのは堅苦しい漢文調。
男にしてみれば興醒めなことこの上ない。
でもそこはお互いにまだ初心な頃の、それも下々の階級のことですから、なんとかそれなりに過ごしていたんだわ。
女に逃げ腰になっても、これからの出世に彼女の漢学の知識は必要不可欠。
やんごとなき生まれの公達たちと違って、試験に受かっていくことでしか階段を上っていけないのですもの。
上が上の公達たちにはとうてい理解できない下の階級の者たちの暮らしぶりを、藤式部は自分を笑い者にしながら、座をしらけさせまいとして語ったのね。
さすが宮仕えで鍛えられた苦労人の藤式部。自分の求められているもの、己の分を知る男なわけ。
それなのに、そんなバカな話(晴美ノート参照・極熱の治療に蒜を食う)があるもんか と信じようとしないのね。信じられないくらい、下々の生活を知らないわけ。
香を選りすぐり、焚き染め、気を持たせた恋の歌を詠んでみせる女 しか知らない彼らには、蒜の臭いをさせながら、衝立超しに男と会う女なんて 鬼の方がまし、なんていう感覚なのよ。
「さわりがあるので」とことづけて帰すこともできるのに、男に会いたい一心の女の純情が、裏目に出てしまっているのが哀しくも可笑しいね。
藤式部もほうほうのていで逃げ出すんだけど、可笑しさの中にも彼の温い人柄が感じられます。
藤式部はすまして「すこしよろしからむことを申せ」と責められても「これよりめづらしことはさぶらいなむや」とすましています。
これ、上が上の公達たちへのささやかなレジスタンスよね。
女性論の果てに
女が思いやりのない文などよこして男を困らせる「わろもの」事例がでてきます。
知ったかぶりで才のあるところを見せびらかすように、相手の状況もわきまえずにありったけの知識をひれかしているのは興覚めなもんだ、と左馬頭が女の教養について語り、女性談義の落ちをつけます。
どんなたくみな歌であれ、「つきなきいとなみ」場違いで時をわきまえないのには閉口させられますなぁ、などと気がきかない女を嘆いています。
当時は女から歌をもらえば何がなんでも返歌しなければ無粋な男にされてしまうんですから、心ここにあらずのまま返歌するのもうっとうしい。
官吏として大事を前にして頭がいっぱいの折に、風流ぶったすばらしい歌が届いても「なかなか心後れて見ゆ」と左馬頭はいいます。
左馬頭の理想の女像についての本音・結論が語られます。
それを聴きながら源氏はただ一人の女性への思いに「足らずまたさし過ぐべくなむあべかりける と言うにも 君はひとりの御ありさまを、心のうちに思いつづけたまふ。これに、足らず、またさし過ぎたることなくものしたまいひけるかな」と比べようもないあこがれの藤壷への恋慕にひたっているのです。
話は果てもなくつづき、ついに夜を徹し朝を迎えてしまいました。
男は女の話を、女は男の話を、語りついでいけば夜を徹してしまうのは、今も昔も同じ。
みなさま、何を隠そう私め、この歳になって超し方を振り返りますと、破れた恋のひとつや二つ、手痛い思い出の三つや四つ、悔しい思いの五つや六つ、いえいえ涙をしぼった晩は数え切れないほどありますです、ハイ
11月19日 例会報告 帚木第九回 浜岡はるみさん
常夏 :ナデシコの栽培品種。花と葉の色がともに濃く、一年じゅう花が咲く。
四人の話は続きます。中将が、『痴れ者:愚か者・ばか者の話をしよう。』と始めます。
この、痴れ者とは中将自身を指すか常夏の女を指すか二つの説が五分五分にあるそうです。
田中先生は女の方をとるそうですが、貴女はこの章の終わりにどちらを選びますか?
それ程に今回の常夏の女は、男と女の考える内容のギャップが激しく理解するのが難しい章でした。
しかし、田中先生の解説はその難しさを充分理解させてくれます。解説は、そちらをお読み下さい。
関係の説明をします。
中将 :紫の上の弟で、源氏とは義兄弟になります。彼は所謂おぼっちゃまである訳です。
常夏の女:貴族ではあるのですが、落ちぶれて親も亡くなり中将との間に女の子がいます。
北の方 :第一夫人は年上で、高貴な家の娘で、中将が常夏の女と関係する事を極端に嫌っている様です。
P-221
1)いと忍びて ⇒:北の方には絶対内緒で
2)見つ ⇒:会う
3)たえだえに ⇒:時々
4)うち頼める ⇒:夫として頼りにする
5)たまさかなる ⇒:時々、たまに
6)もてつく ⇒:とりつくろう、装う
7)頼めわたる ⇒:頼みに思わせ続ける
8)ありきかし ⇒:あったなーと思い出している
9)ろうたげ ⇒:いじらしい げ:客観的な見方
妻について:一番最初の妻は、源氏の結婚に出てきましたが、ある程度の地位のある家の女で年上ですが、その後の妻たちは、
三日通うと妻にしても良い事になっていたそうです。
P-223~224
1)のどけき ⇒:のどかで心配のない
2)おだしく ⇒:ゆったりと穏やか
3)この見たまふる⇒:北の方
4)情けなく ⇒:容赦なく
5)うたて ⇒:嫌がらせ
6)かすめ ⇒:におわす、ほのめかす
7)むげに ⇒:すっかり
8)思いしおれて ⇒:気が滅入って
9)撫子 ⇒:なでるように大切に扱う→子供でおそらく女 覚えていますか?小萩→男の子
中将の鈍感さ:『いさや、ことなることもなかりきや』ですって。若いって事は鈍さと鋭さが共存しているんですね。本人は自分の鈍感さ
を全く自覚していない。最近の日本の若い男の子たちにも見られる現象です。要するに想像力の欠如。
P-226
1)うら ⇒:心、見えないもの
2)もの思い顔 ⇒:憂わし気な顔
3)きほへる ⇒:競争する 虫の音と競ってしくしく泣く
4)常夏 ⇒:撫子の異称・別名 女の事
5)大和撫子⇔唐撫子
6)ちりをだに ⇒:古今集 おおちこうちのみつね の歌に
塵をだに据ゑじとぞ思ふ咲きしより妹とわが寝る常(床)夏の花
7)うち払う ⇒:塵を払う⇒中将を否定する意味と ⇒:涙にくれている意味
8)常夏 ⇒:私
9)あともなく こそ しか ⇒:強調して、中将のショック状態を表している
中将は女に嫌われてしまった事すら気がつきません。自分が薄情者と思われたくないという自己愛。一方女は、北の方の嫌がらせを受けながら関係を続ける事に対する自己嫌悪の形の自己愛。中将は女に去られて初めて面と向かって付き合ってこなかった自分を後悔する訳です。家をあともなく空にする事は、家人多勢を引き連れて消え去るわけですから、ものすごいエネルギーを要します。常夏の女の怖いまでのプライドと強さを感じて、ぞっとします。私だったら、しょうがないなって居座ってしまいます。
常夏って床との掛詞以外に、一年中咲くっていう事から、いつでも変わらない女っていう意味が含まれているのでしょうか?田中先生。
P228~229に常夏すなわち夕顔の性格が書かれています。夕顔の章が楽しみですね。
常夏の女 その二へつづく
常夏の女 その二 2003.11.19
P-229
1)はかなき世 ⇒:心細い身の上
2)ましかば まし ⇒:仮定 反実仮想
3)あくがら ⇒:フラフラと浮かび出る
4)こよなき ⇒:こんなに
5)さるもの ⇒:妻
6)尋ねる ⇒:住所が解らずあちこち捜す
7)これこそ ⇒:この女こそ
8)つれなくて ⇒:女がつれなくて
9)やうやう ⇒:次第に
10)かれはた ⇒:あの人はまた
11)たもつまじく ⇒:関係を持つ
中将は、自分を捨てて行った常夏の女について現実を見ようとしない、見たくないんです。女が自分の庇護を拒んだ深い訳までは解りません。落ちぶれて今でも中将を思い続けている哀れな女にするっきゃない男としてのプライドなんでしょう。でも幼い女の子を心配する親心はしっかりあるようです。この辺は沈さんに書いてもらったら、とっても面白い所だと思います。お願いします。
P-232
1)さしあたりて見む ⇒:一緒に暮らす
2)よくせずは ⇒:悪くすると
3)あきたし ⇒:うんざりする、飽きる
4)すきたる ⇒:浮気っぽい
5)この心もとなき ⇒:私の頼りない女
6)疑い ⇒:男がいたという疑い
7)添う ⇒:男に走ったと言う事を添え
8)くさはひ ⇒:非難すべき点のある
9)法気づき ⇒:抹香臭い
10)くすし ⇒:薬臭い
今までの指喰いの女、木枯らしの女、常夏の女を中将がまとめています。
先生の解説の中の、『常夏の女が、どこにでもいそうな陳腐な女に変わってしまっていた。』という文章が、中将と常夏の女の心のギャップを表していると思いました。そして、痴者について、最初は中将が自分を卑下していると思っていたんですが、最後になって女の事を言っていたんだと解りました。ちょっとひどいなと思いました。ここも沈さんに書いて欲しい所です。
その二は、スピードアップして終わったので追いつかない感がありました。文の奥に隠れた言葉がとても難しかったです。
いろいろな方のご意見を聞きたい章です。聞かせて下さい。
10月15日 例会報告 帚木第八回 沈光子さん
「木枯らしの女 」 が終わり、次回は 「常夏(なでしこ)の女 その一 」 221ページからです。
木枯らしの女 の情景描写、美しかつたですね。
左馬頭は指喰いの女の嫉妬に悩まされながらも、つまみ喰いが止みませんでしたね。
女を頼みにしているのに、とまりにと思うには少し物足りない気がして、浮気が止まなかった。
でも亡くしてみて初めて、彼女がいたればこその我ががままだったと気づいたのね。
左馬頭は、木枯らしの女を冷静に観察していますね。
同時に 指喰いの女が 自分にとってどれほど大切な女だったか、また自分のような者をどれほど大切に思ってくれていたかを、思い知ったのよね。
若気の至りを悔やむ左馬頭の気持ちが、何事にも派手派手しい木枯らしの女を冷静に観ていることで推察されます。
左馬頭に見られているとも知らない木枯らしの女は、通ってきた眼の前の男へありったけの才を総動員して、丁々発止と恋芝居を演じきっているし、また彼女はそれが身についているのね。
俺のときも女はこんなふうだったよなぁ。左馬頭はきっとそう思ってシラケタわね。
でもあの時は、それがとても魅力的にみえたし、俺はそれにふさわしいエエ男なんや、なんて身のほど知らずにのぼせ上がって、恋多き女にうつつを抜かした。
指喰いの女の嫉妬につれない態度で報い、喧嘩が絶えなかった。
あげくに一途な思いを寄せてくれていた大切な彼女を失ってしまった、って覚めた眼で観てるね。
だから情景がいっそう凛として読者に響いてきた。
悲ししかな、人間ってさぁ、無くしてみなけりゃわからない、ってことあるよね。
あってあたりまえのものは、ちっともありがたくないのよね。でも無くして初めてわかる関わりの深さ。
これって胸に覚えがある人、多いんじゃないかしらん。
左馬頭だけじゃないね、悲しいかな人は無くしながら成長していくのかも。
哀切を知るこの年齢になるまでには、私も大切なものずいぶんと無くしてきたんだわ。
木枯らしの女の屋敷の庭が月明かりに映えている様が、叙情的に描かれていて想像をかきたてます。
池には月が映っているかも、みたいな解説がありましたが、池は薄明かりの中で、ボウウトそれらしい姿を浮かび上がらせているだけだと思う。
吹き抜ける風が、燻し銀のようにな池の面に走っていく。一瞬、波頭が月明かりできらめく。
池に月が映えると派手派手すぎる。左馬頭の心情に合わない感じがするなぁ。
左馬頭は最後におっさんらしく教訓をたれましたが、源氏は彼の蛇足に成熟した男のするどい一言を述べましたなぁ。左馬頭より七才も下なのに、育ちの良さはこういうふうに出るものなの?
にくらたしいほど格好いいのね、源氏は。
ああ、早く源氏が女に翻弄されるところへ読みつきたいなぁ。出来すぎの源氏なんて、手が届かないもん。人間の苦しみを幾重にも孕んでいく源氏にたどりつきたいなぁ。
浜岡はるみさん
木枯らしの女 その一
左馬頭の話は続きます。
1)うち読み :歌を詠む教養
2)手つき :書の才能
3)口つき :歌を即興で吟じて読む
4)さがなもの :本来は、たちの悪い、手に負えない。指喰い女に対する親しみの表現
5)艶 :異性を意識する振る舞い
①あでやか ②優美 ③なまめかしい
6)ありけらし :過去の推量で、あったようだ
7)神無月 :旧暦の11月 今の暦では初冬
旧暦 春1~3月 夏4~6月 秋7~9月 冬10~12月
8)うつろいわたる:霜で変色した菊が辺り一杯にわたって
9)きほへる :競う
10)紅葉の乱れ:枯葉が舞っている
【まとめ】
指喰い女が居た頃には、何にでも有能なその女は左馬頭の中で輝いていたけれど、指悔いが居なくなってみると自分には(まばゆすぎる)存在となっていき、指喰い女を思う気持ちもあり、段々足が遠いていきました。そんな中でその女には誰か通って来る男が現れたようです。
神無月のころほひ・・・・からは、映像を見ている様な素晴らしい文章です。内容は、本で読んでください。
今回は、何と言っても【月】です。
まず浮かぶ景色です。
初冬の冴え冴えとした明るく白い月の下、池に映る月、霜で色褪せた一面の菊と、風と競うように舞う枯れた紅葉の枯葉を映す月の光。私たちは、また漆黒の闇の中の月について話しました。思い出されるのは、【桐壺】の中の(夕月夜の訪問)の月です。この月は、もう少し早い秋でしたね。月影ばかりぞ、八重葎にもさはらずさし入りたる。
私は、改め古代の月を思いました。百人一首の中にも沢山の月があります。何の気なしに読んでいたあの月たちをもう一度思い直してみたいと思いました。そして、竹中さんが犬の散歩で早朝に見る(ありあけの月)のお話をしてくれました。雪の夜の月も又話題になりました。子供の頃、月を見ながら歩いて、自分が止まると月も止まったあの月は、本当に美しかった事を思い出しました。東京の月は周りが明るすぎて可愛そうと思ったのは、上京したばかりに思った事でした。意識して月を観る暮らしをして見ませんか?あまりに多くの光たちに、負けそうになっている今の月を観てあげようではありませんか?
次は音楽です。
横笛の冴え渡る音、次いで和琴の美しい調べ。和琴は本当に美しい音を出します。雅楽演奏会で知りました。
最初は、6弦琴を奏で、その後13弦の琴に変えて演奏するなんて、なんていう才能でしょう。ちょっとやり過ぎですけどね。
でも、香田さんが言った様に、男が来ないんだから、とやかく言う筋合いではないとは思います。女は一生懸命なんですから。
木枯らしの女 その二
左馬頭の、(艶にあえかなるすきずきしさ)を持つ女へのあまりに美しいイメージに、再度紫式部の文才を感嘆しました。
折らば落ちぬべき萩の露 拾はば消えなむと見ゆる玉笹の上の霰 ですよ~。
この頃雨の日の草の上の露の玉の美しさに気がつき感動しています。露を沢山休ませる草とそうでない草があった事も。
なまめかしく、消え入りそうな艶っぽい色気に対して若い心は無防備ですよね。それが自然ってもんでしょう。
最後に久しぶりに源氏が出てきました。
次回は、常夏の女 その一からです。
源氏物語の中では、重要な章です。皆様お出かけ下さい。
ちなみに、常夏とは、撫子の一品種との事です。ハワイの女ではありません。念のため。
以上【月】に感動した浜岡でした。追加、訂正、ご意見お寄せ下さい
9月17日 例会報告 帚木第七回 香田直子さん
例の「指食い事件」があって、しばらくたった頃です。
賀茂神社のお祭りの雅楽練習が夜遅くまであった日、さてどこに帰ろうと─
能天気な左馬頭は思いを巡らすの。
外は雪がチラホラ、職場に帰って寝るのも辛いし、面倒な女の所にもいきたくないし……
そこで、もうそろそろ「指食い女」の恨みも解けているに違いないと、
のこのこと帰るの。帰ってみると、外の寒さを慮ってか、着物を温めて
今夜こそ帰って来るだろうと待ちかねたようになってるのね。
「わぁーい!やっぱり待っててくれたんだ」と喜びも束の間……
肝心要の彼女の姿がない。いつものおつきの女房共がいるだけなの。
彼女は親の家に「ひきこもり」をしているのです。
何の言付けもなく、彼は「嫌われちゃったのかなぁ─」とか、
「他にオトコでも出来たんかな?」なんぞと、うだうだ悩んだりもするのね。
だけど、中々吹っ切れない左馬頭は「やり直そうよぉ!」ってしつこく迫ったり
してみるのだけど、彼女としてはいくら大好きな彼であっても、
自分だけのオトコじゃなきゃイヤな訳で、なのにお馬鹿さんの彼氏は
彼女の本当の気持ちが理解出来ないのですよ。
で、そうこうしてるうちに、彼女は苦しみ抜いて死んじゃうの。
そして、『結婚するならあの女がよかったのになぁ……』なんぞと、
左馬頭は暗~くなったりしてね。
それに気を使った中将は話を明るい方へ持って行こうとする。
彦星と織姫の長き契りにあやかりたいもの……
「結婚相手を見つけるのはやっぱり大変なことで、
結論なんて、簡単にはでないんだよ」 ってまとめましたとさ。
あの頃のオンナ達は、糸を紡ぎ、染め、織り、縫い……
愛(いと)しいオトコの為に頑張ってたのよねぇ。
ちよっとだけウラヤマシイなぁ─なんて思う今日この頃のワタクシの
いい加減な解釈でした。どうぞ皆さま鵜呑みになさいませんように
御忠告申し上げます。
なおこ様 浜岡はるみ
ほんに、何と自分勝手な男たちなんでしょう。未成熟がそのまま許されるのは、今とあまり変わっていないかも。
でも、それが男の一つの魅力でもあるのですが。彼らも暮らしのために、後見の女たちは必要なんですし。
例えば、指喰い、木枯らしの女を同時に相手にしてたら、その女の性格を理解し、
その幸せが何たるかを想像するのが賢い男ってもんでしょう。
女は成長していきます。変わっていきます。それを可能にするのは男の力でもあると思います。
左馬頭は、若かったんで、複雑な男女間の関係を上手くやるのはまだまだだったんですが
そうこうして、彼も大人になっていったんでしょう。
8月13日例 会報告 帚木第六回 浜岡はるみさん
指喰いの女 その一
左馬頭の、まだとっても若かった時のお話です。
はやう、まだいと下?に・・・・からです。
1)下? :勤めてからの年月が短く、その社会で地位の低い人。〔狭義では、年功を経ない僧を指す〕
⇔じょうろう(ジヤウラフ)【上?】
年功を積んだ上位の僧または、上位の△女官(御殿(ゴテン)女中)を指した語。
〔広義では、身分の高い婦人を指す。「女郎」は、この変化〕 ⇔下?(ゲロウ)
2)あはれと⇒心を動かす程忘れられない
3)すき心 ⇒女に対する好奇心
4)『とまり』と『よるべ』:
『とまり』⇒留まる、添い遂げる
『よるべ』⇒頼みとする妻ではあるが・・・・
5)さうざうしい ⇒あるべきものがなくて寂しい
6)まぎれ ⇒他のもの(女)に興味を示す
7)もの怨じ ⇒嫉妬
8)おいらか ⇒おおらか、おっとり
9)数ならぬ ⇒人の数に入らない、一人前でない
10) 見も放たで ⇒見放さず⇒女の方が身分が上
11) なき手をいだし ⇒無い知恵を絞り
12) くちおしい ⇒取柄の無い
13) みさを ⇒我慢、辛抱して
14) けしう ⇒否定の褒め言葉
15) 憎きかた ⇒嫉妬深さ
16) 心をさむ ⇒納得いく
【まとめ】
左馬頭がまだとっても若かったとき、今でも忘れられない女がいました。彼女は彼より身分が上で、おそらく年上の
様に思われます。若い男は自信があるんです。他にまだまだ良い女がいると思うのです。そんな訳で、彼はその女
を、頼みとはしながらも、他の女たちへの思いを絶ち切れず、いつも女の嫉妬に悩んでいました。
この女は、優れた妻とはいえないけれど、この人のためならと無い知恵を絞って、一生懸命男に尽くし、見栄えの
悪さも化粧して、男にうとまれないよう勤め、男が満足出来る合格妻であったのですが、唯一情深さ故の嫉妬深さが
男にとって最悪であったのです。
指喰いの女 その二
そのかみ・・・・・
1)かみ ⇒当時
2)おじたる ⇒(自分を)恐れている
3)かた ⇒嫉妬
4)さがなさ ⇒口うるささ
5)絶えてまた見じ ⇒もう決して会わない
6)なのめ ⇒いい加減に
7)思ひなりて ⇒考えを変えて
8)われたけく ⇒得意満面(自己の未熟さは意識している)
9)言いそし ⇒まくしたてる
【まとめ】
その当時と左馬頭は回想している。
その女の従順さを深く信じていた彼は、強行な態度で今の関係を脅かすと女が嫉妬する心を改めるであろうと考えて心なら
ぬ芝居を打ったんです。未熟ゆえに、われたけく、ちょっと子供っぽい高めの声で。と思うのですが。
すこしうち笑いて・・・
1)みだてなく ⇒見栄えがしない
2)人数なる ⇒一人前になる
3)あいな頼み ⇒あてにならない望み
4)かたみに ⇒お互いに
5)そむき ⇒別れる
6)きざみ ⇒時
7)ねたげ ⇒妬ましいほど冷静に
【まとめ】
ふふん・・行ってくれるわね。って感じで女が言います。
あらゆることに見栄えのしないあんたが一人前になるのを楽しみに、心変わりを我慢して耐えてきたけれど、当てにならない
望みだったわ。お互いに別れる時が来たようね。と、妬ましい程冷静に言われ、左馬頭は逆上して憎たらしい事ごとを更に
言い放ったその時、女は男の指ひとつ(どの指でしょうか?人差し指ではという意見)を喰いました。女の愛情です・
ねたげとかにくげとか今風の表現が出てきて面白いですね。
おどろおどろしく・・・・
1)かこち ⇒嘆く
2)まじらひ ⇒宮仕え
3)いとどしく ⇒いよいよもって
4)人めく ⇒人になる
5)世をそむき ⇒出家する身になって
6)言ひおどし ⇒言いがかりをつけて
7)あくがる ⇒魂が肉体から出てフラフラする
8)ありく ⇒あちこち移動
【まとめ】
何故だ?痛さとショックで、『こんな傷者になったら、宮仕えだって出来ないし、一人前にもなれないし、出家するしかないか
もしれないじゃないか!』などと言って、『さらば今日こそは限りなめれ!』と言いました。
不思議なのですが、最後にあんたの嫌いなところは、たった一つだけだったよっていう歌を詠んで別れました。。
そうはしたものの左馬頭は、女は今迄とおんなじで変わらないだろうと、たかをくくって、フラフラあちこちして、女から逃げてい
ましす。
以上が8月の報告です。
嫉妬深さは、愛情の一面だっていう事が解るまでは、まだまだの左馬頭です。
年上の女の若い男に対する心の微妙さが、良く解るお話ですね
[
7月16日例会報告 帚木第五回 工藤さん(新人)
今回の女の心変わり、法の師左馬頭、も、面白かったですね。
何事も基本が大事というようなことを、考えさせられました。絵について、唐絵と大和絵についての日本人の
受け取り方の違いなど、また、目からうろこが落ちるような発見がありました。古語の、なつかしき という言葉が
近づいていきたくなるような優しい感じという意味ということが、なるほどーっという感じでした。
というのは、今、私が懐かしいという言葉を使うときに、思い出がよみがえって懐かしいと言うときと、
なんか懐かしい感じがするという郷愁について言うときと、両方あり、なんとなく、自分で不思議だったのですが
もともとの意味がこういうことで、現代の意味になったのかな、などと思い、懐かしいという言葉が自分の中で明確になりました。
唐絵はうるわしだけれども、なつかしくはないということですね、と先生がおっしゃってましたが、
なつかし、の感覚が大事なのかな、と思いました。
前回の甘えた妻の話、私も、本当に甘えた妻なところがあります。妻としてというより、私は仕事のことを
思いました。自分が、会社で何をやりたいのか、要求もせず、勉強もせず、嫌なことがあるとすぐに会社を休んで
そういうことで、周りに、訴えようとしたり、本当に甘えていました。ちょうど、こんなことでは、だめだ、と
心を入れ替えたところだったので甘えた妻、身にしみました。やはり、逃げてはいけないのですよね。
特に、仏もなかなか心ぎたなしとみたまひつべし。
というところがぐさっときました。社会の厳しさは、今も昔も本当に変わらないと思いました。
5月21日例会報告 帚木第三回 沈さん
「葎の門」153頁から始まりました。
(先生が当時の官位の表と瀬戸内源氏の訳のコピーを用意して下さいました。)
左馬頭は若い貴公子たちにこと知り顔に、上調子な女の品定め話に気づいて
話題を変えます。
何といっても新鮮に感じるのは、葎(つる草)におおわれた落ちぶれた家の奥に人
知れず世間から忘れられたようにひっそりと住でいる、可愛らしく美しい人が閉じ
込められたようにいたりすのは、新鮮で、意外で、好き者の心をそそりますなぁ。
没落した老いた父や世をすねた兄なんかがいて、でも家の奥には気位を高く保っ
て暮らしている女がいたりするもんだよ。意外な場所にちよっとした振る舞いにも、
凛とした品格がある女がいるなんてのは、めっけもんでなぁ。
みたいなことを年長らしく、したり顔で話しています。
ここの箇所の「思いあがり」は 気位たかく保っている という意味で、現代とは異
なり、褒め言葉だそうです。
源氏の姿が語られ、育ちの良さが、崩れる一歩手前の、容姿・出自に恵まれた
源氏の、くつろいでいながらもその姿はため息が出るほど美しく、シャレぶりなんか
を描いています。ため息は作者の式部のものでしょうね。エエ男はどんな格好して
もええ男! ほれてますなぁ、式部は源氏に。
実際に源氏はたいそうおしゃれだそうです。女のところへ通うときなんかはとっても
おしゃれなんだって、先生が補足してらした。
「家の主人」(いえのあるじ) 「妻の条件」まで進みした。
坂斉さんが「妻の条件」を読んだのが、何かちょと面白かった。
男に媚びたりせず、「そういう自分は許せなかった」なんて独身談義などが、思わ
ず零れ落ちたという感じで坂斉さんが言葉少なに出たのも、「およすく会ならでは
だね。隣の高見沢さんが「そうなのよ私たち」、という感じで笑ってましたなぁ。
先生は経験からでしょうが「男は馬鹿だから、かわい気に芝居する女に引っか
かるんだわ」なんて男談義を挟んだりしたので、一同深くうなずき、はるみさんが
出席していたら、もっともっと盛り上がっただろうなぁ、って皆おもっていたんじゃない
かなぁ。
女のはかなげな芝居もばれてしまえば、興醒めで、そこのところは年長者らしく
左馬頭は過去の手痛い失敗からか、強調していた。
次回は「167ページ」からです。7月までシルバーセンターの和室がとれています。
人数も増えたことだし、今回のお部屋(1900円)でもいいんじゃない、という意見
多かったので、椅子の部屋ですし、トイレは近いし、狭からず広からずでいいねぇ
ということで、8月からはここを押さえたいと思っています。
はるみ節が聴けないのは淋しいよ。新人も入りましたし、来月も新人が来ます。
次回は元気なはるみさんにお会いできるのを楽しみにしています。元気なお姿も
さることながら、はるみ節がないとあるとでは、大違い。誰でも一人でも欠けると
淋しいね。
4月16日例会報告 帚木第二回 諏訪
今月はイメージで読む源氏物語<桐壺帚木>の巻P139の”中将の幻滅”からはじまりました。
参加者は、天田・今福・香田・沈・高見沢・諏訪
竹中・永田・浜岡・吉田さんにはじめての”くどう”さんの11名でした。
”雨夜の品定め( よき → よろしき → わろし → あし )”
高貴で若い男たちのとまどいの経験理論描写。
否定語・反語に 、二重否定など 振り回されました。
そして女の評価ポイント ”かど(才) と かたかど”
人生経験豊富な熟女たちの休憩時間での会話。
自分たちの人生の経験と照らしてうるさいこと。そして……。
なにやら うなづいた後のみなさんの結論は”男は子供だ” だった。
女性はすぐに母親をやりたがるものだなと再認識しました。
”かたはらいたきこと多かり”
「えっ! かたはらいたしとはそういう意味なの。 片腹じゃないの」
--- うさぎのおいしい山 や ウスが棲む…… 追われて見た赤とんぼ ---
沈光子の報告
「中将の幻滅」から始まりましたが、難しかったですね。
1行目から「女の、これはしもと難つくまじきはかたくもあるかな…」ですもんね。
「…しも」が強調の言葉だんて、知りませんでしたね。
「なん」も強めの言葉だし、いろいろ強調することが多い、中将の女への幻滅を説くには、ぜひ黄泉がえって「およすく会」の女に一度会うことですなぁ。
予習というほどではありませんが、「かたかど」という語彙に悩まされ、????
で先生の講義を楽しみにしていました。
それにこの章は高校生のとき「雨夜の品さだめ」として印象に残っているところです。
高校生の頃には、さわりの部分だけの授業だと思うけど、その後、すぐ夕顔にとんだので、”勝手なことを言いやがって」という印象がいまでも鮮明にのこっています。
それなのに長じて私ったら「かたかど」の下の品の男をつかんでしまい、自分はそれに似合いの下の品の女と、いじけています。
私のことはどうでもよろしい。
源氏は最上の品に囲まれて育っているし、桐壺の幻影を抱いたマザコンの君だから、なんだかんだ言ってもこれから女で苦労するのが、楽しみですねぇ。
女がわからない男には心の平安は訪れないんだから。
「三つの品」1454頁」「耳たたずかしの中の言葉「耳たたずかし」、これ現代でも使えそう。わたしの常套句にしようと思ってます。都合の悪いことはすべて「耳たたずかし」と聞き流す術は、使えます。精神衛生上、この上なく便利。医者いらずになるわ(精神科医)。
3月19日例会報告ー<帚木>第一回
浜岡はるみ
*【ははきぎ】とは、帚草の事だそうです。
5年間の空白の後、源氏は既に17歳になっています。
藤壺への思いは断ちがたく新妻への思いやりの余裕なぞ全く無いようです。
左大臣家の頭中将が、はっきりした形で(P-118の蔵人の少将と同じ人)登場しました。
源氏と中将との微妙な関係が、言葉のそこここに見られます。
今回は【恋文】の文章の、つれづれと・・・が感動的でした。大殿油は、おそらく菜種油を燃やしているぼんやりした光でしょう。
影絵の様に二人の男たちの影が映り、外は雨がしとしと降っている宵を想像出来ます。
恋文は当時の女性にとって自分を表現する大変重要なもので、内容はもとより紙の色や香り、
結び付ける季節の木や花の選択等々大変手の込んだものの様で、若い時からあまりそういう事が上手で
ない私には羨ましいです。
香田なおこ
「忍びたまひけるかくろへごと」
「なよびかにをかしきこと」
「すきがましきあだ人」
「つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵」
なんて綺麗なんでしょう!
改めて古語の美しさ、柔らかさ、優しさ、たおやかさに
感じ入りました。
内容よりも、古語に惹かれてしまいます。
1月15日の源氏読書会断片
* 『イメージで読む源氏物語1桐壷』も終わり近く、<少年源氏の恋>の場面
藤壷に恋をした源氏の気持ちが「常に参らまほしく、なずさひ見たてまつらばや」と書かれている
ことに感じたなおこさん、叫ぶ『私は23年間恋をしてました』。
* <妃と御子>の場面では皆さん「弘き殿の女御、またこの宮とも御仲そばそばしきゆぇ、うち
そへて、もとよりの憎さの立ちいでて、ものしとおぼしたり」(”ものし”は不快の感情を表す)の
文に感じたようで、例のごとく、はるみさんが『弘き殿は鋭い』とつぶやく。『ねたみっぽいひとだ』
きっと職場で弘き殿的いじめにあってるのだろう。弘き殿が出てくると妙に活気づく。母上の介護中を
ぬけだして車でかけつけてくれた久美子さんまでが、『わたし弘き殿のような姑になりたくないもん』
とおっしゃる。現文学少女のぱくちゃんが『私小学校のとき桐壺よんで葵の上に共感してしまった』と
言ったのでびっくり。
すると近寄りがたい美女ライターのさかちゃんが『<光君と聞こゆ><かかやく日の君と聞こゆ>の
”聞こゆ”にほんとうはよくわからないがーーーというパラドックスを感じる』と言う。さすが。
[読書会一覧に戻る]
|