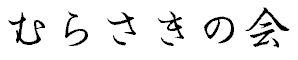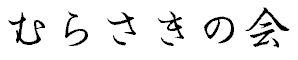

江東区女性センターパルシティーに集う主婦のグループ
そのひとり、高橋賀子さんのメッセージです。
多くの人に愛され続けている源氏物語の原文を読みながら、古文の美しさ、意味の深さ、雅の世界を堪能しています。現代にも通じる人の生き方、女性の生き方に共感を覚えます。そして知ること、理解できたとき喜びをわかち合える貴重な時間、場所でもあります。
各自分担を決め当日読んで感じたこと、意味を話し合いながら先生に補足して頂いて進めています。
現在メンバーは7人です。
参加御希望の方は江東区女性センターむらさきの会まで申し込んで下さい。
会費は1回2000円です
9月2日(金) むらさきの会
夕霧5 於:西大島総合区民センター(西大島文化センター)
テキスト:新潮日本古典集成 源氏物語六
今回:40頁9行目―48頁9行目半ば
次回:10月2日(金) 48頁9行目半ば―56頁2行目
【小見出し】
「翌日一日中、夕霧、隠された手紙を探す」
「夕方、ようやく手紙を見つける」
「夕霧、とりあえず返書を送る」
〇前回に引き続き、終了時刻が迫り慌ただしく散会したため、
参加者の「感想」は回収できませんでした。
かわりに、「“待ちぼうけ”と夕霧」の話を一席。
〇P42の注1に「典拠明らかでないが、『韓非子(かんぴし)』五蠹 (ゴト)に
宋人の田を耕す者が、兎が木の株に触れて頸(くび)を折って死んだのを見て
その株を守ってまた兎を得ようとして国中の笑いを買ったという話がある。」とあります。
これは、落葉の宮と夕霧との仲に嫉妬して、御息所(落葉の宮の母君)からの手紙を、落葉の宮からの恋文と誤解して、後ろから奪い取る雲居の雁の振る舞いに憤慨した夕霧が、「一人の女に執着する男も魅力ないよ」と諭した際に引き合いに出した、つまらない男の例です。
これを見たとき
「あっ、これは高校の漢文で習った『守株』(株を守りて兎を待つ)の話だ」
と思い出しました。
そんな漢文を知らなくても(若い人はともかく年長の方は)
「それって、あの“待ちぼうけ”の歌じゃないの!」
と、ピンとくる人も多いのでは。
童謡を通じて紫式部を身近に感じ、「へえー」と頬がゆるむ瞬間、でしょうか。
ざっとネットを見た限り、残念ながら、待ちぼうけと源氏物語の繋がりを書いた
本は見当たりませんでした。
作詞:北原白秋 作曲:山田耕筰
待ちぼうけ 待ちぼうけ ある日せっせと 野良かせぎ
そこへ兎が とんで出て ころり転げた 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ しめたこれから 寝て待とか
待てばえものは かけてくる 兎ぶつかれ 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ きのう鍬とり 畑仕事
きょうは頬づえ ひなたぼこ うまい切り株 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ きょうはきょうはで 待ちぼうけ
あすはあすはで 森の外 兎待ち待ち 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ もとはすずしい 黍畑(*きびばたけ)
今は荒野の ほうき草 寒い北風 木の根っこ
(どの歌詞も、黍畑を黎畑と間違えているので訂正しています)
待ちぼうけ 待ちぼうけ ある日せっせと 野良かせぎ
そこへ兎が とんで出て ころり転げた 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ しめたこれから 寝て待とか
待てばえものは かけてくる 兎ぶつかれ 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ きのう鍬とり 畑仕事
きょうは頬づえ ひなたぼこ うまい切り株 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ きょうはきょうはで 待ちぼうけ
あすはあすはで 森の外 兎待ち待ち 木の根っこ
待ちぼうけ 待ちぼうけ もとはすずしい 黍畑(*きびばたけ)
今は荒野の ほうき草 寒い北風 木の根っこ
(どの歌詞も、黍畑を黎畑と間違えているので訂正しています)
6月17日(金) むらさきの会
夕霧3 於:西大島総合区民センター(西大島文化センター)
テキスト:新潮日本古典集成 源氏物語六
今回:25頁13行目―32頁末
次回:7月17日(金) 33頁1行目―40頁8行目
小見出し
「落葉の宮の心中」「落葉の宮、夕霧の手紙も無視する」
「御息所、律師の話から、昨夜の夕霧のことを知る」
夕霧と落葉の宮との気持のすれ違い。
律師によって夕霧の事を知らされた御息所も気の毒だと思う。
誰にも知られたくなかった落葉の宮だったのに、誤解されたままで
かわいそうに思いました。
がこちゃん
昨日、義母と堀切菖蒲園に行きました。たくさんの種類があり
(清少納言、葵の上、紫式部、十二単衣・・・)、美しく咲きほこっていました。
平安の都にも、こんな光景があったのでしょうか。
紫の会のメンバーだった母は93才になりますが、今でも源氏関係の
本を読んでいます。
私も見習って勉強を続けたいと思いました。
ふなぼり・お嫁
夕霧の思い、落葉の宮の思いが明確になり、そこに女房たちの
うわさ話も加わり、こっけいであった。
世間は狭く、阿闍梨から、夕霧と娘の関係が御息所にバレてしまう。
二人はハッピーエンドになるのか、次回に期待する。
撫子
八王子の星 今回欠席。
面白い校注がありますので書き写します。
「一向(いこう)に」、「本妻(ほんさい)」「族類(ぞうるい)」
「女人(にょにん)」「長夜の闇(ぢやうやのやみ)」、いずれも
僧侶らしい堅い用語。(p31注21)
漢籍、仏教経典に出てくる言葉? 紫式部の漢文学への知識
5月6日(金) むらさきの会
夕霧2 於:西大島総合区民センター(西大島文化センター)
テキスト:新潮日本古典集成 源氏物語六
今回:18頁10行目―25頁12行目
次回:6月17日(金) 夕霧3 25頁13行目―32頁末
小見出し
「夕霧、部屋に入って直接宮に訴える」「落葉の宮の心中」
柏木が亡くなってからの夕霧は、ずっと落葉の宮に想いを伝えていたにもかかわらず、いつも知らぬふりをされていたけど・・・
でも宮の中には世間体を気にしていることが今回はじめて分かったと感じました。
今迄の態度に納得しました。
がこちゃん
ふなぼり・お嫁 今回中途退席
夕霧の落葉の宮への思いを切々と訴える場面であるが、想像すると笑ってしまう。
大の大人が障子を隔てて押し問答。
撫子
今回の受け持ち箇所の言い回しがとてもむずかしかったです。
夕霧の思いと落葉の宮の思いがまったくかみあわず、夕霧の思いだけが
一人歩きしていて拒む落葉の宮がかわいそうです。
八王子の星
まめびと(忠実人)の評判どおり、控えめに落葉の宮を口説くかと思うと、
いじめにも似たことばで高飛車に迫る夕霧の姿は、思いがなかなか伝わらない
男のじれったい思いを、うまく描写しているようにみえる。軽そうで深い男?
mrk
4月1日(金) むらさきの会
夕霧1 於:西大島総合区民センター(西大島文化センター)
テキスト:新潮日本古典集成 源氏物語六
今回:夕霧1頁―18頁9行目
次回:夕霧2 18頁10行目―25頁12行目
「夕霧の落葉の宮への思慕」「御息所、物の怪をわずらい、小野に移る」
「八月のなかば、夕霧、小野に赴く」「落葉の宮、夕霧と挨拶を交わす」
「夕暮の山荘のさま」「夕霧、宮と歌を贈答」
今月から六巻に入りました。冒頭「まめ人の名をとりて」から始まった夕霧の巻、
「まじめな人」を思わせる反面、常に一条の宮の存在が頭から離れない。
スキあらばと云う構えで、ちょっとかわいそうな感じ。
がこちゃん
桜の花も満開で、昨日は孫たちと小松川千本桜まで出かけました。
平安の都人もお花見をしたのでしょうか?
今日から夕霧に入りました。生真面目な人柄だけでない様子で、
これからの展開が楽しみです。
ふなぼり・お嫁
「夕霧」の巻、突入。タイトルにもなっている「夕霧」は「夕霧」の
性格がはっきり書かれている。まめ人が、なぜ落葉の宮に恋心を
抱いたか不明。
撫子
夕霧の一途な恋心に同情しました。三年も口説いているのに、落葉の宮はなびいてくれないなんて、鈍感なのか純情なのか、育ちが良過ぎるのか・・・
八王子
「山里のあはれを添ふる夕霧に、立ち出でむそらもなきここちして」
の「夕霧」が、この巻の名および主要人物である大将〔源氏の子〕の呼び名に
なった。「霧」に包まれた素顔ははたして垣間見えるのか、謎が深まるのか?
mrk
3月4日(金) むらさきの会 鈴虫2 西大島文化センター
テキスト:新潮日本古典集成5 鈴虫355頁8行目―362頁末
次回:新潮日本古典集成6 夕霧1 11頁1行目―17頁2行目
六条院から冷泉院にみんなで参上した後、秋好む中宮の心中を
源氏と話されたことで母の御息所のことをずっと気にされていた
ことがわかりました。
「鈴虫」の最後、母御息所のための追善供養ができることで、
ほっとしました。
がこちゃん
コロナで2ケ月ぶりの勉強会で楽しくすごしました。
秋好む中宮の哀しみや苦しみがよくわかりました。母・御息所のためにも
仏門に入りたい気持を源氏は、もう少しわかってほしいと願います。
船堀・お嫁
鈴虫の章の終わりは、秋好む中宮の出家願望を、源氏にストップかけられながら退位した冷泉院とほっこり夫婦をしながら、母を思いお経を唱える静かな日々がハッピーだと思える。
撫子
風雲急を告げる昨今のウクライナをめぐる慌ただしい展開をみると、いまのところ
厭離穢土のこの地上の生活がいかに大切なものだと納得する。弱者でいいから
生きましょう。
mrk
2022年1月は雪のため2月はオミクロンのため休止
2021年12月 船堀行船公園に遊ぶ
11月5日(金) むらさきの会 西大島文化センター 10月1日(金)は台風のため休止
横笛4―鈴虫1
テキスト:新潮日本古典集成5 横笛338頁11行目―鈴虫349頁14行目
次回:12月3日(金) 鈴虫348頁13行目―355頁7行目
夕霧が東の対へ渡り、源氏と物語などして一条の宮をおなぐさめしている様子等も
源氏が「同じうは心きよくて」間違いのないように、との言葉に、「さかし」、人のことは心強げだけど、ご自分だったら、とちょっと皮肉が入ったところはさすが、と思いました。
がこちゃん
「鈴虫」の巻に入り、女三の宮の持仏開眼供養では源氏と紫の上の準備・しつらいが豪華ですごいです。出家した女三の宮に思いは届かずですが、いたしかたないのでは?
富士山噴火の描写があり、おどろきました。
船堀・お嫁
「横笛」が源氏のもとに・・・そして誰の手に渡るか 薫かな?
「鈴虫」では、女三の宮の持仏開眼供養が、源氏の趣向を凝らした配慮で開催。
葵の上も元気になって、嬉しく思う。
撫子
なにかにつけて折り合いがつかない源氏と女三の宮
その場面をを示す言葉は「くたす(腐す、朽たす)」でしょうか?
源氏が思いやって投げかけた言葉に、女三の宮からの率直な気持ちが返され、
それが腹にこたえる。女三の宮の源氏への不信はどこまで続く?
mrk
9月10日(金) むらさきの会 西大島文化センター
横笛3
テキスト:新潮日本古典集成5 横笛329頁14行目―338頁10行目
次回:10月1日(金) 横笛338頁11行目―鈴虫349頁14行目
夕霧が一条の宮家から三条殿に帰った時の落差!!
宮さんの子供と云えども、やはり甘え方等は今も変
わらないのが、ほほえましい。
がこちゃん
柏木の遺愛の笛が夕霧の手に渡る。
その夜、夕霧の夢に物言いたげな柏木が
現れるところは、ブラックファンタジーでもある。
最終、誰の手に渡るのでしょうか?
撫子
夕霧の処世術(物に執着しない)と、ほんわかな家庭の様子。
六条院の賑わしさ。三の宮(匂宮、三歳:やんちゃで負けず嫌い)
二の宮(式部の卿の宮:一の宮、下に薫に挟まれて控え目を身上とする)。
夕霧(薫も含めた三人の子の格好のお相手。親戚のお兄ちゃん風)。
源氏(皇子に交じって遊ぶ薫と、女三の宮の心に潜む鬼の扱いに心を砕く)など、
飽きさせない描写が続く。
mrk
船堀・お嫁(早退) 八王子(欠席)
7月2日(金) むらさきの会 西大島文化センター
横笛2
テキスト:新潮日本古典集成5 横笛321頁14行目―329頁13行目
次回:9月10日(金) 横笛329頁14行目―338頁10行目
?
源氏が若宮「薫」を見て、
“わが御鏡の影にも似げなからず見なされたまふ”。
とありました。
柏木にも女三の宮にも似ていないこの若君を、
わが子とみなしてもよいと思う源氏。
がこちゃん
?
幼い薫君の描写がとても面白く、我家の孫と
まったく同じ行動です。
千年の昔も子供の様子・親心(源氏の見せる)は
余り変らないので、なんですか嬉しい気持に
なりました。
船堀・お嫁
?
?
「横笛」の章ですが、まだ「横笛」は出てきません。
夕霧が落葉の宮の琴の音を所望するところから、
次回どのような展開になるのか、楽しみです。
撫子
?
薫の、色が白くて口唇が赤くてすらっとして、
可愛いらしくて美しいのが、柏木にも女三の宮
にも似ず、自分に似ていると思っているところが
ナルシストの源氏らしくておもしろいですね。
八王子
?
「まめ人(実直・誠実な人)」(ウィキペディアによる)
と評判の夕霧。「好き者」源氏(当時は人の心の
機微を解する粋な人と好意的に見られていたそうです)
と違い、恋愛にうとい彼だが、こと落葉の宮にはご執心。
この二人どうなるのか?
それにしても、紫式部は駄洒落がよっぽど‘好き者’
なんですね。
mrk
6月4日(金) むらさきの会 西大島文化センター
柏木8―横笛1
テキスト:新潮日本古典集成5 柏木 311頁7行目―横笛321頁13行目
次回:7月2日(金) 横笛321頁14行目―329頁13行目
夕霧が度々一条の宮をお見舞いする様子。
「もの思ふ宿」 「暮しかねたまふ」は
主人のいなくなった雰囲気がよく伝わっている。
「蓬(よもぎ)も所得顔(ところえがほ)なり」も、
あわれさが増していると思いました。
がこちゃん
誰しも柏木の早逝を悼んでいる。
源氏も、思うところはあるが柏木を気に入っていた
ので、薫の中に柏木を見い出している。
撫子
一条の宮に、枝を「さしかはし」て茂る柏木と楓に
託した贈答歌がきっかけで、衛門の督(及び、この
巻の名)を「柏木」と呼び慣わすようになったそうです。
楓は落葉の宮だが、夕霧は大胆に柏木の枝に自分を投影して、
将来の契りを夢見て、御息所にたしなめられる。夕霧も苦笑するが・・・。
前回の感想で薫と夕霧をごっちゃにしていたようです。失礼しました
mrk
船堀お嫁 は欠席 八王子は早退
5月7日(金) むらさきの会 西大島文化センター
柏木7
テキスト:新潮日本古典集成5 柏木 301頁10行目―311頁6行目
次回:6月4日(金) 柏木 311頁7行目―横笛321頁13行目
柏木の死にあれこれと思いをめぐらす夕霧。
やはり不思議に思うのは当然かも。
柏木の父の悲しみ方で、涙の表現がいろいろ。
がこちゃん
柏木の死を皆が受け止められずにいる。
夕霧が初めて落葉の宮邸を訪問。
まだ落葉の宮には会えない。・・・・・・次回でしょうか?
撫子
柏木の弔いに訪れた先々で、大将の君(夕霧)は、落葉の宮の
母・御息所、柏木の父・致仕の大殿から、柏木を失った悲しみ
の心情を知る。
その深さは、春雨・軒の雫・柳の芽をぬく玉など、
技巧をつくして描かれる。
その愁嘆場にあって、対照的に、あくまで「きよらなる」夕霧。
手持ちの古語辞典を見ると、「きよらなり」は第一流・最高の美。
最高の美を表す。『源氏物語』では天皇と皇族関係の人に用い、
第二級の美の「きよげなり」と区別している、とあります。
源氏をしのぐ主人公になる予兆か?
mrk
船堀お嫁 は今回コメントなし 八王子はコロナ禍でお休み
4月2日(金) むらさきの会 西大島文化センター
柏木6
テキスト:新潮日本古典集成5 柏木 294頁14行目―301頁9行目
次回:5月7日(金) 柏木 301頁10行目―311頁6行目
柏木はとうとう泡の消え入るようにて亡くなる。
悲しみの中にも女三の宮、まわりの人とは一味違って
心細さで泣かれている。
若君のかわいらしさと、出家した女三の宮を、
女房連はどう思っているのかな?
がこちゃん
若君「薫」、五十日(いか)の祝。
源氏の思い、宮の思い、女房たちの思い
重なることが無く、若君の成長
影が潜んでくる感じがした。
撫子
約1年ぶりに出席して 楽しいひとときでした。
不義の子供を産んだ女三の宮が子供を捨て尼となったことが
理解できるようなできないような……。
大人たちの思惑を知らず、無邪気な赤子があわれ。
八王子
先回、「柏木をはじめ平安朝の貴族はどんな体調管理をしていたのか?」
の一文を書き忘れていました。
今回、八引用された白楽天の漢詩「自嘲」にある
<老年になって子宝に恵まれて嬉しいやら気恥ずかしいやら>のうきうきした気分、
源氏には毛頭なし。自分の轍を踏むな、と将来を危ぶむ。
同じ詩にカラスは子だくさん<八子>のくだりがあり、これが童謡の<七つの子>の
発想のもとになったのかな?
mrk
3月5日(金)
「柏木」5
病床の柏木が、落葉の宮のことを誰にも
お頼みになる。
親友の夕霧がお見舞いのとき、
「六条の院にいささかなることの違ひめありて」
と、やはり肝心なことは言えず、
ただただ、残してゆく妻をよろしく、と頼む。
がこちゃん?
柏木の病、思わしくなく、関係者は心配中。
帝は「昇進」をお見舞いとしたが、とうとう死期を感じ、
夕霧にやんわりぼかしながらも、ことの次第を話したが、
夕霧は分からない…。
どうなることやら
撫子
柏木の病状が悪化して夕霧に死後を託すも、
本当のことは伝えず、夕霧は悩むことになるのでしょう。
心の病で亡くなることになるのでしょうが、
あまり同情できない、と思いました。
船堀 お嫁
乾布摩擦が、また流行しているとテレビで知った。
今度は裸にならず、着衣の上からやさしくこするようだ。
子供のころ、この「カンプーマサツ」を、耳から覚えたため、
寒空に上半身はだけて手拭いで肌をこする様子から、
「寒風摩擦」と覚え込んでしまった。
男の冬の風物詩と思っていたし、語感もぴったりだった。
これが耳学問のコワサか。
mr k
2021年2月5日 「柏木」4
朱雀院がとうとう下山して、女三の宮を見舞いに。
いつの世も子の行く末を案じる親心。
源氏にまかせれば後々迄安心と思っていたけど…。
でも尼になった後も、
それ相応にと頼むところは親ならでは、かな。
がこちゃん
女三の宮にも、六条御息所がとりついていたことにびっくりした。
過保護だった女三の宮が母となり、
自分の意志で出家して尼になると思っていたが、
六条御息所が言わせたとのこと。
ネンネはネンネのままだった。
撫子
今日も見学の方がいらして、緊張しました。
女三の宮にも、六条御息所の霊が出て来たのには、
おどろきです。
女の嫉妬は怖いです。
船堀 お嫁
はじめて参加しましたが、今までの物語がわからないので、
理解できない部分がありました。
美しい古文を聞けてよかったです。
新人
…やがてこの恨みもやかたみに残らむ…
「かたみ」は互み(おたがいに)で、形見ではないのですね。
「蛍の光」の“かたみに思う千万の”は、この意味だったということを
はじめて知りました。
ついでに「千万」は“ちよろづる”と覚えていました。
別れ→千万→千羽鶴と思ってしまったんでしょうか。
mrk
2021年1月8日 「柏木」3
女三の宮の出産。男の宮であったが、源氏の心寒い態度が女三の宮の心労と身体の衰弱から、出家したい気持ちが大きくなってきた。父朱雀院は、娘かわいさから下山して来てしまった。次回
どうなることやら・・・! 撫子
1/8? ?柏木
年が明けてコロナがますますひどくなり外出もままならぬ時、勉強会に参加。
女三の宮の出産、男子誕生で源氏のゆれる気持が面白く、先が楽しみです。 ふなぼり嫁
柏木が弱っていく一方で、女三の宮の出産。本来であれば源氏にとってめずらしくうれしい事なのに・・・
源氏自身の事を思い返せば、よく言う、因果応報なのだろう。 がこちゃん
源氏物語は最初取っつきにくかったが、辞書を見たりして少しずつ読んでいくと何となくわかってくるような気がしてきます・・・と思ったけれど‥とならないように、少しずつ少しずつ進んで行きたいものです。 mr k
2020年12月4日(金) 「柏木」2
今年も最後の授業となり
一年があっという間に過ぎました
柏木の病状も心配ですが彼の気の弱さに時々いらつきます
つい源氏とくらべてしまいますが無理があるようです
来年の展開を楽しみにまた勉強に励みます
船堀お嫁
平安貴族の家、特に大貴族は
物事の決め方に陰陽師や聖に伺いを立てることは
現代の「占い」にも通じるものがある。
柏木の状態を見て小侍従はどう思っているのだろうか?と思った。
撫子
重い病にもかかわらず最後にいいたいことを
小侍従似たのみ女三宮からの御返りを待つ
その御返りは私の方が何倍もつらくて情けない
「煙」の競いには負けないとの気持ちが出ていると思いました
がこちゃん
源氏絵巻の感想
致仕の大臣(頭中将)が若々しく描かれていたのに一驚。柏木と比べ
兄のような風貌なのが面白かった。また山伏の無骨さが後の武士の姿を髣髴とさせていて
時代の移り変わりを垣間みせてくれて
時代を先取りした画家の視線の鋭さを感じました
川島
2020年11月6日(金) 「若菜下」27、柏木
今日で若菜が終わりました
長いお話でしたが面白く勉強できました
柏木は想像していた人ではなかったので
少しがっかりです
今日は見学の方がいらしたので緊張しました
船堀お嫁
長かった若菜が終了
柏木に突入しました
柏木が主役の巻です
マイナス思考の「死」で
解決しようとしてます
撫子
源氏と対面したと重病になった柏木
女二の宮と離れて実家に戻る柏木と二宮との別れから
「柏木」の巻に
死を前にしてあれやこれやと思い悩む様子
自分を美化させたいきもちがいっぱいなのかな?
賀子ちゃん
いろんな 感想を聞くのが楽しいし参考になります
今後共に宜しく
新人
2020年10月2日(金) 「若菜下」26
源氏の柏木に対する気持ちは老いに向かう自分
若さに嫉妬する感情が入り交じり複雑のようです
若い頃に源氏のイメージが少しずつ崩れていく様が
淋しいです
船堀お嫁
六条院の試楽時に重い腰を上げて柏木が登場。
源氏の圧を全身に受け、
気分がすぐれず退場した柏木。
源氏の意地悪じいさんと長いものに巻かれてしまった柏木は
気弱な男性なのだろうか
撫子
柏木が試楽の拍子合わせのため
源氏に呼ばれる場面
それぞれのきもちはとても穏やかではいられない
その描写、源氏の前から下がる時
「すべり出でぬ」等面白い表現だと思いました
賀子ちゃん
2020年9月4日(金) 「若菜下」25
若菜も後半になり
今までにない源氏の姿ー年老いた自分を嘆くよう
意外でした
女三宮への接し方も
もう少し源氏でいてほしいです
船堀・嫁
寝取られ源氏の悲哀が意地悪じじいとなって
女三宮を責め立てている
何も言えない女三宮がどう変化していくか
今後の楽しみ
撫子
朱雀院からの消息へのお返事
源氏の立場がなぜ悪い噂として入っているのかと思う
反面「さだすぎたるありさま」などと
柏木への恨みがでたのにはちょっと驚きました
がこちゃん
2020年6月6日(金) 「若菜下」23
コロナのせいで3ヶ月も、お休みになり、
久しぶりに本を開きましたが、読むのがたいへんでした。
でもやはり、おもしろいなあと思いました。
若菜の巻も終わりが見えて きました。
頑張って勉強します。
船堀・嫁
コロナ騒動で「源氏物語」から遠ざかり、前回の内容を思い出すのに苦労
しました。柏木の身から出た心労がどうなることやら
撫子
今日はコロナウイルスの関係で、三ヶ月もお休みの後の源氏。
源氏が柏木の手紙をみつけ、女三の宮の処遇をあれこれ思う内、
自分の昔の事を思い出す「院は知らず顔つくらせたまひけむ」
ほんとうはどうだったか?
かこちゃん
2時間ドラマがいくつも出来そうな、サスペンスフルなシーンがたくさんありますね。
(自習では)宇治十帖に入る所ですが、わからなくなると大和和紀さんの「あさきゆめみし」を参考にしてます。
北砂・ヒッポ
2019年5月10日(金) 「若菜下」15
*がこちゃん
女楽の後、対に残った紫の上、急に具合が悪くなった
それと知った源氏の驚きとうろたえ方
御修法に高僧たちも心を起こして祈りきこゆとあるので
見ていても大変だったようですね
*お嫁
紫の上の病におろおろする源氏の様子
紫の病の原因は?ストレスが多いのかなと。
紫の人柄や皆に慕われていることがよくわかり
彼女には長生きして欲しい気持ちになりました
*撫子
紫の上がとうとう発病
源氏のあわてふためき
六条のひとびとや近親者の悲しみで揺すり満ちる様子が描かれていた
明石の女御との娘母の情愛が感じられた
*八王子
とうとう紫の上が床に伏せってしまい
病名もわからずオロオロしている源氏に
回りの人たちも振り回されている様が気の毒!
平成31年4月5日(金) 「若菜下」14
*がこちゃん
とうとう紫の上が突然発病のシーンです
源氏から出家の許しでず「心のほど見果てたまへ」とのみ。
紫の上は心やましく」とてもつらい気持ちで過ごしていれば
胸も病んでくるのは当然だと思います
*船橋お嫁
紫の上のつらい気持ちが(出家したい)
源氏には理解されず
苦しむ様子が哀れです
源氏から見た葵の上、六条御息所、明石の上
の女性像が面白いと思いました
*撫子
源氏の女性経験など聞きたくなかったと紫の上は
おもっていると思う。が源氏は話すことで「お前が1番」とアッピールしている
やはり自己中心的な思い、考えを押しつけている。
二人の関係が冷えていくのがはっきりしてきた
平成30年11月2日(金) 「若菜下」8
*かこちゃん
六条の院の女楽の場面
女君4人が一同に会するのも
きわめて珍しい。
それぞれの童女たちの装いにも
趣があって楽しめました。
夕霧が参上して調弦する前の
「心掛けして」が
ちょっとおもしろいかな
*船橋お嫁
4人の女たちの合奏のため
童女の衣装の色が鮮やかで
日本の色の多さのいつも驚きです
今日はゲストがいらしてちょっと
緊張、でも楽しかったです
*撫子
ファミリーコンサート(女楽)が
はじまるまでの時間経過が面白い。
紫の上、明石の上、明石の女御、女三宮
それぞれの童女の装い、色彩表現が美しい
平成30年5月11日(金) 「若菜下」3
*世代交代というべき冷泉帝が譲位され、太政大臣も《冠を挂けむ》と言うときの「冠」の意味深さ
がこちゃん
*:源氏や頭中将たちの時代も変わり、ひげ黒夕霧たちの時代に変わりつつあり
また新たの楽しみが加わります
船堀嫁
*今日は紫の上は出てこなかったが、それ以外の主な登場人物の様子が伺えた
世代交代の巻、次の世代への移行を暗示させていた
撫子
*今まで思っていた髭黒のイメージが先生の説明で全くちがっていたことがわかりました
スター
*しばらくお休みしてましたので頭も目もよくまわりません。
でも久しぶりに楽しいひとときでした、ありがとうございました。
ふく
平成30年4月6日(金) 「若菜下」2
*前回柏木が春宮から猫を手に入れるところがありました
今日はその柏木が猫を女三宮に見立てている描写がおもしろかた
久しぶりに「玉鬘」の近況もあってその場面がめに浮かびました
がこちゃん
*柏木が猫を女三宮に置き換えて変人となっている情景が滑稽だった
独身者を《一所のみに居る》と表すのが通い婚時代を言い当てておもしろい
平成30年2月2日(金) 「若菜上」29
*やっと「若菜上」が終わりました
六条院での蹴鞠のあそびのあと
夕霧と柏木の話では
冷静に女三宮を見る夕霧と憧れの女三宮を
かいま見た柏木との思いがズレていく所は
この先何かおきてきそうです
がこちゃん
*柏木は女三宮を見てさらに恋心がヒートアップ
親友の夕霧は父源氏のことを悪く言われたり
女三宮をほめたたえる柏木をうざく思い始めた
女三宮も柏木からの恋文で姿かたちを見られたことに
気がついた
撫子
*長いこと体調を崩していましたのでなかなか
本文にはいっていけません
物語の主人公達もそれぞれ大人になられて
楽しみと心配と
どちらかといえば
孫達を見守る心境大です
ひろこ
*柏木の女三宮に対する気持ちが一途で一方的で
何も手につかずもんもんとし
小侍従あてに手紙を書くも
相手にされず切ない思いになります
相手が相手だけに思い通りに事が運ばない
さあ、これからどうなる…
スター
平成29年9月1日(金) 「若菜上」24
*明の上と尼君が入道の文を見ての
場面で、今願いが叶って山に籠もる入道に対して
明石の上の気持ち…複雑でしょうね
がこちゃん
*明石の上は身分の違いを充分過ぎるほどわきまえ
女御に対して母の気持ちをおさえる様子はわかるものの
そこまでするものか?
身分社会は何ともしがたいものなのですね
船堀嫁
*明石の上が娘としての立場、母としての立場から
自分を出した場面だったと思う。
「明石の上」あなたも出家希望者なのですね
撫子
*4ヶ月ぶりの源氏との再会にとまどいつつ
明石の上、父君入道との関係性の強さ、紫の上の
思いやりの深さに感心しました
波音
平成29年7月7日(金) 「若菜上」23
*明石の入道の「遺言」で今いろいろな事が明かされたという所でした
明石の上の心模様がとても複雑な感じ。尼君の人生も都から明石へ、明石から又都へと数奇な一生
がこちゃん
*明石の入道が深い山に入る覚悟のほどや回りの者たちへ財産の寄贈などなど準備が完璧ですごいです
尼君や明石の上も入道の気持ちを理解してよかったです
船堀 嫁
*入道の入山に至る経緯、その手紙で父親の心情を知った母と娘の情景が描かれた場面であった
入道の夢を叶えるための行動、それがなった後の潔さがクールでした
撫子
*本日は久しぶりにノートに書いてみました
なかなか感想もかけませんが、登場人物の本音の部分が見えてきて
そうだったのかといまさらに合点致しました
浩
平成29年5月12日(金) 「若菜」21
*明石の女御が尼君から自分の出生を知り、思い乱れる様子、
明石の君のかいがいしい様子など親子三代のそれぞれも珍しい場面
がこちゃん
*姫君の刀自を尼君が話し、理解され良かったと思う。
明石の上はもっと後に刀自をはなそうとしていた思いとは違ったが
安産、男子誕生とすべて良くすすんでいる
撫子
*明石女御の男子出産
尼君の祖母としての気持ち
いつの世も孫はかわいいものです
明石の君の母としての献身
身分をわきまえたふるまいはなかなかのものと思います
船堀嫁
平成29年3月3日(金) 「若菜」19
*源氏、40の賀の祝い
身分の高い方が下賜する禄の違いがはっきりした
前回の紫の上は楽人だけでしたが。
がこちゃん
*源氏の40賀の祝いに
玉かづら、紫の上、秋好中宮の
ぜいたくで素晴らしい品々に圧倒され
当時の生活を想像するとわくわくします
船堀嫁
*源氏40の賀の盛大な祝いが華やかに
延々と続く様が目に浮かぶようで
楽しくおどろいてしまいます
星子
*源氏の40祝賀が延々と続き
宮廷雅の宴をかいま見ているようだ
撫子
*久しぶりの源氏楽しいひとときでした
すっかりご無沙汰してしまいましたが
またがんばらなくてはと思います
浩
平成29年1月6日(金) 「若菜上」17
*紫の上の心情を思うとやはり複雑です
でも自分の立場をわきまえた振る舞いはさすがというべきでしょうか
がこちゃん
*女三宮と紫の上が親戚関係ということがわかり
また紫の上の苦悩がわかった気がします
表面上優しくするのも心の内では辛いと思います
光源氏も罪な人ですよね
月
*紫の上の苦悩が徐々に浸食されてきています
源氏は心の中で紫最高!とつぶやくが、
声や文にして紫の上にささやけば
今後の状況が変わったかも…と思います
撫子
平成28年11月4日(金) 「若菜上」15
*女三宮のことで心を痛める女君
源氏が朧月夜とあったその明け方源氏を迎えた様子
返事のことばに「中空なる身のため苦しく」とあり
この一言に尽きると思いました
がこちゃん
*「若菜」に入ってから紫の上の気持ちがずいぶん変わってきたようです
源氏との関係は絶対のもの思ってましたが信頼が薄らいだのでしょうか
源氏は気づいているのでしょうか、紫の上が心配です
船堀嫁
*育った環境が源氏と紫の上の心離れに拍車をかけたあ
「中空なる身のため苦しく」が物語っていて切ない
撫子
*自分の訳の所だけの予習ではものがたりの内容を理解できないことが
全体を通してよんでみるとダメなことだとわかりました
もうすこし勉強しないと…辞書片手に。
夜空のスター
平成28年10月7日(金) 「若菜上」14
*朧月夜に逢うために強力なつてをたのみ、口実を付けて紫の上に話すところで女君の
「すこし隔つる心添ひて」とあって、二人の心がすこしずつ離れていく予感がした
がこちゃん
*源氏の女遊びが復活した呈である。
紫の上の気持ちが本格的に離れていきそれに気付かない色ジジイという感じがぷんぷんした
撫子
*いつもながら先生の解説はわかりやすく面白いです
スター
*最近目の調子がわるくて文字が書けませんあしからず、お許し下さい
ひろ
平成28年9月3日(金) 「若菜上」13
*朱雀帝の姫君を思う気持ちは理解できるものの
重すぎる感じもします。このような状況の時も源氏は朧月夜の君と文をかわす仲となり
紫の上の気持ちもあるのにやはり源氏は源氏でした
船堀嫁
*朱雀院の親ばかぶりのところでした
娘への思いを夫である源氏や妻である紫の上にも手紙に書いて未練たらたらは女々しいと思う
紫の上の返歌は蜂の一刺しのようですっきりした
次回朧月夜との再会が楽しみだ
撫子
*源氏は女三宮の人柄に触れるに付けますます紫の上のことを思い
恋しくてゆゆしきまでに思う一方
朱雀院が心配する様子が今回も見られた
がこちゃん
*物語の内容を理解してないと具体的なことが頭に入ってこないのと
言い回しがむずかしいです
とんちんかんな答えで源氏物語に対して申し訳ないです
すたー
平成28年7月1日(金) 「若菜上」12
*紫の上の悩みが思いの外大きいのをげんじは理解してない様子
これからの展開はいかに?女三宮がもっとすてきなじょせいであれば良いのに
船堀嫁
*紫の苦悩と源氏の苦悩の歯車がズレ始めた章である
紫の確固がハンパなく身分の差を痛切に感じた
撫子
*古典の文になれないので文章の前後のつながりが
理解できないままことばを流し読みしてしまいます
読み込まないとむずかしいです
奥深い世界でした
★のバサマ
平成28年6月3日(金) 「若菜上」11
がこちゃん
*3日目の最後の夜に源氏を送り出す紫の上
まわりで女房たちが自分のことを想像する
何とも切ない気持ち
重たい場面でした
船堀嫁
*紫の上のつらい気持ち
プライドがそれを面に出すことを許さない
これからの紫の上が心配ですが…楽しみでもあります
ひろ
*源氏のもどらない夜
終夜眠らないまま
夜明けを迎える紫の上。
苦しい彼女を抱きしめて
あげたいような
今日の一節でした
撫子
*紫の上の心情がどんどん内向していく
くだりに入る
本心が出せるおおらかさがない分
強がり、良い人を見せていて
読んでいるこっちがどうにかならないものかと思ってしまう
平成28年5月6日(金) 「若菜上」10
*とうとう、「女三の宮」が六条院に降嫁
結婚の儀式がとどこおりなく行く過程で
紫の上が尽くす気持ちは
計り知れない苦痛の日日が続きそうで…がこちゃん
*女三の宮がいよいよ六条院におわたりになり
三日間通って結婚の儀式がおわり
源氏がどのように紫の上に寄り添うのか
これからの展開が楽しみです…船堀嫁
*とうとう、女三宮が嫁としてやってきた
源氏の着物等準備をするにつれて
紫の上の見た目と内面のバランスが保てなくなるさまが大きくなっていくと思う
源氏が早く気付けば良いが…撫子
平成28年4月1日(金) [若菜上]9
*朱雀院のたっての依頼だということで
源氏とずっと築いてきた年月がぐらぐらとくずれゆく紫の上の心の内は大変
(がこちゃん)
*源氏の四〇の賀の豪華な祝いの品々にびっくりポンです
紫の上の気持ちも哀れですが、気高く生きてほしいです
(船橋嫁)
*紫の上の苦悩の始まり。
源氏の四〇の賀の祝いを、ひげ黒大将と尚侍の君夫婦が取り仕切って
いるのが面白かった。
(撫子)
平成28年3月4日(金)「若菜」上8
*朱雀院の申し出を、源氏は引き受けたものの、六条の自宅に帰って「なま心くるしう」と心が乱れる様子。紫の上に打ち明ける場面では「いとよく教えきこえたまふ」とあった。紫の上の心の中をどう思っているのかとかわいそうに思いました。(がこちゃん)
*女三の宮の降嫁が決まり、紫の上の気持ちはいかばかりか?
源氏がそのきもちをわかっていない様なのでこの先のお話が楽しみです
若菜の巻はよみずらいです
(ふなぼり嫁)
*源氏のお調子者さ加減と裏腹に、紫の上のショック状態の心中を読みとらせない態度が、今後の気がかりとなる
(撫子)
平成27年10月2日(金)「若菜」上3
*朱雀院が乳母たちと女三宮の今後を話し合う場面では身分社会の重みが伝わってきました。乳母の見る目が世間一般の目なんでしょう
*女三宮の降嫁をめぐり、朱雀院の親としての思い、女房たちの思惑などこれからの展開がたのしみ。紫の上が心配です
*源氏本人がいないところで大きなお世話が始まろうとしている展開で今後が楽しみだ
平成27年9月4日(金)「若菜」上2
*「若菜」に入ったとたん、「あれぇ!」という感じです。
もう一度「人物関係図」を見直しながら読んでいきたいと思います
*夏休みがおわり、本を開いたのですが、読むのがとても難しいです。先生のお話では話しことばがずらずら続くからだそうです。がんばって読み込んでみます。気持ちはあるので…
*「若菜」に入りました。紫の上の悲しみが思い遣られます。今から。
平成27年7月3日(金) 「若菜」上に入る
*朱雀院が心の重荷を夕霧に話す様子に、人はいつの世にも悩み、高貴な身分の人も同じだと思う
*朱雀院の現世への心残りを、一つひとつはき出していく様は、身勝手だと思う
*今日から第五巻の「若菜」へ。朱雀院の身勝手さと紫の上の嘆きが、思われて、心おだやかになれません
*「若菜」に入り、人物関係図を頼りにひとつづつ確認してからでないとわからなくなりそうでした。今後が楽しみです
平成25年11月1日(金) 「真木柱」
髭黒の北の方が、式部卿の宮に引き取られ帰った所、宮の北の方が
源氏を悪く言うが 宮は今迄の報いと悟っている。
対照的な親の反応。 がこちゃん
実家の母親が継母で 気性が激しいタイプである様子が思い浮かびました。
それとは対称的な 式部卿の宮は、貴族典型の「まろ」的な要素たっぷりで
何とも言えない。 「風おこりて」は、風邪を引くがことわりの言葉
だとは、平安時代から「あり」だったと、おもしろかったです。 撫子
平成25年12月6日(金) 「真木柱」
髭黒大将の男ずるさと、妻となった玉鬘への心配りで
少し男をあげた巻でした。 撫子
玉鬘が内裏に上るのに 男踏歌の場を選んで、とても華やかな
デビュー。 六条院は きっと淋しくなるだろう。 がこちゃん
聞くだけで 精一杯です。 なごやかで皆様 楽しそうでした。 恵美子さん
大将の家庭のゴタゴタで 大将はいろいろ苦労するけど
玉鬘の美しさに いやされる様です。 玉鬘が尚侍の君として宮中に
出る時は後見人が沢山いて 花やかに にぎはしく。 新屋君子
遅刻しました。 予習も出来ず申し訳なく思っています。
宮中の女性達の きらびやかな衣装、色目を想像すると 楽しいです。 船堀、嫁s
平成25年10月4日(金) 「真木柱」
父宮からの迎えの車が来る中、今も変わらぬ離婚。
親同士はよくても 子供の心は 相当傷つく事になるだろうなー。 がこちゃん
北の方の心情が よくわかり 共感、同情を得る場面であった。 撫子
日々の忙しさを理由に、予習もせずにいました。 そのうえ今日は
大遅刻です。 反省しております。
内容の感想がなくて 申し訳ありません。 船堀、嫁
源氏物語の美しい絵図からは推し量れない離婚劇の真相。昔も。 浩
髭黒の様な 真面目な人の中年の恋は 一途になるので
家族の者は 大変です。 子供の中でも 下の男子は小さいので
良くわからず遊びまわっているが、 上の娘は 今迄 父に大層
かわいがられ 大事にされていたので 父にあいさつもしないで
別れることは出来ないと 父の帰りを待つが なかなか帰らないで
暮れたので 歌を書いて いつも寄りいたまいし柱のわれめに
笄の先で押し入れる娘の気持ちがあわれです。 新屋君子
平成25年9月6日(金) 「真木柱」
髭黒の北の方は 前から少しはおかしかったのでしょうが
髭黒が 玉蔓の所へ行く様になってから 心のみだれがはげしくなって
灰をかぶせる様な事になって。 おとなしく情ある人が この様になるのは
かわいそうです。 髭黒が真面目で 普段 浮気をしない人が 急に
玉蔓に入れ上げたので、一層こたえたのでしょう。 新屋君子
いつの時代も 夫の心変わりで、泣くのは妻なのでしょうか。
髭黒の北の方は 心を病み 身分もあり プライド高い分、
悲しみも深く、又、口惜しい限りと 想像出来ます。
髭黒が 玉蔓と結ばれ 幸せになるのは、チョッと許せないです。 船堀嫁
平成25年7月5日(金) 「真木柱」
真木柱のハイライト。 北の方の気持ちも落ち着いた頃、
髭黒が香をたきしめていた火取りを、出かける髭黒の脊に あびせる。
物の怪の なせるわざとは言いながら うとましくなる。
ここで周りを はばかり 加持をして、落ち着かせる事にした髭黒の
打算かな? がこちゃん
髭黒のしたたかさが ありありと出て、北の方が可哀想であり
非情な章だと思った。 実家にも帰れず 居場所のない北の方の
感情が 〝灰かけ”となって現われていて、私としては 少しすっきりした。 撫子
髭黒の北の方は やさしい おとなしい方なのに、病の為、乱心
なさる事があって、髭黒の気持ちが玉蔓の方に移ったのは気の毒です。
昔から 男の身勝手はしかたのない事でしょうか。
今迄、堅物で通っていた人が 急に外の女の人に心奪われるのは
長年つれそった北の方としても 心外でなほ 心が乱れることでしょう。 新屋君子
以前、護国寺で見学させていただいた香道のひととき。
静謐さと、かぐわしい香りに満ちていて、平安の昔にいる心地でしたが
夫婦喧嘩の武器になろうとは、思ってもみませんでした。
でも、その後「一夜、打たれ 引かれ 泣きまどい 明かし給ひて」とは
北の方に、大いに同情してしまいました。 浩
平成25年6月7日(金) 「真木柱」
髭黒が 自邸に玉蔓を迎えようと、北の方を説得する身勝手さが
より以上に、心の病を増長させて行く。 がこちゃん
髭黒の強引さ、男のいやらしさ全開の場面で、あった。
北の方の 心の弱さが目立ち、悲しいやら 情けないやら・・と思った。 撫子
男女の関係がおおらかな平安の時代でも やはり女性の立場は
弱いようです。 髭黒の北の方の嘆き、プライドの高さ故、思い悩み
心も病んで 哀れなりです。
男の身勝手さは許せません。源氏を見習ったら如何なものかと思います。
船堀嫁
であり
玉蔓と髭黒が結ばれたが 玉蔓は髭黒になじめず、源氏や蛍の宮の
優雅なくらしをを なつかしがる。 髭黒は荒れたる屋敷を 玉蔓の為に
リホームを急ぐ。 髭黒の北の方は美しく大人しい人だったが
御もののけがつきて、時々 心をみだして あらぬ事をするので
夫婦の仲が良くなくて、玉蔓に夢中になって
北の方を顧みないで かわいそう。 新屋君子
髭黒が自邸に 玉蔓を迎えようと 北の方を説得する身勝手さが
より以上に 心の病を増長させて行く。 がこちゃん
平成25年3月1日(金) 「真木柱」
玉蔓への求婚相手、髭黒大将 左兵衛の督 兵部郷の宮の性格が、
文よりわかる部分であった。 玉蔓の気持ちとして
出仕には気が重く、源氏にも 内大臣にも 自分の心情を打ち明けられないまま
「藤袴」の章は 終了。
「真木柱」で 髭黒の手中に落ちてしまい、玉蔓はショックであり、
源氏もショックでありつつ 認めざるを得なくなった。
今後 どうなるのか 楽しみである。 撫子
真木柱に入り、玉蔓の急変を知る。
まわりの女房とのコミュニケーションが、足りなかったのか、
守ってもらえなかったのが残念。 がこちゃん
玉蔓の運命がいよいよ決まりそうになる。
髭黒は熱心で 蛍の宮はあきらめます。 内大臣は 髭黒をと
思いますが、源氏に遠慮して言い出さない。
玉蔓は 宮中の出仕には あまり乗り気でなく、蛍の宮の方が
と思っている様ですが。 新屋君子
「初霜むすぼほれ 艶なる朝」 霜のついた草の華麗さが蘇ります。
植物の美しさを改めて知ることの多い源氏物語です。 浩
平成25年1月11日(金) 「藤袴」
夕霧が、玉蔓に、藤袴の花を、御簾のつまより差し入れる
場面で、時代じだいの絵に変化があったのは、珍しいことなんでしょう。
突然、「尚侍の君」として、出てきたのは、玉蔓の立場が、
六条院で、微妙であるらしい。 がこちゃん
玉蔓を中心に、彼女に関わる人物の思いが、
源氏を通して、語られている場面であった。
夕霧が、ちょろちょろ自己主張をしているところが、面白かった。 撫子
「尚侍」になる事は 中宮や女御に 遠慮があるので 玉蔓は悩む。
思いやりのある 心やさしい人柄が あらわれている・
夕霧が 源氏に 玉蔓の行く末を いろいろ言う程に大人になっている。
玉蔓の身の振り方は、源氏と内大臣の 板挟みになり どうなる事かは
新屋君子
夕霧が、玉蔓に蘭の花を贈る場面で、手を放さずいて
袖をつかんだりする。 彼の真面目さ、不器用さが 面白い。
笑うにも 色々 種類があり、たのしい。 船堀お嫁
平成24年12月7日(金) 「藤袴」
「行幸」の章が終り、「藤袴」に、突入した。
「行幸」では、養父の源氏と、実父の内大臣の、心中対決。
又、実父、内大臣の二人の娘、玉蔓と近江の君の、育ちによる
所作、性格が対比されていて、面白かった。 撫子
「行幸」の終り、近江の君の様子が、今迄の女君には
ないキャラで、ほほ笑ましくも、ありました。
常に、一歩引いて、相手を気遣う、玉蔓とは対照的。 がこちゃん
平成24年11月2日(金) 「行幸」
源氏の女性の中に 末摘花や 近江の君の様な方々が
出てくると 楽しいです。 身近に 感じるからでしょうか。 船堀 嫁
玉鬘の 「裳」の腰を結う中での 内大臣の気持ちは
さぞ 複雑だったと思います。
源氏から 「昔の事は 口にしませんので」の一言。
さぞ言いたい事が 山ほどあったでしょうに。 がこちゃん
玉鬘の裳着の式もすみ、懸想人達は色めき立ち、
内大臣の兄弟達は事情を知り、近江の君は、玉鬘が
自分と同じ劣り腹なのに、源氏と内大臣、二人に大切に
される事に不満を言う。 私は一生懸命、女房のやらない
事までやっているのに なにもしてくれないと、女御の君の
薄情を恨む。 自分がかたほなる事を自覚しない。 新屋君子
玉鬘の成人式、「裳着の儀式」の当日の
参列者の心情が 良く表われている章だった。
内大臣の 子供達の個性が はっきり出ていて面白かった。
撫子
昨日、11月1日は「古典の日」。
1008年(寛弘5年)の、この日、式部日記にある
藤原公仁の言葉から、設定されたとか。
2008年の、源氏物語千年紀のことなど、面白く伺いました。 浩
平成24年10月5日(金) 「行幸」
源氏が 内大臣との話を くわしく玉鬘にお話してくれたので
玉鬘は これで本当の父親に会えると 長年の念願をはたす
ことになる。 玉鬘の裳着の日の盛儀は 色々の方から
お祝いの品を頂く。 夕霧は父から 玉鬘が内大臣の娘と
聞いて 源氏の振る舞いが 少しあやしかったのを納得する。
内大臣も 玉鬘の裳着の支度の立派なのに驚いて ? と
思ふ。 新屋君子
玉鬘をめぐって、脇役の人物像が 浮き彫りになっている章でした。
忘れていた 末摘花が登場して、ユーモアと滑稽さで 源氏が
困ったように恥ずかしくなり、顔が赤くなったり、肩で笑っている
ような様子が 想像出来て 楽しかった場面です。 撫子
裳着の当日、事情を知った大宮からの文にある歌は、
優しい大宮の人となりが、良く分かる。 夕霧に影響を
与えた人と、合点できる。 浩
平成24年9月7日(金) 「行幸」
やっと 源氏と内大臣の 対面で、若い頃の話で盛り上がり、
夜更けまで過ごす中、 さらりと「玉鬘の事を ほのめかし出で
たまひてけり」 どんな風に話したのか?
内大臣が、あれこれ臆測するのも わかる気がする。 がこちゃん
久し振りに 源氏、内大臣の二人の出会いとなり、
話しているうちに 昔の相睦んだ頃の気持ちになり、源氏が
玉鬘の事を うちあけて 裳着のことをたのむ。 玉鬘が
二人の気持ちをなかよくさせることだろう。
夕霧の結婚も うまく行く様に なるだろう。 新屋君子
源氏と右大臣の 心理合戦ともいうべき章でした。
玉鬘のことを どう打ち明けるのか、と ハラハラしていると
源氏が「そのついでに、ほのめかし出でたまひてけり」と
あっさり文章が進み、右大臣が「いとあはれに 、
めずらかなることにも はべるかな、と、うち泣きたまひし」とは
なんだか内大臣に、大いに同情してしまいました。 浩
平成24年7月6日(金) 「行幸」
久し振りの 源氏です。
内大臣と 源氏の関係が 興味深く、次回が楽しみです。 信
源氏は 玉鬘のことを打ち明けるため、大宮の見舞いに行く。
内大臣は いろいろな人達をさしむけながら、自分は行かない
つもりだったが、源氏が内大臣に話したいことがあるから来て
下さい との大宮の手紙をもらって、いそいで支度をして、二条の
大宮の家へ行く。 なんとなく仲違いしていたが、会えば
昔の話に うちとけ合う。
人間は離れれば疎くなる事、会えば又、うちとけられる。 新屋君子
大宮からの文で「直接聞こえまほしげなることもあなり」
内大臣は さまざまに思いをめぐらし 会ってから、その場で
決めようと思う。 縁組の事だと思う内大臣。
やっと二人が対面し、昔今の事を語り、友達関係の時代から
今の上下関係に移っていく展開が 見事。 がこちゃん
何年振りかで会った 内大臣と源氏。二人への描写は、
内大臣に対して厳しいものがある。 玉鬘の件には触れないまま
今日の講義は終了。 次回を楽しみに! 浩
平成24年6月1日(金) 「行幸」
とうとう大宮に 玉鬘の事を 話し出しました。
宮中での 女性の仕事、 「内侍」の地位の高さ、
宮仕えは 女御 更衣にならなければ・・・ がこちゃん
左大臣も大宮も 心やさしい人なのに、子供の
葵上や内大臣は 情の強い人達の様で、大宮の見舞いにも
内大臣は来ない様で 孫の夕霧が 一生懸命、お世話をしている。
大宮の心配は 夕霧と雲居雁とのこと。
源氏は 玉鬘のことを 内大臣に打ち明け様としているけど
なかなか むずかしい。 新屋君子
源氏と 大宮との会話が難しい。
・・・がないを 否定するような言葉が多く、
文意を読み取るのに 時間がかかります。 さくら
今日は遅刻しました。 担当の所を 少し予習したのですが
区切る箇所がわからず、読むのに苦労してしまいました。
勉強が足りない・・・反省です。 船堀嫁
宮中の内侍所の詳細が面白い。 この時代も
キャリア・ウーマンが、しっかりと仕事をしていたことが伺える。 浩
平成24年5月11日(金) 「行幸」
帝を拝して 玉鬘の心が動き、宮中に上る事になるのか?
源氏も 大宮を通して 内大臣に話す展開になり、 先が
楽しみです。 船堀、嫁
行幸の後、玉鬘を からかうような源氏。
裳着の儀式を 二月に決め、玉鬘の「お披露目」を
どうしたものかと いろいろ思いめぐらす源氏。
将来の事を思い、病気の大宮を 訪ねる事にする。 がこちゃん
玉鬘の進退に 源氏は悩む。裳着の腰結を内大臣に
頼んで 親子の名のりを あげさせようとする。 もし大宮が
亡くなったら 孫として喪に服さなければならないから その前に
親子の名のりを しなければ 喪に服せなくなる。
いよいよ 玉鬘の運命が きまりゆく。 新屋君子
物忌みの為、行幸のお供をしなかった源氏の元へ
帝から 雉一枝が おくられた。
平安の昔の 豊かな自然が 思われた。 浩
平成24年4月6日(金) 「行幸」
師走の 大原野の行幸の 様子が とてもあでやかで、
その中での 玉鬘の 心の移り変わりが 興味深いです。 信
行幸の 行列の美しさが 目に浮かぶ 場面であった。
源氏の 玉鬘の幸福と 恋慕が 音無し滝という表現が
おもしろい。 撫子
大原野の行幸で 玉鬘も 見物に出かけた。
目にした二人の印象の違いが・・・。
父大臣は、「限りありかし」 「きらきらしゅう」
帝は、「なずらひ きこゆべき人なし」 がこちゃん
玉鬘の 帝に対する想いや 父の大臣や 他の
人々の描写が 面白い。 玉鬘のこれからが 楽しみです。
今日も 矢を入れる道具「胡ぐい」を 覚えました。
又、男達が どんな化粧をしていたのか、興味はつきません。
船堀お嫁
源氏は 内大臣の おおげさな性格を知っているので
玉鬘の事をあきらめ よき身の置き所に四苦八苦する。
玉鬘は 帝の行幸を見物に行き 帝のうるわしさにひかれる。
源氏や夕顔の様な すぐれたきれいな人を見なれた玉鬘は他の
上達部など目に入らない。 源氏はやっぱり内大臣を父とするのが
いやなのだろう。 髭黒の大将を見て とても好きになれないと
玉鬘は 思う。 新屋君子
行幸の折、初めて冷泉帝を見かける玉鬘の反応が面白い。
我こそはと、綺羅を尽くしている人々よりも、「うるはしう 動きなき
御かたはらめ」たる帝に、心、魅かれている。 冷静な女性で
あると思う。
平成24年2月3日 「野分」
夕霧が 源氏と玉鬘の様子を かいま見て、
心悩ませる姿が なんとも おかしい。
「野分」は、衣裳や 草花 情景に、沢山の色がちりばめられていて
日本の 色の名もステキで 美しいと 思いました。 船堀 嫁
夕霧が 野分のおかげで 見たいと思っていた二人の
女性の姿を 見ることが出来て その美しさに見とれる。
でも 源氏の玉鬘に対する態度に 娘なのにと驚く。
夕霧の ういういしさが いいと思う。 新屋君子
野分のお見舞いで、紫の上と 玉鬘を見る機会があった夕霧。
「玉鬘」の まみの あまりわららかなるぞ、いとしも品高くみえざり
ける <紫の上と比べての印象>
「わららかなる」は、やはり内大臣家の血を引いているからか?
がこちゃん
夕霧の 個性、感性が現れている場面でした。
源氏の男性部分と 父親部分が、相手によって使い分ける
巧みさが、何とも言えない おもしろさである。
夕霧も 玉鬘と父の接する場面だけでなく、花散里の在所まで
お供していれば、父の自分に対する愛情も しっかり感じられた
と 思う。 撫子
平成24年1月13日 「野分」
新年、初めの会ですが、相も変わらず 一夜漬けです。
今年は、もう少し しっかり予習しようと思っていますが
源氏は長いので、さて続くでしょうか? 船堀 嫁
野分で、女君を 見舞う。 中宮の御殿の様子が
きれいに 丁寧に 描かれている。 がこちゃん
源氏も 人並みな親の欲目を持って 夕霧を見て
満足している。 中宮、明石の上などに 野分のお見舞いに
いらっしゃる心遣いはこまやか。 紫の上との親密なやりとりが
見てとれる。 紫の上に引かれながらも 自制する夕霧の
まじめさが よく出ていると思います。
風の見舞いに行ったのに すぐ帰るなんて明石の上に
気の毒です。 新屋君子
野分後の 六条院の各邸宅の様子が 夕霧の目を
通して 美しく描かれていた。
平安の 「雅」の色使い、実際に見てみたい と思った。 撫子
平成23年12月2日 「野分」
”夕霧と源氏”親子の違いが よくわかる野分の場面でした。
ちらりと見た 紫の上は どんなにきれいだったか。
誰も 見たことがない・・のに驚くばかりです。
嵐が吹きあれたのは 外と 心の中でした。 龍馬の妻
野分の中の夕霧、三条の宮から 気になって
六条の東の院に行き 花散る里を見舞う。
又、紫の上を気にしながらの 心の動きが新鮮でした。 がこちゃん
夕霧の性格、育ちが 良く表われていた場面であった。
しっかりした女性に 育てられた情景が 目に浮かびました。
撫子
夕霧の まめやかな真面目さが良くわかり
紫の上に 心うばわれながら 似げなきこと、と
一生懸命にあきらめる。 源氏との違いがよくわかる。 新屋君子
平成23年11月11日 「野分」
野分に入り、秋好む中宮の お庭は
秋の草花で素晴らしく 見てみたいです。
夕霧が ついに紫の上を ご覧になり おもしろき
樺桜の咲き乱れたる姿が 想像され ため息です。 船堀 嫁
野分は 今の台風、 昔もひどい風が吹いたのでしょう。
夕霧の思いで「大臣の いと気遠く はるかに
もてなしたまへるは」 こう言う事だったと思い当たるあたり。
がこちゃん
夕霧の几帳面な 真面目な人柄が良くわかり
さびしい大宮を なぐさめる。
紫の上を見かけて その美しさに驚き 源氏が大事にして
見せない様にしているのが よくわかると夕霧が思う。 新屋君子
夕霧が 紫の上を見てしまうシーン。 義理とは言え
母を見るのが初めて・・なんて、おかしな話ではありますが。
源氏自身、おのれを知るが故の話しなんですね。
平安時代の台風の様子も わかりました。 龍馬の妻
夕霧が 紫の上を初めて目にする場面、 映像の
ストップモーションの様に 印象的な場面です。
「おもしろき樺桜の咲き乱れたるを見るここち」で、紫の上
その人を、直感します。 来年の桜の季節が待たれます。 浩
平成23年10月7日 「篝火」
秋になり、5,6日の夕月夜。
篝火の火を絶やさないように 人にともさせる。
明かりだけでなく、源氏の燃える想いを 篝火に
かえている所が、火の勢いを思わせる。 がこちゃん
琴を枕に 源氏と玉鬘が臥している様子は
美しく 不思議な光景です。 源氏も年を重ねた為か
チョット物足りない気もします。 船堀 嫁
玉鬘は 近江の君の話を聞いて 源氏の深い
思いやりや やさしく色々おしえてくれ 一人前の
姫君になれた事を 源氏に感謝する様になる。
親となのりながら あやしい様子をする所は すこし
いやなのだけど と思う。
源氏も 強くは手を出されない おかしな関係。 新屋君子
心の思いを 篝火に託して 源氏は玉鬘を
見ているが なかなか その思いが伝わらない。
もどかしさが なお更 篝火になり燃えつづけていく。
源氏 36の年です。 また柏木の 実らぬ恋の
篝火でもあった、 柏木 20の年。 龍馬の妻
平成23年9月2日 「常夏」
近江の君は 内大臣家が困っているのも知らないで
内大臣を父として 女御中将などと兄弟とみとめられ
ミーハーながらうれしく 一生懸命につとめて 色々
心をくだいている 憎めない可愛い人だと思う 新屋君子
「常夏」の章、終了で、近江の君の人物像が
浮かび上がってきた。 貴族社会に属していない
育ちながら 生き生きとしたチャーミングさが 女御と
対称的に 書かれて、おもしろかった。 撫子
父から女御殿に参れと言われ 女御に歌を送るが
装飾過多の歌になる。 また返歌を 中納言の君に
書かせるが、同じような歌を書く所が、さすが女御つきの女房。
結び文と おしつつみて と 文の出し方の違い。 がこちゃん
近江の君の登場は、いつもの貴族の姫たちとは違い
チョッとずれていても 可愛げがあると 思います。
紫式部の それぞれの人に合った和歌を作るところが
すごいです。 船堀 嫁
平成23年7月1日 「常夏」
近江の君と 内大臣の 親子対面の場面は、
娘が 思っていた以上に ひょうきん者であり、
可愛さと 困った面のある子だとわかり、困惑して
いたのが、おもしろかった。 撫子
貧しく そだった娘を さがし出して 引きとり
その娘の進退に 心をなやます内大臣の様子。
近江の君の早口言葉 下司様な言葉づかいでも
愛嬌があって かわいい所があるとは。 新屋君子
平成23年6月3日 「常夏}
内大臣が 娘の事(雲井の雁、近江の君)を
あれこれ思い悩む親心が 面白い 新屋君子
内大臣が 近江の君の事で いろいろ気を
もむ様子が おもしろい。
双六で遊ぶ二人「せうさい、せうさい」と こう声。
片や「御返しや、御返しや」と 筒をひねりて と、
お互い我を忘れて 楽しんでいる様子は 生き生きと
している感じで、ほほえましいと思いました。 がこちゃん
平成23年5月6日 「常夏」
玉鬘に対する源氏の気持ちが ますますつのり
色々、思い悩む様子が面白いです。
玉鬘が どのように変わっていくのか、先が楽しみです。 船堀の嫁
むくつけく・うたて・劣り花・心の鬼・とこなつ
すえの妻・許す・愛敬づき・思い入る・関守
御かたらい・・・・全くけしからぬお考えである(草子地)・
ほきたる・をさをさ・・・・源氏の心はわからない・・・・ 龍馬の妻
玉鬘の処遇について あれこれと思い悩む源氏
せずともよい恋をして 心休まる時のない
物思いを するのだろうと・・・
いろいろな想定が おもしろい がこちゃん
姫を 自分のものにしようと 策を巡らしている
中年オヤジの悲哀を感じてしまう。
また、姫の心境の変化が 生じてきた章でもある。
内大臣の 源氏に対する心情も おもしろい。 撫子
男であり、父親であり、悩める乙女のようでもある
繊細な源氏は、現代の ここかしこに見られるような
親近感を 感じます。 浩
平成23年4月1日 「常夏」
今日は 3.11の 地震の話で盛り上がりました。
恐かった! これからのことは、どうなるのか・・・ 龍馬の妻
親恋しさの娘と、少しだけ親バカの源氏が、
和琴談議をしながら、 心の内を見ている様は
もどかしく感じられた。
今回は地震被害で、自分自身、気分が落ち沈んで
のりが、いまいちでした。 撫子
和琴の音色は どんな音色でしょうか。
一度 聴いて みたいものです。 Ⅹ
楽器の和琴は 耳にする事がありません。
「すががきの音」が どんなに 素晴らしいのかなあ がこちゃん
「夕霧と雲居の雁」との結婚を許さぬ内大臣のことを
玉鬘にこぼす 源氏。
催馬楽の一節を 口ずさんで、やんわりと反論する玉鬘。
源氏が魅かれるだけのことは、ありますね。 浩
秋の夜の 月の光の澄む頃、
庭前の 虫の声に合わせるように弾く 和琴の音を
ぜひ聞いてみたい と思う ぜいたくな願い。
被災地の方々には 申し訳ないですが、
日常をはなれて 優雅な気分に ひたりたいです。 船堀の嫁
玉鬘は 実父が 琴の名手と聞いて、自分も上手に
なりたいと思うが、源氏と実父の確執があるのを知って
実父に会うのは 難しいと 心配する。
玉鬘は やっぱり実父に ちゃんと会わないと 自分が
中ぶらりんの様で おちつかないのでは ないでしょうか。 新屋君子
平成23年3月4日 「常夏」
暑き日の 過ごし方。
それも 食事の風景は 珍しい。
随分 昔から 「氷室 」があったのも おどろき。
源氏の 内大臣に対しての 気持ちが おもしろい。 がこちゃん
暫らく お休みしていたので 原文を読むのに苦労してしまいました。
「常夏」で 撫子の花が 出ましたが、 お花だけでも
知らない事が 色々あり 勉強になります。
源氏は 本当に 奥が深いです。 船堀の嫁
昔から 内大臣とは友達と言いながら 競争相手であり
特に 内大臣の方が 源氏に嫉妬している様な所があり
玉鬘を 自分の娘とは知らず 悔しく思って 自分も探し出した
近江の君が どうしようもない娘で 困り果てている。
無理に 捜すと ロクでもないものに あたる。 新屋君子
「意地悪な源氏」が 出ていた場面と 思います。
自己中心で まず自分、自分。 自分が一番な、文でした。
誰に 似たのでしょうか? 育った環境のなせる業なのでしょうか?
それも含めて 源氏の個性 だと思えた。
そんな 腹黒源氏も 好きです。 撫子
玉鬘の御殿の庭には 垣を風雅に結んで 唐撫子(石竹)と
大和撫子が 咲き乱れている、とありました。 源氏物語には
花の名をあげた章が多いのですが、昔も今も、花を愛ずる気持ちは
変わりない、と言うより、源氏物語が花に対する感性を伸ばし
続けていてくれる と思えました。 浩
平成23年2月4日(金) [蛍」
娘を 自分の出世の道具 として使う時代の 男親の心情
(源氏と内大臣)が、卑しく思われた 一節であった。 撫子
明石の姫君の 教育上の配慮には 源氏 並々ならぬ
物が ある。 昔の 雨夜の品定のような場面が
それぞれの 息子達の間で かわされるのが 又、
時を 感じさせてくれる。 がこちゃん
昔の 自分の所行を思って 夕霧を 紫の上の所へは
近づけない様にする。
明石の姫君の教育に 紫の上と話して 物語なども
いろいろ よりわけて 用意周到な 源氏の有様。
やはり 自分の子と 玉鬘との違い。 君子
立春の今日、「蛍」が 終わりました・
終わりの場面、夢解きの占いに 玉鬘の現状を示唆
するような答えがでました。 さあ次は、どうなるでしょう! 浩
平成23年1月14日(金) 「蛍」
?
源氏の口を借りて 物語の重要性を 紫式部は言っています。
自分の知らない人生や 人々の考えを 知る事が
本を読む たのしみだと おもいます。 君子
?
源氏は 女君達が好む物語を 上から目線で
「こちなくも 聞こえおとしてけるかな、、」と言い乍らも
たいした物のように 諭してしまう。
玉鬘に対しての 気遣いなのかな? がこちゃん
?
明日、八十三歳の誕生日を迎えられる お仲間が
いらっしゃいます。 とても素敵な方で 一緒に
お勉強 出来ることを 幸せに思います。 信子
?
この段は、玉鬘と、源氏の口を借りての物語論と思いました。
物語好きの姫君や、女性達の手を借りて、今の世まで
伝わっているなんて、素晴らしいですね! 浩
?
?
?
平成22年12月3日(金) 蛍
五月五日の節の様子 。
御殿の様子 。
裾濃の色使い 。
優雅な世界に浸りました。 X
花散里の心情が良く出ている場面でした。
源氏との気のおけない会話が、夫婦らしく、その中でも
しっかり源氏が、自分を主張しているところが、さすが
「俺様」「源氏様」って感じでした。 Y
馬場での騎射の催しは、相変わらずの華やかさ!
童女、下仕えの衣装の色目が、若やいでとても美しかったでしょう。
花散里の人柄もよく出ていて よかったなぁ
にお鳥も、いい感じ! かこちゃん
六条院の大きさ、広さに、再び驚きました。
また 着物の色の奥の深さも 知りました。
花散里の生き方、、、考えました。
源氏物語の もう一つの話になるような気がします。 お龍
蛍の宮を玉鬘に薦めたり あぶない人だから近かよらない様になど
矛盾した事を言う源氏の心は 玉鬘をくどいたり あきらめたり
ゆれうごきながら自制するようです。 花散里は老女の様にめばえのしない人だけれど、、、。
蛍の宮は たしなみのより立派な方だけど たいした事はないと
自分とくらべて おとしめる花散里は 人柄のよい静かなる人なので
源氏も自然体でいられる様。 年はわからないけど 源氏より年上のようで 髪はうすく、容貌も良くないので 共寝を遠慮しているよう。
私は 源氏の女君の中で 一番好きです。 新屋君子
ひさしぶりに出席しました
「蛍」に入っていて おどろきました。
童女たちの かさねの色目を 本で見せていただき
たくさんの色が あふれている所が イメージできました。
また 花散里と源氏が休む様子に 花散里の素直な気持ちを
感じました。 haru
今年も残りわずか、忙しさを理由に予習もせず参加しました。
いつも思う事なのですが、色の描写が美しく 童女たちの
衣装(薄物)が、想像するだにステキです。
日本の色の名前を 大事にしたいと思います。 野辺の花
平成22年10月1日(金) 「蛍」
巻名の「蛍」の場面にゆく迄の
源氏の「心懸想」が いたずら心いっぱい と言う感じ。
「玉鬘」の美しさを 「蛍」をはなって 見せようとする気持ちは
「どうだ」と言う感じかな? 高橋賀子
源氏は 自分の思いとは別に 宮に玉鬘を見せようと
玉鬘の居る所に 蛍をはなして 宮の恋心をつのらせる。
玉鬘は 源氏の事を警戒して すきを見せない。
あれこれ世話をやく源氏を見て 本当の事を知らない女房達は
かたじけない事と 皆で言い合う。 新屋君子
源氏の 単純で あまのじゃく的な 恋愛感情が
こっけいであり、 玉鬘の 大人の大らかさが
際立っていた。 有明敬子
「蛍」を沢山、集めて、闇に放ち 玉鬘の美しい姿を
瞬時 見せると言う発想! 紫式部は なんて豊かな
イメージを持った人だったのでしょう! 福川浩子
平成22年7月9日(金) 「胡蝶」
有明 敬子
源氏と玉鬘のすれ違いの思いも面白く その気配を感じとる
紫の上がしっかりした妻としての成長を感じました。
福川 浩子
実の親に会いたいと思いながらも 直接は表面に出せない
玉鬘の愛らしさ。ますます魅かれていく源氏。あなたを
頼りにしていらっしゃるのがお気の毒と紫の上。
三人三様の心情が面白かった今日でした。
新屋 喜美子
今日はメガネを忘れたので活字を見る事無し。
耳を傾けていると古文の美しさ、心地よさが伝わってきます。
音読をもっとたくさんやろうと思いました。
新屋 君子
源氏は玉鬘に心があるのに玉鬘は知らな い。右近は二人並べても
おかしくない源氏の若さに玉鬘を源氏にあげたいと思ってる。
紫の上も源氏の浮気心を知っているので玉鬘に手を出すのではと
疑う。源氏自戒する。
小笠原 信子
源氏の心理状態を紫の上は ちゃんと見抜いていますね。さすがです。
平成22年6月4日(金)「胡蝶」
高橋賀子
げんじが公達たちの恋文を見ながらの感想
予期していたことでしょう
中に気になる歌があって右近にいろいろアドバイスするおせっかいさ
玉鬘を他人の妻にするのが惜しくなる源氏
有明敬子
源氏が父親もどきから男性へと心情変化していく様が面白くなってきている
他人の恋文に甲乙つけているあたりはいじわるじいさんのようだ
福川浩子
平安時代の身分の高いかたの結婚観、大変でしたね!
でもげんだいにも通じることなのかとも?
新屋喜美子
今日も予習しないで出席するのですが
原文を読むのはたのしいです
玉鬘の衣装の襲の美しさがとてもすてきです
新屋君子
玉鬘の所に来る恋文を源氏は読んで右近にいろいろいいきかせる
(女房として心得ること)
姉弟とは知らず内大臣の息子たちも手紙を寄越す
玉鬘が色々人のありさまを見て
着るものや化粧が不足なく美しくなったので
源氏は心引かれて他人に嫁がせるのが惜しくなる
小笠原信子
撫子襲の細長が美しく
草木染めのはすばらしいと思いました
平成22年5月7日(金)「胡蝶」
福川浩子
「遊びやせんとや生まれけん」「戯れせんとや生まれけん」の原型を見るような
心地がする抄でした。
いったいあの貴族たちは何時ねるのでしょうかと思うことしきり
新屋君子
管弦の遊びの華やかさ盛大さをもり沢山にもよおし
六条一番の盛り場面を見る思いで
源氏の思惑通り若者たちが玉鬘に心を奪われる様子がよくわかる
高橋賀子
六条院の里に下がった中宮の季の御読経が行われたり紫の上からの
鳥蝶の舞のはなやかさに圧倒される
源氏の権勢がすごいと思う
新屋君子
六条院のはなやかな生活
舞楽の種類
舞の美しさの描写が素晴らしい
平安貴族のぜいたく、時間の流れが面白い
小笠原信子
六条の院での宴の情景が美しく楽しめた場面でした
有明敬子
大貴族のはなやかな行事が目に浮かびました
平成22年4月2日(金)「胡蝶」
新屋君子
六条院の盛大さを表した紫の上の春の御殿のすばらしさを
中宮の女房たちに見せて感心させ中宮に伝えるようしむける
そのことで秋好中宮からの秋の歌の仕返しをする
諏訪峰子
胡蝶に入りました
六条院の想像のつかない大きさにびっくりした
南と西の御殿の庭の池の大きさは
竜頭鷁首の船は二艘ほどで
平安時代ならではの豪華絢爛さが目に浮かぶ
六条院を見てみたい気になりました
有明敏子
春の季節の美しさが目に浮かぶ情景描写でした
この季節にもってこいの勉強会でした
小笠原信子
春の御殿の素晴らしい所が想像の世界ではあるけれど
垣間見えました
福川浩子
本日は強風の中先生は列車を乗り継いで
教室にたどり着きました
先生を待ってる間今日は
新屋さんの東京大空襲の体験談を伺う
生と死をわけた日々を淡々とかたる新屋さんに感嘆しました
平成22年3月12日(金)「初音」
新屋君子
二条院の女君の所をわたって空蝉と昔のことを語り合った
末摘花がこの程度の話し合いが出来たらと残念に思う
正月14日の男踏歌は珍しい催し物ですが絶えたとの事
高橋賀子
源氏が空蝉を訪ねる所から始めました
源氏と空蝉の今までの関係をていねいに
語ってくれて空蝉の風情に涙ぐむ源氏の思いが
少しわかった気がします
新屋喜美子
源氏の女君たちに対する
こまやかな心づかいがいつもながら
すごいと思います
福川浩子
今日は空蝉の消息、その後が
良くわかり安心致しました
源氏は何と面倒見の良い人なのでしょう
小笠原信子
男踏歌の様子が興味深く思いました
平成22年2月5日(金) 「初音」
新屋君子
正月の人々の集いのにぎわいに六条院はたいへんであったが
静まってから源氏は末摘花、空蝉のいる二条院に行く。二条の院で末摘花は源氏の贈った
柳の衣を着ていたが全然不似合いで、下着をかさねていなくて寒さにぶるぶる震えている。
兄阿闍梨のお世話で自分の衣は縫うことができなくなったという
素直でよいけれど源氏は身も蓋もないと思う。
でも末摘花程無欲で正直な人は今時めずらしくさすがは貴族の姫様と
これで顔が良かったらこんなすばらしい人はいません
小笠原信子
明石の君と末摘花の対比がおもしろいと思いました
奥が深いですね
福川浩子
本日は「初音」
明石の御方の項が担当でしたが紫の上との生い立ち、性格の違いなどを
伺って目のさめるような思いでした
源氏物語は深いなーと今更に。
高橋賀子
源氏が明石の上を訪れ一夜を明かす
源氏を迎える明石の様子が他の女君とは違った感じで読みました
有明敏子
新年の挨拶まわりの源氏と妻たちの様子が生き生きと描かれていた
平成21年12月4日(金)「初音」
新屋喜美子
お正月の六条院の華やかな様子が色と香りとともに感じられる文章です
幸せな
女君たちの中で明石の上の淋しさが印象に残りました
高橋賀子
六条の院での新年の様子
女房たちが祝いごとなどして「そぼれあへる」ということばが面白い
いかにも楽しそうで思わず源氏も仲間に入りたそう
有明敏子
初音は時節柄いろいろ楽しく読むことができました
新年の行事がよくわかり、友人たちに
話題として提供したいと思います
源氏と女君とのいろいろな夫婦関係もかいまみることができました
福川浩子
今日から「初音」新年の様子が描かれている。
花散里が登場するも私は読んでいないためか源氏の
心のひだ、内面がよくわかりません
急ぎ取りかからねば…。
平成21年11月6日(金)「玉鬘 最終章」
新屋君子
玉鬘は数奇な運命で源氏の六条の邸に引き取られ思いもよばぬ上流の暮らしに入る(シンデレラ姫)
でも玉鬘にしたら父でもない源氏に手厚くもてなされるのは異和感がある
福川浩子
年の暮れに源氏にかかわる人たちの
装束が新調されます
源氏の見たてに心穏やかならざるところもみえる紫の上の心のうち
華やかな衣装選びの中に、微妙な内心が交錯します
「日本の色辞典」で当時の色を拝見しました
高橋賀子
年の暮れ、源氏が新春の晴れ着を女性たちに贈る華やかな場面
それぞれの着物の説明が一層想像をかりたてる感じでした
有明敬子
玉鬘の最後が末摘花で終了したのにはびっくりでした
衣の色見本と想像で素晴らしい色調を古の人は着ていたと思う
平成21年10月2日(金)「玉鬘」感想文
新屋君子
玉鬘は父でもない邸に引き取られるのは本意ではないが、そこにいれば父に知られるよすがもあるから
と、皆になだめられて六条院に行くことになり、源氏は衣装など色々取りそろえて送る、手紙を玉鬘に出し返事を見て安心する。玉鬘の住まいは六条院の花散里の西の対に。花散里が夕霧をまかされてお世話がうまくいったので源氏は玉鬘のお世話も頼む。花散里の人柄の良さがわかるような源氏とのやりとりだった
福川浩子
本日も玉鬘の巻
源氏はこれから会おうとする玉鬘の様子が心配で、まず自らが文を書き、その返事を待つのでした。当時は文と筆跡を見ればその人となりが一目瞭然。現在にも通じることでしょうが当時の身分の高い人々が日々教養を身につけるべく研鑽している様子が忍ばれました
有明敬子
玉鬘が六条院へ行くきっかけとなる源氏との文のやりとり、玉鬘のとまどいと不安の心情がよく出ている場面と思う。その中にしっかり自分が確立されている玉鬘の様もうかがえる章でもあると思う
高橋賀子
源氏から夕顔のことを打ち明けられた紫の上の気持ちにはつらいものがあったと思います。姫君がらうたげであればある程つらいと思います
新屋喜美子
しばらくお休みしたので予習の時読んだのですが、口がまわらない感じです。
源氏は夕顔の話を紫の上にしますが、源氏の気持ちを聞いてどんな思いだったのでしょうか
平成21年7月3日(金)「玉鬘」感想文
新屋君子
右近は夕顔の遺児の姫君に初瀬で出会いその美しさ、気品があって優雅な風情に
田舎に育ったのにこんなに立派に成長して乳母の苦労に感謝します
でも皆田舎人になったのに姫君だけがと心得がたく思いますが
私も心得がたく思いました
福川浩子
源氏を読む毎に
その場所に行きたい思いにかられます
今日は長谷寺に。いつの日か。
有明敬子
姫君の行く末に光明が差し込んで場面で
右近も乳母もいろいろな意味感懐思惑
ひとしおであったと思う
高橋賀子
右近が見る姫君の様子
乳母の養育が光っている
小笠原信子
今後の展開を楽しみにしています
平成21年6月5日(金 )「玉鬘」感想文
高橋賀子
長谷の椿市での右近と乳母一行との出会い
京都からの旅はどんなにたいへんな事かと思いました
とても劇的な場面でしたが「樋洗めくものなどカルチャーショックでした
新屋喜美子
長谷寺での姫君一行と右近との再会は
ドラマチックで面白いです
20年の歳月は人の様子も変えて
右近も自分の年を感じる
三条とのやりとりが楽しいです
新屋君子
一心に祈った甲斐あって
右近と姫君がぱったり会うことになり
お互いに相手の事情を知ることができる
姫君はここで右近に会ったことにより
運が開けて行く長谷観音の御利益は
験あらたかなり
福川浩子
本日の印象深い言葉二つ
①法師(宿の主人)…「頭掻きありく」
部屋割りに苦心惨憺の体
②三条(古き下衆女)…「食物に心入れて」
食物に夢中になってる様
紫式部は参詣の折りなど
鋭い観察眼で周囲の人々を見つめていたのでしょう
有明敬子
夕顔の使用人である右近と
三条がドラマチックに再会する場面で
二人の立場、心情がひしひしと伝わってきます
小笠原信子
久しぶりの参加で勉強不足ですが
物語の展開に心動かされました
次回も楽しみです
平成21年5月8日(金) 「玉鬘」感想文
新屋君子
九州から大夫監の手を逃れるべくそれぞれ
妻、夫を捨てて姫一人を守るためだけに
「あやしのわざ」と自身もあきれるおもいで
京への船旅に出る劇的場面
どうしてそこまでするのだろうと現代から見れば
考えられない逃避行
福川浩子
思い切った逃避行
ダイナミックな展開にわくわくしました
式部の精密な想像力に感服
この章はとても魅力を感じます
新屋喜美子
乳母、豊後の介の苦労や心情がよくわかり
当時の貴族の主人にたいする思いが伝わります
30日かかったという京都までの船旅を式部はどのように
調べて書いたのか不思議です
有明敬子
玉鬘の巻は源氏の中でも登場人物がさまざまでおもしろいと思う
この時代の人でも乳母や豊後の介のように
姫様主義、ご主人様大事による後先かえりみずの行動のすごさには
ただただ感心するばかりです。
豊後の介は母思いの草食系なのではと思う
高橋賀子
昔の旅の大変さを感じました
追っ手を心配し生きた心地がしないまま
やっと川尻にたどりつく
姫君のために取った行動がどんなに無分別であったか
京についても何のあてもなく心細い日々
従者たちも筑紫へかえってしまう
しかし監に味方して自分たちが多少の羽振りがよくなっても
「何ここちかせまし」心穏やかにはくらせないのだ
平成21年4月3日(金)「玉鬘」感想
新屋君子
大夫監という武士が出てきて
色々言いまくるが
公家社会からみて荒々しく
押しがふとい人たちを
うとましくいやと思う感じがよく出ていました
高橋賀子
少弐の役人としての現地での
生活ぶり「仲あしかりける国の人多くなどして」は
真面目であったろうと思う
上京する旅費等もあまりなさそう
大夫監の描写がおもしろい
桜井陽代
大夫監の言動について
自分の行動はまちがいないと
思い込んでいるところがおもしろい
ただその一途さが
応対した乳母にとっては野蛮で恐ろしい
この対比がおもしろく
思わずくすっと笑ってしまう
「肥ゆ」と「ふとる」のちがいを知って
なるほどと思いました
それにしてもこの時代と今のことばの
何と違うこと!!
新屋喜美子
少弐と乳母の
姫君を大事にする気持ちが
とてもよく伝わりました
田舎者の大夫監から姫を
どのように守るのか展開がおもしろそうです
平成21年1月9日(金)「少女」
新屋君子
六位に対する劣等感から
また雲井雁への思いに「心くづほれて」
いろいろ悩む多感な青年、夕霧が
花散里の美しくない容貌に驚くけど
「心ばへのやはらかさ」にその人の優しさを思う
ところがよかった
高橋賀子
大宮の生きがい(?)になったのか、
夕霧のために睦月の装束の用意にはげむが
心が晴れない夕霧、
大宮の作る六位の装束には
心が沈むばかり
いろいろ感じやすい夕霧が印象的
FUKU
箱入り息子の夕霧と
現在の政治の中枢に居る二世の方々の
頼りなさがオーバーラップした
今日の授業でした
平成20年12月4日(金) 「少女」
新屋君子
娘に文をよこしたのが源氏の息子の夕霧と知って
手放しで喜ぶ惟光を見て昔の、源氏の供をして
歩き回っていた惟光が彷彿として思い出されうれしくなる
新屋喜美子
「まし」「きむじ」の二人称を表すことばは初めてで
面白いと思いました。今は全く使われていないことばが
たくさんあるのですね
福川浩子
登場人物の年齢関係が今ひとつはっきりしないので
もどかしい思いです。でも今日は惟光の親子関係がリアル
なところが面白いと思いました
高橋賀子
惟光の親心
夕霧の文を見て「名残なくうち笑えて」
「きむぢ」らは自分の息子達と比べている所
平成20年10月3日(金) 「少女」
新屋君子
夕霧と雲井の雁の幼い恋物語で、一緒に住んで育っって自然発生した恋心を、周りが騒ぎだして本人
たちはただはずかしいばかりに困って行き来ができない
大宮は二人のことで大宮に睨まれるが、二人に愛情があるので心では許している
新屋喜美子
夕霧と雲井の雁のゆくすえが楽しみ。
夕霧の生真面目な性格が源氏と違いおもしろいです
内大臣の今後の行動もどうなるのでしょうか、気になります
高橋賀子
一つの部屋で障子を置いて男女が寝ている状況に驚く。
二人ともお年頃なのに。
内大臣が急に雲井の雁に目をとめたのは?
小笠原信子
風の音の竹に待ちとられてうちそよめくに」の表現は何ともその時代の風景を感じ印象に残りました
夕霧と雲井の雁の今後どうなるのでしょう
福川浩子
源氏と内大臣の確執の、やりとりのすさまじさを改めて知りました
平成20年7月4日(金) 「少女」
新屋君子
源氏の政治力の強大さには驚く
夕霧の大学の入学に上達部などがわれもわれもと見送り
立后には弘徽殿の女御、式部卿の王女御を押さえて梅壺を押して立后させたのだ
女君の時代から政治権力の争闘が繰り広げられていた
新屋喜美子
源氏の政治力に感心したり
夕霧と雲井雁のさきゆきが心配だったり
楽しみだったりします
高橋賀子
内大臣の家の栄と源氏の政治力との差がおもしろい
H,F
雲井雁の父君、内大臣の娘に寄せる心情は
昔も今も変わらぬところが有るものですね。
大饗の内容、特に食事の献立は知りたいなと思いました
源氏物語の流れを、まだ捕らえられませんが、いつの日か。
平成20年5月9日(金) [朝顔」[少女」
桜井陽代
いつもながら色彩のきれいなことに驚きます
月の光、氷、藤、浅黄
源氏の蓮の上には誰が…?と考えると面白いです
新屋喜美子
あらためて源氏の藤壷への強い想いがわかり
紫上の気持はいかにと想像しました
新屋君子
源氏は息子の夕霧を元服させて四位にはせず
大学の学生の六位にして学問をさせ基礎をしっかりつけさせるという
考えに感心しました
また朝顔の意志のはげしさに源氏はすこし気持が引くが
敬意を感じるからであろう
高橋賀子
藤壷が源氏の夢枕に立って恨み言を言うところ
また源氏の思慕の情がずっと続いていることが印象的でした
平成20年4月4日(金) [朝顔」
桜井陽代
源氏の言い訳めいたことば。紫の上を煙にまいてるの?
言い繕ってるように感じます
雪まろげの色彩の豊かさ、きれいでした
原文ではじめて味わえるんだと思いました
小笠原信子
雪まろばしの場面の雪の白さと
童女の着る衵の色との鮮やかさ
楽しげな様子が時代を超えて伝わってきました
高橋賀子
紫上を慰めながら雪まろばしの場面で
気分を変えさせる様なちょっと複雑な
気持ちになっていたのかな?
平成20年3月14日(金)[朝顔」
新屋君子
久しぶりに源内侍が出てきて、老いた姿でいろいろ言いかけるのに辟易する源氏。
清少納言の”すざまじきもの”におうなのけさうとあるが。
源氏のすばらしさを知りながらあれだけ源氏に求愛されても身を辞して受けない心強さに
驚かされます
高橋賀子
式部卿宮が亡くなって半年くらいで庭の荒廃振りがはげしくなったことには驚かされた
でも現代の家と違い、寝殿造りとは庭が殆どという説明を聞いて納得した
平成20年1月18日(金)「朝顔」
新屋君子
『枯れ枯れ』の庭の渋さに合う朝顔と源氏の出会いは源氏の一人相撲の様、
朝顔の巻に初めに登場するのが女五宮、女五宮の老女ぶり、今も似たような
年よりがいるなあと思った……この方はもう?才のすごいとしなのに全然老女じゃありません
新屋喜美子
斎宮と斎院の違いが今日わかりました。毎回何か発見があり楽しいです
朝顔の巻に入り、前斎院に想いを寄せる源氏ですが喪に服している
斎院はどのようなお気持ちなのでしょうか
これからの展開を楽しみにしてます……お嫁ちゃんと呼んでます。すごーく優しそうな方
高橋賀子
斎院と斎宮の違いが新潮日本古典源氏物語二巻めの「賢木」を読み返して納得。
前斎院には会えないのにその様子は女房たちに知られてしまい
その後の「うわさ」がどのように広まっていくのか楽しみ。……うちらの美人姉御事務局長
小笠原信子
日頃の忙しさから離れむらさきの会の時間の中で源氏の世界を楽しんでます…どんなに遅くなっても
人形町からはるばるかけつけてくれるの、うれしいですよ
平成18年11月10日(金)絵合を終えて 新屋君子
11月10日 出席者、新屋君子、新屋喜美子、小笠原さん、高橋さん。
> (すこし遅れてくる)
> 先生、学校がお休みとのことで5時頃迄やって、絵合せ全部終わる。
> 令泉帝の後宮では権中納言の女御と斉宮の女御がいらっしゃるが令泉帝は
> 年上の斉宮の女御になじめなかったが女御が絵が上手であったため絵の好きな
> 帝としだいに親しくなる。これを聞いた権中納言は絵師を集めて今様の
> 珍しい絵を描かせて娘の女御に贈った。源氏も伝来の古画を斉宮の女御に
> 差し上げる。朱雀帝もそれぞれ二人の女御に絵を下さる。
> かくて後宮は絵の論議が高まり帝のおなりをあおいで左右にわかれ
> 勝負を競うことになる、審判は源氏の弟の師の宮がなさる。皆すぐれた絵ばかり
> なので師の宮も定めかね夜に入り最後に左方(斉宮女御)が出した源氏の
> 須磨で描いた絵を出した所皆感涙して左方の勝ちにきまる。
> その夜の打ち上げの宴で、源氏、師の宮と学問絵書について論議する。
> 絵の上手な絵師が空想で画いたのと源氏程の人が實物を見て感慨をもよおし
> ひまにあかせて丁寧に心をこめて画いたのは全々勝負にならない事でしょう。
> 昔は源氏と権中納言(頭の中条)とは何処へ行くのも一緒で親友でしたが
> 歳を取り位が上がるとお互いに権力を競う様になっていく様です。
平成18年4月8日(金) 読書会を終えて 高橋賀子
今日は、「蓬生」の三回目。
私は、「惟光蓬生の露を払いつつ 源氏邸内に導く」を担当しました。
源氏に「よく尋ね寄りてを、うち出でよ。人達へしては、をこならむ」
との命を受け、恐ろしくさえ思える邸内で、月明くさし出でたるに
見れば、格子二間ばかり上げて「簾」 動くけしきなり。
女房どもに 《姫の変わらぬ御ありさま》を確かめ 「よしよし。まず、
かくなむと聞こえさせむ」と、源氏の元へ。
随分またされた源氏。「かかるしげきなまに、何ごこちして過ぐし
たまふらむ、わが御心の情けなさもおぼし知る。」
あまりのご無沙汰で源氏は、(ふと入りたまはむこと、なおつつましう
おばさる)と、あります。
前回の叔母がいきなり車を寄せた光景とは、かけはなれたものでした。
尋ねても われこそはとは【め】道もなく 深き蓬のもとの心を
と、ひとりひとりごちとありますように「とはめ」の【め】は、源氏の
強い意志の表れと、教えられました。
惟光は、足元の露を「馬の鞭して払いつつ入れいれたてまつる」
「御傘さぶらふ。げに木の下露は、雨にまさりて」と、
源氏が、女を訪ねる場面の素晴らしい演出の様におもえました。
最新の技術を駆使して再現された「よみがえる源氏」を、
見せて頂きました。
真ん中に描かれた荒れ果てた庭 点々と生えている草 右の方には
朽ちた板が落ちかけている簀の子と老女 左の上には、松と藤の花
左の方は「馬の鞭して・・・・御傘さぶらふ・・・・二人の姿。
「蓬生」のこの場面は、絵になります。いいところを担当できまして
よかったです。
さて、次回は五月。いよいよ再会をなるか?・・・・お楽しみです。
平成18年3月17日(金)読書会を終えて 諏訪峰子
乙一が書いた「暗いところで待ちあわせ」を読んだ時、ふと思いました。
主人公は自分の置かれた状況を素直に受け入れ、きっちり生きています。
そんな事が確かにあるのだということを!!知りました。「蓬生」で決して
貴族の生き方を変えず(それが不自由な生き方であっても)<なごり>を尊ぶ
姫の思いのうち…なんで??と理解しがたいものでした。今回、上記の小説を読んだ時
思いました。主人公ミチルは、目が見えません。それをすっかり受け入れた生き方を選んだミチル。
「杖をついて歩く練習をしたら?ガイドヘルパーを頼んで外界にもっとでたら」と
私は思うのだけれども…。ミチルは目が見えないことを楽しんでいるかのようにじっと家に
籠って生きているのです。私は見える。そうなのです。
目の見えない人の状況を理解する事でした。
私は貴族ではないし、目も見えます。貴族の人や目の見えない人の
素直な気持を丸ごと受け入れて読み取ることの重要性を感じました
全く私的な感想から始まったことを許してください
理解することの原点を知ったことをお知らせしたくて。
今回の「蓬生」は…
ひたすら叔母の猛攻撃に耐える姫君でした
姫君の分身のような乳母子の侍従を引き連れて行ってしまった叔母。
身分ちがいの二人に共通点は何もない
どんな仕打ちを受けようがどんなことばを浴びせられようが
一歩もひるまない姫君でした
後々源氏の共感するところになった行動でした
何と言っても、叔母が訪ねて行くところです。
門は壊れる、道はふさがれている、おたおたする住人…
いきなり姫の寝殿に車を横付けにする叔母。
どこまでいっても接点の見出せない二人でした
次回につづく!
平成18年2月3日(金) 読書会を終えて 諏訪峰子
今日は、「蓬生」の2回目でした。なかなか面白い話しにふれることが、
できました。前回は「なごり」の正しい解釈がありました。
それを踏まえた今回は、「塵は積もれど、まぎるることなき うるはしき
御住ひにて、明かし暮らしたまふ。」です。
その暮らしぶりというと、まず、誰一人としてお伺いする人はいない。
生い茂る草やヨモギを、刈り取るということに、気がつかない。
茅は、寝殿の南の白砂が見えないくらい生い茂り、ヨモギは軒をあらそいて
生いのびる。東西の御門は、つたにすっかり覆い隠れ閉ざされてしまう。
かえって用心がよくて心丈夫?だけど・・・・春夏には、土塀がすっかり崩れ
牛馬が踏みならした道ができ、お邸の中で牛飼いが牛を放牧している。
下屋の板すきの建物は、わずかに骨組みだけが残っているだけで、盗人に
して外見の貧弱さに愛想をつかして、入ってくる者もいない。
「蓬生」をして源氏物語を知るとまで言われている巻です。が・・・・
「末摘花」という、地味でみにくい女の話となると、一歩ひいてしまいます。
内容はと言うと、すさまじくあれはてた邸・叔母の攻撃・・・そんな所に
源氏の君は、やって来るのだろうか???
私の頭の中では、理解しがたいのですが。
俗世間にどっぷりつかり、世情の波に流されている私には、平安の貴族の
ほこり・気品なんてもは理解しがたいです。が・・・・・
源氏は再びやって来るのか? 次回の展開が気になるところであり、期待
したいです。
平成18年1月13日(金) 読書会を終えて 桜井陽代
今回で「澪標」がおわりました。15番目、「蓬生」に入りました。
常陸宮の君(末摘花)のお話は、この人が一生懸命なほど、
私のような庶民には、ユーモラスに映ります。
経済的にとても大変なのに、「名残」を大切に生きています。
どちらかと言うと、女房たちのブツブツ言う言葉に、共感できて
しまいます。
私にとって、ここでは「名残」という言葉がポイントでした。
(私の感覚では「なごり」とは、香とか、そんな風にしか捕らえて
いなかったのです。)
P55ー3L 常陸の宮の君は、父親王の亡せたまいし名残に・・
(名残は、死んでも生きているもの)
末摘花は、食べ物が底をついても、父宮の生きていた時のように
生活している。父君の生活していたように、ものも心も大切にして
いるので、女房に言われても、品物を売るくらいなら飢えても良いと
言う。
自分だけに、あつらえられた家具、父母との生活のままに暮らしたい
ーと言う希望があります。
「名残」を理解しないと、この部分はわかりにくかったです。
平成17年12月16日の講読会から 諏訪峰子
「澪標」を終えて
平成17年の12月の読書会が、終わりました。「澪標」は、あとわずかを
残して、終わりませんでした。
六条御息所は、源氏に娘(前斎宮)の行く末を託し死んで行きました。
源氏は男としてではなくて、親として斎宮の身を案じ良い方向へ、導いて
いくのでして。入道(藤壺)に相談し、二条の院に迎い入れ、そこから入内
させるのでした。そんなところで、「澪標」は終わっていきます。
次回の展開が「蓬生」期待されます。
前任者の福田さんが勇退されましたので、レポートというか、感想文を
書かせてもらうことになりました。
何かと行き届きませんが、精一杯がんばります。
(私一人が、いつも書くのではなく、むらさきの会には大御所が何人も
いらっしゃいますので、年間通じてみなさんと書いていきたいです。
宜しくお願いします。)
平成17年7月1日の講読会から 福田達(とおる)
澪標の巻の第2回
「みづからも、もて離れたまへる筋は、さらにあるまじき
こととおぼす。あまたの皇子たちのなかに・・・」から「・・・五日に行き着
きぬ。おぼしやることも、ありがたうめでたきさまにて、まめまめしき御とぶ
らひもあり。」まで。
前回に続いて、源氏の思いが綴られる。先帝の思し召しで臣下に下り、自らが
帝の位に就くことなど考え及ばぬ宿世と思うが、宿曜師の占いどおり、御子の
お一人(公には知られぬことではあるが)は帝位におつきになられ、また明石
の娘には女児がお生まれになり、いずれは后になられる方と予言されている。
あの偏屈な明石の入道が、娘の将来に及びもつかない高い望みを抱いたのも、
宿縁であろう。さびしい片田舎で高貴なお方がお生まれになったことは恐れ多
いこと、ぜひ京にお迎えしようと東の院の修理を急がせる。
かの地では「はかばかしき」人はいないだろうと、人伝に、母は故院に使えた
宣旨で、父も宮内郷兼参議も勤めた身分ある家の娘のことを聞き出し、明石で
のお世話を頼もうと打診される。両親も既に無く侘しく一人児と暮らしていた
ところに、源氏からの頼みとあって、深くも考えずお受けするとの返事を返
す。
源氏も、故あることとはいえ、遥けき明石に遣わすとあって、乳母をお訪ねに
なり、「特別に思う仔細があってのこと」と自ら考えるところをお話になる。
流石に家の構えは大きいが、手入れが行き届かない有様。源氏も乳母の品ある
姿にひかれて近くに迎えたいと思いつつ、歌を交わす。
信の置ける家来をお付けになって、明石に旅立たせる。「他言は無用」と心づ
けを与えて言い含め、お守刀を初め入用の品々を持たせる。入道への文にも
「くれぐれも大切にお育てになるように」とあり、迎えた入道は喜び畏まり、
京を向いて伏し拝む。姫を産んだあと物思いに沈んでいた娘も、源氏のお心遣
いに気を取り直し、お付きの人に格別のもてなしをして返歌を託す。
遠く田舎道を下ってきた乳母も、類無く「いとゆゆしきまでにうつくしい」女
児に接して、源氏が大切にお育てされようとするのも納得し、お世話申し上げ
るのであった。
指折り数えて、女児の五十日(いかのひ)に「遅れることなく着け」と、心遣
いの品々を持たせて使いを遣わす。身近の京でお育て出来ない歯がゆさなが
ら、明石で不遇を託っていたがゆえに、女児に恵まれた宿縁を思う。
今回の焦点は、紫の上に明石のことを打ち明けて、京に迎えることに理解を得
たいとするところ。「願う方(紫の上)には気配が見られないのに、明石でお
子が生れるとは。それも男児ではなくて張り合いがないが、放ってもおけない
ので京に迎えようと思う。悪く思わないで。」と本心は語らず、しかし明石の
娘の魅力を思い出しつつ話して聞かす。これを聞いて紫の上は、離れている間
もひたすら源氏のことを思い続けていたのに、その間かの地に心をとめる方が
いたのか、と心は深く傷つき悩む。源氏は「理解してもらえないのは残念」
と、空涙を流しつつも、腹立つご様子に魅力を見出す。女児であるが故の宿縁
を、どうして紫の上に語ろうとしないのか。生れたばかりで入内も遥か先のこ
と、確信が持てなかったのか。宿縁とはいえ、入内の構想が表沙汰になって壊
れることを怖れてか。それとも、紫の上と明石の君との、女同士の確執を恐れ
てのことか。
源氏の本心と紫の上への振る舞い、紫の上の思い、に会でも多様な意見が語ら
れる。
-古語あれこれ-
源氏の告白に対して紫の上が心境を読んだ歌「・・・われぞ煙にさきだちなま
し」、源氏が乳母に贈った歌に添えた言葉「したひやせまし」、など、助動詞
「まし」が随所に使われている。古語辞典では、[事実に反する状態を仮定し
て、想像する意を表す]として[①事実に反することを仮説する条件が上にあ
る場合]と[②事実に反することを仮説する条件が上にない場合]とに分けて
意味を説明している。上の例はいずれも②に該当するが、その意味として[も
し・・・だったとしたらよかっただろうに]を示しているが、源氏物語で使わ
れている実例は、どうもこの意味ではしっくりしない。仮定したことへの願
望、というよりも「こうありたい」「こうしたい」といったもっと強い意思を
示しているのではないか、と解される。
平成17年6月3日の講読会 福田達(とおる)
今回から澪標の巻に入る
「・・・」から「・・・当帝のかく位にかなひたま
ひぬることを、思ひのごとうれしとおぼす」まで。
源氏は、京に戻ると、夢にお悩みのご様子であった先帝桐壷院のご供養にと、
法華御八講を執り行われた。帝のお召しで参内し、政などご相談になっておら
れる。世の人々も喜び、ご威勢に靡き従う人々も昔のとおり多い。
弱気の帝は譲位を心に決めて、尚侍(朧月夜)と打ち解けて語り合う。尚侍の
父太政大臣も既に他界し、姉弘徽殿の大后もご不調とあって往時の権勢は見る
影もなく、退位したあとの尚侍のことを心にかける。「源氏に比べて見下げて
おられたようだが、いずれ源氏の庇護を受けることになっても、貴女への気持
ちは私に比ぶべくもないことでしょう。どうして御子が出来なかったのか」と
涙ぐむ。尚侍も、源氏のお気持ちが分かるにつけて、どうしてあのような若気
のいたりで源氏にも迷惑をかけるようなことをしたのか、辛い気持ちになる。
東宮は十一歳となって元服の儀を迎えられる。源氏と瓜二つのご様子で、眩い
ばかりに、母君入道の宮は人知れず心をお痛めになられる。
帝は東宮にいずれ位を譲ると語っておられたが、俄かに譲位を決意された。弘
徽殿の大后は源氏を退けることが果たせなかったと悔やむ。
源氏は先ずは内大臣に復位する。摂政として大役を務めることは辞退し、一旦
は退いていた致仕の大臣に譲る。初めは固持していた大臣も、周囲から説得さ
れて太政大臣に就かれる。息子の頭の中将も権中納言になり、一族もさまざま
に栄誉に与る。
葵の上が亡くなられて母大宮や父大臣が不遇を嘆いていたが、源氏は若君にも
お心をおつかいになって童殿上される。源氏不遇の間も退出されることなく、
若君をお世話してこられた方々、二条院でも引き続きお世話しておられたお付
の人々にも、源氏はお心遣いで適切な処遇を配慮される。
明石の娘のことも忘れることなく、そろそろかと使いを立てられたところ、急
ぎ立ち戻り「女児めでたくご出産」と報告する。初めての女の御子誕生を喜
び、帝の即位といい、若君といい、宿曜師の占いどおり望みが叶ったと嬉しく
お思いになられる。
澪標の巻に入って、これまでの須磨、明石での不遇な境遇から、一転光を浴び
る華やかな源氏の姿が描かれる。だが、その中で、譲位直前の帝(朱雀帝)の
心境が綴られる。これまでも、帝の弱気な性格、権勢欲旺盛な母君弘徽殿に頭
の上がらない様子が、随所に語られていたが、ここに至って弱々しいお姿に留
まらず、尚侍の前で気を許したのか、源氏への対抗心、嫉妬心も恥じる様子無
くあらわに口にされる。「人間」としては本来の姿であり、物語がとりあげる
のは素直なことであろうが、「天皇」の姿として描かれることは、他の物語に
見られたのであろうか。紫式部が初めてのことであったのか。宮廷の生なまし
い実態を把握する手法として、歴史学者は、この場面を素材として注目してき
たのか、それとも「ありえない語り物」として、無視してきたのか。
-古語あれこれ-
現在、会で使っているテキストの解説では触れられていないが、別のテキスト
で[自発の助動詞「らる」]を指摘している。これは、これまでほとんど意識す
ることのなかった助動詞である。帝と尚侍との語らいの場面で、尚侍の様子を
ご覧になっているところ。[女君は、顔はいとあかくにほひて、こぼるばかり
の愛敬にて、涙もこぼれぬるを、よろづの罪忘れて、あはれにらうたしと御覧
ぜらる。]の結びの「らる」。帝のご様子を語るところであり、「尊敬」とし
て軽く読み過ごすところ。それをあえて「自発」とこのテキストでは解説して
いる。「御覧ず」という語が、そもそも手元の古語辞典では[「見る」の尊敬
語。ごらんになる。]で、[「見給ふ」よりも敬意がやや高い。]とあり、これ
に尊敬の助動詞「らる」を付け加える必要は無い、ということから、ここの
「らる」は「自発」と解されるのであろう。
[平成17年5月13日の講読会 福田達(とおる)]
明石の巻の最終回。
「このたびは立ち別かるとも藻塩焼く 煙は同じか
たになびかむ」の歌から巻最後の「・・・おぼつかなく、なかなか怨めしげな
り。」まで。
[をとこのおんかたちありさま・・・]と語る最後の逢瀬の場面が、纏綿と続
く。なかなか琴を弾こうとしない娘に、源氏は京から持ってきた琴を取り寄せ
て先ずは自ら奏でる。娘も引き込まれて弾き始める。入道の宮の琴の音が思い
出されるが、ともに素晴らしい奥ゆかしさながら、対照的な雰囲気の音であ
る。心をこめて再会を約し、形見にと琴を残す。
出立の朝も、人目を避けて娘と文を交わし涙を流すが、お付のものは、住み慣
れたこの地を離れる淋しさかと察する。
入道は、源氏をはじめお付の者どもに、盛大に旅装束の支度をする。そこに、
娘が自ら裁ち縫い上げた狩衣に歌の添えてあるのを目に留めて、わざわざこれ
に着替え、身につけていたのを形見にと娘に贈る。
源氏の一行は、急ぎ京に上る。二条の女君をはじめ、京の人々、お供の人々、
夢心地に嬉し泣きの大喜び。悲しみに沈んだ明石の娘を思い、女君にお話にな
る。源氏の深い思いを察しつつ、「忘らるる身をば思はず・・」と歌を読んで
さらりと源氏の胸をつく。
源氏は、位あらたまり権大納言となり、冷遇されていた人々も元の官位を賜り
春が戻る。内裏に上り、帝も三年の間の源氏の不遇に涙しつつ、歌で「今さら
過ぎし年月を恨むな」と語る。
東宮、入道の宮にも久方の対面、そして明石の娘にもお付の者に文を託す。
源氏は、明石の娘をいずれ京に迎えると約したものの、身分故にかくなるも定
めと思いつつ嘆く娘。「それみたことか」と入道をきびしく問い詰め、娘にも
つらく当る母君。乳母ら周囲も入道を非難しあうのに、入道は源氏が懐妊した
娘を忘れる筈も無かろうとは思うものの確信が持てず、修行も上の空で怪我を
し病に臥せる。
初めて読み続けてきた当時の読者は、ここにきてどのように思ったか。やは
り、と明石の娘の境遇に涙したか、それとも源氏は必ず約束を果たすと明るく
確信して読み終えたか。
-古語あれこれ-
先ずは「正身」。[さうじみ]と読むとのこと。現在は全く使われない言葉であ
るが、古語辞典では「[(さうじん)の転か] その人。本人。当人。」とあ
る。手元の漢和辞典や広辞苑には出ていないが、漢和辞典で「正」の字義で、
「まさに、まさしく、ちょうど、たしかに、あたかも」とあることにつながる
のか。明石の巻でもここまでに2箇所見出している。一つは、入道が源氏と対
面して心を許して語りながらも、娘のことは言い出せなかったと、母君と語り
合ったあとに、「当の娘は」と娘のことに著者が話題を転じたところで使われ
ている。今一つは、今回の個所。入道と源氏の最後の語らいで、源氏が娘のこ
とは忘れまいと語り、入道が涙にくれる場面のあとで、著者が当の娘の心境に
転ずるところで使われている。まさに、「当人は」と解するのが最適か。先生
からも「つきはなした表現で、筆者が尊敬する人には使わない言葉」とのご指
摘であった。
今一つ、娘が源氏の歌への返歌で使った「頼める」。[他動詞マ行四段活用]の
「頼む」と区別されて、[他動詞マ行下二段活用]で「頼りになるように思わせ
る。あてにさせる。」とあって、まさにこの時代の男女の仲をピッタリと象徴
する言葉。[四段活用]と[下二段活用]の違いで意味が変わることは、「給ふ」
(四段)と「給ふ」(下二段)で用法が異なることと同様、注意すべきことと理
解した。
平成17年4月9日の例会は小石川植物園のお花見でした
[平成17年3月18日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第8回
「あはれとは月日に添へておぼしませど、・・・」から
「・・・塩焼く煙かすかにたなびきて、とりあつめたる所のさまなり。」ま
で。
とうとう源氏が京に戻ることが公に許されることになる。帝の病も思わしくな
く、弘徽殿の大后も悩みが続くなか、帝は東宮への譲位を決意し、政を行なう
後見役として源氏が適任と考え、京に戻ることを許す旨の宣旨が出される。
ここで直ぐに(素直に)出立することとならないのが、物語というもの。紫の
上への思い深く、娘のもとに通うのを控えて、独り絵を描いては思うことを書
き込み、また紫の上の返歌が書き添えられる工夫がなされる。紫の上も同じよ
うに絵を描き、日記風にご様子を書き込んでおられる。
京に戻る宣旨が届くと、再びこの地に来られないのかと、途絶えることなく娘
のもとに通うようになる。娘に懐妊の徴が現れると、尚更心残りで日一日と出
立を延ばし、郎等どもに顰蹙を買う。
旅立ちも間近という夜は、いつもよりも明るいうちに娘のもとを訪れ、初めて
みやびやかで由緒あり、気品のあるご器量に、いずれ都に迎えようと心に決め
て娘に伝える。
明石の地で源氏を巡る様子と朝廷での帝を取り巻く動きが、対照的に語られる
中で、源氏の紫の上と娘への思いが交互に描かれて、明石の巻の終焉へと向か
う。その間に、入道の悩みと喜びも綴られる。
最後になって、娘の姿を明るいうちに眺めて人品卑しからざる雰囲気を初めて
知るというのも、現代の読者からは「え?」ということになるが、当時男女の
仲を取り結んだのは何だったのか、几帳の外から六条の御息所を偲んだことが
思い出される。
-古語あれこれ-
今回の締めくくりは、明石での娘との最後の逢瀬の場面。ここで、源氏は[男]
と表現されている。因みに、明石の巻のここまでで、源氏と女性3人の呼称を
まとめると、次のように整理できた。
○源氏 [君×8、わが君、源氏の君、さる人、人、源氏、男]
○藤壺の宮 [入道の宮]
○紫の上 [二条の君×2、二条の院、京のこと、恋しき人、やむごとなきか
た]
○明石の娘 [娘×4、女×3、人×2、正身×2、女の童、岡辺、人ざま]
[をとこ]を古語辞典で調べると [(「男君」の略か)愛情関係にある身分の高
い男女のうち男の方をさす]とあって、例文として、まさにここの一文が紹介
されている。著者が、ここで特にこの表現を用いたのは、二人の男女の深い関
係を強く浮かび上がらせようとしたのであろうし、当時の読者もそのように理
解して受けとめたのであろう。
なお、[をんな]についても、辞典に同様の記述があるが(例文として、源氏物
語の野分の巻を引用している)、物語に該当する表現はみられない。上述の事
例で、明石の君を[女]と呼ぶ個所が3回みられるが、特定の場面での表現では
なく、名も無き女性の一般的な表現と理解される。
[平成17年2月4日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第7回
「近き几帳の紐に、筝の琴のひき鳴らされたるも・・・」
から「・・・なだらかにもてなして、憎からぬさまに見えたてまつる。」ま
で。
入道の密かな配慮で娘を訪ねることが出来た源氏に、突然のことで驚いて拒も
うとする娘であったが、結局(ここをどう表現すればいいのか、「とうとう」
「ついに」「やっとのこと」「思いを果たす」など、現代的感覚で言葉を並べ
ても、どうもしっくりしない)結ばれる。しかし、人目を忍ぶことゆえ夜の明
けぬうちに思いを残して分かれる。入道の側も後朝の使いに[ことことしうも
てなさず]対応する。
それからのお訪ねも忍んでのこと。時に控えることがあると、娘も「やはり」
と思い、入道も修行を忘れて気が気ではない。
二條院の紫の上に噂話で耳に入っても、と気が咎める源氏は、日頃の思いを一
段と細やかに記して届けるが、そこにそれとなく匂わせる。紫の上からも歌に
寄せてきびしい文が届き、源氏の足は遠のくが、娘の方はお会いする以前より
も遥かに嘆きが深まり「今ぞまことに身も投げつべきここちする」
いずれ娘の生んだ姫が入内するほどの身分となるというのに、最初の出会いの
何と淡淡としてむしろ冷ややかなことか。かえって、娘を訪ねて几帳の外から
「ほのかなるけはい」で、「伊勢の御息所」を思い出すところが印象に残る。
源氏と紫の上とで交わされる文「われながらこころよりほかなるなほざりごと
にて、うとまれたてまつりしふしぶしを、おもひいづるさへむねいたきに、ま
たあやしうものはかなきゆめをこそみはべりしか」「うらなくもおもひけるか
なちぎりしをまつよりなみはこえじものぞと」も、筆者の筆は冴える。
-古語あれこれ-
百人一首で親しんだ[末の松山波越さじとは]の[松より波]が登場する。そもそ
もは古今集の[君をおきてあだし心をわがもたば末のまつ山浪もこえなむ]が本
歌とか。[松山]は、松島海岸の辺りというが、かなり高い山(丘?)があった
のだろうか。この本歌からは、自らの決意(約束)を述べていると読めて、紫
の上の詰問とも解されよう。
[平成17年1月14日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第6回。
「その年、朝廷に、もののさとししきりて、もの騒がしき
こと多かり。・・・」から「・・・乱れ怨みたまふさま、げにもの思ひ知らむ
人にこそ見せまほしけれ」まで。
源氏が須磨に住まう折、夢に現れて「・・・内裏に奏すべきことあるによりな
む、急ぎ登りぬる」と告げた故院が、雷鳴轟く風雨の夜、朝廷の帝の夢に現れ
てご機嫌悪くお睨みになる。源氏の身の上のことにも触れられたのか。帝は気
に掛かって母后に相談されるが、軽々しく振舞うな、と諌められる。しかし、
帝はお怒りの故院と視線が合ったゆえか目を患い、外祖父の太政大臣もお歳と
はいえこの時期に他界し、母后も患って衰弱されるなど、不幸が続く。それで
も、母后は、源氏を許すことに同意しない。
明石では、源氏が入道に娘を連れてくるよう促すが、娘は相変わらず頑なに考
えを変えようとはしない。とうとう入道は母親にも相談せずに、占いで吉日を
定めて源氏を迎える準備を進める。源氏はお忍びで月夜に娘の元に向かうが、
入江の月を眺めて京の紫の上のもとにこのまま駒を進めたいと歌を詠む。
娘の住む家は、入道の住む家に比べれば地味だが風情ある様子。娘は突然のこ
とに驚くが受け入れようとはしない。近くまで来ているのに拒みつづけるの
は、我が身がやつれているが故に侮っているのか、と源氏は悔しく思う。
都と明石の動きが並行的に叙述される。母后の強気な性格に対比して、帝が
弱々しく描かれるが、このような「人間味溢れる天皇」の姿は、筆者が身近に
見聞きしたことに基づくのであろうか。
娘の元に駒を進める途中で、入江の月影に京の紫の上を思う源氏は、女性の愛
読者にはどのように受けとめられるのか。
-古語あれこれ-
帝の弱気を諌める強気の母后を「弘徽殿の女御」と称するのは、お住まいの名
称から来るが、「弘徽殿」とはどのような由来のある名称か。漢和辞典を引く
と、[弘=ひろい、おおきい]、[徽=よい、うつくしい]とあって、字は難しく
親しみがなかったが、意味を素直に受け止めれば、特異な言葉と考えて詮索す
ることもないのか、と思い至る。
[平成16年12月3日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第5回。
「横さまの罪にあたりて思ひかけぬ世界にただよふも、・・・」から「今さら
に人わろきことをばと、おぼししづめたり。」まで。
入道の来し方の話、娘への思い入れを聞き、源氏はわが身に重ねて感慨深く、
「何故これまで語ってくれなかったのか」と思う。娘のことも風の便りに耳に
しながらも、落ちぶれたこの身には近づくまいと思っていたが、と関心を示
し、入道は嬉しく思って、娘の心境を歌にして申し上げる。
入道は漸く思いが叶ったか、と爽やかな気持ちでいると、早速翌日源氏から娘
への文が届く。入道は喜び勇んでお使いの者を酒肴で歓待し、立派な裳を授け
る。娘は、格が違いすぎると思い返事を差し上げようとはせず、入道が返事を
代筆する。源氏は折り返し、使う紙にも書き様にも一段と心を配って文を送
り、娘もやっと「会ったこともない我が身に、何故それほど心を寄せられるの
か」と歌を差し上げる。
源氏は娘の文に接して京の身分高い女と変わることがないと感心するが、余り
人目に付いてはと数日おいて、時節を話題にして文を送り、やりとりが始ま
る。ますます関心が募るものの出かけることもならず、女房として出仕させて
くれればと願うばかり。娘も自ら動こうとはせず、意地の張り合いが続く。
京の紫の上のことも恋しい思いが深まるが、こっそり明石に呼ぼうかと思いつ
つ体裁を慮って我慢する。
入道と娘と源氏の三者三様の心境が綴られる。一族の栄華を願う入道は、何と
しても娘を源氏に近づけたく、源氏の言葉に即座に反応するが、「一人身の寂
しさは同じこと」と娘の気持ちを歌で語り、返事を書こうとしない娘に代わっ
て、悟りの身で色文を代筆する。源氏は、娘に関心を示しつつ一方京の紫の上
にも思いを抱きながら、いずれにも周囲の体裁に拘って行動に移せない。須磨
から離れる時と同じく、「世間」から注目されている立場を意識した迷いが繰
り返される。
折角の好機ながら、身分の余りの格差を思って、「まだ見ぬ人の聞きかなやま
む」と歌で投げかける娘一人が正常というべきか。
-古語あれこれ-
敬語は難しい。源氏と入道が語り合う場面で、入道に対して「たまふ」と敬語
をつけて源氏は語る。かって、京からわざわざ訪ねてきた頭の中将との語らい
の場面でも、中将に「たまふ」と敬語を使っていたことを思い出す。無官と
なった身を意識しての相手への敬語であろうか。それとも、作者が話者を区別
するために、源氏の言葉には「敬語」を使わせているのか。
今一つ。この「たまふ」には二種類あることにも気づく。一方は、四段活用と
して「尊敬の意を表す敬語」は、古語では頻出する言葉だが、他方、入道が自
身のことに使う「たまふ」は、源氏物語の原文を読み出して初めて知った用
法。下二段活用で、「自己の動作に付けて、話し相手に対しへりくだる意を表
す」とある。
そこで又混乱の生ずる例が出てくる。娘がこの地に長く住んでいることで源氏
が「浦なれたまへらむ人」と述べるところ。ここの「たまへ」は下二段活用と
も解されるが文意にそぐわない。あれこれ考えた挙句、四段活用「たまふ」の
命令形「たまへ」+完了の助動詞「り」の未然形「ら」+推量の助動詞「む」
の連体形「む」、と考えて、前者の用例と理解した。ということで、ここでも
娘に「たまふ」を使っている。
[平成16年11月5日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第4回。
「四月になりぬ。更衣の御装束、御帳の帷など・・・」から
「君も、ものをさまざまおぼし続くるをりからは、うち涙ぐみつつ聞こしめ す。」まで。
春になって、装束や調度などの入れ替えなど、何事につけて入道は懸命にお世
話するのを、源氏はそこまではと思いながらも、入道の人柄から受け入れる。
京からお見舞のたよりも次々と届くようになり、気持ちもゆとりが出来て、眺
められる景色から、住み慣れた京の趣が懐かしく思い出される。
久し振りに琴を取り出して弾くと、周囲の人々も心引かれる。入道も勤行を取
り止めて参上し感激する。源氏も、御殿で帝をはじめ人々から賞賛された往時
の有様を思い出して夢の心地がする。
入道も琵琶、筝の琴などを取り寄せて弾く。延喜の御世の名手から弾き伝えて
三代となることを語り、京では途絶えた技がこの地に弾き継がれていることを
知って興味を深める。「女性の手で弾くのを聞けば素晴らしいこと」と気軽に
口にされるのを、入道は「娘も弾き継いでいることから、是非お召しいただき
たい」と心中喜びを篭めて申し上げる。
酒もすすみ宴もたけなわになる中、入道は問われることもなく明石に住み始め
て以来のこと、勤行のこと、娘のこと、親代々のことなど残りなく語る。大臣
を務めた
親に比べて、田舎に住む我が身、娘を何としても京の高貴の方に嫁がせたい
と、神仏に毎年お祈りを続けてきたと泣き泣き申し上げる。
源氏も我が身に思い合わせて涙ぐむ。
現世を捨てて来世のために祈り続けお勤めに励むのが、出家の身の行いと思う
のだが、ここには娘の身を思いつつ一族の出世を願う親の心情が綴られて、い
つの世に変わることのない「人間」が描かれる。
嵯峨天皇の御世のこと、樂の奏法のこと、秘曲のこと、神仏のことなど、唐土
からの出典も含めて、作者の学の広さに思いが及ぶ。
[平成16年10月15日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第3回。
「浜のさま、げにいと心ことなり。人しげう見ゆるのみな
む。・・・」から「・・・似げなきことかなと思ふに、ただなるよりはものあ
はれなり。」まで。
移り住んだ明石の様子、入道一族の生活の様子が語られる。入道の出自もあっ
て、単なる土地の豪族とは異なる貴族的な雰囲気が、あれこれ綴られる。さす
が齢相応の知識も深く、「古事」など源氏も初めて聞くこともあって、つれづ
れのまぎれに耳を傾ける。
気持ちに余裕が出てきて、源氏も京の人々に手紙を認める。出家して入道と呼
ばれる藤壷の宮にだけは、須磨での恐ろしかった体験、「めづらかにてよみが
へるさま」などを申し上げる。
二条の院紫の上には、届いた文への返事も、思いが募って思うように筆が進ま
ないが、明石に移ったことを伝える。
そんな中、入道は娘のことで悩んでいることを、源氏に時々愚痴を申し上げる
ものの、源氏は現在の身の上を思い、紫の上のことも慮って関心を示そうとは
なさらず、入道は仏神に念じ、母君と嘆き合う。娘本人は、遠くから源氏を見
上げるにつけても、両親の願いは不似合いなことと思いつつも以前よりは心境
が変わっている。
入道の人物描写が、貴族の出であることを語る一方、「まばゆきさまはまさり
ざま」といささか異なる雰囲気も述べられて興味深い。
[平成16年9月3日の講読会から 福田達(とおる)]
明石の巻の第2回。
「やうやう風なほり、雨の脚しめり、星の光も身ゆる
に、・・・」から「・・・飛ぶやうに明石に着きたまひぬ。ただはひわたるほ
どは片時の間といへど、なほあやしきまで見ゆる風の心なり。」まで。
落雷を避けて大炊殿に移り、夜の明けるまでと念じ続ける。これほどの異変に
見舞われても、近くにこの天変地異を占う賢人もいない。「神の助けでこの程
度で済んだ」と語るのを聞いて心細さは募るばかり。疲れてまどろむうちに、
亡き父君が現れて、「住吉の神の導きで、早く船を出してこの浦を立ち去れ」
とのお告げ。「今はこの地で身を捨てる覚悟」と申し上げると「いとあるまじ
きこと、この異変はささやかなることの報いに過ぎぬ」「これより内裏にも奏
すべく京に上る」とのお言葉。「お供に」と申し上げた時にはお姿は見えな
い。
突然小舟が浜に着き、「夢のお告げで舟を用意しましたが、神のお導きか、あ
の異変の中で不思議な風に吹かれて辿り着きました。お心当たりは」との明石
の入道の言上。「父君のお告げの通りか」と源氏が舟に乗ると、飛ぶように明
石に着くのもあやしき風の心か。
父君のお告げとは言え、軽軽しくこの地を去ることで後々の非難はいかがか。
入道の迎えは折角の神のお導き、これに背くは後の世の物笑いか。と迷いつづ
ける源氏の心境が縷縷語られる。
身に降りかかる不幸は過ぎし世の因果かと思うも、何とか救われたいと神仏に
縋る。だが現世の人々の見る目を思うと、神のお告げとは言え素直には従えな
い。神のお告げに、千載一遇のチャンスとばかりに、嵐もものともせずに小舟
を仕立てる入道。いずれも今の世にも通ずる人の生き様か。
何の悩みも無いかのように、「あやしき」土地の人々の姿も添えられる。
-古語あれこれ-
助動詞「まし」のこと。記憶に残る意味は、「今しばし止まざらましか
ば、・・・」とあるように、「事実に反する仮定」と理解していたが、父君の
お告げに対して「今はこの渚に身をや捨てはべりなまし」と源氏が申し上げる
ところで、「はて?」と首を傾げる。先生のご指導で、古語辞典の本文を繙く
と、後段に「上に、「や」「か」「なに」「いかに」などの疑問の意を表す語
を伴って思い迷う気持ちを表す。・・・たものだろう(か)。・・・たらよい
だろう(か)。」と解説してあることに気づく。中途半端な記憶に頼ることな
く、じっくり古語辞典に傾注すべきことと反省する。
今一つ。火事となって仮の御座所となったところを「かたじけなく」と、周り
の人々の「申し訳なく恐れ多いこと」と気持ちが語られているのに、後段で疲
れてまどろみ父君の夢を見るところで、同じ場所を「かたじけなき御座所なれ
ば、ただ寄りゐたまへる」とあるのに、これに「もったいない仮の」とテキス
トに付記されているのは、この場に適さないちぐはぐな注釈であろう
[平成16年7月2日の講読会から 福田達(とおる)]
須磨の巻から明石の巻へ。
「弥生の朔日に出で来たる巳の日,・・・」から「・・・空は墨を
すりたるやうにて、日も暮れにけり。」まで。
頭の中将が都に戻りまた孤独の身となった源氏は、弥生の巳の日、
促されて海辺でお祓いをさせるが、穏やかだった日和が、一天俄か
にかき曇り、笠も間に合わぬ肘笠雨に雷鳴も轟き、お祓いも早々に
皆引き上げる。このようなことは初めてのこと、願の力でいのち落
とさずに済んだか、と皆語り合う。
巻改まって明石の巻に入るも、なお嵐は止まず。雨風の中、二条の
院から文が届き、小止みなく続く雨模様に源氏への思いが綴られ
る。使いの者の語るには、京もまた氷降り、雷鳴る悪天候が続い
て、公の行事も絶えているとか。
潮高く満ち、波音荒く、雷鳴りひらめくこと止まず、住吉の神に大
願を立てたまい、海の竜王、よろづの神に願を立てさせるが、ます
ます激しく、住まいの廊に落雷し、燃え上がる。
これでもかと書き続けられる天変地異は、菅公の怨霊になぞらえた
ものか。源氏が去った都であれば頷けるが、源氏の周りで起こるの
は、孤独な源氏の心境を浮かび上がらせることが狙いであろうか。
舟に乗せて流される人形を見ては我が身を思い、凪ぎわたる海原に
来し方行く先を思って八百よろづの神に思し召しを願う。夢に「何
故宮のお召しに応えぬ」と問われると、海の竜王に見入られたか
と、須磨の住まい堪えがたく思う。
都に戻るのも未だ許されぬ身であれば世の人に許されることもなか
ろうと思い、深山に絶えなんとすれば後の世に軽々しき名を残すか
と思い乱れる。
びしょ濡れの使いの者にまで親しみを感じ、京のことを尋ねようと
お前に召し出でる。
自然現象を具象的に描き続けながら、思い乱れる源氏の心境が綴ら
れる
-物語の構成-
源氏が須磨に赴くのは、弘徽殿、右大臣がたの画策によって、朝廷
の勘気に触れたがゆえ、というのは公知のことと思うのであるが、
どういう訳か、菅原道真などの史実に見られるように地方の官職を
発令することによる公式の「手続き」がなされなかった、というの
がどうしても納得できないことであった。
手元にあるいくつかの源氏物語の解説書を繙くうちに、次のような
解説が目に止まりました。
「かれは追われることを避けて自発的に京都を脱出していくことに
なっていることは注意しなければならない。作者にとっても、読者
にとっても、光源氏は公的に断罪されてはならないのであ
る。・・・・(略)・・・
もし左遷人として追放されてしまったら、当時の史実に照らして明
白のように、光源氏はけっしてふたたび政治家として都に返り咲く
ことはできない。須磨へ、明石へと、かれが流浪していくことが、
将来のかぎりない栄耀のためにかならず通過すべき試練にほかなら
ないとする構想からすれば、光源氏は断罪されてはならない。史実
の例から離脱して、かれのみずから退去するほかないゆえんであ
る。」(秋山虔著 源氏物語 岩波新書)
これには、中国の周公旦東征の故事からきていることを論じた研究
があるとのこと。
[平成16年6月4日の講読会から 福田達(とおる)]
須磨の巻第8回。
「明石の浦は,ただはひわたるほどなれば,良清の朝臣,・・・」
から「・・・名残、いとど悲しうながめ暮らしたまふ。」まで。
いよいよ,次の明石の巻に向けて、新たに明石の入道一族が舞台に
登場する。明石の入道は、今は国守ながら,そもそもの我が身の出
自に自負を持ち,播磨の国の貴人の世界には関心がなく、年に2度
も娘を住吉大社に詣でさせるなど,都に縁ができる機会を願ってい
た。娘も、身の程を弁え,高貴のかたがたは見向きもしないであろ
うとは思いながらも父と同じ気持ちを抱いている。源氏の君が近く
に住まうと知って,入道は千載一遇の機会と思い切った行動をとろ
うとするが、母は謫居の身の源氏には猛反対。
年月が流れて、春を迎えると源氏も都の華やかな集いを思い出して
は、涙ぐむ。一方,都の頭の中将は源氏との友情が忘れがたく、き
びしい指弾を受けることも覚悟して、思い切って須磨の源氏を訪ね
る。源氏も思いもかけぬ来訪に再会を心より喜び、夜を徹して文つ
くりなどして語り合う。
瞬く間に過ぎて暁を迎え、今一度都で再会できることを願いつつ
も,適わぬ望みかと菅公の例も思い浮かべつつ,都に戻る中将と
「はつかなる別れ」を惜しみ悲しみに沈む。
淡淡とした前回とは打って変わって,今回は今後の大きな展開の端
緒を語る。親の代の栄華を忘れえず、折があればと都の華やかな世
界に戻る機会を求める地方住まいの貴人。現実を見据えて地道に歩
むことを受け入れる母親。ともにいつの世にも通ずる心情であろう
が、地方官人の姿を描けるのも、父に従って越の国で暮らした紫式
部の体験が生きているのか。
頭の中将との別れの場面での記述で,意外なことと驚いたことは,
源氏から中将に向かっての挙措振る舞いに,「たてまつる」、「申
したまふ」と謙譲の表現が使われていること。謫居の身であれば源
氏といえども,今をときめく中将にはこのような敬語の使い方が当
然であったのか。
-古語あれこれ-
一語一語の分析が出発点と,一つ一つ古語辞典を引いて意味を把握
することに努めようとしているが,多彩な意味を持つ言葉に出会う
と「さて,どの意味が?」と迷うこと仕切り。そんな折に、テキス
トの漢字表現にも疑問が及ぶ。恐らくそもそもの古文書では,ほと
んど(すべて?)が「かな」で書かれているのではと推察される
が,テキストには随所に漢字が使われている。この漢字表現は,
「源氏物語学」として共通に認知されていることか。例えば,華や
かな都の行事を偲ぶ個所で,「ひととせ」と振り返るが,現在使っ
ているS社のテキストは「一年」と漢字をあてて「ひととせ」と
「かな」を振っている。
「ひととせ」は辞典では,「一年」の意のほかに「過去のある年、
先年」という意味も載せている。後者の「先年」の意であれば、欄
外の注釈とも矛盾しないのに、何故「一年」と本文に書いて,振り
仮名に「ひととせ」と記したのか。因みにI社のテキストは,本文
に「ひととせ」と書き、欄外の注釈には同じ内容を紹介している。
それぞれの「編者」の裁量(解釈)であろうか。
[平成16年5月14日の講読会から 福田達(とおる)]
須磨の巻第7回。
「そのころ,大弐はのぼりける。・・・」から「・・・家にあから
さまにもえ出でざりけり。」まで。
大宰府から京に上る大弐は,須磨に謫居する源氏を知りながらも,
訪ねることをためらい,手紙を送り、息子の筑前の守を遣わすが、
その息子もあわただしく立ち戻る。共に来た娘の一人五節の君は,
是非源氏に会いたいと憧れるが、文を届けて,返事を貰えたのがせ
めてもの慰め。
帝をはじめ都にいる貴人たちは,時とともに懐かしく思って源氏に
文を送っていたが、弘徽殿の大后からきびしい叱正を伝え聞くと途
端に源氏との交流を絶つ。悲しむ東宮を見るにつけて、入道の藤壺
の宮も悲嘆に暮れている。
二条の紫の上も時経ても癒されることはないが,源氏の許から移っ
てきた女房たちはお傍近く使える中で、その人柄に惹かれてゆく。
久しく須磨に住まう源氏も耐えがたくなってきたが,紫の上をここ
に迎えること適わずと思う。土地の者の暮らし様に興を覚えるもの
の,供のものと音曲を囲んでも、王昭君の故事に不吉な思いが広が
り、西に傾く月の光、明け方の千鳥の鳴き声に涙を催す。
今回はニュースバリューのある特別な展開はなく,都も須磨も悲し
みの雰囲気が綴られるが,弘徽殿を巡る権力の怖さに貴人たちの萎
縮した心情が語られる。
-古都でのこと-
先月末高校の同窓会で関西を訪ねたあとに,京都洛北を歩く。深泥
池近く,比叡山の借景で有名な円通寺。鷹が峰の源光庵、常照寺。
大文字の送り火舟形の麓の正伝寺。と,修学旅行生で喧騒の中心街
を離れて、静かな新緑の古都を満喫してきました。最高気温29度
近くの好天の一日でしたが、お寺のお堂に入ると、ひんやりとした
爽やかな風が流れてホッとする。京の建物は、冬の寒さよりも夏の
蒸し暑さを考えて建てられていると聞いてはいたが,初めて「成る
程」と実感してきました。
[平成16年3月12日の講読会から 福田達(とおる)]
須磨の巻第6回。
「尚侍の君は,人笑へにいみじうおぼしくづほるるを,大臣いとか
なしうしたまふ君にて・・・」から和歌「憂しとのみひとへにもの
は思ほえでひだりみぎにもぬるる袖かな」まで。
源氏との係りで謹慎していた朧月夜の君も,父右大臣の計らいで参
内を許され、再び宮仕えに戻る。朱雀帝との語らいの場面で描かれ
る帝の性格は、何と弱々しいことか。母弘徽殿大后の権勢を恐れ
て,先帝の遺言も実現し得ない。
須磨にも秋が訪れ、侘び住まいする源氏の淋しさはいやが上にも募
り,一人夜分に起き出して、琴を弾き歌を詠む。だが,仕えの者た
ちの眠りを妨げたことから,「はっと目覚める」。仕えの者たちは
皆,栄達の望みを捨て家族と別れて源氏について須磨まで来た。口
には出さないが、真情はいかばかりか。自分一人が悲しみに打ちひ
しがれてばかりはおられない。
心を取り直して,昼はお付の者たちと,手習い、絵描き,歌詠み、
と明るく振舞い,親しく時を過ごす。
だが・・夜,月を眺めると,やはり都のことが忘れられず,入道の
君のお言葉を思い出しては涙を流す。「恩賜の御衣は今ここにあ
り」と,故事を引きつつ先帝の面影を偲ぶ。
明治憲法にいう「天皇は神聖にして侵すべからず」からは想像も出
来ないことだが,このように(弱さを表に出した)人間味溢れる帝
のお姿が描かれるとは。紫式部は,内裏でお近くから帝のありのま
まのお姿に接することがあったのであろうか。それとも,「源氏」
のストーリーを際立たせるための式部の創造であろうか。対照的
に,悲しみに沈むだけの源氏ではなく、部下への心遣いも丁寧に語
られる。
-古語あれこれ-
古文を理解するにあたっては,「一語一語の単語の理解」-「各文
章の主語を把握して、文意の理解」-「各場面のストーリーの把
握」と来て、その上で,「文学鑑賞」となるのであろうが,今はと
もかく古語辞典に使い慣れて,一語一語を理解することで精一杯で
ある。
純粋に古語であれば辞典に向かうが、現代でも使われていてしかし
意味の異なる単語が要注意と知りつつ,つい見過ごしてしまい迷路
に入り込む。
今回の範囲でも「さうざうし-心淋しい」「めでたし-素晴らし
い」「なつかし-心引かれる」「ののしる-声高に騒ぐ」「下-心
のうち」「まもる-じっと見つめる」などなど。

[平成16年2月6日の講読会から 福田達(とおる)]
「須磨の巻」に入って5回目。
「やうやう事静まりゆくに、長雨のころになり
て、京のことおぼしやらるるに・・・」から「・・・近き国の御荘の者などもよ
ほさせて、つかうまつるべき由のたまはす。」まで。
侘び住まいでの生活も落ち着くと、分かれた京の人々が恋しく思い出されて、あ
ちこちに手紙を出す。入道の宮、尚侍、大殿の宰相の乳母、二条の院の君、伊勢
の宮、花散里。それぞれにお返り、またそれへの返信で、お互いに歌を伴って率
直な心境が交わされる。添えられたお付きの女房の文に綴られる「あるじ」の挙
措からも、心の内が伝わってくる。遠く離れて、いつまでという見通しのない境
遇に置かれて、それぞれ淋しさ故にか、率直な心境が描かれる。
世間に「露見」することなく過ぎたことに心を許したのか、入道の宮は「あはれ
に恋しうも・・」と語る。御息所には、「ひとふし憂しと思ひきこえし心あやま
り」と悔いて、共に伊勢に行ければと心を寄せる。
悲しみにくれる姫君には、「今は異事に心あわたたしう、行きかかづらふかたも
なく、しめやかにてあるべきものを・・」と述べる源氏には、女性の読者はどう
反応するのか。
朝日新聞新春の連載「私の古代和歌」で、島田修三教授は「古代和歌を読むこと
は、異文化に遭遇する」と同じで、当時の習俗、信仰、深層心理を理解すること
の必要を、「袖を振る」を例題として語っておられるが、まさにこの巻で、御息
所が「罪深き身」と自らを語っていることは、初めて知る驚きであった。
十字軍に見るように、内には博愛を説きつつ、異教はきびしく排撃するキリスト
教に比して、日本では「本地垂迹説」を見るまでもなく、神仏の融合が自然の姿
と理解していたのだが、「隠微」に排撃する深層習俗が形成されてたとは。思い
もかけないことであった。
-古語つれづれ-
これも初めて勉強したこと。
「・・・世にしほじみぬる齢の人だにあり、まして馴れむつびきこえ・・」の
「あり」が、後述の「恋しう思ひきこえたまへる」の意を代行しているという。
英語の「do」が、先行する形で使われているともいえるであろうが、「あり」
を古語辞典で引いてもこのことは読めない。
[平成16年1月9日 講読会 福田達(とおる)]
「須磨の巻」に入って4回目。
和歌「亡きかげやいかが見るらむよそへつつ・・」から、「・・いかで年月を過
ぐさましとおぼしやらる。」まで、が今回の範囲。
父君先帝のお墓にお参りして帰宅してから、都を離れるにあたっての春宮へのご
挨拶を、お付きの王命婦宛に送る。王命婦からは、春宮のご様子とあわせて、感
慨を込めた和歌が届く。宮中においてお仕えするさまざまな階層の人々の、去り
ゆく源氏への哀惜の感慨が語られる。源氏華やかなりし頃、源氏に恩顧を賜った
人々も、権勢を失った今、世を憚って、都を立ち去ろうとする源氏に挨拶に訪う
人がいないことに、源氏の世の人々への思いは深い。
二条の院で紫の上と最後の別れ。源氏に促されて、初めて御簾の外に出て月影に
映えるその美しさ。明け果てぬ前に、都を旅立つ。
須磨について、見慣れぬ風情、家居も珍しくはあるが、心から語り合える友がい
ないことの寂しさ、そして添い続ける紫の上の面影。
いくつかの古典の引用は語られても、あっさりとした須磨への旅の記述は、著者
が須磨に旅したことがあったのかと、会でも話題となる。
「須磨の巻」と名付けられたこの巻も、旅立ちまでの別れの場面に全体の4割を
割いて語られるのも、落魄の身の心情を読者に伝えたかったのであろう。
-古語つれづれ-
古語辞典に辿り着くのに、今一つ頭の転換を求められるのが、いわゆる「仮名遣
い」である。つい、現代仮名遣いで引き始めるが、求める単語が見当たらないこ
とがある。「何でこの言葉がないの?」と苛立つが、そんな折はえてして当時の
仮名遣いを忘れている。気がつきにくい最たるものは「ゐ」と「を」であろう。
そして、今一つが「音便」。
今回も「旅所ともなう、・・」で「伴う」かと思ったがどうしても意味が納得で
きない。ふと「ともなふ」ではなく「ともなう」となっていることに気づく。先
生にお尋ねしたら、「‘ともなく‘の「う音便化」したもの」とのご説明。「な
るほど、そうだったのか」と納得する
[平成15年12月5日の購読会(福田達(トオル)]
「須磨の巻」に入って3回目。
「よろづのことどもしたためさせたまふ。
」から「・・・ありし御面影さやかに見えたまへる。そぞろ寒きほどなり。」ま
で。
前回に続いて別れの場面が続く。尚侍(朧月夜)にも、先方の周りの人々に見つ
からないよう気を使って文を送る。いよいよ出発の前日に、先帝の墓所にお参り
に行く途中、入道の宮(出家していた藤壺の宮)に別れのご挨拶に参上して、
直々に対談し、さまざまな思いが駆け巡る。そして、北山の墓所に参拝。ご恩顧
に思いを馳せ、生前のお姿を偲ぶうちに、「ありし御面影さやかに見えたまへ
る。そぞろ寒きほどなり。」心理学ではどう表現されるのか、余りの悲しみの行
き着くところであろうか。恩顧を受けた方が失脚すれば、不遇を託つのは今も同
じ。
その間に「堅い」話が挿入されている。先ず、不在の間(というよりも、戻って
くるという見通しのない状況で)のもろもろの「殿のこととり行ふ」べき事柄
を、信頼できる人々に分担して定める。資産もすべて西の対(紫の上)にお渡し
になり、「はかばかしき者」と見立てた女房の小納言にお任せになる。そしてお
付きの人々も、(「待ちつけむ」と思うならば)西の対にお仕えするよう勧め
る。
作者が女性でありながら、このような「堅い」「公」の世界の事柄が具体的に縷
縷語られるのも、国守の父を持ったこともあろうが、やはり公的世界にも鋭い感
覚を持ちつづけた紫式部の天性の故であろうか。
古語辞典を繙くのに戸惑うのが、今使われている言葉でありながら、意味が全く
異なるか、別の意味も含まれている言葉。うっかりすると見過ごしてしまい、文
意に辿り着けないことになる。
「よろづのことどもしたためさせたまふ」の「したたむ」は、手元の古語辞典で
は、5つある語意のうち「書き記す」は第5番目、「整理する、支配する、用意
する、食べる」と今では使われない語意が並んでいる。
「あやしの山賎めきてもてなしたまふ」の「もてなす」も、辞典では「執り行
う、ふるまう、取り扱う、もてはやす」と続いて、最後に「ごちそうする」が出
てくる。
[平成15年11月7日の講読会(福田達(トオル)]
「須磨の巻」に入って2回目。
「若君の御乳母の宰相の君して、・・・」から
「・・・明けぐれのほどに出でたまひぬ。」まで。
お忍びで亡き正妻葵の方の実家にご挨拶に伺う。帰ろうとする頃に、北の方から
文が届き、乳母を通じて挨拶を交わす。二条の御殿に戻って、紫の方と、旅立ち
を前にしてしみじみとした語り合い。弟の帥の宮、三位の中将も訪ね来て対面。
そして、ここで又花散里の方を訪ねて、別れの挨拶。
ということで、須磨に旅立つ前の源氏と源氏を巡る人々との別れの場面が続く。
これからの筋立てを知っていればこそ、物語の展開も「客観的に」たんたんと読
み進むことになるが、物語の登場人物たちにとっては(当時初めて接する読者に
も)、源氏自身も、都に残る人々にとっても、「この先どうなるのか」「果たし
て、再び会うことがありうるのか」という深い不安と悲しみの心境であったこと
であろう。それゆえに、「これでもか、これでもか」と悲しい別れの場面が続
く。
今でこそ、JRの快速電車で1時間、100キロに及ばない距離だが、当時の
人々には「遥かな異郷の地」、我々には想像を越える心境であったろうと推測す
るほかはない。
華やかなりし頃に往き来していた人々も、表面的な付き合いの人は、失脚した源
氏には距離を置くようになるのも、これまた今と変わることのない心情か。
ここでも「花散里」が大きな存在として描かれているのも、将来への伏線か、源
氏の心に大きな存在となっているのも興味深いところ。
ところで、田中先生のご指導の下、原文を読むようになって早いもので1年半。
原文講読の第1歩である古語辞典で一語一語確かめることは、何とか軌道に乗っ
てきました。往時の受験文法がいまだ錆付いていないことを嬉しく思っています
が、ただ単語そのものに馴染めない(新発見の)言葉があることを知り、これに
はともかく幅広く読むほかはないと覚悟しています。
先日の講読会で読んだ「よのひとのおもへるよせおもくて」(賢木の巻)で、
「よせ(寄せ)」も初めて知った言葉でした。
[平成15年10月3日の講読会から 福田達(トオル)]
今回から「須磨の巻」に入る。
都を離れるに先立って、亡くなった正妻葵の上の
実家をお忍びで訪れる。帰り際のお言葉「・・さしも急がで隔てしよなどのたま
へば、ものも聞こえず泣く。」まで。
葵の上の父上致仕の大臣、兄上三位の中将らと御酒を交わしながらの語らいが続
くが、夜もふけると女房たちをお前に召してお話などさせる。そして、「人皆静
まりぬるに、とりわきてかたらひたまふ」
繋がりの解説も無いままに、場面がパッ、パッと切り替わる。葵の上の実家の邸
宅で、葵の上づきの女房一人と夜を過ごし、別れ際に独り言のように心情を吐露
して屋敷を離れる。葵の上の身内の人々には、「公認」のことだったのか。ここ
もまた、現代の「常識」でははかることのできない情景が自然なこととして進展
する。
ところで、源氏物語とは大学入試で取り上げられて完敗の苦い思い出。これまで
は解説書を読み漁るだけで、なかなか原文に立ち向かえなかったのを、フリーに
なって一念発起読もうと思い立つが、この際と、英、独、仏、露訳と合わせ読も
うと神田を歩いて訳文を買い求めた。英訳をベースにすれば何とか原文に近づけ
るのではと考えたのと、独、仏訳は特に時制の勉強を狙い、露訳は初歩から勉強
しようと考えその意味で、恐らく過去を振り返る記述が多用されるであろうと、
「須磨の巻」から読み始めることとした。だが・・・肝腎の英訳で壁に突き当
たった。
[Royall Tyler]訳の「Suma」の巻冒頭の記述
He faced mounting unpleasantness in a hostile world, and he knew that to
ignore it might well provoke still worse.
特別に難しい単語は無いのに文意が伝わらない。文学的表現を甘く見たと反省。
「さて・・」と思っていたところで、田中先生の講読会を知人の方からご紹介い
ただく。入学して1年半、ここまでの流れを理解してここの文章に来ると「成る
程」と溝が埋まる。
やはり、先生のご指導の下で、原文に真正面から取り組むのが正道と「学問に王
道なし」と実感しています。
<こののち福田さんからよせられた質問>
ところで、ここまでは「書いては」と思って控えたことがあります。
葵の上の実家で、大臣や三位の中将も交えてのお酒のあと、次の場面には「人々
御前にさぶらはせたまひて、・・」と源氏の主体的意思を表現していますが、そ
の次の中納言の君との場面には「人皆しずまりぬるに、とりわきて・・」とあっ
て、推移のプロセスが語られていません。
多数の「女」の居る場面から、一人の女性との場面に移るとき、どのような「意
思表示」があったのか。興味がそそられます。女性たちが退いたあとに、中納言
の君だけが居残るのはその場に居合わせたみんなが当然のこととして理解してい
たのか。
それも、正妻の実家において・・
余りに現代の常識とは異なる男女の間柄に、想像を越えた世界の存在があるよう
です。
<私の答え>
こういう場面をとても奇異な特別のものと思ってる節があるようですが
ごく自然に好き合った男女間の別れの光景がえがかれているとおもう。
日頃情けをかけている中納言の悲痛な表情を「人知れずあわれ」とだれにもさとられず目に留め中納言の存在を
気にしつつ人々とはわかれを惜しんでる。
この場合他の人々はふたりのことを知りません。だからこそ「人皆しづまりぬる」時
でないとあえないのです。
そういう源氏をイメージしなくては。
それが源氏の主体的意意思であり「人々」から一人にうつるプロセスです
<諏訪さんの意見>
あの福田さんが男女の世界に一歩足を
踏み入れたかと(?)驚きです
年上の方にこんな言い方は失礼ですね
福田さんの考え方は
私にもよくわかります 普通の人達は(私達)
一般常識の世界に生きているから
源氏を読んでいても ついやだ-とか
また とかそんな目で思い感じてしまうのですね
先生がよく これからの2時間は俗世を離れて
平安時代にどっぷり浸かってくださいと
言いますよね それなんですよね
自分でもよくわかります 理解度が足りません
福田さんがおっしゃったように原文にふれ
読んで理解するしかないのですよね
私は日本語一筋でいきます
[平成15年7月4日の講読会から 福田達(トオル)]
賢木の巻で前回の続き「二日ばかりありて、中将まけわざしたまへり。ことごと
しうはあらで、なまめきたる檜破籠ども、賭物などさまざまにて・・」から、巻
の終わりまで進む。
前の巻「葵」で正妻葵の上が亡くなり、この巻に入って父上の桐壺院の崩御、藤
壺の宮が突然の出家、と続き、世は朱雀帝の母方右大臣側が権勢を縦にする中
で、源氏は失意のどん底にある。葵の上の兄で親友の頭の中将が慰めに訪ねてき
て、気の置けない催しが開かれる。
後段は場面が変わって、体調を崩して宿下がりをしていた朧月夜に、好機再来と
ばかりに文を交わし、機会を捉えて寝所に忍び込む。この場面を、朧月夜の父右
大臣に見つかってしまう。これが、やがて源氏失脚への伏線となってゆく。
開放的な当時の建物であったが故に可能で合ったのであろうが、しかし源氏も朧
月夜も何と大胆な行動をとったことか。見つかることを覚悟していたのか、よも
や見つかるまいと高を括っていたのが思わぬ激しい俄雨で算段が狂ったのか。作
者は何も語らない。
だが、それよりも、帝の寵愛を受けている公職の「尚侍」の君を相手にすると
は、戦前の感覚でゆけば「不敬罪」にも相当する行為ではないかと思うのだが、
この当時は朝廷を包む雰囲気は、われわれの想像以上に「おおらか」だったので
あろうか。
若狭の中世史を記述した「海の国の中世」(網野善彦著、平凡社ライブラリー)を
読んでも、あの地の権益を巡って朝廷、公家、寺社、幕府入り混じっての争いが
続くが、そこでも天皇家や上皇家も権力者の一つでしかないことを教えられる。
「天皇は万世一系」とはいえ、決して絶対的権威ではなかったということでしょ
うか
[平成15年6月6日の講読会から 福田達]
賢木の巻の終わり近く、「故院の御子たちは、昔の御ありさまをおぼしいずる
に、いとどあはれに悲しうおぼされて、・・」から「・・・と、めできこゆ。つ
ひに右負けにけり。」までが、本日の勉強した範囲。
これまで源氏物語を一度も原文で読んだことのない人間が生意気にも講読会に参
加させていただき、最初の会で接した葵の巻の文章は全く理解に程遠いものでし
た。
今回で12回目、先生のご指導のお蔭で、古語辞典を引きながら何とか原文を辿
り、予習をしてゆくことができるようになりました。それでも、登場人物のこれ
までの経緯、時代の背景、舞台の設定などに考え及ぶ余裕は全くなく、先生のご
説明で「成る程そうだったのか」と思い当たることしきりです。
源氏と藤壺の対話の場面で、どちらが話しているのかも分からず、「敬語表現で
判断すること」とのご指摘で、あらためて古文における「敬語」の持つ意味(高
校の授業で習ったのだろうか)を知りました。
出家した直後の藤壺と源氏の二人の場面は、交わす言葉も少なく、作者は聴覚、
視覚、嗅覚に訴えて情景描写を進める。具象的な表現は理解も困難ではないが、
例えばよく使われる「あはれ」とはどのような感情であろうか。
機械が発する人工音、夜間の闇を奪う人工照明、そしてやはり人工的に生み出さ
れる異臭、そんな世界に生きている人間に、古文に登場する人々の心の襞を思い
描くことは、果たして可能なのだろうか。
かって、ドイツ文学ヘッセの講読会の席上、先生に「抽象的な言葉の翻訳という
ことは、可能なのでしょうか」と不躾な質問を投げかけたことを思い出してい
る。
TOP ページ
[読書会一覧に戻る]
|