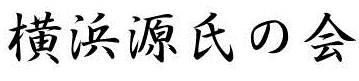
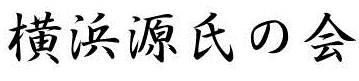

東京都練馬区で、すでに田中順子先生の源氏物語を読む会の「すずしろの会」に入っていたので、横浜に引越したことを期に、横浜でも同じような会を作ろうと思いました。と、いっても知っている人もいず・・
夫を誘って大倉山記念館を会場に、月に一度、「横浜源氏の会」を立ちあげました。その後、知人、友人を誘い「神奈川新聞」に告知を出すなどして、少しずつ 会員をふやしていきました。まだまだ出発し たばかりですが、今後とも源氏物語の原文である古語を読でいくことによって、日本語と日本文化の豊かさにふれていきたいと思います。同好の志をいささかでも
ふやしながら・・・。
横浜源氏の会
tokubetukouza yuhukaho
光源氏が、車中から五条辺りの市井をのぞき見し、物珍しく思っているのが、家の描写や、女性たちへの言及によって生き生きと語られる。
もっとも「をかしき額つきの透き影」が女性たちを指しているとは、先生の説明を拝読しなければ理解できないことだけれど。
女性たちをまるで異星人のように感じているくだりには、笑ってしまうが、内裏の外の世界は、光源氏にとってそれほど隔たりのあるものなのかもしれない。
未知なるものへの好奇心の一方で、初めて見る夕顔の花のはかなさに心打たれたり、みすぼらしい家を見て無常観を覚えたり、乳母に対する細やかな心遣いだったり、光源氏ってこんな感じの人だったのね。と思ったりもしました。
源氏物語を原文で読むなんて学生以来のことなので、頭がとても疲れた一日でしたが、本を読みこんでいる皆さんのお話を聞いて、純粋に物語を楽しむのが大事と感じました。
(翔子)
何よりもまず、参加された方々の情熱と田中先生のエネルギーに圧倒されました。
並々ならぬ、否、桁外れの源氏愛!
怖ろしいほどの熱量、それは純粋にして真摯な眼差しとなり「夕顔」に注がれていきます。
あっという間に2時間が過ぎ、昼食。
午後も時が瞬時に飛翔していきました。
原文では「病気見舞」の段がとても印象的です。
源氏と大弐の乳母との、心の底からの真実の対話が、周囲の人々の胸を打ち、涙を誘います。
見舞いに訪れた源氏に感泣し、あれこれ述べ立てる乳母。
老いたる母のその姿に醜さや体裁の悪さを見る(成長した)子供たち。
しかし、源氏は乳母の外見や振舞いではなく、幼少の頃から受けたひとかたなる愛情への感謝を述べ、自らも乳母を深く愛していることを語ります。
このやり取りは、単に物語を面白くするための叙述ではなく、人間の心理の一面を見事に描き出していると感じます。
子供たちの心理は、現在でも私たちが年老いた親に感じる羞恥・侮蔑である一方、源氏の思いはそうした表面的なものを度外視したいちずな愛情に満ちています。
源氏の色好みの根底には、こうした人間に対する深い愛情があることが暗示されているようにも感じられます。
読めば読むほど、深遠でしかも繊細な世界。
感嘆せざるを得ません。
(サッシカイア)
横浜源氏の会に入会したときに「夕顔」のあたりをやっていたと思います。
当時はよく分からないまま過ぎてしまいましたが、今回改めて読む機会となり、以前よりもよく理解できるようになっていると感じます。
これからの物語の展開に期待しております。
(磯山)
源氏物語については初心の者ですが、ゆふがほの会で学びを深めていきたいと思っております。
(粟田)
夕顔との出会い、の前段の部分を読みました。
乳母(惟光のお母さん)とその家族のちょっとコミカルな描写(病気なのに笑)と、夕顔との出会いを予感させるステキな大人な香りのする部分のコントラストが面白かったです。
それにしても扇子に歌書くって凄くおしゃれですよね。
あと個人的にはこの後の六条御息所が気になります。。。
emi
順子先生のもとで夕顔を読むのは二度目。
「切掛だつものに?惟光の朝臣、奉らす」の間に書かれていること、まーんまこの帖のエッセンスじゃないかと思います。
むさ苦しい下町の、みすぼらしい家にありながら、美しく咲く花は夕顔その人であり、その運命は口惜しきものと源氏が言う。惟光が花を源氏に取り次ぐあたりにも、面白みがありました。
何度読んでも、新しい疑問が生まれ、また新しい発見があって楽しすぎるのです。
ぴ
宮中、六条とは町並みも暮らす人々も違う五条で出会う女君。
惟光が鍵を探している時間に車中から見る光景。上げわたしてある半蔀、白い簾、そして「おのれひとり笑の眉ひらけたる」様に咲く白い花。夏の夕暮れの様子が目に浮かぶ。「遠方人に物申す」と言っただけで「かの白く咲けるを」と返す随身とのやり取りは風情があるなと感心。
わずらう乳母を見舞った源氏が涙を拭った際に袖から立ちのぼる香り、夕顔の花が載せてあった扇から漂う移香と「香り」の描写が人物表現に功を奏している。
そしてまだ見ぬ女君からの「心あてに」の歌。その返歌を持って行った随身は応対を無礼に感じ返事を待たずに戻ってきてしまった。様々な偶然、必然から起こる出来事が織りなす「夕顔」の巻。今後どのように展開していくのだろう。
take
令和2年12月3日 14時~16時
場所 川崎総合自治会館会議室(武蔵小杉の新しい会場)
読書箇所 「葵の巻」 「海士のうけ」「大殿のもののけ」
「御息所は、ものおぼし乱るること、年ごろよりも多く添ひにけり。~はかなかりし車の所あらそひに、人の御心の動きにけるを、かの殿には、さまでもおぼし寄らざりけり」
参加 青景、内田、箕輪、粟田、豊嶋、磯山、下川 7名
会員の感想
ここでは時を遡り、車争いにいたる御息所の内面の懊悩が描かれています。注目すべきは、源氏の言葉。
ヘリ下り、卑屈さを滲ませながらも関係の継続を願う姿勢には、二人の愛の熱量の相違が、じつに巧みに示されています。
複雑微妙な心理の綾を簡潔に表現してゆく。――何という離れ業!
この心理描写は、次の「大殿のもののけ」後段につながっていきます。
(サッシカイア)
葵の上が物の怪にとりつかれる様子が、実にリアルに書かれていて、思わず現代にも書かれた霊の世界の話を思い出した。佐藤愛子の「私の遺言」だ。実に面白く興味深い本だ。
病気が悪霊によって生じるという考え方は、近代の医学の発達以前は、洋の東西を問わず人々に信じられていた。日本では僧による加持祈祷、西欧ではそれぞれの地域に占い士がいたようです。おそらく、キリストの病人を直す術も、この延長線上にあって、悪霊を身体の中から追い出す様子が描かれている箇所もある。源氏もさすがに物の怪の動きや特徴はよく承知していて、ここの葵の上の場合はおそらく若すぎてその知識を発揮できなかったようだが、後に一度死んだ紫の上を蘇らせている。
貴族が病気を治す方法は、効験のあると言われる僧たちを呼んで、祈祷させることだった。護摩壇で護摩を焚く参考書の回覧もあった。
(TK)
横浜源氏の会
令和2年11月5日 14時~16時
場所 戸塚男女共同参画センター会議室
読書箇所 「葵の巻」 「千尋の御髪」~「典侍」
参加 10名
感想
幼児と大人の中間の少女姫(紫)に魅了される源氏。
童たちの髪を(毛先)を切り揃えさせる場面には、少女期の美しさが凝縮されています。ウラジミール・ナボコフ「ロリータ」が現れるのは、約千年後。
作者紫式部の観察眼・想像力には、毎度のことながら敬服せざるを得ません。
(サッシカイア)
今日の読後、先生から感想を聞かれて、思わず「難しい」と答えてしまった。
源氏物語の難しさは、何だろう。
まず、古語の難しさがある。同じ日本語だから、現代でも使われる単語なので、類推するが全然違った意味でつかわれている言葉がたくさんある。
「いとおしい」よくつかわれる古語で、「気の毒だ、いたわしい」という意味の他に、「困ったことだ」という意味にもなる時がある。
それでこの「いとおしい」との言葉が出て来た時、「誰が、誰をいとおしい」と思っているのかその都度、探さなければならない。「いとおしい」がどちらを向いているのか読み込まなければならない。この「誰が、誰を」はほとんどの場合、書かれていない。いないのではなく、省略されています。これが古文の大きな特徴です。そういう文章の動きです。それを文脈から読み当てなければならない。
この日本語の特徴は、学校では習わない(少なくとも私は習っていない)。しかし現代でも通じている文法なので、試しに、自分が書いた文章の、主語を全部削っても意味が分かる。それも、奇妙に日本語的な文章になっている。日本語の一大特徴なのだ。この省略こそ日本的な文章なのである。
(TK)
令和2年1月23日(木) 会場:大船のマンション会議室
出席者(敬称略)下川」、青景、米納、磯山、箕輪、内田、佐藤、粟田、小澤 9名
読書範囲 P26『車争い』
参加者感想
1
最初先生は「葵」ではここをしっかり読まないと先へ続かないのですとおっしゃってどういうわけで左大臣家は御禊の日を迎えたのか。
左大臣家では女房たちや大宮の希望で行列を見物に行くことは名誉なことであり、全国津々浦々から美しい行列を見物に出かけて来るのです。日たけゆきて、日が昇って太陽が動いて時間を表している。前日から準備しているのに葵の上の気分の状態で少し出遅れてしまった。一条大路は賑わいを増して牛車でいっぱいにいい場所がなく斎宮の母御息所も忍んで出かけていた。それには理由(わけ)があります。葵の上、六条御息所は立場が違います。あえて高貴な身分なのにやつれて身分を落としている牛車と第一級の美しさ色あいの上品な牛車。汗衫(かざみ) 子どもの正装もいた。葵の上の供人車副を払いのけ、両車は場所取りの争いになった。祭りなので酔った供人もたちの勢いで騒ぎになった。
左大臣家の中にも源氏の御方もいて争いになったが御息所にも同情し少しそーつとしておこうというやさしさも伺える。
車ども立つ(車を止める)。ひとだまひ(女房とか随行者)が乗っている車御息所の車は何も見えないところへ押しやられてしまった。忍んで出かけたのに知られてしまったのは残念。車は壊されてしまい、悔しくて自分は何のために出かけてきたのかと自分をせめる。
出るに出られず、帰るに帰れずしているうちに行列が近づいている。
晴れの日の源氏(つめたい人)をひとめ見たい一心。待たるるも心弱し。女心は弱いと語り手の女房。源氏は知らん顔で通り過ぎて行く。振り向いてもくれない。
しかし着飾った女どもへは、ちらりみてほほえむ。横目を視線をなげてリラックスしています。北の方(葵の上)には敬意をはらい気をつかっています。御息所としては権力に圧倒されて自分はこの世になきものとして涙もこぼれ無念の思いが沈み、しかし一番の晴れがましい日に美しい源氏の姿を遠くから見れただけでも。
車争いの罵倒が飛び交う中、源氏の想いをたち切れない自分がいる。
六条御息所はどろどろとした情念の人であった。 祥
PS: 講座終了後 令和二年の楽しい昼食懇親の新年会。源氏・萬葉集のおはなしなどで盛り上がりました。
2
実にじつにドラマティックな箇所。
牛車の停車場所をめぐる下々の者たちの争い─暴力的な衝突、暴言─と
御息所の受けた屈辱・精神的打撃が劇的に描かれています。
人を愛することがおとぎ話ではないこと。
時に怒りや悲しみや様々な困難を伴うことが、出来事を通じて陰影深く
示されています。深い!
この「車争い」の段だけでも『源氏物語』が小説であることが
誰でも判るはず。そう思います。(サイカイア)
以上
令和元年
12 月 5 日(木)
会場:大船 のマンション会議室
出席者(敬称略)
内田、青景、
米納、 佐藤、磯山、粟田、小澤、渡 8 名
読書範囲
P18 24
大殿には、かくのみ定めなき 御心を、心づきなしとおぼせど、・・・・
・・・・・・
にわかにめぐらし仰せたまいて、見たまふ。
参加者
感想
1
桐壷帝と弘徽殿の女御との間に生まれた女三の宮が、斎院に選ばれた。
二人の間の娘として共にとても大切に育ててきた。我が娘が神に支える身になることを
表面的にはうれしい反面、別の世界に生きることにもなる。
二人は「いと苦しうおぼしたれど」と
、 心中 、 おだやかな ら ざる と 、 表現される。
我が子三の宮に対する親の愛が書かれることで
、 はじめて夫婦としての二人の愛情が 感じ
られた一コマだった。(孝)
2
葵の上は源氏の噂を知って、不愉快になるが、
ま た かと心の中では思うが、云っても仕方
がない。 深 く 恨んだりしない。 北の方は騒いだりしない。 この時代は今と違って通い婚で
夫婦関係が保たれている。
そんな時
正妻葵の上が懐妊。左大臣家では喜びもひとしお、嬉しいのだが出産は危険を伴
うことは昔も 今も命がけなのです。安産の祈願がなされた。 北の方は気分もすぐれず、病
気 悪阻 体の異変 になり心細げ、不安そうな姿をみて、源氏は珍しく妻をいとおしく心
が動いたが、 10 年目の懐妊なのに心が落ち着かない。何故でしょうか?御息所のことが気
になるがそんな場合ではないでしょう。葵の上を守らなければならないでしょうに。
少し源氏のおかれた状態
もわかるような気がするが「とだえ 多 か る べし」 で良かったと思
う。 御禊の日 弘徽殿の 女三の宮が新斎宮に、賀茂祭の行列に立たれ、源氏も参列。人々は
行列を楽しみにしています。選ばれた人 々の衣装の美しさ、馬鞍など新しく、特に女房た
ちの袖口の美しさ、物見車や桟敷の装飾に余念がない。
当日になっても気分がすぐれず行列を見に行くことができない葵の上でしたが、大将殿や
大宮 母君 を説得した女房たちは物見車や人々で賑やかな一条の大路へ 出 か け る こ と に な
った。美 しい源氏をみる た め に 。 祥
2019年11月7日(木)12:30-14:30
於:大船のマンション会議室
出席者(敬称略)
(10名)
読書範囲: 葵
世の中かはりてのち、よろづもの憂くおぼされ ・・・
・・・
君も、なほことなりとおぼしわたる。
参加者感想(順不同)
葵 御代替わり
はじめに先生より葵の巻はむづかしいとのお話でした。桐壺帝から朱雀帝へ御代が変わったのに源氏は憂鬱な日々を過ごしています。そんなとき春宮の後見人として嬉しく思う。また六条御息所も姫君が伊勢の斎宮になられるので、桐壺院は普通の扱いではなく真摯に受けとめて、丁寧に接するようにお話になった。しかし源氏はそんなこと微塵にも思わなかった。
それはどうしてか、年上だから、気位が高いからな―と。そして朝顔の姫君が登場する。式部卿宮の姫君(源氏とは従姉になる)源氏がお手紙をしてもお返事しない姫君、心づかいがあり、源氏は諦めないのです。
(祥)
今日ばかりは感想を書きたいと思いつつ、文章が難しくなるに、ひけてしまう。
院に諌められて源氏は恐縮しつつも、心はいつも藤壺から離れられない。これからはどう展開していくのか。
(Y)
「御代替わり」
短い叙述のなかで歳月の移り変わり、天皇の代替わりが示され、藤壺の境遇の変化、弘徽殿の現状など、新たな物語を取り巻く状況が明確に設定、提示さています。
後見人のいない春宮の立場、それを支える唯一の支援者となった源氏の複雑な心境。文章の構造はいっそう難しくなり、ここから始まるストーリーの展開に胸がときめきます。
(サッシカイア)
初めの段は難しかった。前の巻から2年は経過している。作者は新しい現状を、あれこれ説明する。それを主語(主体)を書かずにつらねてゆくので、読者は戸惑うのである。つまりこの文章は、誰のことを書いているのか、誰がそう思っているのか、その都度推定しなければならない。文章の調子や全体の流れからあるいは敬語の使い方から推し量るしかない。それが源氏を難しくしている。書かれていない部分を、括弧で補ってみる。
御代が変わって、(源氏は)よろずにもの憂く思い、自身の昇進もあって、軽々しく忍び歩きもできなくなり、(あちこちの源氏の女たちが)、源氏の足が遠のいていて嘆いている、一方で(源氏自身は)藤壺への思慕を断ち切れないでいた。
(藤壺の中宮は)(桐壺院)が夫婦のように側に付き添っているので、かえって忙しく それで弘徽殿女御は気分を害して内裏にばかりいるので、(藤壺は)張り合う人もいないので、心安くしており、一方(桐壺院は)折々に管弦の遊びなどを好み、世間の評判になるほどで、今の立場が気に入っているようであった。ただ、(桐壺院)は(内裏にいる)春宮を恋しく思い、後見がないので気にかかっていて、大将の君(源氏)にあれこれと指図する、(源氏は)いたたまれない気持ちになりながらも、嬉しく思うのだった。
(TK)
2019年10月3日(木)12:30-14:30
於:大船のマンション会議室
出席者(敬称略)
(10名)
読書範囲: 花宴
桜の唐の綺の御直衣、・・・
・・・
と言う声、ただそれなり。いとうれしきものから。
(この巻おわり)
参加者感想(順不同)
「藤の宴」後段
遅れて登場する源氏。その装いの何と華麗なこと!
そうして、朧月夜をもとめ、姫たちの所へと突き進んでゆく恋の亡者。
最終部、歌を交し合う場面は艶麗なる情念の炸裂!
ラベルの「ボレロ」のフィナーレのよう。
(サッシカイア)
目で見て物事を確かめるのが今時。監視カメラがあって事件とか世のものひとが判明するということに比べ、「花宴」では香をたきしめた部屋の匂いであったり、人の動きによって、着物のすれあう布(きぬ)ずれの音、ここでは音なひと表現される。このように五感をフル活動させて事が運ばれてゆく様は千年後の今も感覚として伝わる重要な要素かも。千年後に監視カメラでは、思いは伝わらないかも・・・。
(孝)
花宴もあと数ページで終る。短い巻で、もう少し長くてもよかったと思うのは私だけだろうか。三島由紀夫がすきな巻だとなんとなくわかるような気がした。そして藤宴にでかける。衣装が桜襲の唐の綺の御直衣、直衣は日常着、唐の上等で色彩華やかで、ほかの人はうへきぬ、礼服の私的な行事で一段さげる「さしぬき」下のズボンがすぼまっているのが非常になまめきかく繊細で美しい。いと異なり、特別な衣装であった。源氏も物語の色(太陽別冊)を繙き、さらに感動しました。親王らしい姿で右大臣邸の人々を驚かせた。美しい源氏は藤の花も―けおされて。管弦の遊びも終わりお酒に酔ってしまった。ほろ酔い気分ではない。寝殿には女一の宮、女三の宮がおいでになる。藤の花は寝殿の端にあり、女房たちが出て来て袖口など出している様子が少し下品に見える。そこで藤壺わたり― 藤壺の心づかいや態度で上品で慎み深く思うのであった。気分が悪いので女房たちに同情を請(乞)うが女房たちは簡単にやりかわされてしまう。香も下品で衣の音も下品で好ましくない。女房たちの質も女君も同じようだ。源氏は一人の姫君に声をかけ「扇を取られてからきめを見る」と催馬楽の一節を歌で詠み、帳越しに手をとらえて女を探し求めてきた、と心の内を明かす。女も「心いるかたなら― と返歌。深く心に月の夜にも迷うはずがないのにあなた薄情な人ですね。声を聞けば誰だかわかる。それは有明の女だといとうれしきものから、と花宴は終えた。さて有明の君をもっと掘りさげてみたい。これから源氏の関わりがどのような変化していくのか。葵の上、藤壺、空蝉、夕顔、末摘花、若紫の姫君、源典侍身分や立場の恋愛と重ねて少し振り返ってみたいと思います。
(祥)
花宴は今日でおわり。最後は、いるかどうか分からない女に向かって源氏が呼びかけた歌に、ほの暗いなかから返歌があって、
心いるかたならませばゆみはりの
月なきそらにまよはましやは
と言う声、ただそれなり。いとうれしきものから。(標準本のおわり)
かろかろしとてやみにけるとや。(大沢本)
先生から資料が紹介され、源氏物語・大沢本というのがあって、「花宴」の最後が、その本では上のように書き足しがあってそれが抹消されているそうだ。たいへん面白いと思った。真実は分からないが、ありうると思った。
藤原俊成が「・・・ことに最後の結句の余韻嫋々たる趣は朧々として幽玄の趣をたたえる」とあるのは、いかにもほめ過ぎだが(大人のほめすぎ)、仮に女房たちが姫君に読み聞かせするために書かれたとすれば、子供に(嫋々たる)余韻を感じさせるのは難しく、突然終ってしまったとの印象を与えかねないので、付け加えたのだろうと想像される。しかしそれも意に満たず抹消したと考えられる。俊成はもちろん現代のわたしたちのように、大人の読み物として読んだろう。
(TK)
2019年9月5日(木)12:30-14:30
於:大船のマンション会議室
出席者(敬称略)
(7名)
読書範囲: 花宴
大殿には、例の、ふとも対面したまはず。
・・・
待たれてぞわたりたまふ。
参加者感想(順不同)
今日も原文でしか読み取れない箇所が、いくつかあった。右大臣邸での藤の宴。上達部や親王たちが右大臣の権勢をおもんばかって、はせ参じたのかと思いきや、原文には
「親王たち多くつどへたまひて・・・」つどひたまいてではなく、つどへとあることによって、右大臣側が、本気でかき集めた様子がよみとれた。
(たか)
弓の結に集められ、新しく造られた殿をみがきしつらわれた所へ、左大臣のむこの源氏の君が、これ以上の装いがないという姿で、待ち人が首を長くしている所に出かけてくる。この場面、人の顔、表情の動きを自分で思い描いてみる・・・。
(Y)
「しるしの扇」後段
左大臣と源氏とのやり取りが中心ですが、さり気なく置かれている催馬楽「貫河」の一節が非常に効果的です。
情愛を素直に表明し合う「貫河」。
そこには、源氏が求めても得られない夫婦愛の理想が込められています。
同時に、原作が書かれた千年前から現在まで、変わることのない男女の愛の本質が示されているようにも思われます。
(サッシカイア)
最初の方の音読について先生が褒めてくださったのにはだんだん慣れてきたように思い、ちょっと嬉しく思いました。8年前にはじまった時何回も読み声を出して臨んだことを思い出しました。
左大臣邸でも北の方(葵の上)とうちとけず例のいつものように、ふとも、すぐ逢ってもらえず源氏はひとり残されてしまう。つれづれと源氏はやることがないのでボーとして十三弦を弾きながら「やわらかに寝る夜はなくて」催馬楽の一句。なんとさびしいことだろう。催馬楽の歌、労働の歌、民衆の歌、民謡、田植歌、男女の歌、ラブ夫婦の歌、源氏が歌っているのが何ともステキ!源氏物語は民衆の声も貴族に届けている。折角お帰りになったのだから暖かくお迎えすればよいのに。お互いに歩み寄らなければ―。
左大臣も源氏の気をそこねないように気をつかっている。花宴は盛大だったと、源氏も頭の中将の舞を讃えさかゆく春と。弁、中将など参りあひて高欄に背中おしつつ、源氏物語絵巻で見るきらびやかな衣装をみせびらかせ、笛など調べ合わせ奏でゆったり聴いている源氏であった。「いとおもしろし」大そう趣きがある。源氏と別れた有明の君、逢っている間が短く夢のようで源氏のことが忘れられず、四月には春宮への入内が決まっているので、それどころではない。源氏も檜扇の君を探したいが先々のことを考えるとどうしたらよいか思い悩む。弥生の二十余日右大臣で弓の競技が催され、その後藤の宴があるのですが気が進まず迷っていると帝の一言、右大臣が使いの者をよこしているのですから―。
(血を分けた異母姉妹だから)源氏はすぐ支度をして右大臣邸へ出かけました。
御装ひなど、どのような衣装なのでしょう。いとう暮るるほどに、すっかり暗くなって待たれて、もう右大臣家では待ちわびている様子がありありと目に浮かぶ。一つの言葉で情景が変わってくる。
(祥)
上達部、親王たち多くつどへたまひて、やがて藤の宴したまふ。
ここの説明に、「つどへ」は、集まるではなく、集めるの意であるとの説明があった。右大臣の権勢によって集めた、の意を含む。異本では、「つどひ」(集まる)もあった。下二段活用だそうだが、日本語の文法はまったく分からない。辞書を引きますと(広辞苑)「つどう」【集う】
1 (自五)集まる。
2 (他下二)集める。
とありました。英語の文法を見る思いがする。
(T)
2019年8月1日(木)12:30-14:30
於:大船のマンション会議室
読書範囲: 花宴
その日は御宴のことありて、
・・・
わりなくはしたひまつはさず。
参加者感想(順不同)
朧月夜を思いつつも、若紫を気にかける源氏。
久し振りに二条院を訪れ若き姫の成長に目を見張ります。
源氏が若紫に抱いている気持ちは単なる「好き心」や男女の仲を越え、より広く、深い人間としての慈愛、あるいはより緊密で真実な心の結びつきをもとめているように思われます。
それは、源氏の内奥の渇きのゆえでしょうか。黒々とした闇をも感じます。
(サッシカイア)
源氏の御心のままに育っていく、らうらうじき心ばへの若紫は、すこし人馴れて見えるのが、表裏ということではないか・・・と思う。
(Y)
なまめかしうおもしろし。
なまめかしい、生はんか、完全ではない、コンサートでヘミング・フジ子さんの不思議な1/8のゆらぎのピアノの音に似たようなものが・・・・。
(たか子)
後宴(花宴の翌日の小宴)花宴とは別に帝の周囲の上流の人たちの内輪で行う宴で源氏は筝(13弦)、琴(7弦)を演奏、楽器を奏でる高価で装飾があり、高級な遊び、なまめかしうおもしろい、不完全で自由に楽しめた。藤壺は夜明け前に清涼殿に御局に上り帝のおそばへおいでになる。源氏にとっては遠き人だとほぼあきらめている。そこでかの有明に出会った女のことが忘れられず、いつも源氏に忠実な良清、惟光に見とどけるように指示。牛車3台ほど四位の少将、右中弁(右大臣の息子)が見送った中に女がいたが、いろいろ思い描いてみたが、つくづくながめ臥したまへり、力つきたようだ。
女を忘れられず、ここは冷静になる源氏。しばらく二条院の姫君にも会っていないので心配しているのですが、昨夜の女と取りかわした扇のことでしみじみなつかしう思う。扇は檜扇で桜の三重かさね片方は濃いところに月があり水に写った風情はなつかしう、やさしく人柄がにじみでている 檜扇は厳島神社にあるそうで広島へ行った時は寄りたい。だんだん心が女に動いていく。今までにない恋だと歌を扇に書いて置きたまへり。左大臣の北の方へも御無沙汰していますが妻よりも二条院の女君の方が心配。ところがあまりにもうつくしげ(愛らしい)に成長しているのに驚く。少女から女君になっている様が賢く、愛敬づき源氏はホットしているのです。わが御心のままに教えなさむ、その時の源氏の苦しみの中に日常の中に開放された生活を望んでいる今日は女が源氏をどう思っているのかというお話ができました。
自然の美しさ、舞の美しさ、檜扇の美しさ、管弦の美しい音色読めば読むほど心して原文を読むことに幸せを感じています。
八朔 (祥)
2019年7月25日
読書範囲: 花宴 朧月夜の出会い
上達部おのおのあかれ、
・・・
ありがたう思ひくらべられたまふ。
参加者感想(順不同)
月明かりの下をさまよう源氏。
その心には藤壺への思慕が溢れています。
満たされぬ思いと偶然を契機 弘徽殿へ忍び入った源氏。
そこで新たな恋が。
決して名を明かそうとしない女。謎が源氏の恋心をいっそう掻き立てます。これまでとは違う愛のかたちが提示され、読み手を魅きつける。
物語の魅力と詩的な美しさの魅力。二つの魅力の展開に目が離せません。
(サッシカイア)」
桜の宴も終え、ほろ酔い気分で月を愛でている。源氏は藤壺のことが気になり飛香舎の方へ、二番目の戸が開いていて、内側の枢戸も開いていて、女房たちも眠りついている。すると「朧月夜に似るものぞなき」と美しい品のある声で若々しい美しい女が来るではないか ― 源氏は袖を引っぱると女は驚いてどなた、気持ちが悪い ― 源氏も驚いて可愛らしい女だと当惑する。女は源氏と知って情けなく見られたくなかったが、女のことをまだ生娘で初々しく愛らしい強く押し返すことなくよかったかなあ ― と思う。しかし女はさまざまに思い乱れたるけしきなり、悩みや多かりし。「なほ名のりしたまへ」どうぞお名前をお教え下さい、文をさし上げたい。女は歌でもし死んでも墓まで探しあてて来てくれますかと強気。別れの時がきて源氏も負けていません。嘘だったり騙したり、その場限りだったりではなしかと強気。ふたりとも強気。そして扇を交換する。別れ際も大切な場面。
桐壺の部屋(宮中での源氏の住居)では女房たちは源氏の忍び歩きの話をしていました。朝帰りで横になったが女のことを思い浮かべて想像しているのです。もちろん藤壺のしたたかさに心が動き、逢えないいらだちから、ますます横道に逸れてしまうのか、少し違うかな?そら寝寝たふり(目引き鼻引き)耳打してひそひそ話をしている場面も主人(あるじ)のことを観ているのがほほえましく思う。
その後女房たちの語り継がれて現代まで源氏物語を愛し楽しんでいる私がいるのです。先生は心して原文に向きあうように今日ははじまりから延長して原文をしっかりと学びました。
(祥)
2019年6月6日(木)
12:30-14:30 於:大船のマンション会議室
出席者(敬称略)
(6名)
読書範囲: 花宴 桜の宴
きさらぎの二十日あまり、
・・・
夜いたうふけてなむ、事果てける。
参加者感想(順不同)
国家行事としての桜宴。源氏は春宮に所望されて紅葉の賀の折に舞った一折を舞い、人々の賞賛を得る。それを受けて、帝は頭の中将に舞をうながし、源氏とは正反対に、一生懸命練習してきた舞を立派に舞う。互いが互いを気づかう様子が、なごやかな雰囲気の中に、描写されていて面白い。
(孝)
南殿のはなやかさの中に地下人達の緊張も伝わり、源氏の一人舞台にしないための帝の目配りなど、宮中の行事の一つが目に浮かぶような場面がおもしろく思えた。、
(Y)
宰相の中将、「春といふ文字たまはれり」と、のたまふ声さへ、例の、
人に異なり。
「のたまふ声さへ」の「さへ」により、源氏の声のみならず、容姿、装束、立居振舞いなどの全てが、比類なく優れていたことを、読み手は想像することが出来ます。この省略・簡潔の妙!
また、後段、中宮となった藤壺の内省、さらには
おほかたに花の姿をみましかば
つゆも心のおかれましやは
の後に置かれた、
御心のうちなりけむこと、いかで漏りにけむ。
という作者の述懐に、近代小説のような心理分析を感じます。
とりわけ、「いかで漏りにけむ」には物語の内と外を自在に行き来する作者の遊び心さえ感じられ、改めて脱帽です。
(サッシカイア)
紫宸殿 左近の桜右近の橘があり南殿は紫宸殿の別名。花宴は国家行事で大事なことであった。平安時代の花といえば桜で左近の桜の品種はなんだろう。きさらぎ(2月)20日過ぎ早咲きの桜であろう。薄紅か花の色も気になります。1000年以上の桜といえば山桜、庭は白い砂でまぶしく、帝主催の桜宴がはじまったが藤壺の中宮は上座見物場所で弘徽殿は下座、行事あるごとに心がかき乱れて堪えられないが、物見には出かけずにはいられなかった。いやな思いをするのだけれど好奇心で娯楽が少ない時代やむをえなかった。花日和の中で探韻、前庭の壺(鉢)の中から一字を取り出し詩をつくる。源氏は春という字をいただき美しい声で、次ぎの頭の中将も緊張していたが声づかいもすぐれていた。源氏と比べて帝はちゃんと目くばりをしていた。その次ぎの人たちは(地下の人)殿上人にもなれない、六位以下、御才並々ならずすぐれた才能をもった博士たち文化的に高い文章博士年寄りになって粗末になり、みすぼらしい人たちさまざまで可笑しかったと帝は感じたのだった。宴も盛り上がり管弦や舞楽がはじまりふたりの貴公子の舞い、帝も感動し袿を贈るところは帝らしい一面をみました。
(祥)
源氏物語の中で和歌と言えば、たいがいは贈答の形をとって、誰かが歌を作って贈り、相手はその返歌を返すというもの。ところが、花宴に出席した藤壺の恋心が、藤壺が心のなかで思っていることが、和歌の形をとって外に表れた。そして式部は「御心のうちなりけむこと、いかで漏りにけむ」ととぼけている。通常、地の文で書くところを、和歌に仕立てて、どうして外に漏れたのかしら、などと今は筆は自由自在になったようです。
(TY)
2019年5月23日
於:横浜市市民活動支援センター
読書範囲: 紅葉賀 七月にぞ后ゐたまふめりし。
・・・
月日の光の空に通ひたるやうにぞ世人も思える。
参加者感想(順不同)
「藤壺の立后」
短い文章のなかに政治的な機微・・・
帝の心境、弘徽殿の心理・・・が明瞭に示されています。
最後の段、皇后となった藤壺の御輿を源氏が担ぐシーンは、比類なく劇的で圧巻です。
紫式部はやはり天才、否、大天才ですね!
(サッシカイア)
七月(文月・ふづき・ふみづき)藤壺は皇后に。源氏は宰相(参議・上達部の官位)に昇進。立后とは皇后になる(源氏物語では皇后の表記はなく藤壺中宮(ことばの辞典より)。后とは女性の最高位。女性でありながら帝と同じ位。后がおいでになる時代は国政も安定していた。女御や姫君たちは入内を志し競いあった。后になるには帝の寵愛を受け、後ろ盾がしっかりしていて子を育て弘徽殿の女御で帝が指名するのです。
帝はなぜ藤壺を后に決めたのか、それは若宮を守るために、母宮をだに動きなきさまにく、せめて何々を万全にしておく。この若宮を坊に ― 若宮を皇太子にと考えて、位を譲る(退位)にあたり、若宮の世話役がいないので、若宮を守る決心をした。つまり力強い帝の思いがあった。ゆるぎない位につけて若宮を守るおじいさまのやさしい心づかいである。そして宰相は宮仕えの中核に踏み込んでこれから忙しくなります。藤壺が中宮になれば、弘徽殿の女御はおだやかではない。帝もなだめるが無理、無理。
作者は弘徽殿の見方をしています。春宮の母は必ず皇太后になるのだから ― 納得しません ― のに。いよいよ藤壺中宮として宮中に参内する夜、宰相も御供をした。中宮は玉の光り輝く宝石のように美しく、御輿を担いでいる源氏の胸の内はいかばかりか、切なく悲しく心の中でひとりつぶやく。
帝の妃との許されぬ愛と罪深き悩み、哀感と優美を伴う情景が思い浮かびます。皇子はおよすく(成長)して源氏に似て美しい人間同志が似るのは当然で、月の光日の光と信じ世間の人たちはゆるやかで思いやりに溢れていた。紅葉賀の終了。次回6/6から花宴になります。三島由紀夫が好んだ巻とか、楽しみです。
(祥)
2019年4月4日(木)14:00-16:00
於:横浜市市民活動支援センター
出席者(敬称略)
(9名)
読書範囲: 紅葉賀 君は、いとくちをしく見つけられぬることと思ひ臥した
まへり。
・・・
されど、うるさくてなむ。
参加者感想(順不同)
紫式部の博学がしのばれます。
その例として、「とこの山なる」が勉強になりました。
犬上の鳥籠(とこ)の山なる名取川いさと答えよわが名漏らすな(古今集)
がお互いに内緒にしようという話になる。
非常に奥深い話だと思います。
(マスピー)
「なごりの帯}
源氏と内侍との歌のやり取り。(p.97)
事件の翌朝、心の動揺をしずめていく歌の力が感じられます。
「典侍の懸想」(p.81)の歌とは明らかに水準(レベル)が異なる、見事な応答です。
源氏と頭の中将との歌(p.81)も面白く、催馬楽の巧みな引用がひと味違うアクセントを放っています。
(サッシカイア)
講義の前に2月24日に亡くなられたドナルド・キーン氏の小学6年の教科書に載っているプリントを皆で音読しました。古典文学の偉大さ、源氏物語の心の世界が描かれている。さまざまな人物をやさしく小さないさかいはあっても戦いがない、果てしない美しい世界がある。そしてなごりの帯へ典侍と中将と三人いろいろあったけれど源氏は乱れない人先生は強くおっしゃいました。中将の仕事(公務)は天皇のそばにいて取り継ぐ人うるわしく、すくよかにき真面目で折り目正しく整っている。桐壺天皇は決断力がある。催馬楽の歌のように昨日のことなど知らん顔しています。源氏物語はくわしく書かれていないところが奥深い。催馬楽は庶民の歌だった。憂しつらいとか男同志のちょっと云っておもしろがってうまくいかないね―。内侍もそこそこ楽しんだから。帝もあらあらと明るい結末でした。作者は生き生きと描いてますね。源氏は老婆を避けています。中将は源氏をやりこめる材料を得意になり源氏に嫉妬しているそれには理由があります。帝から愛されています。こんなに仲の良い二人ですが一つ事があると愛情や名誉を得たいと思い自分よりもすぐれているので相手を邪魔にし憎む気持ちになる同じ皇女腹であるのに何もひけをとらない。たしかに源氏は更衣腹で左大臣にも可愛がられてた。中将によって成長したのである。この二人の意地競争はいっぱいあるけれど作者もこれ以上は語らないでさらりと次へ上手ですね。
(祥)
古語というのは現代から遠いから、感覚的にも遠く感じるものですが、そのひとつひとつが的確に表現しているのを理解するのは容易でない。頭の中将が、
頭の君もいとをかしけれど、公事(おおやけごと)多く奏しくだす日に
て・・・
先生から説明があって、中将は蔵人でその仕事が、帝に奏上したり、帝から下命があったりする、その取次ぎであるとのことだった。その日が、簡潔に「公事多く奏しくだす」とあり、帝への取次ぎが双方向で忙しかったのを表現している。そんな表現に妙に感心した。
(KT)
2019年3月7日(木)13:00-16:30 於:横浜市市民活動支援センター
読書範囲: 紅葉賀 頭中将は、この君のいたうまめだち過ぐして、
・・・
と言ひかはして、うらやみなきしどけな姿に引きなされ
て、みな出でたまひぬ。
参加者感想(順不同)
作者(紫式部)の天才に打ちのめされた思い。
最終部分、頭の中将と源氏の間で交わされる歌
つつむめる名やもり出でむ引きかはし
かくほころぶる中の衣に (頭の中将)
かくれなきものと知る知る夏衣
きたるを薄き心とぞ見る (源氏)
ほころびた直衣(なほし)は内侍(ないし)の掛け言葉ではないかとも感じられるほど。
初めから作者が計画した筋立てではないかと思うとぞっとするほどの凄まじさ。まさに天才!
(サッシカイア)
源氏と頭の中将との内侍をさしおいての争いがうまく描かれている。
非常に近い(幼なじみ?)みたいな間柄ではないか。
(マスピー)
えならぬ二十の若人たち―えも美しい天下の貴公子の間にはさまった、ねびたる人(ふけた人)老婆の恥づかし姿と、何ともいえないくらい仲の良い源氏と頭中将のやりとりが滑稽でした。源氏がいつもいい人真面目な人なので、中将は源氏をこらしめてやろうと思って抓ったりじゃれあっている。親しい間柄だからでしょうか。
典侍は普通の女房ではない。催馬楽など歌ったり嘆いたりしていますが、しかし源氏はそんな老婆を大めに見てつきあっています。そこへ何かと張り合っている中将が驚かせようと二人のところへ近づいて来ます。ところが源氏は近づいて来るのは中将とは気がつかず、典侍を忘れられない修理の大夫のような人かと思った。そこで身分社会で、修理の大夫とは(従四位下)おとなおとなしき人に知られたら恥づかしい、蜘蛛のふるまひはと面倒臭い、もう帰るからねと心憂くだましたなと直衣を持って屏風の後に隠れました。中将は可笑しく我慢してごとごとと音を出して屏風をたたみ源氏を驚かせた。典侍は源氏を守らなければと、がたがた震えて男にしがみついている。その間にこの場を離れなければとできれば素性は知られたくない大切な冠だぐずぐずしてはいられないと焦っているところへ中将が太刀を抜いたので、老婆はそれだけはやめて―と手を揉んでいるところを見た中将は噴きだしてしまう。ここで典侍の歳がわかる。57才~58才若い貴公子と戯れている情景が面白い。
中将の仕業が馬鹿馬鹿しくここで抓っちゃう茶目気だが少し陰気な感じもする。ねたきものから、え堪へで笑ひぬ。そしてその後のやりとりが冗談や融通が2人の間を行ききし源氏の袖を引っぱったりしてほころびたり中将の帯をとったりふざけているうちに、袖の縫い目が切れてしまう。綻びをかくしていても人目につくでしょう。後をつけて薄ぺらな人だ。中将ってそんな人。「つつむめる名やもり出でむ引きかはし かくほころぶる中の衣に うへに取り着ばしるからむ」男女の仲と衣、掛け詞(一つのことばに表と裏の意味を持たせたもの)。物事を隠していても表にでるよ。源氏の返歌は かくれなきものと知る知る夏衣 きたるを薄き心とぞ見る。夏衣―薄衣(単衣の枕詞)来たる、来る、夏衣を着る、頭中将もわざわざ驚かしにやって来るなんて薄き心なんだよ―。源氏も負けていない。お互いに恨みっこなし、しどけなき姿(だらしない姿)で典侍の部屋を出て行った。置きざりにされた典侍は可哀想。いつも思うのですがねたきがよくでてきます。いかにも癪にさわる、憎らしい、腹だたしい、いまいましい、恨みに思う。宮澤賢治の作品にもよくでてきます。賢治も源氏物語を読んでいたのでしょうか。
(祥)
2019年2月7日(木)14:00-16:00 於:横浜市市民活動センター
出席者(敬称略)
10名
読書範囲: 紅葉賀 「いま、聞こえむ。思ひながらぞや」
とて、引き放ちて出でたまふを、
・・・
これも、めづらしきここちぞしたまふ。
参加者感想(順不同)
「相手が望まぬように応えられない」場面がある時どう断るか、四の五の理由を言っていると、こちらが嫌と思っていることがついついバレてしまうことが多い。そんな時、今日出てきた源氏の表現。「かなわぬもの憂さにて」と、わかったか、わからない、理由があって理由がない。こうした返答は味わい深い?
(孝)
「琵琶の音」
催馬楽(「山城」、「東屋」)、漢詩(白楽天「夜歌ふ者を聞く 鄂州に宿す」)を踏まえた叙述に、作者紫式部の教養の広さ、奥行きの一端が示されています。
老齢の典侍、その胸中に溢れる源氏への恋慕。
焦りが支配する老女の心そして欲望。残酷なほどに光をあて、読者の目に晒す作者の手腕は、やはり見事と言うほかありません。
(サッシカイア)
典侍(老婆、何歳かわからない)
源氏のちょっかいが典侍を本気にさせ、悪気がないにしろ許せません。よく思ってもいないことがぽろりと口からでることがあり、頭と口がともなわない。うっかり出てしまう。「いま聞こえむ」と逃げセリフでその場を逃げようとする。典侍は老いを嘆き怨みの歌を返す、および腰になって。そんなところを帝に見られてしまった。似合わないカップルであると苦笑していた。そこへ頭の中将が登場。典侍については隈なき心にて十分知っていたのに、源氏との仲を探ってみたくなる。源氏と頭の中将の行く末は・・・。やはり典侍は源氏にぞっこんで真から惚れこんでいる。源氏はさほどでもなく、典侍はしつこく・・・。源氏はかなわないもの憂さに、ものぐさとは言っても気になり、夕立後すーっと涼しくなり、温明殿(典侍の仕事場)の辺りを、様子を伺いながら歩いていた。するとどこからともなく琵琶の音が聞こえてきた。典侍は琵琶の名手であり、歌も上手で聞き惚れていた。
典侍の懸想から・・・源氏の懸想へ・・・。
よくローマは一日にして成らず、老婆も一日にして成らず、齢を重ね長年の琵琶のレッスンといろいろな経験をして来た。だてに齢をとっていない。末摘花といい典侍といい、よく容貌(かたち)を繊細に描写しています。
(祥)
催馬楽について学習した。当時の民間の俗謡が内裏に取り入れられ、曲をつけて貴族たちに演じられ、楽しまれていた。それだけで驚きです。源氏物語の巻名に催馬楽から3曲とられているそうですから、当時の流行のほどがわかります。
ちなみに、源典侍は当時57~8歳、源氏は18~19歳だそうです。
(TK)
2019年1月24日(木)14:00-16:00
読書範囲: 紅葉賀 内裏にも、かかる人ありときこしめして、
・・・
今さらなる身の恥になむ」とて泣くさま、いといみじ。
参加者感想(順不同)
典侍の件
身分もたかく教養もある老女に源氏はちょっかいを出したが、老女は流し目等色っぽく見せるが、源氏もあきれる。歌のやりとりも、私は、他の男から嫉妬されると困るからと口実をつけて立ち去ろうとすると、この老女は源氏の袖をもって、ごう泣する。
(マスピー)
典侍の懸想
才色兼備の若い女房たちには色目を使わず、適当にあしらう源氏。
ここで作者は年老いた嘗ての美女、家柄も良く、教養ゆたかで、地位も高い典侍に焦点を当てます。
老齢をものともせず、色恋に異常な情熱を燃やす典侍。
源氏と典侍のやり取りは、エロティックでグロテスクな人間の欲望の凝縮であり、若き貴公子と好色な老女との、火花を散らす対決を見ているよう。
悪趣味な真っ赤な扇に描かれた金泥の絵。
古今集を踏まえた歌の交換の残酷なほど下品で、恋しい源氏にすがる老女の姿は、何ともかなしい。
(サッシカイア)
帝の悩み。左大臣の葵の上のところでは、あーでもないこうでもないと噂をしている。桐壺帝も少女のことは気にして心を痛めていますが、あえて源氏のことを可哀想だと思っているのです。それはなぜかというと臣籍に下った源氏を葵の上と結婚させたこと、左大臣に申し訳ない気持ちなどである。悩みの多い父親像が見えています。源氏は女房たちにちょっとしたことで言葉をかけているのに慣れているのだろうか、宮中では普通に女房に接していた中には色めいた女房がいて、ちょっとちょっかいを出してみたところ、年いたう老いたる典侍はその気になって、流し目をしたりして扇で顔を隠したり(瞼は黒ずみ垂れて肉も落ちて皺だらけであった)男の気をひき色っぽい、常に恋の道にまい進している。内侍の司は優れた評判の良い高い位の女房。いつも恋心に燃えている。典侍は源氏に思いをかける。惚れる。たまらなく好きで夢中になる。源氏は人の噂になれば世間に恥かしい。源氏は好奇心きはまりて人間の特色で少し典侍には興味があった。
典侍はどれくらいの年齢だったのだろうか。王朝時代のサロン的な風習の中で、自由に仕事した上で恋にかけていた。身分とか教養とかすぐれていた典侍であった。女房は恋の対象になれるけれど結婚はできない人。相手があまりにも年が離れているので、気にしている源氏であった。典侍は華やかで源氏にはますます好意を持っているが、少し気にくわないが裳の裾をちょっと引っぱって驚かした。作者はリアルに描写していて、ド派手でセンスのない強れつな扇に歌が書かれていた。大荒木森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし。老いを嘆く歌。源氏はなんと品のない歌だろう。お互いに歌を交換するが、典侍は本気になり、色っぽい目で源氏の衣を引っぱって袖にすがりついて泣くのです。年寄りを悲しませてはいけません。源氏をうなさせる典侍だったのか。
(祥)
作者は、突然「年いたう老いたる典侍」を登場させる。好色な「いみじうあだめいたる心ざま」の老婆である。帝のそばに仕える女御である。末摘花のときもそうだったが、ちょっと変わった人物を場面に挿入することによって、物語全体がずいぶんリアルな感じになる。
(TK)
2018年12月6日(木)14:00-16:00 於:戸塚区民文化センターさくらプラザ
読書範囲: 紅葉賀 つくづくと臥したるにも、やるかたなき心地すれば、
・・・
など、さぶらふ人びとも聞こえあへり。
参加者感想(順不同)
「二条の院の女君」
子供と大人の中間にある少女と源氏との交流。和歌を介さる、会話による直接的な真意を伝え合う二人の姿が、他の巻・他の女性たちにはない新鮮な映像と感動を生み出しています。
源氏が少女の髪を掻き撫で、
ほかならぬほどは恋しくやある
と尋ねる場合など、平安貴族というよりは映画のなかのラブロマンスのよう。
(サッシカイア)
藤壺より返信がありやはり想いは同じでうれし涙をこぼす源氏。そして二条院の少女のところへ出向く。笛を吹きながらなつかしさのあまり部屋をのぞいて「こちや」と驚かす。なんとほゝえましい情景で琴をかき鳴らし笛と合わせて楽しそう。時を忘れていつのまにか夕やみになり、大殿油(おほとなぶら)尊敬語。灯を燈させ絵を二人で見る。供の人は声づくりして雨が降ってきそうだとか、少女は心細くなり、うつ伏せになる姿を見て、いじらしく髪をかきあげ、なでたり淡い恋心をいだく。紫の君に対して精一杯の愛情表現。少女なのに源氏のやさしさがうれしく膝元で寝てしまう。(祥)
我が家でも孫(女の子)が時々お泊りにくると祖父になる夫はもう愛情たっぷりの仕草を見るにつけ、きっと紫式部の父為時が孫の賢子を可愛がったのだと想像する。賢子が誕生したころから、源氏物語の執筆を始めたようです。先日晩秋の逗子へ出かけた。源氏物語と王朝絵巻展で、嫁入本黒漆塗箱入の写本(表紙をめくれば金箔)を拝観し、貴重な源氏物語を拝観できました。(祥)
源氏は二条院に戻って、大人の恋心でうつうつとしていたが、西の対へ渡って若紫に慰めを見出す。若紫は今何歳だろう。ある推定によれば源氏より8歳年下として、11歳になるそうです。すでに大人の気持ちが芽生えている。久しぶりに会った源氏に対して、若紫が
入りぬる磯の
とつぶやく場面がある。解説によれば、この歌の出典は、万葉集/拾遺集とありますが、
潮満てば入りぬる磯の草なれや見らくすくなく恋ふらくのおほき
(抄訳)
あの人は海の草のよう 潮が満ちれば水の下にかくれて
見ることは少なく恋うるときばかりが多いです
このような歌の一部を即座に引いて自分の思いを託する教養の深さは、驚くべきものです。まだ少女ですから。
(TK)
2018年11月1日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
(11名)
読書範囲: 紅葉賀 四月に内裏へ参りたまふ。
・・・
胸うち騒ぎて、いみじくうれしきにも涙おちぬ。
参加者感想(順不同)
「対面」
前頁で源氏は藤壷にも皇子にも会えず、苦悩している。立場は違っても同じ苦しみも嘆く藤壺、そして命婦も悩みが滲みでています。
二月の半ば皇子誕生し、ようやく四月に帝にお見せすることになった。生まれて二ヶ月、そろそろ寝返りなどできるようになり、健やかに育っていた。対面するやいなや帝は驚いた。まさしく源氏にそっくりなのだ。帝は思ほしかしづくこと限りなし。愛情いっぱいの表現、そこには源氏の母は妃として身分が低く、帝も悩み、ただの人を見ながらあわれに思う。藤壺は妃として皇子の母として振るまわねばならない。胸のうちは悩みも増し、いたたまれない様子を細かに作者は表現している。藤壺のところで管弦の遊びをしている時、皇子を抱いた帝が喜んでいるのを、源氏は見て泣く。はじめて見る皇子、いろいろなことがあって思い出した。皇子は神々しきいとゆゝしきうつくしきに。父帝を尊厳。藤壺もわりなきかたはらいたきに、源氏もなかなかなるこゝちのかき乱れるようになれば、両人心の動きを繊細に描写している。二条院へ戻って苦悩が募るばかり。皇子と会って我が子に会って現実と関わって生きなければならない。藤壺への手紙を命婦に託す。期待していなかったお返事があり、歌が届きました。うれしく泣きの源氏。イメージで読む源氏物語紅葉賀の帯にもあるように。ほの書きさしたるようなるを、墨も薄く、でも胸のうち過ぎてとめどなく涙をこぼす。人間らしい源氏に私もぞっこんです。悲しんだり喜んだり源氏らしい。
(祥)
「対面」
(前段)
疑うことを知らず我が子の誕生に歓喜する帝。源氏を不憫に思う気持ちが新たな御子、疵なき宝石(たま)への愛情となって注がれています。
「宮はいかなるにつけても、胸のひまなく、やすからずものを思ほす」
表面的にストーリーを展開するだけではない、源氏物語の奥深さを感じます。
眩い光の背後に存在する無間の闇。やはり紫式部は凄い!
(中段)
若宮と対面した源氏。紛れもない己の面影を知り。うろたえる様子。
「恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがたうつ
ろふここちして・・・」
詩的な、形容詞の連続が劇的表現されています。
(サッシカイア)
2018年10月4日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
(9名)
読書範囲: 紅葉賀 この御ことの、師走も過ぎにしが、心もとなきに、
・・・
いとわびしく思ひのほかなるここちすべし。
参加者感想(順不同)
藤壺は出産をしてから、微妙に態度が変わってゆく。母親が持つ防御本能だろうか。すべてのことに、いっそう慎重に用心深くなってゆく。それは侍女の王命婦に対してもそうだった。式部はその変化をさりげなく書いてゆく。
(藤壷は)命婦をも、昔おぼいたりしやうにも、うちとけむつびたまはず。人目立つ
まじく、なだらかにもてなしたまふものから、心づきなしと思す時もあ
るべきを、(命婦は)いとわびしく思ひのほかなる心地すべし。
(TK)
見ても思ふ見ぬはたいかに嘆くらむ
こや世の人のまどふてふ闇
王命婦が、新しく生まれてきた皇子をめぐり、藤壷と源氏の気持ちを歌に詠んだ今日のくだり。
複雑な思いが交叉する二人。そして重要な役割を果たした王命婦と藤壺の関係も微妙になってきたことが語られる。
藤壺の心のゆれ動く様子に心引かれる。
(たか)
今日の所を読みながら、弘徽殿の女御が気の毒に思え、又命婦の主人のために全てをつくしているのに、藤壺の苦しみのあとに変化する心の内が素直に納得できない彼女がこのあとどうなるか。
(Y)
久々の参加で、“やまとことば”を音読するとここちよいリズム、又奥深い意味合いに感動する。源氏と藤壺の“あやしかりつるほどのあやまり”、若宮が“めづらかなるまで(源氏)に写し取りたまへるさま”、桐壺帝・弘徽殿側がどうして気がつかないのか、多少不思議な気もするが・・・。
(Hiro)
皇子誕生
源氏と密通し、懐妊してしまった藤壷の罪へのおののき、発覚した場合に待ちうけている破滅への怖れ。
個人、自我の確立している時代、貴人たちは感情の高まりと世のきまり(倫理、道徳)の間で翻弄されていく。
簡潔な文体でその有様を表現し、省略・沈黙によりその本質を暗示する紫式部の天才。
注目すべきは、藤壺と命婦の関係の変化。最も親密であり信頼されているがゆえに主(藤壺)の秘密を握ってしまった命婦。淡々としながらも、正鵠を射た心理の移ろいの表現に感嘆するばかりです。
(サッシカイア)
10月皇子誕生
藤壺は出産を控えている。女性にとって出産という大切な時間、重大な神秘的な時間を待ち準備していますが、誰もが心細い思いをするのです。そんなこととは裏腹に“御もののけにやと世人も聞こえ騒ぐを、宮、いとわびしう”そーっと静かにしていてほしいのに、なんということでしょう。藤壺は身のいたづらに苦労するだけに、悲しく体も弱まり具合がわるく病気になってはと源氏は心配し、内緒で御修法を所所のお寺にお願いする。出産の遅れが藤壺の身にもしものことがあったら―ではなく藤壺との恋が終えるのではないかと、なんと浅はかな男であろう。予定日も過ぎて二月十余日男の御子誕生。帝も三条の宮の女房たちも祝福しているのに、藤壺の心は彩えない悩みが続く。弘徽殿は皇子誕生のことに悪い噂をしていることが聞こえてくる。こんなこと負けてはいられません。強い心になりました。出産後だんだん回復し帝の喜びで救われます。源氏も御子に一刻も早くお目ぼしをと三条の宮を尋ねるが、お断りする。帝に対しての、そこは大人である。しかし紛れもなく源氏の子。藤壺はここで帝を裏切ったこと、してはならないことをしてしまったことを悩み苦しみます。過ちを女房たちにつきつめられ、みじめな身であることを想像する。
王命婦、源氏、藤壺、三人三様、悩みを細密にその立場におかれた心の動きを描いている。
(祥)
2018年9月6日(木)14:00-16:30 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
(8名)
読書範囲: 紅葉賀 今年だにすこしおとなびさせたまえ。
・・・
ほの見たまふにつけても、思ほすことしげかりけり。
参加者感想(順不同)
小納言の悩み、それは少女から少し大人らしい、女らしいことに関心を持ってほしいのに、髪をくしけずることさえ厭そうにしている。少納言は女らしく成長してほしく厭味たっぷりの小言を言う。しかし、「われはさは夫(男)まうけてけり」、10歳過ぎてもう少女ではなく源氏も男君として振舞っている。ほんのちょっとした愛情表現がすばらしい。少女は心の中では源氏の妻になることを決めていることに私は驚いた。
北の方(葵の上)左大臣、源氏にとって舅・義父、年賀の挨拶のために左大臣邸に向かう。「心うつくしき御けしきもなく」、今年こそ夫婦仲良くと心に誓うが、北の方は二条院の若紫のことが気になり、不安でならない。しかし北の方はじっと堪えて最初から似げなくはづかしいと思っていた。源氏は自分の所為であることだとわかっていても顔に出さずもてなす気づかいで対応するが、それにまして、えしも心強からず乱れるところがなく、わめかない、源氏の心の中を見抜いているかのように源氏の上手をいっている。やはり手強い女である。でもそんなところが源氏は気に入っているのです。年上だから―、そうかな―。やはり左大臣の育成によってひとりの女性像ができ、なかなかお互いが歩み寄れず、心が通じあえなくなってしまった。残念。ほんとうは男として心を通わせ歌など楽しく交わしたいと思っていたのに―。
左大臣は甲斐甲斐しくけなげに源氏の世話をする。それが痛々しい。強引なところもあり自己満足していますが、源氏にとってはあまり構わないでほしいと思ってもそうはいかない。それは帝が源氏の将来を案じて決めたことだから。そして藤壺の三条の宮に立ち寄れば、女房たちの騒々しい気配で几帳よりチラッと源氏の姿を見る。身重の藤壷は胸がしめつけられる悲しみが増し、この恋は終わりにしなければとしきりに思う。女を悲しませる男は―嫌です。しかし源氏にもいいところがあるのよ。たとえばたとえば芸もすぐれて声も書も美しいのです。酷暑、猛暑、生命にかかわる暑さ、こんな時私は最近(7月)に出版された紫式部日記を読んだ。又紫式部が越前への旅の無事を祈ったという白鬚神社に参拝した。私も80歳に感謝して淡海にむかってアリガトウ―と。
(祥)
少女に(若紫)に忠告する少納言。
常識的な枠組みのなかで生きている人は、他者にもそうした振舞いを求める。
少女のあどけなさ、天衣無縫性は、ひょっとすると源氏が心の底に秘めていた奇矯な(異常な?)嗜好の反映かもしれない。
貴族の男性の「好きごころ」が称揚された時代、源氏の想像力は奔放に突き進み、常識の枠を越え飛翔して止まるようです。
「左大臣の北の方と舅」
前段は、源氏と北の方との複雑な心理描写。
源氏の心の内の声
なぜ そんなに そこまで・・・?
北の方の高すぎる気位が記されているが、決して意固地でも意地悪でもない。
物語が要請する男女の溝なのか。
やや 気の毒な気もします。
(サッシカイア)
自宅に引き取って育てている若紫。世間的には結婚の形をとっているが、未だ、実の男と女の実態のない二人。雛遊びをするくったくのない若紫。彼女は、いつ、どのようなことをきっかけに女になっていくのだろうか。
対照的に書かれている本妻の左大臣家の葵の上。美しくて気にそわない源氏に対して、こびず、それでいて強情をはらない。高貴な家の生まれ、皆にかしずかれて育った姫君は、源氏との仲をどう深めていけるのか。
舅である左大臣の源氏へのもてなし。おかしくて、やがてかなしき・・・と。語り手は言うが、一生懸命な姿がほほえましい。
(孝)
左大臣の源氏に対する態度は、読む者にコミカルにみえる。舅としての描き方が面白い。
凡帳の隙、上より~は、まさに劇中のクライマックスシーン。藤壺の源氏への想いだけでも、見ごたえがあるような気がする。
(マスピー)
幼い少女を引き取って、養女ではなく女として育ててそのまま妻にするというのは、当時にあっては、さほど異常なことではなかったのか。仕えている女房たちは全然驚いている風がない。姫君のすることが時にあまりにも稚いのが目につくので、少し変だなあと思いながらも、少納言も周りの女房たちも、二人はすでに夫婦と思い込んでいるようです。しかし実際はまだ夫婦の契りをしない添い寝の相手だった。
かく幼き御けはひの、ことに触れてしるければ、殿のうちの人びとも、
あやしと思ひけれど、いとかう世づかぬ御添臥ならむとは思はざりけり。
(TK)
2018年8月2日(木)14:00-16:30 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
(7名)
読書範囲: 紅葉賀 藤壺のまかでためる三条の宮に、
・・・
内裏に参らせなどしたまふ。
参加者感想(順不同)
講義が始まる前に、先生より縄文時代の展示を鑑賞になったお話があり、その時代の人々の心豊かな生活に感動されたと土器の絵葉書を見せていただきました。
藤壺は懐妊し出産のため三条の宮邸で過ごしていた。源氏はとうとう我慢ができなくなり、三条の宮邸に出かけた。女房たち(命部、中納言の君、中務)のもてなしを受けるが、懐妊後悩み続け少し距離を置こうとする藤壺を思いやり、女房をかえして世間話をしている所へ、藤壺の兄である兵部卿の宮と対面し対話しながら宮の世話をしてみたい、異性をみる。両者色めく。この人は紫の上の父親であり、打ちとけて親しみを感じ、宮も源氏の美しさに見とれて婿にと、又女として源氏に近づいてみたいと変に想像している。こんなところが作者は微妙に面白く書いていると思う。
そして日が暮れて兵部卿の宮は、藤壺のいる母屋へ簾の中へ、源氏は取り残され羨ましく思う。以前は帝の取り計らいで藤壺のそばまで出入ることができたのに、今は人づてで侘しい。私は嫌われている、どうしようもない、すくすくしうて別の挨拶をする。悲しさをこらえる。心を切り換えるところが源氏らしい。お互いに胸のうちに秘めているのが、嘆かわしい。いやそれでいいのだと思う。ひたすら心の中で苦悩する嘆きを重ねることしかない。
雛遊び(人形遊び)は少納言の立場で読む。
紫の上は二条院で満ちたりた暮らしをしている。姫君のことを祈って仏の勤行をした尼君(仏)が守ってくれていると思うが、不安もありまだ少女だからいいけれど大人になって煩わしいことが心配でならない。今は源氏が愛情一杯に支えてくれているのが嬉しい。喪が明けたら普通の衣であまり目立たない衣で、地の限りで紅、紫、山吹の小袿は清潔でオシャレで美しい。
少納言の女房がよく明確に故尼君に対して有り難いと惜しむ。1月1日元旦の行事、午前8時朝拝に宮中へ出かける前に、男君(源氏)は少女の部屋をのぞくと、にっこりとほほえみ、今日から大人になるのでしょうかね、いとめでたし、表情が美しく魅力的で素晴しい。人形遊びをして、せかせかと部屋のなかを動きまわっています。源氏を見送った後も、人形遊びに夢中になるのです。今日の源氏の会はスムーズにペンが動き、特別楽しかった。
青景さんの人形遊びの思い出も聞いた。平成30年の夏、酷暑、灼熱の夏、災害レベルの猛暑、1000年前の京都も厳しい夏で異常気象だったと報じていました。都では疫病が流行し、源氏もわらわ?病みで北山へ療養にでかけていた。王朝時代の暑さ対策はどうだったか。源氏なりに涼しく工夫していたと思う。7月の西日本豪雨の時も、鴨川が増水し一時危険な状態だったそうです。平安時代の気象予報士は紫式部だったかもしれません。
自然災害と一言で片づけられるでしょうか。自然を大切に自然を守るようにすればと思います。先月七夕さまの語りの会には、西日本豪雨の義援金の箱を持って参加してくださった方々にお願いしました。私にできるささやかなことですが、何か役に立てたらと思いました。先日代表から広島へ送金し次回は岡山・愛媛へ送る予定だと報告がありました。私たちも防災対策を見直す必要があると日頃思っております。
次回は9/6 セミナールーム 10/4 セミナールーム 11/1 ディスカッションルーム(古典の日)
(祥)
雛遊び
源氏が引き取った少女が、引き取られた直後は泣いて少納言のところに逃げたが、今は雛遊びに熱中している姿がみえる。源氏になついている姿がみえる。
(マスピー)
「三条の宮にて」
(前段)
源氏と兵部卿との対面。
互いの心の内に生じる好奇心(すきごころ?)。
「この人が、女ならば・・・」
湧き上がる想像力の作用をひじょうに巧みに捉え、表現しています。
しかも、両者が互いにそのように思っているとは!
新奇にして、刺激的な心理・欲望のはたらきを描き出す紫式部の畏るべき眼差し!
(後段)
源氏と藤壺との心理の葛藤に焦点が当てられています。
許されぬ恋が二人を隔てていくのか。
懐妊した藤壺の不安、苦悩はいかばかりか。
許されざる恋、その罪の重さに恐れおののく藤壺の存在が、作品全体の陰影を深め、単なる恋物語でない芸術性を付与していると感じます。
(サッシカイア)
2018年7月5日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者
10名
読書範囲: 紅葉賀 宮は、そのころまかでたまひぬれば 、
・・・
いかめしうとぶらひきこえたまへり。
参加者感想(順不同)
「北の方とおさなき人と」
前段は、源氏と北の方、二人の間に広がる心の割裂。通わぬ思いが源氏の思念により、くっきりと浮かび上がってきます。
男女の複雑な心理、葛藤を簡潔かつ明瞭に記述する作者。
千年前にこの源氏物語が出現していたことは、驚異であり、奇跡とも思われます。
後段は、一転して少女(若紫)の暮らしの様子。少女と源氏との素直な、隔たりのない心の交流がしっかり描かれています。
前段と後段との対比(複雑と単純、鬱屈と明快、主観と客観)は、おそらく作者の意図するところ。この構成の見事さにも驚かされます。
(サッシカイア)
今日の収穫は、「ありき」と「あゆむ」、「まかで」「まいる」等と古文の中での言葉を、今頃になって、なるほどと思えるようになり源氏の原文をゆっくり読んでよかったと思う時間でした。
(Y)
北の方(葵の上)とおさなき人(紫の君・若紫)
藤壺は三条の里で過ごすのだが、源氏は落ち着かず、もう一度逢いたく文をするが返事がない。葵の上の父も源氏が顔を出さないので、心配している。二条院で暮らしている若紫のことも葵の上の耳に入り、それは無視されたことで心を痛めています。
しかし葵の上こそ打ち解けて遠慮なくくつろげたらと。源氏は努力しているのだ。結婚以来しっくりいかなかった。親同士が決めた結婚であったし、いつかわかってもらえると、年上の北の方であったしそれはうまくいく筈がないでもいつかはと希望をもっていた。
紫の君のためにも、西の対に人目につかないところに調度品をかざって見事に整わせ、新しい生活がはじまった。源氏自ら手ほどきしてしっかり守っていこうと心した。姫君は幸せだったが、時々尼君のことを思い出し、源氏が北の方や外の女のところへでかけている時はさびしく、可哀想にも思える。今は姫君に寄り添う。それは僧都にとって嬉しく、尼君の法事には心遣いがあり、そんな誰にもやさしい源氏なのだ。この時は男も女もかけもちで働いていた。先生の目次にはいつも感心しています。おさなき人と、をさなき人はどう違うのでしょうか。
(祥)
「心づく」「心うつくし」「心ざま」
今日の会で、作者の心理描写が、千年も前に近代文学をもしのぐ表現法で書かれたことが、話題となったが、今日原文の中に出てきたのも心理描写に手がかりを与える三つの言葉が使われている。
心を表現する表現が微妙に違う。千年前は、あたり前に心のあり様を日常的に使いわけていたのだろうか。
「心」+○○の表現に注目してみようと思う。
(孝)
源氏と葵の上の夫婦仲はうまくいっていない。葵の上は気位が高く打ち解けないと源氏は思い、もっと世間の普通の女のように不満があれば口に出し、心をひらいてほしいと思っている。そして次ぎのように思う。
思はずにのみとりないたまふ心づきなさに、さもあるまじきすさびごと
も出で来るぞかし。
(葵の上が源氏の言動を)思いもよらない邪険な取り方をすれば、(源氏
としては)あるまじき女遊びもしたくなる。
心の動きは現代もあまり変わっていない。
小説には詳しくないが、近代文学の心理描写などと同等にとってはいけないのだと思う。なぜなら、式部にとっては心理描写をしているのではなく、心の動きの現実を書いているのだから。そう思って読んだ方が面白い。
(TK)
2018年6月7日(木)12:30-14:30 於:田中先生の大船のマンション集会所
出席者(敬称略)
(7名)
読書範囲: 紅葉賀 つとめて、中将の君、
・・・
昔の世ゆかしげなり。
参加者感想(順不同)
源氏物語の中から平安時代を知るうちに、菊の花の色が咲きほこった美しさよりも「色うつろひ、えならぬをかざして・・・」と表現しているところが興味深かった。
(Y)
朱雀院への行幸で、数人の楽人を乗せた舟を二艘池に浮かべて演奏させたのは、驚いた。もっとも帝の権威をもってすれば、これも統治のひとつのやり方でしょう。みなよくやったので、それぞれ昇進した。
たしか、空蝉の旦那が、川から水を引いて庭にまわして、それが自慢だったとか、うろ覚えですが。これは受領で富をなしたのでしょう。
(TK)
源氏と藤壺の間で交わされる文、省略の極地とも思われます。
抑圧している情念が、和歌という形式ののなかに封じ込められているよう。
現代のメール利用者よ、とくと学ぶべし。
「行幸」
源氏の舞いの素晴しさが、周囲の人びとの様子、感動ぶりから伝わってきます。
また、途中、他の諸々の芸を省く式部の大胆さ。
これらにおもしろさの尽きにければ
異事に目も移らず(云々)
場面の転換の見事さにはいつものことながら、脱帽の思いです。
(サッシカイア)
朱雀院への行幸をめぐってくり広げられる賀の行事。公の行事ではあるが、それらを担っている生身の人間の個人としての心の動きは、きわめて個性に満ちている。源氏と藤壺の心の動き。式部は公の表面的に進行していく様子を追いながら、しっかりと個人の心をにがさないで書き止める。マクロとミクロの世界観をしっかりと捉えているところは、手法としてもすごい。
(孝)
試楽をご覧になった藤壷に源氏(中将の君)は恋文(真心)を書いた。ほんとうに胸のうちの苦しい想いで藤壺だけに集中して舞ったことを告白している。藤壺は桐壺と源氏の愛を受けて返歌する。
源氏の舞は美しく立ち居振舞は目を見張るもの、心がゆれながらも返歌を戴いた源氏は素直に喜ぶ。帝の妃としてしっかり心を据えている様子が、帝にふさわしい妃であることが嬉しい。
当時は男よりプロポーズ、女は必ずおことわり、そして徐々に恋愛に発展してゆく。
政治も芸能もよき時代で行幸は素晴しく、舞人楽人青海波(二人舞)を垣代して自然現象が鮮やかに(そぞろ寒く)ぞくぞくした帝は、源氏と頭の中将の位を昇進させた。
朱雀院の行幸を盛り上げるために源氏の舞など平安時代を知ることができた。
平成23年に講座が始まって今夏で8年目を迎えます。5月6月会場がとれないで先生には大変お世話をおかけしました。有難うございました。これもひとえに先生会員の皆様の御尽力だと感謝しております。
7月5日(木)桜木町セミナールーム
8月2日(木)桜木町セミナールーム
9月6日(木)桜木町セミナールーム
(祥)
2018年5月24日(木)12:30-14:30 於:田中先生の大船のマンション集会所
出席者(敬称略)
8名
読書範囲: 紅葉賀 朱雀院の御幸は神無月の十日あまりなり。
・・・
見せたてまつらむの心にて用意させつるなど聞こえたまふ。
参加者感想(順不同)
なにかが違う
どこかが違う
いつもの席に
君のいなくて 注)君(進君)
朱雀院への行幸を前に、藤壺に源氏の舞を見せる桐壺帝のおもいやり、こうした情景の時、進君はなんて感想を述べるかなあ・・・と、ふと思ってしまいました。
(孝)
紅葉の賀に入る。
「花のかたはらの深山木なり」という所に、源氏を見る桐壺帝の心が伝わって来る。舞いの中にも楽の中にも余韻を感じる場面。なかなか現代にはそこまでは伝わって来ない気がした。
(Y)
今回から紅葉賀の巻。
「試楽」冒頭は源氏の美しさ舞いの見事さを強調。巧みに読者を物語へと導いていきます。詩を詠じる源氏の声はこの世のものと思われない。観衆は感激の涙を流します。
その後の展開は紫式部の天才の証明。憎まれ口をたたくもの、過去のいきさつを思い出し、情感を深める藤壺。さらに帝の藤壺への配慮、愛情、人間の心理が幾重にも重なり、深み厚みある世界が広がっています。素晴しい!
(サッシカイア)
朱雀院の行幸と試楽について興味深く読ませて頂きました。当時の風習等非常に面白く読ませて頂きました。
源氏物語の年表が参考になりました。
(マスピー)
今日から紅葉賀に入る。
朱雀院への御幸に行けない女房たち特に藤壺のために、帝は清涼殿の庭で試楽(リハーサル)を催す。そこで頭中将と源氏が、青海波を舞った。例によって源氏の舞は素晴しく、それに比べて頭中将のは「花のかたはらの深山木」と作者は評す。
しかし、舞いに対する作者の評はさらに続き、帝の口を通して、中将の舞には、世に名声を博している舞の名手にはない、「ここしうなまめいたる筋」(むずかしい表現、多分、玄人にはない初々しさ・新鮮さ)があると評している。
たいへん高い鑑識眼に感心しました。
(TK)
朱雀院の一大イベント、帝の外出で賀宴のための朱雀院の行幸を控えておもしろがるべきで、都の人たちは楽しみにしている。御方々奥に務める女房たちはみられないので、帝は是非藤壺にみせたいと清涼殿の東庭で試楽をお見せになった。藤壺にやさしい帝であった。
源氏と頭の中将が舞曲青海波を舞った。やはり源氏は何事においてもすぐれていた。このような青海波を見たことがなかった。
楽器が中心であるがピタリととまり、源氏の吟詠の美しい声に感動して涙を流した。
華やかな音に反響して源氏の輝きに、春宮の女御はただならぬ態度でいやみを言っている。「うたてゆゆし」不吉な予感、と平気で言える人。藤壺はうっとりと夢ごこちで見ていた。
おほけなき心、恋ごころがなかったらもっと素晴らしのに。
藤壺のための試楽も終え、帝はどうでしたかと。藤壺はわけもなく帝への後ろめたさがあった。頭の中将もよかったよ、源氏はもっとよかったけれど、自然に身についているのびのびした気品があったと持っている美しさ育ちの良さを帝はちゃんと見ていましたね。桐壺帝の時代は、文化、舞、音楽を大切にした。頭の中将を左大臣の息子らしく評価しています。
古典文学は歴史に参加していると議論が続いて、内容であらためて古文の良さを耳で読みました。
(祥)
2018年4月5日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
8名
読書範囲: 末摘花 二条院におはしたれば、紫の君、いともうつくしき片生
ひにて、
・・・
かかる人びとの末々、いかなりけむ。
参加者感想(順不同)
今日でこの巻も終わり。末摘花を読んでいる間、ずっと考えていた、作者はなぜこれを書いたのだろうか。
末摘花は、源氏の理想とする女性とは全くの正反対。醜女、座高が高く大柄、鼻が長く先が赤い、衣装のセンスはない、歌も満足に詠めない、琴は弾けるがうまくない、荒れた邸に手を入れる経済的余裕もない、使っている調度類は時代遅れ、総じて女性として「あわれ」を感じる教養もない、つまり何もいいところがないのである。それをなぜ登場させたのか。
式部はなにも難しいことを言おうとしたのではないだろう。読んで楽しんでもらえれば、それでよしとしたのではないか。そうであれば読者としては、余計なことは考えず、いつものように古語の表現をたどり、読んで楽しむだけであろう。その感想は人それぞれであろうが。
敢えて憎まれ口をたたけば、書いている自分のイジメ嗜好、意地悪さを感じている式部の顔が浮かんできた。
(TK)
末摘花の最後、「かかる人々の末々、いかなりけむ」と結ぶこの巻が思い以上に興味深く、次ぎの巻の展開を楽しみに。
(Y)
「紅はかうなつかしきもありけり」若紫は一段と美しくなり紫の君になり、袿の上に桜の細長の襲をなよよかに着こなしているのをみて、源氏は「いみじう」大へんすばらしい、うれしいと心より思った。お歯黒はまだしていないが、薄化粧してますます輝いて美しい人となりました。源氏は末摘花と関わったことを後悔して、どうしてこんなにいとおしい紫の君を放っておいたのだろう、と胸の痛みを感じながら紫の上と雛遊びをする。紫の君は絵を描いたり、色をつけたりして遊んでいるのを見て、まろもつられて絵筆をとり一緒に楽しんだ。そして長い髪の女を描いて、末摘花そっくりに鼻も赤く塗ってみる。鏡に映った自分を見て自画自賛、見とれていた。自分の鼻にも紅を塗ってみる。あの見苦しい鼻であったと思い浮かべている。そばで無邪気に笑っている紫の君。赤い鼻を消そうとするが、なかなか落ちなく心配している。そんな様子を楽しんでいる源氏。からかっている悪戯はないにしろ、大人げないことをしてはいけません。源氏らしくありません。冗談にもほどがあります。紅梅、紅の花がほころびました。紅の色をみると末摘花との結婚が気がかりであったと改めて心に留めた。末摘花は今後どう生きていくのでしょうか。幸せになってほしいと祈るばかりです。「蓬生」の巻で末摘花が再び登場するそうで、その先を楽しみにしています。
(祥)
「鼻の紅」
紫の君(若君)の生き生きとした可愛さ、美しさ、それを眺める源氏の胸中に渦巻く苦々しい悔恨。外面と内面、二つの思いの相違が、読者を愉しませつつ、端的に表現されています。自らの鼻を赤く塗り戯れる源氏。紫の君との遣り取りは軽妙かつ知的、躍動に溢れる洗練のきわみ。
二人を「妹背」と呼ぶ作者の筆の何と素晴しいこと!
そして、極めつけは最後尾の歌。
「紅の花ぞあやなくうとまるる
梅の立ち枝はなつかしけれど」
理由もなく移ろい続ける人間の心理の本質を作者は見据えている。そう感じられてなりません。
戦慄、畏怖。
脱帽して読むべし。
(サッシカイア)
2018年3月1日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者(敬称略)
8名
読書範囲: 末摘花 またの日、上にさぶらへば、台盤所にさしのぞき ・・・
見苦しのわざやと思さる。
参加者感想(順不同)
女君が新しい年を前にして、源氏に贈った着物と歌に対し、源氏は、今様の美しい着物をお返しに女君に贈って来る。
それに対し、女君付きの古い女房たちは、自分たちが贈った品々は、決してみおとりするものではない、と強く言いはる姿は、滑稽でもあり、悲しくもある。没落しつつある過程の中に、ゆずれない矜持を持ちつつ生きている一族。源氏がかかわることによって、少しずつ変化がおきるのか。
(孝)
ねび人が落ちぶれても、昔の価値観を第一に思っている様子がはっきりえがかれている。
末摘花が短い間にすごく変わったので、源氏は大よろこびした。
源氏は、返事をくれたのが夢のようだと思った。しかし、姫君に対する様々な思いもいっぺんに消えた。
(マスピー)
ねび人たちと末摘花、対源氏や命婦そしてこの時代を生きる人々との感性の差がこれからどうなっていくのか・・・興味深いが、今回の最後で側目より見て”見苦しのわざ”と感ずる源氏に、人間らしさを感じた。
(Y)
「末摘花」の全編、随所にちりばめられているユーモアとリアリズム。
源氏と姫君の対照、対比が巧みにデフォルメされながら物語を展開しています。
読み手を惹きつけ魅惑する作者(紫式部)の手腕は畏しいほど。
また、あからさまではなく間接的に暗示される思念・情緒の何と複雑豊かなこと。
作者は読み手をどこへ連れて行こうとしているのか。そして、それはどんな意図によるものか。
読み進むほどに魅力が深まり、離れがたくなっていきます。
(サッシカイ)
式部はすでに末摘花の容貌を、源氏に見せている。もちろん読者も知っている。「その鼻は象の鼻のようで、先が紅い」と、これ以上ないひどい表現であった。
今回、年が改まったから、姫君の容貌が「すっかり変わったかも」などと源氏に勝手な妄想させて、再びその容貌を見せるのであった。
口おほひの側目より、なほ、かの末摘花、いとにほひやかにさし出で
たり。見苦しのわざと思さる。
相変わらず「いとにほひやかに」鼻は紅い。見苦しい顔である。あえて再びこれを言うために見せたのか。
(TK)
白き紙に(恋文に使用する)捨て書いたまへるしもぞ(強調)
内裏と故常盤宮邸のかけもち女房の命婦が宮中に出仕した。台盤所(女房たちの詰所)にいる命婦に「くはや。・・・」それとかほいとか手紙を投げたり、三笠山のをとめなど、お口の悪い源氏、許せません。ちょっと乱暴な源氏。まろだっていろいろ気をつかい苦労したんだよと言いつつ、ついつい態度に出てしまう源氏。命婦はその手紙を姫君に届けると、女房たちは(姫君と一心同体)手紙を見て源氏の気持ちを思いやり、書もしなやかで美しいので女房たちは見とれてしまう。字の上手な方は得ですね。
新しい年明けを姫君はどのように迎えただろうか気になる。こんなやさしい源氏も有り。そして姫君や女房たちも男君をお迎えする準備(気持)がでてきたようだ。きっと美しくなっているだろうかと胸をふくらませていた。命婦と源氏の関係(?)が面白く、ねび人どももでてきて尚面白く、私は旧家の良いところをかいま見ました。
見苦しのわざやとおぼさる。
なんと悲しい結末だろうか?がっかり肩を落とした源氏。
姫君に着せたいと思いめぐらしながら、贈った着物を着てお迎えしたのに、源氏は姫君からの手紙できっと美しくなっているだろうと胸ふくらませていたのに、それもつかの間の逢瀬で、源氏を見送る姫君は扇で口を隠し、その端からチラッと見えた紅い花(鼻)。
昨日名曲のアルバムで「愛の喜び」を聴いた。愛は一瞬で悲しみが続く。何か源氏のようだ。
(祥)
2018年2月1日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者
8名
読書範囲: 末摘花 年も暮れぬ。・・・
・・・いと恥づかしくてやをらおりぬ。
参加者感想(順不同)
末摘花の源氏への贈りものの件で、命婦の源氏への気持ちがよく表れている。
源氏は人間が良いと思った。
(マスピー)
心なし姫君の常識はずれの贈り物、恋文の使いをする命婦の言葉の巧みさに感心する。
姫自身が非常識だと感じていないことにはあわれさを感じる。
(Hiro)
末摘花は源氏のお眼鏡にかなう女性ではないことを、式部は事ある毎に示唆していたので、読者はすでに承知しているのだが、源氏だけがそうではないと思い込んでいた。ここにきてやっと、次の歌を相手の文の端に手習いのように書くのである。
「なつかしき色ともなしに何にこのすゑつむ花を袖にふれけむ」
源氏物語は、恋心を伝えたり、相手をなじる歌が多いのだが、この歌は誰に向けたものではなく、思わずつぶやいたもので、調子もよくいい歌だと思った。
(TK)
年の暮れ、内裏の宿直所(桐壺の更衣が使用していたところ)に命婦はやって来ました。源氏と命婦の間柄は、親しい関係だった。源氏物語のほほえみはしのび笑い。姫君の手紙を取り出して源氏に渡した。源氏は姫君から手紙など期待していなかったので、わくわくドキドキ、やっと手にした文。源氏は嬉しかった。その様子を命婦は見て、胸つぶるまろはどんなお顔をして手にして下さるか、はらはら心配だった。文の歌も理解できず、衣筥の品もパッとしないので、源氏をがっかりさせた。姫君の身分が高かっただけに残念。末摘花の気持ちは、元日に着てほしいとなんといじらしい健気な末摘花よ。手を添えて教えてくれる博士がいたらと嘆く。命婦は姫君のことを詰られても姫君の味方は確かだ。
どうしてこんな衣筥をお見せしたのか恥じた。相手に贈りものの厚意は真面目で、末摘花はお手本を示している。美貌であることにこしたことはないが、持って生まれた風貌に面白可笑しく貶したり、弄るのはどうかと思う。
文は会話の手段であるのです。
(祥)
2018年1月4日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者 7名
読書範囲: 末摘花 御車出づべき門はまだ開けざりければ、・・・
・・・ともののをりごとには思し出づ。
会の終了後、場所を移して、中華街で新年会をする。美味しい料理がたくさんでて、みな満足したと思う。
参加者感想(順不同)
末摘花の暮らしぶりが、いかに困窮していたか、雪の降った朝の源氏が邸を出立する時の描写でつまびらかに書かれている。
そうした中、源氏がそれをうとむでもなくやや同情した様子が描かれている。
作者紫式部の目と、源氏のものの見方が、対照的。(孝)
下の人々の貧しい生活の描写からこれで雪降る季節が乗り越えられるのかと・・・。身分が高くてもどうすることもできない経済の現実を脱出する手だては・・・。心やさしく思いやりのある通い人だけだったのか・・・。(Y)
王朝びとは、すぐ泣くなあと思っていた。それも、こんなに恋しいのに、あなたはつれないとか、色恋ざたで泣くのが多い。
雪の朝、源氏は末摘花のところから帰ろうとすると、門が開いていない。「翁のいといみじきぞ出で来たる」翁は門を開けようとするが、開けられない。娘か孫かも出てきたが、みな相当に貧しそうななりである。
それを見て、源氏は歌をうたう。
「降りにける頭の雪を見る人も 劣らず濡らす朝の袖かな
『幼き者は形蔽れず』」
源氏は、老人の貧しさに同情して泣いている。こんな泣き方もするのだ、と思った。(TK)
末摘花と空蝉
同じ境遇で風貌もよく似ている。身分は違うけれど空蝉はおもてなし上手であった。それは立ち居振る舞いが上品であった。源氏はもっとコミュニケーションをしておけばよかったとつくづく残念に反省している。意志の伝達ができなかった。
当の空蝉は末摘花と違って、よく自分を心得ていたので、源氏の思惑通りにはいかなかった。
原文は本当の源氏物語、リアルであり絵巻では絶対に表現することはできそうにないと思う。四季こそ源氏物語、雪、寒さ、上下の人々にもやさしい源氏。(祥)
「とろぼふ門」
第2段
雪の美しさ。「末摘花」をつらぬく美の世界は白楽天の詩文にまで広がります。我が国の文学・詩歌が受けた中国からの影響の大きさにもあらためて気付かされます。
第3段
人間的な慈愛ともいうべき源氏の配慮、心づかいが印象的です。しかもたんなる「良いひと」だけではなく、嘗ての苦い恋の記憶(空蝉)を思い出すところなど、人間の弱さをも兼ね具えており、陰影ぶかい描写となっています。(サッシカイア)
年寄りの着物及び貧しさによる暮らしのひどさ等の表現は、源氏が上下まで暮らしの全てを援助する為の前提だったのではないか?
そう思うと源氏の人柄が思われるではないだろうか。(安心した。)(マスピー)
2017年12月7日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
出席者 10名
読書範囲: 末摘花 見えぬやうにて外の方をながめたまへれど、・・・
・・・なだらかなるほどにあひしらはむ人もがなとみたまふ。
参加者感想(順不同)
式部の憧れの女性像とは、まったく対極にある女性、没落した貴族の姫君の顔などの身体特徴や衣服などを、これでもかこれでもかと”異形”に描写している紫式部の筆致に驚く。(Niro)
かなりきびしい言いまわしではありますが解説には、「それは姫君の源氏に見せた初めての意思表示であった」とありますが、今後また姫からの意思表示があると思って良いのでしょうか?
「亡き父宮の魂が自分を導いたせいなのではないか」という処には非常にほっとしました。(マスピー)
常陸の宮の姫君は何歳なのだろうか、一番疑問に思っているのでいろいろ調べてみましたが―。源氏より少し年上なのだろうか。いや若い姫君だとわかりました。源氏が胸つぶれるくらいがっかりした。しかし姫君のことが気になって面白半分に接しているわけではない。「頭つき髪のかかりはりしもうつくしげに」と美しい髪は見事でしたが、黒貂の皮衣には追い風の香がたきしめられていました。冬の寒い日に姫君の顔を見たので、寒さで鼻が紅だったのでしょう。痩せていて顔も青白く紅のお鼻が目立ったのだと思う。寒くて口も閉じていたが、源氏の努力で少し反応してはじらいをみせ、それが精一杯の意思表示。心を開いてくれたらと願うがもう我慢できず歌を詠む。朝の雪の光の中で心を開いてくれたらと。姫君の反応は「むむ」とうち笑う。はじめて源氏に示した言葉のない表現だった。紅は赤なのだ。作者は顔立ちや振る舞いをこれでもかというように細かく表現しているが、もう少し掘り下げて深く色を書いてほしかった。たとえば染色の彩りなど。
寒さと雪の風情と重なってなだらかにあいずちするような姫君であって恋がしたいと思う。麗しい人許される人姫君と一緒に添わせる故常陸の宮の魂に導きかけたのではないだろうか。雪の白さと貧しさと寒さと姫君の鼻のこと。頭の中将は知っているのだろうか。(祥)
末摘花を描く式部の心の内は・・・。
読み手がどう姫君をイメージしてくれるかを、想像しながら楽しみながら書いている気がしてくる。今まで出て来た物語の中では見えなかった衰えてしまった貴族の現実をこの物語の読者は多くを知らないのではないかと・・・。私は思ってしまった。(Y)
源氏がはじめて末摘花の容貌を見たときの描写がすごい。驚くほど背が高く、座高も高い。鼻は先が垂れて赤くなっている。仏教伝来の象のようだとも。
異様な様子に、源氏はおどろおどろしき様に驚くのだが・・・。
しかし女の品をさす髪は、なかなかとカバーすることも忘れていない。
美の常識の領域をはるかに超えてはいるが、そのことを、劣っているとも恥ずかしいとも欠点であることとして全く意に介さない末摘花。
異様ではあるがなぜか源氏は、心ひかれていく様子に、これからの末摘花との絆がどうなるのか私の興味をひく。(孝)
「雪の朝」第2段および第3段
姫の容姿(すがた)が遂に明らかになります。作者は客観的な描写を装いつつ、誇張法を縦横に駆使し、読者の関心と興味を引きつけて離しません。唯一、黒髪が美しいと述べているのも紫式部の怖るべき手腕。
すべてが醜いのではなく、たった一つ美点を提示することにより、他のすべての醜悪さ、異様さがいっそう際立ち、真実味を帯びます。
姫自身には、落ち度も悪意もないのに。
何と哀しいコメディー、否、人間の真実を凝視(みつ)める眼。
「よろぼふ門」第1段
場面の切り換えの見事なこと。
現実と空想の間を行き来する光源氏の美意識、内省、秘めたる恋、禁じられた恋。
(サッシカイア)
雪の朝、源氏がようやく末摘花の姿を見える処まできて、後目で見ると、座高が高く胴長なのでがっかりする。それからさらに顔の描写は異様な鼻に及ぶ。
「うちつぎて、あなかたはと見ゆるものは、鼻なりけり。ふと目ぞとまる。普賢菩薩の乗物とおぼゆ。あさましう高うのびらかに、先の方すこし垂りて色づきたること、ことのほかにうたてあり」
全くひどい書き様である。つまり象の鼻のようだと言っている。さらに、鼻は高く広く伸びて先の方が垂れ下がって赤く色づいている、とまで書けば、もうどうしようもない。全く救われない顔に、紫式部は源氏も読者も驚かす。物語作者の醍醐味であろうか。心理描写ばかり続くので、辟易している読者は、一気に目が覚める。しかしいくら何でも、象の鼻はひどい。(TK)
2017年11月2日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
読書範囲: 末摘花 なほ頼みこしかひなくて過ぎゆく。
・・・・・・・・
・・・あながちなる御心なりや。
参加者感想(順不同)
朱雀院行幸の準備で気忙しく末摘花のところへはおぼつかなしになっていた。捨てられた状態で御無沙汰しているところへ命婦が訪れ姫君の心境を伝える場面、若いと経験もないので、つい我がままになって残酷になった。ありのままを表現するのはむずかしく紫式部は見窄らしい故常陸の宮の邸や姫君の生活をわかりやすく説明している。先日先生のお誘いで能楽堂でお囃子のワークショップで解説と演奏を鑑賞した。笛、太鼓、いつも耳慣れているのでスーッと体に入り、能装束も目を見張るほど豪華で源氏香の襲着も素晴しかった。又昨日は11月1日古典の日厨子の芸術祭に出かけた。
原文で楽しむ源氏物語(源氏物語の交響)光源氏と女君の奏でる世界を聴いた序幕に笛の音、続いて原文の音読そして現代語訳の語り(空蝉、藤壺、夕顔、末摘花、小春日和にふさわしくルンルン気分で帰ってきたが余韻がたっぷりなかなか眠れなかった。
今日になってもまだ楽しかったこと連日の源氏物語の学習が私の生きる目標になった。
かろうじて明けぬるけしきなればもう原文で味わうしかない末摘花と話をしたい一心の源氏。早く源氏の前においでなさいと女房たち、素直に出ていらっしゃいと言い聞かせる。姫は少しずつその気になったようだ。(祥)
だんだんとクライマックスに近づいてきますね。
当時の貴族の生活の一端も見え、おもしろい。末摘花との対面が、「雪の朝」になるのがすごい設定だと思う。
源氏のあわれの心がしみてくる。(桜子)
「官家の御達」
第2段: 命婦の訴えに対する源氏の返答の面白さ。短いやり取りの背後に繊細で屈折した心理が交錯していること。
横浜源氏の会
2017年10月5日(木)14:00-16:00 於:横浜男女参画センター
読書範囲: 末摘花 二条院におはして、うち臥したまひても~
・・・秋暮れはてぬ。なほ頼みこしかひなく過ぎてゆく。
参加者感想(順不同)
暫く介護等で教室を欠席していたが、久々先生の解説、皆さんの議論を聴き、一気に「紫式部の世界」に引きもどされた。(ヒロ)
「御粥、強飯召して」のところで、平安時代の食事の説明があった。着物や住まいにくらべて食事の描写が少なく、何を食べていたのか書かれていないので、著者も食事については書くべきほどのことではないと思っていたのだろう。かなり粗食で、一般庶民とさほど違ったものを食べていたのではないのではないか、と勝手に想像した。新発見であった。(TK)
源氏の仕事ぶりをうかがい知った。
「いかに思ふらむと思ひやるも、安からず」の姫君の気持ちを思いやると落ち着かないというところに、源氏の気のまわしようの良さ・優しさを感じた。(桜 柏尾)
「後朝の文」
第1段 前夜のクライマックス後に流れる間奏曲。頭の中将との親しげな間柄が読者の心
を和ませます。
第2段 交わされる歌により明らかになる姫の未熟な筆づかい、文・手紙への無知。式部
の描写は残酷なほど。誇張+細部の観察=凄い!
「官家の御達」
第1段 対象(コントラスト)の面白さ。
フィニッシュ「秋暮れ果てぬ」芭蕉を思わせる侘びさびの味わいが感ぜられます。 (サッシカイア)
男女の仲にうとい末摘花は、源氏との一夜の邂逅から、あわただしく結婚のスケジュールが、進めらていくのに対し、人々の期待からずれ、光源氏からもうとまれてしまう。しかし末摘花の心の中は、静かにしかし着実に変化して来る。
どう変化し、源氏がそれにどう応えていくか、いかないか、楽しみ。(青)
2017年9月7日 横浜市市民活動支援センター
曇り。蒸し暑い。狭いディスカッションルームは聴講者であふれかえる、熱気。活気。講義は、源氏物語のなかでも一風変わった末摘花の巻。受講者の間からさまざまな意見が飛び出す。講義後は五階に上がって、コーヒー片手に楽しい歓談タイム。
【末摘花】52頁~63頁
命婦の手引きでなんとか常陸の宮邸を訪れ、廂の間に通された源氏であったが、男との逢瀬に慣れていない姫君はおっとりとかまえている。邸にも緊張感もなく、年老いた乳母などは夕まどいする始末。さすがに若い女房たちは心化粧しているけれども。
源氏は襖障子の向こうの姫君に向かってさかんに歌を詠むが、一向に返しがない。イエスかノーか、返答をせまる源氏に対して見兼ねた乳母子の侍従が代わって返歌を詠む。「鐘つきてとぢめむことはさすがにて/答へむきぞかつはあやなきと」と。
やっと返事がきてうれしくなった源氏は、障子に向かっていろいろ話しかける。しかしまったく反応がない。苛立った源氏はついに障子をあけて、姫君の臥所に押し入ってしまう。
【感想】
末摘花のような、本来なら源氏の舞台に上がれないような女性を、どうして書いたのか、不思議に思う。(KT)
源氏の若さが思いのふくらんでいく様子が反応の無い姫君と比べることで一層浮かび
上って来る。
命婦の動きもなかなか……。(Y)
そそのかされて、いざり寄り近づく姫君の香の薫りに胸躍らさる源氏だが、相変わらず無反応な姫君。障子を押しあけて部屋に入ったが、姫君の「我にもあらず」の様子に驚いた源氏のところが面白く感じられました。(平茶良)
「手引き」(後半) 2017年9月7日
屋敷の様子は、現代にたとえれば、倒産寸前の会社事務所のよう。社員は、皆、てんでに行動し、トップ(姫)は本業に興味なし。そんな所へ忍んでいく源氏のひたむきさ。期待と想像は膨らんでいく。
一方、姫はイマジネーション・ゼロ。
この対比の妙。
仲を取り持つ命婦の不安。三者それぞれの心理の起伏が、短くも鮮やかに描かれています。面白い!(サッシカイア)
いよいよ命婦が源氏にせがまれて姫君をその気にさせて安心させる。その日がやって来ました。
末摘花は気が小さく、はずかしく、ひっこみじあんで、心構えがない。源氏が訪ねて見えるというのに、乳母だった老人は横になり、夕まどひ、うつらうつらして、若い女房たちは心化粧(相手によくみられたい)している。心を美しく見せる女房と正反対なのは姫君。命婦は末摘花の衣装にも気配りしているが、末摘花はぼんやりしている。源氏よりのお手紙にお返事も書かない。何んという姫君だろうか。何か理由があるに違いない。末摘花の心境をもっと知りたいと、源氏は廂の間より襖障子の奥の母屋にいる末摘花が膝をすすりながら近づいて来ました。えびの香の薫りの着物でしのびやかに???。源氏は有頂天になって喜びを伝えるが、姫君は何にも感じない。なぜだろう。口も開かず???。源氏の落胆振りは伺える。もう二度と訪れない。それは大へん。そこで侍従の若い女房が代りに返歌するが、辻褄の合わないのは当然で、源氏は末摘のことを普通ではない、もう我慢できなく襖間を開いて中へ。源氏はぶちきれた。進むしかない。そこで目にしたものは、命婦や若い女房たちは驚いた様子、末摘花も困った様子。源氏は呆れて邸を後にする。何んと後味の悪い思いをしたことか。命婦は源氏が帰ったのだなあと挨拶もしなかった。何んということだろう。源氏、命婦、末摘花、侍従(女君の御乳母子)が折りなす場面でした。(祥)
2017年8月3日(木)14:00-16:00 於:横浜市民活動センター
読書範囲: 末摘花 p39 秋のころほい、静かにおぼしつづけて~
p47 ~御茵うち置き、ひきつくろふ。
参加者感想(順不同)
「ものづつみ」「手引き」
姫君のキャラクター ― 内気で、引っ込み思案で世間知らず、そのうえ非常識なほど恋愛に無関心な人物像がくっきりと浮かび上がっています。難攻不落な城、あるいは登山者を拒むアイガー北壁か。今後の展開から目が離せません。(サッシカイア)
源氏と常陸の宮の姫君の様子を思うと、各々のからまわりしている日々がおかしいほどだ。
こういうキャラクターを設定する力量を思う。
当時しっかりした後見のない貴族の女性の生き方、その境遇の変化の激しさを教えられた。読者にとって世間を渡る指南書になったと思う。命婦の処世のみごとさ、さすがである。(桜子)
物語が書かれた頃、世慣れて有能、かつ生気ある女房がいたのだろう。末摘花と命婦の誇張されているとはいえ対照的な女性の関係と会話がとても面白い。末摘花にはモデルもいたのかも知れない。(アキラ)
源氏は姫君への手引きを命婦にしつこく頼むところと、命婦がその強引さに負け、手引きをすることになって廂の間に入れることに成功したところに面白さを感じました。
(平茶良)
源氏からの何度も便り(歌)が贈られてくるも女君は、かたくなに、返事を返そうともしない。完全無視の状態の中、なんとか先に進ませようと源氏と命婦は、会う機会を作る。それにしても、この女君のかたくなな態度は、なんか意図あってか、否か。(孝)
もの思いの秋、なんとなく悲しくなったりするころ、夕顔と過ごした板屋のことを恋しく思い出していました。常陸の姫君に恋文を書いて送っているのに知らん振りひたすら無視されている源氏。源氏が一生懸命になればなるほど相手にされずそっぽを向いている。いろいろ思わくがあるか、姫君だっていろいろ考えがあるでしょう。そこで命婦に相談するがお似合いではないと。源氏は信じない、逢って対話をしたいと思うところがいい。絶対に無理をしないから、姫君に対して気をつかうからと命婦を説得する。もてなしという美しい古語。先日友人とお茶した時、源氏物語で「もてなし」が語られているところはどこですかと質問されました。今日音読した「ものづつみ」の最後にありました。先の若紫の巻きも記憶しています。源氏の心には、おもてなしが身についているのです。源氏物語にはそのような場面があるのです。
源氏の手紙はそれは素晴しく美しいものであった。香でたきしめた和紙で字もあでやかで。その手紙を荒れはてた邸に使者が届けると下々の女たちも喜んでいるのに姫君は驚きあきれて手紙を見ようとしない。命婦は手引きは上手で、几帳越しに会ったらとすすめる。遅く出る月、午後10時~11時の月の出を待っている。
源氏物語では星はあまり出てこないのにここでは星がキラキラの夜源氏がやって来た。荒れはてた邸を月がきみ悪いほど照らしている。そのとき琴の音が聞えた。命婦はハラハラ不安に思いながらいた。源氏は荒れた邸など気にしないでいた。気軽なお出かけではないのでお断りするのは心苦しいと命婦。姫君はどうしたらいいのか奥に行ってしまう。世間づれしていない、いと若々しゅうあまり物づつみがはげしいので世なれていない。しかし経済事情でのんきにしていられないでしょうと言い聞かせる。姫君は仕方がないと素直に格子を閉めて、などわがままですね。(祥)
源氏は、命婦を責めたて、ようやく末摘花に逢うことになる。命婦は、琴の音を聞かせて、物越しに話を聞くだけで終わりにしようと考えて、姫君を説得する。物越しで話を聞くだけなら、格子を鎖して聞きましょうと姫君。つまり源氏を中に入れず、簀子(すのこ)に立たせたまま話だけ聞きましょうということになる。さすがにそれは失礼と命婦は「簀子などは便なうはべりなむ」と言って、格子を開けて廂の間に通して、障子(今の襖)を「強く鎖して」源氏を招じいれる。こうして、「強く鎖された」襖を隔てて、末摘花と源氏は向かい合うことになった。寝殿造りの構造がよく頭に入っていないと、このあたりの微妙は分からないところだ。
さてどうなるのだろう。(TK)
2017年7月6日 横浜市市民活動支援センター ディスカションルーム
)
【参加者感想】
末摘花(P27 ~38)
今日はこの会場に来るまで嬉しいことが二つありました。
1つは玉虫に出会ったこと。丁度玉虫色のイヤリングをしていた。偶然とは思えない
光りによって緑や紫色に見える厨子,帚木の巻で源氏が女性の手紙入れ筥を思い出して
います。もう1つは紅花の栞をいただいたこと。何とも上品で淡いピンクでした。
その淡いポツンポツンと爪弾く琴の音忘れられない貴公子、源氏と頭の中将の可笑しいこと。
頭の中将(近衛の中将)のことを責める。なぜか。美しい女の所へ忍び歩きしていることが
源氏らしくない。そして頭の中将に見つけられてしまう。
しかし優っているのもがある。かの撫子は頭の中将の子であることを右近から聞いていた。
それから両人はどうしたか---。各々それぞれ行くところ(もちろん女のところ)があったが
急に仲良くいい気になってそれは末摘花の女君の邸でかち合ったため,え行き別れたまわず
(不可能な助動詞)歌の話をしながら、一つの牛車で月がちょっと雲にかかったりする都大路
を笛を吹きながら大殿に向った。人目にかからないように先くれ、人払いも伏せて邸に入り、廊下で狩衣(袖口を紐でしぼる)から直衣(立ち袴)に着替え、今来たんだよというような顔をしてずーっと笛を吹きながら合奏を楽しんだ。
音楽は教養の一つであった大殿は大喜びで高麗笛を吹き楽曲が深まり快感を得た。
大殿は高麗笛の名手であった。(高麗笛は細くて竹製の笛。七つの穴があり高い音色をだす)
そして女房に琴を弾かせ美しい音色の合奏を楽しんだ。大殿は嬉しそうで源氏が訪ねることを喜んでいたが 葵の上はどこにいるのですか? ここで紫式部は琵琶の名手である葵の上の女房を登場させる。中務である。ここで源氏・頭の中将・中務の関係になる。
中務はたまにしか来ない源氏を懐かしく思う気持があり、好意を持っている頭の中将には振り向かず、大宮(左大臣の北の方で頭の中将の母)は思い悩んでいる。
皆が合奏を楽しんでいるのに中務はひとり離れている。
中務もどうしたらよいか悩んで苦しんでいる。
好きもの多くの女君、女房(召人)を愛しながら情をかける光源氏。
源氏と頭の中将はあの荒れ果てた邸で聞いた琴、美しくて、可愛いい人がひとりで寂しく暮らしている常陸の君の女君を思いだしています。頭の中将からみると源氏を見張っていなければとこのまま奪われてしまってはと焦っている。両人の心の葛藤。それから
源氏も頭の中将も常陸の宮の女君に文を出したが返事がきません。身分、育ちから返事を
出せないのか、書けないのか、恥しいのか、両人は心を探りながら競い合っているのです。
ここで少しわかったのは頭の中将は隠し事をしない。源氏は複雑な人(物事が色々絡みあって込み入っている)、頭の中将は甘い(旨い)言葉を並べてものにする。
得意顔で言い寄ったのに振ったようにされるのはたまらないと源氏は本気で命婦に相談する。命婦はあっさり源氏のお相手は無理です。と。しかし源氏は素直で子供のような
可愛いい人だろうと思う。ふとそんなとき夕顔を思い出していた。
男性同士の張り合い、女性同士は? 進君「ありすぎて困る」と云っていた。
★コーヒータイム(5F)
・田中先生より楽器に触れたときのお話をして下さって興味深く増田さんにアドバイスなさっておられました。そして北九州・北陸各地を襲った線状降水帯がかかって被害がでていること、もう七夕さまにお願いして祈るしかありません。盛りだくさんのお話で楽しいひとときを過ごせました。
・今日は早めに会場に来てボードに七夕飾りをしました。
あまり派手にはしませんが気づいたかしら・・・。ちょっと余計だったかしら・・・。
七夕の由来は6世紀―8世紀とも云われています。ラブストーリーで中国の物語です。
又、今の若者の中では「涙をみせないピエロ」の歌があり、太陽も月も何も見えない。
平安王朝・貴族社会の時代とは違った現代です。明日7月7日は小暑(やや暑熱を催す)。
・日の出町駅より徒歩の下川さん汗を噴き出してみえました。着いた途端、椅子の用意をお願いして御免なさい。今日はお休みの方も多く、どうぞ気をつけて次回はお元気で参加なさることを期待しています。そしてお茶の御菓子は増田さんからの美味しいケーキをいただきみなさま思わずホットされた時間でした。
・6/25(日) 田中先生の八雲オーケストラの演奏会へ荻窪まで行ってきました。ビオラを持って晴れやかに入場なさった先生。少女のようでした。素晴らしい演奏を聴くことができ嬉しく思いました。
◎源氏原書講読会のあとお時間の許す方は、引き続きコーヒータイムにも是非ご参加ください。 楽しい懇談の場ですよ。
祥
末摘花をめぐって源氏と頭の中将とのライバル意識が面白く思えました。
(平茶良)
話の起伏・展開の意外性・面白さに魅了されました。
大殿での笛吹きのたわむれ。デュエットがトリオに。
トリオから大きな調べへと膨らむ変化は胸がときめくよう。その合間に置かれた中いう
絶妙なアクセント。
プロットに人間の心理のあや が加わり、複雑かつ重層化されていく
恐るべき物語の愉悦です! (サッシカイア)
源氏と頭の中将の末摘花をめぐって心をめぐらすところ、張り合うところに
面白さを感じる。月の美しい夜に楽器を奏でる様が美しく感じられました。 (香)
源氏が頭の中将との男同士の張り合いが非常に興味深い。 (マスピー)
頭の中将と源氏が常陸の宮邸で出合い驚く。それから先の予定もやめて
若者が同じ牛車で笛をかなでる夜が美しく若々しく感じた。 (Y)
頭の中将と源氏、若い二人が同じ女君をめぐってそれそれ心騒がせる場面。
身分制度の社会、上流貴族と言われる二人・・・案外対象となる範囲が狭いのか・・(孝)
以上
2017年6月1日 横浜市市民活動支援センター
ことしも暑い季節になった。暑さに負けぬように気合いを入れて講義に臨んだ。話も新しい巻の「末摘花」に入って2回目、いよいよ面白くなってきた。
【末摘花】14頁~27頁
大輔の命婦が何気なく口にした故常陸の宮の姫君に興味を惹かれた光る源氏は、十六夜の月が明るい夜に姫君の邸を訪れる。そして、姫君の琴の音をきかせるようにと強い口調で命婦に迫る。命婦は、仕方なく姫君を口説き落としてなんとかして琴を弾かせることに成功する。しかし、姫君はすぐさま弾くのをやめてしまう。存分に聞かせては源氏の熱がさめてしまうだろうという命婦の判断である。
もう少し琴の音を聞きたいと思ったものの、ひとまず源氏は引きあげることにする。そのとき、透垣の所で寝殿の様子を伺っている者がいることに源氏は気づく。なんと北の方の兄の頭の中将ではないか。源氏がどこへいくのか気になって、宮中から後をつけてきたのだが。
【感想】
命婦のあわてぶり、気っ風のよさ、気転と源氏とのかけあいもあり、面白い。頭の中将とのかけあいもあり、ここは人の気持ちのあちこちがみえ、面白い。(桜)
「常陸の宮の姫君」
若い命婦の姿の何と生き生きとしていること! 源氏と姫君との間で右往左往するさまの可笑しさ。源氏と交わす会話の自由な雰囲気。笑いながらも、生身の人間の動きを見ているような臨場感を覚えます。
「好敵手」
頭の中将と源氏の間で交わされる歌の見事なこと。十六夜がきちんと折り込まれた中将の呼びかけ。源氏の返歌は、月そのもの、普遍へと高まっています。詩的感動をしみじみ味わいました。(サッシカイア)
姫君をめぐって源氏と命婦のやりとりする様子が面白く感じられ、また帰らないで寝殿の方へ向かって、透垣に身を寄せて、頭の中将とのやりとりにも面白く感じられました。(チャ・ランポアー)
大輔の命婦は色気づいていたり、利発な魅力的な女房であり、源氏との軽い言い合いも面白い。頭の中将のふるまいも含めて、作者はこの巻を狂言、喜劇の人間模様に描こうとしているのがわかる。(アキラ)
ストリーテラーとして評価の高い紫式部は、同時にキャラづくりの名手でもあった。なかでも、「末摘花」に登場する源氏の乳母子の大輔の命婦は、その独自性て群を抜いた存在だと思う。若くて美しく、「いといたう色好める」女性としても宮中で評判の女房であった。かてて加えて、一所に留まらず、あちこちの邸に仕えたというのは、いまでいうフリーランサーだね(ランサーというのは槍持ちのことで、中世も末期になると、かつては一君に忠節を誓った槍持ちも条件のいい君主に自由に仕えるようになった)。身分社会にあって、源氏との気さくなやりとりに見られるような、いかにも自由な人柄は、「源氏物語」のなかでは出色のものだ。(とんぼ)
常陸の宮の姫君
命婦は軽い気持で姫君を紹介したの「のたまひしもしるく」源氏がおっしゃった通りおいでになりました。ほぼ満月と同じような美しい十六夜の美しい月が昇るころ、源氏はうきうきしながら姫君の琴を聞きたい一心で常陸の宮邸を訪れた。「むなしくて帰らむが、ねたかるべきを」ただ一声でもと姫君の寝殿に案内した。姫君は梅の香ききながら月を眺めておいでになった。源氏は月を愛でながら胸ふくらませて期待していた。命婦のたくらみに気がつかず、姫君が琴を弾こうとすると、命婦はあわてた。なぜだろう? 名手の源氏に聞かせる程のものではないので、ほんの少しつまびいた。命婦ははらはらして胸がつぶれるくらい困ってしまった。少し命婦のサービス精神が行き過ぎたようだ。源氏は昔のことを思い出しながら、荒れ果てた邸には美しい姫君がいる。姫君には不快な思いをさせてはと、源氏の懐の深さが伝わってきました。命婦もこれ以上琴を弾かせては無理と判断して止めた。源氏は不満である。姫君は気乗りしていないので、その場をつくろった。残念だ。命婦も源氏のことをいやみたっぷり云っていますが、源氏も負けていません。まろは姫君とおつきあいしたいのだ。源氏も気が多い弱点があることはわかっている。平安時代は恋ができない人は駄目な人になっている、命婦も少し云い過ぎたかしらと黙ってしまった。
命婦と源氏は対等なお友達のようで自由に遠慮なく云いあえる仲のようだ。身分が違うのに気がきく。宮中で活躍している命婦、乳母子惟光のお母さんより2番目の乳母子。
寝殿の方へ行くと、壊れかかった透垣からのぞいている頭の中将がいた。源氏のことが気になって、後を追って来た。仲の良い二人だが、お互い張り合っている。尾行していたわけではない、送って来ただけといいわけをする。二人共歌を詠む。当時の人は歌の世界で心を詠んでいた。親しければ、なを歌で表現していた。歌は客観性がないと出来ない。
隋身は(護衛)4人から女の元へ手引きしてもらってうまくいくことがある。忍び歩きは間違いがあるかもしれないと。いつも見つけられるのはくやしい。夕顔の娘撫子を知っていますよ、と右近から聞いていたから。(祥)
横浜源氏の会
2017年5月4日 横浜市市民活動支援センター
世間は黄金週間だけど、光る源氏には無関係だ。教室には扇風機がまわりつづけていたものの、とりわけ暑い午後だった。新しい参加者もあって、活気のあふれる講義となった。講義後、5階で恒例の楽しいコーヒータイム。論談風発なり。
【末摘花】6頁~14頁
長かった若紫の巻が終わって、新しく末摘花の巻に入って気分も一新。時系列でいうと、末摘花は源氏が若紫に会う前の話で、夕顔に亡くなられていつまでもその悲しみから抜けられない源氏。そんなとき、故常陸の親王の娘で、琴をよく弾くという姫君の話を大輔の命婦から聞き、興味を惹かれた源氏は、その姫君に会わせよ命婦に迫る。ぜひとも娘の琴を聴いてみたいものだ、と。それが末摘花だ。新しい恋の予感。
【感想】
脇役の面白さが話題になり、源氏物語の良さと感じた。すみずみまで、神経をゆきわたらせて、式部が書いていたのだと思った。命婦の仕事のかけもち(生きかた)は、興味深かった。(時)
「夕顔の面影」 甘美なメロディーで始まる「末摘花」の巻。音韻の美学に留まることなく、源氏の内面の陰翳を描く、流麗にして奥深い、思考と感情のシンフォ二―の湧出に浸りました。
途中、「いと目馴れたるや」と、物語の外側から聞こえてくる語り手の声。印象的な一閃です。
「大輔の命婦」は、進展する物語の序曲。命婦の描写に脇役ながら、若い女房の個性が立ち上がってきます。当時の自由な恋愛の様子もうかがえ、まさに「平安」な時代と感じました。(サッシカイア)
源氏は女性に対して飽くことなき探究心は同じだけれど、女君達にはそれぞれの置かれた、育てられた環境によって形成された感性は一通りではないのではないか……。(Y)
今日から「末摘花」の巻に入った。
源氏は、北の方、六条の女君など、〝心を開かず、競争心の強い女を好まず〟、気がねなく心を開き、うちとける夕顔の面影を忘れることができない。
また、故常陸の親王の末娘の噂を聞いて関心を持ち、大輔の命婦を通じて、この女(むすめ)に近づこうとする。
女性に対して、飽きることのない関心を抱き、女性の美しさを追求する源氏の心情が見ごとに描かれている。(雄太)
夕顔を忘れられない源氏は、色々な女性を想いうかべ、自分の理想の女性を求めようとするところと、また大輔の命婦から常陸の親王の娘の話を聞き興味を持ち、命婦に手引きを命じるところに、今後の展開に期待を持ちました。(チャランポアー)
「末摘花」という父と生き別れ、人との交わりに不器用で引っこみ思案な娘。またユニークでこんな女性もたくさんいただろうキャラクターの登場。作者はよくいろいろな人物を作っていくものだと思う。色好める大輔の命婦との組み合わせも面白い。(アキラ)
乳母子の歌
光る源氏には何人か乳母子がいたけれど
(源氏と一緒に育てられた乳母の子どもたちだ)
実は
平民のわたしにも乳母子がいた
乳が出なかった母は
わが子を近所のおばさんに預けたのだ
ここまでは珍しい話ではないけれど
ある日
赤ん坊を大阪に置いたまま
いきなり
九州に
行ってしまった
父の転勤で
五十年後
ごめんねと
母はいったけれども
古稀をなんとか越した孤独なこんにゃく男は
ときどき思うのだ
(蚕のように)
わが乳母子はいまごろどこでどうしているだろうかと
(詠み人知らず)
今日から末摘花
夕顔のことが忘れられない。思っても思っても飽きない、はかない、先だたれ、突然だったので、ショックも大で、立ち直れない。年が明けても、その悲しみは一生忘れることができない。やさしい源氏だから
源氏は、藤壺(初恋の人)や六条御息所、空蝉、軒端の荻、夕顔の女君を相手にして来た。北の方(葵の上)の外に上の品の女房や中の品の何人もの女君など、気位が高くて心を開くことができなく、打ちとけられなくて、以前は姫君であっても、今は中の品の夕顔とは心が通じ合って、何かと強引だったが、源氏に寄り添ってくれた夕顔のことを思い出していた。それほど受けとめてくれた夕顔、まろを信じてくれた夕顔があわれ愛しい。
源氏は「いかで、(疑問に)ことことしき……」気位が高くなくて、夕顔に対して自由にでき、打ちとけて対話ができた。そんな女君が好きだ。夕顔のような女がどこかにいるはず。今まで何人もの女君を思い出して悩んでいた時、惟光の母(乳母)の次に大切な乳母の女(むすめ)大輔の命婦のお世話で故常陸の親王の末の女(むすめ)と会うことになる。
どのような展開になるのか、どのような女(むすめ)だろうか。作者は末摘花(紅花)にたとえたところが面白そう。
常陸宮の晩年の女(むすめ)で可愛いくて可愛くて、(ろうたし)よりももっと可愛いい女(むすめ)がひっそり荒れ果てた邸にさびしく過ごしていることを語り出したので、源氏の心が動いているが、なかなか出しおしみしてもったいぶっている。命婦のじれったさに我慢できず、姫君の琴を聞いてみたいと高揚し、朧月夜(十六夜)に常陸の宮邸に出向いた。人をたずねるのは朧月夜がよい。さて、その琴の音は?(祥)
横浜源氏の会
2017年4月6日
お花見のシーズンとはいえ、桜の開花はまだ4分程度。でも、横浜では20度近い気温を記録し、桜の開花もいっそう進んだはず。講義はようやく「若紫」の巻を終え、次回からは「末摘花」に入る。
【若紫】153頁~165頁
恐怖と不安のうちに突如二条の院へ連れて来られた若紫であったが、源氏の君の細やかな心遣いと応対で次第に落ち着きを取りも出し、心をひらくようになっていった。源氏から書や歌の手ほどきを受け、同い年の子供たちと遊ぶようになり、将来の明るさと可憐さを取り戻していった。ようやく、二条院に静かで幸福な日々が訪れるのであった。
【感想】
祖母の住居(すまい)から、明日は父方の邸に引き取られるというタイミングで、源氏に、四の五の言わないうちに連れ来られた二条院。恐怖の夜を過した翌朝、源氏に起こされた女君は、目にするすべてのものが、うらぶれ果てていた祖母の所から一転、めずらしく、美しいと感嘆する。そして恐怖心もうすらぎ、笑みもこぼれる。それを見て源氏は、今まで以上に可愛いと思う。
大人目線でみると、この急展開には、少々違和感を感じるところであるが、さすが紫式部、疑問をもつ輩のいることも百も承知で、最後に一言、「はかなしや」の一言を文に添える。紫式部の配慮に感服です。(孝)
「若紫」が終わり、いよいよ源氏のへんれきが興味深くなりました。若紫の利発さとしっかりした保護者(親権者)を失うと大層なお姫様もたちまち落ちぶれると知り、びっくりです。若紫はかわいいね――。(桜子)
源氏と若紫の関係がある時は幼く、ある時はするどい直感がのぞいたりして、ここぞ式部の作品の魅力かなと、大人っぽい部分と幼い行動がおもしろく感じた。(Y)
荒れ放題の大納言邸から、今を時めく源氏の邸へ連れてこられた若紫は、とまどいつつも、新しい環境に慣れ、源氏の愛を受入れてゆく。その様が見事な筆致で描かれている。
いささか異常とも見える源氏の若紫への愛であるが、ひとつの特異な愛の形が現実感をもって語られている。(雄太)
二条院に連れて来た紫に、内裏にも行かず、書など教えたり、ひな遊びをしながら、思いどおりになっていく紫に、満足をおぼえ、源氏に安心し切って心を開いていくところに、やれやれ、思いどおりになったなと思い、興味深く思われました。(チャランポア)
紫の上が父宮の元に行って、つらい生活をするよりも源氏の元にひきとられて、きみょうなかかわりであるが、幸せになってくれれば、それでよいけどな……と思った。(N)
深夜、なにも知らされずに、いきなり源氏の二条院へ連れてこられた幼い若紫の胸の内を思うと切ないものがあったけれども、源氏のやさしい配慮と対応とによって普段の落着きを取り戻した姿を見てほっとした。それにしても、若紫の巻は神経によくない。いまだに好きになれない一巻だ。常識にとらわれた、わたしの読みが浅いのだろうか。(とんぼ)
源氏は少女と少納言を風のように二条院へ連れて来ました。広い庭園の石など宝石のようにかがやいて、室内の飾りも美しかった。荒れ果てた少納言の邸とは違っていた。何がなんだかわからず早く慣れてくれるようにをかしき絵をみせたりすると、絵をみながら「いとうつくしきに」可愛い、愛らしい笑みをみて源氏は和む。少女にとって二条院は珍しいものばかり。源氏は付き切りそばにいて、御屏風絵をみせたりして過ごす。たった一日で馴れてしまった様に、「はかなしや」と語り手はいう。やっぱり無邪気な子どもですね。とりあえず目の前のことがうれしそうだ。内裏へも、葵の上の所へも、仕事にも、ほかの女のところへも行かず、手習の紙をみせて、わけがわからないのに墨の筆の美しい字にみとれる。
まだ寝てはいないが、露分けても会えない人、そのゆかりの少女に返歌を求めたが、「わたしは書けないわ」。その顔がまた可愛い。返歌で答えるのが礼儀ですよ。少女は源氏を見上げながら袖かくして書く様子が、その姿がなんとも生々しい。無理に上手に書かなくてもいいんだよ、思ったままで――。ほのぼのした情景、少女は賢く、たどたどしいが、尼君に似て才能がありそうと源氏の心は躍る。雛遊びなど興じながら幸せな時を過す。少女のまっすぐな性格をはっきり作者は書いている。動作は子どもっぽいが、芯はしっかりしている若紫。わけがわからないが、素直なのだ。源氏は子ども扱いをしていない。身代りなのかしら。紫、藤壺の。この歌は素直で、もっと歌は技巧をこらしたもの。歌は身分にとらわれない。人と人として、平安朝の人たちは許されていた。少女を君と呼ぶようになった。少女のいない大納言邸に少女の父君がやって来ました、女房たちは何とか辻褄を合わせて少納言が連れだしたと告げ、父君はあきらめて帰って行きました。北の方も連れて帰ってほしいと思っていたのが、当てが外れたようで、果してそれがよかったのかどうか。何ともいえません。北の方の娘の女房として、使用人として利用しながら、自分の思う通りにするつもりだった。尼君が父君の方へやりたくなかったのがよくわかる。
二条院で過ごしている少女はだんだん遊び相手もふえて元気になっていったが、時々尼君を思い出して泣く。しかし源氏と一緒にいることに気付き、源氏と自然体にほほえましく過ごせるようになった。今までとは違った父親のように――恋人のような。
昨年の3月より読みはじめ、4月6日、桜の満開の横浜で1年がかりでゆったりと堪能できました。源氏物語絵巻の若紫の巻では桜の場面が数々あります。幼い姫君への愛が実った若紫の巻でした。
田中順子先生、御指導、有難うございました。参加して下さった方々、御協力有難うございました。先生の京都のおみやげ「じゃばらアメ」御馳走さまでございました。(祥
横浜源氏の会
2017年3月2日 横浜市市民活動支援センター
雨催いの日で、夕方には天気予報どおり小雨になった。しかし、講義の方はひさしぶりに新しい参加者もあって、楽しい時間となった。講義のあとは、5階にのぼって恒例のコーヒータイム。おしゃべりにくつろぎのひとときを過ごした。
【若紫】141頁~153頁
妻のいる大殿の邸を訪れたものの、いつものことながら女君の対応はひややかで源氏としては遣るかたない。そこへ若紫の邸へ行っていた惟光がやってくる。そして、明日、父君が少女を引取るため迎えにくるという。それを聞いた源氏は、素早く行動に出る。すなわち、夜明けを待たず、惟光を連れて少女の邸に向かう。邸に着くや、強引に車を中に引き入れ、戸を叩かせる。事情をつかめず、慌てふためく少納言や女房たちにおかまいなく、源氏は寝屋に入ると少女を連れ出し、二条へ向かう。わけもわからず、少納言は取るものも取りあえず、その後に付き従う。
【感想】
常識を破る。物語文学。
若紫の巻。今回も古語を通して臨場感あふれる、手に触れるようにあざやかな先生の講義だった。(N)
知識、教養をそなえ、倫理、道徳にも通暁している源氏が、内面の葛藤の末に少女の略奪を決行してしまう「狂気」の沙汰。
純粋な思慕、願望をつきつめていった果て、限界を超える行為と情熱が、細やかな筆致で描かれています。時代を超越した人間の本質(追求する行為が限界を突破してしまうこと)を感じた、ひとときでもありました。(サッシカイヤ)
若君をさらい結婚してしまうという、常識や世間体をはばからぬ行為は、物語のなかで最もドラマチックなシーン。読者としては、世間そのものの気持ちと、掟破りの源氏の行為への喝采する気持ちがぶつかって心動かされる。(アキラ)
父君が引き取りに来ることを惟光から聞いた源氏の少女を連れ出し、二条院に連れて来る行動の早さ。そして強引さが面白く感じられました。ああ、やれやれー。(茶良)
少納言についても描写が詳しい。しかし、少納言の今後については保証されているような気がする。
少女の描写もよく現われている。少女から大人になるのが大変であることが良くわかる。(マスピー)
今日は会の様子を知る為に、見学ということで参加させて頂いた。和気アイアイの雰囲気の中で、何とかついて行けそうに感じた。入会したい。(TK)
十八歳の源氏の為したことは、若いエネルギーなのか、天皇の子と生まれ、臣下に降りた人の何事も思うままになるという生いたちか……式部の心の中をのぞきたい気分の今日でした。(Y)
連行、拉致、強奪、略奪、奪取、誘拐……なんといおうと、源氏の若紫を強引に連れ出すやり方は、非常に危うい。禁じ手といえば禁じ手といえるのではないだろうか。あえてその禁じ手を使った所に紫式部の並々ならぬ決意と、エンターテイナーとしての手腕がうかがえるのである。(とんぼ)
源氏は妻(葵の上)の元、大殿に戻って来た。妻に対面したが、相変らず冷たくされ面白くない。和琴(あづま)で口ずさむ。なんとも色っぽい美しい声であったとか。しかし嫌味たっぷりの歌になり、六条の女にも逢ってもらえず気持がくしゃくしゃしていた。惟光が少女ところから戻って来て、明日父宮が迎えに来ると伝える。源氏は今まで何をしてきたのか。父宮に渡してたまるものか。少女を連れだそうと決心する。しかし迷う。世間体が気になる。世の中ではしてはいけないことをしよう、事を起こさなければ自分のものにできない。この機会をはずしたら、後悔するだろう。後悔したくない。くやしい思いはしたくない。幸い葵の上がそっぽを向いて相手にしてくれないので、善は急げ。決意をかため、すぐ出かけるよ、と告げて惟光とともに少女の邸に向う。少納言を説き伏せ、少女のそばへ――少女は父宮が迎えに来たのかと思い込んでいる様子。さあ、目をさまして――こんなに朝霧なのに、目をさまさないのはないでしょう、少女はすやすやと眠っている――そして髪をとかして――声を聞いてびっくり、父君と同じ人です。少女は源氏と気がついたと思ったら、源氏は素早く抱きかかえ、少納言、女房を払いのけようとしたが、少納言も負けていない。仕える女房たちはどうなるのかと責める。少女は泣きだし、よろしき衣に着がえて少女と一緒に車にのった。夜も明けないうちすぐに二条院に着いたが、少納言は迷っている。すぐには降りない。無理遣り連れださなくても――渋っている少納言。源氏は「そは心なり――」しぶしぶ車から降りた。胸は張り裂けんばかり、今は涙を流してならないと我慢した。少女もおびえている。西の対に少女の部屋を用意するように惟光に命じ、少しづつ少女の部屋らしくなったが、少女は突然知らない場所に連れてこられて不安に脅えて体が震えているが、さすがに声を立てて泣かないで我慢した。少納言のそばへ行きたいとさびしく泣いた。少女の可憐さが何とも愛しい。少女から大人の女になる、しかしそれも道なれば……。
代表になってから2年、何かと慣れないものですから、昨日も若紫の巻で源氏の馴れ顔(いかにも心やすく)、慣れと馴れと辞典を見たしだいです。休憩なしで2時間、感想文も書き、充実した時間です。(祥)
横浜源氏の会
2017年2月2日 横浜市市民活動支援センター
寒い一日。風邪とインフルエンザが流行っているせいか、ちょっと出席者が少なかった。けれども、「若紫」もいよいよクライマックスに向かって田中先生の講義はいっそう熱くなって、寒さを忘れました。生徒たちも積極的に質問していた。講義後は、恒例のコーヒータイム。楽しいひと時を過ごした。
【若紫】130頁~140頁
尼君の四十九日の喪があけると、さっそく兵部卿宮が若紫を訪ねてくる。荒れ果てた邸を見た父君は、こんな寂しい所に取り残されて若君はさぞや心細い思いをしていることだろうと心を痛める。かねてより少女の養育を気にかけていた父君は、そこで少女を引取る決意を固め、その旨乳母に告げる。乳母には部屋を用意を用意するし、少女には遊び友だちもいて楽しいだろうと。
しかし、少女のためを思えば年頃になるまでもう少しこの邸にいる方がいいのではといって、乳母は兵部卿宮の申し出を断る。とはいえ、若宮を見るにつけ、不憫さが募るのをどうすることもできない乳母であった。
ある日、源氏の命を受けて惟光が乳母の邸を訪れてみると、なんと兵部卿宮の邸へ引越しの準備に大わらわであった。
【感想】
若紫を育てていた尼君がなくなり、にわかに若紫の周辺があわただしく変化することに。乳母は、源氏の若君(姫君)へのこれまでの思いと行動を、どう計っていいかわからない。立場上、養育の役を担おうとする父宮も、形式的で、それ以上の親しみが感じ取れない。乳母の微妙な心の動きをたんねんに追う作者の筆先が、さえて面白い。(孝)
若紫に対する父宮、乳母、源氏、そして亡き祖母等の温度差と、各々にゆれ動く気持ちとで物語りを複雑にしているような気がした。(Y)
少女(姫)の心、気持は、誰にも理解されず、少女を中心にして側の人々があたふたと自分の気持のままに動き、乳母の気持と、源氏の気持のままに、複雑な物語の展開、当時の人々の生きざまがおもしろく描かれていて、大変興味深く、作者の才能に脱帽する。(恵)
源氏の君の行いでまわりの者が振りまわされる様がわかる。
当時の生活の様式が少しわかった気がする。(マスピー)
「父宮の訪問」
父宮(男性)の無神経さ、物事を表面的にしか見ない思慮の浅さが発言の端々に現れています。社会的、経済的……あらゆる面で弱い立場に置かれていた女性からの視点で描かれている。作者が女性であることの意味が深く感じられます。
「乳母の立場」
前半のゆるやかなテンポから後半の急激な加速。テンポの変化が魅力的ですね。(サッシカイア)
源氏と一夜すごした後の少女(紫)の処遇をめぐる父宮と源氏の行動。また、先々を気づかう乳母の心境が語られ、少女の行末がどうなっていくのか。少女のもとへ通うべきかどうか迷う源氏の心境にも興味を持ちました。(茶良)
少女は源氏と一夜を過ごした。明け方、源氏は帰って行った。今日しも(強調)、今日人気(ひとけ)のない荒れはてた邸にやって来ます。いかでか(反語)、どうしてこんなところに住めようか、いや住めない。どうして尼君にまかせていたのだろうか。それは北の方とのことや異兄妹とうまくやっていけるかどうか不安で、悩んで、思い切れなかった。しかしそんなこと云っていられません、ちゃんとしたものもおやつなども口にしない少女は面痩せになり、いとあてにかえって可愛く見えた。少女の痛みが少しもわからない父君。ここでひとふんばりしなければならないのに、帰ってしまった。少女は泣くばかり。父君が帰ってしまったさびしさ。もう尼君はそばにいないことに気づく。将来どうなっていくのかと、悲しみがつのる。特に夜になると悲しい。乳母はどうすることもできず、泣く。何とかしたいが、乳母には力がない。お互いに血を分けあった身分格差があり、茨の物語。日本版のシンデレラ物語。荒れ果てた邸に惟光をつかわす。惟光は宿直して警護するためにやって来たが、乳母はがっかりする。乳母は源氏と一晩過ごしたにもかかわらず源氏が来ると思ったのに。この仕打ちはなんたることか。父君に知れたら、「さいなまむ、あなかしこ」、ああ恐ろしいことだ。少女が子供っぽいので、口止めするが、少女の幼さを心配する。源氏と結婚することもできるかもしれないと少納言は惟光に打明けるが、どうしたらいいのでしょうかと悩む。惟光の報告を聞いて、源氏はどうしていいかわからない。少女をめぐって父君、乳母、源氏が(惟光もどのようなことがあったのかと)悩むシーン。源氏は又手紙を書いて、惟光が届ける。ところが少女は明日父君に引き取られていく。乳母は少女の着物など縫っていて、それどころではなくあわただしくなってきました。(祥)
横浜源氏の会
2017年1月5日 横浜市市民活動支援センタ―
本年第1回目の講義。そのせいか、出席者も多く、講義にも熱がこもっていた。講義のあと、石川町の中華料理店で和やかな雰囲気のもと新年会が行われた。
【若紫】123頁~130頁
少女の御簾のなかに素早く入った源氏は、これからは自分が尼君に代わって守るとまず伝える。あわてた尼君に対しては心配するようなことはないといって安心させる。
外は嵐で、こんな荒れはてた邸でわずかな女房たちと少女を置いておくわけにはいかないと、源氏は思う。そして、女房たちにてきぱきと指示を出す。事態が呑みこめず、怯える少女に対して、源氏は不安を取り除こうと親しく話かける。自分の邸にきて、絵を描いたり、雛遊びをしてはどうかと。
嵐の一夜があけた。源氏は一刻も早く少女を自邸に迎えたい旨を乳母に伝えると帰っていった。邸にもどると、源氏はさっそく絵とともに文を少女に届ける。
【感想】
久しぶりに源氏の会に参加して、楽しかった。源氏の心理描写の移り変わりの軽妙さ、源氏の心の中には少女のおもかげが有り、男の微みょうさがおもしろく、作者の作品への想像力がこれから楽しみである。
京都の霧の夜の舞台背景が一層盛り上げている。(恵)
源氏のかっとうが目まぐるしく書かれて、興味深い。この時代の恋の作法がわかって良かった。(桜子)
恋に生きる源氏の面目躍如。
この時代の恋愛形式、制約、常識を踏み破る振舞の数々が、生き生きと描かれています。
翌朝ぼらけ、寄り道のエピソードは、作者紫式部の恐るべき手腕。なるほど、物語とはこのように展開させるのですね。
万能・完璧な存在に見える源氏も、このような軽率な行動により痛手を受ける者であり、人間であることが示されており、作品全体に陰影と立体感、さらに複雑化の効果を上げていると、感嘆しました。(サッシカイア)
日本文化の深さ等を田中先生の源氏で解ってきました。古文を読むと素晴しいと胸の内にひびきます。(N)
紫式部の書き方が非常に興味深い。言葉づかいひとつで登場人物がわかる。よく、深く読まなければいけないと思った。
また、後朝(きぬぎぬ)、あるいは四十九日にナナナヌカと読むのははじめてであった。まだまだ勉強が足りないと思った。(マスピー)
天候のめまぐるしい変化、「霰降り荒れて」→「風すこし吹きやみ」→「霧りわたれる」→「霧はいと白うおき」のそれぞれの間に恋の場面が転換していくのが印象深い。<朝ぼらけ>の歌を交わすシーンの特異さもいろいろと考えさせるところだ。(アキラ)
霧のふりしきる夜。
少女は、心ぼそい思いで夜をすごさなくてはならないと、源氏はかわいくて、いとおしいと思う心から、積極的な行動に出る。一夜、そい(・・)寝(・)する。かわいくて、いとおしい存在だからこそ、守りたい、守りたいけど、我が妻にも。
源氏のゆれる心を式部は上手に描写している。(青)
気象や自然描写が多いのが日本文学の特徴のひとつだと思うけど、とりわけ『源氏物語』には顕著で、それが光る源氏の心理描写になっていることが面白いと思った(たとえばドストエフスキーの小説には気象や自然描写がほとんどなくて、『白痴』に一行天気のことが出て来て、びっくりした記憶がある)。(とんぼ)
一夜を少女とともにする夜、源氏は≪いと馴れ顔に≫少女を抱きかかえて御帳台の中に入ってしまう。ぬけぬけとかかる大それたことをする源氏の、恋に対するひたむきさは、並大抵のものではない。
源氏はまだ暗いうちに少女の家を出て帰路につくが、途中物足りなさをみたすため、他の女の家に立ちより、歌を供の者に朗唱させて女に働きかけるが、振られてしまう。ここのところで作者、紫式部の書き手としての力量の大きさが感じられる。(雄太)
源氏は強引に少女と一晩すごしてしまう。肌がふるえている少女に単衣を着せ、少女に自分の邸に来るように誘うが、少しうちとけるが、まだ源氏が気になっている。
少女の髪を撫でつつ、帰るのだが、その帰途、別の女のことを思い出し、寄ろうとしたが、女からはことわられたあとに、源氏の内心がよくうかがわれる。(茶良)
尼が亡くなって荒れはてた邸での生活は、たださえ夜になると恐い。それ霰が降り、京都の霰はすごいらしい。嵐になって、ぼろやの邸におびえている少女をみて可哀想でならない。この少女をおいて帰ることはできない。今夜は宿直人になって、一緒にいて寂しい思いをさせまいと涙ぐむ。そして馴れ顔でこの邸の人みたいに、乳母や女房たちにも何も云わせないずうずうしい態度で少女を抱っこして御帳台に入る。源氏も我ながらきもちがわるい異常に思えた。乳母は心配でならない。なぜかというと、まだ少女だから。世間に知れたらとため息をつく。怯えている少女をみて、いと美しき――。をかしき絵や雛遊びできますよ、まろのところへおいでといといとう怖じず、少女は疑ってどうしていいかわからず、そわそわしていた。源氏のやさしさに恐さはないが、少女は気をゆるせなくて寝つけなかった。源氏は将来美しき人になるだろうと恋をしている。一晩中強風の音や木や葉ずれの音で女房たちはまんじりともせず過ごし、源氏さまがいてくれただけでよかったとささやく。ようやく風も止んで、明けぬうちに帰らなければならない。一夜を共にしたことでいとおしいと思っている。こんな荒れはてた邸で暮すことはできないでしょう。いち早く自邸に引き取りたいと申し出る。しかし乳母は49日が過ぎたら父君がお迎えに来ることになっていると敬語で告げる。まろの方が父君より縁遠いが愛情を持っていると告げた。空もただならぬ霧と霜が一面につつまれて、いつもの空とはちがう。気象条件が心をかきたてる。そんなことを思いながら、途中通っていた女のところへ寄ったところ、女に逢えず、声のよい御供人に歌をよませた。2回も。なぜまろがよまないのだろうか。歌のやりとりがなんとも可笑しい。時間といい、生い茂っているけれども、いつでも入ってこれますよとふられてしまった。女は疑い、相手にしなかった。ふられてしまったおかげで、よかった。
そんなにふられてもへこたれない源氏である。すぐ少女の方へ切り替え、少女の可愛らしさに心が和む。そしてきれいな絵を描いて手紙を届けるやさしい源氏です。京都の女とのやりとり、物語はテンポが早く、私は追いついて行くのに大へんです。しかし文学よりたくさん力を貰っています。(祥)
横浜源氏の会
2016年12月1日 横浜市市民活動支援センター
朝方の雨も昼前にはやんで、傘を持たずに出かけてきた人も多かった。膝の手術を受けられたという田中先生も元気な顔で現われ、講義もいつもどおり熱のこもった雰囲気のなかで時間オーバー気味に行われた。
【若紫】113頁~123頁
尼君が亡くなって少女が北山から京に帰っていると知った源氏の君は、後ろ盾もいなくなってさぞや心細く思っていることだろうと、少女の邸を訪ねる。家は見る影もなく荒れはて、女房たちの数も減って、いっそう侘しく見える。
迎えに出た少納言は、少女の今後の身の振り方に気懸りを感じていてそれを口にする。父宮の元に引取られたら、どうなるか。少女の母親の姫君が北の方のひどい仕打ちに苦しみ抜いて命まで落したことを思い出しているのだ。それなのに、少女は幼くてとても人前に出せない……。
そこへ源氏のことを父宮の訪問と勘違いした少女が現われる。と、源氏はとっさに少女の手をとって御簾の内にすべり込んでしまうのだった。
【感想】
「尼君の死」 第三者を話題にする会話の難しさ、正しく理解するうえで必要な繊細さを実感いたしました。
また、当時の家屋構造によるプライバシーの無さと、それゆえに対話の背後の暗闇に女房たちの耳があることも現代とは全く違う点と思いました。
「身にしみて若き人々思へり」はそのような背景のなかではじめて理解出来ました。
ここから「少女との一夜」へは、少なからぬ飛躍も感じられますが、注目すべき箇所に集中する紫式部の頭脳の冴えに圧倒される思いです。(サッシカイヤ)
10月、11月と欠席している間に、「密会」「懐妊」というこの物語の肝要な所を、先生のお話が伺えなかったのが残念です。今回は、源氏と少納言の歌の応答が心に残りました。「少女との一夜」はさらに。(アキラ)
尼君の死によって、少女の引取りの邪魔者はいなくなった。しかし、少納言との少女に会いたい源氏のやりとりに興味が持たれ、今後のことに期待が持たれます。又、やっと少女に会え、そのやりとりと、少女の手を取って共にすべり込んだ源氏のすばやさに驚き、興味を感じました。(茶良)
先生の講義を聞いていて――とくに敬語の話を聞いて――、昔、トロント大学の教授が書いた『日本語に主語はいらない』という本を読んだことを思い出した。そして、納得したのだった(残念ながら、日本人の著者名は忘れてしまったけれども)。(とんぼ)
尼君のお見舞いをした後、10月の朱雀院の行事、宮中での一大イベント、内裏から朱雀院まで舞人などの行列の練習に忙しい源氏。政治は文化的な遊びであった。尼君のお見舞いも行けず、手紙を出す。わざわざ使いをさしむけた。僧都の返信で尼君の死を知った。僧都の悲しみ、ついに死者として「世間の道理なれど」哀しみはどうにもならない心の内を読んだ。源氏も幼くして母君、祖母を亡くしている。あまり覚えていないが、少女の気持は胸が痛いほどわかるような気がした。手紙の返事は大切である。うしろめたげに、うしろめたい人、尼君が心配していただろう少女のことを。げがあるために理解しがたい。古文のむずかしさ、またやさしさがわかったような気がした。
少女へのお悔みの手紙を書く。乳母からの返事がきました。どんな慰めの手紙だっただろうか。少女は北山から京へ戻っていることを聞き、みずからのどかな夜におはしたり、荒れはてたゾーットするような邸に「をさなき人恐ろしからむ」源氏は心配でたまらない。少納言より人のおもむけをわかる年令ではない。どっちつかず中空で暮していくのはむずかしい。主語がなくて敬語で、尼君の臨終の様子を聞いて涙、涙。少女との宿命的な縁だと、少女との面会をお願いする。なんとしても立ちながらこのまま帰るのはつまらないと源氏。しかし少納言は歌でお断りする。声を出して誦じ、源氏の声、姿にしびれちゃうと若い女房たちはうっとり、体にしみた。
紫式部の文章はすみずみまで読む面白さがある。若紫に逢いたい。少女は泣き伏している。御遊びがたきは人を表わす。童女たちが慰めようとしている。直衣(貴族の普段着)を着ている人、お父さん。通い婚だから、時々しかこない。直衣着た人はどこーと探す。なんとも可愛らしさ。源氏は見えないところで父ではないけれど、近い人ですよと云う。ああ、あの人だと驚く。少女は父と間違えてはずかしくなる。源氏の声だー。乳母はそばへ引き寄せたり源氏の方へ押しやったり、なんと可愛いと源氏は抱っこしたい、簾の中にいる少女に手をさしだし、髪はゆたかで、髪の先はふさふさしている。私が守ってあげたい、美しい人に育てたい――。あのすてきな人でも恐ろしい。少女は寝ようとしているのに、源氏にあっという間に引きずられてしまう。源氏は私こそまろぞ思うべき人よ。今は若い女の子なのでわからない。私の志を見守ってほしいと乳母に誓いました。源氏は宮中で育っているので、女君を扱うことには素早く身分の差を感じた。乳母にお願いすることは、少女の母君や尼君のことをたくさん若紫に語ってほしいと思いました。(祥)
横浜源氏の会
2016年11月3日 横浜市市民活動支援センター
祭日(文化の日)のせいか出席率はあまりよくなかったけれども、講義は時間を大幅に超過しての熱いものとなった。
【若紫】102頁~113頁
北山の寺の尼君が小康を得て山を降りて京に帰ってきたという消息が源氏の耳にも入ってくる。少女もともに帰ってきているはずと、在所を探して使いの者に便りを届けさせる。しかし、一向に、源氏の申し出が受け入れられる気配はない。
秋も末のある日、内裏から六条へ向かう道筋で源氏の一行は鬱蒼と木々の生い茂った荒れはてた屋敷の前を通りかかる。すると、惟光がここが故按察使の大納言の屋敷だと源氏に告げる。わたしも先日お見舞いに伺ったところだと。その折り、尼君の具合がはかばかしくない旨、女房たちから聞きましたと。
それを聞いて源氏は急遽尼君を見舞うことにするが、突然のことで女房たちは途惑いを隠せない。取りあえず源氏を廂の間に案内する。臨終の床の尼君は最後の気力をふり絞って源氏にいう。どうぞ少女の後見人になってほしいと。ただし、かならず妻にすることと。
その折り、少女の可憐な声を御簾越しに耳にし、ますます恋心を募らせた源氏は、翌日、心情を歌に託して贈る。
【感想】
尼君を見舞った時に、自分の死後もし気が変らなければ、紫が大人になった時には妻の一人に数えてほしいと、尼君より託され、やっと念願がかなうと思う源氏の内心がありありと伝わってくるように思われた。(茶良)
「手に摘みていつしかも見む紫の
根にかよひける野辺の若草」
源氏が詠んだこの歌、ただ単に野辺の花を摘む時の仕草を詠んだのかと思っていたら、読後に皆さんの読みを聞いていたら、なんと血縁つながりの、藤壺と若紫をかけて歌ったものとの発言に、私一人ではよみ取れなかった深さを感じさせてもらいました。(孝)
幾度も聞いていても、4段階評価の「よし、よろし、わろし、あし」という言葉を今日は覚えたい。今回の尼上の気持ちに、現代の自分に通じるところがある気がした。(Y)
何びとの死によって変転する人間の運命がテンポ良く、素早い展開により描かれており、いつもながら感心いたしました。また、「少女の声」における矛盾(間の悪さでしょうか)が生み出すユーモアと、少女の声の鮮烈な響きが非常に印象的です。(サッシカイア)
今日の授業は何か神秘的な人と人との奥深さを感じました。
尼君は源氏の想い(少女の後見人になること)を無視していたのに、死を前にして、「かならず数まへさせたまへ」と希望することへの熱い想いが切ない。源氏と少女の恋のスト―リーが楽しみ!(恵)
手に摘みていつしかも見む紫の
根にかよひける野辺の若草
源氏から少女へ宛てられた歌。この「紫」はムラサキ科の多年草のことで、その根は昔から紫色の染料の原料として使われたという。だけど、ここでは暗に藤壺のことを示していて、若草(若紫)が藤壺の血縁(姪)であるということを意味していると。藤壺と紫の上は『源氏物語』の二大ヒロインであって、それゆえ『紫の物語』というふうにいうこともあるらしい。作者は紫式部。つまり。紫は『源氏物語』のキーワードなのだった。――そんなことがきょうの講義でわかった(とんぼ)
若紫(p102遺言)
月のをかし夜、源氏は冷たい雨の中六條あたりに行く。荒れた尼君の家をみつけた。女房より尼君の病状が思わしくないことを惟光から聞いていたので、すぐ使者を出して尼君にお目にかかれた。御座所で御無沙汰のお詫びをして、少女の後見人をお願いした。尼君は少女を残して先行くのはつらい。どうぞ妻にして下さるよう切願した。幼くて御挨拶もできないことが残念でたまらない。源氏ははじめて少女を見た時から思いを寄せていたので、一声愛らしい声を聞きたい。しかし女房たちはもう寝ておられるといいます。少女も源氏がおいでになっていることに気づいて、どきどきしているのに、大人たちの間にいても無邪気に育っていることをほほえましく思った。少女の声を聞いてしっかり育てようと決心する。翌日もお見舞いの手紙、少女への恋文を届ける。どんな恋文だったのか、それは幼い少女にもわかるような、こんなに少女を大切に思っている、あなたの可愛らしい一声に引かれている源氏です。その後、恋文は御手本になる。まもなく尼君の御容態も危なくなり、死が近づく哀しみ、この秋は特につらい、悲しい秋だ。そうはいっても、そんなことでへこたれる源氏ではない。野辺の若草のような少女を迎える準備に希望を見い出していました。藤壺との血縁の(根にかよひける)少女との暮しを夢見て。(祥)
横浜源氏の会
2016年10月6日(木) 横浜市市民活動支援センター ディスカッションルーム
参加者 12名
【若紫】密会89頁~ 99頁
【感想】
密会の段、たいへん面白く拝聴いたしました。
とりわけ「命婦の君ぞ、御直衣などは、かき集め持て来たる」の一文は、闇をつらぬく閃光のように 源氏と藤壺との一夜を照らし出しているかのようです。
表現しぬいこと――沈黙――の効果、雄弁さがこれほど如実に示されている例も少ないと思われます。
ダンテ「神曲」の前半部に若い二人が学習(読書)をしながら恋に落ちる場面があり、
源氏と同様に二人が具体的に何を為したか示すことなく、ただ「私たちは、その日(その本の)先へは進みませんでした」と記してきることを思い出しました。(サッシカイヤ)
源氏と藤壺との再度の情事が描かれ、ともに悩み苦しむ様子が悲痛に感じられ、また
子供を宿し、その子が源氏の子であると確信し苦しむ藤壺の心痛が痛ましいように
感じられました。(茶良)
今回は、源氏の初恋のひとであり、帝の后である藤壺との二度目の密会の場面である。
帝を裏切ってしまった藤壺の罪悪感と源氏への愛着の間で、苦悩乱れる心がよく
描かれている。しかも、藤壺はこの密会によって源氏の子をみごもってしまったので
ある。「源氏物語」の“すごさ”がここにも現れていると言うのだろう。(雄太)
語らずして場面を想像させる,広がる紫式部の文章に今日は目をむけさせてもらいました。(Y)
今日はとても良い所を読めました。紫式部の器量の大きさを感じました。すごい!
(桜子)
本日の密会、懐妊は凄まじい何とも恐ろしいストーリーなのです。
北山の少女(藤壺の姪)を引き取って養育したいと思うこともままならず、ふてくされている源氏。その頃、初恋の人藤壺は病気で里帰りしていた。そんな時 つツーと気持ちが
思わぬ方向へ――。なぜでしょう。どうにかして藤壺に逢いたくて、王命婦のところへ走ります。誰かとめて――。
逢いたい気持ちはわかるが人間は理性を失うことがある。
夏の短夜に王命婦の計らいで逢うことができたものの、夢のようで舞いあがり焦って喜びではなく、侘しい切ない、どうしたの?藤壺もずーっと悩み続けたのに受け入れてしまった。もう後悔してもどうにもならない泣きの源氏。しかし年上の女君は空蝉も信念を持っていた。藤壺は心を決めて冷たくあしらう。ずるいですね。二人のことは秘め事にしておきたいと手紙を書いても手に取ろうともしない藤壺。もうお先真つ暗それだけに苦しみも大で立ち直れない源氏。父帝に対しても怖く、藤壺も源氏も後めたさ身も心も罪深き人。王命婦も罪ありき人。
帝は藤壺の懐妊を知る。藤壺の気持ちはそれどころではない。一時も心安まるところではない。気の毒である。源氏は自分の子ではないかと一。もう一度藤壺に逢いたい一心だったが、王命婦はきっぱり断った。文月になって少しふくよかになった藤壺は参内し、帝は大喜びになり身籠もを案じる。
秋(七月)になって管弦の頃、お琴や笛など演奏する源氏も帝や藤壺の前では、内面的にも外面時にも乱れ帝は複雑。しかし藤壺は何とも哀愁だヽよう情感の響きに一時も忘れることはなかった。(祥)
横浜源氏の会
2016年9月1日 横浜市市民活動支援センター
相変わらず残暑の厳しい午後で、あまり広くない会場に大勢の出席者が机を並べて勉強することになったけれども、珍しくクーラーがよく効いて、時間を延長しての、熱心で快適な講義となった。
【若紫】73頁~88頁
源氏の帰京を伝え聞いた左大臣がさっそくやって来て、源氏を強引に牛車に乗せると女君の待つ邸へと連れて行く。自分が行くと人目につくので、北山には代わりに息子たちを遣わしたのだなどと言い訳しながら。だが、久しぶりに対面した女君との間にはひややかな空気が流れていて、「具合が悪いときに、ひと言も声をかけないのはうらめしい」と不満をもらす源氏に対して、「そう聞かないことが、どんなにつらいことかあなたにはわからないでしょう」と、女君は切り返す。源氏がいくら言葉をつくしても、女君は源氏の愛情が自分に向けられないことをわかっているのだ。
眠れぬ夜を過ごす源氏。それにつけても思われるのは、北山の、あの初々しい少女だ。
そこで、源氏は山寺に滞在中の尼君に<御文>を届ける(そのなかには少女宛ての文が同封されていた)。尼君の返事は源氏の真摯な気持ちはわかるけれども、少女はまだとても幼くて源氏の申し出を受けるわけにはいかないというものだった。僧都の返書も同様だった。
困ったときの惟光頼み。万策尽きた源氏は使者として惟光を北山に遣わす。少女の身の周りの世話をする<少納言の乳母>に会って源氏の真意を直接伝えよと。しかし、惟光がいくら熱弁をふるっても、尼君たちの考えを覆すことはできなかった。
その後、少納言からていねいな返事がくる。尼君の病が回復し、京の殿に帰ったらきちんと返事をすると。
【感想】
「妻の一言」 心理の細やかなうごきが対話のなかに見事に描かれており、驚きました。とりわけ、「思ふこともうちかすめ……、御心のへだてもまさるを」には内的独白のような手法の鮮やかさを感じました。(サッシカイア)
源氏と女君(葵の上)とのぎくしゃくしたやりとりが面白く感じられました。また、紫のことを思い出し、尼君に意向を伝えるが、拒絶されるが諦めない源氏に、以後のことが思いやられました。(茶良)
源氏は妻である女君と打ちとけた話合いをしたいのに、女君はひと言もしゃべらず、二人の間には気づまりな空気が流れる。それで、「たまには、妻らしい様子を見たいものだ」とぐちってしまう。冷めてしまっている夫婦間の厳しいやりとりである。そして、結局源氏は、一人で眠れぬ夜を過すこととなる。こんな状況の中で、源氏のあの初々しい少女への想いはますますつのっていく。
何とかして少女を自分の手に引取り、自分の理想とする女に育てあげたいと源氏は心の底から思い、少女に宛てて恋いのうたを送る。男であれば、そう思い、そうするのは当然だと共感する。(雄太)
年の差のある二つの男女関係(源氏と葵・源氏と若紫)がどのように経過していくかが並べて書かれていて、いっそうドラマチックである。(桜)
葵の上との息づまる関係が書かれたあとに、すぐ若草を求めて画さくする源氏の心情が面白い、というか若草を欲する気持ちの必然性が書かれる。このような男の心の動きを作者は良く描くものだと思う。(アキラ)
女性を果てなく求めていく姿の物語は、それはそれとして楽しく面白く読むことができる。おかしく、せつなく、美しく、リアリティあり、当時の娯楽としては宮中で最高の物語だろう。(N)
源氏物語は基本的にはファンタジーだと思うけど、源氏と葵の上との激しいやりとりの場面は非常に迫力があり、平安朝の文学にはきわめて稀なリアリズムだと思う。(とんぼ)
少女は源氏を「めでたき人かな」と見つめていた。ただ見つめるだけではなく、源氏の人形をつくったり、絵を画いたり、その人形や絵に話しかけたり、人形に着物を着せたり(着せかえ人形)、人形遊び(ひとり遊び)がなんともほほえましい。淡い恋心がめばえた。初恋というものかしら。
今年の夏、5才の女の子の孫が泊りに来ました。祖父が靴のプレゼントをした。何度も箱から出したり入れたり、よほど気に入ったのか笑ったり、そんなひとり遊びを見た。どんな時代も子どもって可愛いな――と思いました。
源氏は北山より帰京し、帝に御挨拶に内裏に行く。あまりにもやつれた源氏を見た帝は驚く。苦しんでいる人を助ける聖や阿闍利、僧都の尊さを伝えた。そして久し振りに葵の上のところへ――しかし葵の上は冷やかに、源氏はなごやかに話ができたらと思うが、待つ身のことをどう思っているのだろうか。妻に要求することばかりに思えるが――。
美しい人妻なのに、美しい源氏とは合わないのか、葵の上も年上だったら少し母性本能を表現し、近づいたらいいのに。源氏も年下のくせに「はしたなき御もてなし」なんて、つれない、無情だ、そっけない、ああ、これでは駄目ですね。わかってもらえない夫も「よしや命だに」なんて寂しいことだ。
山から戻ってから源氏は少女(若草)のことが気になる。少女の成長を見守りたいが、小さな恋人になんていったらわからない。
少女の父は「にほひやかになどもあらぬを」で、艶々した魅力がないようだ。少女の父(兵部卿)と藤壺が兄弟なので、少女が藤壺に似ているのが源氏には嬉しいことだ。源氏は尼君に文を出す。それには少女への恋文も添えた。源氏の筆が素晴らしく、尼君も舞い上がっています。まずラブレターがきたが、お断りの返事をする。(少女が大人になる前なので、まだお手紙が書けないのです。)僧都からもお断りの返事がきた。源氏はくやしい。困った時の惟光。
惟光は北山の僧都のところへ出かける。惟光も少女を見ていたが、別にはっきりと見たわけではない。けれども、一生懸命思い出して、こと細かく伝える。源氏のためならととうとうと言葉をつくしても、尼君には伝わらない。世話役の少納言の乳母の返事は、少女はまだ御放ち書きしか書けないので、御返事はできませんというものだった。尼君の病気がよくなったら、御返事いたしましょうと。源氏はますます不安になりました。(祥)
、
横浜源氏の会
2016年8月4日 横浜市市民活動支援センター
参加者が17人と史上最多を数え、広くない会場はあたかもすし詰め状態。とはいえこの日はクーラーがよく効いていて快適で充実した2時間となった。源氏物語も話がいよいよ佳境に入って、会員たちの気持ちも一段と乗ってきた。
【若紫】60頁~73頁
さて、源氏の病も癒えて、都に帰る段になると、送別の宴が催されることとなった。聖は護身の術を施すとともに、長年身から離さず所持していた護身用の独鈷(とこ)(仏具)を源氏に贈る。それを見ていた僧都は、負けじとばかりに聖徳太子が百済から手に入れたという貴重な金剛子の数珠を献上する。
いよいよ山を降りるというときに、都から大勢の公達や従者たちがやってきて、花見の宴が始まる。源氏の身を案じた大殿が差し向けた者たちで、頭の中将や左中弁の顔も見える。頭の中将が笛を吹くと、弁の君がそれに合わせて扇で調子をとりながら催馬楽の一節を歌い、随身たちも篳篥(ひちりき)を吹いて加わる。さらに、僧都が琴を持ち出して源氏に爪弾くことを強要する始末。
そんなこんながあって源氏たちが去ると、山にはふたたび元の静寂がもどる。だがそこには、尼君や女房たちとともに、源氏の姿を心に深く刻んだ者があった。無邪気に雀の子を追っていた、あの少女である。
【感想】
源氏の送別の宴での僧都や聖の行動、又、宴の様子が面白く感じられました。(茶良)
聖と僧都の源氏への贈り物の場面、迎えに来た君達の別れの宴の場面と転換の鮮やかさも見事だが、若紫が源氏を見て幼い恋心を抱くというロマンチックな記述がすばらしい。ここは物語の核心の一つだろうか。(アキラ)
大盛況 充実のひとときでした。「めでたき人」の最終部分は作者(女性ならでは)の 細やかな配慮と 表現が強く心に残りました。(サッシャイア)
今回は、高貴で洗練された源氏と、身分は高いながら、野暮な僧都との噛み合わない歌のやり取りや、対話が興味深い。大人たちのやりとり(会話)や贈物の交換などと関わりなく、少女がひそかに源氏へ想いを寄せるようになるところも興味深い。(雄太)
源氏の君と僧都の考えの差、心の移りかわりが非常に興味深い。(マスピー)
源氏と僧都の人間模様がおもしろい。なやめる源氏と、富を見せつける僧都、まわりの人々と、少女のこれからの運命に物語のすばらしい展開が楽しみである。(恵)
少女の初恋がその年らしく書かれて興味深い。
この宴会の場面が想像しにくい。山の中なのに、そして岩の上で演奏していて、屋内で女性達がすだれ?ごしに聞いているという舞台が私の頭では設定できない。(桜子)
世間に評判の高い源氏がわらやみになり、身も心も弱まり、お忍びで春がすみたなびく静寂な北山に聖の坊に施しをお受けになり、少しずつ快方に向かわれながらもかいま見の美しい少女に惹かれ、恋い慕ってる方にあまりにもよく似ているので、涙がちになり……その生い立ちを知り、源氏の幼少の頃と重ね合せて……おやさしい源氏は……少女を身元にてお育てになりたいと思うのでした。これからのストーリーがとても楽しみです。(M子)
源氏物語は基本的にはロマンスであるけれども、今回の僧都のように、ときどきユーモラスな話をはさんで読者を飽きさせない工夫をしているのはエンターテイメントとして流石だなと思いました。(とんぼ)
若紫 2016.8.4
7月末より昨日まで奥琵琶湖で過ごした。帰りは樫田より山越えし、京都大原に出た。緑豊かで清らかな水、少の間涼を嗜みました。御所に車を止め、ランチをとり、すぐそばの府民ホールでコンサートを聴いて、のぞみで帰横。そして昨日の今頃は猛暑の京都で。さぞ源氏も暑かっただろうと思いながら。こんな気持わかっていただけるかしら。
P60 送別の宴
源氏は京では味わえない山や風、読経の声や滝の音に涙ぐみ、僧都と歌を交換し、自然の美しさに驚き、鳥や鹿に癒されたが、僧都は耳なれているのでさほど珍しくもないと返歌した。帰京にともない、宴の御馳走も整い、宴が始まり、名残り惜しゅう、再び訪れることを約束する。
僧都は美しい源氏とお目にかかることができた。優曇華(3千年に一度花開くと仏典で説かれている)のようだ。源氏は少し恥かしくなった。
聖から源氏へ酒杯、お目にかかれたよろこび、護身用の独鈷を贈る。僧都も数珠と壺を贈る。源氏もお礼の品々を贈る。尼より少女を引取るのはもう4、5年待ってほしいと。しかし源氏は今引取りたいと。尼より「まことにや花のあたりは立ち憂きと/霞むる空のけしきをも見む」と返歌が届く。「よしある手のいとあてなるを」(気品あふれた美しい筆跡を)見て、源氏は大いに感心する。そして、少女との縁をつないでいけそうと悟った。左大臣家の頭の中将や君達も加わって、花の宴がはじまった。中将は笛を吹き、弁の君が催馬楽の一節を歌う。源氏は少し苦しかったが、岩かげに寄りそう。皆、ひと際源氏の美しさに見とれていた。不吉なくらい美しい。たとえようのないほど気高い。ほかの者をみても仕方がないくらい目を奪われている。普段お目にかかることができないお方である。高い音がでる縦笛。リード(葦)でほっぺたをふくらませて演奏する。琴(中国)を僧都が持って来て、源氏におねがいした。源氏はポロンと演奏して出発した。
簾の中で源氏をはじめて見た人は、この世で一番美しいお方だと感動した。僧都もうっとうしい日本にあわせたのだろうかと嘆く。少女のお父様より素敵、女房たちはあのお方の子どもになっておしまいと云う。少女は少女で源氏の想いがあり、淡くいとおしい。(祥子)
横浜源氏の会
2016年7月7日 横浜市市民活動支援センター
七夕の日。本年最高の猛暑にもめげず、扇風機の故障にもめげず、時間を30分延長して熱気あふる講義が行われた。活発な質疑応答。会員たちもすっかり大宮人になった気分。講義のあとは恒例の楽しいコーヒータイム。
【若紫】45頁~60頁
僧都の口から少女の素姓を知ってますます少女への思いを募らせる源氏は、ただちに引き取って育てたい旨を尼君に伝えてほしいと僧都に頼むが、むげに断られてしまう。僧都が去ったのち、心乱れて眠れぬままに夜をすごす源氏の耳にねぶたげな読経の声やかすかな数珠や衣すれの音が入ってくる。意を決した源氏は、扇を鳴らして女房を呼ぶ。少女への思いをのべた歌を託して、尼君に取り次いでもらうけれど、女房を通してのやり取りはまどろこしく、頼りない。そこで、使いの者に申し入れる。尼君にお会いして、じかにお話したいと。尼君に対面した源氏は少女への真情を熱意を込めて述べる。幼くして親を失った者の悲しみはよくわかる。自分と同じような生い立ちの少女はいわば仲間であって、ほっておけないのだと。源氏は思いの丈を打ち明けるが、尼君は源氏の心をはかりかねて孫はまだそんな年齢ではないと申し出を断る。
【感想】
今日の授業は長い長い物語りで、源氏の一途の気持ちと周囲の人々との思いの変化と、これからの運命に興味がそそられる。源氏は、恋多き多感性がおもしろい。(恵)
「意中を切り出す」の対話、「眠れぬままに」における様々な〝音〟による立体的な表現、さらに「心中を訴える」の対話。考え抜かれた構成と理知的な対話、感覚を駆使した表現に感嘆しました。小説を書くためのお手本を学んでいるようにも思われます。(サッシカイア)
すずろなる人
今日はいろいろな音が出て来た。かすかな音に心をとぎすまして反応している様子が語り合いの中ですずろなる人(自分)にも雰囲気が伝わって来た。(Y)
幼い少女を見て、惹かれていった源氏が、僧都からその生いたちを聞き、自分の妻にと思い、女房をとおして尼君に恋歌を渡し、思いを伝えようとし、尼君とのやりとりする場面に感銘を受けました。(茶良)
源氏の心の深層に「いふかひなきほどの齢にて、むつましかるべき人にも立ちおくれはべり」という不安定さや寂しさのようなものがあって、感情や行動を支配してゆくと書かれる。同伴者となっていく紫とのきづなの深さの一つの理由も紫の身の上が似ていることだと思わされる。(アキラ)
源氏の「初草の若葉のうへを見つるより/旅寝の袖も露ぞかわかぬ」に対して、尼君の
「枕ゆふ今宵ばかりの露けさを/深山の苔にくらべざらなむ」の返しは、詠み歌の最上最高の趣向であると思う。
良い場面を観せてもらって、非常に得した気分である。(マスピー)
香の香漂う漆黒の闇、かすかな人の気配と衣ずれの音……静謐ともいうべき平安時代に比べて現代はあまりに騒々しい。かそけき月の影に対して煌々たる照明、大音声のテレビジョン、夜でも鳴きやまぬ蝉の声、上空を爆音とともに飛翔する爆撃機、どたんどたんと大股で歩くわが家の大宮人たち。ああ。(とんぼ)
尼君の孫(娘の娘)にあたる少女に、ほれこんでしまった源氏は、僧都に訴える:「自分が少女の後見人となって、いずれは少女を妻に迎えたい」と。僧都は、少女が全く世間のことを知らず、人の妻となる準備などできていないから、と源氏の願いを冷たく、拒否する。源氏は、尼君に直接思いを伝えずにはおれず、家中誰もが眠れずにいる夜に、尼君へ歌を送り、ついに直接自分の思いを伝える。源氏自身と少女の生い立ちが似かよっていることも強調して……。尼君は、あくまでも源氏の申し込みを受け入れられないと断るが、源氏は自らの思いを充分に伝えられたことで、満ち足りた思いになる。(雄太)
若紫(源氏意中を切り出す)
「亡くなりはべりしほどにこそはべりしか」。こそは強め、亡くなった時に女の子が生まれていた。みなさんそれぞれに思いを語りました。源氏はいとほしい少女を引きとって理想の妻に育てたいと夢みている。今源氏の現状をわかってもらえるように尼に伝えてほしいと僧都にお願いするが、源氏なぞに少女を育てられるわけがないと僧都は憤慨し申し出を断るのです。少女は大人の助けにより成長して人妻になる――そうだ尼に相談してみようと「すくよかに」。源氏は少し突っ走ったこと恥じる。「えよくも聞えたまはず」。Cannot.
源氏の心は沈み、晩春の雨にともなってがっくり肩を落す。眠れない、そんな時かすかに聞こえる衣ずれや尼の数珠の音に「あてはか」気品にあふれている。なんとか尼君に取り次いでほしいと歌を女房にお願いする。
あまりの気品に溢れいる源氏の声なので、女房もあわてる。ねばりの源氏、少女への恋の歌は「あな、今めかし」と尼は驚いて突っ放す。源氏の雅な心を見抜いていた。これでしょげる源氏ではない。今日は七夕さま。源氏ガンバレ――。源氏は必死である。どうしても理由があって伝えなければならないことがある。
P31「初草の生ひゆく~~」かの若草の歌を知っていたのだろう、尼は深山に住みつらい生活をしている。源氏の涙とくらべないでほしいと返歌した。
古文でしか味わえない音がある。
尼君は落ち着いて、源氏のとまどいを察してくれた。尼は娘の少女の母君と思って、源氏とこのような機会を心の内をお話したいとはうれしいが、年頃の娘だと思っていますが、本当はまだ幼い娘なのでお断りをする。源氏はなんとか説得したい。(祥)
横浜源氏の会
2016年6月2日 横浜市市民活動支援センター
風が強かったけれど、よく晴れた日。ふたたびいつもの慣れ親しんだ会場に戻っての講義。やはり落ち着く。新しい参加者もあって、活気あふれる2時間となった。
【若紫】36頁~45頁
光源氏が横になって休んでいると、僧坊の主の僧都がやってきて、自分の庵へと誘う。涼しい水が流れる庭などもご覧いただきたいと。気が進まない源氏であったが、あの少女がいることを思って誘いを受けることにした。
仏の話をつづける僧都をさえぎって、少女のことを聞いてみると、僧都は少女の身の上を語り始めるのだった。それによると、僧都は小柴垣の庵の尼君の兄だった。尼君の亡き夫は大納言まで登った人(按察(あぜち)大納言)で、二人の間に姫君が一人いて、すでにこの世にはいない。その忘れ形見が、源氏が目をとめた例の少女であった(このへんの人間関係は複雑で、わかりにくい。先生からいただいた若紫の<系図>を参照のこと)。そして、源氏がなぜ少女に惹かれたかが次第に明らかになっていく。
【感想】
僧都の人物と、源氏の対面によって自分の運命が、まか不思議に開けていく運命と、これからの少女の事など、その当時の女性達の悲しさや物のあわれが、現代にない優雅さと幻想で展開する事が今後の楽しみである。(恵)
源氏が僧都の説教を聞きながら、自分の煩悩に思いなやみながらも、一方で、昼に見た少女に惹かれ、その少女について僧都とのやりとりが面白く思われました。少女を教え育てて自分の妻にと思いふくらんでいく源氏にも先々の展開が期待される思いでした。(茶良)
たちまち場面転換するので、ついていくのが大変です。
月のない夜に(月なきころに)たちまち訪ねていくのは、けっこう大変な夜道と思うのですが。
夜もものせず行動するんですね。(関)
「僧都の坊」の後半部分がひじょうに印象的でした。月のない闇、水に映る篝火、静寂と薄明が支配する空間に広がる、洗練された部屋と調度、そこに漂う三種の薫香に作者紫式部の鮮やかな手腕を見た思いです。(H.S)
美しい少女をかいま見た源氏は気になり、僧都より聞くことになった。源氏はこっそり北山に来ているのに、僧都は恐縮している。僧都の住みかは草のむしろでそまつな宿坊だが、源氏を迎えたいと思う。趣き深い月のあかりのかわりに遣水にかがり火をともして工夫して庭を作った。軒先の燈籠に火が入って幻想的な寝殿造りの客間が整えられ、隣の部屋で香をたき、ほのかにおくゆかしい。さらに名香、仏前にたく香が濃い源氏の香り(追い風)。源氏がおいでになったので、女房が感じとる。平安朝の特徴である、五感の世界なのだ。
源氏は少女が美しい大人になったら藤壺のような美しい人になるだろうと想うと、罪深く想い悩み心が辛くなり悲しく涙がこぼれる。泣きの源氏。僧都は源氏を招き寄せ、僧都のおもてなしを受けるが、お説教もうわの空で仏様に申し訳なく「あじけなし」どうしようもない気持になる。しかし昼少女を見た面影が気になり、ここに来た目的は何かと問いただす。僧都は源氏にはぐらかせられたが、源氏の心を読み取り語りはじめた。
北山の僧都、尼君(僧都の妹で故安察使の大納言の北の方)、少女は尼君の子どもだろうか? 大納言には娘がいた。兵部卿の宮との間に女の子が生まれ、娘は兵部卿の正室(北の方)との間で苦しみ亡くなってしまった。その少女の父は藤壺の兄。だから藤壺と似ているはず。少女と祖母(尼)の間柄がわかりました。今朝も朝ドラをみた。家族写真、祖母と孫のほほえましいスナップ、いつの時代も同じだと思った。昨日は私の78才の誕生日。花束もいただいたし、鉢物の紫陽花もいただいた。その花を眺めながら寿命まで健やかに過ごしたい。孫からのバースデイ・カードや家族の寄せ書き、折り紙など、幸せな一日でした。
源氏の心に焼きついた少女の素姓を聞かされて心ひかれて共に暮らしたいと思い、養い育てたいと夢のように思う。源氏のやさしいところであるが、人間関係が複雑ね。(祥)
横浜源氏の会
2016年5月12日 戸塚フォーラム(男女共同参画センター横浜)
五月晴れの気持ちのいい一日。黄金週間もあって、一週間遅れの講義となった。初めての会場だったので、道に迷った者もいた(お気の毒さま)。旅行先の千葉の農家から直行し、筍や野菜を持参した会員もいて、何人かが旬のもののお裾分けに与るという一幕もあった。
【若紫】24頁~36頁
高僧の加持祈祷によって瘧病から恢復した光源氏は、折からの春の陽気に誘われてあたりを誘われて気軽に歩いてみた。すると、小柴垣をめぐらして小ぎれいに住みなした僧坊があった。御簾が巻き上げてあるので、小柴垣越しにながめると、尼君が柱に寄りかかって経を読んでいた。年のころは四十歳ほど。色白で、顔はふっくらし、いかにも上品な風情。小ざっぱりした女御たちが出入りするなかに、十歳ぐらいの女の子がばたばたと駆けこんでくる。肩までかかった髪の毛が扇のようにひらいてふさふさして、白い衣の上に山吹色の襲(おすい)を重ねている。いかにも可憐だ。「さても、いとうつくしかりつる児かな」。源氏は、少女の愛らしい顔立ちにすっかり心を奪われて立ち尽くすのであった。
【感想】
「なぐさむ」
この段ではじめて源氏が若紫と出合う、その時になぜ、こんなにこの幼い少女に心ひかれるのかと源氏考える。そう言えば、許されぬ思い人である藤壺にも似ている。自分のこの苦しい状況をすこしでも心おだやかに、心がなぐように自分がこの子を育てることは出来ないものか……「なぐさむ」、心なぐさむという意味をはじめて読み取りました。(孝)
若紫の登場 十ばかりで白い衣、山吹などのなれたるを着て、走って出てくる。小柴垣から一部始終を眺めている内に源氏の心が動く。「さても、いとうつくしかりつる児かな、何人ならむ、かの人の御かはりに、……」と、緑豊かな山の中に次の展開を予想させる芽が出て来る。(Y)
女の子について「うつくしげなる容貌なり」「額つき、髪ざし、いみじううつくし」「さても、いとうつくしかりつる児かな」と短い部分に3度も「うつくし」と書いて強調している。若紫の幼くとも美しさが、その物語における意味が伝わってくるよう。(アキラ)
泣きながら走って来た眉もととのわない美しい少女に惹かれていく源氏。その姿に愛しいしあの人(藤壺)に似ているからとダブラせて見ている源氏に、これからの発展に興味を持ちました。(茶良)
「歩き」と「垣間見」
若紫は、歩きと垣間見とによって話が展開していくという物語の仕組み/構造が透けて見えたシーンであった。(とんぼ)
若紫の登場が、とても奇抜で、源氏の心の動揺がありありと浮かんでくる。「涙ぞ落つる」で少女を愛しく見たことで秘めた恋を切なく思い出したのが、「尼君の心配」では、少女を養育すれば、この(源氏の)心も穏やかになるだろうと変わっていく。源氏は、「では、どうしようか」と考え、実行に移していく、未来志向の実行型だと思った。(桜子)
源氏物語はスケールが大きく貴族ばかりでなく、階級・受領などを描いている。たった一人娘を入内させ妃へとその時代は勝ち運命をしょっていた。明石の入道は娘が都へ出ていっても恥かしくないように教育し、最高位の身分の男に嫁がせて、都に戻りたいと思っていた。そんな入道をみて源氏は娘に心が動いたが、もう一晩加持の治療をすることになった。翌日少し時間ができ気になっていた小柴垣の庵に行ってみた。そして、かいま見たものは、経文を唱え祈りをしているなやましげな尼の姿、そばでは女房や童女が遊んでいる。10才位の白地袿の上に山吹襲の少女が目に入り、その美しさと可愛らしく走ってくるのを見た。可愛がっていた雀の子を童女が逃がしてしまったと嘆き、女房たちは烏などに襲われはしないかと心配している。源氏は女房たちの髪の美しさにほれぼれする。尼の命は今日か明日かもわからないのに少女があまりにも幼いことに心が痛む。尼の祖母は孫の少女を手招きし、少女は素直に膝まずき、その美しさに源氏は首ったけ、少女が大人になった時のことを思い浮かべ、我に帰る。その少女はあまりにも藤壺に似ているので、思わず涙がこぼれた。なぜだろうか。今朝、私は朝ドラを見た。祖母と孫の心模様がひしひしと感じ、孫の幸せを祈っていることは昔も今も変わらぬ愛情、三女の私は祖母に育てられ、喜びも悲しみも味わった頃のことを思い出しました。(祥)
横浜源氏の会
2016年4月7日 横浜市市民活動支援センター
花を散らす生憎の雨にもかかわらず、ちいさな会場にあふれんばかりの出席者たち。新しい巻(若紫)に入って会員の心も高まっていて(若紫にちなんだ紫の着物、源氏物語絵巻の帯の生徒の姿もあって)、先生の講義にも自然と熱が籠る。あとで聞くと、先生は術後の身を押しての出講だったという。
【若紫】14頁~24頁
光源氏は、瘧病の治療のため評判の高僧の加持祈祷を受けに北山の寺にやってきた。その合間に、春の陽に誘われるように、あたりを散策した。そんな源氏に供の人たちはいろんなことを面白可笑しく話して聞かせる。なかでも播磨の国主の息子が語る、明石入道の話が源氏の興味を強く惹いた。大臣の末に生まれながら、出世が適わず、みずから申し出て播磨の国主になった男で、任期を終えても都に帰らず、出家してしまった。
男には大事に育てた一人娘があって、その将来におのれのすべてを賭けていた。もし願いがかなわないときは、「みずから海へ入って死ね」と娘に遺言を言い残しているという噂だった。
【感想】
明石入道の話がおもしろく、一人の人間性の生き方に興味をもった。
都の位を捨てて播磨の地方で野心を持つ一人の人間と、娘のこれからの展開の物語、紫式部の作家としての才能に脱帽する。(恵)
明石入道という人物の描写が面白い。都での出世競争に見切りをつけ、播磨の守になる。都での近衛中将(従四位下)の地位を投げ捨てて、従五位上の播磨の守に身をやつしても、
実を取って蓄財にはげむたくましさが、よく描かれており、面白い。(雄太)
親心のあり方今もいにしえも同じ事に思い、考え深いものがあります。
しかしそれがすべてでない思いがします。なんとしても目の黒いうちに志を引き継いで
もらいたいと言う入道のなみなみならぬ思いがヒシヒシと感じられます。(M子)
明石入道の話から明石の上の話の段でした。次回は若紫に入るようです。
入道の話は面白かった。娘の明石の上の運命、心がまえ、しつけを知り、よい勉強になりました。
次回からがまた楽しみです。(N)
供人から、明石の入道の出家の様子や、財の事の話、また入道に育てられている女の話を聞き、その女に興味を持っていく様子が後の物語の発展に心惹かれた。(茶良)
明石入道のことを、源氏の供人(播磨の守の息子)が語る所が物語の先を予測させてくれる。
明石入道が位を捨て受領になり蓄財に徹した理由がそのあたりにありそうで、これからが楽しみ。(Y)
夕顔が終わって、展開が急に早くなって、読者としては思わず話に引きずり込まれていく。とくに明石入道の話は当時の貴族の事情がよくわかっておもしろかった。(極楽とんぼ)
源氏を慰める供人たちの話
源氏も供人たちと洛北から眺めた春霞の都。先日、同窓会があり全員喜寿を迎え、上野の森へ花見にでかけた。国立博物館の裏庭の開放で、思う存分桜のトンネルや池の周囲をゆったりと散策した。眺める所が違っても自然を愛でることは同じように思う。平安時代に移植され京都でも花見の客があふれ、花見の習慣になった。供人は近くに明石の浦があり、近衛の中将を捨て都落ちし前国主と娘と住んでいる。任期が過ぎても都に戻らず頭を下して入道になった。山よりも海を選んで法師まさりしたる人、出家して人柄がよくなった。そこで源氏は娘への関心がはじまる、源氏物語のストーリーの展開、人物がすべて描かれています。(祥)
横浜源氏の会
2016年3月3日 横浜市市民活動支援センター
新しい巻(若紫)に入るので楽しみにしていたのに、体調不良(頭痛、悪心など)で欠席せざるを得なかった。残念。せっかく、予習したのに。桃の節句だし。
【若紫】
夕顔の四十九日の法要も無事に済み、空蝉も主人に従って遠い任地に下って行った。
そんな折り、源氏は瘧(おこり)に罹ってしまう。間欠的に熱が出、悪寒と震えに襲われるマラリア性の病気である。呪(まじな)いや加持祈祷を行なう行者を手を尽くして探し出し、呼び寄せて、治療を試みたものの、一向に効き目がなかった。
困り果てているとき、北山(京都北方の山地)の寺に衆生を疫病から救う高僧がいるという噂を耳にし、使者を遣わせたものの、高齢の故をもって断られてしまう。そこで、源氏は身近の供人を数人連れて、自ら北山に聖を訪ねて行くことにした。
聖は一目見るなり、正体を見抜き、さっそく準備を始め、源氏に取り憑いた病魔や物の怪(け)を追い払う加持祈祷を熱心に夜通し行なった。
源氏は読経の合間を抜け出し、見慣れぬ風景に心奪われながら周りを散策した。そんな源氏に供人たちは諸国の話を面白おかしく話して聞かせるのであった。
【感想】
若紫に今日から勉強がはじまった。たのしみである。
ひじり、僧都など対比として登場し、くらま山からの京都の美しい景色、山の桜などの描写は、とても印象に残りました。(N)
源氏一行の健脚ぶりに驚きました。(桜子)
あかーと云う言葉 始めてで、驚きました。(ダン子)
私の若い頃に京都に住み、「源氏物語」の源氏の歩いた道が絵のようによみ返り、北山の風景と重なって、これからのすばらしい風景と物語りが楽しみです。
十八才の源氏は、どんな女性と恋に落ちるのか。(恵)
病を治しに北山に行った源氏と会った聖の驚きが面白く思いました。また、聖の庵室の後の山に立って見下ろした風景に心奪われる源氏の顔が浮かぶようでした。(茶良)
僧都と聖、聖が源氏を一目で見破る。その時の表現「おどろき騒ぎ」は非常に興味深い。
また、供人が源氏をなぐさめる話が面白い。源氏が感動して「絵にいとよくも似たるかな」とつぶやく様子が目にうかぶ。(マスピー)
美しい描写である「はるかに霞みわたりて……絵にいとよくも似たるか」という文章は、作者は実際の風景を見て書いたのではなく、文字どおり絵を見て類型化されものを書いているとも言えるのでは。文章の力を感じさせる。(アキラ)
若紫の巻
源氏 18才
源氏の瘧病が「ししこらかしつる」こじらせてはと周りの者たちが心配して北山の行ひ人のところへ惟光とお供を連れて、夜明けに二条院を出た。当時は医者はいなく、病を治してくれるのは僧侶だった。僧侶には二種類ある。行ひ人は修業をした人。
昨年の初秋、私は大原より北山の美山を谷越え山越えて花背、鞍馬、花折り峠を九十九の坂を登ったり下ったりして琵琶湖へ行って来た。弥生の末になれば、都では花盛りが過ぎ、北山は山桜の見頃で、源氏は十二分に景色を楽しんだ。宮中にいると、このような美しい景色をみることなく新鮮だった。身分社会では生まれ育ちで雰囲気で高貴な源氏だとわかった聖は、「あなかしこや」とああ慎むべきことだと敬う。私は幼い頃祖母とお経を諳んじた後、御文書の終りに「あなかしこ」「あなかしこ」と二回静かに唱えた。
源氏は大徳にめぐりあってホっとした。そして大徳の祈りがはじまるのである。
僧都(朝廷から授かった人)の庵は立派で、今は心恥かしく普段着で来たことが悔やまれる。庵には雑用係の清らかな女の子が仏前に水や花を供えたりしている。僧都が女を住まわせているのではないかと小柴垣よりのぞいた。源氏は一生懸命に修業をする。お経を読んで病を忘れようとする。供人も病気のことなどくよくよしないで気分をかえてと源氏をはげます。源氏は高い所より京を眺め、春霞の芽吹きの情景を楽しむ。供人は富士山とかいいところがありますよと慰めた。浦々の話や明石入道の話や須磨の話や構成がおもしろいと先生のお話でした。(祥)
横浜源氏の会
2016年2月4日 横浜市市民活動支援センター
講義開始時間間近に会場に着くと、すでに10人以上の会員が集まっていて、今や遅しと講義の始まりを待つ熱気に包まれていた。そこに5年目に入った横浜源氏の会の成熟を見たのはわたしだけではないだろう。
【夕顔】326頁~342頁
夕顔の葬儀は人目を避けて鳥辺野の粗末な板屋でひっそりと行なわざるを得なかった源氏であったけれども、それを補うかのように四十九日の法要は天台宗の総本山である比叡山延暦寺で高僧の手によってお布施の品々も気を抜かず類例を見ないほど格式も高く執り行った。そこに夕顔に対する源氏の深い愛情と哀悼の念が込められていたことは、いうまでもない。
一方、空蝉が伊予の介に従っていよいよ任地の伊予に下ることを知った源氏は、細やかなたむけの品々を贈る。そのなかには例の小袿もふくまれていた。空蝉との恋に終止符をうつべく、「逢ふまでの形見ばかりと見しほどに/ひたすら袖の朽ちにけるかな」という歌を添えて。それに対して、空蝉は「?の羽もたちかへてける夏衣/かへすを見てもねは泣かれけり」と返歌空を寄こしてきた。
かくて長い、長い「夕顔の巻」は終わりを告げる。
【感想】
自分がつれ出したことが原因で、亡くなってしまった夕顔に対する源氏のなんとなくうしろめたい思いが、手あつく手あつく夕顔を弔(とむら)おうとする姿。
同じ頃、空蝉は、夫とともに地方へ下ろうとする、そこへ持ち帰った小袿を返す源氏。小袿を無断で持ち帰ったこと、これを返すことによって、源氏は、お互いあとを引かない思い出とでもしよう、区切りをつけようとしたのか。(孝)
夕顔の夢に物の怪も添っているのは不吉で恐ろしい。ちょっと考えられない形だ。「過ぎにしもけふ別るるも」の歌で、夕顔と空?の二人の女性を並べて、共に別れることの感慨と確認は源氏にとって青春の一段階が過ぎたのだという意味?(アキラ)
夕顔は病気で逝ってしまう。葬儀は、ひっそりと行われ、侘しいものだったが、四十九日を迎える頃に平静さを取り戻した源氏は、死者の名を秘めながらも盛大に法要を行う。その後も夕顔を想いつづける源氏の悲痛さ。人間関係が錯綜して分かりにくいところもあるが、―惟光、撫子などとの関係―源氏の悲しみは深く描かれている。
一方、夕顔の四十九日の法要が終った頃、空蝉には夫に従って地方へ下るときがやってくる。
源氏は,豪勢な贈り物をして、空?との恋に終止符を打とうとする。夕顔の死による別れ、空?の地方への旅立ちによる別れ。ふたつの別れによる源氏の悲痛な心情があはれに描かれている。(雄太)
源氏の歌もかなり大げさに表現して、自分の気持ちを伝えていると知り、漢詩の「白髪三千丈」もそれほどまれな表現でもないのではと思った。
場面転換の見事さ、まるで舞台の転換をみているようだ。
t
この巻が発表される頃は、式部の耳に直接いろいろな感想が届いていたのだろう。(桜子)
夕顔の四十九日の法要での、源氏の願文に、夕顔の想いが切々と伝わってきました。また、最後に二人の女(夕顔と空?)に去られた源氏の想いにも胸をうたれました。(茶良)
長い、長い<夕顔の巻>がやっと終わった。快い疲労感とともに、ほっとしたと同時に、いつまでも終わってほしくない気持ちもある。新しい巻へ入っていく期待もあるけれど。
それに、物語のポイント、ポイントに歌が出てくるのも、おもしろいと思った。(とんぼ)
餞別として櫛、扇そして幣(ぬさ)(現在神社等でおはらい等で使っている)であったことは新しい発見です。
小袿を空?に贈ったくだりは、非常にはげしい、恋の終りだった。(マスピー)
軒端の荻は空?にはないにぎやかで明るさを持っていた。新春の講義の後、場所をかえて新年会の席で、会も盛り上り、少々お酒も入って私は終りの挨拶のことを考えていた時、斜め向うの席の先生と目があった時、軒端の萩の内田さんといって下さって内心嬉しかった。その夜は興奮して眠れず、空?の文、軒端の荻の文。何度も読み返し、翌日、同じ講義を受けた友と話し、同じ意見に、又、自から感動しました。軒端の荻は源氏に憎まれなかったこと、それだけでもよかったと思った。源氏は夕顔の法要を立派にやりとげ、念仏や読経も美しい声だったことでしょう。素性のわからぬ女のために源氏は涙をこぼし、深い悲しみを周囲の人がみて、これほど悲しんでいるのはどんな女であろうか。手厚く葬られたこの人は源氏に愛された人でした。源氏の愛した人には女の子がいた。内裏で中将と顔をあわすたびに、夕顔の子どものことをいいたいけれど、恨みが恐いのでついいいだせない。惟光も知っている様子をみせず、源氏物語はそれぞれほったらかしにしないで、けじめをつけていくようです。五条の家では主人と右近がいないだけで、きつねにつままれたように夢のように思っていた。伊予の介の出発に空?も女房など連れていくので、源氏も餞別を送る。その品々は美しい櫛や扇、そしてかの形見の小袿も添えられた。そして訣別したが、空?はショック、そして歌を詠む。?が羽が生え変るように冬衣を着て、私は?のように声をあげて泣いてしまいました。気持だけ寄り添って生きたかった。源氏の元から去っていった二人の女、今日は立冬、時雨模様。源氏は胸にそーっとしまっておきました。失恋の巻でした。後書きでは、源氏は二人の女のことを隠そうとしていた。欠点がない女の作り話、ついほんとうの姿を伝えたかったが、後悔している。源氏は空?との生き別れだが、また逢えるだろうか。(祥)
横浜源氏の会
2016年1月7日 横浜市市民活動支援センター
本年最初の講義は、まだ松のとれない1月7日。14人と参加者も多く、新年から熱気のある講義となった。夕顔、空蝉、西の御方をめぐって活発な意見が会員から発せられ、講義はいちだんと盛り上がりを見せた。講義のあと、横浜駅東口の崎陽軒に場所を移し、フレンチのフルコースという豪華で楽しい新年会となった。
【夕顔】316頁~326頁
夕顔の死のショックにから長らく病の床に伏していたけれど、ようやく病も癒えた源氏のもとへとつぜん空蝉から便りが届く。源氏が重い病に患っていると聞き及んで、伊予の介にともなって任地に下る前に源氏の身を案じて寄こしたものだった。思い掛けない女の文に驚いた源氏は、心を込めて返事をしたためるが、筆跡が乱れている。空蝉といえば、もう一人の、蔵人の少将を婿に迎えたという伊予の介の娘、西の御方は、どうしているだろうか。軽い悪戯心から女への手紙を小君に持たせる源氏であった。
【感想】
話は一転して、空蝉と軒場の荻に。源氏と夕顔の展開の中で忘れ去られたような空蝉、軒端の荻の女心の変化が興味深かった。(Y)
女心の恋のはかなさと、女心の本心は、いつの時代でも、むずかしく、わかりにくいが、源氏の空蝉の思いと、空蝉の源氏への想いのすれ違いにおもしろおかしくて、物語の展開のダイナミックが痛快である。(恵)
源氏物語 深く読むほど感心しますネ。(源子)
夕顔への追慕という悲しいシーンが続いてきたのに、唐突に空蝉の存在が示される。この転換が心憎い。空蝉の人妻でありながらも源氏への思い(思われること)が心の支えでもある、という複雑な心の形、また狂言回し的な役目をもった軒端の荻の存在も、物語の大きなアクセントとなっていると思う。(アキラ)
夕顔の死で、病気になってしまったほど、落ちこんでいる源氏に、かつて源氏から逃げてしまった空蝉は、夫とともに四国へ行かなければならなくなったのを機に、その後源氏から音沙汰のないまま別れてしまうことができず、源氏へ文を出す。ここで、女心の機微が見事に描かれている。空蝉の身代りとなって、源氏と一夜をともにした軒端の荻の女と源氏との関係描写も興味深い。(雄太)
いったん表舞台から消えたと思われた空蝉や西の御方がとうとつに登場するなど、物語には重要な話ではないとしても、紫式部のストーリーテラーぶりを痛感させられる場面ではあった。また、なにをしても許されるだろうという源氏の思い上がりに対して、「御心おごりぞ、あいなかりける」とたしなめる語り手の批判は痛快だ。(極楽とんぼ)
空蝉は身分相応に生活の為に伊予の介と結婚したが、心は源氏にある。それは女心のまことに微妙でセンサイで複雑である。そのことは「益田はまことになむ」一言に表わしていると思う。
源氏の気持は夕顔のことで一杯である。(マスピー)
空蝉や源氏の赤裸々な心が読みとかされ、人の心の動きは、今も昔も変わりないと思いました。(桜子)
再び空蝉が登場してきて、源氏と文のやり取りがはじまり、又、空蝉と間違えて契りを結んだ軒端の荻が再び登場し、今後の展開が楽しみである。(茶良)
空蝉の文
「……憂しとおぼし果てにけるをいとほしと思ふに、かくわづらひたまふを聞きて、さすがにうち嘆きけり。遠く下りなむとするを、さすがに心細ければ、おぼし忘れぬるかと、こころみに、……」
空蝉の源氏への思いを表現するのに、作者は、短い文章の中に、同じ言葉をくり返し使っている。くり返しのリズムの中に、空蝉の本人にも見えていない恋心が吐露されているように感じる。(孝)
「空蝉の文」で皆さんいろいろと意見が飛びかい、七行の原文で1時間たっぷり空蝉の話になった。
源氏の心にはしっかりと夕顔の面影が生きていた。話は変って、何の便りもない空蝉には源氏のことが気になりだし、忘れることができない。気持も高揚し、文を書く。お互いの胸の内を交わし、空蝉も心得ているのに源氏との恋はどうしても不満であるが仕方ないと思う。源氏は片の方(伊予の介の娘西の方の御方)が気になる。蔵人の少将を婿に迎えているようだ。空蝉の巻で1年半前に学習した「人違え」の西の御方との契りを思い出した。小君を使って軒端の荻へ文を渡す。その返事を品なしと。恋多き源氏は又懲りずに前に進む。源氏は上の品の女と付き合ってきたが、中の品の空蝉のもやもやなど、しかし女君の強さ(したたか)も、伊予の介にとってはよかったと源氏は思うのであった。(祥)
横浜源氏の会
2015年12月3日 横浜市市民活動支援センター
生憎の雨もやんで、絶好の源氏日和(?)。ディスカッションルームは会員であふれ、あわてて補助椅子を運び入れる始末。講義のあとは、5階に移って、恒例のコーヒータイムで楽しいひとときを過ごした。
【夕顔】306頁~316頁
秋も深まったある夕暮れのひととき、源氏と右近は亡き夕顔をしのんでしんみりと語り合う。庭を見ると、色づき始めた黄葉が美しく、絵に描いたような深い情趣を醸し出している。虫の音もか細く、いかにもはかなげだ。夕顔に忘れ形見の幼い女の子がいると知った源氏は、自分の元で育てたいと切に願う。また、夕顔と右近は乳母子であって、早くに母親を亡くした右近は三位の君(夕顔の父親)によって夕顔と姉妹のように大切に育てられたことを初めて知る。
夕顔への追憶は女性論をまじえていつまでもつづく。とまれ、素姓を明かさぬまま妙な格好で訪れる自分を信じてついてきてくれた夕顔の君。そのような女君と夫婦として共に暮したかったとしみじみ思う源氏であった。
【感想】
白楽天の思想が源氏の頭によぎり、砧の音と一致する心境と、失くした夕顔の悲しみの深さ。右近との会話の中から、各々の人間像が浮かび、又京都の関係が一歩づつ理解出来てくる物語の魅力が、さらに増えて来ると思う。(恵)
「ものせよ」「ものし」
ストレートに言い表わすことをしないで、気持ちを通じさせる奥ゆかしさにホッとする。
夕顔に対する源氏の思いと右近のイメージが「あえか」と「たのもしき人」とある。いくつもの顔をもつ夕顔に魅力を感じるようになった。(Y)
右近の生い立ち、性格など、新しい発見でした。(磯山)
源氏の心の中は、夕顔を失ったことでいっぱいである。右近と話しても心は晴れない。読めば読む程源氏の心がわかるような気がする。
現在では失われつつあるような気がする。
現在は、心が豊かな人が少なくなっているような気がする。(マスピー)
源氏と右近の会話だと意識して読むことができました。場の様子がありありと浮かびあがってくるので、会話は、人の動きをしっかり見せると思いました。(桜子)
源氏にとっては、別れがたい恋人としての夕顔。
右近にとっては、女主人としての夕顔を偲んでの二人の語らい。
間接的に語られる中で、夕顔のイメージが浮かんで来るところだが、私にとって、もう一つ、夕顔がつかめない。もっと想像してみようか?(孝)
源氏の目をとおして語られる夕顔、右近の目をとおして語られる夕顔の様子に心うたれ、また、夕顔の子供の出現に、この後の期待と興味を感じられました。(茶良)
右近より女君には女の子がいたという話を聞いて、源氏は女君の形見として育ててみたい気持になり、「いとうれしかるべくなむ」と決心する。その女の子は中将の子どもなのだ。中将に知られないように悩んだ末、右近によくいい聞かせて、右近も「いとうれしくなむ」と喜ぶ。最近、人の子を育てることを里親という制度はあるけれど、一度は愛した人の子を育ててみたいというやさしい源氏が見えて来た。秋も深まり、京の紅葉は千年経っても素晴らしく、二条院も紅葉や虫の音など右近は楽しんで幸せを感じていた。五条の家とくらべながら想像して、女君の死がわかったような気がした。女君が恐がっていたことをどうしてわかってあげなかったかと悩む。源氏も女君が幾つだったことも知らなかった。右近は19才だったんですよと伝えた。そして女君と乳母子で、女君の父様(三位の君)に育てられたと話す。女君と同様に育てていただいたのになぜ女君は亡くなって、私だけが生き残ったのかと右近は悔む。しかし女君は頼もしい方で穏やかで繊細で芯があったとお話する。源氏も右近に負けずに女君の柔軟な振る舞いに感心していたことを語る。
宮中のことば「ものし」は古語で、云わなくても伝わる。はっきりしないけれど、わかる。遠慮がちでいいがたい時の申す。源氏物語の登場人物は500人、女房は今でいう職業婦人、源氏は自らダメ男と思っていて、右近に素直に語っている。(祥)
横浜源氏の会
2015年11月5日 横浜市市民活動支援センター
あとで思い出したのだけど、11月1日は古典の日だった。それに、11月3日は文化の日。まさに、『源氏物語』を読むのにふさわしい季節の到来だ。
【夕顔】296頁~305頁
思いも寄らぬ夕顔の死によって病の床に伏した光源氏であったが、一か月もすると癒える。そこで、主人を失った右近を身近に置き、しみじみと夕顔の話をする。それによって、夕顔の真の姿が次第に明らかになっていく。
【感想】
右近から明かされる夕顔の素性、その生い立ち、右大臣家からのおどしに逃げて隠れた夕顔の思いに強く心動かされました。
また、右近から聞かされた夕顔の悩みを知った源氏の感情が身にしみる思いでした。(茶
良)
「ほそやかにたをたをとして……ただいとらうたく見ゆ」と本当に愛らしい女である夕顔が、実は生い立ちの不幸など「物づつみ」をして表面に出さず、苦悩をかかえた女性であった。これはとてもショックなこと。女性の二重性、人間的な闇や深みを教えたくれるようだ。(アキラ)
ごく短い文章の中に当時の世相・政治・それぞれの人物の性格まで込められていて、複雑この上なく感じられました。(磯山)
平安時代の上流社会の女性の生き方(生活の成り立たせ方)に、興味がわきました。生活の激変におどろきました。死して後に話がふっとうする夕顔でした。(桜子)
夕顔という人のイメージが今日の勉強会で変りました。素直で、こどもっぽい純真なだけでなく、大変な美意識を持って生きていたのを、知りました。強さを感じます。(N)
源氏の心に強い思いを残した夕顔の秘みつが、あらわに又美しくはかなく美しい物語を現代まで続くすばらしさを思う。(恵)
右近の目を通して夕顔像が明らかになる。
源氏は女君のことをあやしうと思っていた。女君も源氏のことをあやしうと思いながらもそんな素振りを見せずに振舞っていたと右近から聞き女君のやさしい気持が嬉しかった。
名もあかさず憂きこと思っている源氏にじーっと耐えていたのです。早く身分を明らかにすればよかったと女君への思いやりが足りず、自分を責めて反省していることを右近にわかってもらいたかった。それは無理な話、1回や2回でお互いの気持がわかる筈がない。理解できるわけがない。所狭し帝、北の方(葵の上)の手前、羽を伸ばすことができない――のにもかかわらず押し切って女君に夢中になった。今はそれを悔んでいる。七日七日の供養もどうしてよいか悩んでいる。右近も生前の女君のことを話してよいのか迷いながらも在りし日の女君のこと話しはじめた。女君は上の品で両親は早く亡くなり上流社会では生きていけそうになく、その頃頭の中将と知り合い中の品の暮しになったが右大臣にはよく思われなく身を隠してしまった。女君はナイーブな人ではない。塞がり――違ふとて、山里いも暮せず方違えをして五条に住み夕顔の花を丹精して花を咲かせていた。その花に魅せられた源氏、板屋の家だけど下の品などと思われたくなく、おもてなしをした。そんな健気な振舞いが源氏の心を引き寄せたのです。心の苦悩を表に出すのは恥かしい、私みたいにね。(祥)
『源氏物語』のなかでとりわけ傑作の名が高い<夕顔>の巻は、病気見舞に乳母の家に寄ったとき、ふと隣家の垣に白い花が咲いているのを見て、魅せられた源氏が、従者にその花を手折らせる場面から始まる。そのとき、なぜ夕顔は歌をしたためた扇を童女に持たしたのか。頭の中将がふたたび通ってきたと勘違いしたのだという説を最近読んだ。どうなんだろう。(吟遊詩人)
横浜源氏の会
2015年10月1日 横浜市市民活動支援センター セミナールーム1
早や10月、神無月となりました。すっかり秋らしくなりましたね。珍しく欠席者が多く、参加者は10名。(男性3名、女性7名 内 新入会員 鎌倉在住の磯山ツヤ様)
【夕顔】P288 源氏、病に倒れる~P295 右近と語る
源氏が病に伏して容態が悪くだんだん重体になっていく衰弱していく。
あらゆる人たち、都中の人たちが祈りにみち、云いつくすことができないくらい
源氏のように美しい人は、神にもっていかれたくない。当時美しいものは神が魅入り
天寿を全うできないつまり早死にしてしまう考えがあったのです。絶世の美しさは
その命さえもこの世を超えてしまう。美しすぎるのは不幸と世間の人たちはうわさした。源氏は弱気になり女君とつきあいはじめて三か月。源氏も右近のことを心配してやさしく世話したい気持ちを伝えた。右近も後を源氏に託した。源氏を慰めるのは右近だと惟光の発想で乳母子として配慮している。帝と源氏、親と子、源氏は生きなければと強く思う。穢らいの忌と床上げの日が来て内裏の御宿直所(桐壷の私室)にでかけた大殿は御物忌しなくてはと世話をやく。源氏はほんとうは帝にご挨拶したかったと思った。
久しぶりにもどって来た宮中は別の世界のようだが女君に夢中で過ごしたことを思い出している。右近との語らいの中で真実が明らかになる。病み上がりの美しい源氏は心の傷は癒えていない。時々大声を出して泣きじゃくる。物の怪にとりつかれたように泣く。 (祥)
【参加者感想】
源氏が右近を思いやる気持ちを「よろずにはぐくまんと」という言葉が使われ
はぐくむは、親鳥が羽で雛をつつむの意と知って、とても美しい表現と思いました。 (弓月)
源氏が病に倒れてからの二条院の人々が騒ぐ様子や主人(夕顔)を亡くした後の右近に
部屋を与えて助ける源氏の心配りまた帝が勅使を出し、病の状況を報告させる様子が
ありありと描かれ、心に残りました。 (茶良)
きょうも素敵な言葉に出会いました。女主人を亡くした右近を側近に仕えさせ、同じ
悲しみを共にしつつ、源氏は右近を支えていこうと思う。その思いを「はぐくむ」と
こそ。と表現している。先生のお話によって「はぐくむ」は鳥の羽の「は」と「くくむ」、
「くるむ」、「つつむ」であること。親鳥が子どもを羽の下で、あたたかくつつんで
育てるイメージが広がる。いい言葉です。 (孝)
やまとことばの美しさをいつも講座で感じます。はぐくむの語源が親鳥の羽の下にひなを包んで子育てする(羽くくむ、包む)という。母の温かい愛・・・・・・
古典教育を受けた若い母親なら自分が苦労して産んだことども虐待することは絶対に
しないなと「はぐぐむ」ということばの解説を聞いていてふと思った。 (弘)
源氏は二条院に戻るまま病気になる。何故 ?・・私(マスピー)の考えとしては、源氏は物の怪の世界に入ったと思う。実際に物の怪の世界にひきずりこまれたのは夕顔であった。源氏はこの世に残ったが心身ともに極度に疲れたのだと思う(後遺症である)。
その時是光がこれ以上出来ないくらいの介護を源氏にする。惟光の配慮により右近と源
氏を救ったと思う。惟光の手腕が光っているところだと思う。
現在の世にも惟光の手腕を持っているものは居ると思うが、大多数はメディアを騒がせる悪徳の者であろう。今の世にもあてはまるのではないだろうか。 (マスピー)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●物の怪(気)について
夕顔は死んでしまった。源氏や右近は嘆き悲しむ。又それを支える惟光にくっとくる。
悪霊は人に取り憑いて病気や死に至らしめるような危害を加える。死霊と生霊がある。
夕顔の巻で夕顔に憑いて死に追いやった物の怪(絵巻で楽しむ源氏物語 ことば辞典 より)。
-先日鎌倉芸術館で愛するゆえの女の情念の田中順子先生のレクチャーに参加した。六条御息所の真の姿を求めてのお話であった。「葵の巻」では葵上に憑いた六条御息所の生霊など、これから読む楽しみがふえた。
-先週、初秋の京都にでかけた。行ってみたいところは夕顔町。夕顔の石碑がありました。源氏とのはかない恋、源氏にとって忘れられない恋だった。五条あたりを散策し小さな車が一台通れるくらいで、民家の前には夕顔が咲いていた。夕顔を偲んでしばらく
たゞずみ久しぶりに旅を楽しみ京の空は晴れの日でコバルトでした。 (祥)
☆ 源氏物語を紐解く講座(鎌倉芸術館)☆
9月19日の田中順子先生の公開講座では大広間で130名の参加で盛り上がり青景さんが原文の朗読。私たちもご一緒に音読しました。又茶話会では大内さんが須磨の巻を語ってくれました。 (祥)
横浜源氏の会
2015年9月3日 横浜市市民活動支援センター
この会も回数を重ねるにつれて、顔ぶれも固定し、講義も和やかで和気藹藹とした雰囲気に始終した。講義のあとは五階に移って、先生を囲んで恒例のコーヒーを楽しんだ。
【夕顔】280頁~288頁
夕顔に今一度会いたいと、立待月のもと光源氏は惟光や随身をともなって東山の寺に向かう。弔いの場に着いてみると、右近が板屋に伏して泣いている。源氏は、亡骸に向かってもう一度声を聞かせてくれと懇願し、声も惜しまず号泣する。右近に一緒に二条院へ行こうと誘うが、右近は女君と離れるわけにはいかないと泣く。
惟光に促されて、朝霧のなか、山道を帰路に着く源氏。しかし、川の堤まできたとき、憔悴のあまり馬から落ちてしまう。
ようやく二条院に帰り着いた源氏であったが、心痛のあまり床に就いてしまう。
【感想】
互いを思いやり、やっと二条院にたどり着いた源氏と惟光。そんな二人の事情を知らず、不快感を抱く女房たちのザワザワした感情の対比がおもしろく思いました。(弓月)
女(夕顔)の死骸に対面した源氏の心境や、帰り道、源氏の落馬にうろたえる惟光の心境が、ありありと伝わり、その悲哀感に心をうたれました。(茶良)
突然の夕顔の死、その後の源氏、右近、惟光の心の内がそれぞれに細かに語られている。
普段見られない三人の追いつめられた様子が印象的。(Y)
源氏は3歳で母を、6歳で育てて呉れた祖母の死を経験している。そして、今、17に(大人になって)、いとしい人を、突然の形で失ってしまう。茫然自失、悲しみの極限に直面している。女をあきらめきれない様が、せつせつと式部は語っている。それは父・桐壺帝が、更衣を失った時の様子と重なって、読み手に悲しみを増幅させる。(孝)
源氏が人目もはばからず大泣きするは、現在と違って人間として非常に純粋であったと思う。覚めている部分もあるが、この世のことでない体験をした惟光(源氏もそうであったが)は気も動転して神仏にすがる。しかし、この二人は共に助けあう。打算が入らない関係である。二条院の女房達はますます疑いの色を濃くする。(マスピー)
今回は、夕顔の死の場に源氏が行き、死の悲しみを極限まで語りついたように感じた。(N)
「御紅の御衣」が輝いて見え、夕顔が美しいままこの世から消えたのを印象づけられました。
帰宅後の二条院の人々の反応が冷静に書き込まれているのが、物語に厚みを作ったのだと思いました。(桜子)
夕顔の急死からつづく一連のシーンは、悲劇であるはずなのに、源氏の馬から落ちて落馬した場面には思わず笑ってしまった。このへんの悲喜劇の描写は、大作家レディ・ムラサキの腕のさえをまざまざと感じさせた。(ズボン堂)
夕顔の死に対する悲しみと態度が、いろいろな表現で表わされて、感情の移り変わりがとても面白い。鳥辺野へと見送る時、「うとましげもなく、らうたげなり」とあり、板屋に横たわる夕顔には「いとらうたげなるさまして」といずれも美しく可愛い様を強調している。そこがまたすごい。(アキラ)
女君の亡き骸と最後の別れ、まだ生きているようで可愛らしく思わず声をかけ、私をお
右近も女房と一緒にあの世に行きたいと申せば、源氏は別れは辛いだろうが私を頼りにしてと言う者の、源氏も女君を念じ、穢れを穢れと思わないで、源氏の心模様を作者は読者に細密に死の悲しみを伝えている。右近の悲しさを心配した源氏は二条へ来られたらと勧めるが、右近は小さい時から一緒に過ごして来たため、五条の人たちにどう話していいか途方に暮れ、主人の煙といっしょに空に昇ってゆきたいと涙する。右近の身を案じているが、源氏もそれどころではない、時間がない、荼毘にされもう帰らぬ人となり、最後の別れになる。何度も何度もふり返り胸もっと塞がりて馬に乗って朝霧と朝露の鳥辺野を下る時、――御紅の御衣(源氏の着物)で横たわっている女君を想い出し――愛の衝撃、精神的なショックで)馬からすべり落ちそうになり(源氏は神の下で育ったひ弱な人)、惟光は人間こういうこともあるのだなと何度も何度も手で押さえていましたが、とうとう馬から落ちてしまいました。もう意識もなく、このまま途絶えてしまうのではないかと。惟光はパニックってしまう。源氏自ら必死で祈る。惟光も清水観音に祈る。惟光の手当てで漸く二条院へたどり着いた(二人の関係はうらやましいほどである)。女房たちも心配して嘆く。しばらく源氏をしばらくそっとして休ませてあげよう。(祥)
横浜源氏の会
2015年8月6日 横浜市市民活動支援センター
いつものように暑い日でしたが、いつものように楽しく講義が行われました。ただ、講義後にちょっとした趣向がありました。すなわち、みなとみらいの、海を見下ろすレストラン「橙屋」で暑気払いが行われたこと。櫃まぶしをおしゃべりしながらおいしくいただきました(ごちそうさまでした!)。
【夕顔】269頁~280頁
夕顔の死によって二条院に帰った源氏は、悲しみのあまり御帳のうちに引き籠って見舞い客にも会おうとしない。そこへ現われた惟光を傍らに呼びよせると、夕顔のことを事細かく聞く。語る惟光もそれを聞く源氏も、袖を顔にあてて涙にくれる。惟光の導きによって平静にもどって、錯乱した右近の様子なども聞く。そのうち、どうしても夕顔にもう一度会いたいと思うようになった源氏は、惟光の反対を押し切って身をやつし、数人の供を連れ、馬に乗って、立待月の月明かりをたよりに夜道を夕顔が葬られる物淋しい東山の鳥辺野へと向かうのであった。
【感想】
葬儀の手配をする奔走ぶりと、源氏を励ます惟光の様子。もう一度亡き女に会いたいと云う源氏に対する惟光の思いやりや、その場に立った源氏の心の動きが手に取るように感じられました。(茶良)
久々の講座 大変楽しく学ばせて頂きました。源氏の 心深い女への思いが ひしひしと心にしみ渡りました。東山の夜道のおそろしい中をひたすら女の骸を目に焼きつける
と思う源氏 実にすばらしく思います。(M子)
源氏は、まわりの人に本当の事が云えず、惟光と夕顔の死をめぐって、策をねる、その様子を女房たちは、なにか変だと疑う。その様を式部は、「ほのぼのあやし」と表現する。情景をあざやかにほうふつとさせる。まさに「言いえて妙」。又、一つ源氏から奥深い言葉を教えてもらった。(孝)
惟光が日暮れどきに現れて、すべてを取りしきる。夕顔の異常な死が世間で取りざたされないよう、内密に処理するのである。それは必要なことであり、それを適切に実行する惟光は有能な人物である。源氏の悲しみは深く、何とか夕顔を生き返らせることはできないかと願うが、それが不可能と知るや、どうしてももう一度夕顔の屍骸に対面しようとする。惟光は、そのようなことはもってのほかと思いつつも、源氏の願いをかなえることとす。源氏は馬に乗り、惟光等を従えて、まっ暗な遠い道を夕顔の屍骸が待つ鳥辺野へ向かう。屍骸のある寺の静しゅくとは対照的に、近くの清水寺には光が多く見えている。(雄太)
源氏の思いの深さと大胆さにおどろいた。(桜子)
源氏が 鳥辺野へ夜中に行くということに想ぞうを絶する気がする。源氏の純スイさがみえる。惟光は仕事の為といえ大変だったと思う。(マスピー)
道遠く暗い京の町を、馬に乗って恐ろしいとも感ぜず只、女の遺体に会いたいと言う、その源氏の気持に添う惟光の、けなげな強い使命にささえられて、源氏の恋の悲しみと、鳥辺野のすごさの風景、仮屋の右近の泣き声と清水寺の光のにぎやかさ、文学をささえる対比の風景に、絵巻が目に浮かび、作家のすごさが一段と感動!(恵)
二条大路から馬にのり、夜、鳥辺野に夕顔に会いに行くところが、大変印象深く残りました。(N)
鳥辺野の夜、尼の住いから、女の泣き声が聞こえてくる情景はなんとも痛切きわまる。近くで経を読む法師たちの様子も含めて小説の世界の広がりや闇の濃さを感じる。作者の筆力のすごさを。(アキラ)
惟光の覚悟
源氏はまだ女君の死を受け入れられない。
生きをふき返すのではないだろうかと。
源氏は袖に顔を押しあて、しぼりあげるように泣く。惟光も大泣きする。しかし、惟光は死の真実を説得する。右近も一緒に逝ってしまうのではないかと源氏も女君の後を追いたい―。気弱になり生きていけそうにないと弱音を吐く。困ったものだ。惟光は源氏を立ち直らせなくてはと決心し、後始末の事を伝え、源氏も惟光に対して立ち直らなければならないと思う。そこが源氏のいいところ、男の友情を感じる。しかし、女房たちは、何か隠しているのではないかと勘繰られる。
丁寧に葬ってもらいたい願いから女君の葬儀の作法を惟光に伝えるが、惟光は表沙汰にならないように大袈裟にならないように配慮しているのにと思う。さらに悲しみが押し寄せて、女君に一目みたいと、葬る前にもう一度顔をみて確かめたいと無理に依頼する。惟光は源氏の気持を察し、着換えをさせ、例の大夫随身を連れて闇の中を東山鳥辺野の火葬場へと向かう、立待月の月が東山の向うに出、月光が一向を照らす、真暗な闇に女君が横たわっているのを思うと源氏はいたたまれなく胸がはりさけんばかり穢れに向かって行く。
あたりさへすごきに――ぞっとするような恐ろしいところ、粗末なところに尼が勤行している、うす暗いほのかな燈明の中声をたてないで念仏してお経をあげていて、右近の泣き声が聞こえる。
源氏は悲しみが増して涙が止まらない。清水寺と鳥辺野が印象深い。(祥)
横浜源氏の会
2015年7月2日 横浜市市民活動支援センター
雨催いの日であったが、会場も先月からゆったりとした広い部屋で、新しい人の参加もあって、楽しい講義となった。また、講義後の楽しいコーヒータイムもすっかり定着したようだ。
【夕顔】261頁~269頁
二条院に帰るとそのまま御帳に入った源氏を自責の念が襲う。なぜ焼場まで夕顔に付き添って行かなかったのか、と。もしかしたら生き返るかもしれない。そのとき、傍らにいなかったら、女は見捨てられたと苦しむにちがいない、と。そこへ内裏より御使いがやってくる。源氏の姿が見えなかったことを心配した帝が、寄こしたのだ。そのなかに頭の中将を見つけた源氏は、招じ入れて御簾越しに作り話をする。乳母を見舞ったところ、たまたま下働きの者が亡くなり、穢れの身になってしまった。そこで宮中に参内することを控えていたのだ、と。
【感想】
心底から愛する女、夕顔を死なせてしまった源氏は、取り乱しつつも、帝のもとへ出仕できなかった理由を取りつくろうために、乳母にかかわる事実を基にした嘘の物語を創り出し、事こまかに中将に語る。危機に直面した源氏のしたたかさが見事に描かれている。(雄太)
やっと思いがかなって、夕顔と二人きりの夜を過ごし、源氏は、恋の絶頂の中、相手が急死することによって恋する気持が立ちきられてしまう。
しかし死は現実。源氏の心のあて(・・)を失った様子が目に浮かぶ。大内さん、さすが『これまでの空蝉、のきばのおぎへの源氏の対応が格段に違う。』ということと、『源氏がここで絶望を味った』ということを指摘して下さいました。納得です。(孝)
二条院に戻った源氏が、もし夕顔が息を吹き返したら自分のことを冷たい男と思うだろうと行かなかったことを悔む心の内の悲壮観と、源氏の作り話でごまかそうとするのを見やぶる中将の場面が面白く感じられました。(茶良)
原文と解説と交互に出てくるので、立ち止まって読むことができ、集中しやすい。
源氏は、なかなか、したたかな人だと思った。(桜子)
恋人の死の悲しみの極みに絶え入りそうなのに、公的な立場や父帝とのしがらみが押し寄せてきて、そうした現実に対してくどくどと言い訳を並べる所がまた面白い。悲しみの
死の穢れの話が出てきて、興味を惹かれた。考えてみると、すでに仏教は渡来していたけれども、『源氏物語』の時代はまだ古代。死に関しては古代人の感覚がなお濃厚に残っていたことがわかる。(ズボン堂)
惟光の父の乳母、お年は何歳ぐらいだろう。源氏、惟光十七才、惟光の父は三七才位、はて乳母の年令はと、一〇〇〇年前を思い巡らす。乳母は年をとって信頼されている。山寺で尼になっているので、安心な場所へ、女君の遺体を右近と共に運ぶ。源氏の悲しみを少しでも手助けできるように丁寧に扱った。源氏はなぜ女君に付き添わなかったかと悔む。苦しくて御粥も口にできず、女君を失った寂しさが募る。内裏では源氏の行方不明を帝も心配している、頭の中将もやって来た。そこで源氏はどう釈明したのだろうか。困惑しながら作り話をしてしまった。中将は信じなかった。引返した中将の目をみて白状し、死者の穢れに携わったことを帝や大殿にも伝えた。(祥)
横浜源氏の会
2015年6月4日 横浜市市民活動支援センター
相変わらず暑い日の午後だったけれど、いつもと違う、広い会場でゆったりした気分で講義を聴くことができました。また、講義のあと、いつものように場所を5階に移してセルフサービスのコーヒー(50円)を飲みながらの、先生を囲んでのお茶会もすっかり定着。おしゃべりに花を咲かせ、和やかなひとときをすごしました。
【夕顔】251頁~261頁
夕顔の突然の死にすっかり動転した光源氏は、惟光を呼びにやるが、なかなか現れない。そのうちに一番鶏が鳴き、夜明けが近いことを知って、緊張の極点に達した源氏は涙をしとどに流す。そこへやっと惟光が現われて、てきぱきと事を処理する。すなわち、源氏を馬で二条院へ帰すとともに、夕顔の亡骸はふとんにくるみ、右近を付き添わせて、人目につかぬ東山あたりの山寺へ埋葬しようというのだ。そのとき、ふとんからこぼれた夕顔の豊かな黒髪の美しさはえもいわれぬものがあった。
【感想】
夕顔の死に面して悲嘆する源氏。その事態に対する惟光の采配ぶりの場面が、あざやかさが鮮明に想像させられました。(茶良)
惟光は、主人の源氏のなみだに同調してはげしく泣いたが、主人より世にたけているので、しゃべりながら、どこか無難な場所を捜している様子がありありと描かれている。源氏は納得して惟光の指示のままに従うきになる。
惟光は主人(源氏)の為に身を捨てる姿がみごとに描かれている。(マスピー)
今日の場面で、惟光の源氏につくす様が、単に乳母子としてより、源氏の魅力にひきつけられていると見た方がいいか、「われかのさま」の状態の源氏に乳母の子としてなんとかして傷を付けずにという思いでいるのか、その両方がないまぜた気分なのか……と。(Y)
悲しく美しく哀れな物語の最高表現が出ていると思う。源氏の胸に迫る驚きと感情と惟
光の冷静さが対比して、物語を盛り上げている。右近等側の人達も目に浮かび、そしてこれから長くストリーに、どう反映させていくか、源氏物語が読み継がれていく魅力があると思う。これからが楽しみである。(恵)
夕顔の亡きがらの描写が、直接的な表現をさけ、「うはむしろにおしくくみて」全身は見えず、ただ豊かな黒髪だけがこぼれ出ているのが雅で美しく、いかにも『源氏物語』にふ
さわしいと思った。(ズボン堂)
女君が亡くなり、源氏の泣き嘆く様を間近にした惟光は、最初は源氏の気持を察し、共に泣いていたが、その後は我にかえり、女君のなきがらの処理、源氏を二条院にもどす等、てきぱきとした動きを取る。悲しみにひたる中、次の舞台へと惟光がキーマンとして動く。その必死の様子が生き生きと感じられる。(孝)
美しい錦の縁どりの≪うはむしろ≫から豊かな黒髪だけがこぼれ出ている様は、遺体と
なった女の妖艶さが引き立つ話と思いました。(弓月)
白地に地模様が浮き織りにされた唐綾の表に、紅の絹の裏を付け、周囲に約三寸程の錦を付けた(うはむしろ)。中に薄く綿が入っている。金、銀など五色の糸で織られた厚地の錦の縁どりが高貴な輝きを放っている上質の(うはむしろ)にくるまれる。らうたげな遺体の黒髪がこぼれ出でたる美しさ。ここの段は、あまりにも美しい表現で、女君の遺体の様子に、エロティシズムを感じる。日本文学の美ともいえそう。(N)
詩や散文詩ならば、夕顔との物語は夕顔の死で終え、後の事は余情や想像にまかせることになる。しかしこの物語は惟光という他者を登場させ「いとめづらかなること」と大悲劇を客観化し、様々な現実的差配を行うことを書き込んでいく。そこが源氏物語のそれまでの昔語りを超えたすごさなのでしょうか。(アキラ)
とまどう源氏、恐ろしい一夜の出来事で疲労困憊。惟光の朝臣をみるなり今まで気丈夫にいたが気がゆるみ大泣きする。泣きの源氏。
右近は大夫(惟光)が来たらしい――主人が死んだことで悲しく泣く。源氏もひたすら泣くが泣いてはいられないが――思い切り泣いた。信じられないことが起ったので祈願しようと思い阿闍利を呼んでほしいと頼むが阿闍利は山へ帰ってしまった。惟光は冷静に判断して 病だったのかも。「いとをかしげにろうたく」子どもが甘えて泣くようにはげしく美しく泣いている、惟光ももらい泣きをする 男の友情を感じる。
源氏も惟光も若く身分も違って、夕顔の咲いている五条の家に遺体を安置すればどうなるかを考え無理だと思い、山寺がよいことを勧め源氏も納得。源氏を守らなければと夜が明けるとまずいので早くこの場所を出て二条院へお帰りになって下さいと指示する。急いで車を用意させる。源氏は女君の死をまだ受け入れられなくて抱きかかえることもできそうにないと惟光は思い車に乗せた、丁寧にうはむしろでつつんだ。(うはむしろは豪華な掛物)ところが髪がこぼれ生きているように美しかった。源氏ははじめて悲しく覚え涙がとまらない。
惟光は心を鬼にして、とにかくこの場所を出て下さいと。後に惟光が右近と亡き女君を東山の庵に連れていく。惟光の馬に乗せられた源氏はやっと二条院にたどりつけたが 半ば意識もなくなっていた。可哀想な源氏です。(祥)
横浜源氏の会
2015年5月7日 横浜市市民活動支援センター
長い連休あけのせいか、珍しく欠席者が多かった(狭い会場でちょうどよかった?)。来月(6月4日)からは広い会場になるので、窮屈な思いをせずに講義に集中できると思います。また、長らく会場が固定せず、遊牧民のようにあちこち会場を移動していましたけど、そんな苦労は今月で終わり。次回から支援センターに固定されます。
【夕顔】242頁~251頁
物の怪に取り憑かれた夕顔は、あっけなく息絶えてしまう。突然のことに源氏は呆然とし、途方に暮れる(読者もびっくりしたけど)。泣き崩れる右近を慰めることもできない。源氏の命を受けて惟光を呼びに預かりの子が去ったあと、荒れ果てた屋敷にひとり取り残された源氏の思いは悪い方へ悪い方へと巡っていく。女のことでこのような報いを受けるのは、かつて身分不相応で恐れ多い恋(藤壺との恋)などしたからだろうか。
【感想】
その夜惟光の朝臣が居合わせていれば、ものにおそわれても、少しはどうにか対処できたかもしれない。一人で耐えなければならなかった源氏はさぞ大変だっただろう。
それにしても≪はかなきやどり≫には泊まらない様、気をつけたい。(弓月)
夕顔の死を前にして、源氏や右近の動ようの状況がひしひしと伝わってくる場面に感動しました。また、源氏が一人自分だけは<さかしき人>と思っているところに悲哀の中に少しおかしみも感じられました。(茶良)
女君の突然の死に遭遇し、頼りにできる者もいない状況の中で、源氏が取り乱しつつも、何とか己を失わず、冷静に対処しようとする様が見事に描かれている。作者紫式部の人間観察の深さがよく解る。(雄太)
今までにないおもわぬ場面展開で源氏の思い、心の内がていねいに書かれています。先生の解説によりよく想像できました。
私はお互いに想っている二人の恋をもう少し愉しみたかった。(Hana)
灯がすべて消えた中、やっと灯を預かりの子が持って来て、長押の所でおろおろするなど、ともすのに時間がかかってしまった様子が、しっかりと書かれている。そして灯がともされる時、「いとおしげなる女」の幻影があらわれたと源氏は感じる。
灯がともると、夕顔は、冷たく、むなしくなってしまっている。夕顔の死は、すべて暗やみの中で、おきてしまった。灯の明暗を、作者は上手に大変な死を読者に強く想像させているようだ。(孝)
枕上に、夢に見えた容貌をした女の面影が見えたと思うとふと消え失せてしまう。同時に夕顔の君を抱きあげれば、すでに息は絶え果てていた。冷えに冷え入りていた。夕顔の突然の死における源氏の様子。古文の短い文面の中にどれだけ、心のもようが深く、また情景、場面が手に取れるように感じることができたことか。「あっ!」という間の展開のはやさに、おどろきを持つ。また、「あるまじき心の報い」藤壺との関係を思うと、『源氏物語』のなみでない人間の奥の深さを感じました。(N)
本日はゆったりした気分でお勉強させて頂きました。ありがとうございました。(曽我)
物の怪に取り殺されるなどいうのは、現代人からすると荒唐無稽でなかなかに理解しがたいことだけど、そこまで想像力の舌先を伸ばさないと、『源氏物語』を十全に鑑賞することも困難になるように思う。(ズボン堂)
闇の中での出来事。今までは「女」でしたp234で「女君」となる。
「息絶えた女君」
息は疾く絶え果てにけり 右近も恐くて腰がぬけそうになって動けなくなる。女君をゆさぶり目を覚ましてほしい――。しかし、息は途絶えていた。源氏は途方に暮れるが、そんな場合ではない。「あが君、生きいでたまへ」と叫ぶが、その甲斐もなく死んでしまった。右近も悲しく泣く。若い頃児童文学を勉強したことがあった。物語や小説を書くには「死」を書けなくては――と教わった。童話でも同じだ。なかなか死が恐くて書けなかった。源氏は女君の死をみとめていない。ずーっと孤独に堪えて一番鶏(午前3時)も鳴きだしたとたん力がぬけてしまった。可哀想な源氏だ。(祥)
横浜源氏の会
2015年4月2日 横浜市市民活動支援センター
気持ちのよい晴天。ジプシー状態だった会場も固定化してきたせいか、参加者も過去最高の16名を記録し、会場も手狭状態。会員の皆様には窮屈な思いをさせてしまって申しわけなかった。
【夕顔】232頁~241頁
やっと二人きりになったものの、荒れ果てた屋敷は人の気もなく、日暮れとともにいっそううら寂しく感じられた。うたた寝する源氏の枕元に優雅で美しい女が座った。そして、恨み、つらみを源氏にぶつけるのであった。ただならぬものを感じた源氏はふと傍らの女に目やると、様子が尋常ではない。物の気に取り憑かれたようで、怨霊に怯える右近は頼りにならないし、供人を呼ばわってもだれも現れない。そこで、意を決して渡殿まで行った源氏は、やっと現れた殿上童に明かりを点けさせ、邪気をはらうようにいい付ける。そして、寝所にもどると、女君は息も絶え絶えで身動きもしない有様であった。
【感想】
宵すぎに源氏は夢とも現(うつつ)ともつかぬ女のものの怪を感じるところから不可思議な物語が展開する。しっこくの闇の中、あかりが次々と消えて女君は、息たえる。源氏はたしかに六条の女君のことをこの時、感じてはいるが、女君は同時に何に息をひきとるほどおびえたのか。同床異夢か。(孝)
今日の源氏の場面は、幻想の世界であり、大変恐く、もののけの女と驚く源氏の姿の描写が真に迫っていて、大変おもしろかった。いとをかしげなる女とは……源氏の心の底にある想いの影なのか、又なぜ女君も恐怖にかられて正気を失うストリー性など、いろいろと場面が展開する事に楽しみがある。(恵)
寝殿で何か異変があっても渡殿では気がつかない様なので、あまり広くては用が足りないと思いました。(弓月)
1年ぶりの源氏の会
今日は枕上の女でした。やっぱり源氏はゆっくりと読んでいくものですね。人間の心の深い見えない所を書いているので、何度読んでも感じる所が多く深みにはまります。田中先生、青ちゃん、すてきな時をありがとうございます。(夢光香)
物の怪を受けるアンテナを源氏ただ一人が持っているか? あるいは 生霊を源氏一人が受ける原因があるのか、深く読みたいと思います。(轟さんが体験したことは本当にあるあると思います。やはり「アンテナ」を持っておられると思います。)
女君はアンテナを持っていて、枕上の女を感じて、恐怖のあまり亡くなったと思います。
(マスピー)
宵過ぐる時刻に、源氏の枕上に〝いとをかしげなる〟女が現われ、自分を見捨てたことに対して恨みごとを言う。源氏は宿直の者たちを起こそうとするが、起きてくる者がいないので、自ら人を起こしに向かう。その後、寝床にもどると、その場の雰囲気にもともとおびえていた女君は、失心して死んだようになっている。その無気味さリアルに描いている式部の力量は、並大抵ではない。(雄太)
前回の源氏と夕顔の愛の高み、ロマンチックな場面の直後に、物の怪に憑かれて暗転するのにとても驚かされてしまう。物語の最も印象的な個所の一つです。夕顔がずっと不安定な精神でいたことも思い起こされます。(アキラ)
これから源氏と夕顔の楽しい語らいの場面がくり広げられるものと期待していたのに、突如、思わぬ展開をみせたので驚いた次第。(ズボン堂)
枕上の女
源氏は真面目に五条の女と素晴しい時間を過ごしている。源氏だけではなく、読者の男性は夕顔の女が好きのようである。
宵過ぐるほど(日没から十時ぐらいの時間)に源氏は夢を見た。枕の上に美しい女がいて様子がおかしい。恨みをぶっつける。まさかと思う、六條あたりに住む女が、心の闇にでてくる、心の鬼がでてくる。源氏はぞーっとする。物の怪を感じて太刀を引いて追い払う、若い右近も体が動かない。女もどうにもならなくなって正気を失っていく 突発的に一瞬の出来事がなにがしの院で起った。
この女は昼も恐がって空のみ見ていたなあー。源氏はどうしても女を救わなければと闇の中右近を引き寄せ奮闘する。闇の深さが想像できる。源氏は不安になる 女君を手さぐりしたが、息とだえている。途方にくれる。
このような荒れたところでは狐など出てきて馬鹿にされる。まろ(源氏)がいるから大丈夫だよ。右近も気分がすぐれずおかしくなった。女主人を守らなければといえば源氏もそうだそうだとうなずく。
今日は原文から離れないように想像するようにとのことでした。
読者はまどわせられる。(祥)
横浜源氏の会
2015年3月5日 横浜市開港記念会館
国の重要文化財に指定された、日本大通りの開港記念会館での初めての講義。クラシックな建造物で、まさに『源氏物語』という雅な古典の世界にふさわしい雰囲気だった。出席者も15名と、これまでの記録を更新。講義もいっそう熱のこもったものになった。
【夕顔】222頁~231頁
やっと二人きりで静かに時を過ごせる屋敷に落ち着いた源氏は、顔を隠していることをやめ、正体を明かす。と同時に、女にも名を名乗るように迫る。ところが、家も定まらぬ不安から、女は身を明かそうとしない。
いまごろ、内裏では源氏がいないことに気づき、大騒ぎになっていることであろう。また、源氏はこのところ足が遠のきがちの六条の君のことをふと思い起こし、<あはれ>と思うのであった。
【感想】
夕顔を心から恋に燃えている源氏……それに添い ユーモアも出して 心をなごませる夕顔はすばらしいと思います 身分を 明かさず 心をときあかし和らげる所など実にすばらしいと思います(M子)。
女の魅力を見出し、なおさら惹かれていく源氏の心情。また、女との語らい、充ちたりた気分になって、平静になったときの源氏の様子が面白く感じられました(茶良)。
今日読んだ「夕映え」などから改めて感じたのは、日本人ほど時刻の移ろいや季節の移り
変わりに敏感で、それを文章等で表現する民族は、世界中で他にないのではないかと、いうことだった(雄太)。
本日のあたりが源氏物語最高の場面と、先生がいわれてましたが、まだよく意味がわかりません。時間をかけて勉強したいと思います(徳正)。
「夕露に紐とく花は玉鉾の/たよりに見えしえにこそありけれ」という源氏のナルシスティックな歌に対する夕顔の返歌「光ありと見し夕顔のうは露は/たそかれどきのそら目なりけり」にはちょっと驚いた。夕顔の茶目っけは、夕顔が単にかわいいだけの女ではなく、聡明でセンスのある女であることを雄弁に物語っていると(ズボン堂)。
自然の中に住んでいることを意外にも忘れてしまいがちの暮らしだが、今日は「夕映え」を勉強して、いかに源氏物語が、自然の内(心)に素直に生活していたことを知る。それが素晴らしいと思うのだ。源氏と夕顔の屋敷の暮らしが目に見えるように、イメージが浮
かぶ(N)。
夕顔が源氏によんだ歌「たそがれどきのそら目」だったかしらと、ほのかに言ふ。というくだりで、「たそがれどき」が出た中で、「かわたれどき」の言葉を出して下さった方があり、夕方時と、明け方に使う違いを学びました(孝)。
たそがれ(誰そ彼れ)と 彼は誰れがそれぞれに使い方のある言葉と知り、今日の収穫。われからという不可思議なわかめに付く虫もなんともおもしろい(Y)。
夕顔の最初の歌「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花」も素晴らしく印象深いものだったが、今回の「光ありと見し夕顔のうは露はたそがれどきのそら目なりけり」も美しく可愛い歌で目を引かれる(アキラ)。
源氏はやっと顔を見せ歌を読む。美しいことばで最初にめぐりあった時のことを思い浮かべて――。女もチラリとみる。あの時は美しいお方だと思っていましたのに、夕闇でよく見えなかったと。ほんとかしら、よくみていたのではないかと思う。世間では美しいお方だと評判なのに、それほどでもないわと、ぬけぬけとよくそんなことを言えますね――。それが源氏によくとれてなお一層女を好きになった。源氏は顔をみせ名乗ったのに、女はなかなか明かさないので責めるのだがやっぱり女は狐だ。しかし女は家も定まっていないので明かしたくない 海士の子だと言う。源氏は強引すぎたことを反省し、女を悲しませないことだ そーっと暮したい。
源氏の行方を探し惟光が果物を持ってやって来た。右近を避け 源氏に女を譲ってしまったと残念に思った。
源氏は女との時間をゆったりと過ごしているが女は荒れ果てている邸は何となく恐ろしく感じている。源氏は女の名前を知らない。女を恨む。どうしても踏みこえてはならないものがある。それは一体何であろうか? 心の奥に秘密があり、自身を守る、源氏が護衛しているのに――。
内裏では源氏の不在を心配しているだろう。どうしても身分の低い名前も明かさない女を捨てることはできない。
心苦しいのは六条御息所のことだが、御息所に逢いたいとは思わない。わかるような気がします。六条御息所ではなく、五条の女の方がよいのです。何人もの女をみて源氏はそう思った。これこそと思う女を見つけたのです。今日 学んだところは名場面で ほんのわずかな時間を大切に何がしの院で恋人と暮したい。通い婚ではなくずーっと生活したい。という進君の説(祥)。
横浜源氏の会
2015年2月5日 横浜市市民活動支援センター
今回の会場は、桜木町駅近くの市民活動支援センター。初めての場所に加えて雪という天気予報に会員たちの出足が不安視されたけれど、欠席者も少なく、新しい参加者もあって、心配も吹き飛んでしまった。
【夕顔】209頁~221頁
夕顔の仮屋で逢瀬を楽しむ源氏であったけれども、静かな宮中と異なって、屋敷が建てこんだ環境とあって、鶏の鳴き声もかまびすしく、御嶽精進をする翁の声もうるさい。とてもくつろいで語り合うことが出来ない。そこで、源氏は夕顔を牛車に乗せると、荒れ果てた、さる院に至る。やっと何の気兼ねもなく語らう所にきた二人であったが――。
【感想】
源氏が女を連れだし、「なにがしの院」で初めて外泊する経験の心情が面白く感じられました。(茶良)
源氏のロマンと夕顔との女性のロマンの相違にこれからのストーリーが、楽しみでもあり、古典の言葉のおもしろさで、毎月楽しみに通っています。いつか京都の旅が楽しみです。(恵)
高校の時に習ったのとはかなり違います。文法が関係ないということで、イメージがかちりわいてきます。廻りの風景等が非常に気になります。もっと副読書等を読んで勉強したいと思います。(増田徳正)
夜明け前に夕顔を連れ出し、「なにがしの院(河原院)」に着いた源氏は“いにしへもかくやは人のまどひけむ/わがまだ知らぬしののめの道”とうたい、夕顔の共感を求めるが、夕顔は源氏にひかれつつも、ためらいの気持が強く、気持が行きちがう。男と女の“恋の
かけひき?”、荒れはてた大邸宅での恋の逢瀬の様が味わい深く描かれている。(雄太)
なにがしの院へ連れてこられた右近は、日頃の疑問がとける。いよいよ話がこの荒れた院の中でどのように展開するかが期待出来る。(Y)
源氏の恋唄への返歌「前の世の契り知らるる身の憂さに――」「山の端の心も知らでゆく月は――」に、突然の運命の揺らぎに惑う夕顔の心情が表れていて、男女の思いの違いが印象深い。(アキラ)
すっかり舞い上がって、こんな恋は初めてだと「いにしへもかくやは人のまどひけむ/わがまだ知らぬしののめの道」と詠んだ源氏に対して、「山の端の心も知らでゆく月は/うはの空には影や絶えなむ」と返歌した夕顔は「誘われるままについてきたけれど、きっと捨てられて死んでしまうだろう」と不安を隠せない。夕顔の不幸な行末を暗示しているような歌だ。(ズボン堂)
明けてしまわないうちに女房の右近を呼んで随身に車を用意させ、女をのせる――。近所の老人(御嶽精進修行の翁びたるしわがれ声、弥勒の世、弥勒菩薩に願いを託し来世、事を女と約束したいと歌を詠む。源氏が燃えるほど女は不安になっていると紫式部は大げさにうるさくどうでもよいことと第三者的にみている。源氏が「こちたし」するほど女は心揺らいでいる。とにかく急がねばと女を抱っこして乗せ、右近も乗り込む。
荒れ果てた河原院、木立がおおいかぶさっているなにがしの院に連れだしたが咄嗟の行動で動揺している。先が見えず心細く思う。源氏にとってははじめてのことで、昔の人もこんなことをしたのだろうか。源氏はのぼせているので女を思いやることを忘れていた。女は我をとりもどしこの恋は実らずと悟るが、歌をくり返し詠む。源氏ともあろうひとが供人をつけず困っている。わざわざ隠れ院を求めたのに、心より(自分より)もらすなよ。
賄食(かゆ、米を煮たもの)を右近につくらせたが、源氏は食べただろうか。たぶん食べていない。やっと女とゆっくりできると思うとホットした。四町の屋敷がほとんど池で一面に秋の野良になっている。池の水もみえず水草にうずもれている。疎い――しーんと静まり返ってきみ悪さ、鬼が住みそうな気配がする。私は帝の子だし鬼も見逃してくれるだろう。(祥)
横浜源氏の会
2015年1月8日年1月8日 戸塚総合庁舎
新しい会場での新年最初の「源氏物語を読む会」は、新たな参加者もくわえて、予定を30分も超える活気のある講義となった。
【夕顔】199頁~209頁
源氏の通う女の家は粗末な板屋で、夜明け間近ともなると、周りの家々からの物音や人の話し声が筒抜けに聞えてくる。初めは物珍しく感じていた源氏も、やがて落着かず居心地の悪さを感じ始める。それにしても、女の「ほそやかにたをたをとして、ものうち言ひたるけはひ」に、これまで経験したことのない新鮮な魅力を感じ、いよいよ恋にのめり込んでいく源氏なのであった。
【感想】
今年初めての源氏物語の講義で場所も変わり夕顔と源氏の恋の内容も新鮮に感じられたが…。みめうるわしい十八才の源氏と 可れんな気持の良い、源氏の心を離さない女性が?
なぜこの貧しい住宅に住んでいるのか? と 身分をかくしての、これからのストーリーが楽しみであるが古文の奥深い言葉のやさしい発音にも魅力を感じる。(恵)
夕顔に夢中になっていく源氏にういういしい若者を感じる。白き袷、薄紫色のなよよかなる重ねた装いをして二人並んで庭を眺める様子がなんとも美しく、夕顔はこんな時も顔をおおぎで、かくしているのだろうか……?(Y)
源氏が、女の質素な家のまわりでの出来事に驚き、また、虫の鳴き声、呉竹の葉の露に風情を感じとる様子が面白く思えました。(茶良)
庶民の人声や暮らしの音は物語の中で破調のように、またリアルに描かれて驚かされる。この貧しい場所に、可愛さの描写を尽くして書かれた夕顔の様相には読者として、他の女性とは異なった魅力を感じざるをえない。(アキラ)
純粋な人間の裸の姿を読ませていただいた気がします。恋する源氏、素直でたをたをしている夕顔。かわいらしさを感じます。まだ十八歳という源氏の若さは、美しい恋を思わせました。打算の無い夕顔と二人の間は、よかったな、と思う巻でした。(N)
貧しい板屋に住みながら、そんなことにまったくこだわらず天真爛漫に振舞う女。しかも、〝ほそやかにたをたをとし〟た女、夕顔の不思議な魅力に、源氏はひきつけられ、心の底からいとおしく思う。そして、二人だけで心おきなく過ごせるところへ行くために、車でしゃにむに夕顔を連れ出す。駆け引きを越えた二人の恋の行方のありさまが見事に描かれている。(雄太)
詳しく説明して下さって、たのしいです。
マンガと違って、やっぱり良いですネ。
文章の意味が分ると、たのしいですね。(SK)
源氏の初々しい気持ちがよく伝わりました。
実に文章の巧みさに感心にしました。(はな)
宮廷に生まれ育った光源氏からすると、下の品の女の粗末な家で隣近所の物音が物珍しく、それに驚くシーンがことのほか興味深く思われた。雅な源氏物語のなかではちょっと異色な場面だと。(ズボン堂)
間近に聞こえる、庶民の生活の音や、人々の会話に、異和感を覚える源氏の様子が、面白く語られている。下の品の住む家に住んでいる女(夕顔)は、はずかしく思いつつ、しかしさして動ようもしないで、たおやかにしている。まっすぐに源氏(男)に、恋心をこれまで接して来た女性とは、何かが違うと思いながら、ひかれていく様子が、うまく書かれている。(孝)
夕顔はどんな女でしょうか
夕顔が咲く下の品の女 年令は何才だろうか 源氏より年上のようで、女の素性がはっきりしていないのに源氏は夢中になる。
女は上品で可愛く世を知っている。源氏はこれも前世からの因縁にちがいない もっとゆっくり話し合いたいと強引なので女は恐ろしくなって狐につままれたようでどうなってもよい。狐の馬鹿しあいと源氏は苦笑しながら心を許す。中秋の名月の夜あばら家に月光がさしこみ、明け方ざわざわと細々とした男たちの声がして女は恥ずかしと思うだろうーがそれが一向に気にしない可愛いー。臼で米つく雷よりもおどろおどろしい音、庶民の生活をみて源氏はどう思ったか。白い布を打つ砧の音、空を飛ぶ雁の鳴き声、そうした秋の終りの音があわれに感じたが、引き戸を開ければ呉竹や草花の朝露を見て立派なお邸の庭と変らずキラキラと輝いていた。源氏は発見した、屋内では秋の虫(蟋蟀(こおろぎ))の声とあいまって女を想う心は一層深くなった。素直で源氏に心を寄せている。心と心が一つになったことは今までなかった。来世まで女を裏切ることはできないと心に決めた。源氏は真じめです。源氏と相性がいいのだ。今年も美しい古語を愛し美しい羊の年にのどやかにお茶を楽しみながら美しい心で過ごしたい。(祥)
2014年12月4日 大倉山記念館
今年最後の源氏の会は、午後から生憎の雨となったけれども、それが少しも気にならないほどの、時間を超過しての、熱気に満ちた講義となった。
【夕顔】186頁~199頁
世間に知られまいと、身をやつし、供人の数も絞って下の品の女の所に通う源氏であったけれども、いつも心を占めていたのは女が頭の中将が話していた<常夏の女>ではないかという疑いであった。いつかとつぜん姿を消してしまうのではないかという不安。そんなことなら、いっそのこと、女を二条院に迎えるしかないと覚悟する源氏であったが。
【感想】
源氏の恋の心情がよく語られており、夕顔の魅力がふくらみ、二人の語らいのやりとりがうらやましいほどの結びつきを感じ入り、読後感がとてもここちよかったです。(はな)
自分の意識を外してありのままの女性と向き合い、その点での純な愛にのめりこむ夕顔と源氏の姿が素晴らしい。夕顔の他の女性にない美点が理解できそうな気がする。(アキラ)
狩衣姿にまで変えて女の所に通う源氏が、しだいに強く惹かれていく胸の動きのなかで、いつか消えてしまうのではないかと不安がる姿に興味を持ちました。(茶良)
お互い身分をかくしてのおうせを重ねる中、源氏は女の「やわらかにおほどきて」いる様子に心ひかれるという。わざと身をやつして接する源氏が次第に「人にしむ」という表現で女のことを思いつめる。不確かな状況描写の中で、恋心をまっすぐにつきつめてゆく源氏の姿が対照的に語られている。(孝)
源氏は 心くばりがすばらしく 身分を まどわし 女の魅力の新鮮な事におどろきを感じながら いろいろ考えあぐねていて 心苦しく なかなか思いを一言で表現出来かねている そんな源氏がとても 深く知れば 知るほど楽しく思います(M子)
源氏の恋は切なくて純心で、夕顔を想う 男心と、身分を明かさない関係の裏に惟光が〝私は何も知らないよ〟と道化に務める姿が目に浮かび面白い。高貴な源氏と、身分の低い女との心情、心が柔らかい、人を信じる女とのロマンに、益々 私の読む気持ちが引かれていくと思う。今まで読み継がれていく深さと歴史がうなずける。(恵)
恋の相手夕顔について。
源氏物語も、ひとつの虚構の世界。造られた男女の恋の物語。現実から離れた恋の物語り。虚構の生活、常識からかなり遠い場所を幻のように創っているわけで、そうすると、恋(人にしむ) 夕顔への源氏の懸想は、現実よりも純粋に描かれているような気がする。それは夕顔が、人を信じる力を持っている由。自分をあずける、源氏に身をあずける、そういう自由性を持った魅力のある女性(人間)であることが、大きな理由のようだ。(N)
源氏と夕顔は何度も会っているのに、お互いに顔もわからなければ正体もわからない。現代の人間からすれば不思議な話ではあるけれど、それが源氏物語なのであろう。頭ではわかっていても、感覚的にはもうひとつぴんとこないね。(ズボン堂)
「やわらかにおほどきて」源氏を惹きつける夕顔。おおらかな気持で男を信じるような、打算のない恋に憧れますが、この先の展開がどうなるのか心配です。(弓月)
源氏は下の品の女に夢中になる。いつもと違って正気にもどることなくのめりこむ。女はいとあやしくそしてやわらかで、源氏好みの女で若々しい。よくいう恋とは盲目、どうすることもできないくらい理性を失いつつ、知られてはまずいと思い、身分を隠して、狩衣普段着で顔もみせないように用心し、寝静まる頃をみはからって出入れする。惟光も知れてはまずいと奮闘する。家の者は両人が寄ってくるので不思議に思う。源氏も不安になり女を失いたくない。常夏の女のように突然消えてしまうのではないかと気が気でない。世間体もあり苦悩、二条院に迎えたい――。こんなに恋い焦がれたことはなかった。前世よりの宿命かもしれない。私たちも人生をふり返って一度くらいはこれは運命だったのかと思うことがある。その時気が付かないことも後でしみじみ思い出し、ホットする。(祥)
2014年11月6日 大蔵山記念館
落葉を掃き清める人の姿が秋の深まりをいっそう感じさせる大倉山公園。まさに、「源氏物語」の雅な世界に浸るに最適の季節だといえましょう。
【夕顔】174頁~186頁
源氏の命を受けて隣家を探るうちに女房の一人と懇ろになった惟光。その惟光から詳らかな様子を聞いていよいよ好奇心と冒険心を募らせた源氏の君は、家の外観から下の品の女だろうと思いつつも興味を惹かれて、とうとう通うことになった。ただ人目にふれぬように、車にも乗らず地味な装いで。
【感想】
惟光の隣家の話に心を動かされていく源氏の様子、また、源氏のために働き動く惟光の様子が面白く感じられました。(茶良)
夕顔の巻での今日の時間で、人間の条件などなにも考えないで、恋のみという純粋な心だけの恋愛とは、なんと自由なのだろうかと思いました。魅力あふれる源氏物語です。(N)
どんな無骨な人でも心を動かされ、誰もが自慢の娘や妹を下仕えでもいいから仕えさせたく思う源氏ですが、その源氏の誘惑に対して冷静に対処した中将の君はあっぱれでした。
(弓月)
右近の君の喜劇的シーンの面白さ。物語の節々に漫画的な所を挟んで息抜きと次の展開のために置かれていて感心させられる。「例の、もらしつ」の省略と対照的。(アキラ)
「源氏物語」にはしばしば後朝の別れが出てくるけれど、夜の十一時ころきて夜の明けぬ前に帰っていくという。だとすると、素朴な疑問なのですけど、お役人でもある貴族たちは昼のお勤めはさぞや眠かったのではないだろうかと思うのですけど。(ズボン堂)
源氏をみただけで 心をとめるほどで、だれしも源氏のそばに仕えさせていただけたらと思う。中将の君も慕っている 源氏は六條の御息所とはうちとけていないので中将は心配している。源氏と御息所との関係。物おもいにふけって とことん考えるタイプ。
まことや――そうそう 源氏は下の品の女に興味津々、ひと目逢いたいと心が動き惟光に頼む。惟光は(たばかる)惜しまず 調べを手助けする。可愛い女であったと報告。中将が通っていたらしい、もっとくわしく調べるようせがむ。
真実のことを知りたい、中将の車、そして常夏の女だと判断する 古語は場面変換をする。惟光もちゃっかり隣家と親しくなっても 見てみぬ振りをする。女たちのご機嫌をとっていた。惟光は一生懸命だ。
下の住居には葎(むぐら)、つる草が這っているのを思い出しながら、どのようにして女のところへ通うことができるか。それはね 人に逢いに行く時は少々なりとも身なりをしていくが、
今度は人目を気にして目立たないように気をつけて 歩いていくといったが 惟光は歩かせるわけにはいかぬ。それはまずい。源氏を馬にのせて 綱をひく。紫式部は一番大事なことを書かない 想像にまかせる。と先生のお話でした。女の方もつつましく人目を憚って暮しているのに通ってくるのは心配。そんな状態でよいのか 源氏も女を愛しく想う。これ以上 女に迷惑をかけてはと思う
横浜源氏の会
2014年10月2日 大倉山記念館
「夕顔」159~174頁
ようやく残暑も治まって、秋らしい日が訪れました。冷房の季節は終わりを告げ、窓をあければ、さわやかな風が入ってきました。読書の秋にふさわしく、時間を大幅にオーバーランし、熱のこもった講義となりました。
【内容】
乳母(めのと)の病気を見舞いった際、ふと隣の家の塀に目をやると、夕闇のなかに白い花がぼおっと浮んで見えた。興味をひかれた源氏は、その花を採ってこさせる。すると、歌が書かれた女主人の扇を手に、家から女童が出てきた。ますます心ひかれた源氏は、乳母の息子の惟光に隣家の様子を探らせる。惟光の報告にいっそう心をときめかせる源氏であったが、話は一挙にすすまず、その前に空?の主人の伊予の介の上洛の話があり、六条の女君の話がありと、読者はしばしじらされる。
【感想】
この短い文章の中に、夕顔、空?、軒端の萩、六条の女君、中将のおもと、と目まぐるしく源氏の心を過ぎていくのが印章深く面白い。(アキラ)
空蝉の夫、伊予の介が任地から帰り、主人筋の源氏のもとに、あいさつに。妻である空蝉と、女と関係をもった源氏と、実直な伊予の介との対比がおもしろい。(青)
空蝉から、つれなくされても思い切れず、他の女とはからずも関係を持ってしまう源氏。さらに、そんな源氏の前に空蝉の夫が現れる。旅から帰って来て、忠臣としての報告をするが、彼の妻に心を寄せている源氏はうわの空で、罪悪感にさいなまれつつ、空?の夫(伊予の介)に対して申し訳なく、≪あはれ≫を感じる。男女の関係の複雑さや機微を描く作者、紫式部の力量は並大抵でない。(雄太)
女の思いの重さ、複雑さ、熱さ、苦悩など、源氏という男の象徴に対して、この空?や、六条御息所、夕顔の登場等の、女性はなんと男性にとって解りづらい存在なのかと、今日は感じました。源氏物語に登場する女性たちの心の理解は、なかなか難しいだろう。(N)
男心と女心があまりにもロマンチックなので、感想は書けません。深い深い、複雑な男女の心と、人と人とのすれ違い! 大変おもしろく!(恵)
源氏と空?の間は何もなくなっていたと思っていましたが、しっかり手紙のやり取りがあったとは、源氏の筆まめさに感心しました。空?、六条の女君、中将の君と次々に手を出していく源氏はいかがなものでしょう?(弓月)
新しい女との出会いを夢みながら、伊予の介が北の方(空?)を伴って任地におもむくことを知り、もう一度会いたいと思う源氏の胸中を知り、今後の展開に興味がそそられました。(茶良)
紫式部のエンターテイナーぶりは驚くばかりだ。夕顔が出てきて、話がすっとそこへ行くのかと思ったら、部下の惟光が出てき、空?の主人の伊予の介が出てきて、さていよいよ夕顔が出てくるのかと期待したら、話は六条の御息所にさかのぼって、という具合になかなか夕顔に行きつかない。平安朝の宮廷の女房たちがつぎはどうなるのかとはらはらどきどきしながら源氏の君の写本を回し読みする姿がありありと想像できた。(ズボン堂)
いつも書くことに苦労しています。今日は毎晩四~五輪咲く夕顔の花の報告を。
七月初め貰った苗がなかなか育たず、今年はだめかと思いましたが…。
夕方すこし暗くなり始めると葉の陰に白い大きな花がひっそりと咲きます。周りが暗くなり、本当に目立つことなく一晩でしぼみ、はかなさ?を感じます。(Y)
講義がはじまるまえ、米納さんより夕顔の花を写メールで見せていただいた。
源氏物語には季節の花、朝、昼、夕と時間で咲く花、いろいろな花、花に学ぶ美しい心、花を愛でる。それは私たちに美しい心を持ちなさいと力説しています。
源氏より隣家の女の情報を得るようにと惟光も母の看病をしながら気になり、女たちの褶(しびら)は女主人に対しての礼装。惟光が見たのは美しい女主人が手紙を書いていた。やはり美しい人がいた! 惟光の話を聞いた源氏は思い描いていた美人にちがいないと思った。惟光は色っぽい源氏像を見た。宮廷生活は窮屈で自由がない源氏を自分がお守りしてあげようと考える、惟光のやさしい思いやり、女主人や若い女たちはきっと期待通りでしょうと源氏はますます火がついたように高揚する。
伊予の介が伊予から都に戻り源氏のところへ真先に御挨拶に行く。空蝉に振られた源氏はいとねたく癪にさわるが伊予の介にとってはけなげな妻でよかったと思う。こんなところは心憎い、しかし自尊心を傷つけられ、このままではすまない。他の品々にも目が向くようになり幅が広がった。
秋になって、葵の上や大殿にも遠慮がちでうらめしく六条に通う。
六条の女君には強引だったが熱も冷める。貴公子である源氏の性格、女も物事に耽る性格で年令も、身分も深刻に悩んでいる。
ここにも草花の庭があり秋の草花よりも美しい源氏であったと語り手がいる。作者は別で、六条御息所は庭に興味があった、後の賢木で登場するそうで楽しみ。(祥)
横浜源氏の会
2014年9月4日 大倉山記念館
?の声のうるさい、残暑厳しい日でした。しかし暑さに負けず、いつものようにたのしくも厳かな雰囲気のなかで実りある講義が行なわれた。
【夕顔】149頁~159頁
乳母の病気見舞いのため、惟光の屋敷に立ち寄った源氏だったが、そのとき、歌を書いた扇を渡した隣家の女君のことが気になって、惟光に様子を探らせる。源氏の命とあって、これ幸いと中垣の隙間から隣の家を垣間見る惟光であった。すると、そこは揚名の介の家で、なにか曰くありげだった。
【感想】
先日、テレビで映画『源氏物語―千年の謎』を見ました。夕顔の巻の扇子に夕顔の花のシーンが出てきて、印象深く美しく構成されているので感動しました。(アキラ)
「夕顔の部」に入って、当時の風景が、ほのかに暗く、闇の中で浮かび上ってくる男女の恋の行えと惟光の第三者の心情の取り合せがおもしろい。女の謎(なぞ)めいた、忍んで生きている事が、又物語を深くして,ますます興味深く作者の才能に感動する。(恵)
夕顔から歌が源氏に渡されたのは、夕暮れ時、乳母の家を立ち去ったのが、夜……
六条の家で一夜をすごし、朝方その前を通る、惟光に、さらに歌の主の様子をさぐらせる。惟光が夕日のさし込んだ夕顔邸をかい間見して女を描写する時、顔がすこぶるいいと伝える。……時間をうまく使って表現する、作者、式部のうまさにカンシンです。(孝)
揚名の介の家に住む女に惹かれていく源氏の様子が興味深く感じられました。(茶良)
「はかなき一ふしに――」この言葉に、夕顔の巻の始まりが在る。今日はこの場所を読んでいて重要な場面だと感じました。あざやかに映っています。物語は、ここから深く広く人の心の世界が、語られていくわけで、勉強になりました。(N)
源氏は、通いつめている六条の女の品の高さにひかれつつ、夕顔の住む小家の前を通るたびに、夕顔の魅力をあらためて思いだし、心ひかれる。その心の動きがきめ細かく描かれていて、すばらしい。また、惟光は、源氏の命により、夕顔の小家の様子を、はじめは
気のりせずに調べはじめるが、調べているうちに、その家のいわくあり気な様子が分ってきて、調査にのめりこんでいく。その様子も興味深い。(雄太)
横浜源氏の会
2014年8月7日 大倉山記念館
立秋間近といえ、まだまだ暑さの厳しい日の午後。緑の多い大倉山の静かな部屋で?の鳴き声に包まれてしばし王朝文学の世界に浸った。
【夕顔】139頁~149頁
六条の女を訪ねる途次、五条の大弐の乳母が重い病の床に伏せているという噂を耳にした源氏はいまや尼になった乳母を見舞った。この日のくることを心待ちにしていた乳母は、源氏の姿を目にするとあたりをはばからず感涙を流すのだった。邸に詰めていた惟光や兄の阿闍梨、乳母の娘やその婿などがはしたないと思ったほどに。源氏は心を尽くして乳母を慰めるとともに、僧の祈祷などをてきぱきと手配した。
そのときに至って、源氏は家に入る直前に惟光から手渡された扇のことを思い出し、紙燭を持って来させて見る。すると、水茎の跡も美しく歌が書かれていた。「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花(あなた様はもしや夕闇にも光を添える美しい夕顔の花(源氏の君)ではありませんか)」とあった。心を動かされた源氏は、傍らの惟光に問うのだった。西の家に住む者を何者であるか、と。
【感想】
源氏の前で取乱す母(乳母)を子供たちはにがにがしく思っていた。しかし、源氏の心のこもった母への言葉を聞いて、母が並の人ではないことに気づき、しんみりとする。その情景がよく描かれている。
源氏は、乳母もさることながら、扇に歌を書いてよこした夕顔のことが気にかかり、惟光に、その女は誰か調べさせる。源氏の心の動きも興味深い。(雄太)
年老いた乳母を見舞った後、源氏は扇のことを思い出し、その女に興味をそそられていく様子に、惟光が「またか」と思い、源氏と惟光のやりとりにユーモアを感じられました。
(茶良)
ほろほろと流れる人の心が美しい。
乳母と源氏と惟光の心の彩と、扇の上にある文字の彩、あやしく動くこれからの物語の導入が、次への期待に胸がふくらんで、源氏物語が読みつがれる魅力に引き込まれています。(恵)
夕顔の花を求められた時、花、それだけをさし出すのではなく、扇にのせて源氏の方に持たせる。乳母を見舞った後、扇をひろげてみると、なつかしさを感じる香りが……。その上に手なれた字で歌が。あなたは源氏の君ではと問いかける。そこまでする女主人の思いはどこにあるのか。次が楽しみ。(孝)
○源氏が涙をおしぬぐうと、たきしめられたかおりが満ちてくる。その高貴なかおりに、それまで「すずろに涙がち」の母を見苦しいと目くばせしていた子供たちが手の平を返したように、母の思いを汲んでしんみり涙ぐむ場面がおもしろかった。(弓月)
「思ふべき人」――平安期、子育てする乳母の存在がときに実母以上に重要だったことがよくわかる場面。(ズボン堂)
「心あてに――夕顔の花」の歌の解釈が色々とありうるらしいのが意外でしたが、この歌での夕顔が源氏を指していることも意外な感じを受けました。(アキラ)
「おしのごひたまへる袖のにほひも」と、または「もてならしたる移香、いと染み深うな
なつかしくて、をかしうすさび書きたり」など、香に深い文化を感じます。書体にもおもむきを重く感じ入ります。全て、人の心の動き。欲望を素直に純化していて、まして、美と
氏ました。現在には無い、世の濃さなどに、興味を持ちました。「源氏物語」の面白さの一つかと思います。(N)
源氏と乳母との対面(病気見舞)
乳母は何も思い残すことはないが、変り果てた尼姿になって、口惜しくつらいが仏の道に入って源氏とお目にかかれることができ、うれし泣きをする。源氏の位がさらに高くなるよう願う。源氏も涙しながら尼を励ます。
「さてこそ九品の上にも障りなく生まれたまはめ」あの世での極楽浄土、最高の位になれますように功徳(行と善を十分につんだ功績)それでこそ九品の最高位(上品上生)にも支障なくお生まれになるでしょうと乳母をやさしくなだめる。
自由が丘の近くに九品仏という駅があり、お寺がある。九品(くほん)→訓読九品(ここしな)の上→九品((往生の)浄土(仕方))の略。九品仏の先には上野毛、近くには五島美術館があり、よく源氏物語の展示があり、よく出かけた。寝殿造りを模写した美術館で、参考になる。
☆極楽浄土は上品(じょうぽん)、中品(ちゅうぽん)、下品(げぽん)の三等があり、各品が上生(じょうしょう)、中生(ちゅうしょう)、下生(げしょう)の三つに分れて、全体で九階級がある。
惟光や兄の阿闍利たちは母の泣きじゃくる嘆きにはらはらして老いという切実なところが悲しい。私の老いも間近、行く行くは変りはてるのだろう。しかし最近こんな楽しいことがあった。数年前から戸塚の八重山で兄と畑仕事をした。仮の小屋を建て農作業の休憩をしたり、野良弁当を食したり、冬の畑は寒く、いろりで暖をとったり、夏は涼風をいれるため窓(半部)をつくったり、楽しく語らいをした。
先生が源氏物語の「能」のことについて「半部」にふれられ、以前、婦人画報で一年間馬場あき子が源氏物語の「能」の特集で読んだ。写真付きで格調あるものでした。
先月の感想文で夕顔の住んでいたところを東本願寺の近くの渉成園と書いたが、「源氏物語色辞典」(吉岡幸雄著)では江戸時代の儒学者頼山陽が渉成園らしいという説は誤りだと書いてありました。先月、大倉山記念館での講義が終わって、帰りはいつもカフェで二次会、これまた源氏の延長が続き、楽しいひとときです。
源氏の香りは高貴。部屋の中は香りがいっぱいに満ちて、非難した子どもたちは母は幸運な人だと納得する。源氏も言葉が巧みだ。乳母を忘れたわけではない。乳母と逢わないでいると心細くなる。乳母も源氏を大切な人だとお互いに心の内を明かす。
夕顔はどうして扇に歌を書いたのだろうか。夕ぐれにかすかに見えた品格のある人に興味があったのかな。(祥)
横浜源氏の会 2014年7月3日 大倉山記念館
梅雨の晴れ間、薫風が淀んだ空気を爽やかに動かし、大倉山公園の緑が体に染まるほど鮮やかでした。
【夕顔】132頁~138頁
長かった<空?>の巻もようやく終わり、新しい巻へ。いつのころからか光源氏に都のはずれ六条に人目を忍んで通う所ができた。ある日、思いついて待つ女の所ではなく五条の大弐の乳母を訪ねることにした。風の便りに、いまは髪を落して尼になった乳母が、重い病の床に伏せているという噂を耳にしたからだった。
乳母の家に着いてみると、門には鍵がかかっていた。門が開くまでの間、源氏が眺めるともなく眺めていると、となりに檜垣の家があって、夕闇迫るほの暗さのなかに白い花がほのかに咲いていた。その花の美しさに心奪われた源氏は、供の者(随身)に思わずもらす、「あの花はなんというのだろう。とって参れ」と。「夕顔と申しはべる」と答えると、供の者が門に入っていって折り取った。そのとき、門の内より黄色の生絹(すずし)の単(ひとえ)袴(はかま)を長めに着こなした童(わらわ)がこれにどうぞと香を焚き込めた扇を差し出したのだった。
【感想】
いよいよ「夕顔」の巻に入った。未だ夕顔という名の女性は現れない。その前段として、身分の低い人たちの住む五条の大路の〝ものはかなき〟家の檜垣に咲く夕顔の花が、おそらく身分は高くないが美しい女性の出現を予見、期待させられる。これからの展開が楽しみだ…(雄太)
今日久しぶりに参加して、優がな世界に引き込まれました。源氏のこれからの恋の行方に、白い花の夕顔の導入はさすが…… 花のはかなさが美しさと心情が想像されて、これからが楽しみです。
「おのれひとり笑(えみ)の眉ひらけたる」という花の印象と、人と人との情景が美しい。(恵)
源氏が乳母の病気見舞に行った時の話で、五条の家のかたわらの住いをのぞき見、夕顔の花に接する様子が面白く描かれている。又、女に出合う予感めいたものも感じられる。(茶良)
「白き花ぞ、おのれひとり笑(えみ)の眉ひらけたる」「くちをしの花の契りや」と夕顔の花との出会いと、心に残る思いを恋の始まりにするこの場面の美しさは、物語の最も印象深い所の一つだと思う。(アキラ)
源氏の古歌の独りごちに古歌の一節で答える随身とのやり取りに雅を感じました。
夕顔のつると花や、女の童の様子の細やかな描写はすばらしく、見習いたいと思いました。(弓月)
「遠方人(をちかたびと)にもの申す」
源氏が古歌の一ふしをもってぽつり話すと、すかさず随身はそれを受けて問われているのが垣根にはっているつるの白い花と分かって、即答をする。
このなにげないやり取りが、平安期のみやびを静かに伝えている。(孝)
「夕顔」に入り、これからの展開が楽しみになって来た。
五条なるという源氏の生活には今まで見たことのない雰囲気が、檜垣・遣戸口・きりかけだつ物という言葉で出て来て、説明をききながら、納得する時間でした。(Y)
六条わたりの御忍びありきのころ、内裏(うち)よりまかでたまふ中宿(なかやどり)に、大(だい)弐(に)の乳母(めのと)のいたくわづらひて……と始まる「夕顔」の巻の出出しの文章のすばらしさ。これにふれるだけで『源氏物語』を読む価値はじゅうぶんにあると思った。(ズボン堂)
今日から夕顔の巻になる 特別の巻。
源氏物語を読んでいる人に 女君が何人も登場するが どの女君が好きですかと尋ねると男性も女性も「夕顔」だといいます。人それぞれだがそんなに魅力があるのでしょうか。これから楽しみだ 源氏は六条の女君(六条御息所)の所に通っていた頃、部下の惟光の母が尼になって病に伏しているので見舞に立ち寄った。源氏の乳母は惟光の母である。惟光の家は鍵がかかっているので車が中へいれられないので鍵をさがしている間待っている間周囲を見渡していた。隣は涼しげに半蔀(はじとみ)が上げられ美しい女たちが見える。女たちもこちらを見ている。貧しい塀に絡んで咲いている(笑の眉ひらけたる)白い花に目を奪われ、周囲のものに尋ねる 随身は白い花は夕顔(庶民の花)、この美しい花は堂々としていると源氏に説明する 納得した源氏は花をいとおしく心をよせてよく手にとってみたい。花を折ってくるよう命じた 随身が花を手折ると風情ある引戸から黄色に染められた生絹の単袴を長めに装った女童がでてきて この上に白い花をのせてさし上げて下さいと白い扇をさし出す。香をこがした濃く薫きしめた扇の持ち主はこの家の主人。その時 惟光が出てきて 惟光より源氏さまへと。なんと優雅ですね。
初夏の夕に咲く夕顔。私が通っている読書空間みかも(奥沢)へ行く途中毎年夕顔を鑑賞し、夕顔を思い出していた。今年も梅雨が明ければ見られると思うとわくわくしてくる。 偶然季節が重なって一層心がたかぶる 先月表千家の喜寿の祝典があり 京都へ行って来ました。京都タワーより眺めた目の先が五条あたり 緑濃きところ 渉成園あたりが源氏と夕顔との逢瀬したところだと思いを走らせた。惟光は鍵をなくして探すのに手間取り外で待たせて恐縮する。(祥)
横浜源氏の会
2014年6月5日 大倉山記念館
この日は朝から雨で、午後になってもやまず、予報どおり関東地方は梅雨入りした。
【空?】114頁~129頁
はからずも西の御方と契ることになった源氏の君は姫君に口外することを固く禁じてその場を後にしたのだが、折しも暁に近く月の影が白く射していて女房たちに見とがめられてしまう。しかし、幸い、背の高い女房とまちがわれて、難を逃れる。二条院(自宅)に帰ったものの、女君への思いをとげられなかった源氏の君は、持ち返った薄衣(小袿)を取り出すとともに満たされない気持ちを歌にして懐紙に書きつける。図らずも小君はそれを姉の女君に見せてしまう。源氏の君への深い思いを知った女君の胸に熱いものが込み上げてきて、思わず懐紙の隅に歌を書きつけるのであった。かくて、波乱万丈の空?の章は、唐突に終わる。
【感想】
空?を西の方と取り違え、普段通りでいるよう説得し、自宅へ帰るが、空?のことが忘れられず、眠れないで、小袿を見入って忍ぶ源氏の胸の内にしんみりとした。(茶良)
御達の勝手な思い込みのおかげで、源氏が脱出するところはハラハラするもユーモアのある場面でおもしろく思いました。
しかし、まだ若く疑うことのない西の御方を誰にでも言うような口説き文句で契りを交わし、それを自分の都合よく言いくるめてしまう源氏に男の身勝手を感じました。
西の御方には同情します。(弓月)
その時代の人々の 心の交流の すばらしさ 深さに 学びつつも又 せつなさが あります、 源氏を思う小君のすばらしさと共に 切ない思いがつのります。(M子)
どうなるかとはらはらどきどきした空?の章も、なにごともなく(?)終わって、ちょっとあっけなく思ったけれども、どう終わらせるかも作家の腕の見せ所だと思った。(ズボン堂)
西の御方を源氏は情々しく情愛し、人々が認める男女関係よりは忍んでいく愛が、ずーっとあわれだと昔の人は云っている 貴女も忘れないで待っていて下さい。口説くのは相手を本気にさせる。契りを交わした時は後朝の文をかわす何事もなかったようにしてほしいと。かの(あの)女 憎たらしい女の絹の小袿を持って立ち去る。「身分の高い人は相手
を傷つけないでゆとりをもって自分を守っていく」と大内さんは説得力がある。明け方の御達の目にとまり女房勤めも大へんつらく御達の愚痴など聞かされ やっと紀伊の守をぬけだすことができ、小君を車の後に乗せて二条の院に戻った。
目的だった空蝉に逃げられ空振りしたことを あやにく、苦しい、悔しい、腹が立つ、癪にさわる 不快 傷つけられ落ちこむ源氏失恋する。この気持を小君にあたりちらすが 小君は源氏に同情するがどうすることもできず、二人の心模様をしみじみ語っている。女君の態度を恨みながらも女君の薄衣をそばにおきながら、悔しい想いで寝つけない。その想いを歌を畳紙に書く。薄衣をおいて去った人がらをなつかしく。小君はその手紙を大切に懐に入れ紀伊の守に戻る 西の御方も気の毒なのだが、源氏は薄衣を身近において女君を慕う、未練たらたらであった。女君は小君の行動を批判し きつくきつく叱責した。源氏からも姉君からも叱られ、小君は良いと思って使者をしたのに両者から怒られ可哀想だ。女君は自分の脱ぎ捨てた小袿が源氏が持って帰ったことが恥ずかしい平静ではいられない。
西の君は 源氏より便りがないので源氏に捨てられたのかと。源氏の手紙を見た女君は 源氏の愛を感じながら 娘の頃だったらと今は伊予の介の後妻になった今 涙ながら畳紙の片すみに 源氏の手元に届いただろうか? 届かなかったみたい。(祥)
横浜源氏の会
2014年5月1日 大倉山記念館
さわやかな季節。新緑につつまれた大倉山記念館で行なわれました。
【空?】106頁~114頁
源氏との思いもかけぬ出会いのとき以来、「昼はながめ、夜は寝覚がち」な苦しい日々を過ごしていた女君であったけれども、寝所に忍び入った源氏の気配にいち早く気づくと、生絹の単(ひとえ)をさっと纏って、部屋をそっと後にした。傍らで眠りこける西の御方をその場に残して。そこに忍び込んだ源氏だけど、空?はすでに蛻の殻。その後、ようやく人違いだと気づいたものの、いまさら間違いとはいえず、源氏は西の方を口説きにかかる。このあたりは大衆小説のようなスリルがあって、さぞかし当時の女房たちの好奇の心を揺り動かしたことであろう。
【感想】
読み進む中に「寝ぎたなし……」という言葉がねむりほうけている姿を表現しているときき、ちょっと西の方がかわいそうな気がする。まだ若く健康そうな様子とは取られない平安時代の貴族社会の価値観……? 今にひきつけ過ぎるのかしら……と。(Y)
平安時代の宮廷で源氏物語を数人の女房が集まって声に出して読んで、この「人違へ」の場面にドッと笑い合う光景を想像してしまいます。面白いです。(アキラ)
目指す空?に逃げられ、別の女と寝ることになってしまった源氏の困惑と、空?への思いはいや増し、憎いとさえ思いつつ、恋心を捨てられない複雑な心がよく描かれている。
空?への想いが深いことを自ら思い知りつつ、目の前にいる女をも傷つけたくない気持との間でかつとうする源氏。これからの推移が楽しみだ。(雄太)
空蝉は、しのび込む源氏のけはいにいち早く気づき、身を守るため、義娘を残して寝所(しんしょ)をすべり出る。
本能的に一人だけ、身を守るために抜け出す。超おせっかいの私にはやっぱり出来ないかも。
人違いだったと分かった源氏の対応も、考えさせられる。女に対してやさしいようで、やっぱり、本心ではないことをいつわっているのは、如何なものか、18才の源氏のなせるわざか。(考)
床の下に女房が二人臥していても、源氏にはいりこまれてしまうとは、中の品の女房たちは頼りないと思いました。
男性は逃げられると惹きつけられるようですね。(弓月)
久しぶりに参加して古典文の綾の言葉に深い意味と現代の言葉の違う内容があり、時と共に精神のゆらぎがおもしろい。
源氏と二人の女性の遍歴に、ゆかいでもあり、心の動きのあやうさと意識の違いに男性の思いやりがあると思った。(恵)
今日は軒端の萩を少し知りました。かわいい女の子でした。恋の遊びばかりしている源氏の相手としては、幼すぎるかも知れないと思いました。でも空蝉の大人の恋よりも、まだまだ、若い軒端の萩の気持ちに共感しそうです。(N)
小君の導きで空?のもとへ忍び込んだのはよいが、空?に逃げられ、<人違へ>で若き女と接することになった源氏の落胆さと空?への思いが面白く感じ取れました。(茶良)
お目あての女に逃げられ、思ってもみなかった女と鉢合わせする場面の、スリルとサスペンス。世界の大文学『源氏物語』にはけっこうエンターテイメントの要素もあるのだというのは面白い発見だと思う。当時、紫式部が書いた『源氏物語』が宮廷の女房たちに回し読みされるほど人気があったのもむべなるかなと。(ズボン堂)
小君は何とかなると思って、両開きの妻戸をたたき押し開けて中に入り、空寝をしながら、源氏を母屋の中へ源氏はどうしようかと迷ったり、なんともおかしく真剣だ。
今は夏なのに古歌の「春ならぬこの目(芽)もいとなく(せわしない)嘆かしきに」あの一夜のことを思い出して眠れない。なぜ眠れないのか。女は心と体が別々で苦悩し、昼
はボーッと夜は夜で悩み落着かず、寝付きが悪く頭がはっきりしない。碁が打ち終って西の方はもう部屋にかえりたくなって一緒に泊まることになり、若いのでパタンキュッと寝息をたてている。空蝉は眠れずにいると、暗闇の中あの方の匂いと衣ずれ、音と足音がする。ハッとして、とっさに寝床を離れる。生絹なる単を一ッ着たまま。体が素速く反応した。心の中に源氏を想っているからこんな行動に出たと身についていると先生のお話であった。
人違へ――暗闇の中に押し入るが、床の下に二人の女房が臥している。大きなものものしく思い、焦っている。人違へとわかって落ち込んで心が傷つく。その場しのぎの軽々しさはよくないことだ。形は大事なこと。形を整える。
空蝉を表わしている、あのつらき人、たどらむ人、うれたき人。
つぶつぶとした女が目を覚まし、呆然とする。源氏がそばにいたから。まだ男女の仲を知らないので、反応がにぶい。源氏は考え直す。空蝉の立場を傷付けない。源氏は不真面目でない。どうにかしなければと思う。娘を口説くしかない。何て口説くのかな。(祥)
2014年4月3日
「空?」93頁~105頁
夕闇にまぎれて紀伊の守の屋敷に忍び込んだ源氏の君は、空?のいる寝殿の東側の簾と簾との間の暗がりに身をひそませ、格子の隙間からなかを垣間見る。すると、思い人が若い女と碁をうっていた。主人の紀伊の守が不在とあって、女はくつろいでだらしない格好をして碁をうっている。それに対して、源氏の思うひとは暑さにもかかわらずきちんとした姿形をくずさない。そこに品の良さと魅力を改めて感じた源氏の恋心もいっそう募るであった。
小君の居ない間に女たちを観察する源氏の目配りが面白く感じられた。また、そのことを小君に知らせない源氏の心配りにも心惹かれました。(茶良)
源氏がかいま見をする様子を通して西の御方と空蝉の比較が面白い。十七才の源氏が、若き西の御方のつつぶと肥(こ)えて髪もふさふさ、あいきょうのある姿を認めつつ、やせやせの空蝉に、なお心ひかれる様子。陽だけでなく、陰になぜかおくゆかしさを感じる源氏は、若くして、ろうたけているのか? (孝子)
源氏は容貌よりもたしなみ深い<心あらむ>人に惹かれるという、見掛けによらない男性でした。でも目移りしている様子もそれはそれでおもしろく書かれていました。(弓月)
源氏物語を読んで、大変、情景が立体的であることに、驚きます。細部にわたる文章が、場面を映像として見せてくれることに、喜びを感じます。古文の魅力でしょうか。(N)
空蝉と向かい合って囲碁に興ずる、若く、肉感的で華やかな女と比較しつつ、空蝉の内面的美しさに惹かれる源氏の心が見事に描かれている。と同時に、源氏は、伊予の守の娘である〝華やかな娘〟は自分とは合わない女だとは思いつつ、どこかで惹かれるものも感じている。男の浮気心、ユーモラスな面もおもしろく描写されている。(雄太)
源氏が惹かれる空?の<心あらむ>所をくみ取るのは難しいと思う。軒場の萩の若々しさは分かりやすいのだが。<アキラ>
源氏の観察する、空蝉の様子とつぶつぶとした若い義理の子との対比が生々としていて、はなやかなる人と物げなき人を感じることが出来た気がする。(Y)
『源氏物語』はまじめな恋愛小説だと一般に考えられているけど(それは間違いではい)、意外とユーモアがあることも指摘しておきたい。(ズボン堂)
伊予の介の後妻空蝉の衣装は 濃き綾の単襲、濃い紫 紫根染めの単 幸菱紋と生絹。伊予の介の娘の衣装は 白き羅(うすもの)の単襲二藍の部屋着。源氏物語に登場する女君の衣装に興味を持ったのは半世紀前 茶道の稽古などで着物を着ることが多く色合せなど参考になり自然と身に着いてきた。
碁打ちをしている二人の女君の容貌をよく観察をしている、やせているがたしなみのある空蝉。色白で、つぶつぶとなめらからな容姿だが品おくれで美人だが 源氏好みではない。二人の碁打が終え 闕さし静と動。再び想いをかけている女君を凝視する源氏。
源氏にとって内面的な美しき振舞い、しぐさにひかれ鼻もねびれて老けてみえる。美人かどうかより心が通うかどうかということが大事であり 二人の女君をくらべながら浮気心をどうしようもできなく落ち着かない。そんな気持になることは小君に対して恥かしい。
源氏と小君の心づかいがたまらない。(祥)
横浜源氏の会
2014年3月6日
「空蝉」82頁~93頁
【内容】
方違えと称して強引に紀伊の守の屋敷を訪れた源氏に対して、空蝉は女房の部屋に身を隠して源氏を拒んだ。しかし、諦めきれない源氏は紀伊の守が所用で任地に下って不在の隙をねらって警備も手薄な紀伊の守の屋敷を三度訪う。源氏に同情した小君の手引きによって。
【感想】
源氏はたびたび空蝉にこばまれるが、想いを抑えきれず、小君を使ってついに再び女の寝殿にしのびこむことに成功する。その様子が見事に、ときにはスリリングに描かれている。(雄太)
源氏に見られた空蝉の容姿、貧相さの表現に驚く。にもかかわらず空蝉に魅かれている源氏の心の複雑さ、広さも考えさせられます。(アキラ)
源氏が小君にたばかれて、女君の所へしのび入る。寝殿づくりの中の、どこをどう移動し、どうかいま見たのか、お話の展開にあわせて動線を追うと、一そう楽しめる。(たかちゃん)
源氏の心内と女(空蝉)の心内の葛藤が面白く感じられ、この先の二人の展開が楽しみ
に思われました。(茶良)
久々に皆さんの音読する古語、『やまとことば』の美しいリズムを感じた。意味はすべて理解できなかったが、イメージが少しなれてきました。(H)
源氏に命令され、小君が恋の手引きをする様子がおもしろく書かれていました。“夕闇の道たどたどしげなるまぎれに”などの表現や寝殿の様子など興味ひかれました。(弓月)
囲碁が平安時代の貴族の女性の大きな楽しみだったと知って、ちょっと意外な感じがした。囲碁って、かなり理詰めのゲームだと思うので。当時の女性の精神世界をうかがえるのも源氏物語を読む楽しみの一つだ。(ズボン堂)
源氏物語三帖空蝉の巻
帚木の巻の最後は生まれてはじめて伊予の介の女君に拒まれ消えてしまいたい気持で小君と帰邸する、そして空蝉の巻になる。
失意の源氏を小君はいとほしく思う。源氏と小君の間柄がなんともいえないお互いに気遣いしているのが私にはわかるのです 女君も心痛めて心の奥にしまっておこうと決心する。源氏はみじめに思うが腹立たしく、再三紀伊の守邸に小君の車で出かけ南側の戸をたたき、その隙に源氏は東側から、廂の間に入り簀の子に立ってのぞき碁を打つ二人の女君を見る。ひとりは濃き綾織の単衣を羽織って少しではなくやせてやせていて器量もあまりパッとしない。しかし内面に美しさがあるように思った。源氏はよく観察をしています。次回はもうひとりの女君 さてどのようなお方でしょうか。どんな装束でしょうか。(祥)
横浜源氏の会
2014年2月6日 大倉山記念会
「帚木」63頁~79頁
*「帚木」の章が、やっと終わりました。
【内容】
弟の小君を手なずけて文を送り続けても女君(帚木)との逢瀬がいつまでもままならないことに業を煮やした源氏は、ついに強硬手段に出る。つまり、方違えと称して帚木(空?)の暮らす紀伊の守の屋敷を強引に訪れ、目的を遂げようとするのだが……。
【感想】
空蝉は心のゆれを次第に自分の意志で抑えていく過程がよく浮きぼりに描かれていると感じ、楽しい時間になりました。
Y
身分制度のはかない恋、女君の気持がよくわかり哀しいが源氏の男の想いもよく描けていて大変おもしろい展開、小君との三人の姿に目に浮かぶ風景がある。
恵
源氏の女君に対する一図な恋心と、女君が内的要因(自らの心の状態、かつとうなど)や外的要因(身分の違いや人々の目)によって、心の奥に秘めた恋心を抑えこまなけばならない様子が見事に描写されている。
男と女の恋愛の微妙さ、複雑さは昔も今も変わらないものかと、考えさせられ、生きることの意味の奥深さを思わせられる。小君の動きも興味深い。
雄太
女のとても冷静な大人の女性を感じると同時に、古今東西、自分ではどうすることも出来ない運命の哀しさをおもってしまいました。
源氏のあっさりできない心情がおもしろかった。
はな
源氏の小君を使者として文を通じての思いに苦しむ女の心情が切なく心に迫る思いがしました。
茶良
楽しく勉強をさせて頂き、ありがとうございます。女の、心の奥の深さが伝わります。源氏の苦悩もいかばかりか……小君がかわいそうです。
M子
源氏は可愛い、小君をなづけて、二条院の衣服をあつらえて、実の親のように振る舞う。小君が源氏と姉(空蝉)の間を行ったり来たりお使いをする姿が目に浮かぶ。源氏の文を姉君に渡す役目をするが、もしも落したらだれかに見られたらと空蝉は心配なので小君に注意する。源氏ほどに好かれるのはめでたきことであるが、今は伊予の介の妻ということで心を許した文など書けない受け入れることはできない。空蝉はしっかりした堅実的な女であるが、源氏を忘れることができない。上の品のみがかれた女としては夢のようであったらしいが――。いきなり源氏がやって来て紀伊の守は驚く。源氏が立寄って下さるのは遣水のおかげと紀伊の守は喜びをかくしきれない。しかし空蝉は自分の運命は自分の運命は前世より決まっている、今は心にない、つまらない女だと思わせてこの恋はやめにしようと堅い決心をしようと悩む心のけじめをつけた。源氏も強引だったか落ちこむ源氏をみて小君はいとおしく思う。
源氏は帚木の心の歌を届けるが、女君は源氏の心にふれて苦しい歌を返歌する。無理なことはどうしようもできないと小君は源氏に伝える。源氏も小君がそばにいてくれるのでホットしてうれしい。私たちもだれかそばにいてくれてうれしいことがあります。
祥
女君の源氏への思いは、今は中の品におさまっている立場から、その域を出ないことを自分の判断の第一におく。かって親のいた頃なら、つきづきしい自分がいた。源氏に心ひかれつつ、それでも自ら下した判断はゆるがない。若い源氏は相手から拒絶されると、意地にもなって女君を追う、
あなたは伝説の帚木と源氏が詠めば、
そうです、私ははかない身、まさに帚木ですと答える。格下だと言われる女にほんろうされる源氏がおもしろい。
考ちゃん
横浜源氏の会
2014年1月9日 大倉山記念館
「帚木」51頁~63頁
【内容】
紀伊の守の家からもどったものの、女君(空?)のことが忘れられない源氏は、紀伊の守を呼んで弟の小君を供の者にしてなんとか女君と文を交わそうとするのだが……
【感想】
女君と一夜を共にした源氏。逢瀬の余韻につつまれていると、あわただしく、一目見ようと、女房たちがあたふたさわめいている様子が生き生き描写されている。女君の立場を考えて、女君の身を守る気づかいが見られない。空蝉(女君)は、立場上(中の品になってしまった)自分の身を思い、源氏の思いを受け止められない自分。霧りふたがりて……深い思いに涙する。
孝ちゃん
読んだだけでは、わかったようなわからないような文を、ひとことずつ、かみくだいて説明していただき、源氏物語の世界が広がっていくのを感じました。
ありがとうございました。
樹子
「何心なき空のけしきも、ただ見る人から、艶にもすごくも見ゆるなりけり」という箇所に心が留まった。また「霧りふたがる」という言葉の綾をもう少し考えてみたい。
アキラ
源氏は、いよいよ小君を使者にし、空蝉に心の内を文にして持たせる。空蝉にも源氏を思う心があり、文を通してどのように展開していくのか……楽しみ。
茶良
今日読んだ部分の人間関係は複雑で分かりにくいところもあるが、源氏の女君に対する思いと、心の底では源氏を愛してしまいながら、何とかしてそれを抑えこもうとしている女君の心のかっとうが興味深い。
雄太
本日の学びは一つ一つがとても面白い場であり、世界観でこれからの源氏と女君との展開なり結末に興味が湧きました。女君を気の毒にも思い哀しかった。
NaNa
久しぶりに授業に参加して、源氏の優雅な恋の世界の舞台の雰囲気に、現世を忘れる想いがするが、空?の運命に、その当時の女性の悩みと源氏への気持のずれが時代に反映していると思う。久しぶりに出て、なかなか物語の中に入りきれないものもあって、これから真じめに楽しんで学んでいきたいと思う。
恵
心のこり
源氏は心細く 夜も明け紀伊の守邸の朝 女房たちは邸内に憧れの源氏がいることで又チラリとみたことで満足している。女房たちはミーハーである。夜明けに女のもとを去ることはただあることだが今度は心に響いた。式部は自然の心をとらえて自然と人間の深い
かかわりを描写している。気持を通して日本の伝統的な表われて、左大臣邸にもどっても女君のことを想い胸が痛い。この想いを伝える手段がないつらいこの想いをたたなければ
ならない。ふり返りふり返り未練がつのってかきむしられる。源氏にとって中の品の女君(空蝉)は魅力的だった。その魅力というのは見苦しくなくて感がよい。自分を持っている身から出るたしなみ振る舞いがさわやかだったこと。源氏は自邸にもどり女君との再会を思い想像する。源氏も空蝉もお互いに一夜の契りを心痛め悩む。そんな時女君の弟を手なづけるため紀伊の守を呼びよせた。参上した紀伊の守に弟を身近に使う人にしたいと帝には私からいいます。源氏はいろいろと継母に対する気持をさぐり両者のやりとりで紀伊の守は継母と子という立場を心得ている。世間では継母子は不仲といわれていると話す。上司と部下の話になる。上の品、中の品の女をもう一度おさらいをした。
上の品で育てられた義弟は気品にあふれ優雅で美しい姿に満足し源氏は手紙を弟によって女君へ。女君は自分の意志ではどうにもならない運命だと。語り手より女は恋する女。いきなり源氏のラブレターを持ってくる。空蝉は面隠しに読む。目さへあはで→まぶたが閉じなくなる眠れない日が続き熱烈な みてもみてもあきない書体だった。空蝉は涙で目がふたがりわが身の宿命。身分をおとして源氏とのめぐり合い宿世だと泣く。身のほどを心得ている女君だ。翌日、源氏小君を呼ぶ。小君は返事を要求する 小君はひにくに笑う。小君は源氏の側に立っている。もう源氏のところへは行ってはいけませんと姉をおこらして小君は困る。紀伊の守は伊予の介の妻にしておくのはもったない 紀伊の守も源氏に負けずおとらずはりあうところが男同志の奮闘。
祥
横浜源氏
2013年12月5日
帚木 二巻 41頁~51頁
【内容】
女君は源氏の口説きに心から恋をし、源氏は女君に自分が本気に魅了されていることに気づく。しかし、女君は一夜限りの(逢瀬)浮寝と、かたくみずから決心するのである。夜が明け空が白んでくるころ、二人はつらい気持ちを抱きつつ、しのび別れるのである。
【感想】
方たがえした先で出会った、源氏と空蝉。源氏の思いがけない求めに、女君のゆらぐ心。一夜の浮寝で後瀬のことも考えられない、お互いの身分。そんな中で最初、身分違いで身を引いていた空蝉が、世に名高い源氏が現実に我が身の真近にいて、自分が求められている。いろいろ、迷いながらも、一夜の浮寝を受け入れる。「よし、今は見きと なかけそ」空蝉自らの決断がここに見られる。 (考ちゃん)
心の中のあり余る思いを、泣くことで出すという源氏に(現代人は泣かな過ぎるという声)。乏しい感性がついていけるだろうか・・・。でもこの時間は楽しいです。(Y)
源氏は方塞がり、方違のため立寄った紀伊の守の邸で紀伊の守の父、伊予介の後妻と空蝉と結ばれる。一夜限りで忘れてほしい、娘の頃だったらうれしいのだが、なかったことにしてほしい。源氏は堅実な空蝉に惹かれる。ずーっと以前に(四十代)読んだ本に作者は空蝉に置きかえて、源氏物語を執筆した中川あたりの邸宅で紫式部と空蝉はよく似ているように思う、と語っていた。私ももっと紫式部のことが知りたい。今年はいろいろな場所で月見をした。琵琶湖ではつかの間の月見だったが、芦原の月は美しく月見台で眺めることができた。源氏の色男の色色な場面可笑しくもあり滑稽だ。古語にふれたことが素晴しいことで小春日和が何日も続いているので読書にもってこいの時間で心の動きを知ることの大切さがわかってきました。 (祥)
「見ざらましかばくちをしからまし」など、ましかば~ましの反実仮想の用法が使われていて、昔どこかで習ったような気がしました。 (弓)
主語が表に出てなくて、それを特定するのが難しいといったら不勉強といわれても仕方なく、そこに日本語の特性があるのが面白いといえば面白いといえよう。 (ズボン堂)
源氏と空蝉の互いの思いの違いが判り、その思いの哀れさが感じとれた。また、源氏とは世界の違う身を知らされ空蝉のおかれた生活が身にしみて感じられました。(茶良)
「不倫」などという道徳観がなかった時代に、夫を持つ身の空蝉が源氏に口説かれて、愛するようになる様が美しく描かれている。しかし、一方で空蝉が源氏との関係を夫に知られたくないと思う気持ちが、充分に納得しにくい。今後読み進むにつれ分かってくることかも知れない・・・。 (雄太)
今月は、議論活発でした。平安時代と現代社会では、男女関係での倫理感の違いがあって面白かったです。新しい発見がありました。空蝉は、男女間では、身持ちがかたい印象でした。 (囲碁青年)
空蝉が源氏に惹かれつつも思い悩みとの葛藤の中に身を任せるシーン。この女性の感情に男の僕としては呆然とする。 (アキラ)
横浜源氏 2013年11月7日
帚木 30頁~40頁
【内容】
紀伊の守の家で、その父親の妻になった若い女君に、源氏の君が夜しのび込みいいよる場面。源氏の君の口説きに、女君の心はゆれる。
【感想】
源氏が女君の寝所をさぐりあてしのびこむ、寝殿作りの部屋の見取り図をみながら、話の展開と共に源氏と女君、そして女房の中将の動きを想像しながら読めて、楽しかった。きぬずれの音、息づかい、見えぬ世界がかえってさわやかに浮かぶ。
考
空蝉の気持ちの動き、中の品に嫁いでいても突然の出来事に揺れ動きつつも、己を固く持ち続ける姿が・・・。これからが楽しみです。
Y
『イメージで読む 源氏物語』帚木の巻き 30頁
源氏が空蝉とはじめて対面する場面、伊予の介の後妻になって、潔く献身的な生き方をしようと決めているところへ源氏の求愛に応じないところがドラマであり、王朝時代の恋愛だから興味津津になる。帚木の巻きの冒頭で源氏は(近衛中将、近衛府の次官、従四位相当)の地位で、その場限りの恋を重ねていくことは好まない。思いつめる癖があるという。紀伊の守の寝所ではなかなか寝つかれず、まわりが気になり暗やみを進んで行く。女君も寝所が変わって不安で恐い。源氏は近衛の中将を名のり、やさしく気持ちを打ち明けるが女君は「お人違いでしょう」と小柄な女君が手さぐりで寄って来た。源氏のお召し物に焚きしめた薫りが匂って中将が驚いた。
先日横浜市大倉山記念館の秋の芸術祭(29日)に出かけた源氏物語の桐壺の巻と六條の御息所の朗読を聴いた。司会者が「雅びな世界をお聴き下さい」とはじまった。田中先生はよく決して雅びばかりではないそして今も昔も男女の仲は同じではないと力説なさいます。懇談の中で男女の仲(不倫)をテレビのドラマで放映されると今も昔も同じよとしかし時代(貴族社会)も違って同じでない。その根本を履き違えてるように思う。作家たちの物語の基本は源氏物語のような気がいたします。
横浜源氏の会は三年前から神奈川新聞に御案内が掲載されていますが、大倉山記念館の秋の芸術祭に参加して公開講座をしては如何でしようか。源氏の口説き上手。鬼神も
あらだつまじき、源氏がやわらかい全体すべてのけはいにあっとうされる。しかし女房は弱々しく抵抗する。しかしだんだん源氏は女君にひかれていく。軽い気持ちで口説いたのになぜ抵抗する人ををかしと思ったのか。まだ出会ってまもないのでいとおしいと思っていないが中の女なんだけれど生まれは上の女の出で源氏も空蝉の魅力を感じた。口説くとは女君の心をつかむことだ古文は五感で読み中将は悟った。源氏は真面目になり女君は源氏の口説き上手に惑わされることなく「際は際とこそはべなれ」と聡明なところをみせた。源氏も真剣に、空蝉も真剣、そんなところに読む人を魅了する。
祥
「帚木」に至って『源氏物語』も佳境に入ってきたようで、面白くなってきました。
ズボン堂
本日の部分は、男女の真剣勝負の場面で色々考えさせられましたし、面白いです。女の気持ちが、未だ充分わかりませんし、一方で中将の君の演出かとも考えもしました。今後の展開が楽しみです。
囲碁青年
源氏にしのび込まれ、口説かれる女君の女心、だんだんに源氏に心ひかれていくさまが見事に描かれている。自分をしっかりと持って、簡単には意のままにならない女君に源氏はますます、ひきつけられる。女君が真剣に拒み続けると源氏はますます思いがつのり、しどろもどろになっていく。真面目に愛するようになっていく。
雄太
若い源氏の行動と言葉の口説きに対して女君の返す態度と言葉のかけ合いは読みごたえがありました。
弓
読みとくごとに文章の巧みさにほれぼれします。女の人を口説く時のきり返し言葉が面白く、先生の解釈により源氏の人となりの性格や魅力も少しづつわかり、楽しくなってきました。
はな
源氏が空蝉の部屋に忍び込み、空蝉を口説いていく様子が面白く、また、興味深く感じられた。この後、どのように口説きおとすかが楽しみです。
茶良
横浜源氏の会 2013年10月3日
帚木 二巻
[内容]
源氏は偶然にも中の品の家に身を置くことになって、女房達を仕切り越しに観察する機会を得た。若い姉君(父の衛門の督が亡くなり弟を連れて、しかたなく受領階級の年老いた男の後妻となった女性)が、そなた(紀伊の守)の継母かと聞く源氏の意図は、もはや、紀伊の守にはよく解かっている。源氏は紀伊の守が、一番触れて欲しくないと思っていることを、そのまま口に出して聞くのである。〈似げなき親をも、もうけたりけるかな〉おまえに不似合いな若い親をまあ。という具合に。源氏は紀伊の守の若い継母への想いの危うさを、さらりといってのけるのだ。継母は、故衛門の督を父として生前まで、入内の話があった。そのままであれば、帝の妃として格段の晴れがましい人生が待っていたはずの女性だったはずだ。源氏はその女性の運命の哀れさに、胸が打たれるのである。
[感想]
紀伊の守は、父伊予の介の後妻となっている女性に、心惹かれ、源氏も父宮桐壺帝の後添いの藤壺に惹かれ自ら悩んでいる。ニ重写しのような設定の中で、源氏が紀伊の守を、その点するどくつくのは、自虐的とも取れて、面白い。
考
いくつかの場面を学ばせていただき男女の関係を主に人間関係の心模様の文章のたくみさに感嘆しました。
はな
源氏と伊予の介の女(気品の高い)のことに対する会話が面白かった。この後、源氏と女かかわりがどうなっていくのか楽しみです。
茶良
源氏が女房たちの噂話におぼすことのみ(藤壺との秘めた思い)、気になっている場面で(まず胸つぶれて)という言葉から源氏と藤壺との間に何かあったとわかるという解説に、この先の展開が暗示されていておもしろいです。
弓
・・おぼすことのみ心にかかりたへば・・というさりげない表現で、源氏の藤壺によせる思いが語られている。
・・高貴な身分の父親が死ぬと、天上童となるはずだった息子、帝の妃となるはずだった娘の運命も、哀れな道をたどることとなる。
・・源氏と紀伊の守のやりとり。源氏が紀伊の守をからかうさま、いろいろと面白い。
雄太
京都観光した折御所近くの梨木神社に行った。今時分萩が咲きほこっていることでしょう。萩の宮とも呼ばれている神社、京都名水の場所で、中の品の女房たちが、源氏の噂をしている。源氏は気になる、そこには深いわけがある。それは「思いあがれるけしきー受領で年老いた伊予の介の後妻のことである。源氏は衣ずれの音や笑い声が気になり、聞き耳をたてている。藤壺のこと噂になったら大変だと、中の品の女のことも少しわかってきた。紀伊の守は明かりをふやしたりくだものを持ってきたりしているのだが、源氏は寝床はどうなっているのかと、このやりとりが可笑しい。紀伊の守の家では大勢の子どもが働いている。源氏は可愛らしいと思う。その中に気品のある子どもに目が止まった。いろいろと事情があって紀伊の守のところで姉と一緒に暮らしている。姉とは紀伊の守の継母である。源氏は帝が気にかけていたことを知っていた。紀伊の守にはあまり聞きたくない話になる。源氏は幼い頃から宮中で育ちいろんなことを見てきた。紀伊の守は「男と女の縁は宿世なのだと源氏と論じ合う
祥
横浜源氏の会 2013年9月5日
帚木 源氏と女房たち 二巻
[内容]
長い一夜が明けると、久しぶりに雨もあがっている。源氏は内裏を退出して、左大臣邸を訪ねる。高貴な家柄にふさわしい風格をそなえた邸宅で、奥の間には北の方(葵の上)が、侵しがたい品位をたもち、端然と控えている。源氏は妻(葵の上)との間の気づまりな空気から女房たちに〈たはぶれごと〉を云う。暗くなるごとに、方角が悪いということで「方違へ所」へ行くことになる。そこは中の品の家で、紀伊の守の邸であった。
[感想]
左大臣家に、久々に訪れた源氏。語り手が描写する左大臣家は「おほかたのけしき、人のけはひも けざやかに け高く」となる。一方、紀伊の守邸(中の品の家)、「田舎家だつ柴垣して、前栽など心とめて植えたり。・・・蛍しげく飛びまがひて、をかしきほどなり。」上の品との比較して読むと一興。楽しめました。
青
久しく「源氏の話」をきき、楽しい時間になりました。中の品と上の品の厳然とした違いの社会背景をまず、理解して・・・と。ついつい現実に引き当ててしまいがちだけれど・・・。
Y
やっと雨がやんで源氏は宮中より妻(葵の上)がいる左大臣邸(大殿)に帰るが妻はあいかわらずうちとけず、義父の左大臣も婿を気づかいしてとりはからうが、それがうっとおしい。しかし、女房たちの振る舞いで少し気がまぎれる。私には源氏や舅の気持ちがよくよーくわかる。夕方暗くなって女房たちが思い出して、宮中より左大臣邸に行くのは「方塞がりで方違へして行った方がよい。平安時代月と太陽を中心に動き「方塞がり」「方違へ」が流行した。なぜなのか?陰陽道で外出する時方角が塞がりで神のいるところへ行こうとするには無理で中神のいる方向を避けて寄道して前夜は他の方角で一泊し方角を変えてから翌日改めて出かけたところが紀伊の守邸であった。三年前源氏物語に出てくる場所を観光した時、陰陽師の祀った清明神社にもいった。人気の場所らしい。紀伊の守の父の伊予の守のところでも物忌があって大勢で紀伊の守邸に来ていた。源氏を迎えるために紀伊の守はてんてこ舞い盆と正月が一緒に来たような、源氏は中の品の家をゆったりと見た。そして中の品の女に興味を示した。紀伊の守が源氏をおもてなしする姿が目に浮かんだ。
祥
平安時代には「方違へ」と言う習慣があり、現代とは違う文化(?)でしょうか。その辺が特に面白かったです。
囲碁青年
悪い方角を避けるための「方違へ」により、左大臣の家から中の品の家へ移ることとなった源氏が、中の品階層の生活ぶりやその階層の女たちの様子を体験することとなる記述、描写が面白い。
雄太
女房たちの忍び笑いを源氏がお茶目に制するおかしさが際立つ場面で使われた「あなかま」という言葉が印象的でした。
弓
長い、長い〈雨夜の品定め〉がやっと終わって、話が流れ始めてわくわくしてきました。今後、ストーリーがどう展開していくのか楽しみです。
ズボンの君
横浜源氏の会 2013年8月1日
帚木 蒜食いの女 234頁~249頁
[内容]
中将は、今度は藤式部丞が一風変った面白い話を告白する番だという。藤式部丞は、まだ大学で学んでいた時に、子だくさんの貧乏博士の娘と縁があった。その娘は大変な博学で、特に漢学の才能が並みはずれて高く、藤式部丞は女を師として漢詩のひとつもつくれるようにもなったという。ある日、女のところに立ち寄ってみると、女は暑気あたりの薬を服用していて、ひどく臭いので会えないという。にんにくの臭いがあまりにも<はなやかに>ただよってきて、なすすべもなく、式部は<逃げ目をつかひ>ながらも返歌などして、別れた話をする。それぞれの公達の話が終わると、左馬頭がそれらの女性たちの女性論をまとめる。左馬頭の理想とする女性は<心に知れらむこと>をも<知らず顔にもてなし>、<言はまほしからむこと>をも<一つ二つのふしは、過ぐすべくなむあべかりける>人であるという。男性達がはなしている間、源氏は物思いに沈んでいた。源氏の心に在るのは、藤壺の女御ただひとりである。公達の話は、果てしなくつづき宿直所で夜をあかしてしまう。
[感想]
(中将は言う。痴者は、果たして誰か。女は、中将の北の方のある行為を受けて、決断。中将の前から身を隠す。なぜ身を隠したのか、痴者の中将にはわからない。今後、常夏の女の次の登場が、待ちどうしい。)7月4日の「常夏の女」の感想です。孝 *
蒜食いの女。日頃、才をいかんなく式部に見せ付けるおんなが、急に生身の人間として風病(神経痛)をおさえるため、にんにくを食べて、式部には物越しにしか会えないという。においぷんぷんに辟易した式部が、逃げ目をうかがう。才女も人の子。このような女と男のやりとりは、今も昔もかわらない。作者の紫式部は、才を顕にだす女には、厳しい一面がここにある。
孝
身分の上下がはっきり言葉に表れる場面が、多くみうけられました。中将の命令口調や、式部の「はべる」の連発など。蜘蛛のことを「ささがに」。(ちいさなカニ)歌にとり憑かれていく人を「歌にまつわれ」。これらの言葉を特に趣き深く感じました。
弓
蒜食いの女 その一
さて藤式部丞の話になる。式部が学生のころ打ちどころのない女がいて悩みなどを聞いてくれて心強かったが、女の親からいいよられことわれなかった。久し振りにたずねると、風病にかかり治すために蒜を食べたので会えないとか云っちゃって、式部もどうして、いいのかわからなくなる。女のことを少しいとほしく思うが女は追いかけてくるが式部はとまどってしまう。そして歌の交換をする。なんとも女はすばやく返事をするが、口疾くが式部は冷静である。藤式部丞の話が終り左馬頭は身分の高い女の中にも自然に教養や知識を得て平凡な人が良いと云う。
三人の話を聞いて源氏はいつ話してくれるのかとーとうとうはなさずに。私は思うには男はやたらとしやべらないーそんな男が私は好きだ何か秘めているようでー。
三人の話を聞いて理想の女は「中の品の女」藤壺で、ますます思慕が募り胸がふたがり はりさけんばかりになる。三人の息子たちを見ていると、「ほどよい」がうまくいっているように思える。
祥
式部の博士の娘との体験談、左馬頭が女性論のまとめをする所など面白く思われました。また、源氏が話しを聞きながら藤壺を思い出している所に興味を持ちました。
茶良
雨夜の品定めの最後…『源氏物語』にこんなユーモアがあるなんて、うれしい発見でした。
ズボンの君
今までいろいろの女性が出てくるが、蒜食いの女の才女等いろいろの女性と男性の、女性に対する思いの関係がおもしろく思う。
源氏のこれからの恋愛にどう変化するか作者の教養の深さに、ますます魅力を感じて、これからが楽しみである。
恵
下級官吏である式部の丞と同じく身分の低い博士の娘で、女ながら漢学に通じている人との間のちぐはぐな男女関係が面白い。こういう才気走った、自らの才能、教養をひけらかす女は、特に日本では、昔から嫌われる。この点、百パーセント以上自己主張しないと無視されてしまう、西欧やラテンアメリカ文化との差異を感じる。
雄太
未だ全体の流れが分かりませんが、平安時代の男女関係やそのやりとりが面白いです。特に現代と違う部分が。また、当時は、上流階級と下層階級の人々の考え方が、大きく違って面白いですね。
囲碁青年
横浜源氏(大倉山記念館にて) 2013年7月4日
帚木 常夏の女 そのー・その二
内容
「なにがしは、痴者の物語をせむ」と前置きして、中将が密かに通い始めた「常夏の女」の話をはじめる。女は何時行っても変らない態度で甲斐甲斐しくもてなしてくれた。中将が安心し切っていたところ、女に辛い事件がふりかっかた。中将の北の方(右大臣の四の宮の方)が、人を介して陰険な嫌味を言わせたのである。女は、身に襲いかかった災難を強烈な言葉例えば〈《山がつ》とはきこりなど山に住む賤しい身分の人のことで、自らのことをたとえた。〉で、訴えたつもりだったが、中将には女の気持ちが届かない。やむえず、女は、我が子(中将の娘)をつれ逃亡したのである。女はどんなに追いつめられていた時でも、男の前では何事もなかったように振舞っていたが、そのことが中将の鈍さを一層助長することになった。自分の言動で人を傷つけることが何より辛かった女にとって、恨むとか嫉妬するとか言い募るとかいった、人とあらがうかたちの自己主張では人とかかわれないたちだった。それゆえ、極めて繊細な神経と鋭い感受性の持ち主だった。逃亡はそんな女の選択したひとつの自己主張でもあった。「指喰の女」は、嫉妬深くって一緒に生活するのは、わずらわしい。「木枯の女」は男にとって〈すきたる罪〉が、重くって安心できない。中将は「常夏の女」は、他に男ができて失踪したのかもしれないと言う。すでに、中将が愛したあの「常夏の女」はどこにでもいそうな陳腐な女に変ってしまっている。「『吉祥天女」を思ひかけむとすれば、法気づきくすしからむこそ、またわびしかりぬべけれ』とて、皆笑えぬ。」中将の茶目っ気たっぷりの言い方が皆の笑いをって、「常夏の女」の幕が下りる。
[感想]
人は思いやることが大切である。男の鈍さ女も自己主張が強く、繊細な神経と鋭い感受性のために行方をくらました。中将は指喰いの女もいや、木枯しの女も安心できない。常夏の女も愛していたが娘を連れて姿を消したので女を悪者にしてしまった。女は男を恨んだり、男は片思いだったりと、理想の女はどこにいるの! 吉祥天女のような女を
妻にするのも「くすし」うちとけない、堅苦しいと、皆で笑う。常夏の女(そのー、その二)が終わった。
祥
女のはかない想いと親心の切ない心に、華やかな文学の中の濃厚な息吹に感動! 古典の中の男性と女性の生き方が、どう物語の世界を作っていくかが楽しみ。現代の恋愛状態の男女の姿とは、はるかに遠い宇宙的な・・・それとも相通じるのか痛快である。
恵
中将の女への思いと女の中将に対する心情の違いが、女に逃げられたことで顕になって面白く感じました。
茶良
中将たち男の間で思い出話のネタにされたくないなぁ、と思ってしまいました。心のことをうらというのは趣きありますね。
弓
初めてでしたので前後関係が、良く分かりませんでしたが、-字-句ていねいに説明しているのが、大変印象的でした。また、会の中では議論活発なことも印象に残りました囲碁青年
中将の“常夏の女”に対する言動から、男、特に人生経験の浅い若い男の、にぶさ、愚かさを感じた。わが身に照らしながら、男女間の関わりの微妙さ、複雑さも改めて認識させられた。
雄太
初めて参加させていただき、とても楽しく嬉しく勉強させていただきました。アメリカ滞在二年後に、突然古典の世界に入り、再び外国語に出会ったような気がしました。豊かな日本語の世界に、数十年ぶりにひたり、幸せな時をすごせました。ハマリそうです。
KO.KO
いろんなタイプの男女えお書き分ける紫式部の散文家の腕は、さすが世界三大作品の一つといわれるだけのことはあると関心しきりである。
釣魚主
横浜源氏 2013年6月6日
帚木 木枯の女 その一 210頁~218頁
左馬頭には、指喰の女と並行してつき会っていたもう一人の女がいた。そのひとは<人も立ちまさり、心ばせまことにゆゑありと見えぬべく>女人であった。しかし、指喰の女が生きていた時には、輝くように映っていた才気も心ばえも容貌も、今となっては色褪せて見えるのである。通わないでいるとその内、木枯の女のもとに他の上達部が訪れていた。男の求めに一心に応えようとしている女を見て、左馬頭は目をそむけずにはいられなく、きっぱりと女を見限る。一生つき合うには、木枯の女のような傾向の女性は<たのもしげなくさし過ぐにたり>と評価えを下す。左馬頭の長い話が終わると、源氏は<いづかたにつけても、人わろく、はしたなかりける身ものがたりかな>と言い放つ。源氏の遠慮のない感想に、みんな思わず笑ってしまう。
感想
嫉妬深い女も亡くなり又浮気心で別の女のところへ通う左馬頭。木枯の女は源氏絵にある。平安時代において、人柄も品も指喰の女に比べれば才能もある女がいた。しかし、派手で浮気っぽい女なので、左馬頭の信頼がうすれてしまった。久し振りにある月がおもしろい夜(美しい月夜)に、殿上人の後をつけた時左馬頭は、現場を見てしまった。かつて、女は輝いて見えたが別離した。色っぽい女は信頼できないから、気をつけてと忠告する。王朝の時代も平成の時代も世は変っていない。帚木の巻がこんなに面白いところだったのだと再確認した。一帖から五十四帖まで、四十年余りくり返し三回目。五月雨の一夜、宮中で物忌みのため籠っている源氏の宿直所に四人で集まった男たち、浮気やいろいろな女の話題を打ち明け、おろかな男たちの話。紫式部はすごい! 田中順子先生のご指導で原文を正確に丁寧に読んで又楽しい。源氏の「いづかたにつけても人わろくはしたなかりける身の物語かな」とうすら笑い三人で笑う。男を恨んだり片思いだったり、理想の女はどこにいる?
祥
今日で四回目、ほんのり少しですがおもしろくなって来ました。長く続いていけるようにします。
夢
「木枯の女」「指喰の女」それぞれに個性的な女性、あと二通りの女性が楽しみです。男性の好みを満たす女性がはたしているのでしょうか。
Y
左馬頭が宮中から下がる時、同乗した男が、左馬頭がかれがれに通っている女のもとにむかった。笛と琴のかけあいで恋のかけあいをする二人をみて、左馬頭が女に興ざめしていく様子が面白い。女のもとに少しずつ近づいてゆく表現が「歩む・・・」と使われている。「歩く」と「歩む」の言葉の違いが情景を面白くしている。
孝子
この「雨夜の品定め」は、紫式部の人間観察の面目躍如として場面で、感心しきりだ。
中上哲夫
左馬頭は「木枯の女」の元に通わなくなっていたにもかかわらず<すきたわめたらむ女>と言ったりその後、近寄るまいと思うと語るが自分勝手な男の考えにおもえた。
弓
横浜源氏 2013年 5月2日
帚木 指喰いの女 その三 203頁~209頁
[内容]
賀茂神社の臨時の祭りを控えて練習があった折、いざ帰ろうとすると霙が降り、大変に冷え込んだ夜だった。その日、左馬頭は家に帰る場所は、やはり指喰いの女のところしかないと思うのであった。そこで、女の家に入って見ると〈火ほのかに壁にそむけなえたる衣どもの厚肥えたる、大いなる籠にうち掛けて、引き上ぐべきものの帷などうち上げて〉あるのを見て、自分の来訪を女は待ちわびていたのだと思うのである。ところが、女は親の家に帰ってしまい〈ひたやごもり〉をし、いないということだ。何の言葉も残さずに、女は身を引き消え入るように死んでしまう。左馬頭の話を聞いた中将は、妻を選ぶのは〈かたき世〉、結論がなかなか出せないのだと話をまとめる。
[感想]
時は変れど男女の心は変らじ、変化し進歩したのは身の回りだけ? 源氏、式部の心の内をもっと知りたいと、思えるようになりました。
野中夢
指喰いの女 その三
人を疑ったりしては心が淋しい。せっかくの心づくしも、相手に伝わらないのも悲しい。才能ある女が男の浮気を悩んで、嫉妬深い女は亡くなってしまった。お互いに意地をはっては悲しい話である。男女の仲はむづかしい。
祥
「指喰いの女」はなぜ死んだのか
自分がこれこそと見立てて、身分の低い時から後見して来た男だったが、自分ひとすじに向かって来れない男。女は自分が選んだ男だったが、自分の思うようにならないことにも心きれた。しかし、それ以上にそういう男を選んでしまった自分に絶望したことによって、「はかなく」なったのではないか?
青考
「指喰いの女」がひたむきな自分の気持ちを通すことは、相手の心の成長を待つほど・・・寛大ではなかったのだろう・・・と。(生き続けたら又違っていたかも・・・)物語がおもしろくなくなったかもしれないが・・・。
Y
授業が大変わかりやすくおもしろく思いました。古典の中も現代の中にも、常に女の悲しみは多くの人々に理解されて、男女の仲は永遠の問題! これからの物語がどう展開されていくのか楽しみです。古典の言葉が少しずつ慣れてきました。
千
初めてで、前の話がわからないのですが、左馬頭の浮気相手の事は話にどの程度出てきたのでしょうか? この指喰い女のような人が相手だと、とてもやりにくい感じがしました。執着はあまり人を幸せにしないようにおもいますが、執着してしまうのが女の性なのかもしれません。
中野由美
男女の間の愛着、しがらみは平安時代も現代も変っていないと、つくづく感じた。一千年前に較べて自然科学は驚くほど進歩したが、人間そのものはこの間に進歩し賢くなってはいないのだ、と認めざるをえない。哀れで愚かで愛しい人間よ!
雄太
女の心(思い)を読みとれない左馬頭が、命を失うほど苦しんだ女の悩みを知って、後悔する様子。そのあわれさがひしひし感じられました。
茶良
横浜源氏 2013年4月4日
帚木 指喰いの女 そのー 191頁~202頁
左馬頭が、昔まだ身分の低いかけだしの役人だったころの、恋物語を始めた。恋人は決して美人とはいえないので一生連れ添うつもりには、なかなかなれなっかた。しかし、しっかりと左馬頭に尽くす女だった。多くの女のもとに通うことは当時の慣わしからすれば、男が責めを負うべきことではなっかたが、あまりにも女が嫉妬深いので、そのことがなければ正妻にとも考えていた。そこで、女に嫉妬深さを言い聞かせるつもりで、左馬頭は他の女のもとにしげく通った。ところが、思惑に反して女は、思いがけない反応をみせる。「すこしうち笑ひて」いつ改まるとも知れない男の浮気心に苦しむのはたまらない。女にとって、自分の誠意が実らないことほど甲斐の無い人生も無い。と静かにはなす。だが、左馬頭は女を錯乱させようとし、挑発し怒らせようとした。そのことで、二人の気持ちが高ぶり、とうとう女は「指ひとつを引き寄せてくひてはべり」という具合になる。女が折れてくるまで、左馬頭は外で浮かれて気ままにやり過ごしていれば、わずらわしい女(妻)との軋轢から逃れていられると思っていた。
感想
左馬頭の女性に対する批判を聞いていた女は「すこしうち笑いて」この表情を想像する時不気味さと、ひややかさと、困惑とのいりまじった情景を思い描いてしまう。 Y
左馬頭の恋物語の過去の身分の低い時の体験談が興味深く感じとれました。左馬頭と女の愛情のもつれのやりとりが面白く思えました。
茶良
指喰いの女
よるべとは思いつつ、とまりには、もう一つ。嫉妬深さが、気に入らぬ左馬頭。よくつくしてくれることを認めながらも、さらに自分の思いのままに女としたいと、しばいを打つが・・・結果は予期せぬ別れ話に・・・女が別れぎわに指をかむ→未練がみえる。果たしてどの指をかんだか・・
想像すると楽しい。 考
今回で二回目出席させていただきました。早く皆様について行けるようにしたいと思っております。すてきな方ばかりの会に出会えて感謝しております。 野中夢
人間はある時は我慢も必要であるが、どうしても我慢できないこともある。語り手の左馬頭は過去の女そのーは、男を信じて心をこめて尽くし、男も好意を持っていたけれど、女が嫉妬深いので嫌いだった。その二は女は辛抱して、男の浮気の休むのをいつまでも待っていたが「おぞましい」とか「身だてなし」とか「われたけく」思い上がりも。とうとう堪忍袋が切れて、男の指に噛み付いた。口喧嘩が烈しくなり夫婦喧嘩も犬も喰わぬとよく言ったものだ。女は声を立て、すこしあざ笑い「あいな頼み」で別れよう思い男の指を喰ってしまった。どの指を噛んだのだろうか。行きすぎるとあとのまつりでよく考えて行動することが大切である。 祥
『源氏物語』といえば雅な文学ということになっているけど、なかなかにウィットもユーモァもあるというのを知ったのは、面白い発見でした。
中上哲夫
横浜源氏」2013年 3月7日
帚木 179頁~190頁
[内容]
女の心変わり
他の女性に夫が恋をしても、夫を恨んだりしないで、昔、夫に見染められたことを思い出して、互いの縁はあるのだからすべてをおだやかに事を運んで、恨むふしもにくからずかすめなさば、夫の心も女の出方でおさまります。そうすれば夫は妻をさらに可愛いと思うものです。他の女性に心が向いている夫にあまり何も言わずに見放ちたるも、夫からすれば「つながぬ舟の浮きたる」ためしがだと左馬頭は中将に語る。中将はわが妹(葵上、源氏の正妻)は、よくかなっていると思って、源氏の方を見れば、源氏はうとうとと居眠りをしているのを見て、中将はものたりなさを覚える。
左馬頭は指物師の調度品とか絵画の話をしたり、書道の話をして、女性の品さだめを得意げに語る。
[感想]
源氏物語の講座に出席して約一年間、紫式部の男性を見る思いの人生観がおもしろく、夫と妻の心のゆれ動きが痛快であり、なるほどと、頷ける。
それを左馬頭や中将に語らせて、物語の土台は出来あがり、これからの女性をめぐる話の展開が楽しみである。
恵
夫婦の仲は目にみえない宿命的な縁があると信じている。心変わりなどで動揺する、つまづきもあり妻はほのめかし、なだらかに、にくからずかすめる。そんな妻がいとおしく思う。夫のあわれ、これこそ源氏物語のあわれ文学なのだ。男はつなげるのが反発もエネルギーなのだ。中将が感心して聞いている。
妻はよるべ頼り所であってほしいと左馬頭は思っている。
中将は男が心変わりするよりも女が心変わりする方が一大事であると思っている。
女の気持ちを正しくして、男と女の仲は決してうまくいかない。我が妹は夫婦の仲たえしのんでいる源氏に聞かせたいのだが源氏はうとうとと居眠りをしている。左馬頭は夢中でひひらき(鼻の穴を開けて)得意気に話す。
左馬頭はたとえばなしに指物師のことなど例をあげて話をしているのに、源氏はうとうとしているが聞いているのか聞いていないのか。
絵師の集まるところに墨書に選ばれて決してけじめがはっきりわからない、すぐには見分けがつかないが、だれも見たことのない理想郷荒海の恐ろしい波など画家がイメージで書く絵は人目をひこうとした絵唐絵。それに対して大和絵はなるほどとみえ実景がやわらかく書かれて線は静かに構造的に書かれている垣根に囲まれた家、絵師の配慮が決め手になって、上手は勢いがある。
未熟なものは及ばない。
妻選びとはどうつながるのかな?
人の心は目先だけの情愛など信頼にかかわる。とっておきの話を現にお聞かせしたい。女の心は派手に見えてもおもわせ振りに目先だけの愛情にだまされない。頭中将は真剣に聞いているところでした。そして睦言が打ちあけ話になる。
次回が楽しみ。男たちの昔の失敗談のはじまりはじまり。
祥
左馬頭の女(妻)に対する持論を指物師や、絵についてや書についての例を出して語るところに大変おもしろしく感じられました。
これから体験談が語られるのを楽しく読みたい。
茶良
大和言葉の「言い得て妙」今回もいくつか出て来ました。
・寝ぶる→寝ると体を前後に動かす
・ひひらき→馬のいななき。鼻をふくらませて得意げ
・さればみれる→しゃれたもの→この言葉に初めて出会いました。
左馬頭の男と女の関係を舟にたとえた個所。
「男はつながれるもの、女はつなぐもの」
えっ、本当?奥深いかも。
孝
左馬頭、中将らが熱心に語る男女の間の心の機微についての話を源氏はうとうとしながら聞いている。そこから話は工芸、階が、書道へと話が飛躍し、そこから再び、男女の話(女の品定め)へと戻っていく。その展開が面白い。
雄太
細野豊
ドナルド・キーンさんは日本文学の特徴を清少納言の〈をかし〉と紫式部の〈もののあはれ〉だといっていたけど、源氏物語の〈もののあはれ〉ばかりでなく、〈をかし〉もある。振幅のある文学だと再認識しました。
中上哲夫
横浜源氏 2013年2月7日 大倉山記念館にて
帚木 171頁から178頁
内容
どんな女が理想の妻なのか。左馬頭は子どものような未成熟な女は、男にとって理想の妻に育てる楽しみがあるといいながら、夫とは別の人格を持って、他人のことばの是非を判断できる人が好ましいなどと語る。また浮ついたところがなく落ち着いた女性こそ伴侶にふさわしい。男が「妻」に求めるものは、何よりも自分が頼りにできる存在であって、些細なことで夫への信頼感を失わない情緒の安定した妻がいいという。そして、厄介な妻の例を出す。心の内には、夫への不平不満が渦巻いているのに、夫に一言も伝えようとしない妻。それが故に、ついに妻は、家出という手段をとって(夫を振り向かせるために、ちょっとすねてみたという程度の家出にすぎないのに、世を捨てる程の決心なのだと周囲に思い込まれる。)尼には、なってみたがどうにも気持ちの整理ができずにいる。まだしも、俗世間(濁りにしめるほど)にあったほうがいい。かえって、(なまうかび)の状態での出家生活をする方が、あの世で(あしき道にただよひぬべくぞおぼゆる)と、女性に対して左馬頭は厳しい見方をする。
感想
言葉の使い方に現代にないリアルさがあり、面白い。女性の生き方の紫式部の見方に深く感動。大変おもしろく授業を受けています。
恵
作者、紫式部は左馬頭に、妻としてふさわしい女とはどのような女かを語らせているが、作者は左馬頭に代表させている男をよく見てよく描き出しているばかりでなく、女である紫式部の〝女〟に対する厳しい目が思われて興味深い。
雄太
式部の人間観察の深さをまざまざと感じる場面でありました。この場面はもう少しつづくようですけど。
中上哲夫
「子めきて」「そばそばしい」の対比を聞きながら、ついあれこれ思い浮かべ、重ねあわせてしまった。
Y
初めて参加させて頂きました。楽しいお話を本当にありがとうございました。また、チャンスがありましたらおじゃまさせていただきます。甘い妻に私も考えさせられました。
佐藤雅子
左馬頭が女性について語り続ける理想の妻の条件や、夫婦像のあり方に興味深く感じられました。
茶良
本日はありがとうございました。5年振りに健康を取り戻して、外出。細やかに読み説いて戴き、何となく上面だけ解かったような気でいた自分に気づきました。出来ればまた、教えて戴ける機会があれば・・・と存じます。
安藤
ある意味で、仏教による国の統治が成り立ち。物語の筆者も古代後期の平安の末の人物。時代は次に台頭してくる武家社会が目前にある。父性原理(ロゴス)もすっかり時代の変遷により定着している。女性はそうした男性に柔軟な対応を迫られ、厳しい状況下に置かれている内容だった。雨夜の品定めによる左馬頭の男女(夫婦)等は、現代にも相合するところが多々ありすぎるので、紫式部の真意は他にあるのではと思ってしまう。登場する女性達の心の姿(苦しさ)を考えると、左馬頭のようには語れない思いも残る。
えむ
左馬頭が語る理想の妻は未熟な妻を理想の妻に育てる。現在もよくある話。たとえば、先生が生徒に教えるように、夫好みに飼育する。夫もそれが楽しく生き甲斐だったりして、しかし、なかなか理想の妻に持っていくことは、簡単ではなく左馬頭は苦悩する。顔立ちもよく、気立てもよく、綺麗で、品良く、そんな八方美人にこだわらなくてもよいと左馬頭は思う。同感だ。「まめやかに静かなる心のおもむきならむ」夫と誠実に信頼しあう妻こそ、理想の妻なのだと熱弁した。ずいぶん長い間半世紀共にした夫に対して、理想の妻であったか_____振り返ればなつかしい。これから、第三の人生を助け合って歩みたいと思う昨今である。
横浜源氏の会二年目を迎え五月 四、五日に開催される「座間の大凧」の文字が「祥風」に決まった。大空に舞う夢をみつ、源氏の会の会員がふえるといいですね。源氏物語にでてくる衣装に関心があり、先日十二単衣のデモンストレーションを見てきました。特に京都は底冷えがする厳しい冬で「如月」きざらぎの由来はその寒さゆえに「衣をさらに着る」とする説も。
祥
2013年1月24日(木)
帚木 159頁から170頁 大倉山記念館にて
内容
左馬の頭は、妻を選ぶのは難しいと語る。妻は使用人たちに采配を振るったり、染色・裁縫などに始まる家での様々な事が、勤まる人でなければならない。男が避けるべき女についても話す。女は物語の中の恋に憧れ、男との理想的な出会いを夢みている。さらに、「女らしさ」を演じていたりして、はなはだ子どもぽいから、気をつけるようにと語り。しかし、妻になった女房が「耳はさみ」がちになった場合は、つまり、実質一辺倒の妻は、無神経で醜く映ると言う。また、会話のできない妻では、男を失望させると左馬の頭は話すのである。
感想
今回は、左馬頭の女性観、妻選びの苦労が主として語られているが・・・実は作者の紫式部のするどい女性観が読み取れる。「耳はさみがちに、びそうなき家刀自」の女性こそしっかり者で家全般のことはまかせて安心であるはずなのに男の側から見ると、世間の動勢、うきよのきびなど男は話したくとも話せないと言う。女も同様に話したくとも、うちの夫に話してもわからないのだろうなぁ?と、双方からの見方が面白い。
考
常識的な男の典型である左馬頭の女性観や妻選びの難しさ、女のみにくさなどが語られるが、今も昔も変わらない男女関係の機微を、著者は鋭敏にユーモァさえ交えて描いている。
紫式部の人間観察の深さ、鋭さはすごい。
雄太
左馬頭の話によって平安朝の主人(主婦)の仕事が、よくわかりその大変さを知りました。また、妻選びの条件も、左馬頭の女性論からおもしろく読みとれました。
茶良
今の世にも通用する内容で共感しました。男も女も、親しくなってもだらしなくなってはいけないな、と思いました。
裕
男が女に求めるものは時代に関係ないことがよくわかった。平安時代をもっと身近な時代として、これからは考えることにしよう
S
左馬の頭の妻論が現代にも通じる所があり、千年以上も前の文の中に生き生きと感じ取れ、楽しい時間になりました。
Y
先月に同じで困ってしまうのですけど、言語の経済性というのがあって、日本語の場合は、代名詞を省くのが一つの特徴であるのを痛感しつつ読みました。
中上哲夫
文章の流れが美しくここちよく耳に入ってきました。お話を聴いていると百人一首の歌にもつながっていると思います。
長谷川好子
人間は何年何百年も男女の想いは変らず、女性に対する切ない感情にホロリとさせられる。大変おもしろく、読み継がれる理由の訳は、社会風情の違いに生活が変化、いくら文明が発達して電化されても人間の本質は、変らないという事だろうか。
恵
時代を超えた男と女のかけひきが描かれているように感じた。男女の営みは紫式部の時代も今も、まったく変らないのだろう、と
土屋
昭和59年11月横浜市大倉山記念館が開館して30年、昨年の秋から改修がはじまり平成25年1月に改装された記念館で再び源氏物語の学習が始まったことは、私にとって最高の喜びであります。
平成25年1月24日
イメージで読む『源氏物語』
講師 田中順子
帚木〈第二帖〉頁159
家の主人
左馬頭の談議が続いて、恋の相手や妻の選び方を話題にし、特に妻選びには慎重にしてまつりごとについてしっかりした考えを伝えた。王朝時代は、妻が家の主人であって妻選びに一家の主人が不十分であって困るので妻選びに苦労する。縁あっての夫婦の在り方平凡な妻のことを差馬頭は熱心に常識を話すが、聞いてくださっている源氏や頭中将にも目くばり気をつかっているようすがまたいい。週刊絵巻で楽しむ源氏物語も51帖まで読み52.53.54帖と2月3週で完了。
横浜に初雪(積雪13センチ)が降った翌日から冬晴れが続き夕映の富士山を眺めながら絵巻を楽しみました。
祥
2012年12月6日 「横浜源氏の会」 神奈川近代文学館にて
帚木 148頁から158頁
内容
左馬の頭(中央政府の長官。5位相当の中流貴族)が、頭の中将に代わって源氏の問いに対して、世間一般の常識を持ち込みながら答えていく。成り上がり者を、世間は厳しい目でみるものだという。蓄えた財力のお陰で今はたいした勢いだが、やはりもともと身分のある上達部(三位以上の大臣、納言、参議および四位の参議など)とは違うと噂をする
ものだという。人々の雰囲気が伝わってくる。
その逆に今は落ちぶれている者を評価する場合も同様である。名門の誇りというものを保っていきたいが《こと足らず》であることが《わろぶ》、つまり体裁を保っていけないので悪く見えるという。しかし、源氏は財力で上流階層の顔をしている者を話題にしたっかたのだが、うまく左馬の頭にかわされてしまう。成り上がり者と落ちぶれた者を中の品としてくくって結着をつける。受領のことも中の品に位置づける。今時の受領の中に悪くはない、かなりなものがいると話す。
っていので悪くみえるという。しかし、源氏は財力で上流階層の顔をしている者を話題にしたかったのだが、うまく左馬の頭にかわされてしまう。成り上がり者と落ちぶれた者を中の品としてくくって結着をつける。受領のことも中の品に位置づける。今時の受領の中に悪くはない、かなりのものがいると話す。
を中の品としてくくって結着をつける。受領のことも中の品に位置づける。今時の受領の中に悪くはない、かなりなものがいると話す。
成り上がり風情と思いたいが、実際には財力のお陰でいい女に仕上がっている現実を無視できない。そんな女が入内して女の幸せをつかんだ例も多いという。すると、源氏は《すべて、にぎはしきによるべきなり》と口をはさんで笑う。それに対して中将は、左馬の頭の話を中断させて笑う源氏を無礼と受け取る。故に左馬の頭は話題を変え、身分と財力の釣り合いがとれている女の話をする。上の品の女には、たとえば人もうらやむ恵まれた家で育ちながらにして、何故にこんな育ち方をしたのか気がしれないものもいるという。身分財力があっても面白みがないことがあると語る。しかしながら、世間から置き去りにされてしまったような家の門には、葎がからみつき、手入れのしていないそんな家の奥深くに閉じ込めれて、ひっそり暮らしている美しい女人がいると話す。家の住人は《ものむつかしげにふとりすぎ》ている年老いた父と荒んだ暗い表情の兄。思うに任せぬ世を呪いうつうつと暮らしている父や兄とはちがって、女は、気の滅入る家の奥に住んでいても、気位を高く保っているのである。そういう女人にはたまらなく心惹かれるものがあると左馬の頭はいう。源氏は、はるか遠くを見つめるような眼差しで、すっかりくつろいでいた。源氏のくつろいだ姿は、形というものを極限まで崩しながら危ういところで均衡を保っているという、心にくいまでの姿である。
感想
左馬頭が上、中、下と細やかに語る。経済力が物をいう今時受領(地方官)の女性は、中の品として悪くないと夢中に話すので源氏は困ったように苦笑する。
世間に知られていないつる草で門がおおわれている荒れた家訪問者もいないところに、案外可愛い女がいる新鮮なことである。左馬頭の経験など身分と経済力のかねあいなどリラックスして耳を傾けている源氏の姿を思い浮かべながら、思い上がる王朝のことばを習得した、男を超越した源氏。
次回、妻選びなど楽しみだ。
祥
左馬頭が複雑な気持ちでする女に対する評価に、源氏が笑ったことに中将がおこるところや、話題を変えて、左馬頭が語る葎のはびこる荒れた家に住む太った老人や荒んだ兄と住む美しい女の話が面白く感じる。
茶良
「雨夜の品定め」は貴族たちが女性の品定めをしているわけですけど、逆にいうと作者の紫式部が男の品定めをしていることになるのが面白いと思いました。
中上哲夫
左馬頭を中心に女性論が展開される。
彼が心ひかれる女性は、意外性のある、驚きをともなうものと言う、ありきたりでは満足しない。当時のすきどもたちの中身に少しふれたよう。
孝子
魅力ある女性と家柄の関与について、ここまでこだわる当時の社会と今の世の中、違いがあるような、ないような、文学のテーマは普通的だから結局いつの世も同じかも……
S
ことこまかに女性を評する熱心さに驚きました。千年以上時がたつと、こんなにも常識も言葉も変わるものかととにかく驚くばかりです。直衣だけの源氏の姿というのが格好のいいものなのか? なかなか想像がつきませんが……。
裕
平成24年11月1日
関内技能会館にて
帚木2
内容
思うように乗ってこない源氏の様子から、中将は自分とのずれを感じた。源氏は大事な手紙を見ようと思えばいつでも見られるのに・・・と中将は思うのだ。御厨子から引き出した
手紙の束は、二の町の心やすき女たちからの手紙なのだと中将は決め込む。
源氏は、複雑な自分の恋に踏みこまれたくない思いでいる。しかし、源氏は友に普段の顔を向けて、中将の女性論を引き出すべく誘い水をかける。中将の女性論は、以外にも女
性への幻滅のことばから始まった。中将が女性に求めていた物は「かど」の有無であった。教養として、その女性に身についている本物の「かど」である。対話の成り立つ相手とし
ての女性を常に求めているのである。中将の幻滅もその点に由来しているようだ。源氏は、中将に共感しつつ、さらに女性論をそそのかす。
三つの品があり、身分高く生まれ育った女性、中の品ー中流階層に育った女性、下層の身分に育った女性。などなど。そこへ、左馬頭と藤式部丞がやってくる。四人は階層の判
別について、議論を展開していく。
【感想】
源氏、中将の女性論のやりとり、また、中将の三階級の女性への持論、それに対する源氏の意地悪な問いかけが面白く感じとれ、この先が楽しみになってきました。
茶良
源氏と中将の会話の中にさまざまな人間像を鋭く見ている感覚がおもしろい。でも・・・源氏物語の勉強会で古典の言葉の難しさと、言葉を整理して覚えていきたいと思う。これから
展開が楽しみです。
恵
初めての参加でついていくので精一杯でしたが、次回からもっと予習をしてきたいと思います。現代語訳をしてもわからない部分を先生が埋めてくださったのでよくわかりました。源
氏物語のよさがよくわかるようになることを期待して続けたいとおもいます。
田中裕子
女性の品定めについての源氏と中将のやりとりが面白い。彼らは「すきもの」であるが、質の高い知識人でもある。そういう目で、知性と高い教養を備えた理想的な女性を求める男
たち。男は常に「理想の女性」を求めている。
(雄太)
紫式部はもしかしたら男だったのではないか・・・・・・・? S
『 源氏物語 』を読んでいて感じることの一つは、助動詞の複雑さ/厄介さだ。明治期以降、口語の時代に入って、助動詞がきわめて単純化されて、そのぶん、古文の助動詞に対
応できなくなったので。『 源氏物語 』を読むのをつづけるのなら、今後、古文の助動詞を学ばなければと思った所以。
中上哲夫
十一月一日は古典の日
二千八年 源氏物語千年紀に定められた。
本日 講義がはじまる前に先生がくわしくお話しして下さいました。
源氏と中将がとりかわす恋談義、中将は源氏の恋文に興味深く、けれど源氏は心の内を知られたくない。中将の口上手にのって、二人のとりかわす女性に対する人間像から、女性
談義になり若い体験など、「うわべばかりの情けに手はしり書」など、いろいろの女性がいて「見る」「歌の交換」へと展開されていく。妙に面白く思えた。女性側の男性談義はどうだっ
たのでしょうか。これは女性が書いた作品で男をやっつける、女性はわかっている。あっ、なるほどと思いました。
中将の三つの品に源氏の鋭い質問に中将は答えられなくそこへ左の馬の頭、藤式部の丞がやってくる
平成24年10月4日
関内ラジオ日本にて
帚木に入る
【感想】
帚木に入って本中の人物の心理状態が面白く、今まで印象をもっていた源氏のイメージが新しく変わりつつある物語に一層心が引かれそうです。また、今改めて古典文学の言葉のやわらかさと奥深さに魅力を感じます。これからの源氏の生き方が楽しみです。
恵
帚木に入り、文法の難しさが身に染みています。もっと古典の勉強をよくしておけばよかった。
S
本日はありがとうございました。久し振りに頭を使ってみました。楽しい時間をありがとうございました。(先生の御声は物語に引き込まれてしまいます。)
柳
朗読が日頃のゆるみっぱなしの気分を緊張させてくれる。 Y
突然のお電話で申し込みました。内容はとても奥が深く、高度お勉強かなーと実感です。皆様の熱心さに驚きました。 山
いよいよ、源氏の遍歴への始まり。その前に源氏の恋愛に対する性格が書かれており、これからの物語が楽しみです。 茶良
作者の語る十七才の源氏の性格は、「うちつけのすきずきしさなどはこのましからぬご本性にて」に対して、頭の中将について「すきまがしきあだ人なり」
と、対象的。これからの二人の人生にどのように展開していくのか。
源氏十七歳のころの「・・・語り伝へけぬ人のもの言ひさがなさよ」との作者の詠嘆的表現が印象的。源氏が実は浮きな性格ではなく、真面目で一図な男なのだという記述が面白い。
雄太
関係語をもう一度勉強しなければ、と痛感しました。 中上哲夫
社会的な身分、官位に対する言葉関係を表わす敬語、今日は尊敬語と謙譲語の学習をしました。お友達のような頭の中将との恋愛談議のはじまりで興味津津。源氏物語は美しい選ばれた言葉である。厨子の中にある恋の手紙など、頭の中将はさぐろうとする。お互いにそれぞれの恋人がこないかなーと。親友だからかたはらいたし、心くるしい源氏をみたい。
祥
文学は内なる心を開放するところに生まれると田中先生はおしゃった。源氏物語の世界は、身分社会である。尊敬語と謙譲語によって、主語がわかり人々はそうした日常のなかにいる。ところが、身分の上下を超え、自分の内なる声を和歌にたくすことができた。ただ、五七五という型を守ることで、自由に身分を超えて思いを語れるのである。源氏物語は主語をつかわなくっくてもわかる散文と直接登場人物の思いを伝える和歌によって、物語をたくみに創りあげている。千八年に若菜の巻を書きあげたという。正確にこの物語を読んでいくと、紫式部がいかに大きい存在か、スケールをはかることが不可能に近い人物であるという確実性を感じるのである。そのわけのひとつは、千八年に若菜の巻をかきあげた、そのころ「交野の少将」
などという物があったそうだ。そうした時代への挑戦であったそうだ。今日から見れば日本などではなく、世界への挑戦でもあった。
えむ
日時:平成24年9月6日
場所::関内技能文化会館
内容:桐壺最終章『さまよう魂』と関弘子さんの朗読を聞く
【感想】
さやうならむ人をこそ見め、・・・・・
思うやうならむ人をすゑて住まばや・・・・・
源氏の藤壺に対する気持ちが、単なる憧れから現実に恋する人へと確実にふくらんでいく様子が、こうした言葉によって表されていく。原文を丁寧に読むことで、源氏の思いに、きずくこ とができるのだと思います。 考
源氏の心の中を想うと、感情に正直で理解できるが、新婚の妻に愛情を持てないのは悲しい。この物語は、すぐれた文章ではあるが内容は楽しくない様に想う。 E
桐壺の最終 結婚した源氏が、藤壺に心惹かれ、琴と笛の音で思いを通わせる切なさが心にしみてきました。
いよいよ次は 「箒木 」、先が楽しみです。 茶良
初めての源氏物語、毎回、毎回学ぶことが多く、楽しく過ごしています。今後の展開やいかに? S
今日で 「桐壺 」を読み終えたが、この時点で思うことは、十一世紀にすでに日本でこのようにすばらしい文学作品が女性作家によって書かれたことの凄さを思い知らされた。
西洋において、これほどまでに男女の恋をきめ細かく繊細に描いた小説が現れたのは、十九世紀になってからだったはずである。
シェイクスピア、セルバンテスとならんで紫式部が世界の三大文豪のひとりとして評価されるようになったのは、当然と言えよう。 雄太
さまよう魂
政略結婚した光源氏は、藤壺との初恋が忘れられず、(葵の上)二人の間には溝ができ、内裏で聴く琴や笛の音、心の音を通じていっそう想いは深まり・・・・・・藤壺に対する気持ち
高ぶる気持ち。作者も恋にこがれて憧れがあるのでしょうか、それとも紫式部の経験からでしょうか。
葵との住居が整っても気持ちは、気持ちはただ藤壺のことばかりでこれからずーっと嘆き崖ぶちに立たされていく危ない終わり方の桐壺の巻きを終えました。
造りの、レるは文学的で活気があふれている先生のお話でした。
小学生の時から美しい古語を教えるべきだという声がみなさんからでました。
関弘子さんの朗読が謡ににていて・・・
祥
関弘子さんの朗読が、ひじょうに印象的でした。これが、日本語本来のリズムなのでしょうか。わたしには義太夫を連想しましたけれども。
ズボン堂
平安時代の読みを聞き、響きや景色や情景を描かせてくれるような気分になりました。これからの朗読も余裕をもち、ゆっくりと読みたいものと。
Y
桐壺の巻きは、光源氏の母君(桐壺の更衣)の死に至るまでの悲しい話が、九割方であったという印象である。父君(帝)の新しい妃になった義理の母(藤壺)に恋をしてしまう光源氏。
新妻(葵の上)のことは、まったく頭に無く、ただただ義理の母にあたる藤壺に、激しい恋慕の情をいだく光源氏。作者紫式部は、何ゆえに苦しいまでの恋の対象を母にあたる人に、して描かなければならなかったのか。悲劇である。また、世界には、このような神話が、あったような気がする。人間の深層にふれているのだろうか。紫式部よ・・・。
えむ
日時:平成24年8月9日 午前
場所:大倉山記念館
内容:P113『帝と大臣』・P115・P117『結婚』
【感想】
元服式の夜が源氏の結婚の日となる。
当時としてはあたり前のように行われたことかも知れないけど、添ぶしの姫君も、源氏も
しきたりの中に、自らを投じていく二人がせつない。
左大臣の姫ではなく右大臣家の姫君との婚姻であったなら、また展開は大きく違って来ただろうと、いろいろ想像すると…。 (孝)
左大臣が甘やかして育てた娘、光源氏との結婚を祝福する歌の交換をする親心がほヽえましく、帝と大臣の位は違っても歌の世界では平等にということでしょうか。
平安時代に心と心、男と女が対等だったというすばらしいものがあったということですね。
女御たちにより語り継がれ、千年過ぎた現在も語り継がれ、読者のひとりになれたことは誇りで、美しい古語を学べることはなんと幸せでしょう。 祥
当時の上流階級の婚姻についていろいろ知ることができ興味深かった。女性は大変!
S
源氏物語の当時の華やかで美しい物語の中にながれている、はかない恋の行く末が
とても気になり楽しみですが…。
源氏物語が今の時代にも読み続かれる大きな魅力を感じます。
折櫃が折詰につながっているのか、籠物が籠物として少し前まで結婚式に残っていたりと二時間は楽しくあっと思う間に過ぎました。当時の結婚相手に血縁の濃さは、判断基準はと…。
源氏の結婚の巻でした。左大臣の女君との初夜は、少し女君のことを考えました。
女君の(自分には、ふさわしい相手ではない)と感じた女君の今後の展開が楽しみです。
(N)
元服式や結婚の場面に優雅な気分に浸れましたが、源氏の心中はいかばかりかと思うと複雑でした。
いよいよ源氏の結婚生活が始まります。楽しみ!楽しみ!
最近、ホメロスの長編叙事詩「オデュッセイア」を読みましたが、戦争や略奪の連続で、辟易しました。『源氏物語』は殺人がなくていいねえ、といった鬼怒鳴門(どなるど・キーン)
の言葉を思い出しました。 N・T
いつの世でも、権力を持つ者たちは、結婚を政略に使ったが、平安時代の政権中枢における政略結婚の複雑な関係を、作者、紫式部は冷徹に見つめ、表現している。
(雄太)
日時:平成24年7月5日 午後
内容:P103『少年源氏の恋』・P106『妃と御子』
運命的な出合いをすることになった光の君と藤壺、幼い光の君(10才頃)、おさない
恋心これからの展開が楽しみ・・・
(孝)
少年源氏の恋、藤壺の若ううつくしさにひかれる。いつまでも親は子ども子どもと
思っているが、子どもは成長しているのに気付かない。光源氏が義理の母(藤壺)に
ときめき、亡き母を慕うように初恋をする。常に参らまほしく。藤壺も切に隠れ
たまへど。もう止められない。弘徽殿の嫉妬がある桐壷の巻は源氏物語のすべてを
語っているという先生のお話でした。
やまとことばはイメージできる。
元服式 親として最後にしてあげられることで、式のために帝の御心が微妙に細やか に表現されている。
きよら-帝のレベルで帝が尽くした。
元服式の当日 帝の心情や大蔵人の心情が描写されている 源氏は御衣に着がえて
庭に下りて 美しい源氏の姿に皆涙する おごそかに式は終わり帝もホッとされた
文章が素晴らしい。
におう-顔の美しさ、つやつやした顔、源氏が生まれた時 御子は色彩的な美しさ。
二時間たっぷりの講義は老年には少しきびしかったですが楽しいひとときでした。
祥
久し振りに源氏物語の世界に引き込まれて、とまどいながらも、なつかしく 学ぶことができました。 ○S
長い物語が大和言葉の意味の深さと美しさは、今の現代の社会では決して出会わないことに驚きと共に、華やかなストリーの人間模様の複雑さが、益々趣味をそそられる。
今後、源氏のきよら(・・・)な生き方が楽しみです。
○ゑ
源氏の元服式の様子、その元服式に思いやる帝の心情-父としての-が細やかに
伝わってきました。帝自ら<仰せ言>まで発して、春宮とたがわぬ元服式をと動き回る様子から源氏に対する愛情を感じとれました。 茶良
「にほひ」が色彩的な美しさという話は、今日の収穫でした。 ○Y
元服式を今日は読みました。とても、感動いたしました。とくに、「いときよらなる
御髪をそぐほど、心苦しげなるを、上は、御息所の見ましかばと、おぼしいづるに、堪えがたきを、心強く念じかへさせたまふ」父帝の息子への愛する心が伝わってきます。よい、時間を過ごしました。
N
源氏となり、父帝の美しい妻に恋心を抱き、元服式に臨む場面を生々しく思い浮かべ
ることができました。この時が初恋だそうで・・・。
出生の時を振り返ると、こんなに成長されたかと感無量です。帝ならずとも桐壷の
更衣の事が想いおこされます。 ○E
「にほひ」「きよら」など古語の意味がわかり、少しだけその時代に近づいた感じが
しました。言葉の発音も今よりは多かったと聞きますから、感覚ももっと豊だったのかと思います。 (K)
今回は、リズミカルな文章に魅惑されました。
『源氏物語』は当時女御たちの間で回覧雑誌のように回し読みされたようですが、たぶん、声に出して読まれたのだと思います。それで口調もいいのだ、と。
(ズボン堂)
源氏の藤壺への初恋が見事に描かれている。
現代のわれわれから見れば、十一、二歳の少年にしては、大人びすぎていて、現実ばなれしているようにも思われるが、当時は十二歳で元服して大人になったことを
考えれば、不思議なことではないのだろう。
木目細かく、多角的な視線で物語を綴った紫式部の作家としての才能の豊かさを想わずにはいられない。 (雄太)
【6月7日(P94『帝の決断』P97『藤壺入内』)の感想文】
亡き更衣に心ひかれつつも、年月が流れ、次の主要人物、藤壺を登場させる作者。
更衣が身分が低かったために、帝の愛を受け入れるにふさわしくないと判断した
ギャラリーに対し,先帝の四の宮、さらにこの世に例のないほどの容貌人(かたちびと)
ときている。周囲を納得させるにふさわしい作者のこころづかいに感服です。
(孝)
P94若君から光源氏へ
帝の苦悩がよく描かれて、若宮の才能を見つけて教育する、親として立派だと思います。藤壺の入内にあたっては、母后の思いは決して望んでいないうちに亡くなって
しまい、帝もようやく立ち直ることができた。
初夏の陽ざしがさしこむ室内でゆっくりと音読ができ、時々小鳥のさえづりなどが聞こえて、おだやかな午後のひとときでした。
祥
六回目の参加で物語はいよいよ藤壺の登場に入り、帝の我子に対する想いと、新し
い女性との新たな展開に楽しみが深まって来て、日本の古典のすばらしさに、目か
らウロコです。
(千恵)
若宮を源の姓を名乗らせるに至る帝の様子や四の宮に心が惹かれていく帝の様子がよく判り、これからの展開に期待が持たれます。
(茶良)
四の宮の獏とした印象が、今日のお話の中で姫君のしかも女帝、母后の亡くなった後の弱い立場が理解出来、親の年代の帝に入内することが宮に生きる道だったのだと・・・。 ?
時のうつろいは人の心もうつろわせるものであるのは古今東西共通のようで
帝もまたその波に乗りました。このうつろいがあることによって、ひとは悲しみから
逃れ、新たな道を踏み出せるのだと認識しました。
帝頑張れ!若宮頑張れ!藤壺に救っていただきましょう!
(e-co)
先生の朗読の声,奥行きが心に響きます。音読が大切というお話、興味深かった
です。そういえば、私の小学校の頃、先生についてよく声を出して読みました。
算数も、国語も空に指で字(書順)をかいたりさせられました。
黙ってパソコンの画面を見るだけでは、身をもって学ぶところまではいきませんね。 (K)
<代名詞について>
藤壺に登場の場面に(102頁)「かれ」という代名詞が出てきて、当時は男性名詞/
女性名詞の区別がなくて〈彼女〉という女性名詞は明治になって、西洋語の影響で生まれたことを思い出しました。古語の代名詞を調べてみると、面白い発見があるかもしれない、と。 (ズボン堂)
今日のはじまりは、若宮に源氏の姓を与えるところ。光源氏の誕生。
そして帝はあれほど桐壷の更衣を愛し、忘れがたかったのだが年月の経過とともに気持ち
が変化する。その様が、人間のありようが、見事に描き出されている。こうして藤壺が登
場する。これからの展開が楽しみ。
(雄太)
【5月17日の感想文】
内裏で生活する幼い源氏。父帝につれられ弘徽殿の女房他、他の妃のもとに訪れ、彼女たちの中で、えも言えぬ美しさとかわいさで受け入れられる。圧倒的な存在感をこういう形で紹介する語り部。特別な存在としての源氏をこれから成長するへんりんをここで語っているのか。 (孝ちゃん)
P84~P92
亡き母、亡き祖母、いとおしい若君の幼い心模様を、作者は語り、帝をはじめ周囲の人々が見守る情景が細やかに描かれた「あわれ」、特に弘徽殿も若君を心よく受け入れたことに救われて、ホット胸をなでおろしました。幼少年期に、才能がうちだされて、これからの光君が楽しみです。
祥
大変おもしろく授業が楽しみです。
帝の心の動きと我子を想う感情はとても切なくいつの時代にも共通するドラマがおもし
ろい。 (千恵)
帝の若君に対する心の揺るぎ、若宮の三歳から六歳、七歳へと成長していく様子がよく
判った。これからの楽しみが増してきた。 (茶良)
「右大弁の子のやうに・・・」相人に見せたのに朝廷より多くの物賜はす。ということをすれば帝がもらさなくても 春宮方は気が付き、疑心暗鬼になるのは仕方がない。
と思うが。
?
史実なのか、物語なのか、解らなくなってしまう、もうひとつの人間の世界を、この場所で、今日もわたしは貴重な時間を得た。
大倉山記念館を出ると、五月の青い空が、清々しかった。
(N)
『光源氏』の原点を今日知りました。
紫式部の頭の中にはこの物語の全容が始めから出来上がっていたのかと思うと、あらためてその偉大さに驚きます。 (E-CO)
光源氏の波乱の発端が見えてきて、これからの展開が楽しみです。
平安という世は、とても興味があります。
帚木ほうせいの国銅で、底辺の労働者からみた都。大仏を創る時の銅鉱山で
働く人の苦しさなど読んでいたので、表裏の世界をみるようです。 (K)
ここにきて(若宮が内裏にすむようになった場面 )、ストーリーがとみに動き出して、
物語に引き込まれていくのを感じました。話の筋もふくらみ見せてきた。 (N・T)
今回の「若宮内裏に住まう」や「若宮の微笑」には、光源氏という特異な男の人物が
形成されていく、幼時からの成育の過程が見事に描かれている。幼い頃から、内裏に住ま
う身分の高い女性たちの生活をま近に見て育った源氏。生まれながらに身についていた
高貴さ、雅びさに加え、育った環境の中で創られた人格(人間性)の描写が面白い。
(雄太)
【2012年4月5日の感想文】
更衣を偲んで嘆き悲しむ帝の様子が語られる段が続いています。
白楽天の長恨歌をひいて、楊貴妃と更衣を比較してその美しさを表現している箇所に
楊貴妃は「う(・)る(・)わ(・)し(・)」、更衣には「な(・)つ(・)か(・)し(・)う(・)、ろ(・)う(・)た(・)げ(・)」という言葉で表現している。
なつかしく、ろうたげ・・・もう少しこの表現をほりさげて、帝の心情を、かいま見たいと思う。 (孝ちゃん)
春の嵐が去って大倉山の桜もようやく咲きはじめ、おだやかな日に
源氏物語の学習ができました。
幸せな午前中でした、 祥
帝の個人的な悲しみと公人としての立場がバランスがとれない。
でもそれが物語かもしれない。 (M・O)
源氏物語の深みに入っていくストーリー性がたまらなくおもしろく感じています。
長恨歌が舞台に裏打ちされている作者の知識に驚くばかりで、人の心はいつの
時代にも同感されている人生観はすばらしい。
長恨歌をじっくり読んでみたいと思います。中国生まれの私ですので。 (千恵)
帝の沈み切った生活。弘徽殿の性格がよく読みとれました。帝のこれからの生活がどうなっていくのか、興味がわいてきました。 (茶良)
長恨歌との「かたみの釵」の所で出会え、この先、少しずつ物語の奥にある世界を知る
楽しみが出来た気がしました。
思うようにならない現実をかかえた弘徽殿の行動を、かわいそうと思ってしまうのはいけないのだろうか。恵まれた環境の中に置かれているとはいえ、虚しさが募る日々だったのではないだろうか。官中での帝と更衣との恋愛は、真実の愛は、だれもが求める関係であり、満たされるものだ。しかし、帝は一人しかいない。相互の愛の関係を求めようとしたら、想像を絶する醜い争いが、展開される。それ故、そっと見守るか、無視するか、どちらかでしかない。
弘徽殿は、無視しているかのようでいて、管弦の遊びを決行した。これは帝への伝言なのか、それとも突きあがってくる烈しい動情に従ったものなのか。そして、突きあがってくる烈しい動情といった激しい狂気とは、何か。弘徽殿という人間が、失ったもの、それとも、手にしたいこの世の呪縛からの、開放か。・・・弘徽殿の行為もよしとして読むことが、賢明のような気がする。 (N・S)
「長恨歌」の資料を引いての説明は、とても参考になりました。また、当時の美しさを表すことばとしての「うるはし」と「ろうたげ」の違いは勉強になりました。
(S・S)
「源氏物語」と「長恨歌」が同時代のものだという事にびっくりました。
千年も前に外国の作品をに手に入れられるとは・・・。紫式部にネット社会並みの情報網があったということはすごいなと思いました。又、それをすぐ作品に取り入れられる
能力にも改めて驚かされました。 ????????? ????????????????????????????(E-CO)
情に流れる男性と現実をみている女性の生き方がはっきりとあらわれていて、とてもおもしろく、にわかに自分の日常に近くなってきました。 (K・T)
源氏物語に飲食の記述が少ないことについて、先生は美意識に反するからだろうとおしゃっていましたけど、わたしもそう思います。
昨今では事情が多少変わってきましたけど、短歌(和歌)の世界でも飲食は美意識に反するとして敬遠された。雅ではないと。それに対して、俳諧は俗を旨として、飲食をことさら題材にしてとり上げたことは面白いことだった。 (NT)
「かたみの釵」の部分では、平安時代に日本が独自の文化を創りつつあり、中国に学びつ
つも批判的に見る目も養われつつあったことが伺われ、興味深い。
「弘徽殿の立場」では、正妻としてのくやしさや女性としてのプライドが現れていて面白い。
「遙かな現実」では,帝の更衣に対するあまりの打ちこみ様に仕える者たちもあきれ、
嘆く様子が興味深い。 (雄太)
【2012年3月15日の感想文】
*月は入りかたの空清う澄みわたれるに…
更衣の母君と、帝からつかわされた命婦とが、更衣をしのんで語りあい別れがたい心情の
末、時が長くたってしまった。
この言葉が読むひとにその雰囲気に誘い込むなにげない言葉だけれども心にしみるいい表現だと感心してます。 (たかちゃん)
*P66 虫の音
ゑ ず が わかってうれしいです。
P72 帝は母君に感謝している
私も100才で亡くなった姑(はは)に感謝しています。 (祥)
*母君と帝との悲しい想いと人を思う心のはかない美しさに、遠い時代の生き方に
想像することの楽しさで、これからの源氏物語が一層、教室の勉強が楽しみです。 (千恵)
+帝、母君、若宮、女房たちの様子がよくわかった。
早く宮中に戻りたい若宮と女房たち、そばに少しでも長く置いておきたい母君の気持ち
などから、当時の宮中と外の生活がうかがわれ興味が惹かれた。
(茶良)
*千年の前の物語を通して、母君の思いが現在のこの時間に、つかめるように伝わる。
ここに、更衣に母君がそばに座っているように感じます。
気品のある心とは、このような母君の思いのことをいうのでしょうか。
母君は美しい。桐壺の更衣と母君が重なって感じるのは私だけでしょうか?
(N・S)
*本日はありがとうございました。
丁寧なご説明なので、よく情景と雰囲気をつかむことができて勉強になりました。
特に、自然描写と登場人物の心理の寄りそいということばは、大変参考に」なりました。
(S・S)
*立場によって想いは様々でも、大切な人を失った時のどうしようもない心のうちを想像させる場面だと思いました。遠い昔の…高貴な身分の方々のことなのにどうして共感できるのかしらと不思議な気持ちです。 (E-CO)
*紫式部何を思って源氏物語を描いたのだろうと思いました。
帝の心はこのように素直に表現されたものか、それとも、そうあってほしいという思いか、
などと思ってしまいました。 (K・T)
*昔「日本語に主語はいらない」という本を読んだことがありますが、対過表現に
日本語の本質を見る思いがします。
それが「源氏物語」を読むことによって痛感できます。
貴重な経験です。 (T)
*公人である帝としての節度を失ってしまうほどの、帝の更衣に対する深く、
まことに人間的な愛情がとても的確に書かれていると感じた。
恋する男の心情は今も昔も、社会的地位にかかわらず、変わりがないことを
改めて感じた。
また、母君についての描写も深く、的確である。
日本語の持つ、他の言語にはないと思われる繊細さをも認識した。
他の言語も別の面での繊細はあるが…。 (雄太)
源氏の会に参加し古典に興味を持つ私は千年前の夢の境地に重ねて楽しみ乍ら、
私の耳に折り込んで居ります。理解力がどれ程出来ることかちっと心配致して
ます。
この節、眼も弱くなりました。
御迷惑おかけすることもございませうが、私自身は頑張ります。 (S・W)
【2012年2月2日の感想文】
*子を思う母君の心情がかたられている場面…
「心の闇」という表現に、心をとめました。
心まどう、心いためる…それ以上の出口のない どうしょうもない
これを闇という、
私にとっては考えさせられる言葉です。 (たかちゃん)
*今日はじめて声に出して読みました。30回くり返し練習しました。
先生の講義で語言など、帝の歌など繊細な情景に胸を熱くしました。
そこをもう一度読んでみたく思いました。 (祥)
*「源氏物語」講和に参加して、現代社会と違う雅美な世界と言葉に
心がとろけそう。
2回目です。大変に魅力を感じています。 (千恵)
*宮仕へにあがった娘に対する母親の気持ちが
ひしひしと伝わってきました。 (茶良)
*今回はひきつづき更衣の母君と帝の使い靫負の命婦との場面である。
命婦の繊細な心の動き(母君を思いやる気持ちなどなど)をつづる古文の美しさと、
更衣(娘)を亡くした母君の苦悩を語る古語の、みごとな日本語に出会い、2時間
余りの源氏物語の世界にタイムスリップしたような具合だった。 (N)
*日本語は変化の少ない言語だと、専門家(言語学者)はいうけれど、
源氏物語を読むと、それをにわかに信じられない。
一語一語、辞書(古語)をひかなければならないので。
日本語の特徴なのでしょうが、一語につまずくと、先に進めないことが
しばしばあるので。
たとえば、英語だと、わからない言葉が出てきても、前後の文脈から
推測できることが多いのだけど。
源氏物語をよんでいると、日本語の本質にふれるような実感があって、面白い。
(T)
*今日の講義で最も心にひびいたのは、母親の子を思う心でした。
「ひとの親の心は闇にあらねども」の作者は男(藤原兼輔)で、男親ももちろん
子を思う心は持っていますが、母の愛(子に対する)に比べると、やはり母の愛が
大きく深いと思います。
「親の有難さは、親に死なれた後にならないと分からない」ということもあると思います。
(雄太)
*源氏物語の帯を装ってお茶を入れて下さる方
美しく朗読して下さり、うれしい2時間を楽しみにして来月も出席したいです。 (Y)
*「心の闇」がこの時代から使われていたことばだったとは驚きました。
闇の深さは今とは段ちがいだったのでは?と思いました。
(ペンネーム これから考えます。)
*一つ一つの言葉にこめられた意味の深さに感動します。
母の心 今にも通じるようです。
みなさん 心あたりがあるような表情でした。私も同じです。
しかし、時代の違いで微妙な違いもあることでしょう。
勉強しながら少しずつ分かってくると良いと思います。 (今日も花は「萩」でした)
【2011年12月1日の感想文】
言葉の一つ一つが深い意味を持っていること、
読みあげの中、その後の説明で、感じることが出来、感謝です。
①まいる、
まかずの違い
②泣きこがれる→焦がれるまでに…
深いです。
等々です。 (青景)
はじめて参加しました。先生のゆったりとしたお話に感動いたしました。
女性の先生でお話がきけましたこと、うれしゅうございました。 (内田)
物語に関係する様々な皆さんの話がおもしろく、源氏物語が今と通じる人間の
様々なありようを考えさせてくれます。 (小倉)
早く光源氏の生態が知りたいですね。 (川端)
「いずれの御時にか…」を高校生の頃覚えているのみで、時折あちこちの講座で
一節位の話をきいて今日に至っています。
始めて参加して、50年前の気持ちがよみ返ったような2時間でした。
皆様についていけるかは分かりませんが、参加してみたいと思います。 (米納)
《「亡きあとまで、人の胸明くまじかりける人の御おぼえかな」とぞ、
弘徽殿などにはなほ許しなうのたまいける。》
の文面に対して、先生から「弘徽殿の立場になって、あなたならどのように
いいますか?」と問われましたので、次のようにお答えします。
「帝の位などお捨てになってみてはいかがですか。
ああ…それでも、人間でいるかぎり、難しいですわね。
そうだわ。一掃、人間をやめて、トンボになったら、いかがでしょうか。」
といいます。
わたしは弘徽殿の女御のような立場の方々に同情的です。
恋をして帝と結婚したわけでないことは、講義ですでに周知の事実です。
ただ女性は子供を産む体です。
子を産めば、子の父親を大切にし、愛していきます。
それは女性の宿命のように思えます。帝もしかりです。
帝としての宿命を果たしていかなければなりません。
こうした、バックグラウンドを背負って女性は宮中に入り、帝はバックグラウンドのある
強い後ろだてを持つ女性を尊重していく。
これも古代後期の平安京の政治の絡んだ結婚である。時代の流れです。
純粋に恋をし、愛に苦悩していく男女の美しい姿には、心をうたれます。
本来の人間の自由な在り方かもしれません。
紫式部は「源氏物語」でこのような「愛」を、または「愛」の姿を物語り
したかったのかも知れません。多くの女性の悲しみ、を知っているからこそ…。
弘徽殿の女御は、その登場人物の一人として描かれていると思います。
先の感想文の言葉には、そうしたものが、含まれています。
ひとこと、帝も時代の下での人間であることを、言っておきます。
弘徽殿と帝が相互の関係でないことが、弘徽殿には悲しいわけですね。
おわり。 (佐野)
今年最後の源氏物語は桐壺亡きあとの場面でした。
古歌の引用が心に残りました。 (清水)
物語もだんだん佳境に入ってきて、ついつい物語にひきこまれてしまいました。
少し文体にもなれてきまして。 (中上)
第2回目の出席でしたが、ますます面白く、楽しい時間を過ごさせていただきました。
回を重ねるごとに深く知ることができるような予感がいたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。 (細野)
2011年11月17日 第1回「桐壺」
感想文
**************
口語に少し慣れてきて
美しさが解り始めました。
源氏物語の世界に少しずつ
入っていけて嬉しいです。(清水)
桐壺の更衣の別れの情景が
なんともよく表されています。
とても判りやすく、これから先が楽しみです。
桐壺の死後の源氏がどうなるのか興味が
強くなりました(川端進)
日本語の豊かさの一端に触れることが
できて、よかったです。もっと源氏物語を
読みたいと。(中上哲夫)
本日始めて参加させていただきました。
まだ始まったばかりとのこと。これなら
なんとか追いついていけそうです。
あまり難しくは考えず楽しみながら
続けていきたいと願っています。
(小倉みち子)
初めて参加させていただきましたが、古文の
すばらしさに感動しましら。先生の適切かつ
ご丁寧な解説で、源氏物語の真価の一端に
触れることができた気持ちです。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。(細野豊)