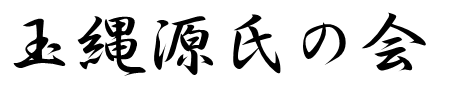
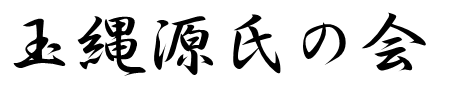

鎌倉にあります玉縄源氏の会です。
マンションの集会室で2か月に一度集まっております。
1000年前の原文の美しさに感動し 四名のスタートでしたが
二回目にして七名に増えました。
2016年3月から始めた新しいクラスです。
そして5回目にして八名になりました
玉縄源氏の会メンバー紹介
☆さくらちゃん
「よもぎ蒸し」と「経血コントロール」の仕事をしています
和装が日常だった頃の女性の立ち居振る舞いを思うと、
現代女性よりも身体機能が優れていた部分があると思います。
生活の中で美しい所作を心がけて、自然に沿った生活をすることが大事だと考えています。
源氏物語の時代は、現代のような病気は無かったかもしれません。
☆moonba
化粧品を通して、人がより素敵になるお手伝いをしています。
美しい地球を未の子供たちのために残したいと願って、仕事をしています。
☆KUNKO
仕事はマンション管理人です
好きなことは…手作業。最近はオルゴナイト制作
苦手なのは…人の顔と名前を覚えること
☆小夜の中山
仕事は団体スタッフです
好きなことは…散歩・乗り物に乗る・旅行
苦手なのは…混雑した場所に居ることなど
☆とんぼ
無芸大食です
嫌いなことは…楽しめない空間に居ること(喫煙車、蒸し暑い所、高い所など)
☆源氏のこころ
仕事は針灸マッサージをしています
好きなことは…美味しいものを楽しく食べること
不得手なのは…スポーツをすること(観るのは好き)
☆ 葉
教育の仕事に40年近く関わってきました。
現在は定年退職し、教師を目指す方々の指導に当たっています。
教員時代は科学教育に関心があり
「常識から科学へシリーズ」で『コックリさんを楽しむ本』や
自然界の発明発見物語「日本人の発見した植物ホルモン」などの執筆があります。
外国の方に日本文化のことを尋ねられ、知らないことを再認識。
この歳になってやっと日本の文化を学びたいと思い始めました。
「玉縄源氏の会感想文」
2025-5-20?
「末摘花」P52手引き~P58君がしじま
☆竹とんぼ
末摘花の巻を、すでに数回分は読み進んでいるのに、この姫君の人物像が一向に腑に落ち
てこない。
極端な引っ込み思案で、歌を詠むのも字を書くのも稚拙、容姿も見劣りがするという貴族出身の女性が、この時代生きていくのは難しそうだ。
長所は、おっとりとした人柄のよさか?
この巻の最終章には、作者の意図が見えるようになっていたい。
☆KUNKO
源氏が来るというのに、〈夕まどひ〉している乳母だつ老人
浮き足立って〈心けさう〉若き人たち
一人気を揉む、命婦…
さっぱり心情が測れない姫君。
そして、期待に胸膨らむ源氏…。
乳母たち、若き人たちにも喝を入れたい。姫君のことを一番に考えてあげて欲しいです。
この邸の人たちは、呑気過ぎだと思います。でも、読み手としてはユーモラスで、ロマンチ
ックで且つ、緊張感も伝わってくる面白い場面だと思います。
こんなに予測のつかない物語ってないのではないでしょうか。大抵は、こんな風になるん
でしょうと展開が見えてくるものですが、全く判らない。
〈やをら押しあけて入りたまひにけり〉とうとう、実力行使の源氏!
どのように展開していくのでしょうか。
☆葉
とうとう源氏の君が女君と襖障子を隔てて会う場面である。姫を取り巻く人物の描写から、
日々の人間関係が浮かび上がる。
≪乳母だつ老人≫は≪夕まどひ≫とある。こんな肝心なときでも年老いた乳母は、眠たが
って宵寝をしているのである。さすがに≪若き人二三人≫は一目でも見たいと思い≪心げさう≫しているとある。「心化粧」とは初めて耳にするが、なんと素敵な言葉だろう。こんな言葉があったのかと驚く。
そして何よりもおかしいのが、いつまでも押し黙っている女君に耐え切れなくなり、成り代わって歌を返してしまう侍従だ。一度返したものの、その後を続けるわけにはいかないところが辛い。
一度口を聞いたのに、その後いくら語りかけても返事のない姫君にとうとう源氏は耐えられなくなり、襖を押し開けていきなり中へ入ってしまう。襖には確か錠がかかっていたのでは?命婦は、「強引に近づくことなど、けっしてないから」と語っていただけにこの展開にはびっくりだ。さて、どうなることやら。
☆源氏のこころ
何を言われてもしじまの姫君に成り代わって歌を返してしまう侍従にも驚いたが、源氏
が一時の感情に駆られ我慢の限界を超えて強引で無謀な挙動に出てしまう展開には唖然と
した。
しかしこうでもしなければ過剰奥手の姫君を現実の人生に引き戻すことは出来ないだろ
う。一体姫君のしじまの背景には何が隠されているのだろう?
さて、吉と出るか凶と出るか?
2025-4-15?
「末摘花」P43ものづつみ~P51手引き
☆竹とんぼ
平安の時代、特別な後ろ盾のない女性は、自分で生きる術を考えなくては生きることもま
まならないということを、ここで学んだ。
末摘花は貴族の姫だが、親は亡くなり、通ってくる男性もいない。先行きは暗い。
男性が女性の元に通う女系社会のシステムは、女性にとって縛り付けられる苦痛が少ないと、肯定的な感想を持っていたが、女性が生き延びるのが大変な社会でもあったのだ。
一方で、源氏の乳母子・命婦のように生活力と開拓精神のある女性は、自らの才覚で道を
切り開いて行くこともできる社会だったのかと思う。
☆KUNKO
源氏を手引きした命婦の気持ちは、いかばかりだったでしょうか。姫君もお年頃。真剣
に結婚を考えていただかなくては、この先の生活すら危ぶまれるのです。
多くの女が、一目会いたいと憧れる源氏が手紙を寄越してしかも、わざわざこうして来て
くれているのですから、姫君よ、このチャンスをモノにしないでどうするのですか。
そして、源氏よ、どうぞ姫君を気に入ってくれて結婚してくださいますように…とこんな
気持ちでしょうか。
きっと、命婦とは正反対の性格の姫君。
何卒、この先うまく行きますように!と願うばかりです。
☆葉
紫式部は、千年前の様々な姫君たちの暮らしぶりをよくぞ丁寧に描き出してくれたもの
だと思う。もちろん身分の高い人たちの暮らしなのだが。源氏物語(京内)地図などを見て
いると、末摘花邸とある。父常陸宮の死後、末摘花が受け継いだ邸と解説がある。丸太町通
りに面した京都御苑の南東の角、今はテニスコートになっているあたりだ。源氏物語は千年
のときを超え平安の世を覗き見るドキュメントとしての面白さがある。
さて、今回の姫は、父親王を失い後見人がいない。なおかつ極めて引っ込み思案。これま
で描かれてきた姫君とは全く異なる。そんな彼女を取り巻く、命婦、乳母、女房たちの姿が
実にリアルに描かれている。
十六夜の月に照らされ、不気味さが漂う垣根。その奥から聞こえる琴のかすかな音に迎え
られた源氏だが、命婦の手引きでなんとか襖越しに姫と会う運びとなった。
「答へきこえで、ただ聞けとあらば、格子など鎖はありなむ」という姫君との出会いはいか
ように展開するのであろうか。
☆源氏のこころ
大輔の命婦の活躍が語られる場面、四方八方に配慮し考えをめぐらして源氏にも姫君に
も良いように企て行動を起こしていく、賢くも大胆に行動できる苦労人の印象である。
しかし、こんなにまでして導かれ手引きしてもらっても引っ込みたいばかりでどうした
らいいのかわからない姫君の深窓度は深すぎて理解不能、著者の冗談、遊び心ではないか
と思ってしまった
2025-1-15? 「末摘花」P10大輔の命婦~P22常陸の宮の姫君
☆竹とんぼ
大輔の命婦という女性が登場する。源氏の乳母子で、惟光同様、源氏とは幼なじみ。
この命婦の両親は離婚していて、それぞれ別の人と再婚している。
主語がない古文の状況説明だと、これらの人と人の関係性が何だかとても分かりにくい。
当時の人は、この文をくっきり分かって読んでいたのか? 理論先行の現代人とは異なる
理解の仕方で読んでいたのか?と想像します。
☆KUNKO
左衛門の乳人の娘、大輔の命婦という女性が新たに登場してきました。この女性は〈いといたう色好める〉人で、しかも〈かどある者にて〉と気転も利く女房なのです。
これだけでも、何とも言えない魅力的なキャラクターなのだけれども、源氏とも、上下関係を越えて、やりとりする様子は源氏のまた別の側面がみれて面白いと思いました。
源氏の中で常陸の宮の姫君の印象が、美しい人とへと勝手に盛り上がっているようですが、どうなるのでしょう。
☆源氏のこころ
またまた魅力的な女性が登場した、源氏のもう一人の乳母子「大輔の命婦」。
乳母子といえども源氏がこのように心を開いて軽口をきける同世代の女性がおり、惟光とはまた違った心温まる乳母子関係があったことにホッとした。
なかなか賢くやり手の命婦と相変わらず自己中の源氏とのやりとりがテンポよく語られて楽しく読めた。
2024-12-18? 「若紫」P160二つの邸~「末摘花」P10夕顔の面影
☆竹とんぼ
若紫は源氏の屋敷に来てから程なく、源氏にも屋敷にもすっかり馴染んだ様子。
若紫は、無邪気なだけではない、美しい物を愛でる感性もある。
夕顔は率直なところが魅力だったが、若紫は幼さ故の率直さがある。
様々な異なるタイプの女性を描き分けて、それぞれが魅力的なところが、筆者の並々なら
ぬ力量。
☆KUNKO
少女との暮らしは、心穏やかで、少女の存在は『いとさまかはりたるかしづきくさ』になっているようです。
まだ幼さが残る少女と源氏の関係は、男と女ではなく、かと言って親と子でも無い。何とも不思議な関係ですが、この先の展開はいかに?と思っていたら、物語は少女と出会う前に戻ってしまいました。
亡くなった夕顔とのことはもう話しが膨らむとは思えず、空蝉や軒端の荻が、再び登場したりするのでしょうか。
全く予測のつかない事になり、驚きました。
☆葉
『末摘花』の巻に入った。「末摘花」とはどんな花か調べてみたところ、染料や油の原料として栽培されているベニバナの事だとわかった。和名の由来は、茎の末に咲く花を摘み取って染色に使う事から付けられたとのこと。この巻の女主人公につけられた名前のようだ。
さて、この巻の冒頭では、「夕顔が忘れられない。夕顔のような女にもう一度出会ってみたい」と切に願う源氏の気持ちが語られる。そしてそのためにどんな機会も逃すまいと耳をそばだてているようだ。が、果たしてそんな女がいるのであろうか。式部は実に巧みに様々な境遇にある平安の世の姫たちを描き出す。源氏がこの巻でどのような女性に出会うのか楽しみである。
☆源氏のこころ
父宮の訪問をうまくかわした女房たちも若君と少納言に合流し、不安な日々から新た
な明るく心配のない生活へと切り替わることができてほっとした。
若君のみならず周辺の人々の源氏に対する信頼は何倍も増すことになり、雄々しい印象の源氏と周辺皆のほんわか気分で若紫が幕となった。
その幸せな場面から一転、末摘花の読み始めは面食らってしまった、何の説明もなく時間の後退が起こり、源氏の心中描写へと移った。
すれ違った程度であっても触れ合った女の魅力を忘れることなく自身への注目を継 続させようとマメに動く源氏に感心した。
光り輝く身体にこのマメさが加わって「源氏の君」が完成したのだと合点した。
2024-3-20? 若紫P89密会~P98懐妊
☆竹とんぼ
若紫の巻に、突然のように藤壺と源氏の密会の場面が立ち現れる。
そして藤壺が懐妊。
このような一大事も、古語の表現では何だかテキパキして、少しも湿った感じがしないと感じた。
☆KUNKO
逢瀬は、束の間でしたがその結果、源氏の子を宿す藤壺。
王命婦は、子を成すほどの<御宿世>と感じているようですが、不義の子であるのですし、
喜ぶ帝の気持ちを思うと藤壺の、苦悩は永遠に続くのでは無いのかしら?
と心配になります。
今後、源氏はこの事実を知ることになるのでしょうか。
だとしたら、源氏の苦悩もまた生涯にわたって続くのでしょう。
華やかな物語と思っていましたが、複雑な人間ドラマがどのように展開していくのか気
になって仕方ありません。
それにしても、里帰り中の、懐妊を『もののけ』のせいにしてしまうところは、良い時代
だなぁと思いました。
☆源氏のこころ
藤壺似の少女を結婚前提になんとか手許に呼び寄せたいと画策する一方で藤壺の宿下が
りを知ると逢いたくてたまらず無鉄砲な言動に走ってしまう源氏、歯止めは効かない。
藤壺も同様に倫理観で自分を律することができない。
これが宿世というものか、命婦が「逃れ難い御宿世」と言うように強い絆で結ばれている
のにたった2回の逢瀬しか許されない二人。むごいことだと思った。
辞書によれば「宿世」とは前世からの因縁のことだそうだ、一体二人の前世やいかに?
懐妊の告知遅れを物の怪のせいにしたり、納得できない運命や幸福を前世の因縁に結び付
けていくのは「持って行き場のない問題やわからにことはわからないままに」心のバランス
をとるための古代人の知恵のように感じる。
今もそのように信じられればPTSD等も少しは軽減できるのだろうか。
2024-11-20? P150二条の院へ~P160手習い
☆竹とんぼ
若紫は、源氏にさらわれるようにして二条院に連れてこられる。
供に付いてきたのは少納言ただ一人。 その夜は泣き寝入りした若紫だった。
翌日、二条院の庭や調度の美しさ、人々が出入りする様に姫君の心は惹かれてくる。
この姫君が子供っぽいための気分変化、とも云えるけれど、私はむしろ、心柔らかく頑な
さが無い姫君の資質が表現されていると感じる。
読者の私も、光源氏と同様に若紫に惹きつけられてしまう。
これまで出てきた女君が、それぞれに違う魅力を持っていて、読者は毎巻で感情移入をさ
せられる。
異なるタイプの女性を生き生きと書き分ける紫式部がすごい。
☆KUNKO
有無も言わさぬような形で二条へと連れて来られた若君と小納言。二人とも、不安な夜を過ごしますが、一夜明けて見た御殿の美しさに、別世界に来たように感じたと思ったでしょう。
小納言は、源氏の心づくしのもてなしに、若君の行く末を託しても良いと思い始めたのでは無いのでしょうか。若君も、美しい御殿に遊び相手の四人の童女と、傍らに居てくれる
源氏の存在。今までの生活では経験出来ない事を体験して少女は、ぐんぐんと吸収していくのでしょう。少女の成長が楽しみです。
また、少女の存在が葵の上に知れた後のこともどうなっていくのか、興味深いです。
☆葉
源氏が手習いの一つとして少女におくった歌とその返歌がとても印象に残った。今一つ分からないところがあったので、調べてみた。
少女に向けた歌は
【ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の 露分けわぶる草のゆかりを】というものだ。
「ねは見ねど」の「ね」は「根」と「寝」の掛詞になっていることも興味深い。武蔵野といえば当時紫草の生える地として知られており、その根を使って高貴な色とされている紫を染めていたとのこと。この歌の中で草といえば、紫草。そしてそこから紫色の花を咲かせる藤=藤壺へとつながる。藤壺のゆかりである少女ということになるのだろう。
そしてこの歌に対して少女の返した歌は
【かこつべきゆゑを知らねばおぼつかな いかなる草のゆかりなるらむ】
嘆いておいでですが、なにも分からないので不安になります。私は一体誰の、どういう草
のゆかりなのですか?というものだ。
歌を詠むなど不慣れなはずだが、自分に向けられた気持ちを真正面から受け止め、しかも自分の疑問を言葉にして返したところに「雀の子を犬君が逃がしてしまった」と走り出てきた少女の姿が重なった。
☆源氏のこころ
暗闇にまぎれての略奪決行という恐ろしさの中でこの先どうなるのだろうという不安と高い緊張にかられていた若君と少納言、一夜明けて場面は一転する。暗から明へ、不安から希望・期待へ、明るい賑やかな活気ある場面へと変わったとき、かれらの心持も変わったことがわかる。
著者は文字による細かい説明に変えて鮮やかな場面展開を設定することによって「若君の心が吹っ切れたことや少納言の覚悟が定まったこと」を読者に知らせる。
この明暗描出の見事さに驚く。またしてもすごい技だなあ、かっこいいなあと感心する。
2024-10-16? 若紫P136乳母の立場~P149決行
☆竹とんぼ
若紫を、源氏が「拉致」といってもよい強引さで二条院に連れてきてしまう。
若紫の父宮が迎えに来るより先に、という非常事態ではありながら、読者としては仰天する。
作者の紫式部は、物語の先々まで緻密に、矛盾がないよう構成しているはずなので、この事件も読み手が納得する形に収束するのだと予測する。
思慮深さがある源氏の人物像だが、状況によっては今回のような事件も起こしてしまう。
特に若いうちはそうなるなぁー、と結局は読み手を納得させる作者の筆力に、今回も感服した。
☆KUNKO
とうとう父宮が、少女を迎えに来るという事になりました。
引っ越しの準備で慌ただしい最中に惟光は、訪れて事の次第を知り、とって帰って
源氏に報告するのです。
それからの源氏の行動の速さには驚きました。女君の元に居たのに、少女を迎えに行く
と決断するやいなや、惟光を従えて少女の屋敷に入り込み寝ている少女を起こして、攫
うのです!
源氏にしたら、お迎えに来たでしょうけれど少女側にしたら攫われたと思うのでは無いのでしょうか。この時代においては、ままあることなのでしょうか。世界的には、略奪婚、誘拐婚が罷り通っていたようですが。
いずれにしても、少女の心情が判らぬまま。源氏の想いのみで物語は進んでいってる気
がします。少女の心のうちが語られることはあるのでしょうか?少女の気持ちが蔑ろにさ
れている気がしました。
物語としては、波乱の展開で先が気になって仕方ないのですが。
☆葉
源氏は少女の邸を出て、女の家に立ち寄るが会ってもらえず、その後妻の待つ大殿の邸を
訪ねるが、妻から温かく迎えられることはない。やり場のない気持ちでいるところへ、惟光
からの報告で、父宮が明日少女を迎えに来ることを知る。源氏は父宮より先に自分が少女を
連れ出すしかないと決断し行動に移すのだが。
改めて思うが、源氏はいつも自分の心の赴くままに動いていく。よりおもしろいことを見
つけて自分の心をそちらに移していく。女に振られ、妻に冷たくあしらわれたからといって、
そこでの感情にはまり込まず、新たな情動に突き動かされていく。「この機会を逃したら、少
女とは二度と会えないかもしれない」と次なる行動に駆り立てられるのである。
読者の一人としては、まま母のところより、いいかもしれないなあなどと思ってみたりす
るが、源氏は少女の幸せなど考えに入れていない。ただ「二度と会えなくなるのは辛い」と
いう情念である。私にとって源氏という人物はある意味つかみどころがないが、源氏の相手
として描かれる女性たちにはリアルな存在を感じる。
☆源氏のこころ
スピード感溢れる文章には古代のゆったりした雅な雰囲気は全くない、現代の危機迫るサスペンスを読んでいるのと同じ感覚である。命がけの所業を成そうとするときには我々現代人も当時の人々も変わりがないのだと知る。だから時代を超えて面白さも伝わり楽しめる源氏物語の凄さ。
むしろ古代はのんびりしているなどという認識でこの箇所を読むとおいて行かれそうな勢いである。
しかし源氏の行動は非道であまりにも自分勝手、現代の感覚では許容できない。「女子供に人権は無いのか?」と叫びたくなる。もっともこの時代、誰にも人権など無かったのかもしれないが。
若君はペット同様に扱われている。このときのトラウマは後年大切にもてなされることで幸せ感に変わっていくのだろうか。
2024-3-20? 若紫P89密会~P98懐妊
☆竹とんぼ
若紫の巻に、突然のように藤壺と源氏の密会の場面が立ち現れる。
そして藤壺が懐妊。
このような一大事も、古語の表現では何だかテキパキして、少しも湿った感じがしないと感じた。
☆KUNKO
逢瀬は、束の間でしたがその結果、源氏の子を宿す藤壺。
王命婦は、子を成すほどの<御宿世>と感じているようですが、不義の子であるのですし、
喜ぶ帝の気持ちを思うと藤壺の、苦悩は永遠に続くのでは無いのかしら?
と心配になります。
今後、源氏はこの事実を知ることになるのでしょうか。
だとしたら、源氏の苦悩もまた生涯にわたって続くのでしょう。
華やかな物語と思っていましたが、複雑な人間ドラマがどのように展開していくのか気
になって仕方ありません。
それにしても、里帰り中の、懐妊を『もののけ』のせいにしてしまうところは、良い時代
だなぁと思いました。
☆源氏のこころ
藤壺似の少女を結婚前提になんとか手許に呼び寄せたいと画策する一方で藤壺の宿下が
りを知ると逢いたくてたまらず無鉄砲な言動に走ってしまう源氏、歯止めは効かない。
藤壺も同様に倫理観で自分を律することができない。
これが宿世というものか、命婦が「逃れ難い御宿世」と言うように強い絆で結ばれている
のにたった2回の逢瀬しか許されない二人。むごいことだと思った。
辞書によれば「宿世」とは前世からの因縁のことだそうだ、一体二人の前世やいかに?
懐妊の告知遅れを物の怪のせいにしたり、納得できない運命や幸福を前世の因縁に結び付
けていくのは「持って行き場のない問題やわからにことはわからないままに」心のバランス
をとるための古代人の知恵のように感じる。
今もそのように信じられればPTSD等も少しは軽減できるのだろうか。
2023-12-20? 若紫P45意中を切り出す~P54心中を訴える
☆竹とんぼ
源氏は、僧都に申し出をきっぱりと断られて恥ずかしい心持ちになっている。
源氏が眠れぬままに一人鬱々と過ごしている僧都屋敷の寝所。外の情景描写が心に沁みる。
雨・風・かすかに聞こええる読経の声などなど。
簡潔な表現でその場の空気感を余さず伝え、読者を源氏の時代に引き込む古語の力と、式部の文章力に感嘆した。
☆KUNKO
源氏が初めて自身の言葉で伝えた母を失って生きて来た喪失感。同じような思いを少女に
はさせたくないから自分の側に置いて守っていきたいのだという思い。
世間の常識からは想像できない申し出に納得することは出来なかった尼君ですが今後、心
が動かされることが起こるのでしょうか。
源氏が自分自身の言葉で語った場面は、源氏の素直な気持ちが現れていて読んでいて切な
くなりました。
☆葉
一瞬の出会いから運命的なものを感じた源氏は、すぐにでも少女を引き取りたいという気
持ちが抑えられず、ゆくゆくは妻にしたいと僧都に意中を切り出す。「自分は妻とはそりが
合わず、あまり妻のもとへは行っていない」などと今風に私的な事情まで打ち明けだしたの
には驚いた。読者の私としてもあまりにも唐突な話だと思ったが、僧都からもきっぱりと断
られる。
僧都が勤行の為に去った後も、自分の真剣な気持ちを分かってほしいと、尼君に直接の対
面を申し出る。非常識なことだと自覚しながら、心の声に正直であり一途に行動に出るとこ
ろが源氏らしさなのだろう。尼君に源氏の真意は伝わったが、孫娘はまだ一人前に育ってい
ない。とても無理な話だと言われる。さて、この続きがますます気になる。
今回、歌を通して気持ちを遣り取りしていくところがとてもおもしろかった。
生ひ立たむありかも知らぬ若草を おくらす露ぞ消えむそらなき (尼君)
初草の若葉のうへを見つるより 旅寝の袖も露ぞかわかぬ (源氏)
枕ゆふ今宵ばかりの露けさを 深山の苔にくらべざらなむ (尼君)
☆源氏のこころ
また作者好みの素敵な女性が登場した、尼君。楚々として凛として自身が置かれた運命を
受け容れ、なすべきと考える仕事を全うしようとする姿勢は魅力的だ。薄幸な幼い少女の身
の上を案じ、祈り、保護・教育しようとしている。
一方の源氏、若紫との生い立ちの類似や憧れの人に似ている等、さもありなんと思える点
はあるもののいきなり「将来を約束して欲しい」との申し出は唐突で違和感があり、源氏の
わがまま勝手な言い様・若気の至り・高貴な身分故の傲慢とも聞こえてしまう。
尼君の反応は当然だろう。
もしも若い時代にこれを読んだら私は相当に反発を感じただろうと思う。今、この物語を
読めて良かったと思っている。
2023-11-15? 若紫P36僧都の坊~P44少女の素性
☆竹とんぼ
源氏は、僧都に乞われて僧都の屋敷の客になる。
僧都は「柴の庵」と謙遜しているが、庭は水が流れ、かがり火をともした立派な屋敷だ。
庭の趣味が良いこと、部屋の香りが心にくいことなど、屋敷のしつらえの描写が詳しい。
この時代は、生活全般の「美」が人の美しさと同じく重要なのだとおもった。「美」がこの
ように大きな価値をもっていた時代の世界観に、もっと浸ってみたい。
☆KUNKO
少女の素性が判りました。何とあの愛しい藤壺の血縁者ではありませんか。道理で似ている筈です。しかもこの少女の生い立ちが源氏と同じ境遇で成長して来た事も判りました。それは、親近感も湧きます。(読者も)
源氏は、まだ17歳で、少女は13?14歳でしょうか?もう少し歳下だとしても、源氏の妻として何の違和感の無い年齢なんですね。
源氏にとっては、実に初々しい恋になるのではないでしょうか。
☆葉
源氏は熱心な誘いを受け、僧都の坊に泊まることになった。お忍びで治療に来ていただけに躊躇したが、藤壺に似た少女との出会いに運命的なものを感じていただけに事情をはっきり知りたいという気持ちが勝ったのだ。
鑓水のほとりに篝火。軒先の灯篭の明かり。客室に漂ってくる≪そらだきもの≫仏前の≪名香≫情緒ある風情。そして控える女たちの衣擦れの音がしてくる。山奥でありながら見事な造りの僧坊に源氏は迎え入れられた。
僧都の話からいよいよ少女の素性が分かってくる。まさに藤壺の兄の子供。藤壺の姪子だったのである。その上、少女を残して亡くなった母君は北の方の嫉妬に苦しみ抜いて死んだというのだ。源氏は自分との境遇が重なり、増々特別な思いが心の中に広がっていく。
しかし十ばかりの女の子である。源氏は僧都や尼君に何を伝えようというのだろうか。
☆源氏のこころ
若紫の素性が明かされ、源氏と遠い血縁関係にあったこと、幼くして産みの母を亡くした
こと、その母の境遇も似通っていること等、生育期に類似点のあることが判明し、源氏は愕
然としつつも彼女に惹かれた意味が心の中でほどけ、運命を感じたことだろう。
長じては自分の良き理解者となってくれるだろうとも思い始めていたことも想像に難く
い。
☆竹とんぼ
源氏は、僧都に乞われて僧都の屋敷の客になる。
僧都は「柴の庵」と謙遜しているが、庭は水が流れ、かがり火をともした立派な屋敷だ。
庭の趣味が良いこと、部屋の香りが心にくいことなど、屋敷のしつらえの描写が詳しい。
この時代は、生活全般の「美」が人の美しさと同じく重要なのだとおもった。「美」がこの
ように大きな価値をもっていた時代の世界観に、もっと浸ってみたい。
☆KUNKO
少女の素性が判りました。何とあの愛しい藤壺の血縁者ではありませんか。道理で似ている筈です。しかもこの少女の生い立ちが源氏と同じ境遇で成長して来た事も判りました。それは、親近感も湧きます。(読者も)
源氏は、まだ17歳で、少女は13?14歳でしょうか?もう少し歳下だとしても、源氏の妻として何の違和感の無い年齢なんですね。
源氏にとっては、実に初々しい恋になるのではないでしょうか。
☆葉
源氏は熱心な誘いを受け、僧都の坊に泊まることになった。お忍びで治療に来ていただけに躊躇したが、藤壺に似た少女との出会いに運命的なものを感じていただけに事情をはっきり知りたいという気持ちが勝ったのだ。
鑓水のほとりに篝火。軒先の灯篭の明かり。客室に漂ってくる≪そらだきもの≫仏前の≪名香≫情緒ある風情。そして控える女たちの衣擦れの音がしてくる。山奥でありながら見事な造りの僧坊に源氏は迎え入れられた。
僧都の話からいよいよ少女の素性が分かってくる。まさに藤壺の兄の子供。藤壺の姪子だったのである。その上、少女を残して亡くなった母君は北の方の嫉妬に苦しみ抜いて死んだというのだ。源氏は自分との境遇が重なり、増々特別な思いが心の中に広がっていく。
しかし十ばかりの女の子である。源氏は僧都や尼君に何を伝えようというのだろうか。
☆源氏のこころ
若紫の素性が明かされ、源氏と遠い血縁関係にあったこと、幼くして産みの母を亡くした
こと、その母の境遇も似通っていること等、生育期に類似点のあることが判明し、源氏は愕
然としつつも彼女に惹かれた意味が心の中でほどけ、運命を感じたことだろう。
長じては自分の良き理解者となってくれるだろうとも思い始めていたことも想像に難く
い。
☆竹とんぼ
源氏は、僧都に乞われて僧都の屋敷の客になる。
僧都は「柴の庵」と謙遜しているが、庭は水が流れ、かがり火をともした立派な屋敷だ。
庭の趣味が良いこと、部屋の香りが心にくいことなど、屋敷のしつらえの描写が詳しい。
この時代は、生活全般の「美」が人の美しさと同じく重要なのだとおもった。「美」がこの
ように大きな価値をもっていた時代の世界観に、もっと浸ってみたい。
☆KUNKO
少女の素性が判りました。何とあの愛しい藤壺の血縁者ではありませんか。道理で似ている筈です。しかもこの少女の生い立ちが源氏と同じ境遇で成長して来た事も判りました。それは、親近感も湧きます。(読者も)
源氏は、まだ17歳で、少女は13?14歳でしょうか?もう少し歳下だとしても、源氏の妻として何の違和感の無い年齢なんですね。
源氏にとっては、実に初々しい恋になるのではないでしょうか。
☆葉
源氏は熱心な誘いを受け、僧都の坊に泊まることになった。お忍びで治療に来ていただけに躊躇したが、藤壺に似た少女との出会いに運命的なものを感じていただけに事情をはっきり知りたいという気持ちが勝ったのだ。
鑓水のほとりに篝火。軒先の灯篭の明かり。客室に漂ってくる≪そらだきもの≫仏前の≪名香≫情緒ある風情。そして控える女たちの衣擦れの音がしてくる。山奥でありながら見事な造りの僧坊に源氏は迎え入れられた。
僧都の話からいよいよ少女の素性が分かってくる。まさに藤壺の兄の子供。藤壺の姪子だったのである。その上、少女を残して亡くなった母君は北の方の嫉妬に苦しみ抜いて死んだというのだ。源氏は自分との境遇が重なり、増々特別な思いが心の中に広がっていく。
しかし十ばかりの女の子である。源氏は僧都や尼君に何を伝えようというのだろうか。
☆源氏のこころ
若紫の素性が明かされ、源氏と遠い血縁関係にあったこと、幼くして産みの母を亡くした
こと、その母の境遇も似通っていること等、生育期に類似点のあることが判明し、源氏は愕
然としつつも彼女に惹かれた意味が心の中でほどけ、運命を感じたことだろう。
長じては自分の良き理解者となってくれるだろうとも思い始めていたことも想像に難く
い。
2023-8-16? 若紫 p6北山療養~p14小柴垣の庵
☆竹とんぼ
源氏は「わらは病(やみ)」を患っている、という若紫の帖の始まりです。
「わらは病」とはマラリヤのように、定期的に熱性の発作が起こる病らしい。文面には「わらは病」についての説明的記述がないから、当時はよく知られている病なのでしょうか。
今は見られなくなっている病が、こうして普通に文中に出てくることで、現代からいっきに千数百年前の時代にワープしてしまう。
これも古典の楽しみだとおもいます。
☆KUNKO
源氏は、北山の奥地に住む『聖』の元を訪ねます。原因不明の発熱を繰り返す病を治療してもらうためです。源氏の病は何でしょうか?夕顔を失った悲しみともののけの仕業でしょうか。
現代においても治療しても回復しない病を抱えた人は、見えない『力』に頼る人がまだまだいますよね。「病は気から」とは、真実だと思います。
源氏の供人達も源氏の気を晴らそうとしているようです。その気遣いがこの先、どんな物語を紡いでいくのか楽しみなところです。
加持祈祷の効果が出て、気が晴れる出来事が起きて源氏が以前のような光り輝くような美しさを取り戻してくれるのが待ち遠しいです。
☆葉
十数年前の事だったと思うが、京ことばで語られる源氏物語を聞きにいったことがある。場所は円覚寺の少し小高いところにある某庵だった。はんなりとした京言葉が心地よかったのだが、玉縄源氏の会で源氏を読み始めてから、あのとき庵で聞いたのは何の話だったのだろうとずっと思っていた。
今回若紫の巻を読みはじめて、あれは「若紫の巻」だったのだと記憶が蘇ってきた。
語りを聞いていた庵の部屋の前に柴の垣根があって、「ちょうど、こんな風に垣根から下の様子が見下ろせたのでしょうね・・・・・」と、話をされたことを思い出した。まさしく若紫の巻だったのだ。
さて、本文に戻ろう。源氏は八方手を尽くして、加持や祈祷の治療を試みたが効き目がない。北山の山奥に住む修行僧が多くの人々を疫病から救っているという話を聞き、お忍びで来ているところである。
ここまで読み、平安の時代の治療手段は本当に祈ることだけだったのだろうかと気になりだした。大陸から伝わってきていた医術は貴族にどのように受け止められていたのだろう。多くの人を救ったというこの修行層は「さるべきものを作りて、すかせたてまつり、、、」とある。「すかせ」は「飲み込ませ」ということなので、体に直接影響を与える治療をしたということなのだろう。さるべきものとは、いったいどのようなものだったのだろうか・・・・・・?
☆源氏のこころ
聖との出会いが興味深かった。源氏の姿かたちを見る前はどんなに身分が高い人であろうと相手に迎合せず、自分の意思を貫いて申し出を断っていた聖が源氏を一目見た途端、嬉しくなって身体全体でその歓喜を体現する、みすぼらしい姿に身をやつしているにもかかわらず、源氏の高貴さを見抜き、素直に喜びを体現する。
聖のとらわれやてらいのない自由な接し方、態度は素晴らしい。こうありたいと願う。
一方対照的に粗末な身なりで僧都に会いたくないと思う源氏、修行はこれからということなのだろうか。
023-7-19? 夕顔 p331夕顔の宿り~p342二道の別れ
☆竹とんぼ
待ち焦がれた夕顔の姿が現れた夢には、、あの夜の物の怪も同時に現れた。
当時は、夢は非現実でなく現実そのものなのだろうから、源氏は夢で夕顔に再び会いたい気持ちを断ち切ったようだ。
空蝉は夫の任地にくだり都を離れる。
源氏の空蝉に対する別れは丁寧で、かつはっきりとしていて、私は感心した。
こうして、源氏の公にできない二つの恋が終わった。夕顔の帖が終わり、心にぽっかりと虚ろな穴があいた気分になっている。
☆KUNKO
夕顔に出会う前の空蝉への恋心は、夕顔との物語の中ですっかり過去の思い出になっていたようです。空蝉が夕顔との物語を知る由も無く源氏との一夜限りの出来事は、いつしか恋心として大きく膨らんでいったのに戻された小袿を見た時に涙と共にしぼんでいったのでしょうか。
空蝉は、少し狡いと思いました。あれだけ逃げてばかりいたのですから心変わりされても仕方ないと思うのです。それなのに、いつ迄も自分を思っていて欲しいなんて身勝手かな?とも思いました。
『過ぎにしも けふ別るるも二道にゆくかた知らぬ 秋の暮かな』に誰にも言えない源氏の寂しさや虚しさが出ていると思いました。
華やかと思われている源氏物語ですが、人に話す事のできない恋心に苦悩する若者の姿が
ありありと描き出されていると思いました。
夕顔の忘れ形見の撫子はどうなってしまったのでしょうか。と、続きが気をになるように仕掛けてあるのは式部が物語全体を最初に構成してあるからなのでしょうか。
いつの世の読者も早く次が読みたいと思わずにはいられません。
☆源氏のこころ
遂に夕顔が完。まったくハラハラドキドキさせられたが「は~、フーン、ほ~」とつぶや
きつつ作者に操られ楽しく読み終えた。
読む毎に意外な展開や事件があり、我々の日常から空間的時間的社会システム的にかけ離
れ過ぎた世界の出来事で目をみはったり疑ったり感嘆したりとこちらの感情も忙しく、物語
の進展についていくのが精一杯だった。
雨夜の品定めでさまざまな女がいることのザックリした輪郭を示し、空蝉・夕顔で具体的
に深掘りしてぐっとクローズアップしていく手法のように感じた。
草子地の起用とその使いこなしも見事だが、主人公にグッと迫っていく書き方は3D表現のようにも感じられ、自分の中で空蝉や夕顔が立体的に浮かび上がってくる気がして感服した。
2023-6-21? 夕顔 p316空蝉の文~p330四十九日の法要
☆竹とんぼ
物語は唐突に『空蝉』の話に移る。
空蝉は、間もなく伊予に行くことになっている。都を離れる前に、思いを伝えたかったのか、空蝉から源氏に文が届く。
源氏はちゃんと返事を書き、空蝉も心に踏ん切りをつけたようだ。
この時代の男女の関係性や心情が、私には今一つぴんと来ていない。恋のあり方に、その人の人間性が今よりもはっきりと表れる時代だったのか?とも思っています。
☆葉
夕顔の巻も終わりに近づいてきた。女君が世を去り四十九日を営む時が来たとある。その間、源氏は亡き女君を慕い続け重い病を患っていたと思っていたのだが、語り手はここで、空蝉からの文、そして空蝉の義理の娘、軒端の荻への源氏からの文について語り始める。
夕顔の巻に夢中になっていた私としては、いまさら何ゆえに?と思うのだが、そういえば空蝉に恋焦がれていたのは、ほんの数か月前のことだったのだと、気づかされる。前の話が次の話へと絡んでいくのが、源氏の面白さなのだろう。
夕顔の巻も、卑しい家の垣根に咲く花だと教えられた夕顔の花を、一房とってくるようにと命じたところから始まった。移り香が立ち昇る白い扇の上に歌を添えて花が奉げられたことにいたく心を惹かれ、女君との深い出会いに導かれていった。「夕顔の花」は、夕方に咲き始め、明け方には花の命を終えてしまう短命の花だ。まさに夕顔の君と重なっていく。
私にとっても、夕顔の花は特別な意味をもつ花になりそうだ。
☆KUNKO
空蝉から文が届きました。都を離れる前に源氏の愛情を確かめずにはいられなかったので
しょう。人の妻ではあるけれど、自分のコトを忘れずに愛しい人として記憶に留めて置いて
欲しいと言うことなのでしょうか。
軒端の荻にも文を出そうと思ったのは、空蝉からの文があったからなのでしょうけれども、マメな性分はモテる男の必須アイテムだなぁと思いました。
女にモテる男(女好きの男では無く)って実にマメで、女性を大切にしようと思って行動する人が多いと思いました。
四十九日の法要を心を込めて執り行う源氏を見て女性の心情に寄り添おうとする男がモテる男なのだとつくづく思いました。
ただ、マメな性格が仇にならなければいいとも思いました。
☆源氏のこころ
夕顔とのことで身も心も右往左往、浮き沈みしている間にも源氏の思いとは別に他の女との恋愛は動いていた。
突如として空蝉からの文が届けられる。夕顔とのことは夏から初秋にかけての出来事だったのだから空蝉の思いは終わっておらず、夫の伊予への赴任が近づいてきたことで、今源氏の気持ちを確かめておきたいとの女心の発露は理解できる。源氏との華やかな恋の思い出を確固たるものにして内心に納め、これからの伊予での生活に心の潤いを持っておきたいと願ったのかもしれない。
また源氏は軒端の荻へもちょっかいを出してみるなどして夕顔ショックから立ち直ったかに見える。しかしあの世へと渡ってしまう四十九日の法要は哀しみに満ちてやりきれない。
作者はここに空蝉と荻の文を挟むことで夕顔の存在がいかに大きく深かったかを鮮明に描こうとしたのだろう。
2023-5-17? 夕顔 p306女君の身の上(続き)~p316それぞれの追慕
☆竹とんぼ
ここで夕顔が遺した女児の消息が、右近によって語られる。
源氏はこの遺児をひそかに育てる決心をするが、このことが何らかの争いごとの種になるのでは? などと読者としては妄想してしまう。
源氏物語は、その後の展開で「あぁ、あのことか」と思い至る伏線が随所に配してある。
まだほんのさわりを読んだだけなのに、今後の成り行きまで妄想し、それがまた楽しい。
☆葉
源氏と右近、それぞれが今は亡き女君のすばらしさを思慕の情あふれるままに語り合う。
<あやしく世の人に似ずあえかに見えたまひしも、、、>と源氏
<ものはかなげにものしたまひし人の御心を、たのもしき人にて、、、>と右近
田中先生の著書『イメージで読む源氏物語』から、言葉を拾わせていただくと、
「人並外れた敏感な感性をそのまま表したようなあえかさを感じさせる人だが、主従の関係
を超えて穏やかな温かい雰囲気で接する人間的な魅力もつ芯の強い人」といった人柄が浮か
び上がる。
源氏はさらに、語り続ける。
「打てば響く柔軟な心の女に初めて出会った。やわらかい雰囲気が悩みがちな心を慰め解き
放ってくれた。理性で身を固め容易に人を受け入れようとしない女と向き合っていると一方
的に気を遣うだけで楽しくない。その点、女君は相手に気を遣わせまいと、深い心の葛藤を
かかえながらも一途に信じ、寄り添ってくれた。女の心をもっと深く知り、打ちとけたかっ
た」と。
まさに、式部がこの時代の理想とする女性を描いているのだと初めは思ったが、いやいや
私もこういった男性に出会ってみたいと思う。時代を超え男女を問わず優れた者を、見抜く
式部の洞察に感じ入った。
☆KUNKO
夕顔が亡くなってから漸く夕顔が十九歳であったこと、幼子が京の西にいる事などを知った源氏。十七歳くらいで産んだ子ということですよね。中将が通っていたのは十六歳くらいでしょうか?
その年齢の女性が一人前として認められていたということでもありますね。
今は右近と亡くなった夕顔を偲んで恋しいと思う日々なのでしょう。亡くなった人は美化
されるものでしょうから、きっと夕顔は理想の女として源氏の中で生き続けるのではないで
しょうか。
夕顔の忘れ形見は、中将の子でも有るのですから本来であれば、姫君として養育されるべ
きでしょう。一日も早くその子を手元に引き取って右近の傍で養育して欲しいと思います。
☆源氏のこころ
「深まる秋の庭とそれを見やる右近の描写が美しく印象的だった。
乳母子の夕顔にぴったりと寄り添いしたがって苦労を重ね、心身ともにズタズタになって
しまった右近にようやく訪れた静かで落ち着いた時間。まだ若い右近であったが人生の秋を彷彿とさせるような庭の描写がしっくりくる。
久しぶりにゆっくりと深く話をする源氏と右近だが、中将に内緒で夕顔の娘を引き取ろうという算段に、また一波乱起きるのではないかと次の展開を想像してしまう。
読者に緩急を与える技はいつもながらお見事です。
2023-4-19? 夕顔 p292源氏病に倒れる(続き)~305女君の身の上
☆竹とんぼ
ここで夕顔の素性が、右近によって初めてあかされる。
右近の語りを聞く源氏の想いが強く印象付けられる。
ただ私は、病み上がりの源氏が、別世界によみがえったように感じている場面が印象に残った。生死の堺まで行った重い病が癒えて、先ず帝に参内しなければと現実対応をしようとするものの、まだ夢かうつつの状態。『わかるなぁ』と感情移入してしまう。
このような状態を、短い文章で的確に表す古語の(紫式部の)表現に感じ入った。
☆葉
いよいよ右近は源氏に女君のすべてを語り始める。さて、夕顔を読み進めて久しく立つので、源氏はどこまで、女君のことを察していたのだったろうかと、前のページを振りかえってみる。惟光の報告から頭の中将が語った「常夏の女」を思い浮かべはするが、《下の品》の女であることから、下の品への好奇心と冒険心で近づいていったのが事の始まりだった。
右近の語りから初めて明かされたのは、父は上流貴族で、広い庭に囲まれた寝殿つくりの邸に生まれ、ゆくゆくは入内もという素性だったこと。夜逃げ同然に逃亡せねばならなかったのは、恐ろしい脅しが右大臣家からだったということ。
夕顔の主人公と雨夜の品定めの「常夏の女」が重なってくる。わが身はこのまま落ちぶれて朽ち果てようとも、せめて幼な子には時たまにでも愛情を注いでやってほしいと歌った「山がつの垣は荒るともをりをりに あはれかけよ撫子の露」が思い出される。
恨みとか嫉妬の言葉をよしとしない、繊細で感受性の強い女の姿と夕顔が重なる。
☆KUNKO
頭中将が通っていた常夏の女が夕顔だという事がはっきりと判りました。しかし、男共(源氏、頭中将)は、女の耐え忍ぶ奥ゆかしさ賢さに甘え過ぎてはいないでしょうか。
自分本位の考えだから、女の思いまで気が回らずお互いの心の内を見せないまま死なせてしまったのでしょう。
頭中将との間に生まれた女の子もいるのでしょう。源氏は今後も頭中将との付き合いが有ると思うのですが夕顔の死や女の子の事を隠し通せるものでしょうか。
ちょっと、サスペンス的な様子も帯びて来た気がします。
☆源氏のこころ
「雨夜の品定め」を読んだときにひときわ不可解で心に残った女性「常夏の女」の素性と人柄が右近によって語られ明らかになり、読者の心も源氏同様に霧が晴れていくと同時に哀しみも増す。
あの不可解さはその不条理な生い立ちや若気の至りの浅はかな頭中将との出会いから形成されたとも思える。
気の毒な姫君の短い一生を考えると、源氏との恋に一時的にせよ喜びの一瞬があっただろうと思いたい。氏素性や背景がわからずに疑いを持ちつつも、純粋に求め合えた二人は幸せだったのではないだろうか。
2023-3-15? 夕顔 p282紅の御衣~p292源氏病に倒れる
☆竹とんぼ
源氏は、夜分密かに夕顔の亡骸と対面しに行った。
源氏は、帰途では、馬から滑り落ちてしまうほど憔悴し、館に帰り着くと病に臥せってしまう。源氏は、右近や惟光に対する配慮を示すなど、自分の役割を果たそうと努めるが、心身の損傷があまりに強くて病に陥ってしまった。
源氏も右近も惟光さえも、情動が激しく落ち込んでいる。
人の情緒がこのように激しく上下するのが、この時代なのだと思った。
物の怪が実際にいて、夜は全き静けさと闇のなかで、物の怪が主役になる時間帯。
現代の都市生活では感性も情動も貧しくなるしかない。平安の時代の豊かさをしみじみと感じた。
☆葉
夜の明けきらぬ深い朝霧の中、女を残したまま戻らねばならぬ源氏であったが、鴨川の堤までたどり着いた辺りで、ついに精魂尽きて馬からすべり落ちてしまう。
「かかる道の空にて、はふれぬべきにやあらむ。さらにえ行き着くまじきここちなむする」とつぶやく。源氏は突然に襲ってきた悲運に憔悴しきり、わが御衣を着たまま、山寺で一人煙に消えようとしている女の命と共に、自分もこのまま野垂れ死にするのがふさわしいのだという思いに取りつかれる。
惟光は、連れ出したことを悔やみながら、もう何の考えも浮かばず、とりあえず川の水で手を清め、清水観音の加護を願って懸命に祈る。
十行ほどのやまとことばで刻まれた簡潔な文章だが、描かれた情景、心理の豊かさに何度も読んでみたくなる。
そして、なんとか生きてたどり着いた二条院であったが、女房たちの疑るような呆れたような全く違う視点がさらりと描かれ、場面がぐっと広がるのがまたいい
☆KUNKO
共寝する男女がお互いに着物を交換する風習があったのですね。昔の絵に女者の着物を着た男性が描かれているのはその名残でしょうか?ずっと疑問に思っていました。
美しい女が紅の御衣を着たまま息が絶えたその姿は、一生忘れる事は出来ないでしょう
源氏が病に倒れ、その傍に右近が居てくれるのが唯一の救いでした。
源氏は快復するのでしょうがその回復の力となったのが何であったのかが次回判明するのでしょう。
リアルタイムで読んでいた人々は、ハラハラして次回を待っていた事でしょうね:(;゙゚'ω゚'):
☆源氏のこころ
夕顔は男の香が焚き染められた美しい「紅の御衣」とともに焼かれ、旅立って行くのだなあ、と思った。
男同士の主従関係と同様のことが女である夕顔と右近との間にもあった。
「煙にたぐひて、したひ参りなむ」には驚いた。乳母子でもあったから大ショックはわかるがそこまでとは。
男女問わず乳母子である主従というのは相互の関係性がことのほか濃いのだろう。それがわかっている惟光だからこそ右近を源氏の傍に置いて源氏に「思い出を語り合える相手」を与え、右近に生きるよすがを与えるというウインウインの関係を作り上げた。
しかし一般的にはこの時代、これまでに登場した姫君たちがそうであったように他を頼む以外に生きる術のない女主人に全存在をかけて生きていた身近な従者たち、自身のよって立つところがはかない立場の女主人であるというのは哀しく恐ろしいことだったろう。
2023-2-15? 夕顔 p269惟光の覚悟~p280鳥辺野の対面
☆竹とんぼ
源氏は、夕顔の亡骸に今一度対面したいという思いに突き動かされ、夜道を鳥辺野に向かう。
月が出てもなお暗い道中の不気味さ、火葬場のある鳥辺野一帯の黒々とした不気味さの描写、
遠く清水のあたりに見える灯火が辺野の暗さを際立たせ、読み手はぞっとする景観を映像を見るように体感させられる。
惟光は、内心大困りでありながら、源氏を案内して共に鳥辺野までくる。
《空蝉》の小君も、惟光も、一生懸命に奮闘し、困りながらも源氏のためにつくす。
このような脇役を配することで、源氏の人物像に厚みが増し、物語の展開が面白くなるという風に、紫式部は計算していたのかな?と想像します。
☆葉
源氏は穢れた身であり、内裏に行くことすらできないと人を遠ざけ、生きる気力さえ失っているように思われたが、今回の場面では、まるでドラマのように、予期せぬストーリーが展開される。
女に一目会いたい、葬られてしまう前にもう一度女の姿を見たいというのである。事が表ざたにならないようにと、慎重に手はずを整えてきた惟光は、当然のことながら説得にかかるのだと思いきや、《さおぼされむは、いかがせむ》と願いを受け入れるのである。
狩野装束に着替え、東山の闇を目指して馬に乗り、黙々と夜道を進む危険な冒険である一行の描写がまたよい。薄気味の悪い鳥辺野の闇、だがそこに火葬されようと横たえられている女にどうしても会わねばならぬという思いに心打たれる。
さて、死者に触れることさえ禁じられているこの時代、亡骸と対面した源氏はどうするのかと読み進めると、源氏は思わず女の手を捉えて《われに今一度声をだに聞かたまへ》と懇願するのである。そして《声も惜しまず泣きたまふ》とある。
今の時代であっても周りを憚り、自分の感情を抑えてしまうのが多くの日本人ではなかろうか。これほど感情豊かに情熱的に平安に生きる源氏が描かれていることに初めて知り驚く。
☆KUNKO
惟光の気の配り方の細やかさが良くわかります。
亡くなった女の元へ行く源氏ですが、主を亡くし絶望の淵にいる右近の心情にも心を寄せる源氏に温かいものを感じました。
そして、源氏が女の手をとらえて「今一度声をだに聞かせたまえ…」と声も惜しまず泣きたまふこと限りなし。の、くだりには涙が溢れてきました。なんて、純粋な心の持ち主なのでしょうか。
今まで、私達が植え付けられてきた『光源氏』の姿とはかけ離れていると思いました。
☆源氏のこころ
自分の持てる能力すべてをフル回転させて献身的に仕える惟光と全幅の信頼を寄せる源氏、形の上では主従の美しい信頼関係に見えるが、それだけだろうか。同い年の乳母子で実の兄弟のように育った二人はそれと知らずしっかりと兄弟愛を育んで来たのだろう。
先生の解説にある惟光が心得ている源氏の側面「源氏が女のことでは人一倍悩み深いたちであること」と「源氏が自分の心に正直であろうとして時に強引になる」等で惟光の源氏に対する理解の深さがよくわかる。今後の展開はわからないが、この二人なら支え合ってどんな困難も乗り越えて行くだろうと想像する。
源氏の出生から幼少期は孤独なものだったと思っていたが、このような暖かい環境もあったと知らされて心温まる気がした。
また源氏の人物像も少しずつ立体的に見えてきたと思えるシーンだった。
2023-1-18? 夕顔 p256惟光の采配(続き)~p269偽りの忌中
☆竹とんぼ
女君は亡くなった。
この重大事にどのように対処するのか?
惟光は源氏の悲しみに同調しながらも、亡くなった女君を連れて行く処を必死で考える。
『ことに対処してつつがなく収めるのは自分だ』と惟光は決意を固めたようだ。
難しいことが起こった時に、逃げずに正面から当たった惟光がめざましい力を発揮して、
応援したくなる場面でした。
☆葉
息絶えた女君、生きているかのようにみずみずしい。五色の糸で織られた縁どりの薄布団にくるまれた女君の亡骸は可憐な美しさを湛え、艶やかな黒髪はこぼれ出ている。源氏はかつてないほどの悲しみに打ちのめされ為すすべもない。冷たくなっていく女君を前に苦しさにあえぐ源氏。作者の描写が実に見事である。
また同時にこの時代の死生観がリアルに伝わってくる。死を悲しむが「死」を穢れとする意識は想像に絶するほど強いものだ。平安時代中期に編纂された律令「延喜式」には、穢れに該当する事柄ごとに日数が定められており、触れた場合は一定期間他人に接することを避け、清めを行うというのが習慣だったようだ。
源氏は死者に穢れた身であり、宮中に参内できないことを中将に伝える。が、もちろん亡くなった女君のことなど話せない。源氏は衰弱に堪えながらなんとか作り話をするのである。一度納得したかにみえた中将が引き返してきて《いかなる行触にかからせたまふぞや》と冷やかです。このあたりは、ふっと笑えてくる。穢れへの意識の違う遠い過去の人物たちが急に身近に感じられてくるのが不思議である。
☆KUNKO
美しい女は亡くなっても美しく…
うはむしろにおしくくみてもこぼれ出る髪…の場面は一枚の絵の様に浮かんできました。
源氏は女を思って泣き、今後の行動まで気がまわる訳もなく
しかし、そんな時でも惟光は源氏の思い人を大切に扱い源氏がとるべき行動も考えてくれま
すし自分がとるべき行動もきちんと考えてます。惟光の活躍なくしては、この難局を乗り越える事は不可能だったのではないでしょうか。
頭中将といい、源氏は良き友に恵まれていると思いました。
平安時代に死人に接する事が忌事で、何日も隔離生活になるというのは今回のコロナ禍とダブってみえました。平安時代は、死とは恐怖だったのでしょうか。コロナを恐れている現代人も同じなのかもしれませんね。
亡くなった女君の身辺は今後どうなるのでしょうか?失意のどん底の源氏は?
気になる次回です。
☆J
今回は亡くなった夕顔の遺体を運び出すところから、その後源氏が自宅に戻って、心配した帝に遣わされた頭中将と対面するというところまで、教えていただいた。
やはり今回のクライマックスは「こぼれ出づる髪」だろう。
床まで届くほどの長さの、手入れの行き届いたツヤツヤする髪がやんわりと身体を包んだ布団の端から、サラサラとこぼれ落ちる様が目に見えるようだった。
現代でも髪は顔に続いて、個性や美を表すものだが、当時は髪への執着が現代の何倍もあったと想像できる。髪=本人に近かったのではないか?ましては髪は生命があろうとなかろうと変わらない。
それを垣間見たことは、生きている夕顔を見るほどのインパクトがあり、源氏にますます別れ難いと思わせたのではないか?と思った。
☆源氏のこころ
前回に引き続き惟光の心と手腕が光る場面、
惟光に促され、そそくさと現場を後にして二条の屋敷へと帰り着き、精も根も尽き果てた源氏が動悸を伴いつつ心底後悔する「夕顔が生き返ったときに傍に自分がいないと知ったらさぞかし心細くつれない男だと思うことだろう、なんとひどいことをしてしまったことか」
死の確証が得られなかった当時、目の前で見ていてもいつが「死」なのかわからない。
ここは源氏の希望的観測からの「生き返り」ではなく、現実に起こりそうなこととして描が
れているように思える。息を吹き返すということが頻繁にあったのだろうか、あるいは生と死の間のグレーゾーンがあってそこにいる時期があるとでも考えられていたのだろうか?
それにしても夕顔はなんとあっけなく亡くなってしまったことか。
2022-12-21? 夕顔
p249孤独の一夜(続き)~p255惟光の采配
☆竹とんぼ
若気の至りのできごとでした。
女君は命を失った。理由は定かではないものの、妖しいものに憑き殺されたと想像されるような亡くなり方だった。
悲しくて涙を流す源氏、もらい泣きする惟光、はなから泣くばかりの右近。三人とも若者なのだ。
思慮不足ゆえの結果だけれど、若さのみずみずしさも感じる。とんでもないことを起こしてしまうエネルギーの発露。
老練になると、愚かな失敗は少なくなるが、新しいことも起こりにくくなるなぁとおもいました。
☆葉
明け方ようやく、惟光が参上する。惟光はこれまでと打って変わって、なかなかの采配ぶりだ。源氏の乳母の子だから、源氏と同じ17歳だと思われるがやはり側近としての立場をわきまえ、感傷に溺れることなく難題に頭を巡らす。
子どものようにさめざめと泣き、普通世間で行う誦経の手配や願立ての準備を頭に浮かべた源氏とは対照的に「これは源氏の身にふりかかる一大事になるかもしれない」と、直感し冷静に判断して事にあたろうとする。そしてまず、世間に漏れないようにすることが肝心だと考えるのだ。下々の者への口止めまで手抜かりがない。そして源氏がこの院に長居することの危険を察知し《まづこの院を出でおはしましね》と進言するのである。
物の怪におそわれることの不気味さや、夕顔の死の悲しみに共にひきずり込まれていた私も、惟光の采配ぶりを知り、現実に引き戻された感じがした。なるほどこうなるのかと。
式部の物語の展開のさせ方がなかなか面白い。
☆KUNKO
源氏の心配事の一番が「かかる筋のおほけなくあるまじき心の報い」とあり私はてっきり、夕顔と密会し、死なせてしまったことなのかと思ったら あるまじき心=藤壺への恋慕 と読み解くのだとわかり、作者は、この物語を書き進めながら綴っていたのではなく、最初から全体の大筋が出来上がっていてそこから一つ一つの場面を仕立てていったのではないかと思いました。
〈しほじみぬる人〉は、しっかり根を張って人生を経験した人を現した言葉だと思いました。
次回の惟光の活躍が楽しみです。夕顔は、右近はどうなるのでしょうか?
展開が全く予想できないのも毎回楽しいです。
☆源氏のこころ
源氏と惟光、同じ17歳の若者である二人、緊迫の場面。
当事者である源氏は危機迫る大変な困難の中、精一杯の「さかしがり」を発揮しているが緊張は頂点に達し、妄想まで発現するほど。一方、事件の詳細はわからないが君と右近の様子から事の重大さを察する侍従惟光は、君の思いに心を寄せつつも客観性を失わず冷静に努め「しおじみぬる」人ほどの手腕を発揮する。
この対比、二人の立場の違い・補完関係をあざやかに描き分ける式部の筆が冴えわたっている。惟光の大人びた賢さが光る場面だった。
2022-11-16? 夕顔 p237闇の中で~p246孤独の一夜
☆竹とんぼ
荒れた屋敷で、女君はもののけに命を奪われてしまう。
しっかりしているはずの右近が、恐怖で正気を失っている。
右近の我を忘れた怖がりようが、現代の私には尋常でなくみえるが、もののけが実在する時代なら当たり前の反応なのだろう。
屋敷内は火が消えて、真の闇だ。
現代の都市部では、真の闇がない。
私は、闇を知らず、もののけが実在する世界を知らず、五感の使い方が当時よりだいぶ縮小してしまっていると感じました。
☆J
今回はもののけに襲われ、あたふたとしているうちに冷たくなっている夕顔を発見する場面でした。
右近は全く役に立たず、源氏もはやっと冷静さを取り戻しつつある中、何も知らない預かりの子が源氏に呼ばれて弓の弦を弾きながら、火の用心と声に出して歩く様子や、紙燭を持ってきても畏れ多しと、源氏に近寄って手渡しもできないなど、暗闇の中でも冷静に行動している描写が源氏と右近との対比として効果的に使われていたと思いました。
☆葉
「女君はわなわなと震え汗びっしょりになり、苦痛は極限に達し、意識を失う寸前となる。」というところで前回終わった。まさに〈つづく〉であった。
さて、女君はどうなったのか。
「息もせず。引き動かしたまへど、なよなよとして、われにもあらぬさま・・・・」「ただ冷えに冷え入りて、息は疾く絶え果てにけり。」と実にあっさりと描かれる。
それに対して動転している源氏の描写は細かく、読み手の気持ちと重なっていく。「源氏はしっかりと女君を抱きしめながら、《あが君、生きいでたまへ。いといみじき目な見せたまひそ》と必死で呼びかける。物の怪が魂を奪ってしまったのだろうか。まさか死んでしまったわけではではないだろう。一時気を失っているだけかもしれない。万一この人を死なせてしまうことになったら、、、、。」と、冷え切っていく女の体を抱きしめ、呆然とし途方に暮れる。
物の怪に魂を奪われ生から死へと移行していく女君のありようが源氏を通して切なく伝わってくる
☆KUNKO
源氏が身分も何も関係無く語りあえる愛しい女が突然亡くなってしまう場面ですが…
今までの大方の訳者は、六条の君が呪い殺した!
というように書いていますが原文のどこにも六条の君という描写はありません。確かに、「いとをかしげなる女」が現れる前に源氏はふと「六条の君」を思い出してはいますが…。
私は、ずっと呪い殺されたとばかり思い込んできましたが、それよりかは憑依されての狂死か、田中先生が仰る心臓麻痺に近いのではないかと思いました。
呪い殺すのであれば、もう少し時間がかかると思います。
源氏は、このような時でも慌てる事もなく、実に堂々とした行動をとっているのが頼もしく感じました。
かたや右近は、何の役にも立たず…大方の女はこの様になってしまうものなのでしょう。
読み手が知りたい、女の名前も素性も解らず仕舞いで冷たくなってしまった女…。今後、女の素性はわかるのでしょうか?
今は、これからの展開をアレヤコレヤと想像して次回を楽しみに待っています。
☆源氏のこころ
思いを深め逃避行を決行した二人を待っていたのが女のあっけない死だったとは!
相手の素性がわからないまま謎めいて続いていく逢瀬、読者は引っ張られ引っ張られ連れて行かれた先でいきなり綱を離され、行き場を失うと同時にようやくひと息つく。
読者を惹くテンションが最高に達したところでパッと放され、驚きと小気味良さを感じた
。
2022-7-20? 夕顔 p226夕映え~p237枕上の女
☆竹とんぼ
源氏が、夕顔の女君を連れ出して、今は住む人のない屋敷で二人、愛を語り合う場面です。
『夕映え』の段で、惟光の思い「源氏が密かに連れ出すほどの女性なら、さぞそれなりの価
値があることだろう・・・」との描写が続く。
惟光の心情描写として読んでいたら、急に語り手の惟光評「あきれたものね」になってい
る。ひとつの文が、惟光の一人語り→語り手の評価と変わっていく。
古文は主語を書かないので、行動の主が分からず、古語音痴の読み手を迷子にさせる。
尊敬語や謙譲語に注意を向けて主語をあぶりだし、迷子にならずに物語を読めるようにな
るには、遠い道のりと実感しています。
☆J
もうふた月ほど前になるが、森に蛍を見に行った。駐車場から離れるほど電灯の数が減っていき、スマホの明かりを頼りに池に向かって歩く。
ここは毎日犬の散歩に来ている森で、道については知り尽くしているはずだが、夜の森は昼間とは全く違う顔を見せる。池の近くになると蛍のために灯りをつけることが禁止されているため、スマホも消し一歩一歩探るようにして進んだ。
私は物の怪は信じないが、やはり薄気味悪いし、不安な気持ちになった。
平安人はおそらく夜のくらやみには現代人よりも慣れていただろうが、物の怪に常に怯えていたらしいから、不吉な夢を見た後になぜかあらゆるところの灯りが消えていたというのは、ものすごくおそろしかったにちがいない。
慄く右近を笑おうとする源氏の引き攣った顔が浮かぶようだ。
さて、この物の怪は六条御息所かそれともなにがしの院に住み着いているものかと、いまだに賛否両論あるそうだ。
こんなつまらない女に心惹かれてしまって、、というあたりいかにもプライドの高い六条御息所がいいそうなことだが、源氏が夢の中でみた女の顔は六条御息所ではなかった。
気になって調べてみたら、源氏物語の書かれた順番についてもいろんな説があるらしく、一説によると葵の上が六条御息所の生き霊に殺されてしまった話が先に書かれていて、すでに読者には周知だったから、夕顔についてはわざわざ六条御息所だと言及してないのだという。
もちろん、お話の順番にも諸説あり、この正体については紫式部のみぞ知る、ということなのだろうか。
☆葉
今回、読み進めた所は、11ページほどで、原文でも30行ほどのところであったが、舞台をじっと見つめていたときのような心地で少々疲れた。
「舞台は廃院。時は宵も過ぎた頃。座敷の奥の渡殿に灯された火が不気味に揺れている。源氏が寝入ったころ、源氏の枕上に女が現れる」と舞台は始まる。情景が目に浮かぶ、舞台の中に吸い込まれるようだ。よく描かれているものだと感心する。
嫉妬と怨念に駆り立てられた枕上の女は源氏に訴え、そして隣に寝ている夕顔をかき起そうとするのだが、ここまでは源氏の呵責の念によって生じた夢なのだろうと思っていた。しかし
《火も消えにけり。・・・この女君、いみじくわななきまどひて、いかさまにせむと思へり。汗もしとどになりて、われかのけしきなり》と、描かれ現実の話となる。女君はひどくわなわなと震え汗びっしょりになり、苦痛は極限に達し、意識を失う寸前だというのである。
右近はおびえて身体が動かない。供人を呼ぶために手を叩くと、その音は不気味な闇にこだまのように響くばかりである。夏の夜にふさわしいおどろおどろしさだ。
この時代、物の怪、生霊はまさに現実のことだったのだろう。
☆源氏のこころ
裏切られた女の恨み心が表出する怖い場面、彼女の言葉は無駄がなく単刀直入で鋭く刺さる。自分の思い(恨み)とその強さ・激しさを言い表すとき、なんの修飾もなく端的に表現する
と恐ろしさが倍・3倍になるのだと知った。
恋する二人は幸せの絶頂からもののけが作り出す真っ暗闇のなかへ放り出され、奈落へと突き落とされそうな鬼気迫る場面にぞっとした。
2022-5-18? 夕顔 p214なにがしの院~p226語らい
☆KUNKO
二人が訪れたのは、源融の屋敷跡です。
融は源氏のモデルの一人ともいわれているようです。
紫式部は、この屋敷に誘い異次元の世界へと誘い込んだのではないでしょうか。
恋を語らうには、うら寂しくて、少しもロマンチックではなくて。女の詠んだ歌
「山の端の心も知らでゆく月は うはの空にて影や絶えなむ 心細く」に、二人の恋の行く
末を不安に思ったのは私だけではないと思います。若い源氏が一人、浮き足立っているよう
にも感じました。若く経験も少ない源氏と人生経験が豊富な女との温度差が見えた気がしま
した。
なにがしの院の描写がリアルすぎて靄の中で二人が寄り添っているような場面しか思い浮
かびませんでした。
☆竹とんぼ
源氏は夕顔を、源氏が所領して空き家になっている屋敷につれていく。
夕顔は、源氏に自分が何者かを明かしていないが、頭の中将の「常夏の女」だ。このような人物像を創造しえた紫式部に、敬服する。
夕顔の性質は、無邪気さ、無垢さが際立つ。策略や計算、ましてや手練手管とは無縁だ。
中将の北の方を恐れ、子を連れて身を隠す次第に至る前に、中将に具体的な助けを求めてもいない。姿を隠すために突然住まいを変えて、暮らし向きの苦労を憂いてはいても、全てを受け入れているような風情がある。
その態度は超然ともいえるが、非現実的ともいえる。非現実だからこその素直さは、妖精が持つ魅力と似ている。
このように稀なタイプの女性を、生き生きと描ける紫式部なのだ。
☆J
今回は源氏が夕顔を『なにがしの院』に連れ去ってきたところから始まる。 この『なにがしの院』という表現に私は強く興味を持った。『なにがし』という言葉に『名前はあえて出しませんよ』というだけではなく『でも皆さん当然ご存知よね』というニュアンスが重なる。
恥ずかしながら光源氏のモデルとされるのが源融だったというのを今回教えて頂き初めて知った。調べてみると源融は紫式部の生きた時代から150年ほど遡った時代の人物だ。嵯峨天皇の皇子であり左大臣まで勤めた人物である。さらに後撰和歌集にも残るほど歌人としても優れていたので、その生涯や恋愛遍歴については150年後でさえ十分知られた人物だったのだろう。
天皇の子でありながら臣下に下り…というところからして光源氏の設定に源融をモデルとするという考えが紫式部には既にあったのだろう。
今回のなにがしの院は六条河原院がモデルとされていると言われている。源融は宇治十帖の舞台となった宇治にも別荘を持っていた。これは融の死後、宇多天皇の所有を経て何代か後には式部の仕えた彰子の父の藤原道長のものとなり、その後息子頼通により平等院鳳凰堂となる。
ちなみに河原院で海水を運び込ませ、塩釜焼きの趣味を楽しんだとあるが、これは融が一時期、多賀城勤務で塩釜に滞在した経験がありそこでの様子を彼は河原院に持ち込んだらしい。多賀城は当時蝦夷と言われた東北の民族に対する防衛施設であった。そんなところに行かされたのは中央政治から外された感もある。
源氏物語という架空の話から実際の歴史へも興味が広がった回であった。
☆葉
下々の者たちの生活の音が聞こえてくる夕顔の住まいから逃れ、もっと心休まるところで、二人だけで心ゆくまで語らいたいと願う源氏。夜の明けぬ前に女を隠処に連れ出すことにする。初めての《御旅寝》。外泊に緊張と興奮。込み上げてくる喜びに有頂天である。女の気持ちを思いやる余裕などなく、不安がる女をほほえましくさえ思っている。しかし、一方女は、突然連れ出されてひと気もなく物寂しい場所を異常なほど恐ろしがっている。
源氏が向かった所は「なにがしの院」。源氏が思うままに使える邸であり、そこを管理している《預り》とも親しいようだ。右近は初め立派な邸と胸をときめかせたようだが、翌朝源氏が目にした庭の風景は、想像を絶するほどの荒廃ぶりで、薄気味悪く《いとけうとげになりにける所か》とある。さらに鬼なども潜んでいそうだという。
このなにがしの院てどこにあったのかしら?と田中先生を囲んでのおしゃべりが始まった。当時の読者にとって「なにがしの院」と聞いたらみんな知ってたのかしら。六条の鴨川の近くってここ?『伊勢物語』では、壮大な景観を誇った院と書かれていたって。造営したのは源融で、その亡霊が出たという話も伝わっていたとか。源融っていうのは・・・
こうしたおしゃべりも実に楽しい。
《怨みかつはかたらひ暮らしたまふ》二人の行く末はどうなるのだろう?
☆さくらちゃん
初めての源氏の「外泊」の様子が面白かった♪女の家に通う事はあっても外泊が初めての源氏の興奮した気持ちがよくわかり「可愛い」と思った。
また源氏が夕顔に初めて顔を見せた時の自分の顔を「露の光」と例えているのが面白かった。
☆源氏のこころ
前回に続き恋の喜びと興奮に先行きの不安が重なって緊張感がみなぎる展開のなか、右近がなにがしの院の立派な様子に昔を懐かしむ描写がはいり、ふっと息が抜けて読者は一息つく。と同時に女が昔は身分の高い暮らしをしていたのだろうと想像がつき、彼女の不幸な人生の成り行きの一端も窺える。
女は右近と異なり、現実の邸の様子よりも廃屋から立ち上る不吉な予感に押しつぶされそうになっている。それでも男の思いに応えようとけなげに振る舞う様子が哀しく感じられる。
一方で「たそがれどきのそら目なりけり」などと言って男に甘えたり二人のときを楽しむ様子もあって救われる感じがする。
「心より他に漏らすな」という表現がきれいで面白いと思った、「他人に漏らすな」じゃなくて心以外の表情や仕種にも出してはいけないという禁止事項なのだろうか?
大英博物館から里帰りしている「北斎展」に源融が作った頃の六条河原院の庭を描いた作品がありました。
夕顔 p199板屋の物音~p213ためらい
☆KUNKO
夕顔の住まいの様子がよくわかる興味深い場面でした。しかし、隣家の物音や会話も筒抜けでは恋を語らう雰囲気にもなれず。源氏は夕顔との静かな時間がもてる所へと夕顔を連れ出すのですが事の展開が早くて若いなぁ!と驚きました。夕顔も驚いた事と思います。
車が出る間際に乗り込んで来た右近は、最も信頼のおける人なんだろうと思いました。
しかし、残された家人はどう思っていたのでしょうか?現代なら誘拐ですよね。
今後、家人は出てくるのでしょうか?夕顔の素性も判らないままですね。
次回で色々とわかるのでしょうか?昔の読者もこの先どうなるのかしら?と、気を揉んだのでしょうね。
☆竹とんぼ
夕顔の女性の住まいは、狭く、隣家の生活音や話し声、外の物音が筒抜けに聞こえるような家だった。石臼のゴロゴロ音を、源氏は何の音だか分からない。源氏が育ってきた環境と、この場所が、いかに違っているかを表すエピソードだ。
近隣の物音や話し声が筒抜けで、源氏は落ち着けない。周囲の庶民の生活ぶりは実に生き生きと描かれている。生活の苦しさを嘆いていても、暗さよりもむしろ活気がある。
源氏は、雑音のないところで女性とさらに深く親密になりたいとひたすら望む。一方で、日々の生活に追われつつ現実感の中で生きる市井の人々。
読み手の私は、どちら側に重心をかけるかで物語の様相が違って見えるのが面白い。
☆J
今回は夕顔の居所で一夜を明かした源氏が、明け方からの近隣の庶民の生活音にややびっくりする場面から始まる。まず筆者は『女はこれについてたまらなく恥ずかしく思う』としている。しかしその後、次々と描かれる女の性格は少し違っている。
<えんだちけしきばむ人>とは違う、<つらきも憂きもかたはらいたきこと>と感じて卑屈になっていない、<のどか>であり、<あてはかにこめかしく>などと貧しい暮らしを気にする風を見せないーーー女のおおらかでおっとりした様子が伺える。
これに従い源氏も<白妙の衣を打つ砧の音>や、<みだりかはしく鳴き乱るる>虫の音でさえ『風変わりで良い』とし、庶民の生活音さえ楽しむ様子を見せ始めるのだが、これは筆者も『御心ざし一つの浅からずによろずの罪を許さるるなめりかし』と、源氏がこの恋に一途であるためと鋭く分析する。
しかしやはり自分の慣れ住んだ静かな世界へ女を連れて行き、自分の理想とする二人の時間を過ごしたいという思いを、女を急いでここから連れ出すことで実現させようとするわけだが、ここでの二人の歌のやり取りが面白い。源氏は一途に永遠の愛を誓うのだが、そんな源氏の想いからかけ離れたところで女は憂いを抱えているのである。
やはり女はそれほどおおらかでおっとりではないのだ。最初にあったように『たまらなく恥ずかしく思う女』であり『源氏との先行きを憂う』複雑な女なのである。
☆源氏のこころ
今回読んだ部分には暗闇から薄暮のなかでさまざまな音の描写が散りばめられている。市井の人々の罵声、おどろおどろしい碓の唸り、かすかに聞こえる砧を打つ音、空飛ぶ雁の声、耳近く聞こえる虫の音、御嶽精進する翁の声等「どんな音なのだろう?どんなふうに聞こえたのだろう?」と興味深く想像を掻き立てられた。暗闇だからこその演出なのだろう。
またスピード感あふれる展開にも驚かされた。源氏の心の動きに並行するように物語もスピードアップしていき、あれよあれよという間に夕顔を抱いて牛車に乗り込んでしまった。
しっかり乗込んだ右近に拍手しつつ読者としてはやや置いていかれ感すら持ってしまった。
そして歌を交わす場面での演出にはドキリとさせられた。源氏は「女との深き契りを永遠に」と願っており、同様に永遠の縁をと願った長生殿の故事を思い出す。しかし哀しい結末に終わった長生殿を不吉と感じて意識的に避け「弥勒の世まで」と歌に詠む。二人で生きて永遠にとの思いを込めたのだ。
こうして読者に強く印象付け、次なる展開がより深く劇的なものとなるように伏線を敷いておくという技、いつもながら感心させられた。
2022-1-19?
[夕顔 }p183下の品への冒険~199いづれか狐
☆KUNKO
惟光が手筈を整えてくれたおかげで下の品の女の元へ通うようになった源氏ですが、
素性がわれないように変身して顔も隠して女の元へ。しかも、夜遅くに…。
源氏は、女に心惹かれて既に恋煩い状態。二条に迎え入れようとまで考えているようです。
源氏にとっては、初めて心から寛げる場を与えてくれた女なのではないでしょうか。生身の人間として、一人の男としての自分を慕い共に過ごしてくれる女。
今の世でも、地位や身分、収入などを考えずにただ人となりを愛してくれる人を大切に思
わない人はいないと思います。一読者としては、この女と幸せになってもらいたいと思いま
す。
今後、この女の素性がわかった時に物語は大きく展開していくのでしょうね。
しかし、疑問も浮かんできます。平安時代の貴族の人々は、完全なる夜型だったのでしょうか。『夜』は『闇』では無く、何か特別な『力』が有る時間帯だったのでしょうか。
夜分遅くに他人の家を訪問することは、現代においては、迷惑なことですし、物騒です。
平安時代は、いつからこんな習慣が出来あがっていったのでしょうか?そんな疑問が頭を占
めてしまいました。
☆葉
《上の品》とは、異なった《下の品》の世界へ足を踏み入れてみたいと、好奇心と冒険心から女に会いに行く。もちろん誰にも気づかれないよう地味で目立たない姿でしかも歩いてさえ行こうとする。だが、単なる違う世界の女への好奇心とは思えない。
貧しい家に咲く、これまで見たこともない美しい花に心を奪われたところからミステリーは始まる。もっと近くで見たいと思ったその夕顔の花は、移り香の立ち昇る扇子に載せられ届けられた。そしてその扇には流れるような美しい手の歌で「あなたは、源氏ではないか」と問いかけていた。
源氏は異様な忍び姿で毎夜通う。お互いに正体を明かせずに逢瀬を重ねるうちに、引き返すことのできない親密な仲になっていく。
《いづれか狐なるらむな。ただはかられたまへかし》と誘えば《さもありぬべく》と女も思う。互いに狐になって化かし合っていると思ったらどんなに楽しいだろうと、、、、、。
この打てば響く掛け合いがなんとも魅力的だ。素性を明かせられない間柄でありながら、いやそれ故に、身も心も吸い寄せられていく恋心が生々しく伝わってくる。
☆竹とんぼ
源氏は、世間の決まりごとの枠を越えた恋に落ちる。
決まりごとは、この場合身分を大きく超える恋愛ということだ。
心に染み入る相手の存在、二人でいる居心地のよさを感じる源氏に、読み手の私も同調してしまう。
それにしても人妻と恋をすることよりも、身分を越える恋愛の方が世間の決まりごとを外れることになるのか??
当時の身分社会の状況をもっと理解したいとおもった。
☆J
かなり長い間お休みをいただき、久しぶりの源氏である。
講義はいつのまにか夕顔に入っていて、私は源氏と女との馴れ初めはわからないまま源氏の世界へと足を踏み入れていく。
ところが、下の品に興味津々の源氏と、主人の望みを叶えるのに涙ぐましい奮闘をする惟光の活躍から始まり、やっと女との渡をつけたそのいきさつを、「くだくだしければ、例の、もらしつ(面倒なので例のごく省略)」といきなり足を掬われた。
え?、それはないでしょ、、、
その後も、源氏がいかに女に恋焦がれているか、いかに正体がバレないように苦心しているかばかりが続く。「なんでそんなにご執心?」歌のやり取りさえ描かれておらず、夕顔の人となりにも触れず、「だいたいそんなに密な関係になっても顔を見せたことも無いって、一体どうやったらそんな事が出来るわけ?」と疑問ばかりが渦巻いていく。そうなると、もはや寝床で半裸になりながら頭巾を被っている源氏は滑稽でしかない(私の勝手な妄想です)。
と、ひさびさの源氏の世界に妙な違和感を感じ得なかったが、ちゃんと講義の最後に「いづれか狐」に至って、夕顔が源氏に愛されてやまない理由が垣間見える、そして私は「行け源氏!夕顔を二条院にでもなんでも連れて行っちゃって!」と言ってしまうのである。
そういえば時間はかなり押していたが、「今日はここまでやってしまいたいのよね?」と先生が仰ったのだった。
さすが田中先生!ちゃんとお終いには生徒の気持ちをあげることを心得ていらっしゃる。
☆源氏のこころ
お互いに身元を伏せ、源氏は身をやつして顔まで覆って訪問する。真っ暗な寝所で手探り状態の二人、想像しがたい情景だが、双方ともに怪しみつつも惹かれあっていく。なぜだろう?
女はのびのびと素のままに振る舞う。自分の素性を明かさず、相手の身分や背景、顔かたちもはっきりしないせいで大胆になり、自分を飾らずに楽しめたのだろうか。
男は女が「下の品」の者であろうということだけはわかっているために「世間の常識」と戦うことになるが、男にとって女の魅力はそれを上回って余りあるものとなっていく。
男がこれまで関わりのあった女たちは身分や環境、立場、「かくあるべし」という自分への規制等にがんじがらめになり、その枠から出られない人たちだった。男は殻を被らない女に初めて接したのではなかったか、その素を演出するには「どこの誰かわからない」という設定が必要だったのかもしれない。
男はこの女のことがなくても「世間の常識」というものとぶつかる運命の下に生まれているようにも思える。この物語のテーマの一つでもある「『タブー』とそれを破ってしまう人の行動のもとにある心」がここでも表現されているように思えた。
2021-11-24? 夕顔 p169六条の女君~183隣家と頭の中将
☆KUNKO
源氏の恋心は移ろいやすいのでしょうか?歳上で高貴な六条の君を口説いて口説いて自分の女にしたら、熱は冷めて、君の女房にチョッカイを出そうとしたりして。六条の君は気位も高いでしょうから、今後この女性がどのような態度に出るのかが気がかりです。
一方で夕顔の君の家に出入りするようになった惟光の報告を興味深々に聞いている源氏。
なかなか素性がわれない夕顔の君…。夕顔の君とは一体誰なのでしょうか?実は既に源氏と関係のある女なのでしょうか?
推理しても私にはわかりませんが、次回には判明するのでしょうか。
六条の君は、他の女には嫉妬したりしないのでしょうか。妻の存在も蔑ろにされているような気がします。なんだか、今回はヤキモキする巻でした。
☆葉
「夕顔」を読み始めたとき、「六条あたりの御忍びありきのころ、、、、」とあった。空蝉が忘れられずに思い悩んでいる源氏とばかり思っていたが、「六条の女」もいて、そこにも忍んで通っていたのかと、漠然と読み飛ばしていた。
今回「六条の女君」の箇所で、「六条の女」とはどんな人で、その恋の成り行きがどうなっているのか初めて明かされた。どうやら七才年上で、相当高貴な身分で気位も高い。初めはなかなか心を許そうとしなかったが、源氏の強引な情熱に押されてついに折れ、今や源氏の訪れない夜は気が滅入ってよく眠れないほど深刻に思いつめている。一方源氏は、いったん手に入れた恋に対してすでに冷淡になっている。
早朝、眠たげに女のもとを出ていく源氏には、もう女君のことなど心にない。早速「咲く花にうつるてふ名はつつめども折らで過ぎうきけさの朝顔」と中将の君の手を取り、思いを伝えている。侍童が朝顔の花を折り取って源氏に差し上げる場面では、みすぼらしい垣根に咲いていた夕顔の場面が対照的に思い出されてくる。
☆竹とんぼ
六条の女君が登場した。どのようないきさつで恋のお相手になったのかは不明だが、今は源氏の心は離れ気味。女君を訪れた帰りがけに、使用人の女房の美しさに気をとめて、歌を詠んでみせたりしている。
この時代の男性は忙しく、気が抜けないだろうと思った。
美しい女性と出会う機会があれば、歌など詠んでみて揺さぶりをかけてみる。恋の相手になったら、気持ちが多少冷めても訪れる義理は果たす。
当時の倫理観や価値観がわからないので、平安時代の暮らしがぴんとこないのだが、「あはれ」にしろ「かなし」にしろ、そこに美しさを伴うことが絶対の条件だったのかと想像する。
☆moonba
謎めいてた六条の女君がとうとう現された。源氏との関係する女性が現れるたびに源氏の性格に少しずつ驚きが見えてくる。振り向かせるまでに熱が入り振り向くと冷たくなるのは薄々わかっていたけど…今回かなりあきらかになった。
六条の女君は歳上と言う事に気が引けている。そして、繊細…これだから後々に続くのかと。
六条の女君の中将の君の忠実心と優秀さが心地よいくらいの切り返してくる。とても気になる女性の1人に加わる。
話は変わっての惟光のお茶目な感じ公の仕事に力入れ方とそれが程よく真面目でもあり熱心さのあまり若い女房と恋人になるって…笑える。
とにかく…源氏が心地よいくらい女性を幸せにする事に興味津々だ。
☆源氏のこころ
若やいでにぎにぎしく楽しげに始まった「夕顔の帖」であるが話は進展し、季節も巡る。
六条の女君の存在が知らされ、女君に対する源氏の掌返しの対応や花ある女と見るや声をかけずにはおられない源氏の性癖が明らかになる。そして源氏は鬱々としていたという。
品格と美しさは申し分ないが世間体を気にする籠りがちな六条の女君の人柄や前栽に漂う秋の気配、中将の君が纏う紫苑色の裳の美しい秋色感などがちりばめられて美しくも寂し気なムードが漂う。
秋色が濃くなり冬へと向かう季節、何が起こって来るのかやや不安な気持ちにさせられながらもその展開に惹きこまれた。
それにしても紫苑色の襲とはさぞかし美しい衣装だったのだろう、と強く印象に残った。
2021-9-15? 夕顔 p156惟光隣家を探る~168伊予の介と対面す
☆KUNKO
惟光の活躍により、少しずつ夕顔の君の姿が見えてきました。やはり美しい人でしたが、どこか〈もの思えるけはひ〉で周りの女房達も〈忍びてうち泣く〉様子のようです。
こんな情景を聞いたら、源氏でなくとも興味津々、頭の中で大妄想してしまいます。
お話しは、このまま進むのかと思いきや伊予の介が源氏のもとへとまいりました。
源氏は伊予の介を目の前にして空蝉を想い、伊予の介の娘とのこと一夜のコトも思い出すのですが、空蝉と会えなくなるとわかると何としても会いたい!って思ってしまうのですね?。
源氏の生きがいは恋することなのでしょう。全てのエネルギーは、恋することに注がれているように思います。普通の人々には、真似する事が出来ない生き方。それ故に、長い年月を読み継がれているのではないのでしょうか?
夕顔、空蝉二人の女が同時に気になってしまう源氏??
今後の展開が楽しみです。
☆葉
今回、夕顔の巻でありながら印象的であったのは、伊予の介が、任国である伊予の国から京都に戻り、源氏の下に挨拶に出向いた場面であった。伊予の介は京都に妻子をおいて伊予の国に出かけていて、船路で帰ってきたとのこと。伊予の介の主人に当たるのが、源氏であり、源氏も日常的には任国の報告を聞くなどの仕事をしているのだということ。当時の読み手にとっては当たり前のことであったのだろうが、こういった描写から改めて納得した。
ここで面白いのは、真面目な報告を受けながら、「伊予の湯桁はいくつ」などと尋ねたい衝動にかられているところだ。主従関係とはいえ大の大人を前にして、その報告を聞きながら、その妻への思いに悶々としており、娘とも一夜を契ってしまった源氏が、奇妙な感情に支配されて、いたたまれない気持ちになっている様子が伝わってくる。空蝉の巻きで碁石をてきぱき数える姿から道後温泉の湯桁を数える姿を連想した場面が伏線となり、当時から有名であった伊予の国の道後温泉の話が面白く重なってくる。
さて、この巻は夕顔であった。ふと、前の巻きに引き戻された感じである。
☆竹とんぼ
空蝉の夫、伊予の介が任地から都に戻ってきて、主人である源氏のもとに挨拶と報告に参上した。伊予の介は、娘には後見の男性を定め、妻を任地に連れて行くことを源氏に申し上げる。
作者は、伊予の介が人品いやしからぬ、それなりの品格をそなえた男性であることを説明している。
また、源氏と空蝉は再び結ばれることは無かったが、源氏からの手紙に、空蝉の女君は時々返事を返していたとある。源氏の心はともかく、読者としては四方それなりに納まってモヤモヤが残らない。空蝉が心にスッと落ちる、よい終わり方だとおもった。
☆moonba
今回は惟光が源氏を喜ばせるための計らいが楽しい。自ら調査までして、それを惟光も楽しんでる様も面白い。始めの頃の『雨夜の品定め』が再度出てきたとは…へぇと。
この時に男達の会話がなんと無邪気なのかと貴族はとても平和なのだと思った事を思い出しました。
やっと夕顔の様子が少しずつ見えて来たと思ったら空蝉の話が戻って読み手のこちらは切り替えに少し戸惑った。けれど、どうなったかと気になっていたのでまたワクワク心が持ち上がる。
空蝉の夫の伊予の介の人柄がいい方とわかると少し気の毒にもなるのもなんとも。
空蝉の揺れる女心はわからなくもない。気にして欲しいからと軽くあしらうような返歌が源氏の心をつかむ…やはりの行動。
伊予の介の娘の方と空蝉の対比で源氏の気持ちがよく表していると思えました。
☆源氏のこころ
雨夜の品定めは源氏の恋の対象となる女性の範囲をぐんと広げるための伏線だったとは、ここでも作者の構成の巧みさと深謀遠慮に舌を巻いた。
源氏や頭の中将、佐馬の頭をはじめとする男性貴族にとって恋はその存在をかけるほどに価値のあるゲーム・勝負であったようだ。
一方、女性も同様に楽しんでいただろうと想像するが、中には恋や結婚が一生を左右する(とくに経済の面において)生存をかけた戦いだったのではないかと思った。空蝉や常夏の女のように。
2023-5-17? 夕顔 p306女君の身の上(続き)~p316それぞれの追慕
☆竹とんぼ
ここで夕顔が遺した女児の消息が、右近によって語られる。
源氏はこの遺児をひそかに育てる決心をするが、このことが何らかの争いごとの種になるのでは? などと読者としては妄想してしまう。
源氏物語は、その後の展開で「あぁ、あのことか」と思い至る伏線が随所に配してある。
まだほんのさわりを読んだだけなのに、今後の成り行きまで妄想し、それがまた楽しい。
☆葉
源氏と右近、それぞれが今は亡き女君のすばらしさを思慕の情あふれるままに語り合う。
<あやしく世の人に似ずあえかに見えたまひしも、、、>と源氏
<ものはかなげにものしたまひし人の御心を、たのもしき人にて、、、>と右近
田中先生の著書『イメージで読む源氏物語』から、言葉を拾わせていただくと、
「人並外れた敏感な感性をそのまま表したようなあえかさを感じさせる人だが、主従の関係
を超えて穏やかな温かい雰囲気で接する人間的な魅力もつ芯の強い人」といった人柄が浮か
び上がる。
源氏はさらに、語り続ける。
「打てば響く柔軟な心の女に初めて出会った。やわらかい雰囲気が悩みがちな心を慰め解き
放ってくれた。理性で身を固め容易に人を受け入れようとしない女と向き合っていると一方
的に気を遣うだけで楽しくない。その点、女君は相手に気を遣わせまいと、深い心の葛藤を
かかえながらも一途に信じ、寄り添ってくれた。女の心をもっと深く知り、打ちとけたかっ
た」と。
まさに、式部がこの時代の理想とする女性を描いているのだと初めは思ったが、いやいや
私もこういった男性に出会ってみたいと思う。時代を超え男女を問わず優れた者を、見抜く
式部の洞察に感じ入った。
☆KUNKO
夕顔が亡くなってから漸く夕顔が十九歳であったこと、幼子が京の西にいる事などを知った源氏。十七歳くらいで産んだ子ということですよね。中将が通っていたのは十六歳くらいでしょうか?
その年齢の女性が一人前として認められていたということでもありますね。
今は右近と亡くなった夕顔を偲んで恋しいと思う日々なのでしょう。亡くなった人は美化
されるものでしょうから、きっと夕顔は理想の女として源氏の中で生き続けるのではないで
しょうか。
夕顔の忘れ形見は、中将の子でも有るのですから本来であれば、姫君として養育されるべ
きでしょう。一日も早くその子を手元に引き取って右近の傍で養育して欲しいと思います。
☆源氏のこころ
「深まる秋の庭とそれを見やる右近の描写が美しく印象的だった。
乳母子の夕顔にぴったりと寄り添いしたがって苦労を重ね、心身ともにズタズタになって
しまった右近にようやく訪れた静かで落ち着いた時間。まだ若い右近であったが人生の秋を彷彿とさせるような庭の描写がしっくりくる。
久しぶりにゆっくりと深く話をする源氏と右近だが、中将に内緒で夕顔の娘を引き取ろうという算段に、また一波乱起きるのではないかと次の展開を想像してしまう。
読者に緩急を与える技はいつもながらお見事です。
021-7-21? 夕顔
p143病気見舞~155扇の歌
☆KUNKO
乳母が源氏にとってかけがえのない人だということがよくわかりました。育ての母のような存在なのですね。その乳母の為に自分が出来る事うることをテキパキと指示する辺りも並の人間ではないのでしょう。
しかし、目下の関心ごとは、小家の女です。扇の移り香、流れるように美しい手の書。
そして、大胆にも源氏を名指ししている内容の歌。
何故このような小家に品のある女が住んでいるのでしょうか?何人もの女達も居るようですし。この小家には、どんな謎があるのでしょうか?歌を送ってきた女の姿形は如何なるものでしょうか?
源氏にとって気になる事が次から次へと湧いてきます。それは私も同じです。
次に源氏はどの様な行動に出るのでしょうか?
惟光は、「また、始まった…」と思いつつも源氏の為に最善を尽くすのでしょうか?惟光の活躍も気になってきました。
今回もまた、読者を惹きつけてならない物語の展開の素晴らしさにすっかり心を奪われてしまいました。
☆竹とんぼ
源氏は、乳母の見舞いに行き、乳母の子供たちが集まっている一室で、乳母と涙ながらの対面する。源氏の衣の香りで、居並ぶ子らは、源氏の高貴さや、源氏がたぐいまれな存在であることを得心する。
源氏の身分素性を元々知っていたのに、心の納得は香りによってもたらされる。香りは深く情動に作用して、情報伝達する。現代のように視力が中心の情報獲得は、心からの深い納得感を犠牲にしているかもしれないと、思いました。
☆moonba
今回は文をくれた女、六条の女、夕顔の家の主…謎めいて先が気にならせるところで終わった。いつもながら面白かった。特に謎めいて面白かったのは二つある。
平安のルールは文は男からと知ったがそれなのに夕顔の花と一緒に女からの文。
源氏とわかっていたからこそなのだ。出会うきっかけをつくろうとしたのか?
それとも源氏をからかっているのか?!
扇は香り、筆跡を変えて送る文は余計に謎めいて気になる。存在をアピールする作戦かしら?
そしてもう一つは面白かったのは身分低い宿守の登場のさせ方。微妙な情報で源氏や読み手の想像をわざわざ撹乱させてくる。謎めく事で想像は確信ない妄想となって広がり放題となった。
☆源氏のこころ
美し過ぎる源氏の登場に小家の女たちがにぎやかに騒いでいる様子は、アイドルを遠巻きにして興味津々近づきたい知りたいとキャーキャー興奮する若い女の子たちのように華やかで楽
しい。貧しくはあっても暖かい空気が感じられる。
それに関心を示す源氏を冷ややかに、やや心配そうに見やる惟光と語り手の存在がまた面
白い。小家にあってこじんまりとこざっぱりと楽しげにセンス良く暮らしている様子の女が自分に関心を持っていると知って興味を示す源氏の気持ちはわからないではない。
一方の六条邸との対比が際立っている。木立前栽をはじめとしてスキのない垢抜けたたたず
まいは女の品の高さの象徴のように語られ、クールで美しい女人を想像させる。
「お膳立てはそろいました」というところ、進展は如何に?毎度のことながら読者を惹きこむ手法はお見事である。
021-6-25? 夕顔
p132夕顔の小家~142病気見舞
☆葉
《いと青やかなるかづらの、ここちよげにはひかかれるに、白き花ぞ、おのれひとり笑の眉ひらけたる。》 黄昏るほの暗い中、貧しい家の軒先で楚々と笑いかけるように咲き開く白き花に源氏は目を止める。そして《一ふさ折りて参れ》と命じ、手元に花を引き寄せてつくづくと眺めてみたいと思う。
夕顔の巻はまさに花の描写から始まる。千年前に源氏が心を奪われた夕顔とはいったいどのような花だったのか、思わず調べてみたくなる。
ユウガオは、アサガオやヨルガオと違いウリ科の植物で花を観賞するためでなく、古くから庶民が栽培する野菜だったとある。家にある花図鑑でよく見ると、五つに裂けた花弁は絞りがかかり、中心のしべが優しくのぞく。
さて話は続く、手折られた花一輪がそのまま源氏の手に渡されるところを思い浮かべたが、なんと《白き扇の、いたうこがしたるを、「これに置きて参らせよ。枝もなさけなげなめる花を」とて、取らせたれば、、》とある。持ち主の香が深くたきしめられた扇にのせられて渡されるとは。なんと粋なことだろう。
扇の持ち主がどなたなのか、たまらなく気になる。
☆さくらちゃん
尼になるのは病気でしかも重篤な状態の人がなる場合もあるというのはとても驚きました。
今ならホスピスでなるべく苦しまず最後を迎えるという手段がありますが、この時代は仏の
道に入り 心の平穏を求めて最後を待つというこの時代ならではの心のホスピス的なものがあった事に驚きと素晴らしさに感動いたしました。
☆KUNKO
源氏は乳母が尼(重病)になったのでお見舞いに訪れることにしました。乳母の家は五条の辺
りにありますが源氏はその様な場所に来た事などなく…。乳母の家の門が開くまでの間に好奇心がむくむくと持ち上がるのです。隣家の中の様子が見えて、「をかしき額つきの透影、あまた見えてのぞく…」のです。源氏は見たこともない白い花を見つけて一枝所望するとこの家の女
の童が香を焚きこめた扇子を持ってきます。その花の名は、夕顔。
ここで場面は、惟光の家つまり乳母の家へと移ります。病を得てスッカリ心細くなっている乳母に源氏は長生きして源氏の位が高くなるのを見届けて欲しいと励ますのです。源氏の優しさが伝わる場面です。
源氏は夕顔の咲く家を〈ものはかなき住まい〉と思うのですが古歌を引用して「何処かさして、と、思ほしなせば、玉の台も同じことなり」などと思うあたり、源氏は決して思い上がった人ではなく、人情のある人なのだなぁと思いました。
先生は、ロマンティックな巻ですとおしゃってましたがいつにもまして光景が目に浮かぶようです。夕顔の咲く家の佇まい、女の童の着物の描写など描けるものであれば描きたいと思う場面です。それと、源氏の旺盛な好奇心と観察眼の鋭さには感服しました。
次回が待ちどうしいです。
☆竹とんぼ
源氏が乳母の見舞いに訪れると、乳母の家の臨家の垣根に、夕顔の花が咲いている。
板塀に緑深い蔓草が這い、そこに咲く夕顔の花の白さが際立っている。
静かな美しい情景描写だ。夕顔の清楚さ、小家に咲くつつましさが読者の印象に残る。
源氏に所望され、供の者が夕顔の花を手折ると、小家から女の童が出て来て、白い扇を差し出す。扇には香が焚き込められている。この扇に夕顔の花を載せて源氏に渡すようにという趣向だ。「美しさ」を、大切に丁寧に味わう優雅さに惹かれる。
日々の自分がセカセカしているのが、情けないなぁとおもった。
☆moonba
始まりは京の街、謎めいた六条と五条から。乳母の見舞いをきっかけに始まりでは…恋とみた。白い美しい夕顔は新鮮で好奇心をそそわれる花(人)となると妄想でいっぱいに。
扇の香りと袖の香り…香りがにくいくらいに演出されてるなぁ。
先を読み進めたくなる。中流階級の暮らしぶりは源氏と共に興味しんしん。
乳母(母)への優しさは実子よりも源氏の母への愛のこだわりがせつなく気になる。
カッコイイ男は言葉のセンスもめちゃくちゃいいのだなぁ?
私も屏風の内から覗き見したいと思いました。
☆源氏のこころ
いよいよ夕顔の巻、「額つき・見入れのほどなく・玉の台・遠方人・真秀と片秀」等聞き慣れないことばが耳に残り、興味深かった。
また女を訪ねるついでとはいうものの母代わりに育ててくれた尼君を見舞う源氏の心境が痛々しいと思った。幼い時期に母、祖母を亡くした17歳の源氏にとって、今また肌感覚で親しい人を失おうとしている、相当に辛いことだったろうと思う。
ところで、六条辺りの女とは「六条御息所」のことでしょうか?
2021-3-26?
空蝉 p112人違へ~うつせみの心p129
☆葉
西の御方を仕方なく口説く源氏、必死に身を隠して邸を抜け出す源氏。その時々の格好の悪さと真剣さが滑稽でもあり印象的だが、何といっても最後の畳紙に書きつけられた歌のやりとりが見事である。薄衣を手に、どうにもならない思いで畳紙に書きつけた源氏の問い歌
《うつせみの身をかへてける木のもとに なお人がらのなつかしきかな》
は、正式な後朝の文ではないけれども、小君を通して女君の目にするところとなる。
そして空蝉は、空蝉で源氏に知らせることなく封印しようと熱い思いを、その畳紙の片隅に書きつける
《うつせみの羽に置く露の木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな》
どろどろと熱くせつない恋心が、美しく昇華されていく。「空蝉の巻」はこの一首でぷつっと終わるが、それだけに、余韻はいつまでもいつまでも続く。
☆KUNKO
西の君は、少しボンヤリなのでしょうか?
この後も、源氏からの手紙を待ち続けるのではないのでしょうか?
小君を見かける度に言いたいのに言えない…って悶々とするのではないのでしょうか?
少し哀れな気がします。結婚すればスッカリ忘れてしまうのでしょうか…。
次の場面には、腹痛の老女も登場して物語にリアリティを感じさせられました。(他の訳者ではカットでしょうか)
今後の物語には、小君はもう登場しないのでしょうか?成長した小君の姿を見てみたいです。
脇役でありながら、重要な役割を果たした小君の健気さが一番心象に残りました。
大人達の恋の駆け引きや、やるせなさなどを経験して彼はどんな大人になるのでしょうね。
空蝉の頑なさに少し意地になっていた源氏…という風にも思えました。
いつか、源氏はやるせない空蝉の思いを知る日がくるのでしょうか?
やたらと?が多くなりました。
☆竹とんぼ
源氏はこの度の忍び込みも成就せず、とにかく女君の家からさっさと出ていきたい状況だが、
手引きをする小君ともども女房に見とがめられたり、女房が腹下しをしていてつらいと愚痴ったりなど、ここは雅の源氏とは別世界のドタバタ劇とスピード感のある描写だ。
《空蝉》は源氏と女君が結局結ばれないまま、それぞれが交すことのない歌を詠んで終わる。
最後の余韻に読者はあれこれ想像をせずにはいられない。
緩急のある展開で物語から目を離すことができない仕掛けに、私も捕まってしまった。
☆moonba
うひょ?って感じで終わってしまった。空蝉らしい終わり方なのかしら…
1人の女性像がしっかりしてカッコいい終わり方にスッキリしたが驚いた。
詠まれる詩の面白さが少しわかって来た。衣と抜け殻。涙と雫。
胸の内を揺るがす、品格とプライド。そして行動をも変える。
身分を踏まえた事ですべてを美しい思い出に…これも幸せなのかもなぁ。
現代小説を読んで語り手の存在に楽しさを感じるのは余りなかったが紫式部は読者のようにこちらで一緒に同感してるように感情を揺さぶる。
☆源氏のこころ
今回も緩急やエンターテイメント性を上手く配した文章に読まされた感が強かった。
「後達をまく」では源氏の存在がばれてしまうのではないか、とドキドキシーンの後に後達の事情が語られ、気の毒に思いつつも「あな腹々」に爆笑してしまうと同時にかろうじて脱出成功、となる。小君はどれだけホッとしたことだろう。このスピード感と展開に読者は乗せられ
て楽しくついていける。
西の方のその後も放っておかずに記し、源氏の想いと女君の伝わらない哀しい心情を描いて
「どうなっちゃうんだろう???」と不安な読者を置き去りにぷっつりと終わってしまう。
空蝉の巻を読み終えて、やはりこの女性は作者の大きな分身なのだという思いがますます強
くなった。
2021-2-26? 空蝉
p102小君たばかる~人違えp110
☆葉
女(空蝉)は源氏に心を奪われ、源氏の面影に苦しみ、あぶられている。いつものように眠られぬ夜を重ねているところへ、ひときわかぐわしい匂いが漂ってくる、この懐かしい香りはまさに源氏。恋する女の研ぎ澄まされた感覚は、すぐさま察するのだが、《生絹なる単を一つ着て、すべり出でにけり》とある。二度と逢うまいとする強い意志は、女にためらう間すら与えない。深い矛盾に身も心も引き裂かれている女の運命に想像を超える痛々しさを感じる。
さて、「女は身を隠した」で終わるなら前回と同じ展開だが、帳台に忍び入った源氏は臥している女を見てほっとする。が、寝ていたのは《いぎたなきさま》の義理娘。夕方の「かいま見」は伏線になっている。読者を引き込む展開の面白さに思わず感心してしまう。 誰が誰かもわかりかねる千年前の深い夜闇に思いを馳せてみた。そんなこともあったのだろうと。しかし語り手も《わろき御心浅さなめりかし》と非難の言葉を忘れていない。
☆さくらちゃん
今回頭に残った言葉
いぎたない←→いざとい
自分はいざとい人でありたい…
「うち身じろき寄るけはひ」暗くても香りで源氏だとわかってしまうその当時の上流階級の人々の香りとはどんな香りなのだろうか…
その中でも 源氏の香りとは…かいでみたいものだ♪
すぐそばまで毎晩想いを馳せていた源氏がいるのにとっさに素早く逃げてしまう空?の理性は素晴らしいと思う。
☆KUNKO
源氏がお目当ての女君の母屋へ行く場面ですが…女君は源氏の気配を察知して母屋からすべり出てしまうのです…
さて、自分が女君の立場であったのならばどうしていたのいたのだろうかと想像してみます。
源氏の気配を感じても空寝をして待っていたであろうか?しかし、隣には西の方が寝ているのだからそれも出来ないし…あら…困ってしまう…やっぱり女君のように出てしまうのかもしれない別室があって此方へどうぞ…とはいかないでしょうし。
ここまで書いて、女君は隣で寝ている西の方のことまでは気が回らなかったのだわ!
それほど慌てていたのだと気がつきました。西の方を残してくるということの重大さにまで
思いは至らなかったということでしょう。しかし、この後の源氏の行動を推察すると…
女君の気持ちが源氏に伝わっていないということが一番悲しいのではないかと思いました。
☆竹とんぼ
源氏は「この度こそ」の成就を目指して3回目の忍び込みを小君の手引きで決行する。
結局、女性は源氏の気配を察知して生絹の白単衣だけを着た姿で寝所から逃げ出す。物語の進行とともに当時の生活様式の描写があるが、場面を絵のように思い描くには私の知識が足りなくて残念。
帚木(空蝉)の女性とその義娘が寝る場所の一段下には女房が二人寝ている。。。部屋はいったいどのような構造なのか?
几帳に上衣を掛けてついでに目隠しの用もなすのは便利だと感心する。着ている衣を身体に掛けてそのまま寝てしまうのは、夏とはいえ簡便でよい。小君などは、畳表のような薄敷きを広げて廊下のようなところに横になってしまう。当時の寝支度は簡便で人数の多少にもとらわれず、何だか羨ましいと思いました。
☆moonba
小君の子供なりの大人びた様子、源氏の大人になりかけていて子供のような様子の対比的な
心持ちが伝わる。
語り手が読み手に詳細を伝えるだけではなく、読み手のドキドキハラハラの感情をゆさぶり盛り上げたり、読み手の気持ちを抑えたりと…語り手も登場人物の一人となっているのが面白い。
灯りも充分で無いこの頃は気配に敏感なのだろうなぁ。身分から来る衣の素材の違いが音も
香りからも感じとれるとは。読み手の頭には音が想像出来てそして香りまでがたってくるよう
に思えた。
今回終わって、これからの目的がひとつ増えた。『美しい原文を美しく詠む』
☆源氏のこころ
小君と源氏のやり取りが面白かった、緊張感がある場の設定や内容にもかかわらず言葉のリズムが流れるように軽妙で、音の響きが美しいと感じた。
「たばかり」に真剣な小君に対してやや軽口を叩いているような遊び心を感じさせる源氏の言い様や態度がそう思わせるのか、あるいはテンポの良い短い台詞回しのせいなのかもしれない。
完了形のこと、昔は「時制」を表す助動詞が「き」「けり」「つ」「ぬ」「たり」「り」とたくさんあり、「き」「けり」が過去を表しているのに対し、「つ」「ぬ」「たり」「り」は完了を表していたそうだ。どのように使い分けていたのかわからないが、平安貴族の人々は言葉も感性もとても細やかだったのだろうと思う。
2020-11-18? 空蝉 p91碁打ち~かたちくらべp101
☆葉
原文の響きを心地よく耳にしながら、源氏物語図屏風に描かれたまさにこの場面を見入る。平安時代の姫たちは、碁を打ったのかと印象に残っていた図絵である。
しかし読み進めるうちに、格子の手前に佇む源氏の姿がクローズアップされてくる。そして女たちをみつめる源氏のまなざしに驚かされる。そうなのだ、この場面は危険を冒して恋焦がれてやまない女に会うために忍び入り、主屋の様子がかすかに見えるめったにない機会を得て盗み見している一瞬が描かれていたのだ。
さらに度肝を抜かれるのは、この源氏の観察眼。冷静に対照的な二人の女を見比べる。意中の女のことを髪の毛はそれほど豊かでなく、小柄でぱっとしない、貧弱な手つき。さらに目も腫れて鼻筋も通ってないという。そこまで言わなくてもと思うが、それを補ってもあまりある魅力的なしぐさに目を魅かれると結ぶのだから、私の源氏像はますます揺らいでしまう。
☆さくらちゃん
「碁打ち」の所で人前で肌をさらさない時代のため、碁を打つ相手にもお顔を見せないように覆い、手先までも覆い隠している様子は「やりにくそう…」と思ってしまう…。そして相手が女性であっても同じというのがびっくりした。
今回のヒット単語は「ねぢける」と「ねびれて」ねぢけた性格になるのも嫌だけどこれからどんどんねびれて行くのも悲しい…「目すこし腫れたるここちして、鼻などもあざやかなるところなくうねびれて、にほはしきところも見えず」のところで源氏は見た目だけで女性を選ぶ様な印象が強いけれど、内面的なものもちゃんと見ている事がよくわかる。
☆KUNKO
今回の場面は「中の品の女二人が碁を打っている所を覗き見している源氏」から始まりました。私が一番驚いたのは、中の品の女とはいえ貴族の女性が(暑いからって)胸もはだけて碁を打っている姿です。もちろん、胸をはだけて碁を打っている女が源氏の思い人の訳ではありませんが、相手をしているその思い人だって、楽しそうに碁を打っているのですから。それを源氏は覗き見しているのです。考えただけでも信じられない図ですが、平安時代にもこんな女性が存在していたことにちょっとだけ感動しました。おおらかでいかにも現代女性の様な新たな登場人物に源氏と同じように興味を持ち惹かれました。
いつもは平安時代にワープして、離れた場所から盗み見ている私だったのですが、今回は源氏のすぐ傍で一緒にこの女性たちの「うちとけたる人のありさまかいま見」させていただきました。覗き見の一体感ともいう不思議な感覚を覚えました。
☆竹とんぼ
源氏が想いを遂げたい女性と女性の義妹が囲碁を打っている。
その二人の女性を、源氏は覗き見ている。当時の上流社会では女性の姿を直接見るのは無いことだったらしい。
源氏は小君の手引きで忍び入った女性の屋敷で「覗き見」の機会を得たが、この間小君は源氏のために屋敷内の状況を探ったり情報収集で奮闘しているのではないか?
女性に対する想いは本気だけど、覗き見のチャンスをのがさない源氏にどこか茶目っ気を感じる。一方小君は真剣に奔走していそうだ。
源氏と小君の温度差は何だろう?これは最上流貴族が身に着けているゆとりなのか???と感じました。
☆moonba
源氏の覗き見はドキドキ感が伝わった。
覗き見されるほど、男達の留守と暑さから不用心な様が描写で良くわかる。
空?と紀伊の守の妹の痩せ痩せとつぶつぶ肥えの碁対決。
源氏の好みは上品で知的好みは知ってたが髪にも拘りがあったとは。
見え難い格子の隙間から覗き見する源氏の姿も大人げな思考と子供っぽい行動の対比が面白い。
そして、覗き見の時間経過で印象の変わる源氏の《あはつけし》な男心もわからなくもないなぁ?
☆源氏のこころ
源氏の女性観が描かれる。ピチピチと豊満で美しく、表面的には何の欠点もない若い女と年齢相応に容貌も老け、お世辞にも美しいとは言えない女を対極に置き、碁を打たせてそのしぐさや態度、気配を源氏が観察するという見事な設定、源氏は身を隠しつつも好きなように覗き見、冷静に評価し語り「女性美は表面的な魅力よりも人目を意識した緊張感のあるゆかしい振舞いや物静かで思慮深い態度、内面からにじみ出る気配・品性にある。それらの特性がもはや美しいとは言い難い容貌を補って余りあるのだ」としつつ、溌溂としておおらかなもう一方の若い女も魅力的だと思ってしまう。そうした自身の性向をも「あはつけし」と客観的に評価、書き手に「若い女のことも捨てがたく思っていることでしょう」などとと言われてしまう。
しっかりとした女性観を持ちつつも真面目一方でなく浮気者気質も併せ持つ源氏の多面的な魅力がありありと語られ、面白かった。
以上
2020-9-16?
空蝉 p82それぞれの夜~三度挑戦p91
☆葉
三度目の挑戦である。子どもながらの小君の必死の手引きが何よりおもしろい。《夕闇の道たどたどしげなるまぎれに》ことを運ぼうとたくらむ。もちろん邸の主は任国に赴いている。そうか、「夕闇とはただ夕方暗くなって」と、思っていたが「月がまだ昇ってこないまさに暗闇」のことを意味しているのだ。千年前の闇の深さと月の明るさの対比を今更ながら感じ入る。さて、邸の東側の妻戸に源氏を立たせ、自分は南側にまわり格子戸を叩いて、注意をひきつけ、その隙に源氏を忍び込ませようという魂胆である。
資料として渡された寝殿造りの図面に見入りながら、「東の妻戸ってどこだ。」「どこの格子戸たたいたの。」と夢中になって探しているうちに、私もいつのまにか紀伊の守邸に忍び込んでいた。
☆さくらちゃん
空蝉に拒絶されたことを恥ずかしく思い これ以上付きまとうこともできず、夜中にひっそりと帰ってしまう源氏…ひっそりと帰られてしまった事に心複雑な空蝉…
この時代の身分による様々な複雑な事情の絡みが面白いけど難しい。
「女どちのどやかなる夕闇の道たどたどしげなるまぎれに、わが車にて率てたてたてまつる。」
「東の妻戸に立てたてまつりて、われは南の隅の間より、格子たたきののしりて入りぬ。」
小君の作戦がとても面白いしやっぱり今回も小君は可愛い。
次回 碁を打っている二人の女性に 源氏がどのような行動をとるのか! とても楽しみ。
☆KUNKO
女に拒絶された源氏の苦悩は、計り知れないものになっています。
小君に胸のウチを明かし力になって欲しいと思うのです。そんな、源氏の心に応えようと小君は知恵を巡らすのですが、源氏は自分勝手な行動に出てしまう…。
一方、小君の姉である女の方も自分の心に正直になれずに悶々としているようです。
目の前にそれぞれのキャラクターが動き出し、あたかも今、目の前で繰り広げられているような感じがします。その臨場感はリアルです。
源氏の行動も気になりますが、小君の活躍と成長を追っていきたい!と思うほど、脇役も生き生きと描かれているのです。だから、面白いのよーと今回も感じ入りました。
☆竹とんぼ
女君への想いを諦めるに諦められない源氏と、源氏を助けるべく奔走する小君のそれぞれがリアリティがある。
小君は12,3歳。子供時代に一区切りがついて、まるで老成したような様子を一瞬見せる年齢だ。それでも経験がないため実際の場面では右往左往してしまう。
源氏は17歳くらいか?ある程度の経験は積んでいながら、青年らしいエネルギーに引っ張られて分別無しの行動をしてしまう。
年少の小君が逆に源氏を庇護するかのような振る舞いをするところなど、式部の人間洞察の深さに心奪われる。
☆moonba
二人のその後。時の経過で起きる心持ちの時差による二人の表現が面白かった。
源氏の気持ち。逢いたい気持ちが悲しさから憎しみにもそして執念へと。
空?は拒否したものの音沙汰無しには心穏やかにはいられない。自分の源氏への想いに揺
れ動く。その合間で小君の動き。源氏を思い心配する様子が痛々しく思う大人びた所とわず
らわしくも思う所は子供らしい。
細かい描写が目の前に顔のイメージや気配や香りや色までも浮き上がるのは素晴らしくワ
クワクする。紀伊の守の妹の存在が源氏にどう関係するのか気になる。
☆J
源氏が空蝉との逢瀬のために忍び込んだが思いもかけずに空蝉に振られてしまい、その弟である小君に空蝉の姿を映しながら落ち込みひっそりと退出する様子
一方で源氏にひどい仕打ちをしたけれどこうするしかなかったんだと自分に言い聞かせながらも苦悩する空蝉の様子が描かれていました。
それでも諦めきれない源氏のために、面倒くさいなぁと思いながらも、また次に会う機会を必死で企てる小君のなんて健気なこと。
きっと小君の中には、源氏と姉が結ばれたなら、自分の得になるかもしれないなんて邪念は全くないことでしょう。
最後に西の御方が登場して今後の展開がますますたのしみなところです。
☆源氏のこころ
いよいよ空蝉を読む段になった、「空蝉」とは「蝉の抜け殻、魂が抜けた虚脱状態の身云々」
と辞書にあり、何か予感してしまう。
今回のエピソードでは何といっても「小君」が主役である。彼の源氏への思いや活躍が小賢しいところも含めて可愛らしくほほえましい。小君の行動の一部始終をテンポよく緊張感をもって活写し、読者を惹き込む技はすごいと感じた。
「夕闇の道たどたどしげなるまぎれに」について、
「夕闇」という言葉があることは小説や歌謡曲等で知っていたが、常に明るい都会では「夕闇」など現実に味わうことも言葉として使うこともなく過ごしてきた。
旧暦の20日以後は月の出が遅くなるという、因みに横浜の本日10月1日(旧暦8月15日)の月の出は17:29、10月9日(旧暦8月23日)は22:01となっている。
今晩は中秋の名月、俳句歳時記によれば月の清さは秋に極まるそう、しっかり観察して豊かな古代文化を感じてみたい。
また万葉集に「夕闇は路たづたづし月待ちていませ我が背子その間にも見む」という一首があった「夕闇は暗くて道がおぼつかないものです。月の出を待ってお帰りください、あなたよ、その間は一緒にいられるでしょう」の意。万葉の時代は「たづたづし」だったんですね、その頃は平安貴族と違って恋人の家を夕方退出していたのでしょうか?
以上
2020-7-15? 帚木 p68手引き~帚木の心p79
☆葉
女に会うためにはやはり「方違へ」しかないと源氏は用意周到に、細心の心遣いで事を運ぶ。さて今度はどのようなやりとりが、、、、と思いきや女は自分の寝所を出て身を隠してしまう。源氏の想いが本物であることを知り、自分の立場を《まばゆければ》と感じる女。「逢いたい。感情のままに身を委ねてしまいたい。だが、夢見心地のあとに襲ってくる耐え難い悲しみ、、、」さんざん思い乱れたあとの決心だったのだろう。
源氏と女の激しく燃え上がる感情は抑え込まれ、恋の悲しみが歌に詠まれる。
「帚木の心を知らでそのはらの 道にあやなくまどひぬるかな」
「数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さに あるにもあらず消ゆる帚木」
皆が寝静まった夜更け、歌を持って歩きまわる小君の姿が浮かんでくる。
☆さくらちゃん
また「例の」方違いの手を使い空?に会おうとする源氏
そうとは知らず「遺水の面目とかしこまりよろこぶ」紀伊の神…
かわいそうだけど おもしろい!
「渡殿に分け入りて」のところの小君が源氏の役に立ちたい思いで必死で「分け入りて」姉を探す姿が目に浮かぶ。
小君はともかく源氏の役に立ちたくて でも姉によって思ように役に立てず 慌てふためく小君がかわいそうだけど とても可愛いかった。
☆竹とんぼ
女君は伊予の介の妻という自分の立場では源氏の想いを受け入れられない。
中品の身分に落ちた自分は、高貴な源氏とあまりにも不釣り合いで惨めな気持ちになるのが分かりきっている。
後々までその惨めさに苦しむか?ひと時のきらびやかな思い出で後々を過ごすか?
美しい思い出にただただ酔って暮らせる自分ではないことが、女君には分かっている。
この後の長い年月、女君とは教養が違う周囲の人たちと共にこの女性は生きていくのだ。
文化が違う人たちと生きていくのはつらい。
女君がこれからもこの環境で生きていくことを想像すると、源氏との恋が実る実らないよりもやるせないと感じる
☆moonba
源氏は上手く家に入り込めたのに空?にはこばまれるとは。
何故、空?は会うことすらせずにこばむのかなぁ?。
高貴な源氏に寄り添って生きる人生もあろうに…。
自分が今ある立場に落ちてしまった事に対してプライドが許さないのであるのか…。
もうほんろうされる人生を避けたいのか。
最後は小君とほのぼのする源氏が落語のオチのようで面白いかった。
☆源氏のこころ
空蝉の返歌は「帚木はとるに足らない貧しい在所に生えて身動きできないでいることが辛くて仕方がないのです、世が世ならあなたの気持ちを受け容れて生きるという道もあったかもしれない、けれど中品の身分に成り下がった今、その選択肢はありません。お逢いする度に天国と地獄を見ることになるのですから。
こんなふうにしてあなたの私に対する真心と思い切った行動を有難く感じ、受け止めながらも切り捨ててしまわざるを得ない私は、生きている甲斐もなくはかなく消えてしまう帚木そのものなのです」と言っているようで哀しい。
そういう空蝉だからこそ惹かれながらも彼女の真意をくみ取れずにジタバタする世間知らずの源氏がもどかしくまたやや滑稽にも見える。幼いが賢く姉に似てきりっとしたところのある小君が、捨てられた源氏を「あなたが大好き」と癒してくれる。優しい草子地が「つれなき人よりは…云々」と言う。「こうして源氏はまた少し大人になっていくのでしょう」と述べているように感じられた。
☆J
今回は女君のところへ会いたさ一途に「方違へ」と口実をつけて紀伊の守邸を訪れる源氏から身を隠す女君が描かれていた。
一夫一婦制にこだわらない現代人から見ると奔放とも思われる結婚制度で、源氏ほどの身分の人の思われ人になることは名誉であり、隠すというよりはむしろ公にする、少なくともほのめかしてもおかしくないところである。
女君は教養や理性が優っているからこそ、身分違いの自分がそのようなことになることを自分自身で良しとしない、ということは授業でわかったが、今回感想文を書くにあたり読み直してみると、源氏自身も自分の行動を人に知られないように「方違へ」にかこつけたり、女君のお付きのものではなく小君に頼って接触をはかるなど、2人の仲を隠そうとしている様子が窺える。
既成事実として容認されるまでこのような行動様式を取るのが普通だったのか、それとも源氏との仲をすんなりと受け入れない女君の気持ちを憚ったことなのか?
巻名のははの木という言葉がやっとでてきた。次巻はいよいよ空蝉。
楽しみです。
2020-5-15帚木
p56したごころ~にわかの文~p68使者小君
☆葉
女君が抗うことのできぬと感じる《宿世》。釣り合いのとれない立場では、源氏の思いを受け入れることなど到底できない。プライドが許さないのである。切ない思いをもって心の奥に閉じ込めた恋心、その不憫さが益々源氏の心に火をつける。主張するところは主張してなおたしなみをわきまえていた女君の振る舞いは鮮やかに蘇り、源氏はもの狂おしい心の状態から抜け出せない。女君の辛さも十分承知でなおなお追い続ける源氏。
続きが読みたくてたまらぬ当時の人々の気持ちに私もなってきた。
☆さくらちゃん
源氏と「姉弟」の3人の関係性、やりとりがとても面白かったです。
「かかる御文見るべき人もなしと聞こえよ」こんな手紙を見る人はうちにはいません。と一切を否定する姉に対し、源氏への返事を迫る弟…幼くて純情な弟がとても可愛く思いました。
「あこは知らじな。その伊予の翁よりは先に見し人ぞ」などと源氏が弟の気持ちを取り込むための作り話が面白かったです。
☆KUNKO
恋する源氏なのに思い人は文も返してくれない…とうとう、女君の弟に作り話までする始末。一途になると、あらゆる手を尽くそうとするのですね
というのがよくわかります。一方女君の胸中の苦しさも伝わってきますし…
次の展開がとても気になります。
☆竹とんぼ
源氏は一夜の契りを結んだ女君を忘れられず、手紙を何度も届けるが、女君は今の身分も含めて、源氏と自分が釣り合わないと承知して源氏の手紙を無視し続けている。
女君は源氏の家臣筋の男に、身分を下げて後妻となっているが、出身は上流の出だ。
女君の拒否は自らのプライドによるのであって、不倫の罪悪感からではない。不倫という概念はこの時代には無かったそうだ。結婚しているものが他の相手と通じることを罪悪とする制度ではなかったようだ。
制度はなかったけれど自分の女(男)になっているのに他の男(女)と通じるのは、嫌だったり腹立たしかったりする感情は勿論あったはず。ずっと自分だけの女(男)でいてほしい、とも思ったはず。
そのような感情と折り合いをつけながら生きるのは大変ではないのか?と制度に守られる現代の私は思います。
☆moonba
空?の高貴で品格があり聡明さは素敵。源氏との一夜でお互いが惹かれ合うのは感性、感覚で触れ合えはわかる持ち主たち。そして離れ難く、また逢いたくてならない。どちらもが…。
2人が今後がどうであれ、そんな方に巡り会えたら素晴らしいなぁ?源氏は単純に好きだから逢いたい。空?は色々な心葛藤で逢いたいけど拒む。恋が人生、命がけ…人生の問題がこことは。シンプルでロマンチックでまぁ?いいのかなぁ??
☆J
今回の部分で、「顔も見たことがなく、歌のやりとりもしていないのにこんなに恋焦がれる気持ちがわからない」といった私でしたが、源氏と空蝉の一夜のやりとりの部分の授業に出ていなかったことに気がつき、その後田中先生からご親切に補講をオファーしていただきまして、昨日zoomレッスンしていただきました。
押し入ってきた男のありきたりな恋の告白に容易になびかず、自分の立場を鑑みて身分違いな関係と、自分の思いをキッパリと伝える様子やそう言いながら、一夜だけと思い切る空蝉の心の動きがよくわかりました。
それにしてもこの時代の恋愛については謎ばかり。
人の噂や和歌の上手さ、焚き染めた香や重ねた衣のテイスト、
字のうまさ、そして親の地位など。
もちろん現代の恋愛にもこういう要素は人を好きになるのに大きいものではあると思うけども、それよりもパーソナリティが恋に落ちるのに必要不可欠であるのに、どうもその部分は後からついてくるもののように思われる。
きっとこの違和感は源氏を読みつづけるのに付き纏うと思うけども、田中先生の講釈を聞きながら、出来る限り平安の人々に心を寄り添った形で、これから先も読み進めていきたいと思います。
☆源氏のこころ
空蝉は源氏に心惹かれているにもかかわらず、何故ここまで拒否の態度を貫くのか?プライド故・独特の美意識故?そんなに強い心の持ち主なのか?謎だった。
週刊朝日百科にヒントがあった。
「帚木」とは「遠くからは見えるが、近寄ると見えなくなるという伝説の木のことだそうだ。紫式部がこれを巻名に持ってきたのは、空蝉を遠目には凛として美しく、その魅力に惹かれて近づく男をするりとかわしてしまう女として登場させたかったからだろう。
気高くあらねばならないとの美意識を大切にする彼女にとって、昔はともあれ受領の後妻となった今の自分と身分も見映えも光り輝く源氏の君、身分違いの恋の屈辱を潔しとしなかったのは当然の帰結と言えるかもしれない。自分の美意識・矜持を護ることはどんなに魅力的な男との恋よりも大事だった。
十二単よりも重く固い美意識・矜持を身に纏った空蝉はさぞかし生きづらかっただろうが、彼女の内面的納得や落ち着きは想像でき、クールで気高く印象深い人物として心に刻むことになった。こうした美意識・矜持は作者も共有していたのではないだろうか。
2020-3-13
帚木 p48夫の面影~p54したごころ
☆葉
一番鶏が鳴く。源氏はこの女と再会するために、どんな手立てがあるだろと胸が締め付けられるほど辛い。がしかし一方女の方は、伊予の介の妻の立場に戻らねばということ以外何も考えられなくなっている。しかも夫への申し訳なさではなく。
『源氏物語』に描かれる初めての源氏の逢瀬が男と女の異なる心理のあやをくっきりと描いていることに引き付けられた。
☆さくらちゃん
男性と女性の考え方の違いは今も昔も一緒…
女性はいつの時代も現実的。男性は夢を見続ける…
そして源氏の空蝉の弟をてなづけようと言う考えが「さすが!」と思いました。
今回も「一夜限りの関係でOK」ではない源氏の本当はプレーボーイではないと言う一面がありとても楽しく読ませていただきました。
☆KUNKO
「伊予のかたの思ひやられて、夢に見るゆらむ」の一文に心惹かれました。「思ひやり」が「思いを遠くに投げる」「気を飛ばす」と言う意味である事。「夢にや見ゆらむも」夫の夢に自分の心が現れるのではないかと心配する様であったり。共に「思い」が相手に届く時には「波動・エネルギー」として届いているということをこの時代の人は実体験として知っていたのではないかと強く思いました。
現代人よりも人の思いや念を感じとれる敏感な感性を持ち合わせていたからこその表現なのだと思いました。
☆竹とんぼ
前回で光源氏は紀伊の守の若い義母と、一夜限りの時を過ごした。
恋が始まったばかりなのに、その後会うことも手紙を送ることもできない状況に源氏の未練心がつのる。
源氏は「(相手の)女君もさぞ苦しんでいることだろう」と相手の気持ちまでも思いやり一人悶々とする。恋の始めで恋心は最高潮だ。
源氏は歳にしては老成していたり、恋の経験もすでに豊富にあるようだが、ここでは若々しい恋心の表れようが印象的だった。
☆moonba
覚悟の上の一夜が明けて2人の心模様の違いが面白い。源氏は離れ難く引きずる気持ち。空蝉への気持ちの大きさが空蝉を益々魅力的な女と思える。空蝉の方は夫が気になり居てもたっても。夢でバレるのではないか…今では考え難いがこの頃にはあった事なのかもしれない。心のこりの源氏が思い立った『したこごろ』を閃く様の展開が面白かった。
☆源氏のこころ
一番鶏が時を告げ、あわただしい別れの時がやって来る。有明の月を浮かべてだんだんに明けて来る曙の空のをかしき情景、こんなに美しい朝に愛する人と別れ、二度と逢う術が見つからない悲しみと混乱の中にいる源氏。一方の空蝉は、現実に引き戻されて自分の思いが夫に届くのではないかとおろおろする。気の毒だが、結婚が女の生活のすべてを支配していた当時、源氏のように夢の続きの中にいるわけにはいかなかった。弟のこともあり、空蝉は厳しい現実をしっかりと生きていたということだろう。
「何心なき空のけしきも、ただ見る人から、艶にもすごくも見ゆるなりけり」という草子地から著者の自然観が伝わってくるという先生の解説を伺い、いつの時代も人は己が心の趣を自然に託し、委ねて心を慰めてきたのだな、と感じた。竹を渡る風の音、山の唸り、川のせせらぎ、深々と降る雪、枯葉の舞う音、青葉と風の合奏等々に心を通わせ、共感してもらっているのではないだろうか。電子音に囲まれ、警鐘のサイレンにビクッとする都市の日常を考えると、こんなところにも自然に親しみたい、触れたいと願う要因があるのかもしれないと思った。
<ご参考:朝の情景表現調べてみました、夜~暁~東雲~曙~夙(つと)にの順>
暁(アカトキ(明時)の転) 夜を三つに分けた第三番目、宵・夜中に続く 午前2時頃~
東雲 夜明けの薄明かり、東の空がほのかに明るくなる頃
曙 夜明けの空が明るんできた時、夜がほのぼのと明け始める頃、日の出の一歩手前
夙(つと)に 朝早く、早朝
・有明の月 夜明けになお空に残る月、月光は消えているのにその輪郭だけがくっきり見える
・一番鶏は、夜が明けかかったら鳴くので、時間は季節によって違うらしいです。古代中世の人は一番鶏を「もう行動できる状態になった時間帯なのかどうか=夜が明けたかどうか」を知りたかったために、鶏をあてにしたようです。
2020 年1月10日
帚木 P33~P47
☆さくらちゃん
今回のお話で
決して強引では無い源氏の振る舞いなどから
原文ならでは味わえる
本当の源氏の姿なのだなと 改めて原文の面白さを味わいました。
☆moonba
空?(うすせみ)が高い身分のままだったらここまで魅力的に思えたのだろかぁ?
源氏は数奇な人生の女に好奇心が揺れた。
空?の拒む態度と変わりゆく言葉に魅力を感じ引き込まれて行ったのも源氏の好奇心。
空?は歳上の夫でしかも後妻そして身分も低くなってしまった運命は自分ではどうする事も出来ず満足出来ない人生に悲しく思っていたはず。そしてプライドが高くなってしまった。
頭ではまずい事だと思っているが始めからすでに香りと気配で源氏とわかり引かれてしまい、そんな自分を許せないと葛藤し受け入れられるまでに時間が必要になったのでは…。
そして夢のような現実を手にする理由も欲しかったように思えた。
ワクワクする楽しい場面だった。
☆KUNKO
源氏が女性を口説く初の場面です。夜更けに忍び込み、言葉上手に口説く様は手馴れた感じもします。
しかし、女君の動揺に源氏の心も揺らいでいるようです。
男の人と心を通わせることもなく、恋も知らずに歳の離れた男の妻となった女君の心は千々に乱れていて…
その描写が読み手に深く刺さって来ます。源氏の口説く手管よりも女君の心の内が切なく伝わってきました。
☆源氏のこころ
「空蝉…セミの抜け殻」と言われる女君は空虚でうつろな哀しい存在のイメージが先行する。厳しい身分社会のなかで、弟と自らの生活を確保するために辛いはかない身の上を受容せざるを得なかった女君は気の毒である。
そんなところへ口説き上手で超魅力的な若い源氏が登場した。慎み深く繊細で考えが深い彼女は「抵抗」すべき自身の立場を理性的に実行しようとする、弟の行く末も考え、案じていたかもしれずパニック状態にありつつも頭の中は様々な思いが去来していたことだろう。一方で高い身分にあった者として「世が世なら・・」というプライドが若い貴人との釣り合いを是としただろうし、年の離れた面白くもない夫との空疎な生活のストレスも後押しになったかもしれない。源氏にとっては、その慎み深さ、はかなさ、懸命に理性にすがろうとする姿が魅力的に映ったのである。もしも普通の姫君として出会っていたら、こんなに口説いただろうか…などと考えてしまう。
☆葉(2020.1.10分 しのび込み~口説き上手)
「方違へ」で紀伊の守邸に身を寄せている源氏のことを知った女房たちは興奮気味である。中の品の女房たちにとって源氏は遠い世界の憧れの存在であり、今を時めく噂の貴公子を一目でも見たいと気持ちは高ぶり、噂話に夢中になる。
そんな状況で迎えた夜、寝入りばなの夢うつつな空蝉のところに、突然現れるのが源氏である。《「や」とおびゆれど、顔に絹のさはりて、音にも立てず。》《いみじくにほひみちて、顔にもくゆりかかる心地する》の描写から、源氏の柔らかな着物がふわりと顔に触れる様や香をしたためたかぐわしき衣の香りに包まれる様が感じられ、うっとりさせられる。
しかし何よりも面白いのは、突然に忍び込まれた空蝉の心の動揺、源氏の魅力に圧倒されながらも抵抗の気持ちを必死に伝えるやり取り。拒まれてさらに気持ちを自分に向けようと口説きに心を向けていく源氏。父が亡くなる前は帝の妃としての人生を一度は思い描いた空蝉にとって、現時点では不釣り合いな源氏との《仮なる浮き寝》は、後に襲ってくるわびしさを思うと堪えがたいものだったのだろう。
《よし、今は見きとなかけそ》と固く約束し、源氏に身を許したところに身分、男女の力関係を超えた対等さが表現され好ましく思えた。源氏のしのび込みを通して、空蝉の心の底の葛藤をこそ、ここでは読み味わってみたい。原文のすごさが伝わってくる。
2019年11月8日 ≪帚木11≫
中の品の家 ~しのび込み
☆さくらちゃん
この時代の身分を考えならが読むのが難しいです。今とは違い 身分制度が厳しそうで大変だなと思いました。
☆KUNKO
本来であれば帝の妃としての人生が待っていたであろう女が姉。
殿上童として上がる筈であった弟…この美しく不運な姉弟に心惹かれていく源氏。
一方、若く美しい継母を密かに想う紀伊の守。
一人の女性を巡り
年寄りの伊予の介、紀伊の守、そして今、隣室に居る源氏…!
もう、ラブサスペンスのような展開です。続きが気になって仕方ありません。
☆源氏のこころ
「噂話、姉弟、しのび込み」
いよいよ貴公子の世界が貴族社会の外へと広がり始める。紀伊の守邸の人々とそこに身を寄せている伊予の守の家の人々の様子や彼らの源氏への対応・饗応が語られ、源氏が住む貴族社会と中の品の家との身分格差と民度の違いが描かれる。なかで空蝉とその弟の翻弄される身の上も明らかになり、身分社会のなかで寄る辺ない女子どもの厳しい状況が胸に迫る。整い切った左大臣邸から来た源氏は、彼らの至らなさを批判的に見つつもゆるい感じに少しほっとしていたかもしれない。
源氏が紀伊の守に無遠慮で辛辣な言葉を投げかける様子には、帝の子に生まれ頂点とは言わないまでも相当に高い位が約束されている者のけれんみの無い爽やかさがあり、嫌みがない。一方で姉弟のはかない身の上に思いを寄せることのできる源氏の優しさも感じられて、17歳にしては確かにおとなびており、深い人柄を持った人物であることが伝わってくる。
☆竹とんぼ
「うわさで聞いていた女性」は紀伊の守の父親、伊予の介の後妻になっている。
女性は父の死亡で後ろ盾を失い、格違いに身分が低く年齢も不釣り合いに年上の伊予の介の家に弟を連れて入っている。
姉弟の身の上を聞き及んで運命のあわれさに心を添わせる源氏は、自らも人生の苦しさを知る老成した若者だ。一方女性に対する好奇心が更に募り、女性も自分にもっと関心を持ってくれてもよいのになどと勝手に思う若さも見せる。
貴公子でありながら人間源氏の多層な面が見られる場面だ。
☆葉
中の品の家 ~しのび込み
「雨夜の品定め」に語られた「中の品」の女性に好奇心いっぱいだった源氏は心弾ませ紀伊の守邸に行く。「中の品」の意味は四位、五位の殿上人の家柄のことだそうだ。三位以上の「上の品」との境に、これほどの身分の差があることに気付かされ驚いた。「上の品」しか知らない源氏の目を通して映る邸のたたずまいや女たちの様子が生き生きと描写されていてとてもおもしろい。
「水の心ばへなど、さるかたにをかしくしなしたり。田舎家だつ柴垣して、前栽など心留めて植ゑたり。風涼しくて、そこはかとなき虫の声々聞こえ、蛍しげく飛びまがひて、をかしきほどなり。人々、渡殿より出でたる泉にのぞきゐて、酒飲む。」私にはなんとも風情ある貴族のたたずまいを想像するが、源氏に言わせると「それなりに格好をつけているが、都の洗練さがなく野暮ったく上の品の邸とは格が違う」ということなのだろう。
源氏は大勢の女の衣ずれの音に交じって聞こえてくる若い女房たちの噂話に聞き耳を立てたり、襖障子の向こうに聞こえる空蝉の声に思いが高ぶったりする。
これまで静止画として眺めていた「源
2019年9月13日 ≪帚木10≫
☆moonba
今回は源氏の様子が見えて楽しい場面であった。源氏は品格や性格から大人びた様子に思えていたが居る場所や人と関わる様子で無邪気さや幼さが見えて可愛らしくもあり寂しそうにも見えた。女房とは気が許せるのか冗談を言い、年頃っぽい源氏。昨夜までの大人な話を興味深く聞いてる源氏は大人びてみえたが時代とは言え幼過ぎる政略結婚に上手くたち振る舞えず周りをハラハラさせていている源氏もいる事を知った。庶民的な生活にも興味深い源氏、占いが生活に密着している事など背景がわかってこれからの先の見方が変わると思います。
☆KUNKO
陰陽道に従うのが常とはいえ、
よそ様の邸に、いきなり訪問するなんて!現代では考えられないですし、しかも 訪問された方がおもてなしをしなければならないとは大変です。
昔、夫が酔った後輩を突然連れてきた事を思い出しました!
紀伊の守が気忙しげに歩く姿が目に浮かび、気の毒な気もするのですが少し可笑しくて、クスッと笑ってしまうような場面でした。
噂に聞こえてる「思いあがれるけしき」の女が逗留しているとのこと。これからの展開が気になるどころです。
☆源氏のこころ
「源氏と女房たち、方違え、中の品の家」
雨夜の品定めで源氏はさまざまな女性の話を聞いた。そこには自分が経験したことのない貴族社会の外に生きる女性の話もあり、源氏は関心を持ったことだろう。自分の妻は話に聞いたどの種類に当てはまるのか?とも考えたかもしれない、風格があり塵一つなく整っている左大臣邸同様に気高くつつましくしっかり者の我が妻は頼みとなる主ではあるものの近寄りがたい。彼女は自我が強く嫉妬深い女でも、浮気っぽい女でも男頼みのひたすら耐える女でもない、源氏は知りたくて近づこうとするが何かバリヤーを感じてしまう不幸な関係。彼の関心はいよいよ外の未経験社会へと傾いていくという設定、加えて方違えのため中の品の家へと向かうことになるという早い展開、そこでも女房達が源氏の噂話をしているらしい、まだ何も知らない貴公子の世界が少しずつ広がっていく予感が感じられる。
☆竹とんぼ
{方たがえ}のため、源氏は思いがけず急に紀伊の守邸に行くことになる。
紀伊の守の格は「中の品」に当たる。源氏は上の品の中でも上級の出身で、中の品の暮らしや女性をこれまで身近には知らなかった。前夜の女性談義の席では自ら語ることなく超然としていた風情だったが、源氏は若者なのだ。談義で語られた中の品の女性たちにも好奇の心が向いたことだろう。
2019年7月12日 ≪帚木9≫
☆moonba
【藤式部のおかしな恋話の巻】
身分の低い式部が学問で昇進して出世したいと思っていたから引きあった女との関係が面白い。その才ある女に助けられ学べる特での付き合う仲は続かなかった。漢文調の女に色気があったら続いていたかも。程よく学問が身についたから才ある女から気持ちが離れたのかなぁ。蒜の香りの出来事を別れるチャンスにしたようだ。それもフラれたふりはちょっとズルい。けど、少し要領の良い可愛い式部にも思えた。
☆KUNKO
藤式部丞が語った女性は、あまりにも才女で どうも男心がまるでわかっていないようです。
「目から鼻に抜ける女は可愛く無い!」と亡き母がよく言っていたのを思い出しました。
この時代、教養は大切であったのでしょうが、それが鼻に付くようでは、男の足も遠のくというもの。
今回は、「蒜食いの女」ということで匂いも鼻についてしまったのでしょうかね。
上流階級と下流階級の人々が出会う女性すら全く違うのだという事がよくわかりました。
☆源氏のこころ
「蒜食いの女その1~2」
式部の公達に対する落ちつき払ったような人を食ったとも言えそうな態度で彼らの世間知らず振りがますますあぶりだされて面白い。すべて真実か式部が面白く背びれ尾びれを付け足したのかわからないが、なかなか痛快な筋立てと式部の人柄設定に爽快感が残った。このような従六位が存在したかどうか不明だが、いたとしたらなかなか自由な風通しの良い貴族・官僚社会であり、存在しがたいとしたら「こんな若者がいたらいいな」という作者の思いを込めた遊び心の現れた章なのかもしれない。いずれにしても指喰い、木枯らし、常夏とやや肩に力の入る内容を読んできて、軽くて面白くスーっと肩の力が抜けた。読者を飽きさせない疲れさせない配慮の構成がここにもあった。
☆竹とんぼ
式部が語る番になった。式部は左馬頭よりもずっと格下の、低い身分の貴族だ。左馬頭や頭中将が語ったような女性談義をすることは自分にはできないし、この場に相応しくないと承知している。どのような話をするか「思いめぐらし」て語ったのが《蒜食いの女》の話だ。式部は、あえて突拍子もない女性の話を選んで、皆に「そんな馬鹿な!」と言われている。「もっとましな話があるだろう」と言われても「これでおしまい」と引き際も上手。真面目顔もせず道化にもならず、はるかに身分の高い貴族たちと同席している我が身の処し方の心得ぶりが面白く描かれている。
☆葉
さて、次の話し手は籐式部丞。「下が下のなかには一風変わったおもしろい恋話があるだろう」と責め立てられるところから上流中の上流である三人とは身分の違う式部が同席しているのだと気づかされた。ここで式部は自分も傷つかぬよう座も白けないよう話を選ばねばならない。それが蒜食いの女だ。確かにこれまでの女とは全く違っておもしろい。
貧乏な博士の娘で、学のある女なのだが、話すのも書くのも漢語調。久しぶりに立ち寄ると「風病重きに堪えかねて、極熱の草薬を服して・・・」とのこと。その草薬が蒜。ニンニクの匂いが臭くて会えないというのである。
それは口実だろうとふられたふりをして逃げる式部に、「毎晩逢う仲ならば、にんにくの匂いなんて恥ずかしいことではないでしょう。」と返歌も強烈だ。上の上である聞き手らは虚言と笑うが、実に存在感のある女だ。こんな話も源氏物語には書かれていたのだとたまげてしまう。
☆J
中将が部下である式部に恋の話をさせる場面。
「あはれ」ではなく「けしきある」話をさせて笑いの種にするところに、中将がはなから式部を小馬鹿にしているところが読み取れる
すっかり話終わっても、「虚言とて笑ひたまふ」とは、、
なんでちゃんと話しているのに信じないかなぁ
でもそれに対して卑屈にならず、
「これよりめづらしきことはさぶらひなむや」と言い放って、
『をり』とすまして座っているところが式部にとても好感を持てた。
2019年5月10日 ≪帚木8≫
☆moonba
『常夏の女ⅠⅡ』
いよいよ中将の出番。
源氏に笑われ立場を失った左馬頭に同情した気持ちから入った話しだからなのだろうか…「あはれ」から始まった関係はかなりコミカルに思える。
頼りにされる事で続く中将と頼りたいがゆえに嫌な顔もせず慕う女…私には耐え難いがそれが平安の女の生きる道なのか。私は令和で良かったな!
叶わぬと悟って跡形もなく去る事で自分を表現した繊細な女と悲しみの中将。かと思われた昔話は皆んなを盛り上げるためなのか…締めには去った女には男が居たのでは…などとオチまで付けた。こんな話は女子トークにはありそうだが男女変わらない恋話は楽しい。
☆KUNKO
常夏の女は万事控え目の女性であったが為に、中将は足繁く通う事も無い、思い出したように通うのみです。二人の間には娘もいるというのに…中将は女心も親心も解ろうとしないのですから。呆れてしまいます!
自分の都合のいいように話しを持っていく身勝手さ…
現代の男にも、この手の男は多いと思いました。
いつの時代も同じなのですネ?。
☆源氏のこころ
「常夏の女その1~2」
若く世間知らずな頭中将のおめでたいボーっと鈍な感じと切羽詰まった女のすれ違いの状況にあきれた。
「なでしこ」を「撫子」と「常夏」に描き分けて表現していくセンス・アイディアはすごいな、と思った。いつも歌詠みを考えていた当時の人々にとっては朝飯前なのかもしれないが。
「指喰いの女」「木枯らしの女」そして「常夏の女」、作者がもっとも描き出したかったのはこの「常夏の女」ではなかっただろうか、当時の社会(男性目線)が求めるもしくは想定する女を「常夏の女」・・はかない哀しい存在として登場させたように思える。対比的に前の二つのタイプ(嫉妬深い女と浮気な女)を提示しておくというところが素晴らしい、この二タイプは当時の社会に受け入れられにくかっただろうが、「自分自身」のものさしを持っているという共通項があるように思える。
☆竹とんぼ
中将が語る女性は、中将との間に子をなしている。女性が幼子と共に跡形もなくいなくなってしまういきさつを語るが、若い中将は自分の側からしか物事を見ていない。
『ああ若いな』と感じるが、70歳に近い私はそれを『仕方ない』と許している。
それに引き替え左馬頭の下世話な感じには辟易している。
私のこの不公平さは何でしょう。
☆葉
常夏の女その一 その二
左馬頭に代わって話し手は中将になる。たまにしか通わなかったが、責める様子もなく、ただ頼ってくるけなげな女であったという。『・・・あはれかけよ撫子の露』『・・・あらし吹きそふ秋も来にけり』と絶望の中にあることを女は歌にするが、中将には気付いてはもらえず姿を消す。そこで初めて中将はことの重大さを知ったという。
北の方からのいやがらせがあり、逃亡することで身を守るしかなかったというのだからほんとうに恐ろしい。どんな脅し文句だったのだろう。お付きの者たちもいたであろうが、その後暮らしていくことはできたのだろうか。
通い婚や一夫多妻制のことがなかなか想像できず、どのようなものであったのだろうかと思い巡らしてしまう。
2019年3月8日 ≪帚木7≫
☆さくらちゃん
左馬頭の作戦が大失敗に終わったところが面白かった。そして現代の男性も、この当時の男性も女心のわからない生き物なのだなぁと思いました。
☆KUNKO
指喰いの女が嫉妬していた対象の女の話です。指喰いの女が存命中は魅力的に見えた女だったのに…
女の元に通う上人と女とのやり取りを目撃してしまい、左馬頭は「すきたわめたらむ女」への情熱は冷めてしまうのです。
若さ故ですよ…と
左馬頭も語っていますが、現代においてもよくある話です。頭に血がのぼっている時には、当人には判らなくなっているものです。
一千年以上昔の若人も同じなのですよね。
しかし、恋のかけひきは、ロマンチストなんて言葉で片付けられない、教養の深さを思い知らさせれ
現代人との隔たりを感じました。
今後も、私達は恋のかけひきを目撃?する事になりますね。とても楽しみです。
☆源氏のこころ
「木枯らしの女その1~2」
築地塀の崩れが見せる池の月影、初冬の菊の風情、木枯らしに舞い踊る紅葉、その音を背景に男が奏でる笛に女の和琴が寄り添う、木枯らしのせいでくっきりと冴える月、完璧なお膳立てに読者は自然と五感を刺激され、誰もが情景を浮かべるような設定の見事さに舌を巻く。崩れた壁や時の移ろいを体現する菊を肯定し愛でる大人の感性は素敵だなあと思う。
作者は一般の若い男性は「目の先三寸しか見渡せず単純で鈍感!」と位置づけ、源氏の君はちょっと違います、と際立たせる手法もすごい。次の「常夏の女」にはどのような女が登場するのだろうか?
☆竹とんぼ
左馬頭の長い女性談義が終わった。左馬頭が自分の経験から得た教訓を語ると、中将の君は素直にうなずく。源氏は、一拍おいて「どれにしても、見くびられるような中途半端な話ばかりなりけり」と一言述べる。周りの者たちも思わず笑ってしまう。これは源氏がいかにもタイミングよく、皮肉も無く悪意も無しにスパッと言ってのけたので周りも笑えるのだろう。
左馬頭の語った話とは比べるべくもない、深い悲しみを源氏は既に経験してしまっているのだ。
☆葉
木枯しの女 その一 その二
左馬頭の最後の話は、指喰女と並行して付き合っていたもう一人の女、木枯しの女の話であった。妻同然に思っていた女をいざ失ってみると、浮気相手としては輝いて見えていた女が、実は自分には合わない頼りにならない女だと気が付いたというのだ。いつの世もそんなものなのだなあ。真実を言い当てているなあと感心した。
さて、左馬頭の恋話を私もここまで読者としてありがたく聞いていたのだが、最後に式部は、「いづかたにつけても、人わろく、はしたなかりける身物語かな」と源氏にあっさりと言わせている。ありがたく話にのめり込んでいた私としては自分まで笑われた気分になる。
なのだが、私はここで源氏の声を初めて聞いたような気もした。なんともカッコイイ。そういえばまだ源氏の話ははじまっていなかったのだ。これからの『源氏物語』が益々楽しみになった。
2019年2月12日 ≪帚木6≫
指喰いの女 その二、三
☆moonba
指喰いの女2
嫉妬深い女への若き浅はかな左馬頭の思惑が
女を死に追いやる話の結末には驚いた!
確かに妻の嫉妬深さは愛するがゆえにでは
あったが男に対する愛だけで死まで行くの
かなぁ?!
それよりも自分の愛に振り向かない夫への
執念が自らを滅ぼしたようにも感じた。
平安時代の男と女は対等である。
ここにも驚きの気づきがあった。
今の今まで対等な背景を持つ時代がある事を
考えた事も無く、自分の偏見さをベースに
平安時代をみていたのだった。
だからこそ妻である女が夫に養われている
よりも男を育てている立ち位置にガッテン
した。
☆源氏のこころ
帚木 2019/1/12
「指喰いの女その1~3」
「指喰いの女」はただの面白いエピソードではなかった。彼女は自己主張できる自我の強い女、自分をしっかりと持ち、それを男にわかって欲しいと願う人だった。こうした女性を描出できる作者の力量もすごいが、背景に古代社会の自由な風があったのだろうと思う。古代貴族社会の男女間は中世近世よりもリベラルであったと知ると同時に自分が中世から近世にかけての男尊女卑的歴史観に強く支配されていたことがわかり、目から鱗の思いだった。
強い自我を曲げられない故に主張を譲れず、男になよぶことがかなわない「指喰いの女」は、現代の女性ともだぶる。今は女性も経済力を持つことができる社会である点で幸いなのかもしれない。
2019年1月11日 ≪帚木6≫
指喰いの女 その二、三
☆さくらちゃん
左馬頭の作戦が大失敗に終わったところが面白かったです。
そして現代の男性も この当時の男性も 女心がわからない生き物なのだなぁと
とても楽しく読ませて頂きました。
☆KUNKO
左馬頭は若い頃、少し軽薄だったのでしょうか…。
とはいえ、プライドが高く、教養も技もある女が惚れ込んでしまう魅力があったという事でもありますね。
相手の心情を慮ることができない男とプライドが邪魔して素直になれない女…。読んでいて何とも歯痒い二人なのです。
まさか、思い煩い亡くなってしまうとは思いもよりませんでしたが。
この女を失ったことから、左馬頭はこの先、人して、男としてどのように成長するのでしょうか。
とても、ドラマチックな巻でした。
☆竹とんぼ
若き日の左馬頭に、強く深い想いを寄せた「指喰いの女」
女の強い想いに比べて、若い左馬頭の想いは軽い。
左馬頭は、今となっては当時の自分の言動を反省しているような口ぶりだが、年齢を重ねても深く女性を思う男に変容している風ではない。
男は宮廷社会の中で出世しなければならないし、前進していきたい。深い想いは前進する力を錨のように引っ張るかもしれない。
当時の社会の様子や結婚?に対する考え方が十分に分からないので、男の想いが軽いことを簡単にダメと決めつけられない。
☆葉
左馬頭と女のやりとり、その挙句の思いもかけない行動には度肝を抜かれた。「指ひとつを引き寄せてくひてはべりしを、」の映像がいつまでも心から離れなかった。しばしこの指喰いの女の心情に浸ってみた。
泣き崩れるのではない。怒鳴り返すのでもない。物を投げつけるのでもない。まさに指をつかんで、その指に歯を立てるのである。愛憎極まって及んだこの行動に、愛を求めるあまりの飢餓感。身を裂かれんばかりの嫉妬と己を強く保ちたいと願う意地との間の深い葛藤が感じられる。「憂きふしを心ひとつに数へきて」と返答の歌に詠まれたように、これまでの苦しさがこの行動に及んだのではなかろうか。
左馬頭の別れ際の歌を聞き、さすがにうち泣きてとあるが、「・・・わかるべきをり」と歌を結んでいることから、気持ちの高ぶりもあろうが、訣別せねばと自分に言いきかせる涙ではなかったのかと私には思えた。それにしてもこれだけの愛憎劇のあとにも歌が交わされるとはなんて粋で美しいのだろう。二人の歌を何度も読み返し、大和ことばの心地よさにも酔いしれてしまった。
☆J
指を噛むという行為には叩いたり引っ掻いたり突いたりするという行為とは違った意味の相手への抗議が感じられる。
手という器官は心を伝える時に使われることが多い。
握手をしたり、相手を慰めるのに身体をさすったり、相手の両手を自分の頬に持ってくるというのも心を通わせるのによく見られる行為だ。
手の一部である指を噛む、という行為には、指を自分の口に持ってくるという愛情の表現とも思われる行為が転じて悔しい気持ちを相手に知らしめるという、怒りや憎しみだけとは違うニュアンスがともなう。
男を愛していながらも男のわがままには屈しない強い心をもった魅力的な女性を、この行為によって見事に描ききっているところが素晴らしい。
2018年11月9日 ≪帚木5≫
☆さくらちゃん
今回は 大工さんや絵師 物書きなどに例えて
「見栄えの良い女性より 中身がしっかりした女性の方が良い」
と言うことを力説していました。
例えがとても面白く 分かりやすかったので 楽しかったです。
☆KUNKO
左馬頭の例え話を少し退屈して聞いていた源氏もいよいよ、実体験の話となれば興味も湧くはず…。
器量は劣るが献身的な女性との思い出。
今日、読んだ限りでは、嫉妬深く私は苦手なタイプ。
左馬頭は献身的な女性を有り難く思っているようですが…。
次回、指喰いの女の謎が解明されるのでしょうか?
楽しみです。
☆源氏のこころ
「法の師左馬頭」と「指喰いの女その1」
左馬頭の工芸・書・絵における蘊蓄には耳を傾けるべきところがあって、著者の文化的素養の幅広さと深さを感じさせる。工芸・書・絵においてはそれほどの知識や感受性のある左馬頭であるが、こと「女こころ」となると簡単に説明できるものではない、として経験談へと移っていく。恋愛や結婚がいかに分類分けができない個別性の高い「縁」としか言えないようなものであるかを表している。
「指喰いの女」とは何だろうと先を読み進めてみるとなんと!面白いエピソードに笑ってしまった。「雨夜の品定め」がいつの時代も人気が高い訳がわかり、さらに先が楽しみになった。
絵に関心がある私は、先生の「当時、国風化で唐絵に倣って大和絵が誕生したこと、描く対象が唐絵は空想の画題であり、大和絵は世の常のものであった点に興味を惹かれた。左馬頭が指摘する文化的なものへの「奥ゆかしさを大切にする価値観」や「もののあはれ」とどこかでつながるのだろうか、それとも単純に「唐絵が想像の産物ならこちらは現実を捉えよう」というだけのことだったのだろうか?
☆竹とんぼ
左馬頭の男女論が続き読者がそろそろ飽きてきたところで、一般論から左馬頭の実経験談に移る。読者も改めて「何々?どれどれ?」となるだろう。読者を逸らさない作者の巧みさだ。
世俗の語り手・世間知にたけ経験豊富な左馬頭、その話を熱心に聞く若い中将の初々しさ。この舞台の上で、光源氏だけが「俗」と無縁の別次元に居るように見える。源氏の心の中の悲しみと憂いの紗布が、俗の空間から源氏を隔てている。
舞台か映画の美しい1シーンを見るようだ。
☆J
妻選びのうんちくを左馬頭が、芸術に絡めて語る様が興味深かった。
指物、絵画、書などに、うわべの華やかさ、派手さよりも根幹の確かさ堅実さに真の価値を見出していたことがうかがわれる。
そして妻選びもそのようにありたいが、それはとても難しいと言っているわけだが、
正直なところ、当時の結婚観や夫婦のあり方が私の想像していたものと全くちがっていたので、そこが一番のおどろきだった。
上流階級の結婚とは血筋と地位と財力のみが重んじられて、それ以外の人間らしい触れ合いは側室のような立場にある人に求めるものと思っていた。
それにしてもちらっと姿を見たり、歌をかわしたり、人の噂で妻を選ぶというのはさぞ難しいだろうと思う。それとも現代のように自由に会うことができていたのでしょうか?
2018年7月13日 ≪帚木2≫
2018年9月14日 ≪帚木4≫
☆さくらちゃん
男性と女性の関係が 今とさほど変わらないことに 驚きです。
この時代でも 女性はしっかりと男性を操作しているのだな と。
☆KUNKO
平安時代も男が求める理想の妻の姿は、結局
「うしろやすくのどけき」所のある女性であると言う左馬頭。
こんな妻は、御免被りたい、と言う女性も語る。
いつの世もあまり変わりはないようです。
それにつけても、毎度思うのは紫式部の人物描写の巧みさ。
文章の美しさ、リズム、生き生きとしたリアルさ…。
今回も、平安時代の男性の方の姿を垣間見させていただきました。次回も楽しみです。
☆竹とんぼ
左馬頭の夫婦論と理想の妻論は続く。
左馬頭は年長の経験者として自分よりも若い者に話をしている内に、興に乗って舌滑らかにどんどんしゃべってしまう。
かと思うと、ハッと今の状況に気付いて、話を何とか話をまとめようとする。この左馬頭の様子がリアリティがあって面白い。
このリアルな左馬頭に惹かれて、左馬頭の長い女性論も中だるみしないで、先へ先へと読みたくなってしまう。
紫式部の場面を構成する力量に、読者として乗せられるのが嬉しい。
☆葉
左馬頭は妻を選ぶのに一番大事なことは「《ものまめやか》で《静かなる心のおもむき》」であるという。つまり誠実に夫と向き合い、些細な事で夫への信頼を失うことのない、情緒の安定した人こそ伴侶としてふさわしいのだと語っている。私もこの年になったからこそ実感できる本質をここで言い得ていることに、千年以上前に書かれた源氏の面白さを改めて感じる。
また、同時に妻とするには厄介な女も描いている。田中先生の言葉を借りると「仮面をかぶった妻」「自分を殊更かわいそうな女に仕立てる自己愛の強い妻」「独りよがりの主張は発信するが相手のいいたいことには無関心な妻」等である。
夫が迎えに来てくれることを期待しながらも叶わず尼になった女に対して《仏もなかなか心ぎたなしと見たまひつべし》《なまうかび》であると、女の醜さを容赦なく描き出す式部の鋭さには小気味よいほどである。
そして夫婦円満にいくには妻はどう対応したらよいのかも左馬頭は語り続けるのであるが、ここまで夫婦論を聞かされると、この時代の母系社会と通い婚がどうなっていたのか、家族制度や家族の在り方はどう変遷してきたのかなども気になりだしてしまった。
☆J
源氏物語は訳をさらさらと読んでいくだけではただの光源氏の恋愛遍歴にすぎなくて、それでも長い間読み継がれるのは、やはり登場人物たちの機知に富んだ会話に面白味があるからではないだろうかと、思っていました。
しかしそれを理解するにはバックグラウンドになる知識や読み解く力が足りなくて、いつかこんな講座を受けたいと思っていました。
初めて参加させていただき、田中先生に細かく解説をしていただくことによって、たった何十行の中にもいろんな面白い発見があって、あっという間に時間が経ちました。
次回も楽しみにしております。
2018年7月13日 ≪帚木3≫
☆源氏のこころ
「雨夜の品定め」の続きを読んだ。
左馬頭が女に対する一般論を展開する。恋のアバンチュールを楽しむ相手と結婚すべき相手の選び方は違う、男の一生の大事、お家の大事がかかった「家の主人」を決める難しい大仕事だと言う。大変興味深い講義であるが今一つピンと来なかった。現代でも「恋愛と結婚は違う」という話を聞くことはあるから今も同じようなものだと思ったが、全く違った。
この件は、家の繁栄・永続が最大最高という当時の価値観がわからないと理解できない。当時の家の考え方の根底には「個」がないうえに当時の価値観の時間単位は長くそこに安定と安心があったのだ。
また、当時は家の都合で世間通の親が決めた顔も知らない相手と結婚するものと思っていたが、あにはからんや親ばかりではなく夫となる本人もあれやこれやと悩み、決めかね、考えあぐねていたというのだから驚いた、女側も同様に悩んだことだろう。
家制度の重さは想像以上だった。
☆竹とんぼ
左馬頭の女性談議は続く
様々なタイプの女性について、女性が妻となった場合の様々な夫婦のありようについて、話は続いていく。この場面では年長の左馬頭は、自分が見知った事々を披露しながらも常識人としての枠は超えない。
左馬頭が、説明役の登場人物になってしまわずに「こういう人は居る居る」と思える実在感があるのが式部の筆力だ。
左馬頭が話す夫婦模様は、現代も身近にこのような夫婦がいると感じられる普遍性がある。式部の人間観察眼にも、いつもながら感服する。
☆葉
今回は左馬頭が「妻にするにはどんな女がよいか」と、光源氏らに得々と語る場面であった。「墨つきほのかに、心もとなく思はせつつ・・」と言った自意識過剰な女にはまると、災難である。また「まめまめしき筋を立てて、耳はさみがちに・・」と実質本位の味も素っ気もない女では、話したいことも話せず、独り言をつぶやいているしかない。ではどんな女が理想の妻なのかと続くのである。
田中先生のイメージ豊かな講釈があってこそだが、左馬頭の語る失望する妻たちの姿が原文から生き生きと浮かび上がってくる。女らしさを演じる子供っぽい女、夫の視線に余りにも鈍い無神経な女、その描写が実に巧みで面白く、吹きだしてしまうほどだ。そしていつの間にか「男ってこんなに、妻に期待しているものかしら・・」などと我が身を想い、源氏の世界だったことを忘れてしまいそうになった。
まだまだ能弁な左馬頭のおしゃべりは続きそう。次回も楽しみです。
2018年5月18日 ≪帚木2≫
☆さくらちゃん
源氏と周りの男性陣の女性感がそれぞれ違い
またその違いがとても面白かった。
そして 現代にも言える感覚なので
リアルに感じました。
☆moonba
源氏を囲い四名の男達の様子がとても面白い。
今も昔も恋話は楽しいのだ。
違うのは位が関わる事。
女達は階級の差で品格、美貌、才能まで違う。
そして話している男達にも階級があり
その上に品格、美貌、才能で人格が
出来ている。
さすが源氏。女達よりも遥かなる魅力が
ありありと文章から読み取れる。
「思い上がり」この意味は今とは違ってた。
志しを高く持つ。
これはどの環境であってもそして今も大切だと感心しました。
☆KUNKO
この場面は、彼らの姿が目の前に見える様です。
きっと、左馬頭は身振り手振りで語っているのでしょう。
それを、藤式部丞が関心した様で見ていて、若い貴公子の二人は、半ば呆れた様に聞いているのでしょうか?(よく、喋るなぁ…。)彼らの脳裏には、左馬頭が語る女が描き出されているのでしょうか。
女の品定めですネ。
いつの世も、同じなのですね。
☆源氏のこころ
有名な「雨夜の品定め」のリード部分を読んだ。
語り手の状況設定、人物配置の妙とその描写の巧みさに驚かされる。若い上達部の貴公子である光源氏と頭中将と年嵩で世間通の常識に安住しつつも夢見がちな中流階級(五位)である左馬頭、彼らより身分が低く(六位)控え目だがわきまえがあり、賢そうな若者の藤式部丞、4人の共通点は「すきもの」である点。物忌みの雨の夜、すきものの男たちが集まって暇つぶしに関心の高い話題「女の品定め」に興ずる、といういかにもありそうな設定、立場や環境が異なる者たちに語らせ、反応をみる面白さ、次回の展開がますます楽しみになる。彼らは身分社会・階級社会のなかでそれぞれにごく狭い社会に暮らしていたことが了解されるのだが、すべてを俯瞰的に見て描いているように思われる作者の立ち位置、観察眼の鋭さにまたまた感服してしまう。さまざまなところに出没する行動力もある人だったに違いないとも思う。
☆竹とんぼ
光源氏の元に集まった三人の男性が女性談議をしている。
身分も年齢も違う三人と光源氏。光源氏は私空間に居る者らしく、いかにもゆったりとくつろいでいるが、自らは多くを語らない。外は雨。灯火のほのかなあかり。光景がまざまざと目に浮かぶだけでなく、雨の空気の匂いまでしてくるようだ。
紫式部の舞台設定の見事さに感嘆してしまう。
2018年3月9日 ≪帚木1≫
☆さくらちゃん
源氏の従兄弟とのやりとりが
まるで現代のようで。
そこがまた この物語に親近感を覚えるところなのでしょうか。
それにしても 源氏と従兄弟との女性感の違いがとても面白かったです。
☆KUNKO
源氏と頭中将二人の青年が織りなす恋の
駆け引きが見えてきました。
よく知らない女性に想像力だけで文を書く。
彩色された紙に記し、結ぶ草花も選んでおくる。
はぁ…大変です!受けとった女性も、
いただいた文には直ぐに返歌…。
それだって、センスが問われる…。
容姿の他にも教養とセンス…。
さてさて、この お二人の心を射とめる姫が
どんな方なのか?
全く知らない私は、とても楽しみでございます。
☆源氏のこころ
源氏の舅である左大臣がまるで妻が愛する夫のためにするように彼の身辺を細やかに気配りし、源氏の気を惹こうとして衣装や調度品などをきらびやかに設えて待ちわびる姿や、頭中将の源氏に対するあこがれとライバル意識がないまぜになった感情がとても興味深く臨場感をもって描出されていて面白い。右大臣などは彼が心配そうにうろうろしている姿が目に浮かび、源氏の人間的魅力がかれらをしてそうさせているのだということがよくわかる。
また、頭中将の人となりの描き方も第三者の目をからませて重層的もしくは複眼的に表し、読者にアレ?と思わせ、考えさせる書きぶりにも感心させられ、こうして段々に式部の術中にはめられていくのだと思った。
☆竹とんぼ
光源氏は17歳、
左大臣家の頭中将は、源氏との友情関係を築いている。たぶん、頭中将からアプローチしてこの関係を築いたのだ。 源氏の身分が上でも構わず、どんどん行く中将の性格が明・陽とすれば、源氏は若いながらどこか憂いを帯びている。このキャラクターの違う二人の青年が、楽し気に若者らしく会話をする様子が微笑ましい。
この後きっと様々な社会的しがらみで二人の関係はどうなるのか? 物語を知らない私としては気になるし、当時の読者も物語の先が気になって仕方なかったと想像する。
☆小夜の中山
源氏、17歳の夏
元服を迎えて大人になった源氏は17歳の夏を過ごしています。左大臣からは下にも置かない待遇を受けて大事に大事にされています。今回は源氏と頭の中将との仲良し振りがよく分かる場面から読みました。ふたりとも貴公子で頭が良く通う妻とはしっくりいかない、そんな共通点があります。それでも、頭の中将が源氏のもとへきた文を見たがったり、親しく振る舞えば振る舞うほど、頑張っている頭の中将と、おっとりと余裕に構えている源氏との違いが際立っていたように思いました。ここから先、いよいよ雨夜の品定めの展開に繋がっていくようなので、期待が高まります。
☆しお
古語を発音し、その成り立ちや
その時代での意味を知ることの楽しさに
こころ弾みました。
☆葉
中将が浮き浮きして、源氏 に届いた恋文をのぞきこむシーンは、今を生きる若者と同じ様に感じられとてもおもしろかった。
千年の時空を超えて、人が同じ感情を共有していることを改めてリアルに感じることは新しい発見のような気分でもある。
恋文の束、恋文の和紙の質、恋文の歌にふさわしい色合い、とり合わせの妙に美意識が競われたとのこと、その優雅さを想像して、うっとりしてしまう。
この後に続く「女性論」も楽しみだ。
2018年1月12日 ≪桐壺9≫
☆さくらちゃん
光源氏が父の帝とよく似てるなと思いました。
一人の女性を愛すると
もう何も見えなくなってしまう…
親の血を引いてしまった源氏…
なのに 「女たらし」の代名詞で今の世に伝えられる源氏…
何故だろうという疑問が解けました。
人の口とは恐ろしい…
これが今日の1番の感想でした。
☆KUNKO
光の君は、藤壺への禁断の恋心を抱いたまま
結婚して5年の歳月が流れました。
新妻の胸中を思うと、読み手の私すらも
胸が苦しくなるようです。
世間で噂されるような恋多き男
ではない 光の君の本当の姿を知り
藤壺への一途さにも心痛めてしまいます。
これからの展開が気になります!
☆源氏のこころ
桐壷の最後のパートは短い文章のなかに明と暗、騒と静を入れ込んで源氏の若さ故の青さ、頑なさ、まじめな気質を浮き彫りにしている。作者の表現力にまたまた驚かされると同時に、源氏が「生来のプレイボーイとは一線を画している」ことがよくわかった。また、源氏物語の底流にある「タブー」というテーマについて、現代を含めていつの時代もある禁止とそれを破ってしまう人の行動のもとにある心、この永遠とも思える「謎」がロングヒットの要因の一つなのかもしれない。光り輝く美男子であるけれどもとても生真面目な源氏でさえ、禁止を破ってしまうのだから。
桐壷から帚木までの5年間の空白について、12歳から17歳までの成長と変化の著しい時期を書かないという選択は何なのか?先を読み進めるのが一層楽しみになった。
☆竹とんぼ
源氏は元服式で成人し大人社会に加わることになったが、この時まだ十二歳。
藤壺への恋情は、源氏の初恋なのだろう。ほかのことは目に入らない恋心の一途さ、自分ではどうしようもなく制御できない気持ち、初恋のせつなさに「わかりますよ」と共感させられる。
一方、源氏の妻となった左大臣の姫が初めから心を閉ざしてしまう心も「分かる分かる」と共感させられる。
次の≪帚木≫では5年後、17歳の源氏が登場する。
2017年11月17日 ≪桐壺8≫
☆KUNKO
二人の父の思いが、深く羨ましい程です。
ただ、左大臣の「お前の幸せを思って
のことをだよ??」が重いですし、
娘の心を解ろうとしないのは、今も
ある事だと思いました。
源氏の心情は、解りませんでしたが、
年上の妻と今後どうなって行くのかが
気になるトコロです。
☆源氏のこころ
今回の学習でとても印象深かったのは、和歌の世界は自由で貴賤の別無し、敬語も無し、ということだった。厳しい身分やしきたりにがんじがらめのストレス社会に風穴をあける知恵と工夫に舌を巻く。しかも歌作りが貴族社会の最高の教養の一つとされ、男も女もその研鑽に努めていたとは!皮肉あり揶揄あり風刺あり恨み節ありの和歌の世界は大変魅力的だと思う。
☆竹とんぼ
元服式を境に「少年」から大人の男性に変容する
元服式の夜に妻を迎えるのが、当時の習わしということだ。
宮中で強い力がある左大臣家の姫が源氏の妻となった。帝は源氏の後見に権力のある者が必要と考え、左大臣は「うつくしい」源氏を迎えることで左大臣家の権勢が更に盤石になると考える。
当時の価値観では「美し」ということが大きな要素になっていたのを知った。数値や論理では測れない「美」というものに最重要の価値を見ている世界観に魅かれると感じた。
2017年9月8日 ≪桐壺7≫
☆葉
源氏の元服式の描写は実に印象的でした。我が子の童姿をずっとこのままに変えずにおきたいと願ってみたり、春宮に劣らない式を挙げてやりたいと奔走したりするなど、帝の親心が丁寧に描写されていることに驚かされました。
亡き母、更衣の面影に我を忘れて「念じかへす」帝。大人の装いを身につけた光源氏に感涙にむせぶ帝。なんと情の深い熱き人なのだろうか。大きな節目ではあるものの、一刻一刻を深く感じ入り生きている人間としての帝の姿が映し出されている。
何事にもスピード感が求められる今日、つい感情までをもせかしてしまい、ここまで我が子の成長を味わってきたのだろうかと
2017年9月8日 ≪桐壺7≫
☆KUNKO
少年源氏は、光源氏へと成長し、藤壺に寄せる 初めての恋心。
藤壺も年の近い源氏に少し、ときめいているようで…。
帝が元服した愛息を見て、一人感慨に耽っている時も、
弘徽殿は、「フン!面白くないわ」って顔して、何処からか
見ているんだろう…なんて想像もして見たくなります。
其々のキャラクターが各々の中で、出来上がっていくのでは?
1000年モノ間、人々を引きつけて 止まない理由の一つですね。
☆源氏のこころ
元服を通して父帝の御子を思う心情が痛々しくみずみずしくリズミカルに描かれていて
すごいな~と思う。
最愛の人との一粒種にどんなにでもしてやりたい、最高のセレモニーを提供したいという帝の心根を阻むさまざまな壁、
良かれと思ってではあるものの源氏の運命を「臣下」と定めたこと、片親であること、
「春宮」とまったく同じようには遇してやれないしきたりの限界があること等が語られる。
作者は、最高権力者といえどもその力には限界があることと「運命の人源氏」の行く道を暗示しているように感じる。
☆竹とんぼ
「光」の字が初めてでてきた。「光源氏」の呼称の始まりだ。
光源氏と藤壺の出会いと初々しい恋心が描かれる。
① 光源氏の恋心は、藤壺が亡き母に似ているから母の面影に魅かれたのではなく、
藤壺その人に恋をしたのだということ。
② 光源氏の一方的な恋ではなく、藤壺も少年源氏を意識していたということ。
この解釈に、なるほど!と納得した。これが分かると物語の中にスーッと入っていけるように感じた。
この時光源氏は十二歳、幼い少年から恋する少年に成長している。
この後元服式の描写が続き、源氏は少年から大人の男性になる。
2017年7月14日 ≪桐壺5≫
☆さくらちゃん
(新しい妻の入内を)
帝の心がやっと、少し受け入れられるようになった事を
とてもうれしく思えました。
そして藤壺のお母様が娘を心配しながら亡くなられたのが
とてもお気の毒でした。
藤壺は、桐壺のようにいじめられる事がない様なので
安心して物語を読んで行けそうです。
「源氏」という名前が初めて出てきて
父としての愛のもとに、つけられた名前だということを
初めて知りました。
☆KUNKO
[相人・高麗人/藤壺入内]
いつの世も占いは人の行く末を
導いてくださるのでしょうか
しかし、帝の冷静に子を思う気持ちが
素晴らしい・・・。
ただヌクヌクと傍に置いて愛でるのではなく
持てる才能(能力)を伸ばしていこうと
見守る父の姿が実に頼もしいです。
新たに美しく若い妻をむかえました。
ますます楽しみです。
☆源氏のこころ
最愛の女(ひと)との1人子の行く末、
いつまでも後見できるわけでもない我が身、
女児ならば「これぞ!」と見込んだ人間に後見を頼めば安心できるところ、
子の将来を見通そうとする帝の心持はいかばかりか、
当時としてでき得る限りの情報を集めたが確たるものも得ず、
かえって不安が高まったようにさえ思える。
なぜあの決断に至ったのか、説明がないのでわからないが、
最後は「自身だったら・・」と考え、自分と我が子をつなぐDNAが鍵だったのかもしれない、
桐壷帝は政治力に自信があった人という設定だったりして?!
読者に想像させる物語ですね!
☆竹とんぼ
帝は光源氏の将来の道を熟考模索している。
7歳になった光源氏は才気煥発過ぎるほどで、
人並みの平穏な人生に落ち着きそうではない。
父帝の我が子に対する愛情と葛藤が、読者にも苦しいほどに伝わる場面だ。
帝は、我が子が自らの力で朝廷での地位を切り開いていく道を選択する。
源の姓は、この時に帝が与えたというのを初めて知った。
光源氏として、朝廷社会の荒波に出ていく準備段階になる。
この後に藤壺の更衣が登場して、物語は新たな展開をする。
読者を引き付ける新展開の仕方・タイミングが上手だと思いました。
☆小夜の中山
今回は子どもの光源氏の、高麗人による人相見の場面と
藤壺の入内の場面を読みました。
印象深く感じたのは以下の三点。
① 桐壺帝の親心、我が子よ、お前を決して
「ただよはさじ」と、子どもの将来を決める。
親王の身分を与えず、世間の波風に押し出す。
② 藤壺の入内にあたって、お付きの女房たちが内裏に行きたがることが
入内決定に大きく関わっていたこと。
③ 桐壺の更衣と藤壺の、残酷なまでの対比。
顔だちが似ているだけに、まるで合わせ鏡のように
身分の差がくっきりと際立ちました。
哀れ、桐壺の更衣。
☆葉
私にとっては2回目の源氏勉強会である。
原文を声に出して読むことが、心地よくなってきた。
古文はただただ、分からないものであったが、田中先生が誘う源氏の世界に引き込まれるうちに、
登場人物は千年の時を超えて今そこにいる人になってきた。
桐壺の母が子を想う無念さ、藤壺の母が娘の入内を案ずる心持ち、
帝の桐壺との子ども(源氏)の行く手を深く思い悩み決断する様。
いずれも殿上人という身分をも超えて、親が子の幸せを念ずる深い情が身近に伝わってくる。
次が楽しみである
≪桐壺5≫2017.5.19
☆さくらちゃん
帝の悲しみの深さ(深すぎ)と弘徽殿のイライラが
とてもよく分かる
そして、帝のウツ病とも思われる症状が気の毒にも思う
若宮の育つ環境が特殊で、
将来の源氏を作り上げる基礎が
ここにあったのかと、とても納得した
☆moonba
帝の立場は、
プライベートも公的でなくてはならないはずなのに
恋に落ち入り・・・
死に嘆き悲しむさま、周りの様子、この源氏物語の始まりは、
今日のあたりで、増々くいつきと興味深さ出して来てる。
まんまとやられてしまった。
先に進む楽しみが出来ました。
☆KUNKO
<弘徽殿の立場・遥かな現実・若宮内裏に住まう・若宮の微笑>
帝の溺愛した更衣の、忘れがたみが成長し
帝の新な心配と希望が生まれました。
この世のものとも思えない姿に 宮中が華やいでいる気がします。
これからの展開が楽しみです。
いつまでもウジウジしていた帝ですが、
父君として別の面がみられるのかな? と思っています。
☆小夜の中山
今日は久し振りに玉縄源氏の会に参加できました。
桐壺の更衣が亡くなってもう6,7年の歳月が過ぎていました。
その間、桐壺帝は、ずーっと長々と涙にくれていたのですね、
ちょっと驚きです。そして一方で時間は着々と流れ、
光源氏は六歳になり、お祖母様は他界し、宮中に引きとられて来ました。
私は今日の所を読み、最初は弘徽殿女御はイやな女かと思いましたが
まだ子どもの光源氏を可愛がって、自分の娘2人と比較して「私の娘より優れている!」と感じるところは、
ひと筋縄ではいかない弘徽殿の人間としての深さが感じられました。
今後ますます光源氏は成長していき、ただ可愛がってばかりはいられなくなるだろうけど、
その弘徽殿の変化を注目したいと思いました。
☆源氏のこころ
今回も紫式部の複眼的視点に、またまた感心させられた。
帝の長く深い悲嘆、北の方の浅茅生での暗い生と
若宮の光り輝く登場の明暗もまた素晴らしいと感じた。
☆竹とんぼ
更衣の死から数年経っても、帝は悲しみから現実になかなか立ち戻って来られない。
正妻である弘徽殿はあくまでも現実に生きている。
非現実世界の哀しさ・美しさ、現実世界の確定感・安心感のどちらも納得できる。、
紫式部の描写力が素晴らしい。
☆ 葉
「源氏物語」大変有名な古典であるけれど、今まで血の通う人として、
登場人物が私の中に入ってきたことはなかった。
順子先生の語りで、そこに生きている男性・源氏の父が身近に感じられ、
これから夜も進めていけそうな気がしている。
これまで仕事に忙しく、必要に迫られて読む本や、気分転換に読む本はあったけれど、
少しためらいのある本はツンドク(読)ばかりだった。
日本の古き良きものについて、少し詳しくなりたいという思いもあった矢先で、
先生に導かれ(だまされながら)仲間たちと読みひたってみたいと思う。
昨年京都御所、清涼殿など見学してきたが、今日そこで暮らした千年前の人々の姿がありありと感じられ
心楽しいひとときだった。
2017年3月10日 ≪桐壺4≫
☆moonba
虫の音~
・誰が・・・誰を・・・どうしたか?
これを 言葉の表現でさがし出す事の 面白さがわかってきた。
・それぞれの心情を表す言葉が 奥深いし 美しい。
特に「あはれ」=心が動く には びっくり。
今は美しい意味に思えないが とても素敵な言葉だと驚いた
・魂の存在を しっかりと表してるのがわかった。
今は存在は薄く 感じなくなった時代になってしまったのだなぁ~
☆KUNKO
更衣を失った母君と帝それぞれの想いが
伝わる章でした。
母君は 若宮を心配しているけれど
帝のことまで思いがおよばないし
帝はそんな母君をも想いやり
共に大切な愛しい人を失った悲しみに 打ちひしがれている。
これから 二人が気になります。
☆源氏のこころ
母君、命婦、帝の思いは 理解できたつもりだったが
帝と更衣、玄宗皇帝と楊貴妃のように
深く愛した人たち(当時の)にとっては
肉体と魂の世界がとても近く 隔てがないかのような表現に驚き
違う世界を感じた。
☆竹とんぼ
帝の使いの命婦が 桐壺の更衣の実家を訪れる
ここで 母を亡くした若宮が 祖母と暮らしている
愛する女性を失った 帝の悲しみの深さ
娘を失った母君の悲しみの深さが
景色、情景、匂いとして感じられる
式部の表現力だ。
第3回 9月9日 ≪桐壺3≫
☆さくらちゃん
帝の気持ち、桐壺のお母様の気持ち、弘徽殿の気持ち、それぞれの方々の気持ちがよくわかります。
でも、帝 しっかり!
そして弘徽殿の気持ち良く分かります。
又、子に先立たれた母の悲しみ、
我が身に置きかえて考えると、とても耐えられません。
☆moonba
それぞれの悲しみに対する、心の表現が楽しかった。
特に母親が、生きる希望だった娘の死の悲しみ落胆がわかりやすい。
そしてその状況を見ている女房の冷静さと言葉もクールでいい。
短い文章の中に、いろいろの立場の心を描いている。
素晴らしさと面白さが今日少しわかってきた。
増々楽しみになってきました。
☆KUNKO
桐壺の更衣を亡くした帝と母親の悲哀が、心の中に沈み込むように入ってきます。
良く理解でき、読んでいて自然に涙が出ます。
紫式部の描く平安の人々は、自分の感情に素直でラテン的ですよね。
短い言葉、文章の中に多くの景色が、映画の一場面のように…というか
その場に私も居合わせたかのように思えますから不思議。
☆源氏のこころ
更衣の死、母君の嘆き、死の波紋 夕月夜の訪問
作者の卓越した表現力に魅せられました。
しっかり者で自信に溢れた更衣の母の悲嘆ぶりと、
夕月夜の設定が哀しく美しいです。
☆竹とんぼ
桐壺が亡くなりました。
帝は茫然自失で公務も手につかない状態です。
これに批判的な北の方、帝と気持ちが同調している周囲の人、帝以上に取り乱している桐壺の母、多角的な目線で描かれているところが物語の魅力です
☆小夜の中山
「更衣の死」から「夕月夜の訪問」
儚く亡くなってしまった桐壺の更衣。頼みにしていた娘に死なれた母君の姿が印象に残りました。そもそもこの母君は最初に登場したところで「いにしへの人」と表現されていたので、昔風のたしなみを備えた人物だったはずが、しきたりを破って火葬の場にまでついて行ってしまった・・・
これにまた、お!と意表を突かれました。
そして秋がきて、月の夜に高いところから俯瞰するように母君の屋敷の荒れた庭の様子が描写されて、しみじみとシビレました。八重葎という言葉、素敵です。
この母君の描写だって、本の数行のことなのに、ありありとイメージが浮かんで、これが古典なのだなーと思いました。
第2回 6月22日 ≪桐壺2≫
☆さくらちゃん
帝のありがた迷惑な愛情の中でも
強く優しい心の持ち主の桐壺が、なんともふびんでなりません。
他の奥様方からの嫌がらせは、まるで現実かのように想像することが出来、
恐ろしさで身震いしました。
桐壺の精神的なストレスは、どれだけのものだったでしょう。
その時代にカウンセラーがいればよかったのに。
☆moonba
これほど美しく心優しい更衣を、特別以上に愛し深く入れ込む帝との関係が
ありありと表現されてて、ひやひやとして引き込まれる。
愛は、今も昔も人生のテーマなのかも。
嫉妬も、1000年経てもなくなる事なく、進化しないものなんだと思った。
☆KUNKO
文中には容姿について詳しく記されていないのに、帝や桐壺の更衣の姿形立ち振る舞いまでが、目にみえるようです。
帝が己の立場を忘れて、一人の女性に盲目的に愛をおしみなく与えているというのもすごすぎる。
紫式部の時代にワープして、どの更衣の女官でも良いので、その場に立ち会いたいと思った。(のぞき見したい!)
紫式部という作家の、千年の時を超えて尚、人をひきつけてやまない力って何でしょう?
選び抜いた言葉、構成…とにかくスゴイ!
現代に生まれかわっていないんでしょうか?
☆源氏のこころ
少人数での受講なので、疑問点などをその場で解消でき、スッキリします。
当時の貴族の生活環境や女性の立場は、現代と大きく異なるにもかかわらず、
彼女らの心根に寄り添える感があり、不思議です。
☆竹とんぼ
いよいよ光源氏が誕生しました。
物語冒頭から、帝の恋情と源氏の母桐壺の美しい様に引き込まれます。
光源氏が、幼時から人を魅了する特別な力を備えて誕生してきたのを、「当然」と思わせる導入部です。これからが楽しみです。
第