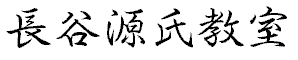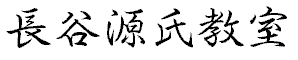
長谷教室は1997年9月から始まった近所に在住の主婦5,6人の集まりです。
最初はお昼をはさんで一日中、原文を読みそれについて色々話をしながら
のんびりと源氏の世界に浸りながら楽しんで居りました。 最近では二ヶ月に
一度午後一時から四時ごろまで会員の自宅を借りてやって居ります。
この15年で桐壺から葵の巻きまで進みましたが、本の関係で又桐壺に
戻り初心に返って読み返して居ります。そしてこれから須磨に入ります
連絡先090−5405−152
2023年5月25日
四月、入道の献心ぶりが好意的には見ているが 不本意でうっとうしい。他人の家で、ぬかりなく世話をされても落ち着かなく居場所がない感じがするのだろうか? 都への思いが切なく現実を思い知る。源氏の心情はこれからどのように変化していくのでしょう。他人の親切すぎるのは、気も使うし落ち着かないきもち…分かります。 あすなろ 都を離れて久しく手にしなかった琴を奏でられた、その音に入道は心を奪われ自らも奏でる機会をえる。源氏にとっても宮中への思いをお越し悲しみが勝るので心を封じてしまう。しかし入道にとってはこの機をのがさず娘を源氏に 近づける好機ととらえる。 ひとつの場面に一緒にいても各々の心の内は様々。当然の事とはいえ今までの自分の行動を反省してしまった。 恵み 源氏が月に誘われて琴を弾き始め都への思いを募らせている時に入道は、それを聞いて心ひかれ自ら琴を弾きはじめる。その巧妙な弾き方に源氏も興味を持つが、それぞれ思惑がちがっても、入道にとっては親心が報われる事になるのだろう。 竹笛
まるで「かすみ( を食べて生きている時代の出来事の様だ。
あすなろ
源氏を迎える事が入道にとって願ってもない事であり、その事にこの上ない喜びにあふれている様子が手に取る様に表されている。
しかしあくまでもつつましく、押しつけがましくない人柄にこの先の成り行きがどうなるのか、楽しみです。
めぐみ
女君への返信は、須磨でひどい目にあった日々を嘆く言葉ばかりで女君はどんなに心配するだろうか。初めての経験とはいえ自分の苦労ばかり言う源氏は情けないが
明石に来て入道の気遣いとおもてなしに慰められたと思う。
竹笛
2023年1月25日 明石の巻
新しい年を迎えささやかなお食事会
。2時間ほど楽しい会話であっという間に時間がたってしまった。今年も源氏物語の世界を楽しもう!
本日は明石の館です、、、。
あすなろ
源氏は都に戻る事を強く願っているとは思えなかったが、
日々の状況は心に思い描いた事はなかった。その日常は慣れるという事ではなく反対に都での生活を人との交わりを強く心に思い起こしていた。その思いが夢に現れた先帝の言葉に心動かされその心の動きを導くように入道の迎えが来た。人は願いを強く持てば道が開かれると言う事なのでしょう。
惠
明石入道の領地は源氏の洗練された目にもかなった趣きのある館や庭であった。明石邸に落ち着いて源氏は京へたよりをだす。特に (入道の宮ばかりにはめづらかにてよみがえるさまなど聞こえたまふ(藤壺だけには身に起こった不思議な体験を全て聞いて欲しいという源氏の心情が伝わる。
竹笛
2023年3月22日 明石の巻
源氏物語の原文は、一文一文の言葉の解釈がとても難しい。でも、奥が深く心細やかだ。 現代で失われつつある風情に溢れている。
2022年9月28日
「さへずる」 と言う言葉の使い方が非常に興味深い。
同じ立場や感性で話す相手がいないのは、とても不安で孤独なことだと思う。人と話がまじわせる事は、心が癒やされ、安心感が生まれます。年を重ねるとそういう事がとても大切だと感じます。
あすなろ
自然に対する人間の力は限りがあり、神仏に頼り祈る、これは今の時代にも変わり無い。人間の行いに対する戒め、罰としての自然の猛威、神仏に祈り願いつつも、人の力、信頼のおけるすべてを許せる人の力を求め心の支えが必要だったのだと強く思わされました。
恵
異常なまでの大風や雷にさらされ源氏は神仏に祈り続けてようやく鎮まるがすっかり心の平衡を失ってしまう。夢に父の姿が出て来てすがる思いで訴える。今までしっかりと生きて来た源氏でも自然の脅威には立ち向かえない。昔も今も身分に関係無く人間の弱さ、自然に対する畏怖を感じた。
竹笛
2022年6月29日
天変地異のただ中に人はなすすべも無く怖れ、嘆き、苦しみの中、神仏に祈り助けを願う。
人間は世の中全てをコントロールする存在ではないことは、、時を
経ても変わりない事を、改めておもわされる。当然の事なのに、、。忘れてはいないかな。
恵
二条の女君からの手紙には京でも
長雨が続く中、心細い日々をおくっている様子で、源氏は何も助けることも出来ず増々不安と恐ろしさに悩む。
竹笛
2022年4月27日
中将との短い再会に互いに夢中で時を過ごしたものの未練が残る出発だ。二人は心の内をぶつけ合う、、、。
長い月日共に過ごした二人だから出来たのだと思う。激しい言葉を投げ合い心の乱れを出しあう。とても深い場面です。 あすなろ
頭中将との再会は喜びが大きく心底心安まる時を過ごしたものであったと思います。その思いが別れの辛さに感情のままの言葉となりそれを中将も受けてしまい後悔の思いを抱えてしまったのだと思います。二人の間柄の深さが伺えました。
惠 源氏は中将との別れの時、もう都には戻ろうと思わないと言ってしまいますます気の晴れない日々を送る。 須磨の巻は源氏の孤独感とそれに呼応するような海や自然の厳しさが印象的であった。 竹笛
2022年1月26日
なんとうらやましい友との関わりでしょう。 あすなろ
須磨での日々に春が訪れ桜の若木に花も都と同じに咲く季節の中、人は人との結び付きで生きている実感、喜び悲しみもあり生命を与えられているのだと思う内容だった。
多くを語らずとも理解しあえる間柄、人間だけではなく生あるもの全てが、個では生きられないのではないかと思われた。 惠
つれづれなる時を過ごしていた源氏の所に三位の中将が訪れ、その暮らしぶりに源氏らしさを見て一気に源氏と過ごした日々を取り戻すように話し、土地の人々とふれ合い、採れたての魚や貝をたべる。
読んでいて実感出来る程 楽しげな二人の様子にこちらも癒やされる。 竹笛
2021年9月29日 「須磨」
冬の須磨 中国の故事、王昭君のことは初めて知りました。画工に賄賂を贈らなかった王昭君は、帝に知られることも無く北方の胡の国へ遣わされてしまった。王昭君がどんな人生を歩んだのかとても興味深いです。 あすなろ 源氏の感じている寂しさの一番大きなものは何なのかと思ってみた。生活環境の違いその中での日々の暮らし方。多くの親しい人々との交わりどれも大切なものだとは思えるが自分の現在の状況が自分が選んだとは言え 想像以上に違いすぎていて受け入れられないからなのかと。 めぐみ 冬になって増々寂しさがつのり源氏は琴を弾いたりして慰めていたが、歌を作っても返してくれる人がいない。それでも源氏は今は耐えるしかないと思っている。しかし下人の仕事などを間近で見なければならない今の自分を[かたじけなう]と自らなぐさめている。高貴な人の思い?プライドなのだろうか。 竹笛
2021年7月28日 「須磨」
須磨に移り住んだ源氏の寂寥感は計り知れなく大きなもの
だったと思うが、私は一番は人との関わりだと思う。
その関わりを切り離すべき時の権力者大后の策は源氏の孤独感を
強めるのに効果絶大だったと思う。
惠
源氏はそっけない訪問もわざわざ足を運んでくれたことに深い感謝が
溢れる。?????????? 一番大変、辛くて悲しい時、
?誰が側に寄り添ってくれたのか、心配してくれるのか、
大切なことを気づかせてくれるものですね、、、。
この世のあぢはいは工夫と心次第で暮らしを楽しむ事は出来ると思う。
貧相な暮らしでもその人しだいではと考えるのは現代だからでしょうか?
あすなろ
源氏はどこにいても風情のある暮らしぶりを楽しむ事が出来る人
なのだろうとおもう。それを弘徽殿は謹慎中の身でありながら趣ある家に住み
漢詩を読み風情ある景色を楽しむなどもっての外と怒り心頭で、
なかなかこれも小気味よい。?? けれど源氏の本当の気持ちは孤独を
深めていくのである。
竹笛
2021年1月4日(月) 須磨
「前向きの自分を装う、、、、」頑張っているけど何か侘しく悲しいおもいです。
私も時々そうゆう自分に「ハっ」として苦しくなります。
素のまま、自分らしく生きていくのは以外と難しい。
あすなろ
環境の変化の大きさは、侘しさがつのる事ばかりの様子、でも源氏と
共にいる人々の源氏に対する思いの深さは、源氏の人々に対する優しさ、
思いやり等人間関係の深いつながりを思わされます。
大切なのは人と人との心のつながりだと。
めぐみ
「須磨にはいとど心づくしの秋風に、、、、」の朗読を聞いていると
当時の言葉で切々と語られ、状況が目に見えるようで、波の音や
風の強さが五感に訴えてくる。そして須磨の地に引き込まれて
源氏や共人の望郷の気持ちに共感して心に響いてくる。
竹笛
2020年9月30日(水) 須磨
尚侍の君との密会で須磨へ行かなければならなくなった源氏。
尚侍の君は世間の笑い者になっても、心は源氏を忘れることが
出来ない。
また、一方で帝はそんな尚侍の君の心を知りながらも愛しい、、、。
なんとも複雑で切ない場面でした。
あすなろ
時の権力者が考える事は何百年の時を経ても変わらないのだと思うと、
親近感が持てるようになりました。
人の感情、喜怒哀楽の表現の方法は変わっても心の動きは一緒なんですね。
当たり前 ?
恵
今回は源氏のことではなく、都に残された人たち、帝と尚侍の君の悲しさ、
淋しさ、嫉妬、後悔、、、、、。
源氏のいないことが光かがやかない、つまらないものであることがわかり
そして院の広く望んだ遺言守れず都から追いやってしまったこと等。
尚侍の君は源氏に会えないことが悲しい淋しいよりも帝が同じように後悔
していることを知り罪深さに心震える気持ちである。
帝は自分のふがいなさに苦悩している優しい人だが母君に頭を押さえられているのが
なんともふがいないと思うし尚侍の君も奔放な姫君であったのに現代ならばとっくに
家を出て働いて生きていたのにこの時代ではしょうがないと思えるのです。
カオル
尚侍の謹慎も解けて再び入内する。帝は世間の目も気にせず愛情を傾けるが、
尚侍の君は源氏への思いにとらわれていて語り手が」かたじけなき」と言って
いるのが面白い。
帝も源氏のいない宮中が物足りなく淋しいことに気付き、亡き院の遺言を
何も守っていないことや春宮を皇子にする願いもかなえられない。
権力には逆らえず自分の弱さに絶望しているようで開き直ってみたり、もっと
しっかりしなさいと言ってやりたい。
竹笛
2020年6月24日(水) 須磨
須磨の地の源氏にとって都にいるゆかりの女性達との
文のやりとりは、ただ懐かしさだけではなく離れて気付く
又、正直な気持ちがのぞく内容で、今さらながらに源氏の
人柄が表れていると思われました。
めぐみ
うつうつとした日々を送る源氏にとって御息所からの長い手紙
は深いなぐさめになったと思う。
都にいたときには実感できなかった熱い思いを今さらながらに
かみしめている源氏である。
花散里からも書き集めた
手紙の数々、、、、。築地塀が崩れてなど使者から聞けばさっそくに
京の家司のもとに荘園の者をかき集めて修理をせよと命令を出したり
する。源氏
自身つらい毎日を送っていても都への目配りはきちっと
しているのに本当に感じ入りました。
カオル
六条御即所からの手紙の返事を書く源氏。
使いの者が何日もかけて届けた心のこもった手紙に源氏は慰められ
使者にもやさしく接している。返事には自分もあの時伊勢に行けば
よかったなどといつもの態度とは違って、優しく愛にあふれていて
御息所をもなぐさめているのしょう。
竹笛
2020年1月29日(水) 須磨
源氏が都を追われ、あの藤壺が源氏に対しての本当の気持ちを
見つめる事が出来たとは、、、、人はその場になってみなければ気が付けない
心の奥底の本音があるのかもしれない、、、。
あすなろ
源氏からの返しで入道の宮、尚侍の君、姫君、伊勢の宮からの内容は
各人の想いや人柄がしっかりと表れていて文は人成りの思いを
強くしました。
恵
話をお聞きして少しずつ不勉強な私でも楽しくなってきました。
これからもよろしくお願いします。
英子
源氏が須磨へ行ってしまってからの女性たちの嘆きは深く、あらためて
源氏のすごさを感じました。源氏からの便りの返事に一人一人の深い
悲しみに源氏も涙します。 とくに伊勢の御息所のこまやかな、教養
あふれる頼りに深く慰められ、自分がかつて若い時深く愛し今も変わらない気持ちであることを確認する。 源氏の女性たちの中で御息所は一番素晴らしいと私も
大好きです。
カオル
源氏は須磨に来て、それぞれの女性の返事を読んだり、子供への気持ち
などを非常に冷静に考えて、自分の態度を見つめていく。
そして何より自分の今までの罪(特に藤壺のことなど)を償う勤行を
日々の目標に定めたことはさすがだと思った。
竹笛
2019年9月25日(水)
源氏物語は一つ一つの事がらがなんと細やかに表されているのだろう。
詫び住まいには、人々の出入りで賑わっているが、対等に話が出来る人は誰もいない、
これから続く空虚な時間に心が暗くなる源氏。語り合える人がいないとは
本当に寂しい事だと思います。
涙ー泣くということの意味と思いを改にしました。
あすなろ
須磨に建つ住まいを目にした源氏の様子が手に取るようにわかる箇所。
おかれた状況により見方が違うという正直な気持ちが伝わってきた場面
でした。恵まれている人生を送ってきても何が起きるかわからないのは今も
昔も変わりない、その時をどう生きるかですね。
恵
源氏がいかに新しい地 環境に慣れるのに苦労しなじめなかった事が
良くわかりました。
兼坂
あの人ともこの人とも別れがたく悲しい思いで旅立って来た源氏は
重い心のまま須磨に着く。住まいもそれなりに風情がありさっそくに
荘園の管理責任者に改築修理を命ずる。
都恋しさしかないとしても、何とか暮らしてゆくのかしらと思うの
だけれど心と心が通じ合うような人がいないと気づく、しかし昔も今も
人の心というものはあまり違いはないと思う。
すぐにそのような人に巡り合えるものではないしこちらも努力をしなければ
求めることばかりで人間関係ではずい分苦労していると思うがやはり
上流社会の人なのですね、ちょっと理解出来ない気持です。
カオル
源氏の須磨への旅の様子は今までの華やかな生活とは打って変わって
山の中の侘しい所でこれからいつまで流謫の日々を続けるのかすっかり
落ち込んでいる。
しかし尚侍への文には「こりずま」という言葉を使って
懲りない自分を歌って、源氏らしさは健在なの
2019年7月24日
「花の都を立ち帰り見よ」大命婦の歌に源氏は命婦の
気持ちを感じ取り、本当に励まされた事でしょう。
日ごろの源氏の心配りが並々ならぬものだった事は、やはり人の心を
捉えるのかもしれない。
それなのに世間は冷たい。
我が身を守ろうとする。
それは今の世も同じだ。
現実の世の複雑な姿に納得がいかない。
あすなろ
いよいよ須磨へ出発の時が来てしまい、源氏のゆかりの人たちとの
悲しい別れがたい気持ちを胸いっぱいに抱えて源氏は旅立って
行きました。東宮に会って無言の別れも言いたかっただろうに、
保身のために右大臣側の顔色ばかりを見ている世の人達の
冷たい態度を恨みながら、女君のことを心配しつつ都を去って行く
源氏があわれでならない。
カヲル
いよいよ出立の日も近く別れをすべき人には別れを、しかし源氏は
納得のいかない出立であって世間の人々はそれを分かっていながら
我が身をまもるため、挨拶もない。
月明りの中狩衣に身をやつして、女君との美しくも切ない別れを
胸にしまい、夜明け前に旅立ったのだった。
竹笛
2019年5月27日
「須磨」 御陵参拝
春宮の行く末のみ案じ、後楯となって守ってくれる源氏に
全てを託した藤壺。その源氏の須磨行きは
、予想だにしなかった
出来事だったでしょう。??? 桐壺帝の遺言が、いずれも時の
権力者のもとでは無かったかのようになってしまう。
今の世も少しも変わっていないと思います。人間の気持ちに
時代は無いと、、、
恵
源氏にとって最も大切な人。入道の宮の春宮への先の事を心配
する心情を無事に実現させなくてはとの決意を新たにした源氏。
須磨への退去は春宮を守ろうとする思いであった。が二人の恋の
胸中は煩悩に苦しんでいる。本当に伝えたい事をぐっとこらえて
互いに案ずる気持ちを込めての別れは本当に切ないものでしょう。
あすなろ
源氏物語の時代には、一時的な別れでも永久に会えないようなあり
様で、思いのある人たちとのいとまごいに時間を取られる。
一番心配でたまらない紫の上への心くばりはさすがとほっとした
気持ちになる。しかし立場を考えずに敵側の女君に連絡をつけたりと
、源氏を心配する人々にたいしても軽薄としか思えない行動をとるなど
わからない面もあるのである。
カオル
出発の前日に入道の宮に会う。 宮は桐壷院も亡くなり、頼りにしていた
源氏は須磨へ旅立ってしまう。自分は出家した甲斐もなく悲しい日々で
あると以前とは違って素直に自分の感情を表している。二人の思いは
ただ春宮の世を実現させることであって、お互いに求め合う気持ちは
まだ我慢しなければならない。
竹笛
新しいお仲間が入会しました。
皆様のお仲間に加えていただきまして、田中先生のお話も分かりやすく
今までになくお勉強をさせていただきまして感謝しています。
これからもよろしくお願いいたします。
英子
平成31年3月27日
「須磨」続き 出立準備
須磨への出立準備で源氏は都に残す女君のために細心の心配りを
する様子が書かれている。今までにも関わりのあった女性たちに
対しての心遣いを思い起こせば、当然とも言えるが。源氏の
おかれている状況を考えると我が身より以上に少しでも不安の
材料を無くしたいと思っての事だったのだろう。
源氏の人としてのこの行為は並ではないと思う。
恵
出立の準備をする源氏、全ての事に几帳面な源氏は須磨へ
持っていく物は最低限にし、二条の邸に残る人を選び、荘園や
牧場の管理をする人や事務の人など的確にえらび、源氏の
人を見る目や女君への教育も充分にしていたので後を任せることが
出来た。この文では源氏の指導力、事務能力経営力が初めて書かれて
いて興味深い。
竹笛
平成31年1月25日
「須磨」続き
大きく力のある源氏に守られていた女君を始めとする女性達にとって、
源氏の存在しない世界など想像出来ない事でしょう。
彼女たちの行く末は大いに気になる所です。
惠
無紋の直衣を着ても「あてきよら」な源氏。なんと、うらやましい限りです、、、、、。
女君の涙を見せまいとまぎらわすさまは並々ならぬ心の深い
先の見えない悲しみが感じられた。
あすなろ
都を去ることになっていとまを告げなければならない人が、それも
「それでは行ってきます」のひと言で済まされない人たちが多く
いることで源氏という人の見栄えの良さに加え心映えの良さで多くの
女性たちに愛されたことが、今更ながらわかり一層あわれでなりません。
カヲル
月影の中を忍びやかに入って来るやつれた源氏はいつもの華やかさとは違い
静かでにおいやかなけはいで、たとえようもなく美しい場面である。
そして月を見ながら花散里と昔語りをして源氏の心は少しは癒された
のだろうか。
竹笛
平成30年11月28日
須磨の巻つづき
源氏の須磨行きは、女房や家臣にとって境遇の変化に
戸惑う様子、 不安に思う様子、 家の色々な所が荒れて
行く様、 世の中のあからさまな変わりように、初めて
気が付く源氏の様子が細やかに書かれていて、源氏の
心の動きが興味深かった。
あすなろ
」世は憂きものなりけり」 源氏の心境である。
父帝の生きていた頃には栄華をきわめていた源氏も
父帝亡き後右大臣側に権力が移ると人々の心変わりを
日ごとに認めざるおえない。
都を去るにあたり愛する人たちへの心残り、心配に苦悩
する。 門前市をなすという状況は権力がある場合であると思う。
落魄した人に見せる他者の心根の優しさこそ本物の愛情だと
思うのである。
いつの時代でも同じ事が言えるのではないだろうか、、、、。
カオル
源氏は左大臣家の人々につらい別れを告げて二条院に戻ってみると
人々は右往左往するばかりで、源氏についていく者、離れて右大臣側
になる者など世間の変わりようを見た思いであった。
紫の上にはこの現実のきびしさをわかってほしいし、この邸を守って
ほしい気持ちを伝える。源氏の紫の上への確かな教育に感心しました。
竹笛
平成30年7月25日
須磨の巻
源氏の生き方、存在そのものが弘徽殿の心を乱す。
色々な人を悲しませる恋。
理解するのが難しい場面でした。
たとえ本当に無罪だとしても人としては有罪だと思う。
あすなろ
流罪の決定を待たずに自ら明石行きを決めた源氏。
左大臣と会いそこでの左大臣の想い悲しみ、嘆きを
共にし人間としての心根を現し思いを語る場面を
好感を持って受け入れられました。
めぐみ
左大臣が源氏と対面して不運な源氏への思いと、
何もできないつらさ、娘がこの事を知らず薄命で
あったことはせめてもの救いである、など、思いのたけを
話す。源氏もなぜ須磨に行く選択をしたかをていねいに左大臣に
説明する。 お互いに信頼しあって気持ちを打ち明け深い心の
つながりを感じた。
竹笛
平成30年5月23日
須磨の巻
源氏の人生が明から暗に次第に移りその間の心根が手に取るように
表現され、やっと身近な存在になった気がします。最後まで春宮の
事を思い罪人になる最悪の状況を避けたのは賢明な選択だと思いました。
恵
右大臣側の攻勢に宮中で孤立してゆく源氏は流罪になり都を追われる
ことになり、 一番の心配は女君の事、、、、、又、出家した宮からは
熱い想いの手紙が毎日届くことに面食らう源氏。
いつ戻るかわからない旅立ちに人々の心の動きがとてもすなおに書かれて
いて面白いと思いました。
あすなろ
今回より須磨に入りました。
日を追って右大臣の攻撃が強くなりさしもの源氏もやりきれない気持ちの
日々、無視をして耐えていれば何とかなるだろうという甘えは通用しないと
感じ初めてきた。 最悪流罪という事になる前に自ら都を立つことを考える。
人生の最大の危機に立ち向かわなければならない。本当に辛いだろう。
読者である私も胸のふさがる思いである。
須磨という所はどういう所だろうかと、源氏にとって心安らぐ場所であって
ほしいと思うのである。
カオル
源氏は今まで何かと危ないことも平然とやり過ごしていたのに今度ばかりは
春宮の身に及ぶことを恐れて須磨という畿内のぎりぎりの地で謹慎するということで
流罪を免れようとする。本当によく考えられた処し方に感心した。
紫の上との別れは辛いが、後を託せる女性として源氏は教育してきた。
源氏の須磨退去によって世の中はどのように変わるのだろうか。
竹笛
平成30年3月28日「花散里」を読んで
```感想文 花散里
桐壷院亡き後の源氏は右大臣の勢力が増すことにより
様々な苦しみ、悩みの毎日である。出家を考えるが、
心に残る人たちのことも忘れがたく、父の女御で
あった麗景殿を訪ねていくのである。落ちぶれた有様なれど
優しく品格のある人と昔話をするうちなぐさめられ、いやされていく。
そして女御の日々がどんなにか寂しいものなのに自分を見失うことの
無い人に心打たれるのである。そして源氏という人も又人間として
品格のある人だとおもうのである。
カオル
この短い巻にどういう意味があるのかと思ったが、源氏にとって
気持ちをリセットする大事なひとときでありほっとする一巻であった。
?? 源氏が麗景殿女御にあいに行き、橘の香りがなつかしく香る中で
お互いに世の中から外れた身の上を解り合え、昔話ができて源氏も
胸がいっぱいになった。そして三の君をたずね久しぶりにかかわらず
お互いに気持ちが通じ合うことが出来た。
五月の木々の様子や橘の香りそしてほととぎすの鳴き声など昔なつかしい
自然の風情が源氏や麗景殿の気持ちと相まって美しい巻になっていると
思いました。
竹笛
平成29年8月28日賢木の巻 発覚を読んで
尚侍の君と源氏の逢瀬が右大臣に、そして大后に知られるであろうと言う事に至る場面。二人の気持ちの高まりは理解できなく無いが、後先を考えない無謀さ!!これが恋する事なのでしょうか?
かい
尚侍の君と源氏の恋。大胆な二人の行動は歯止めが効かない。中宮の事では何も出来ない位悲しんだのに…。現代の感覚では理解するのが難しい。が、その辺がこの物語の面白さなのかもしれないとも思う。男”も”ありー のもの表現はとても面白い!
あすなろ
一番知られたくない人(右大臣)に分かってしまった。ふてぶてしいまでの源氏ではあるが几帳の中に顔を入れられたのではもうどうしようもなくなり死にそうな程の、尚侍の君を慰めるばかりであった。本当に源氏は「こりない」男だと思う。
カオル
源氏は危険な恋程積極的になって尚侍の君との夜な夜な会って読者をハラハラさせる。とうとう右大臣に見つかって自暴自棄になっている源氏は本当にもっと気配りに人では無かったのか。
竹笛
平成29年 6月28日 賢木の巻 「憂さ晴らし」
Windows メール から送信 源
源氏と
中将の友情が自分の心情をあからさまに出すことの少ない源氏に 酒宴の
乱れを誘ったのではと思い、心許すことの出来る友の
大切さを強く思った箇所でした。
かいめぐみ
酒に酔った源氏初めてです。何かホットするような、、、、。
人間源氏千年前も今も人間って変わらないと感じました。
中将との友情もほほえましい。
永田 カヲル
源氏は右大臣の司召しにすっかり気持ちが落ち込んでいたところに
中将が韻ふたぎをしようとやって來る。源氏に何とか気晴らしを
させようと中将のやさしさと共に源氏が心を開いて優雅な遊びや
演奏をする姿にほっとしました。
竹笛
平成28年11月30日 賢木の巻 御八講果ての日を読んで
御八講果ての日の中宮の決意、その事柄の重さが周囲にもたらした影響力の大きさ。
現代の世でも同様な重大事そこまでの決心をさせたのは中宮の母としての思いが一番だったと思うが、凡人である人間には考え及ばないことです。
Kai
中宮の出家に対する強い意志に対し動じない心の強さを感じます。深い悲しみを通し、人はいろいろな決意をしていくのですね、、、。
あすなろ
今日の場面は悲しくも美しい所でした。中宮の出家の強い決心にみんな涙しました。読んでいる私たちも心が震えるようでした。
カオル
御八講の荘厳な場面、月の煌々と照る雪の美しく静かな場面で、それとは反対に人々の心は中宮の出家に対してそれぞれの悲しみと驚きに沸き立っている。
竹笛
平成28年9月28日 「賢木」 隔つる霧
`先帝亡き後の宮中の空気が源氏にとり非常に
悪意に満ちたものに変わり、行く末の不穏さを
感じさせる様子、今の世でも同じ状況があるなあと
納得させられました。
KK
代替わりをする事でいつもの景色が変化して見える
、初めは馴染めずにいるが少しずつ、受け入れて
いくのでしょうね。
GM
源氏が大変な状態になるようないやな予感がする。
右大臣側のわなにからまれてゆくようで、心ふさぐ
思いがする。
NK
弘徽殿の思いどうりの世の中にしようという気配が
徐々に迫ってきて邪魔者の源氏はどんどん追い詰められて
行く。 中宮と亡き帝をしのぶ気持ちは同じ思いで、
雪の中勤行を行う場面は印象的である。
TF
平成28年7月5日 「賢木」 紅葉の山づと
女君が女性として成長し、そのために悩みを抱えることになり、その心情を察しながらも
かわることのない源氏の行動、理解に苦しみ読み進みました。
KM
源氏の自分の心に正直なことが宮の心また姫君の心を苦しめている、、、。
心とは本当に思う様にならない切ないものです。
GM
男源氏と女藤壺の複雑な心模様、、、、。
皆でカンカンガクガク いつもながらの源氏が藤壺には
本当にわからずやになってしまう。
NK
藤壺が必死に隠し通してきた秘密を、源氏の緩い気持ちでヒヤヒヤさせられ本当に
気を許せない。
もっと大人になってと言いたい。
竹笛
平成28年5月31日 「賢木」 雲林院
藤壺への思いで心晴れない源氏も日々に心和らぐ事が
出来た。大きな力が紫の上を思う気持ちだと思うと
なぜか安心できました。
KM
いつも現代の事とあわせて考えています。
つまらなく思える日々の中に幸せがあるのでは、と思う今日です。
GM
源氏は本当にいい人だからバカみたいな所もゆるせるのです。
NK
お寺にこもる程思い悩んでいたのに落ち着いてくるともう
朝顔にふざけた手紙を書くなんて、源氏らしい。
竹笛
平成28年3月15日「賢木」 籠りゐ・母と子
*藤壺の母としての心情があふれる内容でした。目に浮かぶ
親子の場面でした。
*世の移り変わりの無情は今の世も同じ、親子の切なさが
心に残りました。
*千年前のことわりも今の世もあまり変わりないことを感じる。
母子の情も又、、、、。
*源氏の余りにも若い未熟な本気の姿と藤壺の冷静な
大人の対応が切ない。
平成27年5月12日「賢木」 代わり目
桐壺帝の亡き後の源氏、左大臣の立場の変化の大きさは
現代の社会においても、よく耳にする事で興味深かった。
又源氏が暇が出来、左大臣家に出向き若君との多くの
時を過ごすなど仕事中心の夫が失職し家で子供とのんびり
遊ぶ様子が目に浮かぶ、今日の内容は源氏の世も現代の
世も変わりがないことを知らされた。
KM
院崩御後の大后は今までの色々な無念の思いが一挙に
開放されてやりたい放題、源氏も嫌気がさして左大臣家に
通ってわが子と遊び女房達に細やかな心使いをしたり、
今まで出来なかったゆったりと家庭的に過ごす姿に、作者は
「今しもあらまほしき御ありさまなり」と皮肉ってはいるがこの
時代でも男性の理想像として家庭的で忍び歩きもしないことを
さしているのなら現代にも通じる考え方であると思う。
竹笛
平成27年3月3日「賢木」 遺言〜代わり目
千年前も現代も人間の心根というものは同じなんだと思わせる。
現実に院が存命だった時には任官の口添えを頼みにやって来た
人々が院の亡き後は二条の邸に近ずきもしない。
現代のあちこちで見られる風景である。どんなに文明が発達しても
人の心は変わらないのですね。悲しいことです。
永田 カヲル
帝の四十九日の場面では作者は皮肉っぽくて、兵部卿や源氏の悲しみや
特に中宮の悲しみについても余り同情的ではないのが腑に落ちない。
そして帝の死によってドンドン世の中が変わろうとして登場人物も、
いよいよ尚侍の君が登場してどうゆう展開になるのだろうか。
竹笛
平成27年1月20日「賢木」 遺言
院が最後の時を迎え、源氏をはじめとする残してゆく人に対しての
思いのたけを遺言として切々と言い置く。言ってもいっても言い足りない
思いがとてもよく伝わってくる場面だった。
私も父、母、弟等の旅立ちの折に一言でも言葉が聞けたら良かった
と思った。
甲斐 恵
?
院が命の終りに帝に何度も何度も心を帝に祈願する様は、とても人間
らしく、又、心打たれます。
後藤 政子
?
桐壺院が亡くなった。 思えば源氏物語一巻から長い間物語を
生きられた。(年月はさほどの長さではないのだけれど)?
??? 源氏の母を愛し源氏の置かれた立場を思って悩み幼い春宮を
心配する。引退してなを「世のまつりごとをしづめさせたまへることも
わが御世の同じことにておはしまいつるを」若い朱雀帝をも心配する。
情に厚く真面目な人であり故に悩み多い一生だった気がする。
永田 カヲル
?
院の病にさいしての大后の態度が今までのイメージと違っていて
面白い。お見舞いに行こうとして中宮に気兼ねをして思い悩むと
言うところは女性として普通の感情を持っていることに興味を持った。
もし院にお別れが出来たとして大后は何と声をかけるのだろうか。
竹笛
平成26年11月11日「賢木」 野の宮の別れ
世 にいろいろな別れはあるけれど野々宮の別れほど哀切なものは
そうざらにはないのではないか・・・。
源氏の人の良さ、自分本位な行動には笑ってしまうが
御息所の悩みに悩んだ上で、「鈴鹿川八十瀬の波にぬれぬれず
伊勢まで誰か思ひおこせむ」と言い切って女ではなく母の道を選んだ
こと、その強さにいっそう御息所が好きになりました。
永田 カオル
御息所は伊勢出立に先立ち内裏に参り自分の人生の変わり行く様を
思い起こす。大切に育てられ16で結婚、20で東宮と死別し30の
今に至るまで華やかな若いときの暮らしを何もかも失って伊勢に行こうと
している。源氏とも別れ一人で決然と生きてゆこうとする御息所に
とても共感させられた。 竹笛
平成26年1月14日 「賢木」 野の宮の場面
六条御息所の心の葛藤がとても細かく表現されていて
女心というより人間の心の動きの機微をとらえている
内容でした。 今さらながら人というのは昔も現在も
変わりのない心を持っている事を実感しました。
甲斐 恵
今日から「さかきの巻」に入る。
御息所がいよいよ九月に伊勢へ旅立つ直前のこと、
晩秋の野々宮はものさびしい風情がより一層まして
黒木の鳥居が立ち並び本当に神さびた趣が想像
される。この中に仮住まいの御息所はじっと過ごさなければ
ならなかったことを源氏はここへ来て初めて気がついた
のではないか、素直に「いといみじうあはれに心苦し」
という気持ちで対面したのだと思う。
竹笛
平成25年11月5日 「桐壺」最後の場面
源氏と女君の結婚、源氏の心は藤壺にあり、女君の心は
屈辱感で閉ざされてしまうという、左大臣の思いとはかけ離れた
状況で始まってしまった。源氏の心が他にあると言う事は
女君にも感じ、ますます心を固く閉ざしてしまったのでは
ないでしょうか。 プライドの有る無し以上に不幸な出会い
だったと思えます。
甲斐 恵
今回で二度目の源氏「桐壺」が終わりました。一度目は
ただ文章を追うばかり、どこで切っていいものか、古文を学ぶ
とは名ばかりでした。
「帚木」「夕顔」「空蝉」等など「葵」が終りもう一度「桐壺」
にもどってみると少しはなめらかに読めるようになって継続は
力なりです。「桐壺」から始まり源氏のさまざまな人(特に女性)
との関係の中で人間として成長してゆくさまは素晴らしく
越えてはならない恋に苦悩しそれが又成長に力を添える・・・。
私は「末摘花」の人間源氏が好きです。次はどんな源氏に
お目にかかれるやら楽しみです。
永田 カオル
二回目の桐壺を読み終えて一番印象に残っているのは
桐壺亡き後命婦が北の方を弔問する場面です。北の方の
「くれまどふ心の闇もたえがたき」と心情を吐露しなぜ娘は
死ななければならなかったのかを訴える。複雑な母の気持ち
が伝わってきます。帝の悲しみも尋常ではなかった。これから
始まる光源氏の物語には最初に母親の悲劇があったという
ことがずっと底に流れていると思います。
竹笛
平成24年11月19日、平成25年1月21日
2回にわたり白楽天「長恨歌」を読む
長恨歌が源氏物語に関わりが多く有るという事が、
理解出来た。日本と中国の歴史的なつながりを
今さらながらに考える事が出来、日本の文化を始めとする
様々な事柄に影響を与えている事が実感された。
漢文というとただただむずかしく理解しがたいと敬遠していたが、
美しい情景が目に浮かび心情も細やかに表現されている事に
始めて気がついた。
甲斐
源氏物語に度々引用される白楽天の長恨歌を読む。
傾国の美女楊貴妃と玄宗皇帝の有名な話を漢詩で読むと
なじみのある美しい熟語が連なって、栄枯盛衰の模様が
日本の文学に影響を与えたことがよくわかる。 特に玄宗が、
殺された楊貴妃の魂を求めて探す場面は幻想的で面白い。
竹笛
平成24年9月24日 感想文「桐壺5」
澄み切った秋の夜、虫の音…、この上なく美しい情景の中に
深い悲しさ、苦しさに沈む三者の思いが語られている。
帝、命婦、母、立場の違いはあっても世を去った更衣への
思いは少しも癒される事の無い日々が手に取るようにわかる。
帝の何とも人間的な心の動きとその思いを共にしてくれる
命婦という存在、今の私達にとっても心に添ってくれる人が
いることが助けとなる事を改めて感じました。
甲斐
調度今秋の風情の中で母君と命婦の対面の場面を読んで
いると感覚としてすっと心に入ってくるようです。 こんなにも細やかに
季節と自然を人の感情に同化させて表現していることに感動します。
だから千年も前の文学が現代の読者に、現実の感覚として読むことが
できるのかも知れません。
竹笛
平成24年7月2日 感想文「桐壺4」
自分の立場を意識しなければならない帝の悲しみの様子。
娘に先立たれた母君の悲しみは亡夫の言うとうりに従った
事が果たして娘は幸せだったのか? 娘の死によって疑いの
気持ちが出てきた。 命婦の心使いのやさしさ 三人三様が
よく表現されていて、色々考えさせられました。
ありが そら
娘の死という事実に深い深い悲しみを送っている母君である。
帝の優しい言葉もおそれおおく、母君の心身を支えているのは
若宮を養育する祖母としての気持ちではないだろうか・・・。
しかしそれも娘のいない今いずれは帝に返さなければならないのに
、逆縁の悲しみはずっと続く事になると思う。
母君があわれでならない。
永田 カオル
更衣の母は荒れ果てた邸に命婦の訪問ははずかしいと思ったが
帝の更衣への心からの気持ちと母を思いやる気持ちを命婦のやさしい
言葉から心を動かされ自分の心情を思わず訴える。夫の遺言を
守り娘を入内させて一時は晴れがましい時もあったが辛い事も多く
とうとう死を迎えてしまった。母としてはこれでよかったのかという
反省や誰が悪いわけでもなくこのような運命を受け入れ難く、これからも
心の闇をかかえていきなければならない。現代にも通じる親の思いである
と思った。
竹笛
平成24年5月7日 感想文「桐壺3」
更衣が亡くなって野分の膚寒さがことさら身にしみる
帝である。日常の暮らしが悲しみでいっぱいの感じである。
冒頭の いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらいたまひ
けるなかにと同時に習ったのだと思う、あれから六十年近くになり
今じっくりと源氏に向き合える幸せを感じている。
永田 カオル
帝は更衣の死を受け入れがたく様々な言葉でその悲しみを表している。
例えば「はかなく日ごろ過ぎて」 「ただ涙にひちて明かし暮らさせたまへば」
「おもかげにつと添ひておぼさるるにも闇のうつつにはなほ劣りけり」等等
更衣の面影を追って夢の中になぐさめを見い出す程に喪失感から抜け出せない。
竹笛
平成24年3月19日 感想文「桐壺2」
帝の愛が深くなればなるほど妃たちの嫉妬や恨みは強くなり
更衣は身の細る思いである。帝は一人の人間として更衣を
愛した事は素晴らしいと思うけれど帝としての自覚、又更衣の
立場を理解しなかったばかりに一人の女性の命を失うという
悲しい結果を招いてしまう。
永田 カオル
小説とは思えない程人生の終わりに近づいているすさまじい様子が
短い文の中で表現されている。 今の世でも重く感じられる文です。
又、肉体の極限にありながら歌をよむと言う驚きに頭の中でよく考え
られるかなと不思議な気持ちになりました。
ありが そら
御子が誕生してから様々ないやがらせを受ける桐壺はやはり後見の
ない地位の低い更衣だったために上からも下からも嫉妬の対象と
なってしまった。改めてこの時代の身分制が、この物語の根底に
ずっと影響していると思った。
竹笛
平成24「年1月16日 感想文「桐壺1」
均等に妃たちを愛するのが公務の仕事とは
帝の立場を考えれば一人の妃に自分の感情を
赴くままに与えようとする気持ち。 又御子に
対して私物としての育て方。よく理解できる。
イメージでは自分に素直な人、かえって男らしく
感じました。
有賀 そら
?
十年以上前に目にした桐壺を再び学び始める
事になった。 文の区切り方も解らなかった頃よりは、
頭にも気持ちにも内容は入りやすく一度は目にした
はずの文章なのに初めて接したかのような新鮮さも
加わりずっと「源氏物語」が近くなった思いがします。
kai
?
?14年ぶり、2回目の桐壺の巻を読み始める。
葵の巻を読み終え文体にもなれて源氏や周りの状況
も少し理解できたところで最初に戻り読み直すことは
改めてもっと冷静に源氏の誕生と成長を見直すことに
なると思います。今回は桐壺帝の余りにも率直で深い
愛情を感じていたところです。
たけぶえ
平成23年11月7日 感想文「葵」
女君に対する源氏の愛情に打ち解けてくれない女君の
心の様子がよく表現されて何かほほえましいやら、又
源氏に対して何と無くあわれさを感じた。
最愛の娘を亡くした深い悲しみの左大臣が、婿でなくなった
源氏に対する細やかな心使いの様子に感動した。
そら
?
今回をもって葵の巻は終わりとなり、源氏物語を代表する葵上
御息所と二人の女性の源氏を中にしての凄まじい葛藤が展開される。
有名な車争いの後御息所の「ものをおぼえ乱るること」 そして
葵上の死 死を間近にして初めて夫婦の絆を感じる源氏と葵・・・。
もう一人重要な女性若紫との結婚 源氏を異性と意識する折も
なかった若紫の反発 この巻ではその後の事はわからない、とにかく
この葵の巻は源氏物語中の圧巻であると思う。
カヲル
?
葵の巻を読み終えて、葵を中心とした物語ではあるが御息所の本当の
恋の物語でもあるように感じた。源氏に一目合いたい一心で車争いに巻き込まれ
自尊心をずたずたにされたにもかかわらず源氏には理解されずに一人で
のたうちまわっている様子が響いてくる。 葵は最後には源氏と心を通わせる
ことが出来て完結しているが御息所の気持ちはどのように納まっていくのか。
竹笛
平成23年9月5日 感想文「葵」
形ばかりの夫婦から本当の夫婦になった源氏の喜び、
それに対して女君の心に受けた大きな衝撃。
各々に理解は出来るが改めて男女の性差を思わされる。
この回でも惟光の存在の大きさは増すばかり。
源氏は惟光の心遣いにより支え守られているのだと思う。
何ともうらやましい限り。
恵
今まで子供のように一緒に遊んでいた姫君を急に妻として扱うと
いう大きな変化に戸惑う姫君の様子が読者としてはかわいそうで納得が
いかない。この時代と立場など考えれば当たり前のことかもしれないが、、、、。
源氏が知らない女のようだとか人の心こそ怪しいものと持て余しながらも
離れがたく、新しい恋に心を奪われてゆく様子に、今までよりも男性を
感じる。
竹笛
平成23年6月20日 感想文「葵」
文章にはあたかもその場にいると思わせてくれる様に
詳細な表現を主とするものもある。しかし今日の「結婚」の
章はそれとは異なり細かな事は記されてはいない。でも
読み手は深くその場の状況を理解できるという文章だった。
なにげなく読んでいた文のひとつひとつの「ことば」に作者の
表現力の奥深さを感じた。
け い
結婚とは女にとって重大な事である。まして幼いころから
祖母などに育てられて精神的には人より幼いところがある
ので、源氏を男性として見る事が出来なかった。
有名な結婚の場面である。
見事な一行であると思う。
カオル
14歳の若紫は気持ちは少女のままであってももうみずみずしい
大人の女の姿になっていた。源氏の男心として妻に対する
行動であっても若紫としては納得のいかないことであったと思う。
その気持ちや態度を何とも写実的にかつ文学的に読む者に
迫ってくる。
ななこ
保護者として信頼していた姫君。変則的な夫婦関係に
悩まされる源氏、終わりの簡単な一行でもって
一対の夫婦の始まりが表現されているのには、おどろきでした。
そら
平成23年4月18日 感想文「葵」
思いもよらず姫君の成長の変わりように戸惑う
源氏の気持ちがよく表現されていた。
そら
久しぶりの源氏で楽しみに来ましたが、何か頭の整理が
つかなくて感想まで書けないですが、相変わらずの源氏の
話で小さい女の子のことがとても可愛かったです。
ゴン太
二条院に戻った源氏が姫君のこの上なく大人びた姿に
びっくりして動揺を隠せないところと姫君のうちそばみて
はにかむという言葉が印象的。
ななこ
平成23年2月7日 感想文「葵」
源氏は娘を亡くした左大臣の悲しみを受け止めて
慰め、女君を亡くして不安と悲しみにくれている女房達に
これからも度々来るといってなぐさめ、なかなか邸を後に
する事が出来なかった。 源氏が去った後大臣は娘の
部屋に入り手習いの打ち捨てられた紙を見ては涙して
読んでみると源氏の歌の中に「あくがれがたき心ならひに」
という言葉が書かれている。心開かない夫婦と思っていたが
いつも離れがたく思っていたと書くほど仲がよかったのだと
父親としてほっとすると同時に源氏を失う事が残念でならない。
竹田 三枝子
平成22年10月4日 感想文「葵」
妻を亡くしたやるせない源氏の気持ちが所々によく表現されて
いる。又亡き妻の思いにふける源氏のたたづまいの美しさ、
喪服の気品ある美しさ、美に関して何か心の奥にのこりました
有賀静子
今まではたいして仲の良い夫婦ではない関係と思って読ませて
いただきましたが、今日の所で源氏が随分気に掛けていたようだし
男性が見ても源氏がどこまでも美しい人だったのだなあと感じました。
宮川 来仁
「時雨うちしてものあわれなる暮つかた」とか「枯れたる下草のなかに
竜胆、撫子などの咲き出たる」など、初冬の自然の描写のさびしさと
相まって源氏の亡き妻への思いをつのらせ悲嘆にくれている様子は
何とも美しく痛々しい。北の方はやはり幸せな最後だったのだと思う。
竹田 三枝子
平成22年8月2日 感想文「葵」
源氏の心が離れてゆき御息所は源氏への思いで心がいっぱいである。
悲しみや寂しさ、屈辱感で体調までも悪くなり暗い日々を送っている。
しかし源氏への思いとは別に美しく教養の高い人として野々宮に移ってからも
様々にしゃれて楽しいことを考え出し殿上人たちが通いつめたのである。
サロンの主人としての御息所はさぞ生き生きとして魅力的だったろうし
暗い暮らしとは別にこんな生活もしていたのかととてもほっとしたところである。
永田 カオル
源氏と御息所の関係はお互い思いは強いにもかかわらず
その時々の気持ちが行き違っている気がします。
ことに御息所の強い思いは生霊となる程なのに御息所の
生来の奥ゆかしさ、教養の高さからなのか?相手の気持ちを
推し量って感情を抑えてしまったりと。歯がゆい思いもしますが
、これぞ本当の恋心!!なのでしょうか。
甲斐 恵
母大宮の深い悲しみと源氏の深まる喪失感、そんな時に
御息所からの美しい弔問の文が届く。源氏は「つれなの御とぶらひや」
とあの生霊の声を忘れることが出来ない。源氏に対する執着心を
捨ててほしいと返事に書いてしまう。それを見て御息所は源氏が自分の
生霊を見てしまったとさとり絶望する。何てかわいそうな人と思ったが、
しかし彼女の生活には他の面があることが初めて書かれている。その
高い教養と今めいた趣向に殿上人たちが集まる場を持っていたとは。
彼女の面目躍如たる部分があって救われる思いがした。
竹田 三枝子
平成22年6月7日 感想文「葵」
葵の上を見送った源氏の嘆き、悔い、悲しみは、やっと心を
かよわせた後で一層の事だったのだろうが、急に旅立った葵の上は
最後の最後に幸福な思いを抱いて逝けたのだろうか。
身内の死に悔いを残さない人は少ないのではないかとも思うが
葵の上と源氏のこの先を読んでみたかった。
甲斐 恵
出産後北の方の体力は弱まるばかりである。結婚以来心は
離れ離れであった。二人は病を経て夫婦の絆を取り戻した。
「秋の司召」のための夫の外出を一心に見送り、帰りを待たず
あっという間に亡くなってしまうのである。
源氏左大臣家の人たちの悲しみは例えようもない。源氏は
後悔の毎日である。なぜもっと早く打ち解けられなかったのか、
これは源氏の気持ちでもあり私の感想でもある。まったく残酷な
仕打ちである。
永田 カオル
葵の上の急死の前には色々な伏線があったように思う。
一つは源氏がやつれた北の方のそば近くで初めて夫婦らしい
会話をした時の源氏を見送る時にはいつもよりじっと心をこめて
見つめていたと言うところ。今まで源氏に対して他人行儀だったことを
思うと病のためとはいえ何か見納めていたのかも知れない。
もう一つは「秋の司召」のためほとんどの人が参内してしまったという事と
その前に僧都たちも引き払っていたということで他のもののけの付け入る隙を
与えてしまったという事で北の方の死は結果的に納得させられてしまう。
いつもながら構成のすばらしさに益々興味がつきない。
竹田 三枝子
北の方の思いもよらぬ急死でみんなの狼狽ぶりの様子が
如何に大変な事が起こったかがよくえがかれている。
左大臣の娘の死が日と共に現実となり、その悲しみの涙と
院からの弔問を受けた時のうれし涙との複雑な気持ちが
よく表現されている。
亡き妻を偲ぶ源氏の煙と雲とが交じり合った美しい空の
表し方は、私は好きな一節でした。
有賀 静子
平成22年4月19日 感想文「葵」
思いもよらぬ北の方に対し、みにくいねたみ心に気づく御息所の
自分自身に悶々とする様子が分からないでもない気持ちと又
夫婦としての初めての絆を分かち合えた、源氏、北の方の様子に
何か、ほっとすると同時に少しでも長く続く事を祈る気持ちになった。
有賀 静子
御息所があわれでならない。だんだんのっぴきならない所まで
きてしまった気がする。 一方北の方は出産後も体調が悪く
そのため気持ちの方はおだやかになり源氏も長い夫婦生活の中で
初めて妻と同じ目線で感じ、話をしている、よかったなと思う。
永田 カヲル
無事出産の知らせを聞いても「はた」が気になるし芥子の香も
気になるし、ただならずと言う言葉を胸がかきむしられるよう、と
心の有様を伝え聞いても「はた」のひょっとしてが妬ましいが面白い。
宮川 来仁
御息所はまさか北の方が具合が悪いと言われていたのに、安産であった
とは、、、またまた妬み心が沸き起こり、北の方の護摩の芥子の香まで
体中にして人にも言えない苦しみがどんどん心の中に大きくなっていくのが自然
の感情である事がよくわかる気がする。
一方源氏はようやく北の方と話をする事が出来、やつれた姿にあわれにも
美しいと思い早く元気になってほしいと、初めて妻への愛情が芽生えてきた所
はよかったなあと思わずほほえんでしまった。
竹田 三枝子
平成22年2月15日 感想文「葵」
やむごとなき験者により調伏されたもののけが
北の方に張り付き北の方の口を借りなつかしげに言った
言葉が、今まで思っていたもののけとは「おどろおどろしく、
恐ろしい物」という思いとは全く違い親しみを感じてしまった。
もののけにもののけとしての思いを語らせるなんて。
甲斐 恵
まださるべきにもあらず・・・と気を抜いている時の産気づき、
苦しむという場面、あわてているのが面白いし、ただ祈祷して
いるだけというのが千年も前の事なのですね。
宮川 来仁
今の世では理解しにくい正体の分からないもののけに、恐れたり
だまされたり源氏をはじめ周囲の人達が振り回される様子に何か
恐ろしさと面白さが入り交じって滑稽に感じた。
有賀 静子
北の方に取り付いたもののけは本当に御息所の生霊だったのか。
源氏を前にして北の方を通して語られるもののけの言葉は「まさか
こんな所に来るとは思わなかったのに魂がふらふらと体から離れて
来てしまった。どうかこの魂を留めてほしい」とやさしい声で語りかける。
これはまさしく御息所の声であり気持ちの表れではあるが、彼女は
こんな直截的な言い方をする女性ではない。もののけがもののけの
人格を持って代弁しているようで、源氏もぞっとしているばかりでなく
受け止めなければならないのではと思う。
竹田 三枝子
北の方(源氏の)に取り付いたもののけは数を尽くした祈祷にも
びくともしない。 北の方は苦しみ続ける、源氏は
言葉をつくしてなぐさめるが・・・。それにつけても普段の
妻の言葉でも態度でもない優しく打ち解けて理想の
妻の姿なのである。心身の苦しみの中で源氏も心より
寄り添い二人が本当の夫婦になれたんだなと、私などは
思ってしまった。紫式部にまんまと騙されてしまった。
御息所の生霊が北の方に乗り移っていたとは全く驚きである。
永田 カオル
平成21年12月7日 感想文「葵」
今日の感想
御息所の病状を案じながら、見舞いに行っても
弁解ばかりの源氏、御息所との気持ちの行き違いを
うまく表現されている。又御息所の心情が事細かく、
源氏に対してのやさしい思いやりと又せつない激しい
女心の描き方が小説とは、つい忘れて、のめりこんでゆく
自分に、はっと気が付く私でした。
有賀 静子
北の方の事を想う源氏のやさしさが、よく出ていました。
宮川 来仁
今回御息所の苦しみがどんなに心に深く根ざしているのか
よく解りました。
世の中の人々までが北の方の全快を祈っていると言うことを
聞いて今まで押えていた気持ちが「いどみ心」となって芽生えて
しまいあの車争いの時の屈辱感が益々心に深く宿ってしまい
誰にも言えず、源氏にもはぐらかされてしまい持って行き場のない悩み
を悩みぬいてきっと生霊となってしまったのでしょうか。それを自分では
どうする事も出来ない運命として「思ふもものを」なり。と受け入れて
いるようです。
竹田 三枝子
源氏との心のずれ、「御車の所争い」など御息所は体調まで悪く
するほど物思いに乱れてゆく。
左大臣家のもののけ騒ぎが自分の生霊によるものだとの噂にも
ふと、もしかしたら「自分の生霊」なのかもしれないと考える。
なんという素直な気質だろうかと感心してしまう。そういう気質の
ためになお一層悩みが深くなるのではないかと思える。
永田 カオル
平成21年10月19日 感想文「葵」
御息所と北の方、二人の女性の苦しみは源氏への思いが原因だと思うと各々の女性の立場、性格はもちろん源氏からの思われ方に大きく影響があるように思ってしまいます。すべての事柄が、正しい、間違い、右、左と決められない人間の心のあり様に現在と少しも変わっていないなあとある意味安心したりしました。
甲斐 恵
北の方がどうなってしまうのかと人々の驚く様が面白く書かれていて次が楽しみです。
宮川 来仁
又、内侍が出てくるとは。若作りにして当意即妙に歌を詠んで、遊び心たっぷりの振る舞いにただ感心してしまう。若い源氏には人前で恥ずかしげもなく色気たっぷりなのはあきれ返るばかりかもしれないが現代にも居そうでおかしい。
一方御息所のつらい悩みと北の方の病気とは今のところ何の関係もないものと書かれているが、もののけと生霊そしてよりましとか、いよいよおどろおどろしい世界が繰り広げられる。本当の所はどうなのかと一字一句見逃さずに読み進めたいと思う。
竹田 三枝子
常に堂々とした普段の姿はなく女連れの源氏の様子がうまく描かれていて、又短い歌の中に源氏と掛け合うあつかましい女との気持ちのやり取りがうまく表現されていて面白かった。
源氏のつめたさが解りながらどうにもならない御息所の気持ちが何か、読んでいてもいらいらしてくる。源氏ももう少しやさしく又はっきりと言ってやる事が出来ないのかと思った。
有賀 静子
「車争い」の後、北の方が体調を崩し、ひどい苦しみようである。源氏は、あまり近づきすぎたくないと思っていた左大臣家に留まり加持祈祷をさせ、なんとか北の方の苦しみを取り除こうとする。源氏の優しさは、こういうところにもよくでている。貴人は情がないと言われているが、父桐壺院も源氏の後見人である左大臣家の一大事を、源氏のことを思い心配しているのである。こういうところは普通人と同じだなあと思いほっとした。
永田 カヲル
平成21年7月27日 感想文「葵」
源氏の姫君に対する愛情の深さの表現が改めて感じさせられた心温まるところでした。
有賀静子
見物の人々の源氏に対する気持ちが良く出ていて面白かった。又源氏の姫君に対する気持ちもとても可愛いと思いました。
宮川来仁
絢爛とした祭りの景色が目に見えるようです。御車争いの葵の上と御息所のやりとりを源氏は本当によく理解している「貴人は情を知らず」と言うけれどそんな事はない源氏の素晴らしさだと思う
永田カオル
源氏を一目見ようと見物に集まった人々の様子が、身分の高い人、低い人、尼や賎の男などまるで見て来たように一人ひとりをクローズアップしてユーモアと皮肉たっぷりに描いて見事で面白い。又、御息所の心の内を感じて北の方に対する不満が募る源氏、悩みがつきない時には二条の院の姫君の所で冗談を言ったりほほえんだり。
竹田三枝子
平成21年6月22日 例会報告感想文 「葵」
有名な車争いの場面である。 御契の日に源氏も加わるということで、北の方までも が女房達の熱意で急に見物に出かける。慌しく支度をして出かけるのが「日たけゆきて」昼近くになってしまった。この時間の成り行きが車争いの原因の一つでもあったことが解る。もうすでに前の方には、沢山の車が並んでいる所へ、北の方の何台もの車が権威を笠に分け入って傍若無人の振る舞いで、挙句の果てにはまた偶然にも六条御息所が 忍びてやつして来た車と出くわしてしまう。その網代車の、けはい、衣装の色合い等から 自ずと身分が、解ってしまい左大臣家の供達に散々さげすまれてしまった。
御息所はどんなに悔しく悲しい思いをしたことか。自尊心を傷つけられ、やっぱり来なければ良かったと思いながらも、しかし後に押しやられた車の中で、かい間見た源氏の美しさに「出栄を見ざらましかば」と涙ながらに思う真っ直ぐな気持ちが美しい。
この短い文章の中に沢山の牛車の中を華々しい行列が通過するという一大スペクタクルが目の前に広がる。そして北の方の権勢に対して御息所の傷つけられた気持ちや、人々の感嘆のざわめきまでが聞こえて来そうな 大きな場面の描写に魅了された一人です。
竹田三枝子
車争いの上下関係のおもしろさ現社会とさほど変わりないところ人間の感情も今もかわりない所女心の表現に心をゆさぶられました
有賀静子
御息所がこんなに可愛い女だとは想像だにしなかった
世の中の説明は少しおかしい
おそろしい女、おどろおどろしい女と理解させられていた
六条御息所についこれからも読み込んでいきたい
楽しみである
永田かおる
葵がこんなかわいい女の人と思わなかった
宮川来仁
時代が移っても人間の本質は全くかわっていないということをいつも感じさせられる
心の動きの機微は手に取るようにわかり同感できる
甲斐恵
御息所のつらい気持ちと悲しい思いをさせられたのになお源氏を見たいという女心に
なぜという気持ちと切ない気持ちを感じた
竹田三枝子
平成21年4月20日 例会報告 「葵」
いよいよ源氏物語も佳境に入り、「葵の上」の巻になる。
「花宴」より2年が過ぎて、世の中も変わり、朱雀帝の時代になり
源氏も近衛の大将という重責を担うようになってくる。
六条御息所が本格的に物語に登場し、重要な役割を果たしてくるようで
御息所が故東宮妃であり、一流の貴婦人であることがわかってくる。
美しく、教養があり、誇り高い人柄であることも・・・。
葵の上の懐妊で、二人の貴婦人がいかように関わってゆくのか。
御息所が演劇や謡の世界でのように生霊になって他の女性を悩まし
とり殺すという恐ろしい人なのか、それにはいろいろと理由がありそうで
次回からが楽しみです。
永田カオル
平成21年2月16日 例会報告 花宴
の宴も終わり源氏は酔いごこちで去りがたく藤壺の当たりに行って
みるが立ち寄るすきもなく閉ざされていた。藤壺への思いが完全に
断ち切られてしまい感情の持って行き場がなくなってしまった源氏は
「なほあらじに」という領域に踏み込んでしまうのだった。
そして次の恋に偶然遭遇して、「このように男女の仲のあやまちは
するぞかし」等と言ったり「まろは皆人にゆるされたれば」と自信たっぷりで
あったりその変わり身の早さとユーモアに感心してしまう。
一方二条の院の姫君は久しぶりに会ってみると愛らしく魅力的になり
利発な女性になっていた。源氏の御心のままに教えてきたことが実を結んで
きたようである。
桜の宴から藤の宴までの花の宴の巻は、源氏の装束の美しさ、ふるまいの
見事さ、人々の源氏に対する期待等が充分に伝わってきてすばらしく
華やかであるが反面源氏の心の中は、藤壺への満たされぬ思いや
二条の姫君の事北の方の事など思い悩む事ばかりだと思うが、源氏は
その時その時を誠心誠意行動して楽しんでいる様子がよくわかる巻で
あったと思う。朧月夜との今後の展開が楽しみである。
竹田三枝子
平成20年9月22日 例会報告 花宴
宴も終わり、源氏は一目藤壺に会えないものかと殿舎のあたりを 忍び歩くのだが、戸口は固く閉ざされている。 酔いにまかせ弘徽殿の殿舎をふらついてみると開いている。 そしておぼろ月夜の姫君と出会うのである。 どこの誰とも知らない女性を相手に、またも悩み事が待っている 気配である。 源氏はどうしてこう読者をドキドキさせるような困難な人を 好きになるのだろうか。 まったく困ったものだが、それが物語としては面白いのだが・・・。 長谷源氏教室 永田カオル
平成20年7月7日 例会報告 花宴
帝は南殿の桜の宴を催す。弘徽殿の女御は、中宮になった藤壺が 上座に座るので面白くないが、見ないわけにはいかないと言うところが 面白い。 よく晴れたお花見日和にこの広々とした南殿の前には、 親王から上達目、いつもは入れない地下の人々までが入場し、晴れがましい 場所に緊張した面持ちで集まった様子が短い文章に生き生きと表されて 目の前に広がるようだ。 宴のたけなわに管弦と舞楽が披露され、紅葉の賀 と同じように源氏のー春の鶯さえずるの舞ーと頭の中将のー柳花苑ーが 素晴らしく他の人は言うに及ばずといつものとうり。探韻の漢詩も人々が 感心したり、このような折中宮はやはり源氏の振る舞いを目にして、何の こだわりもなく源氏を称えられたらどんなによかったかという意味の歌を作る。 この一日の朝から夜までの出来事に大勢の人々の様子、身分社会の 立場や帝を初め女御中宮の気持ちまで理解でき、大舞台に一挙に 登場させて繰り広げられた宴に読者は圧倒させられました。
竹田三枝子
きさらぎの20日あまり、帝によって南殿で桜の宴が催される。 当日は好天で親王たち、上達部はじめ地下の人たちがうち揃って にぎやかに行われた。 漢詩を作り披露しあったり、楽を奏で舞を舞ったりと春の一日を楽しんだ。 こういう時のみんなの注目の的は、主人公とはいえいつも源氏なのである。 たまには地下の人の中から素晴らしい詩ができて 源氏が感じいるということがあってもいいのに・・・。 詩でも舞でも、他の人が涙するほどの美しさは天性の資質なのかと 感心してしまう。
平成20年5月12日 例会報告 紅葉賀
母の里の後ろ盾のない源氏が、左大臣の怨みを買うようになっては、と
どこの誰とも素性が知られていない女君との噂に父帝は心を痛めている。
宮中には、すぐれた女房たちが揃っているのに浮いた噂もなく
「まことに乱れたまはぬ人」と源氏は見られていた。
女房の一人に典待の司という官位の高い女房がいて(年齢50歳台)
家柄も高貴な上に人品いやしからず、教養もあり、評判の良い人である。
しかし異様なほど男の気を引く色気が旺盛であり、源氏は
よせばいいのに好奇心をそそられ言い寄ってみるのである。
典待は本気に受取り源氏は気がいいというのか優しいというか、はっきり
断わることができない。
こんな事が頭の中将の耳に入り、捨てておくはずもなくドタバタの騒ぎをおこす。
今まで優雅であった源氏の世界に喜劇性のあるおもしろい場面が展開する。
現代でもあまり例をみない年齢差に典待の司という人は
人間的にみてかなりな自信があったものと思えるのである。
永田カオル
平成20年3月10日 例会報告 紅葉賀
ある雨上がりの涼しい宵に源氏がそぞろ歩いていると典侍の琵琶の音が
響いてそれは美しい声で歌っていた。思わず近寄ってしまいすかさず典侍も
言葉をかけて源氏も躊躇するが例のお人よしで部屋に入ってしまう。
頭の中将が目ざとく見つけて、いつも非難されているので仕返しをしたいと
思ってしばらく様子を見て部屋にこっそり入ったら、源氏がすぐに気が付いて
直衣を持って屏風の後に隠れてしまった。中将はおかしさをこらえて屏風を
がたがたたたんで脅かしたが典侍はこういう場面に慣れているようで、源氏に
危害が加わらないように相手を押さえたり大変な騒ぎになり源氏も中将と
気づいて思い切りつねったり、二人が子供のようにけんかする様は可笑しい。
二人の歌のやり取りも面白くけんか両成敗という感じであるが、この若い
人達には冗談であっても五十七八の老女が真剣にうろたえる姿は、何だか
あわれで悲しい。
竹田三枝子
平成20年1月22日 例会報告 紅葉賀
源氏という人はうわさとは裏腹に宮中では乱れ給わぬ人
として見られていた。女房の一人に典侍という年老いてはいたが家柄
も良くたしなみもあり品もよく評判も良い人がいた。ただ非常に色めいて
いたので源氏はその年でどうしてそんなに色気があるのか興味を覚えて
近づいた。女は不似合いとも思わずその気になっていった。ある時
源氏は女を見かけたので裾を引いてみると派手な扇をかざして流し目
を送ってきた。その目つき目元の様子はとても皺だらけで、まぶたは
窪んでけばだっている。この描写はとても表現が現実的で作者の手厳しい
見方が表れていると思う。こんな人に源氏が言い寄るとは思いも寄らないが
若さゆえの好奇心と言うのだろうか。歌のやり取りなどしている所を
帝に見られてしまいうわさはすぐに広まってあのライバルの頭の中将が
聞きつけてしまい又騒動が起こる気配がする。
竹田三枝子
平成19年11月12日 例会報告 紅葉賀
二条の院の女君
源氏は悩んでいる時には、いつも少女のところへ
言って気分を慰められていた。そして今回も西の対
へ行く。ここでは少女を女君と書かれて、一人の女
として扱われるようになってきたようだ。登場する少女
も、すぐに来ない源氏にすねてみたり、「入りぬる磯の」
という歌で一人前の女のようにさびしさを訴えたり、気持ち
の上でも源氏の妻としてふさわしくしようとしている。
教養も身について琴も上手に弾き、あの雛遊びをしていた
少女から又一段と成長したように思う。源氏が一人前の女性
に、自分の好みの女性に育てることを理想としていた事が
着々と実現しているようだ。女君も源氏が側にいないと
寂しくてたまらない、それは幼いながら源氏への想いと、やっと
安心して頼れる人にめぐり会ったという事なのだと思う。
源氏は少女のために邸に止まることも多くなって左大臣邸では
それは「誰なのか」と大騒ぎして非難されていたが帝にも聞こえて
しまい、世話をしてくれた左大臣に申し訳ないとお説教されても
返す言葉もないが帝はそんな源氏を可愛そうに思っていた。
竹田三枝子
平成19年9月3日 例会報告 紅葉賀
藤壺は生後二ヶ月程になった若君を連れて参内して帝に会う。
帝はあまりにも源氏に似ていることに驚くが微塵も疑わない。
源氏が生まれた時には春宮にすることも出来ず臣下に下した
ことを心苦しく思っていたので、余計若宮には愛情を注いだ。
源氏が管弦の演奏に来た時帝が若宮を抱いてきて、小さい
頃からずっと見てきたのは源氏だけである、だからこんなによく
似ていると思うのか、と言われて帝の愛情を源氏は初めて聞いた
ことで、恐ろしくも、かたじけなくも、うれしくも、あわれにもと色々
な思いが一気に押し寄せて涙が落ちそうになった。こんなにも
神々しい程可愛い若宮に似ているといわれて自分まで大事な存在
に思ってしまうという身勝手な気持ちをもってしまう、本当に素直と
いうか源氏のまっすぐな気持ちがよく表れていると思う。
しかしあまりにも似ていることで心がかき乱されて、二条に戻っても
気持ちのやり場がないまま命婦になでしこの花を添えて歌を送る。
どうせ返歌はないと思っていたところへ思いがけず藤壺から返歌が
届く。愛する二人の子供でありながら喜ぶことが出来ない辛さは
源氏と同じ思いである、その上「なお疎まれぬやまとなでしこ」
という返歌は私には理解に苦しむところである。我が子を疎ましくさえ
思ってしまう程辛い思いはわかるが自分を嫌悪するという意味も
含んでいるのではないかと思うのであの一語は使って欲しくなかったと
思うのです。
竹田三枝子
皇子の誕生である。
本来喜びをもって迎えることなのに、出産の時期は当然のことながら遅れ
人々が騒ぎ立てる。
藤壺の心痛はいかばかりか・・・。
弘徽殿の女御が皇子の誕生を「うけはしげに」と語っているという噂に
呪いに負けて死んだらもの笑いになり、みじめであろうと
誇りを失うまいという強い心によって無事出産するのである。
源氏も気が気ではない。
今は帝の子としての母の強さで源氏の子への対面の希望にも
分別がないと拒絶する。
心を許しあっている命婦に対してのうとましさ(何もかも知っているので)なども
命婦にもわかる。
また、命婦の無念さもわかり複雑な心模様である。
まことに読みごたえのあるところなのです。
出生の秘密を隠し通さなければならない二人にとっての苦しみの日々は続く。
源氏の手紙の返事に
「袖濡るる露のゆかりと思うにもなほ疎まれぬやまとなでしこ」と
愛している人の子でありながら嫌悪する気持ちを打ち消すことができない。
藤壺の悲しみが伝わってきて、まことに哀れでならない。
永田カオル
平成19年7月30日 例会報告 紅葉賀
藤壺の出産が遅れ年を越してしまいとうとう二月になり世間の人々も
騒ぎはじめて、この事の秘密がわかってしまうのではないかと藤壺は
心痛のあまり病気になってしまった。ようやく二月の半ばに男の御子が
誕生するが、弘徽殿の女御が呪っているという様子を聞いて、このまま
呪いに負けて死んだら世間の物笑いの種にされてしまうと思った時、
彼女のプライドが目覚めて強く生きなければという思いが、快方にむかわせる。
一方源氏も早く会いたい一心で公務を装って会いに行くが「今はまだ」と
断られる。しかし彼女が見た御子は源氏に生き写しで見る度に良心の
呵責に苛まれる。自分の立場を思い世間に知れたらと「身のみぞ心憂き」
と言う短い言葉に強い苦しみが表れていると思う。
源氏は手引きをしてくれた命婦に会って御子に会わせてもらえるように頼むが
叶えられる筈もなく、命婦も源氏の気持ちを察して悩んでいたが藤壺も同じように
悩んでいることを歌に託す。源氏が寂しく帰って行く姿を見て藤壺はわりなきことと
冷静に批判しているところが彼女の強さをみたようである
竹田三枝子
平成19年6月18日 例会報告 紅葉賀
いまだに若紫はひな遊びに夢中である。
北の方は、そんな幼い人だとは知らないので気をもんでいる。
源氏に聞いてみればわかるものを自尊心が邪魔をする。
娘婿という以上の気持ちで左大臣は元旦の祝賀の衣装を源氏のために
取り揃えてやったり、藤壺の兄(若紫の父)や舅からも良く思われる。
源氏とはそういう人なのである。
永田カオル
平成19年3月19日 例会報告 紅葉賀
藤壺は内裏から実家の三条の宮廷に帰っている。
源氏は何をしていても藤壺のことが頭を離れない。
自分の邸に若紫を引き取り育てていることが
北の方の耳に入り機嫌を損ねたりと頭を悩ますことが
次々と出てくる。
あどけない若紫によってなぐさめられている。
可哀想にと同情しきりであるが、これもしかたがないと思う。
永田カオル
平成19年1月15日 例会報告 紅葉賀
帝は朱雀院の行幸の舞楽をいつもと違ってすばらしいので
是非藤壺に見せたいと思って、前庭で試楽をさせる。
そこで源氏は青海波を舞う。夕方の日差しが差し込む中
で舞う源氏の美しさ、妙なる声の響き、はこの世のものとは
思えない程で観ている人々は皆涙を流す程感動的であった。
この場面は本当に読んでいても、源氏の美しい衣装に夕日が
当たってそれはそれはすばらしい姿であったと思うがこちらの知識
の乏しさから想像に限界があると思うが、朗々としたその詠の声
も聞いてみたいと思った。そしてこの物語の始まりは帝の愛情を
受ける藤壺の気持ちと源氏の気持ちを受け入れかねている藤壺
の葛藤が表現されている。源氏の舞の美しさに感動したことを、
控えめにでもはっきりと、返歌に表していることに注目した
竹田三枝子
年もあらたまり、鎌倉長谷教室も新しく「紅葉ノ賀」の章に入りました。
新年にふさわしく物語りも朱雀院への行幸の話しから始まります。
行幸には参加できない妃たちのために帝の住まいの清涼殿で
当日と同じように演じさせる帝の気持ちである。
源氏はただ一人の人、藤壺に見てほしいと舞い歌う。
演じる方も、見る方も緊張感で息苦しいほどである。
罪深い二人である。
永田カオル
平成18年11月13日 例会報告 末摘花(最終回)
約一年半をかけて末摘花を読み終わった。じっくりと時間をかけて
、毎回どんな展開になるのか今までになく楽しみで、ハラハラしたり笑ったり
で、こんな源氏物語は予想もしていなかった。
この物語は源氏の夕顔への想いから始まった。源氏は命婦から聞いてから
どんどん想像が膨らんで、荒れ果てた邸には美しく教養のある女性が住んで
いると思い込んでしまった悲劇であるし、喜劇であると思う。
姫君の風貌や教養のなさに対する源氏の失望と対応は、源氏の誠実さや
まじめさを際立たせている。それが余計におかしみを誘って気の毒なくらいで
ある。 姫の周囲の人々の描写も面白いし、こんなに貧しい暮らしぶりを
源氏が知るという意味も後々の物語に影響してくるのだろうか。又、十年後
の話に末摘花が登場するらしいという事なので、姫君がどんな女性に成長
していくのかとても楽しみである。
竹田三枝子
源氏や命婦、女房たちの想いが通じて、姫も人の気持ちへの
受け答えができるようになるかと楽しみにしていたが
どうにも人の心というものは、少々の時間では変えることはできないらしい。
少し打ち解けたかに見え、心から喜ぶのだが
別れ際に姫の赤い鼻が見えてしまい<見苦しのわざや>とがっかりするのである。
天は二物を与えないという。
容貌が優れなければ、心根優しく、賢くあればと思うが
どうも末摘花という姫はそのどちらをもそなえていないのでは・・・。
しかし、悪気というものはひとつもなく、この後物語の中に
また登場するというから、その時はと、どうしても期待してしまう。
末摘花の中では、源氏の人として優れたものが随所にみられるが
一般的には外見的な部分だけ大きく語られているような気がしてならない。
またいずれ姫に会えるのを楽しみに、今年の源氏物語は終わりになる。
永田カオル
平成18年6月5日 例会報告 末摘花(第七回)
姫君の邸の貧しい内情を知ってしまった源氏は帰り際にも門番の老婆がよろよろと
出て来て雪の中寒そうにしている姿を見て、一層この姫君に対する気持ちも失って
しまう。それでも細々と生活の面倒をみたり、門番の老婆にまで着物を送ったりして
いた。大晦日には姫君からの歌と衣装が送られてきてどれも古めかしく、渡してよいものか
どうか悩む命婦とのやりとりが面白い。
最初は悲しい姫君の話と思っていたが貧しさに文句を言う女房達や昔からの事を守り
続けている老女房達のおかしさと、源氏の何かの縁と思って尽くしている姿も痛々しくも
面白い。また姫君の歌に走り書きの歌を書く源氏のやり場のない気持ちが伝わってくる。
源氏物語の中にこんなに面白い話があるとは思わなかった。
竹田三枝子
平成18年4月17日 例会報告 末摘花(第六回)
古語のむづかしさをつくづくと、一巻、二巻、三巻と
講義を拝聴して、小説としての筋立ての面白さや、主語が
ないための読み方や、古語と現代語の違いなど、一応理解
出来たように思っておりました。ところが今回の若紫で皆さん
は言葉の使い方が美しいと言われて居りました。私はそれど
ころではなく、呼びかけの名称さえ誰のことかと思い惑う有様、
古語のむづかしさを痛感いたしました。何とか皆さんについて
いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
我妻洋子
姫君に興味を無くした源氏はそれでも顔を見ればもう少し
親しくなれるのではとこっそり見に行くが返って貧しい暮らしぶり
を目の当たりにしてびっくりさせられる。知らない振りをして姫に
会いに行くが相変わらず何の話も出来ず雪が降ってきても風情の
ある言葉もない。翌朝雪明りで明るいので姫に雪を見にいらっしゃい
と声をかけると女房達にも進められていざり出てくるけはいに、源氏
は横目でしっかりと見てしまい余りの奇異な顔立に目が離せない、
しかし色々話し掛けても何も言わずいたたまれずに打ち解けてくれない
恨みを歌にたくすが姫は「むむ」と打ち笑うだけ。
悲劇のお姫様の筈なのに無口無教養で、やる気のない女房達も愚痴
ばかりで、貧しくてかわいそうなのに登場人物が余り深刻に考えてない
所が滑稽な話になっているのではないか。それに対して源氏の対応は
律儀でまじめで何ともあわれでおかしい。
竹田三枝子
平成18年2月13日 例会報告 末摘花(第五回)
P.60−73
姫君に無理に迫るようなことは決してしないと約束していたのに
今までこらえてきた悔しさに耐えられなくなり
襖を開けて押し入ってしまう。
源氏としては、まことにつまらない女だと思うし
腹立たしくもあるが、妻の一人として世話をする決心をする。
源氏の誠実さを感じ取れる。
しかし、末摘花が歌舞伎やオペラになっているところをみると、
なにやら謎めいた魅力のある女性なのではないかしら・・・。
永田カオル
平成17年12月12日 例会報告 末摘花(第四回)
命婦の絶妙なタイミングで、寂しそうにしている姫君に会いに
行く源氏、でも一言も話さない姫に源氏は色々手を尽くして面白い
話をして見るが一向に返事がない。こんなに源氏を無視し続ける
人は初めてではないかと気の毒になる。ようやく歌を返してくるが
女房が近くで訳のわからない返歌をしたのを、源氏は初めて聞く
声と歌にめずらしさとうれしさで口が聞けぬ程だった。その後も
色々話すが何も返事がなく何と変わった女だと、源氏もこんな
人に一生懸命思いを込めて話していたのかと思うとくやしくなって
、思わず戸を押し開けて入ってしまう。その後どうなったかは
来年のお楽しみになりました。
竹田三枝子
P.32−43
源氏は、たいして気のない人ではあるが、もしかすると夕顔のような
人ならいいのに、という気持ちもあり、手紙を出し続けた。
それなのに返事がこない。
まったく礼をわきまえない人、と
頭の中将とのライバル意識もあってなんとも腹立たしい。
源氏が苦々しく思っている末摘花という女性は、まったくの謎で
これからの展開が楽しみである。
P.46−58
命婦が苦心して姫君に会わせようとしている様が
何かおかしくもあり、命婦という人は、まだ年若いのに
賢い人なのだと感心する。
やっと襖をへだてての対面にまでこぎつける。
でも源氏が言葉をつくしても返答がない。
(もっとも返事をしなくてもいいという前提で会っているのだから)
これは奥ゆかしいとか、世慣れていないとかではなく、
人としての教育を受けていないのではと思ってしまう。
永田カオル
平成17年11月7日 例会報告 末摘花(第三回)
源氏と中将との姫君に対する心の中のさぐりあいの様子。思いどうりにいかない姫君の気持ちを命婦に詰め寄る源氏。源氏の真剣さにとまどう命婦の心遣い、自分の意のままを通そうとする幼さを感じさせる源氏、どの人物もそれなりに面白く、又命婦の気持ちが理解できるような気になりました。
有賀静子
源氏は姫君がわびしい一人住まいをしているのだからきっと感性の豊かな女性に違いないと思い込んで、何度も手紙を出しても返事がないのが面白くないし不愉快になっていた。それに引き換えやはり夕顔の素直でおっとりとした姿を忘れられず思い出してしまう。その後わらわ病になり、ここから若紫の巻と平行して書かれていると言うことで、春から夏には若紫と出会って自邸に迎えることで夢中になっていて、秋には又常陸の宮のことが気になりだし命婦を責めて会う手はずをとるという流れは時間の
経過と源氏の感情の流れが相まって分かり易い。これから姫君に会えるのだろうか、
命婦の腕の見せ所で生き生きとした彼女が頼もしい。 竹田三枝子
平成17年8月22日 例会報告 末摘花(第二回)
命婦の駆け引きで源氏は姫君の琴を少ししか聞く事が出来ない。
源氏の思いを募らせておいて命婦も色々気を回して楽しんでいるように
みえる。源氏は頭の中将がつけて来たとも知らずにいたので、送って来
ただけと言われて悔しがる。二人の歌のやり取り、会話が面白いしお互い
に気心が知れているしライバルとして競争心もあるが、笛を吹き合わせて
一緒に家に帰るところなどはほほえましい。二人とも先程聞いた姫君の
哀れげな琴の音を思い出して色々想像をたくましくしているが、どんな女性
なのか、どんな展開になるか、興味を引かれる。
竹田三枝子
「末摘花」
源氏と命婦とは乳母子であることもあって
身分の差を感じさせない気楽な冗談を言い合い
とても楽しい関係である。
また、源氏の北の方の兄である頭の中将とは親友であり
なにかにつけての好敵手でもある。
末摘花に関心のある源氏の後をつけ
行方をくらました源氏にからんで歌をおくり
源氏もまた、男が密かに訪れる先まで後をつける者があるかと
非難の歌を作りやり返す。
しかし、本当に腹をたてているわけではない。
今の若者たちは忙しげに親指を使ってやり取りしている。
昔人はけんかも美しい歌でする、なんとも優雅であったものか・・・。
永田カオル
平成17年6月24日 例会報告 末摘花(第一回)
忘れられぬ夕顔との想い出、源氏の純粋な感情に哀れさをも感じる表現がよく
細かく写しだされている。
真綿につつんでくれるような女性を求める様子、又数々の女性との想い出、頁が進む
につれても変わりなく表している。 命婦の軽い言葉、強引に推し進める源氏と
のやり取りが面白く命婦のとっさの気転の様子が文中に引き込んでくれる、又琴の音
も聞く者の気持ち次第で良くも悪くも聞こえる様子、今私達も少し反省する部分も感
じました。 有賀静子
夕顔を忘れられない源氏が夕顔のように源氏を信じて打ち解けてくれる女性を
探し求めている。源氏が
隈なく情報を集めてまめに「一行ほのめかしてみる」という行動は何かユーモラスで
ほほえましいが本当は
もっと切実に心 安らぐ女性に出会いたいと思っているのではないだろうか。
大輔の命婦という女房が話していた父を亡くして一人で邸に住んでいる姫君に
興味をもち早速例のごとく命婦に無理を言って姫の邸にしのんで行って琴の音を聞
く。このような荒れ果てた邸に住む美しい姫の物語は昔物語にもよくあることですっ
かり源氏は恋する男となってしまうが、ぶしつけな振る舞いは慎もうと殊勝にもため
らっている。これからの展開が楽しみ。 竹田三枝子
末摘花」は、源氏が若紫を知る前の話しで、
夕顔の死後、悲しみに打ちひしがれ、重い病床にあった源氏が
夕顔のような女性に、また会ってみたいとの想いから
大輔の命婦という女房の手引きによって、末摘花の邸へ出かける。
この大輔の“いといたう色好める”女房は男女の機微に
通じているだけでなく、実に賢く、世慣れている魅力的な
女性なのである。
源氏物語には、このような素敵な女性たちが次々にでてくるので
おもしろい。
これからの展開が楽しみである。
永田カオル
平成17年4月11日 例会感想 若紫を読み終えて
瘧病の療養のために北山の奥に入った源氏が小柴垣
の垣根越しに十ばかりの清楚な少女を見初めその可憐さに心奪われる「かの人の御かはりに明け暮れの
なぐさめにも見ばやと思う心深うつきぬ」 藤壺に似た少女への想いでいっぱいにな
りこの出会いに運命的な
ものを感じる源氏なのである。 その後後見人である尼君に自分が引き取り育てたい
旨の口説が続くそして
明石入道の話が又藤壺との密会が唐突に出て来て後の話の伏線としてまるでサスペン
スドラマである。
源氏物語は口説の文学というが若紫を自分の屋敷に引き取りたい気持ちを尼君にわ
かってもらうために言葉
をつくし策を練り上げ現代人にはとても出来る芸当ではない。 若紫を読み終えて
やっと物語のとばくちが見えて
きたような気持ちになってきました。
永田カオル
若紫を読み終えてまず一番印象に残っている所は最初の出会いの場面である。山桜の霞む
山頂から少女の住む家を見ている源氏の姿といかにも子供らしく走り来る元気な少女との構図が美しい。春の終わりの新緑と山桜の霞みという景色も源氏の病を癒している様子が「明け行く空は、いといたう霞みて、山の鳥ども、そこはかとなくさへづりあひたり。、、、、なやましさもまぎれ果てぬ。」という文など随所に出てくる景色の描写がこの巻を美しい印象にしている。そして尼君との理解されない気持ちの応酬の後尼君の死後少女を父宮の迎えに来る前に救出を決行する時の息ずまる源氏の行動力が若々しくその情熱が迫ってくる。
竹田三枝子
平成17年2月14日 例会感想 「若紫」〔決行)
今、読み返してみましたが、少納言のあわてぶり、若君の可愛らしさ、源氏の強引さが面白く、次回が楽しみです。特に少女のおびえる様が手にとるように解って、なんだか源氏がにくらしくなってきました
宮川 来仁
まるで回り舞台を見ているように生き生きと面白く笑ってしまう。「うちとけて古人どものはべるに」、、、の中をまるで眼中になく目的めがけて突進する源氏は実に若者らしく自信たっぷりである。空蝉、夕顔などの時にはみられなかった天真爛漫な少女の前で源氏もまた、自然体で若者らしく、そして保護者として対する事ができたのではと思います。
永田 カオル
真夜中の源氏の行動は一途に思い込んでいるとはいえ、余りにも唐突と思うし一気に若君の寝所まで行って抱きかかえて連れて行こうとする行為は少納言でなくとも気が動転してしまう。しかし源氏の口上といい、素早い動きといい思わず少女の救出劇を見ているようで、はらはらしながら応援してしまうほど小気味よい。
次の朝の若君の様子も「何心なくうち笑みなどしてゐたまえる」という何とも美しく愛らしい姿にこちらもほっとして一緒に微笑んでしまった
竹田 三枝子
12月6日 例会報告 「若紫」(父宮訪問)
物語はいよいよ佳境に入ってきました。父宮が訪れ「こよなう荒れまさり広うもの古りたる所に幼い娘を住まわせておくわけにはゆかない。 言い訳がましいと思われる言葉を残して夕暮れともなればそそくさと帰ってしまう。父宮に対して祖母、母がわりの乳母はなんともせつない。父宮の所へ行くのが筋とは思うものの若宮のこれからの幸を思うと悲しいばかり、、、、。乳母としては自身の力のなさをはがゆ
く思ったのではないだろうか。
父宮の迎えが明日と知り、源氏は二条院に連れ出すことを決断するのも尼君存命の時から幾度か誠のある気持ちを伝えてきたものの、幼いというだけで反対されていた。
この機会を逃したら二度と若宮に会うことができない、やむおえないギリギリの選択だったと思う。世の中にはとても理解してもらえないどころかわかってしまえばどんなそしりを受けるか、、、、。しかし源氏としてはせいいっぱい誠意を尽くした上の決行となるのだろう。次回が楽しみである。
永田カオル
尼君亡き後の若君の面やせて泣いてばかりの日々を気弱な父宮もさすがに察して明日迎えに来ると約束せざるをえない。源氏はその事を聞いて自分の立場上若君を迎えになど行ける訳がないし世間の非難を浴びるだろう。源氏は色々考えるが決断は早い、てきぱきと言いつけ気遣いも万全にしていつもその行動力には感心させられる。さて、しぶしぶの女君に言い訳をして夜明け前に出発してしまうが、はたして若君を連れ出せるのだろうか。推理小説を読むような緊張感がある。
竹田三枝子
10月4日 例会報告 「若紫」(少女との一夜)
荒れ放題の邸に少人数の女たちだけで過ごす若君たち、源氏は打ち捨てて帰ることが出来ない。源氏の若君に対するいちずさとひたむきさ、育ちの良い若者の強引さで物語は盛り上がっている。乳母の不安はいっきにふくれ上がりまことに気の毒である。その気持ちを察し「さりとも、かかる御ほどをいかがあらむ、、、」自分を信じて見守ってほしいと乳母に念をおし誠実さを感じさせる。
実に優しい頼りがいのある源氏である。
永田カヲル
少女との一夜という衝撃的な場面では源氏の言葉で「かかる御ほどをいかがはあらむ」こんな子供にどうするというのだという所と「かつはうたておぼえたまえど、、、」このように少女の寝所に入りこんでいるというのは尋常ではない行為と思うけれど という2箇所に源氏の常識をわきまえた思いやりがあることで読者は安心感を持って納得してしまうのだが、源氏の思いつめた気持ちはどこへ行くのだろうか。
竹田三枝子
8月23日 例会報告 「若紫」(少女の声)
源氏が尼君のお見舞いに行った時のこと 少女の無邪気な声で「上こそおはしたなれなど見たまはぬ」とかちょっと大人びて「見しかばここちの悪しさなぐさみき、、、、」などと言う尼君に対しての思いやりの言葉、これらを聞いた源氏が少女の魅力を強く感じて側にいたい、成長を見守りたいと思うのは自然の成り行きのように感じてきました。そして尼君の死に直面した少女がどんな気持ちでいるのか源氏の思いはますます募ると思います。
竹田三枝子
6月18日 例会報告 「若紫」第六回(懐妊を中心に)
父帝の妃を愛してしまい密会したことだけでも罪深いのに、あろうことか
懐妊してしまう。恐ろしい結果である。それお藤壺にあってたしかめたいと
思い王命婦を責めたてる。拒絶され「当たり前である」つらいいみじうおぼしほれて
と打ちのめされる。このところの源氏は男らしくないと思うし人間的にも好きになれ
ない。父帝の妃を愛してしまったらそれなりの強い覚悟がなければならない。この秘
密は生涯かけてどんなに苦しくとも心の中にしまっておかなければ
ならない、それが覚悟というものではないだろうか。 永田カオル
藤壺の懐妊という大事件に帝や藤壺、命婦、女房たちの様々な気持ちが、
主語のない文章の中にめまぐるしく表現されている。又藤壺の罪の意識に苦しむ気持
ちとつわりの体調とが一緒になって悩む描写が細かい。
一方尼君への病気見舞いに立ち寄る源氏に最後の力を振り絞って少女の後見につい
て願い出る言葉は尼君の毅然とした生き方を映して見事な感じがする。 竹田三枝子
4月23日 例会報告 「若紫」第五回(密会を中心に)
少女に対しての恋心、藤壺に対しての恋心の表現の仕方が違っていてもその真剣さがうまく描かれています。又藤壺と源氏との生々しい場面、短い文章の中で品のある解し方がされていて私の中でもはっきり感じ取る事が出来ました。[感服」
有賀静子
都に帰ってからもどうしても少女のことをあきらめきれない源氏は、病的な感じさえ
する。
山寺に滞在中の尼君や僧都に手紙を出して、その返事の内容も無理のないものとわかっているのにもんもんとしている。源氏に同情よりも常識に犯されている凡人である私にはもっと気長に待てないものかと思ってしまう。そのような不安定な時を過ごすなかで突然に藤壺との密会の場面が始まりなんとも驚いてしまった。藤壺に対して想いがどんなに強くても父帝を裏切り、藤壺を苦しめ、手引きをしてくれた女房をも
罪深い谷に貶め自身も生涯心に十字架を抱いて歩かねばならない。罪深い物語である。
作者は物語の伏線としての重大な場面であることを読者に知らせている。しっかりと頭に入れておかねばならないと思う。
永田カオル
若紫の成長をながめて暮らしたいという源氏が次々にその方法を考えて実行するがかなわない。そこに突然藤壺との密会がかない、他の人とは違う彼女の魅力に夢うつつの源氏に対して藤壺は二度と会ってはならないとつらい想いでいながら、源氏を目の前にすると「なつかしゅうろうたげに、さりとてうちとけず心深う恥ずかしげなる御もてなし」という態度で接してしまう。その女心の微妙さが一つ一つの言葉によく表れていて、彼女の心の深さを感じる所です。
竹田三枝子
2月20日 例会報告 「若紫」第四回(妻の一言を中心に)
少女の源氏に対する淡い恋心がこれから先どのように展開されて、表現されるかが楽しみ。病後の源氏を迎え、自分の意志でなくても帰って来てくれた源氏に対し、態度、言葉の表し方を、もう少しやさしい思いやりで迎えることが出来なかったのか。女君に対して哀れさを感じた。
有賀静子
夕顔の死に、病になるほどの衝撃を受ける繊細な源氏。可憐な少女を引き取りたいと無理を言う源氏。時には世間並みの妻らしい心遣いを見せてほしいと、病気のときにもいかがとも聞いてくれないと、不満をもらす源氏、色々な源氏がいるのである。問はぬはつらきものにやあらむ」 無口な女君がもらす痛烈な皮肉が源氏をいたく傷つける。その一言の中にはあなたが病気になった原因はなんだったのですかという意味もこめられているのでしょうか。身分社会の中にあって女君のひとことは痛快でありました。
永田カオル
源氏が山から下りる時の別れの宴の場面は、山霞みの背景といい、人物といい何ともゆったりとした情景がパノラマで見えるようです。そしてそれぞれが奏でる楽器の音が流れて、この時代の文化の極みを感じます。葵の上の「問はぬはつらきものにやあらむ」という一言は今までの万感の思いがこめられていて特に待つ身のつらさが表れているのに、源氏の言い訳がましいおしゃべりは又若さゆえなのか、もっと重く受け止めてほしいのになあという感じです。
竹田三枝子
12月12日 例会報告 「若紫」第三回
(意中を切り出す〜送別の宴)
少女に対する源氏の真剣さが尼君、僧都に受け止めてもらえなかった時の疲労
感、世間の常識をこえた源氏の願いを
尼君に本心を聞いてもらった事だけで修行する僧の経、外部の風情が、その時々の気
持ち次第で明暗がはっきり表現されている。
有賀静子
今回は源氏の真摯な一人の人間として、若い男としての
純粋さに心打たれました。 「言うかひなきほどの年にてむましかるべき人にも立ち
おくれはべりければ」幼い時に母を亡くした自分の生い立ちの哀しみを幼い若紫に重
ねて非常識とも思える強引さで尼君に自身の気持ちを打ち明けてしまうそこには身分
の高さも、権力もみえてこない。多くの人が源氏に魅せられる理由はこんなところに
あるのではないかと思うのです。
永田カオル
若紫に対する源氏の若々しい情熱を感じました。
源氏は少女の素性や境遇が思っていたとうりだったので我が意を得たりと「されば
よ」と後見人になりたいと切り出してしまい、自分の今の事情まで言ってしまってか
ら「はしたなくや」と反省してみたり思ったことはすぐに行動したいという若々しい
一直線の気持ちに読者ははらはらしてしまいます。
竹田三枝子
10月10日 例会報告 「若紫」第二回
以前まだ何かで若紫のことを読んだことがありました。その時は源氏の人柄や複雑な話の筋を知らず一般的に言われるドンフアンなどの先入観で、幼子を自邸に引き取り理想の女性に育て上げるなんてなんといい気なものと思っておりました。しかし実際に物語を読んで、源氏の性格や物語の背景に源氏自身の父帝の妃を愛してしまった深い罪の恐ろしさにおののく心がわかるにつけ藤壺に似た幼子を見、又その素性など知るに自分で育てたいと一途に思ってしまうことも理解できるような気がします。 次回の展開がますます楽しみになります。
永田カオル
初めて登場する少女の描写は本当に可愛くて、髪は扇を広げたようにゆらゆらとしてつらつきいとろうたげで、眉のあたりうちけぶりとか、泣き顔で 雀の子を犬君が逃がしつる。 と言って走ってくる様子はもう幼い声が聞こえてくるようです。そしてそれを見つめている源氏がいつしか藤壺の面影を少女に見い出して涙を流しているとゆう場面は源氏の苦しい心の奥が見えるようで印象的です。その後の 展開が興味をそそります。
竹田三枝子
8月15日 例会報告 「若紫」第一回
若紫の最初は源氏が加持、祈祷に行くところです。
竹田三枝子
すばらしい山水画の情景に似た景色が現実にあるとは、知らなかった世界を毎日味わえたらどんなによいか。又天下の源氏の申し出を理由をつけて断ってくる僧、今まで思っても見なかった事の新鮮な体験、病も気からの言葉どうり、美しい文面で表現されている所に感銘しました
有賀静子
若紫といえば可憐な子供を自分の理想の女性に育てあげていくお話で、空蝉、夕顔のあとでは興味があまりないなあと思っていたところなんと明石の入道、娘の事等伏線として出てきたりで、やはりぼんやりとはしていられないと思ったことでした。
永田 カオル
6月13日 例会報告 『夕顔』を読み終えての感想
女心は何と複雑なことか!空蝉の心はわかるのですが、やはりどこかでケジメが必要だったのでしょうね
甲斐 恵
魅力的な二人の女性、空蝉、夕顔を終え、やっと源氏の世界に浸りきれた感じがしました
特に夕顔は人間として、女性として、とても強く魅了されました
永田カオル
夕顔とは、六条の御息所に通う途中、ふとたちよった、夕顔の咲いている屋敷に魅せられた一瞬の場面の話とばかり思って居りました。今度二年がかりで勉強し終えて、源氏のあるいは紫式部の評価する本質的な女性像が書かれて居り、登場人物、或いは一つの言葉そのものがおろそかに使われて居らず、すべてが小説的ロマンの筋道に貫かれて表現されていることがわかりました。
我妻洋子
夕顔が終わって、源氏物語がやっと解ってきた様です。源氏を取り囲む人物が面白く、今日の講義などでは右近がとてもあわれに思いました空蝉はあれでよかった。源氏も小袿を返してさっぱりしたと思います
次が楽しみ!!
宮川来仁
夕顔の巻を終えて、今までで一番ドラマチックで面白く読みました
最後に、あの自分の立場をわきまえて自制心があると思っていた空蝉が、せっぱ詰まった思いを歌に託しているのは、ちょっと驚きましたし、哀れな感じがしました。
竹田三枝子
4月18日 例会報告 『夕顔』の正体が明かされていく終わり近くの場面
夕顔について
夕顔の生涯は運命のままに流された一生のような気がしてならない
頭中将との心安まる暮らしも北の方の父右大臣に恐ろしいことを言われ、身を隠すしか自身を守れなかった夕顔
五条の隠れ家から荒れ果てた院に連れだされ恐ろしい闇夜でもののけによって命をおとしてしまう
あわれとしか言い様のない、一日花の夕顔の花のようにはかない女君でありました
源氏の無分別な行動によって源氏自身も非常に苦しまねばならなかった。
夕顔の性格はとらえどころのないかげろうのように見えて、実は身の処しかたなどに判断力や柔軟性を持ち合わせていたのではないかと思えるのです
永田カオル
「げに、いづれか狐なるらむな。ただはかられたまへかし」と源氏が言うように、お互いに化かし合ってだまされていたいなどとふざけて言って夕顔も楽しそうにうなずくところは、二人とも素性を明かしていないのに信頼し合って会話を楽しむ大人の男女のような関係という気がする。
その裏には夕顔の、不安と苦悩をかくして振る舞っている理性的な姿が見えてくる。又環境に左右されない素直な感性が源氏に心をとらえて離さなかったのだと思う
竹田三枝子
私と源氏物語
幼い頃の方言、忘れかけていた頃、源氏物語の中に出てくることに驚きと感激、
ますます入り込んでゆけそうです
有賀静子
私にとって源氏物語の魅力は?何といっても源氏と関わる女性達の個性豊かさです。
これから先とても楽しみです
甲斐 恵
美しい日本語とは縁遠い暮らしの中で二ヶ月に一回の源氏物語との出会いは私にとって
至福の時といえます。日本人にうまれてよかったと思える一日です
永田カオル
高校出てから何十年、久しぶりに活字を見てドギマギしましたが、今ではなんだか
若返ったような気がして楽しんでます。とはいうものの、古語はやはり難しい!
いつまで続けられるかわかりませんが。
宮川来仁
源氏物語の講議を受ける中で紫式部の計算された筋立ての文学的センスに魅了されております
今度「平安の気象予報士紫式部」というお天気キャスター石井和子さんの著書が出たと新聞に
報道されてまたびっくり、そして女性です。女ならでは世の明けぬ国に生まれたことを身に
しみてるこのごろです
我妻洋子
女君に対する源氏の愛情に打ち解けてくれない女君の
心の様子がよく表現されて何かほほえましいやら、又
源氏に対して何と無くあわれさを感じた。
最愛の娘を亡くした深い悲しみの左大臣が、婿でなくなった
源氏に対する細やかな心使いの様子に感動した。
そら
今回をもって葵の巻は終わりとなり、源氏物語を代表する葵上
御息所と二人の女性の源氏を中にしての凄まじい葛藤が展開される。
有名な車争いの後御息所の「ものをおぼえ乱るること」 そして
葵上の死 死を間近にして初めて夫婦の絆を感じる源氏と葵・・・。
もう一人重要な女性若紫との結婚 源氏を異性と意識する折も
なかった若紫の反発 この巻ではその後の事はわからない、とにかく
この葵の巻は源氏物語中の圧巻であると思う。
カヲル
葵の巻を読み終えて、葵を中心とした物語ではあるが御息所の本当の
恋の物語でもあるように感じた。源氏に一目合いたい一心で車争いに巻き込まれ
自尊心をずたずたにされたにもかかわらず源氏には理解されずに一人で
のたうちまわっている様子が響いてくる。 葵は最後には源氏と心を通わせる
ことが出来て完結しているが御息所の気持ちはどのように納まっていくのか。
竹笛
TOP ページ
index付きTOPページ
[読書会一覧に戻る]
|