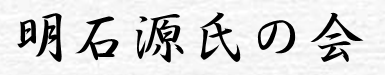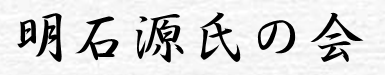
神戸の源氏の会は震災直後に生まれました。東京から講師を招いているため1日を通して行うのがここの特徴です。
最近は神戸から明石に場所を移し、中崎公会堂という創立100年を越す趣深いところで行っています。10時〜午後4時までの長時間、原文と向き合います。緊張しつつも楽しく和気あいあいとした雰囲気の中で平安時代にどっぷり浸って日常を忘れます。家をかかえる主婦が1日まるまる家を明けるのはなかなか大変なことですが、眠気とたたかいながらがんばってます。

***** 明石源氏の会 *
2013年2月3日
・・・紫文ファン
P146の「なおゆゑづきよし過ぎて、、、」の意味を六条御息所のことと解説されており、よく理解できた。もしこの解説がなかったら、意味がもう一つ分からなかったと思う。
・・・酒井 みちよ
源氏物語の解釈からいろんな話題に発展・どんな展開になるのか予測がつかない。毎回とてもスリリングで刺激的です。いつも楽しみです。
・・・山本
源氏は葵が亡くなってから、こんなに悲しむのなら 生きている間に、、、と思いつつ読んだが、それは現代人だからなのか。源氏と朝顔の交流は心温まりほっとする。男女の恋情というより、友情に近い情を二人の交流に感じた。
・・・S・T
葵(妻)を失った源氏の嘆きようはびっくりするくらいです。何も考えられない、取り乱している。“見し人の(亡妻)雨となりにし雲居さへいとど時雨にかきくらすころ”とのたまふ御けしき_。見ゆれば“平安時代の人々にとって、”死“は非常なる別れのようです。今と違って、鳥辺山(京都)に亡きがらを捨てたようです。ですから、その別れのつらさは現在の比ではありません。現在の私が想像してみると、今はお遺骨が手元に届くのでお別れもできます。
・・・山崎
平和な御代ならでわの穏やかな王朝文学すみずみまで心づくしの言葉使い喜び、悲しみ、がその人の装いで察せられる色づかいに心ひかれます。
流行だからで黒づくめとか、ひらひらの、スケスケとかの現在ファションが多い中、つつしみ、奥ゆかしさの文化に日本のこころを感じます。又鈍色・紅・等古の表現が落ち着きがありますネ
“ゆゑづきよし過ぎて人目に見ゆばかりなるは あまりの難も出で来けり”などはやはり男は女のさかしさが我慢ならないのは、今も昔も変わらない男の傲慢さが面白く思いました。
・・・明石のアナゴ
今日も雑念からはなれ、又紫式部の雅な文章によいしれました。妻を亡くした源氏の心境を、自然の移り変わりとその気持ちの中に生かされている一語一語の描写がとても感動的で、イメージが私の脳裏に広がります。又それが心地よくて自分の顔が和らいでいくようです。「今も見てなかなか袖を朽すかな 垣は荒れしやまとなでしこ」今もか(亡き妻の容姿と思いめぐらしながら)先生の解説が無ければ解りえない文章でした。細やかにどの場面も立場を踏まえて真正面から感じとる所がとても源氏らしく、逃げない強さも感じとれた。
・・・明石っ子
・・・多田芳子
・・・節子
十*** 明石源氏の会 葵の巻***
2012年11月4日
・・・哀れを知るわたし
源氏の葵の上の亡き後四九日まで勤める悲しみと心の葛藤がありながらも、通いどころの女たちへのふみを、送ることを忘れない源氏。御息所の源氏に対する愛の深さ、この御代の最高の理知と教養ある女性の一途な恋心が嫉妬となり心の暗となる。「青鈍の」巻紙の文を受ける源氏と、その返事を受ける御息所の心をなやみます。そしてこの二人の心の行方は・・・・・
・・・○○○
源氏の葵に対する愛の深さが表れている場面が、良く文章に書かれている。現在でも、浅く表面だけの交際でも深く(良い事も悪い事も)知ることで、より深く理解できる事も多い。源氏物語が時を超えても、人々と愛されるのは現在にも通ずる事がある故と思います。時代が変わっても人の心は何か通ずる物がある、それがこの物語に知りたいと思う事が読み継がれた様に思えました。田中先生のご指導の賜物と思い感謝申し上げます。
・・・明石のタコちゃんより
今日も久しく雅な一日を過ごす事が出来ました。有難う御座います。本当に古典の素晴らしさを思う事が出来ました。心の世界、自然の世界をゆったりと味わって日が暮れるのは少し憧れをおもいます。楽しかったです。
・・・おのろけちゃん
一回失礼しました。今日は雰囲気を戴きたくてこさせてもらいました。源氏の心の深さ、広さが大いに現われています、御息所の生き霊を見たにもかかわらず、ずばっと、といったことです。北の方の過慕の念が如実に表れています、又若宮への思いが愛のモザイクを思われます。御息所の生き霊になったことが院にばれないだろうかという思いが痛々しい。
・・・紫文ファン」
今日も美しい文を読み心が洗われました、先生の深い説明・訳文も大変良かったです。
・・・酒井宣子
御息所から葵を亡くした源氏の所に手紙が来る。源氏は御息所の生霊を見ているので、返事を書こうかどうか迷っている。でも女からもらった手紙に、返事を出さないわけにはいかないと源氏は苦悩する。御息所を苦しめることはできない。でも妻は御息所の生霊に殺された。この源氏の心情は、現在の心理にも多々あると思う。私もこのジレンマに似た事を経験したことがあるので、涙の出るほど共感できた。最後に源氏は御息所に返事を書いたのです。やはり平安時代の人徳(人情)は素晴らしいです。現在は何だかとげとげしい事情は多い。
・・・明石っ子
時代は葵の上を亡くし今更気がつかなかった良い所が分かり、大事な人であったと段々に重く感じていくさまは、誰にも通じる処があると思います。様々な重たい沈んだ気持ちが続き、読者にも気が滅入る様な時が続きいる時に
ガラッと気持ちを変えるように、頭中将が出場となり、源氏の気持ちも(読者も)ホット明るくさせられる場もあり、読者も引き付けられる処でしょうか。
・・・多田芳子
源氏物語を学びたいと思いつつ過ごしておりました所、前川さんにお誘い戴いて喜んで参加させて頂きました。分かりやすく丁寧に教えて頂いて皆様も熱心な方達ばかりで、教えられることがたくさんありました。人生の先輩たちにかこまれて、又深くお勉強されている方々の中での一日は幸せでした。源氏物語の世界への入り口にたてたので、これから一員として頑張って学ばせていただきたいです。宜しくお願いしなす。
・・・節子
平安時代の雅な日常の中にくりひろげられる貴族の恋物語が、少しもいや味なく下品にならず優雅に綴られている様に、日本語の美しさ奥深さを感じます。読み進むにつれ物語の中へ入って行きそうで、やはり平安のたおやかな世界には一歩踏み込めぬためらいがあります。源氏の男の強さそして弱さ、それと、男ならではの心遣いが一千年の隔たりを覚えます。賢いながら御息所の女心のあやぶさ、悲しさ、弱さが、おさえきれずに生霊となる苦しみが、美しい紫式部の筆により深く感じる事が出来、私の至福の時間となりました。次回が楽しみです。
*** 明石源氏の会 ***
2012年7月15日
・・・七夕織姫
やっと心が通った葵の上と光源氏 このまま心が結ばれた夫婦であったら光源氏の一生は違っていたのに・・・
紫式部の物語作家としての素晴らしいストーリーの展開が益々面白くなりそうです。
・・・都忘れ
源氏と葵は少し前迄は、少し自分の性格とか人生の出会いの様な感じが有り、楽しく読んでいましたが、出会急の涙気等思わない源氏のやさしさを感じとても良い感じでうれしく読ませて頂きましたが、急の病死で人生のはかなさ、むごさを感じて居ます。源氏の人生にも大きな悲しみで人生も変わる事になり、はかない出会いでしたね。
・・・T・Sの娘
久しぶりの源氏物語講読会でした。
ストーリーを思い出しながら、だんだん源氏の世界にひたっていきました。葵の巻もクライマックス、珍しく献身的な夫になった源氏の君の姿がほほえましいのもつかの間、とんでもない事に・・・相変わらず言葉一つひとつが奥深くまで読み込まれ、それによって登場人物の生き生きとした気持ちに触れる事が出来ます。
毎回新鮮な源氏物語に出会えるこの講座を楽しみにしています。
…明石の女性T・S
源氏物語を学び始めてもう7年ぐらいになります。最初は古語(いにしえの言葉)なので、良く理解できませんでしたが、慣れるに従って少しずつ理解できるようになりました。この頃になって始めて、現在の今も使われている言葉が少なからず残っていて、源氏物語の中に見られました。“いみじ”と言う語は“異常”と言う意味で使われていました。この“いみじ”は“葵”の巻に出てきて、死の悲しみにある人々の心情を「特別に、いみじげなること多かり」と紫式部は書いている。現在でも死は異常で“いみじ”なのです。日本人の心細やかな気持ちは、2000年たった今も、平安時代も変わらないのだと、ヒロイン(登場人物)たちの心の中を見つめる事が出来ました。涙が出るほどなつかしいヒロインたちです。私はもう“源氏物語”が手離せません。ずっと読み続けたいです。
・・・あかしのたこちゃん
明石は、源氏物語の中で大きな位置を占める土地ですが、そのPRにあまり熱心でない様に見受けられ残念です。しかし田中先生の読書会が有る!これは明石市民としては誇りです。
・・・○○○
左大臣家の男子出生の喜びも束の間・・・・・源氏と葵の心を通わす二人の心の動きが、私の心を動かす・・・・・二人の夫婦としての情を交わす束の間の喜びをホットさせた・・・北の方の死と彼の女の死に関わった人の疎ましさが、源氏の心を沈めているか・・
源氏の生き様がどう変わるのだろうか・・・妻恋しさの胸の張り裂ける様な悲しみからどのように立ち直るのか楽しみ・・・
・・・○○○
葵の上の悲しみ、源氏の絶望がそくそくと伝わりました。
作者はなかなかのストーリーテラーだ。
・・・明石っ子
源氏の本心は紫の上ですが、葵の上は形式上の夫人で心のかよう部分は少ない処でしょう・・・葵の上が若宮出産にともない産後のひだちが悪く命があやうくなり、源氏は今まで感じた以上に葵の上の端麗さ、特に御髪の乱れない美しさなど、今まで以上に良い処が目につく様になり、人生の終わりに近付き見えていなかった長所が分かるというはかなさ、源氏の君が誰にもやさしく出来ることの集大成の様な気がします。
・・・松陰
葵 色々な夫婦の絆があると思います。源氏にすれば数ある女性の中で、この章で10年も子供が授からなかった夫婦に、源氏に似た男子が産まれ源氏も妻としての愛しさがあらためて絆を感じ、内裏に装束を整えて出かけ、その間の急変した事も予想もできず、心を取り戻す事の大変さが、短い文章の中で先生や皆さんのお話で、式部の深い文章の味と言うか源氏物語に又楽しくなりなした。今後共勉強させて頂きます。
…明石の海の子
今回も素敵な時間ありがとうございました
夫婦の絆、妻の急死、追慕の日々と葵の巻がすすんでいきました
ゆっくりと味わいながら現在と物語の現実を比べながらいにしえの人の気持ちを想像して
楽しく過ごすことができました
*** 明石源氏の会 ***
2012年4月22日
・・・○○っ子
葵の上の出産の場面を学びました。左大臣(父)大宮(母)の心配している様子、座位での出産(坐産)は新しい驚きでした。無事出産後の初夜、3夜、4夜の祝いの酒席等・・・楽しげな様子の中での御息所の生霊にはびっくりしました。御息所の苦しみがよくわかり感動しました。
・・・山本紀男
「なつかしげに」(p86 2行目)と言う言葉についての説明を詳しくして戴き、改めて古語の持つ奥深さが分かり、大変面白かったです。
・・・○○○
この章は奥が深く1人1人の動きが訳り人物の働きそして心の動き立場での思い文章は単々と書いてあるが、先生の講義のお陰で納得がいき、時代が変わってもやはり心遣いを忘れては人生味気ない、今の時代でも小さな幸福、人様の親切を心に止めて毎日感謝の日々を送りたいと思います。今自分に出来る事、他人様に役に立つ事を身近な人の死に逢い、生命のあり限り何をすれば良いか、本当に改めて考えました。今後とも勉強を・・一生勉強としみじみ思えました。
・・・○○○
今までは、ストーリーの面白さにひかれて読んできましたが、今回先生の深い説明に古語のすばらしさを少し理解できたように思いました。
・・・大路久美子
今日は目からうろこの講義でした。ありがとうございました。
・・・○○○
久しぶりに学生時代に戻ったような講義を受講させて頂き、ありがとうございました。今後も勉強させて頂きたく思います。感謝いたします。
・・・おのろけちゃん
久しぶりに参加できましたことが、感謝です。
先生の顔や皆様の顔を見て、感激しております。また、遅れて参加して申し訳ございません。
御息所と生きりょうの関係で、ポーと飛んでしまいました。
北の方が出産できたのがうれしいです。もののけは源氏の方にしか見えないのには、感動いたしました。
*** 明石源氏の会 ***
2012年1月22日
・・・播磨っ子
今日も楽しく源氏の世界へいざなって戴き、有難う御座いました。
葵の巻は六条御息所と葵の上の登場で、奥の深い暗い所が多かったけれど、日本の古い文化に学ぶところ多く良かったです。
・・・桜の園
共に高貴な身分で、教養ある女性「六条御息所」と「葵の上」が同じ男性、光源氏を巡っての愛の型。女性にとっては、どちらの愛が仕合わせであろうかと思わせられる「葵の巻」です。
私にとっては、葵の上より御息所の素直な愛に共感しますが、ただ生霊となって、相手を苦しめるのは、ちょうと・・・
出来たら光源氏に生霊となって心の内を見せていたらどんな展開になっていただろうか・・・など、さまざまな愛の形が興味深い源氏物語です。
・・・水口しげみ
御息所の心の動きが表現される場面。
身体と心が別の行動に出る。
私が悪くなるようにと思っていないのに、魂が一人歩いているのか・・・
愛する源氏に対しては乙女の様に心が騒ぐ。人の中には善と悪があるように思います。 田中先生の説明や資料を頂かなければ理解できません。
この場面に思いをはせ次の場面を楽しみに・・・
・・・T・T
半年ぶりに心豊かな日を過ごさせて戴きました。源氏のやさしさ・心遣いに心打たれました。そのやさしさが、かえって御息所をひどく悩ませることにやり切れない思いもしました。本当の優しさとは、何なのか?時代の違いもありますが、
心を鬼にして冷たくすると言う優しさもある気もします。
・・・酒井宣子
六条御息所の病と源氏の妻の北の方のものの怪にとりつかれた病の対比の場面に
入りつつあり、とてもしんどい大変なシーンですが、波乱万丈。源氏の心情は
いかばかりか。私は感情を抑えがたいです。主人公たちに思い入れをしながら時間の経つのも忘れて、読むことができました。4カ月後が楽しみです。
・・・山本
六条御息所の心理描写がよく理解できて、源氏物語への理解がより深まって
よかった。
・・・明石っ子
源氏にとって北の方の事が一番気になりながら、御息所の症状(生き霊・悪霊にとりつかれる)も気になり訪問せざるをえない優しい心持に感心です。
もののけは、いつの時代にも人の心の中にあるものでしょうか。現実ばなれした中に人の心の弱さとか、たよりたい気持からあるものだと思います。
・・・逃げの源氏と御息所のかなしい恋
知性と感性と、気位の高さ故の苦しみは、源氏を愛した見返りは大きい。
控えめに生き暮らす中での[いどみ心]は、車争い・所争い・・源氏のつれない心には理解できないであろう。
おぞましい噂をたてられ、我が身の宿世のうとましさを身の定めと、生霊の振る舞いを知りながら、どうする事も出来ない御息所のつらさだが、、、。
それらのすべては、つれない人への思いをつのらせながら、、、。
なお源氏の事が、忘れられない我が身の宿命、、、。御息所の生きざま。
**** 2011・10・23 ≪ 葵 ≫ 感想 *****
・・・大路
今日も新しい発見・喜びが、たくさんありました。
千年前と人の心のありようの変わらない事とか。
すぐに忘れてしまう事が残念です。
続けることが力になると信じ、頑張ります。
・・・タンポポ
源氏を取り巻く女性は、六条御息所と葵の上が、心理描写がおもしろいです。
夕顔の様に、男性にとっての単にかわいい女性と比べると、この続きの心理
葛藤の場面を読み解いていただけるのを、楽しみにしています。
・・・酒井 宜子
今日学んだ源氏の気持ち(心持)に、非常に同情してしまいました。
源氏の人生を考えたら、苦しいだろうと思う。
けれど、彼はその時々を自分に忠実にこれまで生きていると、私は思います。
・・・○○○
御息所の女として生きる中で、源氏に対する思い・情熱である反面、
気位から来る表現がうまくかみあわず、源氏に通じないのではないかと思う。
知的で理性が強いためのなやみではないかと、思います。
次回が楽しみです。
・・・○○○
車あらそいからの御息所の心の動き、読書会の皆さんの一人ひとりの読みを
聞かせて頂くのが、先生の指導と共に勉強になります。
原文の奥深さは、先生のお話と音読される声は、本当に和みます。
この所私も色々とありましたが、いつの世も人それぞれの悩み・苦しみの
ある事、自分の弱い所からにげないで、今日は勇気を頂きました
***** 201・7・17 ≪ 葵 ≫ 感想 *****1
・・・明石っ子
車争いの場で、六条御息所の嫉妬深い心がさにあらず、理性が働き自分の車が
ひとだまの奥におしやられて御息所だとばれて、帰るに帰られず「事なりぬ」と源氏の行列が近づくとやはり一目見たい気持ちをおさえられず、心弱しと
云われ、強さと弱さを合わせ持つ御息所だと、、、、。
・・・AKKEさん
三ヶ月に一度の源氏の会、待ち遠しく感じていたのに、あっという間に三ヶ月は来てくれました。
青空に白い雲、明石城を眼前にして、古語で読む田中源氏!!
時折至福の眠りが包み込む。これがまた何とも幸せ。
車争いで「ハッ」と目がさめ、御息所の心の奥底をのぞきみることが出来、
いじらしくいとしく哀しく「御息所のあなたよ、美しい!!」と、心の中で
叫ぶ。こんどは仕舞で葵の上を舞うことのお許しを願おうか?
凛として品よく美しく、炎の心をおさえておさえて静かに舞えるかしらん?
その前にかなりスリムにならなければ・・・やっぱり無理ダァ。
・・・おのろけちゃん
車争いの場面で、二人の女性の対照的な違いがありました。
御息所の一途な心が大へん印象に残ります。
暑い一日でしたが、大へん心に残る一日でした。ありがとうございました。
・・・カサブランカ
‘車争い’身分がはっきりしている時代。今はこの時代に考えられない程、
開放されているが、それが良い事ばかりではない。この時代の事を勉強させて
頂き、良い所は習い、自分の生活に反映させて行きます。
暑いと家に引きこもり、この所体調も悪かったのが、源氏の会は頑張って
出席できよかった。 人の心はこの時代も平安時代も深い所で同じに思える。
・・・酒井 宣子
「葵」を学びました。六条御息所は、源氏をとても愛していると感じました。
しかし源氏には妻の葵がいて、子供も生まれる。六条御息所の気持ちは、
痛いほどわかります。 ほんとうに源氏は光輝く人なので、優しい人でもあると感じています。 私も大好きになっています。
・・・酒井 みちよ
有名な「車争い」の場面を初めて原文で読み、いろいろな発見があり、とても
新鮮でした。意外としんらつな語り手の言葉とか、笑える文章があったこと
など、初めて知りました。
・・・タコノアシ
六条御息所といえば、私の中で怨念すさまじく近寄り難いイメージでしたが、あらためてこの会で「葵」を読み進むうちに、車争いで理不尽に傷つけられた事を思うと、同情の気持ちが湧いてきました。真面目で一途な気持ちの
持ち主だったんですね。式部のこのあたりの伏線の作り方、実にうまいなあ!と思います。 この先、どんな展開になるんやろ?!と、昔の人も現代人と
同様、早く続きを読みたくなったことでしょう。
いろんな女性像を描いている紫式部ですが、式部自身は、どの姫君に自分を重ねていたのでしょうか・・。
・・・ねずみちゃん
今日もとっても暑い一日。でも教室の中は外の暑さもなく、とってもぜいたくな時間です。今日は『葵』を勉強しました。
源氏も色々の巻があるけれど、今回こそは帰ってもう一度『葵』を想いおこして、家でよか(余暇)をたのしみにもう一度味わってみたいと思いました。
・・・波月(はづき)
お城を見渡せる素晴らしい会場で、源氏物語の読書会に参加できる幸せを
かみしめています。
原文で解読できるという又とない会に少し躊躇しましたが、先生のていねいな又深い解釈にひかれ、ご指導あればこそ読み解けるのだなあと思いました。
今日は有名な‘車争い’の場面に、皆さんから色々御意見を聞かせていただき、
物語のひだまで教えられ、とても有意義な一日でした。
ありがとうございました。
・・・ひまわり
紫式部の人間心理を現わすのが、すばらしいです。
葵は、とてもおもしろいです。
・・・へそまがり
源氏物語原文にひきつけられるのは、そこで紫式部に逢えるからかも。
・・・○○○
車争いを読み、御息所の心弱し、を知り、よくわかって、今までとちがった
御息所を知ってよかったです。
・・・○○○
先生の魅力的なお話はもちろん、すばらしい参加者の皆さまにお会いすること、おいしい昼食とおやつをいただくことを楽しみ、出席しています。
まだ一度も期待をうらぎられたことは、ありません。
・・・○○○
体調が思わしくなかったのですが、来させていただいて良かったです。
六条御息所の意外な女心(かわいい)に、ふれる事が出来ました。
女心というものは、千年も昔からちっとも変っていない事を確認しながら
楽しませていただきました。
〜〜〜 2011・4・24 ≪ 花 宴 ・ 葵 ≫ 感想 〜〜〜
・・・明石っ子
華やかな花見の宴に、花にも劣らずとも負けじの源氏の装束が、まぶしく感じ
られます。又、藤の花の美しさ、藤壺の美しさが目に見える様です。
震災で気持ちがすさんでいる昨今、心のやわらぐ様なひとときでした。
・・・赤とんぼ
日常生活からかけ離れて、雅びな世界へ酔いしれました。
今回は新しく4名の方が入られ、源氏読書会がますます充実する様が嬉しく、
又花宴が終盤になりました。
「あづさ弓 いるさの山に まよふかば ほの見し月の 影や見ゆると」と、
この花宴をとても強調し、「心いる かたならませば 弓張の 月なき空に
まよはましやは」と、次回へと余韻を残す形が又以前とは違ったシーンである。
しかし、1句1句本当に大切で、各巻も一期一会であるなと思う。
日常生活も1刻1刻大切に人を迎える心をつくれたら素晴らしい。
震災で大変な時に、この様な時間がある事、新しい人との出逢いに感謝したい。
又次回は、田中先生執筆の葵の巻にも期待したい。
・・・大路 久美子
今日はじめて出席させていただき、講義時間が長いので眠くなるのではと、
心配していましたが、新鮮でとても楽しく受講いたしました。
今日は朝顔の姫君が、わかりました。
・・・生頼 民子
日常生活から離れて、私にとって雲の上の人達の気持ちをあれこれと論じる。
心のさまは、今も昔も変わらないのだなと思いました。
何百年も温められた心の有様でありながら、父親の愛憎、男と女の心の細かい
様子、楽しく源氏の世界で遊ばせていただきました。
ありがとうございました。
・・・おのろけちゃん
たくさん会員さんがふえ、ありがたいです。
宮中の細部がわかってよかったです。朧月夜の心の強さがわかりました。
朱雀帝に世がうつって、源氏のつらさがえがかれています。
代がわりには、愛別離苦つらさがわかります。
藤壺の心がせつなくかかれているのが、手にとるようにわかりました。
・・・酒井 宣子
“花宴”を学びました。
平安時代の男女・地位のある人ない人の思いは、現代の私には目が開かれる思いです。大らかな心は、見事なまでの振るまいになっている。相手を思いやり、非難しながら、自分の思いを遂げている。“葵”が始まり、六条御息所・朝顔の君の関係も、興味津津です。藤壺は源氏にとってどうなるのか、次次と楽しみです。
・・・酒井 みちよ
母からかねてより聞いていた通り、先生もメンバーの方も素晴らしいです。
20数年ぶりに源氏物語の、しかも原文にふれて、心にしみ入るようでした。
花宴や葵の巻きをじっくり味わい、新しい発見がたくさんあり、充実した時間
でした。
・・・水口 しげみ
花宴は短い章でしたが、左大臣家と右大臣家の違いが面白く表現され、平安の
ゆったりした時代にも十人十色の様子が描かれていて、美しい時代が見えて
楽しかった。葵は始まった所ですが、やはり楽しみです。 源氏が、この方と
結婚してからこの人の人生が展開する事が、次の講義が、楽しみです。
・・・山本 紀男
細かく説明して頂き、分かり易かったです。
また、物語の流れも折り込んで話をして頂き、よかったです。また「すき」の
解釈も、古文の持つ奥深さをそれとなく示唆して頂き、よかったと思います。
・・・
新しい会員さんが、たくさん増え、とても充実した会でした。
それぞれにすばらしい方々で、私自身の読解も深まったように思いました。
・・・
原文の解釈が、とても勉強になり、おもしろく、これからもよろしくお願い
致します。
原文から受ける語彙の美しさに、感動しました。
・・・
源氏の浮気心かと思うが、その反面一人一人の女の思いは、その時その時が
真直ぐな気持ちで突き進みながらもどこかで異常な所がある。藤壺のせい
かなァ・・・。父院との関わりと諌めを心苦しく受け入れる純な源氏の心根は
生い立ちのせいかな・・・。源氏に恋する私。
〜〜〜〜 花 宴 読書会感想 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成23年1月16日
・・・明石っ子
二月の華やかな宴の席で、芸を競い合う中で、源氏の青海波を舞う場面や、中将の柳花苑などの場面で、頭の中将の源氏に対してやさしい心くばりのあるやさしい処が印象でした。
・・・明石の猫
「花宴」を読みました。
華やかな宴の様子を読んでとても楽しいひと時になりました。
宴の中で詩歌を創っていたことに驚きました。
それも広場で、皆の前に一人ずつ出て即席で漢詩を作り得意になったり、苦しげな様子もあり、人間観察はおもしろいでした。貴族階級の文化は、現在の私にも理解できるので、楽しかったです。
・・・おのろけちゃん
昨日「イメージで読む源氏物語」を読んだら、あまりおもしろくなかったが、源氏が二十才であれば、なぜかわかるような気がする。
又、藤壺と弘徽殿のちがいがわかる。少しおもしろ味がわかった。
恋のかけ引き、ゲームがおもしろく、源氏の頭の良さと思う。
ほめて上手である。
・・・水 口
今回の講義は、人間は本当に相手の気持ちになって、いつの世もほめられる事の嬉しさが、又人様の良い所を自然にほめる事を学ばせて頂き、すべて良い心で人に接する大切さを学ばせて頂きました。
・・・ゆほびかさん
・藤壺が帝にとっていかに宮中で第一等の女性かが、この桜の宴でもはかり知られる。後宴の夜には弘徽殿女御を。翌あけて暁にともなれば、藤壺が「もうのぼり給へにけり」で、帝の相手に上にのぼられる。この一節で藤壺の教養と人間性の優れていることを式部はさりげなく描写するあたりはさすがである。
・・・赤トンボ
花宴も、ほんのひと夜の出来事を源氏を中心として、数々の登場人物で描かれている訳ですが、又もや源氏をとりまく脇役の描写の素晴らしいこと。又読んで酔いしびれそうです。
今回は「うき身世にやがて消えなば尋ねても、草の原をば問はじやと思ふ」雅な中にも、何か芯の強さ、言葉の巧みさが感じられ魅了される。1度位、その様に語れる相手に出逢ってみたい、夢うつつにでも!!
・源氏の心の動きに、ついて行けない思いを感じましたが、現代とまったく体制の違う時代の心の動きだろうと納得しました。
人を恋う気持は、現代も同じなのだけれど。
・はなやかな宮中の年中行事と、人間模様。
殿上人の心の動きがおもしろくて、朧月夜と源氏の出会いに見るこの時代の恋の行方は複雑である。
源氏の恋のなやみとしては、一番深いものではなかったか。
平成22年10月31日(日) 「紅葉賀その4」
- 源氏の君が宰相になり、身分が上がり、帝の思いは、血のつながりが
考えに多く、いつの世も同じなのでしょうか。
才たけた人はどの時代も身分に関係なく、尊ばれるものですね。
・・・明子っこ
- 中将は些細なことでも、源氏に対する対抗意識を燃やしている。
嫉妬心や恨み心、しかしその裏にはお互いの人間性を尊重する心も
表われているように私には思える。人間は対抗意識出来る人があり、
互いに成長するのではないか。これは今も昔も同じこと。
この心の必要性を今も大切に、子供達に伝えていきたい。
又、帝は若宮の成長ぶりが、とても気がかり。真実を明かせない藤壺。
源氏の運命の悪戯とも言うのでしょうか、源氏の≪尽きもせぬ心の闇に
くるゝかな雲井に人を見るにつけても≫の詩が憎らしく、腹立だしいが、
一面解かる気もする。
又、藤壺も地位が高いとは言え、若宮の母君として、どんな気持ちで
あろうか。人間、正直に生きて行くのが素情であるが、出来あう事全てを
あからさまに出来ない現実。現実大肯定の心の捉え方の難しさ。
又今日も文章の素晴らしさや、ドラマの人間模様を感じた。
・・・赤トンボ
- 紅葉の賀の面白いところを心うきたつ思いで、読ませていただきました。
スリル満点でありながら、ユーモアがあり、紫式部の心の広さが伺え、
面白かったです。
又、最後の方の源氏の子(若宮)をめぐる源氏と藤壺の心のあわれ、
自分が経験しないだけに、自分を藤壺に重ね合わせたりして、現実の世
から退避して、源氏の世界に遊ぶ、うれしい一日でした。
又楽しみにしています。 ・・・あじさいの花
たぶんおもしろいと思います。 ・・・おのろけちゃん
- 初めて参加させて頂きました。 学生時代以来、久し振りの源氏物語。
独特のリズムに触れ、懐かしく心弾むひとときでした。
今日読んだところは、源氏と頭中将の‘若気の至り’が楽しく、
想像を逞しくしながら楽しみました。
「まことは現心かとよ」→現代語だと「マジかよ〜?!」って
感じでしょうか(笑) ・・・新入生A
- 全回は受けていなかったので、前半の物語はよくわかりませんが、今日の
勉強は大変楽しかった。
先生に質問もできて少しは源氏の世界がわかりました。
・・・タコちゃん
- 今日の場面は、紅葉賀の中でも藤壺が后となり、更なる波乱万丈の人生
を暗示させる所です。そのハラハラドキドキの前に、絶妙のタイミングで
描かれた頭中将と源氏の悪ガキの様な悪ふざけは、大阪弁でゆうたら
「ここがめちゃおもろいねん!」神戸弁では「あんたら何しとん?! 」(笑)。
宮中で大人びた振る舞いをしていても、まだはたち前の青年やもんなあ、
と思うと、身近に感じて、笑ってしまいます。
それにしても当時の歌の教養の高さに驚かされますが、掛詞の妙の片鱗
が、関西のダジャレ文化にも受け継がれてたりして・・?但しおやじギャグは
「さむぅ〜」で、片づけられちゃいますが・・・(笑) ・・・タコノアシ
- 内侍の老いた恋心はおもしろいが、誰の心にもあるのではないか?
源氏の歌、内侍の歌などの一つ一つの説明がおもしろく、当時の知的社会が
しのばれる。 ・・・三谷
長い人生に自分の意にそわない事もあり、それを貴族の生活に表わしたら
その場その場の詠の美しさが表現が、楽しく奥が深く、先生の説明を聞き乍
その時代を心に描き、現実から離れ、雅の姿を頭に浮かべ乍一行一行読む
のも楽しみで。
こんな静かな心で読書する幸福 会の皆さんの笑顔 感想を楽しみに
次にどんな風になるか、頑張って勉強させて頂きます。
- 今日はいくつかの短歌を勉強し、当時の教養の高さに驚きました。
現代に生まれてよかった、とつくづく感じました。
紅葉賀の最後のところ、源氏の藤壺への思いを、せつなく感じとりました。
書くことは苦手ですが・・。源氏の事は何も分からないままの参加なので
ただただ先生のお話を聞くのが精一杯でした。
◆ 頭中将と源氏の乳兄弟のような関係がうらやましいです。私もこういう関係
(人間関係)のソウル・メイト(soul・mate)があれば、いいなあと憧れました。
けんかしながら、すぐ仲直りし、いたずらをし、からかいながら、お互いに
楽しんでいる様子。平安朝は自由(平等ではない)な時代だったなあと
思います。武士の時代の封建的な事と正反対です。
どちらも身分制はゆるぎなかったのに。
これから先が楽しみです。
◆ もし許されて映画監督になるとしたら・・・。
誰を配そうか? 源氏・中将・源の内侍、誰かなぁ〜?
源の内侍は希木樹林は、確実にアポ!!
源氏と中将がいないなぁ〜。
私が若い頃の映画では、源氏=長谷川一夫、中将=市川雷蔵、 バツグンに
良かったけど、今この二人に匹敵する俳優、見つからない!!
そのうち見つけましょう・・・。
平成22年7月31日(土) 「紅葉賀その3」
生頼民子
源氏の若い紫に対する思い(外出をとどまったこと)はかわいく感じました
また<年いたう老いたる>内侍の源氏に対する一途な思いが式部の筆をとおして
生き生きと描き出されている
源氏と内侍の歌が催馬楽という民謡や白氏文集の詩の中から引用されていて
いつもながら紫式部の教養の深さに感心させられました
二人のかけあいの面白さに物語の深みを感じました
住野文子
今日は紅葉賀を勉強しました。本当に毎回思うんですが
やはり予習して声に出して読んで先生に習って帰って復習したら
もっと楽しく充実した時ができると思います
何か今日も「もったいない」時を過ごしてしまったかなと思います
来回こそと今日も思って期待をしてしまいました
K.M
若紫の話のあとに内侍の出番でおもしろおかしく拝見しました
内侍のダイナミックでいつまでも旺盛な色気を私もみならいたいと思いました
帝の、子源氏仁対する愛情が快くて、心を通りました
帝の大きさがあってこそ源氏の魅力を感じるものです
源氏と頭中将のかけひきがおもしろい
三谷ナダ子
幼い紫と源氏の関わり
源氏の紫への思いやりとやさしさ
紫の幼さの中にある女としての生育する勘の鋭さ
内裏の中で女房達の噂話しの恐ろしさ
源氏の内侍へのからかいか何か?
内侍の受ける心の動きの中の鋭さ。
内裏では様々な恋のやりとりが種々あったであろう
これが噂の種でそれを楽しむ女房達の暮らしが忍ばれる
源氏と内侍、煙が立って火がついたのか?
源氏の遊び心の中にあるやさしさか?
頭中将とのやりとりがまた楽しい
川上美津子
震災より15年
最初は先生のボランテアから始まった源氏の会という事で
当時参加された方はいらっしゃらないのですが
その後関心のある方の集いとなり私も参加させていただき
勉強させていただきながら会員の方との楽しいおしゃべりに
また次回を待ちたい気持ちでおります
斉藤暁美
内侍と源氏の歌のやりとりに驚天しました
子供の時はわからず読んでいた源氏物語と
70才になって読む源氏物語ではこうも理解が違うとは…
源氏物語の奥深さと凄さを感じました
水口しげみ
源氏が初めて間近で見た内侍は年齢ににあわず
身だしなみがよく好色の女性なれど
若い源氏の気持ちが引かれる様が面白い
人の心の表現が物語を楽しませる
「かなはぬもの憂さにいと久しうなりにけり」といった。
気持ちは行ってあげたいと思うのに気が向かないさまを表す
が内侍は男方の御遊びにまじって琵琶を弾いたりする
名手で美声の持ち主でこのような人生も楽しと思いました
竹花外記
外は猛暑、中ではおいしいちらし寿司をいただき
楽しい一日でした
「年、いたう老いたる」内侍のユーモラスは描写
源氏との関わり合いのおもしろさに
笑い声の絶えないレッスンでした
斉藤隆二
紫式部に自由闊達に描かせている
道長の器の大きさを思いました
酒井宜子
源氏と紫のやりとりはほほえましく
思わずいいなあと思わされました
「年、いたう老いたる」内侍とのやりとりも巧妙で
お互いに気付いていながら
表面上は面白く歌のやりとりをはじめとして
私を楽しませてくれました
K・M
早震災後15年も源氏物語の地が存続しているんだと
今日改めて深く感じた読書会でした
これも明石神戸の地に古文を親しんでもらおうと
T先生が思いを深く実践して下さる証しかと実感いたします
人数も12人と以前より少し多く定着しはじめたのかと嬉しく思います
紅葉賀も式部の文章のすばらしさに胸打たれ
紫との心の触れ合いまた老女内侍との心の触れ合いが
とても美しくまた対照的といってもいいでしょうか
すばらしさが心に沁みました
平成22年4月17日(土) 「紅葉賀その2」
生頼民子
今日も楽しみに源氏仁会いにこさせていただきました
源氏と藤壺の子が生まれて の心の葛藤を
心豊かに学ばせていただきました
自分の分身である我が子の誕生という
人として最高のよろこびであるはずのことが
世の人には決して知られてはならない人との恋ということで
いろんな屈折した心の表現が
日本人としての心のひだの深さを感じました
今の世にも流れている心というものを興味深くかんじました
川上美津子
藤壺の嘆き(帝の子供ではない)や源氏仁対する思いが
今の時代に不義の子を授かった気持ちと通ずるのでは?と思います
水口しげみ
源氏がことばに出さす我が子と対面し
藤壺より返事が来ないと思っていたのに
袖ぬるる露のゆかりと思ふにもなほうとまれぬ大和撫子
の返事に涙が出る程うれしかった
この場面が心に残った
自分の安らぎを求め西の対に行き紫とのやりとりも楽しかった
本文が進むに連れいろいろと楽しい次の回を楽しみに.
酒井宜子
源氏と藤壺が愛しあって生まれた若宮は源氏に似て美しい幼子だった
でも二人とも心苦しいのです。その心の内を歌で取り交わせたのには感動しました
私の感じではふたtり共苦しいけどうれしい。愛があるからだと思います。
この感覚を大事に大切にしたいと思わせられました
竹花外記
前回は休み半年ぶりの勉強でしたので
非常に豊かな楽しい一日でした
桐壺帝と藤壺と源氏との、現代にも通じる心の動きが
とても感動的だった
古語を学べるのが嬉しい
X,Y
今日は紅葉賀の中頃藤壺が源氏の子を帝に披露する場面に
ハラハラドキドキ
源氏「よそへつつ見るに心はなぐさまで露けさまさる撫子の花」に対して
藤壺「袖ぬるる露のゆかりを思ふにもなほうとまれぬ大和撫子」の歌でかえす
歌が感動的で言いしれぬ思いである
古語を我がものにしなさいといわれるが古語に触れ一言では言い表せない
物語のすばらしさに感無量です
明石の場所で13人の仲間と学べたことがとても嬉しく次回が楽しみです
赤松勝子
源氏と藤壺が心が通じあったことが大変好かったです
又古文の面白さとかがよかったです
藤壺が子の誕生を喜べなかったのがひっしでよくわかりました
いつも心から笑わせられます
斉藤隆二
*天皇家にかかわるスキャンダルを扱っているにもかかわらず
不敬罪に問われるどころかもてはやされたことに
疑問を持っておりましたが解けました
*秋田の方言に「うたて」「いたまし」がありますが
平安のことばであることが面白かった
斉藤暁美
初めての読書会
素敵な空間に身を置き
先生の美しい(?)声に心地よく
うっとりと至福の時間をいただきました
紅葉賀からはじまりましたが
とても切なく涙が出る章でした
A、B
こんにちは、初めまして
皆さん、すごいですね
私は古語が読めません
でもみなさんがそれぞれ質問されて
それが面白くよくわかりました
平成22年1月22日、23日 「紅葉賀その1」
前川絹代
この度は紅葉賀へ入って、青海波の舞が中国から伝えられたものであること、日本文学、舞踏もそうであると改めて中国との関わりの深さを感じました。そして当時宮中では音楽や詩文と共に舞踏がとても重要視され(師匠を自宅に招いて学ぶ程)で出来具合によって身分の昇格があると知り驚きでした。今更ながら紫式部の観察力の鋭さが自然描写の中で生かされているのを感じます。植物の必要性、重要性また感受性など拾い上げればきりがありません。が大切な古文に触れ学べる幸せを感じた二日間でした。
この明石で行われている源氏の会がことに触れ、田中先生が震災当時から神戸明石の地に古文を吹き込んでくださったという原点に戻り、大切に存続させて行きたいと思っています。嬉しいことに突然でしたが明石ケーブルテレビのスタッフの方が授業風景を録画しに来てくださり一人ひとりにインタビューしてイメージで読む源氏物語をそれぞれが笑顔で語るのが新しい希望をいただいたようで15年間も続いている先生に感謝するとともに良いものを大切に守っていきたい意気込みを全員で感じた今回でした。
水口しげみ
新しい方々を迎えて改めて勉強に対する気持ちが良い意味で刺激されます
唯読んで先生の話を聞くのも大変でが、源氏物語の深い面白さを知ることが
大切なことです。自分はこの本に親しみが持ててうれしい。現代の不快な
ことをこの本を読む間は忘れることができて幸福な時間がもてます
川上美津子
源氏が若紫に心を奪われて過ごす日と葵の上との心の対比が違いすぎて
作者の気持ちの広さ、大きさが誰にでも分かる様です
今も昔も人間の心のあり様が変わらないものだとつくづく感じます
酒井宜子
光源氏の嘆き,嬉しさ、悲しみ、愛したくても愛せない苦しみを感じ本当に心から共感しました
葵の上の源氏(夫)に対する愛情は彼女の気持ちは複雑だとおもわれる。いろんな
ジレンマがあったと思う。夫を自分の方に向かわせたいが源氏は女性に優しくていろんな人に好かれる
私は葵の上に声援を送りたいです。葵の上がんばれと心で唱えています。
だんだん物語が佳境に入り次が楽しみです
赤松勝子
源氏が青海波を舞う姿を想像すると大変美しいなーと素朴ながら思いました
皆が「源氏」「源氏」というのがほんとうにわかりました
何だか、距離を置いていたのが身近に考えるようになりました
そしてミーハーみたいにファンになりました
源氏の会へ行くにつけ1月前には行く気がしなかったのが、いざ行ってみたら
心がスッーと晴れて、神様とか亡親亡兄弟が応援しているんだ、天が応援して
くれているんだと思われました
住野文子
今回も参加出来ましたことうれしく思います
年初めより腰痛が出ましてどうなるかと思いました。紅葉賀を勉強しました
正月にふさわしいところ、雅な正装とか紫の上のひな遊びなど宮中の様子をたのしませてもらいました
生頼民子
今回の紅葉賀は源氏の華やかな,青海波を舞う、うっとりするような場面を学ばせていただき
また源氏にほれぼれしました。
歯切れ野よい文章にイメージをふくらませ源氏に没頭している自分がうれしくなります
心がうきうきした二日間でした
大平浩子
学生時代より遠ざかっていた古文にたっぷり浸れた喜びと楽しさがありました
午前午後とやることで耳に古文が心地よくなってだんだん背景もイメージできるような
気持ちがしてきて、この時代から今に至るまで人間の根本的な心情の不変さに驚き
とても身近に感じられるようになりました。先生の読む源氏物語がすっと体にしみこむような
心地よさでした。
源氏を理解することで今までの自分の持っていたイメージが変わって魅了されそうです
斎藤隆二
今回から参加しました
源氏物語を現代語訳でさえ読んだことがありませんでしたが
楽しい雰囲気の中で物語のイメージが私なりに浮かんでくる素敵な会でした
片井久子
皆さまがたの雰囲気もっと早く知りたかったと思いました
午前参加しただけですが
源氏物語の世界にほんの少しだけは入ることができました
平成21年10月17,18日 「末摘花その2」
K,M
末摘花の物語はユニークな面白い巻と聞いていたが
このたびはさすがに静と動、表と裏、後継者がいるのといないのとのちがいなど
みごとにわかった
源氏は姫がものを知らなさすぎることもセンスがなないことも知りながら
何か良いところがあるのではないかと求めてやまないその心がとてもすばらしい
姫は人と比べることすらなくただ我が道を行く籠の鳥のようであるが宮家の娘としては?と
不思議な存在に思ったが、老女房たちの源氏の歌に対する批評をしると姫のすがたがよくわかった
紫式部の観察力の鋭さや描写がとても素晴らしく文章のなかに必ず希望を持たせるところがあって
現代人もこのような考え方を持ち続けたい
水口しげみ
末摘花、この姫の過ごしてこられた日々を思い巡らし、人それぞれに運命の出会いがあり
何の変わりもなく暮らしていたある日、源氏と命婦のふとしたことから会うことになり
人生が一変したというか、源氏が身分も教養もすべて理想なのに、決して自分とくらべたりしない
、誰と誰とじゃなく自然体で生きることの育ちのよさが伺えて楽しかった
現代では考えられないゆるやかな風のながれを感じ、
この二日間の時の流れを大切に今後とも心して源氏を読み続けたいと思う
酒井宜子
末摘花を読んで驚きの連続でした
高校時代に「末摘花」を演劇としてとりあげ主人公を演じましたが
昔を思い出して懐かしかったです。
末摘花は心優しい女性だと思います。光源氏も人間に対して優しいです
こんな楽しい「源氏物語」を書いた紫式部の「紫式部日記」を一度読みたいと思っています
今日の箇所では自然の描写でリアルで山、鳥、雪、霜など感動することが多かったです「松の雪のみ
あたたかげに降り積める」
竹花外記
源氏は女性を実に多面的に見ているのに驚いた
美しさ、経済力以外、それ以上に
内面のいとしさに心を留めている
このような男なら
現代でもさぞもてることだろうと納得した
「末摘花」のところで現代でも通じるおもしろさを感じた
生頼民子
末摘花の面白い何ともいえないところを
学ばせていただき
源氏物語の奥の深さを又心新たにいたしました
白氏文集という古い古典まで学んでいる
紫式部の教養の深さにも改めて感心いたしました
これからが楽しみです
住野文子
秋晴れのとってvも気持ちよい中
源氏に参加できてほんとうによかった
今日は末摘花を勉強しました
いろいろの女性が源氏物語には出てきますが
今日また帰って今日の学びを復習して一人で楽しみたいと思います
平成21年7月18,19日 「末摘花その1」
T,T
三ヶ月に一度、往復4時間をかけての勉強会ですが、とても楽しみな二日間です
筋を全く知らず、かえってハラハラワクワクの連続です
この頃、ようやく古語の美しさ、リズムのうるわしさを感ずるようになりました
孫たちには英語よりも日本の古典を、と思います
この時代に末摘花のような女性を生み出したことに驚きました
水口しげみ
末摘花に入り第一日目はとても楽しいお話で
短い文に少しずつ現代語と古語の違いをおそわり
この言葉は深い意味があると感じたりしました
日常にも大切な会話において
今は人と人を結ぶ表現が疎かになっていると思います
昔の物語でなく現代の私に勉強しなさいと言われているようです
原因があり結果がある、結論を急がず
登場人物の個性を楽しみに本文に入る楽しさを教えていただきました
第2日目だんだん面白くなり末摘花の登場で
源氏が一生懸命に姫を理解し努力するさまが良いことだと思いました
酒井宜子
末摘花は少し喜劇のようでおもしろかったです。
平安時だの恋のかけひきは何か優雅ですね
心理描写はものすごくよくわかります
ほんの千年前のことなのに今とあまり変わらない様子に
ほほえましさを感じました
またこの巻はミステリー性もあり
最後はどうなるかはらはらしました
私はこの末摘花は好ましい女性だと思いました
前川絹代
今回は人数が少なく心傷む会だったが
内容はとても意味深く楽しませてもらった
当時は身分社会ではあるが心が自由で
楽しい時代だったのだなあとかんじられた
(今は文をかわすのもメール等で古文から遠ざかり寂しいかぎりであろ)
その中で特に心に残ったのは、
頭中将がしのびで動く源氏を追って透き垣に隠れ様子をたのしんでいるさまや
中将が末摘花の妄想に耽るところ
源氏と中将がライバル意識をもちながら心を深めていく
また一つ車に乗って笛吹き合わせて大殿に帰る様子等
滑稽で美しく情愛を感じた
人と人との触れ合いの中で心を豊かにしてくれる
また古文は包んで物事を表現する故に今回も魅了された
今日の日本人ももっと古文に触れて心豊かになりたいものだ
赤松勝子
末摘花にはいって大変おもしろくなりました
宮中の裏の出来事や人間模様をおもしろくおかしく勉強できました
人生の大変おもしろいひとときwすごさせていただきました
中将と源氏の関係、命婦と源氏の関係がよくわかりました
三谷ナダ子
葵、六条など身分の高い女と
源氏の夢多く軽々しい忍び歩き
夕顔への思い深く夕顔のような女を求めて忍び歩く
末摘花の思いを寄せる
内裏より後をつけてきた頭中将
源氏と頭中将ちおの恋のかけひき
二人の間柄のおもしろさ
末摘花に送る文に二人とも返事はない
命婦と源氏の間柄と末摘花とのとりもち
この時代の男と女の恋のありかたのおもしろさを感じた
源氏はいままでにない経験をする
平成21年4月18,19日 「若紫最終章」
T,O
源氏物語の一番重大な場面で興味津々でした
紫の上の少女時代のあどけなさと源氏の熱の上げようが,紫式部の面白い筆運びでかかれている
読み進んでいくうちそれが心の中にゆったりと広がっていきます
家へ帰ってからも没頭する時間がほしいと思うのですが、一人で読むよりこうやって皆さんと一緒に先生を囲んで源氏の世界に入っていく時の方がぜいたくな時を過ごしております
次を楽しみにしております
H,S
前回に引き続き今回も若紫を十分に味わうことができました。10才の幼い若紫の美しさを、その若紫をとりまく人々の心の動き、源氏の心の動きをこれほど豊かに文章で表現されていることに言葉も何もなくため息ばかりで驚きと感嘆いっぱいです
今回も源氏の雅の世界にたっぷりと浸らせていただいたことを本当に感謝いたします
前川絹代
今回は若紫の終盤に入り若紫が源氏と出会う場面や
いろいろな立場の言葉を出せない思いを絡んだ巧みな
文章にも感動させられた。男女は7才にて席を同じく
せずと昔の人からよく聞いてましたが、源氏がいとも
簡単に若紫に触れるさまにも(立場がある人故)また
敏速さにも決して醜い感じはせず、文章からも美しさが
見えた、これが紫式部の素晴らしい文なのかと改めて
感じさせられた。若紫は無邪気な姫とのみ思ったが、
源氏の「ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の露分けわぶる
草のゆかりを」という,藤壺を重ねて恋しさを歌った歌に対して
姫は「かこつべき故を知らねばおぼつかないかなる草の
ゆかりなるらむ」と歌った。自分の思いをしっかりと
見つめている様にはびっくりした。その後の若紫の行方が楽しみ
である。
酒井宜子
若紫を読み終わり感動しました
源氏は10才の少女を見初め
心が離れられなくなりました
これは親を失った源氏と母のいない源氏との
すばらしい出会いでした。気持ちは純粋で
源氏も楽しそうで、少女も源氏に恥ずかしそう
だが頼っている。
平安時代における「源氏物語」では二人は
夫婦の契りを結んでいるとみるのです。現代とは
だいぶ違うロマンの世界です。
これからの少女の運命はどうなるのか
興味津々の思いです。
源氏物語は夢の溢れた物語と思います
これからどうなるのか待っています
水口しげみ
初めに見た少女に思いがつのり源氏は少女に再会する
この再会が意外の方向に進んでゆく所がとても楽しかった。
愛のためには一途に行動し周りが?然としている間に
事を運ぶ、この源氏が若紫に心を寄せる様子が一千年の時空
をこえて面白く味わえた。
この会の友達にも学ばせてもらっているが
一千年の時空を行ったり来たりできることは
なんといっても楽しい
赤松勝子
一方的な源氏が男らしいと思いました
藤壺への思いを断ち切ろうとする源氏が見えました
源氏の生い立ちが紫の上のそれとだぶって見えました
源氏の丸みのある性格が紫の上の素朴さとからみあって
よかったです
源氏物語をよんでいると映画のスクリーンを見る思いがします
三谷ナダ子
源氏の行動から紫の上に寄せる思いの深さを探ることができる
藤壺に対する思いの深さ、心の動き、
それからまつわる周囲の人々の絡み合い、お互いに深いそれぞれの思いの
からみあい、
今回は今までの中で一番こうした心理のはかり方が面白かった
近代の恋愛小説にないすぐれたものと聞き私も物語の美しさに惹かれている
T、T
三ヶ月に一度平安時代の雅の世界に遊べることをとても
心豊かに感じます
時々現代と混乱してしまうことがあります
なによりもこの会の皆様のすばらしさに支えられて
続けていけそうです
平成21年1月17、18日 「若紫その3」
三谷ナダ子
今回は古語の上流貴族の会話が多くまた心の動きなどがよく書かれていて、
大変難しかったが、また古語の魅力にとりつかれた感じがありました。
若紫の生い立ち、育つ仲での生き方が源氏との関わりによってどう変化していくのか楽しみの一つです
赤松勝子
藤壺との密会は緊張感を感じ、簡素な文章のうちにすばらしさを思いました。また
紫上と尼君とのはかない関係を思い思わず涙しました。
紫の上を思う源氏の一途さ、エネルギッシュな行動力に私にもと思いました
紫の上の素朴さにはえもいわれぬ心洗われる思いでした
酒井宜子
若紫の物語もいよいよ佳境に入りました。
いろいろな思惑があり、人間関係も現代に充分通じる状況です。
源氏の苦しみ、悲しみ、驚き、喜び、相手に対する対処の仕方は現在21世紀に生きる私にも
理解できてとても楽しい物語です。イギリス人によって翻訳された源氏が世界に広がっています。
千年後の私を楽しませてくれて、紫式部さんありがとうと言いたいです。
次のお話が楽しみです。イメージで読んでいるのではっきりと理解できます。
水口しげみ
源氏の中でも大切な場面と聞いていたのに、私の読む場面ですらすら読めなくて
先生の解説を聞いて、こんな美しい文章をなぜ表現力がない読み方で読んでしまったのだろうt
大変反省しました。
読んだ、理解した、その時代を楽しく心に描いてただ読むだけでは深い文章の奥が見えないのだ
K,M
紫の上に出会ったとき幼いのに源氏が心惹かれるわけですが、藤壺と若紫が<根に通ひける>間柄があったのもなるほどと思う
K,T
古文の深さ、すばらしさの入り口に立ったきがします。ひとりで読んでいると文字の解釈のみになりますが、先生のお話で雰囲気までも浮かび上がってきます。楽しい二日間でした
平成20年9月13,14日 「若紫その2」
住野文子
二日間たっぷりと学びました。まだ若紫は半分以上残っていますが今回もゆっくりとわかりやすく進めました。本当に毎回思いますけど、現代に生きる私たちとも違和感も少なく楽しんで居ます。幽玄の世界に入ってとてもよかったです。若紫の成長が楽しみです。
生頼民子
今回初めて、二日間、源氏の君とゆっくりと対面でき、とても幸せな気分です
若紫、まだ10才の少女であるが藤壺によく似ていたことから、源氏の心に恋の火が点る。
まだ18才の若い源氏の若さゆえの言動にも人間味を感じ、源氏の心に寄り添っていきたい気分になりました。
そしていつも感じる事です、歌(和歌)で語りかけられれば歌で返す(返歌)礼儀があるわけですが、人物像の盛り上がりが歌でよくわかるのです。その歌はすべて作者の筆によるものであることが、式部が世界的な天才であることを物語り、ますます紫式部のファンになりました
酒井宜子
若紫の前半が終わりこれから若紫の成長が楽しみになりました。この姫君は「虫めずる姫君」にでてくるような動物好きの10才の少女。平安時代にもこのような型破りの女性がいたことは私にとって興味の対象になりました。この先未来に向かって源氏との関係はどう発展してゆくのかワクワクしているところです。
現代の私たちは超近代的な時代ですが、平安時代も宗教と生活が交差しておもしろい時代だったとよくわかりました。
何か「知りたい」という希望に溢れてきました。次に期待して若紫の人生にたkyしていきます。
前川絹代
久しぶりにの源氏の読書会、忙しすぎて以前のものがたりはすでに忘れていましたが、原文を先生の説明入りで聞き入っている内、源氏は瘧病の身でありながら出会う人美しい姫を目にするが、素性もわかり、うれしさ余りめとりたいと申し出るなかで、世間の常識と戦わねばならない様子がとてもわかりやすく、今の世も変わらぬ内容もあると思った。
源氏の心の動きが素晴らしく、和歌の美しさが心を深めてくれた。特に心に残った歌は「吹きまよふ深山おろしに夢さめて涙もよほす瀧の音かな」で、源氏の心がはっきり出ていると思う。今後の源氏や若紫のさまざまが楽しみ
赤松勝子
若紫が走ってくる姿に惹かれる源氏は本当に感性の優れた人だと思いました。若紫の将来の姿が見えてぜひ妻にと思う心は若くて素直で混じりっ気がなくてまた若紫が源氏に応えていくのは「源氏物語」の魅力となっていると思います。
世間の荒波にもまれて源氏が意志を通していく姿は読者の心を引くものがあります。又和歌が素晴らしくその人となりが表れてなお一層源氏物語がおもしろく思われます。又平安時代当時の様子がうかがわれ歴史の勉強となります
若紫は明石の上とも違い、自然児としておおらかで素朴で源氏をひきこませるにふさわしい人物となっていますが、私も小さい時は自然とよく遊びましたので、若紫がよくわかります。源氏を慕う若紫が今後楽しみです
水口しげみ
源氏は体調が悪く北山に加持祈祷のきく聖がいると知らされ山に行く。宮中に呼んだが断られたのである。このとき一夜旅寝することになり、小柴垣に少女と出会うことになる。修行に籠もっていた僧都と出会い、その人に自分の思いを一気に話してしまった、清々しいが恥ずかしいと思うところが若い。
若紫が山吹色のなれた着物をきて走り来る姿が目に残り、この場面が心に残った。
再度の出会いがあり、若紫は源氏が山を去る姿に目を止め、その気持ちを少女らしい表現で語る場面が今回心に残った
三谷ナダ子
若紫の現れ方が自然であどけない様子がかわいいが、、源氏の少女を見る目は純粋だったのだろうか僧都、尼君に理解されないままの出来事は私自身文章が理解できないまま、もう少し読み込みたいです
平成20年6月21,22日 「夕顔その4と若紫その1」
前川絹代
夕顔に対する源氏の思いの深さに驚く。3、4ヶ月間の交流だけなのに体を壊してしまうほど人を愛せるなんて現代人にはどれだけいるだろう。しかし和歌で表される源氏の心情や名前も素姓も表現しないで願文を読んだ文章博士の理解の鋭さにびっくり、今では理解しにくい。「われにもあらず、あらぬ世によみがえりたるやうに、しばしば覚えたまふ」自分が自分でない錯覚、別世界に生き返った様な、夕顔のことのみ夢中で深まっていく心情は私にはなかなか思い知れないがとても神秘的で不思議である源氏は一喜一憂する中にも倫理的豊かさが溢れている。
生頼民子
いつもの事ながら紫式部の見識の深さ、登場人物の面白さに感激です。空蝉の心情は今の世の中の女心に通じるものがあり面白い。夕顔との間にこんなにも恋愛感情が深まり、後々までに心の財産となる出会いがあるのだという事に驚きです。でも二人とも(源氏も夕顔も)若い青春時代だから純粋に思えるのかも。それにしても源氏の君から(男性から)愛されてみたい心境になりました。
水口しげみ
最初に夕顔が登場したときとても思わせぶりと思いましたが、この度の読書会で人にはそれぞれに背中に背負っているものがあることをしりました、人に対する気配り思いやりが、当の本人が意識しなくてする動作が読者に心よいやすらぎを授けられるのでますます源氏に深く
心が残りました。
夕顔と空蝉と人柄地位の違いが先生のはなしで少し理解ができました。千年の昔の物語なのに全体を見ても今の人にこの美しい心のゆとりがあればテレビ報道の様な事はおこらない?
空蝉像に心と体が別の様にそこはかとなく女心が出ているのが何ともことばに表せない、軒端の荻との対照的な女性の表現も楽しくよませて頂きました
酒井宜子
源氏と頭の中将と夕顔の関係はいわゆる現代でいえば三角関係ですが、源氏の優しさに救われた思いになりました。頭の中将と源氏の友情はすばらしいと感じます。夕顔の死は悲しかった。
住野文子
夕顔の巻はたった3ヶ月であることは驚きです。頭中将と源氏が同じ夕顔を好きになったけどそれぞれに同じ夕顔に対する思いは違うということが不思議です。しかし夕顔の巻は楽しかった
赤松勝子
夕顔が面白いときいていたが本当にそうだと思いました。私とは正反対のような気がしましたが繊細でこわれやすくそれは私と似ていますが、源氏の心を深く揺り動かし女冥利につきるとおもいました。右近の側からの夕顔像、源氏の側の夕顔像がよくわかりました。また源氏が元気になったきっかけが帝のことを思ってなのはすごいことで、大層勉強になりました。空蝉の女心が面白かった。
川上美津子
空蝉の源氏に対する思いが袖(小袿)が朽ち果てることになってしまった事に、空蝉も割り切れない思いだっただろうに、その気持に自分も持っていかざるをえない空蝉の気持…。
三谷ナダ子
源氏の夕顔への思いの深さは身分制度のきびしい中で帝の子ということもわきまえない自由な
思いのなかでおこった悲恋である。夕顔の五条での暮らしに移るまでの悲しみとつらさは現代の女性ではおよそ察することができないだろう?源氏は夕顔の過去を知ることで一層悲しみと苦しみを味わったであろう。源氏が撫子を養育して遣ろうと申し出たり右近の行く先を考えてやる思いやりは現代男性にはない優しさではないだろうか(福祉の心を持つ優しい男)
平成20年3月8、9日 「夕顔その3」
前川絹代
夕顔の物語の急展開には驚く。たった2日間の出来事に一生を過したような場面であった
あまりにも表と裏、陰と陽を露にした場面があるように思う。
しかしまだ若く身分の高い人であるのに一喜一憂する場面でもすばらしく対応していく源氏の
姿が巧みに詳細に書き表されているのも心がみたされます
原文の一字一句がとても美しく人を大切にする情熱が素晴らしい。
古文の深い意味をもっともとめていきたい
川上美津子
源氏が心弱くなり落ち込めば惟光が助け、良く気が回りまたその逆もありで、人の強さ弱さ
を分かりあえる所が誰にもあるものですね。霊がこの世にあると信じられる様な場面でした
生頼民子
若い源氏の恋にドキドキでした。のめり込みもっともっと知りたい
雰囲気を味わいたいと思いました
上むしろの意味が分かった事でことばの持つ意味によって
心のふくらみがずいぶんちがうことに気付きました
図説を繰りながら(調べながら)読ませていただく
だんだん深く分からさせていただきました
赤松勝子
小津安二郎の世界を感じました
夕顔のすばらしさ、悲しければ悲しいほど光源氏の成長を思います
夕顔はなぜ死んだのか、やさしさゆえに物の怪に合いかわいそうでなりません
源氏の情熱を深く感じ夕顔は成仏するんだなと思いました
酒井宜子
源氏の身分の高さが分かりその不自由さを思いやると、
何か源氏がかわいそうに思えました
夕顔の死の場面は私にとって臨場感あふれる思いでうけとめられ
源氏の悲しみをイメージとして頭の中に浮かべることができました
一千年前にできた源氏物語ですが、登場人物の性格、現代に通じる精神心根は
今よりすばらしく地球生成から考えるとたったの?年なのです
ある宗教学者の話によると源氏物語は「もののあはれ」ではなく
平安文化と呼べるものですといわれ同感です
三谷ナダ子
夕顔の死から…源氏の心の動きと夕顔を思う右近に対しての思いやりなど
現代のことばでは表現できない古語の美しさ、ことばの使い方など表現の中で
空想の社会を見ることができることのすばらしさなど…源氏がいかに夕顔を愛したか…。
源氏物語の古文に出会ったことの喜びをかんじました
紫式部のすばらしさもまた感じました
水口しげみ
身分の高い源氏が一人の男性としてただふと出会った夕顔と、一生に一度と言っても過言で
ない美しく心に残る恋をし、時を忘れ…その二人の最高に幸福なわずかな時に、思いもかけぬ
怪しい出来事がおこり自分を律することもできずにいる
惟光に手引きされ夕顔に会って自分でなにも考えられぬ心理状態を素直に惟光に従う他なし
さりながら惟光の世間の広さ手配りのよさが源氏を助する
人は一人では生きていけない…
今もむかしも同じと思います
平成19年11月24、25日 「夕顔その2」
酒井宜子
「夕顔」は有名なので聞いたことはありますが何も知らない私は興味津々でした。先生の熱意ある話にききほれました。夕顔の素直さ、恥じらいおおらかさに感動しました。私も夕顔のようなしぐさ、態度を見習って生きたいです。平安時代の人間関係は複雑ですが、人間の歴史
の中で”人間とは何者?”男と女の関係”について私は興味があるのでこれからの夕顔の行末
をよんでいくのが楽しみです
ケイちゃん
夕顔のこの先を暗示しているような……。源氏にとって純な心になれる女性だったのでしょうか。昔も今も人間の性(さが)は変わりなくあるものですね
水口しげみ
思わせ振りに登場してきた女、しかるに若き源氏の心を取り乱す程捉える、余りにも自分を出さないで、これほど源氏の心を自分に向けさせるその人柄、女性として自然に振舞って人の心を動かす美しさ、素直さ是非見習いたい、この先の展開が楽しみ。
三谷ナダ子
夕顔との出会いによって、源氏の成長に迷いを持ちながら、恋の道には長けるのではないか?
いにしへもかくやは人の惑ひけむわがまだ知らぬしののめの道
住野文子
今年も源氏に触れる事ができてありがとうございました。おかげさまです。源氏によってさらに日本の文化、ことば現在話題になっている日本の品格というものを新ためて感じさせていただいてます。今回は夕顔の巻でした。けれど先生の説明を受けるのを家にもって帰って充分に自分なりに復習したいと思います。充実した時間を本当にありがとうございました
平成19年9月1、2日 「帚木その5」「夕顔」講読会感想
三谷ナダ子
古語のおもしろさにひかれて理解できないまま読み、イメージをふくらませている。
源氏の人間性を見るたのしみあり。今の若い人達に是非興味を持ってほしいと思います。
平安時代の恋のかたちも今の恋のかたちも変わらないと思うが深みのある恋のかたちを今の人
も知ってほしい。
赤松勝子
今回は「イメージで読む源氏物語」を読んで参加したので大変おもしろく授業を受けられました。源氏が17才の時のことであり、私が17才の時と比べると何と人間ができていることかと思いました。源氏は一時一時を真剣に生き、何とすばらしい人かと思いました。これも天皇の子であり上の品の人だからと思い、お母さんやお祖母さんの人となりがすばらしいからだと思いました
酒井宜子
源氏を原文で読む会に参加させて頂いて早や1年半になりました。だんだんおもしろくなり、興味が増してきました。
源氏の品格と優しさ、男らしさに憧れを抱いています。いよいよ夕顔にはいりました。文のプロットもミステリー調でわくわくしています。
平安朝のきらびやかな世界は今の時代と大変異ると思いきや、人間の(男女の)世界、心持ちはいつの時代も変わらぬ、通じる事があるものと思います。
源氏の様に誰にも心優しくできる男性がおこがれの的です
今回空蝉と夕顔の始まりの学習をしました。いつも予習を少しでもしていたらもっと充実していたと思いますが、でもとっても楽しく充実二日間だったと思います。
,
平成19年5月18,19日 「帚木その4」講読会感想
三谷ナダ子
源氏の育った歴史の中で純な生き様がそのまま恋心を一途なものにしているのかな。空蝉のかたくななまでの心の動き、小君の幼いなりの心の動き等、恋に対しては昔も今もかわらないのではないか。この時代に生きてみたいとも思った。今回大変面白く思わず吹き出しそうになり思い出し笑いしそうな場面があった。
水口しげみ
源氏がはじめて知った恋の苦しさ、自分の心の有りのままを小君にぶつける所が面白かった。若い源氏が人妻に心ひかれ、その若妻の源氏にひかれる心はさすがに理解しがたい所であった。講師の話がなければわからない、それがひとつひとつ自分の中で楽しく源氏を読めます
赤松勝子
源氏の好みがわかってなるほどと思った。17才の源氏がてこずって恋をしているのが面白かった。また小君の機転の良さに感心した。源氏物語が世にでてそれに似た恋の仕方を当時の人はしたのだろうか疑問に思った。
住野文子
平安時代の女性の十二単、長い髪の優美さとまたやはりそれにつれての行動の自由のなさは男性社会の反映だと思い、現代に生を受けた私、女性としてよかったと思います
酒井宜子
源氏の女性な対する真摯な態度に感激した。また平安時代の女性の中にも慎ましやかな空蝉のような女性がいることに感動、時間の経つのも忘れて講師の話に聞き惚れてしまった。伝えたいという熱心さにも感動した。
八木桂子
空蝉は楽しみにしていた人、読みながらへえ〜と言いながら楽しく時間が過ぎました
平成19年2月10、11日 「帚木その3」講読会感想
住野文子
2日間たっぷりと源氏に取り組めた事、掛け替えのない時間を与えて頂きました事、とっても嬉しかった。
今回も前回に続いて「空蝉」を学びました。女の品定めという事ですが、生まれ育ちによって品の良い人、そうでない人色々な表現で表されていましたが、今の世も少しも違和感なく楽しかった。
次回も「空蝉」を勉強しますが楽しみにしています。
酒井宜子
源氏の君も結婚して、いろいろ人間関係も広がり、美しい姫君に会ったりしていよいよ楽しい展開になってきました。
21世紀に生きている私が8世紀の時代背景の物語を読みながら、あの時代の風俗習慣を学ぶのも、
とてもおもしろく興味あることで、゛方違へ゛という陰陽道の方角の災いの考え方はおもしろく、
現在も今年の゛恵方゛として残っているように思います。゛空蝉゛はほんとうに好きになりました。゛雅゛な世界をイメージしました。
私もこんな風雅な世界を生きてみたいです。
前川絹代
今回とても少人数でしたが私にとって一番充実した講読会でした。前回の「常夏の女」も印象でしたが、
「蒜食ひの女」の登場より殿上人と地下人の違い・漢語と大和語の違い(使い方でどれだけイメージが異なるか)など
゛ささがにの振舞しるき夕暮れにひるま過ぐせと言うがあやなき゛の歌などから大和言葉の美しさ、
自然と融合して日本の文化が構成されているのをうかがい知れた。
空蝉が身分の高い娘に生まれながら、父を亡くした立場ゆえ身分の低いさらに弟君を連れての後妻に入る厳しさなど
いつの時代も親の存在の尊さを思うとき、空蝉の心の動揺はさることながら人知れぬ・人柄・心の深さを感じます。
先生の解説は時代を超えて当時の知らない世界に引き込まれる気分にもなります。
紫式部の文章の素晴らしさ巧みさにのにほかなりませんが・今回も今現在自然から外れた乱れる事件が多い中で
人として日本人として恥かしくないような心で歩みたい、そして源氏物語の原文のすばらしさに酔いしれた2日間でした。
平成18年11月19、20日 「帚木」その2講読会感想
<水口しげみ>
おおくの女性の態度が一人一人違う、その違いがわかりやすく表現されていて楽しかった。口に出して言う人、言わずに尽くす人、そっと姿を消す人とそれぞれに人が人を愛す愛し方が違って、うん…。
<酒井宜子>
男たちの女定めにはびっくりしました。時代を越えて普遍的な男女の関係は今も面々と続いていることを実感しました。さてわたしはどのタイプの女でしょうか。じっくりこれからの余生で考えてみることにしましよう。一夫多妻制のもとではどんな感じの夫婦生活になるのでしょう、一夫一婦制の元での私達には想像もつかないですが。
源氏をイメージで原文で読み始めてから一年になりようやく端緒についたと感じ、面白さ意味深いことがわかり始めました。
<石谷洋子>
平安時代にもこんな色々なタイプの女の人がいたとは面白かった。辛抱強い人がほとんどだった。「常夏の女」の話で当時は北の方以外に女の人(恋人)がいるのは当たり前だから嫉妬なんかしないと思っていたのに北の方から他の人を通して恋人にいやなことをいってきたのは思いのほかだった
<川上美津子>
いつの時代も才色兼備の女性のみでなく平凡な無能な女性も男性にひかすものがあるのですね。「常夏の女」で男性に重荷にならずに身を引く女性はある意味男性にとって痴れ者なのでしょうか。
大昔も今に通じる人間関係は同じなのだなあ。
<生頼民子>
平安時代の男のひとの自分よがりの考え方が今の世の中にも通じるものがあり面白い。原文で読ませていただいて何度も読んでいるうちそして解説していただいて常夏の女のすばらしさが浮き上がってきました。先が楽しみです。
もっと時間があれば…と思います。のめり込んで面白くなってきた時に時間切れ…心を残して帰ります。
平成18年9月2、3日 「帚木」その1 講読会感想
<赤松勝子>
源氏の恋の遍歴の原点がここにあると思いました。
自分はなにも出来ていないし[こんな女はいやだ」と思う部類にあてはまると思うと、こんなんではいけないという思いにならせてくれました。今も昔も変わらなく源氏の御母さんが苦労に苦労を重ねた人生だっただけに源氏の女性に対する見方が大変であり才能があるだけにとても今後が楽しみです
<三谷ナダ子>
古語のむずかしさを改めて知りました。源氏のキミ12才より17才までの生きざまを何となく感じることは出来る、が上達部の女の見方から始め、左の馬の頭のきびしい女の品定めなど自分の一部を見るようでした
<酒井宜子>
千年前に創られた源氏物語、とてもリアルに人物描写されていて性格的にも面白い人物に興味津々となりました。源氏と頭の中将の人間関係が微妙で、現代の人間関係にも当てはまっていると感じられました。理想として、源氏と頭の中将の関係のような親友がほしいなあと考えて、何か希望が出てきました。
参加して3回目ですが源氏の世界にのめりこんでしまいました。次回が楽しみです。
<石谷洋子>
源氏物語にこういう話があったということは知らなかったので、よい機会に参加できたとうれしく思います。桐壷の巻から参加できていたらもっと良かったのにと残念です。
<箆 さん>
この二日間の勉強で自分自身にあてはまることはよくあります。これからの生き方、男性(主人)との上手な付きあい方、接する方法などを見つけていきたいと思っております。特にお姉様方のお話はよい勉強になります。
平成18年6月16日,17日 「桐壷」(後半)講読会感想
<赤松勝子>
源氏は母更衣をあまり知らないが祖母に育てられたことがよかったと思います
帝の父親ぶりがほほえましく本当に桐壷更衣を愛したがゆえに、源氏がかわいいのだなと思いました。また弘徽殿の性格がよく表れて源氏をかわいがるところはあー女だなあと思いました。藤壷と源氏の出会いは、ただ今の恋愛物語が安っぽく感じられるほどどきどきとしました。葵の上との政略結婚が源氏の不幸の始まりだったことはここでよくわかりました。
<水口しげみ>
帝の更衣に対する気持が少し忘れかけたところに更衣に似た美しい藤壷に会い、源氏と共に人柄にひかれてゆく。人との出会いは神のみぞ知る、自らの人生にこれほど大きな影響を与える出会いは無いと思う。親ばかと見えるが源氏の将来の先先まで考えて妃を選んでいるところ、この物語の登場人物が500人あまりと言われていることに初めは理解できなかったが、先生の指導で桐壷を読みこの物語の深い人と人との絆がどんなに大切なものであるか、そして原因があり結果があるということがわかり、現代にも通じると思い現実でも大切に勉強させて頂きます。
<酒井宜子>
源氏の君の母上の素晴らしく美しい姿、声、優しい気持ちは立派な帝の心をとらえて放さない。式部の筆遣いを通してリアルに伝わってきました。素晴らしい恋愛小説じゃないかなあと感じました。これもひとえに式部の息づかいが伝わる原文に依ると思いました。
本当に感動して、体が熱くなり、ほかほかしてしあわせな気持ちにならせていただきました。まだ始まったばかり(桐壺が終わって)なので「帚木」はどう展開するのか、とても楽しみにしています。初めて「源氏物語」を読んで引き付けられたのは紫式部の力量ではないかと感じました。
<西中満寿子>
原文の良さを改めて知りました。
光源氏の育ってきた環境を詳しく知ることによって物語の深みが増したように思います。藤壺への思慕は母親への思慕が出発点かと思っていましたがそうではないことを原文を読むことでわかりました。「すゑて」おけない人だからなお恋心をつのらせ、その思いは年月を経てなお強く屈折していったのでしょうか。
<三谷ナダ子>
原文で読む源氏物語の「桐壺」を終えて改めて物語の原点を知りました。
光源氏の生きざまを、様子を新しい視点で読み続けてみたいと思いました。古文ゆえの奥深さを感じ、今まで読み終えた物語の感じとどのように受け取れるか楽しみです。
帝の親として子に対する思いは身分も時代も超えたものがあり、桐壺の更衣への思いの深さがあったと思いました。こども、こどもと思って育んだ父帝のあまやかしたいきざまが光源氏の生育歴となっているんではないか。元服ひ対しての父帝と左大臣との歌のやりとりなど講師の説明に感動しました。
<水田知子>
いろんな人がいっぱい本を出しているが原文を勉強したのは初めてでうれしいひとときでした。源氏物語は色んな人がそれぞれの思い入れで書いているけれど、帝、源氏のこころ内を解いてくれたことに感激しました。次の会までにもう一度読み返そうと思います。集まっている方がたとのお話も楽しく初めて輪の中に入れてもらったと思えない程うちとけることができました。学生時代に戻ったような気分のいい時間でした。“因果応報”と強く思ったことが心に残っています。
住野文子
昨日は家の都合で参加できませんでした。が今日は一日ゆっくりと勉強できました。桐壺の巻も終わりました、今度は帚木に入りますが、もう一度テープと桐壺を復習して源氏を味わいたいと思います。本当に心も体もリラックスして楽しいひとときを頂いて有難うございました。
<前川絹代>
桐壷を学ぶことによって源氏の幼少時代の生い立ち、祖母に育てられた心の深さ等がやっとわかり、以前の途中から源氏を学んだ時より源氏のとらえかたが随分変わったと思う。
人間どんなに優れた人も一人では生きてゆけない。いかに人を求めて(和して)分を弁え、自分を律して生きていくかが問われる。(帝の源氏に対する親の情愛によく表れている)原文で学ぶことは現代文では読むことが出来ないほど深みを感じ、また短い文章の中にも(和歌を通して上下の隔てもなしに心ゆくまで語れること等)とても素晴らしく巧みな紫式部の神髄を測り知ることはできませんが、今も尚後世に受け継がれている古文の大切さをもっと知りたく源氏がどう歩んでいくか今後が楽しみです
平成18年2月17日、18日 「桐壷」(前半)講読会感想
<生頼民子>
この度源氏物語の最初から学習できるというのでとても楽しみにしておりました。源氏誕生のことがよくわかり、わくわくする気持で読みすすみました。
簡潔でリズム感のある文章の中に、現代語に訳してしまえば味わえない深い心の世界があること、心豊かな学びに没頭してしまいます。
紫式部の教養のすごさに驚きです。人の心をくぐった自然のとらえかたなど、今の文学では味わうことのできない美しい世界を堪能して心が豊かになった思いです。
平安時代という千年も昔に、こんなにも一人一人の登場人物に生き生きと命を吹き込んで小説をかくことができる人がいたということは日本人としての誇りだと思います。
<住野文子>
又新しく源氏について学ぶことができて感謝です
今日から桐壷の巻が始まりました、今回は半分ですがこれからだと思って
楽しみにしています。とっても楽しい時を過ごせました
<赤松勝子>
桐壷の更衣がすてきな方で、若くしてなくなったことが惜しまれて、
しかもそねみねたみがはげしくて、といったことがよくわかり
源氏物語がすばらしいとされていることがよくわかりました
わたしも母や父の愛情があって育ったと思うと感無量です
紫式部の文才にも感嘆しました
<水口しげみ>
桐壷を勉強して源氏の原点に触れたように思いました
身分の上下があっても人が人を愛すること、自分を自然に表現し
相手の心を素直に理解することで、いづれの日にかその日を迎えたときに
物語の帝と更衣のようになれればこの世に両親から授かった命を全うすることに
なるのではないかということを学びました
<酒井宜子>
20年間、源氏物語を読みたい、それも原文でと願っていたら、突然新聞広告で知り、チャンスに飛びついて、つかまえました。
2日間たっぷり源氏物語の世界にひたることができました。やっと光明の世界(至福の世界)
に入れたことを本当に感謝したいです。
物語も平安時代なのに、現在の私達ににも通じていて驚きました。
「物語の世界に遊ぶ」ということがありますが、このイメージをイマジネーションすることができて幸せな時間の二日間でした。次の機会が待ち遠しいです
<三谷ナダ子>
現代風に書かれたものは目を通しました。しかしこの二日間で、全く知らない源氏物語を知ったように思います。古文、文学的歴史を初めて知ったと思います。
私自身戦中の教育でしたので本格的国語教育を受けていないので自己的な物好きで本をきました。あらためて物語を知りたいと思いました。これからが楽しみです
平成17年8月27日、28日 [薄雲](前半)講読会感想
<赤松勝子>
明石の上と明石の姫君の別れの場面が本当に涙でした。姫君のあどけなさ
が古語によって表され、思わず心打つものがありました。
3歳とは一番かわいいさかりであるのに、母明石の上に乗りたまえと言ってあどけなく、源氏ににているなと思いました。又明石上に対する源氏の心情を感じるとともに、男である源氏と女である明石上との違いが和歌によって表され、紫式部のすごさがわかりました。また紫上の子供に対する思い入れが感じられました。
<石谷洋子>
源氏の時代とはいえ明石上のような女性が多くいたのだろうか。自分のかんがえはほとんどなく、まわりの人のいいなりになっているだけの人にみえる。いろいろなタイプの女性が書かれているが、明石上のような女性になりたくない。現在の女性のことだけを考えての感想だが少し前まではこのような女性も沢山いたのだろう
<住野文子>
薄雲で明石の姫君が母親と離れて暮らすようになっても子供の無邪気さを失わず、読者としては安心だ。明石の上の心情は複雑ながら、源氏が再び訪れてくれたとき、誘われて共に琵琶を弾くところが心なごんで良かった。
<水口しげみ>
「冬になりゆくままに、川づらのすまひ、いとど、心細さまさりてうはの空なる心地のみしつつ、明かし暮らすを、なほかくてはえ過ぐさじ、かのちかきところに、思ひ立ちね、袴着のことなども、人知れぬさまならず、しなさむとまめやかに語らひ給ふ」
源氏の深い心を理解し姫君の将来を託そうという明石上の決心は自分一人ではなく尼君の一言もあり決断させた。千々に乱れる明石上の様子が表現されている。姫君を迎える方は調度も姫君の合わせ小さく整えられ「はなやかに、けはい異なるが」姫君は「泣ききもせず」「やうやう、見めぐらして、母君の見えぬを求めて、らうたげに、うちひそみたまへば、乳母めしいでて、なぐさめまぎらはし聞こえ給ふ」
袴着の儀も母の心とは別に先へ先へと進む
平成17年5月7日、8日 購読会 「松風」
<戸田京子>
明石入道夫婦が常より願っていた都での暮らしが孫娘、明石姫の出生によって思いもかけず源氏に京に上ることをすすめられ娘明石上が京で住むことになって夢が現実となった喜びはいかばかりかと思います。しかし明石姫を連れて京に上ることは入道夫婦の永遠の別れともなり、人生なにもかもが良いことばかりにならない辛さ、悲しさが痛切に感じられる。
源氏のはからいで親子3人ひそかに明石を後にして京の大井邸に向かう。大井邸では源氏に細やかな心遣いをしてもらっての日々の暮らしに、尼君も明石もしあわせになってほんとに明石をでたかいがあったと思います。また姫が源氏に可愛がられている様子に何かほっとする思いがします
<住野文子>
松風に入ってやっと源氏の世界が見えてきたように思います。それまでも古典に親しむというだけで心楽しい思いはしていたけれど、より楽しくなってきたので良かったと思います。今度は少し下読みでもして時間をふくらませたいと思います。
<石谷洋子>
久しぶりに出席させていただいた源氏物語の購読会。諸々の事を忘れ、源氏の世界に浸れた一日、再び高校時代にもどったような 楽しい時間でした。時間の経つのがすごく早かった一日です
<生頼民子>
「源氏物語の勉強会に入りませんか」とお誘いを受けた時、「うれしい」と思いました。一度は原文で読んでみたいと思っていたのです。まだまだ忙しい身で没頭することが出来なくて御迷惑をおかけするとおもいますが、とても楽しみにしております。源氏の登場する場面に心を奪われながら、その心の暖かさ、広さ、たくみさに驚きながら、千年以上も前にこの文章がかかれたのだと思うと、日本文学の偉大さ、その文化を受け継いできた私達(日本人)ということに誇りを持って生きたいと思いました。
またこの度は「松風」で明石上のこと、姫君のことが書かれていて、源氏との心のやりとりに面白みを感じました
<前川絹代>
入道が孫娘を上洛させたい一心で大井邸もきずき、巧みにあのてこのてと思い巡らし夢が実現化する中で、若君にも会えない、孫を見られなくなる辛さ、その多感な思いや、娘と別れる日の入道は
(心すみはつまじく、あくがれながめゐたり。)と、霧が立ち込めて船が遠ざかるにつれて魂の抜け殻のようにボッートしている様子など又母君も、見捨てがたき浜のさまを(または、えにしも歸らじかし)と、寄する浪に添えて袖ぬれがちなり。
入道と明石で最後まで暮らすはずだったけど、、、子や夫に対する心情や感傷的で親としての複雑な思いがよくわかり
相変わらずの入道の面白さが印象に残った。
明石の上
故郷の見し世の伴を戀ひわびて、さえづることを誰か分くらむ
明石の君のいつまでもしたたかな又控えめな謙遜した心の持ち主に源氏は惹かれるのかなとも思い
今回は明石の巻きにつづきとても印象に残る箇所が多く いろいろ登場人物の面白さが出ていて楽しかった。
明石の上が紫の上に姫を預ける(物思はしからぬ)のどうして嘆かずには入られるかの複雑な思いもよくわかり
これからがますます面白くなっていく気がし楽しみです。
平成16年11月27日、28日 読書会 「絵合」
<赤松勝子>
桐壺帝の源氏に対する教育がよかった。
梅壺に対する朱雀院の思いの強さが印象に残った。
絵合せの内の紫式部のへきりんが見えたので、
紫式部はすごいと思った。
<水口しげみ>
源氏物語に出会って本当に登場人物の多さとそれぞれの個性の表現がまた楽しい。この度の絵合わせは雅の時代のこととはいえ、対比が面白くその中でも競う事の妙味が表現されている。私が気に入った一節は「才学といふもの世にいと重くするものなればにやあらん、いたう進みぬる人の命さいはひと並びぬるは、いと難きものになむ、品高く生まれさらでも人に劣るまじき程にて、あながちに、この道な深く習ひそ」ーー色々なことに勝れてなくても品高く生まれさらでも人に劣るまじき有りのままで充分なのよと自信を持たせる、その人にしかない良さを見出しなさい、それが貴方です。
誰にも苦手とか弱い所があると思うが迷いがあったとき適切な助言をしてくれる人がいるということが何よりしあわせでしよう。この物語は現代の人々にも多くの助言をしていると思う
平成16年7月3日、4日読書会 「蓬生」(後半)と「関屋」
<住野文子>
先生・又お世話になります。まだまだ日常に振り回されています。一時現実を離れて
過ごせるので、とてもリフレッシュできて、一週間位はボーと頭の中が夢見心地する
日が(ゆとりのある日)続きます。後は又現実に戻ってしまうのですが・・・
今度は絵合わせですが、中世の人々の心の綾が楽しみです宜しくお願い致します。
<戸田京子>
末摘花の容貌が悪く生まれてきたことで、父宮は姫の行く末を案じてこの世を去って
いかなければならなかったかと思うと、父宮の心労は如何ばかりだったかと思わずに
はいられません。経済的な援助もなく細々と残された財だけを頼りに生活している様
子に可哀相に思います。でも姫を案じて源氏から経済的な援助を受けられるように取
りはかった命婦の働きに心から褒めてやりたいです。
平成16年3月27、28日読書会 「蓬生」(前半)と「末摘花」
<戸田京子>
末摘花が故常陸の親王という高貴の宮家の末の姫君として生まれながら、父宮亡き後
しっかりとした経済的なよりどころがないままに、段々に家が落ちぶれ荒れ果てた
住居にひっそりと細々と苦しい日々を送りながら、それでも宮家の姫としての誇りを
捨てずに
暮らしている様子に、せめて宮家の姫としての誇りだけは持ちたいという強い気持ち
と
父宮が建てたという、父親に対する思いが強かったのが印象的で、
それにしても随分辛い生活を強いられていた姫がすごく可哀相で、容姿もことの他悪
く
鼻の先がたれて赤く色ついている様など、女性としてとても恥ずかしい顔立ちに、
人には見られたくないとの思いが内へ引きこもりがちになったのではないか。
そのような姫に命婦に逢わせてほしいと、心優しく素直で美しい夕顔への思いが、
忘れられない源氏がいろいろと掛け合う様子など面白く、末摘花とちぎった
その後の明朝の明るみに末摘花の全容を見て驚愕するなど、その後の
姫を見限って再び常陸の宮邸へ訪れてこない源氏のつれない様子に又、
侍従が一人一人いなくなることへの淋しさに号泣する末摘花の様子が、
可哀相でつい涙ぐんでしまいます。 戸田京子さんより
平成16年1月24、25日読書会 「澪標」(後半)
<池田郁子>
寒いだろうと思ってきた会場が意外と快適で厳寒の中、源氏もどんどん進んで今回は大変面白
かった。人数がもう少し多かったら最高だったのに。六条御息所の死によって彼女の「女の一生」のまとめができ、『母』であったことを改めて思い知った。
<戸田京子> 漂標を終えて
私は源氏が住吉参りに行く行列を空想していました。
昔は自然色いっぱいの中、行列の美しさを想いました。又春宮は天皇
この日本において春夏秋冬が今よりはもっとはっきりしていたのではと想いました。
又その美しさ、厳しさも想いました。春=東=○ 夏=南=白
秋=西=○ 冬=北=黒
この用にも表される事もすばらしいと想いました。
○には何を入れたら言いかも色々と教えてください。
< 前川 絹代> 感想文
源氏物語の原文を読ませて頂いていますが、言葉の意味が分からない所が多く
一つの文章を読むのに苦労します。一回だけではなく何回も読んで楽しみたいと思っ
ています。
源氏が明石の上との間に生まれた、姫の先々のことを考え都へ迎えてそれなりの暮ら
しをさせたい
気を使う所など父親としての愛情の深さが感じられます。又過去に関係のある女性の
暮らしにそれとなく
経済的な援助をするなど思いやりのある心優しい人であった事に、女性の一人として
何かほっとする思いをしております。以上です 前川
10月18,19日読書会 「澪標」(前半)
<初参加戸田京子の手紙>
とっても楽しいわよ、戸田さんも読書会に入って一緒に本を読みましょうと誘って下
さった日のことが、
昨日の事のように思い出され、読書の秋と言われるこのいい時期に入会出来て本当に
良かったと心から
嬉しく思っています。
一度紫式部の源氏物語を原文で読んで見たいと思っていた私ですが、古文は難しい
と、思い込んでいましたので、理解出来るかしらとちょっぴり不安な心で読書会に望
みましたが、先生始め皆様がとてもいいかたばかりで、学ぶ雰囲気がとても明るくの
びのびしていて不安な心も解きはなれ、平安の雅やかな貴族の生活がほんの少し見え
てくるのが嬉しく10代の学生に戻ったような心境で、楽しく学ばせて頂いておりま
す。
<水口しげみ>
源氏がどの女性にもそこはかとない心遣いをし、それが読者にもなんと快く読む程に
引き込まれ、この世にこれ程女性の気持ちを、夢の中の会話のようにやさしく身分の上下
もなく思いやることのできる殿方は幾人おられるでしょう。明石の姫君に乳母を使いとして
遣る時都を離れるまで車にて送り出し、姫君への御佩刀を「所狭きまでおぼしやらぬ隈なし」
こうした姫君が生まれた時からのおもいやりには感じ入ってしまいます
現代は情報があり過ぎ流されまいと思ってもやはり眼から耳から、自分を見失うことなく生活することは大変です。ゆとり教育ということが最近いわれますが親も子も時間の使い方が
悪いように思います。時には古いアルバムを出して語らうこともなく漠然と一年を過ごして
いるように思います。古き良き時代ということはそうではなく源氏の時代に心にゆとりを持って暮らせた人々のように、現代でも経済的ではなくて心にゆとりを持って生活すれば殿方が女性にやさしくなれ、女性も殿方にやさしく女らしく言葉も身のこなしも自然とやさしくなれる
ように思います。時の流れが止まってほしいと思えた頃が誰にもあるように人を愛することは
今も昔も変わらないと思います。素直な心で暮らすことを忘れかけている自分をふと哀しく思います。いつも一生懸命の生き方を模索しているのですが。
生まれてきた時から男と女にはそれぞれに巡り合いがあり結ばれても相手が自分の心を読める程深い絆があり暮らした時間の長い短いにかかわらず源氏は、その人とのひとりひとりについていつも本気で接してきた人のように思えます。なぜと聞かれてもわかりませんが理屈ではなく私にはそう思えるのです。今私は優美な源氏の時代と現代の時間のながれとの長い長い
空間を皆さんと楽しませていただいております
7月5,6日読書会の感想 「明石」を終えて
明石入道の野心にはすごいものが感じられました。ことが自分の思い通りに進み、内心はほっとしたことと思いますが、源氏が京に戻る日のあの失望ぶり。ふぬけになった入道が出家した人の態度とはおもえず、こっけいに思えました。
北井和子
入道夫妻、親子の心模様、今の世と変わらぬ心情に親しみを持ちました。
自然と一体となった感情の表現の美しさなど心に沁みました
森 弘子
明石の上の心のひだがわかりました。明石の入道の子を思う心がおもしろく、歌のすばらしさを感じました
田中先生とのふれあいは今から3年前葵の巻からと記憶しています、当時何もわから
なかった私でしたが、
賢木の巻〜須磨の巻〜明石の巻と源氏に触れて行く時もっと知りたい〜〜と好奇心旺
盛になりました。明石の巻きは地元でもあるし、賢木の巻きとは違ってとても身近に
感じ入道の親の気持ちが(滑稽なまで)解り理解出来ます。目を閉じて先生の説明を
聞いていると明石の巻は特に自分なりに状況を浮かべ楽しくなったものです。そのお
陰で明石の歴史にも触れる事が出来、又
源氏を読む事によって新たな歴史発見につながって行きます。又昔と今との文章の変
化にも気付き、古文の美しさに触れる時、心が浄化される思いもします。読書は苦手
でしたが、源氏だけははまってしまいそうです。
前川絹代
明石の地で明石の巻読了。皆と人丸神社や明石入道の屋敷跡など巡って本当に楽しかったです
池田郁子
初めて先生のお話に引き入れられてこの時代のこと、親子のこと、その折々の景色が見えるようでとても楽しく勉強させて頂き久しく眠っていた頭が冴えて今朝早くに目が覚めしばらく眠れませんでしたが、それがとても心地良く、何故か不思議な心持ちでした
水口しげみ
遠い昔の私達の先達を色々思い浮かべてのひととき、とっても楽しかったです
初めて原文に接する機会に恵まれ、もう少し源氏を勉強してみたい思いにかられました
2月1、2日読書会の印象 「明石」について
* 明石市に在住の地元の人が3人もいることもあって、作者は明石をどう描いているか
皆興味津々でした。例えば
<須磨はいと心細く、あまの岩屋もまれなりしを、>しかし明石は<人しげき><さまこと
にあはれなること多くて、(源氏は)よろづになぐさまる>という二ケ所の比較の描写は
まさにそのとうりということです。紫式部は現地に行ったわけでもないのにどうしてこんなに正確に土地の感じををつかめるのだろうかと感嘆しあいました
**源氏が<のどやかなる夕月夜に、海の上くもりなく見えわたれる>明石の海を眺めているうちに錯角を起こして都の家の庭の池水に見えてしまうところがあります。<何方となく、ゆくへなき心地したまひて>と都恋しさに夢心地になるが、ふっと現実にかえると目の前には淡路島ばかりだった
この光景がまたリアルだというのです。海が池水に見える角度があるのですって。
*** 明石入道の曲者振りがビミョウな表現の中に浮かんでくること
だいたいほめているのか、けなしているのかさっぱりわからない
それは<物きたなからず、よしづきたることもまじれれば>とほめあげても
<まじれば>とあるので否定の方に傾くから。<すこしつれづれのまぎれなり>
の<すこし>や、<「興あり」とおぼす事もまじる>の<まじる>も同じ。
それから源氏へのいかにもへりくだった物言いの中に、いいたいことを
いおうか言うまいか、源氏をはかってるように感じると鋭い読みもあった
|