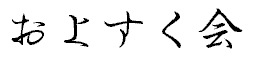 平成20年から平成21年までの読書会の報告です
平成21年11月18日 例会報告と感想文 沈光子
花宴の翌日には後宴が催される。藤壷は明け方には帝の側近く上の局に上がっていた。もはやどうにもならない遠い人であることを今更のように思い知らされた源氏。 世に知らぬここちこそすれ有明の と書き付けた。有明の姫は虚ろを埋めてくれるのか‥‥、源氏の恋は手の届かない人への思慕と背中合わせのようだ。 私は源氏の苦悩に触れるたびに「本当の幸せは水面下で静かに揺れている草のようなもの」というどこかで耳にした言葉を思い出す。だから源氏と左大臣のやりとりは、肉親との縁が薄い源氏にとっては、幸せにつづく「情」のやりとりに似た温もりを感じさせる。
以下、受講後瞬間一言感想です。 ◎ 短い文章に多くの人々が登場しました。藤壺→かの有明→姫君→かの有明→北の方→若君、源氏の心の軌跡でした。 ◎ 朧月夜の桜の扇、そして左大臣の息子達のライブコンサート。源氏の悩ましい想いの中で私も一息つけました。 ◎ 朧月夜に出会ってしまった女の素情やこのまま終わってしまうのは心残り、どうしたらよいものか思いにふけっている時、ふとしばらく訪れていない2人のことを思い出し訪ねるところなど、まめな源氏の様子はさすが。 ◎ 式部の筆の運びに導かれながら花宴の物語が続きます。古文の短い文節から主語もなく登場人物の心理、動作、時の流れ四季の情景、お互いにかわす歌など平安の人々はそれぞれの知識や経験から想像を広げて読み聞きながら、源氏物語に親しみや憧れた式部のイマジネションの豊かさと構成の大きさに感じ入っている。イメージをふくらませて物語を読む楽しさをおよすく会で充分味わうことに感謝です。 ◎ 藤壷への恋の成就ができず、苦し紛れの恋の火遊び。有明の女にも気を残しつつ左大臣宅の妻の処へ行っても、せつない思い。今日の場面、源氏の多忙な出来事、恋は忙しい中に生れるのか? ◎ プライドの 高き妻ある身の憂ひ みずからまねきし 事ゆえ耐へよ ◎ 左大臣の源氏への気遣いがちょっと痛々しい感じ。北の方に会わずとも、この義父の気持に報いてよ! 光の君。 ◎ 北の方は相変わらず「ふとも対面したまわず」。こんな娘をとりつくろう左大臣は花宴での源氏を褒めちぎる。源氏もまた左大臣家の息子・頭中将を褒め千切り褒め倒し、もし義父のあなたが舞えば、もっと盛り上がったでしょう‥‥‥なんて歯が浮くようなことも言ってみせた。左大臣は婿を気づかい、婿はそういう舅をいたわるいつもの風景。
平成21年10月21日 例会報告と感想文 花宴 沈光子 10月 朧月夜 P123〜 深き夜の哀れを知るも入る月の おぼろげならぬ契(ちぎ)りとぞ思ふ 花宴の興奮が覚めやらぬまま、密かに何かを期待して真夜中に彷徨っていた源氏。そして期待どうりのハプニングが待っていた。「わななくわななく」不安を超えて、若々しい女の好奇心が熱く全身を充たしていく。 うき身世にやがて消えなば尋ねても 草の原をば問はじとや思う 別れの刻が近づいていた。戸一枚へだてて、夜明けの物音が沸きあがってくる。気持がせかされる。もう別れなければならない。 二人は扇だけを交わしてあわただしく別れた。互いの身体を包んだ香りはどこまでも胸に拡がっていく。つかの間の契りではあったが、耳朶にをうった声のたおやかさは揺籃のようである。つかの間交わしあった感触、この夜の記憶は、互いを胸深く刻みこんだだろうか。
弘徽殿の姫君たちP128〜 桐壺に戻った朝帰りの源氏に「まあ、相変わらずお盛んですこと」と女房たちは寝たふりをしながら肘をつつきあった。ヤンチャな主人を憎からず思う女房達。そんな声をよそに眠ったふりをしても、しかし女を思って眠れない源氏。 源氏はあれこれ思いを巡らして身勝手な想像にふけった。深刻な恋を求めているわけではない。しかし右大臣家のどの娘でなのかを知るのは、難しい。女は再会を拒絶するという風でもなかったのに、文を交わす手立てを教えてくれなかった。
以下受講後瞬間感想
することができず、また今回も朧月夜の複雑な気持を察することはできない。
プライドが表れています。
考えられない出会いに新鮮さを感じます。
かなかのくどき文句!
其の時その時の情景に、式部の筆の豊かさを感じずにはいられない。
らないはずがない。スリリングなこの出会いが、さて跡にどうなるのか‥‥。式部、お上手ですよね。
素性はわからぬまま別れてしまったが、あれこれ考えを巡らすうち、やっぱり藤壷はす
て厚かましいたらありゃしない。直子さんに言いつけてやる! ホント、ボンは食えな 平成21年9月16日 例会報告と感想文 花宴 沈光子 花宴 p112〜 春たけなわ、如月の20日余り(2月)、南殿で桜の宴が催される。鳥のさえずりも心地よい好天である。 華麗な宴に夜の帳が下り、花の宴が果てた。ほろ酔いの源氏は朧月に誘われるように、彷徨い歩く。藤壷に会えるかも‥‥淡い期待を抱きながら静まりかえった殿舎の辺りをうろつく。しかしそこは隙なく閉ざされていた。寸分の隙もない。もはや手引きをしてくれる女房もいない。
源氏20歳。恋の遍歴は源氏物語を展開する柱になっています。しかし女性遍歴といっても、藤壷は父天皇の后であり、正妻・葵の上は後ろ盾のない源氏を支える左大臣家の娘(冷えた関係)との極めて政治的な結婚だった。そして紫の上は妻というにはまだ幼い。夕顔との出会いのような恋が、また訪れるのだろうか。
以下 受講後瞬間一言感想
のまま自分の地位にもつながるのだから怖いですよね。
っているかのような臨場感をもって感じられた。私は「帝、春宮の御才かしこくすぐ
ました。大変ですね。漢詩の勉強があったんですね。やっぱり戦争のない、好きなこ
ぶっちゃけた話、華麗な催しの余韻覚めやらぬ夜を共に過ごしたい女性が他にいただ
へ。そして宮中で盛大な桜の宴へ、と物語は展開。
美しさ故に間違いが起きるのであろうか。
「朱雀院の行幸は神無月十日あまりなり」 紅葉賀8月 P99 頭中将の宿直所から「これを綴(と)じつける必要があるでしょう」 君にかく引き取られぬる帯なれば 陽が高くなり、それぞれ二人は殿上へ行った。昨夜のことはなかったように知らぬふりした顔の源氏を見ると、中将はおかしくてならなかったが、その日は公事が多く、生真面目であった。(互いに相手の澄ましようをみて)どうかした拍子に目が合うとついほほえんでしまうのである。人がいなくなったときに中将が寄って来て P104 それからのち、中将は何にかにつけてあの晩の騒ぎをいいだしては、どれほど源氏を苦笑させたかしれない。それもこれもあのやっかいな内侍のためと思い知ったのだった。女はその後も源氏の気をひこうとするのが、わずらわしかった。中将は妹の北の方にもナイショにして、自分が源氏をやり込める種に使う魂胆である。 藤壷立后 P104 七月に(初秋)藤壷が中宮になられるようである(筆者は政治的なことは知る立場にないと読者に婉曲にいう)。源氏は宰相になった。帝は譲位する心づもりで、若宮を春宮に、と考えるが、後見人がいらっしゃらない。母方が、みな親王で、皇族が政治に関わることはできないので、せめて母宮・藤壷だけでも中宮という不動の地位に据えて、若宮の力添えにと考えるのであった。 中宮になって宮中に輿で参内する藤壷の夜のお供に、源氏の君も付き添った。后と一口に言っても、この方の身分は后腹の内親王であった。全く尊い珠のように光輝いて、帝の寵愛も一身に受けていたので、人々は特別な思いでもってこの方に心を込めて使えるのである。ましてや耐え難いほどの恋情を燃やし続けてきた源氏は、付き添う輿に乗っている藤壷への思いに身を焦がした。后となり、いよいよ遠いはるかな、手の届かない人になってしまった現実。いても立ってもいられない心境であった。 つきもせぬ心の闇にくるるかな こう独りつぶやいて胸がいっぱいであった。(どんなに悲しくても恋しくても、僕たちはどうすることもできないんだ) 若宮の顔は成長するにつれてますます源氏と見分けがたいほど似てきた。藤壷は辛く思うのだが、あってはならない秘密に気づく人などいない。何をどのように作り変えても、劣るものなき美しいものは、美しい源氏に似てしまうものなのだ。世の人々も二人が似ていることを、月と太陽が同じ形で空にあるようだと思って、疑いを持つ人は誰もいなかった。 以下、受講後瞬間一言感想
中宮になりたるひとを 恋ふおもひ 千々に乱るる 胸ふたがるる
紅葉賀の巻き冒頭のシーン 青海波 を舞う源氏の姿が忘れられません。
帝の皇子への慈愛、弘微殿の嫉妬、頭の中将の競争心。それぞれの思いから源氏
入って行く様です。
ていなかった。だから何かと源氏には対抗意識を燃やす。そのやりとりが微笑まし 平成21年7月15日 例会報告と感想文 紅葉賀 沈光子 田中先生の「源氏生活」ブログに染ちゃんの内侍への「恋の達人」評価は違っているのではないか、という疑問がアップされていました。老いたりとえどその道の達人なら、恋情を託した歌へ性急な返歌で興ざめなものにしないのでは‥‥という指摘。 五十七、八の人 P99 いかにも自分は真面目なんだといわんばかりに、源氏が頭中将(の浮気沙汰)を非難するのが口惜しい。源氏だってそしらぬ顔してここっそり偲び会う恋人が少なからずいるはず。どうにかして尻尾をつかみたいと思っていたところへ、偶然、浮気現場に来合せた。(ラッキー! やったぁ!) P92 中将はおかしいのをこらえて、源氏が隠れた屏風に寄ってゴホゴホ(パタパタ)と畳んでわざと騒いでみせる(男が来たぞ!とアピール)。 P94 自分と知られないように別人を装って怖がらせたのが(やりすぎたのよ)、かえって源氏に頭中将だとわからせてしまう結果になった。内侍の相手が源氏だと知ってわざとしていると思うと、アホあらしくなり、やっぱり頭中将だと確信するとおかしくて、抜いた太刀を持つ腕をつかんで、キュとつねった。頭中将もバレテしまったのがしゃくだと思いながらも、こらえ切れずに笑ってしまった。 そんな衣を着れば浮名はバレバレだね」 源氏も負けずに詠み返した。かくして二人とも恨みっこ無しのだらしない恰好になって、連れ立って出ていったのだった。
なごりの帯 P97 「恨みても言ひがひぞなき立ち重ね(恨んでも甲斐がありません) 受講後の瞬間一言感想
「えならぬい二十若人たちの御なかにてものおぢしたる、いとつきなし」 なんとも辛口のお言葉ですこと。
彼女には空気のように恋が必要不可欠だし、恋することが彼女を彼女たらしめるエネルギーになっているんでしょう)
歌のやり取り・琵琶の音など他もろもろ彼女のインテリジェンスを感じて、源氏も(中将も?)近づいてきたのでしょう。歌は知識の集大成です。まったく。
内侍の外見などを厳しい目で描く式部だが、一方で老いても直 女としての魅力を秘めた内侍を羨む気もあるような、ないような‥‥。
合歓の花 をんな死ぬまで恋をして 内侍は当時のキャリアウーマンである、という講師の指摘に受講生深く合点がいきました。男に頼ることなく生きている仕事のできる女が、老いてなお恋に情熱を傾けている、という前提で読むと、内侍という女性の人柄への想像力が変わってくるようです。 平成21年6月17日 例会報告と感想文 紅葉賀 沈光子 さだ過ぎたる典侍に好奇心からチョッカイを出してしまった源氏。噂になったら恥ずかしい相手との恋に逃げ腰である。しかし冷たくされれば燃え上がるのは、古今をとわず恋の常套というものでしょう。典侍の恋心がいや増さることはあっても、これしきのことで潰えることはありません。彼女には汲めども尽きぬ恋の情熱が満々とたたえられているのです。つい好奇心に負けてしまった源氏19歳、追いかける典侍は恋の達人。56〜5.7歳までだてに年を喰っていたわけではないようです。さてどんな展開になりますことやら。 P84 琵琶の音 P86 ひとしきり降った夕立のあと、宵闇の涼しさに誘われて、温明殿あたりを源氏が歩いていると、典侍が琵琶をじょうずにひいているのが聴こえた。(典侍のいるあたりを歩きまわるなんて、若さ故の怖いもの見たさなのかしらん‥‥、飛んで火に入るなんとやらですねぇ) P88 典侍は嘆息をしている。自分に向けて言っているだけではないのだろうが、どうしてこの女はそんなにも男が待たれるだろうと、源氏は思う。 そういい捨てて、立ち去ってしまいたかったけれど、典侍に恥をかかせて侮辱することになると思い直した源氏は、室内へはいった。典侍と軽い冗談などいい合っていると、こういうものなかなか新鮮で、これもまた一興に思えて悪くない気がしてくるのでした。(源氏はまだ若い。比べて典侍は、その道の達人・老いたぶんだけ性急ではありますが、いまだ恋の手練手管は中々のもの。源氏は恋の達人にまんまと乗せられてしまいましたね。 受講後瞬間一言感想
「これもめずらしきここちぞしたまふ」また「うちうえき」ませんかねぇ?
いつものことながら、せっかく男性の参加があるのですから、女どもとは異なった視点で感想をもらえたら、より多面的にイメージが拡がりるのですが。 平成21年5月20日 例会報告感想文 紅葉賀 沈光子 許されない恋の形見として源氏に瓜二つの若宮が誕生しました。この現実への衝撃、苦しく鬱々と日々を、西の対に迎えた女君に癒されている源氏です。左大臣邸への脚はますます遠のくばかり。 このように二条院西の対の女君に引き止められている(左大臣家への訪問が間遠になる)ことが多いのを漏れ聞く女房たちは、噂する。 典侍(ナイシノスケ)の懸想 P77 かなり歳のいった典侍がいた。家柄がよく才気もあり、品性も備わり評判もよいのだが、好色多情で、恋にはめっぽう軽い女だった。 P80
この巻に出てくる典侍を描いたとき、紫式部は何歳だったのだろうか? と姦しく話合いました。若い女たちは容姿に老いを刻んだ同姓には厳しい目を向けるのは古今普遍であろう、ということで、式部はまだ若かったのではないか、という結論になりました。女が女の醜悪を描くと、これでもかというところまで細やかに鋭い筆が冴えるようです。「およすく会」は老いてますます磨きがかかた女が多いのでありますが、とは言っても典侍への無自覚な老醜への容赦ない式部の筆力に、我がことのようにドキリとさせられたのでした。経験しなくてもいいことにまで手を出してしまう源氏の若々しい好奇心を、式部は戯画化してお灸を据えたのかしらんねぇ。
4 西の対の愛らしい女君の話の後に典侍の話を持ってくる構成は効果的だ。19歳の光の君に色目を使う老女の、ろうそくの燃え尽 きる直前のような赤々と燃えるあだっぽさが滑稽に描かれているが、物悲しくもある。騒々しい世間の噂を恐れて逃げ腰になる天 下の二枚目源氏が、トンだ三枚目役となって、コミカルだ 5 典侍の源氏に対する恋心は、ビックリです。紫式部はリアルにそしてユーモアも含めて書いていますね。鮮やかな赤と金泥の扇、 そして老女、この三点セットが印象的でした。 6 さだすぎた人(典侍)の描写がリアルで実にすばらしい。 いとう身延べたれど・はつれそそけたり 目皮らいたく黒み落ち入りて など等の表現が特によい。 7 1200年前にも典侍のような女性がいたことに絶句し感動。それにしても源氏、若気の至りとはいえ、「罪つくり」だぞ! 8 物語は展開して、藤壷との秘められた恋に破れ、打ち沈んでいた源氏や、内裏での年老いた典侍とのたわぶれのやり取りの場 面。式部の表現の迫力によって、こうして後世まで源氏物語が読み伝えられたのだと思った。 9 さだ過ぎたる典侍は、57〜58才との事。私の年齢に近いのですが、おそらくもっと年寄りであったでしょう。 「目皮ら黒み落ち」や髪の「いみじうはつれそそける」が実にリアルに自分自身の身体で感じられ、式部の鋭い人物描写に感心しました。平成21年4月15日 例会報告感想文 紅葉賀 沈光子 4月講義録 御子は自分に瓜二つだった。心乱れたまま源氏は二条の院へ戻った。せつなさが拡がるばかりの源氏は、気持を鎮めてから、左大臣家へ行こうと思った。 咲いて欲しいと思った撫子の花ですが、私たち二人のように男女の仲はどうにもなりません。児に会えば心が通じ合うと思っていたのに、なんと私に瓜二つでした。しかし帝の児として秘密を隠し通すしかありません。 とだけ、思い煩う筆のままに書いたものを、命婦は返事を待ち望んでいた源氏へ送った。いつものように返事はないものと思い、現実の衝撃から立ち上がれない源氏へ、返歌が届けられたのだった。胸が騒ぎ、そして児への愛おしさと疎ましさにさいなまれる藤壷の本心に触れて、源氏は返事をくれたことをうれしいと思いつつも、しかし涙が落ちるのだった。 二条の院の女君 P66 P71
灯をともさせて絵などをいっしょに見ていたが、源氏は西の対へ来る前に予定を伝えてあったので、それとなく外出をうながす咳が聞こえ
父帝の妻と密通した証に、自分に瓜2つの皇子誕生としてつきつけられた。源氏の苦悩。命を削るようにして出産した源氏と瓜2つの皇子を見るたびに、罪深さにさいなまれる藤壷。しかしひるんでいては弘徽殿の笑い者になってしまう。心を強く持って乗り越えていかなければならない。しかし皇子の顔を見るにつけても、帝の手放しの喜びよう、可愛がりようをみるにつけても、胸がしめつけられる。苦しみの余りに、思わずフッと本音を源氏に漏らしたのでした。やりきれない恋心を、しかし初々しい若紫の成長ぶりが読者をも和ませてくれます。女君は順調に成長しており、淡い夫婦愛のような情の芽生えも見えて、これからの展開が楽しみです。(藤壷の源氏への返歌。「袖濡るる」は「露けさまさる」と詠んでよこした源氏の袖をいう。「露のゆかり」は若宮があなたの子であるという意をこめる。『集成』は、「あなたのお袖の濡れる露に縁のあるもの(悲しんでおられるあなたのお子)と思うにつけても、やはり大和撫子(このお子)をいとしむ気にはなれません」と解し、『完訳』は「「ぬ」は完了の意。打消とする一説はとらない。「なほ--」で、一面には、若宮をいとおしむ気持」と注して、「このやまとなでしこ--若宮があなたのお袖を濡らす涙のゆかりと思うにつけても、やはりこれをいとおしむ気にはなれません」と訳す。この子が源氏の子であると思うと、やはり疎ましい気持ちが生じずにはいない、という真情を吐露した歌。しかし、藤壷がわが子を真底に「なほ疎まれぬ」と思っているわけではあるまい。「ぬ」を打消の助動詞と解せば、「疎むことのできないわが子」の意になり、藤壷のわが子をいとおしむ気持ちの表出になる。この感情は矛盾するものではない。源氏に対しては「いとおしむ気にはなれない」という一方で、わが子は「いとおしい」という。この歌を受け取った源氏もその両意に解したろう。‥‥‥大島本より抜粋) 以下受講後の瞬間感想の紹介です。
今日読み進んだ文章から、藤壷の切ない心情・究極の悲恋の物語を垣間見ました。二条院で美しくろうたげに成長していく紫の上に、源氏は癒されていく日々です。物語の展開、来月も楽しみです。
平成21年3月18日 例会報告感想文 紅葉賀 沈光子 紅葉賀P53 御子の様子を知りたくて、源氏は気をもんでいた。藤壺の実家三条の宮へ女房たちの居ない頃を見計らって訪ね 藤壺は御子を見るたびに我が身が抱えている心の鬼と葛藤していた。今更のように密通の罪深さに苦しんでいるのだった。源氏に瓜二つの御子、産み月の遅れ‥‥、口さがない人々がこのことをとがめだてしないはずはなく、罪深さを隠しようがない。つまらないことにさえ世間は口さがないものなのに、(皇女として人々の羨望を集めてきた自分は、ついに賤しめられる)噂にさらされることになるだろう。 P54密会の手引きをしてくれた命婦に会うことがあると、源氏は言葉をつくして「会わせてくれ」と懇願する。だがなんのかいもなかった。源氏が余りに御子に会いたがるので、 と源氏は訴えるのだった。命婦は藤壺の心痛を目の当たりにしている。かといって素っ気無く源氏を突き放すこともできない。源氏の思いを伝えるくらいは、密通の仲介をした者の義務だとも思う。 「見ても思ふ見ぬはたいかに嘆くらん こや世の人の惑ふてふ闇(やみ) 対面 P58 P60源氏が藤壷の館で管弦の演奏に参加しているとき、帝は御子を抱いてきて、 御子は何か言うように声を出し、笑顔になるのがひじょうに美しかった。だが帝から似ているといわれ、自分まで尊重されているような存在にさえ源氏が思ってしまうのは、はなはだ身勝手である(語り手は手厳しく源氏の甘ちゃんぶりを叱責する)。
この日の受講場面は、御子誕生に向かい合う人々の心情が、緻密な織物のように鮮やかに織り上げられ交錯する様子が描かれていました。読者なら誰もが胸騒ぐ内容です。みなさんの感想も、瞬間感想であることが、かえって読みごたえあるものになっています。藤壷と源氏・王命婦そして帝、それぞれの思いが読者の琴線に触れてきました。 以下 みなさんの受講後瞬間一言感想です。男と女の立場の違いもあるので、毎回男性の感想がないのは淋しいです。 源氏 いみじき言えどもを尽くしたまへど〜 説である証。作者の意図を離れて登場人物が生き生きと勝手に動き出すという小説の 平成21年2月18日 例会報告感想文 紅葉賀 沈光子 朝拝の儀を終えた宮廷から下がって、左大臣邸を久しぶりに訪れた源氏。北の方のつれなさは年が改まっても相変わらずである。(◎箇所で受講者たちの読後瞬間感想を紹介しています。)P45左大臣も婿が足しげく通ってくれないのを辛く思っている。だがこうして久しぶりに会えば、日ごろの恨み言も忘れて、ついつい一生懸命に世話してしまう。 年賀の挨拶といっても多くへ行くわけではなく、内裏、春宮、上皇の邸である一院くらいだった。そして(公的に後見を仰せつかっている)藤壺の実家三条の宮へ。 皇子誕生 出産予定日の十二月も過ぎてしまったのが気がかりだった。一月にはいくら何でも産まれるだろうと待っていたが、その心づもりもむなしく過ぎて、立春(二月)に入った。
下記、皆さんの瞬間読後感想文です。 ◎ 左大臣に対する源氏の後ろめたさが見え隠れし、また藤壺の裡なる声が聞こえた気がする。 みです。 ◎ 藤壺の周りでは皇子の誕生を心待ちにし、今月も生まれなかった‥‥と正に指折り数えて待っている。源氏の子をみごもってしまった罪の大きさに恐れおののいているという心の裡を知る人は一人もいない。この藤壺の心理と周りの期待感との対比が、孤立感・孤独感をさらに浮かび上がらせている。真っ暗な舞台の上で一人、恐怖に圧しつぶされそうな藤壺がスポットライトを浴びている。 は! 広黴殿には負けない皇女としての藤壺の決意に涙がでました。 簡潔な文章で藤壺の人となりが濃密に描かれていたのが印象的でした。帝の寵愛を一身に受けて、后たちから嫉妬を買って早世した源氏の母・桐壺や、頭の中将の正妻の嫉妬から逃れるべく失踪して源氏に出会い、あっけなく死んでしまった夕顔とは異なって、藤壺は我が身が決して世間の物笑いの種になるまいと、毅然と生き抜かんと、病に負けずに生気を取り戻していきました。その強さこそが、真に高貴である証なのでしょう。出自ゆえに源氏に対して素直になれない葵の上とは異なり、芯の強さに支えられた「身分」というものを考えさせられました。左大臣と源氏のやりとりが感想の中で |
1)あいなう⇒訳もなく、ただもう、胸ドキドキ 2)異にはべりつ⇒特別でした 3)けしうはあらず⇒悪くはない 4)手づかひ⇒身のこなし、手の様 5)家の子⇒身分の高い子弟 6)ここしう⇒子子しう、おっとりゆったりしている |
【イメージ】
源氏の舞った青海波の感動覚めやらぬ帝の興奮した声【青海波に事みなつきぬな。いかが見たまひつる】が、藤壺に求めているのは源氏の舞への賞賛と帝への感謝。しかし源氏の舞を観ながら、夢の様な心地に浸っていた自分を思うと問いにすぐに答えられない藤壷の【あいなう、御いらへ聞こえにくくて】二人の心のずれと藤壺の罪の意識がリアルに浮かぶ文章です。【子子しう】【なまめく】という言葉に当時の貴族社会、格差社会の美意識が良く現れています。御曹司は、何時の時代も【子子しう】【なまめく】あって欲しいです。
P−14
1)つとめて⇒(翌日の)朝早く お勤めは6時50分〜11時まで 2)世に知らぬ⇒今まで経験したことのない 3)乱りごこち⇒取り乱した心の状態 4)袖うち振りし⇒青海波の動作、自分の思いを相手に知らせる動作 万葉集 額田王の【あかねさすむらさきの(紫野)ゆき(行き)しめの(標野)ゆき(行き)野守は見ずや君が袖振る】から 5)あなかしこ⇒(手紙文の末尾に添えて)謹んで述べました その他色々な意味もある 6)立居⇒立ったり座ったり 7)おほかた⇒一般的なこと 8)かやうのかた⇒舞楽の来歴 9)ひとのみかど⇒異国の帝(朝廷) 10)かねても⇒前からそうだった 11)持経⇒常に身につけて、声に出して読んで信仰を深める、大切な経典 |
【イメージ】
王命婦が仲介したであろう源氏の文。【中将の君】と言う表現は王命婦の視点から来るもの。源氏もやはり藤壺に自分の舞の評価を聞きたいのです。【袖うち振りし心知りきや】強烈な恋の歌。額田王の歌がこんな所に出てくるとは驚きです。決して返事を書いてはいけないと思う藤壺ですが、脳裏に浮かぶ源氏の舞姿に、どうしても我慢できない、どうしてもこの糸を繋ぎたい、どうしても言葉を返したい。語り手が【・・忍ばれずやありけむ】我慢できなかったのでしょうと。そして歌の最後は、源氏への思慕を隠す言葉【おほかたには】です。隠せば隠すほど、彼女の思いの強さを感じます。恋の歌に返事を書いてはいけない自分なのですから。源氏の感動が【限りなうめずらしう】 です。「やったー!やったー!やったー!」って感じ。藤壺は、やっぱり素晴らしい女性だと誇りに思い【ほほゑまれ】るのです。好きな女性が尊敬出来る人である事は喜びです。二人の純真な若さを感じます。持経の様に藤壷からの文は、源氏の宝物になって生涯彼の懐から離れなかったのではないでしょうか? 沈さんが【究極の忍ぶ恋】と。
行幸
P−17
甚だしい 5)垣代⇒【青海波】などの舞楽で垣のように並び、笛や拍子をとる楽人 6)地下⇒宮中に仕える者 |
【イメージ】
宮中から朱雀院までの距離はそれ程ありません(資料P−9の平城京坊図)宮中が空になるほどの人達の移動は、華やかで賑やかであったことでしょう。朱雀院は広い庭と、楽の船(京都の風俗博物館)が【漕ぎめぐる】池を持つ非常に広い建物であったようです。その庭に溢れる人人人。そして楽の声、鼓の音。またまた弘徽殿の女御が憎らしげに登場ですが、祈祷してもらわなければと思う帝の気持ちに対して「何で?」と思う弘徽殿の女御の気持ちも解かります。粋の、粋の達人を選りすぐって、この日のために練習、練習を重ねてきたことが、よくよく述べられています。国を挙げての大々的催しであったのです。源氏にとっても一世一代の大舞台です。皆が固唾を呑んで源氏の【青海波】を待っています。大舞台の前触れです。
P−19
があせる 5)えならぬ⇒何ともいえない美しさ 6)入綾⇒退場の時に舞う舞の形 引き返してもう一度短く舞う、舞いながらの退場 7)そぞろ寒い⇒ゾクゾクするほど素晴らしい 8)承香殿⇒内裏の後宮の一つ 9)秋風楽⇒雅楽の曲名 四人で舞う舞楽曲 10)さしつぎ⇒次の地位、位置 11)異事⇒他のこと 12)かへりて⇒かえって、反対に 13)ことざまし⇒興ざめ 14)昔の世⇒前世 16)ゆかしげ⇒知りたい、見たい |
【イメージ】
音読してみましょう。感動が伝わってきます。紅葉のもと、40人の垣代の立てる笛と拍子に松風が、【ふきまよひ】【散り交ふ木の葉のなかより】【青海波のかかやき出でたる】登場しました!!【いと恐ろしきまで】の美しさ。霜枯れの菊の花の美しさ(白菊が寒さで赤く変色した)と、さっと来たしぐれ。【空のけしきさへ見知り顔なる】空までもが涙を流すという擬人化がここでも使われます。【入綾のほど】は、【そぞろ寒い】 ぞくぞくするほど。やはり【この世のことともおぼえず】、【ものの心知るは涙おとしけり】の大成功でした!!あの【迦陵頻伽の声】も聞かれたことでしょう。そして大盤振る舞いの昇級です。源氏【正三位】皆々喜び、源氏のお陰と。そして、皆この【人の目をもおどろかし、心をもよろこばせたまふ】彼の【昔の世ゆかしげなり】前世を知りたいと思うのです。あの世からやって来た王子様みたいなんです。
【まとめ】
二人の男が自分に聞きたがる。心が痛い。でも愛する心はどうにもならない。揺れる藤壺の気持ちが、帝との会話や源氏への文に滲んでいました。思いがけない藤壺からの返事は、本番大成功の一因になったかもしれません。いつもの事ですが、風景描写が素晴らしいです。風に舞う、笛の音、木の葉。そして、登場!!「およすく会」冬の京都旅行の「糺の森」で急に時雨たあの時を思い出しました。
前々報で、源氏物語の英訳本について書きました。今月からRoyall Tylerというアメリカ人が2001年に出版した本の翻訳をポソポソ始めています。全文をご紹介出来る程の作文力がないので、途中経過をこの場で毎月お知らせします。まず、驚くほどに原文に忠実です。Arthur Waley氏の翻訳本は世界に源氏物語を知らしめた偉大な本でした。それから時が流れ、日本が世界に認知され、更に、優れた日本人スタッフの力でこの本が実現したのでしょう。丁寧に、丁寧に、注釈も原文に忠実に書かれています。和歌は和歌として、そのまま翻訳してあり、田中・芦部本の各見出しで、全ての文章がすっきり分けられます。
今回は、桐壺の更衣の死の表現です。
【夜中うち過ぐるほどになむ、絶えはてたまひぬる】⇒just past midnight she had breathed her last
【ちょうど真夜中過ぎ彼女は息を引き取りました】如何でしょうか?
she died や she passed away ではないのです!!
平成20年10月15日 例会報告 浜岡はるみ 紅葉賀
試楽
P−6
1)朱雀院⇒嵯峨天皇移行の天皇が譲位後住んだ御所 2)賀⇒長寿の祝い 40歳から10歳刻みに祝った。 3)御方々⇒女房、更衣 4)飽かず⇒物足りない、満足しない 5)試楽⇒舞楽の予行演習 6)青海波⇒2人舞 資料P-30写真 7)片手⇒相手(2つのうちの)一方 8)用意⇒心構え 9)入りかたの日かげ⇒沈み行く夕日 10)さやか⇒鮮やかに 11)詠⇒舞楽の途中で舞人が声を出して詠うこと。その間音楽は中止する 12)迦陵頻伽⇒極楽に住むという想像上の鳥。顔は美女のようで、声がことに美しい |
【イメージ】
朱雀院には女の人たちは行く事が出来ません。帝の藤壺に対する思いやりの試楽の催しです。
夕日が紅葉の葉を美しく染める頃、源氏と頭の中将の二人舞が始まりました。他でもないあの【青海波】。源氏(中将)の美しさを、源氏が花ならば頭の中将でさえ深山木と。【同じ舞の足踏み、おももち、世に見えぬさま】 今まで観た同じ舞とは思えない素晴らしさ。更に【詠などしたまへるは、】吟じるお声は、【仏の迦陵頻伽】の様に【おもしろくあはれ】。まず帝が、そして次々に上達部や親王たちが涙を流し感動する程。カメラワークは、夕日に輝く紅葉の赤から舞の装束へズームそして緊張した源氏の顔へ。管絃の音が止み、シーンと静まり返った廷内に響く源氏の美しい朗詠。嗚呼!! 背中に氷を入れられたような、ゾクゾク感が伝わる文章。胸が熱くなり、涙が・・・。これ程視覚と聴覚に訴えられる文章を、たったこの長さで表せる!!凄い!!
P−10
1)おほけなし⇒身の程をわきまえない 恐れ多い(源氏が藤壺に対し愛情を抱いたときのように、身分上・立場上あってはならない不倫の恋を表すときに使われ、マイナスの語感を伴う。) |
【イメージ】
詠が終わりました。それを待ち受けた様に一斉に管絃が響き渡ります。管絃の賑やかさと、更に美しく【光る】輝ける(大事を成し遂げた)源氏の顔は、あの弘徽殿の女御が平常心でいられない程。【神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし】神が連れて行ってしまうほど不吉な美しさと。藤壺は、【おほけなき心のなからましかば、・・・ましとおぼす】自分に対する源氏の大それた恋心がなかったら、私のために企画された帝にどれほど心から素晴らしいと言えただろう【に、夢のここちなむしたまひける】でも、この夢のような心地はどうしようもなく。どうしようもなく。(藤壺は既に源氏の子を宿しています。)御簾ごしに見える目の前の、美しい紅葉、舞台、【光る】源氏に対し藤壺の懊悩は正に光と闇です。藤壺の心情は、たった2行だけしか書かれていません。その中の【に】に彼女の全ての心が詰め込まれています。
【まとめ】
紅葉賀が始まりました。今の季節にぴったりのシーン。何と優雅で平和な時代であったでしょう。行幸は一大イベントであり、庶民にとってもお祭りであった事が解かりました。帝の輿(資料P-20)はオープンになっていて外から見えます。庶民は帝を見る事が出来たのですね。
管絃の響き、紅葉の赤、舞の装束、この世の人とは思えぬ【光る】源氏の姿と声。源氏の一挙一動を御簾ごしにじっと見守る藤壷。短い、本当に短い文章が絵巻の世界を表し、それは一瞬であると同時に永遠です。
平成20年9月17日 例会ならびに蓼科夏期セミナー報告 浜岡はるみ
鼻の紅 P−118
1)片生ひ⇒未熟 2)桜の襲⇒3種類 日本の色辞典P−50 3)細長⇒女の子が普段着の上に着る上着 4)なよよか⇒やわらかい感じ 5)古代の⇒昔風の 6)ひきつくろう⇒整える 7)歯黒め⇒鉄片を酢などに浸して酸化させた、歯を黒く染めるための液、またその液で歯を染めること。「お歯黒」「鉄漿かね」引き眉とともに万葉集の頃からあった成人女性の習慣 おしろいは、「はふに(白粉」:京おしろい。鉛入り「はらや軽粉」伊勢おしろい:水銀入り 紅:ほほ紅 口紅 整髪:米のとぎ汁 8)きよら⇒最高の美の表現 9)などか⇒どうして 10)世⇒男女の中 11)見あつかふ⇒世話して関わりあう 12)心苦しきもの⇒しめつかれるほど可愛い 【イメージ】 源氏は二条の院にやってきました。初めて紫の君と呼ばれるあの少女は、桜の襲を【なよよか】に着て。お歯黒と引き眉を施した未成熟な美しさは、正に【きよら】です。【心くるしきもの】です。この美しいものを一人にしておいて、自分は一体何をしていたのか?自己嫌悪で一杯になる源氏です。少女の美しさを語れば語るほど、対照的に常陸宮の姫君が浮かんで来る、優れた表現方法です。姫君は何時も紅色として源氏の心の中に、でんと居つくようになっています。同じ紅なのにこんなにも違うとは・・・。 P−120 1)画⇒絵 2)見ま憂し⇒見るのが厭わしい 3)にほはす⇒色をつける 4)いみじく笑ひ⇒はじける様な笑い 5)かたは⇒醜いこと、見苦しいこと 6)うたてこそあらめ⇒「やだー」って感じ 7)さもや⇒そのまま 8)あやふし⇒心配だ 9)空⇒嘘、いつわりの意 10)白まね⇒白くならない 11)用⇒必要 12)すさび⇒気まぐれ、遊び 13)まめやか⇒真面目な様子 14)いとほし⇒かわいそう 15)のごふ⇒拭う 15)平中⇒今昔物語の中の「平貞文(定文)の話」P-123参照 16)妹背⇒夫婦や恋人など特別に親しい男女又は妹と兄、姉と弟 17)心もとなし⇒待ち遠しい、じれったい 18)気色ばむ⇒きざしが見える 19)ほほゑむ⇒花の蕾が少し開く 20)階隠⇒宮中のきざはしの上の屋根 21)いでや⇒(詠嘆・感慨を表す)いやもう 22)あいなし⇒どうしようもない、筋が通らない
【イメージ】
紅の鼻は、忘れようにも忘れられなくなっています。自分の顔を【きよら】と言える程若く美しい源氏です!!少女のコロコロした幼い笑い声が聞こえてくるようです。何て幸せな時間の一コマでしょう。自分の事を信じて疑わない彼女は【心苦しきもの】、抱きしめたい程です。男の子が幼い少女と戯れているだけなのですが、遠目には【妹背】に映るのです。トウのたった古女房にだったら決してこんな事はしない。男達は何歳になっても自分を絶対疑わない女との幸せを求めているのではないでしょうか?【日のいとうららかなる】幸福の絶頂から目を転じて庭の紅梅に。そういえば常陸宮邸を初めて訪れたのも梅の香が香る頃。【いでや】 後悔にまたしても【うちうめく】源氏です。梅の花を【心もとなし】や【けしきばみ】や【ほほゑみわたる】と言った擬人的表現でよりリアルに表しています。開花の程度が推察されます。【かかる人々の末々、いかなりけむ】次をどんどん読みたくなる、末摘花の終りです。 【まとめ】 源氏の【いでや】という後悔の【うちうめき】で終わった末摘花。この巻は「色」と誰かが言いました【紅色】、【雪はづかしく白い】、【黒貂】 、【今様色】、【葡萄色】、【山吹色】、【桜の襲】 等々色々な色が出てきました。以前読んだ本の末摘花のイメージは、他の女たちに比べ、かすれていました。しかし、(昨年11月から)読み続けた結果、一般的に言われている、顔は悪いが性格は良いという平凡な女では決してなかった。
【蓼科高原夏季セミナー】で、帚木の所謂【雨夜の品さだめ】を勉強しました。その中の【葎の門】のイメージを追い求めた結果が、【末摘花】としてまとまったのです。まず伏線を引いておいて、その上に登場人物を乗せていく。素晴らしい作品作りです。【三つの品】の範疇には入らない宮家の価値観。まして【妻の条件】や【甘えた妻】等からは程遠い姫君は、男達の想像を超えた怪物でありました。黒テンの毛皮を着る、手紙の事、源氏に贈った御衣の事等々そして【むむ】。お別れするのが【さうざうしい】お方です。1000年前にこの様なリアルな人間を表したコメディー?が、存在していた事は驚きです。次に彼女にお会いできるのは【蓬生】だそうです。まだ随分先になります。でも彼女のイメージは、しっかり私達の中に残っています。またお会いする日まで、「ごきげんよう」 【蓼科高原夏季セミナー】報告 2008年9月6日〜8日 於:郭公荘 天気も良く、完全自炊体制で、お風呂の外出以外の2日間みっちり読みました。ご飯も美味しかったです。ここは2003年に勉強したところでした。当時自分がいかにやる気がなかったか。読み込んでいなかったか。イメージは浮かんでいなかったかが、良く解かりました。特に左馬頭が語った【家の主人】、【妻の条件】に当時の男が求めていた女が書かれていました。現在の男たちが求める妻との違いは殆ど見られない。実に堅実な家庭の幸せを求めています。また、当時読んでいなかった【蜻蛉日記】が【甘えた妻】と重なっていた事も解かりました。やはり嫁入り道具に入れたい本であったのです。完読を目標にしたのですが、【木枯の女 その一】の途中で時間切れとなりました。今回4名だけの参加で残念でしたが、また次の機会に改めて読み直しても良いと思いました。読めば読む程面白い【雨夜の品さだめ】です。 源氏物語千年紀の今年、多くの催物や出版物が目白押しです。その中で、【和楽】に林真理子氏が連載を始めた【六条御息所 源氏がたり】に話題が集まりました。原文には決して記載されていない、またイメージとしてもあまりに品のない、性的表現が目立つ作品です。何かしなくては。という結論になりました。一方、源氏物語は多くの外国語に翻訳されて世界中に知られています。英訳されたものを日本語に翻訳するのも面白いという寝物語(田中先生と寝ながら話した)に挑戦しようと思い立ちました。外国人がこの様に誠実に、良心的に翻訳している事を知ってもらいたいとも思いました。そこで、英語版【THE TALE OF GENJI】を探しました。Arthur Waley 版が有名だそうですが、ヒットしたのは、Royall Tyler というアメリカ人が2001年に出版した本でした。早速購入しました。何とめちゃくちゃ、ぶ厚い本でした。時間はどれ位掛かるか解かりません。とりあえず、【桐壺】を始める事にしました。翻訳ソフトは溢れていますが、日本語の表現能力のない私には難しそうで、挫折するかもしれないけれど、一人のアメリカ人が描いたイメージを追いかけてみます。新しい船出です。
平成20年8月20日 例会報告 浜岡はるみ
姫君の変化
P−108
1)またの日⇒翌日 2)台盤所⇒御膳を用意する女官の詰所で台盤がある。資料P−12,13 3)くはや⇒それ、ほら 4)心ばむ⇒気を張る 気を使う 5)ゆかし⇒知りたい、見たい、聞きたい 6)梅の花の色⇒姫君の鼻の色 7)三笠の山⇒常陸宮 8)すさぶ⇒心の赴くままに物事を行う 9)心知らぬ⇒訳が解からない 10)なぞ⇒何か 11)とがむ⇒怪しむ 12)掻練(かいねり)⇒灰汁などで煮て糊を落として柔らかくした絹布、紅や濃い紫色 【かいねりがさね】の略 13)つづりし歌⇒途切れ途切れに口ずさむ歌 14)あながち(強ち)⇒無理やりな様 15)にほふ⇒美の最上の表現 16)しろふ⇒・・し合う 17)見め(愛)づ⇒見て褒める 18)へだつる⇒打ち解けない 19)なか⇒男女の間がら なかをへだつる⇒着物を重ねる 20)衣手⇒袖 21)見もし見よとや⇒積もりなんですか?強調 22)しもぞ⇒返って |
【イメージ】
源氏がひょいと台盤所に顔を出す様子が見えるようです。【くはや】いたずらっ子みたいな掛け言葉と
【あやしく心ばみ過ぐさるる】妙に気を使っちゃったよ。という茶化した物言いに、昨日の落ち込んだ命婦の心を明るくしようとする心遣いが。二人の仲は、あ・うんです。源氏の君がお訪ねなさるなんて!!それも微笑んで歌を口すさんでいくとは!!女房たちは、羨ましい限り。言い訳しながら、ほっとしている命婦。早速常陸宮邸に行ったことでしょう。「会わない夜が重なっているのに、私に更に着物の贈り物をしたということは会わないでいましょうというお積りなんですか?」無造作に捨て書いた字なのに返ってそれが優雅です。「つまらないものを贈らないで下さい。」とは決して言わない。言えません。この場面で【ただ梅・・】の箇所は、諸説あるようです。花と鼻ですが、【にほへる鼻】は【花】の方が良いのではという意見がありました。この文章の流れの中で、女房達がどうして花から立派な鼻について話している事が解かるのか難しかったです。歌を書いた【白き紙】に何か意味があるのだろうか?という意見が。女房達にとって白い紙は取り立てて書く程意味あるものであったのではないでしょうか。
P−110
1)晦日⇒陰暦で月の最終日ここでは大晦日 2)料⇒ある目的のために用意したもの、材料 3)具⇒一そろいになった衣服、器具などを数える語 4)葡萄(えび)色⇒葡萄葛(山葡萄)の実の絞り汁の色 紫色 日本の色辞典P−106 5)山吹⇒山吹の花の色 同P−186 6)紅⇒紅花から採った色 同P−38 今様色(同 P−46)より赤い 7)ねび人⇒年をとって経験をつんだ人、老人 8)さだむる⇒決め付ける 9)道理⇒筋道 10)したたか⇒確かなさま しっかりしたさま 11)おぼろけ⇒ふつうである 12)朔日⇒元旦 13)一年おきに陰暦正月14日または15日に行われた帝の前で舞った、男による踏歌:足を踏み鳴らして歌い舞う 14)節会⇒資料P−46年中行事 白馬節会(あおうませちえ):天皇が宮中の庭に引き出された白馬を見て邪気を払った後、群臣に宴を賜る 15)夜深し⇒夜が深く夜明けまで間があって暗い 15)うちそよめく⇒衣ずれや人のざわめき 16)たをやぐ⇒しとやかになる 17)もてつく⇒身につける 18)改めて⇒年を改めて 19)ひきかへたラム⇒前とはうって変わっている |
【イメージ】
常陸宮の姫君が何故歌一つ録に読めない女性に育ってしまったかがうかがえます。それは、姫君を取り巻くねび人達の【さだむる】価値観から来るもの。彼女達の価値観は常陸宮ご存命の頃と全く変わっていません。時間が止まっています。まず、着物の色に対する反応。源氏が贈った、葡萄色や山吹色に対し、姫君の贈った今様色はどっしりと重々しい赤で、【さりとも消えじ】いくらなんでも見劣りするものではないと。次に姫の歌は筋道が解かって【したたかにこそ】 しっかりしていると。源氏の返歌は情感ばかりで筋がないと。おまけに走り書きだと。自分達が選んで贈った着物と対照的な色の着物を贈られた老女房達のプライドを賭けた身贔屓の言葉の数々から、自然に今様の価値観が浮かんで来ます。新年の賑やかな宮中の中で、ふと寂しい常陸宮邸を思う源氏は、あんまり行きたくはないのですが、常陸宮様に対する誠意と夫となった自分の義務を感じています。そして、もしかしたら・・という期待。あまり長逗留したくないので【夜ふかして】遅く訪れたのでしょう。新年改まった事もあるでしょうが、【うちそよめいた】邸内の雰囲気、姫君の【たおやぎたまへる】気配に、もしかしたらあの鼻も【ひきかへたらむ】のではと期待する源氏です。お正月は、物事を【改めて】新しくするのです。
P−113
1)やすらふ⇒躊躇する 2)なす⇒わざとする 3)あばる⇒荒廃する 4)生ひなほり⇒成長して容貌や性格が良くなる 5)いとほしがる⇒気の毒がる 6)ものごり⇒こりごりすること 7)鬢ぐき⇒結い上げた耳の上あたりの髪の毛筋 8)しどけなし⇒乱雑である 9)唐櫛匣(笥)⇒唐風の化粧道具を入れる箱 資料P-18 10)掻上の筥⇒結髪用の道具箱 11)ほのぼの⇒それとなく 12)されて⇒洒落て 13)文⇒模様 14)さへづる春は⇒読み人知らずの【百千鳥さへづる春は物ごとに改まれども我ぞふりゆく(年をとってゆく)】 15)夢かとぞ見る⇒在原業平の【忘れては夢かとぞ思ふ思ひきや雪踏み分けて君を見むとは(古今集雑下)】 16)側目⇒横から見た顔 17)にほひやか⇒色鮮やかな様 |
|
【イメージ】
朝です。わざと出て行きたくない素振りで起きて妻戸を開けた源氏の前には【上もなくあばれたる】屋根もなく荒廃した屋敷が。日も差してきて、少し降った雪で部屋の中が明るくなってきます。横に臥している姫君の黒髪の美しさよ。【生ひなほり】容姿が良くなったのを見たい欲望が。しかし、あの姫君の顔を初めて見てしまった日の記憶がよみがえり、格子を引き上げる力を落とします。「いやいや、いけん、いけん」って感じ。お洒落な男は化粧箱にも興味がゆきます。父君の遺した物何も捨ててない。源氏の行動の一部始終を奥から【すこしさし出て】見ている姫君。二人の動きが見えます。姫君の衣装が今日は世間並みと満足。そして、姫君の【さへづる春は】です。【むむ】以来の生声。【さりや】感動の笑い、【夢かとぞ見る】歌の常套句。良く出来ました。でも、【側目】 にまたあの【末摘花】はしっかり、【にほひやかに】変わらず、扇の端から出ていました。【見苦しのわざや】また【うちうめきたまふ】のでした。
【まとめ】
源氏の【さりや】という喜びの笑いが印象的でした。今回は、【ねび人】に盛り上がりました。最近色々な事を【さだむる】傾向が自分の中に増えてきた様に思います。「いけん、いけん」です。「べき、べき人間」は若い人に嫌がられます。解かっていても、つい一言が。しかし、常陸宮家は【ねび人】達が守って来たのですよね。次に正月の晦日・元旦について。源氏は姫君が【生ひなほり】されると期待しました。あの鼻も【ひきかへたらむ】のではと。正月はそれ程に重要な改まる機会であったのです。私の子供の頃でもお正月は、全て新しいもので始まりました。新しい下着、下駄、足袋、羽子板等々。脱皮して新しくなる自分を感じました。そして1歳年をとって大人になるという自覚がありました。
いよいよ末摘花も次回で終わります。いとおしむ様に読んで来ましたね。寂しくなります。
さて、今年も恒例?【およすく会蓼科高原源氏夏季セミナー】が、9月6日〜8日開催されます。今年は、帚木の所謂【雨夜の品さだめ】を集中に勉強します。しかし残念な事に参加5名だけです。9月の報告に様子をお知らせ出来ると思います。
平成20年7月16日 例会報告 浜岡はるみ
贈り物
P−99
1)梳櫛⇒髪を櫛でとかすこと 2)懸想⇒異性を恋い慕う 3)ひがひがし⇒非常識だ 4)わづらふ⇒思い悩む 5)つつむ⇒秘密にする 6)言籠む⇒口ごもる 7)艶⇒思わせぶりなさま 8)陸奥紙⇒表面にしわのある厚手の上質紙。檀紙⇒檀(まゆみ)または楮(こうぞ)の繊維ですいた厚手の紙。
【イメージ】
源氏と命婦の言葉のやり取りに二人の何でも話せる関係が良く書かれています。時には戯れごとも口に出来る中。【言籠める】命婦が取り出したのは、姫君からの文。当時下記の様な紙が使われていたようです。
1)唐 紙:中国渡来の紙。また、それを真似して色模様を刷りだした紙。後に国産化。
2)紙屋紙:紙屋院(朝廷所属の製紙所)で作られた紙。
3)鳥の子紙:淡黄色で鶏卵の殻に似た色の紙。
4)陸奥紙 檀紙
姫君の文は陸奥紙。陸奥で生産される、表面にしわのある厚手のゴアゴアした上質紙。年を経ると黄色に変色する事から恋文には使わない。恐らく黒テンの毛皮と同様、家にあったものなのでしょう。
平安時代の紙は大変貴重で、リサイクルされていたようです。襖を唐紙と言ったことを思い出しました。
P−94
1)そほつ⇒濡れる 2)唐衣⇒着るに掛かる枕詞 3)うちかたぶく⇒首を傾げる 4)朔日⇒正月の一日
5)元旦のよそひ⇒一番親しい関係の人(北の方)が贈る礼服 6)わざとはべる⇒わざわざ用意する 7)はしたなし⇒体裁が悪い 8)引き籠める⇒家にしまっておく 9)からし⇒ひどい、切ない 10)袖まきほさむ人⇒涙に濡れた袖を枕にしていると共寝をして乾かしてくれる人 11)口つき⇒歌の詠み振り 12)博士⇒先生
【イメージ】
初めて姫君から来た歌は、伊勢物語が元歌で、枕詞が間違っていたり、【かくぞ】などと説明的な言葉が入っていたり、【心得ずうちかたぶく】出来でした。歌詠みとしての厳しい批評の後で、侍従も書の先生もいない中、姫君一人で良くここまで書きおおせたと最終的には感動する源氏です。大人の優しさです。命婦が手紙を差し出した後、更に由緒ありそうな重い衣装箱を差し出す時の台詞が、妙にへりくだった【はべる】が多用されていて、困った様子が良く解かります。実に読みづらい文章ですが。源氏は微笑みながら姫君の歌を眺めています。命婦が赤面したのは、恥ずかしいのと恋心もあるようです
P−104
1)今様色⇒当時流行の色で、濃い目の赤(紅より赤っぽい)日本の色辞典 吉岡幸雄著参照 2)こまやか⇒色が濃い 3)なほなほし⇒平凡でつまらない 4)つまづま⇒(着物の)端々 5)すゑつむ花⇒紅花(鼻)
茎の末の方から咲く花を順に摘み取ることから 6)袖に触れる⇒女と契りを交わす 7)色濃い花⇒美しい女 8)とがむ⇒非難する 9)ひと花衣⇒一回染めの薄い赤色の衣 10)朽たす⇒評判を落とす、汚す 10)かうやう⇒このよう 11)かいなで⇒平凡である事 通り一遍の普通の事を返せる かきなで⇒通り一遍、ひととおり 12)人のほど⇒姫君の身の上
【イメージ】
源氏は目の前の直衣のあまりのセンスのなさと古めかしさに絶句です。元旦用のお召し物は一番近しい北の方が贈るものであって、決して常陸宮の姫君が贈る筋のものではありません。彼女は源氏の愛情を信じているのです。必死なのです。姫君の歌の紙の端に走り書きで書いた後悔の歌は、紅花(鼻)。源氏の歌を面白いと思う命婦は、月の光に照らされた姫君の鼻を知っていたのですね。横からそれを盗み読んだ後の命婦の独り言に、姫君にせめてこの位の素養があったらと思う。平凡でも良いのです。最終的に、姫君の宮様としてのプライドを汚さぬように二人で頑張りましょうっていう所でしょうか。でも直衣は【取り隠さむや、かかるわざは人のするものにやあらむ】と【うちうめきたまふ】程のひどさなのですね。姫の事で【うちうめき】たまわれたのはもう何回目?命婦の後悔は相当なものです。
【まとめ】
命婦に完全に気を許している源氏と、心の何処かで恋い慕っている命婦の女心がそこここに表れていました。命婦のうろたえも言葉の端はしに良く書かれています。姫君のぶっ飛びの常識外れは、本物の貴族の暮しから来るものでしょう。宮家の老女房達の見識が疑われるのですが、紙といい直衣といい、誰か変だと思う女房は居ないの?そこが宮家なのでしょうが、この歳までセンスを磨く機会がなく、ほったらかしの姫君は呆れるほどに素直で憎めない。姫君に対する源氏の【微笑み】は、決して軽蔑する相手には出来ない、なごみの顔です。うち呻きつつも、その素直な姫君の窮状が解かっている大人の男の顔になってきました。
平成20年6月18日 例会報告 浜岡はるみ
よろぼふ門
P−91
1)よろぼふ⇒崩れかかる 2)中門⇒資料P−14,15参照 3)しるき⇒はっきりする 4)荒れ+まどふ⇒凄まじい荒れ具合 【動詞+まどふ ひどく・・・する 例:泣きまどふ、逃げまどふ】5)葎の門⇒つる草が生い茂った荒れ果てた家:雨夜の品定め 6)見忍ぶ⇒世話をしながら我慢する 7)見馴る⇒親しく交わる、世話をする 8)うしろめたし⇒気掛かりだ 幼い者や、若い女性達の将来を案じる場合に使う 9)たぐふ⇒寄り添わせる 10)おのれ⇒ひとりでに 11)名にたつ末⇒歌の文句 【我が袖は名にたつ末の松山か空より波の超えぬ日はなし】 雪の飛び散る様子を波の飛沫に重ねた
【イメージ】
ここは有名な文だそうです。中門が【いといとうゆがみよろぼいて】という表現は訳すのがもったいない位リアルな表現と田中先生。雪のシーンが大変美しく、全ての穢れを消してしまう程、それでも【荒れまどへる】屋敷。【雪のみ暖かげ】が芯からの寒さを表現しています。
【葎の門】帚木のP−153を読み返しました。源氏が思い出したのは、左馬頭が話した【さて世にありと人に知られず、さびしくあばれたらむ葎の門に、思ひのほかに、らうたげならむ人の閉ぢられたらむこそ、限りなくめづらしくはおぼえめ。・・・】この言葉。そして目の前の門とあの話の中の門のイメージがぴったり一致したのです。ここでまたまた【あるまじきもの思い】です。現実の【らうたげならむ】姫君のありさまは【取るべきかたなし】なのです。が、【故親王の魂のしるべ】を感じるのです。
松の木の擬人的な表現【松の木のおのれ起きかへり】について、江戸時代の浄瑠璃、歌舞伎狂言作者、近松門左衛門は【難波土産】の中でこの部分を【大内の草子に心無き草木を開眼したる筆勢なり】と書いているそうです。彼も読んでいたのです!!【さとこぼるる雪】さっと飛び散る雪の美しさを見て【名にたつ末の・・・・・】波のしぶきを連想出来るって!!うっそー。
雪はキラキラ光っていたでしょうね。
P−94
1)いといみじき⇒甚だしく、よぼよぼ 2)はしたなる⇒中途半端な 3)くくむ⇒包み込む、くるむ 4)頭⇒髪の毛 5)わかき者はかたちかくれず⇒白楽天の貧者を詠った「秦中吟」の【幼き者は形かくれず、老いたるもの体温かなることなし非喘(ひぜん)と寒気と併(ふたつながら)鼻の中に入りて辛し】の鼻から姫君の鼻への連想 6)うち誦じ⇒(うちずんず)口ずさむ 7)今⇒やがて、その内に
【イメージ】
まだ明けきらない空の下、真っ白な雪の中に老いさらばえたよぼよぼの老人と、寒そうに震えながら煤けきった着物を着た老人の娘か孫。女の様子は【いとかたくな】です。最初は門が【いとかたくな】なのかと思ったのですが。女の門を開けようとする姿のあまりの見苦しさにお供の人が助けに行ったという感じでしょうか。それにしても、目の前の老人と女を見て、自然と口から【わかき者はかたちかくれず・・・】で今度は鼻ですか!!前の【名にたつ末の・・・・・】から波のしぶきの連想で驚いた私はまたまた驚きました。こんな世界にはとても生きられない!!紫式部の知的レベルは、安い古語辞典なんかでは調べられない位凄いです。
姫君の鼻を思い出し源氏が微笑む。このシーン好きです。頭の中将の女性に対する考えは、帚木のP−145の【三つの品】 に書かれていました。改めて読み直したら面白いです。
P−96
1)思ひ捨つ⇒見捨てる 2)まめやか⇒まじめな、誠実な様子 3)なかなか⇒かえって、むしろ 4)まめやかごと⇒暮らしの実用方面(恋ではない) 5)さるかた⇒そういう方面 6)はぐくむ⇒世話をする 7)思ほしとる⇒決心する 8)打ち解けわざ⇒無遠慮な行為 9)側目(そばめ)⇒横から見た姿、横顔 10)もてなし⇒態度、振る舞い
【イメージ】
源氏は姫君の世話をしていこうと決心し行動に移します。プレゼントの山に埋もれた老女房たちの幸福そうな顔が目に浮かびます。これで生き延びる道が開けてきたのです!!暖かく暮らせます!
【まめやかごと】とはどんなものか、化粧品、寝巻き、下着、薪、その他もろもろなのでしょう。気が利く源氏の事。恋はそっちのけ。姫君の誠実さをいとおしんで、世話を楽しんでいる感があります。
ここでも又空蝉が出てきます。よっぽど逃げられたのが癪に障っているんですね。
【まとめ】
今回はあまり進みませんでしたが、実に充実した時間でした。当時の貴族の奥深い知識と、源氏物語が1000年に亘って多くの人達に影響を与えてきた事が、良く解りました。近松門左衛門の擬人法に関する「難波土産」の1節にこの松が出てきているなんて・・白居易(白楽天772―847年)が生前日本での自分の評判を知っていた事も驚きでした。中国との関係は相当深かったのですね。
帚木の【葎の門】を読み直し、【雨夜の品定め】もそのうちゆっくり読み直したいと思いました。
高校生の時勉強した清少納言の「香炉峰の雪は簾を高くかかげて看る」これも白居易(白楽天)の「白氏文集」からだそうです。当時知ったかぶり女は嫌だと思った私でしたが、参りました。当時貴族の間では白楽天の作品は所謂ベストセラーだった様で、式部は女房として仕えた藤原彰子(一条天皇の皇后)に「白氏文集」を教えていたと言う事です。(下記参考資料)
1000年に亘ってこの物語を語り、写し、伝え続けた事が後世の日本文学を豊かにし、素晴らしい作品を沢山誕生させてきた事が解りました。日本のシェイクスピアと呼ばれる近松門左衛門があれ程の作品群を残せたのは、源氏物語なしにはあり得なかった!時間はずっと繋がっているのです。
参考資料 出典:ウィキペディア(Wikipedia)
※白居易(白楽天)の日本への影響 出典:ウィキペディア(Wikipedia)
白居易の詩は平安文学に大きな影響を与えた。日本では『白氏文集』が白居易存命中に既に伝来していたと
され、風諭詩よりも閑適詩・感傷詩の方がもてはやされた。『枕草子』にも『白氏文集』が登場し、紫式部が
上東門院彰子(藤原彰子)に教授している(『紫式部日記』)ように、当時の貴族達にもてはやされた。
『源氏物語』も白居易の「長恨歌」が影響を及ぼしている。白居易自身、日本での自作の評判を生前に知って
いた。
※「諷喩詩(風諭詩)」は政治や社会の実相を批判・賞賛した詩。
平成20年5月21日 例会報告 浜岡はるみ
雪の朝
P−80
1)斎院⇒斎宮の住まい 2)かきたる⇒(雪や雨が)激しく降る(重苦しい空) 3)大殿油⇒宮中や貴族の殿中で灯した油の灯火 4)いざとし⇒目が覚めやすい、寝られない 【いぎたなし】⇒寝坊 5)埋もれ⇒引っ込み思案すぎる 6)すくよか⇒無愛想な様 更科日記では真面目一方で女性に浮ついた心を持たない良い意味 7)栄⇒張り合い 面目 8)からうして⇒やっとのことで 9)わたる⇒一面に・・する。 10)ふり⇒【振る】と【降る】 11)きよら⇒気品があって美しい(最高の美しさ)【きよげ】は第二等の美しさ
12)いなぶ⇒断る
【イメージ】
屋敷に居るのは年老いた女房たちだけ。消えた灯を点けに来る女房も居ない暗闇の中で、あの何がしの院で夕顔と過ごした、物の怪に襲われた恐ろしい夜を思い出し寝られない源氏です。暗闇の中で、夕顔との語らいや彼女の懐かしい姿に思いをはせます。あのような闇の中でも夕顔と男と女の味わい深い時間は持ち得たのに。今は無愛想な、引っ込み思案も度を過ぎた姫が隣に。闇の中の耐えられない一夜がやっと明けかけ待ちきれず自分から格子を上げると、外は真っ白な雪の世界!!まだ明け切らない薄暗い雪明りの中に見える【きよら】な源氏の若さに思わずうっとりと微笑む老女房達の心のときめきが、とっても人事とは思えず!!老女房達は姫に、早く、早くとせかせて【心うつくしきこそ】と言います。何故?前夜の闇と雪の対比が舞台を印象深くしています。筆者は書割まで考えているんでしょうか。凄い!!
P−84
1)後目⇒目だけ動かして後を見る 2)ただならず⇒普通でない 心が穏やかでない 3)うちとけまさり⇒親しくなったからこそ良く、美しく見える 4)あながちなる⇒ひたむきな一途な様子 5)居丈⇒座高
6)うちつぐ⇒後にひき続く 7)あなかたと見ゆる⇒目に飛び込んできた 8)普賢菩薩⇒一般に六つの牙を持つ白像に載った菩薩 9)真青(さお)⇒真っ青 10)見あらはす⇒正体をつかむ 11)見やる⇒視線をその方向に向ける
【イメージ】
最初姫の姿を後目に眺めます。実に臨場感のある描写です。スローモーションのように源氏の動きが見え、語り手の客観的な冷静さ【あながちなる御心なりや】一途な御心だけど・・、との温度差が滑稽です。まず、座高の高さに、【さればよと、胸つぶれぬ】そして御鼻が目に飛び込んで!!(普賢菩薩にお会いして来たばかりなので、すぐに想像できました。)【先のかたすこし垂りて色づきたる】こと【ことのほかにうたてあり】です。後目で眺め始めた姫の姿が源氏の言葉を通して次々に語られ、姫がリアルに浮き上がって来る手法がやっぱり映像的です。今まで原文がこんなにストレートに理解出来るシーンはあまりなかったのではないでしょうか。【雪はづかしく白うて真青】【こよのうはれたる】【下がちなる面やうは、おほかたおどろおどろしう長きなる】【いたげなるまで衣の上まで見ゆ】何でこんなに見届けてしまったのかと思う半面珍しいもの見たさに、自然に目がいってしまう【さすがにうち見やられたまふ】のです。 この後、およすく会独自の見解が次々に出てきますが、最後にまとめます。
P−86
1)かかり⇒女性の髪の方に垂れかかった様子 2)袿(うちぎ)⇒資料P−26私邸で着た平常服 3)さがなし⇒意地が悪い 4)聴(ゆる)し色⇒禁色(きんじき)に対し誰でも自由に用いてよいとされた衣服の色。普通は紅や紫の薄い色 5)わりのう⇒やたらに 6)上白む⇒色褪せる 7)一襲(かさね)⇒上着と下着が揃った 8)なごりのう黒き⇒元の色が判らない程に黒い 9)黒貂(ふるき)⇒クロテンの古名 毛皮を衣料として珍重した※渤海(698〜926年中国東北地方東部に起こった国727年以来日本と通交)からの輸入品と思われる最高級舶来品 10)かうばし⇒香が焚き付けてある 11)おどろおどろし⇒周囲をはっとさせる程異常 12)もてはやす⇒目立つ、引き立たせる 13)顔ざま⇒顔の表情 14)とかう(とかく)⇒あれやこれやと 15)ひなぶ⇒田舎じみている同義語:【里ぶ、田舎ぶ】 対義語:【雅ぶ】 16)ことことし⇒大げさだ 悪いものを表す 類義語:【ものものし】は美的でよいもの 17)儀式官の練りでたる臂(ひじ)もち⇒ 儀式官が練り歩くときに(笏しゃく資料P−22を持って)肘を横に張る姿勢 18)はしたなし⇒不似合い 19)すずろ⇒思いも及ばずひどい
20)垂氷(たるひ)⇒つらら
【イメージ】
姫の様子の描写は続きます。もう源氏は姫の全体像を正面から(後見なんぞではなく、)はっきり見ています。髪の美しさを褒め称え持ち上げた後、断り書きがあり、着ている物をとやかく言うのは・・・と言いつつ結構手厳しい。色褪せた上下に重ねた内掛けは黒く汚れ、何とその上に黒テンの毛皮!!!次に姫の姿勢、笑い方、いちいち細かいチェックで【ひなぶ】 田舎じみているだの、【儀式官の臂(ひじ)もち】だの。【いとほしくあはれにて】と言う割には恩着せがましく「私以外頼る人がない貴女を見染めた私にはよそよそしくしないでくれたら嬉しいのですが、打ち解けてくれないのは辛い」と。帰るには早すぎる理由付けに、【つらら】の歌を詠んで帰ろうとする源氏に姫が【うち笑いて「むむ」】。ただ「むむ」です。源氏は返しの歌も待たず帰ります。姫の始めての意思表示。「むむ」は何かをしなければという必死さであったのでしょうが、それは源氏には伝わりません。彼女は本気で源氏の事が大好きになっているみたいです。悲劇と喜劇は紙一重です。
【まとめ】
常陸宮の姫様について盛り上がりました。
・ ロシア系の混血では⇒鼻が高い!!大柄で座高、高い、顔が青白い
【渤海】との通交(毛皮の輸入等)があった事から可能性はあるのでは?
・ 栄養失調では⇒ガリガリに痩せて、青白い。
・ 鼻が赤いのは⇒毛細血管か?心臓が悪いか?
・ 髪が長く後姿は最高!!バックシャンだった。
・ 自分の容姿にコンプレックスなど決して持っていなかった。貴族は自分を人と比べる事などない。
末摘花の通説:容姿は悪いが性格は・・・というのは普通の人の話
今回から、原文の翻訳は先生の講義を元に各自が理解しているので省略します。その分【イメージ】を盛り上げようと思ったのですが・・・
次回末摘花が再登場する、【蓬生】(源氏物語絵巻)まで皆が元気でいなくては。という固い決意で今月は終わりました。相変わらずおもしろい【およすく会】の源氏物語でした。
平成20年4月16日 例会報告 浜岡はるみ
後朝の文 P−63
1)こよなし⇒(良くない点で)程度がはなはだしい 2)ゆるぶ⇒気が緩む 3)行幸⇒帝が移動する事 外出をいう
4)粥⇒米を炊いたもの 5)強飯⇒蒸し米 6)客人(まらうと)⇒外から訪れてきた人
打ちうめいて深夜のうちに二条の院に帰り床についた源氏もやはり、今まで経験した事がない、想像を絶した姫とのあれこれを思い出し寝られません。夕顔の様な女を求めたのに。高貴な姫なのに気の毒な方。等々思い乱れ。(朝になり)頭の中将がやって来ました。「随分寝坊じゃないか。何かあったからとしか思えないが?」と。源氏は起き上がって「気軽な独り寝に気が緩んだんだよ。内裏から来たのか?」と問えば「ああ、朱雀院の行幸の楽人と舞人が今日決まると昨夜聞いたので、父(大臣)に伝えようと思ってね。すぐに内裏へ戻るもりだ。」と忙しげ。それなら私もと、朝食の粥強飯を一緒に食べ、牛車を二台続け(連ねて)、その一台に並んで乗る二人。源氏を「まだとても眠たそうだね」と咎める風に、「隠し事が多い人なんだから」と恨めしそうに眺める中将。その日は多くの事が決定される日であったので源氏は一日中内裏で過ごした。
【イメージ】
打ちうめいて帰ってから源氏もやはり一睡も出来なかったのです。頭の中将とのさりげない言葉のやりとり。源氏は緊張しています。昨夜の事は中将には絶対秘密です。しかし、二人で内裏に向かい仕事に没頭すると、姫のことなどすっかり忘れてしまった様子。やっぱり若いのです。この時代食事の事を書く場面は少なく、朝食が出てきたのは初めてだと思います。粥が、普通のご飯で、強飯が、おこわなのですね。
P−65
1)かしこ⇒常陸宮邸 2)だに⇒せめて・・・だけは 3)ところせし⇒やっかいだ、面倒だ 4)とが⇒無礼な事
5)思ひわく⇒理解や判断をする 6)いぶせし⇒うっとうしい 7)えかた⇒型通りの歌 8)例の⇒いつものように
9)灰おくる⇒紫色に染める時色を鮮明にするために用いる椿の灰の効果が衰えて色が褪める。紫の色が褪める。
10)中さだ⇒ちょっとまえの時代に流行った手 11)上下ひとしく⇒同じ行に揃えて 12)見果つ⇒最後まで世話をする
13)む⇒意志 ・・つもりだ
常陸宮邸に後朝の文を出していない事に気がつく源氏。気の毒な姫の事を思い出したのはもう夕方。普通後朝の文は朝一番に届けなくてはいけないものなのに・・(しかも)雨も降り出し、面倒だとちょっと思われたのでしょうか。と語り手。一方常陸宮邸では、朝から待っても、待っても源氏から文が来ない。命婦も(姫は捨てられてしまったと)源氏の薄情さを憂い、姫を心配します。でも姫御当人は、恥ずかしいと思い続けるだけで、今朝来るはずの文が、日が暮れようとしているのに、相手の事を誠意がない、無礼だとも思いません。ただただ恥ずかしい。やっと届いた源氏の歌は、「姫が心を開いて何も言ってくれないのに、うっとうしい雨が宵から降って来ました。雲間を待っているのはどんなに待ち遠しい事でしょう」とあって、こちらにやって来る気配はない様子。本来契った日から三日間は男が女の家に毎晩泊りに来るのが普通なのに!!女房達は皆【胸つぶれ】がっくり。それでも「手紙を差し上げて下さい」と姫をそそのかす。しかし、姫は源氏から手紙が来ただけで動揺し、型通りの歌すら詠めない! 夜も更けて、侍従がいつものように教えて作った歌は、「晴れない夜の月を待つ私の心を思い遣って下さい。同じ心で眺めなくてもよいから」大勢の女房達から責められ、色褪せた【灰おくれた】紫色の紙に字はそれでも力強く、ちょっと前に流行った手で、同じ行に揃えて書いた文。あまりにひどい!趣も何もない!見る甲斐もない!と、うち置いた源氏。自分を悔やんでも、姫の気持ちを思うと心は穏やかではいられない。この様なことを悔しいと言うのではないかと語り手。それではどうしよう。悔しいけれど、この姫を妻の一人として最後まで世話をするしかないか。と思った源氏の心など知るはずもない常陸宮廷の人々は(姫は捨てられてしまったと)大変嘆きます
【イメージ】
姫はポーットと恥らっているだけ。今まで若い男に会った事など無かったのですから当たり前。女房達は必死。源氏に捨てられたら、やっと光が射してきたと思ったのに明日からどうやって生きていくのか。そこで姫に命令口調の歌を。前回の【えび香】同様由緒ある【灰おくれた】紫色の紙に、夜更けに、です。姫と女房達が対照的に描かれ。源氏が【うち置く】仕草まで目に見える様。 最高の喜劇です。しかし源氏は誠実な人ですね。普通は逃げてしまうでしょうに。姫の身分のせいでしょうか。
宮家の御達 P−71
1)そのころのこと⇒日課として 2)声⇒音楽、音色 3)まろばす⇒転がす 4)さうず⇒皆で遊ぶ、盛り上げる 5)切に⇒熱心、非常に大切である 6)ぬすまふ⇒一目を忍んでこっそりしつづける 7)おぼつかなし⇒疎遠、はっきりしない
左大臣が夜になり参内し、退出する際に【ひかれて】源氏は大殿に行きます。左大臣は行幸の催しに興味を示し、我が子息達のアピールの場と子息達を集め、各々が舞や楽器の練習に励む様申し渡し、日課として練習する事になります。左大臣の邸内は色々な音が入り混じって何時もよりうるさくて、公達達はいつもの遊び(楽器)ではなく、大篳篥や尺八(普通は身分の低い者が演奏:ほっぺが膨らんで見苦しい)を大きい音で吹き上げたり、太鼓(身分が低い者が演奏:重労働)をさえ高欄まで転がしてきて自分で打ち鳴らしたり、皆で盛り上げ遊び、練習します。練習が忙しいので、大切に思う女のところへだけ一目を忍んでこっそり通う事となり、あの常陸宮の姫には疎遠のまま秋が暮れてしまいます。
【イメージ】
合奏を楽しむ公達達の姿が生き生きと現されています。楽器の音まで聞えて来るようで、その合間に若い男の子達の声までも・・・資料P30の管絃・舞楽を参考にして下さい。そんな騒ぎの中でも源氏が訪れたい女の人は、六条御息所でしょうか? 梅の香から始まったこのお話は、もう秋も終わってしまったのに進展は見られません。
P−73
1)試楽⇒予行演習 2)見たまふる人⇒傍で世話をする人 3)くたいて⇒駄目にする
姫の方が頼みとする源氏は、相変わらず当てにする甲斐もなく時間は過ぎて行きます。行幸が近くなり、演奏の予行演習に大騒ぎする頃になって、命婦は源氏の前に現れます。「姫は如何にしているか」と、いとおしいとは思うのですが。命婦は姫の様子を話します。「この様に姫を無視して見放している貴方様の冷たい御心は、傍で姫の世話をする者でさえ辛い事」今でも泣きそうに。(もともと)命婦が、(そこそこの所で)止めようとしたのに自分がそれを駄目にしてあげくにこれでは、私のことを非情な思いやりのない男と思っているのだろうと。語り手が源氏の心を説明します。姫が文句も言わず、着物に丸まって塞込んでいる様子を気の毒に思い、「忙しくて暇がないので、しょうがないんだよ」と嘆き、「世の中の事を何も知らない様な姫の心を懲らそうと思って行かなかったんだ」と、微笑みなさった。そのお顔は若く、美しいので思わず我(命婦)もつられて、にっこりしてしまう。女に恨まれる年頃は困ったもの。思いやりも少なく、好奇心のまま行動してしまうのも道理だ。と、命婦は文句を言いに来た事を忘れそう。(しかし)この急ぎの接見の後源氏は時々常陸宮邸を訪れる様になります。
【イメージ】
源氏と命婦の話の駆け引きが面白い。色好み同士の【阿吽】の会話です。やはり源氏は、特にその微笑みは美しい!!
源氏にとって常陸宮の姫は義務ですが、【おぼしうづもれたまふ】姫から推測すると、彼女とって源氏は既に恋する男になっている様な気がしますが如何でしょう
P−75
1)ところせし⇒ぎょうぎょうしい、大げさだ 2)見あらはす⇒正体をつかむ 隠れているものを見出す 3)うちかへし⇒繰り返し何度も 思い返してみて 4)見まさり⇒前より勝って見えること 5)けざやか⇒鮮やかに、はっきりしている様子
6)まばゆし⇒恥ずかしい きまりが悪い 7)立処⇒たっているところ 8)御達⇒老女房 9)御台⇒お膳 10)秘色⇒中国の越の国で作られた青磁の磁器。唐の時代に宮廷用となり、民間で用いる事を禁じたためこの名前がある。平安時代に伝来し、後には天皇の食事を盛るのに使用。11)人わろし⇒外見がわるい お膳も色がはげて 12)くさはひ(くさ)⇒種類 趣
13)まかでて⇒上から下に主人の残り物を食べる 14)いひしらず⇒言いようの無いほど 15)褶(しびら)⇒主人の前に出る時つける前掛け(裳の代用)下級の女房の略礼装 16)かたくなし⇒見苦しい 17)内教坊⇒宮中の殿舎の一つ。舞姫に女楽や踏歌(足を踏みならして歌う)を教えた場所 18)内侍所⇒三種の神器の一つ(やたの鏡)を安置してある御殿 19)かけても⇒(下に打ち消しの語を伴って)まったく 夢にも 20)人のあたり⇒宮中以外の普通の場所 21)などて+か⇒どうして・・か(いや・・ない) 22)そそや⇒それそれ、あらまあ 23)(火)とりなほす⇒持ちかえる 明かりの向きを変える 24)放つ⇒戸、簾、家などを開ける 取り外す
この巻は、【若紫】と並びの巻です。北山療養で幼い若紫に出会い、誘拐するように二条の院に引き取り慈しんで教育に打ち込んでいる頃の事。あまりに若紫がいとおしく、六条御息所の所へも【離れまさり】ますます疎遠になっているのに、まして荒れた常陸宮邸には気の毒と思いながらも行くのが憂鬱になるのも解りますと、語り手。姫の大げさな恥じらいに、会いたいという心も特に無く時が過ぎてゆく中で、繰り返し何度も姫が前より勝って見えるかもと期待する事もありましたが、(いかんせん真っ暗な中での)手探りだけでは解らない。何か変だ、姫を一目見たいと思うけれども、はっきり顔を見させるのもきまりが悪い。遅くまで、緊張もなくくつろいで皆が起きている【宵居】夜にそっと邸内に入って行き、格子の隙間から覗いて見ます。が、姫が近くにいるはずも無く、ひどく壊れた几帳ですが何年も同じ場所に置かれていて、どかしたりして配置が乱れる事がないので奥が良く見えません。老女房が四、五人かたまって食事をしています。お膳、青磁のような食器は(高価な)唐土の物の様ですが、色が剥げたりして外見が悪く、何の趣もなく、いかにもみすぼらしい。主人の残り物を上の者から順に食べている様子。隅の方に居る、とても寒そうな女達の、言いようも無く煤けた白い着物の上に汚れた褶を引いて結んだ腰つきは見苦しい。それでも、櫛をずりおちそうにさしている額の形の古めかしいファッション(こんな貧しい暮らしでも昔のしきたりをしっかり守っている)は、宮中の内教坊か内侍所に行くと見られるかもしれないが、決して普通の場所では見られない。「ああ、何て寒い年でしょう。長く生きているとこんな目に会うんだわ」と泣く者、「亡くなった宮様が生きていた頃の暮らしをどうしてつらいと思ったのかしら。この様に何の頼る人が無くても毎日は過ぎていくものなのに(今に比べたらつらくは無かったのに)」と言って、寒さで飛び上がる程に震える者もいます。女房達のあれこれと外聞の悪い事を嘆き合うのを聞くのも心苦しく、その場を立ち去り、今来た様に門を叩いた源氏に女房達は「あらまあ」と、明かりの向きを変え、格子を取り外し中へ招き入れました。
【イメージ】
相変わらず二人は【手さぐりのたどたどしい】関係です。姫の顔を一目でも見たい。その源氏の目が(常陸宮様が亡くなってから時間が完全に止まったままの)邸内を舐める様に動きます。薄明かりの中で汚く見えるという事は女房達の着物は相当汚いのです。それでも宮中のしきたりをきっちり守った暮らしです。若紫のかわゆさと、常陸宮邸の老女房の対比が悲しい程です。繰り返し思います。源氏は本当に、絶対優しい人です。
【まとめ】
天田さんが【えび香】を持って来て下さいました。私の感想は『とっても地味で、丁子の香が少し。ずっしりと威厳のある香。決して若い女の香ではない』でした。末摘花は喜劇です。他の巻より軽んじられている感がありますが、本当に面白い巻です。次回はいよいよ姫とご対面に。丁寧に、楽しみながら、大切に読み進んで行きたいです。
およすく会は、4月18〜20日京都へ【第4回目源氏物語の旅】を企画しました。今回は嵯峨野界隈でした。
「清涼寺」地元では「嵯峨釈迦堂」の霊宝館では源融が自分の顔に似せて作らせたという国法【阿弥陀如来像(嵯峨光仏)】にご対面しました。これが光源氏のお顔と眺めて参りました。末摘花に登場する象に乗られた【普賢菩薩騎象像】にもお会いして来ました。また来年も再来年も皆が元気で京都への旅が続けられますよう祈ります
平成20年3月19日 例会報告 浜岡はるみ
手引き 続 P−52
1)つつましげ⇒気後れする様子 2)心ばへ⇒心遣い、趣向 3)ゆかし⇒興味や関心が惹かれる、見たい 4)心げさう⇒異性を意識して言動や養子に気を配る事 5)よろし⇒〔よし〕ではない。上から二番目。悪くない 6)つくろふ⇒着飾る
7)きこゆ⇒謙譲の意。お・・する 8)正身(さうじみ)⇒当人 9)なまめく⇒優雅で気品がある 10)栄⇒栄誉、光栄 11)うしろやすう⇒不安がない 12)罪さる⇒罪から逃れる 13)いでこむ⇒くるであろう
セットは出来上がりました。命婦の視点での見た屋敷の各人の様子といえば、姫は大層気後れしています。この様に初めて男の人にものを言う心遣いを全く知らないのですから。でも、命婦の言う事を聞いてそのままその様にすれば良いと。乳母の様な老人などは、自分の部屋で夕方の居眠りをする程で(姫が男を迎えるという緊張感は全くなく)、若い女房達二三人(ふたりみたり)は、源氏の世の中に認められた美しさを一目見たいと、【心げさう】し、お互いの容姿、髪型などに気を配る有様。姫はまあまあの着物に着替えられ着飾られたものの、当人は何の【心げさう】もなさらない。男(源氏)は、忍び姿ではあるが、限りなく美しい自分の姿を綿密に準備した様子。それは優雅で気品があり、この繊細なおしゃれが解る人に見せたい程。何の栄誉もないこの屋敷に渡る源氏を、何と気の毒な事よと。ただ姫があの様に【おほどかに】のんびりと構えている事に不安はなく、(源氏に対して)出すぎた振る舞いはしないだろう。そして、今まで自分が源氏から攻め立てられていた罪から逃れるために姫を利用する様で、この事が姫の物思いの種になってくるであろう事を心配する命婦です。
【イメージ】
後ろ向きの姫、その姫を恋する男が初めて訪れるという大切な日に、このゆったりとした、緊張感のない屋敷の者達。対して、一途に姫を思う源氏が忍びの姿のそこかしこに隠した、自分をより美しく見せるファッションは、命婦のため息が聞こえる程。同時に姫を人身御供に差しだす様な後ろめたさのため息も。舞台の登場人物の今の状況説明が命婦の目で生き生き捉えられ、彼女の困惑が伝わってきます。
君がしじま P−55〜60
1)人の御ほど⇒姫の階層 2)され(る)⇒しゃれる 3)くつがえる⇒度を過ぎて 例:泣きくつがえる 4)今やう⇒今風の 5)よしばむ⇒由緒ありげな様子をする、上品ぶる 6)えび(ひ)の香⇒お香の一種 7)しじま⇒沈黙
8)玉だすき⇒(たすきは両肩で)食い違う 古今集【ことならば思はずとやは言ひ果てぬなぞ世の中のたまだすきなる】⇒どうせ同じことなら、愛していないと言い切ってしまわないのか。どうして男女の仲はたすきのように食い違うのだろうか
9)はやりか⇒せっかちな 先走る10)とぢむ⇒終りにする 11)まうく⇒用意する 12)かつは⇒一方では
13)あやなし⇒理屈にあわない 訳が解らない、つらい 【わりなしの】は類義語 14】おもりか⇒重々しい 15)ほどより
は⇒身分の割には 16)あまゆ⇒いい気になる 17)おし⇒押し込める、唖の様に口を利かない 18)まめやか⇒誠実な様子
19)やをら⇒ゆっくりおもむろに 20)たゆむ⇒油断する 21)いとほし⇒かわいそうだ気の毒だ 22)音聞き⇒世間での評判
23)我にもあらず⇒呆然としている 24)かしづく⇒大事に養い育てる 25)見ゆるす⇒見てもとがめずにいる
26)うめく⇒ため息をつく 27)こわづくる⇒(相手の注意を促すために)咳払いをする
いよいよご対面です。源氏は、姫の階層を考えれば、【されくつがえる】恋にしゃれすぎている【今やうのよしばみ】今風の気取り屋などよりずっと奥ゆかしい。女房に強く促されてこちらにいざって寄ってくる気配と同時に密やかに香ってくる【えび香】がなつかしく、【さればよ】ああやっぱり思っていた通りの身分の高い奥ゆかしい女だと感激します。そして姫にこれまで思い続けていた事を非常に念入りに語り続けます。が、言うまでもなく答えは【絶えて】全くないのです。【わりなのわざや】「どうなっているのか解らない!」と嘆きます。「何十回貴女の沈黙に根負けしただろうか。ものを言うなと貴女が言わない事を頼みに今まで来ましたが、その気がないならないと、はっきり言い放ってください。玉だすきのように食い違った仲は苦しいです。」と言います。それを聞いた、女房達は気が気ではありません。ここで何も答えなければもう源氏は二度と来なくなってしまいます。姫の乳母子の侍従でせっかちな若い娘は、姫をじれったく、はらはらして障子(襖)に近寄って姫の代わりに返歌を詠みます。「鐘を突いて議論を終わる様に貴方様にものを言うなと言うことは出来ない一方で、答えを用意するのはつらい事です」とにかく何か言わなければ。訳が解らない歌ですが、要するに貴方様のお話は受容れますと言う事のよう。若々しく特に重々しくない声を姫の答えと理解した源氏は、身分の割には甘えた、馴れ馴れしいと聞いたものの初めての返事にびっくりして、「突然の歌に口ごもってしまいます。貴女様が何も言わないのは言うことより以上に愛情深いと解ってはいるのですが、押し込められて、唖の様にものが言えないのは苦しい事です。」そして、さらにとりとめの無い事を、あてにならないけれど、話術を駆使し面白く誠実な様子で話し続けますが【何のかひなし】全く効果なしです。(この襖の向こうに確かに姫は居るのに!)又もこんな状態で男を拒んでいるのは、普通の女とは変わっていて男に何の興味も無い、男を問題にもしない女なのか!と、悔しくなり、我慢の限界と、【やをら】ゆっくりとおもむろに、襖を押し開けて姫のいる部屋に入ったのです。
命婦は、【あなうたて、たゆめたまへる】「なんというひどい事、油断させておいて」と驚いたものの、姫が気の毒で、そこにいたたまれず、自分の部屋に立ち去ります。姫と一緒に居た若い人達は、これもまた世に比べるものがない程の世間の評判の源氏の美しさに、突然進入してきた罪も許されると、大げさに嘆く事もなく、唯あまりに急な事なので姫が男と契る心づもりもないのにと心配します。【正身】姫本人は、気が動転し、呆然として恥ずかしく気が引けてどうして良いか解りません。源氏は思います。今はこの様に、おたおたして恥ずかしがる女が【あはれ】可愛いものだ。世慣れず、大切に育てられたのだからと、姫の動揺をとがめはしないものの、男女が共に過ごす時の風情は全く無い様子が理解出来ずに気の毒になる程。【何ごとにつけてかは御心のとまらむ】「何でこの様な姫に心をとめるのか解らない」と語り手が。源氏はため息をつきながら深夜(帰るには早い時刻)に出て行かれた。命婦は、どうしようかと、床の中でその音を聞いていましたが、知らんふりをして「お送りを」の咳払いもせずに。源氏はそっと忍んで出て行きました。
【イメージ】
二人が障子(襖)を隔てて会う場面。姫がいざり寄る音、えびの香の香り。そこで、【およすく会】独自の面白い意見が。えびの香は先祖が使っていた高価なお香であるかもしれないが、今の屋敷の状況から、改めて着物に香をたきしめたとは思えず、長持ちの中の(ナフタリンや樟脳の様な)香りではなかろうかと。えび香を天田さんがお持ちという事で、次回は実際に香を聞く事が叶うと思います。楽しみです。
ついに源氏は姫の部屋に【やをら】入って行きました。【やをら】というと突然のようですが、そうではなく、「ゆっくりと」の様です。「ゆっくり」にしても、空蝉、若紫の時もそうでしたが何時も彼の行動は咄嗟で機敏です。
【あうたて】です。【ものづつみ】の姫の理解出来ない行動を目の当たりにした源氏は、ため息をつきながら帰って行きました。でも契ったのでしょうね。屋敷中の耳と言う耳は、姫と源氏の一挙一動に向いて、しーんと静まり返り、源氏が帰った後、姫は勿論ですが命婦をはじめ殆どの女房たちは朝まで眠れなかった事でしょう。それ程この屋敷にとっては一大事件であったのです。
【まとめ】
まとめを書いていると先生の解説を聞いていた時には見えなかったものが段々見えてきます。与謝野晶子の源氏訳が、インターネットに載っています。それを読んで思う事は、彼女には時間があんまり無かった事。54帖まで書き終えなくてはならないと思うと、イメージを広げる余裕も無かった事。そして、若さもあったと思います。今【老人おいびと】の私に源氏の若さは輝くように映りますが、もうちょっと若い時に果たして今のイメージが沸いたかどうか。この会に参加する時「50歳過ぎたら源氏よね。」と言われた事がこの頃解ってきました。この年齢になって源氏物語に会えた事は本当に有難く幸せです。
平成20年2月20日 例会報告 浜岡はるみ
返りこと 続 P−34
1)うれはし⇒憂わしい、たまらない 2)まめやかに⇒真面目な顔をして 3)おぼつかのう⇒はっきりしない 4)もて離れる⇒冷淡な 5)すきずきし⇒好色めいている 6)短き心⇒短期間に変わる心(移り気) 7)のどやか⇒おっとりしている 8)思わず⇒思いがけない意外な 9)笠宿り⇒立ち寄ること、またその場所 10)つきなげ⇒ふさわしくない 11)ありがたう⇒めったにいない、珍しい 12)らうらうじう⇒利発そうである13)かど(才)めく⇒才能がある、気がつく 14)子めかし⇒子供っぽい、あどけない 15)おほどか⇒おっとりしている 16)まぎれ⇒入り組んだ事情による間違い、乱れ
源氏は中将ほど姫に惹かれているわけではないのです。この様に薄情な姫にむしろ興ざめしているのです。が、中将の何度も言い寄っているという話を聞くと、言葉数多くを使い口説く男に女というものはなびくのでは。そうなったら中将は得意顔で、最初に言い寄った源氏が女に振られ、その女が自分になびいたと言うであろうと。それはたまらない事。そう思い、命婦に真面目な顔をして相談します。「姫君のはっきりしない、冷淡な態度は辛い。私を好色な男と疑っているのに違いない。でも私はそんな移り気ではない、何時も真剣なのに。女の心はおっとりする事がなく、思いがけない事で私を移り気だと誤解し、すぐに離れて行ってしまって、結局私の過ちとなってしまう様なのだ。気を使わないですむ、親兄弟の口出しや恨みもない、穏やかな性格の女は絶対いとおしい人なのだが。」と言うと命婦は「いやいや、とてもとても、こちらはその様に趣がある方の立ち寄られる宿には相応しいとは思えません。姫は一途な引っ込み思案で、引きこもってしまっている珍しいお方です。」と姫の様子を説明します。どうやら姫は利発そうで気がつくような人ではない様だ。子供っぽくおおらかであるからこそ、いとおしいのだろうと夕顔の面影を思いながらつぶやく源氏です。この後瘧病になってしまい(時間的に若紫と重なり)ます。人は知らない藤壺への思い(密会も?)と常陸の姫を思う余裕もないまま春と夏が過ぎました。この春三月の終りに北山へ治療に出掛け、少女の若紫を見掛けたのでした。
【イメージ】
中将には負けたくない!その気持ちが、自分はそんなに乗り気ではない姫に対して妙に積極的な行動を取らせます。『親はらからのもてあつかい・・・』に今彼の置かれている、左大臣の婿としての煩わしい立場が良く表れています。命婦の話から想像する常陸の宮の姫は、益々夕顔の『子めかしうおほどかならむ』に近い『らうたき』人の様に
思われ、まだまだ夕顔を『おぼし忘れず』なのです。そして『人知れぬもの思ひのまぎれも』は藤壺との密通を想像させます。『まぎれ』という言葉は意味深ですね。言葉の端にしか書かれていない藤壷の事。原文で読むと生々しく感じられます。物語が若紫と時進行の形で書かれている事に驚かされます。そして北山のシーンを思い出します。
ものづつみ P−39
1)聞きにくかりし⇒聞くのがいや⇒眠れない 2)おぼつかなし⇒はっきりしない 3)世づかず⇒男女の情を解さない、世間並みでない 4)心やまし⇒思い通りにならず不愉快だ 5)ものし⇒不愉快だ 6)もて離れる⇒(縁がなくて)離れる 7)似げなし⇒つりあわない、似合わない 8)わりなし⇒分別がない、むやみやたらと 9)かかやく⇒恥ずかしがって赤面する 10)そこはかとなし⇒何という事もない 11)つれづれ⇒孤独でもの寂しいこと 12)同じ心⇒同じ境遇
13)うたて⇒事態が自分の望んでいないほうへどんどん進んでいくのを嘆く気持ちを表す 14)たばかる⇒工夫する、だます
15)もてなし⇒態度、ふるまい
秋になりました。静かに夕顔を思い続け、あの五条の家で耳について眠れなかった砧も恋しく思い出されます。その夕顔に重なる常陸の姫には度々文を出すのですが、相変わらず反応はなく返事もありません。『世づかず』、『心やまし』そして中将に負けてはいけないと焦る源氏は命婦を責めます。「どうなっているんですか。こんなひどい目にあったことは無い。」めちゃくちゃ不愉快なのです。今までにはあり得ない事なのです。そんな源氏を可哀いそうと思い命婦は、「お二人の縁がなくて、釣り合わないと申した事はありません。ただ姫はむやみやたらと引っ込み思案で頂いた文を開封して手にとって見る事も出来ないと見受けられます。」と、そんな女がいるとは信じられない!「その事こそ『世づかぬ』事。物が良く解っていない成人前の少女だったならば親の庇護の元で自分の身を思うままに出来ないし、その様に恥ずかしがるのも解るが、何事も思慮深く、親を亡くし孤独で寂しく心細いと解る同じ境遇の私だからこそ返事が欲しいのです。姫との関係は、世の中の煩わしい男女関係にならないで、その荒れた邸の簀子に唯じっと立っていたいだけなのだ。こんなに思いつめているのに姫の真意が解らない。姫の許しがなくとも直接会って確かめたい。何とか会える様工夫をしなさい。イライラやきもきする。姫に無理強いする様な、貴方が困るような事は決してしないから。」と話されます。
【イメージ】
秋は物思いの頃。五条の家で聞いた騒々しい砧の音も今は懐かしく、浮かぶのは夕顔の面影。その夕顔と重なる孤独な常陸の姫のイメージは源氏の中で段々膨らんで来ています。自分は孤独な姫を救い出す貴公子です。自分の幼い頃の孤独をも思い出しながら返事を待つ辛さ。会いたいのです。『心焦られる』のです。若いのです。
P−43
1)なほ⇒相変わらず 2)おほかた⇒一般的なありふれた 3)宵居⇒宮中の宿直のようなもの 4)はかなき⇒ちょっとした 5)わざとがまし⇒大げさに、意識的に 6)なまわずらわし⇒何となく面倒な様 7)よしめく⇒上品な風情である
8)なかなか⇒中途半端だ、不十分である 9)まめやか⇒誠実な様子 10)ひがひがし⇒ひねくれている、素直でない
11)旧る⇒古くなる 12)浅茅⇒丈の低い茅萱、荒れ果てた住まいや場所の描写に用いられる 13)世にめづらしき御けはひ⇒
源氏のこと 14)なま女ばら⇒下々の(未熟な)女房たち 15)御心につく⇒気に入る 15)あだめきたる⇒うきうきする
16)はやる⇒あせる、夢中になる、勇み立つ 17)うち思う⇒心の中でふと思う
命婦の側からの視点です。源氏は相変わらずありふれた話の中から、これはと思われる女の話に耳を留める癖があったのに、寂しい宵居の晩にちょっとしたついでに話した常陸の宮の姫の事をこの様に大げさに言い続けられる事は何となく面倒で、姫君の様子と言えば『世づかわし』、『よしめき』など全くない有様。こんな中途半端な手引きは姫君に気の毒な事が起こるかもしれないと思いつつも、源氏がこんなに誠実に真剣な様子で言ってくれるのを聞き流すのもひねくれて素直でない。父親王がお元気だった時でさえ古くなっていて訪れる人もなく、今や浅茅を分けて訪れる人も絶えたこの邸内は、源氏の気配(文)だけで皆華やいで下々の女房達も嬉しく自然とニコニコして「もっと聞かせて下さい」とせきたてるのに、当の姫君は呆れる程ひたすらに『ものづつみ』し、全く源氏からの文を見ようともしません。命婦は決断します。しかるべき機会を作って、几帳を隔てて源氏が話す事として、もし源氏が姫を気に入らない場合は、それはそれで終りにすれば良し。仮にもし通うようになったとしても、とがめだてする人も居ないのだし。など手引きの段取りをうきうきしながら、夢中に、しかし密かに考えるのでした。彼女の父上は常陸の宮の縁戚に当たるのですが、この事は言いませんでした。
【イメージ】
後悔してももう元には戻れないのです。命婦の心の中です。二人を引き合わせる事を躊躇していた彼女ですが、決めたのです。まずは姫をこの境遇から救い出してあげたい、そして源氏の望みを叶えさせる。姫の事を【女君】と書いて男君の対象とする命婦の意識が表れているそうです。しかし、姫の『ものづつみ』は相当なものですね。
手引き P−46
1)心もとなし⇒待ち遠しい 2)消息⇒手紙、伝言 3)籬(まがき)⇒柴や竹で編んだ目の粗い垣根 透垣(すいがい)⇒板や竹で間を少し透かして作った垣根 4)けしうはあらず⇒そんなに悪くない 5)かたはらいたし⇒苦々しい、困ってしまう 6)しかしか⇒これこれ 7)いなぶ⇒断る 8)なみなみ⇒普通の事 9)たはやすし⇒容易である、気楽である 10)物越⇒几帳や簾を置いて間を隔てている事 11)限りなき人⇒身分の高い人 12)世を尽くす⇒一生を送る
13)おぼしはばかる⇒あれこれお考えになって遠慮なさったり心配なさったりする 14)つきなし⇒似つかわしくない
15)便なし⇒気の毒である、感心しない 16)おしたつ⇒強引に、無理押しする 17)あはあはしき⇒軽々しい
18)よも⇒決して 19)茵(しとね)⇒座ったり寝たりするときに畳やむしろの上に敷く綿入れの敷物 資料P-19
20)ひきつくろふ⇒体裁を整える
八月の二十何日かの夜姫君は中々昇って来ない月を待っています。星の光ばかりさえざえと美しく、松の梢を吹く風の音も心細く、昔の事を語り出しているうちに、声をあげて涙ぐみます。チャンス到来と命婦は源氏に来訪を促す手紙を送ったのだろうと語り手が推測します。夜も更け源氏はいつものように忍んでやって来ました。月が次第に昇ってきて、荒れた垣根を照らし、それを厭わしくぼんやり眺めていると、姫が命婦にせきたてられて弾く琴の音がかすかに。そんなに悪くない音色。
しかし、命婦は、もう少し親しみやすく華やかな感じが加われば良いのにと、乱れた心は不安です。源氏は人目も無い所なので、あたりを気にしないで邸に入り、命婦を呼ばせます。姫の傍で源氏の来訪を聞いた命婦は今初めて知った様に困った振りをします。そして、「困ってしまいました。何時も御返事がない事を恨んで、姫への手引きを頼まれましたが、私の一存ではどうにもならないと断ってまいりましたが、ご承知なさらず、自ら御返事頂けない理由とお気持ちを直接貴方様からお聞きしたいと言い続けられております。何と返事を致しましょうか?普通の人の気楽な振る舞いではないのです。すげなくお断りするのは心苦しゅうございます。几帳を隔てて源氏の君が申される事をお聞きになっているだけで良いのです。」と言うと、姫はたいそう恥ずかしがり「人にものを聞く方法が解らない。」といって奥のほうへいざって入って行く。その様子が子供じみて思わず苦笑してしまう命婦。そして、説教します。「貴女様が大変未熟である事が心配です。身分の高いお方でも親がおられて世話してくれる時ならばこの様に子供っぽいのももっともですが、心細い今の生活の有様で何もしないで男女の関係を避けてあれこれ心配しながら一生を送る事は貴女様には似つかわしくございません。」と。流石に人の言う事を強く拒めない姫は、「返事はしないでただ聞いているだけなら、障子などをさしたら出来ます。」と。命婦は、「簀子ではお気の毒です。強引に無理強いするような軽々しい事は決してしませんから。」と良く言い聞かせて、二間の部屋の仕切りの障子(襖)を自ら強く閉じて茵(しとね)を置いて体裁を整えます。
【イメージ】
資料P-16に寝殿内部復元模型があります。簀子、障子、茵(しとねP-19)等チェックして下さい。また、P-17には透垣(すいがい)と籬(まがき)があります。前回中将が待っていたのは、透垣(すいがい)の傍。今回源氏が入ったのは、籬(まがき)からです。女が生活を支えて生きて行くには、男を求めるしか術がない時代です。命婦の説教は叫びでもあります。しかし、心配です。こんな姫が源氏とどんな話が出来るのでしょう?ここの自然描写も本当に美しく、星の瞬きまでもが見える様でした。月については多いのですが、星が書かれているのは珍しいそうです。
【まとめ】
2008年は源氏物語生誕1000年の年と言われています。それは、紫式部日記の1008年に記載されている、
若紫の巻が完成し藤原公任(ふじわらのきんとう)【滝の音はたえて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれの作者】が紫式部邸を訪れ、「若紫やさぶらう」と言ったのに式部は知らん顔をして出て行かないでいたという内容からだそうです。1000年の時間の経過を全く感じさせない素晴らしい読み物である事が、読めば読む程解ります。
やっと姫に会えそうです。さてこの恋の行方はどの様になるのか次回をお楽しみに。
平成20年1月16日 例会報告 浜岡はるみ
末摘花
好敵手 P−22
1)人⇒姫 2)やをら⇒そっと、静かに動く様子 3)まかづ⇒内裏(高い)から自宅(低い) まいる⇒低いから高い
4)やがて⇒そのまま 5)引き分かれ⇒牛車で離れ離れになる 6)いづち⇒どちら 7)ただならで⇒心が穏やかではない
8)あやし(賎し)き馬⇒みすぼらしい馬 9)ないがしろ⇒無造作なさま 10)異方(ことかた)⇒何時もと違う方向
11)ものの音⇒琴の音 12)した⇒心の中で13)ふと⇒さっと、素早く 14)大内山⇒内裏 15)影⇒月影月の光 16)入るさ⇒入る方向 17)したひありく源氏⇒後をついて行く 18)はかばかし⇒てきぱき進むさま 19)やつれる⇒身分を下げた貧しい身なりをする20)重き功⇒功績 優位に立てる
帰ったはずの源氏ですが、姫の様子をもう少し知りたいと、もやもやしてすぐに帰る事が出来ず、姫の居る寝殿の方へそっと歩いて行き、殆ど折れた垣根の折れ残りの陰に。なんとそこに先客が! 誰だろう?姫に心を掛けた男か?と隠れます。語り手が、それは頭の中将と教えます。源氏はこの人物が誰なのかまだ知りません。頭の中将はこの夕方一緒に内裏を出た源氏とは牛車で離れ離れに別れました。しかしそのまま大殿にも寄らず、二条の院でもない方向へ行く源氏。彼が何処へ行くのか心穏やかでなく、行くつもりの所へも行かず、みすぼらしい馬と普段着の狩衣(資料P-23)を無造作に着て身をやつし、源氏の後をつけました。そんな中将を源氏が気付く由もなく、いつもと違う方向の家に入って行きました。思いも掛けない事。しばらくして流れて来る琴の音を立ったまま聴き、きっと帰りにはここから出てくるだろうと待っていたのです。 先客が誰か判らず、自分と知られない様、抜き足で後ずさりする源氏に中将はさっと近寄り、振り捨てられた辛さにお送りしてまいりました。『ご一緒に内裏を出ましたのに、何処に入るか解らない十六夜の月の様な貴方様』と恨みがましく詠います。こんな中将をしゃくだと思いつつも、彼と知り安心してちょっとおかしくなり、しかし思いもつかぬ事をすると憎たらしく、『どの里も照らす月の光(私)をどの山(女の家)に入ったか訊ねる人がいるでしょうか?』と返す源氏に「こんな風に貴方の後をついて歩いたらどうします?」と。更に真顔で「この様な忍び歩きは、随身に手引きさせると上手くいくでしょう。もう私を後に置いていかないで下さい。このように貧しい身なりをしてお一人で女のところへいく事は、近衛の中将としての貴方の身分に相応しくありません。」反対に、いさめられる源氏。こんな風に中将にいつも見つけられるのはしゃくだと思いながらも、あの夕顔の残した撫子の事は私しか知らないと優位に思う源氏です。
【イメージ】
昔からのライバルである二人のやり取りが微笑ましく、関係の暖かさを感じます。源氏が抜き足で後ずさりするシーン【抜き足に歩みのきたまふ】は本当にリアルで映像が浮かびます。
P−27
1)契れる⇒約束する 2)あまえて⇒甘えて(まあいいやと) 3)前駆⇒人払いのための先導 4)つれなう⇒知らん顔で 5)すさぶ(遊ぶ)⇒興じる 6)例の⇒いつもの様に 7)高麗笛⇒資料P-30 8)わざと⇒本格的に 9)もて離れて⇒振って 10)凄まじげ⇒興味がなさそう 11)ありつる⇒さっきの 12)あらましごと⇒あらまほしきこと こうなったらと願う(妄想) 13)けしきばむ⇒意味ありげな態度をとる 14)さては(然ては)⇒そのままでは 15)なま(生)⇒中途半端な 16)ねたし(妬し)⇒いまいましい 妬ましい17)危うがる⇒不安がる
召人:貴人の家に仕える家女房が男主人との間に恋愛関係を生じた場合、この女房を召人と呼んだ。あくまで使用人としての扱いで社会的には公認されない。本妻と同居。
別に約束した女の所へは、まあいいやと(女に)甘えて、分かれようとしない二人。一つの牛車に乗り、雲隠れの月の下、道中笛を吹きあわせながら大殿へ。前駆もおかず、忍ぶように人の居ない渡殿で直衣に着替え、今来た様に笛を吹き興じていると、大臣がいつもの様に聞き逃すわけもなく高麗笛を持って出て来て大変上手に吹きます。更に琴をもって来させて、上手に弾く人たちに弾かせます。その中の一人中務(正四位)の君は、中将が気に入ったのにそれを振って、時々しか訪れる事の無い源氏の気持ちに答え、その事が自然と皆の知るところとなり、大宮(桐壺帝の妹で、左大臣の奥方、頭の中将の実母)にも良く思われず、悩み、きまりが悪くて上手に琵琶を弾けるのに、つまらなそうに物に寄り掛かってうつむいています。源氏の目の届かない所に離れしまおうとも思っても、心細く思いが乱れます。彼女は召人です。
公達二人は、奏でられる琴にさっきの姫の琴の音を思い出し、心を動かされ、住まいの様子もその理由を色々変えて面白く想像し続けます。中将は、あの荒れた邸宅で、そのまま年月を経ている美しく可愛らしい姫を自分が見初めるなんて、恐ろしく心苦しくて、人にも騒がれるだろうし。そんな自分はぶざまに取り乱すだろうと殆ど妄想の域に。【あらましごと】です。源氏が意味ありげな行動をする様子から、そのまま放っておく訳がないと、なんとなくねたましく、不安です。
【イメージ】
大殿は、今や琴や笛の音が賑やかに流れる管絃の宴となりました。その音の中、一人暗くぽつねんとゐる女房にスポットを当てるという実に映画的構成に、「ほー」。その心乱れる女の視線が遠くで楽しそうにはしゃぐ源氏と中将に移動。その二人といえば、琴の音から先ほどの荒れ果てた邸宅の姫の事をあれこれ妄想しています。中務の君の事など全くです。三人の心の動きが面白く描かれています。今回【召人】という立場の女房を知りました。悲しい恋です。大宮が彼女を不愉快に思ったのは、息子が無視されたからであって、娘の夫の心が移ったからではない様です。本妻公認の女房なのです。男の家は何もせず、たとえば着物などは全て女の家で作ったそうです。管絃の音と対照的に彼女の孤独が痛いほど感じられました。紫式部さんは本当に凄い。女の悲しみが女だから解るのですね。
返りこと P−32
1)返りこと⇒返事・返歌 2)こなたかなた⇒源氏と中将の事 3)べし⇒推量 ようだ 4)おぼつかなし⇒気にかかる
5)心やましき⇒不快で不満がたまる 6)もの思い知りたる⇒ものの情を感じる 7)はかなき⇒ちょっとした 8)心ばせ⇒女の気立て 9)重し⇒身分や育ちが良い 10)うもれ⇒引っ込み思案 11)心づきなし⇒面白くない 12)わるびたり⇒劣って見える13)いられ(焦る)⇒苛立つ 14)かすむ(掠む)⇒ほのめかす 15)人わく(別・分)⇒人により態度を変える
その後二人はそれぞれ例の姫に便りを出した様ですが、一向に返事がなく、気にかかり不愉快であまりにひどいと。あのような侘しいあばら家に住む女は、ものの情を感じて、ちょっとした木や草、空の様子を取り上げてそれを歌(手紙)にして、その気立てを思わせる事が【あはれ】なのに・・・。身分が高いとしてもこの様に引っ込み思案なのは面白くなく、劣って見える・・と。源氏にまして中将は苛立っています。(彼の妄想は膨らみ過ぎました)中将は、何でも源氏に打ち明ける性分で、「あの人から返事はありましたか?私は試みにほのめかしてみたが、相手にされず、みっともなく終わってしまいましたよ」と嘆きます。源氏は心の中で「あー言い寄ったんだ」と、そして微笑みながら「さあ、見ようと特に思わないせいか見たと言うわけでもないよ」と答えます。(何を言っているの?)中将は源氏には返事があったと、姫は人によって態度を変えると誤解し源氏を妬ましく思います。
【イメージ】
恋の冒険者達は、ありきたりの相手ではつまらない。ライバルとしてお互いの腹の探り合いが面白いです。中将は、とても正直で単純で、実直な男の様に思いました。ライバルに話すなんて・・・。求める女の【あはれ】は共通のものなにありきたりの相手では嫌というのは、矛盾です。訳の解らない返事を微笑みながら言う源氏が可愛い!
平成19年以前の報告は[こちらから]