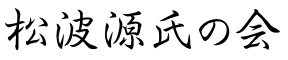
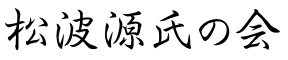

------------------------------------------------------------------------
<松波源氏の会の紹介>
原文の良さ・美しさを直に味わいながら読んでいこうという会です。年4回のペースで、「桐壺の巻」から順を追って読み進んで行く予定です。毎回テーマを設けており、参加者がそれぞれの人生経験に照らして女性の(自分の)生き方を考えながら味わえるような会にしたいと思っています。7月に立ち上がったばかりの会ですが、皆さん、とても意欲的です。
2024年11月23日 穴川コミュニテイにて
今回は5人の参加。「御八講果ての日」に藤壺が出家する内容のところでした。平安貴族にとっての出家の意味が現代人とは違うことや、五感が研ぎ澄まされる優れた表現に酔いしれたひと時でした。
・藤壺の出家に周囲の人々、特に兵部卿の宮が驚き涙を流すさまが不思議な気がする。出家の意味合いは想像をこえる。
又、黒方、名香の香りに極楽思われるというくだりが面白かった。(男性)
・月光輝く庭。香りに依るその場の雰囲気。すべてのことが現代では、かない難いことが文字の中から出現して平安の世界に遊 べました。(女性)
・中宮の突然の出家に戸惑う人達、源氏の心はいかにや。春宮の安泰を願う中宮の決心は揺らぎなく…潔さが光ります。(女性)
・雪を照らす月の美しさ、衣のすれる音、三種類の香りがただよう空間。雅な描写に現代のささくれだった人々の感性を悲しく思いました。想像力を膨らまして、一時、心があらわれました。
弘徽殿大后は、院の死後さえ、藤壺と院の絆の強さに対抗できなかったのですね。どのような思いだったのか…。気の毒に思いました。(女性)
2024/02/24 13.30より 穴川コミニテイセンターにて
11月25日
今回は、御子を守るために、ついに出家を決意し、そのことを伝える母としての藤壺の内面が描かれた箇所でした。「賢木」の巻もいよいよ大詰めを迎えました。
藤壺のひどい仕打ち。いまだに外に出られないほど自分は苦しんでいる。これを思い知って、やさしく声を掛けてほしい。反応なしに腹を立てて源氏はこもっている。それができない中宮の気持ちを理解できないのは、故桐壺帝に対する罪の意識が中宮に比べ弱いためと思われる。東宮の成長を見守ることが罪を償う第一と考える中宮にとって、源氏の執着心が最も怖れるところである。東宮の後見役として一層助けてもらいたい。(男性)
藤壺と春宮の会うシーンは母子の会話する所はまれというか無い場面。それが罪の子という面で単なる母子愛でない複雑なものがあるのか。(男性)
ふさぎこみ、藤壺に対してすねているとしか思えない源氏の「お坊ちゃん」の面がおかしい。藤壺の女房(弁と命婦)がそれでも主人である藤壺より源氏に対して「いとほしがりきこゆ」というのは解せないところです。(女性)
ひたすら春宮の身を案じ源氏の愛をさける為、出家へひたすら進む藤壺。今後どんな形になっていくのか興味深い所です。(女性)
5月27日
今回は「賢木」巻の「危うい密会」から読んでいきました。
「わづらはしさのみまされど…」という状況の中、再びあの朧月夜の君(尚侍の君)と密会する源氏。その心理は?朱雀帝は何をしている?尚侍の君はいったいどんな女性か…と参加者は真剣に議論を交わした会となりました。
源氏物語の中の真骨頂の場面を今日は十分に楽しみました。
追い詰められた若き男性はなんと愚かな、衝動的な行動をするのか。密会とは尚侍の君だけではなく、あの藤壺との密会もさしていたとは、驚きです。
危険な密会を今後も続けるであろう源氏のこの先の予兆を感じさせる刺激的な場面です。
許されない密会を重ね、泣いても苦しんでも、やめる事なく続ける心の底が、少し理解できたような気がしました。
2月25日
今回は桐壺院が崩御した後、いよいよ右大臣方の世の中になり、今までの源氏の恵まれた境遇が一変する場面です
「代わり目」で「例の御癖」がどう扱われるかが問題になる。一番難題は朧月夜の君との関係で、今や朱雀帝の寵愛を受ける身,禁断の恋である。源氏はますます燃えている。「例の御癖」も故院の庇護があればこそである。弘徽殿の大后はもう許さない。この結末は大変興味を持たせる。
この勉強会の皆さんの熱心さにいつもながら驚かされた。たくさんの意見や感想を自由に言えて、楽しい。
朱雀帝が、院の遺言を守ろうとしても母や祖父に押し切られる場面が面白かった。新帝の優しい性格と、これまでのつもりに積もった源氏への恨みを今こそ「報ひせむ」とする大后。とてもリアルだ。
ドロドロした人間模様、政治のことも、原文で読むとやわらかさと味わいがあると感じ、また現代に通じるようなリアルさもあるので、ドラマとしてとてもおもしろかったです。特にい、当時の継子いじめの物語や女遊びをやめた源氏に対する描写などが、語り手の皮肉がきいていて、語り手に少し親しみを感じました。
「嫡腹(むかいばら)の限りなく~」以下は、単に当時の物語を作者がからかっているだけで、筋の進行に蛇足かと思えたが、〇〇さんが後に出る(姫が)と指摘されたので無意味ではないんだなと感心させられた。
身分や位が何よりも尊ばれる中、亡き院の遺言が軽んじられた事、そして今後の源氏の行方がどうなってゆくかの嵐の前の静けさの感があります。
久しぶりに参加させて頂き集中して物語の中に没頭しました。後味はそう快です。ありがとうございました。
今回の章は現代の会社内で起きているかもしれない出来事のような気がしました。社長等の役職降下の様に似ている感じがしました。それに変わって若紫の平穏な日々が長く続くことを祈ります。
11月26日
今回は「賢木」巻。桐壺院が逝去される場面です。院の遺言から源氏・藤壺・弘徽殿大后・朱雀帝・春宮の様々な人間模様が浮かび上がってきました。
感想
・「限りなくきよらに心苦しげなり」という相反する言葉をつなげることで文章の厚みを持たせる。複雑で広がりのある文体だとしみじみ思わされる。「足を空にひまどふ」という表現も面白い。
・自分なりの訳があって良いとうかがってお話を拝聴しました。おもしろいところはたくさん(全部かもしれません)あったのですが、特に心に残ったのは「おどろおどろしきさまにもおはしまさで」の皆さんの読みでした。院が亡くなる時に、遺言を語りたりない心境や、院の庇護がなくなる周りの気持ちがよく伝わってきて、古文は思ったよりも遠くないものだと思いました。
・今回は言葉のひとつひとつがとても大切な使い方ができていて言葉に関する鋭さが改めて感じられました。
・桐壺院が亡くなり今後の東宮・源氏の先行きを暗示しているかのような…読み応えのある章です。
・身分や境遇・時代にかかわらず、すべての人に「死」は平等なのだと思いました。またその時に新たに浮かび上がる人間関係の生々しさ。美しい藤壺や源氏よりも、弘徽殿大后の屈折した心情とふるまいに、共感してしまいました。「物語」なのに「小説」みたいですね。
・将来皇位を争う種にならないため、親王にはしないで臣籍に下し、その政治的能力を活かすべく、凡庸な朱雀帝の政治上の後見役に源氏を起用する桐壺院の遺言は実現が非常に難しい。弘徽殿側にとってはのめる案ではない。院が生存し保証しなければ実現しない。この難題をどのように克服していくか、大変興味がある。
2022/9/24
68回 感想 「賢木巻」 伊勢出立と別れの櫛
伊勢に下向する斎宮・御息所に最後の最後まで和歌を贈り続ける源氏と、それにふりまわされまいとする御息所の心が見どころの箇所でした。ただ源氏が斎宮に出した和歌の解釈が難しく参加者から様々な意見が出され、それもまた読みが深められて意義深い会となりました。
(感想)
野の宮の別れから伊勢出立と源氏と御息所の最後の別れの場面の哀しさが胸を打ちます。
源氏の君と朱雀帝の二人が斎宮に初めての出会いで同時に恋に落ちた。その理由が面白い。母に代わっての厳しい返歌が「十四歳という年の割には面白いところがある人だと」と源氏は心惹かれたという。一方朱雀帝は「別れの櫛」の儀式の時、「斎宮のその気高く匂い立つまでに美しい姿を目にして心奪われた」という。二人の違いが見えて面白い。それにしても、幼い斎宮にともに初めての出会いで恋をするとは、その軽率さに驚くとともに、超エリートの傲慢さに腹を立てている。(80代男性)
出車の女房たちと殿上人の別れのシーンは印象的。斎宮と御息所だけでなくそれぞれの物語と悲劇が浮かびあがる。
伊勢下向への出立から帝への別れの日の時まで興味深い事柄が続き心から楽しめました。斎宮の立場を今の我々は理解できないので子別れなどと考察を一諸させてみたい。
斎宮となる人の気品がチラッと感じられる文章だった。しかし源氏がなぜ木綿につけて「八州もる国つ御神も心あらば~」と詠んだのかよくわからなかった。この物語はやはり難しい。引き歌も含めて和歌のやりとりの真意を理解するには「平安時代」をよく理解しないと…。朱雀帝が若い斎宮を伊勢にやるときに「いとあはれにて、しほたれさせたまひぬ。」との場面は胸を打たれました。
松波源氏の会感想
2022/5/28
六条御息所を訪ねた源氏と、揺れる心を隠して和歌で気持ちを伝える御息所の和歌の応酬が大変美しい場面です。
夜を徹した二人の語らいも終わりに近い。身を引き裂かれるような悲しい別れの状況を明け方の冷たい風と物悲しく哀切極まりない松虫の鳴き声で演出している。二人の心の動きを見事に描かれ、特に「をり知り顔なる」もの悲しい鳴き声などは抜群である。離れがたい二人に冷酷な後朝の別れをぶつけるのもさすがである。(男性)
「源氏物語」の中でも哀しい切ない「野の宮のわかれ」は読み応えがあります。源氏と御息所のどうにもならない心情が身にせまります。(女性)
久しぶりの「松波源氏の会」堪能しました。次回を楽しみにしております。(女性)
人の心の弱さや想像力や全ての事が野の宮でおきたことがこの短い章で表現されていることが不思議です。(女性)
野の宮の別れの場面は源氏物語の名場面の一つだが原文で味わうと一段とすばらしさが際立ってくるように思う。
但し皆さんマスクを掛けて話し合っているので聞きづらいですね。早くマスク無しで開催出来たら良いのにね。(男性)
「夕月夜」とは何と美しい日本語かと思う。今、夜の月が何時にどの方向にどんな姿で出ているのか、本当に実感としてわからない。「月」の運行が時計がわりであった平安時代…。現代は便利な時代であるが、失ったものも大きい。そこに気づかせてもらえるのが古典の魅力だ。(女性)
2020年9月25日
今回は「葵の巻」の最後の場面です。新枕を交わした後の、初々しい若紫の描写。娘亡き後の寂しい左大臣家の正月の描写が印象的でした。
コロナの中ほぼ一年ぶりの源氏の読書会。今日、葵の最終章。内容が哀しく重く葵の上の存在感が源氏にとってどんなに大きかったか印象に残る章でした。(女性)
p198の姫君の心の変化ー源氏への嫌悪感が生まれた所に理解できない、ついていけない気がする。源氏と同じ気持ちか。でも今思い出すと結婚直後の妻の不機嫌もそれと近いのかな。 (男性)
葵が両親からいかに大切に育てられていたかと改めてしみじみと感じられる最後であった。若紫はその点で対照的に哀しい半生であったかも感じられた。秋に読んだせいか心にしみ渡る思いが強い。 (女性)
源氏の美しい衣だけが部屋に飾ってある場面が印象的でした。いつもなら女君の華やかな衣がそばにあるのに。源氏の目から見た女君と親(左大臣・大宮)から見た姫君である葵の上の姿が重なって、しんみりしました。 (女性)
第64回「松波源氏の会」の感想。
1. 源氏と紫の<結婚>の事実に対する受け止め方の大きな違いが印象
深い。物語での最も忘れがたい一文のひとつと言われるのも納得で
きる。
この衝撃的な箇所のあと、モチのやりとりの部分のコメディタッチ
の転回にも驚かされざるを得ない。 アキラ
2. 源氏物語の一つのクライマックスを迎えた今回は男性と女性の読み
方がはっきり別れた章であった。
作者がどちらの読み方も解っていたことが不思議です。
3. 突然とはいえ、紫の上の初夜のショックは異常である。添寝は長く続き何時男女関係に進んでもおかしくないのに未だ契り合っていない。それとなく結婚(男女関係)の意思をにおわせても紫の上に反応がない。そんな中で我慢しきれずに事に至ったという。これまで源氏のそのような行為に不快感を持った女性はいない。戸惑いながらご機嫌をとるが利き目が無い。姫君は全く結婚のこと考えがなく。「どうしてこんな嫌らしいお心を、心底からお頼りにする気になっていたのだろう」とあきれていたことと思う。それだけに心の傷は大変大きい。「初心だ」とか、腹が立つが、それが可愛いという源氏には、姫君の傷は理解出来ないのだろう。 八十台男
4. 久しぶりの参加です。
お葉書頂いた時に、井上久代さんの具合が悪いとのことで、そちらの方が心配で伺ったものの、先生の源氏物語の研修をうけて次回も参加しようという気持ちになりました。 井上
2020年9月26日
2019年11月23日
今回のテーマは「別れ 源氏、左大臣家を去る」です。葵の上の死去により、婿として源氏をお世話できなくなった左大臣家の人々の悲しみや寂しさ、召し使われている者達のあわただしい動きがリアルに描かれている面白さを味わいました。
・源氏がいよいよ左大臣家を去る時が来た時の左大臣家の女房達との別れ、それぞれの気持ちが描かれていました。この時代の社会が少し理解出来た気がしました。
・源氏と大臣、大宮との別れもさることながら女房達が源氏と二度と会えないと思う心の動き、その確かさがよくわかる段となっている。私も女房の立場であったならそう思うかと…。
・源氏の悲しみ、子供の養育をお願いしますなど源氏にも普通の感情があった事を知りました。
・「をり知り顔なる時雨」による状況設定は、他の用例と異なるが分かりやすく適切である。左大臣邸から退出するのに躊躇する源氏の背中を押すように、さっと降って来る時雨を利用している。すごくうまいと思う。股左大臣が時雨れの降り止まぬ空模様を口実に出立を促す場面もあり、時雨の効果が十分発揮されていると思う。
・源氏が左大臣家を出て行く描写が細部に渡って語られいつもながら作者の力量に圧倒されています。
・源氏の姿の美しさ、心情に逢ってみたい。女房達の悲しさが理解できるかも。
・身よりのない女童を引き取る源氏の優しさに感心した。なかなか他の男性はここまで細やかな心使いはしないのでは?身分社会の中で、こういう配慮ができるのが「理想的な男」源氏といわれる所以かもしれない。
2019年8月24日
今回は、「哀悼の心」がテーマでした。葵の上を亡くし左大臣家に籠もる源氏のつれづれを慰める頭中将とのやりとり、嘆きに沈んだまま立ち上がれない大宮を励ます源氏の有様…。感性豊かな、当時の人々に思いを馳せた時間でした。
三位中将と源氏との友情関係は多面性があり面白い。今回の「色めかしき心地に…」では源氏の美しさに色めかしい心地で中将はついじっと見つめながらおそばにすり寄った。その同性愛的はふるまいに源氏もひるんで身構え、直衣の紐だけを直したというくだりは大変興味深い。(男性)
葵の上の死からいろいろと考えさせられた。夫婦、親子、兄弟、友人達との関係について深く読みすすむことができました。(女性)
今回も源氏の世界にひたり雑念を離れて、幸せな一時を過ごせました。ありがとうございました。次回を楽しみにしております。(女性)
源氏の心の哀しみが深く読者に伝わってきます。妻を失ってみてその存在の大きさ、大切さとともに内面の自分をみたのかもしれません。(女性)
高貴な身分の母と娘。感情を上手に表現する練習の機会がなかったのが残念、冷静で物事の判断も適格しかも情感にあふれている「朝顔の宮」は現代女性から見ると理想。紫式部は自分を託していたような気がするが…。(女性)
源氏とのつながりが妹によってきずかれていた中将の気持ちは現在社会もあるなと思いました。関係がきずけなかった事にくやんだ源氏の気持ちもわかりました。(女性)
2019年5月24日
今回のテーマ それぞれの「心の鬼」
松波源氏も記念すべき60回(15年)を迎えました。おいしいお弁当に下鼓を打ち、先生に感謝と尊敬の気持ちをこめて花束贈呈。松本佳子さんのシャンソン独唱と、北村和枝さんの詩吟「静夜思」のご披露で、格調の高い優雅なひとときとなりました。15年前の写真を見ると、本当に皆様、若かった!でも心と感性のみずみずしさは、当時と少しも変わっていません。
今回は、妻を亡くして心に深く痛手を負う源氏と、御息所からの文を巡って、二人の心理描写の妙「心の鬼」を味わいました。
・「つれなの御とぶらひと、心憂し」の一行を、生霊のことには知らぬ顔で弔問の手紙を寄越す御息所に不信の思いも湧くが、御息所が自分の方から源氏への手紙に生霊のことなどどうして、ふれられようか、忌まわしい自分の生霊を源氏にだけは感づかれたくないと願う。未練の情を断ち切れない御息所は隠し通して精一杯装い源氏と向かいたいのだと、ここまで思いを広げられているのには大変感動している。(男性)
・勉強会が60回、おめでとうございます。私は途中参加でしたが、それでも11年間で45回ほど参加させてもらったでしょうか。まだまだ勉強不足で追いついて行けないところがありますが、これからも楽しみにしたいと思っています。田中先生始め会員の方宜しくお願いします。(男性)
・「深き秋のあはれまさりゆく風の音」から「御息所の御手なり」までの文章、情景や物の洗練された美しさに惹かれます。「源氏物語」が追求した<雅さ>の表れている箇所でしょうか。(男性)
・御息所の教養ぶりを知るにつけ、源氏に対する思いは教養ある人にもどうしようもないこと。自制できないことなのだと思う。それを自覚することの辛さは考えられない程のことなのだと思われる。(女性)
・御息所が気の毒でたまらない。弔問の歌を詠んだときは紙や菊の枝や筆跡の素晴らしさに感心し、歌も真情があふれている。しかし、源氏にとっては疎ましく感じ執着心を持つなときっぱりと拒否する。(もっともと思いながら)御息所だって好んで生霊になったわけではないのに…。男と女のどうしようもない心の在り方がせつない。(女性)
・今日初めて、源氏の君のキリリとした言動が見え、御息所の弱い女の部分も見えました。が、最後に又源氏の「元の心」が見えてしまい、残念な気持ちです。この先の転回が楽しみです。(女性)
・田中先生いつもご指導頂きありがとうございます。まだ60分の5程度の新人ですが、この会に出席させて頂くのはとても楽しみです。これからもよろしく願いいたします。(女性)
・この会には手づくりの暖かさがあって良いですね。お弁当の手配からおいしいお茶とお菓子、お手製のおつけ物など、勉強会の休み時間もひそかな楽しみにしています。毎回自由に感想が出て読みが深まっていくのも、そうした雰囲気があるからこそ。15年の味でしょうか。今回は、クールな源氏の一面を感じ、また新鮮な感じがしました。菊という当時大変貴重な植物と、濃い色合いの紙を選んで和歌を届ける心用意が、平安時代を感じさせます。(女性)
第59回松波源氏の会
2019年2月23日<葵その8>
夫婦の絆とは? というテーマのもと、心通わせる源氏と葵の上、そして妻の急死を柱としての講座でした。
・葵の上と源氏のほのぼのとした夫婦としてのやりとり、気持ちの深まりが感じられたのに、人生とはこんなものなのでしょうか。大事な日で男達が留守にいしている時にものの怪につかれ急死してしまうとは…。舞台があまりにも揃いすぎていてただただ驚くばかりです。
・葵の上の最期になってようやく心が通いあったかに思える夫婦、そこに至るまでの結婚生活(?)が切ない。葵の上を失った源氏の心中、左大臣の辛さ、言葉ひとつでそれを表現する筆には驚くばかり。
・葵の中でも壮絶な場面が展開しその中から源氏と葵の上の夫婦愛がなんとも美しい所でした。
・御息所が葵について源氏に名を表す段階の文章の迫力と凄さを感じましたが、今回は源氏と葵の夫婦としての感情の交流がなりたった後の唐突な死。なんというドラマチックな展開でしょう。
・今回は葵に対する源氏の心の機微がよく描かれ、今までと違った感じを受け何かホッとしたと同時に改めて紫式部のすごさを感じました。
・源氏にも普通の夫婦の感情があったんだとびっくりしたと同時に源氏物語のイメージが変わりました。
・今回は大変ドラマチックな場面。心が通いあった源氏と葵、源氏は葵の魅力に気づき、葵も源氏の優しさにほだされる。でも…何という運命でしょうか。
第58回松波源氏の会 感想
2018年11月24日<葵その7>
テーマ:生霊とは?芥子の香とは?
今回は、「芥子の香」からいろいろなことを考え、自由に感想を述べ合う楽しいひとときでした。
御息所の生霊を目の当たりにした源氏の驚愕ぶりを生々しく描いており、感心している。葵の上の看病を通じ、妻の取り繕わない愛を感じ、源氏もそれに応えようとするさなか、突如御息所の生霊が妻に成り代わり源氏との愛をつなぎ止めたいと哀願されては、源氏もさぞ驚いた事と思う。
苦しみながらも男子出産に華やぐ左大臣家、かたや生霊となり深い苦しみにおちいる御息所。場面が変わる毎に心に深く残る章です。
生霊が「なつかしげ」な口調で話し始めたところが御息所の本当の姿がかいま見えた。源氏には北の方の口を通して話した人物が御息所だと判ったのはなぜ?であろうかとも思う。
読むほどに息苦しくなるようなせつない気持ちになります。御息所が芥子の香りに悩まされるのも御息所の心の「芯」のやさしさや思いやりの深さから来ているのでは?と思います。
葵の上がようやく小康状態になったら、またまた「気近う見たてまつらむ」などと考える源氏の心は理解に苦しみます。
この場面の源氏は御息所とのかかわりを持ったことを後悔したことだろう。いくつもの偶然が重なり御息所は生霊のまでなってしまったけれど、そこに追い込んだのは源氏だったけれど…・病に苦しむ葵の上をなぎさめている源氏に「いで、あらずや」と姿を現したときのすごさ。この場面を当時の読者はどんな気持ちで読んだことだろう。平安時代のほの暗い部屋で…。紫式部はすごい!
御息所ほどの、誇り高く知性のある女性が、こんなにも自分をコントロール出来かねて苦しんでいる。恋とは何だろう。男と女の間には深い闇の流れがあるのだろうか。つくづく心の不可思議に打ちのめされてしまう場面だ。物語なのに、創作を越えてリアルなのがすごい!面白い!
もののけが騒ぐって?芥子の香がつくって?心情的にまだまだ深く理解出来ないところが多く回を重ねる毎に楽しみが増しています。
いつの世も女性の心理は変わらないし男子出産すれば昔も今も大よろこびされることは変わらない。
生霊も芥子の香も人間のきびをよく表しているということで式部の表現の素晴らしさにひきこまれ感嘆もします。原文に接することができること、先生の解釈にいつもうれしく思っています。
源氏の会に出席させていただいていつも感謝いたしております。眼に見えないことでも心に感じ入ることが出来るってすばらしいことです。日本人に生まれて幸せです。脈々と伝わっている空気を大切にしたいと思います。
第57回「松波源氏の会」2018年8月25日<葵その6>
テーマ;魂のゆくえ
御息所が気の毒で可愛想でたまらない。生霊となったのも、生霊にならざるを得なかったのもわかる。葵もこんな事態になってやっと源氏と心が通じたなんて残酷。おもしろい場面をみんなで楽しめて良かった。
純粋な心を持ち続けられる御息所がうらやましく思います。
前回は源氏の世界にドップリと入り込んでしまい家に帰ってからも頭から離れない状態が続きました。が今回は源氏と北の方が初めて心を通わせた場面であり少しホットしています。通い婚の時代の女性は辛いですね。
なかなか「源氏物語」を読む機会が無かったのですが本日から参加させていただき人間の内面についてもいろいろ考える機会を得ました。次回からも楽しみにしています。
紫式部のすごさの一言です。深層心理。描写。源氏と葵の上が心を通わせる場面はどなたかがおっしゃったように絵になりますね。もっと早い時期に二人の心が寄り添っていれば源氏の遍歴も違っていたかも。
人間の深層心理を見事に描かれていると、北の方との夫婦としての始めての心のつながりを得た印象が強く残りましたね。
あの穏やかな教養ある御息所が、恐ろしい生霊となって葵の上に取り憑くまでになって行く過程を、順序良く手抜きなく記述している。生霊が取り憑くことを信じられない私ですが、そんなこともあるのかなあとまで思わせる説得力には感心する。
原文で読み解説があり有意義な一時をありがとうございました。皆様の博学にはいつも感心しております。
久しぶりに先生の話がきけて源氏物語の世界が少しわかってきたような気がします。Tさんの話も又納得できてうんうんとうなずきながらきかせていただきました。
御息所の女性らしい心持ちの表れと共に葵の上の本心を吐露する時を得たことが安心しました。
先生のお話を聴いていますと、その様子・雰囲気が感じ取れてありがたいです。今の時代と重ねて思ったりしています。
葵の上の目から一筋涙がこぼれ落ちる様が浮かんできて、心に染みいった素晴らしい場面でした。妻の手をとって泣く源氏もどんなに美しいことでしょうか。
第56回「松波源氏の会」2018年5月26日<葵その5>
テーマ:すれ違う御息所と源氏
1. 源氏の気持ちと御息所の気持ち、それぞれの心情が身勝手でもあり切なくもありでした。きっぱりと切った方がどれだけ楽か。でもそうしない。やはり源氏物語は面白い。
2. 六条の御息所は以前から登場していらしたが、今回は一人の女性としての御息所の深い気持ち。和歌に込めた思い。人間性が感じられて、ぐっと私の中に深く印象づけられました。
3. 源氏物語のテーマである「もののあわれ」を見事に描写している場面です。愛の深さやどうにもならない思いが印象的でした。
4. 御息所の源氏への愛情の深さが源氏の重みとなり、それに答えないではぐらかしている。その事が更に御息所の悩みを深くしている場が良く出ている今回の会でした。 男
5. 御息所の思いと源氏の思いの深さのちがい。男と女の立場のちがいが浮きぼりになって興味深かった。御息所は自分を田子とまでたとえて訴えているのに、それをはぐらかす源氏。読んでいて苦しい。男性三人も含めていろいろ話しながら読んでいく読書会はおもしろい。 女性
6. もののけの意味合いは想像を越えるけれど、源氏物語の人間の心情を考えるとき、見過ごせないもの。葵にたたるもののけ達は興味深い。
六条御息所の田子の歌の切実さ、それに対する源氏の受け止め方は物語のキーのひとつだとも知らされた。
7. 車争いから尾を引いての御息所の気持ちが歌に込められた描写の素晴らしさにおどらかされます。
8. いままでと違って来て少し源氏物語のイメージが変わり、深くなって楽しくなりそうです。
9. ありがとうございました。あっという間に時間が過ぎてしまいました。御息所の思いが胸に突きささるようでした。次回を楽しみにしています。
10.今日も参加させていただいてよかった。と思い乍ら帰ります。先生のお話を楽しみにしています。ありがとうございます。
11. 一夫多妻制の女性の心得は、通ってくる夫をひたすら愛し、決して他に通う
女を意識しない、とくに正妻に対し競争心を持たないことである。
御息所の場合車争い以後、正妻の葵の上に「挑み心」を持ち、愛の独占欲を
意識し始め恋の苦悩が深まるのである。悩みの真情を訴える迫力に源氏はたじたじになって逃げの姿勢をとる。苦し紛れの「浅みにや・・」の返歌は真意を無視された御息所は一層傷ついたと思われる。 八十才男
2018年2月24日<葵その4>
今回のテーマは
賀茂祭に華やぐ源内侍・苦悩を深める御息所とももけに苦しむ大殿北の方
一言一言が深く興味津々の時間でした。先々が楽しみです。ありがとうございました。(女性)
「知」は「美」と思いました。(女性)
毎回の事だが、自分で読んできたことがいかに上滑りなのかを痛感させられる。それが毎回の楽しみである。(男性)
何回かお話を聞くうちに(読むうち)いやらしいイメージは少しづつ抜け原文を読む楽しさもわかってきました。(女性)
描写のすごさ(この時代)に感激ひとしお、原文で読む楽しさを味わうことが先生の解説でよく分かり嬉しく、源氏の日が楽しみです。(女性)
典侍と源氏のやりとり、歌は面白いが典侍の人気が高いということに驚かされた。今一度ふりかえってみたい。最後の葵についたもののけの登場には今後の展開に興味を持った。(男性)
源内侍の行動の面白さと共に自分には無い考え方に驚きます。いよいよ御息所の話が発展していくので彼女の心の内を思うと私自身にひきうつして考えさせられます。(女性)
もののけが葵の上を苦しめている描写は、平安時代の闇をのぞくようで興味深かった。現代人と同じものを感じながら読む楽しさと、1000年前の世界に引き込まれていく部分と…。源氏物語はだから面白い。(女性)
2017年11月25日 <葵その3>
テーマ「車争い」の光と影
今回は葵の巻の3回目になります。車争いの後、通り過ぎる源氏の華やかさと、見つめる御息所の傷つく姿が対照的な見事な文章を堪能しました。
また、参加者の中で、K様が今年88歳を迎えられ、会から花束の贈呈をさせていただきました。ますますご長寿・ご健康でいらっしゃいますように。
源氏の行列を見んと様々の人が集まり様々な面白い対応をしている。その様子がまことに見事に活写されている。中でも印象が残ったのが、源氏がひそかに通っているあちこちの女君たちが、源氏の人気の素晴らしさを前に、いよいよ自分などは物の数にも加えられないだろうと、人しれず嘆きの深まる方も多いと言う。共感するところがあり、気分が沈んだ。(男性)
K様 おめでとうございます!
熱心に授業に打ち込む空気!先生と生徒の取り組まれる雰囲気に今日も出席させていただいて良かったと思いました。ありがとうございます。(女性)
「車争い」で傷ついた御息所の感情の形をどう思うかは(恨みか、内向きの屈辱感か)御息所への親近感、同情心を持てるかどうか変わってくる気がします。今日の話で気の毒な気持ちがわいてきました。(男性)
以前の御息所の印象は悪女のイメージでしたが今回で彼女の女性らしさを認識できました。心を寄り添わせることができました。(女性)
美しい王朝文化が描かれ又身分制度の中で人々の様子がさらけ出されている。しかしこの場面は式部の優しさが感じられる。(女性)
お休みしたのですが、物語の展開がよくわかり楽しく時間をすごせました。筋の展開がとても変化して面白いです。(女性)
少しずつ源氏の人間関係がわかりかけてきました。まだまだ未熟ですが楽しみになってきました。(女性)
いわゆる車争いと言われて絵になっているがその背景にはいろいろな事があったことが分かる今回の勉強会でした。この事を頭において絵を見るチャンスがあれば随分とおもむきが違うでしょうね。(男性)
今回は「車争い」の後の御息所の無念さに読んでいて心が痛む。あんな思いをしながらも源氏の姿が見られた喜びを感じている。「葵の上」も育ちから情の薄い人になっていてそれも気の毒。(女性)
誇りを大きく傷つけられた御息所と、傷つくことをおそれて源氏と関わることを避ける朝顔の姫君。双方、とてもプライドと知性が高い女性だと思う。さまざまな人間模様が本当に面白い。御息所の和歌もまた心にしみる。(女性)
第53回松波源氏の会 2017年8月26日<葵その2>
テーマ:車争いはどうして起こったか
8月26日、「葵の巻」はいよいよクライマックスともいうべき車争いの場面にさしかかりました。争いがおきる過程を色々な角度から描き、大宮や葵の上、六条御息所の心理を丁寧になぞったうえでの争いの場面はとても説得力のあるものでした。今回は大学生2名の参加がありたいへん楽しい勉強会でした。
今日の車争いは私が何となく思っていた内容とはひと味違っていましたが、源氏物語を今回原文で勉強して、その時の情景や車を止めることの大変さ、お祭りさわぎのように高ぶっている周りの人々。車に乗っている人の身分やその方に仕える人たちの気持ちそしれ最後の御息所の女心と盛りたくさんでした。(女性)
今回で4回目の受講です。今まで聞いていてもよく理解できないことが多かったですが、今回は少しですが理解することができました。今からが楽しみです。(女性)
北の方が大宮に促されて見物に急に出かけていくことになったところからの物語の始まりがすばらしい。北の方の気がかわらなければ…。(女性)
読んだだけでは分からないことがこの会の中で話し合うことで深くわかって来ることが多々あるのが楽しいですね。(男性)
先生の解説にうっとりしました。(女性)
その場を早く退出したいと思うも、ままならずいらいらしている。なのに「つらき人の御前わたりの待たるる」気持ちは端から見ると実に悲しいものと感じられる。(男性)
御息所は前東宮妃としてのほこりを貫き通して欲しかったとある面思います。(行くべきではなかったと…)(女性)
語り手の言葉の使い回しが非常に匠でまた時々表れる語り手の気持ち、登場人物への思いは読み手をうんと言わせる凄みを持っていました。源氏物語のなかでもたいへん有名な場面にあたりますが、改めてふれてみると以前読んだ時とはまた違った感想をもつことができました。ありがとうございました。(男性)
この会に初めて参加しましたが、解説が分かりやすく意見交換も活発だったためとても楽しかったです。「車争い」は今回初めて読みました。御息所のプライドの高さがよくわかりました。(女性)
待ってました!車争いの場! 北の方は若い女房たちの希望に添って重い腰を上げ、御息所は源氏を一目みたさに出かけこんな大変な争いになった。その事情がよくわかった。年を経た女からみたら、御息所のあわれさが心にしみた。(女性)
御息所は、身分を隠した車「ことさらにやつれたるけはひ」で来たはずが、「下簾のさまなどよしばめるに」と品と風格がにじみ出てしまっている描写が、凄いですね。時間をかけて醸し出される、その人がまとっている空気感…。現代ではめったにお目にかかれないものの面白さを感じました。(女性)
第52回松波源氏の会 2017年5月27日<葵その1>
テーマ:御世がわりとその余波-車争いに到る各人物たちの状況
御代替わりで始まる「葵の巻」には様々な女君が登場します。意地になっているかのような今后、ゆったりと院と過ごしている藤壺、六条御息所の心模様、懐妊された葵の上、朝顔の姫君、斎宮と斎院。。物語の展開がダイナミックに動いていくであろうことが巻頭から予想され、私たち読者は、暑い気温にも負けない濃密な時間を過ごしました。以下、感想文です。
藤壺との不義密通の子が東宮となり、その後見役に源氏が指名された。源氏は内心気が咎めるものの、うれしく思ったという。良心の呵責をうけながら、わが子の面倒をみるという複雑な感情は大変つらいものがある。
今回から葵の巻。期待が高まる。今日はその前提としての源氏をとりまく状況を丁寧に読んだ。おもしろかったのは退帝した桐壺とおだやかな日々をおくる藤壺。そしてそれを横目で見て、意地を張る今后との関係。朝顔の君のクールさもおもしろい。十三人の参加者がいて楽しい会になりました。
葵の項になり新しい展開がはじまりますが、その前提としての御世変わりが先生の解説でとても興味深く味わうことができました。これからが楽しみです。
前々から六条の御息所の存在が出てきましたが、ずっとその方って何者と思ってきました。今回はっきりと姿を表して源氏より7才年上と言うこと等々私の中で一件落着という感じでした。
葵の巻は初めて読んだのですが車争いの前段として見れば面白い巻でした。
今回2度目の参加です。高校時代に古文の授業を聞いて以来です。聞くだけで精一杯で少しは源氏物語の入り口に入れたかなと思っています。理解できないことがまだまだで質問するものもわからない状態です。回を重ねていくことで少しは理解できるでしょうか。よろしくお願いします。
御息所と葵という格が高く心を開きにくい女性に対して、源氏は結局うまく扱いかねて終わったようだ。光源氏をもってしても、という気がする。
今日も熱心なご指導のもと充実の時間をいただき深く感謝しています。雰囲気も真剣な中にも和やかな空気でありがたく思いました。
平安時代の貴族達の物語でありながら、共感出来ることが沢山あるので、本当に楽しく読んでいます。結婚して十年、ようやく葵の上を源氏が愛しく思う場面が出てきてほっとしました。
第51回「松波源氏の会」2017年2月25日<花宴その3>
テーマ:藤の宴で有明の君をさがす
1. 右大臣家の様子がとてもよく書かれていて藤の宴がどんな風に催されたのかわかりました。その宴の席を利用しての源氏の朧月夜の君探し。登場した時の源氏の姿。又々展開の素晴らしさを感じました。最後の「いとうれしきものから」は
一番いい時でおあづけを喰ったような思いがけない終わりでした。
2. 権勢をほこる右大臣家のあれこれを批評し皮肉に表現しているが、現実のモデルとなる存在に対して強烈なあてこすりであるだろう。当時の読者はそれを推量
して拍手する者と反発する者の二つの反応があったのではないか。(アキラ)
3. 今回も優雅な源氏にうっとり。彼の服装、言葉、そして女の人や右大臣家の暮らしぶり、美意識に対する考え方はさすがです。
4. 右大臣家での藤の宴への登場の仕方、有明の君を確かめるやり方など源氏の
絶妙なやり方を感じられます。
5. 朧月夜との出会いは、ほんの偶然である。源氏の強引さにあきれる間もなく
しるしの扇を交わし別れた。再会には「藤の宴」が用意されているが、春宮への入内を間近に控えた姫という難しさ。前途多難、どきどきさせ物語に思わずひき入れられた。紫式部のストーリーテラーの素晴らしさには感心した。
6. 花の宴の最後の場面がはじめての受講になりますが、先生のお話で流れも浮かんでくるようによくわかってきて、うれしかったです。今年は休まずに来ようと思います。
7. 新春にふさわしく、なごやかな時間をありがとうございます。(ふかせ)
第50回松波源氏の会 2016年12月24日 <花宴その2>
今回は、扇を交わして別れた、素性をあかさない姫君に心乱される源氏の姿が印象的な場面でした。
以下感想文です。
新しい恋に熱中しながら何か危険な感じのする進行でこの成り行きが楽しみです。
今日は源氏の心を知ることができました。
源氏が名前を教えてほしいという願いに「名を告げないで私が死んでもあなたは草葉の陰の墓をたづねても下さらないのですか」と姫は答えた。名を告げないでも、調べる気持ちがあれば分かるはずと恋の情緒がわかる情のある女を演じて「優雅になまめいていた」と言う。深窓の姫がこんな対応が出来るのかと感心するばかりである。
今回の僕の宿題は、おぼろ月夜の歌「うき身世に…」の意味あいを味わい確かめること、としたいものだ。
イメージで読む源氏物語を現した田中順子先生のご講義をいただけることは大変幸せなことです。ありがとうございます。
源氏が好きになる女性、気になる女性のタイプがはっきり理解できたような気がします。賢くて少し気が強くしかりしていて勿論美して、ということが明らかになっていったのが、花の宴の巻かなと思います。
桜の三重かさねの扇を持っている姫というだけで、美しいイメージがかき立てられます。言葉のやりとりで深まる恋というのも、いかにも雅な時代だと思います。現代人の持っていない豊かな時間がゆっくりと流れていきました。
第49回「松波源氏の会」2016年9月24日<花宴その1>
テーマ:花宴果て朧月夜と出会う
1. 藤壺の歌「おほかたに花の姿を―」に恋心と乱れ揺れる気持ちが表われて印象深い。朧月夜との出会いと求婚の恋のドラマも面白く読める。
2. 宴の後、朧月夜と出会った源氏。これからの展開が又、楽しみです。平安時代の源氏や頭の中将の教養の深さに驚き、一体いつどのように身につけたのかと考えさせられました。
3. 宴の後の余韻に美しい月光の中をさまよい歩く源氏が求めていたのは藤壺。でも出会ったのはとてもデンジャラスな朧月の君だった。物語としてはとても面白い。
それを味わった回でした。
4. 自然の移り変わりと共に進む物語は現代と全く異なる世界と時間を感じます。
5. 朧月夜の出会いは、今風に言えば強姦事件である。「皆人にゆるされたれば・・」のセリフは、全く勝手な脅しである。驚き、おろおろする女が、源氏の君であったのかと聞きわけて、少しはほっとする。あんまりだとは思うものの、恋の情緒もわからぬ情のこわい女だと、源氏の君に思われたくない。この女の心の動きがよくわからない。
帝一人のための女性群である後宮に住む人たちには、帝に召されるままに仕えることが務めである。源氏の行動も、朧月夜の対応も、この特殊な後宮風の考えが底辺にあるのではないだろうか。
第48回「松波源氏の会」2016年5月27日<紅葉賀9>
「二十の若人たちと五十七、八の人」というテーマで、源典侍との恋の現場を取り押さえられた源氏と中将との騒動を読みました。また、最後に藤壺の立后が描かれたことの意味も考える会となりました。
年老いた典侍が、なぜ二人の若き貴公子を手玉にとるるのかずっと疑問に思ってたが、「面無のさま」(あつかましさ)のせいじゃないかと考える。
あの茶番劇を引き起こした原因が自分にあるのを棚にあげ、二人が急いで帰ったあとの寂しさを嘆くという「あつかましさ」があるから、年をとっていたが色っぽく振る舞うすべに長けている女が自分の思いを遂げるのを手助けしているものと思われる。テレビで若作りのあつかましい女性をよく見かける。
源典侍はコミカルに描かれつつも。現実にいそうなリアルな人物として造形されている。女性性を失わず、情熱的で敬愛すべき人にも思える。
源氏の君と頭中将の揚げ足の取り合いがどこか面白おかしかったです。歌のやりとりも大変巧妙で、また技巧を凝らしており、凄いなあと感心しました。最後のシーンで藤壺を想う源氏が可愛そうだと思いました。
紅葉賀の最終局面は帝の心を表していて、帝と源氏の間にある后の苦悩を更に増すことになるという予感が私の心を暗くするようです。
息つまるような深刻な苦悩を読んできた読者にとっては、この源典侍と貴公子達とのやりとりは、ちょっと息抜きさせられた感がある。いつの時代も親しい青年同士の悪ふざけは変わらない。
第47回「松波源氏の会」2016年2月28日<紅葉賀8>
源内侍との恋をめぐる二人の貴公子達がテーマ「紅葉賀その8」です。今回は、ひどい年の差と老醜(?)をものともしない 源内侍の歌のうまさと、源氏の応酬の面白さが味わえた箇所でした。催馬楽の言葉に導かれて男女が恋を言葉で楽しむ平安貴族の教養に触れました。
(感想)
狂言回しの役割をもつ人やエピソードはたえず出てくるが、この老女との場面は他よりも詳しく長いと思う。源内侍に込められた意味は色々とあるのかもしれない。
平安時代の男女関係の大らかさを感じました。ハイミスの内侍の魅力(教養の深さ)が表現されていてたいへん面白かったです。頭中将もようやく源氏の弱点をつかめて良かったですね。
典侍と源氏の漢詩のやりとりの絶妙さがとても楽しくこの時代の宮中人の教養に感心します。
今回の講義は楽しい巻でした。源氏の君は勿論、紫式部の教養の深さを愛でる巻だと強く感じました。自分自身を省みて少し勇気をもらって背中を押されたような気がしました。
この時代は今より女性にやさしかったんですね。時代背景がわかると源氏物語は楽しくなります。
恋ということは心身傷つかずにできれば幸せだと思われるかもしれないが、どきどきしたり、傷ついたりする分
、この世をどれだけ懸命に生きていることに気づかせてくれるのではないか。
源氏の君と源内侍の恋の駆け引きが大変印象的で、古い歌になぞらえたやりとりをするシーンや、瓜作りの妻になってしまおうかと源内侍が拗ねてしまうところが、とても世界に入り込むことができました。気高くパワーのある内侍を現代の女性も見習ってよいのではと感心しました。大変興味深かったです。次回が楽しみです。
源氏と頭の中将の痛快なやりとりに式部の筆がさえます。教養あふれる熟女内侍に完敗です。
源氏の女性(老女)に対するやさしさが表されている内容ですね。これが女性にもてる基本でしょうか。
なごやかな雰囲気の中に思ったことをのびのびと言えることに気持ちがなごみます。源氏物語に、教養の高さを感じて千年伝えられている文化すばらしいことです。学習出来ますことに感謝です。
若き貴公子と老女の逢瀬の様子が面白い。琵琶の音にひかれ近づく源氏を誘い込みつれなさに怨みごとを言う。そのしつこさにうんざりしながら、あまりすげなくするのも出来ぬと女の誘いに従ってしまう。女郎蜘蛛につかまっていく蝶々のように思えてしまう。
いつものことながら、登場する女性達が堂々としている、誇り高き姿に感服してしまう。自分が周りからどう評価されているか、醜い私、年取った私…などとちっとも思っていない。あるのは、教養と恋愛での自分磨き。
現代の女性よりも、女性であることを謳歌しているかもと思った。
第46回「松波源氏の会」2015年11月28日<紅葉の賀7>
テーマ:源内侍の懸想―登場の背景
1. 源内侍という女性の年齢と容姿の形容は物語の中でとても異色だが、バラエティの拡がりということでは極めて面白いと思います。老女の恋は、しかし現実的なことで、切なく訴えかけてくるようです。
2. 今回よりはハイミスとの恋模様。文章の言葉が具体的で、映画やアニメやマンガにすぐできそう。源内侍のバアサン度はとても高い。しかも教養あり、文学の
素養も抜群。源氏が興味を持ったのもわかるけれど返ってくるものも大きかったね。
3. 今回の源氏は「源内侍」の登場で場面が大きく変わり驚きあり笑いありと楽しい場面でした。こんな女性うらやましい。
4. 今回の源氏程、声を立てて笑った回はありませんでした。周りの知り人の中から内侍に近い人を思い出したりしながら楽しい時間を過ごしました。
5. 色事の好きな源氏を知らない帝の、左大臣に同情はするものの、北の方との
仲がしっくりいってない源氏を責め切れない。父親としてのこまやかな情がよく書かれている。厳しく言えば情報不足とは言え、親馬鹿な一面が見えてくる。
6. 源氏と周りの女性との関係を少し深く分かり楽しい時間でした。その時代の貴族社会も分かってきました。
7. 今回2回目です。当時の時代背景を説明頂き、興味や理解が深まりました。
男女同等という貴族社会の中で老女といえど生き生きとしていること(恋愛、男女
関係)がわかりました。女性の生き方としては現代につながる部分がありますね。
2015年8月22日<紅葉賀6>
我が子を抱きながら帝に対する罪の責めに苦しむ。二人の愛どころでない。藤壺に較べ源氏の態度は無邪気すぎる。
罪の子面会した源氏の立場の厳しさ。それをつきつけられた源氏の苦しさ。このつらさから逃げられる二条の邸の姫君も成長していて源氏の苦しさをやわらげる。一夫多妻制の下の女の苦しさに読んでいて息がつまりそう。
藤壺の宮と若宮に会った時の源氏の何とも言えない切ない重い気持ちが伝わり説明のしようがない位でした。終わりに女房のお陰で藤壺の宮の源氏への思いが伝わって私としてはまずまず良かったと思いました。話は一転して女君の成長ぶりが描かれてこれからどのような大人の女に育っていくのでしょうか。その変化が楽しみです。
なごやかな雰囲気のなかに熱心に交わされる会話に感動いたしました。お一人おひとりのさりげないお気遣いに触れしあわせな気持ちになりました。
源氏物語について全くの白紙の状態で参加しましたがわかりやすい先生の説明や皆さんの感想を聞き興味がわいてきました。イメーシ゛がわきました。とても充実しました。
藤壺との緊張感あふれる場面、二条の姫君との心あふれる間柄が対照的で見応え、読み応えがあった。
源氏は「若宮という花が咲いて二人の恋も花開くことを願っていたがそれははかない望みだった」と添え書きしたが、藤壺の返歌では「誕生を祝福できずわが子を疎ましく思う気持ちを率直に歌っている。」不倫という行為に対する対処の仕方が男女で深刻さが違うところがよく描かれている。
若紫からむら紫の上へ変わりつつある女性の姿を式部は細かく描写して成長が益々楽しくなります。
藤壺の苦しみ、我が子の存在すら疎ましく思う程の悩みに対してやはり源氏は男で苦しんだとしても解放される場を持っている。藤壺の苦しみをどこかで解放して少し楽にしてあげたいと思います。
若紫が幼い時からだんだんと成長し女らしく育っていくさまがとてもよく表現されていることに感服してしまいます。藤壺の苦悩も歌を通してよくわかりました。
藤壺、源氏の苦悩と姫君の成長がよくわかりました。また、わずかな紙面でしたが、王命婦の積極的な行動が利いていました。女房がリアルな物語は他にはないと思います。
第44回「松波源氏の会」2015年5月30日<紅葉の賀5>
4月、藤壺は若宮を連れて参内し帝と対面します。帝はあまりに源氏にそっくりな若宮を見て驚きますが「ならびなきどちはげにかよひたまへるにこそは」と感激するのでした。
(感想)
恋の仲立ちをした命婦、また密通の結果としての子の誕生と三人の複雑な感情が良く表されていると思う。対面した帝の喜びの気持ちが伝わってきますね。
複雑に絡み合う心の糸が少しほぐれて更にからみ合うような展開に、目がはなせなくなっています。
源氏の若宮を見た時のかわいさとナルシステイックな感想と「心の鬼」に怯えつづける藤壺とがあまりに対照的で強い印象を与えます。藤壺はずっとこの苦しみを抱きつづけて気の毒です。
不倫の子との対面での帝の対応が興味深い。源氏に生き写しの若宮に驚くが、不倫には考えが及ばず並外れた美しい者同士だから似通っているのは当たり前であると納得しているが、少し無理があるようだ。問題を避けている。
また源氏を臣下したのが心残りで、これに対し若君は「疵なき玉」と思い大切に育てている。このような疑心を持たない帝の態度は、源氏・藤壺の二人には居たたまれない立場に追い込んでいるようだ。
皇子が生まれて源氏・宮の立場も気持ちも変わっていく。それぞれの気持ちの動きが美しい古語で書かれ面白い。現代でも不倫は大きな話題を呼び小説の題材になるが平安時代、宮廷という世界ではのっぴきならない緊張の中での出来事だったろう。紫式部は今回もまた私達を物語の中に引き込み魅了した。
帝の源氏に対する父親としての思いがずっと今まで引きずっていたのを感じ、人間性に触れた思いがしました。若宮の出産に伴っての藤壺の苦悩がとてもよくわかり、そしてあまりにも自分に似ている源氏の驚きようなど内容のこい場面でした。
中身の濃い内容で興味深くあっという間に時間が過ぎてしまいました。次回を楽しみにしております。
参加させて頂いて浅いのですが回を追うごとに訳では味わえない心の機微が伝わってきて改めてこの時代にこのような物語を書いた紫式部の偉大さを感じます。特に今回は帝と源氏と藤壺、命婦の心の機微がよく読み取れました。
帝・源氏・藤壺の心理描写が細やかで大変面白い場面でした。また、手引きをした命婦がどれだけ主人を思っていたのかも感じさせる場面もあり、多角的に人間をとらえている作者の力量に驚くばかりです。また、若宮の愛らしい表現には、子育て経験ある母親の眼差しを感じました。
第43回「松波源氏の会」2015年2月28日<紅葉賀4>
葵の上の正妻としての取りすました態度(源氏にも半分罪があるにしても)を描いて、次に大臣の源氏への惚れ込み方を対照的に表現しているところが面白い。また、藤壺の苦悩が良く伝わってきた。
久しぶりに参加させていただき登場人物の深いところを聞くことが出来ました。源氏物語にただただ触れることができるのだけです。深い内容は読み取れませんが、次回を楽しみにしています。
源氏物語の中でもクライマックスの所だと思います。源氏・宮のそれぞれの気持ち、宮の誇り高き強さが印象的でした。
娘に冷たい婿に対しての父親である左大臣の愛情・行動が少しユーモアでもあるがよくわかるな。貴人でも同じなんですね。
源氏物語の原文にふれてまだ回を重ねることが少ないのですが、、物語への見る目が変わってきました。この時代にこのようなことが書けたなんてすごいと思います。
藤壺が心を痛めながら産むことになった皇子がいよいよ誕生し、今後の展開が楽しみでもあり心配でもあり。
源氏と北の方の夫婦としての様子。源氏の北の方への気持ちが見えてまた北の方が今まではつんとすましているきれいな方とイメージしかなかったのですが、それ以外に育ち方やある程度のすばらしいものをもっていらっしゃるのが伺えて興味深く考えるものがありました。
ここまで物語を読んできて、意地が悪く冷酷な「正妻」を想い出した。たとえば、夕顔や若紫の母親がどれほど嫌な想いをして命を縮めることになったか。それと比べると葵の上が、心の動揺はあっても、それを、源氏に関わる他の女性にあらわにぶつけないというのは確かに女性の美点であると思う。そのことを源氏の言葉から気づかせてもらった。
第42回「松波源氏の会」12月13日<紅葉賀3>の感想文
テーマ:源氏と藤壺の切ない関係、雛で遊ぶ若紫
今日は二人の女房の心配を楽しく読んだ。藤壺に仕える命婦は三条の宮邸に来た源氏と他人行儀にしか対せない。まして藤壺の兄もいて三人の気持ちが手にとる ように分かるだけに命婦のつらさは大変だったろう。又若紫に仕える少納言は幼すぎる主人にやきもきしている様子が読んでいてわかる。
?
兵 部卿と源氏の出会いで互いに「女にて見む」「女にて見ばや」となる心の動きには異様さを感じる。宮が色っぽくもの柔らかであることから、源氏は「自分が女 としてこの宮にお会いしたらさぞおもしろかろう」と発想し又、宮は源氏の親しみやすさから、婿とは思わず「君を女にして逢いたいものだ。色めきたる心にな る」という。万事色好みの世界を覗いた感がするが、理解は難しい。平安期の特殊性なのだろうか。
?
藤壺とのせつない恋…若紫の無邪気さ、その落差が楽しませてくれます。これからの成長がどうなるのでしょう。
?
源氏物語を古文で読め解説により今までの源氏物語のイメージがかわってきました。とても嬉しいです。
?
「はかなの契りやとおぼしみだるること、かたみに尽きせず」の箇所の源氏と藤壺の苦悩がとても印象的です。若紫の可愛らしさが引きたちます。
?
藤壺への思いが通せないまま一方若紫への暖かい眼差しの好ましさが出ている場面でしたね。
?
若紫の無邪気な様子が印象的でした。でもあまりにも幼くてちょっと心配になります。藤壺がぴしゃっと源氏を拒否している応対が際だちました。「源氏物語」は主人公の女君になったり女房になったり様々な立場で読めるところが本当に楽しい物語です。
?
第41回「松波源氏の会」9月27日<紅葉賀2>の感想文
テーマ:青海波を舞う公人源氏と私人源氏、その妻たち
1. 行幸の日の青海波の舞のすばらしさが、背景を含め目の前に浮かぶような表現
がすばらしい。また北の方と若紫の二人の妻の対象的な表現から今後の展開が
楽しみですね。
2. 紅葉賀は行幸にはじまり、青海波の美しさあでやかさ・・・
そして源氏の女君を巡る今後が楽しみな七帖です。
3.「行幸」では短い文章の中に当時の位について知ることが出来、又行列の様子、
楽士の方達の状況も知ることができて驚でした。最後では北の方に対する
源氏の気持ちが語られていて中々面白く感じました。
3. 今回は有り得ない源氏の美しさを知った。自然さえもかなわない美しさ。こんな人は現代にはいない。正妻葵の上と若紫の二人の女性の対比も興味深い。特に
葵の上の立場には同情する。
今回源氏の行動に苦しむところと源氏が彼女を正妻としてきちんと認めているところがあって、ほっとした。
4. 北の方(葵の上)の人となりと不満を源氏の言葉で述べて居る。
一番の不満は、源氏に対して、恨みごと(不満)があるなら、直接はっきり言って
くれ、勝手に悪い方へ想像しないでくれ。これでは源氏の事情を釈明することも
出来ないし、おたがいに理解が深まらない。源氏は北の方として、尊敬もし、頼り
にもしている。この辺を早くわかってくれという。相手が「未熟」というなら源氏
の方から働きかけるべきと考えるが、それもしない。やはり、源氏も「未熟」と
言えるのではないか。
5. 原文を読む楽しさがだんだんわかってくるような気がして、これからを期待して
います。時代のこともわかりうれしいです。
6. 青海波を舞う源氏のこの世ならぬ美しさの形容に驚かされました。「いと恐ろしき
まで見ゆ」と極致の表現、その前の「神など、空にめでつべき容貌かな」に続く
ものですね。
7. 源氏の光り輝く美しさと舞を一度見てみたくなりました。再び若紫が登場してきたので、次の進展が楽しみです。
8. 原文で読むことの楽しさを知りました。今まで全く気付かなかった言葉遣いなど、
とても興味を覚えました。これからが楽しみです。このようなサークルがあること、
もっと早く知りたかったっと思います。
思い掛けず前島さん(高校の同級生)と御一緒できて嬉しさも一入です。よろしく
お願いいたします。
第40回「松波源氏の会」 5月24日 紅葉賀の感想文
紅葉賀がスタートしましたが試楽美しき…これからの源氏と藤つぼの心の揺らぎがどうなるのか次回が楽しみです。
試楽での源氏の青海波のすばらしさ、帝の源氏に対する父親としての愛情、最後に藤壺の源氏に対する気持ちが感じられて、なかなか変化があって内容のある章でした。
松波源氏の会も四十回目を迎えました。物語を原文で読むすばらしさを今回も感じました。疑問や感想を皆で話しあえるのがこの読書会の良いところです。今回は藤壺のちじに乱れる思いを味わいつつ読みました。
子煩悩な帝の源氏に対する感想を求められた藤壺の「ことにはべりつ」はあまりにも素っ気無い。何かあるなと思われても不思議でないくらいだ。源氏に「おほけなき心」があるため「あいなう御答へ聞こえにくい」という藤壺の精一杯の対応。緊張感がよく伝わってくる。
青海波の舞をはさんで、帝、藤壺、源氏、そして春宮の女御までの複雑な気持ちが良くかかれていますね。続きが楽しみです。
紅葉賀というめでたい宴の中に、源氏、帝、藤壺、それぞれの人物の心の中の思い等が、短い中にうかがえて心ひかれました。
源氏物語の原文にふれることができ、短い文、ことばの中に託された多くのことが先生の解説で知ることができ、原文の良さを感じることができ幸せでした。もっと早く参加していればとくやまれますが、これからもよろしくお願いします。
藤壺という女性の魅力が和歌によく出ています。教養あふれる内容のようでいて、分かる者にはわかる本音を折り混む、しかも言い逃れることもできるというすごい歌だと思います。源氏が惹かれるのは知性のある女性なのですね。
第39回「松波源氏の会」3月8日末摘花の感想文
末摘花の赤鼻の強調と紫の君のあどけなく愛らしい姿との比較が鮮やかな終わり方。最後の歌の鼻をうとみつつ「梅の立ち枝」はなつかしいという二つの感情が印象的です。(男性)
末摘花になぜこんなに気にかけているのかと以後が楽しみです。式部は残酷なまま末摘花を終わりにしないのかと思いますが…。(女性)
末摘花が少し変化して普通の女性らしくなった様子がほのぼのと見えて来て、今度の展開は?と思ったところが紅い鼻で一巻の終わりと言うか現実に戻った感じが伝わってきて何とも言えない。対比して紫の君の愛らしさが強調されて、これ又何とも言えず、私の心の中は整理がつかない状態です。(女性)
あの世慣れぬ姫君の成長ぶり、そして赤い鼻を茶かされていても豊かな黒髪の存在感はやはり源氏の心をとらえていると思えるのです。(女性)
末摘花も少しづつ世間並みになってきた。「夢かとぞ見る」とも思うが、あの赤い鼻は気になる。姫との逢瀬には心の満足感がない。これと対照的に紫の君とのやりとりには明るさがあり、心がなごむ。源氏には満足感がある。紫の君の素晴らしさを際だたせるために末摘花を登場させたと思う。(男性)
はじめての参加でしたが、よく分かる解説で源氏の楽しさを味わうことができて楽しくすごすことができました。幸せを感じました。もっと早く入っていれば良かったと悔やまれました。高齢ですが、これからよろしくお願い致します。(女性)
今回は末摘花がたをやぎ、やや世間並みになったり「さへずる春は」と返事をしたりして、読者もとてもほっとして嬉しい。「人は成長するんだ」と思えて。最後は又現実をつきつけられた。ここの場面の源氏は大きらいだったが、うちうめかれるほどの打撃もうけていると思えば同情もできると思えた。(女性)
結婚した女への淡い期待が裏切られた事の落胆ぶりとその後の若紫と常陸の君と対比が残酷な程に描かれていることが印象的でした。(男性)
「見送りて添ひ臥したまへり」と、顔をさらして源氏に甘えるそぶりをみせる姫君が、かわいらしく思えた。女性らしく変貌をとげたのも、やはり源氏だからだろう。頭の中将が相手だったらこんな風に成長しなかったかもしれない。(女性)
第38回「松波源氏の会」12月14日末摘花の感想文
今回は末摘花が一人の女性として成長してきたのが書かれている。一生懸命歌を作ったこと、それをメモしていることなどいじらしい。(女性)
二回目の参加です。少し源氏の世界に入れたでしょうか。楽しい時間でした。(女性)
男女のコミュニケーションは歌のやりとりが一般的の中で、姫君から初めて歌が贈られてきた。しかも「手作り」で、出来が悪いが、その変化が嬉しい。これからが楽しみだ。(男性)
姫君の育った環境、宮家に仕えている人達の考え方がわかり、今後源氏との好みの違いがどんな風に変わり変化していくのか全然変化がないのか。その辺が興味深いものがあります。(女性)
末摘花の人柄が少しづつ判ってまいりました。何となくにくめないけれどでも…と思ってしまいます。世の中の動きを知っていくことは今の世にも通じていて、引きこもっている上品の家の姫君が気の毒に思います。(女性)
末摘花は容貌の特異さのみ印象があったが、挙動や性格の細かな所が少し理解できたように思える。なぞり読みだけでは分からなかった点。(男性)
末摘花が歌を上手に読めるようになって、ほっとした。容貌や、生真面目さがどこかおかしい女性として読者の笑いをさそっていたが、丁寧に読むと、いじらしい。私はだんだんこの姫君が好きになった。(女性)
第37回「松波源氏の会」の感想文
1. 下々の生活の様子や源氏の心根のやさしさが良く表現されている章ですね。
一人で読んでいる時と勉強会で感じることとの差があり、勉強会に参加する意義を
深くしました。
2. 今回は恋愛小説ではなく社会派小説であった。源氏の視点の幅広さを初めて知った。
自分一人で読んでいては気が付かなかった事である。やはり講義は受けてみるべきだ。
又源氏の人間性の一面も又知ったし、貴族から極貧の生活を垣間見て、それを心深く
感じ、更に想像を逞しく、頭中将なら何に例えるだろうかと、思いがはせるのも、又
おもしろい!
3. 源氏のあたたかさが表現されていて、うれしい場面。がっかりしながらも決して
棄てない。だから源氏はすてき!その源氏を創りだした紫式部はすばらしい。
4. 原文を丁寧に読み説いていただき源氏物語を深く感じることができます。末摘花は
余りに古風ですが源氏の君の優しさがあふれて嬉しくなります。
5. 末摘花のごく一部しか今まで知らなかったと確認しました。今一度初めから改めて
源氏を読み返してみたくなりました。
6. 赤い鼻の姫君。見た目が何の取り得もなさそうで、経済的にも相当困っている末摘花
に対する源氏の気持ちが伝わって来ました。そして即、行動するところ。素直に共感
出来ない部分もあります。けど、それが源氏の君なのかと妙に納得した部分もありま
した。
7. 女の美しさは容貌じゃない。立ち居振舞いが奥床しければ女の魅力はある。この点
末摘花は容貌も立ち居振舞いも満足するものがない。努力して示す気配りもチグハグ
である。いつか源氏の感性にあうような振舞いが身につくか、気の遠くなるような
話である。 70才台男性。
第36回「松波源氏の会」の感想。
みごとさなどを知り、彼女の今後について楽しみです。
出された。
私は紫式部のサービス精神だと思ったが、田中先生は、「本物の
貴族を描きたかったのではないか」と言われた。
本当に、そうだなと思いました。 (女性)
女性なのか私の中では想像がつかないし、思い浮かびませんでした。
それなのに見捨てずに、今後も見守って行きたい気持ちが源氏に
あるのが、最終的に感じられてホッとした気持ちです。 MY
男は女のもとを去って行くものだが、かえって、いとしくも心惹かれ
後見役を買って出る。ここに源氏の君の謎めいたところがある。
一見上から目線の行為のようであるが、早くに母をなくし、さみしい
思いをして育った者が持つ、弱者を見ると他人ごとに思えない、形を
変えた愛情の深さがあるのではないかと思う。 (70台男)
5.始めたばかりで、先生のお話を聞き、内容を理解するだけで精一杯
です。
平成25年3月23日(土) テーマ:源氏は見た!姫たちの○○○暮らしぶりを。(「末摘花」7回目)
今日は初めてなので良く分からないまま過ぎてしまいました。あらためて古語の難しさ・深さを感じました。(女性)
今回は格式あり常陸宮家のかつての生活ぶりが源氏の目を通して理解できて、とても興味深く面白く思いました。それに現在の宮家の暮らしぶりも見えて源氏の気持ちを汲み取る命婦と源氏との関係も…今後がとても楽しみです。(女性)
落ちぶれた宮家の様子が良く表現されている。その様子をのぞき見ている源氏の気持ちの使い方も良く表されていて面白い。(男性)
末摘花の周りの様子が手に取るように描写され、姫君フアンの私としてはここまではと気の毒に成ったり今後幸せな描写を期待したいですが…(女性)
姫を訪れぬ言い訳を深刻にせず少しいたづらっぽく言うあたり、悪者に成りきれない源氏の人の良さが思われる。「ほほえみたまへる」は、「少し悪な二枚目」がいたづらっぽく笑っているのが連想されて面白かった。(男性)
何十年振りの古語文にふれ先生の説明を聞いて内容を理解(読む)のに精一杯でした。古語の言葉を一つ二つ思い出しました。(説明より) 回を重ねていくと源氏の気持ち・様子など先輩の方々の様に読み取るようになれるでしょうか。楽しみです。(女性)
飛び立つように寒さに震えている老御達の様子・せりふが大変リアルで面白かったです。雪が降った翌朝、「をかしきほどの空も見たまへ。尽きせぬ御心の隔てこそわりなけれ。」という源氏の言葉に、夕顔と共に「夕ばへを見かはし…」たあの美しい場面を思い出しました。(女性)
平成24年12月8日(土) テーマ:後朝の文ーそれぞれの事情(「末摘花」6回目)
感想文
こっけい話のような内容になっているが末摘花の人柄、それを想像たくましく思いこんでいる源氏の君の気持ちが良く表現されていて面白いですね。
(男性)
末摘花フアンの私としては世慣れぬかたくなな姫君では有りますが最後に源氏の君が一生姫を見放さないとの心を聞いて安心しました。(女性)
勝手に期待をふくらましてきたが、現実にぶちあたり、その落胆ぶりは、喜劇をみるようだ。その中で源氏は、うち捨てるのでなく最後まで面倒を見る決意に好感が持てる。(男性)
後朝の文に託して源氏の姫に対する考え方が表現されていました。姫の様子が垣間見えてきますが、まだまだ本当の姿が見えてなくてこのような方に育てたのは、どういう状況でのことか思い巡らせると今後がなかなか楽しみです。(女性)
命婦も面白いと思いましたが、気が短くてちょっとずれた感じの侍従も、真剣なのでしょうが、吹き出してしまいます。
うまく世渡りのできない「常陸宮家」の家の雰囲気が、よくわかります。それにしても、身分や生まれだけではなく、教育が姫の一生を左右するということがよくわかりました。亡き父君から可愛がられ、今はおちぶれた姫君に、なぜか惹かれてしまいました。(女性)
理想の女性を求めたのに、何ともトホホな結果になってしまった源氏の様子が、おもしろい。末摘花のまわりの人の無力さ、事情を理解していない正身の様子も詳しく書かれていておもしろい。紫式部の筆力に頭がさがる。(女性)
平成24年9月15日(土) テーマ:しじまと闘って惨敗に追い込まれた逢瀬の顛末(「末摘花」5回目)
感想文
荒れはてた屋敷も姫君の事なんか考えていない使用人たちも、そして姫自身も自分の身の上に怒りつつある事柄が分からない状況も源氏にしては「深窓の佳人」モデルとして好ましく思う。このカンチガイが読者にはおもしろくてたまらない。紫式部は読者の心の動きが手に取るようにわかって筆を進めているんだろうなあ。(女性)
いつもは絶対にもてる源氏が今回はわざわざ会いに行ったのに何の反応もない姫の態度。源氏の当てが外れた思いがどれ程のものか考えると、なかなか面白いものがありました。(女性)
「いくそびか君がしじまに負けぬらむ」と「無しの礫」にいらいらして来たが、この無言という行為はひょっとすると姫君は初心なだけで「深窓のすばらしい女性」ではないかと、はかない夢を描かせる要素を持っていた。はじめての返歌をうけても「しじま」状態が続くのに、業を煮やし「強行突破」に及び、初めて現実にもどされ、源氏のショックは大変なものである。第三者から見れば、結末は時間の問題と思うのだが、「男女の情」にまったく初心な姫君を周囲が取り繕い、それを暴き、その現実に落胆する様子はコメデイーを見ているようだ。(男性)
今回はこっけい!!面白い!!姫君のびっくりぎょうてんの様を想像させるシーン。こんな筈では、とこれも又あ然とする源氏。読者も常陸宮の姫君の本性を知りたくて源氏の気持ちと一緒に読み進んでいくスリル。この後、どうなるんだろう!続きが読みたい。早く!(女性)
あまりに世なれぬ女君の対応に驚くと共に不思議な感を持った源氏。紫式部の筆力に思わず拍手します。(女性)
平成24年6月23日(土) テーマ:源氏、ものづつみの人に近づく(「末摘花」4回目)
源氏の「にほひやかな文」が、常陸宮の姫君の邸を一気に明るくしたように、今回は美しい3人の大学生の参加のおかげで、「松波源氏の会」も華やいだものになりました。10代から70代まで、幅広い年齢の方々が自由に感想を伸べ合う楽しい会となりました。
感想文
末摘花の途中からしか詳しい話を知らなかったので、そこまでの話が大変興味深かったです。これからの展開が待たれます。(女性)
源氏の今までの経験にはなかった姫の反応のない態度に対してのいらいらした気持ち。命婦の気持ち。辺りの情景などがみえて今後の展開が待たれます。(女性)
学校の授業とは全く違う視点で、源氏物語を読むことができました。。(女性)
1 世なれない気配りのない女と、源氏の仲をとりもつ命婦の対応力には驚いている。
2 男親に育てられたと思う姫のぎこちなさは女房のバックアップもないため、一種の喜劇のように見える。(男性)
驚く位に世慣れない姫君が今後どのように変わってゆくのかが楽しみです。それにしても描写が美しくて。(女性)
源氏物語は心情の描写もすばらしいが情景の描写がすばらしく、イメージすることが出来やすいし、きれいな描写になっていることに感動しますね。(男性)
「源氏物語」の言葉の美しさに毎回心惹かれます。情景の美しさはまるで目に浮かぶようです。今回の末摘花は「ものづつみ」の人として描かれていましたが、極端に源氏をおそれるその行動、手紙も見なければ手さえも出そうとしないのですから、ある種に可愛らしさのようなものも感じます。顔のイメージ゛が先行してしまいますが、原文ですと新たな発見がたくさんありました。(女性)
「姫は素直な人だなあ」というのが今回の感想です。事前に末摘花の容貌をおぼろげにも知っているので、そりゃあそうだろうと客観的に見てしまうから源氏の様に全く境遇しか(系図とか)知らなければ私も源氏と同じく創造を逞しくしていて「何て、女なんだろう。プライドが高すぎるのか!」等、色々と考えてしまうところである。それにしても命婦の世慣れたキャラクターと「ものづつみ」との対比が又おもしろい。(女性)
今回初めて「源氏物語」の原文に色々ふれることができたので良かったです。自分が知っている源氏物語の世界と、今日学べたことが違っていたり新しい発見もありました。やはり読んでいると、その場面をイメージできるのでとても楽しかったです。(女性)
「八月二十余日、宵過ぐるまで待たるる月の心もとなきに、星の光ばかりさやけく…」頃に、亡き父を思いだして泣く姫君がいじらしかった。存命中から訪れる人のなかった父親王にしてこの姫ありということがよく伝わってきた。源氏物語は親子の関係が丁寧に描かれていてしみじみとする。あらすじしか知らない人は本当に損。原文を読むに限る。。(女性)
この末摘花もなかなか魅力的。不如意(?)な生活の中で俗世間の常識や暮らしの方便から離れて純粋にというかきちんと教育もされずに育ってきた。心ばえのよさ素直さはとてもすてき。命婦から残酷なまでに現実をつきつけられている場面は、痛々しく感じた。本人がわかっていないだけに切ない。(女性)
平成24年3月10日(土) テーマ:左大臣家の貴公子たちー婿殿と総領息子ととりまく女房たち(「末摘花」3回目)
世馴れぬ世間しらずの姫君に結果として冷たくあしらわれ、腹たち、いらだちはては夕顔の面影を見る妄想におちいる。まったく喜劇のヒ゜エロを見ているようだ。頭の中将との競り合いやこのまま引き下がれないという意地など会わせ見るといったい何をやっているのかと思えてくる。(男性)
源氏と頭の中将の恋のかけあいが物語をおもしろく盛り上げてくれます。紫式部の筆のすばらしさを読む女房達も楽しみにしていたことでしょう。
(女性)
頭の中将と張り合う源氏の気持ちがいままでの源氏の印象と違って面白く感じられました。頭の中将の育ちの良さの開放的ナアッケラカンとしたところも見えてなかなかでした。(女性)
源氏と頭の中将の関係も面白いと思いました。ライバルでもあり、友人でもあり、興味深いです。また、命婦に対する源氏の信頼感も良いと思います。(女性)
常陸の宮の姫君の実体を知らぬ源氏と頭の中将がお互いを意識して妄想を重ね恋心をつのらせていく様子がとてもおもしろい。
鳥羽一郎の名曲「兄弟船」”兄弟は生死のかかる海では協力して漁をするが、休みの日は酒場の女を張り合う”を思い出しました。左大臣家に仕える中務の君がおもしろい。(女性)
源氏物語が書かれてから1000年も読みつがれているが、それを期に映像化されているが、なかなか表現することがむずかしい様に思う。映画でもテレビでも中途半端になって逆に源氏物語を歪めて伝わらせていることを残念に思う。やはりむづかしい事だと思うが原文を読んで見ることが理解につながっていくと思う。(男性)
源氏物語は姫君だけではなく、女房がよく描かれている。今回は中務の君の憂いが実にリアルだ。こういうおもしろさは丹念に原文を読むからこそわかる。最近はやりの映画を見て、「源氏物語」だと勘違いする人が多いが、本当に残念だ。苦労しても原文を読まなくては。(女性)
平成23年12月17日(土) テーマ:源氏、姫君の琴の音を聞く(「末摘花」2回目)
思わぬ源氏の踏み込みに、とまどいながら「琴を聞く」を材料に気のきかない姫君を源氏に取り持つプロセスがハラハラさせながら機転を利かすようすが良く描かれていて面白い。(男性)
源氏の想い(考え方)の深さを感じたり命婦と源氏との上下関係を保ちながらのやりとりの絶妙さ。頭の中将の行動を通しての源氏とのやりとり等。考えがまとまりませんが。変化に富んでとても面白く思いました。(女性)
イギリス文学にはユーモアがある。命婦と源氏とのやりとり。源氏と中将との友情?その行動。コミカルの中にその登場人物の知性。愛憎、感情、才覚。魅力。一言
、おもしろい!会話を楽しむ(返歌を楽しむ)これこそが教養だ!(女性)
貧しく寂しげな姫君のかすかな琴の音と対照的に命婦と源氏。頭の中将と源氏のかけあいが何とも楽しくおかしいのが印象的でした。(j女性)
「かど」ある女房。命婦がおもしろい。ひょんなことから源氏の心をとらえた「末摘花」。その家で琴を弾かせたい。琴を聞かせたくないと心が揺れる。その場その場で出る言葉の面白さ。自分の立場も源氏の立場も姫の立場もそして気持ちかる命婦の動きが手に取るようにわかっておもしろい。(女性)
最近、源氏物語がテレビ放送や映画化されているが、どうしても表面的な表現で終わってしまってつまらない。これほど映像化するのにむずかしい物語はないんではないかと思う。ぜひ原文に少しでもふれて「源氏物語」を感じられたらと思う。(男性)
平安時代の物語なのに、姫君や源氏だけでなく、女房である命婦が良く描けていることに驚いた。映画で源氏がはやっていると聞くが、やはり原文でなければ本当の源氏物語のことが伝わらないと危惧する。源氏はストーリーではない。源氏の乳母子である命婦の言葉の軽さに思わず笑ってしまった。(女性)
平成23年9月18日(土) テーマ:大輔の命婦、常陸の宮の姫君を紹介す(「末摘花」1回目)
輔の命婦が源氏に末摘花を手引きする場面。さすが「色好み」人の心をよく知っていsる。①心細い境遇②琴が好き で源氏の関心を引きさらに「心ばへ。器量はくわしくない」とはぐらかし、琴も遠くからさわりだけ聞かせ、源氏の関心をつなぐなど「大輔の命婦」は大した女だ。(男性)
古語の美しさと深さ。「火影の乱れ」にはちらちら動く灯台の火や、姫君達のしどけない姿まで感じる。だから原文で読む「源氏物語」は面白い!(女性)
大輔の命婦を初めて知りました。今後の彼女の言動が楽しみです。(女性)
思へどもなほ飽かざりし…との名文で始まり、夕顔や空蝉・軒端の荻などの女君たちを思い出し、夕顔みたいな女に是非会いたいと思う源氏の気持ちはよくわかる。そこへ登場の大輔の命婦がちょっと言ってしまった琴を弾く薄幸な女性…源氏が興味を示さぬはずはない…。紫式部って本当にたくみな語り人。(女性)
この会に参加して三年目になるでしょうか。原文を読み、その解説をお聞きすると源氏の色恋沙汰の中味を思われているが決してそのような内容でないことが少しづつ解ってくるようになった。(男性)
平成23年6月25日(土) テーマ:少女と少納言、新たな世界へ(「若紫」8回目)
コメント集
1. 源氏の若紫に対する気持ちがよく分かる場面でした。
ただいまいち源氏の本心がわかりませんでした。(藤壺にまだ
気持が行ってしまっていて、少し若紫がふびんです。)
2. 形式だけでも結婚というのがおもしろい。少納言と寝るのははっきり
禁止したり、一つの夜具に共寝をしたり。 女性
3. 源氏の女性とのつきあいをみると年上や夕顔など、色々な女性が出てく
るが、一人の人物の色んな趣味の一環と考えれば、この巻きの若紫もうなずけた。
源氏の女性を好むには一本の筋があって、それは、「おぼろげにはあらじ」
の人である。天分、性格、美貌、その他全てに於いて、並みでない人物
が好みという点で理解できる。 女性
4. 源氏物語のメインの源氏と女君の出逢いからの展開が読んでいて楽しく、
今後の二人の夫婦の形がどうなるのか興味しんしんです。
5. 若紫がかしこく、秘めた才能のある子供であるという伏線が今日はっき
りとわかりました。 匿名
6. 若紫が二条の院に来て、二条の院の様子が描写されて邸宅の雰囲気が
垣間見られました。
若紫の年齢よりも幼いところと持っているセンス、中に持っている意志
のはっきりしているのが受け取れた今回でした。 女性
7. 源氏にひきとられ育てられどの様な理想な大人に育つのか興味深い。賢い少女のことだから楽しみでもある。
8. 若紫の巻が終りましたが、やはり自分で読んでいることよりも、先生の
解説を聴きながら読み進めていくと実に深みが出てくるような気がします。 男性
9・いろいろあったが「今はただこの後の親をいみじう睦びまつはしきこえた
まふ」。こんなにうまくいくのかと若干疑念が生じる。実父との縁の薄さ、
持前の素直さのためだろうか。 70歳台 男
平成23年2月26日 テーマ:少女、源氏の元へ(「若紫」より)
第27回目の感想文
時代は問わず、男性は自分の心に強く生きる動物のようです。(女性)
源氏の豊かな感情が若紫への想いにいちずに向かっていくところなど感動でした。情景が美しく思い浮かべられる文章にひたり気持ち良かったです。(女性)
源氏が「若紫を迎に行こう」と決めてからの展開がスヒ゜ーテ゛イでカッコイイです。少し前には葵の上にツンケンされていたのに…(笑)「かき抱く」良い表現です。(女性)
若紫の君がいよいよ源氏の邸へ。その前段の源氏の生活、決断、そして決行への素早い行動力。でもその中に現れる源氏の洗練された物腰、言葉が垣間見えて物語の中に自分が入り込んでしまいました。(女性)
様々な立場の人の心理や思惑が丁寧に描きこまれていて面白い。三日間来ない源氏への乳母の不満や、主(若紫)がいなくなる時の、女房達の困惑。こういう階層の人々の気持ちに及んでいるのが「源氏物語」の凄いところだと思う。女君(葵の上)が「とみにも対面したまはず」や「しぶしぶの…」という表現で、心通わぬ夫婦の姿が浮かび上がってくる。若紫への執着も一層、際立つ所だ。(女性)
今回は源氏の行動力がきわだっていた。時にぐずぐずしている少納言に「帰りたいならここに居るかどうかは君の心次第。送ってやるよ。」という所が面白い。(女性)
「若紫」はとても魅力がつまった巻だと思いました。源氏が少女が幼いことの壁を感じていた。世間体を気にしていたというのが意外でした。それでも、やはり少女への想いを諦めることができなかった源氏がとても素敵でした。(女性)
少女の略奪劇に対する源氏の決断力・実行力は十八歳の若者としては目を見張るものがある。何か、やんごとなき身分に備わる、身分保証や自信が背後にあるように思われる。(男性)
光源氏が少女を連れ出す過程が見事に描写されていたと思います。読み手に源氏の格好良さをよく伝えている書き方だと感じました。言葉の美しさも巧みです。登場人物をうまく書き分けられる作者の文才に感心しました。(女性)
内容がドラマチックで思わず「くす」と笑えるようなコミカルさも感じ楽しめました。(女性)
今までは若君が割合早い時期に源氏の元に引き取られたと思っていたのですが、ある程度の日数が要されていたことがわかりました。しかし、時機を得たら一気な行動をしたことは正に源氏らしい一こまです。(女性)
平成22年12月11日 テーマ:少女と一夜を過ごす(「若紫」より)
第26回目の感想文
最愛の祖母に死にわかれた少女は運命にもてあそばれる。この少女のもとを訪れた源氏と父宮の二人を紫式部は本当に鮮やかに書き分ける。読者は引き込まれて読む。次の展開が待ち遠しい。宿直人として一夜を過ごして朝帰りする源氏にあたかも「ことあり顔なりや」とからかう作者。原文ならではの楽しさ。(女性)
それぞれの立場「源氏・父宮・乳母・君」の気持ちが良くわかる。その心理の交錯が面白い。又、物語の展開が次々と設定されるので読者は次はどうなる?と先が知りたくなる。(さすが式部) それにしても紫式部の人間の分析力、描写力は世界の源氏といわれるゆえんでしょうね。(女性)
源氏の美少女趣味というには余りにもあっけらかんとしており、又、少女の幼さとあいまって非現実的なおかしな場面を見ているようだ。(男性)
少女が、訪れたのが父だと思っていたら源氏であるとわかり、おもわず乳母にすがる所がなんともほほえましい。女の子の気持ちが手にとるように描写されていたのが印象深かった。帰朝する時の清らかな自然描写(深い霧と霜)があるからこそ、この場面が清冽な美しい場面となると思う。
原文を読むからこそ味わえる事だと思う。漫画や某氏の源氏をなぞって、読んだ気になっている人は大損をしていると思う。(女性)
源氏の会、参加楽しかったです。今も昔も家族(親子・夫婦)の絆を思いしらされた勉強会でした。どこまでさかのぼっても人間の営みの中での様相ですから、深く深くデイスカッションしたくなるような会でございました。有難うございました。(女性)
先生の解説を聴きながら読み進んで行くと、原文はもとより訳文では伝わってこない事まで解ってくるように感じます。勉強会の前には何回か読んでくるが、先生の解説を聴くのが楽しみです。(男性)
少女が源氏に対してどう思っているのかここだけでは判断しかねるが乳母と共に安らかな日々を早く取り戻して欲しいと願わずにはいられない。(女性)
若君(少女)の愛らしさがなんとも言えず源氏の心魅かれる気持ちと共にこれからの展開がより楽しみになります。いろいろ取り様がありますが物語のメインは源氏と紫の上と思っていますので。(女性)
平成22年9月11日 テーマ:少女が近づく
第 25回目の感想文
この短い文章の中に「かたはらいたし」という言葉が3つも出てきました。それだけ少女が無邪気であるのだと思います。このような場面は、教科書では省かれがちですが、とても重要ですね。(女性)
初めての参加でしたが、とても楽しめました。源氏物語をますます好きになれました。これからもぜひ、源氏を味わっていきたいと思います。この会に誘ってく ださったT先生に御礼申しあげます。ありがとうございました!!次回からどのように話が展開していくのか楽しみです。(女性)
自分で読んで解ったようでも先生のお話を聞くと別の事だったりもっと深く理解する事ができて、参加する意義を感じます。(男性)
少納言の教養ある立ち居振る舞いが式部の姿と少し重なっているように思えます。姫君達の傍には教養ある女房がいたことを改めて思いおこされました。和歌の力もしのばれました。(女性)
光源氏の母の面影が藤壺への恋、そして若紫へといたい程に感じられ美しく表現されているのが印象的です。(女性)
源氏が心ひかれている少女の状況(住居の様子や面倒をみてくれていた尼の死)がとてもよく表現されています。後ろだてを無くした少女がこれからどのように成長していき、どのような境遇を過ごしていくのか興味しんしんです。(女性)
「少女が近づく」ととても興味深いテーマでの講座がスタート。三時間という長時間が長いと感じない間に閉じられるときが来ていました。イメージで読むとい う中でそれらをふくらませるためのお話、楽しく正にイメージがふくらみ豊かになりました。難しいと思っていましたが楽しい時でした。(女性
)
尼君が亡くなった後に、少納言が源氏にかなりこまかに少女を取り巻く状況(父君方に引き取られることへの不安)を語っていた場面が印象的でした。何度も、 源氏が尼君に少女の後見を頼んでいた姿があったからこそ、信頼して胸のうちを明かしたのだと思います。人間関係を丹念に描き込む作者の筆力に感心しまし た。(女性)
十代の少女をとりまき、後ろだてのあるなしで境遇が変わるということがよく表されているのがわかり面白く思う。(もっとも現代にも通じるかな?)それにしても十代に恋の詞を送るとは感じ入りました。(女性)
源氏はなぜ若紫にひかれるのか。
①若紫と源氏は境遇が同じ。祖母をなくして孤児となったばかりでなく母親がいじめられて死ぬことになったことが同じ。
②若紫の「根」が藤壺と連なっていること
などがよくわかった。(女性)
平成22年6月19日 テーマ:藤壺との恋・密会・懐妊
24回目の感想文
多くは語られていまいのに、とても映像が浮かぶような描写で紫式部は凄いなあと思いました。藤壺と源氏の密会から懐妊までの人々の心の動きが細やかに特に 弁と命婦の君が互いに藤壺の子供を悟るシーンが印象的でした。歌で気持ちを告げ想いをやり取りしているのを読むと昔の人は教養がなければ大変だなあとあら ためて思いました。(女性)
たった一言の「し」と言う文字だけで、かつてあったであろう出来事が想像できるという言葉選びに感動しました。遂に思いをとげた源氏と藤壺の今後の物語とともにますます楽しみな展開に心ときめきます。(女性)
源氏物語の作品の中でドラマチックな場面が今日の勉強会の中味だと思われる。特に今日だけの事ではないが古典では、特に源氏物語では日本語の奥ゆかしさ・美しさが表れていて、深い意味が解らなくても、やさしい感覚になれるのが楽しい。(男性)
現代にも通じる恋ではあるけど密会の恋にこれほどまで恐れを持ってそれもでも愛してしまうことに何とも言いかたい気持ちです。一目ぼれとはこういうものかしら?心からの恋が義理の母というのも運命的な物語だと思う。(女性)
藤壺の宮との密会。文中に前回もそんな機会があったことがしのばれ、宮の心の葛藤。結果の懐妊に悩む女性としての気持ちがかかれてあり、そのことについての身の廻りにいる人達の様子。盛りだくさんの文で私の筆では書き切れない内容でした。(女性)
道ならぬ恋に心が激しく行き交う宮と源氏の描写が古語でなんとも言えず表現されている所に源氏物語の魅力が満載されていると思います。ますます読み続けることが楽しみです。(女性)
内容に圧倒されてしまい言葉が思いつきません。(笑)たった一文でその状況が想像できるそのリアルさが凄いと思います。「御直衣~」の描写だけで2人の行 為の気持ちの激しさが伝わってきます。又このような恋愛こそを「悲恋」というのだなと目からウロコが落ちる気分です。最後ね…やっぱり惟光は素敵だなと思 いました。(女性)
密会の秘事は「命婦の君ぞ、御直衣などは、かき集め持て来る」の一行ですましている。これが「懐妊」をもたらし。二人の苦悩が始まる。なぜこんなことにな たのか。道ならぬ恋。お互いに好きになってしまったから仕様がない。「あさましき御宿世のほど心憂し」と源氏と出会うのも自分の運命(前世からの因縁)で 「のがれがたき御宿世」であったのだろう。子まで宿した罪深さ。秘密を共有した二人の関係はますます付加待ていく。人生いろいろ、こんな事も起こるのであ ろう。(女性)
藤壺と源氏ののっぴきならないかかわりが緊迫した文章で綴られている。藤壺のおののきが手にとるようにわかる。妃の懐妊は私事ではないこと。帝(国)をあ ざむき通さねばならぬこと。でも月が進み、体はふっくらとして、顔はやつれてそして美しい。様子も心も手にとるように理解できる文を楽しませてもらった。 (女性)
平成22年3月13日 テーマ:少女を心に秘めた源氏の周辺事情
冷え切った夫婦関係の記述は、新聞の人生相談欄を読む思いである。「…心も解けず、うとくはづかしきものにおぼして…。」これでは血のかよったふれあいは 出来ず、改善への出口も見つからない。源氏のただ「おぼしなほる」を待つだけでは解決にならない。周囲に適正なアドバイスをする人がいなかったのか、残念 である。(男性)
今回、初めて参加させて頂きまして、有難うございました。普段大学では英語を勉強しており、古文に触れる機会がなかったので、とても楽しい時間でした。原 文で読むことが不安でしたが、解説も分かりやすく源氏物語の面白さの一端をかいま見れました。ぜひ、また参加したいと思います。(女性)
夫婦の行き詰るような会話がとても重い場面でした。時代が変わっても人間はそうそうかわらないのですね。とても1000年前に書かれた物語とは思えず作者 の筆力にただ脱帽です。また聖と僧都の生き方の違いや、聖を優れた者と見ることのできる、桐壺帝の人間味。さすがに源氏の父です。(女性)
自然の情景の美しさ。そしてそれをめで楽しむ雅。それぞれの心の動き、読み進む程に源氏の奥深さが知れて楽しみが広がります。(女性)
岩によりかかかっている姿にまで目を奪われてしまうなんて、ますます源氏像が美しくなっていきます。若紫が心ひかれている様子が可愛いかったです。今回は惟光が出てこなくて残念でした。(笑) (女性)
源氏に対する人々の思いや若紫のほのかな愛などと対照的な妻、「葵の上」の態度が生き生きと表現されていて面白い。一回欠席したので久しぶりに解説していただいたが大変面白い。(男性)
ほとんどの人々、童女にさえ美しいと思われ美そのものの源氏の気味が妻にだけとげとげしく会話するキ゛ャッフ゜に式部の物語のひろがりを感じた。宴の様子はまことにのんびりとロマンチックでなつかしい。
世俗の聖と身分の安定した僧都の対比が重しろぴ。身分は低くても源氏に自分の一番大切な独鈷を送る聖とブランド品の数珠と薬壺を送る僧都の人間性の違い。 紫式部は良く書き分けるなあ。葵の上と源氏の関係。息詰まる言葉のやりとり。本来ならきっとうまくいくのに。何とかしてやりたいなあと横からみていて思 う。
(女性)
北山での送別の宴。北山の自然の描写はそこに自分が身を置いているようでしたし、京から迎に来た方達が即興で合奏出来るのが、その頃の上流社会の方達の教養の高さが感じられました。妻の一言。初めて源氏夫妻の様子が詳しく見えて中々考えさせられるものがありました。
平成21年12月19日 テーマ:常識への挑戦―夢見る源氏の覚悟のほど
垣間見た少女の魅力に源氏は頭に血が上っていく様子がわかる。源氏の若さから情熱からの言葉を僧都の常識がぴしゃりと止めるところが面白い。(女性)
源氏物語=もののあわれと言われているけど私は、情より叙事的な描写が大変、楽しくイメーシ゛が沸いて、楽しい。どうも源氏が、女の子〔紫の上)にひかれる気持ちに違和感を感じる。これから先が楽しみ。〔女性)
一見無茶な「紫の君」の略奪につながる少女との出会い。お膳立てのうまさに感心している。初印象の「ねびゆかん様ゆかしき人」から「限りなう心を尽くしきこゆる人」の藤壺への連想。これが尼君から少女の身の上を聞き、ますます藤壺の身代わりとして「心のままに教へ生ほし立てて見ばや」の考えを強くしていく過程が後ろ身のない少女の行く末に、余命いくばくもない、尼君の不安が加えられ、説得力ある展開を見せている。又以上のドラマが病気治癒のため、俗世間を離れた山寺で源氏の心細い心の状態で、事を展開させている。ストーリーテラーのすごさを感じている。(男性)
今の人にも通じるものを「源氏物語」に感じてきたが、今回は平安時代の貴族の空間を堪能した。北山に泊まる、闇の中の源氏が向こうの部屋にいる女性や尼君の身じろぎ・数珠のかすかな音・気配を感じる場面。また、遣り水に篝火が写る中、「そらだきもの」と「名香の香」がまじり、さらに源氏の「追い風」用意が立ち上るところなど、とても幻想的でデリケートなものを感じた。(女性)
10代の少女にこんなにも想いを寄せるのに、尼君・僧都の反対はよく理解できるが、それにしても18歳の源氏の一途さはいつものごとくピュアで驚くしかない。(女性)
今まではすぐに少女を源氏に託したのだと思っていたのですが、源氏の思いがまず、拒否されたことで、次に若紫に対する思いがつながっていく事が想像できる。(女性)
平成21年9月26日 テーマ:涙の出会いー北山の少女と明石入道の女と
自分で何回か読んでいるが、先生のお話を聞いていると、イメーシ゛が広がって行き、面白さ、奥深さが少しは解ってくるように思えてくる。次回を楽しみにしています。(男性)
年齢も同じ人が(明石と若紫)氏と育ち方で、今後の展開が楽しみだと期待するので次回待遠しいです。(女性)
遂に若紫が登場!明石の君も現れて、これからが楽しみです。(女性)
古文で解説していただいて本当に深くて広くて源氏がますます楽しくなります。(女性)
情景が目に浮かぶ。特に走り来たる女の子の可愛らしい様は源氏のみならず読者をもひきつける。また、北山の晩春の風景は特に好き。明石の入道はどんな顔つきか、体つきか面白そう。(女性)
明石の入道やその妻がリアルで面白い。出世できない「ひが者」がリベンジを果たすために、娘に期待をするのはなんと残酷なことか。対する若紫の幼さが、伸び伸びして可愛らしい。こういう育ち方の違いから書き起こしていく作者はやっぱり凄い。(女性)
今日は美しい貝合わせ「若紫」を見せていただいた。小さな雀も描かれていて今日の読書会に花を添えた。源氏の供の者から聞いた「明石」の君と目の前で見ている若紫の姿。源氏の運命に大きく関わる二人の少女の登場を今日はたっぷりと楽しんだ。(女性)
源氏物語を読んでいて、あたかも構成のしっかりした「交響曲」を聞いているようです。全編を通じての主題は「藤壺への思慕」と思われますが、「権力の獲 得」の副題としてあり、これを愛した女と、それらとの間の子供の入内工作で結びつけていると思われます。「若紫」の章は、「紫の上」と「明石の君」のその 後の展開への提示部分と考えられますが、紫式部は物語執筆前に、この壮大な構成を完成していたのか。もしそうだとしたら、驚くべき「構成力」と思われる。 (女性)


平成21年6月20日 テーマ:源氏、夕顔の真実を知る
夕顔を最後まで読めてすばらしかったです。原文は美しいですね。(女性)
夕顔の巻は古語の持つ情感や情景があます所なく表現されて心にくいばかりです。源氏は楽しいですね。(女性)
夕顔のイメージが今日で変わり驚きました。同時に空蝉も同様で「ニ道の別れ」で歌われた歌がそれをあらわしている様で興味深かたです。それにしても
若き源氏の君は現代の「誰」かしら?次が楽しみです。(女性)
夕顔は心の強い人だったのかと感じられた。心の内の悩みを打ち明けずにいることは常人にとっては重いことを一人で耐えていくことのできる心を私は羨ましく思いました。これからの源氏がますます楽しみになりました。(女性)
怖がりで子供っぽい女性というレッテルをはられがちな夕顔。原文を読むとそれが雑な読み方であることがわかります。人に、自分が悩む姿を見せたくないとい う美意識を持った繊細な女性。そして三位の中将であった父親の優しさが一行だけですが書かれてありとても興味深い箇所でした。原文を読まなければ、源氏の 本当の面白さはわかりません。(女性)
空蝉の話がどうしてこの場面に出てくるのかわからなかったが、今日謎がとけたように思う。六道のどこへ行ったかわからない夕顔と一緒に任地へ下る夫と共に去る空蝉。今回も紫式部の筆力・構成に感心するばかり。(女性)
先生の話を聞きながら、話が進んでいくと深く理解できて面白くなる。また、原文を読み直すとまた味わうことが出来て大変助かっている。(男性)
得体の知れない訪問に戸惑いながら、その不安を源氏に見せないで、さりげなくもてなした態度が夕顔を謎めかしている。相手の気持ちも考えないで自分の苦悩 をさらけだしては今の関係がこわれる恐れがあったのではないか。源氏らしき人への憧れ・愛などが表にあらわれてないので、後ろだてなしでは、生きられない 当時の女性の悲しさが背景にあるように思えてなりません。(男性)
平成21年2月28日 テーマ:悼む心 ー源氏 遺体と向き合う
夕顔の遺体の描写の美しさにも感動しました。私は「声も惜しまず泣きたまふこと限りなし」この一文が強く印象に残っています。皆さんの話題にもなりました が、あまり男性が泣いている姿を見たことがない今、この時代の人々の悲しみに対する接し方に学ぶものが多いなと思いました。(Y・S)
この中で「紅の御衣」というのがとてもイメージが鮮明である。そういう華やかな場面から死の場面への移ろいが何とも悲しい。雅な方の生活、歴史が知られて楽しくもある。(女性)
夕顔は幸せだと思いました。源氏のピュアに改めて驚き右近の律儀さも古の時代とは申せ感心するばかり…(面白くて感謝いたしてます)次回が楽しみです。(M・N)
若き源氏の初恋は本当はこの夕顔であたのかと思われる場面を感じつつ読みました。日頃は華やかな源氏がホ゛ロホ゛ロにクタクタになっている様は興味を引き ます。惟光の仕事ぶりを見るに、昨今の中川某の行動を制することができなかった秘書官達の無様さが情けない思いです。(女性)
何回か本を読んで出席しているが、先生からいろいろそして直接説明して頂くと、更に理解が深まっていくのが大変参考になる。やはり独学には限界があることが判る。(T)
夕顔の突然の死に源氏がとまどい容易に死を受け入れられない様子が微細に描かれ、身分を考えると、異常な行動ではあるが、かえって、源氏の純愛ぶりが強く感じられ感動した。(男性)
夕顔の様子(死相も現れず美しい)からも源氏は夕顔の死を受け入れられないだろう。「うはむしろ」からこぼれ出る美しく豊かな黒髪、対面した時にまとって いた「紅の御衣」が帰り道でも心から離れない。美しい描写の連続であきない。最後の二条院の女房たちの反応もさすが紫式部と思わせる。(H・I)
夕顔の死に直面した源氏の様子、深い悲しみに、心を乱され、でも表立って表現できないところ。源氏と惟光の対比。また最後の三行に書かれている第三者の目でのこの出来ごとに対しての見方がまた面白いと思いました。(女性)
源氏の悲しみがつきないものであることが、多様な表現でよくわかります。「目くれまどひて」「われかのさまにて」「御せきあぐるここちしたまふ」「御ここ ちかきくらし」「胸もつと塞がりで…」など。十七日の月の光のもとで「上むしろ」から美しい黒髪がこぼれ出る描写に、動かせない、夕顔の死の悲しさを感じ ます。(C・T)
平成20年12月13日 テーマ:「源氏、孤独と闘う」
惟光が好きな私としては彼の登場シーンが一番内心で盛り上がりまし た。そしてその後「君もえ耐へたまはで~」から源氏の惟光に対する絶対的な信頼感が伝えわってきました。高校時代に読んだ夕顔の巻の鮮やかさが、見事によ みがえってくる有意義な時間を過ごせました。(Y・S)
源氏の心の動き、あたりの情景が細やかに伝わってきて源氏物語の広がり、その深さをひしひしと感じます。読み応えのある一節でした。(A・M)
ドキドキしながらお話を聞いてしまいました。今でが考えられない状況ですけれど、その場のフンイキがヒシヒシと感じられ、源氏のすごさを実感しました。久しぶりに参加しましたがなかなか素晴らしいですね。(M・N)
若い源氏にとってこの出来事はとても耐え難いものだったのにちがいない。「これはあの事のむくい」と考えても無理はない。惟光が来るまでよく耐えたものだ。惟光に会った途端、心がおれてもしかたなかったと思う。(H・I)
描写が真に迫っていて細やかでびっくりしました。人の心の動きも細やかに描写されていて臨場感がありました。原文から読むことのよさをひしひしと感じています。(Y)
現代文に訳してある本は数多くかつ有名な作家が訳されているが、この松波源氏の会では原文を解説しながら進ので古語の微妙な言い回しなどが良くわかて大変面白いし、深さが解るように思います。(I)
初めて参加させていただきましたが分かり易く本当に学生時代にもどったようで熱中しました。知らないことが多く改めて勉強させていただいた意義あるものでした。これからも楽しく参加させてください。(M・N)
突然の夕顔の死の遭遇した源氏のとまどい、悲しみが心理状態の変化を含めて表現されている。その素晴らしさに感動した。(T・M)
今回はたっぷりと女君との別離を読みました。古文の基礎を改めて考えさせられました。助詞をまた勉強し直してみたいです。(N・Y)
枕上にいとをかしげなる女」が座っているという出だし、「面影に見 えてふと消えうせぬ」という表現。本当に恐ろしい描写です。闇の深さと時間の長さを感じさせる秀逸な表現にまたまた魅せられてしまいました。原文ならでは の迫力を楽しみました。やっぱり「源氏物語」は原文で!(T)
平成20年9月27日 テーマ;「夕顔の魅力ー柔らかさと憂わしさと」
「対比・比較の名文」の一言につきる本日でした。空蝉とのコントラスト・源氏の心情と夕顔の思いの格差・五条の住まいとなにがしの院との大違い等々。世間 では夕顔をはかない「女らしい」、美しい「女」そのものの様に印象づけられている様だけど、今回によって私観だけれど、不安を抱きながらも決行する性格等 から、実業家タイプの男っぽい性格、見かけの美しさ故に誤解されているようだ。女っぽい源氏と気が合うわけだ。きっとジュデイ・ホスターみたいな顔をして いる。(前川)
夕顔について。美しく可愛い過去のある女。でも自分を見失わず浮かれている源氏のい同調せず。なにがしの院での2日間楽しかったでしょうね。(井上)
初めての講義でしたが楽しく学ばせていただきました。少し短歌をしておりますので歌に興味を持ちました。(女性)
「雨夜の品定め」で知った理想の女性に巡り合った若き源氏の姿が眼前に浮かび上がってきました。式部の歌の上手さも改めて知りました。(女性)
恋を語らう二人の充実したひとときが良く伝わってきました。それにしても自然描写の素晴らしいこと。
刻々と移りゆく雲の様子や「いさよふ月」「たとしへなく静かなる夕の空」など秋の涼やかな空気や匂いまでもが表現されていることに感動しました。(女性)
平成20年6月7日 テーマ:「やつしの恋ー恋に生きる源氏と夕顔像」
分室の門構えが目に入った途端に和の世界へ入りました。源氏の世界にはうってつけの部屋です。65歳ですが20代に谷崎源氏を読んで(光源氏は一度も好きになったことはない)千年前の人の心、男心、女心に魅了され続けています。谷崎の本は読みやすくてサラリとしていますが今回、原語を拝見し読んで尚一層とりつかれました。(三橋)
源氏が夕顔に惹かれる気持ちがよくわかります。今ならばこんな風な女性は沢山いるのでしょうけれど。二人の話し合い、すてきですね。(中川)
夕顔の巻はお聞きしていると情景が美しく思わず引き込まれうっとりとしてしまいました。(前島)
やつしの恋に挑戦する源氏のひたむきさの中にとまどいの様子がよく描かれており、興味深い。また未知の女性との遭遇の驚きも新鮮に見え十七歳の源氏の共感を覚えた。(男性)
魅力は夕顔の素直さ。下の品の人々の中にあっても卑下することなくふるまう。源氏が魅かれるのも当然。夕顔の置かれた環境を美しい文で描く紫式部の筆力のすばらしさに今回も驚かされる。(井上)
今回のハイライトは、「源氏『げに、いづれか狐なるらむな。ただはかられたまへかし』…女もいみじくなびきてさもあるぬべしと思ひたり。」ではないでしょうか。「だまされてみるか?」「そうね。だまされてみようかしら」こんなに平安貴族の会話が現代に蘇って身近に感じられるとは。田中先生の解釈の妙に本当に感服しました。空蝉とのかけひきの恋ではなく、六条わたりの女の気の張った恋でもなく、源氏は心から夕顔とくつろいでいる。恋とは「人にしむこと」納得しました。(塚内)
今回は源氏物語の中で始めて庶民の生活が出てきて私のような者にとっては別に変わった生活とは思えませんでしたが源氏の感じ方が面白く思えました。夕顔と源氏との会話もとても生き生きとして面白く、初めて人間らしい源氏の恋心が文の中から心にしみて感じられました。(松本)
第15回平成20年3月15日 テーマ「はかなき一ふし」に感じる見知らぬ女との出会い」
男性を迎えて今回はいつもより女性が静かだったような気がします。
源氏物語は千年も前に書かれた作品ですが人間の心の動きは1000年前と同じだと思いました。雅の世界に浸ることができてあっという間の楽しい二時間半でした。人の心をいろいろと忖度する有り様は今のコミュニケーションの薄い時代には大切なものだとまた思い知らされました。(亀井)
今日より夕顔の巻。夕日が差し込む部屋で手紙を買いている美しい女性。夕顔の花が咲く古びた垣根。舞台はそろった。この女性の召し使いや源氏の隋身の文化度の高さにもなるほどと思う。次回が楽しみ。読売新聞のおかげで新
会員が増えてうれしい読書会でした。(井上)
まさに映像の世界であった。余韻?を感じさせる「一ふし」夕闇の中の真っ白な夕顔の花。あじろ編みの垣根。黄なる生絹の袴。そして「それかとぞみる光」「寄りてこそそれかとぞ見め」今日もこの蔀の前渡りしたまふ…。その時の光源氏の顔の表情、目の行き場所。いくらでもイメージがわいてきます。(前川)
ほんの少しの時間に感じた小家に住む女の方の様子。まだ姿も見えて来てませんがこれからの展開に期待を持たせて今回は終了。次回がすごく楽しみです。(松本)
初めて参加したが源氏物語を原文で読み適切な解説を聞くと今までと違った源氏の世界を興味深く味わうことができた。(男性)
早速寂聴さんの訳を読んで原文に忠実かと比較しながらその他も読んでみたいものです。(平井)
数時間があっという間に過ぎてしまいました。源氏の世界にひきこまれ美しい情景が目に浮かんで平安の昔を日本人としてうれしく思いました。世界に誇れる大切な物語だと思います。(前島)
きりかけだつ物に、ここちよげに白い花が咲いている。どんな女性が住んでいるか、源氏でなくとも心惹かれるすばらしい書き起こしだと思います。対照的に、洗練された住まいの六条渡りの女の所から出てくる源氏の姿が「朝明の姿はげに人のめできこえむもことわりなる…」とありましたが、距離を置いた源氏のほめ方に、この二人の心の隙間を感じます。源氏がどんどん夕顔の家の女性に傾いていくのが自然に読者に伝わってくるようです。(塚内)
第14回平成19年12月15日 テーマ「二人の女ー口説きの折に」
もしかして源氏の人生の中で最も強く愛した女性が空蝉でしょうか。そんな風に感じました。紫の上はすてきな女性なのは伝わるのですが、今ひとつ精神性を感じませんでした。とても面白かったです。(中川)
40年ぶりに晶子訳の帚木と空蝉を読んでみました。正直楽しいちうより気が重くなりました。平安時代の貴族の女性の生き方の大変さとでもいうのでしょうか。一夫多妻、心のつながりで夫婦が成り立ち、法の保護がない時代…。(匿名)
今回も反源氏派です。参加者の中には空蝉を誇り高い、気高い人と思うとありました。私は誇り高き自尊心ある行動力ある人と見るより自分を傷つけたくない、自分を守る故の行動とみる。「今の若者と似ているな」と。恋愛するのが怖い。失恋するのが怖いという心理と似ていると思った。(こんなことを書くと不評を買うかな)私は西の方の芳は好き。可愛い!あの生まれつきの鈍感さがうらやましい。憎めない。西の方に対する源氏は許せる。決して人を傷つけてはいけない。(前川)
この場の空蝉はいつもの通りの拒む女。いつもの行動をとったが残してしまた薄衣。義理のグラマラスな西の方も中の品のちょっと足りないこの娘も気の毒だけどちょっとおかしい。源氏と西の方が関わっている間滑り出た(逃げた)空蝉はどういう思いですごしたのか。この事はとても気がかり。いつものことながら源氏もどじ!紫式部のこういう人物を創り出す力に感動。(井上)
今日の「もぬけ」を読み聞いているうちに、もしも西の方と一緒にいなかったら空蝉の態度はどうだったのかしらとふっと思いました、でもそれでは、この話は全然つまらないものになってしまいますね。西の方への源氏の対応は男の気持ち、行動を理解していなければ書けない事と思いました。登場人物が又、新しく加わって何の知識も持っていない私にとっては、これからの話がどのようになっていくのか興味が次ぎに向かっていくのを感じて楽しみです。(松本)
初めて参加させていただきましてありがとうございました。昔々を思い出しながら講義をうかがいました。私の好きな空蝉を改めて読み直すことができました。行動力と自制心のある空蝉をさらに愛着を持って読めました。敬語、助詞を注意しながら読む大切さを思い出しました。(矢富)
面白かったのは「ものものしくおぼゆる」「いぎたなきさまぞ」と表現された西の方の眠り方のリアルさ。口をあけて寝ている様な…。対照的に、源氏の面影が離れずに昼は物思いにふけり夜も寝覚めがちという空蝉の苦しさがよく伝わってきます。今回は、闇の中で聞こえる衣擦れの音と「かうばしくにほふ」様から源氏と察して、生絹なる単を一つはおって「すべり出でにけり」という空蝉の行動がまるで映画でも見ているような印象深さで残りました。かなりドキドキする場面なのに下品にならないのは何故?ちょうど良い間合いで、作者が時々顔を出して「困ったものですね」と言ってくれるからでしょうか。(塚内)
第13回平成19年9月8日 テーマ「二人の女ーかたちくらべ」
ずいぶん久しぶりの参加でした。物語の進度はすすみ具合はわかりませんでしたので、ちょっとついて行くのに大変でした。
平安時代の言葉がどのくらい現代に通じているのか考えさせられます。日本の言葉なのですから、微妙なニュアンスが読み解くごとに、日本人の心を思い起こさせてくれます。特に明治~第二次大戦後と変わってきた現代の日本人を考えさせられます。 (土器屋美千代)
今回は屋敷の様子が良くわかった。渡殿・妻戸・格子・屏風・ひさしの間等々。
空蝉に対する源氏の思い切れない想いを今回学びましたが、一言、私は源氏に言いたい!それは恋心ではなく、”自尊心”が傷つけられたのであって恋ではない。あくまでも今まで味わった事がない思い。それは源氏の自分では気がついていない自尊心である。もう一つ、伊予の湯桁も「おやじギャグ」みたいでないほうが良い。また、ついぶつぶと肥えた人を源氏は「親の世になくは思ふらめ」とあるが17才の少年が、そんな事想像するだろうか!?(前川綾子)
二人の女のどっちが好き?奥床しく上品な空蝉と大柄で美人で開けっ広げな若い娘と。こんな立場に立ったら若い男だったらどう思うだろうか。源氏は前者に魅力を感じている。が、後者も棄てがたい。いつも思うが紫式部は優れているストーリーテラーだ。さあ、源氏はどうする。次回が楽しみ!(井上久代)
源氏の表面的な女性の美しさにだけ惹かれるのではなく、自分と同じ感覚を持っている女性により惹かれていく様子が感じられました。それと、今回は女性の普段の様子を目の前にして観察?したのはもしかすると初めての経験だったのではと思いました。まだまだ若い源氏なのに、考えの深さを思い知らされました。繊細で思慮深いところが素晴らしい。(松本佳子)
「女どちののどやかなる夕闇の道たどたどしげなるまぎれに、わが車にて率てたてまつる」とあるだけで、神経質な紀伊の守が留守で、ほっとしている家の空気が良く伝わってくる。また、小君の大胆な作戦、源氏に応えようと懸命に考えたんだろうなという事もわかる。これを現代語訳にすると本当につまらなくなる。今回は源氏が息をひそめて二人の女を見ているが、女達を照らす傍らの灯の明るさまでわかったような気がする。人物描写もさることながら、闇の深さも空気も描いているなんて、やっぱり作者の腕はすごい。(塚内千寿子)
第12回平成19年6月9日 テーマ「恋する源氏と拒絶する女」
恋する源氏と、魅せられながらも拒絶するしかない空蝉の心模様が面白かった。お互いにまっすぐに相手に想いを伝えられない苦しみが連綿とつづってあるような気がしたが、少しも重い気分にならないのはどうしてだろう。今回、逢瀬の直後の源氏が、南の高欄にもたれて物想いにふける姿の美しさに答えがあるようだ。「月は有明にて光をさまれるものから、かほけざやかに見えて…」心の有様によって普段見慣れているはずの空や月が変わって見えるという描写によって、どこかしら解き放たれる気分になる。夜明けの空気の中にいる源氏の美しい横顔を風景とともに味わっているうちに主人公達のせつなさよりも、冷たい空気によって清らかに洗われたような心持ちになる。「源氏物語」には主人公の生き方や筋をたどるだけでなく、まるで映画の一コマを見ているかのような楽しさがある。 塚内千寿子
突き進んでしまったら、自分が苦しむに決まっている様な状況に私だったら絶対に陥らないとおもうけど、こんな結婚の形態だったから仕方ないんでしょうか。考えてしまいました。 中川美枝子
箒木の巻の弟「小君」が可愛い。一途に源氏の役に立とう努力する様子や源氏から姉についてあれこれ聞かれても申し上げて良いことは答えあとは静かに口を閉ざしているところなどに育ちの良さ、素直さがかんじられる。下心のある源氏も「これ以上は踏み込めない」端正さがある。箒木は自分の立場(現実)を冷静に判断して源氏の情熱に負けない。恋の手引きをする弟を叱る場面など彼女の高い品性が感じられる。今回もまた源氏はある意味滑稽である。「彼は本当に恋しているのか?」世に並びなき自分ほどの男を拒む女にいたく自尊心を傷つけられ、幼い小君にやつあたりして困らせたりしている。紫式部は源氏や小君を自分の弟や息子の行動を見守るような気持ちで「まったく…」とか「おやおや」などと思いながらこの章を書いていったのだろう。箒木は自分に重ねて…。ことらは相当真剣に慎重に人物設定をした上で書いたのではないかな? 井上久代
面白かった!
源氏の一途な想い(年をとるとこうはいかない)
空蝉の頑なな決心(どこまでもちこたえられるか、ちょっとした ミステリー小説の味わい)
つきなしという宿世(現在、勝負で使う「今日はついてないな」はここからきたんだ?)
神のなした二人の運命!(やっぱりこれが現実なんだ)
いじらしいほど源氏を思う小君(育ちの良さとはこういうもの、女君が元は上の品であった証拠)
空蝉の「心のうちは いとかく品さだまりぬ身~をかしうもや あらまし」の一節では、可哀想で泣けてきますね
それにしても、帚木を引用した歌のやり取り。旨い!上手!素晴らしい想像力、最高の美意識、究極の恋愛、と私は思う(シンデレラでもわかるように身分の違いは女性の憧れの恋)
“帚木の正体みたり女君”今回は謎が解けてよかった
それにしても、こういう恋は聞くにはいいけど、自分が味わうのはイヤだな私だったら、身の破滅を招いても源氏との恋にはしるかも。若かったらね! 前川綾子
空蝉の自意識の強さを文中から感じられてビックリ。
もし自分がその立場にいる空蝉だったとしたら、どうしたかしらと思うとまだ気持ちの整理はついてません. それと弟の小君の源氏に対する思慕の情、心づかいなどが少しずつ表現されていてほほえましい。
松本佳子
第11回平成19年3月17日 テーマ「中の品の女空蝉の意識のありようを考える…源氏との出会いがもたらしたもの:揺れる心のままに向き合う源氏と空蝉像を通して
伊予の守の後妻となった元上の品の空蝉にとってこの出会いは幸せだったか
源氏ははじめこの女性を今までの方法で何とか出来ると思ったろう。しかしなかなか手強い。ついには本音で、しかも泣きながら訴えることによって、女の固い心がほどける。
一生一度の恋として「よし、今は見きとなかけそ」と女が覚悟するところが見事。生きている証しとなったであろう
(井上久代)
ちひさやかなる人と源氏との一夜の契り。短い時間での男と女の気持の葛藤がとても丁寧に描写されていて、読み解いていくにつれて心に伝わったのがとても興味深い今日の章でした
(松本佳子)
改めて今さらながら、光源氏という男性の、自分に対する自信のようなものを感じ、ソフトな立ち居振る舞いに嫉妬さえ感じます。
一夜の別れの切なさを実感しました。今であれば再会する機会を陰ながらにつくるでしょうね。女の歌に様々な思いを感じました。
(中尾和夫)
この場面はつい先日講師の本を読んだばかりで、昔玉上先生の本で読んだ時には、場面の途中で一夜の契りがあったと記憶していたので、へえ~とびっくりしてしまいました。でも講師の本の方がずっと深くて素晴らしいと思います。こういう解釈の違いってどこから生まれるのでしょう。絶対的なものってあるのですか
(中川美枝子)
本日は渡辺淳一も真っ青になる程の、恋愛場面!!ヒロインは好みも淳一好みで、きゃしゃで、小柄で、ちひさやかなる人!(ソフィアローレン系が好きな人にとっては魅力半減かな?)
相手がいくら源氏とはいえ、襲われそうになって私ならけっ飛ばすのにと、今日読むまでは思っていました。ところが、源氏物語の人気の秘密がわかりました!! 源氏の人間性、女性の身分、息詰まる会話、そして一夜の終わり。つづく……。
(前川綾子)
第10回平成18年12月23日 テーマ「中の品」と「上の品」と…空蝉と出会うまで
・伊予の守の女房達の噂話にドキッとする源氏のところがとてもおもしろい。芸能人
や皇室の話題が今も人を惹き付ける、昔も同じだ。藤壺のことが口の端にのぼったら
どうしようと動揺する源氏。これまでに何かあったのだと示唆してくれた田中先生に
感謝。自分のことがこんなに他の人に知られるというのは不愉快を越して恐怖だった
のだろう。 (井上久代)
・はじめて源氏物語に触れました。先生のわかりやすい解説で物語りの流れが理解で
きました。「中の品の家」の噂話は現代にもつながる心理が描かれ古典を身近に感じ
られました。「姉弟」のところでは後ろ立てを失った女性の定めを書き古代の社会構
造・女性の生き方・社会のあり方までとらえることに接し、とても感銘を受けまし
た。源氏物語を身近に感じられるご講義をいただき感謝申し上げます。
(篠原美保子)
・なぜ、「帚木の巻」でこれまで中の品・上の品の女の事が源氏をとりまく頭の中将
達の会話で縷々出てきたのかやっとわかりました。身分社会の中で「上の品」と「中
の品」では教養も人柄も感性も違うのですね。中の品の女達がわざとらしいふるまい
で源氏を意識し、噂話に興じている様子。「ことさらびたり」「すこしほほゆがめて
かたる」など古語ならではの的確な表現に驚かされます。なぜ空蝉が源氏の心を捕ら
えていくのか。没落していく理由、それでもあふれる気品。「思ひあがれるけしき」
という心に誇りを持った女性に源氏が惹かれていくのがよくわかります。
(塚内千寿子)
・言葉の美しさに驚かされます。現代の子供達、特に女の子達の言葉の汚なさにうも
れていると、こうした古語がなくなってしまっていることが残念です。学校で古文を
勉強した頃はそうは思いませんでした。
(中川美枝子)
・上の品と中の品・階級の違いと同じように生活している人々の姿が浮かび上がって
来ました。空蝉の今置かれている状態が少しずつ見えてきてこれから出てくる彼女の
こと、源氏との出会いがとても楽しみに思えてきます。
(松本佳子)
・女房達との会話とのやりとりのおもしろさ、源氏の表情のちょっと、ふざけたしぐ
さ等、まさしく、イメージの世界でした。「方違へ」は今でいう:風水:なんだと
思ったり、源氏の「中の品」への興味深々さが想像できたり今の時代も変わりないな
と思いました。「噂話」では自分はまさに中の品の人物だと確信したり「姉弟」の段
では身を落とさざるを得なかった「女」の運命を想像してこれからのストーリーを楽
しみ、先に一人で読んじゃおーかな…。
(前川綾子)
__________________
第9回平成18年9月23日 テーマ「木枯らしの女と蒜食いの女」
例会報告 前川綾子
今回はお彼岸のせいもあって、出席者は5名、しかし、キンモクセイの香り一杯、さわやかな空気のなか、雨夜の品定め、終盤に入りました。
このここちよい読書会を紫式部ならなんと表現するだろうかとつい考えてしまいます。
さて、「木枯の女」何故「木枯らしの女」かというと「神無月のころほい~」つまり、10月初冬、木枯らしの季節から来ている。(私的には、一見緑の葉に覆われて美しく魅力的だが、葉が落ちてしまうと、味気ない軽薄な女のことかなと思っていました。違っていました。これだけでも出席した甲斐があった)
前回、左馬頭の「指食いの女」(見目麗しくないが、気立ても良く生涯の妻にと考えていたが、並外れてやきもち焼きの為、勢いも手伝って別れることになった女)と同時進行していた女、つまり、浮気相手の女のお話です。
「見はべりしほど」の「ほど」に注目。「ほど」とは期間限定を表す。つまり、はなから浮気。
その浮気相手の女とは、才色兼備、華やかで、魅力的で、楽しむには新鮮で刺激的である。然し、生涯の妻にと考え始めると、今まで魅力であった所が厭になってくる(何時の世も同じかな)
しかも、どうも男がいるらしい。
ある日、勤め帰り上人と牛車を同乗する事になった。上人はどうやら女に逢いに行くらしい。しかもその方向が以前、自分が浮気していた女の方である。もしやと思い後をつけると案の定、見覚えのある崩れた塀、その隙間から月の影落とす池、まさしくあの女の家である。
そうと陰から様子を窺っていると、プレイボーイ名高い上人は、やおら懐から笛を取り出し奏で始める。当時、女を口説くには楽器がひけて和歌も達者な風流人でなければ資格が無いのである。一方、女は待っていたとばかりに、琴で応える。キザの一言といえる男の振る舞いにすっかり舞上がる女。一変に熱がさめてしまったと言うお話。
独白(コメデイになりそう、結婚してみたら、なあんだ、こんな男だったのかとよくある話 )
ここでのキーワードは「さし過ぐ」⇒度が過ぎる、派手である 「まばゆき」⇒眩しい、目映しい⇒目を伏せる⇒見てられない、恥ずかしい
次に、式部が話す「蒜食いの女」これがまた、面白い。
式部と言うのは今で言う、平社員である。周りは皆、源氏ら重役陣の中で1人、平社員が加わっていることになる。こういう人物を1人いれる事が源氏物語を更に面白くさせている隠れたエッセンスではないかと私は密かに思っている。式部のキャラクターが窺い知れる場面でもある。
面白い女の話を早く言えといわれて、式部は「蒜食いの女」つまりニンンクを食べた臭い女の話を始める。
式部が学生だった頃、(貧乏人が出世するには勉強して官僚になるしか道は無かった。今は勉強するにも裕福でなければ出来ないけど)師と仰いでいた人の娘に軽い気持ちで言い寄ったところ、師に見つかり早速、結婚しろという事になってしまった。何しろ、師には大勢娘がいたのである。
そこで、師は漢学の歌を挙げて説得する。「金持ちの娘は夫をバカにするが貧乏な娘は婿を大事にする」
その娘、さずがに師の娘だけあって、全ての面で博学である。何しろ、寝物語の時でさえ、漢文調である。(学のある人は女でも仮名でなく漢文を書いていた)
それでも、式部は女から学問が何時でも学べるだけでなく人生悩みに何でも答えてくれる師のような存在であったので、つい女の所に通っていた。(貧乏な男の人間性がよく出ていおもしろい)
ある日、女の所に行って見ると、物越しの対面に出くわす。風邪を治すために蒜を食したので臭いから臭いが消えたら逢いに来てくれと女が言う。
式部は「受けたまわりぬ」とそのまま帰ればよかったものを、「そんな事を言っていい男ができた口実ではないのか」といった歌を詠んでしまう。
即座に女は(ここがまた、面白い所)「逢ふことの夜をし隔てぬ仲ならばひる間(蒜と昼をかけて)もなにかまばゆからまし」と返す。
(ごもっとも)一本とられた女の話をするが(私にはここが落語のオチのようで一番面白かった)上流階級の貴族たちはそんな女がいるものかと誰一人信じない。
このへんも、階級の差がでていて興味深い。
式部は小さくなるわけでもなく、貴族達の間にはさまれても平然としている。今でも式部のような人物が一人は居そうではないか。
以上は前川綾子による解釈のまとめである。
あれ?と小首を傾げられる方もおられるであろう。
どうぞ、そういう方は、原文を更にお読みになって、私の間違った点、気づかなかった点を教えて頂ければ幸いに存じます。
例会感想
木枯の女も蒜喰いの女も初めて読ませていただきました。私の知らない源氏物語の中
にはこういう話もずいぶん色々あるのだろうと、ますます興味が湧いてきました。食
わず嫌いを直せそうでこれからが楽しみです。今日はありがとうございました。
(岩城)
面白かった!1000年の空白は全くないのが又すごい。今、読んでも何の違和感も
ない木枯の女と。蒜食いの女であった。木枯の女はニュースキャスターをイメージし
てドラマができるし、蒜食いの女はさし当たって弁護士かな。どの人も、木枯の女、
蒜食いの女の要素を持ってるので、きっと皆が親近感がもてて、面白い原因なのだろ
う。(前川)
こんな話があったのかなあと面白く聞かせていただきました。男の立場から「勝手な
ことを言ってるわ」と。友人で「源氏物語の楽器」を卒論のテーマにした人がいまし
たけれど、そんな重箱のスミをつついて…と思いましたが、そうではなかったようで
す。(中川)
安っぽいドラマは、恋の成就までのあれこれを描く。しかし「源氏物語」の作者は恋
が成った後の男女の心の微妙な変化をじっくり観察する。そこが実にリアルで面白
い。左馬の頭は、木枯の女の本質を見てしまって、指喰いの女の妻としての誠実さが
よくわかっただろう。(しかし、もう遅い。)「上人」の口説き文句の巧みさ。恋の
手練れとはこういうものかと、しばし感心する。でも本当に女性の心に届く誠実・真
剣な恋をするのはやはり源氏だけだと今回も、源氏と較べながら読んでしまった。
今回で「帚木の巻」は終了。いよいよ次回「空蝉の巻」で源氏が表舞台に登場する。
乞う・ご期待!(塚内)
第8回平成18年6月3日 テーマ「常夏の女の生き方」
例会報告 井上久代
梅雨空の下、時おり松波分室の和室には涼しい風が吹き込む。今回は常夏の女、会場の庭にはまだ撫子は咲いていなかったけれど、集まったのは人生をよく分かっている11人の女性。雨夜の品定めの後半部分、頭の中将が若い日に関わり、今でも未練をもって思いだす女の話である。
中将は「なにがしは、痴者の物語をせむ」と話しだす。<痴者(しれもの)>とは頭の中将が自嘲を込めて自分のことを言ったのではないことにまず驚かされた。(瀬戸内寂聴は「馬鹿な男の話をしましょう」と訳している)読み進めていくうちに講師の言う通り痴れ者はこの女のことなのだと合点がいく。後に夕顔の女として源氏と深い関わりを持つこの人・常夏の女は頭の中将の恋人となり、たまにしか通わなかった中将にもまめまめしく尽くす。幼い子ども(撫子)まで設けたのに、ある時中将の北の方からの脅迫を受け苦悩する。山がつである自分はどうなってもいいが撫子には情けをかけてほしいと歌を詠んで中将に助けを求めるが中将はそれに気づかず、撫子より常夏が一番と見当違いの返事を返す。女は絶望し、中将の前から姿を消す。逃亡はしかし生活手段を失うことでもあった。
<常夏の女は何故逃亡したのか?>について全員で話し合った。結論は[常夏の女は自分の誇りを守ったのだ」というところに落着いた。なかなかおもしろい問いであり答えであった。
今回も紫式部は女も男もしっかり描いていてすごい!今も昔も心はかわっていない。逃亡した女の気持もよくわかり、また男の現実認識の甘さはほんとうによくわかる。講師に導かれ原文の魅力を充分味わった読書会であった
例会感想
松波分室も初夏です。常夏は咲いていませんが楽しい会でした。中将が「痴者=女」
の話をしようと言った時私は自分のことを言うのかと思っていましたが、なぜこの女
を痴者と中将が言うのか今日よくわかりました。原文で読む大切さがよくわかりまし
た。(井上)
雨夜の品定めの女の話というとどうしても中将の目から見た、うんでもなければす
でもない女・常夏というイメージが強かったです。それが今回参加させていただいて
一語一語じっくり考えながら味わいながら読むとその奥に常夏の込められた思いが
数々あったということがわかりました。その後の源氏とのつきあいとの対比、語の多
重構造のお話もおもしろかったです。(岩城)
「常夏の女」は、高校の教科書によく載るあの「夕顔」という女性のことである。こ
の巻を丁寧に読むと、はかなげというより、人を傷つけてまで自分を全面にだすこと
をしない、優しげな繊細な女性であることがわかる。頭中将に和歌で必死に自分の窮
状を訴えても理解して貰えなかった無念はいかばかりであったろう。どんなに言葉に
命をふきこんでも、理解して貰えぬ淋しさに彼女は絶望したにちがいない。やはり頭
中将だからか。もし源氏なら?こうして次の巻、源氏の恋に期待が高まっていく。
(塚内)
「源氏物語」の中では、夕顔が最も好きな女性ですが、今一つ性格が読みきれない所
がありました。今回のお話でそれがすべてわかったような気分です。しかし、女が隠
れて住んだ平安の社会はどんな社会か、想像できません。(中川)
常夏の女・女性の心細いしっかりした賢い女性であり、中将より思いのこえた方で
あった為に後では、中将も心残りの女性でありました。(福田)
「謎の女」こそ「常夏の女」というのが今日の感想です。殆どの方の感想はこの女性
はとてもしんが強くてプライドも高く、知的で繊細で…というものでしたが、私は内
心、意識して自分をコントロールしてる女性ではなく本来そういったものを持った人
物「天性の魅力」を持った女性、魔性の女というイメージです。今の世でも自分がど
んなに努力してもなれない人物といった人がいるのを実感してます。本人も努力して
る様には見えないのに魅力的な人がいます。(前川)
身分制度の時代で和歌だけが対等に表現できる手段としてとても重要だった。女性の
側から男性に手紙を出すことはない時代に和歌に託して伝えたのに中将は理解してく
れなかった。結果として彼女は子供のことよりも自分自身のプライドを守って逃亡の
手段を取った。中将より器の大きな女性だったと思われる。(松本)
第7回平成18年2月4日 テーマ「指食いの女の生き方」
例会報告 井上久代
今回は左馬頭の<理想の妻>の話である。彼がまだ若かった時のこと、美人とは癒えないが、低い身分の
彼を立てて、気配りも気働きも優しさも持ちあわせている女がいた。しかし左馬頭は頼りになる恋人と思いながらも「とまり」=妻に定められない理由があった。それは人並み外れた<もの怨じ>(嫉妬心)を持つ女だったからである。左馬頭は一計を案じる。これだけ自分を思ってくれている女だから、ちょっと懲りさせようと「別れ話」をする。この時の女の出方は左馬頭の意表をつくものだった。彼としては「もう嫉妬しないから別れないで」と泣いてとりすがってくるとでも思ったのだろう。女は「すこしうつ笑ひ」「みだてなくものげなき」男でも出世を待つのは平気、辛いのは「あいな頼み」の浮気心であるといい、私も今が別れ時だと思うと言い放つ。男もかっとなって無分別に言い立て、喧嘩がエスカレートしていく。ついに気持を高ぶらせた女は男の指に食いついてしまうという結果にいたる。
男は女の嫉妬心にうんざりし、女は浮気な男が許せなかったのである。別れてしまった二人だが、霙降る夜に訪ねてみると女は不在だったが、夜着など暖めてあり、女のけなげさに反省もする。しかし左馬頭が態度を改めないうちに女は死んでしまった。男は源氏や他の貴公子に「ああいう女が妻にふさわしいかったのかもしれない」と語るのである。
例会感想
源氏の指喰いの女の男女の様子が細かくかかれています。生活の様子がうかがわれ
ています。又、細かな強い心づかいが男女にはあったと思います。
福田翠
「もの怨じ」の女が左馬の頭の計略にかからないところがなかなか痛快です。又、
いつまでも自分のことを思っているとタカをくくっている男を、そむきもせず…あし
らっている女は、自立していてすてきです。こんないい女が不幸になるなんて…相手
が悪かったわね。
井上久代
これだけ強い意志を持っている女の人が何故はかなく死ぬのか不思議です。(源氏
にはこういう死に方をする女の人が多いように思いますが)やはり女は弱い存在だっ
たのでしょうか。この時代こういう指をかんだりする程の激しさを勿、又、表現出来
る女の人がめづらしいことではなかったとしたら頼もしく嬉しい感じです。でも、ど
うしようもない、くいちがいの悲しさ、淋しさも思いますが…。
池坂明美
通い婚であっても、男性と女性の対等の立場が喧嘩のやりとりに表れているのが、
発見でした。今までは何となく只女の方が待つだけと思い込んでいました。
松本佳子
今回の「指喰いの女」面白かったです。先生の話し方が面白かったんでしょうけ
ど。今昔物語かなんかに似たような話があったかなあと思って聞いてました。どんな
に時代が変わっても男女の駆け引きは同じようなものですね。今朝の毎日新聞で、中
山千夏が男社会に嫌気がさしていた時に、古代社会の女が生き生きしていた事を学
び、自分を取り戻したと書いてましたっけ。
男女の気持ちの表し方の食い違いが悲劇を生んだ話であるが、激しい感情のぶつけ
合いの後に「手を折りてあひ見しことを…」など歌を交わし合うのがすばらしく、し
んみりさせられる。また、男が女の元に行こうかと心の変化をもたらす舞台立てが、
「調楽に夜更けていみじう霙降る夜」というのが心憎いではないか。「源氏物語」
は、もののあはれに満ちている。
男女の心の動きが割り切れず言葉には出せない深さを感じます。其の頃の日常生活
はどうなっているのか興味があります。
飯高定子
久々に楽しめた。いつもは作者の影がちらちらして物語りに没頭仕切れない場面も
あったが、今回は作中人物に同化できた。フジテレビの「電車男」の後に8回シリー
ズのドラマ仕立てにしてみたい。配役は誰にしようか。
前川綾子
第6回 平成17年11月19日 テーマ「妻選びの考え方と現実」
例会報告 前川綾子
今回はサプライズがありました。清水国朗を20歳若くして一見、アウトドア風の男性が参加して下さいました。男性からの生の声「男性なら、まず羨ましい結婚制度」との発言を聞きながら、これは女性否男性必読の「妻にしたら最悪の女達」(あしかるべき・最下級・複数形)について学びました。
前回に引き続き「雨夜の品定め」は恋の相手から結婚の相手の条件へと左馬の頭の弁舌なめらかに続きます。
一方、源氏は聞いているのかいないのかそんな様子です。
さて、左馬頭曰く妻とは「わがものとうち頼むべき」つまり、夫にとっては自分の人生を左右する全てのよりどころとなる存在である。政治の要人(vip)を選ぶのも難しいがこれは「上は下に助けられ、下は上になびきて、こと広きにゆづろふらむ」のように一人で行なうものではない。
ところが、妻はそうではない。このように、政治を引き合いに出して説得するところなど、世慣れた左馬頭の人物像を読者は感じ取る。
もちろん、妻たるもの全てにおいて、完璧にこした事はないがそのような女はいない。そこで少々大目にみてみるが、それさえもそういるものではない。そのことを7・5調でどんぴしゃに述べている。「なのめにさてもありぬべき人の少なきを」イメージの発揮のしどころ。
そこで、現実は、妥協して結婚する事になるが、これも何かの縁だと考える事のできる人は、はた目にもこころにくくうつるのである。
このように世間を見る事ができる左馬頭には敬服致しますね。(一読者として)
そして、いよいよ「困った妻達」の登場です。
その1、今で言う「ぶっりこ妻」(これには同感)どんなぶっりこ振りかはP、164~P、165を)そういう女を妻にした挙句の果ては「あまり情けにひきこめられて、とりなせばあだめく」底無し沼にはまったようなもの、どこまでも、あだめく。
その2、家事一辺倒で味気ない妻(独白:身につまされる)
今で言えば、色気も髪型も関係無くひっつめ髪にして、なりふりかまわず、家事にのみ専念する妻。それを一言で「耳はさみ」と表現。(おもしろい!)当然、夫は妻に嫌気が差して孤独となり失望だけが残る。
その3、何事も自分で判断できないかわいい妻
出席した男性の声(個人的には好みでは無い)確かに、自分好みの女に仕立て上げる楽しみはあるが、何から何まで自分で処理出来ないとなると矢張り、結果は、いとくちをし。
その4、甘えた妻(おねだり妻の事ではりません)自分を悲劇の主人公にしたがる女。夫と真正面から向き合おうとせず、ある日、突然家出をする。
しかし、その目的は夫の愛を試そうというもの。ところが、世の中、そんなに甘くは無かった。夫は迎えに来ないどころか世間は深刻に受け止め、勢いも手伝って心ならずも尼になる羽目に。しかし、動機が動機故に涙に明け暮れる日々となり仏さえ、不純な気持ちを知っているので、救ってもくれない。まさに「なまうかび」イメージを楽しむところ。(笑えそう)
そして、最後に、左馬頭は落とし所として次の様に結論づけます。
生まれも容姿も、もうよい。性格がねぢけなく誠実に家事をこなし安心できる性格であれば表面的な女らしさは自然と後から供わってくる。
これを瀬戸内寂聴の口から聞くのなら「ああ、さすが」と頷きもしますが、源氏より7つばかり年上とはいえ、まだ青年である人の考える事かと意外な感じがしました。
最後に、何よりもこの会の魅力は「うち頼むべき」「なのめにさても」「なよびかに女し」「耳はさみ」等など「イメージで読む」そのままなのです。現代語訳は参加者各々でいいということです。(当然あるきまりの中での話ですが)次回も現代語訳は前川綾子で源氏物語を先生の手をお借りして楽しみたいと思っています。(まとめと感想)
今回の困った妻は現代にも通用する。どれも男から見たら困った妻だろう。”耳はさ
みがちにびそうなき”なりふり構わず不器量、その上夫の世話をまめまめしくしない
現代の」妻は左馬頭からどういう評価をされるのだろうか。自分勝手な要求をして結
果として「なまうかび」の人生にならぬよう、相手の気持ちを考えて行動できる妻に
だけはなろうと思う。
先回も意外におもいましたが、この時代の女性は人格が独立していたのだと驚きまし
た。江戸時代(のことも良くわかりませんが)よりも、結婚なども個人と個人の結び
つきという気がしますし、女性に対しても家柄、外見などだけでなく個人の素養が求
められていたのだと意外に想いました。ある意味自分が年を取って、人情のキビが少
しわかるようになったかたかもしれませんが)
現在にも通じるお話ですね。読み手の方のお声もやわらかく心良く耳に入って来ま
す。(女性)
平安時代の一夫多妻の結婚制度は、どう考えても男性本位と考えていたが、理想と現
実の間で悩む貴公子達の話を聞いていると、妻に求めるものの中に、深い精神性があ
り「わがものとうち頼むべき」と言う風に心の拠り所を求めていることがわかった。
それにしても作者の人間観察の深さには驚く。男が避けるべき困った妻の4タイプ。
現実にいそうである
難しい古文が読む方によってこんなに心地良く入って来ました。先生の解説もわかり
やすくて時々笑ってしまいます。大変良い時間でした。
左馬の頭の女性論は良く女性の心情が出ていて面白かったです。やはり女性である紫
式部の文章だと思いましたが改めて彼女の人を見る目に驚かされました。左馬の頭の
理想の女性は、やっぱり性格重視。今と共通する部分?じゃないでしょうか。「外見
的な美はいずれあきる」ものなんでしょうね。初参加でしたが来て良かったです。
前回に続いて、とても面白かったです。現代にも十分通用する内容でした。だんだん
読み進むにつれて、本文を読んだだけでは、全く分からない部分も増えてきて、先生
の説明についていけない所もありました。次回が楽しみですが、先の予定が全くわか
りません
第5回 平成17年9月3日 テーマ:いい女の条件とは?いい女は中の品にいる!
例会報告
17歳になった光源氏。世間の噂では『咎多かる』恋多き貴公子と見られている。しかし本人はその場限りの恋を重ねていくことなどは好まず生真面目なのである。結ばれることの難しい相手に心奪われ思い悩む青年は胸の奥に藤壷への思いをつのらせ『内裏にのみ』多く生活し北の方のいる左大臣邸へはたまにしか訪れない。『長雨晴れまなきころ』五月雨の降り続く夜、帝の物忌みに従って、源氏も内裏の宿直所に逗留している。そこに親友の頭の中将が訪れる。厨子のなかにしまってある源氏あての女の手紙を見たりしているうちに自然に理想の女は?という話になっていく。頭の中将は『すきがましきあだ人』上手に恋を重ねていく貴公子と称されているが、彼が口にしたのは意外にも女性への幻滅であった。『これはしも難つくまじくはかたくもあるかな』これはと思う女はなかなかいないことが最近わかったというのである。
それでは平安朝にあっていい女の条件とは何であろうか。ー紫式部の女性論が展開される。当時女を品定めするにはA手紙、B人の噂、C出身階層などによる。Aの手紙の場合紙質、文字、結んだ草花、などから教養、人柄を推察できる。が女性を取り巻く周囲の影響や違う自分を演じるために技巧をこらすことが可能であり本当の姿をつかむのはむずかしい。男性は女性の『かど』才能があることに多大の魅力を感じ、期待してつきあっているうち実像が現れがっかりしてしまう。噂を信じてはいけない訳である。出身階層の上の品の女性でも、案外拍子抜けするような物足りない人もいる。下の品の女性は論外である。『中の品になむ』中流の女性にこそ注目に値する人がいるのだと頭の中将は言う。
左馬頭と藤式部丞が加わる。左馬頭はいい女は中の品、『受領』の中にいるという。受領階層は家柄も『いやしからぬ』し、安定した気持を持って暮らしている。『家のうちに足らぬことなど』ない。充分な財力で教養を身につけさせ、いい女にしあげていくというのである。さらに左馬頭は葎の門の奥に暮らす『いといたく思ひ上がった女』の話をする。失意のうちに『ものむつかしげにふとりすぎた』父と『顔憎げ』の兄と手入れもままならぬ家にひっそりと住む、プライドの高い美しい人。若き源氏の興味を引く話ではある。
(感想)
<前川綾子>
お呼びでない雨夜の品定め
源氏物語といえば雨夜の品定め、雨夜の品定めといえば源氏物語。男が好む女とはどんな女か、マリリンモンローかはたまた、オードリーヘップバーンかと期待しました。ところが正解は「かど、才能」のある女性ということでした。これで私は、男にもてない女、お呼びでない女だということが分かりました。もう、面白くない。
そういうわけで、今回のお話は今までのうちで一番理解のできないことでした。まず、恋のシステムのイメージが膨らみません。すべては女房の手の内にある、腕のよい才覚のある女房に当たれば、良い男がゲットできる。本人の顔、形なんて無いも同然。何しろ薄暗い中での事んp様ですから。この点に関しては私には分があります。もう既に上の品になっている。この女房が発展して、今の見合いの仲人になったのでしょうか。ならば、歴史を感じるけど。
受領の段では、さすが式部。社会評論が冴えてます。人間の本質、社会を見る目、先を読む洞察力は松本清張なみだと。それほどに、分析力、知的な式部が男の理想の女性は才能、つまり、私式部なのよといわんばかりの解答。式部もただの人、式部の人間性を知らされたようで、がっかり半分、親近感半分。人間性と知性とは関係が無いということですが。
それにつけても、源氏の常に斜に構えたポーズはヴィジュアルですね。それに、頭中将とのやりとりでも「手紙はそちらにこそたくさん集まっているんだろう、ちょっと見せたまえ」なんて、誰もが映画監督の才能を刺激されてしまいます。ストーリーを追うだけの源氏も充分たのしいです
おちゃめで意外な源氏が登場する二つの場面。
1,頭の中将が女性を三つの品に分けた時『いづれを三つの品に置きてか分くべき。もとの品高くうまれながら、身は沈み、位みじかくて、人げなき、また直人の上達部などまでなりのぼり、我は顔にて家のうちを飾り、ひとに劣らじ、そのけじめをいかが分くべき』と迫って頭中将をぎゃふんといわせた
2、左馬の頭が中の品の受領層の女性について熱っぽく語ったとき『すべてにぎははしきことによるべきなり』それでは財力がすべてというわけかい?とからかった
ふたつとも光源氏は世の中を見ていて知っているんだなあということと、しっかりした価値観があるということが表現されていて興味深く読んだ
第4回 例会報告(平成17年5月21日)テーマ:光源氏の恋と結婚
いよいよ青年になった光源氏の登場です。父帝は、典侍の口利きで亡き桐壷更衣に生き写しの新しい妃「藤壷」を迎えます。母のことは「影だにおぼえたまはぬ」源氏ですが、典侍からとても母に似ていることを聞き、自然に御簾の中で芽生えた恋でした。この源氏の心情を「常にま参らまほしく、なづさひ見たてまつらばや」と本文では表現しています。一方藤壷は源氏を男と意識してその視線から「せちに(ひたすら)隠れ
たまへど」という様子。ところが父帝は我が子に新しい母を「な疎みたまひそ。…なめしと(無礼)おぼさでらうたくしたまへ」と紹介し、子供の恋心には一向に気づかない。とうとう少年源氏は「をさなごこちにも、はかなき花紅葉につけも心ざし(幼い恋心)を見えたてまつる」と藤壷に思いを告白するのでした。その源氏は12歳の成人の儀式と同時に左大臣の娘と政略結婚させられます。源氏の心を占めていたのは藤壷のみで、美しいとはおもうものの左大臣家の娘にはうちとけることができません。娘も源氏の若さに圧倒されて、年上の自分を恥ずかしいと思い込み「いと若うおはすれば、似げなくはずかしとおぼいたり」と心を閉ざしてしまいます。こうして心通わぬ不幸な結婚が始まります。改築させた里の邸、二条院にも左大臣の娘でなく「思ふやうならむ人(藤壷)をすゑて住まばや」と嘆かわしく思うのです。
ドラマチックに幕を開けた「桐壷の巻」はこうして「光る君」と愛でられ成長した源氏の結婚と恋の痛みに苦しむところで終わります。さて次回はいよいよ「箒木」の巻にはいります。青年達の恋愛談義から女性(人間}ヘ興味・世界を広げていく源氏の姿が新鮮です
<前川綾子>
「源氏の結婚」のここがすごい!
すごい!その1
まず思い浮かんだのがチャールズ皇太子とダイアナ妃との類似性。年齢、美貌の点ではかなり異なるが設定は同じ。つまりダイアナにとっては、父のように甘えられる包容力のある男性が良かったし、チャールズにしても母のような優しい女性が妃であればそれなりにうまくいっていたのではないか。そしてカミラの存在。世間ではよくある話だが、舞台が宮中であるという所がすごい。なにしろ一番のぞいてみたい世界であるから。紫式部は1000年後の、この結婚を知って、今ごろ何と思っているだろうか?益々自信を深めているかな?
すごいその2
式部がすごい!のは人を見る目だけでなく、それ以上にその手法にあることに気がついた。
例1 源氏が光るの君といわれるゆえん、藤壷の登場、一方、四の宮の立場、二人の結婚、不幸な予感
読者は完ぺきな女性の不幸は大好きである。これからのふたりの関係を知りたくなるのは当然。
例2 この手法の極め付けは書きだしの部分。これは田中先生が一番先に教えて下さった事だったのに私は今、気づいた。たいした身分でもない女性が宮中(ここが大事)で一体何があったんだろう?ここで本を閉じる読者はいない。もう、この段階で読者は式部の手に落ちた。
次回はどんなすごい!を発見できるだろうか。
<土器屋美千代>
源氏は父帝の若い后、藤壷への恋心を抱いたまま、12歳で元服した夜、左大臣家の娘と結婚します。この結婚は母方に後見人のない源氏に、有力な後見人をもたらし、左大臣にとっても大切にそだててきた娘の婿としてこれ以上はない望ましい結婚でした。しかし、源氏より4歳年上の女君は美しい源氏に気後れし劣等感で心を閉ざしてしまいます。この女君のこころは玉の輿ねらいの現代の女性より、私はずっと奥ゆかしく思われ共感できて、今後の女君の言動や生き方を理解する助けになるような気がします。
塚内さんが原文を読み田中先生がかいせつするのを聞きながら昔印刷技術がなくて、写本によってしか書物を読めなかった平安時代、もしかしたら貴族の家々や宮中のつぼねで、声がきれいで読むのが上手な女房のひとりが物語を読み女性達が取り囲んでみんな固唾をのんで読み手の一語一語に聞き入り物語のなりゆきに胸をときめかせていたのかもしれません。そんな風景を想像しました。
漢字とひらかなだけで語られる原文はもともと私達の祖先が使っていた言葉ですからだんだんに回を重ねて聞きなれてきたら、カタカナ英語とコンピューター言語ばかり並んで理解するのに苦労している現代文と同じくらいには理解できるようになるかもしれません。
それにしてもここ、千葉市の松波分室ほど源氏を読むのにふさわしい場所は他にないかもしれません。平安貴族の寝殿造りにはおよびませんが、もともと旧家の私邸で、本格的な茶室や池のある日本庭園は広くよく手入れされています。木造二階建のこじんまりとした外観の家は見事な日本建築で建てた大工さんや職人さんたちの腕と誇りが随所にみられます。昨今、新しい家はみんなビバリーヒルズ風の邸宅ばかりで、はずんだきもちにはなりますが、ここは昔の日本の懐かしい落ちついた雰囲気で充たされています。
さて最後、今回のテータイムは[黄身しぐれ」とおいしい「ささや」さんのおかしがたくさん、それに新茶、そしておしゃべり……何を隠そう、私はこの時間が一番すきなのです。田中先生あしからず。
気の毒な左大臣の娘と光の君
副臥の妻となった左大臣の娘は本当に気の毒である。彼女は源氏より4歳年上ということ意外(それでも花も恥じらう16歳)何も引け目を感じる必要はないのに!と27歳で結婚した身は思う。春宮の后に望まれたとあれば美しさも教養も申し分なかったろう。家柄、経済力そしてあんなに寛大で婿を大事にする父の子なのだから。
藤壷を恋する源氏も何とも痛ましい。男の子が母を慕うのは理解できる。まして幼いうちに母をなくしその人に似ていると典侍にいわれて恋心が一層つのるのも当然と思うが、藤壷以外にもっとふさわしい恋愛対象もいたのではないか(もちろん、でも他の人と比べられないほどなにもかもすてきだった)源氏が元服まで宮中で生活したということは優れた美意識、学識などを育てた。しかし6歳から12歳という多感な時代友と遊んだりけんかをしたりなか直りをしたりといった経験を通して学ぶ円満な人間関係、家族観には欠けるところがあったのではないか(源氏にも頭中将という親友がいた)
そこが昭和生まれの庶民と皇子との違いなのだろうか
元服まで内裏で育った源氏がどのような状況で亡き母そっくりと噂されていた藤壷に会ったのかが私の中の疑問でした。
帝の父親としての盲目的とも思える愛情の表れで源氏をいつも御簾の内に連れていったことは私にとって驚きでした。内裏で成長したということはこのことも含んでいたのですね。光源氏の人間形成が見えてきたような気がしました
第3回 例会報告(平成17年2月19日)テーマ:父帝の子育てについて
「狂言半ばではございますが、口上を以て申し上げます。」と、舞台上の演者が突然平伏して、芝居や舞踏が中断される。歌舞伎役者の初舞台の口上である。まだ口が十分に廻らない挨拶や、一生懸命な演技。まことにけなげで愛らしい。観客も大喜びで、次回も来て成長した姿を是非見たいと思う。
桐壷帝が手元に引き取った幼い源氏を宮中に連れていった姿と、初舞台の子役の姿が重なる。幼いものは動物でも可愛いものである。まして源氏の愛らしさは神々しいなでの美しさ賢さを伴ったものであったろう警戒心の強い弘徽殿女御さえ、ふっと柔らかい心で接することができたほどのものだった。幼い源氏は全ての人々を暖かく優しい気持ちにさせたのだろうと思う
今回のテーマは私に言わせれば「源氏は帝に如何に育てられたか」とすべきである。何故なら「こんなふうに育てられた源氏は、これから一体どんな人生を送るのだろう」と、読み手は興味津々にさせられてしまうからである。その事こそが面白い小説「源氏物語」のすごさなのではないだろうか。私個人としては父親としての桐壷帝に興味はない。
「源氏物語を読む会」に参加しませんかと誘われて最初はあまり気乗りしなかった。私自身仕事もあり、まだ学生の息子もいる、趣味に英語も習っていて、けっこう忙しい。それに高校時代古典はあまり好きでなかったし、卒業後現代語訳で読んで、ストーリーはあらかた知っていた。もう30年前のことだが。しかし松波源氏も3回を終えて、だんだん面白くなってきた。といってもわたしは作者の紫式部に関心が向く。今から千年も昔に中宮彰子の女房という本業のかたわらこれほどの長編小説を書き続けた女流作家のスゴサに感嘆する。登場する多様な人々の心を一人ひとりていねいに描いている式部は冷静な目と豊かな想像力、自由で柔軟な精神を持っていたのではないだろうか。田中先生の解説で原文一語一語の深さを味わう時、式部という稀代の女流作家に近づいてゆけるような気がする、それが楽しみだ。
12歳で源氏にはぺヨンジュンやイビョンホンのような男になって欲しいと、ひそかに期待しているが、国宝源氏物語絵巻のような顔で夢にでてきたらどうしよう?
楽しいです。田中先生の熱の入った「源氏物語」の講義はもちろんですが、休憩時間
のおいしいお茶とお菓子をいただきながらのおしゃべり(?)(今回は韓流につい
て)もとっても楽しく、2時間30分があっというまでした。
昔から源氏物語は好きで、現代文で読んだり漫画で読んだりしてましたが古文そのも
のに触れるのは高校の授業以来です。かなりわかっているつもりでしたが、今回、こ
の会に参加させていただいて、こんなにも源氏は深かったのかとびっくりしていま
す。世界に誇れる物語文学と言葉では理解していましたが、改めてその素晴らしさに
感動しています。
第2回 例会報告(平成16年11月13日)テーマ:母君の人間像について
前回は大変魅力的な桐壺
の更衣について学びました。ではそのような娘を育てた母君とはどんな女性だろう、
何を拠り所として、どのような生き方をしてきた人なのだろうかという事が今回の
テーマでした。
「いにしへの(由緒ある家柄)人のよしある(深い教養や奥ゆかしさ)にて」とい
う母君ですが、「かへすがへすいさめおかれはべりしかば、はかばかしう後見思ふ人
もなきまじらひは、なかなかなるべきことに思ひたまへながらただかの遺言違えじと
ばかりに、出だし立てはべりしを」からわかるとうり、ひたすら亡き夫の志をかなえ
させようと、強い意志と行動力で娘を入内させたのでした。華やかな妃の生活を陰で
支える気丈さは母としての深い愛情と誇りがなければなかなかできる事ではありませ
ん。母君は「妻として母としての役割を自覚しそれを全うすることに賭け凛とした姿
勢で生きてきた、だからこそ娘をもごとられたことに納得いかず<心の闇>を抱え
る。 :夫や子に寄り添って生きることで得られる充足感を大切にしていたのでは?
それがあるから他の価値観、出仕の栄達など見向きもしなかった。 家族へ注ぐ深い
愛情が生きる支えとなる。 分をわきまえているので権威に媚びたりしない」(レジ
メより)という人なのです。しかし、娘の入内は自ら選んだ事とはいってもその為に
「横様なるやうにて(非業の死)、ついにかくなりはべりぬれば、かへりてはつらく
なむ、かしこき御心ざしを思うたまへられはべる。(かえってつらい。深い帝の愛情
がこんな風になるとは…)これもわりなき(言葉でははかれない)心の闇になむ。」
では、誰が悪いのかと自分を凝視し苦しむ母君の苦悩。そして常に「とかくつくろひ
たてて、めやすきほどにて過ぐしたまひつる(家をきちんと感じ良い具合に気を配っ
ていた)」母君が、今は屋敷が荒れるにまかせて起き上がることもできない程落胆
し、娘の死を悲しみ取り乱す姿に同じ子を持つ母親として(会に参加した)一同、深
い悲しみを共有したのでした。
田中先生が用意してくださるレジメの各場面のキーポイントとなる言葉を中心に細
部にこだわって読み進めてきましたが、作者の周到に用意された表現の巧みさにたく
さんの発見と共感があった一日でした。
次回(2月19日)は「桐壺帝」を「父、帝の子育て」
というテーマで学習します。お楽しみに。
<参加者の感想>
*私の考える母君像、顔の輪郭は意思の強さを示すややえらの張ったおとがいの尖った五角形顔、目は頭脳の明晰さを表すぱっちりとした二重まぶた、鼻は人格を表すように鼻筋が通り(眉間の間が高いということ)もちろん鼻の下は下向き。決して高すぎずだんご鼻であってはならない。そう、若かりし頃の「岡田茉莉子」を私が監督だとしたらキャスチングしようと思う。(今の女優さんでそれ程のキャラクターと持った人を思い浮かべられない)となると娘の更衣には…目下思案中。こういう場合はいいキャスチングにならない。なによりひらめきが一番大事。(三谷幸喜もそういってた)当然、光源氏は優しさとまめさとその他の理由でやはりキムタクだろう(目元と口元がいまいちなのでドンピシャが思い浮かんだら替える)とくると
その親の帝は感情の気弱さと純粋さと高貴さと育ちのよさ、わがままさ(子供っぽさ)とを考えるなら田村亮といったところか。正和はハンサムだがちょっと子供っぽさが無い。ニヒル過ぎる。眠狂四郎の影響かな。眠狂四郎は市川雷三をおいてこれ に勝る者はいない。とこんな具合にまさに『イメージで読む源氏物語」をそのまま地でいってます。この役はこの人でしょうなんて気分はまさに監督!!そしてもう一つ重要なこと。 「夕月夜」から「虫の音」までは特にリアルに母君の邸の風景を映像として私の頭のなかに創ることが出来る。これはどうしても9月24日ころに読まなければならない。何故ならこの時期こそが虫の音が一際高く、空気は澄んで、台風一過で月の光が<さはらずさし入りたる>なのである。冬の寒さに震えるところで、夏のギラギラ太陽を実感することは出来ないのである。だから、この箇所は9月24日に読まなくてはならない。すべてをセッチングしてこそ『イメージで読む」の本の読む秘訣だと私は一人、確信しているのである。
第1回 例会報告(平成16年7月10日 参加者8名)
テーマ 「恋」とは何か
今、冬ソナ人気で純愛という言葉がはやりですが、実はこの物語は恋する帝の登場で 幕があきます。「いづれの御時にか女御更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやんごとなきはにはあらねど(それほど高貴な身分ではない) 時めき(外から見た状態で、もてはやされる・愛されるという意味)たまふありけり」という冒頭から、当時の帝は身分の高い女性から大切にしなくてはいけないという掟があるのにそれを破っている帝が登場し読者を驚かせるのです。
公人と言う立場を貫かねばならない帝なのに、人間として一人の女性に恋してしまいました。立場や理性、人の忠告、周りの批判が一切耳に入らずひたすらこの女性(桐壺の更衣)を愛しくてたまらなく思ってしまう心の不思議を作者は「いよいよあかずあはれなるものに思ほして 人のそしり(批判)をもえ憚らせたまはず(聞くことができない)」と表現しています。帝の恋の波紋は身分社会の中で人々の非難怨恨の対象となり二人は孤立していきます。
「あまたの御方々を過ぎさせたまひて、ひまなき御前わたりに、人(桐壺更衣以外の後宮の女性達)の御心をつくしたまふ(また、桐壺更衣が呼ばれていると、神経を集中させている様子)も、げにことわりと(語り手も当然と思っている)見えたり」「事にふれて、数知らず苦しきこと(汚物をつけられたり閉じこめられたり )のみまされば、(更衣が)いといたう思ひわびたる(万策つきて困る様)を(帝)はいとどあはれとご覧じて、後涼殿にもとよりさぶらひたまふ更衣の曹司を、ほかに移させたまひて、上局(控えの部屋)に賜はす。その恨みやらむかたなし(はらいのけようがなかった)」不憫に思った愛する桐壺更衣の為に、元からすんでいた妃の一人を追い出してその局に住まわせるという帝動。参加者の中からも、更衣のために良かれと思ってする帝のすべての行動が逆に更衣をつらい立場に追い込んでいるのではないか、という帝への非難の声があがりました。
帝も後で述懐しています。「世にいささかも、人の心をまげたることはあらじと思ふを、ただこの人のゆえにて、あまたさるまじき人の恨みを負ひし果て果ては 」少しも曲がったことはすまいと思ってきたのに桐壺更衣いとしさゆえに人々の恨みをかってしまった、と。そして身も心も病み疲れた桐壺更衣はついに臨終の時を迎えます。向き合う男女として作者は更衣と言う言葉ではなく「女」と言い、死の間際にも歌を詠んで帝の心にこたえようという人となりを作者は伝えています。
次回は同じ「桐壺の巻」を 母君の生き方 というテーマを切り口にして読んでいきます。 11月13日(土) にお会いしましょう。