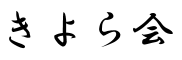
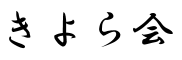

2008年にスタートした「源氏物語を原文で読む会」です。田中先生の指導の下、毎月第2木曜日、午後2時から2時間程度、文京区シビックホールで開催しています。
当初、文京区アカデミー市民講座の受講生を中心に「予習・復習・テストなし」をモットーにして始めました。メンバーは現在(2012年)10名、女性・男性ほぼ半々の構成です。
4年目を迎えても、まだ「夕顔」というスピードで、たっぷり時間をかけて「物語」を読んでま
す。読書会の2時間は、先生を中心にメンバーが自由に語り合い、「源氏」の世界に浸り
きる「至福の時」と言えます講義終了後、メンバーから寄せられた感想は「物語」
むことが、いかに深い感動を惹き起こすか、この短い文章の中からも窺うことができます
2022年12月8日「須磨」19
「三位中将来訪」「天変地異」を了えました。次回から「明石」に入ります。
〇禁を破り罪人になる事も覚悟で須磨に来た中将の想い。源氏の魅力の大きさが知れる。
まどろむ事もなく、都の諸々の話をし、歌を詠み交し、漢詩を作り合う。二人の友情の深さ、再会の歓び、切なさがひしひしと感じられる。
長い時は許されず、夜が明け無情な別れの時が来る。京へ帰る中将、帰京の約束のない源氏、複雑な立場で交わした別れの言葉は夫々の心に傷を残す。楽しい時であったが故に、悲しみや寂しさの大きい時を過ごす事になった源氏が切ない。
弥生朔日、海辺での御禊の行事は不幸を払うという。源氏の心の内の訴えに応えたのか、暴風雨、雷、高潮と天気が急変、荒れ出す。皆々急ぎ帰り着き不安の中で過ごす。
源氏は静かに経を読み続け、おさまった暁にまどろむ。そして夢の中で龍王に見入られ海に引き込まれるのではと気付き、この海辺の住居が気味悪くなる。
この天変地異による気持ちの動きが、次の明石へとうながすのであろう。楽しみである。
〇弘徽殿により源氏は孤立させられ、今は誰からも文は来なくなりました。文を運ぶ使者が罰を恐れていなくなったからです。そんな中、三位の中将だけが須磨の源氏に会いに行きました。
中将は源氏が都から離れてからの出来事など話します。源氏が知りたがっている左大臣家で養育されている子供のことなど、二人は夜を徹して話し合い、漢詩を作り合っているうちに夜明けを迎えます。
源氏に会いたいという想いを貫いた中将でしたが、罪人になることも厭わないと覚悟を決めたものの、かなり気にしているようです。出発すべき刻限となり、中将が源氏に「つぎ会えるのはいつになるのだろうか」と言ったことにより、源氏を苦しめます。後味の悪い別れとなってしまいました。
「須磨退去」から始まった、源氏にとって初めての孤立させられた現実を、受け止めきれないと思いますが、なんとか須磨十二帖は終わりました。
〇「源氏物語には、催馬楽がたびたび出てくる」と何かの本で読んだことがありましたが、今月の学習も「飛鳥井」という催馬楽から始まりました。もっと前の時代には馬子唄だったようですが、雅楽の楽器を取り入れて、身分の高い人も歌うおしゃれな歌になっていったようです。
源氏にとって、思いもかけない中将との邂逅でした。二人が別れてからの出来事は、お互いに語りつくせぬほど沢山あったに違いありません。
「泣きみ笑ひみ」という言葉が二人の様子をとてもよく語っていると思いました。
〇「生きる」を前提とした 源君と中将の 純粋で心暖かい「若さ」は 心地よいです。
馬も 情の深い動物なので 故郷を離れ 源君とお別れするのは 辛く寂しいでしょうが 新しい主人が中将なら すぐ懐つき仲良しになれることでしょう。
良く気がきく 源君のことだから 帰途につく皆に 須磨の幸を盛りこんだ おいしいお弁当を 用意したことでしょう。 勿論人参も沢山。
〇短い時間の中で深い友情を交わした二人。源氏は更に鬱鬱とした日を過ごすことになりました。
弥生朔日の御禊で、源氏が無実であることを訴えると「天変地異」が生じ、更に夢の中に「そのさまとも見えぬ人」まで現れ、「この住ひ堪えがたくおぼしなりぬ」となり、物語は「明石」へと移っていきます。
「須磨」では流謫の源氏とまわりの人物とのかかわりを、つぶさに知ることが出来ました。「明石」では物語はどう展開していくのでしょうか、楽しみが尽きません。
2022年11月10日「須磨」18
「明石入道一家」を了え「三位中将来訪」に進みました。
〇入道の源氏への思いは強く深いし、人間性を信じしっかりとらえている。
娘の幸せを思う母の心配は、源氏の心遣い、心くばりの諸々を知り、そしてその高貴で雅び、たとえようのない美しさに思いはきっと変わると思う。
地方で生きる事を選び、財を成し、それにより娘を高貴な女へと育てる入道。知的に、誇りを深く秘め、魅力的な女へと応えている娘も凄い。正に親子!!
住居の情景の詳細がわかる。全てを唐風に、そして質素に、粗末に、簡素にといったしつらえは、さすがに源氏も非難の目を気にしているのだと興味深い。
そうした地味ななかで、尚、美しさが引き立つ源氏が素晴らしい。
〇娘の相手に高い身分の男を望む明石入道と、流人とわかっている人に大事な娘を縁づかせる親がどこにいるのかと反論する母親に、入道は負けそうになり何やらぶつぶつつぶやくばかりでしたが、源氏の亡き母御息所は、おのが叔父、按察使の大納言の御娘で自分とは従妹の血縁関係があると、源氏の存在感を際立たせて再び自信を取り戻して持論を披露する。幼い頃から入道の教えをたたきこまれた娘は、入道に言われたとおりにしようと決心したようです。
源氏が須磨に来てから1年あまりたちました。都に生まれ育った源氏にとって住めば都にはならないようで、須磨の桜花はかえって都で行われて来た「花の宴」を思い起こして源氏の心はかき乱れます。
一方で、源氏の親友、元三位の中将は宰相に昇進しましたが、源氏のいない都の暮らしに張り合いがなくつまらないと、自分の身に何が起ころうと会いに行くと覚悟を決めて、須磨に向かい源氏と感動の再会をはたします。
〇1960年代ごろからでしょうか、「教育ママ」という言葉が盛んに使われるようになりました。東大→官僚コースを目指して、幼児のうちから塾に通わせ国語、英語、算数の基礎を教え、ピアノ、水泳等に通わせる家庭が増えてきました。
明石の入道は、その「教育パパ」版のハシリだと思います。都から師や女房たちを呼び寄せて一人娘を立派な令嬢に育て上げよう、もし願い通りになれないのなら、「尼にもなりなむ、海の底にも入りなむ。」とのすさまじい教育を一人娘に授けるのですから驚きです。
娘もその教えに素直に従い何の疑問も持たないのですから二重の驚きです。
〇調度品を 田舎作りにしたり、山がつめいた 狩衣を着たりしている源君は 何となく可愛いいです。
単に 須磨辺りでは その様な物しか 手に入らなかったからとも 思うのですが。
〇源氏の須磨退去は、明石の入道にとってまさに僥倖でした。彼の執念ともいうべき思い入れは、果たして成就するのでしょうか。そしてそれはどんな風にして。楽しみです。
2022年10月13日「須磨」17
「冬の須磨」を了え「明石入道一家」に進みました。
〇須磨冬の季節に。
月の光が部屋の隅々まで明るくするという侘び住居。狭いという事がよくわかる。それ故、供人逹は源氏の生活をすぐ側で目にし、聴き、美しさや新しい一面に触れる事になり、ますます魅了され献身的に仕える。その心遣いは源氏を慰さめている。
源氏が須磨にいる事を知った明石入道。名を捨て、実を取った野心家であり、娘に野望を託し育てている入道にとって、娘を源氏にという希望が大きくなる。諸々の噂に、幸せを思えない母は反対するが、源氏との出会いが楽しみなこれからである。
〇源氏にとってどんどん厳しい状況になってきました。春ではなく冬になりてと、尚更厳しさを強調します。
供人たちはいるのですが、孤独に耐えている源氏の寂しさは、「友千鳥諸声に鳴く暁はひとり寝覚の床もたのもし」、夜寝れない時の源氏の寂しさを表しています。なんとかこの寂しさを振り払うため、経を唱えたり、琴を奏でたりします。
月は部屋の隅々まで皓々と照らし出すとか、月は何の邪念もこだわりなく真っすぐに西へと動いて行くなどと、なぐさめるように月が強調されています。現在は先週10月8日が十三夜でしたが、忘れ去られた感じがしました。
「明石入道一家」に入りました。もう少しで源氏に春が来ると感じました。
〇日本列島全体から見れば、冬とは言え瀬戸内の気候は温暖な方でしょうが、流謫の地で迎える冬は、源氏にとって心底暗く、寒い冬だったと思います。
火桶(ひおけ)と言う火鉢のようなものが、枕草子に出てきましたが、その頃の暖房器具はそれくらいだったと聞きました。竪穴式住居の真ん中には囲炉裏があったようなので、それに比べると暖房面では劣る気がします。
その寒さの中で琴、横笛等でかろうじて遊べるのだから、やはり瀬戸内はやや暖かだったのかなあ、それともその頃の人は寒さに強かったのかなあ等と読みながら考えました。
〇明石の入道は 高貴な人への執着にも近い憧れが 強すぎる人のようです。
彼には 妻は中務宮の孫であるという 自負があるようです。だからこそ この思い込みが激しい入道と 冷静な北の方との 対等な会話が成りたつのでしょう。
〇明石入道の北の方が、「あなかたはや、京の人の語るを聞けば・・・・まさにかくあやしき山がつを、心とどめたまひてむや」と直言しています。良くも悪くも源氏の行いが広く知れ渡っていること、母親の娘の行く末に対する心遣いなど、今の世と寸分変わらないので大変面白く感じました
2022年9月8日「須磨」16
「弘徽殿の一言」を了え「冬の須磨」に進みました。
〇帝をはじめ、源氏とかかわりのあった人々の京での夫々の立場での深い思い、納得である。
紫の上は源氏の理想の女として素敵に成長している様子。哀しみの中でも細やかな心配りは仕える人々を魅了し、信頼を得ている。
そして、今も交流をする人々により、源氏の素晴らしさは世間の知るところであるが、弘徽殿はそれを許さない。女帝の面目躍如である。
源氏への便りはとだえ、孤立を深めていくばかりである。孤独、寂寥、冬の須磨での生活、源氏の君厳しい時をどう乗り越える?
・“この世のあぢはい”の含蓄ある言葉が楽しい。
・“立つ煙”に、塩焼く煙と柴を焚く煙があることを知り、新鮮さに歌を詠む26才の源氏。貴族の雅との格差を思う。
〇春宮が源氏のことを思い出しては、切なくて時に忍びて泣くとありますが、春宮にとって
源氏が特別な存在であり、父親と思って慕っていたように思います。乳母や命婦は春宮の泣
く姿にいたたまらない気持ちと、源氏の存在の大きさに戸惑ったと思います。
弘徽殿の一言は策略なのでしょうか? 怒りを抑え冷静な口調で言い放った口伝えの
生々しさのまま、人々の間に伝播されてゆきます。源氏と手紙や漢詩のやりとりを密かに楽
しんでいた者も身を引いたため、源氏は都人から切り離されて孤独を深めて行きます。
一方、二条院の姫君「紫の上」は気立ての良さ、人々への細やかな心遣いを知った女房た
ちから慕われて、誰一人離れて行くものはいませんでした。
源氏の住まいには、都から便りを運んで来る使者は途絶え、山人の焚く煙の訪問は時々受
けるが、本当に来て欲しい京の便りを運んでくれる里人はこない。孤独に耐える源氏でした。
〇弘徽殿にとっては“目の上のたん瘤”とも言える源氏が都落ちをして、すっきりしたは
ずだったのに、その源氏が都のだれそれと文を交わして楽しそうにしているというのを知
ると、全く許せない悔しい思いでいっぱいだったことでしょう。
「かの鹿を馬と言ひけむ人」は、中国で書かれた歴史書の一文で、それは、紫式部の時代よ
り千年も前のものです。その頃の知識人は中国という異国の史書にも親しんでいたのかと
思うと驚きます。しかも漢文で。
〇弘徽殿様は 源君の一行が ぼろの着物を着て 岩穴に住んで 里の畑や田んぼに出か
けて 野菜を盗むか 又は お百姓さんに頼みこんで しぶしぶ分けてもらうか、 秋に
は 落穂拾いに勤しむか、 海を目の前にして 魚を捕る術も知らず ぼうっとしている
様を 想いを描いていたいのでしょうが、 残念でした。 この方 つくづくストレスの
多い人ですね。
〇権力者の理不尽な横暴、それに忖度する卑屈な人達、ネライを付けた人物に注がれる監視
の目などなど、千年の昔も今の世も、何も変わりませんね。
2022年8月25日「須磨」15
「望郷の秋」「海路のあいさつ」を了えました。
〇ふと気がつけば今宵は十五夜であったとは、源氏の孤愁切々である。
その月明かりの中思うのは、都での折々の宴、朱雀帝との語らい、最愛の人藤壺との逢瀬、見果てぬ夢だ。
時の権力の目を憚り訪なう人もまれ、淋しさの中で思わず詠う声、琴の調べの中に、供人逹は源氏の思いを感じとり涙する。須磨での流謫の源氏の日々に、哀しさといとおしい思いを強くする。
源氏物語にふれて、月の美しさに気付いたこと、古語との出会いがとても嬉しい。
今回「娘がち(辞書によると娘勝ちと出る)」、何とも楽しい!!
〇毎年旧暦8月15日に催されていた月見の宴も忘れていた源氏でしたが、高く上がった月がまぶしいばかりに照らしている、まさに中秋の名月を見て思い出し、流謫の我が身を改めて思い知ります。それにしても、「白氏文集」の一句を朗詠する源氏にとって想定外だったと思います。
季節は春から秋の半年で、生活がすっかり変わってしまいました。太宰府での任期を終えた次官一行が船にて須磨のあたりまで来ますと、源氏がこの地にいるそうだと女たちの間でざわめきが走ります。
岸辺に船を着けると、源氏の奏でる琴の音が風に乗って聞こえて来ます。今の源氏に会いに行くことは次官も無理との判断でした。源氏も一行の素通りはしかたないと思ったことでしょう。
〇藤壺の暮らす尼寺にも、紫の上が守る源氏の邸にも、須磨のわび住まいにも十五夜の月は美しく輝いています。それぞれの気持ちが伝わってくるような「須磨」の場面です。
月をテーマにした曲はベートーベン、ドビュッシー、フオーレなどから現代の作曲家のものまで沢山あると思いますが、ドビュッシーの「月の光」がこの場面の登場人物たちの心の葛藤をとてもよく表しているように聞こえました。
〇「憂しとのみ ひとへにものは 思ほえで」
これこそ 「情けを尽くす」ということなのだと 思いました。
〇十五夜の月明かりのもとで「よよと泣かれたまふ」場面から一転、大弐、五節の君、筑前の守などとの交情、この対比を面白く感じました。
2022年7月14日「須磨」14
「望郷の秋」に進みました。
〇季節が移り、須磨に秋の気配。
供人逹の悲しさ寂しさを思いやり、昼は明るく振る舞う源氏。夜ともなれば、覚えのないままに涙に濡れているという。優しさ、苦悩、孤独の深さが知れる。
秋草の乱れ咲く夕暮れの中、趣き深い装束、涙をぬぐう黒い数珠の映える白い手の仕草は、京に残した人恋しの供人逹を、慰めるという。ぞくっとする艶やかしさだ。
久し振りに幽玄、優美、美しい源氏に出会えて嬉しい!!
〇源氏には住めば都は無理なようで、秋風がいっそう寂しさをさそい、須磨にとどまりこんな所で寝まなければならないこと自体が悲しく、泣いたつもりはないのに涙が溢れ出てしまいます。
源氏は寝られぬまま琴をかき鳴らして供人たちを起こしてしまいます。供人たちは源氏の様子を見て、皆、涙が出るのをこらえていたようです。
秋を彩る庭の花々が咲き乱れている廊に立つ源氏に、供人たちは気づきます。薄明りの中に浮かび上がる源氏のゆゆしうきよらかな姿に、「この世のものと見えたまはず」と、はっと心を打たれます。
それにしても、以前から天は源氏に二物を与えたと思っていましたが、絵の才能もあるなんて、ずるい。
〇侘び住まいの淋しさに涙する場面の学習。
私は、小学校3年生の時に、親元を離れて学校の先生の引率で“集団疎開”をしました。田舎の駅から3.5㎞も離れた田んぼと森に囲まれたお寺の本堂に布団を敷いて寝る生活が、戦争が終わるまで1年間ちょっと続きました。
初めは遠足気分でしたが、だんだん家が恋しくなりました。でも、当時はどんなにつらくても、淋しくても泣き声を立てることは許されなかったので、みんな布団をかぶって、歯を食いしばって泣いていました。鼻水をズルズルすする音が方々から聞こえていました。
源氏たちも淋しさを隠すことができなかったでしょうか。「昭和の少国民」よりマシかな?
〇屏風の表絵を 墨で立派に描ける源君なら 絵具さえあれば 作り絵を見事に仕上げられたことでしょう。 はるかに楽しいはずです。 しかし その肝心の絵具は 絵師の秘伝のもので 手に入らないものだったのかも 知れません。
〇しみじみとした流謫の生活、私自身の単身赴任期間のあれこれを思い出しつつ、味あわせていただきました。(見当違いも甚だしいですが)
2022年6月9日「須磨」13
「帝と尚侍の君の涙」を了えました。
〇許されて参内する事になった尚侍の君の心は源氏恋しさに満たされていて帝への愛はない。
帝は嫉妬もし、からんだりも有りながら全てを許容し、尚侍の君へのひたすらに恋い慕い愛する気持で一緒の時を過ごす。
権力者達の妨害により桐壺院の遺言も守れず、思うように政治が運べないという煩悶もかかえ、そうした自分の事もしっかりと理解している帝は、魅力的だし愛おしい。優しすぎるのかな?
尚侍の君、逢えない源氏より、すぐそばで一途に愛してやまない帝を見直しては?
〇源氏の運命を変え、娘尚侍の君を参内停止にしたのは、父親の右大臣が大后に話したことからでした。娘の処分撤回を求めて大后にも帝にもぬかりなく上申します。
女御や御息所と違って、単なる内侍司の長官という官職にすぎないという考え方を強く押し出して正当化したと言うことで、尚侍の君は許され監視が解かれ再び参内することになりました。でしたら相手の源氏も罪が軽くなると思うのですが、右大臣はそこまで考えていなかったようです。
帝は源氏を恨むどころか、院の強く望んでいた遺言を何一つ守ることが出来なかった良心の呵責に苦しみ涙を流します。この涙、尚侍の君の前だからなのかと思ってしまいます。本当は源氏に対して複雑な心境ではないかと思います。
〇今日の学習は、大スキャンダルにも拘らず、参内復帰が許された朧月夜と、それを優しく受け止めた帝との心理的葛藤の場面でした。
源氏は勿論ですが、兄に当たるこの帝も“いとなまめかしうきよらなれど”と、お姿も御容貌も大変な美男子のようです。気持ちも優しい方なので、故院の遺言が守れなかったことも気に病んでおられます。優柔不断なその性格が、弟源氏への嫉妬心、右大臣や弘徽殿からの重圧としてのしかかっているのでしょう。
〇「生ける世にとは、げに、よからぬ人の言い置きけむ」と 嘆息する朱雀帝を とても かわいそうに感じました。ここまで 恋の為にみっともなくなってしまう 男の純情は 私は嫌いではありません。
〇権力者に依ってどうにでもなる理非曲直。参内を許された朧月夜の心は源氏に焦がれたまま。「いみじかりし御思ひの名残」の帝は、にも拘わらず源氏の不在を嘆き、自身の不甲斐なさを責める。権力の頂点に立っても悩みは尽きぬものなのですね。
2022年4月14日「須磨」11
2022年5月12日「須磨」12
「伊勢よりの使者」を了えました。
〇御息所からの文の返りは、若き侍が直々に源氏の許へ。詫び住まい故に使者の座は源氏の側近く、その美しさに涙する。地味な装束は源氏の美しさをなお一層にした事だろう。久し振りに美しい源氏が想われて嬉しい。
花散里からの、悲しみと荒れていく住まいの様子の文への素早い指示と心遣いは、落ち込んでいても尚、優しさと力強さが感じられたのも嬉しい。
終わりも見えず、逢うこともかなわない中での文は、各々、夫々に癒しがあると思える。この項は手紙に一入の嬉しさを感じている。
〇須磨にて生活を始めた源氏でしたが、退居前に女君たちとは別に、伊勢の御息所にも使者を送って手紙を届けていたがと、言い訳のような入りでしたが、伊勢よりの使者が手紙を届けに来ました。御息所の手紙は素晴らしく、源氏を感動させます。
長い手紙のことば一つ一つに込められている御息所の思いは、源氏に直に伝わり、使者をそのまま帰す気にならず二、三日留め置きます。このようなことを語り手が忘れるはずはなく、むしろ強調されたように思います。
花散里からも、出した手紙の返信が姉の麗景殿女御の手紙と一緒に届いて、悲惨な情況に心を痛める源氏でしたが、麗景殿の邸の修理を荘園からの人々を招集して行うよう申しつけます。
「須磨退去」からの勉強会も一年を超えました。
〇都に残してきた女性たちに便りを届けるだけでなく、伊勢に住む六条の御息所にも手紙を書いたのは何故かと考えました。
御息所は、葵上の妊娠にも心を乱され生霊騒ぎをおこしたので、源氏の気持ちも御息所から少し離れていたように思います。その女性にまで、便りを届けたのは、ただ単に無聊を慰めるためだけではないような気がします。
今までに、源氏には数えきれないほどの女性がかかわってきましたが、知性、教養、美貌等、どこをとっても申し分のない女性といえば、六条の御息所ではないでしょうか。共に暮らす「妻」としては難しさはあるでしょうが、心の奥底で共鳴し合うものをお互いに持っている、そんなお相手なのではないかと思います。
伊勢という辺鄙な場所に身を置いて三年という御息所なら、須磨に住むことになった自分の苦しさ、侘しさが一番よく分かってもらえると思ったのではないでしょうか。それに対し、御息所も真摯に応えていると思いました。
昔はlove、今はrespect。
〇「かく世を離るべき身と、思ひたまへましかば、おなじくは慕ひきこえましものを」
ここに 源君の甘言にも似た 不誠実を感じてしまいました。
下手な歌を捻出する暇に 海辺に出て 忘れ貝(二枚貝の片方 又は一枚貝)の美しいのを 一生懸命捜しあてて 六条の御息所に贈ってあげた方が いいのではないかしらと 私は思いました。
〇かつてない逆境の中での「文」の交換。引き続き登場人物の源氏とのかかわりや、それぞれの心情が描かれている。この項では「六条の御息所」と「花散里」。
麗景殿や花散里の窮状に対して、源氏が京の家司に「各荘園から人々を招集して邸の修理に当たれ」と直ちに指示した点、源氏の「有能な実務家」としての面目躍如で興味深かった。
「それぞれの文」「都人の返りこと」を了えました。
〇京の夫々へ出した文の返りが源氏の許へ。
逢ふ事がかなわず涙のうちに過ごす日々と
離れてみての源氏の深い人間性にも思いはせる心の動きで
皆、尚一層恋い慕う気持ちあふれる文。
源氏もまた涙する。
みそひともじ(三十一文字)の短い中に深く大きな意をこめる短歌の優雅なやり取り、本当に素晴らしい。才能無しの自分としては大いに楽しみたい!!
〇源氏が都から姿を消したことで女君は精神的不安定になり、見かねた少納言は僧都に祈祷を依頼しますが、僧都の祈りが通じたのか女君は少し平静さを取り戻します。
思えば源氏が走っていた10歳の少女を北山で見て、藤壺に似ていると養育を熱望したのが始まりでした。18歳の女君が源氏と結ばれたのは、4年くらい前14の時でしょうか?
この4年間は女君にとって源氏との相当濃密な期間だったようです。
少し平静さを取り戻した女君は、無紋の夜具や夜着などを作り源氏に思いを馳せます。
もう一人の入道の宮は、春宮の後見をしてくれていた源氏が都からいなくなり、不安で胸が張り裂けそうになります。まだ8歳の春宮はこの状況がどこまで理解出来るのでしょうか?
左大臣家にいる若君は、左大臣や大宮、頭中将といった強力な後見人が付いていますので、なおさら春宮が哀れに思います。
〇今では「入道の宮」と呼ばれる藤壺は、本当に賢く、しっかりした人だと思います。源氏は今までにも、隙あらば何とかして藤壺ともう一度逢う機会を持ちたいと策を練ったりしていることもしばしばでした。
しかし、藤壺は、それにも応えることもなく、不安に慄きながらも人々に怪しまれるようなそぶりを全く見せずに過ごしてきたのですから、「あっぱれ!」としか言いようがありません。
しかし今、遠く離れた場所からの源氏の便りに、やっと周りの目を気にせずに自分の心の内を明かすことが出きたと思いました。
〇「かく憂き世に罪をだに失はむとおぼせば、やがて御精進にて、明け暮れ行ひておはす」
源君の心の成長、悲しくも褪せていく若さを感じさせる記述です。
〇「源氏とかかわりを持った多くの女性たちの長大な物語」を焦点の一つとして毎回の講義を楽しんでおります。彼たちはみな魅力あふれる女性であるだけでなく、それぞれの苦悩に満ちた人生を歩んでいる点でも共通しているのです。
今日の箇所でも「二条の院の君」「入道の宮」「尚侍の君」について深く味わうことができました。
2022年3月10日「須磨」10
「須磨の家居」を了え「それぞれの文」に進みました。
〇家司達の働きにより、思いのほか趣のある、風情のある住み処で須磨の生活が始まるが、語り合える友も、遊びを共にする者もいない孤独な日々は、京(みやこ)恋しが募るばかり。その心の内を京のゆかりの人々へ文にする。
別れの時は悲しみや辛さを隠す事もできた源氏だったが、今を、ゆく末を思う諸々の感情の深さ、痛みが解る。
源氏の真情の吐露に、文をもらった人々、夫々に切ない想いにくれる事になる。相変わらず罪な事であるが、大きな挫折と若さとに許す事にしよう!
光り輝く雅な世界から奈落の闇へ。どう乗り切るのか楽しみである。
〇源氏は須磨にも荘園を所有していたのですね!! まさか自分が住むことになるとは!!
源氏の嘆きが聞こえるようです。
住むには家の改築、修理が必要ですが、良清の献身的な働きによって家の改築も庭の造築も仕上がりました。須磨の新たな源氏邸が出来上がり人々の出入りで賑わい、源氏の不安もなくなり落ち着きを取り戻しました。
最初は都と同じ環境と思っていた源氏でしたが、源氏の性格として頭中将のような対等に話が出来る相手がいないことに寂しさがどんどん増して行きました。語りの出来る友達がいない源氏の孤独感、寂しさが良く分かります。
都が恋しくてならない源氏は手紙を何通か書きますが、会えないまま都を去って安否を気遣う女にも出しました。源氏の文は京のあちこちの邸で読まれ、手紙に目を通した多くの人が心をかき乱されたとあります。
紫の上は手紙を見て起き上がれなくなってしまいます。源氏はこの手紙が紫の上を嘆き悲しませることを予想したでしょうか?
〇リモートワークのこの頃では、田舎暮しをよしとする人が増えてきています。それぞれ家族がいればこその田舎暮らしですが、源氏の場合は価値観や趣味が同じような者は周りにはいないのですから、淋しくて、退屈な毎日だったことでしょう。
本文に「をかしうもありなまし」と言う言葉が出てきて、<なまし>はきっと~であったろうにの意とのことでしたが、私は歌舞伎の花魁が「くんなまし」などと言って話しているので、「なまし」は江戸言葉かと思っていました。
〇源君が 藤壺と朧月夜に贈った歌 何か野暮です。 これら二人が自らを 「松島のあま」 「塩焼くあま」と 言うのならまだしも 源君は 意地悪な私の目には 「しょってるね」と 思ってしまいます。
〇須磨での新しい生活が始まり、下司達の献身的働きで住居などの基盤は早々に整います。でも、都で係わりのあった人々への想いは断ち難いのは当然で、夫々に文を送ります。やはり源氏は「まめ」ですね。
2022年2月10日「須磨」9
「残されしゆかり草」を了え「須磨の家居」に進みました。
〇月明かりの中での旅立ちの日の別れの場が切なく素晴らしい。耐えきれず、みずからの手で御簾を上げ、紫の上の姿を追う源氏。悲しみに耐えている紫の上。美しい言葉のみ。
紫の上を思いやり、悲しみの大きさを隠す源氏。女としての思いのたけを詠む紫の上。男と女、難しい。
そして須磨へ。悲しみの旅は道中の風情にも心動くことはなく、辛い思いがつのるばかり。供人逹も見守るしかないか。今の京都、須磨間を思い少し理解が難しい。
住めば都になりますようにと祈ることに。
〇翌日、いよいよ出発当日を迎えるところから始まりました。
源氏も生きているうちに女君(紫の上)と別れることになるとは考えていなかったこともあり、この別れがどんなに辛いことか想像がつきます。その日一日女君の側を離れず、語り合って時を過ごしました。源氏と女君の別れがたい未練の気持ちなどを、詳しく解説していただきました。
そして源氏は心を鬼にして急遽出立します。山崎から船に乗り換え淀川を下って難波に至り、一泊して翌日船にて須磨に着いたようです。
勉強会当日雪が降ってきたこともあり、ここまでとなりました。この部分で多くの人が載せている解説文、あらすじが省略されて簡単に訳されているように思いましたが、源氏のイメージにも関係してくるのかな?と思いました。
〇ついに旅立ちの日を迎えました。希望に燃えての旅立ちとは違うので、源氏も後ろ髪引かれる思いでいっぱいだったことでしょう。
でも、広い屋敷に取り残される女君も、どんなに心細かったでしょうか。恐怖や不安で、気が休まることがなかったと思います。
ただ、どちらかと言えば、家に引籠っているより、旅に出たほうが気が紛れるのではないでしょうか。引籠っていては、唐の屈原に想いを馳せたり、歌を詠んだりする気分にはなれないと思います。
〇当時の時刻は 不定時報で 昼と夜の長さを それぞれ基準としたので 四季により 一刻の長さは 違っていたことが 今回初めて分かりました。
〇紫の上との別れを最後に、源氏は都を去り須磨へ向います。二条の院から山崎へ、そこから船で難波を経由、須磨に至ったとあります。この行程は我が人生の前半を過ごした周知の土地柄ですので、知悉している今の姿をなぞりながら読みました。
さて物語は須磨でどう展開していくのでしょうか。楽しみが尽きません。
「須磨の家居」を了え「それぞれの文」に進みました。
〇家司達の働きにより、思いのほか趣のある、風情のある住み処で須磨の生活が始まるが、語り合える友も、遊びを共にする者もいない孤独な日々は、京(みやこ)恋しが募るばかり。その心の内を京のゆかりの人々へ文にする。
別れの時は悲しみや辛さを隠す事もできた源氏だったが、今を、ゆく末を思う諸々の感情の深さ、痛みが解る。
源氏の真情の吐露に、文をもらった人々、夫々に切ない想いにくれる事になる。相変わらず罪な事であるが、大きな挫折と若さとに許す事にしよう!
光り輝く雅な世界から奈落の闇へ。どう乗り切るのか楽しみである。
〇源氏は須磨にも荘園を所有していたのですね!! まさか自分が住むことになるとは!!
源氏の嘆きが聞こえるようです。
住むには家の改築、修理が必要ですが、良清の献身的な働きによって家の改築も庭の造築も仕上がりました。須磨の新たな源氏邸が出来上がり人々の出入りで賑わい、源氏の不安もなくなり落ち着きを取り戻しました。
最初は都と同じ環境と思っていた源氏でしたが、源氏の性格として頭中将のような対等に話が出来る相手がいないことに寂しさがどんどん増して行きました。語りの出来る友達がいない源氏の孤独感、寂しさが良く分かります。
都が恋しくてならない源氏は手紙を何通か書きますが、会えないまま都を去って安否を気遣う女にも出しました。源氏の文は京のあちこちの邸で読まれ、手紙に目を通した多くの人が心をかき乱されたとあります。
紫の上は手紙を見て起き上がれなくなってしまいます。源氏はこの手紙が紫の上を嘆き悲しませることを予想したでしょうか?
〇リモートワークのこの頃では、田舎暮しをよしとする人が増えてきています。それぞれ家族がいればこその田舎暮らしですが、源氏の場合は価値観や趣味が同じような者は周りにはいないのですから、淋しくて、退屈な毎日だったことでしょう。
本文に「をかしうもありなまし」と言う言葉が出てきて、<なまし>はきっと~であったろうにの意とのことでしたが、私は歌舞伎の花魁が「くんなまし」などと言って話しているので、「なまし」は江戸言葉かと思っていました。
〇源君が 藤壺と朧月夜に贈った歌 何か野暮です。 これら二人が自らを 「松島のあま」 「塩焼くあま」と 言うのならまだしも 源君は 意地悪な私の目には 「しょってるね」と 思ってしまいます。
〇須磨での新しい生活が始まり、下司達の献身的働きで住居などの基盤は早々に整います。でも、都で係わりのあった人々への想いは断ち難いのは当然で、夫々に文を送ります。やはり源氏は「まめ」ですね。
2022年1月13日「須磨」8
「残されしゆかり草」に進みました。
〇いよいよ別れの挨拶の全てを終え出立の時を迎える。
文にて交された春宮との別れは、当然ながら臣下としてであり、秘して持つ子への情愛を思うと心が痛む。
これ迄の源氏の細やかな目配りのきいた心遣いに、御所中の上から下々の者達までが悲嘆の涙にくれる。源氏の人間性の素晴らしさだ。今でいう上司にしたい人ナンバーワンかと。
源氏から受けた恩を忘れる事はなくても、右大臣の権勢を恐れ、源氏から人々は離れてしまった。自己保身は千年の昔も現代でも同じ、人の心は変わらないとつくづく思う。
挫折の中で人の本性をみた源氏、大きな豊かな人間味を持つ事になったなあと・・・。
〇須磨退去を決断した源氏ですが、決断した時から何日で都を去ったのかと最初のページに戻りました。車で移動したのが左大臣家、花散る里の住む西面、北山にある父故院の墓前と入道の宮の御座所である三条の宮邸かと思います。関係のある女性には手紙を出しました。夕刻北山に行くなどかなりきつい日程から3日ぐらい前かなと思っています。
物語は3月20日過ぎの頃、人知れず都を去った源氏一行と、須磨退去の様子を伝えています。出発の2.3日前です。出発前の時間にさかのぼり、最初の網代車での訪問は我が子のいる左大臣家です。嘆き悲しむ女房たち、そんな時に源氏をめがけて走り寄る幼子がいたとあります。当然源氏に似ていると思いますが、春宮とは?と考えてしまいます。物語の最初の方に出して来たこの幼子が、いずれ表舞台に出てくる流れは「若紫」の「走り来たる女子」にもありましたが、推理小説家がよく使っていたなと改めて思いました。
〇母藤壺が仏門に入った後、春宮の身の回りのお世話は王命婦に引き継がれました。源氏、藤壺、春宮の全ての経緯を知っている王命婦に対して、源氏は春宮への想いを歌に託して預けました。
八才の春宮は、父親とは知らずとも、身近に見守ってくれていた源氏との別れが淋しくて、歌にはならないが、自分の気持ちを短い言葉にまとめて命婦に伝えます。春宮の散文のような言葉の中に、目に見えない血のつながりを感じます。
〇春宮は 母は生きていても 出家の身で会えない。父帝は既に崩御した。唯一の頼りの義兄の源君も 勅勘を蒙って遠国への下向。
数え年八歳の子供が 右大臣の勢力下の内裏で暮らす 寂しさ 心細さ 悲しみを 思い遣ると 可哀想でなりません。
〇「さしあたりて、いちはやき世を思ひ憚りて、参り寄るもなし」「身を捨ててとぶらひ参らむにも、何のかひかはと思ふにや」
今の世と何の変りもない当時の人々の心を、式部はみごとに描き出しています。しかし逆に、我が日本人の心は千年を経ても何変わることなく脈々と引き継いでいるということですか。
2011年12月9日「須磨」7
「御陵参拝」を了えました。
〇藤壺と桐壺院の御陵と別れが終わる。
藤壺は源氏への断ち切れない心の奥を歌で伝えていて切ない。生涯ただ一途に慕う源氏との出会いは女として幸せな事だと思う。大きな秘め事であっても二人の間には春宮という子供がいる。
源氏には初恋の人であり、妻も多くの恋人達誰も凌駕できない女(ひと)なのでもある。
この時代の御墓の在り方に驚く。何かにつけ加持祈祷をしていたにしては、草深く道もわからなくなる程手入れされていない。死者に対する祈りはどんな形だったのかと思う。
〇出立準備にだいぶ時間がかかりましたが、ようやく北山に向かって馬を進める源氏でした。供人も5,6名。下人だけの少ない供人の中にも官職を剥奪されしかたなく供人に加わった人もいて寂しい旅立ちになりました。
北山に着いた源氏は故院の墓に向かって参拝します。あれほどの位を極めた人でもこんな草茫々の深い山奥にと、源氏の寂しさが伝わって来ます。故院にこれから須磨に向かうと別れの挨拶をします。
供人全員の名前が知りたいです。惟光は?
〇三条の宮邸は、御簾越とは言え、源氏の御座所が宮のすぐ近くに設えてありました。これは今までになかったことです。理性的に振る舞ってきた宮も、これが最後と思うと本当の気持ちを吐露せずにはいられなかったからでしょう。
源氏への想い、二人の秘密、我が子の行く末等、誰にも知られないように、うわべだけは毅然とした態度で過ごして来た宮の気持ちが一気にくずれおれたのは、おそば近くでの対面によるものだと思います。
〇藤壺の「見しはなく」 源君の「別れしに悲しきことは尽きにしを」 これら二人の哀傷歌に あの世の桐壺帝は 決して犯すべきではなかった罪にもかかわらず 二人を愛しみ続けることでしょう。
帝は 既に仏様になられているのですから。
〇宮の「見しはなくあるは悲しき世の果てを そむきしかひもなくなくぞ経る」に、万感迫る思いがします。
2021年11月11日「須磨6」
「出立準備」を了え「御陵参拝」に入りました。
〇源氏、まだ残る気がかりは尚侍との別れ。厳しい看視が思われるが、文のやり取りを成就。人脈の深さが解る。
この旅立ちでの源氏は今迄にない政治的な、経営者的な面をみせてくれる。いつもながらの細やかな心配り、心遣い。そして夫々の女達へ残した源氏への忘れ得ぬ情と想いへのてだて、男も女も魅惑されるなと思った事である。
そして別れのクライマックスは、故院の御陵参拝と宮との別れ。御簾の前での別れの時は、姿も声も永く隔てられていた事でもあり、春宮の御世への祈りを込めた言葉を交わしていながらも、熱い想いを秘めているだろうと切ない。
〇須磨に出立する前、源氏は親しかった人、女性などに別れの挨拶に出かけますが、目立たないように人目を避けながら行動します。右大臣側の、源氏と親しい人への風当たりが強くなり、不利益にならないよう源氏も心配したのかと思います。
音信不通の状態だった朧月夜に手紙を出し届けますが、右大臣側のだれかに物を与えて届けさせたのかな?と推測してしまいます。受取った朧月夜も源氏の筆跡を見て涙を流します。
源氏にとって最も大切な人、故院のお墓詣と藤壺に逢います。御簾越に別れを告げます。後見を失った春宮がどんなに弱い立場に立たされるかと思うと不安でいてもたってもいられない状況であると心配しますが、気持は痛いほど良くわかります。
明日にでも出立するようです。
〇年立によると、二人の出会いは源氏二十歳の春。桐壺帝ご在位時代の桜花の宴のあと、ほろ酔いの源氏が憧れの藤壺を求めて殿舎の周りを彷徨い、それが果たせず、戸締りのゆるい弘徽殿の邸に入り込んだところからでした。暁の慌ただしさに女の名も分からず、ただ扇を交換して別れたのですが、お互いに気になる存在だったのでしょう。
朧月夜が宮中に仕えるようになってからも思いを交わし合う二人ですが、この二人以外にも忍び逢いが横行していたようなので、手紙を届けることはそれほど困難ではなかったように思います。
御陵への参拝が、有明の月を待って行われるというのが何とも不思議な気がします。貴族以外は太陽と共に生活しているのに、貴族は平民が寝静まった真夜中に人を訪れたりするのでは牛車や供人の声などで眠りを妨げられそうに思います。
2021年10月14日[須磨」
「月かげやどる花散る里」を了え出立準備」に入りました。
〇気がかりを残しては旅立てないとはいえ、残された時間のない中、花散里の許へも別れを。源氏は優しい!! 優しくなければ男でないと言った人がいるなあ。
流れる香りで源氏の訪れを知る。月の光の中、過ごす二人の時間。別れの時は「明けぐれ」。いつもながら情景の美しさ、言葉の美しさに魅せられる。
そして、いよいよ出立準備。組織を治める管理者としての新しい面を見せる源氏。適確な指示は、紫の上、家司、女房、信頼を得た人達の安心と希望になる。
いち早く須磨への退居を決めた事が理解できる。天は二物を与えずというが、源氏はいくつの才能を?
〇源氏の出立の日は迫って来ていますが、花散里を無視したまま都を離れるのは忍びない、何とか顔を出さなくてはと疲れた体を引きずるようにして牛車に乗り込み麗景殿邸を訪れます。夜もかなり更けてからのことでしたが、何とか花散里の願いをかなえることが出来ました。
別れをひどく悲しんでいる女に慰めの歌を詠み、細やかに思い遣ったことばをかけて別れます。多くの女性の中でも素直に自分を語れると言っていますので、ゆっくりしたいところですが、鶏が鳴くので急ぎ邸を出ます。
出立準備の所で初めて源氏の持っている財産が分かって来ました。沢山の財産を残して旅立つには、安心してまかせられる人が必要です。何から何まで紫の上に委託しました。源氏の所有する荘園や牧場、領地の所有権を証明する書類すべて。
それ以外、金銀絹綾などの財産を収納する財産を収納する建物の管理を少納言とし、若い紫の上の代理人に立てることにするなど、旅立ちはまだ!!
〇花散里の穏やかで、源氏より一歩下がった優しい性格が月の光と相俟って素晴らしいと思いました。源氏は、出立を前に気忙しく落ち着かない日々の中で、ほっとひと息つける時間をとれたのではないでしょうか。今では、どんな事でも気楽に話し合えるプラトニックな関係に違いないと思います。
二条の院の片付けは現代の断捨離を思い起こさせ慌ただしが伝わります。遊んでばかりいるのかと思ったら、財産の管理、使用人の処遇等こまごまと指図しているのを読み、一家の長としても素晴らしいのだと初めて知りました。
〇花散里は 我が袖に映る月影に 源君の美しい面影を焼き付けて 透明な悲しみの中で死んでもいい位の幸せに浸った と私は思っております。
一方 源君の頭の中は 当然色々忙しそうです。
〇源氏は不在の間、紫の上を頂点にした指揮命令系統を見事に整えます。家臣や女房達の人となりについても充分把握していたようです。
これらの手腕は、現代においても企業経営や組織運営上必須のもので感心しました。
2021年9月9日「須磨」4
「落魄二条の院」を了え「月かげやどる花散る里」に入りました。
〇旅立ちが迫り、時がない源氏。冷たい人と思われたくないと、そこかしこへの別れに疲労の極みにあるが、最後と思わせられるような逢瀬に、女達には哀しみ、熱い想い、生きるよすがを残したのではないかと思う。
深い哀しみと不安の中にいる紫の上と過ごす中で、一番大切な女との思いを強くする源氏。この思いを忘れないようにと思うのだが・・・?
夫婦の会話の中でも、想いを歌にしてやりとりをするとは、何と雅な時代と驚くばかりである。
〇須磨に源氏が退居することで、別れを悲しむ人、源氏によって生活を支えてもらっていた人、「好い気味だ」とばかり喜ぶ人など様々ですが、源氏の支援によって生活してきた人は相当不安になると思います。源氏のことですから、今後も支えていくと思います。
源氏の一番の気がかりは女君を残して旅立つことですが、女君の悲しみは尋常でなく、何とか耐えようとしている姿に、一番の大切な女だと痛感させられます。
出立準備までは、まだ数日かかりそうです。
〇今月の学習でも源氏のご出立は叶いませんでした。巻十二「須磨」は須磨の地から始まるのかと思っていたので、まだるい感じです。
挨拶回りに忙しい源氏の二条院へのご帰還もなく、紫の上もどれほど気をもんでいらしたことでしょう。
まだあどけなさの残る少女の頃、源氏のもとへ引き取られ、源氏の愛情だけを頼りに暮らす姫君にとって、源氏への悪い噂も耳に入るし、いつお戻りかもわからず、心配の毎日だったでしょう。
今のような通信手段のなかった時代の心配事は現在の比ではなかったと思います。
〇兵部卿と北の方は 似たもの夫婦。厭な人達です。
紫の上は ほんの子供の内に 源君に掠われて この様な人達の手から離れられたのは、 たとえ此の先 どのような悲しみ、寂しさが待っていようとも 彼女にとって 有難い宿世であったと 私は信じます。
〇失意の中で都を離れるにあたっても、源氏はきめ細やかに係わりのある人たちと心を通わせます。そして、その人たちのそれぞれの立ち位置や思いのありようを、私たちは知ることが出来ました。須磨での物語の展開が楽しみです。
2021年8月12日「須磨」3
「忍びて大殿へ」を了え「落魄二条の院」に入りました。
〇須磨への旅立ちの前、左大臣邸での別れの様子。
大臣、大宮、三位の中将、女房達。女房の中の一人秘めた恋人中納言の君、そして我が子。夫々辛い思いの言葉をかわし夜は更ける。
有明の月の美しい光、散り残る白き桜花、そしてかすかな霧、この儚い情景は源氏の今を写しだしているよう。
二条の院へ戻れば、もうそこは源氏が過去の人になった様相が在り在り、寒々しい。家臣達の保身は千年の昔も今も変わらない。
光の中を歩んできた源氏、“世は憂きものなりけり”と25才のこの時初めて気付かされたのは幸せだったのか? これからどんな闇が待っているのだろうか?
〇源氏は出発前に左大臣家に暇乞いに行き、左大臣と話していると三位の中将もやって来て、3人で別れの杯を交わしていると夜更けになってしまうとありますが、今まで左大臣家で3人での杯を交わすことなどあったのでしょうか?
左大臣辞任、源氏須磨に退去になりましたが、源氏と仲の良い三位の中将ですが、自分の立場を冷静に判断しているように思いました。
旅立ち前に、関係のあった中納言を召して永の別れを告げるなど、追い詰められても源氏らしさは失わないなと思いました。
物語は出発前の2,3日前にさかのぼっています。この2,3日で多くの人逹との別れ、特に女房たちとの別れは源氏としては断腸の思いだったと思います。今の二条の院は馬や車の影さえ見えず、源氏といえども冷静ではいられないはずです。
〇やっと旅立ちと思ったら、まだまだ女たちとの別れは続いていて、都への未練の深さが感じられます。
左大臣家にとっても、婿共々、凋落していく哀しさをひしひしと感じていると思います。
そして最後のお別れは二条の院。都を去るにあたり、どのように責任をとるのでしょうか。
〇源氏の「ものをおぼいたるさま、虎狼だに泣きぬべし」の一節 何だか 絵本を見ている感じがして ちょっと楽しかったです。
〇「明けぬれば、夜深う出でたまふに・・・・・秋の夜のあはれにおほくたちまされり」美しい情景描写だと思いました。それにしても、いつもながら人の心は今と一つも変わっていないなぁとしみじみ感じました。
2021年7月8日「須磨」2
「忍びて大殿へ」に入りました。
〇源氏は須磨への旅立ちを前に左大臣邸へ。
誰とわからぬ訪いの様子に左大臣家の人々の嘆きと悲しみは深い。左大臣の悲しみの深い思いを慰める源氏。
“前の世の報い”といい、右大臣のとどまる所の見えない理不尽な横暴に、自ら都を離れると語るが、将来への返り咲きを秘めたなかなか野心的な源氏の思いがうかがえるし、久し振り
の父の来訪に無邪気にはしゃぐ若君の愛しさに、涙をこらえる優しい源氏もいる。
戻る約束のない別れは哀しく切ない。
〇左大臣家には何としても暇乞いをしなくてはと、格式の低い「網代車」で簾まで垂らし、女が乗っていると見せかけて訪れます。左大臣家の人々は呆然としたまま源氏の異様な姿を見つめますが、源氏にしたら「してやったり」の心境だったように思います。
久しぶりに我が子に会いますが、源氏は若君がしばらくぶりの父を覚えていたことをほめ、膝の上に乗せ感激します。
源氏は左大臣に須磨退去を決意するに至ったわけを丁重に説明します。源氏は無実の罪を被る覚悟を決めますが、幼い我が子の記憶が薄らぎ遠のいていくのが悲しいと心から思っているようです。
〇前回の学習で、三月二十日過ぎに都を後にしたところまで読んだので、次回は旅の様子かと思っていたら、まだ都での別れの場面が続いていました。最後にお別れのご挨拶に出向いたのは、前の左大臣邸でした。こんなにあちこち挨拶したり手紙で知らせたりしていて、右大臣側に捕まらないのかと心配になりました。
右大臣側としては、朧月夜との不倫をいいチャンスと捉え、官位の剥奪、東宮の後見解任など自分たちに有利なように策を練っていると思われるのに、のんびりし過ぎです。現代なら、敵前逃亡しても逮捕状はどこまでも追って来るけれど、この時代には、自分から都落ちしてしまえばセーフという所が面白いです。
藤壺が自らの出家によって、東宮の出自に関する秘密を全く葬ってしまったように、先手を打てば何とかなる世の中だったようです。
〇致仕とはいえ 源君を愛しみ大切にしてくれる前左大臣が まだいてくれることは、 この上ない救いです。 この人は心がきれいで 立派で とにかくいい人です。
〇源氏は弘徽殿の執念に満ちた執拗な攻撃により窮地に立たされる。このまま「濁りなき心にまかせて」やり過ごしていると「いと憚り多く」、「これより大きなる恥じにのぞまぬさきに」都を離れることを決意したと致仕の大臣に伝える。
従前、順風満帆ともいえる道を歩んできた源氏がむかえる逆境。今後の展開を興味深く読み進んでいきたいと思います。
2021年5月13日「須磨」1
「須磨退去」を了えました。
〇右大臣側からの流罪という罪人扱いもみえてきた源氏は、須磨へと密かに旅立つ。千年の昔もパワハラ有りと人の心を思う事である。
ただ、今では考えられない時間と距離の大きな差異に驚くばかり。都とそれ程離れていなくても、荒涼の地であり、今生の別れの想いがあるのに驚く。
愛しい女達には思いを募らせるような文を届けている。罪にも思えるが、語り手は“真情溢れる素晴らしい手紙”という。残される、恋する女達には宝物かも知れない。
そして藤壺、出家してもなお熱い想いが消えていない事を文にしている。結ばれなくても、逢えなくても、源氏への心情は殺せない!!
〇源氏が思っていた以上に右大臣側の攻勢が強くなって追い詰められて行きます。多くの人達が権力者である右大臣に近づき、源氏に対して非難攻撃をすることによって、右大臣側の勢いがどんどん強くなって行ったように思います。
ほとんど味方のいなくなった源氏は、流罪の決定が下り罪人とされて都を追われる前に、自分から都を離れる決断をします。この決断には、源氏も自分の行動に対して自業自得とまでは考えていないでしょうが、心当たりもあったのだと思います。
3月20日過ぎの頃、源氏一行は七八人ばかりのお供にて旅立ちます。源氏のことですから、しかるべき女君たちの許には別れの手紙は届けていました。
最悪の場面は脱した源氏でしたが、この先、厳しい日々を覚悟していたと思います。
〇「身から出た錆」とは言え、誰にも相談せずに京の都を離れる決心をしたのですから、光の君にとって、これまでになかった大決心だと思います。俗にいう“夜逃げ”をするのですから、負け犬としての屈辱感にどれほど苦しんだことでしょう。
でも、現代の夜逃げと違ってゆとりがあります。自分の都落ちを、気が置けない人たちには、かなり広範囲にお知らせしているようです。
そして、行く場所も、辺鄙とはいえ、今の神戸市須磨区。何となく形式的な禊の儀式のようにも感じます。
〇源君が 須磨出立前に さるべき所々に出した手紙は あはれと忍ばるばかり尽くいたるもの と ありますので 読めるものなら 読みたかったなあと思っています。
〇「都人として最高級の教養と美意識を身に付けて育ち、申し分ない貴公子として自他共に認める源氏」が嘗てない「人生の大きな決断」を迫られました。
この短い項の中にも、紫の上、花散里、藤壺、しかるべき女君たちが描かれています。成程、なるほどと思った次第です。
2021年4月8日「花散里」2
「花散里」を了え次回から「明石」に入ります。
〇ほととぎすの鳴き声、橘の花の香り、二十日の月の光、何と美しい自然。その中で、ひっそりと生きる麗景殿と故院との佳き時代の思い出話。久し振りの逢瀬にも静かな喜びで迎える恋する花散里。穏やかな時が流れている。
麗景殿との昔語りで流した涙や、花散里との語らいに、源氏は心癒されたはず。
上の品の女達の奥床しさは素晴らしい。
〇三の君に会うために源氏は邸を出ます。中川のあたりを過ぎた時、ふと一回逢ったことがある女の家に気づき惟光を使いに出すが、惟光の気転により振られたと思ってしまい、あっさりと引き下がり麗景殿に向かいます。
麗景殿の邸に辿り着きますが、想像していた通り人影もなくひっそりとしています。麗景殿女御に会い故院の思い出を話すうちに、源氏は抑えていた感情が一気にほどけ、むせび泣いてしまいます。女御の前だと自分の弱さをさらけ出せるし、傷付いた心を癒される気がする源氏でした。
以前の源氏ですと、もう一押しして中川の女の所によってしまい、三の君に会うために邸を出た源氏でしたが、辿りつけなかった気がします。
〇「花散里」が終わりました。今まで吹き荒れていた風がやんで、波がおだやかになる“凪”を思わせるような短い巻でした。
「花散る」と言うと、現代では桜が真っ先に思い浮かびますが、ここで散るのは橘でした。王朝人は初夏には薫り高い橘の花と、ホトトギスの組み合わせがお好きだったようです。
麗景殿の女御のお年はわかりませんが、光の君のお母様も桐壺帝の御寵愛を受けていらしたのですから、同輩?かとも思いましたが、麗景殿の妹君が光の君のお相手と言う事なら、桐壺帝晩年の女御かなあと思います。
ほんのたまにしか顔を出さない自分を温かく受け止めてくれる三の君は、光にとってまさに“凪”のような女だったのでしょう。
〇ありつる垣根の 中川の女は、源君にとって 初めから憎げなくとはいえない お互いに情をかわしたとはいえない 人だったから、ありさま変わりたるというのは不適切な表現だと 思います。ただの あいなき仲らいというものです。
PS この巻名になった源君の歌「橘の香をなつかしみ郭公 花散里をたづねてぞとふ」は、何ともいえない優しい歌だと思いました。
〇この短い巻は、源氏が深く重い転機を迎える「賢木」と「須磨」をつなぐ間奏曲のようでした。
でも、「麗景殿女御」と「花散る里」の二人の女性が初出しています。これからの物語の展開に、このお二人はどのように影響してくるのか興味が尽きません。
また、久し振りに我が惟光の健闘ぶりも認められました。
2021年3月11日「花散里」1
〇桐壺院が亡くなり、後見のなくなった麗景殿と淡い交わりであるが、その妹三の君を人知れず気遣っている源氏。後見がなければ生活できないこの時代の貴族の女性にとって、この源氏の性格は何とも貴重である。財力の大きさは、いかほどのものかと思う。
少し心の折れている源氏、この二人に癒される事を祈るばかりである。
〇花散里に入りました。
さすがの源氏も厳しい状況に気弱となり、また出家願望が頭をもたげます。源氏のことですので、あれこれ心に掛かることを思い浮かべます。ふと浮かんで来た女が三の君でした。おちぶれた様でひっそりと住む女に無性に会いたくなり、天気も良かったため邸を出ます。
途中、たった一回逢ったことがある女の家でしたが、家の佇まいにどこか惹かれるものがあったので思い出します。惟光を使者に向かわせますが、女も今頃どういうつもりで来たのかと怨む気持ちを籠めたため、惟光もさっさと引き上げて源氏は振られることになりました。
花散里の花散るは、何となくこれからの源氏が置かれた立場に思えてしまいます。
「橘の香をなつかしみ郭公 花散里をたづねてぞとふ」
このほととぎすは托卵の鳥ですが、たまたま鳴いていたのでしょうか?
〇今月は「花散里」に入りました。
父桐壺帝の女御の妹さんともお付き合いがあったのかと思いましたが、その家を訪ねる手前に、もう一軒、昔関係した女の家があったことを思い出すと言うのですから驚きです。でも、その女に愛想尽かしをされると、筑紫の五節だったら、こんなつれないことはしないだろうとまた別人物を思い浮かべるのですから、「いい加減にせい。」と言ってやりたくなります。
作者の紫式部も、この短い十一帖の中に源氏の華やかな女性関係をよくも沢山詰め込んだと苦笑してしまいます。
〇どうでもいい昔の女に 声をかける気になり、どうでもいい 拒否の意を示された源君の 心の隙間風を感じました。
惟光の「よしよし植ゑし垣根も」という一種の捨てぜりふは 上出来です。
〇源氏は麗景殿と三の君を訪ねる道すがら、中川の女を思い出し惟光を使わす。会いたいと思った女にすげなく振られた源氏は、筑紫の五節のことなどおぼしつつ、かの本意の所に向かう。もし中川の女が源氏を受け入れていたら、この物語はどうなっていたのかなぁなどと思いました。
2021年2月22日「賢木」感想26
「右大臣と太后」を了えて「賢木」は終了しました。次回は「花散里」に入ります。
〇右大臣は目撃した事実を忖度も遠慮もなく全て太后に訴えるが、憎悪の深さ、強さに驚き“男の例とはいいながら・・・”などと源氏をかばったりする。何とも人の好い愛すべきところが笑える。
太后は源氏の行為は自分達への侮辱でもあり、春宮の世を願う意が有ると怒りが止まらない。復讐心は源氏を失脚させるよい機会とし、策略をめぐらし実行をうかがわせる。冷静で執念深く怖い。朧月夜に逢うチャンスと覚悟はあった源氏、大それた考えは持っていないだろうに。
大きな波乱を予感させて賢木が終わる。楽しみ益々である。
〇右大臣は源氏と娘(尚侍の君)との密会の証拠である畳紙を持って太后の元に行き、源氏のことを激しくなじる。なじっていた右大臣だが、いつのまにか源氏をかばう論調に傾いていく。
逆に、聞いていた太后の怒りは父右大臣の話など耳に入らなくなり、昔のことがまるで昨日あったことのようにまくしたてて、さすがに右大臣もしゃべったことを後悔する。源氏を失脚させるためのはかりごとを立てる。
平成30年(2018年)11月より賢木(決断)よりスタートしてから2年数カ月(右大臣と太后)、源氏にとって大きな出来ごとがありました。六条御息所の伊勢下向、桐壺院の死、藤壺の出家など。でもこれから先、もっと源氏にとって厳しいことになりそうです。
〇今日で「賢木」の学習が終わりました。六条御息所や藤壺とのような大人の恋ではなく、この巻は、ちょっとしたお遊び的な恋で幕を閉じました。
左大臣家と右大臣家という設定は、西洋で言えば、ロミオとジュリエットの家を思い出させる所があります。二大名家の積年の恨みが二人の恋を終焉へと向かわせます。西洋では悲劇でしたが、源氏はこのあと、また朧月夜と再会することがあるのでしょうか。
「空蝉」学習の時、「何という哀しい別れ」と思ったら、後でまた会う機会があり、「あれ!」と思ったので、この恋も後に続くのかなあと考えています。
〇「帝と聞こゆれど昔より皆人思ひおとしきこえて・・・」
お人好しの愚息のために ヒステリックに怒り 悔しがる弘徽殿に お母さんとは 時には こんな風になってしまうものかも知れないなと 親しみを感じました。
〇この物語は、しばしばオペラの舞台を想起させます。太后の敵意と怨念に満ちたアリアの絶唱で「賢木」の幕が閉じます。暗転した舞台でしばらく続くオーケストラの響きが、観客の魂を揺さぶり、限りない不安を呼び起こします。
2021年1月14日「賢木」感想25
「発覚」を了えました。
〇右大臣邸に退出していた尚侍の君の元に、毎夜通っていた源氏は激しい雷鳴の朝、寝所を出られず、右大臣により密会は発覚。
右大臣、我が子とはいえ若い娘の寝所に入るのはいかがなもの? そして怒り極みとはいえ、畳紙の証拠の品を太后の元へとは。感情のままの行動、品性がうかがわれるところである。
発覚すればどんな運命が待っているか覚悟の源氏、呆然自失の尚侍の君を思いやる、この優しさが好き!!
〇瘧病みにかかり宮中にて長い間加持祈祷を受けていた尚侍の君でしたが、一向に効き目がなく実家に戻ります。実家で修法を受けたところ、たちどころに快方に向かいますが、源氏に逢う機会が出来たことにより、何としても病を治さなければと強い気持が病気に勝ったのではないでしょうか?快復に向かいます。
完全に良くなれば宮中に戻されますので、夜な夜な逢瀬を重ねます。ある日の明け方、雷鳴とどろく激しいにわか雨に見舞われます。
娘尚侍の君の様子を見に来た右大臣が部屋に入って来て、密会していたことが露見してしまいました。尚侍の君は痛々しいほど思い乱れますが、源氏はいずれ露見するだろうと覚悟していたようです。自分の思いより女君を何とか慰めたらよいか?と心を砕きます。
これから先、右大臣方からどのような仕打ちを受けるか思いやられます。
〇恐れを知らぬ源氏と朧月夜が逢瀬を楽しむ雷雨の一夜が今日の学習でした。
「神鳴りやみ」という言い方に初めて出会って、私はとても素晴らしいと思いました。「鳴る神の」という言い方は万葉集で何度か目にしたことがありましたが、「神鳴りやみ」は初めてでした。光も音もすべてが神の意志と思われていたその頃の人々の畏怖の気持ちをとてもよく表していると思います。
源氏が忍び込んだのは皆が寝静まったころかと思いますが、そんな頃に御帳台の中で、畳紙で手習いなんてそんな筈はないのでは?
〇雨が激しく降り、 雷が鳴ったら、 まして 病後である朧月夜を 誰かが必ず見舞いに来るはずなのに、 二人は迂闊でした。 源君は もっと用意周到に 隠れるべきでした。
〇前項で「よろづのこと人にはすぐれたまへる」と称えられる源氏が、自らの愚かというか軽率な行いによって窮地に立たされることになる。何か感情移入の出来ない本項でした。
2020年12月10日「賢木」感想24
「憂さ晴らし」を了えました。
〇右大臣の権勢により職を追われた中将と源氏は、「韻塞ぎ」などで時を過ごす。賞品も用意され、わいわいがやがや高度な知識で遊ぶクイズを楽しんでいる様子が面白い。
ライバル意識を持ち、言いたい事をいい合いながらのじゃれ合っているような二人の仲の良さが伝わって楽しい。
源氏の博識は勿論だが、その夏姿は絽だろうか紗だろうか。雅な色の着物から透けてみえる肌の美しさに老博士達も涙するとは。
エロスを感じる一幅の絵のようであったろうか? 多くの女達が源氏を忘れがたくなる気持ちが良くわかる。
〇「夏の雨のどかに降りて」から始まりました。のどかと言うのですから、ゲリラ豪雨の筈はありません。陰暦の4,5,6月に降る五月雨のような感じでしょうか。
昔、(私より前の学年に)小学校の唱歌で“降るとも見えじ春の雨”というのがありました。そんな穏やかな感じを受けます。教養のある方たちにとっては、韻塞ぎのような室内遊びに興じる時期だったのでしょう。
中将の家の階のもとに薔薇が咲いていたと書かれていることに驚きました。バラはイギリス王室の象徴のように私は思っていたからです。バラと言われると、改良に改良を重ねたゴージャスな花を思い浮かべますが、千年以上昔から野いばらの類なら日本にもあったのでしょうか。
才気溢れる少年の美声に感動して褒美として自分の上着を脱いで与えた源氏といい、その光景を落涙して見つめる博士たちといい、感情表現の豊かな、右脳の発達した人々が沢山いたことがうかがえます。
〇年老いた博士達は 源君の才気と優美な姿態に すっかり惚れてしまったようです。
この段は 私の知識が及ばず 難しかったですが 暖かい雰囲気で 私も お仲間に入れてもらいたい気がしました。
〇身分を問わず通じ合う者たちを集め知的遊戯を楽しむ源氏。
老博士たちが落涙するほどの才気と美しさを兼ね備えた源氏。
一方、鬱屈した気分を持て余し少しく乱れる源氏。
果たして憂さは晴らされたのでしょうか。
2020年11月12日「賢木」感想23
「司召の仕打ち」を了えました。
〇右大臣一族が栄に栄えてきている。
左大臣一族には何の加階もない。
中宮は仏に祈る日々を。左大臣は身を引き自邸に引籠る日々を。宮仕えもせず源氏、三位の中将は、源氏の邸で若き日の二人を彷彿とさせるやんちゃな日々を。
「思ひ知れとにや」の左大臣の報復、憎しみの強さに驚き入る。上の品の雅びはいずこに。パワハラ、モラハラは歴史も古く根も深い? 怖い!
〇諒闇明けに、最初の除目で右大臣方が攻勢を強めて来ました。
中宮に仕えていた宮人逹、源氏、三位の中将などが標的となり、今国会で野党がさかんに追及している問題に少し似ている気がします。
左大臣も嫌気がさして辞任します。59才でした。
〇右大臣方の勢力に押されて、藤壺に仕えていた人々はベースアップ無しとのこと。ベアは誰が決めるのかは分かりませんが、こんなところに弘徽殿の仕打ちがあるのでしょうか。女は政治に口出しをしない世の中かと思っていました。
もしかして、春宮は不義の子という噂が囁かれていたのでしょうか。
〇帝が 父故院の遺言を 尊重する意志に比べ、中宮の年爵もさし止める右大臣は 敬意を知らない 品格の無い人です。
〇権力の異動がどういう風な結果をもたらすのか、多面的・論理的に描かれていて大変面白い項だと思いました。今の世と一つも変わりませんね。
それにしても卑しい人間が権力を握るとどうなるか。これも今の世と変わらないことに唖然とし、暗澹たる思いがします。
2020年10月8日「賢木」感想22
「青鈍の人」を了えました。
〇権力も右大臣へ移り出家もしたという事で、新年を迎えていても正月の行事もない三条の宮邸はひっそり。
挨拶に訪れた源氏は青鈍色に様変わりした部屋にことばもない。しかし、ここで仏につかえて勤行にいそしむ日々は藤壷に安らぎをもたらしている。
源氏は訪問を喜んでくれる宮の返歌に、藤壺の気持ちに変わりのないことを感じ“ 涙ほろほろとこぼれたまひぬ ”。
源氏の君、早く一人になって思いきり号泣を!!
〇早いもので、十帖の賢木の勉強に入り新型コロナで4・5月の2か月間は休みでしたが、2年経過しました。源氏は23才でしたが新年となり25才になりました。
故桐壺院の服喪も明けて正月の宮中は華やいだ雰囲気が戻って来ましたが、人々は三条の宮邸を素通りして右大臣邸に車を止めるのでした。
源氏だけは美々しい正装で三条の宮邸に入り、人々は安堵し女房達は感極まって涙顔になりました。
この先宮に係わっている人々の処遇が心配です。
〇桐壺院の喪が明けて内裏周りも再び華やかさが戻ってきました。俗世の縁を断ち切った中宮のお住まいだけが「明」の中に取り残された「暗」としてひっそりと静まっています。
優しかった夫、桐壺院のこと、激しく苦しかった源氏との恋、太后の恐ろしさ、もう今は何にも煩わされずに生きていけると思うと、この暮しは、「暗」より「静」と言った方がいいかもしれません。
一人残してきた春宮だけが気がかりだと思います。
〇出家した藤壺にとって 源君とのことは「むつかりしこと」として 終わったようです。
ひたすら哀切。
〇桐壺院の喪が明け、世の常として人々の動きは大きく変化していきます。一人源氏だけがひっそりとした宮邸を訪れ、心をこめた歌を宮とかわします。宮も源氏との事を色々と思い返すのでした。
舞台が激しく転換する直前の静謐さが、しみじみと描かれている項でした。
2020年9月10日「賢木」感想21
「御八講果ての日」を了えました。
〇中宮の出家により、さすがの源氏も思いを行動にも、口にする事も出来なくなる。
中宮のその姿を前にしながら、幼少の頃からの恋情、その思いの深さを伝える術は歌に託すしかない。
死による別れならば、時が忘れさせてくれる事もあるかも知れないが、切ない事である。
現代とは違い、出家するという事の重さを深く思った。
〇12月御八講の四日目に中宮は出家を表明しました。いつごろから出家を考えていたのでしょうか? 春宮も6歳になり、源氏にもっとしっかり後見人として臨んでほしいと思ったのでしょうか?
自分が出家することによって、支えていた女房逹の運命も変わってしまいます。
源氏も中宮の苦しい思いがわかったようで、居残るのが耐えがたく邸を退出してしまいました。その内、春宮が成長してくるともっと源氏に似てくると思いますし、どうなるでしょうか。
〇九月は、桐壺院の追善供養が済み、中宮が出家なさるところを学習しました。
月が煌々とあたりを照らしているとはいえ、昼間の明るさとは比べようもない影の世界。ため息、嗚咽、涙の中に薫物の香りだけが人々の気持ちを癒し和ませるように漂っています。
現代でも、暗い夜道を歩いている時、キンモクセイやクチナシの香がどこからともなく漂ってくると、「極楽思ひやらるる」とまではいかなくても、ほっとしていい気分になります。
香りの効用は古くから人々に知られ、現代のアロマテラピーまで、絶えることなく続いていることを想うと久々にお香を焚いてみたくなります。
〇源君の 「月のすむ雲居をかけてしたふとも この世の闇になほやまどはむ」は 源君の藤壷への想いと 春宮が我が子であることを 吐露してしまった かなり危険な歌のように感じました。
〇院の死去から1年、そして藤壺の出家により源氏との二人のかかわりは大きく変わりました。そしてこれからどのように展開していくのでしょうか。更に、春宮の行く末に暗雲が漂い始めました。大変気に掛かるところです。
2020年8月13日「賢木」感想20
「御八講果ての日」に進みました。
〇人の心は千年を経た今も変わらない事が多いといつも感ずる事だが、行事についてはなかなか難しい様である。
御八講のしつらえも極楽を思わせるとは。極楽をみてみたい! もっとも宮中の行事で庶民には無関係かな?
そして出家するという事が大へんな事だとも知った。
美しく地位も高い中宮が人々の前で出家を告げ髪をおろした事は、諸々を守る為には必然だったろうし、大きな衝撃や深い悲しみを隠し冷静にふるまう事は、源氏にとって人の目から自分を守る事であるが、なりふりかまわず号泣させてあげたい!!
〇中宮は桐壺院の一周忌法要にあわせて法華八講を執り行いました。
御八講は順調にことが進んで第四日目を迎えます。儀式の終わりがけに、御座所の中にいた中宮は出家の意志を表明します。兄の兵部卿は止めにはいり、源氏は動揺します。中宮の意志は堅く、反対されそうな兄や源氏には一切話していませんでした。
源氏はただ茫然とするばかりですが、横川の僧都により中宮の美しい髪は瞬時に失せました。源氏も冷静になれば、中宮の気持ちもわかって来ると思います。
〇中宮によって、御八講と呼ばれるはなやかな追善供養が行われました。「まことの極楽思ひやらる」と言うのですから、その絢爛さは貴人の供養の中でも群を抜いていたのでしょう。
四日間にわたる供養の最終日に中宮は、心に決めていた自らの今後の生き方を比叡山の座主の口を通して人々に告げたのです。
出家。源氏からも弘徽殿からも逃れるには、これ以外に方法は見つからなかったのです。
〇御八講を かくも尊く美しく主催できる藤壺は さすが帝の皇女です。
出家を決め 俗人としての最期の供養を 立派に行いました。
〇この物語の中でも「屈指の劇的場面」ではないでしょうか。
それにしても、現代の「出家」とは違った趣が感じられ不思議に思いました。当時のそれはまさに「世を捨てる」という悲壮感を伴ったものだったのでしょう。源氏の出家願望も同じ。
ときに「葬式仏教」「観光仏教」と揶揄される時代の「出家」との違いは、いつどのようにして生じたのでしょう。興味津々です。
2020年7月9日 「賢木」感想19
「隔つる霧」を了えました。
〇出家を決意した藤壺の春宮への親の深い思い。
久し振りに母親と共に過ごす子のよろこびの思い。
逢ふ事も難しく、手紙もまゝならない尚侍の君からの切々たる恋情の手紙。
滅入っていた気持を束の間忘れ、心のこもった返事をしたためる源氏の姿。
左大臣から右大臣へ権力が移り、様変わりした宮中と日々の生活の中、源氏も藤壺も亡き院を恋い偲び、悲しみにくれる痛切な想いが、雪の降りしきる墨絵のような情景の中に深く思われる。
千年の時を経た今も人の心は変わっていない。
〇源氏も尚侍の君が気に掛かっていましたが、大后の妹との付き合いにためらい、便りもしないまゝ長らく時が過ぎていました。初時雨もまぢかな時に、尚侍の君の方から手紙が届きます。心を深く動かされる手紙に源氏は大喜びで返事の手紙を書きますが、まず高級料紙を使い、筆の穂先を念入りに整え、得意の(?)情熱のこもった手紙を書き上げます。便りが出来なかった本当の理由は書けませんでしたが、嘘のない言い訳と、長雨の空でも憂いを忘れられようと慰めの言葉を添えました。
中宮に出した手紙の返事を受け取ることが出来た源氏の気持は落ちつきます。中宮の自然体に近い筆跡などで、源氏に対する気持を振り切りたいという思いが感じられます。
〇月の光が静寂さを醸し出し、故院を偲ぶ場面に素晴らしい効果を出しています。日本の古典を読みながら、ドビュッシーの「月の光」が中宮と源氏の歌のBGMとなって聞こえてきます。
明日はもっと暗くなる下弦の月の持つわびしさが、これからの源氏を暗示しているように思いました。
〇藤壺の心は帝と春宮への愛で占められており、そこに源君がしのびこむ隙が全くないようです。
源君の きらびやかな美しさは 少しずつ あせていくようです。
〇あれこれと憂きことが多いのに、尚侍の君からの便りに念を入れて料紙を選び、筆先も整えて返事を記す源氏の浮き立つ姿に、この人は本当にまめな人だなぁと思いました。
また、その「けしき艶なる」に「つきじろふ」女房達もほほ笑ましく感じました。
2020年6月11日「賢木」感想18
「異母兄弟」を了えました。
〇朱雀帝と源氏。異母兄弟であり、尚侍の君との三角関係にありながら、穏やかな語らいの場を持つ。帝も源氏も人柄の良さがうかがわれる事である。
今宵内裏を退出する中宮のもとへと急ぐ源氏は、失脚を窺う右大臣側の頭の弁に姿をみられ、権勢の衰えを感じさせながらも、さりげなさを装う。ここにも源氏の人の良さを思わせられる。
危機がじわじわと迫っているのでは?
〇雲林院より戻った源氏は帝に会いに行きます。久々に対面する帝と源氏は様々な世間話をしますが、早く中宮の元に行きたい源氏は故院の遺言を持ち出して退出しようとします。
帝も源氏を見ると尚侍の君(朧月夜)が頭に浮かびますが、秘めた思いを源氏に打ち明けたことで気持ちが浮き立ち源氏を放そうとしません。源氏にとっては兄である帝も頼りなく、故院の遺言である春宮を養子にするよう取り計らってほしいと言うのも難しいと色々弁解をする。
源氏も段々と攻めてくる敵の危機を感じているのでしょうか?
〇満月を過ぎてだんだんと欠けて行く月を気に留めて見ることは、今の生活ではほとんどないので、「二十日の月やうやうさし出でて」のフレーズに、明かりの乏しい時代を深く心に感じました。
それにしても、二十日の月と言えば月の出は10時頃でしょうか。そんなに遅くまで帝も中宮も内裏にいらっしゃるというのは驚きです。
〇異母兄弟である源君と帝が 本来なら決して打ちあけないだろう それぞれの恋心を 上品に語り合う姿 若々しくて いいですね。
それにひきかえ 頭の弁の朗詠は 何とおっちょこちょいのことでしょう。
〇この短い項の中に、物語の進行上深い意味を持つ内容が示されていると思いました。
権力を保持し行使する立場の者には不似合いな朱雀帝の人柄の良さと優柔不断さ、異母兄弟で尚侍との複雑な関係がありながらも心温まる朱雀帝と源氏との交情、一方弘徽殿たちの周到な策動とその深化などなど。
向後この二人に降りかかるであろう不穏な運命を暗示する伏線が張られたのでしょう。いつもながら、式部のみごとな筆の運びに感じ入った次第です。
2020年3月12日「賢木」感想17
「紅葉の山づと」を了えました。
〇紫の上は、源氏の鬱屈した様子に女の存在を思い、不安も嫉妬も感じながら表に出す事はなく、心に秘めている大人の女としての存在感が思われる。
藤壺は、雲林院土産の紅葉の枝に結ばれた文に、源氏の不用心さに冷めていく。
源氏は、藤壺のつれない態度に悔しく残念がる。
三人夫々の結ばれない心模様、人間模様が面白い。
〇二条の院で、帰宅した源氏を待っていた姫君は〈女君と呼ばれる〉ところから始まりました。葵の巻で源氏は姫君と結婚しましたが、姫君は源氏に対して頑なに背を向けたままで源氏も困り果て、どう機嫌をとったら良いか悩んでいました。
その後(雲林院)のところで、〈浅茅生の露のやどりに君をおきて四方の嵐ぞ静心なき〉数日会わないだけでもこのような歌を送る源氏の心は、姫君を思う気持ちで一杯でしたとあります。しきりに手紙を送っていたのが分かります。受け取った姫君も源氏の愛情を感じて涙をにじませます。女君も返歌を送りますが、不安の状況を訴える〈乱るる色かはる〉の入った返歌でした。
藤壺とは分からないようですが、源氏を夢中にさせている女の存在を感じて不安と不信感で一杯の女君でした。そんな最愛の妻の気持ちを知りながら、見事な雲林院の紅葉の枝に恋文らしきものを結び藤壺に送りますが、藤壺を怒らせてしまいます。喜んで貰えると思っていた源氏は、なぜなのか分かっていないようです。
〇小見出しは「紅葉の山づと」だったので、源氏の帰りを待つ二条の院へのお土産の話かと思ったら、藤壺への贈り物の話でした。
「げにいみじき枝どもなれば」という言葉から、数本の小枝などではなく、さぞ立派な“大枝”だったと思われます。今で言えば、デパートのいけばな展に出品されている流派の家元作品並みの大物だったのでしょう。しかもメッセージ付きで。
藤壺にしてみれば、誰にも覚られたくない秘密を抱えている身なのですから、知らんふりをしてほしいのに、目立つことばかり考えつく源氏に、ほとほとあきれ果て、腹立たしくなるのも無理はありません。
〇確かに 同じ赤でも ハッとするほど 美しく燃える赤の 紅葉があります。昔 どこかで 見た覚えがあります。
〇二条の院の女君は、「葵の巻」で源氏と結ばれた時とは見まがうばかりで、驚きました。
2020年2月13日「賢木」感想16
「雲林院」を了えました。
〇煩悩を断ち切りたいと雲林院での仏の道にふれている中にあっても、春宮の事、若紫の事、雲林院より近いという事で朝顔の君の事に迄思いを馳せ、文を使わす。なかなか心静かな日々は難しい源氏である。そして、どうしても藤壺への愛憎、思慕入り乱れた思いから離れる事はできない様である。
源氏の思いの深さも解り、藤壺の魅力の大きさ思う事しきりである。
〇源氏は雲林院にて六十巻に及ぶ天台教典を読み、不明な個所は僧たちに説明させたりして仏道修行に専念し、藤壺のことを忘れようとしましたが忘れられず、見切りをつけて帰路に着く決心をします。
一方、近くにいる齋院の朝顔に手紙を出しますが、まだイメージ的に子供と思っているように思いました。もっと成長し美しくなっている齋院と考えれば、「かけまくは かしこけれども そのかみの 秋おもほゆる 木綿襷かな」などの手紙は書かなかったと思います。
〇源氏は天台宗の教典六十巻を読み、法師たちに読経をさせ、法師たちも喜びにむせた。というのは、法師たちには身分の低いものも居て、このような機会にあうこともないのだ。
雲林院には感謝の気持ちを込めた布施を納めた。上下の僧だけではなく、里人や樵まで気を配った。そんな光源氏の功徳の限り、仏道に対する気持を表した。
〇朝顔の姫君の名前は今まで学習してきた中で、二回ほど出てきたと思います。一度目は「帚木」、二度目は「葵」..。「賢木」は私の記憶では三回目の登場です。
いとこ同士という長い付き合いはあっても、お互いに恋心とは無縁の関係に過ごしてきたようです。彼女は、六条の御息所がどれほど光との恋に苦しんだかも知っていて、自分は、ああはなりたくはないと冷静に考えられるような理性の持ち主のようです。そういう女性だから、光の方も安心して少し甘えられるのではないでしょうか。
今日の学習でびっくりしたのは、齋院にあてた源氏の歌の後書にあった「昔を今にと思ひたまふるもかひなく」と言う部分の注釈、*②でした。この歌が、伊勢物語出典の和歌だと書かれていたのです。私が子供の頃読んだ静御前の絵本の中で、頼朝と政子の前で、静御前が「しずやしず しずのおだまき繰り返し 昔を今に なすよしもがな。」と義経を想って歌いながら舞う場面がありました。その歌は静御前の即興の歌だとばかり思っていたのです。(80年近くも!)
でも、もっと古くからあった歌の本歌取りと知り、「そうだったのか。」と感激しました。やはり学問は面白い。
〇「かけまくは かしこけれども」と思うなら 朝顔の君を困らすお手紙は 止めましょう。
〇源氏の今置かれている状況を思うとき、ここしばらくの源氏のありように違和感がぬぐえません。一方、「源氏の行動の底辺に『女性崇拝』のテーマが満ち溢れている。フェミニストの象徴である」との見方(女性)も聞いています。
それやこれや気迷いつつ、この物語を読み進んでいきたいと思います。
2020年1月9日「賢木」感想15
「雲林院」に進みました。
〇源氏との断絶を貫く藤壺。なお振り向かせたいと駄々っ子の様にとじ籠り続けた源氏も、さすがに目が覚めたか、仏の力にすがる事でついに外出。
道すがらの秋の風情、色づきはじめた紅葉の様子を「・・・いとなまめきたる・・・」、何と素適な表現。京都の紅葉の素晴らしさを彷彿とさせる。
宿坊から紫の上に送った手紙は愛情あふれるものであるが、同時に、行き詰った気持を仏に頼ったと理由も打ち明けている。紫の上の側にあっても充たされないのはと、女にとっては残酷である。胸に小さな石が? さざ波が? たったのではないか?
〇春宮に会いたい源氏でしたが宮中に行く決心がつかず、二条院に籠って藤壺のことばかり考えていました。その中、だんだん腹立たしくなったようで、藤壺がひどい仕打ちをしたとか、外に出られないほど苦しんでいることを時には思い出してほしいなど、多少支離滅裂な考えになりつつも、心密かに藤壺からの反応を期待していました。
藤壺から何の反応もなく、今の状況にだんだん不安になって来たようで、仏の力を借りてどうにかしようと思いますが、かえって煩悩さえも断ち切れず自己嫌悪に陥り、僧侶の簡素な暮らしに憧れながらも出家は出来ないと、結論に至ります。
ここまでで、紫の上を忘れているのかと思っていましたが、源氏の心は姫君を思う気持ちで一杯でした。
〇「人わろくつれづれにおぼさるれば」という解説を聞いて、何をしていいか分からない意味があるという、空回りをしている自分に気がつかなければいけないという、奥があることを知ることができた。
特に、源氏の苦しい思いを断ち切るためには「観無量寿経」の文句を唱える必要があり、「仏教」が生活の中に浸透し、身近なものになっていたことがわかる。奈良期から平安期に時代区分が変わる時期として、現代人は理解しようとするのである。
〇今月の学習は、はらはら、どきどき、いらいらなどの場面がない、晩秋の静けさに包まれた雲林院詣でが舞台でした。
紅葉の名所と言えば、今日では、押すな押すなの大盛況ですが、本文から、紫式部の時代の静謐さが感じられ、落ち着いた気持ちで活字を追うことができました。
百八もある煩悩を数日の勤行で取り払える術などないことは源氏自身も気づいていたことでしょう。それでも仏の力を借りて、恋に狂った蟻地獄から這い出ようともがく源氏の理性の小さいかけらが感じられました。
〇紫上の返歌の上三句 「風吹けば まづぞ乱るる 色かはる」は、 何とも かっこう良い言い回しだと 感心しました。
〇常軌を逸した行為のあとも藤壺への煩悩を断ち切れず、雲林院に籠り出家願望と向き合う。しかし、姫君へは「御文ばかりぞ、しげう聞こえたまふめる」ようで、本当にまめな人だなぁとつくづく思いました。
2019年12月12日「賢木」感想14
「母と子」を了えました。
〇久し振りに訪れた宮中の雰囲気は、勢力の移行に伴い全くの様変わり。その中で源氏に生き写しの春宮のこれからを思う藤壺は、強く出家の気持ちを固める。我が身可愛に権力者に阿るのも、母が子を思うのも人間の性。
ひき籠っている場合でない源氏。藤壺との愛の形を昇華させ、魅力的人間模様に残して欲しいものだ。
〇藤壺の春宮に対する思いは切ないほど伝わって来ます。春宮の身の上に良くないことが起こるのではないか? 悲惨な目に遭うのではないかと気を揉む気持ちは良くわかります。
源氏は目を覚ませと誰もが思うところです。
だんだん源氏に似て来る恐怖も、さらに藤壺は不安になります。
〇「式部が・・・」(P.115後ろから2行目)ということばを考えてみると、特定の女房を指していると言う。式部は官名であるが、この表現は一般的に使われているのであろう。
親(母)と子の関係で離れて暮らしているのであるが、現在の親(母)と子の関係とは違うと思うが、自然体でいい関係(ほほえましい)だったのであろう。
〇今月は、春宮出生の秘密を抱えた母藤壺が、出家を決意して我が子に会いに行く場面を学習しました。
庶民と異なる宮中の生活の中で、親子の親愛の情は、庶民より浅いのか、より深いのか知る術はありませんが、子供心にも、漠然とした不安を抱く春宮の哀れさが胸に迫る場面でした。
やがて母が出家した理由や本当の父親について分かる時が来るのでしょうか。早く読み進めるために現代語訳を読みたくなりました。
〇源君は 親王ではないが 帝の皇子であり、 学識も有り、 能筆家であり、 読経も上手そうだし、 さっさと仏門に入って 劫を積めば 大僧正になれること 間違い無し。
〇権力の異動の様子が藤壺の目を通してリアルに描かれている。母親として子に対する情愛に揺れ動くが、春宮の身を守るためには源氏を覚醒させるしかなく、その為に出家の意思を固める。母はつよしである。
男というものは幼児性から中々抜け出せないものなのですね。いつの時代も。
2019年11月14日「賢木」感想13
「狂乱」「籠りゐ」を了えました。
〇受け入れてもらえない恋心に、常軌を逸し狂気の源氏の前に、藤壺は心を殺し応える事はできない。そして否応なしの、しらじら明けの時は別れをもたらす。
守らねばならない諸々をもつ二人、決して男と女には戻れず、心に大きな痛みと憂いを持つ事になる。
夫々の知性、高貴な美学は、どのようなかたちをとるのか楽しみである。
〇藤壺は春宮を守るため、せまって来る源氏から必死に逃れるが、藤壺を思う源氏は冷静な判断力を失って、命婦と弁の忠告も耳に入らない。藤壺はあえて源氏を軽い男と見立てて危機を逃れました。
しかし、御息所との別れで女君とも会う気にならず、何もする気にならないと引きこもったことに懲りずに、それ以上に引きこもってしまいますが、源氏のことですから、すぐに立ち直るでしょう。
もっと真剣に藤壺と春宮のことを考えてもらいたいです。
〇藤壺は、源氏との事が露見すれば、右大臣側が追い落としを伺っている以上、史記に描かれた残酷な報復の有様すら頭に浮かべる。
藤壺は、源氏の恋心をあきらめさせるため仏門に入り尼になろうと、最後の切り札を考える。そのことが、春宮の後見に専念してもらうことになると思うようになる。
藤壺は忍びやかに宮中に参内するが、源氏は気持ちが滅入って、大事な儀式でありながら
外に出る気にならないでふさぎこむ心の状態が伝えられる。
〇相手の事など考えず、《明け果つれば》と言う、あきれるほどの長い時間、男に粘られたら、女はうんざりするのは当たり前。
理性が全く効かなくなった男と冷静さを失わない女との対比が面白い。二人の間に生まれた子が、春宮そして帝へと登りつめて行くことを考えれば、女は、当然打算が働く。
〇源君の「逢ふことのかたきを・・・」の歌への藤壷の切り返しの歌は お見事です。気品があるだけに バッサリ 切ってくれました。
そこで 私も 田舎藤壺の気持ちになって 一首作ってみました。
「永き世を怨まば怨め 人のほだしは我ことにあらず」
〇「もの心細く、なぞや、世に経れば憂さこそまされとおぼし立つには、この女君のいとらうたげにて、あはれにうち頼みきこえたまへるを、振り捨てむこといとかたし」
この項で、やはり源氏だなあと思った次第です。
2019年10月10日「賢木」感想12
「接近」を了え「狂乱」に進みました。
〇果物や菓子の盛り方に“なつかしきさま”、藤壺の静かにそして凛として思い沈む姿に“のどかに”と使われている言葉、古語の何と趣き深く豊かなことか、原文で読む楽しさを味わう。
夢、現の中に理性も自制心も失くした源氏は、ついに御帳台のうちに入る。あふれる恋情、その想いを言葉につくすが藤壺からの答えはない。愛しく想う心が藤壷にあっても、何としても許されない禁断の恋なのである。
素晴らしい大人の女と青さの残る美しき男、どうなるのかなあ。
〇源氏は女房たちによって塗籠にへ押し込められ、香り強い上質な着物は二人の女房が預かっています。身軽になり、より敏捷な動きで藤壺のごく近くに身を潜ませて、屏風の隙間から藤壺の姿を目の当たりにします。源氏は感動のあまり涙を流します。
藤壺を間近で見て、姪である紫の上と瓜二つと対の姫君を思いますが、今は藤壷のことしか頭にありませんので、姫君と比べることなど出来ないと考えます。
本当に恋は盲目ですね。紫の上の方がかわいいと思いますが。
〇源氏は藤壷が年と共に美しくなっていくと見とれ、ため息が聞こえてくるようだと語り手はみている。その様は高貴さを表している「のどかに」にと表現するのも、伏線として読者を引きつける。
おかしてはいけないことをやろうとしている。気がつけば藤壺の髪の毛まで押えられ、どうにも出来ない自分がそこにいるのかと思うと、悲しく思うのである。
藤壺は感情むき出しの源氏の言葉をいやな冷めたい気持ちで聞き、そのような源氏を見るのはいやで返事をしない。
語り手は、存在すること自体が許されぬ恋であると、二人を包む「あはれ」の深さを世間の人が想像することができないと、文章は続き余韻を残している。
〇「ただかばかりにても、時々いみじき愁へをだにはるけはべりぬべくは、何のおほけなき心もはべらじ」とは 源君の ひたすらの おほけなき をこ ぶりです。
〇源氏を取り巻く環境は激変し、政治的にとても困難な局面に至っているのに、いったいこの人は何をしているのだと、あきれ果てる思いで読みました。
しかし、この物語の主人公は、源氏というある意味では架空の人物を中心に据えた、それを取り巻く女性たちなのだと考えれば、彼女たちの真摯に悩み苦しむ姿を引き続き見つめていけば良いのだと、新ためて強く思った次第です。
2019年9月12日「賢木」感想11
「接近」に進みました。
〇表舞台から遠くなった源氏。朧月夜と重ねている密会は藤少将にみられているし、藤壺への思慕の念で三条の宮へ忍び込むという暴挙で、破滅への道をひたすら進んでいる。
源氏の美しく愛しい姿、懐かしい声を目の前にした藤壺であるが、冷ややかである。憎しみで封印した恋心ではない、驚き、困惑の極みの中にこみ上げる歓びはあったはず。
緊張と煩悶の中で倒れる藤壺。言葉の限りをつくしても拒絶され、宮邸からも退出できなくなった源氏。
輝く明るい道を歩んできた源氏に、何やら不吉な前途がみえてきたようである。
〇源氏にしたら見つからない自信があったのでしょうが、藤壺の所に忍びこんでしまいます。最悪の場合、春宮の地位が奪われかねません。そのような危険を冒してまでも藤壺に会いたいと、頭の中は自制出来なくなっていたようです。
藤壺を目の前にして源氏は夢中でかきくどくのですが、藤壺は源氏を冷たくあしらいます。春宮を守りたいと言う気持ちが良くわかりますが、源氏は理解していないようです。
絶望に源氏は正気を失い、女房たちに塗籠に押し込められます。命婦の君と弁は、源氏をどうしたら良いか処置に苦しみます。
この先どうなるのでしょうか?
〇源氏は藤壷に逢いたくて忍び込む。藤壺は女として恋する人であるが、男の迫りに拒否する。この情景は源氏の心を傷つける。
このような場面は誰もが想像できないと語り部は伝えているのだろう。
源氏をかくまっているのだから宮は具合が悪くなるのだが、そんなことで右大臣家の騒がしさが伝わってくる。
男と女の恋心が現代に伝わってくる。
〇ストーカーまがいの行為に及んだ光源氏にびっくりしました。
人事異動でほとんどが右大臣派で占められ、四面楚歌の状態にもかかわらず、朧月夜と逢瀬を重ねたり、中宮の住む三条邸に忍び込むなど、大胆にもほどがあります。自分の欲望だけで行動し、理性が感じられません。
塗籠という納戸のような部屋をどこかで聞いたことがあったと思ったら、竹取物語のおじいさんが、かぐや姫を隠すのに使っていたのを思い出しました。
〇恋情を消すための祈?を 僧侶はどのような呪文を唱え 祈るのか知りたいです。
〇源氏ほどの地位にある人間が、単身で、しかもなんぴとにも知られずに中宮の身近に迫るなんて全くの異常事態で、狼藉を働いたとまでは言えないにしても、とんでもない修羅場であったのではと推測しました。
兵部卿などが「僧を召せ」と騒ぐほどの中宮の様子や、あの海千山千の源氏が正気を失ってしまったようなことが、その状況を示しているのではないでしょうか。
2019年8月8日「賢木」感想10
「代わり目」「危うい密会」を了えました。
〇権力が弘徽殿、右大臣に移り、源氏は勢力の消長、疎外感を、あちこちの女たちとの恋で埋めようとしている。
状況の難しさは源氏にとって恋の成就の力となるのだが。朝顔の姫君、朧月夜の君と逢瀬の機会の難しさと危険含みの恋は、憂さを忘れていられる時でもあろう。
しかし、この時代の貴族達の女性の自由奔放さには驚くし、女房達が手助けし、源氏との逢瀬を導くという、主を思う気持ちの強さにはただただ脱帽。それだけ源氏の魅力も強いのであろうが。
この危険な密会は、権力側の藤少将にみつかってしまった。どんな大きな波乱が生まれるのか?
〇右大臣側の特に大后の憎しみの矛先は源氏に向けられます。朱雀帝も、大后や右大臣に逆らってまで源氏をかばう力などありませんので、どんどん源氏の状況は悪くなります。
この状況を、「恋」への逃げ道として少しでも和らげようとしたのでしょうか? 長年親交のある朝顔に以前と同じようにせっせと手紙を送り続けます。尚侍の君には思いのたけを伝える手紙を出すと、熱烈な返事が源氏の元に返って来ます。
この厳しい状況となった源氏は一層尚侍の君を求めたように思います。二人の密会場所を中納言が手引きをします。源氏への風当たりが強く、源氏の力が弱くなっても応援してくれる多くの女性に支えられています。
〇国家的行事としての五壇の御修法の日が密会の日である。源氏の姿は目もくらむばかりであり、女は幸福感に包まれ夢心地になる。
朱雀帝に愛されながら、源氏との恋に身を投じてしまう苦しみを吐露する様子は、男の気持ちにも伝わり源氏の胸を締め付ける。
源氏の行動に心良しとしない勢力として、弘徽殿側の藤少将の口から非難攻撃の格好の材料となるだろうと、語り手は源氏の立場に同情する。源氏の将来を暗示しているのであろう。
〇光の君の大胆不敵さにはあきれ返ります。鬱憤晴らしもあるのでしょうか。政ごとの中心から外れた所へ追いやられたとはいえ、帝の寵愛を一身に受ける尚侍の君と一夜を過ごすなど、いくら何でもやり過ぎです。
夜明けにはまだ間のある霧のかかった空、細い残月、源氏の朝帰りはいつも一幅の絵を見るような美しさです。
〇源君と朧月夜の今回の場面のように 恋はお互いがすべてを覚悟し しかも大胆な心を持ちあわせていなければ 成立しないものかもしれません。
〇・五壇の御修法の日、帝がつつしみおはします隙をうかがひて、源氏と尚侍は逢う瀬を持った。
・二人を導いた中納言自身がそら恐ろしうおぼゆ。
・源氏は朝夕に見たてまつる人だに飽かぬ御さまで、尚侍は、げにぞめでたき御さかりで、をかしうなまめき若びたる御けはひなり。
・ほどなく明けゆく頃、ほんのすぐ側で「宿直奏」の合図があり、ユーモラスな半面、そこかしこでの恋の逢う瀬を知ることができる。
・その一人である藤少将に、静心なく出でたまふ源氏の姿が認められてしまう。
これって悲劇なのでしょうか、喜劇なのでしょうか。リアリスト式部の面目躍如たるものありですね。
2019年7月11日「賢木」感想9
「代わり目」に進みました。
〇朱雀亭の御代とはいえ、桐壺院にあった実権は崩御により勢力図が大きく変わる。11月の崩御、明けて2月には早くも大きく様変わりをし、源氏の上にも影を落とす。
弘徽殿の源氏への強く深い憎しみ、右大臣と左大臣の確執。異母姉妹になる姫の紫の上への憎しみと、女の持つ執念深さ。権力の持つ無慈悲さはどんな形で源氏に現れるのか?
挫折を味わう事のなかった源氏の傷つく心が思われるが、変わらず尚侍との危険な恋を秘かに4年も続けているとは何と懲りない事か? 危ない予感がいっぱいである。
権力に対して理不尽と思える事でも、決められてしまえばそれまで。権力におもねる様子は現代でも同じだと、つくづくと思った事である。
〇「后の御心いちはやくて、かたがたおぼしつめたることどもの報ひせむとおぼすべか(ん)めり」
弘徽殿の女御の今まで積もり積もった恨みつらみを、相手がむかいうつひまもなく容赦なく仕返しをする性(さが)が、意外なことに現実感があった。
〇源氏にとって生まれて初めての経験となりますが、昨年までの華やかな光景は影をひそめて人々が源氏から離れて行きました。大きな存在であった桐壺院が亡くなればこうなると源氏は覚悟していたはずですが、世の中の変わり身の早さに愕然とし、侘しさに自邸に引き籠ってしまいます。
世が変わり太后の源氏と左大臣に対しての意地悪が始まりますが、左大臣が家に閉じこもってしまうため、太后の憎しみの矛先は源氏一人に向けられる。
生まれて初めての挫折感、屈辱感を味わいますが、でも源氏には元気の源である女性達がついています。
〇桐壺院(帝)の後ろ盾に守られてきた源氏は、無念の思いをしていた太后に憎しみの矛先を向けられる。
そんな源氏は14才になった姫君を正式な妻とし、世間を喜ばせる。兵部卿の姫君は女の幸せを仕留めるのは自分ではないかと悔しさが増し、憎悪が渦巻くのである。語り部は物語のようだと皮肉る。ママ子いじめのようなのかもしれない。
右大臣家と左大臣家の確執がつづいている。
〇はなやかな光源氏のまわりに、薄雲が漂い始めてきたようなところが今月の学習でした。
大将殿の人柄が素晴らしいから、人が押しかけて来るのではなく、自分は、実権をにぎる上皇への取次役だったというみじめさ、むなしさをしっかり味わったことでしょう。
太后は上皇の崩御を悲しむより、我が一族に春が再び戻って来たという気持ちの方が勝っていたのではないでしょうか。
〇らうたく うつくしき 朧月夜の人柄も いとよくおはすれば、 かたみに 心ひかれたまはむは 心得ども 「今しも 御心ざしまさるべかめり」と源君あらば いとあやふし。
太后 里がちにおはしますとも いと恐ろし。
〇暗転する源氏の行く末。式部は源氏の周辺に生じた多くの不吉な異変を示します。
それでも源氏は「ものの聞こえもあらばいかならむとおぼしながら、例の御癖なれば、今しも御心ざしまさるべかめり」なのであります。
2019年6月13日「賢木」感想8
「遺言」「院崩後」を了えました。
〇桐壺院崩御四十九日の法要も終わる。引退後も政の実権は院にあった事を思うと、これからの様変わりが劇的なのでは?
弘徽殿の複雑な女心、プライドは復讐へと。性格悪しの右大臣は絶大な権力を持ち、若き未経験の朱雀帝を翻弄しそう。
中宮は桐壺院との濃密な愛ある思い出が生きる力になるだろうし、出家願望の源氏も庇護を必要とする者達が生きる力となるだろうと思う。それが救いになります様にと祈るばかりである。
〇桐壺帝が亡くなり、四十九日(なななぬか)後の藤壺女御の身の振り方で、実家三条の宮邸に去る想いがよくわかった。桐壺帝との睦まじくすごした院の御所の方が、実家より懐かしく去りがたい想いが痛々しかった。
〇桐壺院が重態となり、太后も見舞いにいかなければと思いつつぐずぐずしている内に院が息を引きとってしまう。左大臣にとって、格下だった右大臣との力関係が逆転した瞬間でした。
四十九日の間、亡き院を弔って共に過ごした御息所と呼ばれた人たちも里の方に退出して行き、中宮も儀式を終えて里に帰ることになります。
右大臣の権力が強くなり、弘徽殿の源氏いびりが始まりそうです。源氏の母親の桐壺更衣を今でもしつこく恨んでいるのでしょうか? 亡くなってかわいそうと思わないのでしょうか?
〇中宮のゆれ動く心情が心にくい。
人の姿が次第に消えて静かな空間が広がっていく。
故院の思い出話に花を咲かせる源氏の歌も、さえわたる池の鏡にたとえる歌も、語り手は何の工夫もない歌だと冷静につき放す。ここが物語の進行で面白いところだ。
中宮の胸には院と共に過ごした心豊かな日々がよみがえり、深い悲しみが全身を包む。
ここで終わらず、源氏の藤壷に対する懸想の苦悩が続き、場面の展開がいかなることになるか、読者をひきつける。
〇桐壺院のご逝去は悲しいことではありますが、中宮と大将殿にとっては、秘密を隠し通せたという安堵感もあったのではないでしょうか。
死者を悼む挽歌の類いは、万葉集には数多く出てきますが、紫式部は見事にそれを切り捨てました。過去を振り返ってうじうじするのは、紫式部の性には合わないのかもしれません。和歌の素養のない私には、兵部卿の歌も大将殿の歌もとても上手に思えたのですが。
〇兵部卿と 何事も無かったように 歌を詠み交す 源君の神経が 私には 分かりません。
それとも 源君の歌が下手なのは 心の動揺からだったのでしょうか。
〇権力の中心にあった人が亡くなり、その周囲にいた人たちがそれぞれの行く末に向かって散っていく。何時の世にもあるこの儚さを、式部はさりげなく描いています。その余韻が胸を打ちます。
2019年5月9日「賢木」感想7
「遺言」を了え「院崩後」に進みました。
〇桐壺院の重態の床での、いろいろの不安が物哀しい。親心、権勢を知る者の後事を憂える心が、遺言としていい尽せるものではない多くの言葉が物語る。言葉を連ねる程に、煩いも悲しみも深くなっていく事が知れる。心安からに死に向かうのは難しい。
朱雀帝、春宮、源氏、中宮は最後の言葉を交わしたのに、弘徽殿はとうとう行けなかった。弘徽殿も女だったのだと思いもし、女の切なさと怖さを思う。この事の思いが怨念として残るのではないかと・・・・。
〇10月に入り桐壺院は重態になるが、幼い春宮のことが心配で帝に言い残しておかなければならない。右大臣側の力が強くなり自分亡き後の源氏のことも心配で、帝に伝えて安心するまで死ねないと言う思いでなんとか力をふり絞って生きてきましたので、帝の顔を見ると少し安心して遺言を伝えます。
源氏が長男で跡継ぎだったら院の気持ちはどうだったのかな?と考えてしまいます。でもそれでは源氏物語が終わってしまいそうですが。
〇院の訃報は、都中の人々を驚かせた。
桐壺院は位を春宮にゆずり、余生を楽しんでいたかに見えたが、実際は院の元にあったことを世間の人は改めて思い知らされた。
人々は、朱雀帝のことが若すぎるのではないかと心配する。
源氏は藤の御衣の喪服に身を包んでいるが、父帝亡き後のこれから世の中のことを思うと痛々しくも美しく感じられる。昨年の北の方に続いて、父帝と近親者の死に目に会いこの世の中がつまらなく嫌になる。出家願望も断念するのであった。
平安時代の宮中の喪のことが興味深かった。
〇死の床にあった桐壺院は、第一皇子の朱雀帝に、帝の弟にあたる幼い春宮とその後見役の光大将との行く末の庇護を懇願する。右大臣側の帝に世話を頼むのもどうかと思うが、藁をも掴む気持ちだったのかもしれない。
弘徽殿女御は、家柄の良さ、入内の時期、皇子、皇女の数からみても第一夫人としての誇りがあるのに、桐壺院から何の遺言もなく別れなければならなかったのは、プライドが相当に傷ついたに違いない。
〇実の親子の 源君と春宮が(源君は臣下として 春宮に同行)、 二人の父親 桐壺院のお見舞い(お別れ)をする。
春宮は まだ五歳で 可愛い真っ盛り。
悲しいの 一言です。
〇院は朱雀帝に、東宮と源氏の御ことをかへすかへす聞こえさせたまはれた。また弘徽殿の立場にも心を砕き、わづらはしさを避けるため源氏を親王ではなく臣下にし、おほやけの御後見にさせようとした院の心積もりに違えるなと遺言した。
一方弘徽殿はすぐにでも御見舞いにと心がはやるが、中宮のかく添ひおはするに心置かれてためらっているうちに、院はかくれさせたまはれた。(これは必ず後に尾を引きます)
譲位後も院は実際の政の中軸にいて少しの乱れもないように気を配っていたが、その死により均衡が「きふにさがない」右大臣側に傾くことになり、いかならむと上達部、殿上人みな思ひ嘆く。
院の死によって左大臣側と右大臣側の勢力均衡が大きく崩れ、源氏の運命はこれを境に暗転することになるのでしょう。人の死と権力闘争の絡みは今の世もまったく同じ。物語の進行に増々目が離せないことに相成りました。
2019年4月11日「賢木」感想6
「別れの櫛」を了えました。
〇御息所は伊勢へ旅立った。
源氏は喪失感に、もの思いに沈んだ時を過ごす。
未練そのものの源氏の歌に、御息所は伊勢へ行く道のみと返歌し去って行く。
逢えない時間の長さ、伊勢という遠い距離の長さは絶望的だが、野の宮での身も心も想いを尽くした哀切な別れの時は、二人の胸深く残り消える事はないであろう。
女として、男として、魅力あふれた二人の十年という年月は長い。埋み火のように何かの折甦り、熱い想いの時を持つ事があるだろう。
〇源氏が六条院御息所に渡した歌
ふりすてて 今日は行くとも 鈴鹿川
八十瀬の波に 袖はぬれじや
〈私・源氏をふり捨て、今日は六条御息所は行くとも、鈴鹿川を渡る時は 川瀬の波に袖を濡らして後悔するのではないかと〉
六条御息所からの返歌
鈴鹿川 八十瀬の波に ぬれぬれず
伊勢まで誰か 思ひおこせむ
〈鈴鹿川の八十瀬の波にぬれようがぬれなかろうが、伊勢まで誰が私のことを思い起こしてこようか〉の毅然とした返歌に、六条御息所の凛とした人柄を感じる。
〇斎宮は帝との「別れの櫛の儀式」が行われる宮中の大極殿に向かいます。
朱雀帝は白の衣装を身にまとって斎宮を待っていました。この斎宮の美しい姿を目にし
た帝は一目惚れしてしまったようです。斎宮の額髪に黄楊の櫛を挿して「京の方へ赴きたまふな」と言います。自分が帝である限り斎宮は都に戻る事はない! 帝は深い悲しみに打ち沈みます。
このような帝の斎宮をいとおしむ切ない心情を斎宮は感じとっていたのでしょうか? この黄楊の櫛に帝の思いは魔除けの願いを託しているように感じました。
御息所、斎宮共に美しい二人の親子は悲しみにくれる源氏、帝を都に残して伊勢に向けて出立するのでした。
〇斎宮の伊勢路の行列は暗くなってから出発する。
源氏は邸にこもって思いに耽っていたが、二条の院の前を通る行列の面影が浮かぶと、思わず和歌を榊につけて御息所に送る。「鈴鹿川の波に袖はぬれているぞ」と、振り向いてほしいと呼びかける。
御息所の返歌では、「袖はぬれじや」と源氏の心遣いをふり切り、私の道を行くしかないと去ってしまう。
源氏は優美で洗練された字で示された和歌に、野の宮での恋を断ち切れないのだと思う。切なる源氏は御息所の去って行った逢坂山を、霧で隠さないでほしいと語りかけるのであった。
〇庶民の着物は手織り木綿の地味なものばかりだった灰色時代に、出し衣、出し車を連ねた貴族の行列は、まぶしいくらいカラフルで華やかなものだったことでしょう。
その行列がいつ見られるのか、人々はどのようにして知ったのでしょうか。
京都から伊勢まで、今なら2,3時間で行ける道のりですが、輿に揺られて峠を越えていくのは、担ぐ方も担がれる方も大変な旅だったことと思います。
光の君だけでなく、帝も好色男でおかしくなりました。
〇紫の上は 斎宮の伊勢下向が 邸の前を通る事は 女房から聞かされていたでしょうか。 もしそうなら その盛儀を一目見たいと 源君にお願いしたでしょうか。
〇御息所は「十六にて故宮に参りたまひて、二十にて後れたてまつりたまふ。三十にてぞ、今日また九重を見たまひける。」
斎宮は「十四にぞなりたまひける。いとうつくしうおはするさまを、うるはしうしたてたてまつりたまへるぞ、いとゆゆしきまで見えたまふ」
帝は「御心動きて、別れの櫛たてまつりたまふほど、いとあはれにて、しほたれさせたまひぬ。」
源氏は御息所に未練に満ちた歌を送る。
御息所は心を残しつつも、決然とした言葉を源氏に返し、京を去っていった。
こうして余韻を残しつつ、一旦、野々宮の別れの幕は閉じました。果たして向後、登場人物にまたの逢う瀬が参りましょうや。
2019年3月14日「賢木」感想5
「伊勢出立」を了えました。
〇惑い深い思いを封じ伊勢下向へ心を決めた御息所に対し、源氏の未練が止まない。女性からの別れに誇りが傷ついた(?)源氏の若さが見える。
凛とした魅力にあふれながら源氏への断ち切れない恋心、娘に慕われる母親、自らを省み揺れ動く女心、御息所の多くが語られる。
御息所への思いを深くした事である。
〇一旦は諦めて帰路についた源氏だが、情熱のこもった文を書き出すことによって又御息所への未練の情が沸き上がり、なんとか伊勢出立を思い止めようとして餞別の品々を山のように届けます。
御息所にしてみれば、斎宮の母との同伴を喜んでいることを考えれば思い止まることなど考えられません。
源氏もそのことは分かっていると思いますが、今度は斎宮に対して母の伊勢下向を取り止めるよう手紙を出します。源氏は斎宮の筆跡が分かりませんので、届けられた斎宮の返事が女官の代筆とは分からず、斎宮に対して恋のやりとりが出来る大人の女を感じ取り、興味が湧くのでした。
〇斎宮の伊勢下向に親が同伴するのは前例がない。語り手は客観的に見て世間の声がさまざまに聞こえていることを伝える。それ故に御息所の女としての立場は「もんもん」とした気持ちを伝え、高貴な女性である程に気苦労も絶えない見方が綴られている。
御息所の心境を源氏に対する気持に揺れ動いている描写はすさましい。人間の心の動きは、今も昔も変わらない。式部の物語は現代に通じる「女の心」を描写する。
出立の日源氏は斎宮に対して、母御息所と私との仲を考えてくれと嘆願する。語り手は、斎宮の年の割には面白い人と心惹かれる。源氏は若さに任せて斎宮のことを思い馳せる。
〇御息所様へ
後朝の文が届いたと言うことは、聖域の中にありながら、それなりの一夜を過ごされたということでしょうか。
あなた様は、これが光さまとの最後の夜と心に刻み、恋の炎に身を焼き尽くされたこでしょう。それでもあなた様は、元春宮妃としてのプライドからか、いつまでもくよくよと思い悩んでいらっしゃる。
世間の目とか、歳の差なんて気になさるほどのことではありません。高貴なご身分のあなた様なら、御夫君が亡くなられたその時点で、出家されても当然のような人生だったはずです。
報われなかった恋とはいえ、激しく熱い人間本来の気持ちを味わえた半生を送ることができたのですから、素晴らしいことではないでしょうか。
〇「斎宮は、若き御ここちに、不定なりつる御出で立ちの、かく定まりゆくを、うれしとのみおぼしたり」
この一文に 御息所が娘に慕われていること そして 彼女の幼さ 可愛らしさが よく表れていると思いました。
〇紆余曲折を経て別れの一夜をともにしたのに、なお果てしなく思い悩み続ける御息所と、深い処で本当に心がこもっているのか何か疑わしい源氏の所業に、正直「辟易感」を持て余しました。前項の「野の宮のわかれ」の場面が、この上なく美しく描かれていただけに、その想いは一入です。
とは言え、物語の面白さは毎回深まっていきます。
2019年2月14日「賢木」感想4
「野の宮のわかれ」を了えました。
〇夕月夜から暁まで、離別を感じながら故に、二人の逢瀬は切なくて甘やかで濃密な時であったろう。あふれつきぬ想いは、御息所の心深く大切な思いの恋心として秘められると思う。
嵯峨野の庭の晩秋の風情、夕月夜の光、別れをせまる暁、御息所の恋の終わりが何と美しい事!
〇P32.5行目
「女もえ心強からず、名残あはれにて、ながめたまふ。」
(女〈六条御息所〉も強情をとても張ることができず、心に残る源氏の面影をうっとり思いながめている)
という文で、六条御息所の恋の納め所を知りました。
〇御息所は伊勢下向を止めよと源氏に言われて動揺します。
思えば、御代替わりとなり娘が斎宮に就任して六条の御息所が初めて表舞台に出てきます。
「夕顔」の巻で、源氏が御息所のもとに通っていたのが分かりますが、あまり気が進まないと足が六条より遠のきがちで、また六条に行く途中で予定を変更したりしています。
この時、源氏17歳、御息所24歳でした。
「賢木」の巻で、野の宮に御息所に会いに行った源氏が23歳で御息所は30歳ですので、6年もの間、御息所は源氏への想いに苦しみ絶望的な日々を過ごしてきたと思います。「源氏の通いを心待ちにして明け方まで寝覚めがちな夜を過ごしている」と、これだけ源氏に執着した女性は他にいないと思います。
伊勢へ下向することで源氏への未練を断ち切り離れる決意をした御息所を、源氏は引き止めることが出来ません。源氏も、どんなに御息所を苦しめて来たのかと今更ながら後悔します。
「おほかたの秋の別れもかなしきに鳴く音な添へそ野辺の松虫」
9月8日の明け方、現実を受け入れて源氏は帰路に着きます。
〇源氏と御息所の別れの場面であるが、「おほかたの秋の別れもかなしきに鳴く音な添へそ野辺の松虫」、松虫に呼びかける御息所の気持ちはどのように展開していくのかわからない。
御息所の気持ちは、「伊勢下向」という現実と恋心が交錯している。
語り手も、着物の袖を露に濡らし、その上に涙を濡らしていると情景描写している。そんな情景を展開しながら、源氏の面影を写しつつ恋の余韻を残している。源氏のすばらしさを愛でるのがまだ続きそうだ。
〇「出でがてに、御手をとらへてやすらひたまへる、いみじうなつかし。」の一文は、もう会うことがないかもしれない人との別れのシーンを描いた素晴らしい表現だと思いました。
源氏のストレートな気持ちと、御息所の埋め火のように押し殺した気持ちとが「いみじうなつかし」に込められていると思います。
晩秋の「いと冷ややかな」風、「鳴きからしたる」虫の声、「いと露けき」道と、別れに相応しい大道具小道具も備わってセンチメンタルな学習でした。
〇さしも 思はぬことをだに 情のためには よく言ひつづけたまふべかめるは 罪です
嬉しがらせて 泣かせて 消えた
〇源氏と御息所の別離の場面を式部は思いを込めて美しく描き出しています。
併し、世間にも広く知られ、地位や資質にもこの上なく恵まれた二人の恋は決して実ることはなかった。さらに、近くには「車争い」「生霊」など常に不協和な出来事も重なってきた。それらを考えるとき、この恋の葛藤は二人に深い傷を残しているに違いなく、これからも濃い陰翳を落としていくのだろうと思います。
それやこれや、何かもやもやとした違和感を覚えながらの受講でした。
2019年1月10日「賢木」感想3
「榊のしるし」を了えました。
〇秋草が枯れ もの寂しい野の宮の夕月夜
月の光の中に在る源氏 それはそれは美しいだろう!!
終わりの兆しのみえる今 この恋の始まりの強い恋心が甦る源氏
伊勢下向を決心して 尚 思い切る事の出来ない御息所の恋心
行動的な源氏 知性が自由奔放さを抑える御息所
心に深く思いを残す 素敵な恋の終焉でありますように!!
〇伊勢下向を決断した御息所に対して源氏はそれほどの反応を示さなかったが、野の宮に滞在している間に会いに行かなければ、世間体もあり後悔すると言うこともあり野の宮に向かう。
源氏はここから積極的な行動に出ます。御息所を前にした時、弁解の言葉が出てこないことに気がつく。小さく手折った榊の枝を手に持って御簾こしに差し入れます。
和歌のやり取りをするうちに、御息所に伊勢に行ってもらいたくない気持ち、出会った時の燃えるような恋心がよみがえったようで涙を流すのでした。
〇源氏は御息所と和歌のやりとりを通じてお互いに通い合う。二人の出会いは夕暮れの頃であり、明るく照らし出された夕月も真夜中になり、ここ野の宮で恋人同士として気持ちを通わせる。
源氏は、御息所を恨んでみせたり口説きの言葉を寄せたりして打ち解け合い、澄みきった空間が広がる。
語り手(式部)は「つらさも消えぬべし」と男の源氏の気持ちではなく、御息所の気持ちを代弁する。御息所の胸奥のつらい思い出の数々は、源氏とみつめ合う中で溶けて流れ去るに違いないと、語り手(式部)は確信しているようだ。
〇先生のご説明がなければ、「はなやかにさし出でたる夕月に」という文から、私は満月を頭に描いていました。「はなやかに」」と言う言葉に惑わされていました。先月の学習で、九月七日という言葉が出ていたのに、陰暦が頭に浮かびませんでした。
この夕月夜が十五夜だったなら、夜通し月に光を浴びていることになり、「月も入りぬるにや、あはれなる空をながめつつ・・・」とはなりませんでした。
この場面では、相手の表情も見えない暗さだったからこそ、意思の疎通に繋がったのではないでしょうか。月齢七日の月を物語にとり入れる芸の細かさに感心させられます。
〇今回の源君の訪れで 未練心はお互いに さっぱり切り捨てて よい思い出の 終わり良ければ全て良しです。
〇源氏と御息所の恋の、複雑に絡み合った葛藤、そして別れ。式部は美しくみごとに描き出しています。
それは先生の深く重い解説文から、さらに強く感じ取ることができました。
2018年12月13日「賢木」感想2
「野の宮へ」を了えました。
〇伊勢下向を決意し、未知への不安にも心揺らぐ日々に、再会を乞う源氏の便りは残酷。
決断をした源氏の行動は早い。御息所を訪れ、嵯峨野の風情ある自然に圧倒され、人が入る事を拒んでいる神域に臆する事はない。
この行動力と思いの強さに、御息所の決意と女心が惑う事に納得。
心のままに行動する源氏の魅力、逢瀬を拒絶出来ない御息所の消せない恋心、二人に素適な時が来ますように。
〇源氏は自分から離れて出立した御息所を追いかけて野の宮に向かう。どうしても会いたいと言う源氏の気持ちは、一分の隙もない洗練された装いで分かります。神域に縄を張り巡らせて部屋に入れない所に、強引に入って行く源氏にはあきれてしまいます。
御息所も複雑な心境のままに源氏の近くに進み出ますが、内心は嬉しかったのではないでしょうか。
〇伊勢下向を前にした御息所の住む寝殿の北側を回り、源氏は身をひそめながら来訪した旨を女房に取り次ぐ。心得ている女房は、待っていましたと立ち居振舞いは源氏には心そそられて、御息所を待つのである。
御息所は対面には応じないと決めているので、源氏ははるばる気の重くなるのもこらえて会いに来たのにと、引く気はない。
御息所は女房たちの手前、渋々ながら会うことになる。源氏は寝殿の簀子に上がり、座を占める。御息所のけはひを「心にくい」と思いながら、源氏は胸をときめかせて待つのである。
〇神司の人々の毎日も つまらなさそうです。
源君は 彼等への おみやげを 用意したでしょうか。
〇源氏はいよいよ野の宮に向かいます。
「遥けき野辺を分け入りたまふより、いとものあはれなり・・・・・ものの音ども絶え絶え聞こえたる、いと艶なり」
晩秋の嵯峨野の描写に感銘を受けました。
2018年11月8日「賢木」感想1
「決断」を了えました。
〇都を離れる事を決断した御息所の気持ちが揺らぐ。源氏の姿をみる事も出来ず、消息をきく事も出来ない遠い伊勢での生活への不安も、愛しい人への切ない思慕をかきたてる事になるだろう。
理知的な御息所のこのあふれる哀切な女心、とても魅力的である。
別れなければならないのであれば、夫々が美しい時を持ちたいと切に希う気持ちがよくわかる。
いい時が持てますように!!
〇本日より賢木に入りました。
系図も右大臣が中心になって左大臣は左の端となり、権勢が右大臣、弘徽殿大后に移って源氏の立場も厳しくなりました。
一方、御息所は源氏への思いを断ち切り、娘の斎宮と伊勢下向に向かう覚悟を決めるが、それを知った源氏は情愛あふれる手紙を何度も送る。
御息所は心弱い自分を封じ込め、源氏から離れようと野の宮に入る。源氏は聖域である野の宮に向かう決意をする。
〇賢木の巻に入る。
御息所は伊勢へ斎宮と出立しなければならない。源氏との恋は、北の方が亡くなってから偲ぶ仲であったが、世間に漏れて源氏のことが噂されていた。源氏と御息所はしかるべき正式に結婚するのでないかと風評が立つほどであった。
御息所は源氏への未練を捨てて、伊勢下向に斎宮と同行することを選ぶ。
源氏は御息所に手紙で伝える。御息所は源氏からの手紙により、会いたい気持ちを抑え、心弱い自分を封じ、源氏との恋はあきらめ離別することを決断する。自分自身に立ち返るのであった。
〇今月から「賢木」に入りました。何故普通に使われる「榊」ではないのか、おいおい分かるのかと思いますが待ち遠しいです。
斎宮と共に伊勢へ下向することを一度は決めた御息所の逡巡する気持ちの部分を学びました。
二人の交際期間は、とぎれとぎれとは言え長く続いていたのですから、美意識とか価値観などは、お互いに共通する所がかなりあったと思います。花を見て「きれいだね。」と言ったとき、すぐに「そうね。」と返ってくるような近くにいて欲しい光の気持ちもよく分かります。
魂が苦しみのあまり生霊となって飛んでいくほど、一人で苦しみぬいた御息所ですが、当時の女性には悩みを打ち明けられるような友達というのはいなかったのでしょうか。
〇華やかな 都の生活しか送ってこなかった人が 嵯峨の野宮より はるかに遠い伊勢へいつまでという事も許されず下るのは お気の毒です。
卜定されて 本当に不運です。
〇伊勢下向を目前にして、御息所、源氏ともに心が揺れに揺れています。
物語の波乱のこれからを、ひしひしと感じさせる「賢木」の幕開けでした。この巻の学習も、大いに期待し、楽しみつつ臨みたいと思います。
2018年10月11日「葵」感想25
「左大臣家の新年」で「葵」を了え、次回から、いよいよ「賢木」に入ります。
〇桐壺帝が退位し、朱雀帝の世に変わり、源氏も22歳となり、葵の巻が始まった。
御息所、若紫等々、色々な出来事の中、子供を残しての葵の死。凛とし毅然としていた葵が、源氏を想う深い心を伝えて逝く。
喪が明けても、なお悲しみの中にいる源氏、そして大切な子供を亡くした左大臣、大宮の尽きぬ悲しみの中、新年が始まり葵の巻が終わる。
結ばれた紫の上はどうなるのか。哀切な女心にゆれる御息所はどうなるのか。千年の昔から変わらぬ心情。新しく始まる物語が楽しみ。
雅さ、想いを深くし拡げる古語に、益々魅せられている。
〇葵が始まった時、すでに桐壺帝は退位して新帝朱雀帝の世になっていました。
源氏にとっては、今まで支えてくれた父帝には頼ることが出来なくなり、源氏を憎んでいる弘徽殿から、この先どのような報復があるのかな?というところからのスタートですが、有名な車争い、北の方の出産と急死。その後、若宮が春宮とそっくりになって来て「ドキッ」。若紫と結ばれるが、嫌われてしまうなど大変なことになりましたが、大宮からは、変わらず衣装の数々を贈られ大切にされる。
平成28年7月14日に葵に入り、2年4カ月かかりましたが、中身の濃い充実した時間でした。
〇心づくしの数々の着物を大宮から贈られた源氏は、お礼の手紙をしたためる。
左大臣家に外の風(春や来ぬる)を入れて、鎮魂の思いで、うちひしがれている気持ちを変えようと左大臣家に足を踏み入れたが、思い出が押し寄せ言葉に出せず歌に託す。
「あまた年今日あらためし色ごろも きては涙ぞふるここちする」。昔のことを思い出し、気持ちを静めることができないと悲しみを伝える。
大宮からは、老いた「親の涙は新年になっても降っている」と、嘆き悲しんでいることを伝える。
元旦の悲しみが余程のことがあったと、左大臣家の状況にあることを語り手は語る。
〇長い葵の巻が終わりました。28回に分けての学習でした。娘(葵の上)に先立たれた親(左大臣夫妻)の悲しみで終わる今日の学習は、読んでいて胸が詰まる思いでした。
目次をはじめから読んで内容を思い出してみると、題名は「葵」とは言え、「御息所」にかかわる内容が多く、しかも葵は、周りの人の言いなりに行動するだけの人形っぽい人物のように描かれています。
急死する直前には、内裏へ出仕する夫を《常よりは目とどめて、見いだして臥したまへり》となりますが、話をしたわけでもなさそうで、文楽人形程度の動きしか感じられませんでした。
〇「今日ばかりは やつれさせたまへ」なんて とんでもない。
大宮が選びに選んだ 気品・格調高い、渋めの下襲を 完璧に着こなした 源君の姿が 目に浮かびます。
〇「葵の巻」は、哀切に満ちた「左大臣家の新年」で幕を閉じました。
私の場合、今回の項で特に感銘を受けたのは先生のあとがきで、P.209から211にかけて、この物語のとても深い理解・解釈が記されていると思いました。わが理解を顧みて、何と浅い事かと思うことしきりです。
その自戒を込めて、「賢木の巻」に挑戦していきたいと思います。
2018年9月13日「葵」感想24
「まことのよるべ」を了えました。
〇保護者としての夫から、男としての夫に変わった源氏を受け入れられない女君。
それに対し、ひと時も側を離れたくない程、いとしく恋い慕う源氏。手塩にかけた4年の年月は、女君を魅了的な女性にしている。
女達からの便りにも、訪ねる気をおこしていない。庇護がなければ生活できない女達は、さぞかし気がもめた事と思う。心ひかれている女達とは、縁を切らずにおこうとする源氏、この男あるあるは昔も今も同じの様である。
さて、正式な妻としての立場を明らかにする儀式はささやかに行われる。このささやかであった事が、後々のドラマにつながるらしい。
興味がつきない!!
〇惟光の努力によって秘密裏に事を進めて、女房たちにも知られずに無事に三日夜の餅を祝ったが、女君にはすっかり嫌われてしまう。
源氏の方は熱に浮かされたように、一時も離れたくないほど女君に燃え上がってしまう。
一方、四十九日が過ぎたからでしょうが、付き合っていた女性達から誘いの手紙が来る。体調がすぐれないことを口実にしてやりすごしていたが、服喪中にした方が良い事に気づき、女性たちの気を鎮めることに成功する。
女君の14歳になる御裳着の儀式も、世間に知られずに行はれました。
〇源氏は、姫君と枕を交わした。今まで以上に姫君の立場をしっかりしたものにするために、男子の成人式にあたる女子の成人式として、「御裳着」の初めて裳をつける儀式を、並々ならぬ思いを込めて準備をした。
語り手は、社会的評価がされていない姫君のために努力している源氏を、「いとありがたけれど」と褒めたたえるが、姫君は、源氏に対する反発と自己嫌悪の情で一杯になり、もがき苦しみ、そばにいる源氏がうっとうしい。
姫君の打ち解けてくれない態度に、「恋こそまされ」(万葉集の歌の一節)と、源氏の思いは自分の気持ちを伝えるのである。源氏の気持ちが理解できるか、読者に判断をまかしている。
〇4年もの間、夜は源氏に抱かれて安心して寝ていた姫君にとって、枕を交わす出来事は晴天の霹靂だったに違いありません。でも、あの好色の男性が、よくここまで我慢したものだと思いました。
今回の学習にも古今集、万葉集の歌が引用されていましたが、普通に勉強したくらいでは、なかなか引用するまでにはなれません。万葉集は、長歌、短歌合せて4500首以上あるし、古今集も1100首以上あるとのこと。いにしえの人たちはどのようにして学んだのか不思議な気がします。
〇紫の上が北山から突如消えて しかも時を経た現在 自分の元にいることを 源君は 兵部卿宮に どう説明するか 出来るか 興味津々です
〇源氏は、身も世もなく女君にのめり込んで憚らない。女君は、源氏に対する反発と自己嫌悪がないまぜになって苛まれている。
弘徽殿大后は、御匣殿が2年を経てもなお源氏に執着しているのが忌々しく、父右大臣が、この際、源氏に鞍替えしても差し支えないと考えている事も、腹立たしく許せない。
御息所を、源氏は「いといとほしけれど、まことのよるべと頼みきこえむにはかならず心おかれぬべし」と強く思う。
さらに、並々ならぬ思いを込めて準備した「御裳着のこと、人にあまねくはのたまは」なかったことが、意外にも、女君の行く末の重要な伏線となっているとの由。
「まことのよるべ」の項は、かくも複雑・深遠な人模様を見事に描き出している。
2018年8月9日「葵」感想23
「子の子餅」を了えました。
〇結婚を祝う〈三日夜の餅〉の宮中行事が、現在も残っているというのは興味深い事である。
この行事が惟光により密かに進められ、翌朝少納言他、女房達にも結婚の事実が明らかとなり、手伝いが出来なかった心残りはあっても、正式な妻となった事は大きな大きな喜びであったはず。
久しぶりの惟光の、その心遣い源氏への深い思いがわかる。源氏の人となり故もあるなと思いつつ・・・・。
〇源氏は女君の思わぬ反発に戸惑ってしまう。そんな時に宮中より女君の元に亥の子餅が届けられる。源氏はそれを見て三日夜の餅を思いつき、惟光に明日の子の日の夜に届けるように命じる。
惟光は源氏の気持ちをすべて察して、女房たちに知られぬように実家で家の者に作らせた三日夜の餅を、少納言の娘、弁に持って行かせる。意味もわからずに持って行く弁ですが、受け取った女君の方も、子の日の夜の餅の意味はわからなかったのではと思います。
食べて筥を下げたと思いますが、女房たちはその意味を覚る。乳母の少納言は感無量です。惟光の評価は大いに上がりました。
〇十月に入って、亥の子餅行事は無病息災・子孫繁栄を祝って餅を食べる習わしがあり、女君と結ばれたことで、源氏は事情の分かる「惟光」を呼んで彼にまかせる。
惟光は配慮して、少納言の娘の弁(女房)を呼び出し、香を入れる壺を収める筥に餅を収めて、枕上に言われた通り差し入れた。語り手は源氏がいつもの調子で「三日夜の餅の由来」を女君に教えている様子を、それとなく、いつも仲睦まじい光景を伝える。
翌朝、三日夜の餅のことを惟光が内密に進めていたことが、側近の女房たちは筥の意味を覚る。まさか正式な妻となるとは思ってもみなかった。源氏を恨んだり、惟光の心づかいを口々にささやきあった。
〇源氏物語の中に「惟光」が登場してきたのはいつ頃のことなのでしょうか。この会に“途中入学”した私にはよく分かりませんが、印象に残ったのは「夕顔」の巻です。
荒れ果てた“なにがしの院”へ女を連れて逃避行した源氏を見つけ出した上、その女の亡骸の始末も秘密裏にやってのけた惟光の働きには、本当にびっくりしたのを覚えています。
今回、源氏は、惟光が、“亥の子餅”を“子の子餅”に変身させてくる事に「もの馴れのさまや。」と感心していましたが、まだ二人とも十代だったあの頃に、鳥部野に密かに女を葬ることの方がもっともっと大仕事だったと思います。
〇亥の子餅は いかにも栄養があって 万病を祓いそうですが 何か まずそう。
惟光君が張り切って 里で作らせた 子の子餅は おいしそう。
彼の つまみ食いしている姿が 目に浮かびます。
〇女君と結ばれて、源氏は自身もあきれ果てるほど更に深く愛するようになる。そして密かに三日夜の餅を届けるよう惟光に命じる。惟光は全てを察知し、肌理細かく心遣いを尽くして見事役割を果たす。翌朝女房たちが初めて知るところとなり、口惜しがったり、惟光の業に感嘆する。少納言は源氏の心ばえに感涙する。
院や帝から宮仕えの者たちに至るまで、その全てに式部の目配りが行き届き、私たちはこの時代に生きた人々の姿を活き活きと感じ取ることができる。
2018年7月12日「葵」感想22
「結婚」を了えました。
〇美しく理想的な女として成長している紫の上。心癒されている源氏。二人は結ばれる。
夫として認識はしているものの、保護者であり庇護者との思いの紫の上にとっては、大きな衝撃であった。源氏に対しても自分に対しても。
容姿や所作の美しさは生まれもっているかも知れないが、作法他については、乳母少納言としては教育の手抜きでは?
しかしながら、源氏は苦しみ悲しみ拗ねるその様子全てが愛おしい。先々の幸せが思われる。
突然、昔読んだ「風と共に去りぬ」のレッド・バトラーとスカーレット・オハラが結ばれた、真逆の幸せな朝の情景を思い出した。こちらは大人の男と女の話。
〇源氏が姫君と北山で出合い、邸に引き取ってから4年たちました。幼かった姫君も14歳になりましたが、精神的にはまだ幼いままで成長していない気がします。
源氏を父親だと思っていたのにと、衝撃で朝起き上がることが出来なくなったとあり、源氏も姫君の幼さを理解出来なかったのでしょうか。今じゃないでしょうと思いました。
まして、北の方に先立たれた悲しみは、北の方に対しての後悔の念もあったのにと思いますが、あまり源氏がそこまで気を使い喪が明けてからなどと考えると、読者の源氏に対する評価を狭めてしまうのでしょうか?
〇光源氏は、成長した若紫を心苦しいと思いためらう気持がありながら、焦る気持をもってしまう。
語り手は、いつもの夫婦とは別の不審な行動をとってしまうと、衝撃の事実を語る。
源氏は女君の衝撃を受けた姿にたじろぎ、どのように慰めていいかわからない。枕元の硯箱を使って和歌を書いているのに、返歌がないとため息をもらしながら几帳の中に入り込んで、源氏はいとおしみながら気持を募らせている。
男女の夜の秘め事を、式部は巧みな情景描写として語るのに、読者を惹きつける。
〇これまでに学習した中で、心に残るドキッとした場面はいくつもありました。
例えば、突然死した夕顔の亡骸を《うはむしろ》に包んだとき、見事な黒髪が《こぼれ出でたる》ときの情景。また、葵の上にとりついた生霊退治のためのケシの香が、六条の御息所に移り、着替えても洗髪をしてもとれずに残るという描写。こうしたところから紫式部の着想の豊かさが垣間見られました。
でも、今日の学習の《男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり》は、物語の品格の高さを改めて感じさせてくれました。原文を読まなければ感じることのできない素晴らしさでした。
〇「いかが ありけむ。さらに 起きたまはぬ 朝あり」
これは 様々な場面において、或る出来事を 的確に想起させる 使える名文だと 感心しました。
〇「男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり」に強く感銘を受けました。源氏と若紫との間に起きた艶やかな出来事を、式部はこんなに見事に表現するのだと。
それに、受けた衝撃に打ちのめされている若紫、どう慰めてよいか分からずたじろぐ源氏、この二人の描写もほほ笑ましく読
2018年6月14日「葵」感想21
「帰邸」を了えました
〇左大臣邸を去り、桐壺院のもとへ。院はやつれた源氏を慈愛にみち、心を尽くして迎える。源氏の喜びが思われる。
地味な色の喪服、憂いの中にある源氏、いかにも美しい。
夜更けて二条院へ戻る。源氏を迎える院は人々も全てが華やいでいる。
久し振りの若紫は美しく、“心尽くしきこゆる人”にそっくりに成長している。源氏のよろこびは大きい。
悲嘆の別れから、優しさに包まれた院、喜びと華やぎの二条院と、夫々に複雑な感情の動きの長い長い一日だった事であろう。
〇4月5月と長恨歌120句の勉強をしましたので、久し振りに本に戻って来た思いがします。
源氏も四十九日が過ぎ左大臣家を後にする際、別れ際に首を垂れてずらりと居並ぶ光景が頭に浮かびますが、振り払うようにして西の対に渡ります。
久し振りに会う少納言は洗練されていて、姫君もとても愛らしくなっていて、願い通りに成長していることに夢が叶えられるようで、源氏は胸を躍らせます。
不在中の出来事を源氏は姫君に話しますが、縁起の悪い部分は省略し、これからはいつも訪れるからと機嫌を取りますが、少納言は本当だろうかと疑う。
〇宮中の四十九日法要をすませ、光源氏の妻「葵」を見送る。
少納言や女房共は側近として洗練された感性で心安しく迎える。
そこには、とても愛らしい「紫の上」が大人びた姫君となって、源氏に見とめられる。そのはにかむ様子に、源氏は姫君の成長に胸を躍らせる。
少納言の心配事として姫君の幸せを考えると、果たしてこれでいいのかと心配していることを「語り部」に語らせ、源氏は心安しい人だと自問自答している。
心にくい風景描写である。
〇光を取り巻く「暗」から「明」の生活について読み進みました。
古事記に例えれば、黄泉の国が左大臣家、黄泉平坂(よもつひらさか)を上り終えた現世が二条の院でしょうか。光は、誰もが驚くほどのやつれ方だと言うのですから、かなり精神的に大きなダメージは受けたと思われます。
現代では和装の喪服は女性には見かけられますが、男性は見かけません。小説の中に喪服を着た未亡人の美しさが書かれたものがありますが、和服の持つ雅さと着ている人の悲しみが溶け合って一層美しく見えるのでしょう。
〇院の前に かしこまり 上品に食事している源君の姿が 目に浮かびます。
ニコニコ パクパク おかわりしてくれたら お父さんとしては どんなに嬉しく 安心することでしょうに。
〇四十九日を経て、源氏は新しい生活に踏み出します。
院や中宮、二条院の人達、とりわけ紫の上の成長、そして少納言の持つ不安など、源氏を取り巻く人物について余すところなく的確に描かれています。また源氏の艶めかしいやつれ姿も。
短い文章の中に、こうした叙述がてんこ盛りになっていて、読者は物語の今後の展開に惹きつけられていくのです。
2018年5月10日
「長恨歌」感想2
120句読み了えました。
〇皇帝に命じられた修験者により、楊貴妃の亡魂の行方がわかる。訪ねた修験者に託した皇帝への伝言は“比翼連理”の言葉である。
玄宗皇帝と楊貴妃の強い絆と、深い永遠の愛を教えてくれるが・・・。男と女に永遠は夢物語?
美人を、風情を、情緒を表す漢詩の美しい言葉が素適だった事、漢詩を読解していた平安貴族の教養の高さに脱帽し、どれ程の勉強をしていたのか尊敬の念しきりである。
〇長恨歌後半に入り、修験者は命じられて、楊貴妃の亡魂を求めて天空の果てから黄泉の底まで捜しに入り、蓬莱宮に住んでいた楊貴妃を見つける。
夜も眠れないほど楊貴妃を思い続ける皇帝だが、楊貴妃の方は皇帝の声も面影も思い出せない。思い出せないながら懐かしさだけはあり、記念の品によって思い出そうとする。皇帝と交わした聖言の言葉を添えて、皇帝への伝言を使者に託すのであった。
〇長恨歌を通して、皇帝と楊貴妃の愛情を学んだ。
源氏物語にそれとなく引用されていることは、式部の物語を綴る上で参考になったのである。それは、式部にとって、光源氏という男性を通して「心」の大切さを語りたかったのであろう。
道長は、自分の娘を天皇に嫁がせることで、しっかりとした政治の仕組みを作ることに、「源氏物語」の作成作業が待ち遠しかったのである。道長の長期政権の礎が、その後の日本の政治、文化の流れに影響を与えたことに相違ない。
〇120行にもなる長い詩を読み終えました。高校時代に、どの位の抜粋部分のものを勉強したのか定かではありませんが、全文ではないことは明らかです。
今回全文を読んで、子どもの頃習った長唄「鶴亀」というのを急に思い出しました。新年を寿ぐおめでたい歌詞でしたが、その中に「君の齢(よわい)も長生殿に、君の齢も長生殿に」と繰り返す所があったのです。
長生殿とは玄宗皇帝と楊貴妃が愛を誓い合った場所だったのだと知り、子供の時の記憶が、千年以上前の中国にまでつながっていたことに感動を覚えました。
〇人の道に とりわけ君主の道に 外れた 幸せは 人故の物であり、とにかく 楊貴妃は 玄宗の目に とてつもなく 可愛らしく 耳に 心地良過ぎたのでしょう。
〇当時の貴族たちに広く知られていた長恨歌。その要素を巧みに取り入れて、式部はこの物語を進めていったのだと思いました。特に「桐壷」。一面学びつつ、更にその上に独創的な展開を図って行く式部に、改めて感銘を覚えました。
このことからも、平安王朝の文化が中国の影響を強く受けている事、そして、外部から得たものを独自のものに仕上げていく日本文化の特色が、すでにこの時代から見られ、それが現代にまで営々として受け継がれている事など、興味深く感じた次第です。
2018年4月12日「長恨歌」感想1
2回目の回読で80句まで進みました。
〇ほんの一節ぐらいしか記憶になく、玄宗皇帝と楊貴妃との恋物語で悲劇と破滅への物語と思っていた長恨歌であるが、源氏物語に大きな影響を及ぼしている事も知り興味深く楽しんだ。
一国を失っても悔いはなしと思う程の絶世の美女楊貴妃を見出した皇帝の夢のような日々は、長くは続かず面前で殺され失う。その悲しみ、傷心の思いが自然の景色や風情の歌の中に深くうかがえるし、七文字の漢詩の一行で季節の移ろい、時の流れ、美しい情景や心情を思い描かせてくれるのが興味深い。そして物語の結末は?
〇娘に先立たれ源氏に去られ抜け殻のようになっている左大臣。源氏が残した手習いの紙の中に長恨歌の一節が書かれ、源氏の歌が書き添えられてあった。
桐壺帝と桐壺更衣の関係も長恨歌を参考にしたのではないか?と言う説もありますし、桐壺から葵までの中に参考にしているのかなと思うような所もあります。漢詩特有の漢字の重みを感じますし、七言百二十句で長編小説を書いてしまうと言う素晴らしさもあります。
長恨歌は白楽天34歳のころの作のようですが、漢詩ですので当然省略して作られているわけですが、楊貴妃の場合は以前の姿を省略したのは故意のような気がいたします。
源氏の手習いの紙に和歌とありましたが、紫式部は和歌も参考にしていたと思いました。
〇式部は、長恨歌を手にして、どのように理解しようとしたか。漢文の素養があったから十分わかった上で、皇帝と楊貴妃のロマンスをとり上げたかったに違いない。
石山寺の式部の部屋が残されているが、その寺には、日本の興福寺の僧で遣唐使に派遣され、日本に帰れなかった僧「霊仙三蔵」(後に中国皇帝から三蔵法師の称号をもらった人物)の碑がある。
この人物との関係は不明なことが多いので、研究、調査が必要であると思う。
〇「漢皇 色を重んじて 傾国を思ふ」という出だしの部分に違和感を感じました。
玄宗皇帝は唐時代の皇帝なのに、漢時代と言えば、かなり時代が遡るからです。初めて読んだ時には分かりませんでしたが、読み直してみて、「漢」は日本で言えば縄文、弥生の時代であり、「唐」は奈良、平安の時代に当たるほどの年月の差があることに気づきました。
作者白楽天は、唐時代の詩人ですから、現在の為政者に遠慮をして「今は昔、」という手法を用いたのだと思いました。
まだ途中までの学習ですが、中国特有な大げさな表現や、あり得ない登場人物などエンターテイメント性が高く、次はどうなるか楽しみな長編詩です。
〇玄宗と楊貴妃の 愚かで 身勝手で あてどもない 長恨などは、時を経ず 朽ち果てていくことでしょう。
白居易の 目指したものは、恋愛賛美ではなく 教訓の長詩であると 私は感じました。
〇「漢詩」をつぶさに読むのは今よりはるか60年前、高校生時代の「漢文」の授業以来のことです。源氏物語の「古文」もやはり「国語乙」の授業以来です。喜寿の齢を越えて、錆びつきかけた感性をこの二つの同時進行が揺さぶり、懐かしさと共に深い喜びを感じさせてくれます。
2018年3月8日「葵」感想20
「残された手習ひ」を了えました。また「長恨歌」の回読も始めました。
〇源氏はついに左大臣邸を去る。娘に先立たれ源氏とも別れるつらさに、源氏達の部屋に入った左大臣は、手習いの紙に残された二首の歌に夫婦の深い愛と、妻への強い恋情を見る。
死に近い床で通い合った葵と源氏の細やかで甘やかな時と、この歌に詠みこんでいる夫婦愛に、葵の幸せが思われ嬉しい。
高貴な家柄に育ち、気品高く育った葵。それ故に、思うがままに気持ちを表す事も、秘さざるを得ない事も多々あったはず。千年前の昔も今も、そしてこれからも、夫婦の事は二人だけにしかわからない事と納得した事である。
〇十年一昔。源氏は12才で葵と結婚し、22才で葵が急死しました。この間いろいろありましたが、お互いに愛し合っていたと言うことになりました。
北の方の良い所をしっかりと源氏は見ていて、北の方も源氏を心から慕っていたように思います。
左大臣、大宮、源氏が悲しみに打ちひしがれているのに、頭中将はその悲しみの中に入っていませんが、当時はそんなものだったのでしょうか? それとも単に省略されているだけでしょうか?
〇亡くなった北の方は、源氏との関係をことばで表現するのが苦手であったのか、誰にも表面からはわからない。
「あくがれがたき心ならひ」の言葉(注)が、左大臣、大宮、そして女房共に余韻を残した。(注)手習いに書き残した「長恨歌」の一節に、源氏が書き添えていた。
源氏に北の方は愛されていたことが伺われる。源氏の北の方に対する愛情表現から、複雑な諸々があったことがわかる。
〇妻の葵の歌が一首もないのは不思議な感じがしたのですが、源氏自身も生前の妻に後朝の歌など贈ってないのでは?と考えてしまいました。
葵が、いくらおとなしい女であっても、女遊びに忙しい夫に、何の感情も持たないはずはありません。嫉妬心めらめらの歌が、葵の文箱の中から見つかるかもしれません。
亡くなった妻を恋うる源氏の歌は、遅きに失して本気さ加減がわかりません。
〇源君は 幼くして 母を失い、 又もや 我が子も 母を失ってしまいました。
前世の契りの 無慈悲さえ感じました。
〇源氏の書き残した歌は亡き妻をおくる歌で、深いところでは葵を愛していたとの心を歌ったものとは思えないのです。せいぜい失って初めて、その存在の大きさやありがたさに気付いた程度のものではないでしょうか。
若紫へのみずみずしい想いや、夕顔を亡くした後の落魄ぶりと較べてみると、そう強く感じます。ここにも、この物語の悲劇性の一面が見えるように感じました。
初めて長恨歌を詳しく読む機会を得ました。始まったばかりですが、とても面白く来月の講読会が楽しみです。
2018年2月8日「葵」感想19
「別れ・大宮と左大臣」「別れ・女房三十人」を了えました。
〇いよいよ左大臣邸からの別れの時。悲しみに耐え泣く姿も、“たびたび鼻うちかみて”いる姿も、皆をうっとりさせる源氏。その品、美しさ、雅さ、想像が難しい。
会う事も最後と思う左大臣は、葵との冷たかった夫婦仲の恨みをいい、源氏は若君の様子を見に来るのでこれきりではないと、少し信じがたい言葉を並べる。別れの中での言いたい事いっているのが面白くおかしい。
しかしながら、源氏の去った後、二人の部屋に入る左大臣に、哀しさや淋しさ、源氏への深い愛情を感じる。
〇源氏は桐壺院に参上するための準備を始める。大宮には直接挨拶に行かずに手紙を届ける。左大臣は出立を知るや源氏の所に渡って来てお互い泣き合うが、左大臣の悲しみは甚だしく、とても院には参上出来る状態ではないので、このありさまを院に伝えてほしいと源氏にお願いする。
出立の時を迎え、源氏はあたりを見回すと、女房三十人ばかり一所に集まって不安気な表情を見せている。左大臣は、女房逹の思いは源氏はもう来ないのではと思っているが、そんなことはない、若君がいるので必ず来ると言い聞かせているのだが、見すてられると思っているのですよと源氏に言うが、女房以上に左大臣の方が、源氏との別れに身が切られるようにつらく、涙を流すのでした。
〇左大臣家が源氏たちの夫婦仲がうまくいっていないことを心配していた様子を、女房や左大臣を通して語られる。源氏はこの空気を察して、今までの自分とは違ってたびたび訪れたいと言い訳をして、邸を後にする。左大臣はそれを見送るが、すぐに部屋にもどらず源氏たちの夫婦の部屋に入り、空蝉のような、抜け殻のような虚しさを感じるのだった。
このような心の襞を描写することのむづかしさは理解できても、読者には判断をまかせてくれない。源氏物語がいつまでも現代の人に問いかけているのだろう。
〇右大臣系の血を引く朱雀帝の世となり、左大臣家の勢力図にも、やや翳りが出始めた頃かと思われます。左大臣にとって一人娘の死は、子に先立たれた悲しみにとどまらず、政治的にも大変なできごとだったことでしょう。
婿、光源氏との別れは、邸を去るのが寂しいと言うより、これからの左大臣家の行く末を考えると不安でたまらなかったことの方が大きかったのではないかと思います。
〇源君の うちとけおはし 常に訪れ給はむを あいな頼めしは 女房もしかり、 されど 誠は 大臣にこそあらめ。
親の 子を失った時の悲しみが 切々と 胸にせまりました。
〇「さらば、時雨も隙なくはべるめるを、暮れぬほどに」と、源氏に出立を促す左大臣の姿に万感迫るものがあります。左大臣のお人柄を示して余りありです。
いつもそうですが、導き手なしにはこの物語を読み進めていくことは不可能と、重ねて思い知らされています。
2018年1月11日「葵」感想18
「別れ・仕える人々」を了え、「別れ・大宮と左大臣」に進みました。
〇通い婚のこの時代、亡き妻葵の上の四十九日が過ぎれば左大臣邸を去らねばならない源氏。夫々仕えていた主がいなくなれば職を失う女房逹。葵に仕える女房の中に、長い間源氏と密かに心を通わせている女房が存在するという事。諸々の習慣が興味深い。
さりげなさを装いながら去っていく源氏に、ついにきたその時を感じ、左大臣、大宮、女房逹の別れの悲しみの大きさ深さが溢れ、止まらない涙にひしひしと伝わる。
男女関係の大らかさも、主従関係の強さにも惹きつけられるものがある。
〇源氏にとって49日間も喪に服して外出を控えるということは初めての出来事と思います。前回ではその間中将と語り合ったり大宮に手紙を届けたり左大臣邸の人々との交流だけでは心が満たされず、言い様のない寂しさが心を覆うとありました。
朝顔の宮なら寂しい心を満たしてくれるのではと、特別に上質の紙を使い気合を入れた手紙を出して返事をもらいます。磨きぬかれた感性を持ち教養の深い御息所では重すぎる、
「対の姫君」はまだ大人になっていないなどと関係のある女性たちを思い浮かべますが、今回は「中納言の君」というかなり以前から付き合っている女性が出てきました。
妻を亡くして寂しいという気持ちは、夕顔が亡くなった時のショックとは違うのでしょう。多くの女性と付き合っていながら朝顔のみが今の寂しさを満たしてくれる。「対の姫、紫」をどんな時も心を通わせられる女に育てたいと決意を新たにしました。
49日を過ぎれば左大臣邸を出なければならない源氏は、親しい女房たちを何人か呼んで語り合うが、主人を失う女房達は悲しみに泣き源氏も涙を浮かべる。会えなくなるわけではないのに、左大臣も大宮も源氏との別れに泪に暮れるのでした。
〇北の方が特別に目をかけていた女童がいた。そんなことは知らなかった源氏は、その子に心細い思いをしているだろうと声をかけ、「私を頼りにしていいのだ」と同情する。その優しさに女童は泣き出す。
語り手は、北の方(葵)、源氏、女房・女童などを登場させ、冷静に描写して各々の人物像に具体性を感じさせている。
当時の宮廷社会においては、「通い婚」であったことをリアルに物語っている。物語の展開はまだまだ継続されそうだ。
〇葵上の四十九日法要後、光は、自分たち夫婦の身の回りの世話をしてくれた女房達を集め、やさしくねぎらい別れを惜しみます。
その後、光の義父母に当たる左大臣夫妻に、自分は邸を去ることを告げるのですが、十年の長きに亘る恩を考えると、はっきりとは言い出せず、院へ参上するためという名目で、出立を告げます。
左大臣夫妻は、覚悟はしていたものの、一人娘を失った悲しみの上、更に娘婿も出て行くという、寂しさに号泣されるところまでを今月は学習しました。
親として、子に先立たれる「逆を見る」悲しさはどんなにつらいことでしょう。これからは、老夫婦と娘の残した乳飲み子だけが家族という心細さと不安でいっぱいだったと思います。降り止まない時雨がその想いを一層際立たせています。
〇燈を うちながめたまへる まみの うち濡れたまへるほど めでたき人こそ、 見まさりは 難けれと 思います。源君だってしかり。
〇源氏が左大臣邸を去るにあたり、源氏自身、大殿、大宮、そして女房逹の涙々の愁嘆場です。「をり知り顔なる時雨うちそそきて、木の葉さそふ風、あわたたしう吹きはらひ」と、門外漢ではありますが、まるで歌舞伎の舞台を見ているような気がしました。
一方、「御車さし出でて、御前など参り集まる」、「侍ひの人々も、おのおの立ち出づる」さまなのに、源氏は『わずかの間の外出なのに心が乱れ挨拶も充分にできない有様だから、失礼すると丁寧な言い回しで』大宮に告げます。こういうのは、慎ましく相手を慮って奥床しいと言うべきなのでしょう。現代の京都人にもこうした作法が見事に脈々と受け継がれている事に思い至り、直截を旨とする大阪人として深く感じ入った次第です。
2017年12月14日「葵」感想17
「貴公子ふたり」「朝顔の宮と」を了えました。
〇源氏は左大臣邸に籠り続け、寂しさと満たされない時を過ごしている。そうした中、冷たくうちとけてくれない朝顔の宮を想い、文を送り魅力的な感性に想いを深くする。
反面あふれる恋心を秘める事の出来ない御息所には気が重い。
そしてしばらく逢っていない紫の上に、心の通い合う大人の女に育てようという思いを強くする。
振り向いてくれないと追い、強く求めれば疎みと、いつの時代も人の心は変わっていないとつくづく思った事である。
〇源氏二十二歳、今まで昇進を含めて順調だったが、御代替わりで後ろ盾がなくなり、思ってもいなかった妻の急死で寂しさが一層募る。左大臣邸の人々との交流だけでは心が満たされず、このやるせない気持ちをわかってくれる人として朝顔に手紙を出す。
この気持ちを受け止めてくれる人として若紫では幼過ぎるし、御息所は教養の深さが度を過ぎているときびしい見方をしている。
結局、朝顔がごく平凡な女性とみているのでしょうか?
〇所在のない時間の中で、源氏は左大臣邸以外のところで、自分の気持ちを理解してもらいたいと、朝顔の宮に薄墨の唐紙に手紙を書こうと思いつく。
源氏は朝顔の宮に対して、長い付き合いがあってこのような源氏の心を理解してくれると考えたのだろう。
源氏は朝顔の宮と、感性豊かな御息所を思い浮かべているのだ。御息所の教養の深さに、どのような女の理想を求めているのだろうか。
〇朝顔の宮と御息所、そして対の姫君について、葵の上を亡くしたのちの源氏の思いを式部は記述しています。
この物語は、あの時代に生きた女性たちを、源氏の存在をいわば鏡として、写し描いている要素が強いと思われてなりません。「源氏」と言うより「女性たち」の物語なのではないかと思うのです。
登場する女性たちは、それぞれの背景は違っても、皆、豊かな個性と魅力に満ちています。また、これらの女性像は現代と重ね合わせてみても、特に違和感がないのも面白い所です。
2017年11月23日「葵」感想 16
「貴公子ふたり」から
〇 葵の上の服喪で左大臣邸に籠る源氏を頭中将は度々訪れ浮気の話、世間話で時を過ごしている。悲しみの中での男同士2人の心の通い合う様子は熱いものが感じられ心地よい。
もの寂しい暮れ方に訪ねた折の、うすらかな鈍色に装いを変えた中将、元の喪服の濃い鈍色の下に紅色のつややかな色を重ね、憂いに沈み、霜枯れの庭に見入る源氏、ため息が出る
程美しい情景である。そしてその様子に妹の葵と源氏の強く深い情愛を知る事になった頭中将。 男と女の間の事、夫婦の間の事は他人にはわからない事であろう。
〇 前回で「御息所がもし自分のことに見切りをつけて伊勢に下って行ったとしたならば・・どんなにか寂しい思いをするだろうか」という所が気になって、ちょっと先読みしました。「でしょうね」でした。亡き妻のこともそうですが、源氏自ら距離をおいていたのにと思ってしまいます。源氏は49日を迎えるまで左大臣邸に籠るつもりでいるが、三位の中将がいつも部屋を訪れてさまざまな話をして慰めてくれる。でも中将は妹の死亡によって源氏との強い繋がりが失せていく予感に意気消沈するのでした。
〇 源氏と中将の関係が面白い。亡き妻を想い悲しみにふけっている、その心を想い中将は
慰めてくれるのだ。中将は源氏の姿にほれぼれと見つめながら、そばに襟元を直しながら寄っていく。源氏がつぶやいていた唐の詩人の亡き妻を悼む詩を受けて中将は歌を詠む「雨となりしぐるる空の浮き雲を」とたとえ空の彼方を眺めるのである。当時の宮延文化の水準
の高さを知る事になる。式部の筆さばきは、男性の心の奥底まで見えていたに違いない。
〇 妻を失くし、落ち込んでいる光の元をたびたび訪れてくれる三位の中将の存在は、光に
とってどれほど慰めになったことでしょう。若い二人の公達の楽しそうな声が聞こえてくるような場面です。葵上を追慕する光の様子を覗き見た中将は、夫として、こんなにも自分の妹を愛してくれていたのかと、意外に感じもしたし、今まで以上にこの義弟をいとおしく感じたに違いありません。
〇 漢詩を何気無く誦して 自分の気持ちを伝えるのは いいですね。
2017年10月12日「葵」感想 15
「御息所の文」の途中から終わりまで
〇 御息所の生霊の事は源氏の心に深く影を落としたが、そのままにしておく事も出来ず
に返した手紙は全てを察している事が解る内容、御息所の苦しみはいかがばかりか、恋の苦しみに重ね眠れぬ夜かと思うと胸が痛い。源氏の求めに恋に落ち、浮名や生霊の噂まで流した御息所ではあったが、教養も高く洗練された感性で殿上人を惹きつけているのが御息所の本来で、源氏もその素晴らしい人と別れるのは戸惑いもある。
魅力的な女として輝く御息所に早く戻れますように!!
〇 御息所より文が届いていたが、理由をつけて長い間返信するのをためらっていた源氏だが、結局手紙を届けることにする。六条の自宅で源氏からの手紙を受け取り、胸のときめきを覚えながら開く御息所だが、手紙の中には生霊を見てしまったという内容もありました。自分を忌み嫌い遠ざけようとしている。いずれ桐壺院の耳にも届くと言う絶望的な気持ちになったのではないでしょうか? 今まで御息所はひっそり六条で暮らしていたのかと思っていたのですが、野の宮では趣向を凝らした催しを披露して人々を引きつけたと言う事で教養、とぎすまされた感性の持ち主で美しいと申し分なく、源氏の熱烈な求愛を受けていなければ違う人生を歩んでいたでしょうし、生霊など無縁であった。結局源氏一途という感じですが、いつも源氏の行動を監視して割り込んでくる頭中将は何していたのでしょうか。
〇 御息所は若々しい源氏の求愛に許されないことと拒む気持がいつか年の差など感じなくなって行った。源氏の熱が冷める一方、かえって身を焦がすようになり、浮名が世間に知られ、生霊の祟りではないかと噂が広まるようなこととなり、体調も異様な状態となるのであった。このような「心の鬼」を持つ御息所の感性を源氏の気持ちが伝わってくる。
〇 今までの学習を復習してみたら、「夕顔」の巻の始まりは、「六条わたりの御しのびありきのころ・・・」でした。光と御息所との付き合いは、夕顔よりもっと前からだったと気づきました。 光は、付き合いが深まるにつれ、教養、才能、品位、趣味等どこを取っても他の女性より一段上の御息所が、だんだんと重く感じられるようになっていったのではないでしょうか。
一途に思いつめる性格の御息所にしてみれば、男が自分から離れていくことは、屈辱的な事だったかもしれません。
それにしても、「私への執着心を消したらどうか。」という手紙を御息所に出すのは、自分が蒔いた種でしょと言いたくなります。
〇 野宮に趣を添はすべく、風流殿上人がせっせと動き回るのは、御息所の女房の気を
引くためなのでしょう。「ゆゑ」「よし」の誉れ高い御息所に仕える女房の質の高さ
が伺えます
2017年9月14日「葵」感想14
「追慕の日々」から「御息所の文」に入りました。
〇子供を亡くした親の悲しみは古今東西変わらない。母大宮の、時だけが過ぎているという日々は、葵の上が一人娘であり女性としても素晴らしいものを持っていた故、一層痛ましい。源氏もまた左大臣邸で、外歩きもなく、出家迄も思う悲しみの日々を過ごしている。
そうした中に、途絶していた御息所からの文。生霊の事はかくしておいても尚、源氏への想いを断てず文をする心情が哀切である。生霊の事もあり断絶を思いながらも捨てきれず、御息所を思いやる源氏の優しさはとても好きである。
この場面の文章は絵が見える様である。
“深き秋のあはれまさりゆく風の音、身にしみけるかなと・・(中略)・・朝ぼらけの霧りわたれるに、菊のけしきばめる枝に、濃き青鈍の紙・・・”
古語の深い美しさ、原文で読む魅力、楽しさがいっぱいである!!
〇葵の上の死は多くの人を悲しませたが、特に父親である左大臣は弔問を受けた時悲しみのあまり立ち上がれなかった。それ以上に母親の大宮はショックで起き上がれない。左大臣から見ても命に障ると心配し、方々に頼んで祈祷をさせるほど絶望の悲しみが伝わる。
源氏も左大臣家に籠ったまま二条の院に行かない。行って紫の上に会いたい気持ちを抑えているのかな?と思います。悲しみの中で御息所以外の女性には手紙を届ける。
そんな時、御息所より手紙が来る。手紙には前書きが記され「人の世をあはれときくも露けきに おくるる袖を思ひこそやれ」という弔問の歌が添えられていた。
〇源氏は左大臣邸で喪に服していると、深い秋の移ろいをしみじみと感じる。眠れぬ夜を過ごしていると、源氏に奥床しい一通の手紙が届く。北の方のはかない死を思い、源氏の気持ちを思いやる御息所の心遣いが手紙を通して伝わってくる。手紙のすばらしさを源氏はわかっているのだが、北の方についていた生霊への嫌悪感が蘇る。御息所は生霊について隠し通して源氏と向かい合いたいと思う。
このすれ違いの心境を巧みに描写している。男女のすれ違いの心境についての式部の表現は他の追随を許さない。
〇喪に服す光の君は、秋の深まりを「風の音」でお気づきになられたとか。何と言う繊細さでしょう。
「風がひんやり」してきたとか、「日が短くなった」とかでなく、「風の音」という言葉に式部の五感の鋭さを感じます。
万葉集には、牡鹿(さおしか)が鳴く声に秋を感じるという歌がいくつかありますが、京の都には、鹿の声はないのだと気づきました。
眠れぬままに迎えた朝ぼらけの霧に包まれた景色を、源氏も御息所も別の場所にいながら、同じように美しいと感じる所は、同じ感性を持ち合わせた二人なのだと思いました。
〇「袖の上の玉の砕けたり」の引き歌は不詳のようですが、興味があります。
「私の涙も枯れ果てた」より「私の涙は砕け散った」の方が悲しみに迫力を感じます。
〇葵の上の急逝は多くの人に衝撃を与えました。源氏、左大臣、そして大宮。さらに御息所と源氏の交情にも深い翳を落とします。
それにしても「御息所の文」の出だしの文章「深き秋の・・・」の美しさ見事さに、何と表現したらいいのか分からないほどの感銘を受けました。
2017年8月10日「葵」感想13
「追慕の日々」に入りました。
〇左大臣家の、葵の甦りの祈りや希いは叶うはずもなく、鳥部野での野辺送りとなる。
子供に先立たれる悲しみは解るし、左大臣の慟哭は目にみえるようであるが、多勢の会葬者の前で立ち上がる事も出来ず、這って動く様子は少し情け無い。
源氏は、夫婦としての希んでいた情愛が交わされ、これからを楽しみにした矢先の急逝、悲しみの深さが思われる。
葵との事が偲ばれ、つきぬ恋しさ、深い悲しさにうちのめされている源氏、存在が無くなるという事は受け入れる迄呆然とするのみ、それが死であると思う。
救いは美しい若君、希望がみえる。
〇北の方の死で司召の除目も途中で打ち切りになってしまう。左大臣の悲しみは相当なもので、立ちあがることが出来ない。うずくまって慟哭するしかない。左大臣の姿を多くの人々は痛ましい思いで見守る。
源氏も近い人の死に目に遭ったのは夕顔の時ぐらいで、殆どない。妻恋しさで胸が張り裂けそうになる。左大臣の悲しみは、わが身につまされる。野辺送りより左大臣邸に戻って来た源氏だが、妻のことを思って一睡も出来ない。結婚してから今日まで共に過ごした妻の姿が次々と浮かぶ。源氏は子を見るたびに妻を思い出し、形見の存在を改めてありがたく思うのでした。
亡き妻を悼み悲しみにくれる源氏だが、妻以外の女性を忘れたわけではありません。
〇左大臣や源氏の悲しみは続くのであるが、葵の上に対する思慕はかけがえがないのである。鳥部野の野辺送りには、寺々から集まった念仏僧たちで溢れ、慕いこがれる様子を語り部が伝えている。
人々の去った後には荼毘に付され遺骨が形見として残される。八月の有明の月が美しく、澄み切った空に煙と共に上がっていくのを見て、源氏は妻を偲ぶ。
古今集の歌をふまえて、「なべて雲居のあはれなるかな」と結び、余韻を残す。
〇京都には、千年以上続く葬送地があるという事実に驚かされます。
東京でいえば、江戸時代からの三、四百年ですが、寺院が管理する墓地、東京都が管理する墓地など整理されていて、鳥部野や化野のように込み合っているお墓は存在しないように思います。江戸時代の刑場跡も、東京では、ビルが建ったりして様子が一変しているのに、京都はさすがに千年の都だと思いました。
夕顔の急死に直面した頃の源氏は17歳。全て惟光が頼りで、源氏は、泣く、落馬する、病気になるというように取り乱していましたが、今回は、自分を深く反省し、読経に明け暮れ、妻を偲ぶよすがとしての幼子を愛しく思うなど、5年の歳月がだいぶ源氏を変えたことが分かります。
〇「忍ぶ草を摘む」という表現に 大和言葉の美しさ 優しさを 改めて 知りました。
〇次の二点が印象に残りました。
・野辺送りに「院」「后」「東宮」の御使いが参ったとあります。しかし「右大臣」の使いについては記されていない事。(先生のご指摘で気づきました)
・語り手が「念誦したまへるさま、いとどなまめかしさまさりて…」「法界三昧普賢大士とうちのたまへる、行ひ馴れたる法師よりはけなり」と述べている源氏の様子。
2017年7月13日「葵」感想12
「夫婦の絆」「急死」を了えました。
〇病床にあってもなお目を瞠る美しさの北の方、「はらはらとかかれる枕のほど、ありがたきまで見ゆれば・・・」髪の美しさのこの描写、絵画のように目にうかぶ。
希っていた夫婦の通い合う時を過ごしたのも束の間、北の方は急死。源氏の受けた悲嘆の大きさははかり知れない。
御息所の生霊をみてしまった事と相まって、心を閉ざしてしまった源氏。どんな立ち直りをするのか・・・?
〇源氏は病に臥せっている北の方を懸命に看病する。これまで北の方に対して不満の気持があったが、今はあとかたもなく消えてしまったような気がする。
夫婦の絆と言う意味では若宮を出産したこともあるでしょうし、病に臥せって苦しんでいながら御髪の乱れもない。北の方の命も長くないと言う予感がしていたのかもしれないといろいろ考えてしまう。
司召の除目の日、源氏を見送る北の方も、源氏に愛され必要とされていると言う喜びを感じながら送り出す。源氏と左大臣とその子息たち、左大臣家の男たちが内裏へと向かったあと、北の方に異変がおこる。北の方がいきなり胸をつまらせて、苦しみもがいてあっと言う間に息が絶える。
北の方の急死に宮中大騒ぎとなる。生き返るかもしれないと一縷の望みもかなわない。数日たつと美しい北の方も死相を帯びて、左大臣も娘の遺体を火葬する決断をする。悲嘆にくれている左大臣も、桐壺院からの思いを込めた弔問にうれし涙を流す。左大臣は悲しみの涙とうれし涙と泣いてばかりいる。
頭中将の名前が出てこない。何をしているのでしょうか?
〇北の方が急死したという知らせは、司召(人事異動)という大切な行事で男性が出ていくのだが、源氏を始め宮中から男性は急遽戻ってきた。あわてて戻ることは、大切な行事は投げ出しているのである。北の方の急死は政り事よりも大事な出来事であった。
その表現は人事異動を心待ちしていた人にとっては、事破れたようだと語り部(式部)は表現している。式部の洞察力に感服。
〇10年間にもわたる夫婦のわだかまりがとけて、読者にも、ひと安心させた直後、どん底に突き落とすストーリーに式部の小説家としての実力のすごさを感じました。
病状が回復傾向にありながら、急逝すると言うことは、今でもあるでしょうから、御息所の生霊のせいとは言い切れないようにも思います。
司召除目に出かけると言うことは、「公人」としての仕事中なのに、悲報を聞いてあわてて全員が帰宅するということは、勝手に「私人」に戻ってしまうのですから、そのゆるさにおかしみも感じました。
葵上は桐壺院の姪に当たる方だから、現代でも、皇室から弔問や御供花はあると思うので、左大臣がそれほど感激することでもないように、思いました。
〇源君と 葵の上が お互いを しっかり見つめ 心を通わす事ができたのは 若君の誕生があっての事と思います。
幼くして 母を失った 源君の悲痛が 私の胸にも こたえます。
〇長い間のわだかまりが消えてようやく心の通い合いができた途端に、別離が訪れることはよくある事です。これを式部は劇的に描いています。
源氏の「年ごろ何ごとを飽かぬことありて思ひつらむと、あやしきまでうちまもられたまふ」、葵の「常よりは目をとどめて、見いだして臥したまへり」が哀しい。
ひょっとして葵は死を予感していたのではないでしょうか。
2017年6月8「葵」感想11
「芥子の香」から「夫婦の絆」へ進みました。
〇御息所にとり、北の方無事出産の報は予期に反するものであった。幸せを希いながらも不幸せも希うという事有る、と納得できるものがある。そういう自分を疎ましいと思い、髪や御衣の消えない芥子の香りに生霊の動かぬ証しをも見て、悲しみや苦しみは深くなるばかり。立ち直る術は何?
北の方の容態が悪く、外出できず、源氏似の美しい若君に父親としての愛情を注ぐうち、その面差しに東宮を思い、会いたい思いが募るのは藤壺への想いも重なるのではと思ってしまう。
久し振りの外出に先だち、北の方を労い世話をやく源氏に優しい夫の姿をかい間見る。
〇御息所は北の方の命がすぐにでも尽きると思っていたが、頑張って安産の上、美しい子供まで生んでしまい「しぶとい女」と言う思いが一瞬でも頭を過ぎたのでしょうか。「ハッ」と、自分の気持ちを《あやしく》ということばと共に見つめようとする。
この時は、生霊はどうだったのでしょうか? 御息所は自分の身体から抜け出した魂が、生霊となって北の方に取り憑いたに違いないと思っているのですか?
源氏も、耳目に焼き付いて離れない御息所の「声」と「けはひ」に戸惑ってしまう。北の方の体調も一向にすぐれない。源氏は左大臣邸に足止めされる。源氏の関心は生まれたばかりの若君に向く。源氏に似て怖しいほど美しい。東宮とそっくりなのでしょうか?
〇源氏は妻の出産でひとまず心が落ちつく。北の方が産後の肥立ちがよくないので、御息所に顔をあわせるよりも、手紙で自分の心を届ける。若君に逢いたい気持ちもあり複雑な心境である。
さらに、娘の親である左大臣は娘の気持ちも理解しながらも、男の子の出産という事態に発展したのは、源氏に婿入りしてもらったことは間違っていなかったと感じているのである。語り手は、そんな左大臣の父親としての気持ちとして、産後の肥立ちを心配しながらも喜びの心境も語っている。
〇左大臣のニコニコ顔が目に浮かびました。幸せは はかないのでしょうか。
〇北の方が、東宮にいみじう似た、という事は源氏にもそっくりな美しい若君を産みます。御息所の(?)生霊も絡んだ産前の苦難、そして産後の肥立ちの悪さ。これを契機として、物語が次の段階に大きく展開して行く事を暗示しているように感じました。
2017年5月11日「葵」感想10
「二重写し」を了えました。
〇もののけに苦しむ北の方を励ます源氏は、否定し続けていた御息所の生霊を目の当たりにしてしまい、衝撃を受ける。
やがて生霊が調伏され、北の方は無事男子を出産。男子という事で祝宴、儀式の盛り上がり、祝の品々の豪華さは目を瞠るばかりのようだ。
人の心や行動は千年を経た今でも変わらず同じだと感じていたが、もののけにとりつかれるという現象、生霊とか死霊とか、なかなか理解しがたいところである。
厄災を除くのは加持祈祷によっていた訳で、こればかりは現代の科学の進歩が凄いと思うこと大である。
〇源氏は、泣き続けあの世に旅立とうとする北の方に慰めの言葉をかけ続けるが、いつもの冷静な北の方とは違う口調、情感に違和感を覚える。気がつくと北の方とは全く別人に変わっていて、源氏は奇怪な現象を目のあたりにし背筋が凍る。あの人は誰か? 生霊は御息所であった。
御息所も辱めを受けたとは言え、北の方を取り殺すほど恨んでいたとは思えないし、御息所本人も何んで?と思っているのではないでしょうか?
名告をあげたことで生霊はやっと調伏され北の方の声が静まる。無事に男子を出産して、もう大丈夫と尊い僧たちは満足げに引きあげる。
赤子が男子だったことで祝賀行事が盛大に行われた。北の方の危険な状態は脱し、もう大丈夫だろうと左大臣家は安心する。
〇左大臣家の男子誕生の風景である。
北の方の出産後の様子を心配していた左大臣や大宮も、もう大丈夫と安心する。御修法の祈祷も手を抜くことなく行われた。最新の祈祷なども行い、警戒を怠らなかった。
そのような変化を、語り手は指摘することを忘れないのである。
左大臣家の祝宴は、三・五・七・九夜にわたって延々と催され、親族や関係者からの贈り物は屋敷内にかざられ、喚声と興奮した驚きがどよめく。
〇出産に伴って行われた祈祷で、たくさんの物の怪が現れましたが、葵上を苦しめた生霊のすごさは群を抜いています。御息所の“挑み心”がどんなに激しいものであったかが伺われます。
調伏で少し落ち着いた葵上に、「隙おはするにや。」と言って薬湯を差し出す大宮に、母の優しさがにじみ出ています。
〇源君は 契った人を背負って 何回三つ瀬川を渡る定めなのかしらと つい 考えてしまいました。
〇さかのぼってP.60に、「《もののけ》は人に取り憑いて病気にしたり死なせたりする死霊などの総称、《生霊(いきすだま)》は現在、生きている人の体から抜け出し、人に取り憑いて災いをする魂(もの)をいう」とあります。
なにがしの院に現れ、夕顔を死に至らしめた物の怪もそうですが、いったい何なのかよく分かりません。多分、怨念が込められた魂(精神)の作用なのでしょうが、この物語の進行上の重要な要素になっているので、これからも注目していきたいと思います。
2017年4月13日「葵」感想9
「妻のまなざし」を了えました。
〇御息所は、源氏の心が自分から離れているのも充分知り、自分の立場も充分理解していながら、なお源氏への想いを断つ事が出来ず、“ただあやしくほけほけしうて、つくづくと臥しなやみたまふ”。人を好きになり恋うる気持ちは、どうする事も出来ないと御息所は教えてくれる。
もののけに苦しみながら産気づいた北の方。御几帳の中は調度、装束全て白。白絹の微妙に輝く白と、豊かな黒髪の美しさが目に浮かぶ。
そこで、いつものきつい北の方ではなく、やさしく涙まで見せる様子に、望んでいた姿を見た源氏のよろこび、愛しさの深さが思われる。
〇長い間、ぎくしゃくした関係が続いていた源氏と北の方でしたが、北の方のもののけに苦しむ姿に、改めて北の方の大事さを確認する源氏でした。
一方、御息所も病気になり見舞いに行く源氏でしたが、御息所は、源氏の頭の中は北の方のことで心ここにあらずと見えてしまい、みじめになる。
左大臣家では、まだ先と思っていた北の方が産気づき、周りの人々は慌てふためき祈祷を強めるが、しつこいもののけに験者達も困り果てる。
北の方が苦しみ悶える姿に、改めて魅力的な北の方を案じて泣く源氏でした。
〇一人娘が斎宮に選ばれ、親としての務めで多忙な筈なのに、自身の恋に苦しみ、“心ここにあらず”の御息所。
一方、源氏は、御息所の見舞いには訪れるが、葵上の容体が思わしくないので、こちらも“心ここにあらず”状態。
お互いのすれ違った気持に、御息所の苦しみは増すばかりだったと思います。
教養、知性、身分、美貌と、どれをとっても申し分のない御息所としては、自分の気持ちを押し殺すことにどれほど腐心したことでしょう。
〇斎宮の潔斎内裏入りを 大幅に遅らせた 様々の障り事とは 何なのでしょうか。 ここにも 身近に頼れる人のいない 御息所の孤独を 想いました。
〇結婚や家族などの社会制度が変化しても、人の心は千年前も今も変わっていないわけだから、当時数多の女性が御息所のように、やり場のない嫉妬心に苦しんだことでしょう。式部の筆致には、そうしたことも織り込まれているのだと思われます。
2017年3月9日「葵」感想8
「うちかなぐる魂」を了えました。
〇北の方の病状が良くならないのは御息所の生霊かもしれないとの噂が広まって、御息所の耳にも入って来る。最初はそんなバカなと否定していたが、段々もしかすると言う思いになって来る。我が身を振り返っても車争い事件だけでなく、主人の死、源氏との関係など、どれだけ悩み苦しんできたかわからない。数々の不運の中で夢に出て来るほどの怨みの対象が車争いかと思います。
怨みなど思っていないと心で否定しても、夢で何度か姫君をいたぶる自分の姿に夢覚めて慄然とする。源氏をいたぶる夢は、一度も見なかったのでしょうか?
〇北の方につく女房たちは、源氏への恨みが絡んでいるとみて、うなずきあいながら寝所に源氏を入れる。祈祷の僧たちは、もののけ退散と法華経を読む。当時は遣唐使などにより最新の精神医学とされ、律令貴族社会に導入されていた。
物語は素早く展開していき、式部の深き教養に脱帽。
〇たまにしか来ず、つれない男と知りつつも、あきらめきれない御息所に腹立たしさを感じます。そのくせ、世間はこう思うだろうかと、気にしているのですから。
「去る者は追わず!」
死霊は、あの人が憎いという思いが高じて、死者の魂が現れるのに、生霊は、生きている自分が一途に思いつめたときに、魂が勝手に体を離れて行ってしまうというコントロールがきかない厄介なものだとのこと。いつ、誰が言い出したのか分かりませんが、面白いことを考えついたものです。
現代でも、除霊と称して祈祷をしたり、高額なお守りを買って拝んだりしているのですから、霊界関係の事がらは、千年たってもほとんど変わりがないようです。
〇私が 御息所なら 源君に 生霊で とり憑いてしまいそうです。
〇果てしない懊悩にのたうちまわっている御息所の姿に心から同情します。
2017年2月9日「葵」感想7
「大殿のもののけ」「こひぢの田子」を了えました。
〇北の方の様子を心配する桐壺院からも度々の見舞いが届いたのは、源氏にとっての左大臣家の後見の重大さ、北の方の存在の意義の大きさが解る出来事である。
皆に大事にされている北の方の様子を、知れば知る程孤独感が深くなっていく御息所。車争いで受けた傷は、自分でも思ってもいなかった北の方への“御いどみ心”となって御息所は苦しむ。
それを知った源氏は見舞いに訪れるが、無沙汰の言い訳を左大臣家の大げさな騒ぎのせいにしてみたり、男の身勝手な責任転嫁をする。それでも御息所の余りの変り様に労わりの気持ちも持つのだが、御息所の一途で切実な、あふれる恋心を込めた歌を受け流す残酷な仕打ち。
御息所の心は尚一層傷つき壊れていく。
〇御息所は、源氏に対する強い思いと、時折見せる源氏の不誠実な言動に心が揺らぐ。もっと誠実を見せてほしいと言う叫びが聞こえる。
御息所がすごい流麗な筆跡の持主とわかりました。源氏は筆跡に感心するが、送り返した歌で御息所の心を傷つけてしまう。
〇源氏は御息所を痛々しく思い、車争いの以後深い傷を負ってしまったことで労わる気持ちが描写されている。左大臣家という高級貴族の家でありながら、内面は救いがたいものがある。
源氏の気持ちと、相手の気持ちが打ち解けられないまゝ一夜を明かす。
御息所の心は深い教養にあふれ、知的なセンスが窺うことができる。「山の井」に例えて、自分より逢い初めたことが悔やまれ、涙に暮れる。この思慕感情を誰に分かってもらおうかとつくづく思うのである。意識の世界から無意識の世界に転回することの描写の恐ろしさを感じた。
また場面の展開がある。
〇御息所の「袖濡るる」の歌で 気位の高い彼女が 「おりたつ田子」にまで 身を落として 源君への想いを 吐露したのは 病的なもの思いの 乱れ故かもしれません。
しかし 源君の返歌「身もそほつまで 深き こひじ」は 実に 実の無い男ではないかと 少々不快です。
〇源氏がお見舞いに行った頃の御息所の佇まいは、長恨歌の一節「梨花一枝春雨を帯びたり。」という風情だったように感じました。
体調がすぐれず、気が弱くなっているから、源氏への想いも余計に募るのではないでしょうか。
御息所とは長い付き合いですから、源氏は葵上が、いかに冷たい女かということを寝物語に何度か口にしたことがあるに違いありません。
その冷たい筈の女が身ごもったと聞いたときは、どんなにかショックだったことでしょう。
〇身分も気位も高く知性あふれる女性が悩み抜き、すべてをさらけ出して恋を訴えているのに、何とも実のない対応をする男。式部の筆に脱帽です。
2017年1月12日「葵」感想6
「海士のうけ」から「大殿のもののけ」に進みました。
〇御禊の日の車争いでの屈辱的出来事。源氏の心が離れている事を重々知りながら思い切る事の出来ない女心。教養も高い御息所であろうにと、少しもどかしい思いがする。
思い余って問いかけた源氏の答えは「あなたが私を捨てたり見限ったりしないで欲しい」というもの。何という事。式部は源氏に男の嫌な面を投影させている様である。
これでは御息所の懊悩は深まるばかりであるし、経済的後ろ盾、精神的より処がなくなる事は怖い事だし、あゝ、御息所可哀相。
一方、北の方はもののけ、生霊の為に病に苦しむ。今では理解するのは難しいが、災い、病い、死がもののけ、生霊によるものだというのは実に面白く、興味深い。
北の方の病い、御息所の苦しみ、どんな展開をして行くのか?
〇六条御息所は車争いの後、邸に籠りがちになる。物思いがひどくなり精神的に安定しない。今は、左大臣家から受けた酷い仕打ちよりも、源氏にした伊勢下向の話の返事として、うわべだけの遺留の言葉に許しがたい強い虚しさに苦しみ、憎しみもあったのではないでしょうか?
娘について伊勢に行こうかと考えるが、源氏への断ち切りがたい思いと、源氏に捨てられて立場がないから伊勢に下るのだろうと笑いものにされるのもいやだ。いずれにしても世間の目に曝されてつらい思いをする。
御息所が苦しんでいれば、一方の北の方はもののけが取り憑いたように尋常ではない苦しみに襲われてしまう。源氏は北の方に付きっ切りで見守り、左大臣家の中の自分の部屋に数々の加持祈祷を行わせる。今までにない執念深い霊に僧たちももてあますばかり、一向に良くならない。
北の方の回復を祈るように見守っていた左大臣家の女房たちは、御息所か二条の君など誰かが、北の方に怨みを持っているものが絡んでいるのではないかと考える。いつも毅然としている北の方が悶え苦しむ様子に、左大臣家の人々は悲しみと不安に駆られる。
〇本年の干支は“酉”で、聞くところによると“酉”の字は、東アジアに位置する日本は象形文字の漢字文化圏に属しているからか、西方浄土に鳥が一列に並んで飛んでいる形になっているという。
きよら会の初読が先生のお世話で、鎌倉(大船観音)で開かれた。冒頭、年長会員の方の訃報が報ぜられ一同驚愕。そのお人柄を慕い、ご冥福を祈りつつ葵の巻が進行された。
六条御息所は光源氏の恋愛遍歴が気にかかり、伊勢神宮の斎宮になる娘と一緒に伊勢に行くか行くまいか迷いに迷い、車争いの後体調不良になる。
左大臣家では、北の方がもののけにとりつかれたのではないかと心配し、陰陽師(律令時代の官吏で、病魔を退散させたり、地鎮祭を司った医師や神主のような存在であった)に占いを頼み、加持祈祷をさせる場面は具体的で迫力があった。
現代のアニメの“もののけ姫”が分かっていたら、面白い論評ができたであろう。豊かな大和言葉に誘われた至福の時間であった。
〇自分よりかなり年下の好色男を、心底愛してしまった御息所の哀れさが、今月の学習でだんだんと分かってきました。
御息所の揺れる気持ちを分かっていながら、つれない言葉で、自分の身を守る源氏。理知的で教養のある女性でありながら、恋にのめり込む御息所の切なさが、苛立たしいです。
〇源氏とかかわりを持った女性たちの苦しみや哀しみ、深い懊悩がきめ細やかに描かれています。振り返ってみれば、すでに登場した女性たちも皆、大小・深浅はあっても悲劇性を帯びていたのではないかと、今さらながら思い出されます。そして肝心かなめの源氏の人生も、きっとそれから免れることはないのでしょう。
華やかな貴族社会にあっても、千年たっても一つも変わらない人の心と、常に底に潜んでいる悲劇性が、この物語の魅力になっているように思
2016年12月8日「葵」感想5
「千尋の御髪」と「尚侍のかざし」を了えました。
〇紫の上はあどけなさを残しながら、女としても成長している。源氏の行動や人間性に関しても、しっかり見る目が育っている様である。美しさも増していくばかり。源氏にとってどんなにか愛しい存在かと窺われる。
それでいながら賀茂の祭り見物では、典侍の他の女達は源氏の連れに気兼ねし引いているのを、出会いがなく物足りないと不満げである。困ったものである。
再登場した典侍「旧りがたくも今めくかな・・・」と相変わらずであるが、かなり侮辱的な源氏の歌にも負ける事なく詠み返す。さすがで、華さえ感じてしまう。
〇賀茂の祭りの当日、源氏は姫君を見物につれていくために、二条院に向かい姫君の部屋を訪れる。姫君の髪に手をかけると、その豊かさが感触される。美しく多すぎる髪に削ぐのが大変、後れ毛がまるでないのもおかしな感じと言いながら削ぎ終わる。
姫君逹を連れて一条大路まで行くと、物見車があたりを埋め尽くし、車を止める場所もない。その時、女車の中から扇を差し出したのがあの典侍だった。檜扇の端を折って書かれた歌の筆跡で、源氏は典侍とわかりました。源氏は腹立たしく、素っ気ない歌を返す。
他の人は中が見えず、さぞ若くて美しい人が車中にいると思ったことでしょう。次々と身を引いて行く。残ったのが典侍だけとなる。
〇祝言葉の「千尋」(ちひろ)と呼びかける。姫君の髪の多いことを、源氏の手をかける感触に嘆いてみせながら、内心は喜ばしい。
千(ち)は奈良時代に中国大陸から伝承されてきたようだ。尋(ひろ)は日本の単位で、はばを意味していた。その数の単位を使って表現する。宮中の中では「ちひろ」で通用する表現だったのであろう。
姫君が、歌のやりとりを通じて成長していることがわかる。源氏は姫君を乗せて一条大路までくると、扇をかざした女はいかなるすき者かと好奇心がそそられる。
神の許してくれる祭りだから、今日こそは逢えるかと待っているのに、源氏の車には誰か女が乗っていて逢えないと嘆く。式部の洒落た言葉使いは「逢ふ日」と「葵」のつる草と言葉合わせをしながら、見覚えのある典侍の歌の筆跡を目にする。
〇姫君の豊かな髪を切りそろえた後、「千尋」と言祝ぐ源氏の言葉が印象的でした。昔は、ひと仕事し終わった後に、まじないの意味も込めて言う言葉が、他にもたくさんあったことだろうなと思いました。
私が子供の頃は、乳歯がぽろりと抜け落ちると、母親が、「鬼の歯になあれ!」と投げていたのを思い出しました。
同じように、子供の頃を思い出させるのは、「けしうはあらじはや」の「はや」です。小学校の国語の教科書で「あづまはや。」という文語文を学習しました。
日本武尊の妃が海神の怒りを鎮めるため、海中に身を投げ、その後、妃の櫛が岸辺に打ち上げられたとき尊が言われた言葉です。
〇紫の上の切り返しの歌 「さだめなく 満ち干る潮の のどけからぬ」は 常套表現かもしれませんが よく語っていると思います。
今回の 源典侍の「くやしくも かざしけるかな」の歌、私、好きです。
〇紅葉賀でもそうでしたが、源氏の歌のやり取りは、こと典侍相手になると俄かに品のよくないものになります。あまり見たくない源氏の一面ですね。
2016年11月10日「葵」感想4
「見物の人々」から「千尋の御髪」に進みました。
〇御禊の折の“御車の所あらそい”の様子を知った源氏は御息所を不憫に思い、北の方の行動を苦々しく思うが、二人が仲良くしてくれたらとあり得ない願いをつぶやく。何と身勝手?
この時代の結婚、夫婦の形は現代では思いもよらないが、この時代に生きた人にとっては普通の事だったはずと思う。忘れられたり、身分の差による悲哀、嫉妬、後見をなくす怖さ等々、辛い事や苦しい事が沢山あるだろうに、精神をどのようにコントロールしていたのだろうか?
源氏は重い気分を晴らしに、美しく成長してきている若紫のもとへと・・・!!
〇源氏は御息所が受けた仕打ちに同情し、北の方の悪い所は他人の立場や気持ちを量ったり、思いやりが身についていないと、争いの原因が北の方にもあると分析する。
源氏は御息所が不憫で邸に訪問するが、榊の憚りにことづけて会ってなどくれない。自分を避ける御息所の気持ちもうなずける。もう少し定期的に御息所の邸に通っていたらと後悔の念があったのでしょうか?
そのような源氏の心に影を落としている重苦しい気分から逃れるように、加茂の祭見物に出かけようと思いたち、二条院の姫君の部屋を訪れる。姫のつやつやと美しく輝いている髪だが、先の方が揃っていない。揃えればもっときれいに見えるのだがと、髪をそぐのに適した陰陽道の吉日に髪を切ることをそれとなく伝える。それほど髪が大事だったということでしょうか?
〇加茂の祭りの日、源氏は左大臣家において、車の所あらそいがあったことを伝え聞いた。源氏は北の方に対しては、もう少し配慮が足りないのではないかと思い、御息所に対しては、かわいそうに想うのであった。
この時代の男女関係について、源氏の生活はあたりまえのことである。現代に生きる者から見ると理解しにくいことである。
左大臣家と源氏とは、頭の中将という兄弟のように仲よくしてきた親籍であるだけに、源氏にとっても緊張状態が続くのであるが、この物語の進行は他の者から見ると興味がそそられるのである。
〇皇室出身の大宮(葵上の母君)は、御禊の行列を見に行きたいという女房逹のために、すぐに娘(葵上)の背中を押して、見物に出かけるように手配をしてくれたりしています。そこまで心遣いのできる母親なのに、葵上には生活全般にわたって心遣いのかけらも見られないのはどうしてなのでしょう。
彼女は、人形のように笑ったことはない人のような気がします。
〇葵の上は「ものに情けおくれ」、御息所は「心ばせのいとはづかしく」などと評する源君は、この二所同様、余り幸せとはいえませんね。でも大丈夫、あの可愛い若紫ちゃんがいる!
〇原文で三段落、テキストで7ページの短い「物語」の中で、朝顔の君、葵上、御息所、若紫が目まぐるしく登場します。その中で源氏から見たそれぞれの人物像、そして源氏の感情(愛情)がきめ細やかに、かつ的確に描き出されています。
社会制度の変遷は別として、ここで描かれている人々の感情は、不思議なことに現代に生きる私たちの目から見て全く違和感がないのです。一つ一つ納得して受け止められるのです。
ここに、この物語の魅力をあらためて感じる次第です。
2016年10月13日「葵」感想3
「車争い」から「見物の人々」に進みました。
〇北の方一行に追いやられ、素姓まで明らかになってしまった御息所。痛み、みじめさ、尚慕う気持ち。そのつらさ思うに余りある。混雑の中、去ることもできず、源氏の「目もあやなる御さま」をはるか遠くから見る事になる。そして源氏への断ち切れない想いを自覚する御息所。
源氏の仕打ちにも心を決めかねる女心を思うと、源氏の魅力はどれ程のものか・・・・?
御禊の行事の特別さと、一般の人々の様子がいきいきと描かれているのが楽しい。
〇源氏の晴れ姿を一目見ようと出かけて行った御息所でしたが、左大臣家の北の方一行に網代車の榻などへし折られて、前坊としての誇りも無残に傷つけられます。
それでも一目見たいと思う御息所の源氏への強い思いが語られていますが、源氏はここまで御息所に思われていると思っていないように感じます。御息所の気持ちが初めて分かりました。
馬上の源氏の美しい姿を一目見ようと、勤行に励んでいるはずの尼さん、年老いた女たちまで見物する人々の姿が目に浮かびます。
〇光源氏見たさに集まった女房、尼、老女などに対する式部・語り部の表現がおかしかった。をこがましい光景として当時の時代を楽しげに映し出している。
皇族である光源氏は貴族社会のしきたりとして、祭礼には近衛兵や上級官吏に護衛されていた。皇室に対する特別なしきたりが昔も変わらずに励行されていたことがわかる。
式部は女性の目で面白おかしく皮肉まじりの筆描きをふるう。式部の描写の筆は止まらない。
〇「車争い」。何という乱暴狼藉でしょう。壊された車に乗っていた御息所の恐怖はいかばかりかと思いやられます。
学生運動華やかなりし頃、私が乗っていたバスが、学生と機動隊の間に挟まれてしまったことがありました。乗客は思わず「キャー」っと悲鳴をあげてしまいました。
高貴な方は、そんな時にも、じっと耐え忍んでいられたのでしょうか。
源氏が御息所のもとへ通いだしたのは、空蝉に振られた頃で、まだ夕顔も健在でした。御息所との付き合いが、こんなにも長く続いていたのかとびっくりしました。恋人としての屈辱感は、いかばかりかと心底同情してしまいます。
〇さりげなく 微笑んだり、 流し目を送ったり、 権威の前では うやうやしくしたり、
役者ではあるまいに、 今回の源君は好きではありません。
〇御息所のどうしようもない深い懊悩が描きつくされています。罪は全て源氏にありです。
2016年9月8日「葵」感想2
「御禊の日」から「車争い」に進みました。
〇前回、桐壺院が源氏に対し、六条御息所のお扱いについて叱責がありました。その時は何となく理解に苦しむ処がありました。併し、今回の車争いの場面で理解出来ました。御禊の日は一大パレードで、上つ方から下々の人々迄見物するのを楽しみにしていた行事だったのです。
御息所も源氏の晴れ姿をご覧になりたかったのでしょう。ひっそりと網代車二台でお出掛けになりました。一方、葵の上は身孕られておられましたので、その気はなかったのですが、大宮のお指図で急にお出掛けになる事になりました。先にひっそりとしていた御息所の車に、後から来た左大臣家の車が強引に割り込み、争いとなって了いました。
こともあろうに網代車の素性まで知れて、今を時めく左大臣家の者達が“「さばかりにては、さな言はせそ。大将殿をぞ豪家には思ひきこゆらむ」など言ふ”となじられ、隅に追いやられて了います。
こんな屈辱を受けて了い、御息所の心が如何ばかりかと思いやられるのもあわれな事でございます。
〇御禊の日の華やかで美しい行列の見物の中で、ひっそりと身分をかくし忍んでいる御息所の車と、左大臣家の権勢をみせつけた何台もの車を連ねた北の方の車が、場所取りで互いの供人がののしり合う大へんな事に。
衆人の中に明らかになってしまった噂の立っている御息所。源氏への思いを、ひと目見る事に安らぎを求めていたのに。
これから辛い思いを耐えなければと思うと胸が痛くなる。
〇弘徽殿太后の子、女三の宮が齋院となり、御禊の日が近付いて来ました。新帝の配慮もあり盛大に執り行われ、女三の宮の評判も良く世間も大いに盛り上がる。
左大臣家の女君も当初は見物に行く予定などしていませんでしたが、母である大宮の女房たちの気持ちと、体調も落ちついている時だからと外出をと促されて、見物に出かけることになりました。
遅れをとっての出発のため、着いてみると立錐の余地もなく、身分の低い者が使う牛車に割り込んで行きます。そこで六条御息所らしき網代車と出合い、この車が御息所とわかり争いになる。
有名な「車争い」も、左大臣家がもっと「早く決断して、早く出発していれば」とか、「北の方の体調が悪く行かなかった場合」には争いは無かった訳で、六条御息所にとって心に大きな傷を残すことになりました。
〇葵の上(北の方)は左大臣家の高貴な家柄の血筋か、おおらかさがあって人の意を解さぬようなところが面白い。祭り見物に、葵の上も急遽あわただしく車の用意をさせて出かけた。
この物語の展開は、貴族社会の行事にこだわった生活の一面を見せている。式部は貴族社会をリアルに表現するのに、「漢字」だけでなく「ひらがな」を駆使し、彼女の過去に調査してきた中国の白居易の「長恨歌」や、日本の「万葉集・古今集」など、当時としてはあらゆる情報を使って描写しつづける。
物語の表現に「ことば」と「文字」を組み合わせ、その「表現力」に感動を与えている。
〇新しく齋院になられたのは、いつも源氏を嫌っている弘徽殿太后の三の宮の姫君です。
その方は、新帝(朱雀帝)の妹に当たるのですから、権力は右大臣系列に移ったということかと思われます。
御禊の行列は、右大臣サイドで行えばいいのに、源氏にも宣旨が下ったということは、ただ単に華を添えるためだけでなく、「あなたは供奉する家来の一員よ。」という意味もあったのでしょうか。
いずれにしても庶民にとっては、大スターのお出ましですから、その大騒ぎは目に見えるようです。
今でも花火大会、お花見などの座席争奪戦が、幾日も前から行われているのですから、イベントの少ない時代では、大変なことだったでしょう。
〇源君を筆頭に 目もあやな 御禊の行列を見る為に 下(くん)だりから 妻子を引き連れて やって来るお父さんは、 たとえ 貧しい 田舎者であったとしても 若くて幸せな人だと思いました。
〇意図せぬ偶然が重なり合って思わぬ展開となり、残酷な結果に連なっていったのです。怖ろしい事です。
「車争い」のP.26関連
・身分の低い牛車に当たりをつけて、有無を言わせず力づくで立ち退かせる。権柄づくのやりかたが身についている左大臣家の供人の振る舞い。
・「若き者ども酔ひ過ぎ立ち騒ぎたるほどのことは、えしたためあへず。おとなおとなしき御前の人々は『かくな』など言へど、えとどめあへず」
・左大臣家の供人の中に、源氏の供人だった人も交じっていて、御息所に同情を寄せるが、「用意せむもわづらはしければ、知らず顔をつくる」
虎の威を借りて傍若無人に振る舞う者たち。騒動が起きても口先だけの事しかしない「大人」たち。人間としてそのまま見過ごすことに疑問を持っても、見て見ぬふりを決め込む人たち。今の世との余りにもそっくりな相似形に驚きました。
2016年8月11日「葵」感想1
先回に「御代替わり」を、今回で「院の諌め」を了えました。
〇桐壺帝は退位され、上皇となられ、藤壺と悠々自適の生活を楽しまれます。春宮は御所に残され、源氏が後見となりました。
そこに六条御息所にスポットが当たります。と言いますと、代が変わりますと斎宮が変わり、御息所の姫が選ばれました。御息所は桐壺帝の妹君で、前坊のお后だった高貴な方です。その方と源氏が関係を持っておりましたが、あまり源氏がお尽くしならないので、噂が立ち、院のお耳まで達するようになり、源氏はご注意を受ける事になりました。
葵と結婚しているのに理解に苦しむ処ですが、当時の社会通念ですから仕方ありません。又御息所はそんなお育ちのうえ、前坊を亡くされているお方なので、源氏に深い情念を寄せられたのでしょう。
責める気はありませんが、時として恐ろしい事にもなる事も否めないと思われました。
〇源氏の冷めている気持ちを知りながらも、身の処し方に決断できない御息所の女心。
そうした関係の噂に、我が身は二の舞を踏むまいと思い惑う若き朝顔の君の女心。
源氏の浮気沙汰は達観し、毅然としている葵の君の女心。
夫々切なくて愛おしい。源氏が振り向き、心をかけてくれるのを待っている、恋する女の哀しみ、よく解る。
御息所への不実を父院よりたしなめられた源氏であるが、10年振りに懐妊した葵の上にばかり足が向く。少し周りが見えない源氏、だいじょうぶかな?
〇源氏は桐壺院に呼ばれて上皇御所に出向く。院にとって大切に思っている六条御息所に対して、源氏の不実、勝手気ままな扱いに院は強い口調で叱る。源氏には、世の中の厳しさを分かってほしい。軽々しい振る舞いは慎み、御息所にはしかるべき扱いで接してほしいと親心をぶつける。
おそらくこんなに厳しく父院より怒られたのは生まれて初めてだと思いますし、すごくショックを受けたと思います。しかし、藤壺との秘密の露見が恐ろしく、父院の心を真摯に受け止める余裕もない。院の忠告の意味が分かっているのに、どうにもならないと思ってしまう。
一方、この御息所の扱いに用心している朝顔の姫君は、源氏からの手紙にも殆ど返事を出さない。でも源氏は何とかなると思っている。
葵の方が10年ぶりに懐妊する。源氏にとって予想外の出来事であり、狼狽する。
源氏物語の勉強会100回目で、葵の10年ぶりの懐妊でした。
〇桐壺帝が朱雀帝に譲位する際に、伊勢神宮の斎宮も御代替わりすることになるので、話題を語り手が替えるのである。
そこで今まで話題にしてきた「六条あたりの御息所」を詳しく説明する。六条の御息所は、亡くなった前の皇太子の妃だった人であり、前坊との間に姫君が居り、その人が伊勢の斎宮に出立する。今まで源氏の夕顔、若紫、末摘花の場面では、「六条あたり」ということで、ないがしろにできない密会の場所として紹介されてきた。六条御息所は、もはや源氏の心が自分から離れていってしまったと、下向する気持に重ね合わせるのである。
式部は語り部を通して源氏の心の変遷を語りつぐが、姫に対する思慕の気持ちは変わらいのだ。
〇・固く身を守っていた六条の御息所が、ついに源氏と一夜を過ごした場面を学習したのは、「夕顔」の巻のことでした。
夕顔が、物の怪に殺されたとき、私は物の怪イコール六条の女君だと勝手に解釈していました。あの頃源氏は17歳、「葵」の巻では22歳になっているので、御息所との仲は、とっくにおわっていると思っていたのですが、まだまだ続いていたというのが不思議な気がします。
御息所の情の深さがよく分かります。
・斎宮の制度は古代に始まり、南北朝時代に廃絶されたと聞いたことがありました。古代の中でも古代、古事記や日本書紀にしか記されていない伝説の天皇の時代から斎宮の制度はあったと聞くと、その役目は何だったのかと考えてしまいます。卑弥呼のように、卜占などを行っていたのでしょうか。
大切に育てた内親王を差し出すのですから、権力のある天皇が制度廃止を決めればいいのに、神の祟りが怖かったのでしょう。
〇御齢29、13歳の娘持ち、春宮未亡人である六条御息所が、立ってしまった源君との浮名を どんなに恥ずかしく 苦しい思いをしているかと かわいそうでなりません。
〇「花宴」から2年が経って御代も変わり、源氏は近衛の大将に昇進しています。「御代替わり」「院の諫め」で、源氏を取り巻く人たちの複雑で深刻な関係や動きがてんこ盛りで記されています。物語は急展開していくのです。
源氏は相変わらず自らの情念の世界を彷徨っています。しかし何やら不穏な雰囲気が漂うこの巻の出だしです。物語の進行に緊張感をもって浸っていきたいと思います。
2016年7月14日「花宴」感想5
「藤の宴」の最後の項を了えました。「葵」に少しだけ入りました。
〇右大臣家の藤の宴に招かれた源氏は、打ち解けた親王らしい装いで現れ、人々を驚かせます。管弦の遊びなど楽しみ、夜も更けゆく頃、酔ひなやめるさまで、席をお立ちになり、寝殿にやって参りました。
女房逹の袖口の“出し衣”が目を奪う華やかさの中、衣ずれの音もことさららしく、そらだきものもひどく煙たく、その中を源氏は“扇を取られて、からきめを見る”と言いながら、あたりを見廻します。
そして“あづさ弓いるさの山にまどふかな ほの見し月のかげや見ゆると 何ゆゑか”と当て推量に言いますと、“心いるかたならませば ゆみはりの月なき空にまよはましやは”と返す女がいます。“朧月夜の君”です。源氏は几帳ごしに手をとらえて“うれしきものから”でこの巻は終わっています。
その後の事はご想像にまかせます、と言う事でしょうか、心憎い幕切れですね。
〇酔った風を装い右大臣家の寝殿に身を入れ、女房逹の香のたきしめや、衣ずれの音が度をこしていると奥ゆかしさの無さにふれているが、源氏のとった行為は棚上げて!?
しかし、ついに探していた女をつきとめた源氏、どうするか? どうなるか? 花宴は波瀾を予測させて終わり、葵へ。
2年がたち朱雀帝の時代へ移る。新帝になるという事がもたらす慣習が、夫々の身辺を大きく変えている。これからどう展開していくのか、怖さも伴い興味深い事である。
〇源氏は朧月夜に会うため知恵を絞ります。気分が悪いのに酒を強いられてとか言って御簾の中に入り、「扇を取られて、からきめを見る」と、わざとおっとりしたような声で言って長押に身を寄せる。返って来た声と答えに、この人は違うとわかる。
しばらくすると、かすかなため息をもらしている人がいる。「あづさ弓いるさの山にまどふかな ほの見し月のかげや見ゆると 何ゆゑか」と詠みかけると、女は「心いるかたならませば ゆみはりの月なき空にまよはましやは」と詠んで返して来る。その声だけで朧月夜とわかる。
源氏のうれしい気持ちに「ものから」ということばで遮り、花宴が終わりました。朧月夜の出会いが「朧月夜に似るものぞなき」と歌いながらやって来て、再びの出会いが「かすかなため息」でした。
源氏物語「きよら会」が平成20年5月8日に始まり、平成28年7月14日で8年3ヶ月、99回目です。来月8月11日で100回目なります。
〇催馬楽の歌を識っているからであるが、それを発展させる技術を身につけている式部に驚く。
「帯を取られて、からき悔する」。帯を扇にかえるのもセンスの良さといえるであろう。源氏のもとめていた紛れもない女性と逢うことができることを暗示している。
式部は物語を終わらせないで、次の場面に余韻を残すのである。
藤壺と源氏の想いが、催馬楽の歌や和歌を通して吐露されている。
〇人が生きているという事は、行動する事であり、その意味では源君は人一倍生きているのですが、行動には責任が常に伴いますので、つまり、生きることは大変疲れる事だと、改めて感じました。
〇「花宴」が終わりました。振り返ってみますと、源氏の言動から、物語の折角の趣が少々削がれたと私自身が感じたことは否めません。
でも、桐壺帝とのかかわり合い、絶えることなく深まっていく藤壺への思慕、藤壺の苦悩、若紫の成長、そして何と言っても圧巻の朧月夜との出会い、右大臣家との確執が弘徽殿女御だけでなく、もっと拡大・深刻化していくのではないのかとの不穏感等々、物語の今後の展開上、重要な伏線がいっぱい張り巡らされた巻とわかりました。
そして心憎いばかりの最後の「うれしきものから」。
「葵」の巻への期待が高まるばかりです。
2016年6月9日「花宴」感想4
「しるしの扇」から「藤の宴」に入りました。「花宴」もあと僅かを残すだけで、次回からいよいよ「葵」の巻です。
〇源氏は久しぶりに左大臣家に行きますが、北の方はすぐには姿を見せません。催馬楽で“やはらかに寝る夜はなくて”と筝の琴をまさぐっておりますと、大臣が出て来て、盛大だった花の宴の源氏の働きを誉めちぎります。源氏も頭中将の“柳花苑”の出来映えを“後代の例ともなりぬべく見たまへし”と返します。
一方、右大臣家では自慢の藤の宴をなさいました。源氏は右大臣家にとって歓迎される客人ではないのですが、又こうした会になくてはならない方でもありました。大臣は“くちをしう、ものの栄なしとおぼして”、“我が宿の花しなべての色ならば何かはさらに君を待たまし”と誘いの使いを出されます。
丁度源氏の傍らで、帝は“したり顔なりや”とお笑いになりつつも、“わざとあめるを、早うものせよかし”と促されます。
これ等源氏をめぐる三人の大人達の様子が、興味深く書かれています。そして源氏は“桜の唐の綺の御直衣、葡萄染の下襲、裾いと長く引きて”現れたのです。
“役者やのう”ですね。
〇左大臣邸に戻った源氏を、相変わらず北の方は出迎えない。北の方との心の通い合いを求める源氏が少し可哀相。
迎えた左大臣は花の宴の素晴らしさをたたえるが、源氏はこのプロデュースでも力を発揮、仕事でも出来る男の顔を見せた。
右大臣邸で催された藤の宴に招かれた源氏の、装い色の美しさにはため息が出てしまう。日も暮れ灯りの中での優美さは想像するに楽しいし、高欄に垂らした裾、御簾の下の女房逹の袖口、あでやかで、華やかで素晴らしい。
〇二条の院を出て、気にしていた左大臣邸に向かう源氏。相変わらず北の方はすぐには源氏に対面することはしないし、夫婦の部屋に一人ぽつりと置かれる源氏は、十三弦の琴を弾きながら、催馬楽という歌の中の一句、現実とは逆の「やはらかに寝る夜はなくて」と口ずさみ、北の方の対応にため息をつく。
歌の文句と違って北の方の親である左大臣が源氏の機嫌を伺いに来て、先日行われた花の宴がおもしろく大いに楽しみ、源氏の舞も楽曲も管弦の音も素晴らしく、寿命が延びる思いがすると絶賛するのに対して、源氏は頭中将が舞った柳花苑が後世の手本となるほど素晴らしかったと大臣方を誉めちぎる。
一方、右大臣が主催する弓の競技会が催されるが、源氏は気が進まない。右大臣は子息に「わが宿の花しなべての色ならば何かはさらに君を待たまし」という歌を持たせて源氏をさそう。源氏は宮中にいた時歌を受け取り帝の見せると、「したり顔なりや」と帝は笑う。右大臣邸に登場した源氏は正装ではなく大君姿で現れ、人々は驚嘆する。
疑問ですが、北の方(葵)はどんな楽器が得意なのでしようか? まさか、下手なのに上手に見せかけた鼻の赤い人と同程度と言うことはないと思いますが?
〇藤の宴は弥生の二十日ばかりに、右大臣家に上達部、親王たちが大勢集まって弓の競技をする行事である。その後の宴会に源氏不在では、右大臣家としては体面がたもたれない。
右大臣家は弘徽殿女御の実家であり、内親王たちも生い立ちの場所であることから、そのような場所には敷居が高く、源氏は行きたくない。そのような源氏の気持ちは帝としても理解できる。「なべてのさまには思ふまじきを」と帝はさもありなむと思うのである。
帝の父親らしい気持に源氏は従う。源氏は、女性に対する気持と、父親の愛情との板ばさみになるが、父親の優しさ、温かさに従うのである。宮中の政りごとのさまざまな行事をこなしていかなければならない。
源氏の女性に対する思慕はどうなるか、式部は語り部として物語を展開する。
〇不快な思いをさせないように気遣う義父の左大臣と源氏との会話に、お互いへのいたわりの気持ちがよく表れていると思います。
義理の兄弟たちが顔を出し、「とりどりにものの音ども調べ合はせて遊びたまふ」のも、源氏への気遣いかと思われます。
左大臣の言葉だけを取り出してみると「ここらの齢」「(明王)四代を見はべる」「翁も…」等々、どんなに年寄りかと思ってしまいますが、二十代の子供たちの父親ですから、まだ四十代と思われます。論語の「四十而不惑」ということは、自称「翁」ということなのでしょうか。
紫式部は、派手好きな右大臣家の家風を表現するのに、藤の宴と言いながら、満開の遅咲き桜、リニューアルしたての邸なども登場させ、その華々しさをより強調していると思いました。
〇帝は 源君にとって とても良いお父さんで 源君も 帝ご自慢の愛し子です。
二人の ほほえましい会話にもかかわらず 悲しみがサッと流れるのは 仕方無い事です。
〇「花宴」では、何と言っても朧月夜との出会いが最もインパクトのある出来事でしょう。今までは弘徽殿女御との確執だけが目立ちましたが、これによって、右大臣家そのものとかかわりが深くなって行く事になるのでしょう。
この物語が新しいステージに展開していきます。楽しみです。
2016年5月26日「花宴」感想3
「弘徽殿の姫君たち」から「しるしの扇」へ進みました。
〇“朧月夜に似るものぞなき”の一夜の出来事は、思いもよらぬ事に増幅して行く事となります。併し、今の源氏はそうした事態にあまり心を奪われる事はありません。
もしかしたら春宮に入内する六の君かも知れない、そうしたらお気の毒な事をしたと思いながらも、それよりも朧月夜に再会したい思いの方が強いのでした。
例の櫻の三重襲の檜扇を眺めて、“世に知らぬここちこそすれ有明の月のゆくへを空にまがへて”と書きつけて懐かしんでいます。
困ったものですね。
〇宴の後に契った姫君が誰か、思いをめぐらせる源氏。右大臣の五の君か六の君かと。六の君であれば春宮への入内が決まっている姫君である。藤壺は帝の中宮である。何か危険な匂いいっぱいである。
二条の院では若紫が美しく、心も大人に成長しているが、“男の御教へなれば、少し人馴れたることやまじらむと思ふこそ、うしろめたけれ”が興味深い。この時代の姫君の教育は、母、乳母、女房逹からで、父親、兄弟と日常的に接する事があまりないという。
心していても源氏は男である。若紫にどんな影響がでるのであろうか?
〇源氏は会った女君の名を聞くことが出来ず別れてしまい、文を届けることも出来ない。良清と惟光に宮中を出る時の様子を探らせる。久し振りに惟光の名が出て来ました。張り切って働いている姿が目に浮かびます。
物陰に待機していた幾台かの牛車が出て行った時、右大臣の子息たちが見送っていたとの報告を聞いて、源氏は胸が締め付けられるのでした。
右大臣にしてみれば、源氏と北の方の不仲を知っていて、別れて娘の婿になってくれたらと思っているようですので、春宮に入内の予定の六の君だったらと、源氏も複雑な気持ちになるのではないでしょうか?
源氏はもう何日も二条の院に帰っていませんでした。若紫がどれほど寂しがっているだろうかと思いやり、いじらしく思います。しかし昨夜の女が置いて行った扇を目の前にして女に惹かれる。左大臣邸も気になるが、二条の院に行き、久し振りに成長著しい姫君の変化に目を見張るのでした。
ああ、忙しい!!
〇小宴会は盛大に開かれた大宴会の方より、十三絃の筝の琴などもあり、気心の知れた者同士の会は充実しているなど、現代人でも想像がつくような出来事である。式部の描写力の凄さがわかる。
源氏の手の届かない藤壺を追い求めていながら、恋の行き先は「朧月夜」の女に逢いたいと考えあぐねている。平安時代の宮中の恋物語は「月のゆくへを空にまがへて」と和歌を添えるところなど、「有明の月の行方を見失った時の人情」を、寂しさとして扇に書き付けて側に置いている情景は「見事」というほかない。これだけの状況を、言葉で表現することの凄さに感動している。
〇思ひ至らぬ隈なき 良清、惟光、 いつもいつも 御苦労様です。
〇藤壺への深い思いに突き動かされたうえでのこととはいえ、「まろは、皆人にゆるされたれば、召し寄せたりとも、なんでふことかあらむ」や、「帥の宮の北の方、頭の中将のすさめぬ四の君などこそ、よしと聞きしか、なかなかそれならましかば、今すこしをかしからまし」などの源氏の言動・思惟に、少々うんざりして講義を聞いておりました。
しかし、よくよく考えてみると、「花宴」は、これからの物語の展開に大きく影響する伏線を目いっぱい張りめぐらせた、重要な「巻」なのではと思い至りました。
そして、久々に登場した惟光の健気な業務精励ぶりがほほ笑ましく、また懐かしさも覚えました。
2016年4月14日「花宴」感想2
「朧月夜の出会い」を了えました。
〇雅な花の宴もお開きになり、皆、各々帰途につきました。が、源氏の君は“酔ひごこちに、見過ぐしがたくおぼえたまひければ”で、例のそぞろ歩きが始まります。
併し、藤壺のわたりは用心深く閉ざされています。それでも、なおも危険区域である弘徽殿の細殿迄行き、“かやうにて、世の中のあやまちはするぞかし”とわかっていながら、開いている口から入ります。すると、美しい声で“朧月夜に似るものぞなき”と口ずさみながらやって来る女君がいます。
こうして朧月夜が弘徽殿の女御の妹君とも知らず、契りを結んで了うのです。すべて源氏の“まろは、皆人にゆるされたれば、召し寄せたりとも、なんでふことかあらむ。ただ忍びてこそ”のちょっと考えられない超過剰な自信というか、思い上がった気持の成せる結果でしょうか。
この事が源氏の前途に陰を投げかける事になるのも、尤もな事と思わざるをえません。
〇桜の宴が終わり、月も美しく照らしている。酔いもあり気分の良い源氏は、藤壺への深い思いに帰りがたく、偶然を頼みに歩き廻る。
すきのない戸締りに望みは断たれるが、弘徽殿の細殿に入り込む。そこへ歌いながら来た女との出会いが始まる。皆寝静まり、人の気配もなく、月の光も届かない細殿を歌いながら歩く。大胆でもあり、自己主張も強い?
闇の中で、女は香りや声で源氏と理解し、源氏もまた、若々しく美しい声に並みの身分の女ではないと思う。五感で想像する優雅で素敵な世界である。
名を聞く源氏に、感応的でもあり、若さもありながら、恋のかけひきもする。どんな女性か興味深い事である。
〇花の宴も終わり、夜も更けて、心地よい酔ひごこちに寝所に下がる気になれず、さまよい歩く。藤壺に会えるかも知れないと、殿舎の辺りを開いている戸口を探り歩くが入れない。頼みの王命婦の部屋の戸口も、閉ざされてびくともしない。
向かい側の弘徽殿の殿舎に立ち寄り、細殿の三番目の戸口が開いていて中に入れました。相当に長い時間さまよい歩いていたと思います。源氏の執念が実ったと思いますが、結局、弘徽殿と言う、源氏を嫌っている所の女性とかかわりを持つことになります。
名前も年齢も分からず、朧月夜に出会った女性と言うことで「朧月夜」となりますが、この女性幸せになれるのでしょうか?
〇源氏は、弘徽殿の細殿のあたりまで、酔いごこちの気持ちで訪ね歩き、慕う藤壺を追い求める。その景色は朧月夜で、源氏の気持ちは最高になる。
女は、男性が源氏であることを知り、慰められる気持で、「わびし」と思うものの拒む気持ちもなくなる。
そんな女を源氏は愛らしい人と心惹かれるのであるが、夜が明ける前に女房たちに気付かれないように気になるのである。
弘徽殿を舞台にして、恋のやりとりが繰り広げられ、「愛憎」というテーマが語られる。
〇今回 気に入った 一文
「かやうにて 世の中のあやまちは するぞかし」
〇春爛漫、朧月夜と聞けば、それだけで、今回登場するお姫様が、どんなに華やかな方か想像できます。
暗い夜更けとはいえ、家の中ですから、安心しきっている時に、不意に袖をつかまれたら、どんなにびっくりしたことでしょう。今風に言えば、鼻歌交じりで、隙だらけの状態だったのですから。
でも、「あな、むくつけ。こは誰そ」なんて、そんな悠長な言葉を発しているなんて、さすがに、お姫様ですね。これが下々なら、「キャー」とか「ワーッ」とかいう叫び声が、出そうと思わなくても自然と出てしまいます。
弘徽殿の女御の身内でありながら、源氏と知りつつ、身を任せるのは、ちょっと節操に欠ける気がします。
〇源氏「かうてやみなむとは、さりともおぼされじ」
女「うき身世にやがて消えなば尋ねても 草の原をば問はじとや思ふ」
源氏「わずらはしくおぼすことならずは、何かつつまむ。もし、すかいたまふか」
藤壺への想いに突き動かされているのに、「酔いごこち」であえて危険な弘徽殿の細殿に踏み込み、こうも軽々と恋の駆け引きにのめりこむ源氏。
蒔いた種は自ら刈り取るほかないのです。
2016年3月10日「花宴」感想1
「花宴」に入りました。第1回は「桜の宴」でした。
〇宮中行事では、春は桜、“花の宴”が賑々しく取り行われます。南殿に后、春宮の御局と着座の順も定まります。ここでは宰相中将、頭中将、上達部、地下、博士達の行動が興味深く描かれています。
そのそれぞれの様子をじっとご覧になられていた統治者、帝の御様子が印象深く思われました。まさに平安時代の爛熟期を思わせる場面です。
この宴で、探韻が披露されます。探韻は韻字を探り、その韻で漢詩を作る事ですが、漢学の素養、それも並々ならない高度さを要求されます。中国文化、韓国文化を取り入れ、消化し、熟成させていった賜ものです。日本人の先人に頭が下がります。
〇千年の昔から桜を愛でる心は変わらない。まして染井吉野と違い、山桜の風情は趣き深い事と思う。今も花に事寄せ浮かれるところは日本人の心模様だ。折しもこの季節、花が待ち遠しく心騒ぐ時期である。
花の宴は皆の楽しみな盛大な行事の様で、上の者から地下の人々迄の様子を楽しむ席。存在そのものが、あらゆる魅力をはなつ源氏。いろいろ気遣い、準備をし、賞賛を受ける頭の中将。源氏を目のあたりにし、心まどう藤壺。などと、集う人々の夫々の性格やら屈託が描かれ、楽しく面白い宴の様子である。
〇花の宴が始まりました。
左近の桜が見頃な2月20日すぎ、紫宸殿で盛大に催されました。一字を庭に置かれた鉢の中から取り詩を作る探韻でも、春の文字を引き当てた源氏の韻字を披露する声が、他の人とは全く違い、素晴らしいと称賛されました。
一方、頭の中将は源氏を意識して緊張しましたが、落ちついて口上を述べました。素晴らしいのですが、源氏には今一歩と言う所です。宴たけなわになり、続いて催される管弦と舞楽も、中将は源氏よりも時間をかけて舞いましたが、予め出番を想定して準備していたようで、巧みに舞う柳花苑という舞楽に、帝から身に着けていた袿をいただく。頑張っています。
2月2〇日すぎと言うことで、早いもので藤壺の子も誕生日を迎えたと思いますが、お祝いはなかったのでしょうか?
桜の宴の方は夜も更けて、人々に様々な余韻を残して事果てける。
〇宮中の行事の「桜の宴」に場面は変わる。
漢詩を詠むのは、韻をふまえなければならない約束事を、こころえていなければならないが、すべて予習してきているのだろう。緊張はするが、うまくこなすことができるのだろう。
それに「春鶯囀」という舞楽の舞が披露される。源氏の舞はさりげなく舞うが、左大臣が涙を流すほど感銘を与える。頭の中将も「柳花苑」という舞楽をしっかりと舞ってみせる。
この場面を帝が観ていて、「(まずこの君=源氏を)光にしたまへれば」と賞賛し感嘆する。
藤壺は源氏の姿を目にして、つややかな美しさに目を奪われてしまうのである。側に控えていた女房たちも、この様な有様に心を痛めて我が事のように思うのである。
夜のとばりはすべてのことを呑みこんでいった。
式部の筆さばきは、人々の心の動きをあざやかに描き出した。
〇弟の源君に 花のかざしを与え 春鶯囀を促した春宮は 穏やかな 良い人だなと 思いました。お母さんに似なくて 良かった。
〇桜の宴、あざやかな幕開けです。紅葉賀の試楽もそうでした。そもそも「いづれの御時にか…」にも痺れました。新しい巻の魅力あふれる始まりです。
2016年2月11日「紅葉賀」感想13
「なごりの帯」から「藤壺立后」に進み、「紅葉賀」を了えました。
次回から「花宴」に入ります。
〇話変わってと言うべきでしょうか。藤壺は立后なされました。(もう源氏の手の届かない処に行ってしまわれたのです。)
立后については、帝ご自身が退位なされた後、まだ幼い皇子を春宮になさりたいという深い心積もりがおありになっての事でした。后腹の皇女が皇后になって、皇子の後ろ身になれば盤石で、将来の春宮は揺るぎありません。
式部は源氏と皇子の事を、“皇子は、およすけたまふ月日に従ひて、いと見たてまつり分きがたげなるを”“月日の光の空に通ひたるやうにぞ、世人も思へる”と締め括っています。
何と数奇な運命の下に生まれたおふたりなんでしょう。
〇昨夜の騒ぎを忘れたようにふるまいながら、仕事に励む二人の様子は正しく喜劇で大いに笑える。
育ちの良さ、性格、才能と同等のものをもつ頭中将の大らかさややんちゃさが、源氏に一歩も譲らず、おどし合ったり、からかい合ったり、意地を張り合ったりと本当に楽しい二人である。
紅葉賀の終章、藤壺は立后し、源氏も宰相となるも、お互いはいよいよ遠い存在となる。二人の心の内の哀しみは、いかばかりであろうかと切ない。
源氏に生き写しの皇子について、美しい人同士は似て当然と、不義を疑うことはないという考え方、素晴らしい。穏やかで心安らぐ事である。
〇源氏と中将は、お互い帯と端袖を持ち帰り、相手をやり込めようとする。まず中将が源氏宛に端袖を包んで送る。源氏は不快な気分になるが、帯に歌を添えて送ってやる。
その日に殿上の間にそれぞれ参上したが、昨夜のことなどなかったように知らん顔している源氏、格式張っている中将のまじめな様に、二人は笑いをこらえる。この二人の意地の張り合いは面白いです。
七月に藤壺は立后する。いずれ春宮になる若宮の先行きを心配していた帝は、藤壺を中宮にすることにより、揺るぎない地位を確立させて守ろうとする。弘徽殿の反発も覚悟の上で決行する。それほど帝の藤壷への愛が強いのでしょう。宮中の人々も藤壺の美しさに立后を受け入れて行く。
やはりと言うか若宮が成長するにつけて、源氏と生き写しとなって行き、藤壺は苦しむが、疑念を持つ人など誰一人いない。
紅葉賀が終わりました。次は花宴です。
〇帝に愛されている源氏には、頭の中将も、家柄ではさほどの違いはないのにと対抗意識が出てしまう。中将の心情を察して語り手に語らせる一節である。
そのやりとりも、相変わらず「催馬楽」や「古今集」が引用され、式部の教養がにじみでている。
語り手が、二人の話題をここで閉じるのも心にくい。現代の新聞小説や週刊誌の連載小説のように、読者に「次は何か」と気をもたせるのである。
〇桐壺帝の譲位の意向の最大の目的は、自分の在位中に藤壺腹の若宮の立坊を確定させたかった事だと、ここにて私なりに理解しました。
〇「紅葉賀」を振り返ってみると、華やかな青海波の舞から始まって、北の方との確執、二上の院での愛に満ちた若紫との交情、皇子誕生による恐ろしいまでの人としての業、そして藤壺立后を経てさらに藤壺への思慕に苦しむ源氏などなど、この物語の核心をさらに深める重厚な内容であったと思いを新たにしました。
内侍・頭の中将との挿話には、どうしても違和感をぬぐえませんでしたが、締めくくりはこの物語本来の深みのあるもので、満足しました。
2016年1月14日「紅葉賀」感想12
「五十七、八の人」から「なごりの帯」へ進みました。
〇源氏は脱出を試みようとしますが、寝乱れ姿なのでためらっていますと、頭中将は太刀を抜く始末です。源氏はおかしいやら腹立たしいやらで中将の腕をつねりますと、中将も吹き出し、源氏は中将の帯をほどき、中将は源氏の直衣の片袖を引き千切るという結果になりました。
あくる朝早く、内侍から源氏の元にその戦いの残骸が届けられました。
中将 “もの隠しは懲りぬらむかし” 源氏 “立ちながら帰りけむ人こそ、いとほしけれ”“まことは、憂しや世の中よ”と言ひあはせて、手打ちとなるのです。
仲の良い好敵手ですね。
〇中将の悪戯はエスカレート。大げさなふるまいに、仕掛け人は中将であると見破った源氏も負けず、直衣のひっぱり合い。二人はしどけない姿になるという、二人の仲の良さがわかり、真剣に戯れている様子がおかしく楽しい場面である。
典侍もあわて老醜をさらすが、それでも猶、恋の切なさを歌に託し源氏に送る。さすがである。
うとましいと思いつつ、皮肉をこめた内容ではあっても返歌をする優しい源氏。もてない訳がないなあ!!
〇源氏が屏風の後ろに隠れるのを見ていた中将は、おかしさをこらえ屏風のもとに行き、音を立てて源氏を慌てさせるが、あまりの大げさに中将だと源氏はすぐに気づく。中将と内侍の関係もわかってしまう。源氏が着ようとする直衣を中将がしっかりとつかみ、直衣の縫い目がほころび、源氏が中将の帯を引っぱり脱がせる。
朝早く源氏に内侍より届けられた中の内、帯が中将のものだったが、直衣を見ると袖口の方の一幅が取れてない。
愚かしい姿をさらし、源氏も反省したと思います。
紅葉賀に入り今回で丸一年になりました。物語は十月から二月の五ヶ月と思います。じっくりと勉強しています。
〇頭の中将と源氏のやりとりが面白い。源氏物語を現代的に解釈してしまうが、こんなつき合い方がしてみたい。
「性」の問題は、この時代の方が自由であったのであろう。ただ言えることは、男と女の関係だけを考えていられる「時代」ではないことはたしかだ。
式部が残してくれたものは大きい。我々が何に引かれるのかは人さまざまであるが、私は「人間研究」の式部の姿勢から貴ぶものがある。特に男と女の性の関係は、解決できない私達の課題と云えよう。
〇今回 源君の得た教訓
「おり立ちて 乱るる人は むべをこがましことも多からむ」
源典侍には 不要な教訓ですね。
〇今風に言うなら、浮気の現場にもうひとり男が踏み込んできた修羅場であります。
けれども陰湿さはないのです。そして、そんな中でも三者三様の洒脱な歌の応酬がとびかうのですから驚きですね。いったい何と言ったらいいのでしょうか
2015年12月10日「紅葉賀」感想11
「琵琶の音」から「五十七、八の人」へと進みました。
〇傷心の源氏が温明殿のあたりを歩いていますと、典侍の巧みに弾く琵琶の音がします。つい誘われ東屋に忍び入る事になるのですが、老女房の手練手管の術中に嵌まり、大変な事態となるのです。
“人に従へば、すこしはやりかなるたはぶれ言など言ひかはして、「押し開いて来ませ」と”なります。 同じ色事の描写でも、琵琶の音を利かせ、催馬楽の絶妙な掛け合いを混えて、手がこんでいるのには驚きです。
“すこしまどろむにやと見ゆるけしきなれば、やをら入り来るに”は誰かあらう頭中将でした。
〇頭の中将との逢瀬ではみたされず、ひたすら源氏を恋うる典侍。
典侍の歳を思い、慰めたいと思いつつも遠のいている源氏であるが、気になるのか温明殿の辺りの様子を伺う。果たして典侍の巧みな琵琶に出会い、その上手さと声の美しさに聴き入る。
かなり極どいながら当意即妙のやりとりはとても楽しそうである。
そして、その浮気の場に頭の中将が仕掛けた、そっと忍び込むといういたずらに、あわてる源氏の様子が何とも愉快である。
〇前回、源典侍についてしわくちゃな老女と言うことでしたが、源氏の好奇心はこの老女にも興味を向けて近付いていきました。まじまじと典侍を見た源氏は、あまりのしわくちゃな顔に唖然として、末摘花と同じように、一度は逃げようとします。
末摘花と典侍の違いは、年齢は勿論ですが、琵琶の名手であり、年の割にはきれいで素晴らしい歌いぶり、相当な教養を身につけている人であることです。
男たちの演奏に一人交じって弾くとのことですが、何歳ぐらいから参加していたのでしょうか? 若いころは言い寄る男も多かったと思います。寄る年波にたえなくなって来たのでしょうか? それとも好色な女性か、どちらでしょうか?
頭の中将が又出て来ました。源氏と典侍が寝ている現場を押えようとしますが、何者かの気配に源氏は気づき、脱いであった直衣を手に屏風の後ろにかくれる。
〇歳上の女性に光源氏は深い契りを結んでしまった。恋のやりとりは歌問答で進行する。式部の教養のにじみでるところであるが、催馬楽の「東屋」や白楽天の「鄂州に宿す」等を和歌にすることなど見事というしかない。
これは、式部の才能が文章力となって表れるのに、「源氏物語」を読まずして短歌を語るなかれと先人が言っていた意味がわかる。
頭の中将は、典侍と源氏が一緒にいる所に踏み込み、おどかすのであるが、それが三人のさまざまなふるまいとなって、面白おかしく展開する。
〇・老女に付きまとわれるのが煩わしいと言いながら、ちょっかいを出す源氏は、性格が悪そうで好きになれません。
「紅葉賀」の中に、老女との戯れの恋の話が、なぜ急に出てくるのか違和感がありました。
この場面は源氏物語が書かれた後の時代に、書き加えられたということはないのでしょうか。異質な感じがします。
・新古今集、催馬楽などの歌が、共通の知識となっていて、すぐに口をついて出てくる上(かみ)の品の人々の教養の深さに驚かされます。
〇源内侍は 何か鈍感で トンチンカンなところもありますが 風流人である魅力は 確かに有る人だと思います。
〇源氏は「まことには乱れたまはぬ」人と思われていた。――典侍に「かうさだ過ぐるまで、などさしも乱るらむ」と好奇心をそそられる。――女の反応を「あさまし」と思いながらも、この女との恋も一興だと言い寄った。――女と逢っているなどと女房逹に知れたら、さすがの源氏も恥ずかしく、女につれない態度をとる。――典侍が「上の御梳櫛にさぶらひける」とき、「常よりもきよげに、様体、頭つきなまめきて、装束、ありさま、いとはなやかに好ましげに見ゆるを、さも旧りがたうもと、心づきなく見たまふ」――「いかが思ふらむと、さすがに過ぐしがたくて、裳の裾を引きおどろかしたま」ふ。――(中略)――「齢のほどいとほしければ、なぐさめむとおぼせど、かなはぬもの憂さに、いと久しくなりにける」――後略。
このように、源氏の心は揺れに揺れながら「琵琶の音」「五十七、八の人」に続いていく。
2015年11月12日「紅葉賀」感想10
「典侍の懸想」を了えました。
〇この場面は、らしからない展開のように思われますが、それ迄の源氏と藤壺の忍ぶ恋、その結果としての不義の子若宮の誕生、裏切りの父帝面前の御対面と息苦しいばかりの場面続きでした。作者も一息つきたくなったのではないでしょうか。
それは、帝が“御障子よりのぞかせたまひけり。似つかはしからぬあはひかなと、いとをかしうおぼされて”とありますし、それを頭中将が聞きつけて、例によって対抗意識を燃やしたりで、当時は軽い恋愛は一種の遊びでもあったと思われます。
次の幕に移る幕間のお戯れのような気がします。
〇もう一度の逢瀬をもちたい典侍は、源氏とかなり卑猥で露骨な歌のやりとりをする。その臆面のなさに脱帽である。好奇心から気を引いてみたものの、源氏もさすがに逃げ越しになる程。しかし歌の一部をいわれただけで、即妙の返歌があるという教養の高さには驚き入るばかりである。
噂になった二人の仲と、老女房源典侍の“尽きせぬ好み心”に興を持ち、行動を起こす頭の中将。この時代、何とも開放的でおおらかな男と女模様である。
家柄もいいし、才気もあり、かなりの地位にある源典侍、紫式部に老いて尚無類の男好きな女にされて、ちょっとかわいそう。女あるあるの犠牲!?
〇源氏は好奇心から、老女にちょっかいを出してしまいます。自分に気があると思った老女は、源氏に対して流し目を送ってきますが、扇をかざして色目を使う老女を源氏はまじまじと見る破目となります。
源氏は老女を見て老醜と表現しているように、皺だらけのおばあさんと想像出来ます。源氏は逃げようとしますが、老女は源氏に追いすがり、泣かれてしまいます。
二人の様子を見ていた帝が、周りの女房逹に笑いながら話してしまう。このことを聞きつけた好奇心旺盛な頭の中将が登場で、又二人の「恋物語」という様相を呈しますが、順序が逆で、頭の中将が何かの機会に老女に出会っていたら、絶対に逃げていたと誰もが思うのではないでしょうか。
〇「年増な典侍に言い寄られる」の場面。
源氏は、「自分のことを愛馬用の下草で、源氏に食べてもらいたい」と典侍に求愛されるのに、この場を逃げだしたくなる。
帝も、その光景を見て、似つかわしくないちぐはぐな組み合わせだなと、おかしさを隠さない。
典侍は釈明せずに、噂になっても構わないと思っているのだろうと、語り手はみる。
頭の中将は、何でも張り合ってきたが、思いも寄らない女性を見つけた源氏に先を越されたと思う。頭の中将も言い寄り、確執する。
このような展開は、物語の構成を面白くして、読者を引きつけるのである。
〇典侍の裳裾を踏んで、ちょっかいをかけた源氏を、扇で顔を隠しながら振り向くしぐさはさすがです。宮廷に仕える女性らしい品のよさを感じます。
皮膚のたるみも、目の周りの黒ずみも、老女なのだから仕方のないことですが、過度な色好みには辟易とします。
想いを伝える歌の中の「下草」とか「下葉」とかいう言葉に、淫靡な不潔さを感じます。年をとると、だんだんと恥じらいを忘れていくのが恐ろしいです。
〇大荒木の森の下草老いぬれば
駒もすさめず刈る人もなし (古今 雑・上 読み人知らず)
この歌は「うたて」で「すさまじ」なのですが、味が有るとでもいいましょうか、いやはや何とも。
〇深刻な物語の進行の中で、どうしてこのような挿話が紛れ込んでくるのかと、目を白黒して講義を聞いていました。頭中将が登場するに及んで、ますます違和感がつのったのであります。
2015年10月8日「紅葉賀」感想9
「二条の院の女君」から「典侍の懸想」に進みました。
〇案の定、噂は左大臣家に伝わって大騒ぎとなっていました。そして、帝のお耳に迄届いて、ご心配のご様子です。
それは、当時の結婚の成り立ちが、妻の出自を重んじていたからに外なりません。左大臣家の姫葵と結婚させて、源氏を盛り立てさせたい帝の親心からです。
帝も大臣の心を思いやられて、“げに、ものげなかりしほどを、おほなおほなかくものしたる心を、さばかりのことたどらぬほどにはあらじを、などか情なくはもてなすなる”と源氏を諫められます。
ここでは、帝の父親としての親心がよく現わされています。何時の時代でも、親心とは変わらないものです。
〇少女のもとを去りがたく、左大臣邸への訪れの間遠な源氏。謎につつまれている故に、少女の噂が大きくふくらんでいく。少女の可愛らしさと、噂の女の像のギャップが実に面白い。噂話とはこうしたもの。現代もしかりである。
帝の耳にも届き、北の方との満たされぬ関係を理解しながらも、後見役の左大臣家への不義理は、源氏の将来への不安につながると親目線が切ない。
桐壺帝の内裏に仕える女房達は“よしある宮仕へ人”が多く、その中の一人、地位も高く才色兼備の素敵な女房典侍がいる。彼女は高齢であるが“いみじうあだめいている”。好奇心の強い源氏は、女房逹の目を怖れながらも近付こうとする。
火傷をしなければ良いが。この恋の行方は?
〇左大臣邸を訪れることが以前より少なくなったことにより、少女の噂が北の方の女房逹に伝わり、帝の耳にも入ってしまい、源氏は帝よりおしかりを受ける。
帝に対して大変な秘密をもっている源氏ですが、少女の素性も秘密にしています。帝に知られたら父親にもわかってしまうでしょうし、かしこまって聞き流すしかなかったと思います。
それにしても、少女の素性が宮中の女房逹に知られたらすごいことになると思います。
典侍の懸想に入りましたが、感想は次回となります。
〇帝の源氏に対する心情は、左大臣の娘に対する気持が離れているのをわかるのであるが、父親として、源氏の心を理解しようと心がけている。
こんな父親の姿は、現代にも通じる親と子のいき違いである。それが父から離反するケースもあるであろうが、子供が離反するケースとして式部は構成している。ありがたいすてきな父親である。
このような噂にも、源氏を信じている帝は、宮中の女房逹の誰かに夢中になるような人物ではないと思っている。
場面一転、「老いたる典侍」と源氏の恋に変わる。この場面転回に読者はひきづり込まれるのである。
〇・桐壺帝は、生まれながらに高貴な方で、人を疑ったり、人に悪意を持ったりすることを全く知らない人だと思います。
臣籍に下ったプレイボーイの息子についても、疑いを抱くこともせず、懸命に庇護するところに哀れささえ感じます。
・典侍については、「やむごとなく」「心ばせあり」「あてに、おぼえ高く」とありますが、
いい年をしているのに、さかんに色目を使ってばかりいる老女は、品がない汚らしい女というような気がします。
〇若紫は、本来は女王であり、公達の北の方に納まれる身分なのに、今のところは 世間では 何か奇妙な日陰者扱いをされているようで、かわいそうです。
〇源氏へのかくも深き父帝の愛、なのに父を裏切ってしまっている源氏、何と言うべきかその言葉を知りません。この物語の怖ろしさを見る思いです。
2015年9月10日「紅葉賀」感想8
「二条の院の女君」に入りました。
〇若宮をなでしこになぞらえて
源氏 よそへつつ見るに心はなぐさまで 露けさまさるなでしこの花
藤壺 袖濡るる露のゆかりと思ふにも なほ疎まれぬやまとなでしこ
宮中での衝撃的なご対面ですっかり平常心をなくされた源氏は、二条の院に帰られうつうつとされていました。そんな折の慰めは若紫と遊ぶ事でした。
近頃は、子供だと思っていた若紫も少女から少し成長されておりました。源氏がちょっと遠くから“こちや”と言われるのに対し、“入りぬる磯の”と口をおおってのご様子は女としての仕草としか思われません。
源氏も心惹かれ、若紫に琴をひかせ、ご自分は笛で合され、楽しい時を過ごされます。そんなわけで、ついつい夜になっての外出を止められる事が度々となります。
これは又、問題の種ともなり、あらぬ噂となって了うのも仕方ない事です。
〇我が子である若宮との対面を果たし、源氏の煩悶はより深くなる。
永遠に解決するものではなく、若紫に会う事によって癒される。
少女の愛らしさや可憐さの中に、時折みえる女としてのしぐさに驚かされるが、意識しているものではなく、源氏が理想としている姿への序奏か?
若紫の魅力が伝わる言葉にあふれ、源氏の若紫への愛しさあふれる言葉にふれるところである。
〇宮中を下がってから、しばらく部屋にこもってじっと物思いに沈んでいた源氏でしたが、気力を取り戻すには少女に会うのが一番だと思い、西の対に向かう。
久しぶりに見た少女は、大人ぽい女君と呼びたくなるような姿になっていた。少女の源氏への恋心が、源氏が来ても素っ気ない素振りなどで見て取れます。
源氏は少女に筝の琴を、細かな注意事項を伝え笛をふきながら教える。少女は母親がわりの少納言やその他の女房、源氏などによってどんどん大人の女になって行きますが、まだ背伸びしているのでしょうか?
源氏の愛情を確認したあと、膝に寄りかかって寝入ってしまいます。どんな夢をみているのでしょうか?
〇源氏は藤壺に対する思慕から、部屋に籠って物思いに沈んでいた。その際に思い出したのは西の対の少女のことである。
男の部屋着の下着姿のまま源氏は笛を吹き少女を訪ねる。少女は、愛敬ある表情が大人びた感じになってきた。坂上郎女の歌を唱い、皮肉を「入りぬる磯の」と口ずさむ。それに対して源氏は「みるめに飽くはまさなきことぞよ」と歌の言葉で返す。
少女のあいらしさを強調する文章であるが、これも式部の物語の伏線のたくみさである。琴、笛の楽器の使い方も式部の教養の深さを表している。
〇源氏を これから 外出させないように言った 若紫の「寝たまひかねし」が とても 可愛いい。
〇9月19日鎌倉芸術館で行われた田中先生の講演会のあと、各教室(講読会)の交流会が初めての試みとして催されました。そこで語られたことをきっかけとして、ふと思い当たったことがあります。
それはこの物語を読むとき、主として、女性は「光源氏」を見つめ、男性は「登場する女性たち」に注目しているのではないかということです。(「大胆」かつ「偏見」に満ちた「仮説」?)
勿論この物語の要は「光源氏」であることは言うまでもないことです。しかし私に限って言えば、今までのところ「光源氏」の人間像に焦点が合わさってはいません。これから先、彼がたどる運命というか道筋、そしてその行きつくところには興味津々ですが、それよりも何よりも「登場する女性たち」の人となりや心の動き、そして成り行きに強い関心を持ち、物語を読み進んでおります。
2015年8月13日「紅葉賀」感想7
「対面」を了えました。
〇帝にとっては、待ちに待った御子とのご対面でした。そして、その御子は源氏そっくりに美しく、似ていらっしゃるので、非常に驚かれました。併し、驚きよりも、嬉しさ、喜びの方がお強くて、源氏にはしてあげられなかった将来のお望みを果たしたいお気持ち迄お持ちになりました。なにしろ“疵なき玉”なのですから。
そして、次は源氏と御子のご対面です。帝は少しのお疑いのご様子もなく、中将の君に、“いとよくこそおぼえたれ。いとちひさきほどは、皆かくのみあるわざにやあらむ”と上機嫌でございます。一方中将の君は“面の色かはるここちして、恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがたうつろふここちして”万感胸に込み上げて涙を落とされました。そのご様子を見守っていた藤壺はご心配のあまり冷や汗を流されていました。
けだし、ご無事なご対面で、めでたしと言うべきでしょうか。
〇源氏に対しての大きな愛は、母の身分故に思うにまかせなかった事もあり、残念に思っている帝は、藤壺との皇子には何はばかる事なく将来を与えられる。皇子への愛情の深さと大きさはひとしおである。
真実の父親である源氏は、帝がわが子と信じて疑わず掌中の玉のように大切にしている事に万感の思いである。
藤壺は源氏生き写しの皇子に、罪の意識、母親としての愛、そして源氏への断ち切れない愛と苦しそう。
夫々の立場での人間の複雑な心模様に思い至し、どう物語が進んでいくのか興味深い事である。
〇若宮は源氏に生き写しということですが、帝は源氏の生まれた時の顔と比較して似ていると思ったのかなと、思ってしまいます。
源氏は自分の生まれた時の顔を知らないわけですが、わが子が驚くほど自分に似ていると思っています。19才の自分とそっくりと言っていますが、発覚を恐れる思いが関係しているように思えてなりません。むしろ若宮が生長するにつれて源氏の恐怖が増して来るように思います。
なんとか藤壺より手紙をもらいたいと思っていた源氏でしたが、命婦の機転により返事が来ました。あきらめていただけに、うれし涙を流します。
〇藤壺は、生後2ヶ月の若宮を連れて帝のいる内裏に参内し、対面する。帝は、若宮があまりにも源氏に生き写しではないかと驚く。帝の戸惑い。「あさましきまで、まぎれどころなき御顔つき」であることに帝は内心驚く。帝は若宮の美しい面差しに見惚れ「源氏と若宮」は、並はずれている美しい者同士だから似通ってしまうのはあたりまえであると自ら納得する。
源氏を帝にできず春宮にできなかったのは、母「更衣」が、低い身分だという世間的な基準で判断したからであるが、帝は更衣の無念さをいたくわかる故に、心に刻んでいる。その後も源氏の「ただ人」の身分が気になり、いたわしく思う。若宮は、源氏の場合と違って身分は「疵なき玉」という「内親王」の血筋の高さは申し分がない。誰にも遠慮をすることもなく若宮に目をかけられる。
藤壺は、帝の格別な愛情がわかるほど、「事の真相」が発覚することを恐れるのである。心が休まらないのである。
〇藤壺が、帝を欺き、不義の子を出産するという、驚くべき出来事が起こりました。
女房を寝取られたのに、それに気づくこともないお人好しの帝に、おかしさと哀しさが感じられます。
この事実をひた隠しにする藤壺も大胆ですが、この小説を書いた紫式部には、もっと驚かされます。
物語とは言え、皇室が舞台の読み物に、不敬罪にあたる罪は、適用されることはなかったのでしょうか。
〇「わが身ながら、これに似たらむはいみじういたはしうおぼゆ」に源君の生命力を改めて感じました。
〇宮「いかなるにつけても、胸のひまなく、やすからずものを思ほす」
中将「面の色かはるここちして、恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがたうつろふここちして、涙おちぬべし」
宮「わりなくかたはらいたきに、汗もながれてぞおはしける」
中将「なかなかなるここちの、かき乱るやうなれば、まかでたまひぬ」
これはもう人間の「業」です。
2015年7月9日「紅葉賀」感想6
「皇子誕生」を了えました。
〇現代では出産予定日は、はっきりしています。当時でも大体の目安はあったのでしょう。それが年内であって、皆が今か今かと待っていましたが、年が明け、遅れに遅れて、二月十余日になって、男御子がお生まれなさいました。藤壺は長いお悩みの末ではありましたが、“やうやうすこしづつさはやいたまひける”とあります。
おもいは自分独りだけのものですが、恋愛となると相手がいます。懐妊となると自分の体の中にもう一つの命が宿る事で、だんだんと抜き差し行かなくなり、重くなって行きます。まして不義を犯しての事ですから、さぞお辛かった事でしょう。
藤壺はしっかりとした方で、すべての思いを断ち切り覚悟を決められて、源氏の御子への対面の願いにも“人のもの言ひもわづらはしきを、わりなきことにのたまはせおぼして”命婦をも遠ざけられる事となりました。
賢明なしめくくりと思われました。
〇数々の懊悩の中、皇子誕生である。
帝の熱い思いと喜びを知れば、藤壺は一層の罪深さを感じるであろうし、日々刻々がつらいだろうと胸の痛い思いがする。しかしながら御子の将来をみすえ、強い心を持つようになる。いつの世も不変の母親の愛である。そして、断ち切る事の出来ない愛しい源氏との子供であるという事は、その強さを助ける力になってはいないのか、下世話の思いもある。
いずれにしろ、自分の子であると確信した源氏、事実を知っている命婦、夫々がこれから大きな秘密と葛藤の中で生きていく。大変だ!!
〇2ヶ月以上遅れて男子を出産した藤壺は、恐れおののき生きた心地がしない。そのような苦しい日々を過ごしているが、源氏はそれほどの危機感はなさそう。
それにしても、左大臣・兵部卿と同じように、帝もお人好しと思います。2ヶ月以上遅れの出産で大喜び、弘徽殿は呪っているようですが、藤壺が恐れるような情報は伝わっていないようです。
源氏は帝の代理と言って藤壺と御子に会いに行くが、会うことが出来ない。命婦にしつこく迫りなんとか会おうとするが、命婦も源氏の気持ちがわかるだけに苦しむ。
〇藤壺は、心の疵を負っている。そのあり様をリアルに表現するのに「心の鬼」という言葉を使う。「身のみぞいと心憂き」と、自己嫌悪の様を表現する。こんな人間の心理を深く掘り下げてみせる。このような表現力のすばらしさに驚く。
こんな源氏と藤壺のやるせない気持ちは、現代の男女と何ら変わるところはない。式部の文章力はすさまじい。
源氏のせつない恋心を歌にして、「昔むすべる契り」を「なかの隔てぞ」と歌に込める。その気持ちを伝えられない命婦の返歌も、「歎くらむ」「まどふてう闇」と意味する源氏の心がわかるだけに、突き放すこともできない命婦の気遣いが伝わる。
その命婦に対して、藤壺は警戒するようになった。
〇出産までの日数が「とつきとおか」と言われるようになったのは、いつの頃からなのでしょうか。「御もののけにや」と世間の人々が騒ぐなんて、平安時代のおおらかさが、おかしみを誘います。
ふた月遅れで生まれた赤子が、源氏にそっくりとなれば、藤壺も身がすくむ思いだったことでしょう。それなのに、怖いもの見たさからか、しつこく会いたがる源氏。藤壺の賢さと源氏の大人げなさが対照的な場面でした。
〇藤壺が生まれてくる皇子の為に、強く逞しく生きる事を決意したことは立派です。
若いということは、そして生きているということは、罪深くて辛いものがあります。
〇藤壺の心の機微が、御子の誕生前後にわたって語り尽されている。
(以下解説文から抜粋)
藤壺は、出産の遅れから源氏との関係を取り沙汰されたら、きっと身を滅ぼすことになるだろうと恐れ、出産を前に心身の衰弱が限界にまで達する。罪深い我が身が生き長らえたことがつらく情けない。しかし弘徽殿の女御が御子の誕生を「うけはしげに」語っているという噂が伝わり、妃として最後まで誇りを失わずに生き抜こうという気力が充実してくる。
そして御子の父は源氏であるという秘密が露見するのを恐れて、藤壺は源氏を遠ざけるが、罪を犯した自分を容赦なく追い詰める「心の鬼」に苦しむ。世間に自分の過ちが漏れ伝わった時、耐えがたい屈辱に苛まれ、自分の存在は根底から突き崩されることを思い、我が身のいとわしさに苦しみ悶える。
公式に訪問するのではなく密かに会いにくる源氏に対しては、冷ややかな目で見つめ、「人のもの言ひもわずらわしきを、わりなきこと」だと命婦にはっきり言い、命婦に対しても心に隔てを置くようになった。(抜粋終わり)
こうして見てくると、藤壺の心を強く動かしているものは、源氏のそれとはかけ離れたものだという事がわかる。当然の事である。そして、最も恐れていたものが何かもわかる。
2015年6月11日「紅葉賀」感想5
「左大臣邸の北の方と舅」を了えました。
〇こうした噂は何時の間にか伝わってゆくものです。“いとど、かの若草たづね取りたまひてしお、二条の院には人迎へたまふなりと人の聞こえければ、いと心づきなしとおぼいたり”(P.22)
そんな折に、源氏の君は年改まって内裏より大殿の所へ伺われました。北の方は何時もと変わらず、女に対する嫉妬も押し包み、端正で、少しも隙を見せません。
源氏の君が“今年よりだに、すこし世づきて改めたまふ御心見えば、いかにうれしからむ”と歩み寄ろうと思っても噛み合いません。それも、北の方のお血筋がお血筋ですし、お育ちがお育ちですから今更な直しようもありません。男君もそれ相応に接しないと、満足なされないのです。
男君も男君で美しく、皆にもてはやされて、自己顕示力が強いので、この二人の仲睦まじくは望みようもありません。
その渦中にあって、お気を揉まれている大臣の舅としてのご様子は、それはそれは涙ぐましい程で、お気の毒と申し上げるほかございません。
〇家柄も地位も高い左大臣家で、回りの皆から大切に育てられた葵の上が、気位高くなるのは普通と思う。
源氏はそこを理解し、良さも認めているのに、いつもいつもとなるとなかなか難しい。夫々が自分をまげる事が出来ないのは、いつの世も同じ様である。釣り合わぬは何とやら、そこに不幸を感じる。
源氏の“たのもしげなき御心”を恨めしく思いながらも、源氏の素晴らしさに魅かれ、まめまめしく世話をする左大臣が何とも切ない。
皆いい人なのに、上手くかみ合わない、だから面白い!?
〇源氏と北の方が、なぜ大きな溝を作ってしまったのかが語られています。
源氏は名実ともに夫婦らしい夫婦になりたいと思っていますが、一方、源氏の女への浮ついた好奇心に対して、北の方が感情を露わにされたら困ったことになります。
北の方が感情を押えて、傷つきながらも自尊心を保っていることに対して、源氏は「非の打ちどころのない完璧な人」と評価している。お互いに壁を作っているので、けんかしないかぎり、源氏の思いはかなわないと思います。
〇北の方が、源氏の態度から、二条の院の姫君のことで嫉妬していることに、源氏はうすうすわかっているが、北の方の心がわかるだけに、源氏はわざと気付いていないような素振りをする。
そのような関係を、源氏は誇りに思うのは、これも「男と女」の感性の違いとして納得している。このような感性は現代に通じるものだし、解決できない永遠の課題として考えたい。
男女の世界を、これほど深く掘り下げて見せる式部の力量に驚異を感ずる。
北の方に対する源氏の反発の言葉の表現として、「などかいとさしも」の反感の強調が印象的であった。
〇・今月は、光源氏が気の向かない左大臣邸に、年賀の挨拶に出かけた所から始まりました。
ちょっとおすましの葵上に、「今年からは、もっと打ち解けて、夫婦らしく。」などと源氏は要求しますが、それは少し勝手すぎる言い分です。
二条の院の姫君については、素知らぬ顔で通しておきながら、何が夫婦らしくですか。
噂が葵上の耳に入っているのを知りながらも、そらとぼけているのですから、あきれ返ります。
嘘も方便です。若紫について、詳しい出自は言わなくとも、「親のない子を和尚さんから預かった。」程度の説明はすべきでしょう。相手は、根掘り葉掘り聞くような方ではないのです。それだけでも聞けば、心が休まることでしょう。
・内親王を妻に持つ左大臣は、帝からの信望が厚い方のようですが、優柔不断な男のような気がします。(今の世の中でも、降嫁された内親王様の旦那様なんてみんな影が薄い。)
( )内は独り言。
〇左大臣のプレゼントの石帯を 内宴の時に使わせてもらうとの 源君の言葉には 暖かい心に対する感謝が 素直に表されていて とても感じが良いです。
もっと良いものを 上げたくなってしまう 左大臣の気持ち 良く分かります。
〇源氏と北の方との夫婦関係を深く多面的に描写しています。しかしこの二人のかかわりは、今まで登場した女性たちとのそれとはまったく異なります。
容姿などはもとより、互いの出自や地位、そして二人を取り巻く背景など、これ以上には望めない程のもので、しかも互いにそれを認め合っているのに、肝心の心の通い合いがない。この違いは、同時進行している「藤壺」や「若紫」とのかかわりと比べてみても、歴然としています。
この点でも、この巻の持つ重みを感じますし、同時に今後の物語の展開に、何かしら不穏な予兆も感じ取れるような気がするのです。
2015年5月14日「紅葉賀」感想4
「三条の宮にて」「雛遊び」を了えました。
〇雛段飾りを母がするのを手伝って、組み立てた記憶はありますが、あく迄も母が主でした。母の実家は女姉妹が7.8人で男は弟が一人でしたから、時代も羨ましい大正ロマン真っ最中とあって、大騒ぎだった事でしょう。
私の方は男兄弟に挟まれて、物心付いた頃は支那事変、引き続いて大東亜戦争と発展して、学徒動員で終戦でしたから、お雛様どころではありませんでした。
ですから若紫の雛遊びの場面はほほ笑ましく、昔から女子はこうして楽しく遊んでいたんだなあと思いました。
併し少納言に“今年だにすこしおとなびさせたまへ。十にあまりぬる人は、雛遊びは忌みはべるものを”と驚くべき事を言われ、さらに“かく御夫などまうけたてまつりたまひては”ともう妻にされて了っているのです。そして、否応なく“われはかくをかしげに若き人をも持たりけるかなと、今ぞ思ほし知りける”となって行くのです。
何時の時代も何かあるものですね。
〇藤壺、源氏共に懐妊という重大な事実を前に、藤壺は一線を画し、逢う事も声を聞く事もできない状況とする。源氏は何通も送った文に返る文もなく、時だけがすぎてゆく。それ故に、夫々が断ち切れない想いは深く、哀切である。
そうした中、若紫の雛遊びに興ずる姿は幼く、妻としての自覚はまだ余りないが、それを受け入れる源氏の目は優しく慈しみ深い。そこに多くの癒しと安らぎを感じているだろうと思え、ほっとする。
〇「若紫」で、祖母の尼君が亡くなって孤児同然の境遇にあった少女とありますが、いつも見守っている少納言の存在が、時々消えてしまっているように思います。
いつも母親がわりとして見守っているのか?遠慮してある程度距離を保って、見かねてたまに意見を言うだけか?よくわかりませんが、少女のことを相当心配しているのがわかります。
少女も夫を持つ身であることを自覚しはじめました。いずれ、あっ!と言うように変心すると思うのですが。
〇時代背景を古代律令国家の宮中内裏と言うことを押えて、物語が展開するのであるが、さまざまな人物描写が生き生きとしているのに驚く。
この章では、登場人物は源氏、藤壺、命婦、尼君、若紫、少納言等であるが、雛遊びの状況が描かれる。この時代は宮中の出来事であるが、現代にまで庶民の間にも伝承されてきている。
〇祖母尼君が亡くなって三カ月が経ち、その悲しみは消えることはなくても、源君は優しいし、乳母も犬君も側にいて、伸び伸びと可愛いいままで若紫が暮せている事、何よりです。
〇P32の「暮れぬれば…」から始まり「・・・かたみに尽きせず」で閉じる僅か8行の文章に、何と多くの事が織り込まれているのでしょうか。
昔は何の隔てもなく藤壺に接することができたのに、今は藤壺の声さえ聴けず、宮の邸を「すくすくしう出で」ざるを得ない源氏。二人を「たばかった」命婦の複雑な気持ち。そして命婦とは一線を画し、「ありしよりは、いとど憂きふし」の藤壺。
特に、突然挿入されたかのように見える「何のしるしもなくて過ぎゆく」については、導き手がなくてはとても読み切れないものです。
そして「はかなの契りやとおぼしみだるること、かたみに尽きせず」なのです。
2015年4月9日「紅葉賀」感想3
「北の方とおさなき人と」から「三条の宮にて」に進みました。
〇源氏の君は何とかして藤壺にお会いしたいと、強い想いを押さえきれず三条へ向かいます。併し命婦、中納言の君、中務などの方々とのみお会い出来て、落胆します。そこに兵部卿の宮が参られ、ご対面となります。
源氏は、宮が藤壺の兄であり、又若紫の父である事を知っています。宮の方はそうした事をご存知ではありません。その興味深い第一印象は、源氏は“女にて見むはをかしかりぬべく、人知れず見たてまつりたまふ”と、宮の方は“婿になどはおぼし寄らで、女にて見ばや”とあり、とても不思議です。お二人共お美しく、その美しさに惹かれるのはわかりますが、お互いに相手を女性と見ればと思った事です。
併し、宮は一切ご存知ない事になっていますが、“婿になどはおぼし寄らで”とありますから、うすうすご存知だったのではないかと、ふと思いました。
〇源氏は葵の上に諸々の不満もあるが、妻としての素晴らしさを認めているのが解った。伝わらない状態は不幸で可哀想。
源氏を慕う若紫の思いも心に残り、藤壺への切ない想いにも心を奪われている日々は大へんだと感じ入る。
もしかして、式部はサディスティック?
三条の宮邸で対面した源氏と兵部卿、お互いの中に女の魅力を感じるという妖しの世界もでてきた。二人共々がどんなに美しいか窺い知れる。
面白さ満載である。
〇行幸も一段落した後、源氏の心は藤壷に逢いたいという想いが募る。たびたび手紙を送るが返事はない。
舅の左大臣からは足を運ぶよう催促が来る。他の女の所にも行かなければならない。宮中の詰めもあり、慕っている少女に寂しい思いをさせていることにも気に掛かる。
三条の宮邸に藤壺を訪問するが、対面することが出来ない。代わりに兄兵部卿が対面する。少女の父である兵部卿には少女のことは知られてはならないが、兵部卿を見た源氏は女が男を惹きつける時の美しさを感じ、兵部卿も源氏を通う女の一人として異性を見る目で見てしまう。
二人の出会いで源氏が男らしく感じたのは、かなり兵部卿がなよなよしているからでしょうか。
〇祖母の尼君が亡くなった孤児同様の少女を、源氏は引き取り世話をした。源氏を無心に慕ってくる少女を、周囲の者にも素性を明かさないまゝ宮殿(西の対)に引き続き住まわせ、少女に寄り添い、ことこまかに教育するのである。
その様子を聞いた北山の僧都、源氏の意図は理解できないが、大事にされていることで、内心の気持ちは嬉しく思うのである。
心理の描写のこまやかさに、作者の筆さばきはますますさえてくる。
源氏の藤壺に対する気持もますます募ってくるのがわかるが、北の方に対しては「心にもつかず」と思うことで、寒々しい関係が源氏の根っこの心にうずき、複雑な感情をもたらせている。
そのような関係にある中での「紫の上」を引き取り育てるという描写である。
〇源氏と兵部卿の宮とが、三条の宮邸でプライベートに会った時のお互いの想いは、現代人とはだいぶ違うように思いました。
勿論現代にも、バイセクシャルな関係は存在しますが、それほど一般的なものではないと思います。
兵部卿の宮の“色めかしうなよびたまへる”様で思い浮かぶのは、歌舞伎の片岡孝夫(現在の片岡仁左衛門)です。あの柔らかな物腰、品のよさは、兵部卿イコール孝夫だと思いました。
では、源氏は?…思いつきません。
〇いくら器量が良く 気品も教養もあろうが 兵部卿は 少しも魅力がない人だと 私は思います。源氏の卿に対する感じ方には 少々違和感を覚えます。
〇「北の方とおさなき人と」では、源氏を取り巻く登場人物(藤壺、左大臣、北の方、若紫)の複雑なからまりがさらに深く描かれています。
次いで「三条の宮にて」では、冒頭の源氏と兵部卿との初対面の場面で、思いもよらない描写があり本当に驚かされました。この物語から、これから一体何が飛び出してくるのでしょうか。きっと想像をはるかに超えるものなのでしょう。
2015年3月12日「紅葉賀」2感想
「試楽」「行幸」を了えました。
〇中将の君は、ご返事を頂けるとは期待しないまでも、止むに止まれずに“もの思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の 袖うち振りし心知りきや”と激しい思いを込めてお送りしますと、思いがけずも“唐人の袖振ることは遠けれど 立居につけてあはれとは見き おほかたには”と格調の高いお返しを頂き大変喜ばれました。
本番の行幸は、それは豪華で この世のものとは思われないものでした。特に“楽の船ども漕ぎめぐりて、唐土高麗と尽くしたる舞ども、種多かり。楽の声、鼓の音、世をひびかす。”その最高潮に、“木高き紅葉のかげに、四十人の垣代”奏でる中に青海波が舞われたのです。
その夜、源氏の中将は正三位に、頭の中将はじめ上達部は皆加階賜り、夢のような夜は帳を閉じたのです。
美しくも雅な源氏物語の白眉を飾るのはこの巻と思われます。
〇試楽の青海波に込めた熱い恋心を伝えた手紙を、受けた藤壺もまた想いを歌に込め返す。さりげなさを装いながらも二人には通じる恋文は、心ふるえただろうと切なさに胸が痛い。
それにしても、人を介さねば何事も進まないこの時代、秘密を守る為、信頼関係を保つ為の努力は大変だっただろうと思う。
行幸当日の紅葉した木々と松の緑の美しさは目にうかぶし、その中を吹き渡る風と楽の音が聴こえ、舞の美しさが見えるようである。
〇試楽ではあるが藤壺に見せたいという帝の思いは、源氏の素晴らしい舞により見事な出来映えとなり、本番の紅葉の木陰での舞を心配させるほどであった。
帝は源氏の青海波の感動がいかに大きかったか、藤壺に感想を聞いてみたいという強い言葉で伝わる。帝の藤壺と源氏共に愛する気持が伝わって来る。源氏の方は藤壷のことしか頭になかったように思います。
いよいよ行幸の日を迎え、朱雀院祝賀の宴が繰り広げられる。この祝賀の宴は、色鮮やかな紅葉した木々を背景に行われる。青海波を舞う源氏に涙するものまでいる。人々に感動を与えた源氏は正三位に昇進する。ついでにか(?)、他の者も昇進が伝えられる。
〇公式行事の行幸は、紅葉の最高に美しい季節に行なわれる。雅楽の音を背景にして、恐ろしいさまのように盛大に、人々を巻き込んで行われた。
源氏の青海波の舞は、恋しい人に届けられたのであろう。藤壺の返歌に「立居につけてあはれとは見き」と寄せられたことに、ゆかしさが表れている。
この後、上達部たちは官位の昇進があった。この時代の彼らの生きざまを伺うことができる。式部の物語の展開の、読者をひきつける妙味さがある。
〇・その場の情景が目に浮かぶ、比喩を用いた素晴らしい表現が印象的でした。
①持経のように
藤壺からの返事を半ば諦めていた源氏のもとに、手紙が届いたときの嬉しさを「ほほゑまれて、持経のやうにひき広げて見ゐたまへり。」
②まことの深山おろしと聞こえて
40人の楽人の妙なる調べと松の木立を吹き抜ける風との響き合いを「まことの深山おろしと聞こえて吹きまよひ、」
・予行演習と本番では、空模様がだいぶ異なり、小雨に濡れた事を、現代人なら「がっかり」とか「残念」と思うのに、「空模様まで感涙にむせぶ。」とポジティブに受け止めているところがすばらしいです。
〇源君の かざしを 手づから 菊に差し替えた 左大将も きっと とても ステキな人だと 想像しています。
又 この入綾の趣は 下人さへも 美しくしてしまうのが 不思議です。
〇語り手は源氏・藤壺二人を、次のように褒めたたえます。
「かやうのかたさへたどたどしからず、ひとのみかどまで思ほしやれる御后言葉の、かねても、と」(藤壺)
「この君にひかれたまへるならば、人の目をもおどろかし、心をもよろこばせたまふ、昔の世ゆかしげなり」(源氏)
そして華やかな行幸を舞台に、この二人の恋を軸として帝・弘徽殿を絡めた人模様が描かれていきます。さて今後の展開やいかに。月一回の講義が待ち遠しいです。
2015年2月12日「紅葉賀」1 感想
いよいよ「紅葉賀」の始まりです。「桐壷」「若紫」に続く物語のメインストーリを形成する巻とのことで、居住まいを正して読み始めました。
〇長い時間をかけて行っていた試楽の本番が近付いて参りました。
帝は藤壺にも見せたいとお思いになって、朱雀院に行幸になる前に、御前で試楽を行う事になりました。何と言っても当日のお目当ては、源氏の中将と頭の中将との青海波の舞でした。殊に源氏の中将の舞には、皆々涙して感激した程でした。
その中にあって特別なお二人があり、藤壺は不義の子を宿している身で、罪深さを思いつつも“夢のここちなむしたまひける”で、自分の高まる気持ちを押さえ込むのに懸命です。
もう一人の春宮の女御は不快なご様子で、“神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし”とのたまふ。ご自分のお子春宮が、源氏の中将にすべてに劣っている事が腹立たしくてならないのです。まして、帝のご寵愛著しかった桐壺の更衣の忘れがたみなのですから。
人間の性は太古から現在まで、未来までもそんなに変わるものではないのですから、致し方ない事と悲しくなります。
〇行幸に同行しない妃や女房逹の為にとの事で、桐壺帝は清涼殿にて試楽を行うが、ただひとり藤壺の為だったのではないか。そして、その藤壺は久方ぶりに源氏の姿を見ることになるし、源氏もまたしかり。
拒絶しながらも、心惹かれるものをとどめる事の出来ない藤壺。
拒絶されながら恋い慕う源氏。舞に、詠に、こめた想いはいかばかりであったろうか。
罪の意識におののきつつ、その想いを感じ、歓びにふるえたであろう藤壺。
素晴らしい“青海波”をみせる事の出来た桐壺帝の歓び。
三者三様の恋模様に涙が出てきます。
〇朱雀院の行幸を前に清涼殿にて試楽が開かれる。行幸での完璧な演奏を期しての予行練習であるが、帝の、動けない藤壺に祝賀の宴を見せたいという思いが伝わる。
源氏は青海波を頭の中将と二人で披露するが、いかに源氏が素晴らしいかと表現するのに、まず頭の中将の出来は悪くないといいつつ比較すると、頭の中将のは「深山木」だと言う。源氏の歌い上げる声は「御迦陵頻伽」の声と表現している。
いつこんな練習をしているのかと、疑問を感じてしまうのですが。
〇青海波の舞に感動する帝は、藤壺の心をなぐさめる優しい言葉をかける。
それに対して藤壺の気持ちは複雑である。自分の中で隠していることがあるからだ。それでも、源氏に対する気持は押さえなければならない。そんな場面の展開に式部の筆は容赦しない。
そんな式部の冷たさに、怒りが生まれてくるのは私だけだろうか。
〇・新しい巻に入り、王朝絵巻の華やかさが戻ってきました。
何十年も前に読んだ平家物語の中に、平家の美少年が青海波を舞う場面があり、「青海波」と言う舞楽の名前は、その時に覚えたように記憶しております。源氏物語の真似(?)だったとは、ちっとも知りませんでした。
・小学校の校庭に、「天皇陛下(昭和天皇のこと)行幸記念碑」という鳳凰の付いた記念碑があり、いつも敬礼させられていたので、「行幸」と言う言葉は、とても身近なものでした。今日、源氏を学習して、「そういえば、最近聞かない言葉だなあ。いつから使われなくなったのかしら。」と考えてしまいました。
・懐妊を大喜びする帝を、生涯騙し続けるなんて、藤壺は、この先、心の病にかかることは、ないのでしょうか。
〇弘徽殿の女御の 久し振りの ただならずおぼいする 余りの 意地悪なお言葉。春宮の女御になっても 息がつけないようで かわいそう。
〇青海波の舞で始まる華やかな幕開けです。しかし、同時に「帝・藤壺」「源氏・藤壺」「弘徽殿・源氏」と複雑に絡む人模様が呈示され、この巻の不穏な通奏低音が示されているように思いました。
小事ですが、帝の「家の子は異なる」「ここしうなまめいたる筋を、えなむ見せぬ」のお言葉に、「この世に名を得たる男」ですらない私としましては、少なからず傷ついたのでありました。
2015年1月15日「末摘花」感想
「末摘花」の巻を了えました。感想文にはそれぞれの深い想いが込められています。
〇何と締め括ったら良いのかと、非常に悩ましい終章であります。
宮も少しものづつみが解けて、源氏の“待たるるものは”の歌に対して“さへづる春は”と答えられる程になり、帰られる源氏は“さりや。年経ぬるしるしよ”と喜ばれ、業平の“夢かとぞ見る”の一節を口ずさまれたのであるが、見送られる宮を見ると“口おほひの側目より、なほかの末摘花、いとにほひやかにさし出でたり”で、すべてぶち壊されて了った。
二条院にお帰りになると、美しく可愛らしい若紫が待っている。髪の長い女の鼻に紅をつけた絵を書いたり、自分の鼻を赤く塗ったりして若紫とたわむれる。その様子は“妹背”と見たまう程に思われ、将来を暗示させる。
源氏と末摘花は少し雪解けの模様で、源氏の手厚い後見が何よりの救いであります。
〇教育されなかった悲哀、庇護のない宮家の悲哀がつぶさに語られ、胸が痛む思いをした。
故に、末摘花にはハラハラ、ドキドキ、イライラさせながら終章となったが、楽しい折、淋しさにふれた折に姫を思い出し訪ねるなど、源氏の優しさが嬉しいし、もしかしたら姫が大きく変わっているかもと期待し裏切られる様子も、何ともユーモラスで楽しかった。
源氏からの贈り物である今様の着物に身をつつみ、源氏の問いかけに、初めて自ら答えた姫のほんの少しみえた変化の兆しは、これから先への光をみた感有りである。
二条に待つ紫の君の“いみじうらうたし”“うつくしうきよらなり”と成長している様子との余りの違いに切ない思いであるし、紫との戯れに鼻に紅をぬる等残酷さもあるが、何かにつけ末摘花を思い出しているのは、忘却や無視よりは数段救われる思いである。
強烈なインパクトを残した末摘花の巻であった。
〇一昨年12月から始まった末摘花も一年を超えて終わりました。
思えば夕顔の面影よりスタートして、命婦にあやつられたように姫君と結婚した源氏でした。初めて姫君の鼻を見た時、逃げようとしたと思います。頭の中将ならたぶん逃げたと思ったのでしょう? ゆらぐ心が見え見えです。
姫君は源氏に気に入られようと頑張っています。源氏も年が明けて変化のきざしが見える姫君に期待しているのですが、紅い鼻はどうしても拒絶反応が働くようです。
最後は美しい紫の君が出て来ます。これで終わりなら姫君がかわいそうと、思うのですが?
〇やっと源氏に対して、末摘花の言葉が和歌で応えられるようになり、「からうしてわななかしいでたり」と気持を通わせることができた。
源氏も夢のようだと業平の歌を口ずさみながら退出する時、見送る姫君の扇でおおった紅い鼻を見てしまった。残酷なことだが、姫君に対する気持が興ざめしてしまうのである。これも現実。天から地面に叩き降ろされてしまった。
急転するドラマを見せる式部の筆致は読む者をひきつける。
きよらの世界だけでなく、源氏の女性遍歴は常陸の宮の姫君との交際のように、一生の負い目をもつような出来事もあったのである。
いかがなりますことやら、式部は気をもたせるのである。
〇常陸宮の姫君の容貌や言動が、滑稽を通り越して残酷に描き出されていることに、ショックを受けました。女性の作者でなければ、ここまで容赦なく書くことはできなかったと思います。
とは言え、姫の容貌を表した文章の中で一番おおげさでおかしかったのは、垂れ下がった鼻を「普賢菩薩の乗物とおぼゆ」と表現しているところでした。象は、正倉院の御物の中には出てきますが、本物を見た筈はないし、象と言う言葉もなかったと思います。よくそんな事を考えついたと、感心してしまいました。
それ以来私は白象が気になって、昨秋の日展でも「白象来迎図」という絵葉書を思わず買ってしまいました。
〇「心から、などか、かう憂き世を見あつかふらむ」と考えてしまうこと 確かにありますよね。いでや、うたてこそあらめ。
〇この巻を読み進むにつれ、末摘花に対しいじらしさと同情の念が深くなってきました。もともと弱者や困窮者にバイアスのかかった情念の強い私ですから当然の成り行きです。
「姫君の変化」の終わりはまことに無惨に感じましたし、続く「鼻の紅」での源氏と紫の君との仲睦まじい戯れとの対比は衝撃的です。
さらに、源氏は「あいなくうちうめかれたまふ」、そして語り手は「かかる人々の末々、いかなりけむ」としてこの巻を閉じる式部に、我々は徹底的に翻弄されつつ次の「紅葉賀」に入っていくことに相成りました。
この物語の魅力にとことん惹かれていく私たちです。
2014年12月11日「末摘花」感想
「姫君の変化」に入りました。いよいよ後は「鼻の紅」を残すのみです。顧みれば一年を超す長い旅でした。
〇何事も一方からのみ見ると間違いのもとで、今様の先端を行く源氏と零落して当主もいない宮家の姫とでは比べようもない。そしてそこに仕えている者達は、自分の処の主人こそ正しくて、秀でていると自負しているものでもある。
源氏からの御返りを“宮には、女房つどひて見めでけり”と、又晦日に“かの御衣筥に、御衣一具いろいろ見えて、命婦ぞたてまつりたる”とある。女房逹は宮の差し上げた御衣を見劣りしないと自信たっぷりである。御返りにも“これよりのは、道理聞こえて、したたかにこそあれ。御返りは、ただをかしきかたにこそ”と決めつけている。
かたくなな宮も粋な源氏もそれぞれどの位分かり合えるようになるのでしょうか、面白いところです。
〇命婦との軽妙なやりとり、姫への返事の少しブラックな歌、源氏のユーモアあふれる性格が思われる。何と楽しい人なのか!!
ここで、そうした事を理解出来ない姫の謎が解けた。宮邸の〈ねび人ども〉のかたくなさと時代遅れの考え方の故だったと。この女房逹に育てられた姫は、ただひたすら〈ものづつみ〉になったのではないかと思われる。
新年の行事の賑やかさの中で、〈さびしき所〉の姫を思い訪れた優しい源氏、宮邸は少し活気づき、姫も少し女らしい様子がみえる。そこで源氏の妄想がまたまた。年があらたまり姫は見違える様に美しくなっているかもと。あり得な~い。
ここでは源氏のいろいろな性格がみえて楽しい。
〇姫君より贈られた着物の色合いを源氏は「わろし」と考え、別のもっと趣ある色目の着物を贈るが、老女房たちは納得がゆかない。姫君びいきもあると思いますが、歌も姫君の方が、筋が通っていてわかりやすく、筆跡も確かと自信をもっている、おもしろい所でした。
一年も終わり、新しい年となり、源氏は姫君が見違えるように美しくなっているかもしれないと期待してしまうが、それはちょっと?
平均寿命が短い時代、年越しは一抹の不安があるのでしょうか? 源氏はやさしいですね!!
〇「御歌も道理あり」と、姫君の歌を評価している命婦の見識もさすがである。それに較べて、源氏の返歌はいくら上手とは言え、ただ「おかしきかたにこそ」と軽く、掛詞を駆使しているだけではないかと手きびしい。
年が明けて新年になり、男踏歌の歌い舞う行事が始まると、騒がしい雰囲気が嫌になり、さびしい所、常陸宮邸が思い出され、七日の白馬の節会が終わって夜になると姫君を訪ねる。
姫君は、もしかして見違えるような女になっているのではないかと、式部はまた気をもたせる。
〇はじめは“この姫、おバカか”と思っていました。でも、たった一人取り残された宮家の姫君が、博物館から出てきたような老女房たちに育てられたのだから、“ま、こんなものかな”と思うようになってきました。
どんなに貧しい暮らしでも、姫を見捨てることなく、ねび人たちが、姫様びいきであることに、主従の強い絆を感じます。
〇「逢はぬ夜をへだつる中の衣手に・・・」の歌を よこした後日に 増々夜を隔てましょうとばかり 衣を一式 贈ったりして 源君の気持ちは優しいだけではありません。
こんな場合の お礼の和歌を作り上げるのは 相当難しいと思います。
〇《ただ梅》の謎についての講義は、大変面白く興味を覚えました。
また「左近の命婦」「肥後の采女」は一体どういう人物なのでしょうか。省略の多い文章の中に具体的に例示されているので、「帚木」の中の「葎の門のらうたげならむ人」のごとく、「常陸の宮の姫君」でひょっこり触れられるようなことが、以後あり得るのか関心を持ちました。(実は、「好敵手」の中務の君の再登場も、ひそかに期待しているのであります)。
2014年11月13日「末摘花」感想
「贈り物」を了えました。
〇宮の贈り物の段で、くしくも宮、源氏、命婦の三者の歌が並びます。
宮「唐衣君が心のつらければ袂はかくぞそほちつつのみ」
源「なつかしき色ともなしに何にこのすゑつむ花を袖に触れけむ」
命「紅のひと花衣うすくともひたすら朽す名をし立てずは」
宮は、零落の中でも精一杯心を籠めた衣に添えて、陸奥紙に香を深くたき込んで文を送る。その文を源氏は見て紙のはしに歌を書く。それをのぞき見していた命婦は自分の苦しい気持ちを歌で返す。
歌の形体は三様で出来ばえも三様、下手、上手、機転、一生懸命、落胆、後悔。現在でもこういう行き違いはまゝ有るが、誰が悪いわけでもなく、良かれと思ってした事が思わぬ結果となる。
併しながら何事もその世界の水準、枠の内であって、はずれるとぎくしゃくするのも理であります。
〇自分がどういう立場にあるのかという事を理解できていない末摘花。正妻の為す朔日の御よそひを、命婦を通して贈る。文も自分で書いているという努力は認めてもらえても、使用した紙、文の内容、贈られた古めきたる直衣と、益々源氏をやり切れない気持ちにさせてしまう。
源氏から贈られた品々から、何とかもう少しでいいから空気が読めないものかと、もどかしくなる。たまさかにしか訪れない事で、源氏は後見に徹していたいのだという意志を示しているのだろうに、宮から女房逹まで誰一人として気がつかない。何と不思議な世界に生きている宮家か。それでも放り出す事は出来ない、源氏の苦い思いの深さが解る。
姫にも源氏にも切ない思いを感じる。
〇年の暮れ、命婦は姫君の手紙を持って源氏の宿直所を訪ねる。手紙を渡すころあいを見計らっているような命婦の態度に、源氏は何を勿体ぶっているのかと思い、何でも話すように促す。
姫君の陸奥紙に書かれた手紙を大事そうに受け取る源氏を見て命婦は胸つぶる思いがする。歌の出来はあまり良くなく、枕詞に首をひねる源氏を見て、命婦は衣装箱を源氏に押し出す。姫君は源氏の妻としての務めをはたすため、元日の晴れ着として源氏に着てもらうため用意した着物である。
歌にしろ、着物にしろ源氏はがっかりしてしまうが、仕方なく手紙を広げながら、その端に文字を書き入れる。その歌を見て命婦が歌を詠む。
「紅のひと花衣うすくともひたすら朽す名をし立てずは
心苦しの世や」と。
源氏は姫君のために心を砕く命婦の心根を感じる。
〇末摘花は、源氏の妻として格式を重んじる気持ちで命婦に命じているのであろう。歌もぎこちなく、贈り物の衣と箱も古い格式のものである。
貰った源氏は命婦の立場もわかるし、末摘花の筆の柄に手を添える人もいないのだから致し方ないと思うのである。源氏が「いともかしこきかた」と尊敬語を使うのに、命婦はただ顔を赤らめて見せるのである。
式部が、源氏の姿をきれい事ですまさないごとく描き出しているのは、リアリズムの映画を見ているようだ。
〇・「ひと花衣」というのは、一回しか染めてない衣という意味だと知りました。手数がかかっていない分、それだけ安い品物かもしれませんが、とても美しいひびきをもつ言葉だと思いました。
・「末つむ花」とは、源氏がこの姫君につけた“あだ名”と思っていいのでしょうか。
・「やれやれ、えらい女に手をつけてしまった」と、源氏もちょっぴり後悔しているのではないでしょうか。
〇末摘花の贈り物の衣は どうしましょう、父君のお古らしいと 源君は察していると思われますので 本当に 困った贈り物とは このことですね。
人にもあげられないし、捨てることもできない。
〇末摘花をめぐる可笑しくも、哀しきエピソードの数々。しかしその精一杯のいじらしいともいえる姿に、心からの同情を禁じえません。
2014年10月9日「末摘花」感想
「よろぼふ門」を了えました。
〇源氏は帰りに、御車を寄せていた中門の痛み方があまりひどいので驚いたが、門番の翁の一連の家族逹の有様にも驚く。衣は煤けて、とても寒そうで見るに忍びない。雪で門も開けられないので、供の人達が寄って開ける具合であった。
ふと白楽天の「ふりにける頭の雪を見る人も劣らずぬらす朝の袖かな。わかき者はかたちかくれず」と誦し、鼻が赤くなる程寒かったであろう末摘花の事を想い出してほほえむ。
その後、源氏は末摘花のすべてを見てしまった事で放っておく事が出来なくなり、姫はじめ下々まで気を使われるようになった。姫もご好意を受け入れた。
そして源氏は、又しても女の魅力は「げに品にもよらぬわざなり」「心ばせのなだらかにねたげなりし」と、空蝉の事を口惜しく思い出すのであった。
〇雪の朝に、姫の容姿も家屋敷の荒れ果てた状態も全て明らかになり、捨て置ければどんなに楽かと思いつつも、源氏は後見人として援助する事に方向を定め、生活のあらゆる面倒を見る事に。
それを嫌がる風のない姫の性格に、源氏も気が楽で双方にとってめでたしである。
鄙にはまれな魅力的な女性でなかった故、藤壺への想いもまぎらす事が出来ず、過去に受けた空蝉からの口惜しさも思い返す事になる。
源氏の複雑で忙しい心境に、同情したり感心したりと楽しい事である。
〇源氏は姫君を知ることによって、このままにはして置けないと思うようになった。生活面の援助をするのは、姫君の容姿をぬきにして優しさから来ている。
その気持ちの中で、空蝉と比較して優れているとは思わないが(身分は高いが)、恋にこだわるのは源氏の「くせ」なのであろう。このような場面にも、空蝉がでてきてしまうのである。
さびしく荒れ果てた屋敷に住む姫君は、貧しくとも格式の高い家に育った性格を伺わせる。そこに源氏が気になって仕方がないと思ったのであろう。
〇「頭の中将に姫の赤い鼻を見せたら、なににたとえるだろうか」と源氏が思う箇所は、少し残酷ではないかと思います。
心優しい人とは思えません。
〇「橘の木のうづもれたる」から「人もがなと見たまふ」迄の文、私も特に良いなと思っていました。
〇「山里のここちしてものあはれなるを、かの人々の言ひし葎の門は、かうやうなる所なりけむかし。げに、心苦しくらうたげならむ人をここにすゑて、うしろめたう恋しと思はばや」
「あるまじきもの思ひは、それにまぎれなむかし」
「思ふやうなる住処に合はぬ御ありさまは、取るべきかたなしと思ひながら、我ならぬ人は、まして見忍びてむや」
「故親王のうしろめたしとたぐへ置きたまひけむ魂のしるべなめりとぞとおぼさるる」
「松の木のおのれ起きかへりて、さとこぼるる雪も、名に立つ末のと見ゆるなどを、いと深からずとも、なだらかなるほどにあひしらはむ人もがなと見たまふ」
この項の冒頭わずか11行の中に、以上のような複雑で激しく動く源氏の心理を、見事に描写しつくしていることに感嘆したと言うか、いや最早驚嘆したと言うほかないと思いました。
2014年9月11日「末摘花」感想
「雪の朝」を了えました。
〇頼みとする侍従は、斎院に参っておりません。雪が降り出してまんじりともしない一夜が明けると、庭は一面銀世界となっていました。源氏は姫に雪景色を見るように誘うと、やっとゐざり出て来ます。
源氏は姫を(見たいと思って)後目で見ますと、体は大柄で、お顔は鼻が普賢菩薩の象のように垂れ、先が赤いので、目を覆いたくなる有様でした。
が、“頭つき、髪のかかりはしも美しく”袿の裾に一尺ばかりあまりたっぷりとあり、黒髪美人でした。平安時代の美人は顔よりも髪とわかっていたつもりでしたが、あまりにも鼻の赤さが強調され、それ故末摘花と名付けられていたので考え違いをしていました。
併し、源氏の君も口が塞がった心地で“朝日さす軒の垂氷は解けながら などかつららの結ぼほるらむ”と、うちとけようとしない姫をなじって帰られる。姫は“むむ”と源氏の君に対し始めて精一杯のお答えをなさった。
末摘花らしいお返事で、思わず“むむ”と。
〇久しぶりに訪ねた常陸の宮邸は、気のきく女房も去り、その零落振りは夕顔を失ったものの怪の夜を思いださせる程であるから、かなりのものである。
姫の態度も変わらず打ちとけず、眠れぬ夜を過ごし迎えた朝は雪。その雪明りの中でついに素顔を見る事になるが、容貌・容姿は怪異といえそうである。
しかし、ここで式部は姫の髪の美しさに触れる。この時代、髪の美しさは何にも優る美人の条件だったはず。素敵な美点を持っていた事にほっとさせられる。
宮家の過去の栄光を思わせる古色蒼然とした品々や、時代遅れのしきたりの中で生活する姫は、朝帰りする源氏からの歌に、ただ「むむ」とうち笑うのみであるが、どれ程の思いをこめた「むむ」であったのだろうか?
源氏は善悪ないまぜの複雑な思いを感じたであろうと、思いを深くした事である。
〇雪の朝でした。姫君との出会いは春でしたので、ようやく容貌を見る機会が訪れましたが、普賢菩薩の乗り物、白象か?と思ったほどの奇異な鼻、額が異常に広く、顔の下の方が「おどろおどろし」い長さ。
今まで容姿の美しい女性としか付き合っていなかった源氏は、逃げ出したくなるショックを受ける。そうは思うものの、やせて痛々しい姿に源氏の心に憐みの感情がわいてくる。髪に目を向けると、たいそう美しい。
あと2,3回見れば、顔など気にならなくなるのではと思うのですが。
〇雪の朝を背景にして末摘花と源氏の関係が描写される。
末摘花を源氏は怖いもの見たさに観てしまったのである。この場面は決して良い場面ではないが、源氏の探索が続く。姫君の容姿があまりにも痩せ細っているのに気の毒なことをしてしまったと想うのである。
姫君の髪は並みはずれて、袿の裾を引きずるぐらいみごとな「髪の持ち主」であった。その視線は着ている物に及び、色あせた着物や殿方用の黒貂の毛皮の装いは異様であると強調され、源氏には滑稽に見えた。没落した宮家を想い同情する。このような姫君を、源氏はいとほしくあわれに感ずる。
源氏の和歌に対して姫君は返歌をよこさず、ただ「むむ」と口を開いた情景が印象的であった。
〇・何といっても傑作なのは、「普賢菩薩の乗物とおぼゆ。」と言う箇所でした。
日本人の誰一人も、実物を見たことのない時代なのに、長く垂れた鼻を誇張したこの表現に、思わず吹き出してしまいました。
「象」と言う言葉は、いつごろできたのか知りませんが、この時代の人々は、普賢菩薩は
何に乗っていると思ったのでしょうか。
・つららのことを、当時は垂氷(たるひ)と称したとのこと。
つららは、氷が下に垂れた状態ですから、よくできた言葉だなあと感心しました。
そういえば、滝のことを「垂水(たるみ)」というのを思い出しました。
〇姫君のなごりなう黒き袿に、 老人(おいびと)の衣もさればよと、 私の胸もつぶれ、 かわいそうで 涙が出ます。
〇源氏がほの暗い雪の光の中で見た姫君の姿は、まさに異形というほかないものでした。しかし、源氏は胸つぶれる思いをしながらも、ひどく痩せた姫君に「いとほしげにさらぼひて」と憐れむやさしさも示します。
また、姫君の美しく豊かな髪について「めでたしと思ひきこゆる人々にも、をさをさ劣るまじう」と認めます。
姫君の異様な装いに「似げなうおどろおどろしきこと、いともてはやされたり」と見つつも「げにこの皮なうて、はた、寒からましとみゆる」と同情します。
「末摘花」のクライマックスの場面は劇的です。
2014年8月14日 「末摘花」感想
「宮家の御逹」を了えました。
〇零落した宮家の生活ぶりが書かれている興味深い処です。
朱雀院の行幸も間近になって、宮中では其の試楽の練習に一段と熱気が漂っています。その為、源氏は宮家への訪れはなく、命婦に泣きつかれて、やっと夜晩く立ち寄ります。
そこで格子の間から覗いた様子が事細かに書かれています。全盛時代の美しさをすっかり失った唐物の調度品の傷み、くすみ、女房逹の粗末な食事の有様、着物の煤け具合等。それでいて昔の仕来りたりのまゝ褶をつけ、こわれた櫛をつけて格式を守っている具合等々で、“故宮おはしましし世を、などてからしと思ひけむ”、あまりの寒さと餓えで“飛び立ちぬべくふるふもあり”と。
そこで源氏は“ただ今おはするやうにて、うちたたきたまふ”。
〇朱雀院の行幸の準備の忙しさに、末摘花への訪れもなく、季節は夏から秋へと移る。
耐えかねた命婦の訪問でのやりとりで、源氏が姫を思いやる心情を持っている事はわかるのだが、どんなに忙しくても、どうしても逢いたい女の所へは時間を作り訪れているのである。男の本性でもあり、姫の魅力の無さと納得できてしまうのが、かわいそうでもある。そして源氏には、いつくしみ育てている若紫がいる事でもあるし。
それにしても、後見のない宮家の様子はかなり零落したもので、どの様に生活を維持しているのか興味がつきない。そしてその暮し振りに、源氏の好奇心にも火がついた様である。
一生面倒を見ようと思った気持をどの様な形で現すのか、黙している末摘花に隠れた魅力があるのか、物語の展開が楽しみである。
〇行幸も近くなり、源氏も練習に加わり、女達の所へ思うように通えない。そんな折、命婦が源氏を訪ねて姫君の様子を話す。とても気の毒で、これ以上見ていられないと訴える。
源氏も気にかけていて「いとまなきほどぞや。わりなし」と弁解して、姫君を見捨てるつもりはないと命婦を安心させる。足が遠のいたのは、少女を自邸に引き取り、暮らし始めたこともある。
ある時、夜遅くなってから姫君の邸に立ち寄り、あまりにまずしい生活を見て、かえって姫君に興味をそそられる。
姫君が、源氏が来訪するのを切に願っていた姿、感情を命婦に見せていたのでしょうか?命婦の演出のような気がします。
〇宮家のすごく貧しい姿がリアルに描かれている。こんな状態を、名門の家だけにかたくなに守りながら貧しさにたえている。
これを現代の格差社会と比較して考えると、いかばかりか。
式部の筆は、何ものをも許さない鋭さがあるのだろうか。末摘花の章のすごさを感じた。
〇男女が会う様を≪手さぐりのたどたどしきに≫と書かれているように、この時代では、暗い夜中だけが、お互いを理解しあえる場になっているということが、滑稽な感じがします。
〇わりなの 人に恨みられる齢が 日本に限らず 年々急速に高くなっているように 歎かわしく 感じております
〇「御いとまなきやうにて、切におぼす所ばかりにこそ、ぬすまはれ」る源氏。命婦に「いとかうもて離れたる御心ばへは、見たまふる人さへ心苦しく」と訴えられる。ある時、源氏は夜晩く姫君の邸に立ち寄り、宮家の凄まじいばかりの落魄ぶりを垣間見る。
いよいよ「末摘花」の核心に迫ってきました。式部の筆はますます冴えわたっています。
2014年7月10日「末摘花」感想
「後朝の文」を了えました。
〇思い乱れて帰った源氏ですが、そこに朱雀院からのお仕事が入って了って、すっかり文を送るのを忘れ、気がついた時ははや夕刻、さすがに気の毒な事をしたと思って文を送ります。
一方常陸宮邸では命婦をはじめ女房達が待ちに待っていて、“いといとほしき御さまかな”と姫君を思いやっている。
併し当の末摘花はただただ昨夜の事を“はづかしう思ひつづけたまひて”の有様で、文など気にしていません。源氏との突然の衝撃的な“ちぎり”にすっかり包みこまれている。或る意味で言うならば、彼女は幸せな人で、この事だけで一生生きて行けるのではないかと思うに至るのは如何でしょうか。
これもものづつみのなせる技。
〇大きくふくらんでいた思いと、かなった思いの落差は天と地ほど。
この時代の女が生きていく為の条件を、何一つ身につけさせなかった常陸宮は相当な変わり者?
しかし、何も知らないというのも幸せの一つ。後朝の文が遅くても、次の日の訪れのない事も、姫を傷つける事はなかったのだし、それ故に源氏は〈我はさりとも心長う見果てむ〉となるのであるから。
それにしても、後ろ盾がないと〈紫の紙の、年経にければ灰おくれ古めいたる・・・〉という生活になり、片や生涯世話をする女を一人、二人とふやせる格差社会に驚きである。
〇夕顔のような女性を期待していた源氏は、心惹かれる所が何一つなかったことにがっかりして、早朝二条の院に帰ってやすむ。
今まで必ず出していたでしょう後朝の文を忘れるぐらいだから、そうとう落胆したと思います。それでも夕方には届けていないことを思い出し文を送る。気の毒なことをしたと思う気持ちはあるが、会いに行きたいとは思わない。
命婦より、この姫君の話を聞いた18才の春から季節は秋となり、並行して進んでいた「若紫」の巻が終わって、北山の少女は引取ったと思いますが、現時点ではまだ源氏は姫君の顔は見ていません。末摘花の勉強に入った時、姫君の顔を見た後で病にかかったと思っていましたが、まったく違うと言うことがわかりました。
〇常陸宮邸は、京の都からみると東海道の終わりの僻地にあるところではないが、源氏からみてもそんな邸と思われているのだろうか。
さすが命婦たちも、姫君が気の毒でならない。当の姫君は頭がまわらず、男の非を思うほど気がまわらなかった。
「雲間待ち出でむ」と月を待っている源氏の気持ちに対し、命婦たちが姫君に「月を待つ里である」と力強く書いた返歌を送らせる。
姫君をこのまま見捨てられない、素知らぬ顔をしているわけにもいかない。源氏は妻として世話をするとひそかに決意するのであるが、姫君の邸ではそんな源氏の気持ちを知る由もないので、悲嘆にくれている。
常陸宮のうらぶれた邸が、月に浮かぶのである。
〇貴族の教養として詩歌に力を入れていたと思いますが、姫君が歌の書き方も知らないのは、本当に不思議です。
世間知らずで、生まれた時から修道院で育った孤児のような感じです。
〇良きライバル同士の源君と義理の兄さんの のどかで さわやかな 朝ごはんの光景でした。
〇この項で、姫君とちぎったあとの源氏の何とも憂鬱なようす、そしてどこまでもチグハグな姫君、にもかかわらず「心長う見果ててむとおぼしなす」にいたる源氏の心根が、これ以上は考えられないほどのリアリズムで描きつくされています。
先生が「末摘花」はおもしろいと言われているのは、こういうところにもあるのでしょうか。
2014年6月12日「末摘花」感想
「君がしじま」を了えました。
〇いよいよクライマックスの場面となるわけです。
“されくつがへる今やうのよしばみよりは”と、源氏は朱摘花に期待して歌をよんだり、語りかけたり懸命につとめますが、一向にそれ以上には進みません。ついに耐えられなくなって押し入ってしまわれます。
命婦は“あなうたて、たゆめたまへる”と非難して立ち去り、姫君は“ただ我にもあらず、はづかしく”と、すっかり動転して我を失って、源氏は源氏で自分のした事に“うちうめかれて”“夜深う”“忍びて出でたまひにけり”となります。
何とも期待が大きかっただけに、後味の悪い結果になりました。“ものづつみ”のなせるわざとしか思われないと、ため息が出ました。
〇母屋の姫のだんまりは続き、源氏の妄想もふくらみ、ひとり相撲。白黒をつけて欲しいとせまる源氏の態度に心配した若い女房のとった行動に、源氏は姫と誤解、切々と気を引こうとする姿が何とも滑稽である。
それでも続くだんまりに、とうとう部屋に押し入り契る源氏。
姫を心配する命婦と若い女房達のとった態度が真逆なのは、人生経験のなせるもの?
素晴らしい女との契りを夢想していた源氏は、事実の虚しさに闇の中へと去り、姫は身の置き所のない時を過す事になる。
どちらもとてもかわいそう。紫式部は二人をどうしたいのでしょう。
〇廂の間に通された源氏は、襖障子を隔てた奥の母屋にいる姫君に語りかける。熱意をもって語りかけていた源氏も、返事のない姫君にだんだんと怒りを覚える、何十回も出した手紙に返事も無いのに、すぐそばにいるのに何も答えてくれない。強意のことばを重ねて姫君に返事を迫るが、いたたまれなくなった侍従が返歌を詠む。
これで打ち解けて語り合えると思った源氏だが、いくら巧みな話術を使っても、姫君のだんまりが続く。耐えられなくなった源氏は、襖障子を押しあけて姫君のいる部屋に押し入る。
それにしても馴れ馴れしい返歌を詠んだ姫君がだんまりを続けていて、何でだろうと不思議な思いを源氏はしたと思うのですが。
〇源氏が訪ねた女性のなかで、これほどこじれた関係はなかったのであろう。
鐘つきてとぢこめてしまい、「法華八講」の法会にかけたということであるが(天台宗の法華である)、歌に詠んで相手にわからせたいと思うのであるが、命婦の返歌しか得られない。おそらく、もんもんとしたやるせない気持ちをもちながら、源氏は屋敷をあとにしたに違いない。
源氏の人生にも、成功することばかりではないことだと、式部は物語りしているのであろう。
〇えびの香のかおりはわかりませんが、夜道で、クチナシやジンチョウゲがどこからか匂ってくるような、ああいう感じの香りが部屋全体に漂うのでしょうか。
〇心得ず なまいとほしと おぼゆる御さまに うちうめかれた源君。
お気の毒様です。
〇「ねたくて、『やをら』押しあけて入りたまひにけり」。この『やをら』を私は解説文にある如く、耐えられなくなった源氏が、今までこらえてきた口惜しさが一気に噴き出し、分別を失って「強引」に押し入ったと解釈しました。
ところが例解古語辞典や新明解古語辞典を見ると、いずれも「静かに、そっと、こっそり、おもむろに」となっています。また現代語の「やおら」についても、広辞苑は「そろそろ、おもむろに、しずかに」で新明解国語辞典は「目立った動きの見られなかった状態から、ゆっくり動作を起す様子」とあります。つまり「やをら」も「やおら」も同義であり、かつ「やわら」と同根のことばのようです。
私は、「静的な状態」から「動的な状態」に急激に移動するもの(注)と常々理解し使用していたので、全くの誤用であったかと、この「発見」に驚いた次第です。
たしかにこの項の最後で、源氏が「やをら忍びて出でたまひにけり」や、空蝉の「もぬけ」で小君が源氏を「影ほのかなるに、やをら入れたてまつる」は「静の状態」の儘がふさわしい。成る程。
しかし「もぬけ」の最後、空蝉が「やをら起き出でて、生絹なる単を一つ着て、すべり出でにけり」では、「動への急変」ととらえても強ちおかしくないのでは? いや下の品で漫画チックになってしまう?
ともあれ、私だけの誤用なのか、現代上方人はどうなのか、次回帰郷時に調べてみたいと思っております。「ことば」そして「その変遷」って面白いですね。
(注)「いきなり」に近い。
広辞苑:(十分考えないですること)出し抜けに。突然。または直接。じかに。
新明解:段階を踏まないで(それらしい前触れもなしに)決定的な事態が展開する様子。
2014年5月8日「末摘花」感想
「手引き」を了えました。
〇“宵過ぐるまで待たるる月” “星の光ばかりさやけく” “松の梢吹く風の音の心細く”そして“月やうやう出でて”と美文調で、忍んで手引きさせるには、この上ない情景となります。
式部はこれより源氏を“男は”と、男性としての源氏を表現し、物語りは一気に“やま場”を迎える事になります。
どきどきですね。
〇後見人を失った姫がどうなるか父君は充分知っていたであろうに、それなりの教養をつけ、教育をせずにいたのは何故なのか?
百人百様の女性が登場する物語故に、末摘花が選ばれどんな運命を生かされるのか、知らないという事は幸せか不幸か、これからが楽しみである。何しろ世の中の常識から遠い所に在り、久方振りの源氏の訪れにもおっとりかまえている姫なのだから。
手引をした命婦が、成就しないとみているこの恋の逢瀬に、源氏を思いやり、姫がふられて抱えるかも知れない悲しみや悩みを思い、気をもんでいるのは、自分が蒔いた種なのにおかしな図である。
〇源氏が常陸の宮邸を初めてたずねてから、季節は春から秋になり、やっと命婦の手引により姫君に会うことになります。
物語は進んで行くのですが、源氏が姫君の顔を見るまでに、時間をかなりかけてじらしているように思います。辞書によると末摘花は赤鼻の醜女と言うことですが、本当にそうなのでしょうか?
命婦は姫の顔よりも琴の力量の無さを気にしていたように、赤鼻でも顔全体を見れば可愛いい所があったように思いますし、見慣れた命婦が醜女だと思ったら、源氏に姫の話はしなかったと思います。
でも夕顔のような女性を想像していた源氏にしてみれば、おどろくとは思います。
〇八月二十余日ともなると松風の音も心細く、年頃の姫君も泣けるような気持ちになり、月の光も美しく、命婦がこのような時こそ、光源氏と逢瀬をつくることがいいのかなと思う。
しかし逢わせても、どうしたらいいかわからない。命婦の中でも、乳母など年老いた人たちはうとうと眠くなってきたが、若い命婦たちは浮き浮きして、源氏に逢えると思うと落ちつかない。
このような情景は、逢瀬の場としては適当なのであろうかどうか。姫君の気持ちは、手引をしても心苦しく気の毒な想いがする。
末摘花と源氏の舞台は、それなりに淡々と展開する。
〇二十日過ぎの月は下弦の半月ですから、暗く、気も沈む感じの月のように思います。 作者は、常陸の宮邸の陰気くささをこの寂しい月に語らせたのでしょうか。
〇いと尽きせぬ御さまの源君を迎えるに 当たって 姫君には 「よろしき」御衣しかな
いのだなあと つくづく かわいそうになりました。
〇物語は、「源氏と命婦」次いで「命婦と姫君」を軸に進行してきました。いよいよこれか
ら「源氏と姫君」となります。舞台はすっかり秋の気配に包まれた荒れ果てた邸です。
今日学んだ項だけでも、背景として「零落し荒れたる籬の宮家」「その落魄の姫君」、そ
の他の人物「夕まどひしたる老乳母」「心げさうしあへる若き人たち」などなど、心憎いばかりの構成です。
これからの展開に目が離せません。
2014年4月10日「末摘花」感想
「ものづつみ」を了えました。
〇“ものづつみ”と言う面白い言葉にすっかり嵌って了いました。
末摘花にぴったりの名稱だと思って考えてみますと、関係者は大輔の命婦、源氏の君、頭中将がいます。三名とも末摘花の“ものづつみ”にすっかり包まれて了って、どう仕様もない八方塞がりに陥っていました。
それぞれ突破口を考えて、一番先にあきらめたのが頭中将。次に命婦は源氏に責め立てられ、“あだめきたるはやり心”を働かせ、父君にも相談せずに、成行きまかせで手引をする事に決めます。源氏はもう我慢の限界でしたので、命婦に“うたてあるもてなしには、よもあらじ”と、命婦に安心させて決行に及ぶのですが・・・。
〇〈ものづつみ〉に対する命婦と源氏の思いの違いが面白い。男女の情が解っていないとする源氏の戸惑いは、姫に対し、またもや果てしなく素晴らしい妄想を拡げ、いだかせる。つれなくされれば追い求めるのが恋心!!
ひたすら逢瀬を願う源氏に根負けする命婦であるが、源氏とは釣り合わないと思っている事でもあり、逢ってからの姫君を気使う揺れる心情も持ちながら、手引を決心する。
父の存命中より世間とはかなり隔絶した生活だった様であり、姫君の浮世離れの様子がいかばかりか。理解にあまる行動を取る姫君に対する源氏の反応がどう出るか。
興味深く楽しみである。
〇夕顔への思い、失った悲しみは月日がたってもなくならない。命婦の話で、夕顔と同じ境遇の末摘花に興味を持ち手紙を出すが、返信がないまま夕顔が亡くなった秋が訪れる。その思いに耽り、秋の静けさの中で心に刻まれた女たちを思い出すが、やはり夕顔は忘れ難い。
〈常陸の宮〉の姫君のことが呼び起こされ、恋文を出すがやはり返信が無い。なぜ姫君が手紙を書かないのか? 容姿に関係があるのではないでしょうか。
交際の手紙、ましてや恋文など受け取ったことなどなく、お世辞でも美しいと一度も言われたことがなく、手紙をもらってもお返しの手紙を出さなければという気持ちにならないのは、女性と言うより、まだ少女のままと言う気がします。
〇父、常陸の宮が存命の時でも訪れる人はなかったのに、まして今は浅茅を分けて訪ねてくる人も絶えてしまった。源氏の匂いがただよう美しい手紙が時折届けられると、邸全体が華やいだ気分になる。
命婦や下女(なま女ばら)までも、手紙の返事を書かない姫君のことが気になってしかたがない。命婦の気持ちとしては、いよいよ姫君と源氏を逢わせる機会をつくらなければと思う。
式部は命婦やなま女ばらの気持ちまでも、妖しく女心の深層を描写する。
〇水茎のあとも麗しく、香を焚きしめた手紙が届いたら、いつもは暗い家の中も、さぞかしはなやいだ雰囲気に包まれたことでしょう。
〇源君の「その荒れたる簀子にたたずままほしきなり」が とてもおかしく 可愛く思いました。
〇文を出しても全く応答なく、色々思い巡らし苛立つ源氏。文を受けてもまともな対応が出来ない姫君。軽い気持ちで源氏に持ちかけただけなのに、源氏に責め立てられはするが、あだめきたるはやり心でうきうきする命婦。滑稽な場面です
2014年3月13日「末摘花」感想
「返りこと」を了えました。
〇ここの処は、すべて末摘花の“ものづつみ”でつつみ込まれた結果の事と思われます。源氏も頭中将もすっかり翻弄されたと思われてなりません。
末摘花に仕えている女房達は恋の道の方に馴れていないのか、末摘花自身が頑なな程“ものづつみ”が強くてお返事どころでではなかったと言う、何とも不思議な場面です。
その結果源氏と頭中将の恋の探り合い、鞘当てに発展し、源氏の方が少々執着が強い分勝って、次の場面に展開する事となります。
〇姫に妄想をいだく二人は繁く文をしている様であるのに、なぜ姫は返事を出さないのか? 侘しい暮らしに二人の男性からの文は、大きな希望ではないのかと謎である。
積極的な性格ではなさそうなので、恋のテクニックとしている様にも思えないが、期せずして二人の間で恋のさや当てが起きていて面白い。
ところで、主語の省略が多い文章は一行の中でも状況が変わり、読み解くのに苦しんでいるが、この時代の人の想像力の豊かさに舌を巻く。
現代人も、もう少し想像力が豊かになれば、人の痛みが解り、理解に苦しむ事件が起きないのではと思ってしまう。
〇源氏は常陸の宮の姫君に何通も手紙を出すが、返事がなく不愉快でならない。どうやら頭中将にも返りがないことがわかり、からかって見たい気持ちと競争心が涌いて来る。
早速妙婦の所に行き、姫君が何を思っているのか見当がつかない、見むきもされないのは何としてもつらいと訴える。
返信をしないのは姫君にその気がないのか? 命婦の策略なのか? 命婦が琴の音を少ししか聞かせなかったように、手紙を書く能力に乏しいので止めたのか? など、疑問が生じます。
今の所まだ分かりませんが、その内に判明するのでしょうか。
〇源氏と頭中将との確執はつづき、源氏は姫君を競争心の相手としてきたが、命婦は源氏の相手はつとまらないと云う。
しかし源氏にとって夕顔が忘れられない。夕顔に似た姫君にその面影を重ねてしまうのである。夕顔の死はおぼし忘れられない。
病気療養で訪れた北山での少女との出合いから、春夏の時間の経過があり、源氏の想いは「藤壺」に寄せるのである。
文章の省略があるが、事態は着々と進展する。
〇・今日学習した所まででは、この姫君はなぜ手紙の返事を出さないのか、さっぱりわかりません。姫君にアドバイスする女房もいると思うのですが・・・・。
・源氏は侘住まいをしている人は、身の回りのできごとに感じ易く、趣きのある人と思っているようですが、そんな筈はないと思います。
その日暮らしの生活で、心のゆとりがないと思いますが、源氏のような上流階級には、そんなことは、わからないのでしょうね。
〇笠宿りが 多くある人は 大変ですよね。
〇省略が多く読み解くのに難渋しますが、ここでは短い文章の中に、思うように反応してこない姫君をめぐって右往左往する源氏の姿が、てんこ盛りに書き込まれています。そこからは源氏の一面「滑稽さ」とともに、現代と変わらぬ恋に迷う青年の在り様が読み取れて、大変おもしろいと思いました。
また式部は、この項の最後に「夕顔」「藤壺」への源氏の思慕と、春夏の時間の経過にさらりと触れ、さらに読者をひきつけて行きます。それを僅か二行でやってのけるのですから、凄いなぁと言うほかありません。
2014年2月13日 「末摘花」感想
「常陸の宮の姫君」から「好敵手」に進みました。
〇源氏と大輔の命婦とは乳母子である。男子では有能な惟光の乳母子がいる。彼女は彼におとらぬ“かど”ある者と言ふ程で、なかなか才智に秀でた女性である。男の乳母子とは又違ったある種の親しみを持っている。
今迄なんで乳母子の女房が、いろいろ苦労して主人に難しい女性を取り持つため尽くすのかと、今一つわからない処がありましたが、小さい頃から同じ母からのぬくもりで同じ乳を貰って育った絆は、他の者の追随を許さず、わかり合える自然な関係が長年の間に出来上がっていったのでしょう。面白い古代事情とも言うべきかもしれません。
源氏は頭中将と一つの車に乗って、笛を合奏しながら大殿の屋敷に伺います。
〇姫君へまず興味を持ってもらわねばならない命婦は、源氏を上手く誘導し、次への逢瀬を期待させるという女房の役目をしっかりと果たす。
恋多き命婦は男心が良く解っているという事か?
乳母子故の、源氏と命婦の去り際に交わす軽口のやりとりが楽しい。
男としてのライバル意識と慕う気持ちのある頭中将が、源氏の後をつけ様子を探り、源氏と同じ様に末摘花を素晴らしい、いい女と妄想するところ、二人共に“狩衣姿のないがしろにて”と変装して女のもとに通うところ、コメディのような面白さと楽しさで笑える。
それと、源氏が自分の気の多い事を“咎”と意識しているというのは憎い事である。
〇源氏は、乳母子である命婦から聞いた姫君の話に興味を持ち、邸にやって来る。期待に胸ふくらませている源氏に、命婦は気転を利かせて姫君の引いていた琴を止める。これ以上聞かせると琴の技量が低いことがわかってしまう。もっと聞きたいと言う源氏に、命婦は姫君の暮らし向きなどを話し、気乗りがしないと言い、源氏を納得させる。
帰ろうとした源氏だが心残りで寝殿の方に向かうが、頭中将が気づかれないように後をつけて来ていた。その後、一つの車で左大臣邸に行き、笛に興ずる。奥で奏でられている琴の音を耳にして、二人共常陸の宮の姫君の琴を思い出す。二人共、美人で琴の名手であると思いこんでいる姫君が、あのような荒れはてた邸に暮らしている。切ない思いが伝わって来ます。
源氏と頭中将とが姫君の取り合いを行います。
〇源氏と頭の中将との攻めぎ合いの条。
源氏は北の方の待つ大殿に帰らず、二条の院にも向かわない。頭の中将は、源氏のことが気になってたまらない。源氏の秘密が頭の中将に知れていないことで優越感にひたる。しかし皮肉なことに源氏の秘密は夕顔の忘れ形見の女の子だ。その父親が頭の中将であることを右近から聞いているのである。
この二人は笛を吹きながら大殿の屋敷に着く。大殿は歓迎の高麗笛をふく。
中務の君の恋のもつれもからみ、意外な展開をみせる。いかなることになるやら。
〇・零落した悲劇の姫君という幻想に憧れと好奇心を抱く二人の公達の様子が、面白く描かれています。
・深窓の姫君はしっかりした女房たちに守られているのに、常陸の宮の邸には、女房はいないのでしょうか。ここに出てくる命婦は「非常勤職員」と思われます。
・立派な牛車が先払いの声もなく夜道を行き、中から笛の音が聞こえるという場面が、本当に美しい光景だと思いました。
〇若い命婦は 頭をくるくる働かせて 楽しく生き生き 暮らしているようですが、私には 何か 人知れない 彼女の寂しさを 感じています。
それから 中務の君のこと 私 大好きです。
〇今日学んだ箇所は、今風に言うと「公私共に近しい二人の青年が繰り広げる、勤めを終えた後の解放感に満ちた楽しいやり取り」を髣髴とさせ、現代の私たちにも通じる親しみの持てる場面でした。
一方、中務の君に触れた部分では、それとはまったく違った印象を持ちました。
何故か。二人から思いを寄せられた中務の君は、源氏の恋を受け入れています。また大宮は、中務の君が我が子の頭中将を振ったことに遺恨を持っています。奥には肝心の紫の上もいるはずです。しかも、これらのことは全て同じ邸の中で同時進行しているのですから。
この絡み合う五人のそれぞれの思いは、今の倫理観とは、かなりかけ離れているように思いますが、如何でしょうか。
さらに言えば、結局のところ恋多き源氏は誰からも責められないのです。不思議と言うか、何と言ったらいいのでしょうか。
2013年12月12日「末摘花」感想
「夕顔の面影」から「大輔の命婦」「常陸の宮の姫君」へと進みました。
〇末摘花に入りました。若紫の事は一時お休みで、源氏は今迄の女性の事を思い起こしています。
まず何と言っても夕顔の事、“夕顔の露におくれしここちを、年月経れど、おぼし忘れず、”と恋しく、又次に“かの空蝉を、ねたうおぼしいづ。”と今でもいまいましく心残りの思いが強い。それにともない“火影の乱れたりしさまは、”と荻の葉と慾張りです。
そんな折、今度は大輔の命婦の手引きで、琴の音に導かれて好奇心一杯、想像力全開で、末摘花が始まるのです。
興味深いですね。
〇夕顔の心のあり様や行動に思いを深くし、そういう女との出会いを希う源氏は、情報収集に余念がない。
そこに恋の道にたけ、臨機応変に対応する命婦の登場。源氏の好奇心に火をつける。命婦の手引きにより常陸の宮邸に忍び入り、ほんの少し掻き鳴らされただけの琴に素適な恋物語を空想し、ひたすらに出会う状況を思い描き、心ときめかす恋する男になる源氏。一人で空廻りしている様子がおかしく楽しい。
しかしながら、夕顔の死の失意の中、空蝉にさらりとかわされた中、その虚しさが取らせたのか、男心の移ろいの早さに脱帽である。
〇末摘花第1回目
今回から末摘花に入りましたが頭が少し混乱しています。
北山に療養に行く前の話で、夕顔を失い大変なショックを受けながら鳥辺山に行き、亡骸に会い、帰りに落馬して邸に戻るなり重い病にかかり、病床に臥してから始まっています。なぜ思い出したようにこの物語が始まるのか? 末摘花と出会っても病は癒えなかったのでしょうか? 逆に末摘花の顔を見て具合が悪くなってしまったのか? 北山の療養は末摘花のせい?
これからの勉強でわかって来ると思いますので楽しみです。
〇夕顔の露におくれしここちとして、年月がたっても恋い慕い悲しみを忘れることがない。夕顔を失った源氏は夕顔に代わる女はいなくなったと思うのである。
ここで夕顔のことを強調して源氏の気持ちを語るのは、式部の「語りのうまさ」というべきであろう。読者を引き付ける文章のうまさである。
場面は変わり、兵部の大輔の命婦の照会により常陸の宮の姫君と逢うことになる。琴の音が耳の肥えている源氏の鑑賞に耐えられるかと、命婦は「ハラハラドキドキ」するが、「ポロン」と掻き鳴らしただけなので、源氏は姫君を美しく思い描く。
源氏の夕顔を慕う気持ちの変化は理解できないという人もいるが、物語の面白さとして理解したい。
〇・「末摘花」の冒頭の文は、後世につけ加えられた文ではないかという感じがしました。源氏が今までに関係した女性を一人ひとり出してきて読者に思い出させるのは「前号までのあらすじ」のように思え、文のもつ調子も違っているような気がしました。
・なかなか源氏に靡こうとしない《つれなう心強き女》が、《名残なくくづほれて》しまうと、「なんだ、そんな女だったのか」と源氏は気持ちがひいてしまうとのことですが、そういう女こそ賢い女ではないでしょうか。
男に頼らなければ生きていけない世の中ですから、自分の一生を託せる人を見つけることが大事だと思います。
〇軒端の荻に関しましては、「さりぬべき風ある時にしも、おどろかせたまふことなけれ」です。
そのような戯れを再びして、「いと目馴れたるや」と言はれては源君も恥ずかしいでしょ?
〇大輔の命婦の手引きから、新しい物語が始まりました。この巻には、なにやら転調の趣が感じられます。楽しみがつきません。
2013年11月14日 「若紫」感想
「手習」「二つの邸」を了え、若紫の巻を閉じました。昨年の5月から、一年半に及ぶ長旅でした。次回から「末摘花」が始まります。どのように物語は展開していくのでしょうか。興味は尽きません。
〇若紫まで読み終わり、振り返ってみますと、以前源氏の後の方を学習しておりました事を思い出しました。その頃の若紫はと言うよりも、紫の上は、正妻として六条院を仕切っていて、何をやらせても他の追随を許さない、美しく、賢しこく、源氏好みに仕上がっていました。
ですから、この若紫は名の如く可愛いさ、幼なさ、あどけなさはとても新鮮でありました。源氏もお目が高いと言うか、随分と気を入れて育てあげた事でしょう。
始めから源氏を読んでみると、物語の組み立て方と言うか構成が良くわかって本当に良かったと思っています。
〇内裏へも行かず少女との時を過し、少女を育む環境を作っていく源氏。
ひとつひとつの仕草、眼差し、筆跡と全てに才能のひらめきを見、限りない魅力と愛おしさを感じている源氏の思いがあふれて、それが痛い程伝わり、胸がキュンとする思いである。
懊悩をかかえている源氏にとって、癒される別世界とよく理解できる。
少女と少納言の行方不明を知った兵部卿と北の方の、「あたらしかりし御容貌など恋しく悲しとおぼす」「くちをしうおぼしけり」の短い文の意味の深さに驚き、古語の深さに興味がつきない。
しかし、政略的な事は鎌倉、江戸時代そして現代にまで続いていると思うと、人間が不変的に持っているものかとも思う。
〇「瘧病」にかかった源氏が、療養のため北山に出かけた所から始まりました。
雀を追いかけていた少女が二条の院で生活することになりましたが、それにしても少女を大納言邸から連れ出せば、少納言が必ず付いて来るので、少納言が勝手に連れ出したことにすれば、父宮からの追及から逃れられると考えたのでしょうか? 最初から考えての行動だとすると、すごいと思いました。
少女は西の対を我が家と思い、源氏の深い愛情に包まれて育って行く。若紫が終わりました。
〇少女は父宮と生活を共にしていなかったので、父宮を思い出すわけではない。それよりも源氏の方になついて、源氏に寄添っていたいと思うようになる。
源氏は自然な心になぐさめられている。式部はこの夫婦を普通の関係でない「かしづきぐさ」(大切な遊び相手)というかわった夫婦関係のあり方なのだと、ほほえましく思うのである。
現代の男性にとっても、このような夫婦関係が存在するならば、うらやましき心地がするのである。
〇・現代では「やがて」という言葉は、〔しばらくして〕という意味で使われるが、〔すぐそのまま〕の意として使われていたのを初めて知りました。
「もてあそび」も然り。千年の間のどの時期に変化したのでしょうか。
・「若紫の巻」全般で人物描写もすごいが、情景描写もすばらしい。
北山の春を「四方の梢、そこはかとなうけぶりわたれる」とか、少女の顔つきを「眉のわたりうちけぶり」というところに、京都でいう「はんなり」という言葉が浮かびます。
〇紫の上の返歌は上出来で、源君添削の余地無し。
〇「北山療養」から始まった「若紫」は、「小柴垣の庵」「走り来たる女子」「少女の素姓」「意中を切り出す」「心中を訴える」「尼君の死」を経て、「少女との一夜」「決行」「二条の院へ」と展開し、「手習」「二つの邸」に至りました。
この間に「明石入道」「妻の一言」「密会」「懐妊」と重要な伏線が挿入されています。特に「密会・懐妊」はショッキングでした。
この大河小説の悠揚迫らぬ運びに、これからもどっぷりと身をゆだねて行きたいと思っております。
2013年10月10日 「若紫」感想
「二条の院へ」を了えました。「若紫」も、あと一回を残すのみとなりました。
〇源氏が始めて二条の院に迎えた女君は、若紫であった。併し、女君と言うには、いかにも幼い少女でありました。
源氏は、そのいたいけない少女に「今は、さは大殿籠るまじきぞよ」と乳母とも臥せさせず、又朝なかなか起きない少女をば、せめて起し、「かう、心憂くなおはせそ、すずろなる人は、かうはありなむや、女は心柔らかなるなむよき」と最初から手を抜かず教え諭します。
こうして源氏好みの、美しく、控えめで、賢い女君の基礎が築かれて行くのでしょうか。
何事も最初が肝心と感服致しました。
〇あれよあれよという間に新しい環境に移され、「わびしくて泣き臥す」少女。「ものもおぼえず起きゐたり」という少納言。その心細さうかがわれる。
少女は結婚という意識が確としていた訳ではなく、少納言は思わぬ形での結婚に、夫々複雑な思いと不安を大きくしているのが伝わってくる。
明けて目にする源氏の邸の美しさに気後れする少納言。趣き深さに感動し、受け入れていく少女。大人と子供の対称的な様子が面白い。
〇二条の院がすぐそばにあるのに、車に乗って移動してきた。源氏の素姓が一条天皇の関係者であることが判る。式部の筆先は当時の皇室に迫り、宮廷関係の読者はハラハラドキドキするのであろう。
ようやく起きた少女は絵に見入り、笑みを浮かべる。源氏も心をなごませる。少女の好奇心は「霜枯れの前栽」を美しいと思う美的なセンスもある。少女の警戒心は自然とほぐれ「げにをかしき所かな」と感嘆する。
式部は源氏の気持ちを代弁して「はかなしや」と少女のおさなさを表現する。
〇・少女は暗い中で源氏の邸に連れてこられて、少納言とも離されて、泣き出すのは無理もないことです。
・女ばかりの中で育った少女は、男性は僧都しか見たことがないでしょうから、着飾った四位・五位の役人を見てびっくりしたことと思います。
・当時の屏風絵は、唐風のものと、大和絵のものがあったでしょうが、源氏の邸には、どんな絵が描かれていたのでしょう。
〇私も こんなに かわいらしい 紫の上のような 女の子が 欲しい。
〇源氏は、遂に少女を二条の院に迎えることができました。
「少納言がもとに寝む」とのたまふ少女。「今は、さは大殿籠るまじきぞよ」と教へる源氏。明けて「さし離れて見しより、いみじうきよら」な少女の「御心につくことどもをしたまふ」源氏。「何心なくうち笑みなどしてゐたまへる、いとうつくしき」少女に、「われもうち笑まれて見たまふ」源氏。
こうして新しい生活が始まり、少女はそれになじんで行きます。
少女は、源氏のみならず私達をも魅了しました。
2013年9月12日 「若紫」感想
「決行」を了えました。
〇現代では考えられない結婚の形態であるが、それが普通であれば、何人もの妻がいても平常心でいられるのであろう。葵の君はその点、時代に即した女でなかったのが、一つの不幸だと思う。久々に訪れた夫に素直に心許せないのだから、可哀想に思う。
少女の情況の変化に、即行動を起す源氏は、いつもながらフットワークの良い事。
しかしながら、決断を下す迄の源氏の千々に乱れ悩む思いの数々は、皆納得のいくもので、決行する迄がスリル満点である。決断すれば行動は早い。あれよあれよという間に少女は御車の中の人となり、大きく運命が変わる事に。
そして源氏には、どんな難題が起こって来るのか楽しみである。
〇源氏は、父宮が明日少女を迎えに来ると言う惟光の報告を聞き、何とかしなければと頭の中を駆け巡る思いに悩むが、少女を連れ出す決断をする。
父宮が来る前に連れ出さなければならず、まだ夜が明けぬ内に出かける。
正式に挨拶をして少女を迎えるのは無理と判断して、少女の寝所に行き、抱きかかえて起すが、少女は最初父宮かと思い込む。源氏は父宮と思い込ませて少女を安心させようとするが、この部分がなんとなくおもしろいと思いました。
〇少女が、父親に引取られてしまう。源氏はその前に惟光に迎えの馬を走らせる。普通の女性ならもっと違う方法があったのに、彼女はあまりにも幼い故のことである。あとでどんなに悔やんでも致し方ない。ここは決断するしかない。
女房たちは源氏の行動を止めることができない。源氏の車に乗り込み後を追う。
これだけの場面が、早いテンポで転回していく。
〇・この時代に、地方との行き来が今ほど盛んではなかったのに、常陸の国の田植歌が都で歌われたりするのが不思議な感じがします。(特にあづま歌のような下々の歌を、上流貴族が口ずさむとは!)
・「しぶしぶ」という言葉から、仏頂面をした不愛想な女の顔が連想されます。
・自分の気持ちが満たされず、もやもやしているから「まあ、今夜は妻のところへ行こうか」と、のこのこと大殿の邸に出かけていくのは、少し虫が良すぎて、しぶしぶ顔をされるのも当然なようにも思います。
〇源君の頭の中に過ぎった「父宮の尋ね出でたまへらむも」の「らむ」で、父宮の若紫へ
の愛情が薄いことを源君は良く心得ていたのだと思います。
源君の反常識的行為は、いつもかなり理性的に遂げられているよう感じました。
〇「おぼし乱るれど、さてはづしてむはいとくちをしかべけれ」(思いは乱れるが、この機
会を逃したら後で悔やんでも悔やみきれない)。
世のことの決断の動機は、昔も今も変わりありません。結果「吉」と出るか、「凶」とでるかは神のみぞ知る。これが「人生」なんですね。
2013年8月8日 「若紫」感想
「父宮訪問」「乳母の立場」を了えました。次回はいよいよ「決行」です
〇養育を尼君にまかせ一緒に過していない父は、少女の心の中にある尼君への思慕の深さを思いやる事が出来ない。
“今は世になき人の御ことはかひなし。おのれあれば”とかなり冷たい。デリカシーのなさが思われ、引取られた後の事が心配になる言葉である。
少女との恋について世間体を非常に気にしている源氏。父宮の少女の引取りの命に従わざるを得ない乳母達。夫々の立場で保身をしている図は、今も昔も変わらないと面白い。
急展開している少女の運命。さて源氏はどうするのか? 興味と期待でワクワク!!
〇源氏が帰った日に少女の父宮がやって来て、父親である自分が引取ると申し出る。今まで引取れなかったのは尼君のせいで、北の方と疎遠になったと言う。少女の母親が北の方の嫉妬と嫌がらせで、苦しみ死んだことがわかっていないようだ。
少女をこんな寂しい所においておけない、自分の邸に引取るのが最善と判断するが、日が暮れると、少女が泣いているにもかかわらず言い含めて帰ってしまう。
一方源氏は、惟光を使いに出し少女の様子を聞くが、事が急展開していた。宮より明日御迎えに来ると言う。少女の着物を用意する乳母たちの姿を惟光が見て、源氏に報告する。
〇父宮のことを式部は「暮るれば帰らせたまふ」とつき放して描写するが、「いとかう思ひな入りたまひそ」と言いきかせるだけで、少女のかたわらに留まろうとせずに、時間が来たと帰っていく父君の姿をきびしくとらえている。
乳母は尼君をしたっている少女が、その死という現実をしらされて、少女の苦しみがわかるので、ただ泣くだけでどうすることもできない。
源氏本人は来ずに惟光を代理としてよこし、惟光に手紙を託す。乳母の気持ちは、自分の置かれている立場を意識して、態度を表すだけである。源氏のことを口止めをしたり、父宮の忠告として「子供でも男を近づけないように」と言われていることも、源氏に対する不信感も覚えるので、複雑な感情に陥る。
惟光はこの事情をつぶさに源氏に報告する。源氏は結婚の儀式をしていることは、あらゆる意味で相当でないと判断したのだろう。「ただ迎へてむ」と惟光に命令する。
惟光が少女の邸を訪ねると、乳母は父宮に明日は引取られていくと告げる。
事態は急転しながら展開していく。
〇・苦労することなく、のほほんと育った父宮には、相手の気持ちを汲むということは今まであまりなかったのでしょう。少女が泣き出したのを見て自分も涙ぐむのだから、あながち冷たい人とも思えません。
・着古した着物と、お香のよい匂いとのとり合わせが面白いです。萎えた着物には、饐えた匂いがセットになりそうな気がします。
〇心配事や病気で、食事が摂れなくなって面やつれした人を、美しいと見る当時の人々の風潮は、私にはよく理解できません。
特に幼い子の場合、可愛さは半減すると思います。
〇父宮の登場で物語は急展開します。
少女とのかかわりについて弁解がましい言い訳をする父宮、今すぐにも少女の側に飛んで行きたいが「さすがにすずろなるここち」の源氏、「いといたう面痩せたまへれど、いとあてにうつくしく、なかなか見えたまふ」少女。その少女を「なぐさめわびて、泣きあへ」る乳母、少納言から「あはれなる物語」など聞かされて右往左往する惟光、などなど、緊迫した場面のなかで、それぞれの人物が活写されています
見事と言うか、物語の展開がほんとに面白いですね。
2013年7月11日「若紫」感想
「少女との一夜」を了えました。
〇荒れた邸での嵐の夜は、源氏をこの家の主人のようにさせてしまう。
少女を守るという信念のもと、素早く寝所の中に入る。この源氏の行動力とその自然さは、育ちの環境からくるものか? 流れる様で、納得させられてしまうのは見事としか言えない。
しかし、満たされない源氏の足は途中の女のもとへ。男を待つ身でありながら、他で一夜を過した事を感じる女の、源氏を拒否する様は、女心の複雑さも思われ、切なく哀しい。
拒否されて邸へ戻った源氏は、少女の事を思い出しつつ快い眠りへ。気分転換の早さも驚きである。
〇荒れ放題の邸に霰がはげしく降りそそぐ。少女を置いたまま帰ることが出来ない源氏は、少女と御帳の中に入り、吹き荒れる嵐の夜をすごす。源氏の行動は少し異常と感じていた女房たちも、源氏を頼もしい人だと感じてしまう。
朝、嵐もおさまり、暗い空には一面の霧がたちこめている。帰路、女の家に寄るが相手にされず、やむなく自邸に戻る。
少女のことを思い出すと、少女の可憐さを思い出し、思わず笑みがこぼれる。振られたことなどまったく気にしない源氏の性格か? 今、源氏の中には、少女のことで一杯だったのでしょう。
〇風の吹き荒れる一夜、台風が来たのであろう。少女と帳台で過す。
源氏にとっては、一夜を共に添い寝したのであるから、責任を感じているのであろう。四十九日を過ぎてから、父のいる実家に帰ってしまうということも心配になり、自分のところへ来てもらいたいと思いながら朝帰りする。
途中、知り合いの女性の門口で歌を寄せるが、断られる。それも、源氏にとっては邸に戻る気になり、帰ってからも少女のことを思い出し、心がなごむ。源氏の人の良さと、平安女性の気高さを感じる。
四十九日を「なぬ なぬか」と「九九(くく)」で読むのは、数字の展開であるが、中国・シルクロードのインドより佛教と一緒に輸入された知識で、中国の「九章算術」が奈良時代に輸入され、日本で広まったという。
〇・姫君の御帳台の中に、若い男が入ったら、乳母はどんなに心配をしたことでしょう。私だって、少女がうちの子だったら心配でたまりません。女ばかりの中で育った少女の恐怖心も、いかばかりでしょう。
・「いざ、たまへよ、をかしき絵など多く、雛遊びなどする所に」と言う言い方は、「おじさんの家にはおもしろい絵やお人形が沢山あるよ。」という誘拐犯の言い方とおなじようで、源氏がこんなことを言っていいのかしらと思ってしまいます。
〇私が乳母だったら、源君の善意は熟知していても、姫君の御帳には入れません。
高貴な源君のご立腹を和らげるべく、極上の一首をひねり上げて謹呈致します。
〇今回は、迷うことなく思うがままに生きていく源氏の姿に、ある種の滑稽さを感じつつ、楽しませていただきました。
2013年6月13日「若紫」感想
「尼君の死」から「少女との一夜」に進みました。
〇いよいよ難しい段に入ったのですが、自ら“源氏の語りべ”と仰言っていらした村山リウ先生は“源氏は若い娘さん方とは読めません。何もかも知り盡した成人した女性方と読むものです。”と言われました。
そのお話から思いますと、この“きよら会”は、リーダーの先生から熟女数名、万年青年を彷彿とされる数名と、構成は完璧です。五十四帖と長い行程です。でも心棒がしっかりしてます。本当に心強い限りです。
本題に入りますが、御簾の様子は、源氏の仕種、言葉、実に流麗にして品よく、自信一杯に書かれています。これも尼君との約束「数まへさせたまへ」のお墨付きをいただいて、「『なぞ越えざらむ』と、うち誦じたまへる」と決行に及んだのでしょうか。
チャンスは逃さない機敏さ、実行力は、将来大物になるであらう事を予見されます。
〇忌明け後の夜、少女の邸を訪ねた源氏の、少女に会いたいという強い気持ちは、御簾の中にすべり入り、ついに少女と直接言葉を交わすという大胆な行動をとらせる。
“なよよかな御衣”“つややかで、ふさやかな髪”、少女の美しさを彷彿とさせ、うっとりさせられる。
暗い中での恐怖や恥らう少女に、源氏は思いを、どんな言葉を重ねて伝えるのだろうか?
〇源氏は少女のいる京の邸を訪れる。尼君に仕えていた女房の数も減り、邸は一層侘しげに見える。
少納言は、尼君の臨終の様子を涙ながらに源氏に語り、少女の身の振り方に話を移す。
尼君の娘がひどい目にあって死亡した、少女の父の所に渡せない、いずれ源氏に託したいとの思いを少納言は聞いていたが、少女が源氏と釣り合う相手とは思えず、困惑するが、客人の源氏を父宮だと思いこんだ少女が声をかけたことにより、源氏に近づいてしまう。
〇少女に会いたい気持ちは、「なぞ越えざらむ」という意気込みは、女房たちの心をとらえ、美しい声にひかれる。そして少女との一夜を過ごすことになる。
「この膝の上に大殿籠れよ。今すこし寄りたまへ」と、少女を自分の側に留めようとする。源氏は御簾に入って乳母をなだめ、このような子供をどうこうするわけではないと語るのである。
少女へのプラトニックラブを世に知らしめ、自分を見守って欲しいと源氏は想うのである。
〇短歌作りの心得がない私としては、和歌のやりとりが本の中に出てくる度に感心させられます。
ここに出てくる少納言も、以前に学習した六條の邸の女房も、源氏に歌を詠みかけられると、すぐに歌を返す、これには驚かされます。どちらも源氏の申し出をお断りする歌ですが、相手の心を傷つけずにやんわりと伝えるには、歌で返すのはすばらしいことだと思いました。
〇今日の源君の紫の君に対する扱いには、私はちょっと気にくわない思いがしました。
全て無責任で薄情な兵部卿が悪いのです。
〇源氏の少女へのひたむきな想いと直截な行動、尼君や女房たちの逡巡や苦悩、源氏を惹きつけてやまない少女の魅力や立ち居振る舞い、こうした事どもは、現代に生きる私たちにとっても、何の違和感もなく共感できるものです。まことに不思議な物語です。
更にあえて付け加えれば、父宮の北の方と少女の故母君との確執、それに父宮自身の存在感のなさと言うか、不甲斐なさも然りです。
2013年5月9日「若紫」感想
「少女の声」から「尼君の死」へ進みました。
〇年が年だものですから、人生終焉の場面は身につまされます。
“手に摘みていつしかも見む紫の 根にかよひける野辺の若草”
源氏が愛して愛してやまない藤壺の君、その血を引く愛らしい藤壺の姪の若紫、藤壺とは添い遂げられないならば、せめて血が通う若紫を手元において育てあげたいと思う気持、わからないではありませんが、私のように子育てに大変な思いをした身にとってみると、よくそんなしんどい事を考え、実行に迄及ぶ事と思いました。
さすがに“恋しくも、また、見ば劣りやせむと、さすがにあやふし”とあり、いくばくかの不安もお持ちだったようですね。
〇思いがけず得た尼君の見舞いの折に、少女へのひたすらの思いを伝えても、言葉を交わすことも許されない。
源氏の耳に入ったのは、思いをそのまま口にする少女の声。おおらかな少女の存在は、懊悩の中に在る源氏をどれ程元気づけていた事か、思うに余る。
尼君も空しくなり、少女の悲しみを思う源氏。
いよいよ、少女から若紫へとの展開が楽しみである。
〇源氏は何とか少女を迎えたいと、病で床に入っている尼君を必死に説得する。少女の行く末を心配していた尼君は、源氏に託す決心をする。
それにしても、少女の父、兵部卿とのよほどの確執があったのか、尼君の心の中には無かったのか? 重態に陥っていた尼君は山寺に移り、やがて死亡する。
源氏は、行幸の準備に追われたりして手紙を届けていなかったことに気づき、文を届けると、僧都よりの返信に死亡したことを知る。
〇平安京が都市発展をしたのが、遷都後百年位してからといわれ、繁栄していたのは左京で、右京はさびれていたらしい。
慶滋保胤が、六条坊門南の荒地を十余畝購入して邸宅を造った。天元5年(982)に著した「池亭記」に邸宅の記述がある。
奈良仏教を排除した平安京は、東寺と西寺しか創建されなかったという。
朱雀院は朱雀門の前にある。南の守護神であるが、嵯峨天皇以後の上皇の住まいである。
舞台は山寺、内裏、朱雀院と、平安京の地で展開される。
〇・この帖の帖名が「若紫」と名づけられたのが、「手に摘みていつしかも見む紫の・・・」の歌からだということが納得できました。意中の人、藤壺の「藤」から紫を連想し、姪の少女を、「紫の根にかよひける」と詠む式部の巧みさに魅せられます。
・尼君の死までの話と、藤壺の話が同時進行しているのですが、藤壺との恋は、だいぶ前のことのように感じられてしまいます。簡単な年譜のようなものを書いてみないと、よくわからなくなります。
〇「葦間になづむ舟ぞえられぬ」の「えられぬ」に、(彼の恰好良さは認めるものの)源君一流の自惚れを感じ失笑してしまいました。
源君の直筆の歌をお手本に、若紫の君の手習いが上達しますように。
〇「少女の声」の項の終わり、「秋の夕は・・・」から「手に摘みて・・・」の歌の前までの文章は、実に難解でした。
僅か4行ばかりの中に、藤壺への苦悩に満ちた思慕、少女を残して逝く尼君への心情、そして少女への熱い想い、また不安など、対象も時も違えた源氏の複雑な心の動きが、語り手の推量もまじえて、それも圧縮した形で天こ盛りに畳み込まれていて、導き手が無ければ、とても読み解くことができるものではありません。
源氏になじんで最早5年になりましたが、自らの拙さを、改めて思い知らされた次第です。
2013年4月11日「若紫」感想
「懐妊」から「遺言」へと進みました。
〇藤壺懐妊の話は源氏を動揺させるも、確かめる術もなく、うつうつと桜から紅葉へと時が過ぎる。
宴での管弦の響きに思慕の情をこめる源氏、その思いを受けとる藤壺、雅な楽の音と恋心の綾なす切なさにうっとり!!
深く思うと相手の夢に出る事が出来るという夢の考え方、今にも続いていて欲しかった。
そしていよいよ尼君からの許しを得て、若紫の後見人となれる源氏。命の長くない尼君の少女への深い愛情、「かならず数まへさせたまへ」にこめられた万感の思い、心残りを強く感じ、また次へと期待がふくらむ。
〇源氏は不安にかられ、夢解き人に自分のことではないがと、ことわった上で質問をする。結果は凶と出る。「このころ夢を占う人がいたんですね!」
やがて懐妊が現実のものとなり、どうしても藤壺の口から聞きたいと思うが、命婦は会わせない。やがて秋となり内裏では会えるが、その後遥かかなたの人となってしまう。
藤壷への思いで苦しみ続けるが、秋の終わりのころ尼君の容態を聞き、見舞いに行く。臨終の床にある尼君より、少女の後見人を源氏に託したいと願われる。
それにしても「ほだし」が「きずな」と同じ「絆」であるとは、知らないことばかりです。
〇場面は変わり、尼君を見舞う。山寺を下りた京の住まいを尋ねる。
尼君も少女を残して先立つことを考えると、少女の後見人を決めて置くのに、源氏に託するのが一番いいと思い、「数まへさせたまへ」と願い出る。「数まへ」とは、「妻として数に入れ、女性として内裏の生活をさせる」ということである。
ドラマは意外性をもって転開していく。
〇・懐妊した藤壷は《すこしふくらかになりたまひて》《面痩せたまへる》様子で、《げに似るものなくめでたし》とのこと。作者の頭の中には、モデルとなる美しい女性が身近にいたのだろうなあと思いました。
・女の家に出かけた晩は《月のをかしき夜》でありながら、《時雨めいてうちそそく》というのがちょっと矛盾しているように思いました。
〇帝の、皇胤を宿した愛妃への情愛と幸福感、源君と妃との恋情と絶望感が、管弦の調べの中に聞こえる感がしまた。
〇帝の藤壷への深い愛と歓び、源氏の藤壷への思慕と惧れ、桐壺の源氏に対する恋心と困惑、何という人間的な営みと言うか、どうしょうもない煩悩の縺れ。
一転、熱望しても果たせなかった少女への想いが、忍びたる所に向かう道すがら、偶然尼君を見舞ったことから、少女の将来を託される事になる。
式部の筆の運びは、心憎いと言うほかありません。
2013年3月14日「若紫」感想
「密会」から「懐妊」へと進みました。
〇“もののけ”とは現在でも伝わっている言葉でありますが、実に何と言ったらよいか不思議な魔力を持っています
当時の人がどうしようもない、理屈に合わない事が起こった場合等、“もののけ”によるものではないかと言う言葉で万事不都合な事、理解に苦しむ事に用い処理してしまった事は、無用な争いに及ばなかったり、事を収めるには非常に便利で、お互いを傷つけないで済んだのですから、賢い事かもしれません。
まずまずすっきりしないご懐妊でありましたが、“もののけ”で通って了ったのですから幸せというほかありません。それにしても女性だけに現れる生理とは如何とも仕方ないものですが、我々にとって悲喜こもごも一大騒動を生む事になるものですね。
〇藤壺の里下がり、源氏の行動は相変わらず素早く、魅かれ合う藤壺と源氏の逢瀬は夢のうちに成就。しかしながら、これから背負うものゝ重さを覚悟の上の藤壺と、ただひたすら恋い求める源氏との温度差は大きく切ない。
これからを不義の罪に苦しむ藤壺、けれどこの短夜の濃密な時は大きな歓びとして胸の中に息づくはず。公の立場と女としての気持をどう耐えていくのか、哀切であり、興味深い。
密会から懐妊へと、言葉少なく場面が展開していく古語の深さと広さに圧倒される。
藤壺との縁にある若紫の段に、唐突に著されたこの段、どの様にかかわってくるのかワクワクである!!
〇源氏は藤壺に逢いたいと思う気持のみ強く、藤壺は「体調を崩して里に戻っていた」ので見舞いに行かなければとか、身体の具合はどうかなど気遣う余裕がなかったようです。
懸命に王命婦を説得して藤壺に逢い思いをとげるが、懐妊する。その後も源氏は藤壺に逢いたくてしかたがないが、藤壺の身体、気持を考えることが出来るほど成長していないのでしょうか?
〇予習・復習はしないでいいとの講座を受けてきて、講師とMさんの朗読に至福の時間を過してきた。
「密会」の場は、現代語の意味ではそのとおりであるが、恋の記述としては最高の場面である。すべてを承知している命婦が「御直衣などは、かき集め持て来る」という表現の中に、「濡れ場」の最高場面(クライマックス)を表わしている。夢の中の出来事が現実となった。語り部は「はらはらどきどき」しながら続けるのである。
登場人物の登場と描写のたくみさを感じる。そして何故か復習したくなるのである。
〇・妃と密通して懐妊させてしまう等という大胆な物語が、当時は許されていたということに驚きます。時代がずっと下がって明治憲法の世となれば、紫式部は不敬罪に問われるのではないでしょうか。
・明治10年代生まれの私の祖母は、お風呂場を「おゆどの」と言っていたのを懐かしく思い出しました。
〇源君は、「何ともはや・・・、やめなよ!」と私が思うことを色々してきています。
美貌と特権を自負した、わがままぶりで困った君です。
でも 藤壺の宮への深い愛は感動的です。
〇密会そして懐妊、何と生々しくリアルな展開なのでしょう。源氏は恋一筋ですが、藤壺はそうはいかない。式部は女性の目でそれをしっかりと捉えています。この物語はロマンであると同時に教養書でもあるといわれる所以ではないでしょうか。
また男と女の織りなす綾は、千年を経ても何も変わっていない。このことにも今更ながら驚きます。
それにしても、現実に深く根をおろした女性に、男性は脱帽するしかないではありませんか。
2013年2月13日「若紫」感想
「小さき結び文」を読みました。
〇10才の美少女に結び文、18才の美少年が、ちょっと驚く事で、当時でも相当常識はずれの事でしたのでしょう。これに大人が入ると話は別で、何の見返りも無く、栄達も無い純真な恋文、それを大人相手にするのですから驚きです。併し考えてみれば源氏は妻帯しているし、朝廷にも出仕して、中将の位迄戴いて、生活力もあるわけではあります。
たまたま若紫の方に弱点が有ったわけで、都から離れた山の中、母親は早く亡くなり尼育ち、周囲の女房ものんびりと世話をしているだけ、父親は正妻に気を使いあまり娘の将来の事迄考えていない。可愛いい少女としては育ったが、将来どうのこうのと話は出てこない。
そこに一瞬の垣間見があったのである。油断すべからずである。
〇源氏の恋を成就させる為の行動力はたいしたものである。少女にたずさわる人々総てに、思いを伝えようとし、心情をつまびらかにする努力は大へんなものだと感心する。
そして、皆夫々が、源氏の洗練された美しさに心動かされながらも、幼い少女を託すことへの不安を取り除く事は出来ない。
源氏は、想いをとげられないこの恋心を、これからどうしていくのでしょうか?
〇忘れられない少女を、自分で育てたいと強く思う。
尼君に断られても、文をしたため、廻りの人達にも礼をつくしながら、自分の恋を通していく源氏。
いろんな歌を知っていないと、恋のかけひきも出来ない時代に教養を思う。
〇少女に想いを馳せる源氏は尼君に御文を届けるが、少女宛の恋文も同封する。
なんとか自分の気持ちをわかってもらいたかったが、快い返事がもらえない。そこで惟光を使者として山寺に遣わすことを考える。
惟光もあの童女に?と驚くが、なんとか源氏の期待にこたえようと、尼君達を相手に熱弁をふるうが、源氏に託された御文も、惟光の説得も、今回は実を結ばない。
久しぶりに惟光の登場でした。
〇源氏の小さき結び文に、尼君や女房たちは目を奪われる。手習い手本の仮名が書けない幼児に無理ではないかと尼君は想い言う。和歌を結び文で貰った以上、返歌として源氏の歌をなぞって「心とめけるほどのはかなさ」と、源氏の恋をかわすのである。
少女に対する源氏の心は「明け暮れのなぐさめに見む」と想う。純粋に少女を守り育てよう。自分がそれをしなければ、どうしても納得できないと期待するのである。その根底には藤壺の面影をみている。家系を感じている。それは、翌日の行動になって表れる。尼君の不安を取り除くのに、自分の誠意をわかってもらうしかない。それが恋の使いとしての結び文である。
現代感覚で源氏の行動を理解しようとするのは、危険であるとの指摘があった。
〇・少女を「明け暮れのなぐさめに見む」というのを、「なんてひどい!」と憤慨しながら読んでいたのですが、「凪ぐ」からの派生語と知り、納得しました。私は「なぐさみ」のニュアンスをもって浅い読み方をしていました。
・テキスト本には后腹のルビは「きさきばら」となっていましたが、先生は「きさいばら」とお読みになりました。一字違いで、ずい分上品な感じになるものだと思いました。「きさきばら」というと生々しい感じで、現代の「めかけばら」を連想していやらしさすら感じておりました。
・まだ「娘」になっていない「少女」を、若い源氏に預けることを渋る尼君達の不安な気持ちはよく分かります。源氏はきき分けのないわがまま坊やという感じです。
〇源君は 仮名だけでなく 真名書きも きっと姿良かったことでしょう。
好奇心旺盛で多弁の惟光君、けっこう楽しんで仕事しているようです。
〇少女の垣間見、葵の上との相克、そして藤壺の面影に似た少女への思慕の高まりと、舞台は畳み掛けるように展開していきます。読者は今や源氏の一挙手一投足に釘付けです。
2013年1月10日「若紫」感想
「妻の一言」を読みました。
源氏と葵の上との遣り取りは、千年の時空を越えて、現代の夫婦の日常の姿に近いものがあり、それだけに各メンバーの感想には何時にも増して想いが込められていると感じました。
私たちはこの物語から、これから先どれほど多くの事をくみ取る事になるのでしょうか。期待は深まるばかりです。
〇「妻の一言」は普通に読んで了うと、それだけの事ですが、“問はぬはつらきものにやあらむ”と言われると、又違ってきます。後目に見おこせたまへるまみ、いとはづかしげに、気高ううつくしげなりと、凛として気品がある。
源氏が以前夕顔をなにがしの院に連れて、隠していた顔を現した時、夕顔は後目に見おこせて“たそがれどきのそら目なりけり”といたずらっぽく言いますが、これは男になれた女の表現に思われます。
どちらが良い悪いというわけではありませんが、遊びに馴れた源氏と、深窓に籠もって女房達と暮す女君とでは較べようもない処で、この言葉は、葵の上の悲しくも精一杯の女としての、妻としての抗議と思われます。
源氏の君があまりにも幼く、あつかい下手で、葵の君がきっちりと端正すぎた為でしょうか。
〇引かれる様にして、無理矢理左大臣邸に連れられた源氏の、久し振りの葵の上との対面の場は面白い。
女君の“問はぬはつらきものにやあらむ”のひと言は、動揺した源氏に、言わずもがなの愚痴をならべさせる。千年の昔から男のずるさや、責任転嫁は変わらないと面白く楽しめる。
気高く美しい葵の上の万感の思いを込めたこの言葉が、痛烈な皮肉として、源氏に届いた事は小気味良く痛快。
〇都に帰った源氏を、左大臣は牛車の上座に乗せて邸につれ帰る。気がすすまない源氏だが、左大臣に言われると断れない。
何とか娘、葵と仲良くしてほしいと切に願う心遣いがわかる源氏だが、久しぶりに会う妻の身じろぎもせず座っている姿に源氏はいたたまれず、ついぐちをこぼし、反撃をくらう一言「問はぬはつらきものにやあらむ」と目だけ動かして言われる。
では最初に何と言えば良かったか。「しばらくですが、お元気でしたか?」などと言ったら、又するどい責め言葉がはね返って来そうだし、むずかしい・・・・。
〇左大臣は、源氏に牛車に乗ってもらい、娘の女君(源氏の妻=葵の上)は、父親の声にしぶしぶと顔を出す。源氏は、しばらく顔を会わしていないので、気まずい想いで恨みを言う。葵の上も、口を利かないでいることも、つらいものですねと冷たくあしらう。
重苦しい時刻は過ぎ、源氏は臥せていても目が冴えてくる。源氏の苦痛は、「なま心づきなし」との表現につきる。
作者の男性批判も込められているのであろうか。恋愛が自由な平安貴族社会において、女性の強さを感じる。嫉妬をテーマにして、物語として最高。
〇美しい蝋人形の夫婦を見るような面白い場面でした。
多弁に屁理屈をこねる源氏に、冷たいひと言をあびせて押し黙る女君。夫婦げんかの軍配は女君に!
年上女房でなければ言えないセリフだと思いました。
〇斜めに構えた葵の上と 源氏の対座の場面には 肩を凝らすものがありますが、同時に ほほえましさに近い おかしみがあります。
今のところ このあてびと(貴人)二人は 良い勝負。
〇私は源氏と葵の上の応酬を見て、「夫婦の確執」を超えた「破局」を想起しました。男のいい加減さに対する、妻の冷たく突き放した態度は、もう既に「愛」は失われてしまったことを示しているのではと思ったからです。
ところが、女性陣からは「嫉妬」の現れと言う指摘があり、この「受け止め方の違い」をどう受け止めたらいいのか、なかなか答えを見いだせないでいます。
まあ男の身勝手や、浅はかさであろう事は、大体見当がつきかけていますが、どうもそれだけではないような気もしたりして・・・。(いや、きっともっと根が深いのでしょうね)。
2012年12月13日 「若紫」感想
「送別の宴」「めでたき人」を了えました。
〇若紫を引き取りたいとの希いが終わりではないという予感を、尼君の筆跡の中に見出すとは、何という繊細な感受性だろうか。
山奥で過したわずかな時にかかわった人々全てへの細やか心配り。出会った人、かかわっている人々、皆が魅入られるのは、その美しさと共に大いに納得。
そして、若紫の少女の心にまでも、小さく恋心の火がついた様。どう変わって行くのか楽しみ!!
〇源氏の気高い美しさに聖は独鈷を、僧都は聖徳太子の百済より得た金剛子の数珠と、紺瑠璃の壺に入った薬、藤・桜などがついている贈物をする。金剛子の数珠は唐もようの筥に入れてさらに透きたる袋に入れて、五葉松の枝がついている。大事な物は幾重にも包装、必ず表に植物をつけて、とても美しい。
「めでたき人」
若君・雛遊びにも、絵描いたまふにも、源氏の君と作り出でて、きよらなる衣着せ、かしづきたまふ。
ここの場面はとても大事な所のような気がする。
〇僧都、源氏を盛大に送り出さなければと意気込む。聖が護身用の《独鈷》を贈るのを見て、聖徳太子が百済から手に入れたという《金剛子》でできた数珠と紺瑠璃でできた幾つかの壷を献上する(勝った!!と思ったかどうか?)
それに対して源氏は、聖をはじめてして読経をしてくれた多くの法師たちにお礼として贈り物を渡す。
病状は聖の加持を受けてもその日のうちに帰れるようになるとは思っていなかったでしょうし、聖の勧めもあるが、気持ちは最初からもう一晩山に泊り治療を受けることを考えていたのではないでしょうか。世話になった人たちへの贈り物も出かけるときには考えていたように思います。早く治して都に帰らなければ帝が心配するだろうと心を痛める。
このように気配りの出来る性格が多くの人々から愛されて、高価な贈り物も源氏なら惜しくないと思わせてしまうように思います。帰ろうとしたとき、突然源氏を愛する大勢の迎えがやってきて花見の宴が始まる、すすめられて源氏も琴をかき鳴らす。そして北山の人々に大きな感動を与えて都に帰っていきます。
〇めでたき人かなと見られた源氏の意中の少女がかしづき、きよらなる着物をきてはべる。
日の本の末の世に生まれたまえと末法社会に僧都も、山の鳥を驚かせてくれという。
藤壺の宮に想いを起しながら、源氏にもらはれたらと言うことに率直にうなづく。ひな遊びの内裏やお絵描きにも、源氏を想像し、恋心が芽ばえる。
〇よしある手の いとあてなるを、うち捨て 書かばやと 思へど あたはず。 いとうし。
〇雀の子を追っかけていた幼い少女の心に、源氏に対する憧憬の念が芽ばえた事、また、僧都をして「何の契りにて、かかる御さまながら、いとむつかしき日本の末の世に生まれたまへらむ」と言わしめた、当時の時代背景に興を覚えました。
2012年11月8日 「若紫」感想
「送別の宴」に入りました。
〇今日の「送別の宴」の出だしの“暁がたになりにければ”からの文章は実に流麗で、深山のまだ明けるには間がある様子が、現在では想像するにしても何か夢の世界、幻想の世界に入り込んだような気分にまでなりました。
優曇華の花にしても、三千年に一度花が開くと言われているそうですが、三千年と一口に言われても、考えてみるととんでもない年数ですし、その花をあんなに数を集めて映像で見せて頂く時代になった事は非常な驚きでありました。
〇深山おろし、読経に響き合う滝の音、鳥のさえずり、鹿の歩く姿、錦を敷けるという木草の花々、そして山桜、何と素晴らしい深山の自然の美しさでしょうか。
想像するに心おどります。
また、かなり俗世間の匂いを残す僧都の、源氏への思いの強さのあれこれ、もてなしへの大へんな働き、その美しさに感極まって詠んだ歌等々、ほほえましく楽しく思えました。
それにしても源氏はどんなに美しかったのでしょうか?
〇源氏の晴ればれとした気持ちが、大変良くわかりおもしろかった。
やまいもいえる程の、良い事があった北山療養だったようだ。
〇僧都の勧めで、生まれて初めて山深い北山の寝所で一夜を過す。
尼君の心を許すことはなかったが、自分の思いだけは伝わったという気持ちで爽やかな朝を迎える。たった一日の山籠もりで身も心も癒されたものを感じる。私も4年前に高野山の宿坊で朝を迎えましたが、身がしきしまる思いでした。
それにしても同じ一泊二日でも源氏は病を治し、これからの人生にかかわっていく人との出会い、夢のような美しい景色を堪能し、多くの新しい発見などを経験する。
入山した時と違い、僧都は盛大に送り出さなければと張り切る。僧都の源氏に対する思いは「優曇華の花」に巡り合った心地であるという大げさな言葉で伝えられる。困惑する源氏。それにしても、私には考えられないような、長い二日間でした。
〇「送別の宴」の條に入った。
年老いた僧都は若き源氏に杯をすすめ、自分の気持ちを語ることになる。源氏を見送るのに修行中の身であるから、一緒に山を降りる訳にはいかない。それだけに、言葉の上で気持ちを込めて名残を惜しむ。
山桜は心深いもてなしである。源氏はそれに「山桜風よりさきに来ても見るべく」と応え、僧都は源氏の素晴らしさをあらためて間近に感ずるのである。
三千年に一度の「優曇華の花」に例え、最大限の賛辞を送る僧都、それに暫しはにかむ源氏は、天台法華の世界に浸っていた。
〇山の中の朝と夜が、読経の描写で書き表されている。
夜・・・すこしねぶたげなる読経絶え絶えすごく聞こゆ(子守歌風)
朝・・・懴法の声、山おろしにつきて聞こえ、滝の音に響きあひたり(目覚まし風)
〇源君の歌にあった「風より先に花を見に行く」という表現、気に入りまして、使わせてもらおうと思いました。又 UDONGE-NO-HANA(僧都の見事な歌ではありましたが)これも ちょっと楽しく使えそう。
〇「聴覚・視覚を総動員した絶妙な風景・自然描写」「人と人とのかかわりと,それぞれの心の動きの深い洞察」「驚くべき豊富で広範な知識」そして「たくまざる物語の進行」。
これらのてんこ盛りの魅力を味うには、月一回の講読ではまどろっこしい想いがつのるばかりです。
2012年10月11日「若紫」感想
「眠れぬままに」「心中を訴える」を了えました。
僧都に意中を切り出した源氏は、素っ気なく拒絶され、まどろむ事も出来ない。そして尼君にも心中を訴えます。
〇源氏と若紫との出会いは、源氏の一方的な垣間見から始まる。
本人の意志もなく、ただただ源氏の一方的な思慕から始まって、後見者の尼君との遣り取りで進んで行く。
当時でも源氏の言動は非常識で、尼君が非常に困惑されたのは当然であり、源氏に対する対応にも苦慮された事でしょう。
それでも凛とした態度でお断りなさるところはご立派です。併し、確たる後見人でない後見人の悲しさ、悩みも又深刻です。尼君を苦しめるのも事実です。
“生ひ立たむありかも知らぬ若草を
おくらす露ぞ消えむそらなき”
〇心と身体を癒しにきた山奥で、またひとつ憂いに出会った源氏。
藤壺との縁のある事も解った若紫への恋心を、成就させる為にとる諸々の策と行為。
思いをかなえようとする時の、源氏の行動力と頭の回転の良さに敬意を表します!!
僧都にも、尼君にも拒絶されたこれからの源氏の動きが楽しみ。
そして、父親兵部卿の娘へのかかわりが見えないのは疑問。
〇僧都に拒絶され気力も失せた源氏だが、尼君と女房たちの気配に慰められて、徐々に自分らしさを取り戻して行く。尼君に取りついでもらい、心中を訴える。
尼君は源氏の言葉に心を動かされるが、真意は伝わらない。
そこに僧都が戻ってくる気配がして、屏風を閉める。
〇源氏の少女に対する気持ちが、眠れない夜を迎えてしまった。
「初草の若葉」に見立て、結婚を申し込んでしまう。
尼君は返歌をするのであるが、あなたの涙(露)は本物ですかと疑ってかかる。
次の展開は、源氏としてどうしても心意を伝えたいのだが、男としてではなく、母親のような気持ちで少女を守りたいと尼君に訴えるのであるが、源氏の言ったことに信用できると信じられるが、尼君が、断ることがよしとする「大人の考え」を述べざるを得なかった。
源氏は自分の意見を表面に出したことで、満足感を感じたのだろう。
〈僧都の登場により、場面の展開が気になる〉
〇現代人のように、夜ふかしをすることのない当時の人々にとって、初夜の読経は子守歌のように聞こえたことでしょう。
〇高校生の坊やが、まだ幼な気の女の子を愛しく思って、胸を痛めたとしても不思議はないでしょう。まして源君の場合、この女の子は特別な子なのですから。
しかし、体の弱っている尼君にとっては、迷惑な話ですけど。
〇「うちつけに、あさはかなりと御覧ぜられぬべきついでなれど、心にはさもおぼえはべらねば、仏はおのずから」、「あはれにうけたまはる御ありさまを、かの過ぎたまひにけむ御かはりにおぼしないてむや。」、「いふかひなきほどの齢にて、むつましかるべき人にも立ちおくれはべりにければ、あやしう浮きたるやうにて、年月をこそ重ねはべれ。」、「同じさまにものしたふなるを、たぐひになさせたまへ」。
これほどひたむきに、おのが心を人に打ち明ける事ができるでしょうか。さすが源氏ですね。また、少女への想いがいかに深かった事か。
●去る10月3日、浄光悦然さんが急逝されました。熱心なお仲間をうしない、寂しい想いでいっぱいです。つつしんで故人のご冥福をお祈りいたします。
2012年9月13日「若紫」感想
「少女の素姓」「意中を切り出す」を終えました。
〇今日の源氏は、若紫の運命的な出会いから次々と想像がふくらむ様子が、僧都をまじえて事細かに描かれていて、興味が深まりました。僧都の「そもそも女は、人にもてなされて大人にもなりたまふものなれば」で現されている。
〇少女の全てを知りたいという源氏の想いは、僧都の説法も上の空で、とんでもない話を作り上げて聞き出す。
ブレーキがきかなくなり、いわずもがなの事柄を並べ、後見の事迄言ってしまう。僧都よりの素っ気ない答えに茫然となる源氏。
ただひたすらの一途さと、若さ。源氏が可愛く楽しかった!!
〇僧都は源氏を客人として迎え入れて説教を始める。最初、源氏は身を固くして耳を傾けるが、藤壺のことで心の奥深く自分を苦しめていることに思い至る。
僧都の話を聞いて、その少女の父親が藤壺の兄にあたる人とわかり、なんとかして自分の妻にしたいと僧都に話すが断られる。
今回の勉強で、父親の兵部卿が頼れないことがわかり、少女を懸命に育てようとしている尼君の気持ちがわかりました。
〇源氏は藤壺に対する気持ちが持続していたのだが、娘に逢ったことで、自分を失ってしまったことで、意中を僧都に切り出す。結婚相手として、言い出してしまった。
当時の僧は、天台宗の中でも法然などは浄土教を広めていたが、この僧も、阿弥陀仏の堂に参拝していた。平安末期の末法思想が広まっている時代背景があった。
源氏の把えれない恋愛至上の考えは、対立思想として末法思想を対置した式部の構想は、文学的思索の深慮を感じるのである。
〇「若紫」における源氏が、若紫への想いを僧都に伝える時、情熱のままに語る源氏と、冷静な反応を返す僧都の対比が面白く感じられました。
源氏はまだ若く、少女若紫への感情を素直に出しているが、源氏の恋愛感情は、社会の常識からすればいささかいさみ足のものであった。
恋愛とタブー、そしてそのタブーを情熱で越えていく源氏の生き方。
仏法からすれば宿世、因果である業の定めを背負いながらも、源氏はやはり自己の恋愛感情にみちびかれて人生を歩んでいく。源氏は人生をその時その時の心のままに生きており、色好みに徹し、しかしドン・ファンというよりは自然な感情として、恋愛に生き、権力にも志して生きていく。
若い源氏はしかし、その原点として「若紫」で、あどけない少女である若紫に恋をし、人生をスタートさせていく。源氏の原点である「若紫」は、そういった「源氏物語」全体のスタートラインを引く作業の巻として、初回、読んでみました。
《今回初回ですが、今後末長くよろしくお願いいたします。》
〇・お堅い僧都が「うち笑ひて」というのは、自分の説教の内容がこの若者には難かし過ぎただろうという反省もあっての笑いだと思いました。
・本文の中の「 」でくくられた話し言葉は、とても現代では読みづらいです。
・僧都にとっては姪の痛々しい死だけでもつらいのに、ましてやその姪の子まで妻を持つ男には渡したくはなかったとことと思います。
〇源君は、若紫を見付けてしまったら夕顔への深い悲しみはあっけなく消えてしまったようで、夕顔がとてもかわいそうと思いますが、忘れてもらった方が、人は成仏しやすくなるかもしれません。
〇少女の素姓が明らかにされ、源氏はひたむきに少女を求めます。でも当然の如く、それは壁にぶつかり、直ちには想いを遂げることが出来なかった。
今日読んだところは、以上の如くです。
しかしこのやりとりの中に、「この世に起きていること」「それを支配する掟」「それをめぐる人々の複雑で微妙な心の動き」「源氏の人となり」などが縦横に書き込まれています。
それらを知る事になった私たちは、一月後が待ち遠しくてならないのです。
2012年8月9日「若紫」感想
「尼君の心配」から「僧都の坊」へと進みました。
〇余命の知れないと思う尼の、自然児のようなおゝらかな少女への深い想いが伝わってくる。
僧都のかなりの俗世間ぶりも楽しいし、それが、美少女への複雑な想いをもった源氏を少女へと近づけていく場面へ移って行く事にもなる面白さ!!
確かな男の後見がなければ、豊かな人生のないこの時代の女性は何と大変だったか?
作為的に過ぎず、かといってチャンスは作らねばならず、周りの苦労、自身をみがく苦労、あゝ大変だあ~。
〇源氏は、かわいい少女がどんな人か大変気になり、尼君の話を聞き格式高い人だと分かったり、あまりのかわいさが目に焼きつき、一目ぼれのよう。
運命的な出会いの場面が感じられる。
〇少女は美しさをみがくことにほとんど関心がない。女にとって髪がどれほど大事なものかも自覚していない。このことに尼君は養育が十分できなかったと責任を感じて泣いてしまう。
一方、源氏はこのような愛らしい少女に惹かれ、運命的なものを感じてしまい「明け暮れのなぐさめにも見ばやと思ふ心、深うつきぬ」と気持を固める。
〇一千年前の平安末期、律令社会の宮中生活を、式部が漢字交じりのひら仮名で物語りが展開される。ひら仮名は日本語の表現として適している。
源氏の心をゆさぶる少女との出合いに運命的なものを感じる。
若紫の巻の展開は、少女の存在感に心ひかれる源氏の心を垣間見るのである。
式部は日本語を巧みに操り、私たちに日本語の美しさ、すばらしさを教えてくれる。
〇今日の段は、これからの源氏に新展開のある事を予測させ、色々と想像をふくらませます。
十歳程の女の子が既に女性と見なされる事は、何を基準としているか考えさせる。平均年令が三十台位ではなかろうかと想像致します。
今後の展開が楽しみです。
〇・夕顔の亡骸をうわむしろに押しくるんだ時、黒髪がこぼれ出る場面を以前学習しました。今回は悲しみのあまり打ち伏す少女の髪が、肩にこぼれかかる場面にであい、「女は髪がいのち(・・・)」の時代がよくわかります。
・仏につかえる尼が男性に顔を見せない風習は、現代のイスラム圏の女性に似ていると思いました。
・いくつものお香が、ひとつ部屋にまざり合っているとどうなるのか、ちょっと想像できません。
〇聖の験力で源君は元気になったみたいです。季節は春ですが、何とまあかわいい童女といい、遣水に映る篝火といい、源君が深山での、束の間の思い出深い夏休みを送っているような気がしました。
〇少女が決して低い身分の出ではないと窺われるのに、どうして尼君が「ただ今おのれ見捨てたてまつらば、いかで世におはせむとすらむ」と、絶望的な思いに駆られるのかとの疑問を持ちました。母はなくとも父がいるのだろうにと思ったからです。
しかしそうは行かない事情があるらしく、次回以降の源氏と僧都とのかかわりに注目して行きたいと思いました。
このように、どうして、どうしてと読む者に思わせたり、巧妙に伏線を張りめぐらしていく式部の筆の運びに、いつもながら感じ入っております。
2012年7月12日「若紫」感想
「走り来る女子」を読みました。幼い若紫の劇的な登場です。その肌理細やかな描き方に、今までにない筆の運びが感じられ、印象的でした。
又先生から、明石の君との対比についても注目するようご指摘がありました。
〇昔々の事となりますが、17、18の少女を相手に、老教授(竹島羽衣)が自分の孫に話すように、相貌をくずし、嬉しくて楽しくてと言う感じだったこの若紫の出現の場面。
今となっては“髪は扇をひろげたるやうにゆらゆらとして”に感動しますが、当時は、犬君がのがした雀の子の方が面白く感じ、ただただ先生が老年なのに初々しい楽し気だった有様が、懐かしく思い起こされました。
〇ゆとりの時間の出来た源氏の好奇心が、若紫を見つけるチャンスを作る事になる。
女の子で、10才程で、涙の跡を残した顔で、しかも走って来るという登場の仕方は、若紫の天真爛漫で、生命輝く溌剌さと元気さにあふれ、素晴らしい。
そして、その面差しに、深く思いを秘めている藤壺を見るのだから、源氏の動揺の大きさがわかり、興味が次から次へと・・・・・。
〇女性の美しさをこと細やかに、色もきれいに表現され、ことばがむずかしく、なかなか大変だけど、宮永さんの朗読で、目の前に物語りが良く見えるようです。
〇最初、源氏は供人たちの話に、明石入道の娘に興味を持ったようだ。
そして、帰京する予定が泊まることになり、気になっていた小柴垣の庵に足をむける。ここであどけなさの残る美しい少女に魅せられる。
しっかり教育を受けている明石入道の娘と、自由に育ったように見える若紫とを出して、若紫を主役に登場させて、入道の娘はこの物語からしばらくは消えるのだろうか?
〇雀の子のことで、気持ちが一杯になっている少女は、後見の尼君の説教を聞いているのであろう。
あどけなさの残る少女の美しさに、源氏はすっかり魅せられてしまう。心をときめかされ、「らうたげ」「いはけなく」「いみじううつくし」などの表現がされている。
心に秘めていた恋心が苦しく甦り、悲しみで涙が溢れるのは、あの人「藤壺」に似ていることを思い出している。
美しい古語の世界に、時間の存在をかみしめながら、ひとときを過しております。
〇源氏の人を思う心は、その生いたちにあると考えています。
母の愛を知らぬ子供は、大人になったらどの様に家族のふれ合いを作っていくか解らないのではと想像します。
源氏は、愛と恋が混同し、女性に憧れをもって接触し、それが全てに勝る価値観であったのではないでしょうか。一人の女性にではなく、全ての女性の内におのが心を合わせ、その都度に感情移入をしていたのではと思います。
源氏は、紫式部の周囲に実在した男性ではないでしょうか。
〇・やっと若紫の登場です。ゆくゆくは高貴で理知的な紫色がぴったり似合う人になるけれど、この段階ではまだ自然児そのもの。たんぽぽの黄色みたいな感じの少女です。
・色で性格、立場、運命などを表わしていく紫式部の美への感覚のすばらしさに、感じ入ります。
〇顔がふっくらとして 美しい目もとの まだ40位のこの尼君の病気は 何なのでしょう。こんなにも 稚なく あどけない たまらないかわいい姫君を残して 死んではいけません。
〇源氏にとって、若紫は藤壺に次ぐ位置を占める女性になるのではないかと予感しました。若紫について、これ以上はないと思われるほどに筆が尽くされています。
「若紫」は、大きな構想を踏まえた帖になるのではとの期待を込めて、読み進んで行きたいと思っております。
2012年6月13日 「若紫」感想
「明石入道」から「海龍王の后」へと進みました。
「若紫」は「桐壺」に続いて、物語のメインストーリーを形成する「帖」だそうです。きっと源氏の運命を大きく動かしていくことになるのでしょう。
その証と言うか、メンバー各位も期待されている通り、のっけから「小柴垣の庵」「明石入道」と、相次いで意味深長な伏線が登場してきました。
先生からも、原文の中に埋め込まれている深く広い内容を、的確に読み取るようにとのご指摘がありました。
従前にもまして、心して、「若紫」を読み進んでいくことに致しましょう。
〇明石の入道の話は、これからの物語に非常に重要な事と思って、身を入れて拝聴致しました。とても独りで読んではなかなか難しく、興味深かったです。
殊に入道の先を見る眼が深遠で野心満々で、こうでなければ、後の幸運・栄達は得られないものとよく分かる気がし、先が楽しみです。
〇明石入道の、高貴の血筋に生まれながら、地位争いに敗れての身の処し方がすごい。
見栄も外聞も捨て、屈辱を内に秘め、返り咲く為に選んだ国守で思い通り巨万の富を得、その財力で娘を上の品へと創り上げる執念もすごい。
下心と野心がうかがえ、源氏がどうからむのか先が楽しみ。
〇明石の入道 野心家。身分を下げて財をたくわえ 都へ戻るため むすめを女房にすべく 並々ならぬ 教育をする。大変おもしろかった。
これからも 入道が出てくるらしいので 楽しみです。
〇源氏は良清による入道の話を聞くうちに、その娘のことが気になって来る。
この娘が若紫かと思ったが、違うとわかる。
この入道、娘によって野心を実現させるのか? あるいは娘だけが出てくるのか。娘の名前はまだわからない。楽しみです。
〇平安時代の貴族、国守などの生活や思考が、現代の社会からみて理解できるということは、いかなることか。
地位よりも財力が大切であるとしつつも、地位の世界も捨てられないという明石入道の心情も理解できるのである。
娘を登場させる前に、明石入道の人柄を供人に語らせているのは、式部の巧みな文章表現なのであろう。
平安時代の荘園制度が崩壊していく過程で、貴族の国守、武士階級の台頭・対立などの葛藤が始まる前の実際を感じさせるのである。
〇明石入道の心意気に痛感する。家族のために山奥に入らず、海づらに住むところは心やさしい。
〇明石入道が親として娘を思う気持は、古今の違いがあっても変わらぬもののようです。
しかし、娘の幸せの尺度には、現代とは大きな違いがあるようです。
一人娘への男親の想いは、時に理解しがたい事があります。
〇“法師まさりしたる人”・・・現代では、瀬戸内寂聴さんを思い起こします。
“尋ねとる”・・・財力にまかせて優秀な人材をスカウトするのは、現代ではジャイアンツ。
平安の頃には、法皇とか清盛とか、この明石入道とか、仏の道を極めるための入道ではなく、出世の手段として一般的だったのでしょうか。
〇もしも 私が宿世を嘆いて 竜王様の元に行こうと 元気よく 海に飛び込んで、挙句、途中で「みるめ」に引っかかって、うっとうしい奴めと その白い目でみられたら どうしましょう。
源氏は ふと スパイシイな事を 言う人ですね。
〇明石入道の人物像が、短い文章の中に多面的に描かれています。そして娘とのかかわりについても然りです。しかしこの伏線は「若紫」では伏流水のままのようです。何故なのでしょうか。
2012年5月10日 「若紫」感想
「北山療養」から「小柴垣の庵」へと進みました。
いよいよ「若紫」の幕開けです。
〇平安時代は医者もまだいない頃で、加持祈祷しかなく、皆大変困った事でしょう。平均年令も低く、自然と生きられるだけ生き、死ぬ時が来たら、祈りのみで生を終える。
今の事を考えると、ちょっと羨ましいような気がします。
手術もないし、点滴もないし、おびただしい管もなく、死なせなく、生きさせられる。ぞっとしますね。
〇上の品の社会も、窮屈な事が多々あるものと、興味深い。
加持祈祷をする僧にも、夫々の階級向けがあったり、自由な外出の許されない源氏の、美しい風情の景色を絵に見たものだと感激する様は、かわいそうでもあり、ほゝえましくも思う。
ちょっと斜にかまえた僧の、源氏と解って興奮する様、拒否された訪問を、それ故に身をやつして訪ねる源氏の好奇心の強さ。
楽しく「若紫」が始まりました。
〇源氏は、上流社会とは関係ない僧に興味を持ち、いかがはせむと、わざわざ出かけて行く、とても行動的な人物だと思った。
医者の無い時代の治療法が、現代のとげぬき地蔵でも見られるように、今でも日本人の心に受け継がれているのが面白いです。
〇源氏は、瘧病という原因不明の病気、間欠熱を発症する病にかかり、困り果てる。
八方手を尽して、北山のなにがし寺という、苦行を積んで法力を得たという僧に使者を使わすが、来てくれない。僧の器の大きさを感じて、自分から山奥の寺に出向く。
ここで加持を受けるが、岩屋の近くを歩きながら周囲の景色を見渡す。その先に端正な造りの庵が立っていて、そこに童女が大勢出て来るのが見え、その中に若紫がいるのだなと、想像出来ます。
若紫のはじまりです。
〇僧は、源氏に取りついた病や物の怪を追い払うのに、声を出して祈りを捧げる。当時も現在も加持祈祷により病魔を退散させるのであるから、(天台宗か真言宗かの)密教を授けたのであろう。
供人たちは、高い所に登って京を眺めて、京の山々よりも変化のある富士の山などや、西の国の変わった地方を識っていて、海山を紹介する。源氏は絵を描くのが上手であるが、もっと上手になると供人は思うのである。
昔、山科から銀閣寺の上手、大文字焼のところまで歩いたことがあるが、北山は盆地の山々なのでどちらの方角になるのだろうか。そんな山々よりも富士山などは較べものにならないことを、供人たちは識っていたのだろう。
若紫の序章は、またもや異外な源氏の病いからはじまったが、どんな伏線が隠されているのだろうか?
〇源氏物語の時代と現代との違いを探そうとすれば、逆に、何を引き継いだか、守っているかを考えさせられる。
住居についても、寝殿造りを越える知恵が生まれただろうか。
大和言葉に親しむ時間を大事にし、日本人を深めたく思います。
〇ドラマチックな夕顔の巻から、源氏にこれから寄り添う副主人公とも云える若紫、又、源氏の想い人(?)明石の君の登場を思わせる場面へと進んで行く。次回が楽しみです。
どのよう伏線があるのでせうか。
源氏の成長を楽しみながら、読んで行きます。
〇・印刷技術のない時代に「若紫はどこ?」とざれ言を言われるほど、人々に知れ渡っていた源氏物語の人気に改めて驚かされます。
・源氏がわらは病みの治療として受けた護符を飲む治療が、昭和の初め頃まで続いていたとは! 綿々と続く民間療法の歴史に、子どもの頃を懐かしく思い出しました。
〇「(北山)なにがし寺」には「鞍馬寺説」や「志賀寺説」があるそうですが、「大雲寺」が最も想定にふさわしいとの説もあるようなので、先日、岩倉の「大雲寺」に行ってみました。
大雲寺は、天禄2年(971)円融天皇の勅願寺として創建、智証大師流の天台法門を伝えたとの由。最盛期には、数十の堂舎と千有余の僧を数えた大伽藍だったそうですが、今や見る影もなく、「床もみじ」で有名な「実相院」の近くに、ひっそりと仮の建物と墓地があるだけでした。
ただ、今でも付近から京の都はかすかに望見できましたし、往時「やや深う入る所」「峰高く、深き巌の中」「すこし立ち出でつつ見わたしたまへば、高き所にて、ここかしこ、僧坊どもあらはに見おろさるる」「後の山に立ち出でて、京の方を見たまふ。はるかに霞わたりて、四方の梢そこはかとなうけぶりわたれる」などの物語の叙述とは、確かに符合するのではと思われました。
2012年4月12日「夕顔」感想
「夕顔の宿り」「二道の別れ」を了え、10年4月から始まった「夕顔」は丁度2年がかりでした。
次回から「若紫」に入ります。
〇八日目の蝉と言われるくらい蝉の命ははかないもの。それにもまして夕顔の命は夕べに開花し、朝には凋むあわれさである。
夕顔の急死から四十九日の法要を心をこめて行い、彼岸に送った源氏であるが、程なく空蝉の下向にともなう別れとなります。手厚いたむけの品々と共に、幣の間にかの小袿のうす衣を忍ばせ、“ひたすら袖の朽ちにけるかな”と決別の歌を添えて返します。
空蝉はいたく傷つき、かえって源氏への思慕がつのり、衣を“かへすを見てもねは泣かれけり”と嘆くのです。なんとも、やり切れない残酷な事になって了う。
結末としては、“過ぎにしもけふ別るるも二道にゆくかた知らぬ秋の暮れかな”と、実に美しくも切なく、二人の女性の出会いと別れを、見事にしめくくっています。
〇源氏の二つの恋が終わる。
一つは死という形で強烈な印象を残し、女性観にも強く影響を与え、残したと思われる夕顔。
一つは燃える想いを持ちながら、高いプライドが源氏に恋心を失わせた空蝉。
下向地での生活には、源氏に想われているという思いが欲しかったであろうに、バッサリと切った作者が小気味も良いが、空蝉を最後に素の女の顔にした作者に、少々意地の悪さも感じる終わりである。
〇まる4年、48回目で夕顔が終わった。空蝉との恋にも終止符を打つ。
季節は秋から冬に向かい、源氏も17才から18才になろうとしている。源氏の恋の残り火も静かに消えようとしている。
次回、若紫に入り、源氏の新しい恋が始まる。
〇ゆくかた知らぬ秋の暮れかなと、源氏は空蝉との別離にも人知れない苦しさを吐露する。
源氏のことを、語り手は胸中を察してあまりある。
語り手は源氏の悟りの境地を述べているが、式部は女の立場から男の気持ちを察しているのである。
この章において、夕顔、空蝉、語り手、式部と、秋の夕暮れのはかない風景が、過ぎ去っていく終焉の物語である。
〇源氏の時代の庶民の生活は、どの様なものだったか。
相当な貧富差があり、それぞれが交わる時もなく、時代が進行していたのではと推測する。
それはそれとして、「朗読」の素晴らしさに脱帽致します。芸の域と感歎致します。
〇・愛を告白してくれた源氏を拒否し続けながら、相手がその恋に終止符を打つと、あわてて手紙を出す女心がわかるような気がしました。
・空蝉の寝床から、源氏が勝手に持ち帰った小袿なのに、餞別の品々と共に送り返すというのは、あまりにも冷たすぎます。燃やすなりして処分してほしかった
源氏は自分の気持ちには忠実だが、相手の気持ちを思いやれない感じがします。
〇空蝉を しっかり守れるのは 伊予の介だけです。伊予の国で 彼女にはぜいたくな暮らしをさせてほしいです。源氏の手向けの品々も もちろん小袿も 捨ててしまった方が いいと思います。
〇源氏は冬立つ日に、「過ぎにし」女、「けふ別るる」女に思ひを馳せます。
うちしぐれて、いとあはれな空のけしきのなかで、ながめ暮らす源氏の姿は、やはり一幅の絵になります。
「夕顔」もまた、多くの余韻を残し閉じました。次回からいよいよ「若紫」です。楽しみは尽きません。
2012年3月8日「夕顔」感想
「軒端の荻の文」「四十九日の法要」を了えました。「夕顔」も、残すところあと僅かです。
〇四十九日の法要の様子など、事細かく書かれていて、如何に源氏が心をこめて執り行なったかが、わかりました。
現在も、七日七日と、綿々として受けつがれる仏教行事は、これからも引きつがれていくのでしょう。
彼岸も近くなり、こちら側にいる此岸の者も、いろいろの苦しみが年と共にふえて行くような気がします。
〇軒端の荻で始まりましたが、源氏の男の性がみえ、受けた方もまた女の性がみえと、古来よりの人間の変わらぬ性が面白い。
四十九日の法要の準備に涙し、心配りする源氏の人間性にも、またそうした男心があるのも楽しい。
〇夕顔が死亡してから早や四十九日がやって来た。葬儀はひっそりと行なはざるをえなかったが、源氏の、出来ることすべて行なおうとする意気込みを感じる。
四十九日も忍びて催さなければならないが、由緒ある法華三昧堂で行なう詳細は、他の方が書かれている通りです。
〇夕顔に対する願文は、源氏の施主としての言葉を、文章博士に指導してもらうのであるが、「加ふべきことはべらざめり」と、式部は何もつけ加えるものがなかったと、言い切っている。
法然や親鸞が提唱する以前の浄土教の世界が、平安佛教の天台宗・平安佛教の中で、浄土教の世界として定着していたようだ。佛教は、貴族社会に浸透してきていてことがわかる。
〇夕顔の思い出が、走馬灯のように思い出される。
いよいよ四十九日の法要が行われる。葬儀はひっそり行われ、わびしいものだったが、四十九日の法要は「事そがず」比叡山延暦寺で行われた。
源氏の夕顔に対する思慕の情がうかがわれる。
〇初めて源氏物語の世界に入り、思った以上に感動致しました。
和歌 / 仏教 / 法要 / 学問=漢文 / 貴族文化 / 恋愛の様式が関連し、その中に古人の智慧、日本民族の生長期を感じました。
〇・夕顔との別れに体までこわして嘆き悲しんでいた源氏が、急に元気づいて捨てた女にちょっかいを出すなんて性格が悪すぎます!
・愛する人と死別するのを「阿弥陀仏にゆずりきこゆる」と言うのが、美しいと思いました。
・下紐を解く・結ぶなどという歌は、貴族の歌としてはふさわしくないような感じがします。よんどころなく故郷を離れることになる庶民の切実な想いを、歌ったものかと思っていましたので。
〇源氏の君は 夕顔をしっかりと 阿弥陀仏におゆづりすることが できました
かなり立派な人です
〇軒端の荻への源氏の行いは、語り手をして「御心おごりぞ、あいなかりける」、そして「なほこりずまに、またもあだ名立ちぬべき御心のすさびなめり」と言わしめるものです。
またこの項は、「夕顔」を通じた物語の運びにも、そぐわないのではと言うような感じを持ちました。
こうした「あれっ?」も心の片隅に置きつつ、物語を読み進んでいこうと思います。
2012年2月9日
「それぞれの追慕」そして「空蝉の文」を了えました
メンバーの言葉を借りれば「僅か27行の原文」の中に、源氏の深い夕顔への想いと、右近の哀しみ、そして更には空蝉の源氏への深い思慕が綴りこまれていたのです。
〇夕顔の回想の“見し人の煙を雲とながむれば”の歌に酔っていました処、突如空蝉の“問はぬをもなどかと問はで”が出て来て驚きました。物語の流れが、意外性をまじえて連綿として連なって行くのは、さすがと感じ入りました。
〇「季節は移り秋になり」と空蝉から夕顔の物語に入り数ヶ月、伊予に行ってしまったと思っていた空蝉が又登場する。源氏が病に倒れ、重体だと知り文をだす。
忘れられていないかと不安になっていた心は、源氏の心を込めた返事に源氏の愛を感じるが、伊予の介の妻として生きて行く人生を選ぶ。
〇夕顔の死は、源氏の心をさいなましつづけるが、それを伝え聞いた空蝉が源氏に逢いたくなる。「問はぬをもなどかと問はでほどふるに いかばかりかは思ひ乱るる」
はかない空蝉の世は、はかない空疎なことばで源氏は対応するが、「空蝉の世はうきものと知りにしを また言の葉にかかる命よ」 源氏らしい返事を出したのだ。
夕顔のことは源氏にとって、本当につらかったのだろう。
空蝉との恋は、夕顔の終末の段、突如現われ、源氏の中に刻まれていたのだ。
〇右近によって明かされた女君の素性を知り、源氏は女君によって心を慰められたと思った。源氏は、自分の気持ちにぴったり合った女の存在を知り、女の美点を数え上げ、女君こそ源氏の理想の女だと思った。
女は、源氏が「かのもぬけ」を忘れずにいたことに、心のときめきを覚える。
源氏と女との心のもつれ合いは、どこへ行くのだろうか。
〇・男性が好む女性のタイプは、今も昔も変わりませんね。男性の作詞家の作る演歌に出てくる女そのものです。そんな人いないのに。
・「空蝉」の巻の最後に、自分の熱い想いを「畳紙の片つ方」にひそかに書いて、恋を終わらせたことを感動したのに! ちょっと往生際が悪すぎますね。
源氏にラブレターを書いて送っておきながら、「け近くとは思ひよらず」なんてわがまますぎです。作者の紫式部自身が、思い切りの悪い女性だったのかもしれないと思ってしまいました。
〇伊予の介が 空蝉を伊予に連れて行くのは 大正解.
源氏は空蝉を 幸せにできないし する気もないし.
伊予の介なら 人柄も良いし 頼りになりそう. 顔だって 決して 悪くはなさそうだし.
〇「世」のことは、「誤解」によって結ばれ、「理解」することによって別離となる。
でも、その「誤解」から永遠に解き放たれないのは何故でしょうか。
男の「身勝手」、「幼稚さ」からでしょうか。
2012年1月12日 「夕顔」感想
「女君の身の上」から「それぞれの追慕」へと進みました。
源氏と右近との語らいを通じて、夕顔の切ない姿や想いが浮かび上がってきます。
〇なにがしの院で、“「海士の子なれば」とて、さすがにうちとけぬさま、いとあいだれたり。”とあります。まだ生きていた時です。
さて、思いがけない事が起こって、むなしくなって了われた後、源氏と右近が夕顔の事を回想します。“あやしく世の人に似ず、あえかに見えたまひし”とあります。
この“あいだれたり”“あえかに”の語感の違いが、“動と静”“生と死”の違いを微妙に分けているように思われました。
いゝ語韻です。
〇右近との語らいにより、夕顔の人格や思考が明らかになり、源氏は夕顔の行動、やりとりに少しずつ納得がいく。それ故に切なさが一入です。
歳も19才でした。現代では18才です。
上の品のどんな環境で育つと、こんな魅力的、魅惑的大人の女になるのか? ミーハーレベルの私には、夢のまた夢です。
〇ふと外を見やると、秋の暮色をたたえた空が美しく映っていた。この描写が、右近の心が安定して来て、今の幸せをかみしめている様子をうかがわせる。
源氏より、右近の方が年下かと考えていましたが、2才上の19才とわかり、改めて、源氏はしっかりした人物だと感心する。
〇源氏と夕顔の出合いで、夕顔の個性、感性を認め、美意識として女性を認めることができた源氏の感性。こうした源氏の感性は、現代の男性には失われてしまったのであろうか。
宗教、道徳を超えた世界は、人間性の追求として不可能になってしまったのか。
これだけの短い物語の中で、想像もできない世界が現はれている。
「さればよ、とおぼしあはせて、いよいよあはれまさりぬ。」
〇女君は、粗末な家に住んでいることを源氏に見られてしまった、そのことを、つらく思う。
今までかくし通していた女君のすべてを知って、源氏は益々女に惹かれていった。
その女は、今は居ないのだ。源氏の心は如何ばかりか。
〇・自分の悩みとか心配ごとを、顔や態度に表わさない夕顔という女性は、相当にプライドの高い女性だと思いました。孤高の人という感じがします。
・今はあまり使われないとは言え、子を生むことを「ものす」というのは、あまり好きになれません。なんとなく生々しい感じがします。
それとは逆に「鳴きかれて」(嗄れて?)は、晩秋の感じがとてもよく出ていると思い
ました。
〇夕顔には 源氏と 可愛いい幼児と 右近との生活を させてあげたかったです。
さぞ若々しく 楽しいものになったでしょうに。
まだ19才の夕顔は どんなに可愛いくて きれいだったことでしょう。
〇夕顔の哀しい想いが、切々と伝わってきます。一方源氏の恋も、常に悲恋の様相を呈します。これから先、どれだけ多くの恋を、私たちは哀しみをもって見ることになるのでしょうか。この大河小説で、式部は何を語ろうとしているのでしょうか。私たちは、まだその端緒に立ったばかりです。
2011年12月8日 「夕顔」感想
「右近と語る」から「女君の身の上」へと進みました。
病が癒えた源氏は、右近を呼び寄せ、心のわだかまりを語ります。
右近とのやりとりの中で、源氏は今は亡き夕顔への想いを更に募らせます。
〇女君の素姓が、右近の口より明かされる。
いヽお生まれでしたのに、父君の早死によってすっかり人生が変わって了い、当時の女の生きざまが、社会的な仕組みでどう仕様もなく、はひ隠れたまへりとなる。
〇右近との語らいにより、夕顔の心情、人間像が明らかになる。
上の品の出自、大人の女であった事、深い人間性、これらの機微が解るには、17才の若い源氏には無理だったのでしょう。
今回は行数にして23行でした。この短い文章の中に、何と多くの事が語られていたか。
紫式部の筆力と古語の素晴らしさに感動です。
〇夕顔について少しずつ分かって来ました。
実は身分の高い三位の中将(上達部)の娘であったこと、頭の中将は、知り合った時少将であったこと、頭の中将より逃亡することになった原因は、右大臣より脅迫されていたこと(源氏は、北の方からの嫉妬と中将より聞いていた)。それにしても右大臣の脅迫とは、どのようなものかはまだ分からない。
源氏は、夕顔のことを「かかるべき契りこそはものしたまひけめと」思う。また数ヶ月のことなのに、七日七日の供養を行いたいと思っている。
〇貴族社会の身分を超えた恋は、夕顔の死によって終わった。源氏は、仏の供養を心のうちに想像しながら、右近にのたまうことになる。
互いに相手の名前も名のらずに終わった恋である。許されぬ恋であったから、なおさら源氏にはつらい気持ちになる。
夕顔の恐怖心は、頭の中将の北の方の実家(右大臣)からの、恐ろしき嫉妬のたぐいではなく、最高権力者の右大臣ににらまれるという、自分の存在をおびやかすものであったことが、源氏にもわかってきた。
頭の中将に助けられたのも、夕顔が源氏とつかの間の恋に燃えることができた。
〇「七日七日の供養のためにも名前が知りたい」との源氏の言葉に、いよいよ夕顔の名前が明かされるかと思いましたが、やっぱりだめでした。
でも、上の品の姫君ですから、“〇子”という“子”の字のつく名前だったのではないでしょうか。
“〇”にはどんな字を当てはめたら、夕顔の女を表現できるか考えていますが、なかなか思い浮かびません。
〇右近は 夕顔を本当に良く理解し 忠実に仕え愛したことがよく描かれていて この右近を通して 夕顔の姿がはっきりしてきました。
〇「常夏の女」と頭の中将、「夕顔の女」と源氏、式部の物語の運びに、今更ながら感じ入りました。
2011年11月9日 「夕顔」感想
「源氏、病に倒れる」を了えました。
昨年8月から始まった「夕顔」も、いよいよ終幕に近づいてきました。物語の進展に最後の最後まで気が抜けません。
〇15年近く前に、中国の仏教のメッカ、五台山に行った事がありました。北京から石炭がとれる大同を経て、長安近くの竜安窟との間にある、山あいの一大仏教寺院群です。
そこのお寺の中で、仏教、道教、ラマ教と三教を一緒に祀り、お像が三つあり、何しろすべてごっちゃまぜなのに感心しました。ですから日本でも神道、仏教など一緒になっているのでしょうかと思いました。
〇死迄も思わせる程の深い哀しみと、ショックを与えた夕顔の死は、これからの源氏の女性観に何か影響を残すのか、興味深い。
〇源氏は病に苦しめられながらも右近のことを気にかけ、自分が命ながらえたら、心細くしている右近の支えになってやりたいと思う気持ちを伝える。
次第に病も回復して行き、失った女の素姓を知らないことが心にかかる。このことを聞けるのは右近しかいない。右近に苦しかった胸のうちを明かす。
源氏が病の時、葵の上はどうしていたのでしょう?
〇源氏は20余日重くわずらい、痩せた顔立ちがみずみずしく美しかった。
夕顔を思慕する気持ちは、声を出して泣くほどであった。その姿をみて、女房たちは真相を知らないので、物の怪にとりつかれたと思うのであった。
現代男性と比較できない、平安時代の男性の心根である。
〇源氏は二条院に戻ったとたん、病になって床に臥してしまった。
世間や帝の嘆きの様子が細やかに語られる。
〇・天の下の人がさわぐほどの美男子は、現代なら誰? 私にとって美男子は、ダルビッシュですけど。(あ、関係ありませんが・・・)
・人々が神も仏も受け入れて、心をひとつにして、源氏の回復を祈る所が日本的な優しさにあふれていると思いました。
・「足を空にて」・「雨の脚よりも・・」という表現は、今は使われませんが、とてもすばらしい表現だと思いました。
〇源氏は、帝と左大臣にとって、本当にかわいい息子だったことが良く描かれていました。
死にそうになる程、気も狂いそうな程、悲しい目に会いましたが、彼には強い味方が多くいて良かった。
左大臣みたいなお父さん、うるさくてしつこいけど、大好きです。
〇先生から参考として配布された資料の中で、左大臣が源氏のことを何より大切にする政治的背景について、かなり詳しく考察している箇所(陣野)がありましたが、なるほど面白い視点だなぁと思いました。
2011年10月13日「夕顔」感想
「鳥辺野の対面」から「紅の御衣」へと進みました。
源氏は「恐ろしきけもおぼえず、いとらうたげなるさまして、まだいささか変わりたるところな」い夕顔の「手をとらへて」「声も惜しまず泣きたまふこと限りなし」。
そして右近には「道理なれど、さなむ世の中はある。別れといふものの悲しからぬはなし。とあるもかかるも、同じ命の限りあるものになむある。思ひなぐさめて、われを頼め」と気配りを示します。
帰途、源氏は「馬よりすべりおりて」「かかる道の空にて、はふれぬべきやあらむ。さらにえ行き着くまじきここちなむする」「とのたまふ」。そして源氏は惟光ともども神仏に「念じたまひて」、また惟光に助けられつつ二条の院に帰り着きます。
一方、女房たちは「あやしう夜深き御ありきを」「見苦しきわざかな。このころ、例よりも静心なき御忍びありきの頻るなかにも、昨日の御けしきのいとなやましうおぼしたりしに、いかでかくたどりありきたまふらむ」と嘆きあいます。
〇鳥辺野、清水寺のある山の上の板屋での、死者をご供養する有様は、素朴だけど手厚く、嘆き悲しむそれぞれの描写が心がこもっていて、「清水のかたぞ、光多く見え」と絵になるようです。
〇源氏の、右近の、哀しみの深さが強く思われる。
時間に追われている中で、ただただ精神力で二条院へたどり着いた源氏、惟光の描写が興味深い。
〇源氏、惟光共に17才の若者に最大の危機がおとずれる
源氏は精根尽き果て、惟光はどう対処して良いかわからず祈り続ける。
何とか二条院に戻って来るが、女房たちの疑いの目がそそがれる。
〇源氏と惟光は、清水観音に加護を祈る。夕顔の死という事態に今の心境は、神仏にすがるしかない。主従の祈りは通じたのか、やっとのことで二条院にたどりつく。物の怪を恐れる平安貴族は、観音にすがるしかない。
恐らく現在の観音さんを拝んだに相違ない。
〇源氏は夕顔の亡骸を前にして延々と悲しがる。読経する高僧たちも涙する。源氏は落馬しながらも、何とか二条院に辿り着く。
夕顔が生きていた時の源氏と、亡くなってからの源氏、一転して源氏の心を暗くしたのであった。
〇・「われに今一度声をだに聞かせたまへ」の場面は、一番胸をうつ場面でした。
・源氏の心痛もわかりますが、惟光も弔いの手配やら主人の介抱やらで、どんなに疲れたことかと同情してしまいます。
・夕やみに沈む東山あたりの描写が、目からと耳からと両方を使って上手に表現されていると思いました。
目から・・・御燈明のほの明るさ 清水寺の光
耳から・・・女の泣き声 読経の声
〇泣きまどう右近の「煙にたぐひて、したひ参りなむ」の言葉に、桐壺の母君のことを思い出してますます悲しくなりました。
〇夕顔との恋も、その死により終わりを告げることになりました。それにしてもこの魅力あふれる女性は謎だらけです。これから先、私たちが夕顔をもっと詳しく知る機会があるのでしょうか。
物語の中に、さりげなく語り手の思いを挿入したり、当事者以外の第三者の視点を書き込んだり、先生のご指摘の通り実に面白い作法だと思いました。
2011年9月8日「夕顔」感想
「惟光の覚悟」から「鳥辺野の対面」へ進みました。
夕顔の死の後始末をめぐっての、源氏と惟光の濃密なやりとりを、そして夕顔の死を悼み、別れを惜しむ源氏の心の動きを、きめ細かく描いています。
〇「ただ今の骸を見では、またいつの世にかありし容貌をも見むと」と若いから羨ましいと思いつヽ読んでおりましたが、先を知っているもので安心して了っているので、期待を裏切らないと良いと心から思います。
〇状況の難しさ、道中の怖さ、何もかも解っていながらも、どうしても最後の姿をみたいという源氏の夕顔への深い思いが哀しい。
そして若い惟光の冷静に行動する思慮深さ、源氏への深い思いが素晴らしい。
〇源氏一行は東山鳥辺野に向け出発する。草木の生い茂る暗い夜道を馬で行くのに、恐ろしい目に会う不安もあるが、この悲しみをどうすれば癒せるのか、源氏は自分の心に問いかけての決断であった。
〇鳥辺野へどうしても行きたいという源氏の気持を認めざるを得なかった惟光は、危険なことは百も承知で、源氏の気持ちを尊重せざるを得なかった。夜が明けぬうちに帰ってきてくださいと人目を気にする。
火葬にする風習は、亡き骸を一目見たさに、源氏が経験したことがないことに直面する。
二条の院から東山までは距離がある。闇の中を一行の馬はつづく。十七日の月の光は照らし出している。「道遠くおぼゆ」
〇惟光は夕顔の葬儀一切を取りしきる。この一点でも惟光の源氏に対する忠誠心がうかがえる。
〇・私達はふだん「十七日の月」などという言葉は使いません。明かりの少ない時代は、月の出に敏感だったのだなあと思いました。
・すばらしい気配りができる惟光。川柳に詠まれた“たいこもち”も、身分こそ違うが旦那衆に細かい気配りができる人たちだったのだろう。
〇源氏、惟光、随身の鳥辺野への道行きに
見せる三人それぞれの顔つきを想像して
三人ともステキ!
〇「例の太夫、随身を具して出でたまふ。道遠くおぼゆ。十七日の月さし出でて、河原のほど、御前駆の火もほのかなるに、鳥辺野の方など見やりたるほどなど、ものむつかしきも、何ともおぼえたまはず、かき乱るここちしたまひて、おはし着きぬ。」
一幅の絵を見るような描写です
2011年8月11日 「夕顔」感想
「偽りの忌中」を了えました。
本日の講義の前に「朗読 源氏物語」―平安朝日本語復元による試み―(監修 金田一春彦 朗読 関弘子)を聴きしました。当時の発音・抑揚・間合いまでをも甦らせた大変な労作で、原文と突き合せつつ鑑賞しました。よくもまぁこういうことが出来たものだと思うのと同時に、物語が語り継がれてきた雰囲気そのものをも味わう事が出来たのではと思いました。
〇今日の関さんの朗読と言うか語りはとても素晴らしく、まして先生に事細かに、ご丁寧にお習いしたばかりでしたので、とても感銘を受けました。
ちょっと関西風のアクセントで、昔、村山りゅう先生に語りを伺った頃もなつかしく思い出され、嬉しい時間でした。
〇夕顔を失った悲しみの深さが強く思われるところでしたが、居所不明にした理由づけの言い訳が滑稽で、楽しませてもらった。
〇源氏はやっとの思いで二条の院にたどり着く。もうろうとしながら御帳に避難するが、大騒ぎになっていて、君達などがこぞってやって来る。君達で最も仲の良い頭の中将を招き入れるが、けがれないように「立ちながら」と招じ入れる。
中将に対して事実を交えながら偽りの作り話をするが、なにせ源氏はまだ17才、完全な物語にする事が出来なかった。最も心を許してきた友なのだが、特に秘密を打ち明けられない。
〇源氏は女を置いて帰ってきてしまったことを、心の底から後悔する。
いたづらになることが、力を尽くしても無駄に終わってしまう。なんで死んでしまったのだと自責の念にとらわれる。今日使われている「いたづら」とは違い、心の底からの言葉として、印象強い言葉になっている。
「立ちながら、こなたに入りたまへ」と、源氏の言葉は衣服を整えていないので他人をそばに近づけたくないとの配慮からかと思ったら、律令制度の基で「延喜式」に穢れの規定があったことからきているとは、源氏がこのような知識をもっていたことがわかる。
源氏が穢れについての見識をもっていたということは、作者の式部もこのような見識をもっていたということである。
うその話でも、死者の穢れだけは伝えざるを得ない源氏の気持ちがよく表現されている。
〇源氏が参内しなかったことの言い訳をこと細かに述べているが、作り話でも死者のけがれに触れたことは事実であった。
(平安時代の発音の録音テープ。大変参考になった)。
〇今日は素晴らしい朗読を聞き、今更ながら夕顔の巻の文章のたくみさ、式部の偉大さに驚かされる。
現代の劇作家の構成と通じている事を実感しました。
〇・プロの朗読のすばらしさに感激しました。目を閉じて聞いていても、その様子が浮かんできました。
・死は何故これほど忌み嫌われたのでしょうか。
私自身の感覚からすれば、愛する人や、親族の遺体にけがれは全く感じられません。
〇「いかなる行触れにかからせたまふぞや」、事態を全く知らないこの頭の中将の言葉は、ゾッとギョッとするものなのですが、彼のいたづらっぽさが感じられる故に、私は嫌な感じは受けませんでした。
中将と夕顔には、既に幼い愛らしい娘がいたのですから、北の方の目を上手にのがれ、隠れ家に囲ってやさしく面倒をみてあげてさえいたらと残念です。
短い若い時代には、死とは無縁であってほしかった。
〇「内裏より御使あり」、「大殿の君達参りたまふ。]しかし、源氏が真っ先に(家士は別として)夕顔との秘め事を虚実織り交ぜて話した相手が、夕顔と子までなした頭の中将だったとは、何と言う皮肉、いや残酷な物語の展開でしょうか
2011年7月14日 「夕顔」感想
「惟光の采配」から「こぼれ出づる髪」に進みました。
講義終了後の皆さんの感想は次の通りです。
〇「しほじみぬる人」で、ふと、「しほじい」の事を思い出しました。小泉さんの時の財務大臣でしたか。母屋ではおかゆなのに離れではすき焼きをたべて云々。
それから有名な秘書官、名前はちょっと忘れましたがやり手の、なかなか迫力のある人。随分小泉さんは助かったのではないでしょうか。
源氏も惟光というなかなか有為な部下を持って、ただの女扱いがうまいだけではなかったのですね。
一大事を無事に乗り越えました。徒歩より君に馬はたてまつりて。
〇惟光の秘書的能力が遺憾なく発揮され、源氏を守りぬく覚悟、素晴らしい。
そして夕顔の美しい最後の描写は、絵画を思わせる。
〇やっと現れた惟光に、何でこんなに遅いのか?となじりたくなる源氏。
でも内心ホットしていたのではないでしょうか。
ここから惟光が主役となり、源氏と右近は惟光に頼り、惟光は身を捨てて野辺送りをやり遂げようとする。
〇夕顔の美しさは、こぼれ出づる髪として描かれる。豊かな黒髪が、美しき女性の表現となっている。髪をなぜる行為の中に源氏の思いも込められているのであろう。
惟光のはからいで、後髪をひかれる思いで二条の院にたどりつく。自分の目の前で、女性の死をまねいた気持ちはどんなものであったか。
式部の文末は、余韻の残る文章で感服する。
〇「からうして惟光参れり」源氏は惟光にうらみ言をいわず、早速、事の次第を説明しようとするが、直ぐには言葉が出てこない。源氏には、その出来事がショックすぎたのである。
この事件を現代にひきかえたら、どうなるのだろうか。
〇いつもながら状況描写の美しさ、たくみさ、夕顔の巻のフアンが多いのがわかります。青年時の源氏の心情、これからかかり合う女性達との違い、ますます楽しみです。
〇紫式部自身、「豊かな髪がこぼれ出ている」場面に遭遇したことがあったから、こんなに具体的に書き表すことができたのではないでしょうか。
子どもの頃、百人一首で坊主めくりをして遊ぶとき、お姫様の長い黒髪に憧れたのを思い出します。
〇光源氏をはじめとして、男でも女でもすてきな若者には、素直で濁りのないそして優しい暖かい心がどうしても走らせてしまう愚行を多いに敢行して、必ず生きぬいてほしいです。
〇先生から、医者の見立てによると夕顔の死因は「心因性ショック死」であったとお聴きし、なるほどと思いつつ、何だかロマンが失われたような気持ちもしました。
2011年6月9日 「夕顔」感想
「息絶えた女君」「孤独の一夜」を了えました。
夕顔の死に直面し、源氏は「命をかけて、何の契りにかかる目を見るらむ、わが心ながら、かかる筋におほけなくあるまじき心の報い」に思い至り、そして「ありありて、をこがましき名をとるべきかなと、おぼしめぐら」します。
六条の女君と夕顔とが交互に登場する形で物語は進んできましたが、ここで突如藤壺への恋が姿を現し、私たちを驚かせました。
講義終了後、みなさんから寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇死の受け留め方に今も昔も違いはそうないと思うが、つい近く義弟が亡くなった折は、その丁度半年前に会った時「癌が次々と転移して余命半年と医者に云われ」と聞いて、其時非常にびっくりしました。そしてその通り6ヶ月後に亡くなり、本当に今の医学の予知の正確さに驚かされました。
冷え入りにたれば、けはひものうとくなりゆく、いたづらになり果てたまはじ、とは随分と趣きが異なりますね。
〇楽しい語らいの後の急転直下の展開にただただ驚く。
若く経験のない源氏は不安や恐怖のスパイラル、そして我身の来し方行く末への不吉のスパイラルと、現代の世の中と同じだと変わらぬものを感じる。
〇源氏は女をしっかりと抱きしめながら「あが君、生きいでたまへ。いといみじき目な見せたまひそ」と必死で呼びかけるが...余りにも急な出来事で呆然として冷静さを失う。
預りの子を呼び、てきぱきと振舞っているように見えるが、実は何を言っているのか覚えがないほどまいっている。
自他共に良くあることですが、あの源氏がこう言う心境に...何とか生きていてほしいとの必死の思いが伝わります。
〇「おほけなくあるまじき心の報いに」
藤壺に対する思慕とは、それとなく表現しているのでわからないが、本日の説明を聞いてわかるような気がした。
「はらはら、どきどき」させる式部の表現力の巧みさに感嘆する。当時の人たちが源氏を読んで理解できたのであろうから、知的水準が全体として高かったのだろう。
夕顔の花の姿に似て、物語はすすむ。
〇「夢に見えつる容貌したる女、面影に見えてふと消え失せ」たのを見て、源氏は背すじがぞっとする。「まづこの人いかになりぬるぞ」と源氏は胸さわぎする。
「やや」と目覚めさせようとしたが、女の体は「冷えに冷え入りて、息は疾く絶え果て」ていた。源氏には、どうにもならない事態になってしまった。
源氏は女を抱きしめながら「あが君、生きいでたまへ。いといみじき目な見せたまひそ」と呼びかけるが、女は「けはひものうとくなりゆく」のであった。
源氏は惟光を呼びよせるように言うが、惟光はなかなか現れず、孤独な一夜が過ぎる。
〇心が通じ合い、愛し合った二人。
こんな場面でも、ほかの方、御息所のことを思う男性。そんな気持ちがテレパシーで通じてしまったのでせうか...
〇・この非常時に、尼君への指示を細々と出すというのは、源氏にとって、いかに尼君が口うるさい目付役だったかがわかります。
・紙燭の明るさでは、遊園地のお化け屋敷並みの暗さではないでしょうか。まっ暗より、かえってうす気味悪いと思います。
〇私は、随身のことを律儀な堅物と想像し、けっこう気に入っているものですから、彼が、遊び人の惟光君を、暗い中必死に捜しまわっていること、いやはや、本当にご苦労様です。
〇源氏の原罪とでも言うべき「藤壺への恋」が、深く影を落としていることを、改めて思い知らされました。
2011年5月12日 「夕顔」感想
「枕上の女」から「闇の中で」に進みました。
源氏の夢の中にあらわれた「いとをかしげなる」女は、「己がいとめでたしと見たてまつるをば、尋ね思ほさで、かくことなることなき人を率ておはして時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ」と鬱積した思いを述べ、恨み言をぶつける。そして「御かたはらの人をかき起こさむとす」る。
一方、女君は「いみじくわななきまどひて、いかさまにせむと思へり。汗もしとどになりて、われかのけしきなり」。源氏がこの院の預かりの子に指図して戻ってきて、「かい探りたまふに、息もせず、引き動かしたまへど、なよなよとして、われにもあらぬさま」で、「ものにけどられぬるなめり、と、せむかたなきここちしたまふ」とあります。
今までの文脈から、六条の女君の生霊が源氏の枕上に立ち、次いで夕顔にも取り付いたと単純に読んでしまったことは、誤りだと先生から指摘を受けました。
なるほど、源氏の夢にあらわれた女が六条の君だとか、その生霊が夕顔に取り付いたなどとは何処にも書かれていません。それぞれの物の怪が同じものだとも。そもそもその正体自体分からない。
では一体何なのか。物の怪とは、それぞれの思いの中に生じるものであって、客観的に存在するものではないことの証なのか。などなど、実に面白いご指摘だと思いました。
いみじくも、先生が「式部に騙されましたね」と仰ったことは、今後この物語の展開にどう及んでくるのでしょうか。興味津々です。
講義終了後、みなさんから寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇闇の世界、ついこの間にとんでもない事で味わいました。
紙燭の世界、これも体験致しました。
暗い不気味さは現代でも恐ろしいですが、この時代は、まして荒びた院の中での中世の事、もののけが出現するには、ぴったり格好な有様です。
〇源氏とのうちとけた時を過した後の、天国から地獄への余りにも大きな悲劇へ。
何かにおびえていた夕顔は、ものの怪をよび込んだのでしょうか?
とうとう名もあかさずに、一夜花の夕顔のはかなさを思わせる驚きの展開にびっくりです。
〇二人だけの時を過したいとの思いで、連れて来た家でたっぷりと語らい、充ちたりた気分に浸る。この時間は長く続かずに、夕顔が物の怪に取りつかれて次回で死んでしまい、源氏は呆然とし途方にくれる。
夕顔のクライマックスシーンである
〇六条の女君には、思慮深き女性であると想い、源氏は少し距離を置いてきた。
名もなき五条の女に心を奪われた。
物怪にたたられた女に呆然としている。
その二人の関係の中で、式部の語りは枕上の女を登場させているが、六条の君ではないかと思ったが、説明では第三の女であると云う。
誰にもわからないように語りをうまくもっていく手口は、式部流というのであろうか。
このような配慮は、現代人の物書きをする人にも参考になるであろう。
〇「・・・かくことなることなき人を率ておはして時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ」と、枕上の女に言われた。源氏がこのような悪夢に襲われたのは、六条の君をおろそかにしたためだった。
目覚めた時、火はかき消えていた。源氏はこれを物の怪の仕業と恐ろしがり、供人を呼びに行くが、闇の中で何が起きたか?
〇・現代より闇が濃かった昔は、物の怪などの話が人々の間で盛んに語られた事でしょう。私も子どもの頃に幽霊話にキャーキャー騒いだのを思い出します。
・「手をたたきたまへば、山彦の答ふる声」というのは、お化けも出てこないのにぞっとする情景です。
・当然のことなのですが源氏が自分のことを「まろ」と言っていたのだと、今まで気づきませんでした。
〇恐ろしい話の運びですが、情景は相変わらず美しく、そして悲しいものがあります。
〇先入観にとらわれずに、原文を深く正確に読んでいくことの難しさと楽しさを、同時に味わっております。
2011年4月7日「夕顔」感想
「語らい」から「夕映え」に進みました。次回からいよいよ「枕上の女」に入ります。
〇いとあいだれたり、とは、夕顔の事をいみじくも表現しものと、しみじみと感じさせられました。
ただただ可愛らしくいとしいだけでない、あやしいたましい迄も取りつかせる愛らしさ。
〇教養もあり聡明でお茶目でと、魅力的な夕顔。
源氏が、全てを明らかにしたにもかかわらず身分をあかさないのは何故。
何に怯え、恐れ、不安を感じているのか。それが知りたい!!
“~かたらひ暮らしたまふ”は、恋人達の甘やかな時を、何と適確に表わしていることでしょう。
しばし青春時代を思いおこしました。
〇源氏は女の素姓を知ろうとするが、女は古今集からの言葉「海士の子なれば」とかわし、素姓を明かさない。
源氏は悲しませないため諦めようと考えるが、まだ名前も知らない。
宮中にも行かないで、朝から女とたっぷりと語らい、暮れ方を迎え平静さを取り戻す。
夕顔との充ち足りた時間はあとどのくらいあるのか? ちらっと先読みすると、もう時間がない。源氏も読者も呆然とする。
〇夕顔の言葉は、「あいだれたり」甘えすぎではないかと、語り手は客観的にみている。
海士の子にたとえるのに、「われから」海藻の中にいるかぼそい虫と、「自分のせい」とをかけている。
この会話のやりとりの中で、二人の気持ちのかよい合いが伺える。
和歌のやりとりは、教養の深さを物語るが、式部の知識の深さでもある。
〇「尽きせず隔てたまへるつらさに、あらはさじと思ひつるものを。今だに名のりしたまへ。いとむくつけし」と女が名のらないのをうす気味悪く思う。私が名のったのだから、今度はあなたが名のる番だと、源氏は女を責める。
女は「海士の子なれば」と言って、名のろうとしない。
「たとしへなく静かな夕の空を見かはして」女もよろづの嘆きを忘れて。すこしうちとけていく様子。しかし女は素性を明かさない。
〇万葉集、古今集、和漢朗詠集・・・・と色々な書物からの引用が出てきますが、平安時代の人は、それらを独学で学習したのでしょうか。
今なら学校や学習サークルで文学を勉強しますが。
P230「内裏にいかに求めさせたまふらむを・・・・」の一文は、①帝のこと、②自分の気持ち、③六条わたりのことと、3つの内容が一文に盛り込まれています。今では考えられない書き方です。
〇今回 気に入ったフレイズ・・・・「よし、これもわれからななり」
本物の「われから」を 是非見たいです。
〇源氏物語には、華やかで雅やかな展開の一方で、常に悲劇の要素が通奏低音の如く流れています。源氏と夕顔の恋も、頂点をきわめたとき一気に舞台は暗転するのです。次回以降に、息を呑む思いで身構えております。
(講義終了後のお花見を楽しみにしていましたが、体調を崩し残念ながら欠席いたしました。迷った末、「生命ある限り源氏を味わいつくす」ために、「生命」の方を優先させた次第です。お陰さまで検査の経過は「吉
2011年3月10日 「夕顔」 感想
「なにがしの院」そして「語らい」へと進みました。
源氏 いにしへもかくやは人のまどひけむ わがまだ知らぬしののめの道
ならひたまへりや
夕顔 山の端の心も知らでゆく月は うはの空にて影や絶えなむ
心細く
源氏 夕露に紐とく花は玉鉾の たよりに見えしえにこそありけれ
露の光やいかに
夕顔 光ありと見し夕顔のうは露は たそかれどきのそら目なりけり
今回の講義終了時、皆さんが記された感想文は次の通りです。(文責 高松)
〇前回は庶民の暮らしぶりがわかり、今回は貴族の暮らしぶりが、なにがしの院での下家司の言葉や動作などでうかがえられ、面白い。
そして、夕露に紐とくたよりに見えしえ、であり、後目に見おこせて、そら目なりけり、となる。
〇源氏と夕顔の心が通い合って行く情景が、歌によせて美しく楽しい。
〇源氏と女と右近を乗せた車が「なにがしの院」に着く。源氏は想像を絶するほどの荒廃ぶりにびっくりするが、女は広大な庭を見てか?源氏だと見定める。
それにしても、源氏は人目を恐れてずっと顔を隠したままだった、とは。
これからの展開が楽しみです。
〇源氏と夕顔の歌合せは、一幅の絵画のような時間が経過している。
源氏の問いかけに、見も心も許した関係になったことであろう。
それは、年上の女の余裕であろうか。
それをまた、源氏は心にくく思って、頼り甲斐があると思っているのであろう。
〇女と右近を乗せた車は「なにがしの院」に着く。源氏は、女を連れ出してしまったことを「まだかやうなることをならはざりつるを、心づくしなることにもありけるかな」と、感慨を歌に込めた。
これに対し、女は不安な気持ちを歌に詠む。
源氏は人目を恐れて顔を隠したままだったが、歌に託して身を明かす。
女の返歌は「・・・夕顔のうは露は・・・そら目なりけり」。
この返歌の真意を私は理解できなかった。
〇・(恥ずかしながら)「しののめ」東雲ということばは、地名として知っていただけで、意味まで深く考えたことがありませんでした。調べてみたら、夜が明ける迄の間は、あかつき→しののめ→あけぼのと変わっていくそうで、驚きました。
・女は源氏が自分に首ったけだと言うことを承知しているからこそ「そら目なりけり」などと歌を詠めるのだと思います。
女の実年令はわかりませんが、年上の女(ひと)という感じがします。
〇夕顔は、頭も顔も良く、男の人に愛されるタイプの人なのに、結局は、都合よくあしらわれて、余り大切にされない人のように思います。
この理由を夕顔は理解しているのか、それとも、気付きもしていないのか。
私には全くの疑問なのですが、この人、余りに幸せ薄く、何とかしてあげたい気持ちになりました。
〇京都には二度暮らしました。
「なにがしの院」が、たとえば源融の「河原院」だとすると、今の河原町五条辺りになります。院は「いといたく荒れて、人目もなく遥々と見わたされて、木立いとうとましくものふりたり。」「みな秋の野らにて、池も水草にうづもれたれば、いとけうとげになりにける所かな。」とあります。
当たり前の話なんですが、千年前とは言え、あの辺りにそんなものがあったとは中々想像できないものがあります。当時、洛中の人口は何人ぐらいだったのだろうかとか、歴史的・地理的な点にも興味が広がります。
2011年2月10日 「夕顔」感想
「板屋の物音」から「らうたき人」「ためらい」まで進みました。
・源氏と夕顔の恋は更に深まっていきます。
・物語で「源氏の目を通して見た女と、語り手が語る女と、女が直接心の内側を見せる歌の中の女と、幾重にも女の像が重なって、単純ではない女の姿が浮き彫りにされる。」(先生の解説文)
・「いさよふ月に、、ゆくりなくあくがれむことを、女は思ひやすらひ、とかくのたまふほど、にはかに雲がくれて、明けゆく空いとをかし、(ついに源氏は)はしたなきほどにならぬ先にと、例の、急ぎ出でたまひて、(夕顔を)軽らかにうち乗せたま」ったのでした。
今回、皆さんが記された感想文は次の通りです。(文責 高松)
〇夜明けの庶民のくらしぶりが、生活音をまじえてリアルに描かれていて、これが恋物語の源氏物語かと思われ、興味深い。今の時代とちっとも変わっていない。
その中で、らうたき人、ほそやかに、たをたをとして、源氏になびく。
〇若さゆえでしょう、いつもながら源氏の一途さは見事。
夕顔のおおらかでこだわリのない性格とはいえ、高貴の出と推察されるとは言え、何も氏素性のわからない人に怖さはなかったのだろうか?
生活の安定を求めるものも、どこかにあったのだろうか?
これからにドキドキワクワク!!
なよよかなる~、らうたげにあえかなる~、ほそやかにたをたをとしてと、何とおもむき深い美しい言葉だろうと、いつもながらうっとりします。
〇「板屋の物音」の場面で、現実の世界を見せる。この騒ぎの中での女の反応が、源氏をなお一層引きつける「らうたき人」では、流れるような文章から入って行き、現実の話題に区切りをつける。
騒々しい物音に煩わされることなく、二人きりの世界で語り合いたいと、人目につかないよう、やっとの思いで車に乗せて連れ出す。
夕顔のその後と、娘玉鬘は今どこにいるのか?興味深く楽しみです。
〇秋の風情の中で、源氏の心がひきつけられるものがあった。いままでどの女にも感じたことがないものであった。
「南無当来導師」と拝む姿は,浄土教の教えであろうか。弥勒菩薩や「来世のちぎり」まで、貴族社会ではこの時代に普及してきている。
紫式部の物語の展開が、男女の秘め事から佛教のことまでに及んでいるのは、ものすごい知的好奇心の富んだ女性であったのであろう。
〇隙多く月の光が漏れてくるような板屋で、隣家の男たちの声、碓の音など、源氏には「くだくだしきこと」のみが多かったが、女は「のどかに」気にしないようであった。
遣戸を引き上げて庭を見ると、板屋の庭でも露がきらめいている。虫の鳴き声はうるさいが、女の「いとらうたげ」な姿は源氏をひきつける。
明けがたも近くなり、源氏は女を連れ出そうとするが、女はためらう。結局、源氏は女を抱きかかえて車に乗せてしまう。
この結末が楽しい。
〇「らうたき人」も「ためらい」もとてもすてきですね。
白居易の長恨歌が、平安時代の知識人にずいぶん読まれていたのだなぁと改めて感じました。
漢詩を遣唐使が日本に伝え、それを日本風に読み下し、人々が理解し、引用するのですから、その頃の日本人の貪欲なまでの知識欲に感慨深いものがあります。
〇「優婆塞が行ふ道を・・・」に対しての夕顔の返歌に、源氏は反応を余りみせなかったようです。自分の誠意に違う歌を返した彼女に対しての立腹も懸念も感じられません。
紫式部が述べている通り、源氏の君はまだまだ若く、軽く、浅く、「かやうの筋なども、さるは、心もとなかめり。」
〇源氏は多くの女性と恋を交します。そのそれぞれを物語りはきめ細かく描いていくのですが、こうした恋に源氏を突き動かしていくものは、一体何なんでしょうか。ここまで進んで来て、私の思いの中でその謎が更に深まってきました。
2011年1月13日 「夕顔」 感想
「下の品への冒険」から「やつしの恋」「いずれか狐」へと進みました。
源氏と夕顔の恋が深まっていきます。物語を三つの側面から見てみました。
滑稽な姿
「(源氏の)いとわりなくやつれたまひつつ、例ならず下り立ちありきたまふは、(惟光は)おろかにおぼされぬなるべしと見れば、わが馬をばたてまつりて、御供に走りありく。」
「(惟光)懸想人のいとものげなき足もとを見つけられてはべらむ時、からくもあるべきかな(などわぶる)」
「(源氏は)いとことさらめきて、御装束をも、やつれたる狩の御衣をたてまつり、さまをかへ、顔をもほの見せたまはず、夜深きほどに、人をしづめて出で入りなどしたま(ふ)」
源氏の深い想い
「さすがにあはれに、見ではえあるまじく、この人の御心にかかりたれば、便なく軽々しきことと、思ほしかへしわびつつ、いとしばしおはします。」
「かかる筋は、まめ人の乱るるをりもあるを、いとめやすくしづめたまひて、人のとがめきこゆべきふるまひはしたまはざりつるを、あやしきまで、今朝のほど昼間の隔てもおぼつかなくなど、思ひわづらはれたまへば、かつはいともの狂ほしく、さまで心とどむべきことのさまにもあらずと、いみじく思ひさましたまふに」、
「人のけはひ、いとあさましくやはらかにおほどきて、もの深く重きかたはおくれて、ひたぶるに若びたるものから、世をまだ知らぬにもあらず、いとやむごとなきにはあるまじ、いづこにいとかうしもとまる心ぞ、と、かへすがへすおぼす。」
「(夕顔がいつうつろひゆかむかとの疑念にさいなまれつつ)なのめに思ひなしつべくは、ただかばかりのすさびにても過ぎぬべきことを、さらにさて過ぐしてむとおぼされず。人目をおぼして、隔ておきたまふ夜な夜ななどは、いと忍びがたく、苦しきまでおぼえたまへば、なほ誰となくて二条の院に迎へてむ、もし聞こえありて便なかるべきことなりとも、さるべきにこそは、わが心ながら、いとかく人にしむことはなきを、いかなる契りにかはありけむ、など思ほしよる。」
夕顔との語らい
「いざ、いと心安き所にて、のどかに聞こえむ」など、かたらひたまへば、
「なほあやしう、かくのたまへど、世づかぬ御もてなしなれば、もの恐ろしくこそあれ」と、いと若びて言へば、げに、とほほゑまれたまひて、
「げに、いづれか狐なるらむな。ただはかられたまへかし」と、なつかしげにのたまへば、女もいみじくなびきて、さもありぬべく思ひたり。
今回の講義直後に、メンバーの皆さんが記された感想文は次の通りです。(文責 高松)
〇ほのぐらい、ほの明るい、何とも幽玄な世界。
そこで語り合い、睦み合い、想い合い、想像し合い、だましだまされ、それだけで充分満たされる。実に素敵。
〇源氏と夕顔の恋の世界が深まってきました。
奇異な状態での言葉のやりとりの持つ重要さがわかります。
運命的な出会いに、悩み、地位さえもあやうくしそうな程の恋は、これからいかに?
〇源氏は夕顔に対して、片時も離れたくないほどの激しい恋をしてしまう。
この女に、なぜこれほどのめり込んでしまうのか?
昼時も逢っていたい、離れたくないと思う心は本人にもわからない。
源氏にとって、朝顔でも昼顔でもなく夕顔にめぐり合い、今までにない自分が変になりそうな恋も、常夏の女のいつ姿を消すかもしれないと言う思いが頭をもたげ、二条院に迎え、共に暮らしたいと思うまでになるが、どうなるのでしょうか?
〇源氏は、狩衣姿で夕顔に逢いに行くが、今でいうトレーニングウエアーとでもいえるか。からだ・身のこなしが自由にできることを配慮したからであろう。
「心に染む」ということばは、現代では死語になってしまったのか。
「香り、匂いが染む」からとったのであろうが、「心に染む」ようなことに最近お目にかからない。そもそもは、「布を染める」ことから起こって、変化したのではないかとも考えられる。
源氏の「忍ぶ恋」に「快哉」と想わざるを得ない。
〇源氏が顔さえ囲んでという、そんな恋の習俗があったのでしょう。
今日の場面は、互いに心競べをしている会話がほのぼのとして、本当にたのしみました。
〇・源氏が下の品の女にも敬語を使うのは、上下に関係なく、一番使い慣れている言葉なので、自然に口をついて出てくるのではないかと思います。
・下の品の女を二條院に迎えるなどということは考えられません。
相談相手になったり、アドバイスをしてくれる侍従長のような役目の人はいなかったのでしょうか。(今の天皇が、美智子妃と結婚する際の小泉信三氏のような存在の人が)。
〇夕顔は、自分にとって有利な主人を選別できる、頭の良い、そして何よりも何ともいえない可愛いい顔をした魔性の子猫みたいな人だと、私には思われました。
でも、心もかわいい猫ならば、たとえその主人の気配は好ましいと感じても、顔を見せないご主人様なんて嫌うでしょうに。
〇惟光が、源氏に馬を提供し、自らは走りありくさまは、まるでドン・キホーテとサンチョ・パンサみたいだと思いました。
また、やつれたる狩の御衣をたてまつり、夜深きほど顔をもほの見せない源氏の姿に、少し筋違いですが、オペラ座の怪人を重ねてみたりしていました。
不謹慎だと思って発言は控えましたが、この物語にこうした滑稽な要素があるのも面白いことだと思っております。
2010年12月9日 「夕顔」 感想
「六条の女君」に次いで「隣家と頭の中将」「下の品への冒険」に進みました。
ここまでに、六条の女君と源氏についてどのように原文と解説文で描かれているか、まとめてみました。
六条の女君と源氏
「御心ざしの所には、木立前栽など、なべての所に似ず、いとのどかに心にくく住みなしたまへり。うちとけぬ御ありさまなどの、けしき異なるに、ありつる垣根・・・」
〈解説文〉六条の女君の邸は夜目にも見事な枝ぶりを見せて木立が生い茂り、庭の前栽も手入れが行き届いている。他のどことも比べられないほど垢抜けた風情を漂わせている邸である。そんな庭のたたずまいにふさわしく、いとのどかに心にくく暮らしている女君・・・。
他の女とは別格の気品を感じさせる。うちとけぬということばが、六条の女君の品の高さを語っている。こちらの緊張が解けないほどの端麗な美しさを崩さない上の品の上―夕顔の小家とは何もかも格の違うところ―の女である。
「朝明の姿は、げに人のめできこえむもことわりなる御さまなりけり。」
〈解説文〉源氏の朝明の姿の美しさを、語り手はたたえる。源氏にはやはり六条邸が似つかわしいと語り手は一言言い添えたいのだろう。
「ただはかなき一ふしに御心とまりて、いかなる人の住処ならむとは、往来に御目とまりたまひけり。」
〈解説文〉(それなのに源氏は)見知らぬ女と歌のやりとりをした、ただそれだけのはかなき一ふしが、妙に気にかかる。源氏はそれ以来六条への道を往復する度に何者の家だろうかと思って、つい目をとめてしまうのであった。
「(秋にもなりぬ。人やりならず、心づくしにおぼし乱るることどもありて・・・)、六条わたりにも、とけがたかりし御けしきをおもむけきこえたまひてのち、ひきかへしなのめならむはいとほしかし、されどよそなりし御心まどひのやうに、あながちなることはなきも、いかなることにかと見えたり。」
〈解説文〉初め、女は源氏が恋心を伝えてもなかなか心を許そうとはしなかった。それが、源氏の強引な情熱に押されてついに折れてしまう。ところが源氏は、一旦手に入れた恋に対して、手の平を返したように冷淡になる。女に向かっていた熱い気持ちが冷えているのに、形の上では恋人であるという、源氏のしらけた心をなのめということばがとらえる。
語り手は、源氏のこんな扱いに傷つく女がいたわしく、思わずいとほしかしと同情のことばを添える。女が振り向こうとしなかった時は、何が何でも女の心をつかもうと一途だったのに、何ということだろうと、語り手自身、源氏の熱の冷めように困惑している。
「女は、いとものをあまりなるまでおぼししめたる御心ざまにて、齢のほども似げなく、人の漏り聞かむに、いとどかくつらき御夜がれの寝ざめ寝ざめ、おぼししをるること、いとさまざりなり。」
〈解説文〉不幸なことに、女は物事を深刻に思いつめる性格の人だった。その上、女は相当高貴な身分で気位も高かった。女は初めから、源氏とは年齢が不釣合いなのをひどく気に病んでいた。似げなくという言い方に、若い源氏の恋の相手として年上の自分に、ひけ目を感じている女の気持ちがにじみ出ている。
もし世間の人に二人の関係が漏れてしまったら、自分は年甲斐もないと笑われるに違いない、女の恋心は屈辱感と背中合わせに、屈折した形で燃えていた。源氏の心が以前のように熱くて、まめに通って来るならいざ知らず、源氏の訪れがない夜は気が滅入ってたまらないのだった。源氏を心待ちにしながら、明け方まで独り寝覚めがちな夜を過さねばならなかった女のつらさがしみじみと伝わってくる。
「霧のいと深き朝、いたくそそのかされたまひて、ねぶたげなるけしきに、うつ嘆きつつ出でたまふを、中将のおもと、御格子一間あげて、見たてまつり送りたまへ、とおぼしく、御几帳引きやりたれば、御頭もたげて見いだしたまへり。前栽のいろいろ乱れたるを、過ぎがてにやすらひたまへるさま、げにたぐひなし。」
〈解説文〉女は源氏との逢う瀬を人に知られたくないので暗いうちに源氏を帰そうとする。人目をひどく気にして、源氏との恋に我を忘れることができない。
源氏は年上の女にせかされるまま、女のもとを出ようとするが、まだ眠気が覚めやらぬ様子でため息などをついている。女は密会に固くなっているのに、源氏にはその女の心情が伝わっていない。恋の余韻に引かれることもなく緊張感のない源氏の姿が、女とちぐはぐな今の二人の関係をあぶり出している。
源氏と一夜を共にした床に身を臥せたまま、女君は源氏と過した時間に区切りをつけられずにいる。すっかり寝込んで眠たげに出ていく源氏と、源氏との逢う瀬に身も心も浸り切って抜け出られずにいる女君。御頭もたげてという描写が、早めに源氏を帰しながらも、恋々と源氏に未練を残す女君の恋情を生々しく浮き上がらせる。
女君は臥せていた身を起こして、源氏の立ち去っていくのを見やる。源氏は庭に植えられた草花が色とりどりに咲き乱れているのを目にして、その美しさに心奪われ、立ち去り難く佇んでいる。源氏の心にはすでに女君の姿は存在していない。目の前の前栽しか映っていないようだ。その庭を背景に佇む源氏の姿はたとえようもなく美しい。げにたぐひなしという語り手のことばが、源氏の姿を目で追う女君の胸のときめくさまをも伝えている。
あぁそれなのに源氏は、見送りに供する中将の君に早速誘いかけたりするのです。そして惟光の手引きにより、いよいよ下の品への冒険に乗り出します。
今回の皆さんからの感想文は次の通りです。(文責 高松)
〇常夏の女がいよいよ源氏と結ばれる。(惟光の努力で実現する)。
源氏の情熱の強さ、興味・好奇心の強さに恐れ入りました。
〇惟光の働きにより、ついに源氏は夕顔の所へ。
“おはしませそめてけり”によって理解できるという。今日もまた古語の深さに嬉しくなりました。
悲劇の始まりだという事なので、ワクワクします。
〇常夏の女が中将の前から姿を消して、その後どこで生活しているのかと思っていましたが、この「夕顔」で、中将から身を潜めて暮らしているのがわかる。ここで源氏が夕顔の前に姿をあらわす。
頭の中将が家の前を通りすぎる話しにもって行くシナリオがにくい。
これから源氏・夕顔の恋の行方が楽しみです。
〇源氏は惟光の手引きで、やっとの思いで女のところへ通い始めようとしている。
そのために粗末な身なりをしてでも、なしとげようとする。
その心意気が伝わってきた。
〇源氏は六条の女君と別れて出口の門に通じる廊の方へ移っていく。それを見送る中将に源氏は想いを寄せ、朝顔にかけて歌に託し中将の君の手を捕らえる。中将の君はすかさず返歌。
また源氏は隣家の「下の品」の世界に好奇心と冒険心をいだき、源氏の女性に対する好奇心は上も下も関係ないようである。
〇・中将の君の手をとって「いかがすべき」と言うなんて、中年の男っぽくてちょっといやらしい感じがします。若者らしくない!
・名乗りもしない男を家に通わせるなんて、不安で今では考えられません。
現代で言えば“出会い系”という感じがします。
・夕顔に入ってから解説文量が増えました。先生の「夕顔」への思いいれの深さが感じられます。
〇物語とは作者は全くもって自由に書けるものなので、紫式部は自分におまけを加えて、自身を中将の君に投影させたものかもしれないと思いました。
読者も想像するのは自由ですので、もし私が中将の君なら「咲く花を・・・・」と源氏に美しい声で詠まれて「いかがすべき」とやさしく手をとられたら、くしゃみをして「はら、はら」とでも言ってやりますか。
〇今回冒頭で、「夕顔」の展開のキーとなる六条の女君について詳しく引用してみました。
原文と先生の解説文を対置してみる作業の中で、どのようにこの物語を読み解いていけばいいのか、とても大きな示唆をあらためて得たのではないかと実感しました。
そして「夕顔」の持つ重量感をひしひしと受け止めることもできた次第です。
2010年11月11日 「夕顔」感想
「惟光、隣家をさぐる」から「伊予の介と対面す」「六条の女君」へと進みました。
源氏をめぐる女たち、そのそれぞれへの源氏の思いが目まぐるしく交錯して物語は動きました。
夕顔―かの下が下と、人の思ひ捨てし住まひなれど、そのなかにも、思ひのほかにくちをしからぬを見つけたらばと、めづらしく思ほすなりけり。
空蝉―あさましくつれなきを、この世の人には違ひておぼすに、おいらかならましかば、心苦しきあやまちにてもやみぬべきを、いとねたく、負けてやみなむを、心にかからぬをりなし。かやうのなみなみまでは思ほしかからざりつるを、ありし雨夜の品定めの後、いぶかしく思はしなるしなじなあるに、いとどくまなくなりぬる御心なめりかし。
〈伊予の介が〉国の物語など申すに湯桁はいくつと問はまほしくおぼせど、あいなくまばゆくて、御心のうちにおぼしいづることもさまざなり。
ものまめやかなる大人をかく思ふも、げにをこがましく、うしろめたきわざなりや。げにこれぞ、なのめならぬかたはなべかりける、と、馬の頭のいさめおぼしいでていとほしきに、つれなき心はねたけれど、人〈伊予の介〉のためあはれとおぼしなさる。
〈伊予の介が〉北の方をば率て下りぬべしと、聞きたまふに、ひとかたならず心あわただしくて、今一度はえあるまじきことにやと、小君をかたらひたま(ふ)。
〈空蝉の〉なげの筆づかひにつけたる言の葉、あやしくらうたげに、目とまるべきふし加へなどして、あはれとおぼしぬべき人のけはひなれば、つれなくねたきものの、忘れがたきにおぼす。
西の方―うらもなく待ちきこえ顔なる片つ方人を、あはれとおぼさぬにしもあらねど(〈空蝉が〉つれなくて聞きゐたらむことのはづかしければ、まづこなた〈空蝉〉の心見果ててとおぼす。
〈伊予の介が西の方をさるべき人にあづけて任地に下ると聞いて〉主つよくなるとも、かはらずうちとけぬべく見えしさまなるを頼みて、とかく聞きたまへど、御心も動かずぞありける。
そしていよいよ六条の女君の登場です。(以下次回)。
今回メンバーから寄せられた感想文は次の通りです。
この感想文は講義終了後の短い時間の中で、みなさんに書いていただいたものです。にもかかわらず内容はたいへん充実したもので、毎回まとめの作業の中で、みなさんの秀逸且つ思いのこもった感想文を拝見して感銘を受けるとともに、ウィットに富んだ内容に独り感嘆の声をあげることもしばしばです。これぞ役得と思う所以であります。(高松)
〇女君もいろいろ登場しますが、男性の方も惟光、伊予の介、小君とそれぞれの特徴があり、面白い。
源氏の良いところはともかく、悪いところ(恥ともいうべきところ)も知りつくしていながら、源氏を盛りあげ、光り輝かせる。
〇男も女も、恋のかけひきや成就の為には身勝手さも我侭もと、まめでないと難しい。
だんだん複雑な人間模様が織りなされて、面白さ益々です!!
〇源氏は恋の相手を上から中・下に広げて行くことにより、頭の中将と左馬の頭も体験できない面白い恋が出来るかもと、心をはずませる。
かなり二人を意識していて新しい女性(夕顔)に対して情熱を込めて一直線と思っていると、伊予の介との対面で、空蝉が目の前から姿を消してしまうと言うことがわかる。
悶々とするうちに季節は秋に・・・・
六条の女君について語られるが、こちらも源氏の心を悩ませているよう。どう進展するのでしょうか?
〇空蝉は手紙のやりとりが続いているので、源氏とのつながりはときめいていた。
伊予に旅立つという事態に、女君の心は源氏を強く慕うのである。
伊予の介の妻は、源氏との関係を捨てきれないでいる。
源氏は、もやもやしながらも伊予の介を前にすると、それでいいのだと想ったりする。
心理描写のたくみなこと。
〇源氏は「隣家の女」に未練を示している。「下の下」の女の中にも「思ひのほかにくちをしからぬを見つけたらば」と心をはずませるのであった。
一方、源氏は「空蝉」との恋が思い通りにならなかったのが悔しくて忘れられない。しかし、「負けて」終わるわけにはいかない。
「伊予の介」が上京し、「空蝉」を同伴して帰ると言う。源氏は「ひとかたならず心あわただしく」心を迷わせた。
一方、女君も源氏との恋がこれで終わってしまい、源氏から恋文が届かなくなったら「いといふかひなく」寂しいことだろう。
今後の源氏と女君との恋の展開が楽しみである。
〇・まさか空蝉と文通が続いているとは思わなかった。直接会うことがないのなら、遠方で時間はかかるが文通は続けられそうに思う。今ならメールがあるけどなあ。
・秋の草花が咲き乱れているのを目にとめて、佇む青年は少ないかもしれない。源氏の感性の豊かさがわかる。
上村松園に、この様子を描いてもらいたかった。
〇私は今迄、伊予守に対して身の程知らずといった印象を持っていましたが、今回の描写から、案外、結構すてきな人と感じました。
彼が、帰京報告を先ず源氏にしたということは、恩義を持つ忠臣のはずで、二人は以前対面したことがあったのです。若い源氏が彼のことを口では年よりと侮りながら、その渋さ、大人の魅力を憎く思ったのも分かる気がしました。
さて、今回の傑作箇所は、源氏が伊予守の話しを聞いている時「湯桁の数」が心によぎってきたところです。私も、深刻な場面においてさえ、決して戯けているわけでもないのに、馬鹿馬鹿しく下らないことを思いついてしまうことがあります。
湯桁のことは聞かずじまいで大正解!
〇源氏は、空蝉には複雑な思いを持ちつつ、夕顔については惟光に「なほ言ひ寄れ、尋ね寄らでは、さうざうしかりなむ」と命じます。
西の方に至っては、何と、主が決まっても「かはらずうちとけぬべく見えしさま」から、特に心を動かすことはないのです。
次に描かれる六条の女との交情は、今までものとは少し違った趣が感じられます。しかも、その背景には藤壺との道ならぬ恋が影を落としているのだそうです。
下も下、しかも無粋きわまる私などには全く思いもよらない別世界です。でも登場人物それぞれの人間くささについては、私たちと共通するものを読み取ることができます。
2010年10月14日 「夕顔」感想
「扇の歌」から「惟光、隣家をさぐる」に進みました。
源氏は御畳紙に
寄りてこそそれかとも見めたそかれに ほのぼの見つる花の夕顔
と、いたうあらぬさまに書きかへたまひて、御随身につかはせ、乳母の家をあとにします。
それから源氏は
来しかたも過ぎたまひけむわたりなれど、ただはかなき一ふしに御心とまりて、いかなる人の住処ならむとは、往来に御目とまりたまひけり。
日を置いて惟光は隣家の女について源氏に報告します。
時々中垣のかいま見しはべるに、げに若き女どもの透影見えはべり。褶だつもの、かことばかり引きかけて、かしづく人はべるなめり。昨日、夕日のなごりなくさし入りてはべりしに、文書くとてゐてはべりし人の、顔こそいとよくはべりしか。もの思へるけはひして、ある人々も忍びてうち泣くさまなどなむ、しるく見えはべる。
源氏はうちゑみたまひて、知らばやと思ほしたり。
今回メンバーから寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇現代は、朝も昼も夕も深夜もなく明るい。電気があるから。
あの頃は光を大事にして、すき間から見える火の光、松明のほのかな明り、蛍の光、夕日のなごり透影、そして顔こそよく、日さし出づるほどの朝明けの姿。
〇なかなか夕顔の姿がみえず、源氏が心ひかれて行く様子が面白いし、男が女に魅かれてゆくプロセスも面白い!! いつの世も変わりがないなと。
〇8月に夕顔に入りました。9月10月、まだ夕顔がどういう女性か見えてこない。わざと作者がじらしているのか?
今回も、裳、褶(しびら)など新しく覚えました。身分の高い女性の後ろ姿の裳、身分の低い人の褶、どちらも素晴らしい衣装でほれぼれとします。
〇六条の女の邸への往復の道すがら、源氏は気にかかる女(夕顔)が惟光の報告でわかってきた。
中垣からかいま見る、若き女たちに囲まれ西日に照らされた美人だと聞かされ、源氏は自分が想像していたとおりだと顔をほころばせる。
いよいよ源氏の好奇心がふくらむのである。
〇乳母の見舞に行った帰路、隣家の「扇の歌」の女との出会い。
源氏はその女を「めざまし」と思ったが、「憎からず過ぐしがたく」と付き合う。
乳母の家を後にして「御心ざしの所」へ向かったのだが、源氏はそれ以来その道を往復する度に、目を止めてしまうようになった。隣家の女は用心深く住んでいるという。
源氏の探究心はどこへ行くのだろうか。
〇空蝉は美人ではなかったのに大変なご執心で、今回とはだいぶ違うのは何故だろう。
〇夕顔の宿はまったく奇妙です。
揚名の介は、何の為に社会的ポストをお金を出しても手に入れたいのか。成金にしては家は貧相だし、そこに仕える女房達の素姓も描けません。
夕顔を筆頭に、正体不明の人物がここではうごめいています。
今昔物語のように感じました。
〇隣家のなぞの女に、私たちも源氏の思いを通して引き込まれていきます。しかも何か穏やかならざる雰囲気も漂わせているのです。「夕顔」はまだ始まったばかりですが、この展開に式部の力量・面目の躍如たるものを感じます。
2010年9月9日 「夕顔」感想
「夕顔の小家」から「病気見舞」「扇の歌」へと進みました。
講義の中で源氏の心の動きに話題が集中しました。原文を追って見ます。
〈重い病に伏せる尼君(大弐の乳母)を源氏は見舞って〉
「日頃おこたりがたくものせらるるを、安からず嘆きわたりつるに、かく世を離るるさまにものしたまへば、いとあはれにくちをしうなむ。命長くて、なほ位高くなども見なしたまへ。さてこそ、九品の上にも、障りなく生まれたまはめ。この世に少しうらみ残るは、わろきわざとなむ聞く」など、涙ぐみてのたまふ。
〈さらに自らの生い立ちにも思いをはせつつ〉
「いはけなかりけるほどに、思ふべき人々の打ち捨ててものしたまひにけるなごり、はぐくむ人あまたあるやうなりしかど、親しく思ひむつぶる筋は、またなくなむ思ほえし。人となりて後は、限りあれば、朝夕にしもえ見立てまつらず、心のままにとぶらひまうづることはなけれど、なお久しう対面せぬ時は、心細くおぼゆるを、さらぬ別れはなくもがなとなむ」など、こまやかに(かたらひたまう)。
修法など、またまたはじむべきことなど掟てのたまはせて、出でたまふ。
〈一転源氏は〉
ありつる扇御覧ずれば、もてならしたる移香、いと染み深うなつかしくて、をかしうすさび書きたり。
心あてにそれかとぞ見る白露の 光そへたる夕顔の花
そこはかとなく書きまぎらはしたるも、あてはかにゆゑづきたれば、いと思ひのはかにをかしうおぼえたまふ。
惟光に「この西なる家は何人の住むぞ。問ひ聞きたりや」
〈と命じ、うるさがってそっけなく答える惟光に〉
「憎しとこそ思ひたれな。されど、この扇の尋ぬべきゆゑありて見ゆるを、なほこのわたりの心知れらむ者を召して問へ」と
〈のたまふのでした〉。
今回メンバーから寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇仏教の事はよく知りませんでしたので、今日のご説明でとても理解出来、興味が広く深くなりました。
早く花が開く方が良い話、年とって了い、ちょっと困ったなと思ったりして。
〇源氏の性格の多面的なものが感じられ、面白く楽しみました。
やさしさやまめさ、そして次へのドラマが思われ、興味ますますです。
前回の講義で、「常夏の女」が「夕顔」だと知りました。
忽然と姿を消した潔さ、そしてあからさまにしない性格に見えた女(常夏の女)と、大胆に男を誘うような歌を渡した女(夕顔)とが、行いの面で同一人物とは思えず、腑に落ちないところがあります。これから物語がどう展開していくのか、期待しています。
〇いよいよ扇の歌「光そへたる夕顔の花」と、女は源氏を名指している。源氏の気持ちは西なる家に変わる。
乳母とのふれ合いは、浄土教の教えのことまで織り込まれ、当時平安時代において、浄土教が貴族社会にも浸透してきていることがわかる。
〇乳母の病気を見舞った源氏と乳母の涙ながらの遣り取り、真に迫るものを感じた。
乳母の家を出た源氏は、またまた「扇の歌」の主を詮索、全く源氏は多情多恨。
〇・先日湯島天神へ出かけたら、社殿の側面に半蔀がとりつけられていることに気づきました。猛暑日だったので、全部の蔀戸が上に引き上げられていて壮観でした。
源氏で学習したので「これが蔀戸!」と気づくことが出来ました。貧家に使われているのかと思ったら、神社建築にも使われているのですね。
・ストーリーを考えるだけでも大変なのに、いちいち美しい和歌も作って書き入れていく紫式部の才能にびっくり。この時代の物語としては普通のことだったのでしょうか。
〇17才の源氏が 死んでいくであろう 乳母を きれいな目でじっと見つめて、励ましている姿が 目に浮かびます
彼の 囲りには 大切な人が多くいて お互いに愛しあっていますので 彼の心は 乾くことはないのに 何故か彼の心の中には いつも 小さな石コロが生まれて 寂しくぶつかり合っていて 私は その音を聴いてしまいます
〇乳母を涙ながらに見舞う源氏。また手際よく祈祷の僧などの手配を命じる源氏。一転して、しぶる惟光に「西なる家」の住人を問えと命じる源氏。青年源氏の面目躍如たるものがありますね。「才色兼備」且つ情厚く、上司としては申し分ないのでは。いや下々の嫉妬の的になるかも。
2010年8月12日 「空蝉」「夕顔」感想
?「うつせみの心」を最後に「空蝉」を了え、「夕顔」に入りました。
「空蝉」は
うつせみの 羽に置く露の 木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな
で締めくくられた悲恋の物語でした。
その余韻を残し、「夕顔」では一転
「六条わたりの御忍びありきのころ」と、新たな物語が始まったのです。
「空蝉」から「夕顔」へ、私たちの読書会もいよいよ熱を帯びてきたと言えましょう。
メンバーの意気込みが、寄せられた感想文に満ち満ちています。(文責 高松)
〇空蝉のなんとも切ない心情
西の方の哀れな女心で空蝉が終わり
夕顔へ
17才の源氏の諸々の好奇心がみえる
これからが楽しみ!!
〇空蝉は、源氏に対する熱い想いを畳紙の片隅に歌を書き付ける。
悲しいことに、この歌は源氏に届くことはなく幕が下り、その後の空蝉がどうなるか気がかり。
夕顔に入り、新しく源氏と女性の出会いを予感させて、これからが楽しみです。
〇空蝉の心は、ちじにみだれ源氏を想い苦しむのだ。
西の方も、わけがわからないまま源氏を想う。何んと罪深き男よ。
いよいよ夕顔の章に入る。
謡本では「半蔀」とか「夕顔」があるが、夕方に咲く「夕顔」の白い可憐な花が、この物語りの筋書きを暗示している。楽しみである。
〇源氏のもとから紀伊の守邸に戻った小君は、姉君の容赦ない叱責に遭う。二人の間にはさまって振り回される小君は、それでも懐にしのばせた源氏の手習畳紙を取り出して姉君に差し出す。
姉君は、小君を叱責していた態度とは打って変わって、源氏の畳紙に眼を注ぐ。
「もぬけ」の衣が源氏の手中にあることを知った姉君は、恥かしくなってしまう。姉君は拒絶し続けている源氏が、なお自分に思いを深めていることを感じ、畳紙の端に涙にくれる歌を書き付ける。
汗で汚れた衣を「伊勢をの海士のしほなれて」と表現した作者に感動。
〇いつもながら状景描写のすばらしさ、古語の美しさに感動しています。
これから続く長い物語の伏線が、ところどころにちりばめられ、わくわくしながらクラスに参加しています。
〇「空蝉」
・近くへ寄れば身をかくす人を“帚木”にたとえたり、慕う女の脱ぎ捨てた薄衣を“空蝉”にたとえたりする紫式部の豊かな感性と表現力に圧倒される。
・「恋の至極は忍ぶ恋と見たて候」という葉隠れの一節を思い起こす。
「夕顔」
・現在京都駅は九條のあたりだが、平安の頃は六條あたりまでが街中だったのだろうか。
・下々から見れば、「ものはかなき住まひ」と「玉の台」はやはりえらい違いだと思う。源氏は上の目線で見ていると思う。
・警護のSPも、なんと風流なこと!現代では四方八方に目をきょろきょろさせているのに。
〇わが心に 叶はぬことばかりの うつせみゆゑ
ひとしき手習いに 書かれし言の葉は さてありぬべし
源氏の あはれなりつる心のほどなむ 忘れむ世 あるまじけれど
こは とく 棄つべきとぞ 我思ほゆる
〇桐壺、帚木、空蝉、そして夕顔と進んできました。
物語は、源氏を中心とした多彩な人物が複雑に絡み合って展開していきます。
夕顔の出だしは一転格調高い文章で始まりました。
先生のお話では「色んな夕顔論があり、むづかしい章です」とのことですので、しっかりと読み進んで行きたいと覚悟を新たにしております。
2010年7月8日 「空蝉」 感想
「西の御方と」「源氏、御達をまく」「しのぶの薄衣」を読みました。
源氏は西の御方に「人知りたることよりも、かやうなるは、あはれも添ふこととなむ、昔人も言ひける。あひ思ひたまへよ。つつむことなきにしもあらねば、身ながら心にもえまかすまじくなむありける。また、さるべき人々も許されじかしと、かねて胸いたくなむ。忘れで待ちたまへよ」、さらに「なべて、人に知らせばこそあらめ、このちひさき上人に伝へて聞こえむ。けしきなくもてなしたまへ」と言いおいて、女君の「脱ぎすべしたると見ゆる薄衣を取りて」去ります。
「暁近き月、隈なくさし出で」るなか「老いたる御達」に誰何される窮地を小君の機転に救われ、源氏は二条の院に帰り着きますが、またしてもの不首尾に「をさなかりけり」と小君を「あはめたまひ」たり、「かの人の心を、爪弾きをしつつうらみたまふ。」
「などか、よそにても、なつかしきいらへばかりはしたまふまじき。伊予の介に劣りける身こそ」と源氏は嘆き、「ありつる小袿を、さすがに御衣の下に引き入れて、大殿籠もれり。」
源氏は「しばしうち休みたまへど、寝られたまはず。御硯急ぎ召して、さしはへたる御文にはあらで、畳紙に、手習のやうに書きすさびたまふ。」
うつせみの 身をかへてける 木のもとに
なほ人がらの なつかしきかな
小君は源氏が「書きたまへるを、懐に引き入れて持たり。」
一方西の御方には、源氏は「かの人もいかに思ふらむと、いとほしけれど、かたがた思ほしかへして、御ことづけもなし。」そして「かの薄衣は、小袿のいとなつかしき人香に染めるを、身近くならして、見ゐたまへ」るのでした。
今回会員から寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇空蝉の薄衣、ほんとにミステリアス
源氏が共寝し、恋しく思い、懐かしく想い、恨みがましく、腹立たしく、そして疲れて寝つく
〇 ・受け入れてもらえない女性は初めての事でしょう
深く心にきざみ込まれてどんな影響をおよぼしていくのでしょう
・いろいろ心悩ます小君、頑張れ!!
〇この空蝉は、源氏17才の挫折と優しい心、非難、排斥の気持を表すなど、大人になる前の心を表しているのかな?と思いました。
〇源氏は空蝉の脱いだ薄衣を抱えてもち帰り、手元に残された薄衣をじっと見入っている。
源氏の口惜しい心情が伝わってくる。
それにしても小君と西の方は気の毒。
〇心惹かれている女君に「すべり出て」られてしまった源氏は「人違へ」で別の女を口説くことになってしまったが、源氏はこの女の「なま心なく若やかなるけはい」に魅力を感じ、口説き文句を並べた後、女君が脱ぎすてた薄衣を持って退散。
再三にわたって女君に会うことを失敗した源氏は、寝られぬ夜を過し畳紙に恋歌を書きつける。
小君からこの畳紙を渡された女君は、自分の薄衣が源氏の手に渡ったことを恥しく思ったが、更めて源氏の思いの深さを知り、畳紙の片隅に返歌を書きつける。
源氏と女君の恋のやりとりは、どのような結末を迎えるのか、今後の展開が楽しみである。
〇 ・後朝の文ももらえず“夜這い”に遭うなんて女性として腹が立つ!
その後“うっちゃっておく”なんてあまりにもひどい。ウソの理由でもいいから手紙を書いて、文箱とか香炉とかをプレゼントすればいいのに。
・畳紙は、現在は着物をしまう時に包む和紙のことを言うので、ふところに入るような小さな紙を畳紙というとは思わなかった。
〇人柄は 品のほどの名残たるとは なべて まさしと 自らも思ふ
なつかしき人と おもはれむことぞ あらまほしき わざなれ
〇一途に女君への想いを募らせますが、思い通りには成就してくれない恋に源氏は苦しみ悩みます。これって青(少)年の恋ですよね。思い起こせばはるか半世紀以上前に、この私も身を焦がした事がありましたっけ。ありました、ありました。
それにしてもこの物語に登場する女性たちは、例外なく、それぞれに個性的で魅力あふれる存在ですね。驚きです。
源氏の心を通して、いや式部の目を通して、これから私も彼女達に恋心を燃やしていきたいと思っております。ひそかにです。
2010年6月10日 「空蝉」 感想
「もぬけ」 「人違へ」を読みました。
源氏は「皆しづまれる夜」、小君の「導くままに、母屋の几帳の帷引き上げて、いとやをら入りたまふ」。
女君は源氏が「さこそ忘れたまふを、うれしきに思ひなせど」、源氏への想いから「昼はながめ、夜は寝覚がちなれば、春ならぬこのめも、いとなく嘆かしきに」、「寝だに寝られず」にいます。傍らには「若き人(西の御方)」が「何心なくいとようまどろみたるべし。」
しかし女君は「いとかうばしくうちにほふに」、源氏が「暗けれど、うち身じろき寄るけはひ」を感じとり、「あさましくおぼえて、ともかくも思ひ分かれず、やをら起き出でて、生絹なる単を一つ着て、すべり出でにけり。」
源氏は「衣をおしやりて寄りたまへるに、ありしけはひよりは、ものものしくおぼゆれど」、すぐには気付かず、「いぎたなきさまなどぞ、あやしくかはりて、やうやう見あらはしたまひて、あさましく心やましけれど、人違へとたどりて見えむも、をこがましく、あやしと思ふべし、本意の人たづね寄らむも、かばかりのがるる心あめれば、かひなう、をこにこそ思はめとおぼす。」さらに「かのをかしかりつる火影ならば、いかがはせむにおぼしなる」。
そして語り手に「わろき御心浅さなめりかし。」といわれてしまうのです。
西の御方は「やうやう目さめて、いとおぼえずあさましきに、あきれたるけしき」です。
源氏は「何の心深くいとほしき用意もなし。世の中をまだ思ひしらぬほどよりは、さればみたるかたにて、あえかにも思ひまどはず。」と見ます。そして「われとも知らせじと思ほせど、いかにしてかかることぞと、のちに思ひめぐらさむも、わがためにはことにもあらねど、あのつらき人の、あながちに名をつつむも、さすがにいとほしければ、たびたびの御方違へにことづけたまひしさまを、いとよう言ひなしたまふ」。こんなことは「たどらむ人は心得つべけれど、まだいと若きここちに、さこそさしすぎたるやうなれど、えしも思ひ分かず。」と読んだうえでのことです。
源氏はこの女に「憎しとはなけれど、御心とまるべきゆゑもなきここち」ですが、女君にも「なほかのうれたき人の心いみじくおぼす。いづくにはひまぎれて、かたくなしと思ひゐたらむ、かく執念き人はありがたきものをとおぼすにしも、あやにくにまぎれがたう思ひ出でられたまふ。」のでした。
今回会員から寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇空蝉は悩みをかかえ、夜は寝つかれず昼は気もそぞろで、ぼんやりと物思いにふける。
片や源氏の方は健康で、さしたる悩みも持っていなくて、夜はぐっすりと寝入り昼は明るく思うままに振るまう。
そんな対比が面白いと思いました。
〇大人だったり、ちゃめっ気のある若者だったり、源氏の性格の多面性。
そして男性が女をどうみるか。
今も昔も変わらないと面白い。
〇帳台に忍び入った源氏は相手が空蝉でなく人違いだと気付くが、なぜか逃げないで、どこまで帚木なのかと呆然とする。
床の下に二人ばかり寝ている所で、とっさにどうしようかと思いを巡らす。この状況でも空蝉のことを思いやる。
源氏の行動に異論が沸き起こって盛り上る。
〇空蝉にまたもや逃げられ、西の御方のところへ行くことになった。
源氏は空蝉に対する思慕がつのるばかりなのである。
語り部の式部としては、これはこれはとつき離して見ているのだろう。
〇女君は「寝だに寝られず、昼はながめ、夜は寝覚めがち」の心境にもかかわらず、それとは裏腹に「いとかうばしくうちにほう」源氏の気配を感じ「すべり出でにけり」と逃げ出してしまう。
またもや女君に逃げられた源氏の次の手段はいかに。
〇 ・源氏に「つまらぬ女」と思われながら初体験をするなんて、この女性はかわいそう。
・衛生設備の完備していない時代は香(西洋では香水)が必要だったのだろう。遠くにいる人の匂いが感じられるのは、よほど強く香を焚きしめていたのだろう。
〇こたみの源氏の色好みの勇みは、二人の女君にとりては、いとかたはらいたきわざにて、責むベけれど、若やかなる心やさしき人は、をこなるふるまひも、時として、ありてありなむとこそおもゆれ。
〇うまく忍び込めたものの右往左往する源氏、しかも世知長けて思いも巡らす源氏、そして空蝉にさらに想いを募らせる源氏。心の動きに忠実に従う源氏像の姿は滑稽ですらあります。
こうした源氏を肌理細やかに描ききる式部の筆力には何時もながら強い感銘を受けました。
揺れ動く女君の姿についてもそうですし「単を一つ着て、すべり出でにけり」の表現にはしびれました。秀逸というほかありません。
西の御方についてはややきつく描かれていますが、「若さ」の魅力はあふれんばかりですし、若い源氏がそれなりに惹かれるのも理解できます。
ところで源氏物語とは一体何なんでしょう。
2010年5月13日 「空蝉」 感想
「かたちくらべ」から「小君、たばかる」に進みました。
三度挑戦した源氏は、簾のはざまから対照的な二人の女性―空蝉と西の御方―をつぶさに観察します。そのリアルで生々しい描写には驚くばかりです。
源氏は「あはつけしとはおぼしながら、まめならぬ御心は、これもえおぼし放つまじかりけり。見たまふかぎりの人は、うちとけたる世なく、ひきつくろひそばめたるうはべをのみこそ見たまへ、かくうちとけたる人のありさまかいま見などは、まだしたまはざりつることなれば、何心もなう、さやかなるはいとほし」と描かれています。
「さて、今宵もや帰してむとする。いとあさましう、からうこそあべけれ」と抗議する源氏に対し、小君は「などてか。(西の御方が)あなたに帰りはべりなば、たばかりはべりなむ」と健気にも言うのです。
今回会員から寄せられた感想は次の通りです。(文責 高松)
〇新疆ウイグル博物館に行った時の事、頬ペが赤い、髪を高々と結い上げた女性二人が碁を打っている古代の絵を拝見して、その時もああこうしてシルクロードを通って碁が伝わったんだと思いました。
そして今日源氏のこの場面、ご説明もとてもよく、感激でした。
〇源氏の女性観は現代にも通じる男性の願望でしょう。
そして知らない女性の世界をのぞいたドキドキワクワク感が楽しかったです。
〇囲碁をしている二人の性格を源氏は観察する。
多分空蝉については思っていた通りだと思いますが、若い女が対照的にかわいらしい態度を見せる。
もし囲碁に勝った空蝉がはしゃいだらどうだろうか?源氏はがっかりするだろうか?
〇源氏は小君の手引きで二人の女性の碁を打っている姿勢をつぶさに見ることができた。
源氏は小君に、姉のところへの案内をまかせようと思う。小君は子供ながら源氏の気持ちがわかるのだろう。
一夫一婦制(鎌倉時代頃から社会的に定着していったようだが、貴族社会は一夫多妻が続いたであろう)の現代人の感覚ではわからないことである。
式部は貴族社会の様子を克明に記録することによって、宮中生活のノウハウを教えたに違いない。
〇源氏はやっとのことで「碁打ち」中の女の横顔を見ることができた。微に入り細にわたる源氏の品定めが始まる。
若い女は「すこし品おくれ」。想いをかけている女は「わろきによれる容貌」。しかし「心あらむ」女に源氏は好感を持つ。
源氏の品定めは二人の女の間を行ったり来たり。正に「かたちくらべ」であった。
①解説文を読まなければ本文は理解できないくらい簡潔な文章で書かれているのに、当時の読者はその行間を読むことができたということが不思議に感じます。
②源氏は年令は石川遼、女性へのまめさはタイガーウッズ。
③西の御方は“すこし品おくれたり”と源氏は感じたようだが、現代っ子ぽくてかわいい。
〇光君の かいま見は たどたどしかるまじき ここちこそ 我は 思ほゆれ
〇「帚木」から中の品の女を中心に物語は進んできました。「空蝉」に至っては、源氏自身の、上の品から身分を落とした女君との交情、そして対照的な中の品の西の御方が登場しました。
なんとも多彩で変化に富み、しかも肌理細やかに描かれていて、ますます源氏物語に魅了されます。
2010年4月8日 「空蝉」 感想
今回から「空蝉」です。「それぞれの夜」 「三度挑戦」 「碁打ち」 へと進みました。
女君の心は「よきほどに、かくて閉ぢめてむ、と思ふものから、ただならず、ながめがちなり。」と語り尽くされています。
しかしと言うか、そしてと言うか、物語は思はぬ展開を遂げていくのです。
〇話はというかドラマは次々と展開し、微にいり細に及ぶ。
空蝉の身の気持ちのかたさが、用心深さが、主人の留守の時でも、暑さが酷しくても、少しも変わらずくずさない処、なんとも奥ゆかしい。
〇成せば成るですね。小君も源氏のたばかれの命に心をくだき、時を得ました。
こがれていた女を冷静に観察する源氏。
命によろこぶ小君、頑張れ!!
〇空蝉は今まで源氏と係ってきた女性と違い、容姿、見た目はよくないと思いますが、内面の美しさと言うか、振舞いしぐさの奥ゆかしさに源氏は惹かれて、自分でもよく分からないまま恋に陥ってしまったと思います。
こう言うことは現代でもよくあることだと思います。
〇碁打は宮中で流行していたようだ。
奈良時代の正倉院御物にも現存しているのであるから、平安貴族の間では相当普及していたのであろう。
空蝉の心の変化を描写しているところが面白い。
小君が源氏に手引をするところも面白い。
式部が的確に物語を展開しているのも面白い。
〇小君の折角の手引きも功を奏せず、源氏は女に会うことができない。意気消沈の源氏の姿を見て、小君も涙を流して心を痛める。
一方、身を隠して源氏を拒んだ女も、気がとがめている。源氏から音沙汰がなくなると、心配になる。
源氏は気を取り直して「三度挑戦」。正に恋の闘いである。
好機到来、紀伊守の留守中に小君の手引きで、源氏はやっと女の横顔を見るに至る。
さて、その結果は?
・小君は自分のご主人様の無理な願いを叶えるために、どんなに考えぬいたことだろう。いじらしい。
・京都盆地の暑さの中で何枚もの着物を重ね、風通しの悪い家の中にすわっていたら、アセモで苦しめられそう!
・夜中に忍び入るのなら、外見の美しさはあまり関係なさそう。
〇空蝉の心の葛藤あり。源氏・小君それぞれの心の中が書かれ、楽のしい2時間でした。
〇紀伊守邸の造りがどう考えても分からなくて、悩んでしまいました。
格子はどうめぐらされているのか、何故妻戸は必要なのか、基本的なことがまだ分かっていません。
もう少し悩んでみます。
〇こうした男と女のかかわりから何が見えてくるのか、物語をじっくりと読み進んでいきたいと考えています。
2010年3月11日 「帚木」 感想
今回でようやく「帚木」を了えました。ここまで来るのにほぼ二年がかりでした。千年前の人間の恋の物語がこれからも続きます。
人それぞれの思いはあっても、この物語に惹かれる点では何の違いもないことでしょう。時空を超えて物語は私達の心に迫ってきます。
「命ある限り」を再確認して、さらに「源氏」の世界を読み進めていきましょう。
メンバーから寄せられた今回の感想は以下の通りです。(文責 高松)
〇まるで、ドラマを見ている感じで、想像をたくましくされました。
平安時代の色模様は、なかなか奥が深く、味はい深いもの。
〇あきらめようとすれば燃えあがる恋情
拒絶されれば希求する恋情
真意を伝えない伝わらない状況が面白い
懊悩を理解するにはまだ幼い小君の惑いが可愛く愛しい
〇光源氏17歳ぐらい、初めて女にこばまれる。伊予介の妻である女は身分の高い家に生まれたがゆえに、今の立場で源氏の愛を受け入れることができない。ここまでは女としか表現されないが、次回より空蝉として登場する。どう愛が進展して行くか楽しみです。
〇源氏は女君の逢瀬を求めて、弟の小君を使って紀伊守邸にのりこむが、女君は隠れて出てこない。
源氏は小君に同情して一夜を過ごすとのこと。源氏のやさしさを強調している語り手(式部)が気をもたせる。
〇断られても断られても源氏は女の心をつかむまで執念深く迫る。その間に挟まって右往左往する小君。
女の心は揺れに揺れる。
「あはれ」を解さない女だと源氏に思われるように振舞って、この愛を葬り去ろうと決心する。
源氏は「帚木」に例えた歌を詠むが、女もその返歌に「帚木」を例える。
このすれ違い、いつ解決するのだろうか。
・女たちが憧れている光源氏なのに自分の姉は何故逃げるのか、小君はそれが不思議でならなかっただろう。
・こんな時代に信濃の国の帚木の情報が都まで入っていたということがこれも不思議。地方との交流がかなりあったのだろうか。
・女に拒絶された源氏が「いたくうめきて、憂しとおぼしたり」とあるが、この表現、若者より中年っぽい感じがする。
〇今回「遣水の面目」という表現が出てきましたが、私はこの言葉がいたく気に入り、使わせてもらおうと思います。
式部のこの粋な心と豊かな感性が、愛すべき人々を上品に演出しているかしらと思います。
〇女君は、妻であり、姉であり、一人の女でもあります。また彼女のここに至るまでの複雑な背景もあります。そうしたことを全て踏まえて、揺れ動く女君の恋心を重層的に隈なく描き上げていく式部の筆力に脱帽します。
2010年2月11日 「帚木」 感想
「にわかの文」から 「使者小君」へ読み進みました。
今回は休日に当たって何時もの教室が確保できなかったため、何と生徒たちが大挙先生宅に押し寄せ講義を受けた後先生手作りのご馳走をいただくなど、身に余る光栄によくしたわけであります。
生徒たちは、青年の如く旺盛な食欲を発揮したうえ談論風発、実に楽しいひと時をすごさせていただきました。
先生ありがとうございました。
メンバーから寄せられた感想は下記の通りです。(文責 高松)
〇小君の存在が面白いと思いました。青年にならない前の男の子は、まぶしいばかりの美しさがあります。
女性が可愛いいと思ふのは勿論として、源氏も自分の恋のために利用することとは別に、この幼子にひかれるのも可愛いい限りです。
〇恋をあきらめようとする女と 恋の炎をとめられない男
分別と若さ 恋の行方はいかに?
〇恋人への手紙を人づてに渡して、感情が昂ぶっていくのがわかる。
「目も及ばぬ御書きざま」 「霧りふたがリて」 など、現代人の若者がこのような恋ができるであろうか。
〇弟から受け取った源氏の手紙を 「面隠しに」 読んだ女は、「目さへあはで」 の文に 「霧りふたがりて」 源氏への恋心を表す。
されど、女はわが身の 「宿世」 を思い 「めでたきこともわが身からこそ」 と身を引いてしまう。
源氏と女君の切々とした心情が伝わってくる。
〇女を口説けばすぐなびくと思っている源氏にとって、手ごわい女が出現。
女君にとっては、現代でいえば戦後の没落華族のように、生活のために嫁いだ後でハイクラスの男性が現れたのだから、心も千々に乱れたことでしょう。
光源氏は罪作りな男です。
〇小君は何色の衣裳を作ってもらったのでしょう。
源氏の君と小君が二人で仲良く歩いている姿を想像すると、私の方も、ついにっこりしてしまいます。
〇源氏の容姿について直接的に触れられているのは今回の 「頸細し」 のほか一箇所だけだと先生からうかがいました。お茶目や皮肉屋など「光る」以外のイメージも山ほど受け取ってきているのに意外な感じがしました。
そこから敷衍して、はたしてこの物語が描こうとしているのは「源氏」なのか、あるいは「源氏を中心とした群像」なのか、はたまた当時の「人々の心のさま」なのだろうかなどと思いめぐらす事になり、この物語を読んでいく新たな面白さが加わったような気がしました。
2010年1月14日 「帚木」 感想
「夫の面影」から「心のこり」 「したごころ」へ進みました。
源氏のうた 「つれなきを 恨みも果てぬ しののめに とりあへぬまで おどろかすらむ」に
空蝉は 「身の憂さを なげくにあかで あくる夜は とり重ねてぞ 音もなかれける」と返します。
源氏は 「月は有明にて、光をさまれるものから、かほけざやかに見えて、なかなかをかしき曙なり。何心なき空のけしきも、ただ見る人から、艶にもすごくも見ゆるなりけ」るなかを帰っていきます。
「すぐれたることはなけれど、めやすくもてつけてもありつる中の品かな、隈なく見集めたる人の言ひしことは、げに」と源氏は思います。
続いて源氏と紀伊の守のやりとり
「その姉君は、朝臣の弟や持たる」
「さもはべらず。この二年ばかりぞ、かくてものしはべれど、親のおきてに違へりと思ひ嘆きて、心ゆかぬやうになむ聞きたまふる」
「あはれのことや。よろしく聞こえし人ぞかし。まことによしや」
「けしうははべらざるべし。もて離れてうとうとしくはべれば、世のたとひにてむつびはべらず」
今回のメンバーの感想は下記の通りです。 (文責 高松
〇なかなか難解な処でしたが、先生のご説明でよくわかりました。
現代の言葉がじゃまして、なかなか理解をするのが大変な処です。
〇恋も困難になればなる程、いやましてくるのは今も昔も同じ、そしてやじ馬根性も同じ。
なんだか嬉しい今日の感想です。
〇源氏は今までと少し違うタイプの女君と出会ってすっかり恋をしてしまい、なんとかもう一度心を通わせたいと策をねる。弟を手なずけようとするが、意外にも手ごわい。
身分の違う男どうしの火花を散らす場面も面白いし、当時としては珍しいのではないでしょうか?私としては身分の低い人の味方です。
〇源氏の気持は夫のある女性でも近づきたいと思う。そう思うのも当時の貴族社会の特徴か。
現代のような罪悪感は通用しない。オープンで恋愛至上主義なのはうらやましい限り。
現代がいかに「窮屈」な時代なのかということかもしれない。
男と女の上下関係がなくなる時代が到来することがあるとすれば、源氏の世界に近づくことになるのかな。
〇鶏の鳴き声にせきたてられ「心あわたたしく」別れの歌を詠む源氏。それに対する女の返歌は「身の憂さを・・・・」とつらい気持を伝える。なかなか心が一つにならない、歯がゆい二人。
「有明の空のけしきもすごく見ゆる」と源氏の心中を空のけしきに例えた表現力に感心。
〇短い言葉にこめられた真意を考えながら読む楽しみ。
情景を思いうかべながら一言一言の重みを感じます。
〇空蝉の君の純粋な気立ての良さが、源氏の君の心を揺らしたと思います。
光源氏を泣かせられる姫君は、どのくらいいたのでしょうか。
〇別れのとき、女が泣くのが定番と思っていましたのに、女の前で男が泣くとはいささか理解に苦しんだところです。
それと、西洋の物語に00公爵夫人や00伯爵夫人との恋愛沙汰がよく出てきますが、東西の貴族社会の共通性を感じるのと同時に、当の公爵や伯爵はどう思っていたのだろうかとか、伊予の介がこのことを知ったときはどうするのだろうかとか、そんな下世話なことを考えていました。
2009年12月10日 「帚木」 感想
「しのび込み」から、「ちひさやかなる人」、「口説き上手」まで進みました。
いったい「源氏物語」から何がとび出してくるのでしょうか。この「帚木」にしても、長い長い雨夜の品定めから空蝉との出会いまでに、私達の思いもよらなかった、じつに多くの場面に遭遇してきました。今回も、なんともすごいラブシーンが登場したのには正直驚きました。
メンバーが受けた衝撃の大きさが、以下の感想文からもうかがえます。(文責 高松)
〇今日の処は “動もなくて” に圧倒されて、総て源氏に通じているような気持ちがしました。
身分、衣、香り、くどき。 こうした事で始まり、展開して、そして終わりとなる。
〇身分の上下による様々な思惑。 女も男も せつなく哀れの思い一入。
源氏物語の世界が益々面白くなってきました。
〇源氏と女君の「仮なる浮寝」の一節は、純文学の世界か。
仏教的な戒律が平安貴族の中では、浸透していなかったのであろう。
人間的な点ではすばらしい。現代の北原白秋は人妻との交際で、姦通罪で服役した。
〇いきなりの闖入者に女君の驚きよう、遂に果たした源氏の心、まざまざと伝わってくる。
源氏の口説き文句に、「消えまどへるけしき」で抵抗する女君。
抵抗する女君の言葉にたじろぎながらも口説く源氏。
女君の心は揺れ、遂に恋心を告白。
読む方も心が痺れる。
〇「夜這い」は今では考えられないことなので、眠っている所へ男性が入ってきたら、どんなに驚くことでしょう。下の品の女としては「ギャー」と大声を出してしまいます。
空蝉の態度を「なよ竹のここちして」と美しく表現している紫式部の文章にひかれます。
〇かんけつな言葉にこめられた 奥深い意味を考えながら読む源氏、ますます これからが楽しみ。
空蝉のせつない心情を思いながらの 今日の二時間でした。
〇源氏の君は、少し優しさが欠けていると思います。17才でも暖かくて、人の気持ちが分かる子はいると思います。
空蝉の苦しさ、切なさを感じ、この出来事は決して人に知られず、葬ってあげたいです。
〇世の中には男と女しかいないのに、その係わりあいには千年たっても語りつくせないものがあるのですね。また、男と女ではその受けとめ方がまるで違う事にも、今更ながら感じ入るものがありました。
お叱りを受けるのを覚悟の上で申しあげますが、先生の解説文が極めて冴えわたっているように思え、感銘を受けました。
2009年11月12日 「帚木」 感想
「噂話」 「姉妹」 「しのび込み」へと進みました。
源氏が紀伊の守に放った次の言葉が印象的でした。
・「とばり帳もいかにぞは。さるかたの心もなくては、まざましき饗ならむ。」
・「似げなき親をも、まうけたりけるかな。」 「世こそ定めなきものなれ。」
・「さりとも、まうとたちのつきづきしく今めきたらむに、おろしたてむやは。かの介は、いとよしありてけしきばめるをや」
全く新しい源氏の姿に接しました。実に生々しい思いです。
今回寄せられた会員の感想は、以下の通りです。 (文責 高松)
〇女君(空蝉)の芯の強さ、気位の高さ、なかなか源氏のくどきにも落ちない次の場面が待たれる、興味あるプロローグでした。
〇いつの世も噂話は女につきものでしょうか? 週刊誌のタネはつきませんね。
源氏の性格がいろいろわかってきて、興味津々です。
〇女性の運命 父親の死によって入内の話がなくなり、弟の面倒を見るためか、身分の低い高齢の伊予の守の妻となる。
この運命が、源氏の同情もあったのか? 魅力的に見えたのか? 心(気持ち)が高ぶり近づいて行くが、どうなりますか。
私としてはつっぱねてほしいですが・・・・・
〇平安貴族の生活は想像できないのであるが、階級によって部屋、寝所が違うのは面白かった。
また、医学が発達していなかったので短命だった。母との死別も多かったであろう。源氏のようなマセた子がでてくるわけである。
源氏のこれからの出来事がどうなることか。
〇「思ひあがれるむすめ」に興味を抱く源氏。
自分の噂話に夢中になっている女房たちを仕切り越しに観察する源氏。
伊予の介の後妻や連れ子になった「姉弟」への源氏の思い。
帚木もいよいよ佳境に入ったようである。
〇回数を追う毎に、源氏の君の鋭利な感性に不思議な驚きを覚えています。
〇その時々の社会の状況によって、人の年齢とその成熟の度合いは一定しないことは自明の事です。例えば、明治維新前後に活躍した人々の年齢を、現代のそれと比較すれば驚くばかりですから。
ここでの源氏が17歳前後としても、今の同じ年と比ぶべくもない事です。しかし、それにしても源氏は人の世のことに深く思いをいたしている事がよく分かります。
式部は、源氏を中心とする当時の社会に生きる人たちの群像をとおして、人間社会の様相を深く広く私たちに伝えてくれています。そこに、この物語の汲み尽くせない魅力があると私は感じております。
2009年年10月8日 [帚木」感想
長い長い「雨夜の品定め」から、物語は「源氏と女房たち」「方違へ」「中の品の家」へと進みました。私達はこれからまた新しい源氏像に接していくわけです。
源氏と「大殿」「北の方」「紀伊の守」とのかかわりを、「女房たち」や「中の品の家」を背景に、物語は重層的且つ多面的に描いていきます。これからの展開に、私達一同身を乗り出す思いをしております。
今回寄せられた会員の感想は、以下の通りです。 (文責 高松)
〇厳しい階級社会で、未知の社会を見る目が夫々の立場によって違った目線である事がわかり、興味深いものがありました。
〇女性論で夜を明かし、梅雨の間の晴れ間が切っ掛けで、いつも頭のすみにある左大臣への気持がよみがえり、気がすすまない家に帰る所から2冊目がスタートする。
これからが楽しみです。
〇源氏は紀伊の守の屋敷に案内され、女房供と会うのを楽しみにしているなど、興味を女性にもつところが面白い。
それを秋の風情を背景にして描写しているところが、紫式部の文学的に優れているところなのだろう。
〇源氏と妻の行き違いが気になる。人ごとではないようで。
とり込み中の「紀伊の守」の慌てた有様、その気持ちがよく分かる。急に人が訪れて来る時、大忙しで部屋を片付ける自分のように。
〇①今日の学習「源氏と女房たち」から「方違へ」へ移る前に、先生の解説部分(テキストP9~11)を読む時間があると、もっと理解し易いと思います。
予習をしてこないのがいけないのですが、解説を読む時間が欲しいです。
②「はづかしげ」、「さうざうし」、「なやまし」等、1000年の間に意味が違ってきている言葉は、いつ頃から変化してきたのだろうか。
〇父君の左大臣様は几帳隔ててごあいさつ。紀伊の守様は酒のさかな求めて、こゆるぎ 急ぎ歩く。今日の源氏はちょっと楽しいかな。
上の品と中の品の違いがよく描かれていると思います。
〇深夜に近く、飲み会の挙句の果て、上司が「家庭訪問」と称して、お供を引き連れ我が家を襲ってきたときの様子が目に浮かびます。そういえば家内の機嫌がそのあと1週間ぐらい悪かった。すまじきものは宮仕えですね。全く。
2009年9月10日「帚木(雨夜の品定め最終回) 感想
「帚木」に進んで9ヶ月、「蒜食いの女」を最後にようやく「雨夜の品定め」を読み了えました。
最後に源氏は「人ひとりの御ありさまを、心のうちに思ひつづけたまふ。これに、足らずまたさし過ぎたることなくものしたまひけるかなと、ありがたきにも、いとど胸ふたがる。」様子であったとあります。
次回からは「イメージで読む源氏物語Ⅱ」へと進みます。振り返ってみると、08年5月にスタートしてから「遥けくも来つるものかな」との思い一入ですが、物語はまだまだこれからです。物語の新しい展開への期待に、メンバー一同胸を膨らませています。
今回寄せられた会員の感想は、以下の通りです。(文責 高松)
〇雨夜の品定めもいよいよクライマックス。
当時の公達がたの教養の深さが垣間みられて 面白く感じました。
手紙の返事はすべからく早く、一日延ばしにすると とめどなくなりますので、あまり こらないでと思います。
〇この時代ににんにくを食べていたとは驚きました。(それも女性が)
逃げようとする藤式部丞の「逃げ目をつかひて」の表現が確かに面白いです。
それでも女性は追いかけたいと思う気持ちで、「この香失せなむ時に立ち寄りたまへ」と。
逃がさないと言う必死さが伝わってきます。
逃げるなと言いたい。
〇にんにくを喰べたために、男に去られて、歌を相聞する。優雅なひとこまである。
紫式部は、これらの男女についても詳細に叙述している。
驚きである。
〇女はこうあるべきと決められていた時代の女性にも、「蒜食いの女」のような女性がいたことがおもしろい。
現代のトップレディ――雅子様、鳩山夫人――を見たら、どう思うかしら。
〇高熱に苦しむこの才女の元へ、もし若くて美しいエクセントリックな文章の生から、蒜の花を添えた漢詞の恋文が届いたら、どう反応するか想像して楽しくなってしまいました。
しかし、古の雅の世ではありえないことですよね。
この才女、好きな学問をさらに深め、父上を超えた陰の博士になってほしいです。
〇冷厳な階級社会の様相を垣間見た思いがしました。ここまで、あまり描かれることがなかった下級貴族の姿を見ることができたのです。
「蒜食いの女」は登場した女性の中では異色で、むしろ現代では他の女性よりも高く評価されるのではないでしょうか。勿論過ぎたるは及ばざるが如し、ですが。
2009年8月13日 「帚木」 感想
「常夏の女」の講義を受けました。常夏の女は、中将の理解の枠を超えた存在で、ここでもまた男と女のすれ違いの物語が語られています。
常夏の女は次のように描かれています。
中将が「いと忍びて見そめた」人で、「さても見つべかりしけはひ」で「ながらふべきものと」は思わなかったが、「馴れゆくままに、あはれとおぼえ」た。中将は「たえだえ忘れぬものに思」っていたところ、「さばかりなれば、うち頼めるけしきも見えき。頼むにつけては、うらめしと思ふこともあらむと、心ながらおぼゆるをりをりも」あったが、女は「見知らぬやうにて、久しきとだえをも、かうたまさかなる人とも思ひたらず、ただ朝夕にもてつけたらむありさまに見えて」、中将は「心苦しかりしかば、頼めわたることなども」あった。女は「親もなく、いと心細げにて、さらばこの人こそはと、ことにふれ思へるさまもらうたげなりき。」
女が「かうのどけきにおだしくて」中将が「久しくまからざりしころ」、中将の北の方より女に「情けなくうたてあることをなむ、さるたよりありて、かすめ言はせたりける」。このことは後に中将が聞いたことで、女に「さる憂きことやあらむとも知らず、消息などもせで久しく」たった頃、女は「むげに思ひしをれて、心細かりければ、をさなき者などもありしに、思ひわづらひて、撫子の花を折りておこせたりし。」
女の文には『山がつの 垣ほ荒るとも をりをりに あはれかけよ 撫子の露』とあった。
中将が「思ひいでしままにまかりたりしかば、例のうらもなきものから、いともの思ひ顔にて、荒れたる家の露しげきをながめて、虫の音にきほへるけしき、昔物語めきておぼえはべりし。」
中将が『咲きまじる 色は何れと わかねども なほ常夏に しくものぞなき』と詠みかけると
女は『うち払ふ 袖も露けき 常夏に あらし吹きそふ 秋も来にけり』と返した。
しかし女は「はかなげに言ひなして、まめまめしく恨みたるさまも見」せなかった。中将はそのさまを見て「涙をもらしおとしても、いとはづかしくつつましげにまぎらはし隠して、つらき思ひ」をしていると見られるのを、女が「わりなく苦しきものと思」っているのだろうと勝手に思い込み、「心やすくて、またとだえ置きはべりしほどに」、女は「あともなくこそかき消ちて失せにしか。」
こうした結果を招いた中将は、まだ失ったものの大きさに気づいていないし、まともな反省も出来ずにいます。その浅はかさについては、以下の感想文の中でメンバーから完膚なきまでに叩きのめされている次第です。また、皆さんの同情を一身に集めた「女」との再会が、この先あるとのことですので、私たちはその機会を楽しみにして更に読み進んで行くことといたします。
〇常夏の女が後の夕顔の事かと思うと、とても感慨深いものがあります。
頭中将の正妻にもきつい事を言われ、源氏とつき合うようになってからは、六条御息所にとりつかれて哀れな死に方をするにつけて、この方は印象深い存在です。
〇経済生活を、たよらなければならない女性の生き方として、何とあっぱれ。
そして自信過剰の男の・・というか男性一般の、女に求めるものの何と理想の高い事。
古しえでも今でも決して見つからないでしょうが、人間よくしたもので、人は好き好きだろうと思い楽しく読んでいます。
〇常夏の女(夕顔)が中将の所より姿を消して、その後どのようにして生活し、又どのような形で光源氏と知り合い寵愛を受けるようになるのか、そうなった時、中将の心情はどうだろうか?
楽しみです。
〇中将の女性観は、最後笑い話でまとめたが、常夏の女(撫子)の古歌を踏えて和歌で文を寄せる教養のある女性を、もっと大切にすればよかったと後の後悔先に立たず、当時の男性の浅はかさを知ることが出来た。
現代においても言えることである。
〇社会通念は変わっていても、男女の心の機微は本質的には変わらない。
これから源氏がかかわって行く女性の伏線も垣間見えて、ますます楽しみです。
〇この様にもの静かで賢くて、主人を立てる女は素晴らしい。
現在であれば妻の鏡であると信じます。
それに引き換へ石頭の中将は男ではないぞ。
少しは女の立場に立って考へよう。
〇①常夏の女は、どんな恐怖からのがれるために身をかくしたのだろうか。
当時のことを考えると直接殺されるとかではなく、呪いとか、もののけによるわざわい等のたぐいのことを、ほのめかされたのだろうか。
②常夏の女と中将は、どういうきっかけで知り合ったのだろうか。
〇教養の有る貴族の人達は和歌で会話ができるということですが、会話とはつくづく難しいと感じました。
場面は撫子と常夏の花をそえて美しいです。
この女性は、中将よりもっと人間が大きい男の人に巡り会えればいいと切に願います。
〇私なら、こんな人は絶対捨て置かないなぁ。中将は苦労知らずの「ボンボン」で、「猫に小判」「豚に真珠」と言ったところでしょう。
2009年7月9日 「帚木」 感想
「指喰いの女」から「木枯の女」へと進みました。
「指喰いの女」では男と女のすれ違いや行き違いが、そのまま交わることなく悲劇的な結末を迎えました。短い文章の中に、複雑な葛藤のさまが細やかに描きつくされていることに感銘を覚えます。
一方「木枯の女」では、全く対照的な女が描かれています。当時の貴族社会での男女の交情の様子が、臨場感をもって語られていて、興味が尽きないところです。
左馬頭の打ち明けた秘め事に、源氏は「すこしかた笑みて」「いづかたにつけても、人わろく、はしたなかりける身物語かな」と言い放ちます。
今回寄せられた会員の感想は、以下の通りです。(文責 高松)
〇指喰いの女も 木枯の女も 面白く拝見しました。
平安時代と思えない程 リアルで 奥深く 細やかで 筆者に敬服致しております。
〇一途に自分を愛してくれた指喰いの女と、一段上に思っていた木枯の女、どちらも思い通りに行かず、思わず天を仰ぐ左馬頭の姿が目に浮かぶ。
〇左馬頭の女性遍歴を聞いていて、作者式部の男性観がわかる。冷静に、つきはなして男性を見ていて、恐ろしいまでに的を射ている。
〇(今日のへぇ~) 木枯の女 こんなにドライな女は、現在は掃いて捨てる程いる。当時、話題になる位稀だったのですね。
とても雅やかな状況が現出してすばらしい。
〇姫は、左馬頭が自分の気持ちを分かろうとしないので、悲しすぎて、うつ病になって衰弱死してしまったのでしょう。
左馬頭の子供っぽい、そしてこっけいな、何か憎めない可愛いいところが、実はこの姫様好きだったのかもしれません。
かわいそうだったけど、確かに好きな人に愛された姫でした。
〇当時の貴族社会のさまざまな出来事を、式部はどのように取材したのでしょうか。その豊富で多彩な内容に何時も驚かされます。
またその時代の女官達の生活がどんなものであったのかも、興味を覚えます。
2009年6月11日 「帚木」 感想
「指喰いの女 其の一・二」を読みました。
左馬頭が「はやう、まだいと下臈」であった時「あはれと思ふ人」がいた。「容貌などいとまほにもはべざらしかば、若きほどのすき心には、この人をとまりにとも思ひとどめはべらず、よるべとは思ひながら、さうざうしくて、とかくまぎれ」ていた。「もの怨じいたくしはべりしかば、心づきなく、いとかからで、おいらかならましかばと思ひつつ、あまりいと許しなく疑ひはべりしもうるさくて、かく数ならぬ身を見も放たで、などかくしも思ふらむと、心苦しきをりをりもはべりて、自然に心をさめらるるやうに」なっていた。
その女は「思ひいたらざりけることにも、いかでこの人のためにはと、なき手をいだし、後れたる筋の心をも、なほくちをしくは見えじと思ひはげみ」、「ものまめやかに後見、つゆにても、心に違ふことはなくもがなと思」えるありようだった。そして「進めるかたと思ひしかど、とかくになびきて、なよびゆ」く。「みにくき容貌をも」、「見やうとまれむと、わりなく思ひつくろ」う。「うとき人に見えば、おもてぶせにや思はむと、憚り恥ぢ」る。「見馴るるままに、心もけしうは」ないのだが、左馬頭は「ただこの憎きかた一つなむ、心をさめ」できずにいた。
「かうあながちに従ひおぢたる人」だろうから、「いかで懲るばかりのわざして、おど」せば、「このかたもすこしよろしくもなり、さがなさもやめ」るだろうと思って、「まことに憂しなども思ひて絶えぬべきけしきならば、かばかり我に従ふ心ならば思ひ懲り」るだろうと「ことさらに情けなくつれなきさまを見せて、例の腹だち怨ずる」女に、左馬頭は言い放ちます。
「かくおぞましくは、いみじき契り深くとも、絶えてまた見じ。限りと思はば、かくわりなきもの疑ひはせよ。ゆくさき長く見えむと思はば、つらきことありとも、念じてなのめに思ひなりて、かかる心だに失せなば、いとあはれとなむ思ふべき。人なみなみにもなり、すこしおとなびむに添へて、またならぶ人なくあるべきやう」などと。
左馬頭は「かしこく教へたつるかなと思ふたまえて、われたけく言ひそしはべ」ったのです。
ところが意外にも女は「すこしうち笑ひて」左馬頭に返します。
「よろづにみだてなく、ものげなきほどを見過ぐして、人数なる世もやと待つかたは、いとのどかに思ひなされて、心やましくもあらず。つらき心を忍びて、思ひなほらむをりを見つけむと、年月を重ねむあいな頼みは、いと苦しくなむあるべければ、かたみにそむきぬべききざみになむある」と。
左馬頭は、女が「ねたげに言ふに、腹立たしくなりて、にくげなることどもを言ひはげましはべるに、
女もえをさめぬ筋にて、指ひとつを引き寄せてくひてはべり」
左馬頭は「おどろおどろしくかこちて」、こんな疵がついては宮仕えも出来ない、もう昇進もかなわ
ない、世を捨てる身になってしまった「など、言ひおどして『さらば今日こそは限りなめれ』と、この指
をかがめてまかでぬ。」
左馬頭の残したうた
「手を折りて あひ見しことを数ふれば これひとつやは君が憂きふし えうらみじ」に、
女は「さすがにうち泣きて」
「憂きふしを心ひとつに数へきて こや君が手をわかるべきをり」と返します。
ここへ来て、「帚木」がにわかに面白くなってきました。千年前の壮絶な「夫婦喧嘩」に引き込まれ
長々と原文を引用してしまいました。
ここでは、男(夫)、女(妻)の果てしなく続くすれ違いや行き違い、そして決して交わり溶け合うことのない葛藤が、実に生々しく描かれています。それは男の側からで、しかも筆者は女性なのです。この取り合わせは、絶妙というほかありません。
講義終了後、人形コレクターの会員宅、そして「おでんや ふみ」へのにわかツァーに出席者全
員が参加し、コレクションの素晴らしさや、「とまり」と「よるべ」などの話題で大いに盛り上がりました。
今回寄せられた会員の感想は以下の通りです。 (文責 高松)
〇雅びな時代なのに、指喰いの女とは驚きでした。喰いという言葉が強烈だったのですが、その時には噛むという言葉が無かったとの事。
愛情表現がとても興味深い事でした。
〇いつも男を待つだけの受身な女にも、意地があることを感じました。
「すこしうち笑ひて」は、自分へのなさけなさも含めた笑いのようにも思います。
現代でも「とまり」だけでなく「よるべ」も必要かもしれませんね。
〇女の嫉妬、男のうぬぼれ。いつの世でもが程々が・・・・
人間模様が楽しい!!
〇左馬頭の女性観が述べられているが、現代の男性と変わりなく、指をかじられるに到る話が面白かった。
このように奥行きのある文章は、漢文で書かれなくて、さすが「ひらがな」を使ってこそ書かれた。まさに、ひらがなの誕生なくして「源氏物語」はなかったであろう。
〇男と女の愚かな自尊心が生んでしまった悲しい話です。
この二人には、憎めない親しみを感じています。
古典落語の秀作が生まれそうです。
〇男の身勝手、浅はかさ、思いあがり、世間体のみを気遣う愚かさなど、哀れな男の姿が余すところなく描かれています。
一方、健気できめ細かい心遣いを決して忘れない、やさしい女の姿も見事に描かれています。
でも、自らの矮小ともいえる感情をうまくコントロールできない、「業」とも言える女の姿も的確に描いています。(この点については、ご婦人方の多くのご批判があろうかと思います。それは甘んじてお受けいたします。)
2009年5月14日 「帚木」 感想
「法の師左馬頭」を読みました。
左馬頭は「よろづのことによそへておぼせ」として切り出します。
【木の道の工】
「臨時のもてあそび物」は定まった形がないので、見た目がしゃれていて「時につけつつ、さまをかへて」今風の面白いものが出来る。しかし「大事として、まことにうるはしき」「調度の飾りとする」ような「さだまれるやうある物」は実用品の飾りだから、それ自体地味で目立たないけれど、それを「難なくしいづることなむ、なほまことのものの上手は、さまことに見えわかれはべる。」
【絵師】
「絵所に上手多かれど」「劣りまさるけぢめ」はすぐには「見えわかれず。」
唐絵の画材では「人の見及ばぬ蓬莱の山、荒海のいかれる魚のすがた、唐国のはげしきけだもののかたち、目に見えぬ鬼の顔などの、おどろおどろしく作りたるものは」「ひときは目おどろかして、実には似ざらめど、さてありぬべし。」
しかし大和絵の画材ように「世の常の山のたたずまひ、水の流れ、目に近き人の家居ありさま」は「げにと見え」る。「なつかしくやはらいだるかたなどを、静かにかきまぜて」遠景の「すくよかなる山のけしき、木深く、世離れてたたみなし」、近景の「け近き籬のうちをば、その心しらひおきてなどをなむ、上手はいといきほひことに、わろものは及ばぬ所多かめる。」
【書】
「深きことはなくて、ここかしこの、点長にはしり書き、そこはかとなくけしきばめるは、うち見るに、かどかどしくけしきだちたれど、なほまことの筋をこまやかに書き得たるは、うはべの筆消えて見ゆれど、今ひとたび取りならべて見れば、なほ実になむよりける。」
左馬頭は「はかなきことだにかくこそはべれ。まして人の心の、時にあたりてけしきば
めらむ、見る目の情けをば、え頼むまじく思うたまへ得てはべる。」と結びます。
〇今日の木の道の工も、絵の上手、手の道の処も現代に通じて、とても面白く思いました。殊に書
については身につまされて、読んでいて恥じ入るばかりでした。
〇絵所(絵を司る役所だというが、共同作業をしていたという)。このようなことがすべての分野で行われたとのこと。絵が残っていないのは残念。
〇暇つぶしとはいえ、何だか和やかで長閑な場面です。
得意気に講釈を並びたてる左馬頭、それを素直に一所懸命聴いている中将。
しどけなく狸寝入りをきめこんで、「下らんな」と思いつつも、けっこう会話を楽しんでいる源氏。
登場人物全ての人の良さ、育ちの良さが伺えます。
なるほど、とどのつまり良いものは良くて、誤魔化しは効かないですよね。
〇表面の美しさが大切なのではなく、ほんとのものを見抜かなければならない、それは妻選びでも同じだとのご託宣です。ありがたく承りましたが時既に遅しであります。夫と妻、男性女性を問わず、お互いに思うところは同じでありましょう。
「侘びさび」に通底する美意識が、当時既に日本人の中に形成されていたことも興味深いところでした。
2009年4月9日 「帚木」 感想
「甘えた妻」から「女の心変わり」まで進みました。
なおも左馬頭は夫婦(男女)の思い違い、すれ違い、行き違いについて語り続けます。そこで述べられていることは、現在の私たちのそれといかほどの違いがあるでしょうか。驚くばかりです。
面白いなぁと思ったところを幾つか拾ってみます。
「今はただ品にもよらじ、容貌をばさらにも言はじ」「ただひとへにものまめやかに、静かなる心のおもむきならむよるべをぞ、つひの頼み所には思ひおくべかりける。」
「心一つに思ひあまる時は、言はむかたなくすごき言の葉、あはれなる歌を詠みおき、しのばるべきかたみをとどめて、深き山里、世離れたる海づらなどにはひ隠れぬかし。」
「心ざし深からむ男をおきて、見る目の前につらきことありとも、人の心を見知らぬやうに、逃げ隠れて人をまどはし、心を見むとするほどに、長き世のもの思ひになる、いとあぢきなきことなり。」
「濁りにしめるほどよりも、なまうかびにては、かへりてあしき道にもただよひぬべくぞおぼゆる。」
「心はうつろふかたありとも、見そめし心ざしいとほしく思はば、さるかたのよすがに思ひてもありぬべきに、さやうならむたぢろきに、絶えぬべきわざなり。」
「すべてよろづのことなだらかに、怨ずべきことをば、見知れるさまにほのめかし、恨むべからむふしをも、にくからずかすめなさば、それにつけて、あはれもまさりぬべし。」
「あまりむげにうちゆるべ見放ちたるも、心やすくらうたきやうなれど、おのづから軽きかたにぞおぼえはべるかし。つながぬ舟の浮きたるためしも、げにあやなし。」
ここまで言われるとご婦人方からは「何事ぞ」との怨嗟の声が聞こえてきそうです。
今回で講義は12回を数えました。この間に新しいお仲間をお二人お迎えできたこともあり、久しぶりに全員で食事会を催し親交を深めました。
今回、会員から寄せられた感想は以下の通りです。(文責 高松)
〇思い立って尼になって了ったものゝ後にも引けず、こんどは後悔して思い悩む様子は興味深く、さぞかしと思います。現在でもよくある話だと思います。
〇古来より男が女に対するものは同じ。都合が良すぎる!!
〇左馬頭、中将、源氏、三人の男性の性格が浮き彫りされ、式部のするどい観察がつづく。
〇男心、女心は千年経ても変わってないものだと感心しました。
善い女と好きな女、妻にしたい女とは夫々違うんですね。やっぱり。
〇家出を敢行して、尼寺に行って、何だか分けがわからないまま尼さんになってしまって、べそをかいている妻は私の目にはとてもかわいく映ります。
さっさと迎えにいかない夫などいらないでしょう。
〇「言はむかたなくすごき言の葉」や「あはれなる歌を詠みお」かれることもなかった私は、かのひとは「あつれきに身も心も疲れ果て、やむにやまれぬ思い」であったのかなぁと、ぼんやり考え込んでいました。
2009年3月12日 「帚木」まとめと感想
「家の主」から「妻の条件」へと進みました。
左馬頭は続いて語ります。
「おほかたの世につけて見るにはとがなきも、わがものとうち頼むべきを選らむに、多かるなかにも、えなむ思ひ定むまじかりける。」
「狭き家のうちの主人とすべき人一人を思ひめぐらすに、足らはであしかるべき大事どもなむ、かたがた多かる。」
「とあればかかり、あふさきるさに」思い悩んでも、「なのめにさてもありぬべき」ほどの人でも少い。それなのに「ひとへに思ひ定むべきよるべとすばかりに、同じくは、わが力いりをし、なほしひきつくろふべき所なく、心にかなふやうにもやと」するから「選りそめつる人の、定まりがたきなるべし。」
しかし「かならずしもわが思ふにかなはねど、見そめつる契りばかりを捨てがたく思ひとまる人は、ものまめやかなりと見え、さてたもたるる女のためも、心にくくおしはからるるなり。」
美人で若く思わせぶりな振る舞いの女にやっと近づけても「なよびかに女しと見れば、あまり情けにひきこめられて、とりなせばあだめく。これをはじめの難とすべし」ということにもなる。
妻の役割に「なのめなるまじき、人の後見のかた」がある。それには「もののあはれ知り過ぐし、はかなきついでの情あり、をかしきに進めるかた」は「なくてもよかるべしと見え」るが、「まめまめしき筋を立てて、耳はさみがちに、びさうなき家刀自の、ひとへにうちとけたる後見ばかりをして」いるだけなのも困る。
夫は「公私の人のたたずまひ、よきあしきことの、目にも耳にもとまるありさまを、うとき人」には言えないので、「近くて見む人の、聞きわき思ひ知る」妻と「語りもあはせばやと」望み、「うちも笑まれ、涙もさしぐみ、もしは、あやなきおほやけ腹立たしく、心ひとつに思ひあまることなど多かるを、何にかは聞かせむと思」うから「人知れぬ思ひ出で笑ひもせられ、あはれともうちひとりごたるるに『何ごとぞ』など、あはつかにさし仰ぎゐたらむは、いかがはくちをしからぬ。」
「ただひたぶるに子めきて、やはらかならむ人」は「心もとなくとも、なほし所あるここちすべし。」しかし「をりふしにしいでむわざの、あだごとにも、まめごとにも、わが心と思ひ得ることなく、深きいたりなからむは、いとくちをしく、たのもしげな」い。「常はすこしそばそばしく、心づきなき人の、をりふしにつけいでばえするやうもありかし。」
ここまであからさまに、男の女性に対する見方や願望がこの物語に描かれているとは思ってもいませんでした。ことの善し悪しは別にして、また時代の違いを超えて、今もそれは殆ど変わっていないでしょう。そんなこともあって今回は長々と原文を引用してみました。
今回寄せられた会員の感想は以下の通りです。(文責 高松)
〇(今日のへぇ~!)昔の妻えらびは、男の人がいろんな条件をつけたのですね。
現代というより私の時代は親の決めたもので、後は二人の努力で、お互いに思いやりの気持ちで生活するよりなかったと思います。
〇(今日のへぇ~!)女にとって、結婚することが生きていく上での大へんなことであるという事が良く理解できましたし、大変な努力がいる事と、現代に生きれた事をよろこんだ事です。
〇(今日のへぇ~!)式部の時代の女性評は、なかなか微に入り細に入りで興味深い事ですが、現代にも通じていると思いました。
〇本居宣長は源氏物語の基調が「もののあはれ」、風流だといったという。
私は、今までの講義を聞いて、男女(人間)の真実に迫る小説ではないかと思う。一千年の歴史を超える文学である。
〇左馬頭という人は、女の人に「あなたって、良い人ね」と軽くあしらわれそうな人のように、私には感じられます。本当に善良な人ですよね。
私が男なら「耳はさみがちの、びさうなき家刀自」の奥さんをとても可愛いく想って、色々お手伝いしてあげて、用事が終わったら「ごくろうさんでした」とねぎらって、奥さんの為に用意した立派で美しい「くし」を、毎回さし出してあげることでしょう。
〇(今日のはてな?)妻訪い婚のこの時代に、家の中に入れる「つま」を誰がどのようにして選んだのだろうか。親にも勧められたのか。
(感想)理想の女性はこうあってほしいという男たちの雑談を、女性が書いているところが面白いです。
〇男女や夫婦のすれ違いはもう千年も前から始まっていて、未だに何も変わっていない。暗然たる思いです。
男性の女性観は「ないものねだり」で身勝手きわまると、きっと女性は思われていることでしょう。
でもご安心ください。残念なことに、女は男なしで生きていけますが、男は女なしでは生きていけないのです。
2009年2月12日 「帚木」 感想
物語は「三つの品」「今時の中の品」「葎の門」へと進みました。
そこでは、源氏、頭中将それに左馬頭・藤式部の丞も加え、彼らの女性観が続いて語られています。
それはそれとして、ここでは源氏はどのように描かれているか見てみましょう。
・頭中将が「『見劣りせぬやうはなくなむあるべき』とうめきたるけしきもはづかしげな」るさまに、源氏は「いとなべてはあらねど、我もおぼしあはすることやあらむ、うちほほゑみて、『そのかたかどもなき人はあらむや』とのたま」います。
・頭中将の「いとくまなげなるけしきなるもゆかしくて」、源氏は「『その品々やいかに。いづれを三つの品に置きてか分くべき。もとの品高く生まれながら、身は沈み、位みじかくて、人げなき、また直人の上達部などまでなりのぼり、我は顔にて家のうちを飾り、人に劣らじと思へる、そのけぢめをいかが分くべき』と問ひたま」います。
・「世のすきものにて、ものよく言ひ通れる」左馬頭の品定めの数々に、源氏は「『すべて、にぎははしきによるべきななり』とて、笑ひたま」います。
・語り手は、源氏を「いでや、上の品と思ふにだにかたげなる世を、と君はおぼすべし。白き御衣どものなよよかなるに、直衣ばかりを、しどけなく着なしたまひて、紐などもうち捨てて、添ひ臥したまへる御火影、いとめでたく、女にて見たてまつらまほし。この御ためには、上が上を選りいでても、なほ飽くまじく見えたまふ。」と述べます。
こうして私たちは、17歳に成長した源氏の人となりや佇まいを、更に深く知るところとなりました。
今回寄せられた会員の感想は以下の通りです。(文責 高松)
○この時代には、これ程 “かたかど” という事を重要に思っていると思っておりませんでしたので、その言葉の “かた.かど” に、とても面白く感じました。
○家柄というものは昔も今も同じで、成金の人はいかに贅沢にすべてをしても、品がともなはない。やはり気位は高くもつといいのかも? それも困りものかもしれません。
それ相応に勉強するのもいいかも。女の品定めも現在とかわらないかも・・
○進化していない人のこころ。 男性が寄れば話題に上る事々。 女も男も変らな-い!!
○源氏、左馬頭などの男性の女性論は、それぞれが率直な意見交換をしている。しかも身分差も意識しているのが面白い。
○男たちの話す「女の品定め」は、あまりにも具体的でかつ的確、しかも現代の私たちから見ても違和感が殆どありません。
そこで描かれている女性観は、①式部のものなのか ②特定の男性のものなのか ③式部が見聞きした複数の男性たちのものなのか ④あるいはこの「帚木」の著者は式部ではなく男性ではないのかなどなど、ある意味では荒唐無稽とも言える疑問が限りなく広がります。
それにしても源氏物語はほんとに面白いですね。また、式部の取材力にも驚かされます。
2009年1月8日 「帚木」 感想
物語は一変しました。源氏は既に17歳、近衛中将の地位にあります。
頭中将とは「夜昼、学問をも遊びをももろともにして」、「心のうちに思ふことも隠しあへずなむ、むつれ」あう仲です。
「つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵の雨に」、源氏の御厨子にある文どもを頭中将は「わりなくゆかしがり」ます。源氏は、「さりぬべき、すこしは見せむ、かたはなるべきもこそ」とかわしますが、頭中将は、「おのがじし、うらめしきおりおり、待ち顔ならむ夕暮れなどのこそ、見所はあらめ」と食い下がります。
こうしたやり取りの中にも源氏は、「言少なにて、とかくまぎらはしつつ、とり隠す」複雑な表情を見せます。
そして物語は、いわゆる「雨夜の品定め」につながっていきます。
「帚木の巻」はこうして始まりました。先生のお言葉によれば、読了には一年ぐらいかかるとのことです。「桐壺」とは全く違った物語のありように、メンバーは戸惑いつつ、今後の展開におのがじし胸をときめかせています。
今回寄せられた会員の感想は以下の通りです。(文責 高松)
〇いよいよ源氏も17歳となって、現実味をおびて、先々が楽しみになって参りました。
雨夜の品定めの前に、こんな事が書かれているのも知らず、さわりの処ばかり覚えていたと反省致します。
〇源氏の時代は通い婚という事もあって,男の人は割合に自由な生活をしていた様です。非常に真じめとあった様に見えても、仲良しの頭中将とのやり取りで、女の人にまめだったのでしょうね。
恋文が沢山あった様ですから、頭中将はそれを大変うらやましく思っている様子も見えます。でも大した人は見えなかった様にも見えますが・・・。
〇帚木の巻
絵物語を読んでいる様だった前巻から一気に現実に引き戻された。
婿を大事にする親心、女性の人をみる眼力の鋭さにおどろきます。
〇恋文は男から先に出すということは、光源氏が先に手渡しているのであろうから、相手の手紙を識りたいと思う中将の心は、源氏の心を識りたかったのだと思う。
〇次回本論に入る男性の恋愛論、きっと現代に通じるものと思い、楽しみ。
〇源氏が急に身近かな人になってきました。
我が日々の反省もかね、今年は性格改造致しましょうか?
〇雨の日のつれづれに、若者二人が若者らしい会話をしているのが、何かほほえましいです。
こんな折に、多感なお姫様達は女房と何を語り合っているのでしょうか。
〇がらっと変わった物語のトーンに驚きました。でも源氏と頭中将の語り合いに、現在の私たちとどれほどの違いがあるでしょうか。自らはすきがましきあだ人のくせに、女の、これはしもと難つくまじきはかたくもあるかなと言い放つのには笑ってしまいました。
一気にリアリズムの世界に引き込まれましたが、これから先にロマンもあると先生がおっしゃっていますので、それを楽しみに読み進んでいきたいと思っております。
2008年12月11日 「桐壺」(最終回)感想
きよら会での読書会が始まって8ヶ月、長大な物語の序曲に当たる「桐壺」をようやく読み終えることができました。
「帝と更衣の愛」「若宮の誕生」「更衣の死」「藤壺との恋」「元服」「結婚」そして「さまよう魂」へと、物語は光源氏の成長に合わせて、重厚な展開を示していきます。
この日は参加者一同で「望」年会を催し、あらためて、「命ある限り」源氏の世界を読み続けていこうとの思いを確かめあった次第です。
新しい年から始まる「帚木」に胸膨らむ思いです。
今回寄せられた会員の感想は以下のとおりです。(文責高松)
〇源氏物語を原文で読む、8回を終了し桐壺1帖を読み終わったところで物語の面白さが深まる一方で、これからが益々楽しみになります。
禁断の恋の行方はいかに?
〇源氏は元服式を終えた後、直ちに有無をいわさず(一昔前の日本もそうであった様ですが)意志に反して四才年上の気位の高い姫君を妻に迎えざるをえない不幸があった。
その故から母似の、帝の后藤壺の面影が忘れられず、もんもんとした気持ちで過ごす。
これからどう展開するか、気にかかる事です。
〇いよいよ桐壺の巻も終わり、始めから読んでみて(いつも途中からでしたので)、後の展開の理解のためにも非常に大事な事がよく分かりました。
うい冠りの式の有様など、読んでいるうちに眼の前に浮かぶようで優雅な気持ちにひたる事が出来ました。
〇五月から始まった源氏物語の原文による勉強、今日で桐壺が終わった。
一千年前に書かれた日本語のもつ素晴らしさ、難しさを楽しんだり悩んだり、これからか帚木以後五十三帖どこまで行き着けるか・・・。やはり楽しみでしょう。
〇絵巻物のように華やかで豊かな元服式の様子が目に浮かびます。
子供の世界から追放された源氏の切れ長の美しい瞳が、悲しく凛と輝きました。
〇桐壺も読み終わって、いよいよミステリー小説が始まった。
本居宣長は「もののあはれ」が基調となっているとするが、私は恋愛小説として読んでゆきたい。
〇本日はとても面白かったです。
毎回のことですが「おぼしいたつく」など、今まで聞いたこともない言葉が次々に出て来て、いつも新鮮な気持ちにさせられ、勉強した気持ちになります。
帚木が楽しみです。
〇桐壺の帖を読み終えて
華やかな宮中の出来事にはじまったが、人と人(男と女)とが織りなす心の綾と言うか、葛藤とかが次第次第に複雑になり、深くなり、読み手の心を引きつけてしまう。
この帖の終わりになって、複雑に絡まり合った心の糸が、上手くほどけるのだろうかと気が気ではない。
〇これからの物語を暗示する桐壺の終わり。 古文のおくゆきの深さに今更ながら感服します。 何時の世でも変わらぬ父の心情(帝でも)が読み取れました。
〇一千年の時空を超えて、「人間の物語」が私たちの今の心を捉えます。一月に一回、それはこの物語の世界に浸りきる至福のひと時です。私だけではなく、読んでいく中で絵巻物を観るように、またアリアを聴くように、視覚と聴覚も同時に刺激を受けるのはなぜでしょうか。不思議なことです。
2008年11月13日 「桐壺」感想
物語は「藤壺入内」から「少年源氏の恋」、そして「后と御子」・「元服式」へと進んでいきます。
四の宮の母后も「あな恐ろしや」と「おぼしつつみて、すがすがしうもおぼし立たざりけるほど」でしたが、帝の「ただわが女御子たちの同じ列に思ひきこえむと、いとねむごろに聞こえさせたま」いて姫君の入内が実現します。
帝は更衣を「おぼしまぎるとはなけれど、おのづから御心うつろひて、こよなうおぼし慰むやうなる」様子です。
源氏は藤壺のもとへ「常に参らまほしく、なづさひ見たてまつらばや」と思います。
帝は藤壺に源氏を「な疎みたまひそ」「なめしとおぼさで、らうたくしたまへ。つらつき、まみなどは、いとよう似たりしゆゑ、かよひて見えたまふも、似げなからずなむ」と頼みます。
源氏は藤壺に「をさなごこちにも、はかなき花紅葉につけても心ざしを見」せています。弘徽殿は「こよなう心寄せきこえたまへれば」「またこの宮とも御仲そばそばしきゆゑ、
うちそへて、もとよりの憎さも立ちいでて、ものしとおぼし」ています。
一方「世にたぐひなしと見たてまつりたまひ、名高うおはする宮の御容貌にも、なほにほはしさはたとへむかたなく、うつくしげなるを、世の人光君と」「藤壺ならびたまひて、御おぼえもとりどりなれば、かかやく日の宮と」たたえます。 (以下次回)
今回寄せられた会員の感想は以下のとおりです。(文責 高松)
〇日本語=古語の奥深さと趣き深さが何とも心地良く思います。
〇いよいよ物語の始まり。
源氏の君として登場。恋心芽生へる。
〇少年の恋心、今も同じですね。
一千年の 令(とし)を感じさせない 花もみじ
〇(今日のへぇー!) 12歳の少年、源氏が、16歳の、父帝の妃に恋心を抱く。どうしても理解できないが、当時の年代は別として、父は判らないで終わる程、空気を読めない(KY)人間であったか。
〇昔の宮中の生活様式がよく分かり興味深い。ここで源氏が少年となって現われ、母似の人にほのぼのとした気持ちを抱くたぐいまれなる美しい少年であった事でしょう。
これから二人の間に出来る事を、ワクワクした思いで待って居ります。とても楽しい一時でした。
〇「かかやく日の宮」とはにごりが無いだけですが、何とも「かがやく」とは別のひびきがあって、優雅さがただよってきました。光君と日の宮が、可愛らしくしのばれます。
〇帝は、桐壺とは無明の恋に沈んだけれど、「日の宮」に対してはそこまでの愛は読み取れないので、私としては嬉しいです。
光源氏も藤壺も、本当の若く清らかな初恋ができて良かったと思います。
(今日のはてな?) 帝の血液型はO型?
2008年10月9日 「桐壺」感想
回を重ねて、物語は「若宮の微笑」から「藤壺入裏」に差し掛かってきました。
7歳になった若宮は「いみじき武士、仇敵なりとも、見てはうち笑まれぬべきさま」で
「今よりなまめかしうはづかしげにおはす」様子です。また「わざとの御学問はさるものにて、琴笛の音にも雲居を響か」す天賦の才能を示します。
高麗人の相人は「帝王の上なき位にのぼるべき相おはします人の、そなたにて見れば、乱れ憂ふることやあらむ。おほやけのかためとなりて、天下を輔くるかたにて見れば、またその相違ふべし」と見立てます。
帝は「無品の親王の外威の寄せなきにてはただよはさじ、わが御世いと定めなきを、ただ人にて朝廷の御後見をするなむ」「きはことにかしこくて、ただ人にはいとあたらしけれど」「源氏になしてたてまつるべくおぼしおき」と決断します。
さて、物語はここで急転、先代の四ノ宮が登場し、新たな展開が始まります。(以下次回)
このような物語の展開に、会員一同「源氏の世界」に引き込まれ、毎回深い感動を覚えています。以下会員から寄せられた感想です。(文責 高松)
○今更ながら、式部の物語の構成の巧みさに感心します。短い言葉に秘められた奥深さに、ますます楽しくなってきました。
○光源氏の誕生!!で、心がワクワクです。次回の読書会が楽しみです。
(今日のはてな?)藤壺はじゃー兄妹ではないのか?臣下の姓は全部源氏?調べてみたいです。
○先生が読んで下さると、自分もすらすらと読んでいる気分になります。説明も分かりやすく、知りえた気分になります。少しずつ勉強です。
○「相人おどろきて、あまたたび傾きあやしぶ」のところで、ふとThe BeatlesのNowhere Manの歌を思い出してしまいました。
♪He’s a real nowhere-man? Sitting in his nowhere-land? Making all his nowhere plan for nobody♪
光源氏はまさにどこにも属さず、どこにもいない。しかし、チャーミング(魅力と魔力)。そして高貴
なダイヤモンドみたいな人。でも、ダイヤモンドがあっても幸せ(とは限らないし)、孤独からのがれ
る方法はありませんね。
○帝が高麗相人に考えを聞くなど、また倭相・宿曜などに見させて自分の考えを決めるなど、当世風で面白いと思いました。
○昔から占いにたよる事が多かったという事がよく分かり、又源氏のいわれがはっきりして、とても面白かったです。
○源氏の姓を賜い、ただの人になったことは、はたして適格な判断であったのかどうか。
(今日のへぇー!)①更衣なきあと、藤壺の登場と、人変わりしてきた帝の心境。 ②高麗人が宮中を出入りしていたこと。
○(今日のはてな?)帝が外国(高麗人)の言葉を少しぐらい話せたのかな?
○6回を重ねて、すでに物語の興味深さにどんどん引き込まれています。
(今日のへぇー!)親が子を思う心、男が女を思う心、いつの世も変わりがないと思いますが、現代は少し変わってきているのでしょうか。驚く様な事件に心が痛みます。
○段々馴れるのでしょうが、主語→語り手を探すのに苦労しています。
○(今日のへぇー!)若きスーパーチャイルドついに現わる。上流階級の人は、当時の国際語である中国語で高麗人の相人と文(ふみ)など作りかわす程になっていた。
○主人公の人となりが、多角的・多面的に描きあげられ、特に先回の終わり「今は内裏にのみさぶらひたまふ」から、更に深くそれを知ることができました。主人公を中心とするこの物語が、今後どういう展開をとげていくか興味津々です。
2008年6月12日 「桐壺」感想
すべての生活が身分階級できまっていて命を保つことへもつながっているというのが大変な社会だと思いました。そしてそのためにもなのでしょうか、いじめもすごい!!人の心というのは平安時代から同じで変わっていないというのもすごいと感じ入っています。日本語の奥深さ趣深さがすばらしいです。
わたしが参加したのは単に員数合わせみたいなつもりでしたが、興味が出てきましてこれからが楽しみになりました
西川祥子
帝も普通の人だったのですね。子を失った母のなげきがひしひしと伝わってきました。時代が変わっても同じです
小山美智子
今までは帝が一方的に桐壺更衣を愛してやまず、そのしつっこさにかのじょはさぞありがた迷惑をしていたと思ってました。
しかし今回の読書会で彼女の帝に対する甘美な敬愛の情に気づきました。私が描いていたあの有名な渡り廊下の光景もすっかりかわりました。彼女は誇らしく立派に花道を勤め上げたのです。帝に告げ口をして何らかの報復もできたはずなのに、女徳をふりまいてそのような帝を困らせる事はしなかった。彼女は高潔な人だと思います。周囲から追い込まれ痛めつけられるほど、帝の腕の中に愛と安らぎを求めたのだと思います
愛が彼女に死をもたらしてしまったことはとてもかわいそうですが、人の心は変わるもの、帝の桐壺更衣に対する愛も、桐壺更衣の帝に対する愛もいつか必ず色あせていきます。彼女はこの上ない麗しい花を咲かせ枯れる前に美しいままで散っていったのです。
天はごく希にこの地上に信じられないほど美しい、だからこそはかない魂をパラパラとばらまくのかしらとふと感じました。
光源氏が美しいのは桐壺更衣だけが美しかったのではなく帝も美しかったのでしょう、絵になりますね
平井明子