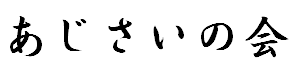
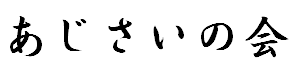

10年前カルチャースクールの「源氏物語」クラスで出会った、現在5名のグループです。
もっと深く源氏物語を味わいたいと思い、現代女性文化研究所で田中先生をご紹介いただきました。
2008年6月 研究所のあじさいが美しく咲いていた日に、この会がスタートしました。
講師の源氏への情熱、そして一つ一つの言葉「古語」を大切にする解釈、美しい表現に酔いしれる毎回の講座です。
この会が長く続きますよう願っております。
あじさいだより
2020年2月12日 「賢木」その13
①藤壺への想いに、雲林寺のお経60巻読みたまふ源氏、が、朝顔への気持ちもあり”吹き交う風も近きほどにて”のしゃれた言い回しでお手紙。
愛すべき源氏です。
②朝顔という名前の由来が「朝の顔」(化粧をしていない顔)であると初めて知った。
その朝顔の君のイメージが大きく変化した今日の学習でした。
③今日一番の気に入った言葉
吹き交ふ風も近きほどにて・・・という言い回し、こんな書き出して手紙を書いてみたい。
そのかみやいかがはありし木綿襷心にかけてしのぶらむゆえ
近き世に
朝顔のピシッとした返歌かっこいい!
④出家を考える源氏、しかしその一方で想いをはせるのは紫の上のみならず朝顔のこと。そして六条の御息所、当然藤壺と想いは続く。
今まで見えなかった朝顔の乙女心が見え興味深かった。
⑤雲林院で行い修している源氏の心の動きと斎院の若い娘の心の動きがわかった。
良し悪しのラチ外のものだと思った。
2020年1月8日 「賢木」その12
①雨林院の法師たちの清らかな日常を目のあたりにして、うらやましがる源氏である一方、なほ、憂き人しもぞと俗世を離れられない源氏。若き貴公子の両面も味わい
ある物語です。
②たちがたい藤壺への想いを胸に雨林院にて論議せさせる源氏。紫の上とうたを交わしつつ成長を喜ぶ源氏。人間味あふれる源氏です。
③藤壺へのどうしようもない想いを持て余し雨林院へ、法師たちの読経や論議を聞き、出家を考える源氏。当時の仏教が現代のわれわれより身近なものであったこと
が感じられた。しかしそんな中でも、紫の上へのことが気にかかり、文を贈り続ける。そこには成長した紫の上が。源氏の方が幼く思えた。
④この時代の上っ方の宗教心に考えを及ぼす項。
紫の上の答歌をかい間みさせることで、自立する女性へ成長する伏線となっているのがわかる項。
新年のクラスにふさわしい宿題でありました。
⑤雨林院へ出かけた源氏が藤壺のことを忘れるために悩み、学習する。
そして出家という道を選ぶべきかどうか悩む。「出家」という行動が何を意味するのか、具体的にどういう生活になるのか少し理解し、源氏の悩みについて考えた。
2019年12月11日 「賢木」その11
①出家の決意をした藤壺が春宮に会いに。「かの御顔を脱ぎすべたまえり」ほどの春宮を玉のきずにお思いになり、不安にかられる藤壺です。
②出家を決意した藤壺が宮にそれを告げる状況を読んだ。まだ六歳の宮の可愛い様子と、母としての藤壺の心がしみじみと読みとれた充実した二時間でした。
③藤壺が春宮に別れをつげる場面。
子どもの面ざしの中に源氏の面かげそのものを見る恐怖心がコワイ話となって読者にせまってくる。
平穏が訪れることを祈りたい。
④藤壺が出家を決意し春宮のもとへ行く場面。母の出家に対する春宮の疑問があどけなく、可愛らしくそれは藤壺をいっそう苦しめ、読者にも悲しみが伝わってきた。
⑤令和 最後の源氏講義でしたが、藤壺の出家の決意を、幼い春宮に伝えるため御所を訪れる場面でした。母の意図が充分にくみ取れず、どことなくちぐはぐな会話の中にも、しみじみとした悲哀を感じ、家で夜、一人で予習中には思わず涙がこぼれてしまった。
2019年6月11日 「賢木」その6
①院崩御後の御所の暗く重苦しい雰囲気が、これから来る世を暗示させる今日の場面であった。今の梅雨空に似てる。
②弘徽殿の女御と藤壺の中宮、二人の后の心のうちが語られていた。弘徽殿の女御の院への切ない思いは 、以前読んだときには感じられず、今回先生のお話を伺ってはじめて知った気がした。
③院崩御の大后、中宮の内面に入った解説が場面の風景と合って、つら淋しい気持ちを誘われた。
④上皇死後のお屋敷の日毎の淋しさを、数十年前の主人のお葬式で感じた淋しさを、久しぶりに思い出した一時でした。
⑤桐壺院重篤の知らせに、弘徽殿女御すぐにもお見舞いに
心は院の元へはやるが、行動に移すとなると気持ちが鈍る
御子三人儲けた自負。なのに、中宮を側に置く院の気持ちにためらう女御を思います
2019年5月15日 「賢木」その5
①源氏の歌
ふりすてて今日は行くとも鈴鹿川八十瀬の波に袖はぬれじや
御息所の返歌
鈴鹿川八十瀬の波にぬれぬれず伊勢まで誰か思ひおこせむ
この二つの歌に、男女の差を強く感じた
②二条の院の前を通過した時、源氏が御息所への消せぬ思いを歌に託したのに対して、去り行く御息所がきっぱりと決別の意を示した歌をどう解釈するか。強がりだっ
たのか?
③院の病いあつくなった場面で親としての情が、源氏の御息所への未練場面をかげうすくした感じであった。
④桐壺院が病の中、春宮・源氏の将来に対する不安を語る場面が描かれていた。院の父としての愛情があらわれていた。帝はどのように受け止めたのだろうか。
⑤御なやみ重くおはします桐壺帝が春宮の心配、源氏の心配を朱雀帝にご遺言。これからの行く末が案じられます。
2019年4月10日 「賢木」その4
1,伊勢に旅立つ斎宮と御息所、別れの櫛をたてまつりたまふ帝や源氏の胸中はいかに。
あはれにしほたれ…涙にくれます。
2,いよいよ斎宮は群行して伊勢へ。当日の源氏の心の動きが、斎宮へ聞こえた歌と返りの歌に表れて、参加者、先生の説明で理解できたように思えたが…?御息所と帝の心はよく分かった。
3,源氏が斎宮に送った歌にたいして女別当が返歌した
国つ神そらにことわる仲ならばなほざりごとをまずやたださむ。
今日の講座ではもっともさわやかに心にしみました。
4,斎宮の伊勢への群行がいかに華やかなものであったか想像した。その斎宮に送った源氏からの和歌が、なかなか理解できなかったが、和歌で表現したひとつの世界であることがわかった。
2019年2月14日 「賢木」その2
1.さまざまな曲折を経て、野の宮で再会する今日の場面、先生の深い言葉に導かれて、これまで学んできたどの帖よりも感動を覚えました。改めて感謝します。ありがとつございましました。
2.「野の宮の別れ」
伊勢に出立する御息所とようやく心を通わせあえた源氏。素直に流れ出る涙。夕月夜の感激にせつなさがつのります。
3.伊勢へ旅立つ前の御息所を訪ねた源氏。御息所の素晴らしさを改めて感じ取った源氏の心が語られていた。伊勢行きを止める源氏の言葉を御息所はどんな思いで受け止めたのでしょうか。
4.野の宮のもつ独特の雰囲気を感じながらそこでの二人のやりとり
苦しんた女と、その女をかつては愛しながら長らく忘れていた
男がおりなす教養あふれたやりとり、全く圧倒されました。
5.榊、斎垣、神垣、長月七日の月、各々の意味を読み解いて、賢木の巻のこれからが楽しみになる。
源氏の涙に、怨みきこえたまふ様に、「純心」がうかがえた
2018年12月12日 「葵」その26
①子を早く失った親の苦しみと悲しみは千年の時を超えて、現代の私たちにも心に迫ってくるものがある。大宮の気持ちに添って、一人で読んでいたら涙が止まらなくなりました。
②車争いから始まった「葵」
六条の御息所の悲しみ、葵の上の心のあや、紫の上の結婚ととまどい、葵の上を失った大宮の深い心の沈み、いろんな人の移ろいにこれからの物語を感じます。
③新年を迎えて左大臣のもとへ向かう源氏、そこは悲しみにあふれていた。そんな中での大宮の源氏に対する心遣い、また源氏の大宮に対する気持ちが美しく描かれていた。
④多くの人物が登場した葵の巻ですが、今日はその中でも若紫との関係の変化「それををかしうもいとほしうもおぼされて・・・」という源氏の気持ちを思いやった二時間でした。
2018年10月10日 「葵」その24
1、 二人の結婚の章 女が受けたしょうげきを静かな言葉で表現されていました。そして女君へと
2、 源氏と紫の上が新枕を交わした後の紫の上の、現代訳では過剰ともいえる反応が、ういういしく新鮮で清々しい古文の美しさをさらに実感した。
3、 源氏と紫の上の結婚のシーン、純粋な紫の上が痛々しく感じられた。
一方、惟光の登場が場面をやわらげ、明るくしていた。
4、『男君はとく起きたまひて女君はさらに起きたまはぬ朝あり』紫式部のひそやかな表現に心ひかれます
5、「結婚」に男と女の性による行動差、女君の細やかな感受性と行動描写をじっくり味わう章でした。
2018年6月13日 「葵」その21
①源氏の”なき魂ぞいとど悲しき・・・・・”のうたが源氏と葵の上の本当の姿であった、との講義で目からうろこの想いであった。源氏の葵の上を失った時の悲しみが理解できた。
②葵が亡くなる前と後で、源氏の妻に対する感情や態度のギャップが大きくてなんとなく違和感を感じながら読んできた。源氏の和歌を解釈してもらった今日の場面でこれまでの違和感が埋められた。興味深かった。
③若君誕生の時ようやく一つになれた源氏と葵。葵の旅立ちによって多くの悲しみが…。源氏、左大臣、大宮、女房.”あくがれがたき心ならひ”の書がものがたります。
④源氏と葵の夫婦としての本当の姿を二つの歌からいろいろと推測し、話し合った楽しい時間でした。
以前からの思い込みが強いだけに、多少は納得できかねる点もありました。
⑤古語の意味深さを先生のお説と共に聞くと、深くうなづくが、今までに得たイメージとちょっと異なる感じがするのも現代人としてしかたがないか?
2018年3月14日 「葵」その19
①今日は歌のもつ力を教えていただいた。
現代人の言葉力の無さ,言魂への信仰を失った状態が、現今マスコミにあふれて、
切ない。いつから、なぜ・・・??考えないと。
②頭の中将が妹夫婦をどの様に見ていたのか、私が今まで思っていた通りの見方だっ
たので驚きました。しかしそれは当たり前の見方でもっと深く読み解く必要があった
のではと反省もしました。
③葵の上喪失感は大宮、頭の中将、源氏それぞれの心に、時雨となり、露となり、木
の葉よりけにもろき御涙となってきます。
④源氏の亡き妻葵の上への想いはつのり、そして葵の上の兄、母のそれぞれの悲しみ
苦しみが重くのしかかる。そんな中、朝顔の宮へ文を届け、また宮からの、洗練され
た文を手にすることで、源氏はつれづれなる日々に一筋の風を感じたのではないで
しょうか。
⑤源氏と朝顔の宮と歌を交換する場面。お互いの歌にはひと言の愛をささやくことば
もなく、ただこの季節の情景を素直に表しただけなのに、心にくい程の意志の疎通が
みられる。すばらしいと思いました。おしゃれです。
2017年11月15日 「葵」その15
①講座の中でも話題になったが、葵がなくなるまで何故夫婦で心を通わすことができ
なかったのだろうか。
なくなった今、どんなに後悔してもかひなし。
②葵の上を失った源氏の悲しみ、大宮の命が危ぶまれるくらいのしづみ入りたまう
姿。
「時しもあれ」声すぐれたる限りの念仏も忍びがたし。
③源氏、大宮、左大臣のそれぞれのなげきの様子が詳細に述べられ、源氏の内省する
心に、今までの源氏観が少し深くなった感じがする今日の個所でした。
④葵を失って初めて彼女の素晴らしさを実感する源氏、その悲しみは如何ばかりかと
思う。
なぜお互いに一歩が歩み寄れなかったのかと・・・
⑤葵を失った源氏の(私にとっては)思いもよらない姿を見た、という感じで読みま
した。
10年間の結婚生活を反省してもーかひなしですね。
2017年9月13日 「葵」その13
①死を目前にして、源氏と心を通わす葵。そして葵の急死。めまぐるしく変化する場面に、古典文学のスピード感を体感した。
②やっと心を通わせた源氏と葵の上、二人の心の中を垣間見た。それもつかの間、葵の上の死という最悪の事態となる。いっそう悲しみを感じた。
③葵の巻のクライマックスであった。夫婦の心の開いた瞬間、男共の心がはなれたすき間をつくものの怪、それに騒ぐ場面。
④初めての夫婦らしい一時が過ごせたことを思い出に、葵は旅だったのでしょうか。 その後の混乱ぶりが際立った章でした。
⑤せっかく源氏に心を開いた葵がまさか、除目の夜、人少なをねらったもののけにて絶命。なんとせつない・・・
2017年8月9日 「葵」その12
①今日は芥子の香という有名な(?)所を読みました。
御息所の源氏に対する深い思いが生霊という形で現れたのだと思いますが、本人に
とっては何ともつらいことだと感じました。
②芥子の香が実在したとの前提で予習していたが、先生の講義で、御息所の深層心理
にまで
粗末な自分の脳でとば口に入り、疲労感あり。
③葵の上の出産で、御息所、源氏の心の本質が表れ、芥子の香と共にそれぞれが苦し
む。
その姿に人の業を見ます。
④御息所が芥子の香に悩まされる場面。
深く考えずに読んでいたが、もう一人の自分との戦いであるとのことが理解でき、
物語の深さを感じとることができた。
2017年6月14日 「葵」その10
①葵がいよいよ出産を控えて、もののけにつかれくるしむ中、長く冷ややかな夫婦で
あった二人が、心を通わせ始める場面、読む私達も心和む。
②斎宮(神)への道すじにある宮の場面と、葵の上出産の場面が交互に出て印象深い
今日の購読であった。その中で女房の感想「さればよあるやうあらむ」はリアルティ
―を示す。
③出産が近づいた葵の上、もののけに取りつかれ苦しむ中、初めて見せた姿、表情が
愛らしく感激する源氏であった。
④源氏と葵が初めて心を通い合わせる場面でしたが、それも死に近づいている時。出
産間近のそうぜつな苦しみの時。さすが「源氏物語」と感じいりました。
⑤あやしくほけほけしう臥しなやみたまふ御息所の姿。出産を控え、源氏が初めて見
る葵の上の姿「これこそが望んでいた妻の姿」おふたりの情景が浮かびとても良い場
面に感激です。
2017年5月10日 「葵」その9
①御息所が夢の中で考えもつかない自分の姿を見て恐ろしくなるなど
自分ではどうにもならないその行動に驚くのを知った。
②魂が身体から抜け出してしまうほどの御息所の”源氏への想いと自己への畏れ”
お苦しみに胸が痛みます。
③御息所は源氏に対する深い愛のため自分が生霊になっているのではないか?と疑
う、
夢の中でその姿を見た時、彼女の心中はいかばかりであったかと思う。
④読み進んでいくたびに、これまで御息所に抱いていたイメージよりも
教養も深く愛らしい姿が浮かび上がってきた。
⑤生霊は?を具体的に記述されていて、式部の分析力と表現力を再認識させられまし
た。
2017年4月12日 「葵」その8
①御息所が前坊姫としての矜持を持って生きてきたという自覚と源氏に対する女とし
ての想いが、二人の間で行違う様子を先生の説明を聞きながら深く考えた二時間でし
た。
②御息所の知性の豊かさと、心の奥深さがひときわ輝く場面であった。これまで、こ
のような読み方をしてこなかったので、大変新鮮であり感銘をうけた。
③前坊の奥方だった御息所、プライドをおもちになりながらも源氏に〝想い”する真
の女性の姿に涙いたしました。
④御息所の源氏への深い愛、情念が描かれていた。一方源氏はあわれと思いつつ、受
け入れきれない。双方の苦しみがそこにあった。
2017年2月8日 「葵」その6
1、賀茂の祭りの日、紫の上の「髪削ぎ」をする源氏。「裳着」を意識し、「新枕」
に向けての準備。
紫の上の成長、利発さをおおいに感じ入ったことでした。
2、今日は典侍登場。当時を想像すると典侍の人物像は目をそば立てる者あり、式部
の作者魂に感服する。
3、久しぶりに登場した紫君の成長に驚きました。
源氏の歌に対して ・・・・のどけからぬに と皮肉をこめて返す姿に。
4、源氏が紫の上をいつくしむ姿が美しく描かれていた。一方で典侍に対する源氏の
ことばは辛いものであった。
5、源侍が久しぶりに登場した。
紫の姫君とのきよらな姿との対で、一層いやらしく描かれているが、私は典侍の努
力に拍手を送りたいと思った。
2016年9月14日 「葵」その2
①源氏の御息所への軽すぎる扱いに対して、父の桐壺院が細やかな諫めの言葉をかけ
るところ。
一方源氏が深く反省はするが、行動に表せない悩みなど深い心の奥が興味深かっ
た。
②六条の御息所の、世間の噂による恥ずかしさ、聞き及ぶ朝顔の姫君の想い、葵の上
の深く怨じきこえ給う御ここち、
それぞれの女君のお気持ちに心いたす回でした。
③六条御息所の置かれている現状・光源氏の気持など次の車争いへつながる前ぶれと
も感じられる箇所でした。
葵の新しい面も知らされました。
④天皇からの叱責~葵の懐妊~心細げな大殿の内面を新発見した源氏~御禊の日の神
事に心おどろす人々に作者の場面設定の妙を見た今日のクラ
スでした。
⑤葵の上の懐妊によるもの心細げな姿を見た源氏の、心の動きが見られ興味深い場面
だった。
そして、車争いへの序章が語られていた。
2016年8月10日 「花宴」終章
①藤壺への想いをたちきれない源氏。花の宴の後、おぼろ月夜の君と出会う。
これが後の逡巡の始まりと思うと、胸が痛みます。
②花の宴終盤。源氏の若さの終わりと、おぼろ月夜のはっきり挑発的な物言いを明ら
かにして
余韻豊かに閉じる。
③はなやかな花の宴が終わった夜、藤壺に会いたくて、朧月夜一人でさまよう源氏。
そこで会った女性とのかかわりが語られる。
その女性の正体、また会いたくて扇を手がかりに源氏の行動を楽しんだ。
④朧月夜との出会いから、またの逢瀬を望んでいた源氏。
酔ったふりをして彼女を探し求め、再会。
余韻を残した終り方が絶妙。
2016年6月8日 「花宴」その2
①藤壺中宮を慕い、意のままにならぬ思いをおさえかねて、夜の宮中をさまよい、朧
月夜に出会う。
扇を取り交わし忘れがたい思いになってる一方、若宮への思いや、一方北の方への心
遣いも怠らない
源氏とはどのような人なんだろう。
②源氏のきぬぎぬの別れ方その一を読んだ。
③朧月夜の先にやはり藤壺を見ている源氏。それでも有明の君に惹かれ、紫の君にも
おもいをはせる
光る君を思います。
④藤壺、おぼろ月夜、若君、葵の上など気に止めなければならない女性への配慮に驚
きながら読みました。
20才の青年なのですよね。
⑤藤壺はもとより葵の上、紫の上、その上朧月夜との新しい恋。
しかしその一人一人を大切に思う源氏の気持には恐れ入りました。
2016年5月「花宴」その1
① 朧月夜との出会いの場面は長い源氏物語の中でも特に華やかで雅びな情景が描
かれていて、
読者は憧れるのではないかと思う。私も好きな場面。
② 藤壺の君を慕う源氏、花の宴の後の「なほあらし」の心で、朧月夜と運命の出
会い。
また切ない恋の始まりです。
③ 源氏と朧月夜の偶然の出会いが、恋へと発展する興味深い場面だった。
出会った瞬間に恋に落ちるお互いの魅力が想像される。
④ 朧月夜の源氏を受け入れながらも、おぼれ流されない対等意識に感服。
源氏はこれからどうつきあってゆくか楽しみです。
⑤ 朧月夜という女性がもつ、今までにない魅力が感じられる導入部を読みまし
た。
これからが楽しみです。
2016年2月「紅葉賀」その12
① 源氏と頭の中将が源典侍をめぐってすまふ(相撲)。
作者はおもしろおかしく描き、こっけいさを浮き立たせている。
② 源典侍の困り果て、取り乱した姿に対し、源氏と頭の中将のふざけあう若者の
姿の対比が面白かった。
③ 源氏と頭の中将の戯れが今月の場面でも続いた。
平安時代の貴皇子たちの遊びはなんと優雅でこっけいなんだろう。
④ 中将、源氏の「恋のさわぎ」というより「ガキのいたずら」場面が楽しい。
内侍は2人が騒いでくれてふるうふるうしながら面白がっていたのではないかしら・
⑤ 源氏,頭の中将、内侍の三人がくり広げるどんちゃん騒ぎにも似た場面を楽し
みました。
でも内侍の教養ある一面も知りました。
2016年1月「紅葉賀」その11
① 若い二人の貴公子と年上の典侍との恋の物語・
古典の世界ならではの優雅さと、滑稽さがあわっさって、思わずひき込まれる。
② どんなに似つかわしくない女でも、相手に恥をかかせて平気でいるようなぶし
つけな振る舞いはしたくない源氏と
老女のしたたかさをもちあわせる源内侍のやりとりに、まいってしまう
③ 源氏と典侍のつやっぽい話の中に、二人の教養の深さを思い知る内容を学んだ
章でした。
④ 催馬楽が頭に浮かび、お互いにうたを贈りあえるという文化に驚かされる。
源内侍の、他に例を見ない女性の登場が興味深い。
⑤初購読にふさわしく琵琶の音から当時の宮中人の教養と当意即妙の話術にしびれる時
間でした。
2015年12月「紅葉賀」その10
①内侍登上の時間第一回目。
これから典侍の像がわっかってくるのが楽しみです。
②内侍の登場で自分の年令も意識しながら,珍しい女性の行動を楽しみました。
姫君ばかりではなく,毛色の変わった女性でした。
③典侍の源氏への懸想、この物語の中でもこっけいな話題としての位置づけが強い。
が、少し違和感を持たざるを得ない。
④源氏とも,頭中将とも関係を持つ、典侍の人となりが興味深かった。
彼女の行動はその自信に基づくものなもだろうか
2015年11月「紅葉賀」その9
①暗くなると出かけて行く源氏をしたう姫君の心細くうつぶせる姿が目に浮かび、かわいいねと思ってしまう
②源氏のまめやかな女君への接し方、それについてくるうわさ話。
帝の父親としての言葉といった情けあふれる場面から、次はどんな転開がまっているのか、
面白い場面構成の時間であった。
③紫の上が源氏に甘えているのが可愛らしく,それに対する源氏の優しさを感じる場面であった。
④桐壺帝の父親としての気持がよく表現された所を読んだのですが,源氏の実生活を全く知らないというのが驚きでした。
⑤桐壺帝の源氏を思う気持ちに心うたれました。
子を思う父親は昔も今もかわらず。
2015年10月「紅葉賀」その8
①藤壺が源氏に返した歌・・・・・・なほ疎まれぬ・・・・・
に否定の意味があることを初めて知った。しかし,私は完了と思いましたが何故なのか。
②緊張と弛緩の場面が続き、眠気が逃げていった今日のクラスでした。
③「袖濡るる露のゆかりと思ふにもなほ疎まれぬやまとなでしこ」の”ぬ”を否定とも完了とも読めるということが大変興味深かった。
私は否定と取りたいが,藤壺のひととなりを考えることができました。
④桐壺帝を前に源氏と藤壺が対面する緊張の場面、思わずひきこまれてしまいました。
⑤いつのまにか紫の上が、とくもわたりたまはぬ源氏に「入りぬる磯の」と口ずさみて、口おほいしたまいける・・・
「女君」になられたとは・・・。
20156月「紅葉賀」その5
①葵の上のこれまで気が付かなかった心の中を知ることが出来ました。
本当は源氏を思っている,それをうまく出せない苦しみがわかりました。
②これから妻になっていく、とっかかりについた紫の上と
妻になってなお男君に添いたくても添いきれない葵の上との対比を
読み取らねばならぬ段ながら・・・・
③源氏の藤壺への想いや、紫の上への想い、葵の上の源氏への想いの
それぞれがせつなく感じられる「紅葉の賀」です。
④葵の上の人となりを初めて知りました。
冷たく美しい鎧を着たような女性と思っていましたが、
彼女の源氏に対する気持ち、心の葛藤がよくわかりました。
印象的な場面でした。
2015年3月「紅葉賀」その2
①青海波を舞う光源氏、藤壺の前の試楽も、朱雀院での舞も美しく、まわりが木のもと、岩がくれ,景色の一部になるほど。
脚光を浴びる源氏がまぶしいです。
②帝もゆゆしさを感じる程の源氏の美しさがあますところなく語られていました。
③今日は東日本大震災の4年目となる日である。
まだまだ辛い日々を送っている被災者が多数いる中。華やいだ源氏物語の場面に浸れる自分にちょっと自責の念を覚えながらも、すっかり楽しんでしまった。
④花の季節前に,紅葉の賀の季節感をしぼり出し,源氏の歌と藤壺の返歌を味わう。
2015年1月「末摘花」総集編
①巻きの最後「紅の花ぞあやなくうとまるる梅の立ち枝はなつかしけれど」と詠む。
源氏は時に煩わしい縁ともかんがえている末摘花との結婚であるが、このお姫さま、並はずれての不器量、無骨。
しかしそれ故あえて手厚くも、末永くも後身をしようと決意する。
末摘花の巻は若き源氏の君の奥深さを照らしだそうとした巻なのだろうか。
②故常陸の親王の御女末摘花、源氏には「赤鼻」や「無粋」を非難され、”見苦しのわざや”とまでいわれても・・・
やはり姫君の育ちのよさによる、おっとりした性格、とってもとっても愛おしく感じられます。
③末摘花を読んで印象に残るのは姫の周りの人々のディテールの数々である。寒さでよろめく老使用人、早々と引きこもって寝てしまう乳母
源氏の訪れに少しはしゃぐ下女達。源氏はその中で様々な心の動きを見せてくれて、物語の現実味を厚く感じさせてくれる。
④零落した高貴な女性の寒々とした生活ぶり、それに一喜一憂する源氏の様子など、大変面白い巻でした。
しかし、最後の章の源氏と若紫の様子はちょっとひどいなあと・・・・
⑤多大な期待を持って通った末摘花の邸、しかし厳しい現実に直面。それでも何時までも面倒を見ようと心に決める広い心には感心しました。
そして、すこし成長した姫君に喜ぶ,大人びた源氏ですが、二条の院で美しき紫の上とたわむれるすがたに、源氏の幼さを見ました。
2014年12月「末摘花」その12
①老女達の超保守ぶりをさらりと書き,年あらたまる時の源氏の期待感との対比に感嘆するのみ。
②源氏が通うことによって活気づいた常陸宮邸、末摘花に仕える女房たちの”うちそよめき”が聞こえるようです。
③どの巻でもそうであったが、末摘花もゆっくり時間をかけて読み込むと奥深さが見えてくる。
④ねび人たちの言葉で末摘花がどのように育ち,プライドをもった女性になったかがわかる場面でした。
その彼女が”少したをやかに”変わりつつあることが面白かったです。
⑤さすがの姫君も
すこしたをやぎたまへるけしきもてつけたまえり
みすを通して感じられる変化が実際はどうなのか、次回末摘花の最後に期待しています
2014年11月「末摘花」その11
末摘花が自分の判断をもって踏み出したことに拍手。そのことで源氏の困惑状態が面白く、作者の人間分析に感嘆する今日の段です。
>
>
> ②唐衣君が心のつらければ・・・・
> 訪ねて来てくれない源氏へのうらみごと。次第に女らしい気持ちが出てくる様子が、源氏と命婦のやりとりの中でなんだか切なく読みました。
>
>
> ③自分のすべき事に目覚めた末摘花。ますます末摘花に失望する源氏。それでも彼女への心遣いを忘れない源氏を見直しました。
>
>
> ④時代錯誤で周囲の空気にも決して迎合居ない末摘花の生き方には、魅了される。
>
>
> ⑤育ちの良さで、ゆるぎない末摘花、源氏にあれこれ言われようが、「あわれ」より「いとおしさ」を感じます。
--
2014年6月「末摘花」その8
2014年5月「末摘花」その7
①末摘花こそ夕顔のような女ではないかと期待をふくらませてしまった源氏
心ひかれるものが何ひとつなかったというのはお気の毒です。
②末摘花の巻がただ外見の悪い女性のおこ話と思っていたが、講義を伺いもっと深い彼女の人となりを感じました。
③回を重ねる毎に「末摘花」の面白さがわかってきました。
源氏との最初の夜の過ごした時の末摘花の気持ちをどうとらえるか話がはずみました。
④末摘花は時の流れに流されないブレ無い人です。
不思議な感覚を持った人です。ある意味魅力的ではあります。
⑤源氏の人間性があぶり出る段であった。でもわかりにくい世の中の話。
2014年3月「末摘花」その5
①今日初めて末摘花の肉声が出てきました。
命婦とのやりとり、父親を思い出し泣く場面など、源氏との関係で今後どう変わって行くのか・・・・。
②”かく世にめづらしき御けはいの漏りにほひくるをば”の一文が、源氏からの美しく、香り立つ便りが送られてくる様が書かれていると、わかり納得。
そのような雅な文をも拒否する姫とは・・・
③命婦の言動はすんなりと理解出来、同情同意するが、姫君のたたづまいは理解及ばず、宿題としたい。
④世間知らずのお姫さま、末摘花の扱いに心くばる命婦のやりとり、興味深いものがあります。
2014年2月「末摘花」その4
①源氏の姫君に対する妄想がいよいよ膨らみ、高まる期待が面白く描かれていました。
責められる命婦の心の中はいかなるものか?
②末摘花をめぐる源氏と中将のかけ引きの場面、中将の問いに対する源氏の返答「いさ、見むとしも思はねばにや、見るとしもなし」と中将を煙にまく部分が深いなあと印象に残りました。
③源氏と頭の中将のライバル意識が末摘花へと向かわせる。興味深深です。
④頭の中将と、また命婦と末摘花に関するやりとりを楽しめた二時間でした。
これからが楽しみだと言われる先生の言葉を信じて、これから楽しみ・・・・
⑤本日の段は主語と省略をみつけるのがむつかしかった。
男心(光源氏の)を想像して、現代人と比較すると「変わらないなあ~、同じだなあー」
2014年1月「末摘花」その3
①今日の段は登場人物多く、その関係が端的に表されていて面白く、作者への驚嘆一入である。
②末摘花に対する二人の男性の盛り上がり方が、可愛らしく思えるほど面白かったです。
また中務の君のエピソードが小さなドラマになっていて興味深いものでした。
③末摘花をめぐる源氏と頭の中将の競い合い。
お互いが妄想に妄想を重ね思いを深めていく様が読者を引きつける。
式部の筆力に改めて感服した。
④源氏と頭の中将ライバル心も加え、末摘花に恋心を抱き想像たくましくする姿、中務の君のエピソード
とても愉快で楽しませていただきました。
⑤「末摘花」の巻はこれまで末摘花の容貌の印象しか残っていなかったのですが、源氏と頭の中将との駆け引き、大きく広がる想像力など
こんなに面白い巻と、今日のところで初めて知りました。
2013年12月「末摘花」その2
1.源氏と乳母子である、色好める命婦との言い合いがとてもほほえましく思われました。
2.末摘花のことを命婦から聞き、思いを膨らませる源氏の様子がほほえましく思われました。
また、末摘花と命婦の性格が対照的に描かれていて面白かったです。
3.命婦の人物像が現代風で源氏物語の中のトピックと思う。
4.末摘花の動きのなさに感心すると同時にイライラしました。
育ちとはそういうものなのでしょう。
5.末摘花に源氏を手引きするかどある命婦が今日のテーマとなった。
利発な命婦が姫君の窮乏を救う。
2013年10月「若紫」その17
①若紫最期の場面、天真爛漫な少女との触れ合いに、心和まされる源氏の姿がくっきり目に浮かぶ。
②若紫読了。
末摘花に入り、夕顔の面影がベースになって源氏の行動がはじまる。楽しみにしたい。
③若紫はこの後の親・源氏を睦びまつはし、あはれに、うち語らひ、御懐に入りゐるし情景を想うとせつなくなります。
④若紫と源氏の睦ましい姿がほほえましく、また末摘花の巻に入り、今度は源氏の夕顔への深い想いが感じられました。
2013年9月「若紫」その16
①2ヶ月ぶりの講義出席
若紫のこの先の才能開花がしのばれてワクワクする場面。楽しい時間でした。
②長年「源氏物語」を読んで、全く意味がつかめない箇所とよくわかる箇所があります。今回はよくわかる所でした。
度々うつくしという言葉が表れるのが印象的でした。作者の「はかなしや」が理解できました。
③源氏の御殿に連れられた紫の君、はじめは泣いていたものの、屋敷の珍しい光景にとけこんでいく、
そんな紫君を書き手は「はかなしや」の表現、しみいります。
④二条の院に連れてこられた若紫の態度、状況が少納言との相対でよくわかる。
若紫の生い先は明るい。
⑤少納言の狼狽がよくあらわれてい、紫の上の聡明さが垣間見えておもしろかったです。
2013年8月「若紫」その15
①父宮に引き取られる前、紫の上を連れ出す源氏の行動力、姫君の運命が大きく変わりました。
②源氏の実行力、それに対する少納言の対応の面白さを実感しました。
③猛暑中のところ、先生の迫力に及ばず、当方の脳ミソ活性化せず。申し訳なし
④若紫が父宮のところに移ると聞いた源氏の決断力、実行力に感心しました。
2013年6月「若紫」その13
①古語と現代語の同じ言葉であっても、微妙な意味合いに違いがあることが興味深かった。
なつかしき、うしろめたき
②今日も古語のもつ意味深さを味わいました。
なつかし・・・・心がしたいよって行く。
寝も入らず
夜中眼が覚めたとき思い出したいものです。
③嵐の中での若紫との一夜の場面、あどけない若紫が言葉を発することなく心細くいる様子が印象的でした。
帰り道で他の女性との歌の交換もまた面白い場面でした。
④若紫のところから帰る道すがらの源氏の気持ちに、はじめて登場する女性の仕打ちの齟齬が大変面白かった。
新しい場面が次々に出て興味尽きず。
⑤あられが降り、荒れてすごい夜、御帳のうちにあらわれた源氏、心細さがありながらも大して怖がりもせず
それでも眠れないでいる若君のお心を深く思います。
2013年5月「若紫」その12
①若紫を守る少納言の返歌を読んだ源氏が彼女に好感を覚え”すこし罪ゆるされ”素敵だなあ
②源氏と紫の上が初めて間近で出会う場面、源氏の必死の思いが行動に表れる。
紫の上の幼さが際立って描かれていた。
③1,源氏と少納言との会話から身分制度上のひびき
2,姫君の登場の仕方の表す若紫の人間像
等を再確認した章でした
④尼君を慕って泣き伏す紫の上に少納言の力強い味方
源氏のうたに対する返歌に感動です
2013年4月「若紫」その11
① 尼君、死の場面で
尼君が代わって少納言が源氏にしたためた「お見舞い下さったお礼は、この現世でなく申し上げましょう」という返事と
僧都が「先月20日過ぎに命が果てるのを見届けました。人の世の道理ではあるが悲しい」という簡素な手紙がすばらしかった。
② 「深読み」は各人心の中で深化させるか、共通項として皆で明らかにすべきか、今日は先生の発問に対してクラスの意見が聞けました。
③ 尼君の死に、源氏自身の母との別れをかすかに思い出し、紫の上の悲しみを想う。
④ 今日も古文の言葉の美しさに酔った2時間でした。
立ちぬる月の二十日のほどになむ・・・・
手に摘みていつしかも見む紫の根にかよいける野辺の若草
⑤ 尼君の死の場面で自分の死に対しても考える時間でした。
2013年3月「若紫」その10
尼君の臨終に間に合った源氏の言葉が生育歴をうかがわせそれをわからせる作者の文章力に、いつもながら感服する。
②源氏の藤壺を思う心の深さがよく表れている場面でした。
また管弦のあそびの際の源氏を、御簾の中から見つめる藤壺の気持ちが切なく伝わってきました。
③源氏がおどろおどろしいさま異なる夢をごらんになり・・・・・藤壺の宮に想いをはせ また宮もそんな源氏の苦しむ様を想い・・・・・せつなさを感じます。
④藤壺と源氏のドキドキするような密会場面。先週は、さぞ盛り上がっただろうな。
欠席で参加できなくて残念!
⑤尼上の「限りのさまになりはべりて・・・・・」
自分の命の限界を意識しながら人生の最期を迎えられるのだと改めて考えました。
2013年1月「若紫」その9
①おもかげは身をも離れず山桜 心の限りとめて来しかど・・・
この歌をさだすぎたる尼君たちが 目もあやに好ましゅう見た という場面 歌も良く 場面が目に浮かんできました。
②源氏の「いかでかと」の心が深い章であり、結び文がイメージでき 一つ知識がふえました。
③源氏の紫の上への必死のアプローチが感じられる場面でした。文では果たせない思いを ついに惟光をつかわし・・・
惟光のいつもの奮闘ぶりが面白かったです。
④今日は大野晋さんの古典基礎語辞典が話題となり
「なぐさむ」・・・・・なぐ
「ほほえむ」・・・・えむ
などの言葉が持つ意味の流れが詳しく説明されているとのこと
一度ゆっくり見てみたいと思いましたが、何時の日になるでしょうか。
⑤幼い若紫をめぐりどうしてもそばにおきたいと願う源氏と、守る尼君のやりとり
双方の思いが伝わり 不安が募りました。
2012年12月「若紫」その8
①源氏と葵の上との関係について つっこんだ会話ができた。
これまで抱いていた葵の上はもっと野心家で源氏との結婚に不満を持っているという認識が変わった。
葵の上はやはり高貴で気高い聡明な女性であったのかしら。
②若紫が源氏に対して「素敵な人!」という思いを抱いていたということを初めて知った。
葵の上の育ち 源氏に対する思いも 初めて知るなど 初めて理解することが多かった。
③本日の章
若紫の幼いながらの源氏へのあこがれは次の伏線であり 葵上の源氏への態度がドラマチックに盛り上がる。
④源氏に対する紫の上の淡い思慕 葵の上の冷たい言葉
この描かれ方の対比に 感心させられます。
⑤「問わぬはつらきものにやあらむ」の葵の上の言葉が 「あなたが私を問わぬはつらきものにやあらむ」と言っているとは
全く思っていなかったので、目からうろこでした。葵の上の人間像を全く違ってみていました。
2012年11月「若紫」その7
①聖と源氏、僧都と源氏とのやりとりを面白く読みました。
また 暁の山あいを目に浮かべて 源氏物語を楽しむことが出来ました。
②都に帰る源氏のもとに集った 聖、僧都の人となりまで見え 大変面白かった。
特に僧都の行動に 笑いを誘われました。
③別れの宴の場面 聖 僧都 尼君達の姿、心性まで読み取る指導あり 楽しかった。
④聖、僧都の人物像 源氏の戸惑い 尼君の困惑など とても楽しめました。
2012年10月「若紫」その6
1,源氏の心中を 尼君にせつせつと訴える今日の場面、原文も 難解であったが
解釈をしていただいた後でも、理解できない部分が多く、今日はとても疲れました。
2,難解な文章で意味がつかめませんでしたが、先生のお話を伺って、少しずつもつれた糸がほどけてゆく感じがしました。
源氏の若紫への一途な想いが、なかなか通じないもどかしさが伝わってきました。
3,光の君の、紫の君への想いがあふれる品の良いお言葉。
迎える尼君の毅然たるものごしが 守られる方に頼もしく安心を感じます。
4,暗闇の中で 音のみで想像する世界を楽しんだ後は 大変難しく、理解するのが大変でした。
源氏物語の世界に親しんで何年になるのかと 思わず考えてしまう二時間でした。
5,場面通り、自分の想像も暗闇の中で 像を結ばず、難解であった。
要再読(自分の宿題)
2012年9月「若紫」その5
1 源氏がが思いのままに語る場面は ずいぶん現代的で、驚いた。
2 今日の授業では 僧都の話し振り、態度などが印象に残りました。
18才の源氏の発言に堂々と反論する僧都が魅力的でした。
3 若き日の源氏のほとばしる情熱が吹き出して、常識の壁に付きあたる場面。
そして思わず恥ずかしくなる源氏 生々しく伝わってきます。
4 かいま見た若紫を運命の人と感じ 僧都に突然、御後身の件を切り出す源氏
決意を感じます。
5 源氏の紫の上への強い想いが伝わってくる場面でした。
そして僧都への必死の訴え、反対に僧都の冷たい反応が対照的でした。
2012年8月「若紫」その4
①猛暑続きと、ドロドロの政争が気分を滅入らされる今日 優雅に源氏物語を読むことができ
つかの間清涼感をあじわえます。先生暑い中ありがとうございます。
②かいまみでオーラあふれる紫の君に出会えた源氏 行く末を暗示させます。
③尼君の紫の上の先行きへの不安が印象的でした。反対に源氏の紫の上への興味が面白く感じられました。
④源氏物語の中の「少女」を味わう。山中別邸の風情もこの暑い時期、涼味で有意義であった。
⑤10才の女の子を見た源氏の心の重さと、僧都に対する源氏の行動の対比を楽しみました。
2012年7月「若紫」その3
①紫の上(10歳)と明石の君(9歳)の二人が登場し、 その育ちの違いが これからの生き方に 大きな差が出てくることを知った授業でした。
②光の君の運命の御方紫の上との出会いと 明石の上との間接的な出会い まさしく印象的なくだりです。
③明石の上の育った環境を読んでみて 今まで明石の上の人となりを全く感じていなかったことに気付きました。
どんな人に描かれているのかがとても楽しみです。
④のちに登場してくる明石の上と若紫の対比 今日の講座ではじめて気づきました。
⑤明石の上と若紫が一場に現れ これからの進行がまたれます。
2012年6月「若紫」その2
①今日は 源氏の居る場のちがいと 周りの人との交流方法が 新場面で印象深かった。
②明石の入道の人となりが ここで明白に語られていることをしりました。
明石の君の布石がここにあったのですね。
③明石入道について 全く別の見方が出来た時間でした。
これからの授業が楽しみになりました。
④若紫の前半の部分で唐突のように明石入道が登場する。
今後の転回が楽しみ。
⑤明石の入道の心高さには恐れ入ります。
後に続く話につながる重要な巻に胸が高鳴りました。
2012年4月「夕顔」を読む その15(最終章)
① 夕顔と空蝉との ”二道の別れ” を経験した源氏。空蝉の激しい思いにとまどいながらも
語りての ”くだくだしきこと…”の結びに 静かにこの段の終わりを迎えました。
② こうちぎを受け取った時の空蝉の心のせつなさを知りました。
今まではなんと通り一遍に読んでいたことか・・・
③ 最後の作者のつぶやきで 空蝉、夕顔の章が物語の中で示す位置がわかったように思えた。
2012年3月「夕顔」を読む その14
①今日の場面は 一途に慕う夕顔の49日にも満たない日に、軒端の荻に恋文を送るという
若き源氏の軽率な一面が描かれていておもしろかった。
②源氏の単純でない男性性を描いた作者に感嘆!!
③「軒端の荻」の荻の写真を始めて見て 長年の誤解が解けました。
可哀想な源氏物語では影の薄い女性を今日は知りつつ学びました。
④夕顔の四十九日の法要を「二なうしけり」源氏,想う心はいかばかり
⑤源氏の夕顔に対する深い愛を感じる四十九日の法要の場面でした。
それに相対して軒端の荻への“ちょっかい”がコミカルでした。
2012年2月夕顔」を読む その13
①夕顔の“やはらか”さにすっかり魅入られた源氏に 空蝉の”こころみに”届けられたうた
女心の”あや”がおもしろい
②問わぬをも|などかと問はで|ほどふるに|いかばかりかは|思ひ乱るる
この空蝉の歌をゆっくり学びました。
主語が誰なのか間違わない様に
③作者の意図が先生の教示によって解明、目からうろこの感激を味わいました。
夕顔のなかの空蝉の段
④ここでの空蝉の登場を何気なく読んでいたが こんなにも深い空蝉の心の動きが書かれていたとは・・・
⑤読みの速度が、あまりにもゆっくりなので 時々先を急ぎたいと思うことがある。
しかし 先生の詳しい解説を聞くことで いままで気づかなかった源氏の奥深い読み方が出来るようになった。
2012年1月「夕顔」を読む その12
新年初の授業は、最近上映された映画「源氏物語」の悪口から
始まった。商業主義が産んだくだらなさに非難が集中した。
今日もまた夕顔の奥ゆかしくも頼もしい人柄に魅せられた。
・ 源氏と右近のしみじみとした語りが、秋の夕暮れの中に浮かび
あがる場面です。
・ ”世の人に似ず”ものづつみしたもう、”世の人に似ず”あえかに
見えたまいし、夕顔について源氏と右近が語り合う場面、二条の
邸の風情をあわせて心に染み入りました。
・ 夕顔の姿が、読み進むうちにどんどん明らかになっていく面白さを
味わっています。
2011年11月「夕顔」を読む その10
① 「もてなし助けつつさぶらはす」 惟光の働き 心づかいはまさに臨床心理士。
物語の近代性 普遍性を感じました。
② 今回は
「御祈り、かたがたに隙なくののしる。祭、祓、修法など、言ひ尽くすべくもあらず。」
「内裏より、御使、雨の脚よりもげにしげし。」
など源氏人気のすさまじさを感じたことでした。
③ またしても 惟光の働きの大きさに感激いました。
また大殿の動きもちょっとユーモラスでおもしろく思えました。
2011年10月「夕顔」を読む その9
1.源氏と惟光、夕顔と右近の濃密な主従関係に 心打たれました。
2,深夜の板屋での源氏、右近、大徳の様子、暗さが一層引き立ち、声も惜しまずの泣き声など・・・・
3,暗闇の中に紅の御衣のあでやかさが印象深く 一層源氏の嘆きがきわ立って 読む者の気持ちに迫ってきました。
4,心ならずも夕顔との別れをせねばならない源氏の深い悲しみは落馬し”はふれ”るほど。
惟光の力で何とか二条の院にたどりつき安堵です。
5,全力で源氏を支えようとする惟光の尽力はすばらしいと思えました。
源氏が弱気になったときの 惟光の狼狽ぶりも、またいとおしいものがありました。
2011年9月「夕顔」を読む その8
①源氏の嘆きと現実を意識する交互の文と惟光の保護者的言辞のかけあいの若々しさを満喫しました。
②夕顔の屍骸に今一度会いたくて 深夜の道を鳥辺野へ向かう源氏の一途さに また魅かれました。
③惟光の有能さにただただ感心です。
夕顔を失った源氏よき友,臣を持って良かった・・・ そんな想いも浮かばない程の喪失の悲しみいかばかりか。
④源氏の夕顔に対する純粋な愛情がひしひしと伝わってくる場面でした。
また 源氏と惟光の信頼関係が素晴らしいと思いました。
2011年8月「夕顔」を読む その7
①夕顔の死がいよいよ現実となって行く課程での 源氏の心の動きを学んだ2時間でした。
19才の源氏の大切な経験だったのでしょう。
②「死のけがれ」の感覚を読みとるむつかしさ、平安は遠い。
③夕顔が死んだ場面
いとささやかにてうとましげもなくらうたげなり 髪はこぼれ出でたるも・・・
こんなに死を美しく描けるなんて素敵です。
④源氏の夕顔を失った悲しみと けがれを帝に話さなければいけない戸惑いが伝わってくるようです。
⑤夕顔を失った源氏の悲しみが切なく伝わってきました。
また当時の”死”に対する考え方が興味深く 「立ちながら、こなたに入りたまへ」の表現が印象的でした。
2011年7月 「夕顔」を読む その6
①4カ月ぶりの源氏の会でした。
久しぶりで 原文を読むのさえ苦労しました。情けない!
暑い時ではあるけれど やはり優雅な気分にひたれてよかったです。
②「おほけなくあるまじき心の報い」に泣きたもう源氏
惟光を見て泣く右近にむねをうたれました。
③若きどちの有様と 事件の深刻さと そのギャップをうめる作業を強いられる段々でした。
④夕顔の急死、あわてる源氏、泣くばかりの右近、駆けつける惟光。
惟光の活躍が始まる前に3人で泣く場面が印象に残りました。
⑤やっと現れた惟光のテキパキとした指示が大変印象的でした。
2011年6月 「夕顔」を読む その5
①「はかなく消えいる」を生身の人間から 想像さえできない自分が イヤになるほどフテブテしい。
②真暗やみの中での話。ものに気取られることの事実が なかなか理解できない時を過ごしました。
③源氏の心の闇の葛藤を考えると 夕顔の命果てる場面がつらすぎます。
④夕顔の死がなかなか理解できない場面でした。しかし源氏の心の葛藤が見事に書かれていると感じました。
また 賢明に指図する姿 いじらしく思えました。
2011年5月 「夕顔」を読む その4
こんなに葉っぱがみずみずしいわれらのあじさいちゃん!

① ようやく心を通わせた源氏と夕顔 夕映えの中 見つめあったのもつかのま
物の怪にとりつかれて あわれ・・・
恐ろしい場面に心ふるえます
② 夕顔の死因について 六条の宮の生霊と思い込まされる物語の進み方だと短絡いていた。
先生の指摘で自分の思考経路を反省!!
③ 今までの雅の世界から一転して 夕顔の巻の恐ろしい表現に驚かされた。
また 夕顔の死は六条の御息所によるものと思い込んでいたのは まったく浅はかだった。
④ 「夕映え」を見かはして・・・・
その美しい情景を想像しながら思ったことは
西向きの部屋で夕映え(夕焼け)が美しい時はよくホコリが目に付くことです。
2011 年3月 「夕顔」を読む その3
現代女性文化研究所の前に芽吹くあじさい

① 今日の読みは、上質な映画を観ているよう。情景が浮かび、音楽が聞こえ、転調あり。
② ろうたげ、おいらか、ほそやかにたをたをとして・・・
夕顔の姿がだんだんはっきり見えてきました。
③ 昨夜の夜更かしが響いて、睡魔におそわれながらドラマチ
ックな夕顔の場面を読んだ。すごい不思議な雰囲気だった。
④ 以面前読んだ時にはみえなかった情景が浮かび上がり、「名場面」というくだりを楽しみました。
2011年2月 「夕顔」を読む その2
やはらかにおほどきた御方に しみいる源氏にせつなさを感じます
「やはらかに」 「おほどきて」 「なつかしげに」 とりわけ「人にしむ」という味わいのある言葉
古語の深さを実感しました
今日の場面では夕顔の “やはらかにおほどきて” という人柄に、
源氏が ”いとかく人にしむ” 心を持つところが印象にのこりました。
古語は深い。
「人に染む」という言葉と意味を70歳近くなって 初めて知りました。
長生きすることにも意味がありそうです。
忘れない様にします。
夕顔の巻 いよいよ確心にはいってきました
「人にしむ」に思いを深くしたいです
2011年1月 「夕顔」を読む その1
夕顔の巻の場面、源氏が六条の女君邸から、早朝退出するところで 中将の君が見送りに出て歌を交わす。
中将の君の賢明な態度が鮮明に心に残りました。
六条邸の賢い女房と夕顔の家の何かドタバタした女たちの対比を面白く読みました。
夕顔の隠れ家の雰囲気を表わす段で 面白く読めた。
「おほかたにうち見たてまつる人だに 心とめたてまつらぬはなし。・・・」
今更ながらそんな御方にお会いしたいものだと強く思いました。
時は秋、六条院の庭には朝顔が咲いていた。
今年初めてベランダで朝顔を育て、秋になって狂ったように花を咲かせた事実から 朝顔が夏の花ではないと知ったのです。
2010年12月 はじめての感想
「源氏物語」と光源氏への田中先生の熱情に圧倒されながら、毎回納得、発見、感嘆を
実感する楽しみに誘われて、巣鴨詣でをしています。
空蝉の屈折したやるせない心、それを忘れられない源氏の女を求め続ける行動を、
田中先生の美しい言葉で表現された本を中心に、素朴で素直な疑問を出しながら、楽しく学びました。
その雰囲気作りに大きな力を発揮しているのが、「現代女性研究所」の素敵なお部屋ですね。
ゆったりと落ち着く心地よい空間で、月一回開かれる田中順子先生の源氏物語。
読み進むにつれて先生の源氏へのあふれんばかりの心情が私たちにも直に伝わり、お話に思わず引き込まれてしまいます。
古語の持つ複雑で微妙な意味合いを丁寧に教えていただき、
登場人物の繊細な心の軌跡が蘇り、自分の中に豊かなイメージがふくらみます。
物語の奥深さ、時代を超えた人間模様の織りなす魅力が少し理解できるようになりました。
また、先生の爽やかな朗読も大好き。私たちの音読も少しは上達したかしら?
今は昔、平安の・雅な時代の・愛の「想い」に せつなさで夢中です。
源氏を読み始めて たくさんの登場人物にめぐり合いました。
愛しても愛しても報われず苦しむ人。愛したくても愛せない人。愛されていても拒絶する人。
そんな横顔を見てきたつもりで居ました。
しかし 田中先生のご講義を聴き始めてから 彼女たちの心の中をもう少し深く見ることが出来たような、
そして後ろ姿までが見えたような気がします。