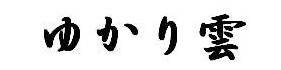
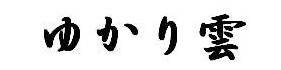
八雲オーケストラの仲間が中心になって作ったサークルです。
講師の田中順子先生は八雲オケのビオラ弾きで、お料理がお上手。
おいしい手料理で私たちを時々もてなしてくださいます。身も心も満ち足りた
そんな食事会の折に、八雲オケでも源氏の会をつくろうという話が持tち上がり、
2011年4月に【ゆかり雲】を立ち上げました。
古語を一つ一つ吟味しながら登場人物の心や暮らしに思いを馳せる
ことばの響きや調子を味わう、そして仲間と素直に感
想を言い合う、
そういうことを一緒にやっていきたいなと思っています
第89回ゆかり雲瞬間感想(2025.7.5)
『院崩後(P60)』から『代わり目(P76)』までを読みました。
・桐壺院が亡くなると こんなにも世の中が変わってしまうのだなあと思い知らされた。
今まで我慢してきた大后(弘徽殿の女御)は朱雀帝の母として源氏や左大臣家に対して手きびしい態度に出ている。源氏はそれでも大后の妹である尚待の君(朧月夜)とこっそりつきあっている。
左大臣家で育ててもらっている息子に会いに行ったり、正妻となった紫の上とも仲良く暮らしているのだから かえって落ち着いた生活のようである。これからどうなるのか?(YOKO)
・院崩後、中宮は院の御所を後にして里に帰る事になるが、実家の三条の宮邸が今はかえって他人の家の
ように感じてしまう。
長い間、里下がりする事も忘れていたことに気づき、院と過ごしたすばらしい、充実した日々が
思い出されて、深い悲しみにくれる。
源氏は十四才となった姫君と結婚を果たした後 世の中の人々の間で喜ばしい事と、大いにわかせたが
継母の北の方は 姫君に対し憎悪が渦巻いている、と語り手は言っている。(SUZU)
・桐壺院の崩御のあと、人々は集まって49日の間 哀しんだあとは、それぞれ実家などに戻っていった。
中宮も万感の思いをいだきながら里に帰った。
物語はかつて源氏と一夜を共にした朧月夜の君や若紫を引き取るはずだった兵部卿の北の方が登場し、
また宮中のまつりごとにおける両大臣の勢力交代も起こり、物語は複雑になっていく。
若紫は源氏によって強引に引き取られなければ、継子としてみじめな生涯を送ることになっていたのだろうか。紫式部のストーリーテイラーとしての才能に驚くばかりである。(まり)
・源氏、他の所にかようのがつまらなくなったようだが、行ってもたいていの女の人は
よそよそしくなったのだと思う
供の人は夜に休めるようになって良かったのではないだろうか。(W)
・桐壺院亡き後に源氏は藤壺の里に行き兵部卿、王命婦らと古き御物語を交わし歌を詠むが
皆、出来が良くない。悲しみが深いと言葉を飾ることも困難になるのか?
御代が替わり状況の変化の描写に源氏物語冒頭を思わせるような「すぐれて時めきたもう」とあるのが
興味深い。右大臣の時代になり源氏に向かい風が吹いてきている。(take)
・桐壺院の崩御後、権勢が右大臣家へ移っていく様子はとてもリアル。人間て、いつの世も自分本位。
斜陽の源氏と左大臣家の静かさは割と好き。
御世代わりで朧月夜の尚待の君が弘徽殿を居室とするようになって女房が多く集まってくる、というのも
ひとってステータスを求めるものよね、と妙に納得。
納得と言えば「例の御癖」で読者を納得させてしまう紫式部の腕。
「例の御癖」が物語のかなり部分をうごかしているのだけれど、西の対の姫君は 例の御癖の
ねじ曲がったところにいるみたい。
第88回ゆかり雲瞬間感想文(2025.5.10)
別れの櫛から院崩後の途中まで読みました。
・源氏にとっては六条の御息所との別れが辛く未練がましい歌を送るが、御息所にとっては煩わしいだけの様でそっけない歌が返ってくる。心中複雑だと思うが前に進もうとする御息所とセンチメンタルな源氏の対比がおもしろい。院も崩御し、これから源氏の周りの環境が一気に変わっていく予感。(Take)
・御息所は伊勢に行く事で自分の気持ちを切り替え、源氏の事で迷っていた時から以前の凛とした本来の彼女に戻れてよかった。(SUZU)
・御息所がついに去って放心状態の源氏。正妻の葵の上に続いて、さらに父の院が急逝してしまった。源氏を取り巻く人々がいなくなっていって、より責任ある立場になっていく。物語はこれからどんな展開をしていくのだろう。(まり)
・伊勢に向かう途中の御息所に未練がましく文を送る源氏。それに対して、もう源氏には全く未練がないように返答する御息所。両者が対照的に描かれていた。伊勢での御息所の生活は寂しいものになるかもしれないが、源氏とのことに踏ん切りをつけた御息所は凛々しかった。(七変化)
・秒で終わった帝の恋があわれ。
「女のまねぶべきこと」にすぐつづいて政事的な背景が見え隠れしているところがおもしろい。当時これを読んで苦い顔をした男性は多かったのではないか。(W)
・斎宮と共に六条御息所が伊勢に去っていった後すぐ桐壺院が亡くなられた。直前、朱雀帝に春宮や源氏の事をよろしくたのむと何度も言われて、翌日春宮や源氏がお見舞いに行くと、源氏に春宮の後見をしっかりやるように言い遺した。大后が中宮に遠慮しているうち、院は亡くなってしまった。中宮は泣いているばかりだっただろう。院をめぐる人間関係は亡くなるまで複雑だった(YOKO)
・「まして旅の空はいかに御心尽くしなること多かりけむ」六条御息所という人物に寄り添う作者の視線が優しくて、わたしの心を打つ。さまざまな思いを断って伊勢へ向かう御息所の苦悩とそれを乗りこえようとする姿にわたしはエールを送りたい。一方の「かわいそうなボクちゃん」との対比が見事でした。(ぴ)
。
第87回ゆかり雲瞬間感想文(2025.3.1)
榊のしるしの途中から伊勢出立までを読みました。
・源氏はなぜこんなギリギリになって御息所に会いに行ったのだろうか?今さら泣いてみても、彼女は決心を変えることなく、伊勢へ斎宮となった娘と向かっていった。源氏はお伴の人たちの装束や調度品を送ったりしたが御息所からはなんとも思われなかった。出立の日になぜか斎宮におかしな手紙を送ったが、女別当に代筆させた返事には痛烈な一言が…。それにニヤリとしていつかあってみたいなあと思っている源氏は転んでもただでは起きない男だなあと思いました。(YOKO)
・源氏と御息所の最後の別れのシーンでは双方の名残惜しい気持ちが吐露されている。源氏はあきらめきれないが、御息所の決意は翻らない。彼女は伊勢に行かないで,京に残る方がむしろみじめな思いを抱き続けることになるのがわかっていたのだろう。娘の斎宮の振る舞いや思いが最後に描かれていたのにはちょっと驚きだった。(まり)
・野々宮でのお互い心がかよった瞬間もあった美しい別れのシーンの後、伊勢下向 までの御息所の気持ちがとても苦しい。最先端のサロンを主宰し才色兼備の御息所が,源氏との関係で生霊にまでなってしまった自分を何度も反芻している感じが伝わってくる。伊勢でおだやかな時を過ごせるといいのだが。(YaugYaug)
・伊勢行きを決めた御息所を野々宮に訪ねた源氏。二人は親密な最後の時を過ごしたようだ。源氏は御息所をずっと疎んじていたのに彼女が自分のもとを去っていくとなると、未練がましく愛を伝える。が、さんざん苦しんできた御息所は「今さら何を…。」である。有名な別れのシーンらしいが、わたしには源氏が演出した「美しい別れ」のように思えてならなかった。(雪割草)
・野々宮での御息所と源氏の最後の逢瀬は九月の月夜で、二人の気持ちが高まり、ビジュアル的に想像できる感じで、情景が目に浮かびます。でもその後源氏は斎宮からの手紙(代筆)で、14歳という年の割には面白いところのある人だと心ひかれ、初めて恋の対象として斎宮を思い浮かべたりもして、彼のいつもの癖があり、どんな展開になるのかしら…。(SUZU)
・いよいよ御息所と別れると思うと別れ難い源氏。そんな様子を見て心が動く御息所だが新しい生き方を選んだ様だ。源氏の心遣いにも「何ともおぼされず」未練はない様子。最後に斎宮にも興味が移るところが源氏らしい。(Take)
・源氏からの餞別の品々を贈られての「何ともおぼされず」
源氏との出会いから、(描かれていない)愛に満ちた日々、夜離れの日々、所争の屈辱や髪に染み付いた護摩の匂い、そして野々宮の甘くかなしい別れ。さまざまの思いの果てに、これを限りとして伊勢に向かう御息所の揺るがない決意を感じた。原文の御息所が大好きです。それにしても賢木の文章の美しいことったら!(ぴ)
第86回ゆかり雲瞬間感想文(2024.11.9)
野々宮へから榊のしるしの途中までを読みました。
・できればこの部分を読んでから野々宮へ行きたかった。かりそめの住まいのわりには、北の対があるのはさすが。(W)
・ついに野々宮にやってきた源氏だった。野々宮の描写が荒涼として寂しく、こんなところで御息所はどんな思いで過ごしているのだろうと考えさせられた。黒木の鳥居とか、もう一度、野々宮神社に行ってみて見たいものだ。榊の枝を切って訪れた源氏はなかなかやるなと思った。(YOKO)
・源氏は御息所に会うため野々宮に向かう。斎宮が滞在する場所は神々しくしんみりとした様子。御息所は源氏に直接会う気配はなく、それを心憂しと思う源氏。御息所は会いたい気持ちに迷いがある様子。榊を渡すシーンでも素直に喜びを表せない御息所だった。(Take)
・源氏が御息所に逢う場面は今まで物語に書かれたことはなく、最後の最後となるかもしれない(?)逢瀬の場面ひとつだけを書くとは、式部のなんとも心憎い演出ではなかろうか。このあとの物語をまだ知らない私にはそのように思えた。源氏が自ら強く求めて御息所に逢いに行ったところには、源氏の心の深さを思った。(竜胆)
・嵯峨野・野々宮の秋の風景とそこを尋ねる源氏の様子、風の音と琴の音が読んでいる者に、はっきりと伝わってくる。御息所の迷う気持ちも切ないが、源氏の心憎い榊という小道具と、押しの強さにやはり負けてしまった感がある。(Yang yang)
・当時の野々宮の様子は今とはまるで違って、神域の神々しさの風情であったことがわかった。源氏は身分の低い神官たちに軽く扱われたり、案内を乞うてもなかなか応待してくれない御息所のあしらいにも業を煮やしたのか、ついには強引に御簾の中に入った。いつものことではあるが、さすがである。(まり)
第85回ゆかり雲瞬間感想(2024.9.7)
『葵~左大臣家の新年』から『賢木~決断」までを読みました。
・葵の物語は、お正月に着る源氏のために下襲の上等な着物を仕上げた大宮の気持、
何も知らずにニコニコ笑う息子の顔が東宮にそっくりというエピソードで終わった。
賢木の始まりは斎宮となって伊勢に下る娘と同行する六条の御息所がもう源氏には
会うまいと思っていたのに結局手紙にほだされて会うことになるエピソードから始まる。
二人はどうなるのだろうか? (YOKO)
・左大臣家では葵の上亡き後の新年を迎える。
大臣、大宮は堪えていたが源氏に会ってしまうと、やはり娘のことを思い出し悲しみが 溢れる。
衣のない御衣掛け、若君の笑顔に寂寥感が漂う。大宮の辛さが伝わる。
そして娘と伊勢に下る際、源氏への思いを断ち切る決意をした六条の御息所が源氏と対面した後、どう気持ちが変わるのか。(Take)
・左大臣、前と違って源氏を家に誘えなくなってより寂しそう。
源氏ももっと来ないと若君に「知らないおじちゃん」扱いされるから気をつけないと。
(W)
・賢木
御息所が娘について伊勢に下ることになり、御息所は今後の伊勢の生活に不安を感じていた。
源氏は、御息所との事をそのままにしたくなくて手紙を何度も書くが御息所は「立ちながら」なら会うと言う。
彼女の女としての源氏への気持はまだ残っているのがわかり、ちょっとかわいそうな気もする。
(SUZU)
・「葵」の最後には半年経っても娘の死を嘆いて暮らしている両親の様子が描かれている。
新年の挨拶に訪れた源氏もていねいに文を返している。
次の「賢木」の始めには、また、御息所の源氏への複雑な女心の移ろいが描かれて、
これからどういう展開になるのか楽しみである。(まり)
・「葵」の最後と「賢木」の冒頭を読みました。
久しぶり(何カ月ぶり?)に参加したので前後関係がまるで??で感想が言えないです(笑)
ただ、源氏がまったく変わっておらず女性の気持よりもまず自分。自分軸全開の男なんだ
ということを再認識した次第です。(e)
・葵Final
姫君のいない左大臣家の新年は、大宮のお歌が、ただひたすらに悲しかった。
物語の登場人物の歌を詠んでいるのは実は紫式部なのだけれども、それが凄いことだと思う。
娘に先立たれた老女の悲しみがリアルすぎて・・・
賢木に移り、伊勢下向前の六条さんが描かれると、どーしてもう この人はこんなに
思いつめてしまうのだろうと。
源氏に会わないまま伊勢へ行ったほうがきっと、楽だと思う。それは判ってるんだよね。
でも「来る」と言われたら 待っちゃうのね。
そんな御息所の心に寄りそってこの先を読んでいこうと思います。
(ぴ)
第84回ゆかり雲瞬間感想文(2024.7.6)
「子の子餅」から「まことのよるべ」までを読みました。
・女君と夫婦の関係になった源氏は惟光に三日夜の餅を頼むと、惟光はしてやったりとみずから家族に指示して作って持ってきた。しかし女君の怒りはおさまることなく、裳着の儀(成人式)をすませた後もまだわだかまりがあったようだ。そのまま年が明けてしまった。何か月もその状態が続いたようで、今後の二人の関係がきになるところだ。(YOKO)
・紫の上の態度は依然として軟化しないが、それに反比例するように源氏の恋心は激しくなっている。他の女性達への気持ちも醒めていき、今後の二人の関係はどう変化していくのか。平安時代の結婚の三日夜の餅などの描写が興味深い。(Take)
・久しぶり登場の弘徽殿さんの味方が誰もいなくて悲しい。父大臣は手のひら返してるし、悪役好きとしては頑張ってほしい。(W)
・葵の上が亡くなってから、彼女とのはかない縁(お互いを理解せず、あまり親しくないまま彼女が死去した事)を思い、源氏はこの世の短さを痛切に感じるようになる。そして女君をすごくいとおしく感じられることを尊い気持ちだと思うようになったが、女君は自分の気持ちの整理がつかず、もがき苦しんだ。そんな状態のまま年が明ける。二人の気持の相違が今後どのように展開してゆくのか興味が尽かない。気になるわ~(SUZU)
・惟光が気のきいた「子の子餅」を用意する場面が楽しかった。久しぶりの源氏と惟光の阿吽の呼吸のやりとりがいい。お餅を二人して食べて正式に結婚した二人なのだが、若紫は源氏を「こよなううとみきこえたまひて、さやかにも見合わせたてまつりたまわず」。恥じらっているなんていうものではなくて、源氏を拒絶している。こののち若紫の気持ちはどのようにして源氏へと向かっていくのだろうか。そこを紫式部がどのように書くのかが気になる。あるいは過程は詳しく書かないかも?(山百合)
・久し振りに惟光を登場させてお祝いの品を用意する役を与えている、紫式部の物語を進める手腕はすごいと思った。そして惟光はその役を完璧にこなしていた。女君の機嫌はよくならず、源氏を避け続けているのに源氏の女君を思う心はかえって激しく、他の女の人の所に通うこともなく、三か月があっという間に過ぎた。(まり)
・惟光の子の子餅準備と弁ちゃんとのからみは微笑ましくてほっとする。先回からの紫の上の苦悩と源氏がまるでそれに気付かないことを今後どう物語っていくのか早く知りたい。(Yang yang)
・源氏が全てを言わなくても、餅の意味を理解して相応の仕事をする惟光。腹心の部下って
こういうことね。餅の準備を他の誰にもさせたくない惟光の気持ち、源氏を敬愛しているのが伝わってくる。なんだろう、二人の心がすぐ近くに見えるような表現だった。亥の子餅の夜から年が明けるまで解けない紫ちゃんの心。少女の心の傷はとても深いのだろう。(ぴ)
第83回ゆかり雲瞬間感想文(2024.5.11)
「帰邸」の途中から「結婚」までを読みました。
・葵の上が死去し二条の院に帰ってきたら、紫の姫君がすっかり成長し女らしくうつくしくなっていたので、源氏は姫君に入れ込んでいく。ある日強引に結婚してしまったが、姫君はその突然の行為に驚き、ゆるせない気持ちで一杯になる。
「男君はとく起きたまひて女君はさらにおきたまはぬ朝あり」この表現で前夜なにが起こったのかを表現しているなんて、すごい!!(SUZU)
・左大臣邸の人々と別れて二条院に戻ってきた源氏だが、明るい二条院の人々を見るにつけ、沈み込んでいた左大臣邸の人々を思い出すのだった。と、人の情もよくわかっている源氏だが、若紫と一線を越えてしまった。若紫は兄のようにしたっていたのに、まさかこうなると思っていなかったようで、翌日ふとんから出て来ないで、一日中源氏がなぐさめたり、文句をいったりしていたのを無視した。源氏物語的に特に面白かった。(YOKO)
・心の準備・体の準備がなにもできていなかった若紫としては、源氏との一夜は衝撃だったようで、朝起きることができないほど打ちのめされており、源氏を信じていた自分がバカだったと思う。一方の源氏はその若紫をみても「気づまりなもてなしだね。意外とひどい人だったんだね」などと言って、若紫のショックに思いがいたらない様子である。これにはあきれた。結局、二条院に一緒に住んでいる女君の若紫は源氏に軽く扱われているのだなと思う。若紫がとてもかわいそうだった。(空木)
・葵の巻では源氏にとって二条院はいつも心安らぐ場所として描かれている様に思う。それは紫の上の存在の象徴の様に。そして会わない間に美しく成長した紫の上に対する源氏の気持ちと二人の関係にも変化が訪れる。何も特別なことではないと平常心な源氏に対し青天の霹靂の様な紫の上の対比が、男性と女性の違いがよく表現されている。(Take)
・古いけど「笑うミカエル」というマンガで179ページの場面がそのまま載っていた。縁起が悪いのはお前の方だ!と女子高生たちにボロクソに言われていた。少し脚色してあるのかと思ったら原文のままでびっくり。思ったよりはるかにひどかった(W)
・結婚の章では紫の上の立場と源氏の様子の対比が鋭い。紫式部がシニアの女房からテイーンエイジの女性、身分も様々な彼女たちを描く視点に感心するとともに共感できる。
(Yang Yang)
・「御装束たてまつりかへて」で左大臣邸と二条院の対比を鮮やかに描き出していると思った。二条院は源氏のプライベートな場である。何もかも自分の気持ちに合うように行き届いていて、その上自由。あの方にそっくりに美しく成長している姫君を見て嬉しく思うところは源氏物語の闇の部分と思う。昂る気持ちを押さえきれない若い源氏が知らずに傷つけている紫の姫君が労しい。(ぴ)
・哀しみにおおわれた左大臣の家から我が家に帰ってきた源氏は、活気溢れる様子にほっとしたことだろう。そのような避難場所がある源氏は恵まれた人だと思う。でも若紫のショックを思いやれない源氏にはがっかりした。これから二人の関係がどうなるか気になる一方、このことを含めて自制心が少し足りない自分勝手な源氏が、自分の行いの報いを受ける日が来るのではと感じられるできごとと思われた。(まり)
第82回ゆかり雲瞬間感想文(2024.3.2)
「別れ・女房三十人」から「帰邸」の途中までを読みました。
・左大臣にも女房達にもあこがれの存在であった光源氏。左大臣家に来ることが少なくなることを見越して女房達のそれぞれの反応が興味深い。源氏の葵の上を失くした深い悲しみは書き散らされた歌からも読みとれる。(うさ子)
・左大臣が悲しんでいる横でたくましい女房達の話が生々しい。この女房たち、寿退職を目指さないのが良い!(W)
・葵が亡くなり源氏も去ってしまった左大臣邸。左大臣や大君は源氏が書き残した文を見ても深い悲しみにくれる。女房達は悲しいと同時に今後の身の振り方も思案しなくてはならず、複雑な気持ちだっただろう。源氏は院のもとへ直接参上する。面やせした源氏へと食事を用意させる院が、父親としてやさしい。さらに藤壺中宮の元にも挨拶に行く源氏のいつもと違う喪服姿に、新鮮な感じをもったという女房達の感想が生々しくおかしい。(YOKO)
・葵の上の死を悲しむ彼女の両親、仕えていた女房、源氏の様子がさらに語られる。今まで語られなかった源氏と葵の上の関係性も明らかになり、それを知った左大臣は妻とともに娘を亡くしたさらなる悲しみにひたる。また当時の女房人生を垣間見れて面白かった。源氏が父の所に寄って、藤壺にも会う場面はなかなか意味深長だった。こういうところが源氏物語の奥深さなのだろう。(まり)
・今日は、源氏が他人となってしまった左大臣の悲しみ、若い女房たちが考えている今後の就職先のことなどについての感想をかこうと思っていたのだが、最後に読んだ部分に心が奪われてしまった。左大臣家を後にした源氏は父院のところへ、次に中宮の御方にも参る。そこで二人がかわしたやりとりの公式部分が書かれていた。公表はされなかったが二人は(なまめかしさまさる源氏と藤壺)、夜が更けるまで語り合ったらしいことが匂わされていた!(雪割いちげ)
・左大臣家で、
姫君と源氏の君に仕えるのは最高のお勤めだったんだけどさ、姫君が亡くなって源氏の君もお通いにならなくなっちゃ、ちょっと考えちゃうわよね。まだ赤ちゃんの若君のお世話ったって、ちょっと働き甲斐がねぇー。ちょっとお休みもらって考えるわ。転職も視野に入れてる。どこかイケメン公達のいるお邸で求人してないかしら。なんて女房の給湯室トークを想像して楽しかったです。
中宮との面会の場面は二人の心の結びつきが垣間見えてびっくりでした。もっかい読も。(ぴ)
・左大臣が夫婦の寝室に入り、源氏が残していった手習いの紙を見て、源氏の手、草、真名で書かれた美しい筆跡の「君なくて塵つもりぬるとこなつの露うち払ひいく夜寝ぬらむ」を読み、北の方が源氏に愛されていたことを伺い知り感慨に浸る。(SUZU)
・身近な人が逝ってしまった後に残された人々の描写が印象に残った。空蝉のむなしきここちぞしたまふ。そぞろ寒き夕のけしきなり、など情景が心のあり様を表現しているところに惹かれる。(Take)
第81回ゆかり雲瞬間感想文(2024.1.13)
「朝顔の宮と」から「別れ・大宮と左大臣」を読みました。
?
・葵の上を亡くして喪中の期間をすごす源氏の君だが、いよいよ左大臣の屋敷を去ることになった。父である桐壺院にあいさつに参上するということで出立するが、誰もがもう源氏は二条院に戻っていくと知っている。大臣も大宮もすべての人が悲しみにくれている様子が心に残った。(YOKO)
?
・朝顔の宮からの返事が少ないから冷たいとのことだが、おそらく女房チェックが入っているせいだと思う。しかも源氏が相手だからすごいきびしそう(W)
?
・葵の上の四十九日が過ぎ、いよいよ源氏が左大臣家を去るということで泣きっぱなしのシーンばかりでした。今日はほぼほぼちんぷんかんぷんでしたので、点をつなげる作業を家でしてみようと思います。(e)
?
・大臣の深い悲しみ(娘を失っただけでなく、そのために源氏との絆も切れてしまう)が伝わってくる(子どももいるのにね)。思えば左大臣は最初から源氏が大好きだった。結婚式の時のはしゃぎよう→今のこの悲しみに変わるなんて…。今日は大臣目線で読んでしまいこちらまで悲しくなった。源氏は多くの人に愛される人生だ。(時雨をしらない女より)
?
・今日読んだところを通じて、時雨がなんて効果的に使われているんだろう、と。
朝顔の姫君が見逃すことのできない文の紙。左大臣家を発つ日の「をり知り顔の時雨」は大臣に決心をさせるものでもあって。そうした時雨の情緒を現代の日本では感じ難くなっていることが、すこしさみしいです。(ぴ)
?
・源氏が左大臣家をいよいよ去ることになって、女房たち・大臣・大宮、皆が打ちひしがれている。また来るからと言う源氏のことばを、皆が本気にはしていないことが伝わってくる。葵との子どもに対する愛はこのあと源氏に育つのだろうか?葵との別れという試練をこえて、源氏はもう少し成熟していくのだろうか?(水仙)
?
・北の方がかわいがっていた女童あてきちゃんがいて、源氏の声かけでわっと泣き出すのがふびん。左大臣は四十九日も過ぎ、いよいよ源氏が帰って行くのに無情を感じるが、「時雨も隙なくはべるめるをと…」と言い、悲しみにくれながらうながす。この時雨が二人の悲しみを表現していてすばらしい。(SUZU)
?
?
・源氏のつれづれなさや妻を失った哀しみ、葵の上の両親の子どもに先立たれた深い哀しみをちょうど秋の季節の時雨をたびたび登場させて、抒情的に物語っているのがよかった。(まり)
?
・四十九日の源氏と左大臣家の人達の様子と心持が伝わってくる。驚いたのは気の置けない人々と語り合う場面で中納言の君に言及されていること。紫式部の時代の常識をつきつけられた感じ。(yang yang)
?
?
?
第80回ゆかり雲瞬間感想文(2023、11,4)
貴公子ふたりと朝顔の宮を読みました。
喪中の源氏と中将。Boys talkで、なぐさめあい、最後には、人生の無情を感じて二人で涙する。
又、喪服を着くずした源氏の姿にほれぼれする中将と、中将の立派な男らしい姿にはっとする源氏。二人の姿を式部も楽しんで書いていたと思う。
(yang yang)
葵の上を亡くした源氏は、秋の時雨をながめつつ、鬱々として過ごしている。それを見つめる三位の中将の思惑が興味深い。自分が女だったら、この美しい人(源氏)を残して死ぬことはできないと、従兄弟で義兄弟で、親友でありながら、特別な想いもふぁ~と出てくる辺り、二人の絆を感じた。
(Yoko)
第79回ゆかり雲瞬間感想文(2023.9.2)
「御息所の文」を読みました。
・葵が亡くなって喪に服している源氏に御息所から手紙が届く。菊の花の枝に青鈍色の紙に書いて庭に置かせた。御息所のセンスの良さが出ているが、お悔やみの言葉が白々しく、源氏は同じように灰色がかった紫色の紙に手紙を書いて送ったが、どうしてもうらみがこもってしまったようだ。たった一往復の手紙だが、二人のこれからの関係を考えさせられた。(YOKO)
・御息所、源氏へ手紙を出したい気持ちを押さえていたが、やっと書いて出したが源氏からの返事に「心置くらむほどぞはかなき、かつはおぼし消ちてよかし」と書いてあった。自分の心の鬼をはっきり感じ、たまらない気持ちにおちいる。だが、時間が経って、野々宮にサロンができて生き生きと女主人となっていった。源氏はそのうわさを聞き、さすがと、良かったと思う。(SUZU)
・妻を失い寂しさにくれる源氏。そこにすさまじい生霊のかげも未だ生々しく記憶に残る御息所からの文。両者の真の思いなのか、様々に解釈できる深い意味合いをもった分の内容が興味深い。いつの世も互いを思う男女の心は複雑だが、他に忙しいことがないからか、今日より、より一途で真剣な気がする。表現力がすばらしいせいかも?!(BB)
・北の方亡き後、御息所は弔意を伝えようか迷いもあったのではないか?「ただ今の空に思ひたまへあまりてなむ」この気持ちに偽りはないと思う。(TaKe)
・御息所と源氏の心のすれ違いは、生霊もからんでますます悪くなる一方であったが、源氏のつれない手紙によって、御息所の心もふっきれたように思われる。野々宮のサロンを始めて、御息所も生きがいを見つけられたようでよかった。(まり)
・葵の上の喪に服している中、御息所の文が届く。源氏は男女の仲の煩わしさを感じている中で、生霊を見た嫌悪感から御息所をうとましく思っている。御息所もいいかげん諦めればいいのに。若くて美しい男性への思いが忘れられないのは分るが・・・。(うさ子)
・久しぶりに出席しましたが、流れるような文章の美しさにやはり源氏はいいなぁと思いましたが、その中にも源氏(年下の男)と六条(年上の女)など普遍的な愛の形が描かれていているから今に至るまで愛されているのだと思いました。(S)
・野々宮のサロンのメンバーに桐壺院の手の者もいたと思う。源氏もなんだかんだ言っても完全に別れたくないのがうかがえる。それほど素敵だったのだろう。(w)
・源氏からの文で、「もうあまり執着しないでください」と言われてしまった御息所。そこまで言われてしまったら、源氏にいい寄られた過去の栄光?は忘れて、源氏をいさぎよく諦め、儀礼的に付き合うに留めたらどうですか?サロンではなかなか魅力を振りまいておられるようだしね。その方がずっとかっこいいです。(ちちろ虫)
・御息所の文の「聞こえぬほどはおぼし知るらむや」、まずは斎宮のことにかこつけているのだろうけど、源氏に文を届けるとなると、車の所争いのことを思い出してしまうから、筆を取る気になれないよね。
このところの文では心も通じない。そのうえ、見知らぬ姫君に乱暴なことをする夢。源氏の北の方が亡くなったと聞き、自分はどうしたらいいのか、考えに考えて書いた弔問の文。ただ「お悲しみをお察しします」って読みとってよ、源氏さん。(ぴ)
第78回ゆかり雲瞬間感想文(2023.7.)
追慕の日々を読みました。
・葵の上が亡くなり、父の左大臣も母の大宮も嘆き悲しんで、起き上がれない。源氏も悲しいが葵の遺骨を持って帰ってくる。今までの自分の行いを反省して、お経をとなえて、二条の院にも帰らず、他の女には手紙だけは送っている。子どもが無事に生れたことや、若紫が寂しく待っているということを思い出して、出家したいという気持ちを押さえているようだ。(YOKO)
・葵の上が亡くなってはじめて、彼女への今までの冷たい接し方をつくづく後悔し、もっと話をしておけばと思う。やっと人間として少し成長したのかな~と思う。人の常として、亡くなってからその人が大切な人だったと気づくのね。(SUZU)
・久しぶりに参加したら、葵の上が亡くなっていた。悲しみ(と後悔)に暮れる源氏の様子が描かれていましたが、そんな時でも、いやそんな時だからこそ?源氏の色気というのは隠すことができないんですねー(e)
・源氏は葵の上を亡くして、今までの夫婦の関係を振り返り深く後悔する。夫婦の間柄というのは難しいものですね。(うさ子)
・葵に対しては、今更…という気がする。が、本人は本気で悲しんでいるのだろう。でも他の女の人には文は出す。(W)
・葵の上が亡くなって、左大臣は「え立ちあがりたまはず」、「もごよふ」(うねりくねり這っていく)。大宮は「しづみ入りて、そのままに起き上がり給わず」。源氏は長年、妻の気持ちを思いやらなかったことを今頃になって悔やむが後の祭りである。葵の両親の苦しみ、悲しみと比べたら、源氏の悲しみはそこまで深くなくて、葵の上の10年の結婚生活は何だったのだろうかと気の毒で仕方がない。(檜扇)
・葵の上が若くして死んでしまって、彼女の父母の嘆きは深く、うちのめされたさまがいたわしい。源氏も後悔ばかりで、家にも帰らず、葵の上のことばかりを考えている様が意外である。源氏は妻の死を経てどのように変わっていくのか気になるところである。(まり)
・北の方の死に悲しみに、ひたすら勤行にはげみ、所々の女君には文を送るけれども、御息所にだけは、神事にかこつけて連絡をしない源氏。生霊を見たことで、どう対処していいのかわからなくなっているんだろうけれど。いや、ショックを受けているのもわかるよ。でも御息所にとっては、避けられるのもつらいことだと思うんだ。どうして思いやってあげられないかなあ。(ぴ)
第77回ゆかり雲瞬間感想文(2023.513)
「夫婦の絆」から「急死」までを読みました。
・病に臥している北の方に寄り添う源氏は初めて彼女のことを認識したのではないか。「いときよげにうち装束きた」源氏を「常よりは目とどめて見いだした」北の方の姿が目に浮かぶようだ。(Take)
・何とか無事に息子が生まれて、源氏は葵の上を見舞った際に、初めて妻をいとしいと思えたのに、左大臣の邸内の男性がみな内裏のつとめに出かけたあとに、葵の上が急変して亡くなってしまった。彼女の父である左大臣の嘆きがつぶさに語られていた。失意の源氏の心持ちはこれから変わっていくのだろうか。(まり)
・源氏の心が葵に向いていくが葵の気持ちが目線のみでしか語られていない。現代の小説なら葵の気持ちが語られるのだろうが…。彼女の本心をきいてみたい。(Yang Yang)
・源氏と葵の上の気持ちがここにきてやっと通い合ったのが読者としても嬉しかった。しかし葵の上の源氏にたいする想いの方が、源氏の葵への想いよりも深かったような気がしてならない。葵の気持ちは一言も語られなかったが…。(蛍袋)
・葵が亡くなる所はあっさり書いてあるのにその後の様子は詳しく書かれていて生々しい。もし生き返ってたら見た目とかちょっとホラーなのではないかと思う。(W)
・ようやく夫婦として心を通わせることができ、難産の末にかわいい子も生まれ、一安心して出かけた源氏に北の方の急死の知らせ。絶望の底にあって、冷静に振舞うことも出来ず、この逃れられない現実にどう向き合っていくのだろうか。(BB)
・「御髪の乱れたる筋もなく」
源氏が御簾内に入る前に髪を整えた葵さんの心の内がはっきりと描かれているように思えてならない。「常よりは目とどめて」源氏を見送る葵さんは穏やかな気持ちだったと思う。生命が尽きるとかそういうの抜きで、夫を見送っていたんじゃないかな…。死んじゃうことよりもふたりの心がつながった瞬間が「尊い」。(ぴ)
・今回は葵の急死がメインだった。出産まで物の怪に取りつかれている様子は仰々しかったが、宮中の行事に正装して出かける源氏をいつもより長く見つめて、その夜に人気のない屋敷で急に亡くなったシーンは物悲しい。最近「メメントモリ」という言葉をよく聞くが、人は突然死んでしまうことを忘れてはならないからこそ、充実した生き方をしなくてはいけない。源氏は後悔しただろうが、葵は生き返るわけではないので心残りだったろう。(YOKO)
・「常よりは目とどめて見いだして臥したまへり」という文章から葵の上の源氏に対する思いが伝わってくる。葵の上の素直な気持ちが表れていて、自分の命の短さを感じていて、源氏の美しい姿を目に留めておきたかったのかも。とにかく最後に二人の気持ちが通いあって良かったと思います。(うさ子)
第76回ゆかり雲瞬間感想文(2023.3.4)
「二重写し」から「芥子の香」までを読みました。
・源氏物語で映画やアニメなどで必ず描かれる場面であるが、原文で読んでみて、やはりこれはすごい!と思った。紫式部の筆の力は素晴らしい。出産直前、苦しみ泣いていた葵(北の方)が「いやそうじゃないのよ、祈祷をやめて!」と言って歌まで詠んでしまい、源氏はこれは明らかに別の人だ、御息所だと思う場面、めちゃくちゃ面白かった。御息所が芥子の香りに悩む場面もすばらしい!(YOKO)
・源氏は苦しみのただ中にいる葵の上に語り掛けたのだったが、返事をしたのは別人で、御息所の生霊と源氏は確信した。この生霊は歌まで源氏によこした。御息所の方は衣にしみついた芥子の香りが取れないのが気になる。正気を失った自分が生霊となって左大臣家を訪ねたに違ないと我が身が信じられない思いだ。このようにして二人から「生霊というもの」がリアルに語られた。何とたくみな展開だろうか。それにしても、苦しんでいる御息所が抜け出すことが出来ない妄想の世界に、読者もひきずりこまれて重い気持ちになっていく。(ムスカリ)
・御息所は身分の高さ、教養の高さ、プライドの高さ故に心の奥底に閉じ込めていた思いが、我知らず生霊となって北の方にとりついたとしか私には思えない。いくら教養が高くても女性としての自分の気持ちをどうすることも出来ずおさえきれなかったのでは?(うさ子)
・御息所の生霊が出産を控えた北の方にのりうつり、源氏はその生霊と対面してしまうというおどろおどろしい描写の場面。だがじつは作者は各々の心底にあって当人が自覚していないような心の本質を語っている。すごい!! 北の方の様子が只一人あまり触れられていないのが不吉な予感がして、次の展開が待ち遠しい。(BB)
・無意識とはいえ、攻撃が女側に向かってしまうのが悲しい。やはりねらうなら元凶の男源氏。その方がいっそスッキリすると思うのだが。(W)
・御息所、北の方、源氏、恋の形、気持ちが様々で御息所、北の方の理想とする様ではなかったと思うが、源氏はやはりこの二人に対しても想う気持ちがあり、それを手放すことはできなかったのでは?でもそれが結果として女性たちを苦しめているのだが…。(Take)
・御息所のストーリは今なら彼女が主人公のサイコドラマ的小説になりそう。生霊や芥子の香、祈祷の読経の音が迫って来る。御息所の深層心理妄想?から解放される時は来ない?
(Yang yang)
・北の方の難産の場に、御息所の生霊が現れたと思った源氏。一方、御息所は自分が生霊になってお産の場に行ってしまったと悩む。どちらも、そのことを他の人に知られないように隠そうとする。お互いの気持ちがかみ合っていない二人。難産で死にそうな北の方に、「頑張れと励ますのでなく、あの世のことばかりを語る源氏は冷たいと思う。(まり)
・「いで、あらずや」の人は誰だったのか。源氏には御息所に思えたし、そうだったのだろう。御息所の気持ちを思うと、読んでいて苦しくなってくるところだ。理性と深層心理がせめぎあって、どんどん追いつめられていく。あの時に受け入れさえしなければ、これほど苦しい思いをすることはなかったのに。
御息所は源氏のことも北の方のことも恨んでいないように思える。絶望だけがそこにあって、芥子の香が消えない。(ぴ)
第75回ゆかり雲瞬間感想文(2023.1.7)
「こひぢの田子」から「妻のまなざし」までを読みました。
・御息所のせつない気持ちがどんどんひどくなって、北の方に対して暴力をふるっているような夢まで見て、自分も病気のようになってしまった。それと並行して北の方は出産を前にしてもののけにますますつかれたように病いがひどくなり、まるで死んでしまったようになった。北の方が源氏に話したいことがあると近づくように言うと、その時、源氏の目に入った北の方はいつもの彼女のようでなくて、源氏はかわいいとさえ思った。死の直前になってこんな感情を抱くなんてあまりにすれ違いな夫婦だったことか。(YOKO)
・うちとけてはいないが源氏と会った後、更に想いが激しくなる御息所。その気持ちを込めた歌を送っても源氏には伝わらない。内に秘めた情熱(情念?)が意図せずに生霊になり北の方を苦しめる。二人の女性が別の場所、立場で苦しんでいる様子がそれどれ辛い。(take)
・御息所の人生、源氏がだいなしにしている気がする。苦しんでいる場面しかなくて悲しい(w)
・御息所は車争いの件をきっかけに、葵の上に対し、自分が思っている以上に口惜しい気持ちと嫉妬心を抱いていることを自覚する。その怨念は体から怨霊となって抜け出し、葵の上にとり付く。全ては源氏への強い恋心とプライドの高さからによるものか?仏にすがっても救われない人間の煩悩というものは、今も昔も困ったものだ!(うさ子)
・つれない返歌をよこす源氏に対する自分の気持ちをもてあます御息所。北の方の様子を伝え聞いて自分が呪詛しているのかもと思い悩むことになる。一方の北の方はいよいよ出産が近づくが、無事に産まれるのか、次回が楽しみである。(まり)
・もののけが人にとりついて病を引き起こすという発想には驚く。そして「御息所の生霊が葵の上について」と具体的なところまでを巷の人々がうわさをするとは!そういう噂を知って、御息所はそういえば最近思い悩むことがひどいから、自分の霊が外に出て行ってしまっているのかもしれないと考えるのだった。ある意味とても冷静な御息所が源氏との泥沼に、はまったまま抜け出すことが出来ないのが哀しい。(水仙)
・六条御息所との暗くて重いどろどろしたシーン、病の中での出産シーン、生霊に取りつかれて苦しむシーン、となかなかの状況の中で葵の上の美しさの描写をとても興味深く感じました。それにしても源氏は物事の表面しか見ていないように思えますが、この後、年をとると変わっていくのでしょうか・・・。気になります。(e)
・六条御息所は早く源氏のとらわれから解放されるといいのだが・・・。冷静に自己分析をして歌を詠むことができる才能ある女性が、階級社会の中でつぶされていく感じが、恋から逃れられない哀しさと呼応している気がする。それにしても様々な女性を描き分けることができる式部ってすごい!!(yang yang)
・「うちとけぬ朝ぼらけ」から切ない。御息所の心の底の底からの歌に対して、上っ面だけの源氏の返歌。しょうがないじゃん、みんなそれぞれにいいところがあって、ひとりに決めることなんてできないんだもん。せめてわたしは御息所のこころによりそってあげたいと思うのでした。(ぴ)
第74回ゆかり雲瞬間感想文(2022.11.5)
「海士のうけ」「大殿のもののけ」、「こひぢの田子」の途中までを読みました。
・御息所は源氏との恋に限界を感じて、斎宮となった娘とともに伊勢にくだってしまおうかと悩んでいた所、源氏の北の方の葵が妊娠中の症状が悪くなった。物の怪と判断されて、加持祈祷などをさかんに行い、源氏の父である桐壺院からも気遣われる。
そんな中、源氏は御息所を訪問して様子を尋ねるがあまり心がこもっていない。御息所があまりに悲しい状況であったことが理解できた。(YOKO)
・御息所は娘に付き添って伊勢に下るべきかいろいろと悩む。下れば源氏とは永遠の別れとなるし、都に残れば世間にあれこれ言われるし。「車のところ争い」は御息所の自尊心を深く傷つけてしまって、ますます追いつめられていく様があわれである。妊娠した北の方が病みがちになって、さすがの源氏も心配しているのが少し意外だった。当時の人々の「もののけ」をめぐる騒ぎが詳しく描かれていて興味深かった。(まり)
・女性の内心がここまで書かれているのは御息所がはじめてな気がする。それほど物語の中では大事な人物といえよう。(w)
・はるかいにしえの話なのにすさまじい心の乱れ不調に対処する方法など、現代にも通ずるものを感じ、今でも占いや信仰に頼る世界など、そうかけ離れていないものがあるのが興味深い。世間体を気にかけるのも関西文化的。人間というものの不変性を想った。(BB)
・車争いの一件がこんなにも御息所の(プライドを傷つけられた)悔しさや葵の上に対する憎しみを増幅させたとは源氏の君にも「これ程までと」予測出来なかったかも。恨み辛みは恐ろしい!
生霊となるまでに至る御息所の心の動きを「海人の浮き」と歌を引用して表現しているのがぴったりで凄い。それにしても相変わらず、源氏の君の自分の都合を優先する態度が、調子が良いと言うかプレイボーイの見本ですね。自分の好きな女性には豆々しく心配り出来るし…。(うさ子)
・北の方は「御もののけめきて」すっかり病みついてしまう。そのとりついているらしい物の怪・生霊の様子がこと細かに描かれているのには驚かされた。さまざまに名乗りするとか、片時も離れない執念深いものがいるとか。
御息所は源氏への想いが断ち切れずにいろいろと悩み苦しんでおられるが、心のこもらない源氏の言葉に、早く目を覚ましていただけたらと思う。御息所の「御いどみ心」がこれからどうなっていくのかとても気になります。(野紺菊)
・御息所の思い悩む様子
京を離れると源氏とも会えなくなる。車の所あらそいが影響し今までとは違う心の動きに自分でも戸惑っているのではないか?
北の方の容態を心配しつつも源氏の態度はどちらに対しても真心があるのかないのか…。(Take)
・御息所を苦しめているのは、自分と源氏のことが人々の口にのぼって笑われているのではないかということと、源氏の心が自分に向いていないこと。これだけに思える。ひたすらに我が身を嘆いているようで、左大臣家の北の方その人を恨んでいるとは思えない。
あ、あと、左大臣家サイドでは二条の君がいっちょまえの大人な女性だと思われているところがおもしろかったです。(ぴ)
第73回ゆかり雲瞬間感想文(2022.10.1)
「見物の人々」から「典侍のかざし」までを読みました。
・今回は葵祭の本祭りをめぐるエピソードで、若紫たちを車に乗せた源氏は、車に乗った典侍にばったり出会う。典侍は簾をあげずそっけない返事しかしない源氏にがっかり。まわりの女たちも源氏と同乗しているのは誰か気にしただろう。葵が「あふひ」で、男女が恋のやりとりをする風習があるとか、葵がフタバアオイという草で髪にかざるものとは今までしりませんでした。(YOKO)
・北の方への源氏の不満、二人の女性の関係への自分都合はやはり、あーあ自分勝手な男だなと思ってしまう。その後、鮮やかに場面転換の髪を切るほっこりシーンはさすが式部。そして典侍の登場が楽しい展開だった。(Yang Yang)
・典侍の再登場に驚く。紫式部自体が典侍を気に入っていたように思う。この時代に60歳位で現役で「旧りがたくも今めくかな」と思われるなんてステキ!!
源氏の紫ちゃんの御髪をそぐところで、二人の歌のやりとりで紫ちゃんの歌がすばらしい(SUZU)
・源氏のふがいなさも、紫の上のかわいさも、典侍の登場ですべて吹き飛ぶ。様々なタイプの女の人の対比で、最後にもってくるところがうまい。(W)
・葵の上、御息所、紫の上、典侍と源氏のまわりの女たちの個性がそれぞれに描きわけられていた。加茂の祭りを当時の人が楽しみにしていたこともよくわかった。(まり)
・車の場所争いが起きてしまった遠因は北の方の気の利かなさにあると分析している源氏。自分の方こそ、御息所や北の方への細やかな心配りに欠けていたことを棚にあげていませんか? 若紫に対しては髪の毛をみずから切りそろえてあげていて、なんとまめまめしい事でしょうか。若紫がいっぱしの歌(源氏を客観視している歌)を詠んでいるのには驚いた。(カンアオイ)
・北の方は正室であるが故なのか、源氏の他の女性(御息所)に対してのふるまいがやさしさや配慮に欠けていると源氏は感じている。今回読んだ段から、どうして二人の間柄がしっくりといかないのか何となくわかる気がした。
それに対し二条の院での紫の上との関係は「うち笑みて」の言葉で楽しそうな様子が良く表されていると思った。(うさ子)
・「かくかたみにそばそばしー」からの二条の院。この場面転換、すごくない?
二条の院の祭見物の支度の場面では、源氏が姫君や女童を大人扱いしてふざけている様子が印象的。
「千尋とも~」の紫ちゃんの歌は大人ごっこの雰囲気に刺激されて、ちょっぴり背伸びして詠んだんじゃないかな、と思いました。「なかなかうまくできたかも!」って作品を書き残しておこうとしたあたりも思春期にさしかかった女の子の感じがします。
あと、「旧りがたくも今めくかな」はメモ。平安時代のスーパーキャリアウーマン。(ぴ)
・北の方と御息所の一件に心を痛めている源氏が二条の院に行き、紫の上の美しい姿にやすらぎを感じる。そして祭見に行った先で典侍に会う。源氏の周りの女性達の年齢の幅の広さがすごい。今回はそれぞれの女性の特性が表れていると思った。(Take)
第72回ゆかり雲瞬間感想文(2022.9.3)
・六条御息所の源氏への切ない思いが、車争いでふみにじられるさまが、伝ってきた。源氏をみられる機会を逃がすまじと思う下々の者たちの様子が面白おかしく書かれていて、当時の庶民の様が目に浮かぶようだった。(まり)
・?六条御息所の牛車が先に行って場所を取っていたのに、葵の上の一行に押しやられて後ろの方に追いやられてしまった。御息所はくやしがったが、源氏をちらりと見ると、来てよかったと感激していた。意外と素直な気持ちに驚いた。
②見物の人々が源氏たちに手を合わせて拝んでいるという場面に、源氏はこの時代のスターなんだなあと、今更ながら感動した。(YOKO)
・六条の御息所の気持ちを思うと本当に胸が痛みますが、それにしてもこれほどまでに人を惹きつける源氏の魅力って一体なんだろうと、いまだに不思議です。倒れ転びながらとか、おがんじゃうとか…。(e)
・車争いでは六条御息所のくやしさ、北の方の供人に馬鹿にされたという屈辱感が文書からよく伝わり気の毒になった。北の方(左大臣家)の品位が御息所の品格の高さに比べると低く、下々の者達のふるまいにも出ていると思った。
(うさ子)
・これが有名な車争いのシーン。左大臣側の供人達、どける車を選んでいるのも腹が立つ。六条側との人々との違いが目立つ。やはり身分の差か。(W)
・すみへ追いやられた牛車にいる御息所が、無念の思いに打ちのめされながらも、源氏の晴れ姿をひと目見て喜びにうちふるえているところが圧巻だった。源氏と車の中の女たちとの密かなやりとりや見物の人々の様子がユーモラスに描かれていて面白かった。軽さと重さ、明暗、群衆と一人が描き分けられていて、筆が冴えていると思う。(コミカンソウ)
・御息所が左大臣家の人達にプライドをずたずたにされ、それでも一目源氏を見ることができて、やはり来て良かったと思うシーンは女心のせつなさと思いの深さが哀しい。お祭りのイベント感は1000年前も今も変わらない感じがよくわかる。アイドル源氏を見て、庶民もみんなhappyになっているのが面白い。(YangYang)
・車争いで御息所は、北の方の車におしやられてしまい、良く見えない奥の方に行くことになったが、それでも一目「目にもあやなる」源氏の姿を見ることが出来て、来て良かったと思った。彼女の女性としての気持ちを知る事が出来たしみじみとしたシーンだった。(SUZU)
・六条の女君の一目源氏の姿を見たいという気持ちが、自分のくやしい気持ちより強く、誇りを傷つけられても帰れない姿をいじらしく感じた。その後の祭りを見物にきていた人々の描写は、当時の人々の様子が細かく書かれていて興味深かった。(Take)
・とりあえず車争ひ
御息所の車が「控え目ながら洗練されてすばらしく美しい」と描かれていて、そこに「どうか気付いてほしい」という彼女の想いを感じた。くやしくてつらくて、それでも一目でも見ずにいられなかったその姿。そのあとに一般大衆の姿も生き生きとしていて、それがかえって御息所の苦悩をきわだたせていた(ぴ)
第70回ゆかり雲瞬間感想文(2022.5.7)
藤の宴から『葵』の御代替わりまでを読みました。
・藤の宴が催され、源氏にも来てほしいと言われていたが行かず、宮中の帝のそばにいた時、催促の歌を受け取り、帝に見せる。帝は迎えの者をよこしているのだから出向くように言う。しぶしぶ源氏は行くことにしたが、支度をゆっくりして暮れてから出かけた。源氏の美しさは皆を驚かせ、満足させるものであった。その後、酔ってぶらぶらして、会いたいと思っていた人の声を聞き「ただそれなり。いとうれしきものから」と終わるのはすばらしい。(SUZU)
・右大臣邸での藤の宴への誘いの手紙を帝に見せ、「早く行きなさい」と言われて、日も暮れてからとりわけ目立つ装いで到着した源氏。酔ったふりをして寝殿の奥に入り込み、ついに例の有明の君に再会することができた。とは言ってもこの姫は東宮妃となる予定もある。この恋はいったいどうなるのであろうか?(YOKO)
・前回、前々回ともお休みしてしまったので、花宴に関しては正直、最後の歌で朧月夜ちゃんがとても魅力的な女の子であることは想像できたものの、よくわからないままでした。葵上は今からどんな展開が待っているのか楽しみです!(e)
・「花宴」は華やかな宮中でも、特に華やかな桜の季節、きさらぎの二十日ごろと、弥生の二十日頃の2回のできごとを描いた巻である。美しい花が咲いているのに、源氏の心は藤壺へのかなわぬ想いでいっぱいであった。そんななかで朧月夜との新しい恋が始まった。きさらぎと弥生、それぞれの桜の季節に「袖を(手を)つかまえてうれしい」という同じことの繰り返し!で語られる。特に2回目はようやく逢えたふたりの嬉しさを思うと…。しかし今回の恋も相手は春宮妃となる女性、またも源氏の恋は悲しい。(N)
・花の宴はお花や服装の色など目に映るように華やか! 源氏にとっても。
葵ではどのような展開になるのか?源氏にとっては辛い時代が始まりそうですね。
(うさ子)
・源氏はついに扇をもらった姫君に再会することができた。源氏に探し出してほしかった姫の歌が力強くて好きだ。(夕化粧)
・「朧月夜に似るものぞなき…」と口ずさみ歩いてきた女の袖をとらえる出会いの場面と、巻末で、うち嘆く気配の女の手を几帳越しにとらえて歌のやりとりをする再会の場面の構成が見事。しかも再会の場面では几帳が障壁として存在しているようにも見えて、興味深かった。自分に正直な女君。嫌いではないです。(ぴ)
・右大臣主催の宴にアイドルも顔負けの登場の仕方は源氏の天性なのだろう。右大臣家と源氏の価値観、作者の価値観が良く伝わってくる。扇の彼女と再会するまでの書きぶりは映画のようなわくわく感があった。(Yang Yang)
・弘徽殿さん、自分の意志で院の所に行かなかったのか、来るなと言われたのか気になる。
記事にでてきた島内先生の授業とっていました。文学なのに源氏物語しかやらなかった。(W)
・心残りのまま別れた二人が、またまみえるまでの顛末がなかなか面白く語られていた。お互いに気になりながらも、手立てがなく日が過ぎた。さすがは源氏のあきらめない大胆な行動により再会できた。ところで突然、余韻だけを残して「花宴」が終わった。「葵」は源氏の父帝が退位して、宮中のようすがどのように変わっていくのか楽しみ。(まり)
第69回ゆかり雲瞬間感想文(2022.3.5)
花宴の「弘徽殿の姫君たち」を読みました。
・扇を取り換えた姫とどうなるのかと思っていたら未だに姫の素性もわからないまま源氏の思いの中にだけ登場。今回は美しく成長した若紫が理想の女性になりつつある様子と、北の方の邸で大臣、頭の中将たちと過ごす様子が描かれている。北の方とは会えたのか? 少しは会話できていたら良いのだが。(Take)
・桜の宴の後に会った若い女性は良清や惟光の調査により右大臣の姫君と確信した源氏だったが、なかなか再会することができず、若紫と過ごしたり、北の方に会いにでかけたりする。やはり彼女は冷たく出てきてもくれないと、父の左大臣や息子の中将や弁が一緒に合奏してくれるという。相変わらず男同士の盛り上がりになんだか笑ってしまった。(YOKO)
・すでにかなり面倒なことになっているのに弘徽殿父にバレる心配をしている場合ではないと思う。早くバレないかと黒い事を思う。(W)
・弘徽殿の姫との後、何番目かの姫かわからず、いろいろ思い悩む。その後、紫ちゃんのところに行って彼女の成長ぶりに大満足。だが葵の上のところに行っても彼女は出てこない。何かすっきりしない思いが続く…。(SUZU)
・相手が誰かも定かでない人との恋で頭がいっぱいの源氏(弘徽殿の女御の妹の誰かではあるのだが・・・)。源氏はまた恋のバリエーションを増やすことになった。こうやって新しい恋に身を焦がすことが源氏にとっては「生きている」実感を得られることなのだろう。でも私は源氏の恋の始まりにはいつも共感できない。1000年前の女性の読者たちは、源氏が素敵と心から思っていたのだろうか?(雪割草)
・昨晩会った姫のことが気になって仕方のない源氏はその正体を知りたくて仕方がないが、なかなかわからない。でも後宴や左大臣宅での遊びには興じて楽しんでいる。若紫が源氏が帰ってこないので寂しい思いをしていることには源氏は気づいていながら、あまりかまってやらないのはどうしたものか。(まり)
・源氏のこころの優先順位
なにを置いても絶対的存在の藤壺、次が目の前の恋、大切に育てている紫ちゃん、北の方である。左大臣家の姫君はどうにも気が重くなるようだ。源氏の来訪があってもすぐに姿を現さない姫君。源氏の所在なさを知ってか知らずか集まってくる男たちとの分奏は面白い。その音を彼女はどんな思いで聴いているのだろう。(ぴ)
第68回ゆかり雲瞬間感想文(2022・1・8)
花宴の「桜の宴」の途中から「朧月夜の出会い」を読みました。
・桜の宴のあと、藤壺に会えるかもと未練がましく宮中をうろついていた源氏は思いがけなく若い女性に出会う。賢い女の子とのこれからの恋の行方が楽しみだ。(まり)
・久しぶりの受講でしたが、楽しかったです。登場人物や風景描写など実に興味をひかれ、この作品のふしぎな魅力を感じます。源氏は身近にいたら、ひくけど、面白くて仕方ないです。(MOCHAN)
・平安時代の宮中、華やかな源氏の一瞬の舞で、皆居合わせる者達が魅せられる... ともしかしたら立っているだけでサマになる現代のフィギュアスケーター羽生結弦選手にもそれが通じるかな?と思いました。
いずれにせよ、登場人物の遣り取りが即座にウタ(詩)によって成立する、というその教養の深さ というか、若くして練磨されている教育の高さに感銘を受けました。
紫式部が書いた小説であるから、彼女による登場人物の描写ですが、当時 実際にこの様な事が日常茶飯事に行われていたのであれば、相当に洗練され、程度の高い文化が築かれていたのだなぁ、と再認識。伝統有る日本文化のレヴェルの高さ、独特稀有な文化である事を、今更ながらに確認・賞讃してます。同時に現在の天皇家でも この日本の伝統は深く引き継がれている筈ですから、その貴重さを認識。フツウの教育では培われ無い、真の意味での品格有る秀でた教養を身に付けられた人が 日本社会の頂点に座する事の重大さに 想いが行きました。
今日読み進んだ箇所全てに於いて、スマートに選び抜かれた言葉の連なりを、ひとつ一つ深く豊かに肉付けして現代語に読み解く作業が、非常に面白く思いました。コトを良く極めるには、物事全てに共通する事かも...と 知識と経験の豊富さが、どれほど大切かと思いました。ひとつの音に対する感受性も、演奏者の様々な体験と感受性に基づいているので、もしかしたら共通性を見出せるかも...と思いました。
「花宴」は色で表現するとしたらピンクでしょうか? 楽しい章で、その後がどうなるのか気になります!(Ebi)
・現代の桜を観る会とは大違い!漢詩を作ったり、舞いを披露したりと、弦楽の調べの中での花の宴は、さぞかし雅で美しい宴だったのでしょう。
そんな余韻に酔いしれて、源氏はまたも良からぬ悪い癖で、弘徽殿の廂の間へ誰とも分からない女君を誘惑してしまう。・自分でもこんな時に得てして男女の間違えが起こるものだと思っているのに、自分でそれを犯してしまうとは!ちょっと呆れてしまうくらいの女好きなのですね!!! (うさ子)
・朧月夜、若いけど色っぽいお嬢さんのイメージ。
本当に源氏物語はありとあらゆるタイプの女性が出てくるな、と実感。そして源氏の君の守備範囲の広さもすごい。もういっそのこと弘徽殿本人との話があったら面白かったに違いないと思う。
最近弘徽殿のような悪役タイプが好きなので、今回もっと出てこないかな、と期待。(W)
・帝、中宮も出席の宴。そこでの源氏の鮮やかな振る舞いに心動かされる中宮。もしかして会えるかもと藤壺わたりを訪ねる源氏。しかししっかりと閉ざされ隙間もない。そのまま帰るのも悔しいと弘徽殿の細殿で出会った女君。夜更けに歩きながら声に出して歌を諳じたり袖を掴まれてもすくむことなく声をあげたりとおとなしいだけの姫ではない様子。・相手が源氏だと分かる察しの良さ、冷淡で強情だとは思われたくないと思う判断力、名を問われた時に咄嗟に歌を返すことが出来る教養の高さ、センスのよさ。そして若さ! 魅力的な姫の登場に次回からの展開に期待が高まります。(Take)
・桜の宴について詳しく描かれていた。桐壷帝の時代は本当に華やかだったのだろう。源氏は漢詩も上手くて読み手が途中で泣いてしまうとかオーバーな表現だが、なんでもできたのだなと思える。舞もほんのちょっと袖をふるうだけで、みんなドキドキしてしまう。頭中将はしっかり練習してきて、本格的。帝はご褒美に衣を授けたり、なんか気をつかっている。こういう細かいところが面白い。その後、源氏は藤壺に会えるはずもなく、さまよい、若い女性と巡り合う。新しい恋の主役の登場に胸が躍ります。(YOKO)
第67回ゆかり雲瞬間感想文(2021.11.6)
紅葉賀「なごりの帯」の途中から花の宴の「桜の宴}の途中まで読みました。
・源氏と中将のユーモアたっぷりのやりとりが楽しかった。職場で思い出し笑いしているところも好き。
「キミと彼女の仲がダメになったらどんな恨み言をいわれるかと思うと縹色の帯は手にとって見る気も起きないよ」
「あなたにこうして帯をとられてしまったことで、女との関係が終わってしまったじゃないか。どうしてくれるんだよ。」青春だな。典侍には気の毒だけど。
感想外(あと、藤壺が産んだ皇子は二月生まれでしょ。成長と言ってもまだひとつにもなっていないのに、それほど源氏に似てるのかってびっくりです) (ぴ)
・典侍のエピソードは中将と源氏に振り回された典侍のお話でもあった。50歳すぎキャリアと才能があり、恋愛でも現役という現代にも通じる女性像だと感じた。「花宴」で宮中の様子を体験できそうでこれから楽しみ。(Yang Yang)
・紅葉賀を読み終わった。読み返すと色々なエピソードの詰まった巻になっている。情に厚い帝は生まれたばかりの藤壺の子を2代あとの皇太子に強引に決めてしまう。彼の行く末が気がかりだ。(まり)
・式部は,源氏と中将の間で起こることは、面白おかしく事細かに書き連ねているが、源氏と藤壺の間のこと、藤壺の心の動きはあまり書いていない。源氏にとっても、読者にとっても藤壺は遠い人。皇子を産んで后にもなって藤壺はどう思っているのだろうかと、読者は想像するしかない。想像するにも、もっと材料が欲しい!(磯菊)
・紅葉賀、短いのに内容は盛りだくさんだった。特に源の典侍が面白かった。当時、若い女房には評判が悪かったかもしれないが、典侍と同年代や齢の近い人には希望になったと思う。(W)
・源氏は藤壺が立后し、夜の御供で宰相としてお供した。その時、藤壺が乗っている闇夜の御輿を見つめながら苦しい胸の内を歌に詠む。「尽きもせぬ心の闇にくるるかな・・・」とある。「心の闇」という言葉が彼の心境を表現していてこちらの心もちに、ずっしりとひびいた。(SUZU)
・典侍と頭の中将と一緒にいる時間と藤壺が后になり自分の手の届かない存在になった事を寂しく思う源氏の心の対比が印象深い(Take)
・今日は大遅刻してしまって、半分参加できていないのですが…。源氏と頭の中将の下りが気になるので、家に帰ったら読もうと思います。あっ、感想になっていない!(e)
第66回ゆかり雲瞬間感想文(2021.10.2)
「琵琶の音」から「なごりの帯」の途中までを読みました。
・中将は、源氏がなかなか言わないので、源氏の恋の状態が気になっていて、典侍といる時にしっぽをつかみたくて乱入の機会をうかがっていた。その時、コメディのようなつかみ合い。さらに太刀を抜いたりとすごい事になり、読者は大笑いです。こんな楽しい場面でおもしろい!!(SUZU)
・典侍の部屋で鉢合わせた二人のドタバタ騒ぎ。巻き込まれた典侍はオタオタしてしまって、かわいそう。さすがの源氏も大いに反省した。恋多き典侍の人生を色々と想像すると面白い。(まり)
・琵琶も上手く歌声も素敵、高い教養があり、会話も楽しい。高齢だがそんな内侍が相手だと男女のやり取りも風流な趣味の一種の様に感じた。源氏と内侍が一緒にいるところへ入ってきた頭の中将。その後の展開の描写は若い(子供じみている)二人と内侍の年齢(世代)差を感じてしまった。(take)
・源氏も頭の中将も、一人一人だと典侍の手のひらで、コロコロ転がされてるけれど、二人揃うと「をこ」状態で勝てる。(W)
・コミカルなシーンが楽しい。源氏も自らを反省? 典侍は57,8歳ながらゴージャスで才能のある人。それにしても宮廷人は多才でないと勤まらない。(Yang Yang)
・源典侍をめぐる源氏と頭の中将のドタバタ劇。ドラマにしたら相当受けそう。二人は本当に仲が良いのだと思いました。典侍はひとりだけとり残されたのでは?(YOKO)
・頭の中将は、そういえば「末摘花」とのときも、源氏のあとをつけて源氏の恋の現場をつきとめようとしていた。今回、源氏と頭の中将が互いの服を引っ張り合う様は中学生のようだった。こんな他愛のないことをしている二人だが、後年ふたりの関係は変わっていくらしい…。その伏線を張るものとして、このコメディタッチの話があるのかなと思った。(ホトトギス)
特別講座桐壺の感想
2021年7月17日
葵の上とどうして、こうも仲がよくなれないのか、と思っていたけど、結婚の経 緯と、姫が自分が年上で、輝かしく、若い光源氏に、おそれ多いというか、自分 がふさわしくないのでは、という思いと、恥ずかしさがあったので、なかなか素 直になれない態度をとってしまったという事がよくわかりました。また源氏の藤 壺への想いが、よく伝わってきました。「桐壺」の巻を修了することができ、そ の後のみんなの気持ちがよく理解できて、今後勉強する上で、本当に良かったです。
田中先生、お忙しいところ特別講座していただき、ほんとうに感謝しておりま す。ありがとうございました。 (suzu)
どうしても左大臣家の姫君のことを考えてしまうので、源氏の君にとってはどん なことだったのか考えてみる。
男親同士が歌のやりとりをして盛り上がって、源氏の君はその夜、内裏から左大 臣邸へ退出しました、だけなんだものね。
心に想うひとがいる場所(かつ住み慣れた場所)から、知らないところへ行かさ れて、当世最上級の姫君とはいえ、いきなりあなたの妻だと差し出されたって、 少年は当惑も混乱もするよね。
事前に姫君の評判を耳に入れていたらよかったのにね(男親たち、まだまだ源氏 は子どもだと思ってたんだろうね)。源氏が歌の一首でも贈っていたらと思う と、残念でしょうがない。
この二人が歌を詠み交わすのはいつになるのだろう。 (ぴ)
後見のない源氏を思う帝と春宮よりも源氏をと願う左大臣。良縁だが当人たちの 望みではない様子。藤壺以外の女性のことは心にもつかない源氏。女君は源氏の 若さに自らをすこし過ぐしたまへると感じる。それに源氏の姿は「ゆゆし」と感 じられるほどきよらで余計に似げなくはづかしと思ったのでは?! 自分の意思や 思いが叶う事などない立場にある御かたがたにも内に秘めた思いがあるのだと文 章で表現した「源氏物語」。平安時代の方々がどれだけ楽しく読んでいたことだ ろう。今の世で古文をよく理解できていない私が「源氏物語」を楽しむ事ができ るのは田中先生とゆかり雲の皆様のお陰です。あらためて感謝いたします。 (take)
元服を終えた源氏が葵の上と結婚。でも藤壺さんに夢中すぎて妻には興味なし。 葵の上も源氏に惹かれているのに、コンプレックスとプライドが邪魔して素直に なれない。なんか切ないお話でした。好きになったもの負け、相手から来てほし い、みたいな感じ、若い時はありますよね。今思えばバカみたいだけど、なんか 自分もそうだった気がします。 (emi)
桐壺補習参加させていただき、ありがとうございました。
以下の文は最初に講義をしていただいた時に書いたものです。
2012年7月7日ですから、ちょうど9年前です。
いよいよ桐壺の最後となりました。元服し成人した光源氏は左大臣の姫君と結婚 しますが、なかなか藤壺のことが忘れられません。少年から青年へどんな物語が 待っているのでしょうか?
やっと一帖が終わり、まだまだ長いですが、楽しみです。
今回読んで、源氏がまだまだ初々しい少年だなと感じました。12歳で今ならまだ 小学6年か、中学1年くらいなのに、結婚して、一家の主人として母の実家をリ フォームしてもらい、独立していくのですが、帝もまだまだ手放せず、宮中にい ることが多いようです。
妻となった葵の気持ちも全然わからず、すれ違いは始まってしまいました。
葵にとっての結婚は辛いものだったのでしょうか。 (YOKO)
葵の名前がハッキリ出てこないこと、頭の中将と兄妹だと思ったら姉弟だったこ と、あの源氏にこんな頃があったのね…と色々衝撃的な桐壺最後の回でした。
左大臣は安定の源氏スキーである意味安心。こんな小さいときから目を付けたい たのか。まぁ見る目があることは確かですが。娘にもうちょっと事前アピールし とけよ!と思いました。
本編ではこの先ちょうど話が繋がってより面白くよめそう。
参加できてよかったです。先生ありがとうございました。 (W)
------------------------------------------------------------------------
2021年4月17日
時が経ち、桐壷更衣の存在も思い出に変わり忘形見の御子も元服する年齢を迎え た。そして源氏の君は美しい藤壷と出会う。花紅葉に託して気持ちを伝えようと する源氏が可愛らしい。
平安時代の元服式の視覚的な描写に想像力を掻き立てられた。
いつも感じる事だが帝の皇帝としてだけではなく男性として、父親としての様子 の描き方が興味深い。
藤壷を推す典侍も受ける帝もやはり決め手は「容貌人」であること?う? ん・・・・・・・(take)
源氏と藤壺の宮の運命の出会い!
現代ならまだ小学生(源氏)と中学生(藤壺)ですよね?
まあ自分も小学生のころ好きな男の子とかいましたから、
そう考えると(この時点では)そんなに特別なところはないのかもしれない
ですが、しかし桐壺帝としては、まさかこの2人が道ならぬ恋に落ちつつ
あるとは想像だにしていないわけですよね?
源氏のために立派な元服セレモニーの準備までしてあげて。
なんだか既にせつないですね。(川崎)
「切に隠れたまへど」が、ものすごく重要なことを再認識。
夫以外の男性に姿を見せてはならないのがルール。童形とはいえ、源氏の君に姿 を見せまいとする藤壺。なんとしてもお姿を見たいと、目で追い続ける源氏の 君。見られているのではと、源氏の君を気にして、絡み合うふたりの視線。
うわうわうわー。二人の想いは、こんなにもはっきりと描かれていて、「な疎み たまひそ」と藤壺に語りかける帝がお気の毒に思えてしまう。(ぴ)
原作ちゃんと読まないとわからなかった部分がたくさん出てきた。
まず藤壺の宮、もっと多くの人に望まれて祝福されて普通に幸せいっぱいで入内 したのだと思っていたら、以外に苦労人。
他、藤壺の宮の方の気持ちとか、源氏が好きになった経緯とか、元服式の様子と か、学者の皆さんちゃんと原作読め!と言いたい。
そもそも話全般にかかわる大事な人物藤壺の宮とのなれそめがおおよそでしかわ からなくてそのままずっと読んできちゃったので、今回しっかり読めてよかった。
たぶん次回で最後だけど、次回の内容も非常に楽しみ。
そうしてどうでもいい余談だけど、日出処の天子という聖徳太子を描いた作品 で、王子はある程度大きくなっても髪型はずっと変わらずみづらだった。あれは 何か意味があったのか、当時はそれほど決まりはなかったのか気になる。 (W)
第64回ゆかり雲瞬間感想文(2021.7.3)
2021年4月17日
時が経ち、桐壷更衣の存在も思い出に変わり忘形見の御子も元服する年齢を迎え た。そして源氏の君は美しい藤壷と出会う。花紅葉に託して気持ちを伝えようと する源氏が可愛らしい。
平安時代の元服式の視覚的な描写に想像力を掻き立てられた。
いつも感じる事だが帝の皇帝としてだけではなく男性として、父親としての様子 の描き方が興味深い。
藤壷を推す典侍も受ける帝もやはり決め手は「容貌人」であること?う? ん・・・・・・・(take)
源氏と藤壺の宮の運命の出会い!
現代ならまだ小学生(源氏)と中学生(藤壺)ですよね?
まあ自分も小学生のころ好きな男の子とかいましたから、
そう考えると(この時点では)そんなに特別なところはないのかもしれない
ですが、しかし桐壺帝としては、まさかこの2人が道ならぬ恋に落ちつつ
あるとは想像だにしていないわけですよね?
源氏のために立派な元服セレモニーの準備までしてあげて。
なんだか既にせつないですね。(川崎)
「切に隠れたまへど」が、ものすごく重要なことを再認識。
夫以外の男性に姿を見せてはならないのがルール。童形とはいえ、源氏の君に姿 を見せまいとする藤壺。なんとしてもお姿を見たいと、目で追い続ける源氏の 君。見られているのではと、源氏の君を気にして、絡み合うふたりの視線。
うわうわうわー。二人の想いは、こんなにもはっきりと描かれていて、「な疎み たまひそ」と藤壺に語りかける帝がお気の毒に思えてしまう。(ぴ)
原作ちゃんと読まないとわからなかった部分がたくさん出てきた。
まず藤壺の宮、もっと多くの人に望まれて祝福されて普通に幸せいっぱいで入内 したのだと思っていたら、以外に苦労人。
他、藤壺の宮の方の気持ちとか、源氏が好きになった経緯とか、元服式の様子と か、学者の皆さんちゃんと原作読め!と言いたい。
そもそも話全般にかかわる大事な人物藤壺の宮とのなれそめがおおよそでしかわ からなくてそのままずっと読んできちゃったので、今回しっかり読めてよかった。
たぶん次回で最後だけど、次回の内容も非常に楽しみ。
そうしてどうでもいい余談だけど、日出処の天子という聖徳太子を描いた作品 で、王子はある程度大きくなっても髪型はずっと変わらずみづらだった。あれは 何か意味があったのか、当時はそれほど決まりはなかったのか気になる。 (W)
第65回ゆかり雲瞬間感想文(2021.9.4)
紅葉賀の「二条の院の女君」の途中から「典侍の懸想」までを読みました。
・典侍がすごく良いキャラ。今まで2行以上にわたってこんなにほめられた人物はいないと思う。作者はモデルになった女性をすごく好きだったのでは。(W)
・この時代の自由な雰囲気、年齢を超えた自由な恋愛観がとてもよく伝わってきた。典侍は仕事も恋愛もバリバリのパワフルな女性だと思うが感情が激しいのですね。コミカルなシーンが楽しい。(Yang Yang)
・源氏はかなり年配の老女官源典侍と戯れの関係を結んでしまう。年の割にはきれいで家柄も良く頭も良いが、源氏に声をかけられればそれは嬉しかったかも。源氏はあまりにあけすけな様子に引けてしまったところに、頭の中将も真似して付き合い出したというのが一番おかしかった。(YOKO)
・いたう老いたる典侍(50代)が登場。才気・気品があり、評判も良いけれど、色っぽくて恋においては少々軽はずみな人らしい。源氏(10代)は好奇心・いたずら心から、この人にちょっかいを出し、女は源氏にのぼせてしまった。そしてドタバタが起こる。その時、女の気品と才気はどこかへ吹っ飛んだ。この二人は「好き心」があるという点で似たもの同士だと思った。典侍は源氏につれなくされて、つらいと思い、大泣きするのだが、悲壮感はない。全力でやりたいことをしているからだ。式部は喜劇を書くのがとてもうまい。(吾亦紅)
・いじらしい典侍の乙女心を傷つけてしまった源氏。反省すべし。父の帝の思いが語られていたが、息子がかわいくてしかたないのがよくわかる。最後に頭の中将が出てくるのが面白い。(まり)
・女はいくつになっても恋をして輝いていなくちゃ。すてきな服を着て、自分磨きをしていたらほらね、年の差なんて関係ないのよ。貴公子からのアプローチがあるんだから。典侍は自由に恋愛を楽しんでいるけれど努力もしていたんじゃないかなー。だから現役なんだと思うんだ。(ぴ)
・源氏は年若い少女の紫チャンと過ごしている一方で、老女の典侍と関係を持ってしまう。それを聞きつけた頭の中将は、いつもながら、源氏と張り合って、典侍といい仲になってしまう。三角関係? 軽いコミカルな表現が出てきて、又楽しい部分があり、変化があり、いいわ~ (SUZU)
第64回ゆかり雲瞬間感想文
(2021.7.3)
紅葉賀の「対面」の途中から「二条の院の女君」の途中までを読みました。
・源氏の君は、帝が抱いて見せてくれた若宮を見て、どんなにつらかっただろう。藤壺が送ってくれた歌も複雑な心情を感じる。若紫が琴が上手になって、源氏が他の女の人の所に行くのに抵抗する様子に、いつのまにか成長してきたと思った。(YOKO)
・若紫の成長ぶりには驚かされた。今までとても子どもっぽかったのに、歌の言葉を引用したり、琴を弾きこなしたりしている。源氏に対しても、少し拗ねてみたり甘えてみたりと、まだまだ幼くはあるが、一緒にいたいという気持ちをあらわしているところがいじらしい。
藤壺が我が子へ抱いている気持ちがどうなのか、知りたい。(かわらなでしこ)
・思いがけず我が子を見ることができたけれど、我が子を抱いた帝を見て、とても複雑な気持ちになる源氏。いたたまれず退出し、家に引きこもっている源氏が命婦に送った手紙を見た藤壺が、短いとはいえ返事をくれたことに感激する源氏。紫の姫君とのくつろいだひとときと、成長めざましい姫君を見る喜びにひたる源氏。 (まり)
・会いたい気持ちが強かった御子だが、実際に会うと様々な思いがわいてくる。藤壺からの返歌にも複雑になる源氏がなぐさめられるのは紫の上の存在。二人のやりとりの紫の上の可愛らしさが際立つ今回の話でした。(Take)
・もしも若宮が罪の子じゃなかったら…。もしも源氏と藤壺が許されない関係ではなく普通の恋人?夫婦だったら…。だからこそなおさら源氏は紫ちゃんに愛情を注ぎまくったのでしょうか…。(emi)
・紫ちゃん、源氏を行かせたくなくて、ふてくされているのは「くねくねしい」人達と同じではないかと、感じちゃったのではないかと。一方で源氏の君が行かないと決めたとたん、計画通りとにやっと笑ったらちょっとおもしろいと思った。(W)
・藤壺の子どもを見て、帝との面会も気まずく、つらい。うつうつとして家に帰ってきた。そこで紫ちゃんのところに行こうと思う。彼女が少し大人びてきて、一緒に過ごす時間が楽しい。箏を弾く彼女との時間が基調で気分がほぐれてきた。(SUZU)
・「なほ疎まれぬやまとなでしこ」この子のことを嫌いになることはできない、なのか、この子を疎ましく思ってしまうのか。わたしは、この子を疎むことが出来ない方を採った上でこのあとの藤壺さんを読んでいこうと思います。(ぴ)
第63回ゆかり雲瞬間感想文(2021.5.8)
紅葉賀の「皇子誕生」から「対面」の途中までを読みました。
・藤壺は予想されていたより数か月遅れて出産した。生まれた皇子は源氏にうり二つだった。藤壺はすでに母として強くなり、源氏にも会うことはない。帝は源氏に似ている皇子を見て、源氏を臣下に下したことを今さら口惜しく思う。源氏は二人の気持ちをどのくらい理解していたことだろうか。(YOKO)
・月日が経ちすぎと心配されたが、無事に御子誕生。美しい御子が帝に深く思われるにつれ、藤壺の苦しみも深まるが、妃として母としての自覚も生まれる。会いたい気持ちが叶わない源氏。それぞれの気持ちが描かれていた今回の場面、これからどう進展していくのでしょうか?(Take)
・藤壺の宮は自分の犯した罪の重さに苦しみ、命婦は藤壺と源氏の気持ちを思って苦しみ、一方源氏は若さゆえか自分のことしか考えられず、帝はいたって脳天気。男の人って何ですかね。(e)
・「昔=前世」の考えがあるのなら、もう前世から結ばれない運命だったとは考えないものか。もののけと言い、この時代の人は都合の良い事を考え付くのがうまいなと思う。(W)
・源氏、藤壺、帝などの人たちの心情をあらわしている言葉の用い方がにくいほど、新しく発見したように心に沁みてくる。人が人であるってつらいナーと思う。(YOSHI)
・藤壺の心痛を思うといたたまれない。母となった喜びを存分に味わうことなく、帝への裏切りや不義を世間に知られ時の我が身の破滅を思って、押しつぶされそうになっている。藤壺は普通の感覚の持ち主だから。源氏にはたぶん藤壺の気持ちは理解できないと思う。藤壺にはもう幸せは訪れないのだろうな。 (丸葉空木)
・待望の皇子が無事に生まれたことはとても喜ぶべきことなのだが、実の母と父と命婦の心中は複雑。なかでも母の藤壺の心の苦しみと決意はいかばかりか。たぶん何もしらない桐壺帝が皇子誕生を喜ぶ姿にはほっとさせられる。皇子の成長が楽しみである。(まり)
・遠ざけられた王命婦について考えた。生まれた子を、源氏を、帝を守るために藤壺は強い母となることを決意したのかもしれない。もう恋する藤壺ではいられないから、心を鬼にして命婦を遠ざける。(ぴ)
第62回ゆかり雲瞬間感想文(2021.3.6)
紅葉賀の「雛遊び」から「左大臣邸の北の方と舅」までを読みました。
・本日は場面転換が鮮やかだった。雛遊びのシーンはとてもかわいい。10歳すぎても遊びに夢中になって、幼さもあるが彼女にとって大切な時間を過ごしている(子ども時代をじっくり過ごすのは大切!)。北の方との関係は息づまるが、左大臣の様子で気が楽になる。(Yang Yang)
・左大臣が源氏の君を好きすぎておかしい。貢物がすごい。葵の上と足して割ったらちょうどよいのでは。(W)
・源氏の君とめぐる人々との元旦のひとときの描写が面白い。若紫は部屋いっぱいに人形遊びをして、もう少し大人っぽくといわれ、葵の上は相変わらず冷たいが源氏との会話は感情を押し殺してしている。そして一番興味深かったのが左大臣。源氏に高価な帯をプレゼントして、自ら締めてあげようとしたり、本当に源氏が好きなんだなと読んでいて実感した。(YOKO)
・北の方の生い立ちを知ることで、彼女の源氏への対応の仕方が少し理解出来た。左大臣の源氏(娘婿)への気持ち(正装した時のホレボレする美しさ)が、手にとるようでおかしい。今後、藤壺、皇子誕生が楽しみ~(SUZU)
・源氏は葵の上に妻らしく打ち解けてほしいと思う。そしてなぜ自分がそこまで妻にちやほやしなければいけないのかとも思っている。でも葵の上が求めていることはちやほやされることではなくて、源氏の誠意なのだろうと私は思う。葵の上は高貴な生まれなのでプライドが高いが、それだけでなく人間としてのプライドも持っていると、現代に生きる私には思える。(紫式部はどう思って葵の上を描いたのだろうか。) 源氏はそれに対して、その時代の男女間の当たり前(男性中心)を疑いもせずに生きているな~と思う。(ムスカリ)
・紫ちゃんはひたすらかわいく、ゆっくりと成長している。左大臣家の北の方とわずかに距離が縮まっている。藤壺の宮は、どうすることもできないほど遠い。左大臣は源氏にべったり密着して着付けを手伝っている。(ぴ)
・源氏の周りの人々(若紫、少納言、北の方、左大臣、藤壺)と源氏のいろいろな関係性と、それぞれの思いが描かれていた。思いがすれ違っている場合が多いが、藤壺と源氏は相思ながら、言葉をかわすことができないのが一番あわれだった。(まり)
? 玉鬘 第5回 2021.4.3
資料テキスト2巻 (水色表紙) p.7~13
?右近、源氏に玉鬘との邂逅を報告する(7行目から)
?源氏、玉鬘に消息を贈る 玉鬘、歌を返す(最後まで) を勉強しました。
本編学習中の紅葉の賀あたりと比べて源氏の君のおっさん化が悲しい。
しかしおっさんになっても女房達には人気があるんだろう。
この時代、家の作りとか身分のせいで夫婦でも簡単に秘密をもてそうもないのがよくわかる。
自分だったら耐えられん。
そして本人出てないのに末摘花ちゃんが人気。やはり本文の表現も本人もかなりインパクトがつよかったせいか。玉鬘ちゃんの活躍も早く読みたい。
w
右近と源氏で夕顔の話が始まり、紫の上は、自分が居合わせて気まずい思いをさせまいと、冗談ぽく「あなわづらわし。ねぶたきに、聞き入るべくもあらぬものを」と冗談のように言って、耳をふさぐように配慮するのが、素晴らしく、またかわいい。紫の上の人柄がよくわかって、とても身近に感じられて、紫ちゃんをもっと好きになりました~
この辺りの描写は、会話になっていて、それぞれの様子、気持ちがよくわかり、とても面白いです。
suzu
年を重ねる毎に美しさを増す紫の上とのどやかに過ごす源氏のお二人の前に玉鬘の存在が右近により明かされる。
文、贈り物で接近を試みる源氏。
戸惑いながらも文を返す玉鬘。
右近と源氏の和やかなやり取り、紫の上と源氏が並ぶ様子など雅な雰囲気を楽しめた。
太宰府から京に登ってきた玉鬘は運命の糸に導かれる様に源氏と巡り会う。
この出会いが二人と回りの人達にどう影響していくのか。
次回の展開も楽しみです。
Take
源氏の行動、玉鬘ちゃんの気持ちを完全に無視して「父親(頭中将)には知らせなくていい」とか、
紫の上が隣にいるのに玉鬘ちゃんの容姿の話だとか、
末摘花の君にたいそう失礼なこと口走ったりとか、
今だったら炎上しちゃうんじゃないかと思うのですが、これくらいのこと笑って許されるような、
おおらかな時代だったのかな、当時は。
そして源氏はオッサンになってもまだモテてるんですね。。。
恵美
旅から帰り源氏の館に参上した右近は、玉鬘に出会えたことを源氏に伝える。紫の上に誤解されないような配慮も必要らしい。
今回は源氏と紫の上の並ぶさまの描写が華やかで、まるで雛飾りのように想像した。重ねて多くの愛人をも養う源氏の様子に、当時の貴族の生活ぶりも垣間知ることとなった。夫婦関係もなかなか微妙のようで興味はつきない。
光っていたのは玉鬘を思う右近の思慮深さ。源氏と紫の上をよく知り信頼されている右近は、如何にしたら玉鬘を印象よく二人に受け入れてもらえるか、思いめぐらしたようだ。玉鬘について源氏に伝えるときにはすべてをあからさまにすることはしない。少しもどかしいが、昔仕えた夕顔への忠誠心も働いた判断と思える。
夕顔の死をいまも心の疵としてかかえる源氏に、右近は玉鬘の養育を促す。右近の交渉が功を奏して源氏は玉鬘に歌を贈り、玉鬘は源氏に歌を返すことに。返歌は内容、文字ともに玉鬘の品格と教養があらわれたものとなり、受け取った源氏は安堵した様子。玉鬘の幸せを祈るこちらもほっとして、次の展開が楽しみとなった。
(T・U)
玉鬘との邂逅を源氏に話すきっかけをいつにするか作戦を練っていた右近は紫の上も同席の時を見計らって夕顔の遺児の話を始める。夫の愛人の話と悟った女君は「眠い」と言って袖で耳を塞ぐ振りをするが、
当然聞こえてますよね。 このやり取りが可愛らしい。
源氏は自分のところに来るようにと玉鬘に歌付きの手紙を装束など贈り物とともに届けた。
末摘花のように歌が下手だったらという心配は杞憂で、しっかりとした返歌も届いた。
いよいよ玉鬘は源氏に会うのですね。
YOKO
伊勢物語 感想文 2022.8.20
第4回 ⑯紀の有常 ?おのが世々 ?筒井筒 ?梓弓
第1部(オレンジ表紙)は今回で終了します。
◆筒井筒、高校の教科書でやったけど絶対に後半はなかったはず。
こんなおもしろい内容だったら忘れるはずがない。飯匙最高。
そして男は女性に色々夢見すぎ。筒井筒の彼女にはもったいない。しかしダメ男
が好きな女は昔からいる。筒井筒の彼女もそういう系統か。
W
◆これまでの旅の話はどこへやら。以後は男女の心模様を中心に展開される。
第16段「紀の有常」の主人公は業平の妻の父、その晩年がつづられる。時代の波に乗れず家は零落、それでも悠然と暮らしを変えることもなく、妻はやがて出家する。当時はそのような女性の選択が多かったのだろうか。貧しくて妻に支度をしてやれない有常。友(業平らしい)に歌で事情を伝え、友は夜具などを贈る。その温情に、有常は再び歌で喜びを送るのである。男女間に限らず同性同士でも歌を送ることが大事なコミュニケーションになっていることに感心する。
第21段「おのが世々」はある夫婦の話。相思相愛のはずがちょっとした心の隙から別れたり元に戻ったり、いずれ別離を迎える。男女が今よりも対等である時代の証だろうか、歌の内容が誰に臆することなく展開しているのが面白かった。
第23段「筒井筒」は幼馴染だった男女が無事結婚するが、女の家が没落し、男は別の女のもとに通うようになる。それを知っても女は怒るでもなく、かえってその様子を男は疑うが、やがて女の優しさに気づき戻ってくる。このとき別の女に男が愛想をつかす理由がなかなか。別の女が手づからご飯をよそったからだという。現代なら愛情がこもっていい、と思うが、当時の身分の高い層では許されることではなく、これにはびっくり。
そして第24段「梓弓」。野心のある男が出て行って3年もの間音沙汰ない。諦めた女が再婚を決めた日のこと、男が戻ってくるのだ。女は戸をあけず再婚を打ち明ける歌を送る。男は新しい夫と仲良くするよう歌を返して去る。悲しく思う女は男のあとを追うのだが追いつかない。自身の指の血で岩に歌を書いて死んでしまう。心はまだあるのに、結末が悲しい。
どの時代にも、またどこの国にでもありそうな男女の物語であると感じた。
(T・U)
◆業平の旅は終わってしまったようで、今回は様々な男女の在り様を歌とともに綴っている。
一番気になっていたのは第23段筒井筒。能楽の曲としても有名だが、木原敏江の漫画「伊勢物語」でも取り上げられていて確かに読んだことがあった。
井戸の周りで遊んでいた男の子と女の子が成長してお互いを好きで結婚する。二人は貧しかったのか、男は生活のため河内、高安の裕福な女の家に通うようになった。
もとの女が不愉快そうな様子を見せないので、もしや他の男でもいるのかと高安に出かけたふりをして家の前の茂みに隠れていると女は綺麗に化粧をしているではないか。てっきり男を待っているのかと思ったら、「風吹けば沖つしら浪たつた山 夜半にや君がひとりこゆらむ」と男が夜中にひとりで出かけて暗い山道を越えていくのを心配している様子だった。いとしいと、思わず茂みから飛び出し、高安には行かずに過ごしてしまった。
それでも高安にたまには行っていたが、だんだん本性を出してきた女が手ずからにご飯を盛って食べているのにはげんなりとしてしまい、もうこの女のもとには来るのをやめたという話であった。
木原敏江の漫画も最初は都会人に描かれていた女ががつがつと食べる様子が描かれていて笑ってしまった。
現代の主婦はお手伝いのいる家なんていないのだから、自分でご飯を盛るものだし、そんなことで失望していては家庭生活が成り立たないが、貧しくてもきっちりと美しくしていて自分を気にかけていてくれているような人が一番良いということなのだと言いたいのか
東下り前半「かきつばた」で、言葉巧みに妻への心情を和歌に詠んだにも関わらず、更に東への旅では、その土地土地の女性と関係を持つ業平。
呆れたことに、京の女性に武蔵にも好きな女性が出来たと便りを出す。
「くたかけ」では、一夜を共にした女性のあまりにも田舎地味た人柄と歌に昔男は呆れかえってしまう。
高貴な生まれの業平が、京の女性との余りの違いにショックを受けたこの段は、とても可笑しい!
それにしても、高子さんの件で傷心の筈が、何のための東下りなのか。センチメンタルジャーニーではないようです😁 うさ子
◆とうとう東北へ。そろそろ旅は終わりかな。いろんな地名が出てきて興味深かった。
たぶん興味持って研究してる人もいそうなので、本を探してみる予定。
男は女性の扱いがだんだんひどくなってくる。モテ男ならもうちょっといいところ見せて欲しい。
個人的にはくたかけの女性が面白くて好き。
W
◆第9段「東下り」の続きは、駿河の宇津の山から。一行が暗い峠道で出会ったのは見知った修行者、すると都の思い人宛てに歌を託す主人公。なかなか未練はたちきれないものと変に感心する。いや、余計に思いは募っているのかもしれない。
さて一行は残雪の富士の雄姿を目にして、次はすみだ河へ。初めて目にした鳥の名を渡守に教えられ、その都鳥を題材に詠った歌は、都にいる人の無事を思う歌。当時の旅の心細さ、郷愁の念があふれている。船に乗り合わせた人全員が涙したとあり、かきつばたの歌と並ぶ業平の代表歌だ。
続く10段「たのむの雁」、11段「空ゆく月」、12段「盗人」、13段「武蔵鐙」、14段「くたかけ」、15段「しのぶ山」は、東国での物語。恋のやり取りがメインの、歌とショートストーリーが展開される。と共に、10段の引板、13段の鐙とさすが、のような生活道具が登場すると興味が湧く。また 14段の‘くたかけ’は鶏をののしっていう言葉とか。辞書では後に雅語に転じるとある。みちのくの女性たちは性格もそれぞれで、おもしろくも一方で哀れさも感じる内容だった。
宇津ノ谷峠は東海道の取材で通ったことがある。単独取材で小暗い山道を歩くのは気持ちの良いものではなく、どうしても小走りにならざるを得なかったことを思い出す。周辺は茶畑が広がる。平安時代は茶畑などなく、かなり鬱蒼と木々が生い茂っていたことだろう。
(T・U)
◆伊勢物語の特に有名な「東下り」だが、さらに有名な
「名にしおはば いざ言問はむ みやこどり わが思う人は ありやなしやと」
の歌にたどり着き、それだけで満足してしまった。
渡守が「これなむ都鳥」と答えたので、ユリカモメは業平達によって都鳥にされてしまい、そのため、今でも都民の鳥であり、かつての都立大のバッジもユリカモメだった。
都の貴族在原業平が本当に関東に来たのだという実感が湧いてくる。
業平一行はさらに今の埼玉県や東北地方まで行っているのだから、行動力が凄いとしか言いようがない。 YOKO
玉鬘感想文
玉鬘 第4回 2021.2.6
資料テキスト2巻 (水色表紙) p.1?7
?翌日、右近と乳母、玉鬘の将来を相談する
?右近と玉鬘、歌を詠み交わし、帰京する
?右近、源氏に玉鬘との邂逅を報告する(途中まで。6行目) を勉強しました。
◇やっと玉鬘本人の人となりがわかるようになってきた。
人気があるのがわかる人柄がうかがえる。
そしてあんなに弱々だった右近が強くなったな~と実感。やっぱり年取るとみん なたくましくなるのか。
おかげでうまく源氏に引き合わせることができるだろう。
W
◇玉鬘がやっと登場してきた。今まではおとなしくしていたのでわからなかったが、実は相当芯がしっかりとしているのでは?母と突然別れ都も離れ大宰府にいる間に、学問や歌に励んでいて、知的な女性に育ったようだ。しかも、最上級の美しさというから、すごい!
これからが楽しみです。
(愛読者)
◇念願叶って玉鬘と再会することができた右近の喜びはどれ程大きかったことか。
姫の褒められて恥ずかしそうに背後を向く初々しい様、筑紫の人々と右近が日一日語らう和やかな様子が伝わってきました。
筑紫の人々、右近、それぞれの思いが今後の玉鬘にどう影響するのか?
源氏との再会など展開が楽しみです。
右近と玉鬘の歌に詠まれていた初瀬川。右近の歌のふたもとの杉。
長谷寺へ行きたい思いもつのります。
take
◇印象深かった点は2つあります。
まず、玉鬘の人となりがわかってきたこと。
昨年参加した第2回では美しい姫君だということのみでしたが、今回は気高く立ち居振る舞いは立派、教養も身についた才色兼備であることが描かれています。
京の都をはるか離れていながら、幼い姫君を育てて教養まで身に着けさせた乳母の手腕は称賛もの。右近に労いのことばをかけられ、家族崩壊させてまで姫君に忠義を尽くしている乳母はどんなに安堵したことかと想像します。
2つめは、姫君が父君にすぐ会えないという不思議。
乳母と玉鬘、右近は、長谷寺の観音さまの導きがあったのでしょう、偶然にも再会が果せました。乳母と右近の相談事は、玉鬘とその父・内大臣との邂逅。すぐに会えて大団円、といきたいところですが、夕顔の死とからみ複雑な事情が妨げになるらしい。なんとももどかしく、またそれが物語をおもしろくするものなのでしょう。
物語は右近のはからいで姫君が源氏に会うことになるようで、玉鬘の運命の行方が楽しみです。
ことばで面白かったのは「ありがたう」。漢字にすると「有難う」、つまり「有るが難し、ふつうにはあり得ない」というのが元の意味だとのこと。そこから現代の私達が使う、いわゆる「ありがとう」となると教えていただき、改めて「ありがとう」のことばをかみしめた次第です。
ことばの発見もさせていただいて、良い午後の時間となりました。田中先生、皆さま、ありがとうございました。
(T・U)
◇それが答えかも!
(長文ご容赦ください)
当日の講義の終わりに、母・夕顔の話題になりました。
源氏は夕顔に魅了され、彼女を現実(生活感溢れる五条の家)から、夢(某の院で二人きり)の世界へと連れ出し、そこで彼女を失います。
源氏とわたしたち読み手は、夢の世界で夕顔を見失いました。一方、五条の家では、リアルな生活の世界で主人を失ったことを忘れがちです。
残された五条の人々は、小さな姫君を誰かに託して、解散することもできたはず。筑紫へ下っても、お姫様として大切に育てるし、成長しては、有力者の田舎侍の求婚から逃れて、京へ戻るほどの無茶もする。母夕顔からどれほどの資産を預かっていたかはわからないけれど、潤沢だったとは思えない。
なのにどうしてそこまで大事にされる?
源氏や、読み手の知らない夕顔、現実に生きる女性としての夕顔の人柄が、五条の人々にとって、尊敬に足るものであったから、ではないかな。
亡き夕顔が、なよなよと可愛らしいだけの女性ではなかったってことが、玉鬘の成長によって、はっきりと語られている気がします。
ぴ
◇玉鬘は、今回初めて参加させていただきましたが、すんなりと物語に、入ることができました。
右近と玉鬘で歌を詠み交わす。
末摘花が、源氏への返歌ができず、「むむ……」と言っていた時の事を思い出しました。大違いですね。
玉鬘の教養と見た目の美しさと揃っているので、今後が楽しみです。
(suzu)
◇右近と玉鬘そして亡くなった夕顔のイメージが右近と乳母との会話や右近と玉鬘の歌の詠み交わしで明らかになってきた。
右近は夕顔が亡くなった時は泣いてばかりの小娘だったが、すでに40歳位になっていて、しっかりとした
女性になっている。源氏にセクハラめいたことを言われても適当にあしらって、計算高いというか状況を把握できる人物になっている。
夕顔は若くして亡くなってしまったが、若々しくおっとりとした性格で、源氏が魅了されていただけでなく、乳母や右近も決して忘れることができない素晴らしい女性だった。
また玉鬘は母の夕顔以上に美しく賢く、歌も詠える教養のある娘に育っている。
乳母は玉鬘の実の父(内大臣、かつての頭中将)に会わせることを熱望しているが、右近には別の考えがあるようで、今後の展開が興味深い。
YOKO
第61回ゆかり雲瞬間感想文(2021.1.9)
紅葉賀の「北の方とおさなき人と」「三条の宮にて」を読みました。
・源氏の里帰りした藤壺への恋慕の情と、手元に置いている若紫をいとしく思って気遣いもしている様と、それでも他の女の人たちの所へ夜には通う、源氏の気の多さには感心する。何と言っても藤壺の心の葛藤を見ると、今日の登場人物の中では一番かわいそう。(まり)
・源氏は紫ちゃんといるときは、手習いを教えたり遊んだり、父親のような気分になってとても楽しいけど、藤壺への気持ちはいつもあり逢いたい気持ちは高まり続けている。(SUZU)
・源氏は実家に戻っている藤壺に会いに行ったが、会うことはできず、代わりに藤壺の兄で、若紫の父である兵部卿の宮と会って世間話をしたが、お互いに女だったら世話をしたいなあと思い合うというエピソードが一番興味深かった。美男子同士でこれは絵になる場面です。((YOKO)
・北の方への源氏の思いと、若紫への思いとの対比が鮮やか。兵部卿との「御物語など聞こえたまふ」シーンは平安朝の自由な感性が伝わってくる。藤壺に直接会うことができない源氏と藤壺のこれからも気になる。(Yang Yang)
・出産を控えて三条の宮に里帰りした藤壺を訪ねて行った源氏は「けざやかに」もてなされる。兵部卿は御簾の内に入りたまふが源氏は入れない。「こよなう」疎まれるのがつらいと源氏は思う。そんな源氏を慰めるかのように語り手がつぶやく部分、「わりなきや」「はかなの契りやとおぼしみだるることかたみに(互いに)尽きせず」が良かった! (水仙花)
・この短い間でも正妻、藤壺の宮、紫の上に加えて、兵部卿の宮まで源氏の相手として登場。源氏の君おさかんすぎる。(W)
・源氏の心の移ろいをこのような表現であらわす、あらわしている作者が何とも言えずすごすぎて、ボーゼンとします。登場人物の気持ちを考えたり、触れようとするのが楽しいです。(YOSHI)
・藤壺の兄であり、紫の姫君の父である兵部卿の宮が特別に親しいものに思えて語らう源氏の雰囲気になんだかちょっと色めいたものを感じて「女にして見ばや」と思う宮。二人して同じことを考えているあたりがよくわからないけれどおもしろいところでした。あっそうそう、「さもあるまじきすさびごと」が出で来るのを人のせいにしているところは気にいらないけれどね。(ぴ)
第60回ゆかり雲
桐壺特別講座の感想文(2020・12・5)
桐壺帝が、弘徽殿の産んだ一の皇子を差し置いて、更衣腹の御子を春宮にするの ではないかと噂する人びとの描写が面白かったー。皇室ゴシップは、この頃から 一般ぴーぷるの好物だったのね。
原文で読んでいるからこそ、こういう些細な文章の面白さがストレートに伝わっ てきます。
千年後の日の本の国でも、「女性天皇を認めて天皇の直子を」とか、「内親王の 結婚相手として相応しい家柄がー!」なんて外野がやいのやいの騒いでいるんで すよ、って紫式部せんせいに報告したいわぁ。(ぴ)
帝は更衣が亡くなって涙に暮れてばかりと思っていたが、更衣の母も亡くなって からは、若君のことをどうしたらいいのか、よく考えるようになった。
自分の考えを確認するために渤海の人相見に若君を会わせて、下した決断は源氏 の姓を与えて臣下として実力で生きさせることだった。
若君が賢くて、目立っては皇太子のライバルとして、危険視され抹殺される可能 性もあるし、母の実家がなく、帝だけでは守ることかできないと判断した。
桐壺の帝は若君を可愛がるだけでなく、現実的で合理的な人でした。(大塚 洋子)
dokusho7_1
初めてゆかり雲に参加して原文で桐壺を読んだのはもう8年も前だそうだ!!時の 流れの早さにびっくりだ
誰もが思わず引き付けられる源氏の愛らしさととは、いったいどれほどのもの か、見てみたいが全く想像できない。さらにひと目でわかる、とてつもないオー ラを漂わせているようだ。親としては、その子の将来が心配になるのは当然だ。
高麗人の相人が気になる。以前、飛行機の中で「観相師」という韓国映画を観た ことがある。韓国人達は人相や占いが大好きのようで、時代劇はもちろん現代の ドラマでも占いの巫女が出てくる。もちろん、源氏を観た相人は、ライバルを 呪ったり、受験や就職を占ったりする者達とはランクが違う、本当に見える能力 があるのだろう。そんな相人が驚いた源氏のただ者ではない感、やはり想像もつ かない (坂本)
月日が経とうとも深い悲しみから抜け出せない帝と祖母も亡くし安らげる里を 失った若君。辛い境遇の二人の内裏での暮らしが始まる。美しく才能溢れ、ゆゆ しうおぼしたりと不安を感じると同時に誰もが虜になるほど愛くるしい若君。そ んな我が子の将来を案じ春宮にはせず高麗の人相見の見解を聞く等して源氏にな したてまつる事を決断した帝。生まれながらにして優れている上、内裏という上 流社会で育つ若君。光源氏がスーパースターになるわけだ?と、うっとりとして しまう反面、その社会の中で生きていくための努力や気苦労があったことを垣間 見ることができた。
今回は光源氏という人を知る上で重要な章だったのではと感じた。今後が楽しみ だと思わずにはいられない。(take)
第63回ゆかり雲瞬間感想文(2021.5.8)
紅葉賀の「皇子誕生」から「対面」の途中までを読みました。
・藤壺は予想されていたより数か月遅れて出産した。生まれた皇子は源氏にうり二つだった。藤壺はすでに母として強くなり、源氏にも会うことはない。帝は源氏に似ている皇子を見て、源氏を臣下に下したことを今さら口惜しく思う。源氏は二人の気持ちをどのくらい理解していたことだろうか。(YOKO)
・月日が経ちすぎと心配されたが、無事に御子誕生。美しい御子が帝に深く思われるにつれ、藤壺の苦しみも深まるが、妃として母としての自覚も生まれる。会いたい気持ちが叶わない源氏。それぞれの気持ちが描かれていた今回の場面、これからどう進展していくのでしょうか?(Take)
・藤壺の宮は自分の犯した罪の重さに苦しみ、命婦は藤壺と源氏の気持ちを思って苦しみ、一方源氏は若さゆえか自分のことしか考えられず、帝はいたって脳天気。男の人って何ですかね。(e)
・「昔=前世」の考えがあるのなら、もう前世から結ばれない運命だったとは考えないものか。もののけと言い、この時代の人は都合の良い事を考え付くのがうまいなと思う。(W)
・源氏、藤壺、帝などの人たちの心情をあらわしている言葉の用い方がにくいほど、新しく発見したように心に沁みてくる。人が人であるってつらいナーと思う。(YOSHI)
・藤壺の心痛を思うといたたまれない。母となった喜びを存分に味わうことなく、帝への裏切りや不義を世間に知られ時の我が身の破滅を思って、押しつぶされそうになっている。藤壺は普通の感覚の持ち主だから。源氏にはたぶん藤壺の気持ちは理解できないと思う。藤壺にはもう幸せは訪れないのだろうな。 (丸葉空木)
・待望の皇子が無事に生まれたことはとても喜ぶべきことなのだが、実の母と父と命婦の心中は複雑。なかでも母の藤壺の心の苦しみと決意はいかばかりか。たぶん何もしらない桐壺帝が皇子誕生を喜ぶ姿にはほっとさせられる。皇子の成長が楽しみである。(まり)
・遠ざけられた王命婦について考えた。生まれた子を、源氏を、帝を守るために藤壺は強い母となることを決意したのかもしれない。もう恋する藤壺ではいられないから、心を鬼にして命婦を遠ざける。(ぴ)
更衣が亡くなって抜け殻になってしまった桐壺帝。
いじめっこ弘徽殿の女御さえ虜にしてしまうおそろしい子(月影千草風)、リト ル源氏。
そして我が子が自立して生きられるよう決断するパパ帝。
占い師まで登場するし、私的には韓流ドラマのように濃厚なストーリーでした。 (川崎)
やっと源氏出てきましたが、最初からスーパーチートぶりを発揮してますね。
まさか弘徽殿さんまで篭絡しているとは!
実写でやると子供時代ほぼ出てこないのは納得。特殊効果でもつけないとこんな キラキラした男児は表現できないだろう。(W)
瞬間感想文(2020.11.14)
紅葉賀の試楽から行幸までを読みました。
・朱雀院の行幸の試楽で青海波を頭の中将と舞った源氏の君は、見ていてくれたであろう藤壺に歌を送ったら、まさかの返歌をもらい、お経を読むように広げて読んだという。その喜びに満ち溢れている様子がかわいらしく思えた。本番の素晴らしさはこの世のものとは思えなかっただろう。青海波、一度実物を見てみたいものだ。(YOKO)
・源氏の青海波の舞いに皆が酔いしれている様子、風景描写もすばらしく、私もその場にいるような気分を味わえてうれしい。源氏の君、藤壺からの返歌があってよかったね~ (SUZU)
・平安時代の雅な儀式が目に映るようです。紅葉や冬の訪れを想像させる菊の花も登場させ、源氏と藤壺の今後の展開も冬模様に連なるのかと思わせます。
(うさ子)
・宮中の人たちが舞いなどの練習にいそしんでいる様子には、その真面目さに驚かされた。帝の誠実な統率力に因るものだろう。みんな昇進して今日のところはメデタシメデタシで終わり(まり)
・紅葉賀の楽の船、大勢の垣代と壮大な舞台と、散りかふ紅葉と松風の風景の優雅さを想い圧倒されました。
・他の上達部を昇進させてしまうほどの美しさってどれほどのものなのか…。まったく想像できないです。それにしても源氏は藤壺の苦しみをわかっているのでしょうか。(e)
・紅葉の美しい季節の行事、青海波を舞う光の君の姿、秋の夕刻の光景などが目に浮かぶ描写を楽しめました。いつの世も美しい事は罪? 山の木の葉にうずもれたる者にはわからない気持ちです。(Take)
・春宮の女御、すっかり悪役だけれどああいう事を言ってしまう気持ちは少しわかる。そして頭の中将がんばれ!(W)
・「玉鬘」のあと久しぶりに前に戻り読んだ「紅葉賀」。最上級の位の方達の優雅なお話、非常に格調高い文章、これぞ源氏物語ですね。「源氏」を映像化すると必ず出てくる「青海波」の場面、美青年二人が美しい衣装で舞う絵になる場面、藤壺でさえうっとりする源氏の美しさ。ここまで美・愛・幸にあふれた場面が描かれるとやはりこのあとに何か不幸が待っているのかも?と思わずにはいられない、ゆゆしと感じてしまいます。(千年後の読者)
・源氏物語に歌が挿入されている意味。それは身分の違う男女の間でも歌によってならば心からの想いを明かすことができるのだと教わりました。今回の場面で、藤壺が源氏に返した歌は源氏の舞を心から称賛しているものの、表向きは平静を装った歌でした(と私は思います)。そのような歌にもかかわらず源氏は歌をもらえたことに喜び狂っています。ここに源氏の藤壺へのままならぬ想い、苦しい想いが語りつくされていると思いました。(柚香菊)
・藤壺の「夢のここち」
源氏が自分を思っていろいろ言ってくることを疎ましいと思う気持ちがありながら、源氏の舞う姿から目が離せなかった自分。そして今、おなかの中にいる罪の子…。彼女にとっての「現実」って何だろうね。(ぴ)
?玉鬘感想文
玉鬘 第 3 回 2020.10.31
資料テキスト 1 巻 p.19?26 ?玉鬘ら長谷寺に参詣し、右近に再会する(途中から) ?右近、三条、御堂で玉鬘の将来を祈願(途中まで) を勉強しました。 ◇豊後介
、ものすごい頑張ったのに姫さんと会えたのすぐ報告されなくて不憫 今後報われればいいのだけど これから玉鬘の気持ちいいとかもっと出てくるといいな、と思ってさらに今後に期待 W
◇玉鬘ちゃん運命の瞬間でした! しかし、右近のことを聞かされたときの豊後介の様子は描かれていないんですね。苦労して姫を京都に連 れ帰ったのだから、それは複雑?な思いを抱いたのではないかな、と思うのですが… それよりも食べるのに夢中で呼ばれても気づかなかったり、京と太宰府を同列に扱っちゃう三条のキャラ 勝ちってことでしょうか笑 川崎
◇苦行の様な長距離歩行の末、たどり着いた宿での一夜の出来事。 夕顔亡き後は源氏に仕えてきた右近。 京から築紫へと生活の場を変えたおとど(乳母)一家。 かつて同じ主人に仕えた二組の異人なる乳母一家の人々が同じ年月を違う環境で過ごしてきた後に再 会を果たす。 お互いに玉鬘の幸せを願う気持ちは同じでも京で大殿に仕えていた右近と築紫で暮らしていたおとど一 家では全く感覚が違うという描写に苦笑。 今回も「田舎びたる」「ふとりにけり」「食物に心いれて」「わが齢もいとどおぼえて恥づかしけれど」等の楽 しい表現が満載でした。 Take
◇親に会いたい一心の若君の述懐がなんとも切なくもの悲しい。二度目の徒歩旅行、しかも今回は長距 離ということで「いかなる罪深き身」との弱音となったのか。 帰京しとりあえず神仏祈願の石清水八幡宮次いで長谷寺詣でを当然のこととさらさら読み進めると突然ド ラマのような再会、という展開に当時の読者も吃驚、頁をめくる手を早めたことだろうと思った。 きっと当時の読者は若君も右近もやはりガチの徒歩での神仏祈願、特に右近は頻繁な長谷寺詣での甲 斐あっての再会と納得したことと思う。 煩悩の法師の描写は実際に当時ありえた話なのか、作者の全くの創作なのかどちらなのだろうか。 「徒歩より歩み堪へがたくて寄り臥したる」にも拘わらず探偵さながらな右近の観察力あってこその再会場 面は、「食ひ物に心入れてとみにも来ぬ」三条のおかしさ、「いといたう太」った三条を見て「わが齢もいと どおぼえて恥づかし」い右近の 相手を見て自分も年をとったことを実感するさま、久々に再会してその年月を瞬時に埋めるかの如く矢継 ぎ早に尋ね合うさまなどが再会の場面を面白くしていて、何度も読み返したい場面だ。 「三日籠らむと心ざしたまふ」筑紫人に合わせて一緒に籠もる右近の平安女子会はさぞや楽しかったこと だろうと嬉しく思った。 それぞれの台詞の部分はそれこそドラマの脚本を読んでいるようで興味深かった。 中田
◇展開が早い。文章もわかりやすい。当時のお寺参りの様子が、生き生きと描かれているのが、 おもしろい。宿の相部屋のシステムとか、持ち運び式のおまるとか、いろいろ興味深い。そんな なか、まだほとんど登場しない姫に早くお目にかかりたいものです。じらしますね。 千年後の読者
◇なんか脇道に逸れてしまうけど、俗物な坊主が気になってしかたない。 今回、宿の坊さんは、あからさまに売上重視で、料金をはずんでくれそうなお客を選り好みして 泊めようとしていた。 ?お金に執着しちゃダメでしょ! 長谷寺の僧は、右近の願いが叶ったのは自分の祈りが効いたからだという。 ?みほとけの功徳じゃないんかい!あわよくばお布施アップ狙ってる? みほとけに近いところにいるはずの僧侶がこれでいいのかしら?と、式部さんは批判を込めて書 いているのかも。 古今東西、俗物な聖職者は珍しいものではないようで… ぴ
◇京都から奈良の長谷寺まで、72km 歩き通した御利益か、玉鬘一行は右近一行と遭遇することが出来 た。普段からほとんど歩いたことがなかった玉鬘は足の裏がまめだらけ。 宿坊に泊まる時は、豊後介は姫君に折敷という粗末なお盆に載せた食事を自ら運ぶほど気を遣ってい る。若者だった豊後介も右近から見ると太って、色黒くやつれてしまったと、厳しい目で、描写されてしま う。 右近自身も 30 代だろうし、長い時が経ってしまったが、偶然同じ宿坊に泊まり、年は取ってもお互いが分 かってラッキーな再会だった。 奈良の長谷寺は行ったことがなかったが、僧たちのお経をあげる声が響き、参詣する人の熱気が溢れて いる様子がリアルで、ぜひ一度行ってみたいと思った。 YOKO
玉鬘 第2回 2020.10.17
資料テキスト1巻 p10からp19.1行目
(4)肥後の土豪大夫監、玉鬘に求婚する (途中から)
(5)玉鬘の一行、筑紫を脱出して都に帰る
(6)玉蔓ら窮迫し、石清水八幡宮に参詣する
(7)玉蔓ら長谷寺に参詣し、右近に再会する(途中まで) を勉強しました。
◇九州からの夜逃げ?脱出?ハラハラドキドキでした。千年後に読んでもドキドキさせる式部の筆力! 次回は涙と感動の再会でしょうか。次回が楽しみです。
式部が、最初に全体構成を考えてから書き始めたのか?という話が出ましたが、ストーリーや系図、相関図、年表など作り(作るだけでも、ものすごいことだが)確認しながら書き進めたのではなく、天才はそういうことは無意識に頭の中にあり、筆のおもむくまま気分のままに書けるのだろうと思った。
千年後の読者
◇まず、最初に田中先生が気持ちを込めて抑揚つけて読んで下さるのが素敵です。古語の魅力的な文章に触れるとともに、先生がどんなイメージになるかヒントを伝えて下さってるかのようです。
そして一文一文に意味や内容を持つこの文学に興味をそそられていきます。 yoshi
◇主役の姫がやっと登場したけど、あまり出番なし。
豊後介のほうがよっぽど出張ってる。考えたら豊後介は母親が 乳母だったというだけで、本人は姫の実家から給料を もらっているわけではないのにすごい尽くしてくれていると思う。
妻子置いてきてるのに従者に逃げられるし。今後ぜひ報われてほしい。 W
◇強引な監から逃れるために旅立つくだりが急展開でしたが監には自慢気に和歌を詠む様子や「おい、然り、然り」の返答など十分に楽しませていただきました。でもこの求婚が原因で乳母一家が別れ、行く先悲しきこと多かり京での生活を余儀なくされ、玉鬘も経験したことのない過酷な船旅、長谷寺詣での長距離の徒歩等を強いられる事になるのですがよく耐えて頑張っていました。また続きが楽しみです。今回も船旅の描写が実在の地名で描かれていて地図もない時代によくここまで正確に書けるものなのか感嘆しきりです。 take
◇大夫の監の描かれ方が面白い。
おらが村では並ぶものがない、無骨な田舎者のおっさんが、「都のモンにゃ負けねぇ!」って息巻いて、 都風を気取るも、付け焼き刃で底は浅い。いざとなったら武力行使で、なんでも意のまま。ゴテゴテ飾り立てた趣味の悪い(本人はご満悦)屋敷に住んでいそう。
これっぽっちも魅力的ではないのに、なぜだろう、紫式部のまなざしは温かく感じた。
「世の大多数の男性はそんなもんよ、いるでしょ、あなたの側にも」とでも言われてるみたい。
はいそうです、光の君のような男性は、リアルに遭遇することなんて超低確率の激レアキャラなんです、わかってます、ごめんなさい。
…玉鬘十帖の、大変興味深いプロローグでした。 ぴ
◇姫君をめぐる大夫監と乳母とのことばの応酬にはハラハラ。乳母の心臓の鼓動が聞こえる思い。それに続く姫君一行の京への船の逃亡劇にはドキドキ。ひと月もの間、追手や海賊の脅威にさらされるのです。ワクワクのスペクタクルでした。
気になるのは乳母の家族。筑紫に留まった者、船で同行した者、一家離散の状況です。いつか彼らが報われるときが来るのでしょうか。また、無事に京へ戻った一行に苦難はまだ続きそうで、今後に目が離せません。
作者は九州に足を踏み入れてはいないとのこと。知らぬ土地、往復の旅模様を描くのは容易なことではなく、それなりの情報源が必要とされます。書物で知ったのか、情報先となる人物に会ったのか、いずれにしても式部は取材力に長けた人なのだろうと推測しました。
田中先生の読まれる朗朗たる声が響きます。テキストを眺めていただけではわからなかった物語が、しっかり伝わってくるのには驚きました。これは音楽にも通じる体験かもしれません。「古語はそれぞれが生々しくイメージの湧くことば」とのお話には納得の思い。千年の時を超えて遊んだ幸せな4時間でした。
(T・U)
◇登場人物の特徴や対比が面白く描かれていると感じた。
まんまと大夫監の口車に乗せられたか、いかにも現代風な自分勝手で都合のいい解釈をしてしまう二郎と三郎。(p8のおのおのわが身のよるべと頼まむにいと頼もしき人なり。から、せぬことどもしてん、まで)
対して長男豊後介の「故少弐ののたまひしこともあり。とかく構へて京に上げたてまつりてむ」と父の遺言を守ろうとする古風な男との対比のおもしろさ。(長男と次男でこうも違うのかとの母の嘆きが聞こえそう)
大夫監の「手などきたなげなう書きて、唐の色紙かうばしき香に入れしめつつ、をかしく書きたりと思ひたる、言葉ぞいとたみたりける(p9)」の良く頑張った!けどいかんともしがたい方言のおもしろさもさりながら、
大夫監と祖母おとどのやり取りの段、とにかくこの娘が欲しいと「私の君と思ひ申して、頂になむ捧げたてまつるべき。」「天下に目つぶれ、足折れたまへりとも、なにがしは仕うまつりてやめてむ。」などと必死に説得をしつつも相手が承諾していないのに「その日ばかりと言ふ」厚かましさ。
だのに下りて行く際に、歌詠みほしかりと頑張る大夫監のおかしな歌を自画自賛する痛さ。
乳母の歌に「まてや、こはいかに仰せらるる」と言ってのけ、その時の乳母や娘達の凍りついた表情が目に浮かぶも、母親をほけほけしき人呼ばわりする賢い娘の機転が際立つ。
大夫監の「をかしき御口つきかな」と乳母の歌を誉めるも返歌できず、「たへずやありけむ、往ぬめり」の面白くも哀れで悲しい田舎人。
田舎の武人だが、 大夫監という役職にあり都人と同等たらんとするも空回りしていて相手にされない悲哀が感じられる。
一方で、やっとの思いで逃げ切ったものの「従ひ来たりし者どもも、類にふれて逃げ去り、本の国に帰り散りぬ」ると大変な状況なのに、「何か。この身はいとやすくはべり。」から、「何心地かせまし」と強い信念の長男、豊後介の天晴れさが格別の光を見せる。是非とも長男としては父の遺志を継いでやり遂げてもらいたいものと感じた。
今回からの参加なので、これまでの巻での源氏と女性達のお話と比べて、別世界のような田舎での緊迫しつつも笑える場面展開に歴代の(?)読者も面白く読んだのではないかと想像しました。
以上長々と雑文失礼しました。 中田
◇今回また舞台が九州から京都へと変わり、玉鬘ちゃんも物理的にはお父さんに近づいてきましたが、一体いつどうやって巡り会えるのでしょうか…
気になります! 川崎
◇玉鬘は強力に求婚してくる大夫監を選ばず、乳母の一家を巻き込んで京都に戻ることになった。
興味深いのが監はドラエもんでいうジャイアンそっくりで強引で自分勝手、乳母の息子の二郎、三郎はスネ夫のように有力者に弱いタイプ、乳母の長男の豊後介はのび太のように本当はたいして強くもないのに玉蔓を守ろうと先頭だって船の手配をした。
乳母の娘の一人は家族を思って九州に残り、一人は夫と別れてまで玉蔓に従い、落ち着いてくると豊後介も置いてきた妻子が気になって仕方ない。
また、乳母も京都での生活が不安になってくるという現実的な描写は漫画的ではない。
この不安を打破するために豊後介の一言で石清水八幡宮や長谷寺を参拝することになるのだが、目立たなかった玉鬘が頑張って歩き抜いたという姿はしずかちゃんのようで清々しかった。
この続きが楽しみである。 YOKO
瞬間感想文(2020.10.3)
末摘花を最後まで読みました。
・末摘花の姫君、少し成長して返歌で「さへづる春は」と言えて良かった(ほっとしました)。でも源氏は自宅にもどり紫ちゃんと絵を描いたりして遊び、彼女の美しさに感動してしまう。やはり美しいもの、かわいいものにひかれる人間の本性を感じます。(SUZU)
・「末摘花」読了。他の巻にも増して原文で読むことで、驚きや面白さを感じた。現代語訳や漫画にはどうしても作家の感想が入る。じかに紫式部の文章に触れることができる幸運に感謝!
「むむ」しか言えなかった姫が、歌を絡めて源氏と会話できるようになった驚きとか、それでも天然の美しさの前では努力が完敗する切なさとか、語りたいことはたくさんあるけれど、今回読んだ部分で妙に印象に残ったのはこれです。
「日さし出づるほどに」からの描写、朝になり東の戸を開けると、冬だから部屋の奥まで日が差し込むという、当たり前だけれど、千年前の小説に描かれていることにちょっと感動。でも源氏が気を使って戸を全開にしなかったのに見えてしまった赤い鼻、「見ぐるし」とは酷い!!!(千年後の読者)
・末摘花の巻が終わった。若紫の愛らしさと美しさを強調するために末摘花を登場させたのかも、とも思わせる結末だが、赤い花を見るたびに彼女の容姿とまつわることごとを思い出してしまう源氏がちょっとかわいそう。(まり)
・源氏の末摘花に対する正直な気持ちがユーモラスに書かれていてとてもおもしろかった。「紅」という色が話の中心になっている。(うさ子)
・源氏は末摘花についてどう思っていたのか? 醜いとわかってからも関係を断つわけでもなく、中途半端である。この先どうなるのだろうか?(YOKO)
・末摘花のお世話をし始めた源氏は、末摘花からの返事に歌の一節を聞いて喜ぶ。しかし末摘花への本音は、「なほかの末摘花……見苦しのわざやとおぼさる」「紅の花ぞあやなくうまるる」であり、「紅はかうなつかしきもありたり」とあらためて若紫を見るのだった! 末摘花を見捨ててはいけないとは思っても、源氏の感覚がついていかないのだった。「末摘花」はユーモラスにかかれてはいるが、最後が怖いと思った。紫式部ってどういう人だったのだろう。(ナンバンキセル)
・末摘花とお別れするのは寂しい。古女房に大切に育てられた彼女がこれからどう成長するか楽しみ。最後はナルシスト源氏がでていたが、末摘花との縁もプレイボーイの宿命。彼女との雪の降る寒い冬から春へと季節は移っていく? (Yang yang)
・何だかんだ言って源氏は末摘花を気に入っていると思う。次の登場が楽しみ。(W)
・原文を解説していく中で、皆さまのイメージがふくらんだり、考えたり、想像したりというのが面白くて、一文一文の意味合いのとらえ方に興味を持ちました。(YOSHI)
・鏡に映った自分を見てうっとりするなんて、やはり源氏は自分大好きなんですね。現代でもこれくらい自己肯定感が強い方が生き易いのかもしれない。ストーリーと関係ない感想になってしまいましたが…。(e)
・生活環境や教育が人格形成に影響を及ぼすものだということを、紫式部が千年前に書いていることがすごいことだと思う。源氏がハズレを引いただけの話ではない。台盤所でのやり取りのような描写は物語に奥行きやリアリティを添えていると思ったし、「雪すこし降りたる光」という表現がとても美しくて、夜の間に少し積もった雪に反射している日の光が見えるようだった。(ぴ)
第58回ゆかり雲瞬間感想文(2020.9.5)
「末摘花」のよろぼふ門から贈り物までを読みました。
・末摘花が初めてひとりで歌を、しかも恋の歌をつくり源氏に送ってきた! 枕詞は間違っているし、ヘンテコな歌だけれど。しかも古びた着物のプレゼント付き! 超奥手の姫が精一杯頑張ったんだね。いじらしいですね。常陸宮家の門番の爺さんがものすごい年寄で、一緒に出てきた娘だか孫だかわからない中途半端な年頃の女とか、この常陸宮家のいまいちな感じが良く出ている、上手い表現だと思いました。(読者)
・自分の好奇心から姫と結婚することになった。自分のイメージの人ではなかったが、身分のあるひとでもあるし、自分がお世話しないとかわいそうだと思い、後見することにした。源氏のやさしさとあたたかい心を感じられてうれしい(SUZU)
・源氏の女性ハンティングの失敗の結果、源氏は女性コレクションの番外編に加えざるを得なかったのだろう。末摘花にとってはラッキーだったのでは…。(うさ子)
・期待しすぎ夢みすぎで逢ってみたものの、期待外れだった末摘花。末摘花を読み始めて、源氏に批判的だったメンバーが源氏を見直す発言をしているのが面白い。末摘花は源氏を好きになる帖でもあるのかな(ぴ)
・今日は命婦と姫、ふたりの女のことを考えてしまった。身分は高くないが、そこそこの才気があり器量もふつうで(?)、仕事も恋もうまくこなす命婦。それに対して、落ちぶれた宮家の深窓の姫で、ご身分はとても高いが才気は育まれておらず、器量もよろしくない末摘花。外や他者との交流がない姫には自分の状況もよくはわかってはいない様子。そんな姫が源氏への働きかけをようやく始めたのだから、応援したくなった。(ホトトギス)
・末摘花の由来がわかって良かったです。ベニバナのことで、赤い花と鼻にひっかけた言葉でした。源氏は文句をいいながらも、末摘花を手離さず、お世話をしているので人間味のある人物だと思いました。(YOKO)
・今日は「ほほゑみ」祭りでした。源氏の君、こんなに簡単にほだされるなんて、ものすごくチョロいのか、ものすごくストライクゾーンが広いのか?(W)
・末摘花の家の人たちの様子や邸内の様子が手に取るようにわかった。源氏の優しさと本音も書かれていた。姫の初めての歌と贈り物にはびっくりしたが、彼女の成長は喜ばしくはある。「末摘花」の最後となる次回が楽しみ。(まり)
・かの宮よりまさかの贈り物と文が届くも、その中身がやはりいまひとつ?
「何にこのすゑつむ花を袖に触れけむ」と思いつつも、かの姫と源氏は縁が深かったのでは?(Take)
・先月の講義とはまた味わいが違いました。一文一文や用いられた言葉や解釈についての皆さんの思いや考えを聞けたこと、そんな時間を持てたことが楽しかったです。(YOSIMI)
2020/08/01 特別講座「玉鬘」(第一回)
玉鬘 第1回 2020.08.01
資料テキスト1巻
p1からp10
(1)源氏と右近、亡き夕顔を追慕する
(2)玉鬘、乳母に伴われて筑紫へ下向する
(3)玉鬘、美しく成人し、人々懸想する
(4)肥後の土豪大夫監、玉鬘に求婚する
途中まで
を勉強しました。
源氏の君が夕顔に出会って、夕顔の死を経験しなかったら、北山に行くことはなく、若紫に出会うことはなかったと話題になりましたが、夕顔の娘玉鬘も母と死別して筑紫まで乳母と行くことはなかったでしょう。
若紫の物語と共に夕顔と玉鬘母子の物語は源氏物語の大きな柱のひとつなのだと実感しました。
玉鬘が成長して、筑紫の土豪達を惹きつけるのは、美しく、気立てのよかった夕顔と高貴な頭中将の子として、夕顔以上に輝いていたのでは?と竹取物語のような面白さを感じました。
YOKO
今まで読んできた源氏物語とはまるで違う作風で、別の物語のようだった。今回読んだ部分での印象だが、どこかおおらかなのんびりとした感じを受けた。桐壺や夕顔など息詰まるような緊張感を感じたが。
当時の読者たちは、都から大宰府へなどほとんど誰も行ったことはなかっただろうが、かわいそうな子供のヒロイン(玉鬘)が都落ちして遥かに遠い土地へ行く描写に、今私たちが世界の旅番組を見て感じるよりももっとドキドキワクワクしたのでしょうか。もちろん作者だって、現地取材など出来るわけもなく、読み聞きした情報を想像力でふくらませていたのでしょう。今は旅番組で見た世界の絶景や、お気に入りのドラマのロケ地巡りができる時代だから。(コロナがない時には)
マッチョで日に焼けた体の大きい田舎者の求婚者、なよなよした貴族に比べたら悪くないと思いますが、どうなるか楽しみです。
(千年後の読者)
古文による表現に不慣れとはいえ、各人物の心の表わし方やその時代、歴史をこんなにも運んでくることに面白さを感じました。(表わし方は田中先生の解説がないと理解できませんが)そして令和の現代に運ぶ物語は未来へも続くのかと想像すると、音楽もそうですが人の創った良いものはよいんだな、と。
ちょっと偉そうな感じになってしまいました。これからもお世話かけます。
望月
川崎
以上です。
猛暑に気をつけてお過ごしください。
大塚洋子
第57回ゆかり雲瞬間感想文(2020.7.4)
「末摘花」の宮家の御達の途中から雪の朝までを読みました。
?
・とうとう末摘花の顔が明らかになりました。ものすごくギョッとした感じで描写されていましたが私はマンガのイメージが強いのか、とっても可愛らしい姫君という印象を受けました。(e)
?
・これだけショックをうけても、きちんと歌を作って帰る源氏の君はすごいと思う。ちょっと見なおした。姫君のかわいらしさがわかってよかった。(W)
?
・初めてでしたが、現代のような表現力の豊かさに驚かされます。とても機知に富んだ文章だと感じました。(浜)
?
・常陸の宮家の様子、姫君の振る舞いと初めて目にした容姿の描写で源氏がどの様に感じたのかが伝わりました。それはあまりときめいたものではなかった様ですが、それでも源氏の姫君に対する思いやりと姫君の源氏への精一杯の想いが感じられ心温まるシーンでした。 (竹原)
?
・今日読んだところで紫式部は、末摘花の顔つきや服について執拗とも思えるほどに書き連ねている。その魂胆は? 「うち笑ふ」ようになった姫と、姫を見捨てはしないだろう源氏とのこれからがますます楽しみとなってきた。(月見草)
?
・末摘花は環境から、ソーシャルスキルがまったくないのだけれど、気立てもやさしくていい子なのだと思う。姫君を応援しています。コミカルで暮らしぶりや心持が生き生きしていて楽しかった。(Yang yang)
?
・ついに姫君の姿が明らかになった。思っていたよりもおどろおどろしかったのには驚いた。姫君の自信のなさはここからきているのか。姫君の姿を見てしまった源氏はこのあと、どのように振るまうのか興味がつきない。(まり)
?
・帰り際、歌を詠みかけてはじめて姫君の声が聞けた源氏。「むむ」だったけれど、コミュニケーションが成立したことが源氏にとっては嬉しいことだったはず。そのあとにうまく言葉を継げない姫君に言葉や歌を求めるのもかわいそうに思えて、早々と出発する源氏のやさしさがほの見えて、ほっこりです。(ぴ)
?
・姫であるのに食事も着物も不十分で過ごしている。源氏はそれを垣間見てかわいそうだなーと思った後に、顔を見たが・・・。源氏の心の温かさを感じられるのがうれしい。(SUZU)
・紫式部の末摘花に対する容姿の表現がとてもおかしい。容赦ない表現だが、あまり冷たさを感じないのは、光源氏の末摘花を助けようとしている気持ちも書かれているからでしょうか?(うさ子)
?
・源氏の君が格子ごしに末摘花邸の老いた女房達が貧しい身なりで、残り物を食べて居るのを見かけたシーンは妙にリアルだった。翌朝真っ白な雪の日に末摘花の素顔を見てしまったのはショックだっただろうが、髪がきれいで長いとか、良いところを見つけようとしているのが、健気。去りゆく君に姫がただ「むむ」と笑うだけというのが、本当におかしい。(YOKO)
?
?
第56回ゆかり雲瞬間感想文(2020.3.7)
末摘花の「後朝の文」から「宮家の御達」の途中までを読みました。
・末摘花との一夜のあと、誠意を見せない源氏の様子に、本人以上に女房達は相当がっかりしただろう。しびれを切らした命婦は直接源氏に会って苦言を呈したものの、源氏の「ほほゑみたまへる」表情に仕方ないと思うあたり、イケメンにはどの人もかなわないのかなあと思えました。(YOKO)
・源氏は思い込みが激しくて身勝手でずるいなあ…。でも結局はこういう人(男)がモテるのかも…。なんだか憎めないしなー。(e)
・侍従といい命婦といい、この頃の使用人は主人の私生活にかなり深くかかわっている印象。きちんと休み時間はあるのか心配。(W)
・末摘花のようすにがっかりした源氏は、頭の中将が来訪したせいもあり後朝の文さえ夕方になって出す始末。通う気持ちが起こらないのを、行幸の準備や末摘花のせいにしていた。でも面倒はみなくてはならないと心には決めているのは立派なのだが。
(まり)
・源氏に対して今まで何の反応もしない姫であったが、一夜の後、姫は源氏のことを「思ひつづけたまひ」ているそうだ。命婦が姫のことを案じて源氏の元を訪ねて、源氏に訴える場面にはほろりとさせられた。乳母子同士のこの二人のつながりによって、末摘花と源氏との縁がなんとかつながっていきますように!(葉欄の花)
・かのわたりにはいとおぼつかなく、足が遠のいていた常陸の宮の姫君のところへ、命婦から様子を聞かされたあと時々訪問することになった様子だが、どんな気持ちで通って言ったのか…。やはり、切におぼす所ではないと思うのだが…。(九十九)
・末摘花は、不細工だから源氏に愛されなかったのではなく、会話が続かず、何を考えているのか反応もなく、一緒にいても楽しくなく、魅力的でなかったからなんですね。でも私は、末摘花が可愛いと思いました。初めてのことに何を話したらいいかわからなかっただけで何も感じていないわけではなく、その後、源氏に恋しているのはいじらしいし、もっときちんと教育され訓練を積んでいたら、違う運命だったかも。源氏物語は恋の教科書ですね。(N)
・「後朝の文」の説明がされなければ、この内容はとても理解できなかった。源氏、末摘花、命婦、それぞれの思わく(心の内)がビミョウに違っているところが楽しめました。(ファジっ子)
・末摘花の気持ちが気になっていたが、一夜をともにしたあとは「思ひみだれたまへる」とようやく吐露された感じ。源氏の思い込みと若さにまわりが振り回されてしまうのは仕方がない…。次回楽しみです。(Yang Yang)
・姫ははずかしいと思っていたが、源氏と契ってからは彼のことを思い、ぼう~っとしている。やっぱり女の子だあ~と思う。かわいいわ。源氏は姫の今後のことを思い、世話をしてやらなければと思う。やさしい人なのだと思い、安心しました。(suzu)
・末摘花のこと、気はひかれないが、気にはなっている源氏。多忙を言い訳についつい足が遠のく。命婦にせっつかれ、大分時がたってようやく時々訪ねるようになる。その間数か月。時の流れの速度が現代と全く違って、ある意味優雅。(あたりまえだけど)(BB)
・ゴーストライター侍従の姫君の歌について
晴れぬ夜の月=源氏、待つ里=姫君であることから、夕顔の巻の「山の端の~」の歌について再考したら、やっぱり月は男で、里とか山の端が女だよなーと思うのです。
今日の最後、先延ばしにされながらも時々通うことになってよかったよね。(ぴ)
第55回ゆかり雲瞬間感想文(2020.1.11)
末摘花の「手引き」から「君がしじま」までを読みました。
・末摘花は鼻が赤い不細工なお姫様だと聞いていましたが、実はおとなしすぎる、何の反応も感じられない、つまらない魅力のない女性だったのでしょうか?それとも少し頭の回転がゆっくりなのか? またまた次回の展開が気になります。(読者)
・作者のそれぞれの女性のキャラクター設定がすごい。末摘花の奥ゆかしさと古風すぎるかつ世間からかけ離れた愚鈍とも思えるキャラクターに、さすがの女性慣れした源氏もびっくりしただろう。(うさ子)
・最初の訪問に期待する源氏。そこには命婦の「シカケ」が。姫はただ言われたとおりに。この各々の立ち位置でぎくしゃく感が生じ、ああ大変!! でも源氏はここから“見えたものが”…。(ふぁじっ子)
・源氏がついに姫君とのはじめての逢瀬となる夜となったのに、まったくしゃべらず、返歌も女房まかせで、それでも実行した源氏があきれる位の対応だった。この日を夢見てきた源氏もさすがに幻滅したようだ。姫君はこの後、大人として変わる事ができるのだろうか?(YOKO)
・ゆかいな展開だった。いつもとちがっていらだち、押し入る源氏。ただただどうして良いのかわからずうろたえる姫君。最後に信じられぬ無責任な行動をとる命婦。みんな必死。さてこれからどうなるのか。(BB)
・末摘花と源氏がついに対面した。これを設定した命婦は姫を手助けするどころかスタコラ逃げ出してしまったので、姫にとってはかわいそうなことになった。命婦が姫にお仕えする姿勢が中途半端でいただけない。姫のことが全くつかめなくて源氏がもどかしく思うのと同様に、読者の私たちも姫の心の動きが全くわからないので、この後を早く読みたいと思う。(冬夕焼)
・姫君が謎の人。さすがの源氏も戸惑っている様子がちょっと気の毒。命婦の事情もあるが、今後の展開がどうなる?どうにもならないのか…。(Yang Yang)
・侍従がかわいい。結局だれもかれも大変な思いをしてだれも良いことになっていない気がする。次回以降に期待。(W)
・姫君の「奥ゆかしさ」に源氏だけでなく、周りの付き人もいらいらするばかり。しびれを切らして押し入った源氏は姫君の反応のなさにさらに落胆して逃げ出してしまった。命婦はことのてん末に知らん顔。姫君の正体はこれから明らかになるのだろうか。(まり)
・源氏は命婦に手引きしてもらってやっと姫に会えると思ったのに、何の反応もなく、我慢できず押し入ったけれど…。あまりにも恋の雰囲気にならず、情緒が感じられなくて…。「うちうめかれて」家を出る。こんなことは初めてだよ~ (SUZU)
・常陸宮邸を立ち去るときの源氏の気持ちについて。
うーん… 勝手にひとりで盛り上がって、勢いに任せて契っちゃったけど、ほんとにあった事なんだろうか? 相手の姫君って存在するのかなあ。あれれ、私の気持ちってどこに?行っちゃうんだろう…? (ぴ)
第54回ゆかり雲瞬間感想文(2019.11.2)
「末摘花」返り事からものづつみまでを読みました。
・この末摘花のお話は源氏だけではなく脇を固める命婦や頭の中将の言動がキュートでコミカルなのがとても面白いと感じました。まだ途中ですが…。しかし何人も同時進行なんて名前間違えたりとかしないんでしょうか。(e)
・女君が美女だったら前からうわさになっていると思うのだが、それに気づかない源氏も中将も甘い。(W)
・源氏は頭の中将と姫のことを話題にして競い合う。姫のことは、忘れている事もあるが、何かの折に夕顔と過ごした時間、彼女をなつかしく想うことが、姫も夕顔のような人だったらと想い、会いたい気持ちがつのってくる…。さあ今後どうなるの!(SUZU)
・常陸の宮の姫君は源氏の君や頭の中将からの手紙に全然返事を書かない。源氏の君と頭の中将のライバル心もおかしいし、源氏の君は意地になって命婦にしつこく手引きするように言うあたりも笑える。妄想の中、突き進んでいくようである。(YOKO)
・源氏と中将、お互いのライバル競争。源氏の能天気な妄想、うんざりしている命婦、ひどく内気な姫、それぞれの人物が生き生きと浮かび上がりおもしろい。(adagio)
・命婦も源氏のしつこいお願いに根負けして、次回はいよいよご対面の場面で楽しみです。でも源氏の中将への対抗意識の強さにも驚くばかりです。(まり)
・頭の中将と源氏、対比される若い二人の心の駆け引きが興味深く書かれていた。時を経て、姫に接したい心を抑えられぬ源氏が命婦につめよる。それに応える命婦の気持ち。細やかな表現がすぐにはわからないが、意味が分るとおもしろい。次回、ご対面がとても楽しみ!(BB)
・「なま」「にほひ」、今日印象に残った言葉です。自分でも調べてみたいと思いました。女君の異常なまでの引っ込み思案はもしかしたらあのせいなのか、いよいよ次回出会いですね。とても楽しみです。(愛読者)
・頭の中将と源氏の君の妄想に読者の想像も加わり、常陸の宮の姫君のイメージが徐々に頭の中で出来上がって行く過程がおもしろい、最終的に姫君の容姿があかされて読者はびっくり!というおち。(うさ子)
・源氏と中将が姫からの返事をもらえず、互いにさぐりを入れたり、先を越されてはならぬと焦ったりする中、姫君の「世づかぬ」様子や「ものづつみのわりなき」がだんだん明らかにされていく。命婦の手引きによる、ふたりの対面はいったいどんなものとなるのや。姫の登場が待たれます。(つわぶき)
・頭の中将への対抗意識や返りことがないことで意地になる源氏に、色好める(?)命婦の画策(?)がからみ、これからどうなるのでしょうか?(九十九)
・「女は熱心に言い寄った男のほうに落ちるものだから、得意顔で熱心な頭中将を選んで、先に言い寄った自分を袖にするようなことがあったらそれが面白くない」って命婦に相談するところ。夕顔の喪失感を埋める行動からは離れちゃってる気がしますね。(ぴ)
第53回ゆかり雲瞬間感想文(2019.10.5)
「末摘花」常陸の宮の姫君から好敵手までを読みました。
・源氏と頭の中将が能天気に盛り上がっていることに大笑いしながらも、中務のような「召人」の女性や葵や末摘花のようなお姫様まで、女性の哀しさに思いをはせた今日の授業でした。(一読者)
・姫君の琴を聞いたあとの、大輔の命婦と源氏とのやり取りがあけすけで面白かった。さらにおかしかったのが、後をつけてきた頭の中将との会話。同じ牛車に乗って、笛を吹きながら左大臣の屋敷まで行き、左大臣まで一緒に合奏してしまうというくだりはぜひマンガに見たい場面。(YOKO)
・常陸の宮の琴の音の余韻を感じつつ退出してみると頭の中将がいる。一緒の車に乗り、笛を二人で吹いて気分が乗ってくる。でもその後大殿邸では…とおもしろい展開になってくる。楽しく読めてよかったわ~。(SUZU)
・源氏に頭の中将はいつもいつも女性のことで頭がいっぱい! でも読む方はおもしろい。紫式部はやはり素晴らしい女性作家です。(うさ子)
・機転を効かせて姫君の琴をそこそこにやめさせて、源氏の想像力をかえってかきたてる命婦。中将を振って源氏を受け入れてしまった中務の君の苦悩。二人の女性の奥深さに比べ、源氏と頭の中将は能天気に笛を吹き、左大臣邸の琴の音から姫君を美しく妄想する。男たちの軽いこと! 左大臣家の場面に中務の君の話を入れるところ、式部の文才は素晴らしいです。(adagio)
・脇の女の子達にどうしても目がいってしまう。彼女たちのそれぞれの物語を想像する(ちょっと切ない系で)。それに対して、男君たちの能天気なことねー。(ぴ)
・左大臣家の女房である中務の君は源氏のことを思っているが、源氏にとって中務はただの召人にすぎない。召人は「お手付きの女中さん」に近いものという。恋多き源氏がこういう女の気持ちに思いをいたすことはあったのだろうか? 時代が時代なのだから、そんなものあるわけない?人間ならば「あらまほし」と私は思うけれど、紫式部はどう考えていたのだろうか?(黄花秋桐)
・頭の中将、すっかりお笑いキャラとなっている気がする。しかしこの時代の人は元気だ。朝から仕事をして、夜は複数の女性の所をハシゴするなんて。(W)
・各人の心のもちよう、感じ方が興味深い。ともすれば同じ人間として、現代という時代背景に生きる我々をひき合いに出してくらべがちだが。心のうつりかわりは理解できるが、環境は全く別に考えないと…。(BB)
・平安時代の貴族の日常生活や心の内が描かれていて面白かった。それぞれの人の心理描写がとても巧で、手に取るように浮かび上がっていた。(まり)
・笛のセッションが、青年二人の盛り上がりが伝わってきて楽しい。左大臣宅の合奏も楽し気なのに、その中に中務の君の苦悩がいきなり書き込まれ、物語に奥行きが出ている。(YaugYaug)
第52回ゆかり雲瞬間感想文(2019.9.7)
「末摘花」の最初から常陸の宮の姫君の途中まで読みました。
・源氏と大輔の命婦の会話が現代の若い男の子、女の子と重なるところがあって、とてもチャーミングだなと思いました。(e)
・姫君の琴のつまびき、梅の香、ほのかに…情景がうかびます。今後どのような展開になるのか…。源氏も読者も期待に胸ふくらみます。(SUZU)
・源氏が亡き夕顔を思い出して恋しく思っている頃、乳母子である大輔の命婦の一言についつい誘われて、故常陸宮の姫君を訪れた。命婦は口が上手くて、そばで聞いている源氏のために、琴を披露させてしまった。源氏は琴の音色に心を動かされてしまっただろう。(YOKO)
・大輔の命婦という「いといたう色好める若人」が登場して、源氏とやりとりする様子が、闊達・軽妙でとても面白かった。楽器を弾くものとして、手づかひ(弾き手)、深き手(名手)という言葉が気になった。(ツルボ)
・まだ見ぬ常陸の宮の姫君は源氏の中でとても魅力的な女性として会えることを期待している。この後の展開を楽しみに今回の話を読みました。それにしてもいつも脇役?(命婦ら)が素敵な役割をはたしています。(九十九)
・荒れて寂しいところに住む常陸の宮の姫君。「どんなに美しい人が住んでいるのだろう?」と源氏の期待又ふくらんでいる様子が手に取るようにわかりますねー! さてどうなる事でしょう…。(みろりん)
・常陸の宮の姫君の琴の音(ほのかに掻き鳴らしたまふ)だけで姫のつつましやかなつつしみ深い性格が想像できるような気がしました。(うさ子)
・命婦と源氏の常陸宮の姫君に関する会話があれよあれよと転がっていく様子がとても面白かったぁー。故常陸の宮の荒れた邸で、命婦がほのかに掻き鳴らす琴の音にどんどん妄想がふくらんでいく源氏。言い寄りたいと思いつつ「心はづかしくて、やすらひたまふ」って、珍しく女の子のことを思いやっている源氏が新鮮。すこし大人になったのかな?(ぴ)
・源氏の想像と妄想がどんどんふくらんでいく様子が、面白くてよくわかる。荒れた邸に響く琴の音が聞こえてくるようだ。(yaug yaug)
・命婦と源氏のやりとりがおもしろい。何気なく話した姫君の話に食いついた源氏と焦る命婦。「心ばへ容貌など深きかたはえ知りはべらず」と命婦は答えるが実は容貌を知っていて話しづらくて言葉をにごしたのかな?などと想像してしまった。(adagio)
・大輔の命婦が末摘花のことを少し話し始めたら、光源氏がうずもれている
故常陸の親王の末娘ということで興味を持ついきさつが、ゆっくり時間が流れて、現実を一瞬忘れることができました。(加山みどり)
・今日から末摘花。連続テレビドラマの途中から見るようにこれまでの復習のような書き出し。その始まりが五・七・五調でいかにもきれい。途中、主語がないので???の部分もあったがこれからの展開が楽しみ。(B.B)
・夕顔のような人ばかりとつきあったら、今度は逆に気品の高い人を求めそう。大輔の命婦は今までに出てこなかったキャラ。今後が楽しみ。(w)
第51回ゆかり雲瞬間感想文(2019.7.6)
若紫の「二条の院へ」から最後までを読みました。
・ひたすらに純粋で真っすぐな若紫、このまま無垢なまま成長して欲しいと思う。(武蔵野の葦)
・父宮、紫の上を利用するつもりだったのがよくわかる。源氏の君、ギリギリだったけれどよく連れだした!(W)
・ついに源氏に連れてこられた紫の上! 今の時代なら大事件ですが、この時代はこんなことは普通だったのでしょうか…。(みろりん)
・姫君は何とムクな!! その無垢に寄り添う源氏。時々はそうでなくてもアリアリの姿。これからどのような二人になってゆくのかな?(ファジッ子)
・二条院に迎えられた姫君は父宮のことはあまり思い出さなくなったようで、父親のように一緒に勉強したり遊んだりしてくれる源氏の君と楽しい日々を過ごしていたようだ。この兄妹のような二人がどのようにして夫婦になっていくのだろうか?(YOKO)
・源氏は念願かなって、やっと自分の邸に紫ちゃんをつれてきた。そして歌のやりとりをしたり楽しく遊んだりとどんどん仲良くなってきて、幸せで充実した日々で、彼の精神が少し満たされているようで、良かったと思う。(うらやましい~)(SUZU)
・若紫が初めて源氏に送った歌には、源氏の心を知りたいという気持ちが表れていて、読んでいてジンと来た。尼君や少納言に「ねんねで…」と言われ続けてきた若紫だが、いまは何もわからないねんねではない。ねんねでいられた時期はとうに終わってしまったのだ。(紫方波見)
・おびえていた若君が、新しい環境になじんでいく様子がとても可愛い。「武蔵野」の歌は源氏のトラウマの深さが伝わってくるが、天然な若君と一緒に遊んだり過ごしたりすることにより源氏のトラウマがいやされているようだ。(yang yang)
・父宮は娘がいなくなったのに、それなりにがっかりはしたが、結局しつこくは探さなかった。源氏が逆の立場になったら、口惜しくひどく嘆いたであろう。思いの深さがかなり違う。源氏と若君の仲睦まじさはほほえましいが、彼女が成長していったら、どのような関係に変わっていくのか楽しみです。 (まり)
・読者はこの先を知っているだけに、いろいろ気になり心配になります…が、今はまだ仲良しの二人。とりあえず無事に源氏の元に来られて、兵部卿宮の所へつれて行かれず良かったです。(読者)
・「まだうまく書けないの」「だからって全然書かないのはもっと駄目ですよ。教えてあげますから」「失敗しちゃった。見ちゃだめぇー」このやり取りの可愛らしさが印象深い。そして源氏の「こよなきもの思ひ」をこれからどう扱っていこうかな。(ぴ)
・源氏の紫の上に対する心情あふれる様子が目に映るように表現されていて、読んでいるこちらも思わず笑みが浮かぶ。紫の上は幼いながらも天性の感性のするどさが感じられ、本当の女君になった 時がいまから連想される。(うさこ)
第50回ゆかり雲瞬間感想文(2019.5.11)
若紫の「乳母の立場」から「二条の院へ」の途中までを読みました
・“決行”ついに若君を二条の院に連れて来てしまった。源氏の君が結構人の目を気にして
逡巡しているのは意外だったが、結局決断してしまった。恋に駆られ、まっすぐに行動してしまう源氏の君はすごいなと感動しました(YOKO)
・深夜に若君をかき抱きて二条の院へ連れ出すことができたが、若君は現状をよく理解できておらず怯えている。これからどのようにして源氏の君と若君の心が通っていくのかが楽しみです。(九十九)
・いつものことながら、源氏の強引さには感服する。少納言は事態が思いがけないことに至ったことに付いていけないし、若君に至っては自分の意志とは関係なく新しい状況に置かれてかわいそう。これから若君の心の変化と成長がどう描かれるのか楽しみです。
(まり)
・どうしたら若宮の父親に知られずに済むのか私もとても気になりました。でも今日はやはりドナルド・キーンさんの言葉が心に残りました(e)
・決行がすごい。あらゆるとりまかれている状況をふまえても決行する。源氏の強い物言いにもドキドキする。文面にこのあたりが直に表現されていないにもかかわらず、人々の心の動きで(会話で)読み取れる文がすごい。(ふぁじっ子)
・今の世ならまごうかたなき誘拐である若君の連行。父宮が迎えに来る前にやるしかないと決めた源氏は、女房達にあーだこーだと言い含めながらすばやく事を進めてしまった。
この先、若紫が幸せにくらすことを祈るばかりである。(矢車菊)
・源氏が若宮を強引に連れ帰った行動。どこか源氏がこれまでよりもきびきびと頼もしい。若宮は父宮のもとへ行くよりも源氏と共に居る方が幸せになるはず。源氏の決断は正しかったのだと思う。(若葉の琴)
・「昨夜縫ひし御衣どもひきさげて、みずからもよろしき衣着かへて乗りぬ」という、少納言の取るものとりあえず、しかし臨機応変に最小限やるべき姿が目に見えるようで面白かった。(加山みどり)
・源氏の君、かなり強引。もっとおだやかに連れてくるのかと思った。しかし若い女子は強引な男が好きな人も多い。きっと当時読んでいた女子達もこの流れにキャーキャー言っていたことと思う。(W)
・古人のシーンはコミカル。若宮強奪計画(?)はどうにか成功したようだが、これからどうなるのか?若君にとっては、やはり恐怖だったのでは。(Yang Yang)
・源氏、少納言、姫君、それぞれの立場での心のうつりかわりは、今の時代に生きる我々の心にも直に感じられるものがあり、生き暮らす環境がまったく違えど、同じ感性を持てることのすばらしさに感じ入った。折しもドナルド・キーンさんの文章を始めに紹介していただいて、文化の違いなども乗り越えて人間としての心の持ちようの共通性に安堵にも似た感動を覚えた。(BB)
・源氏が幼い姫君を迎えに来てから二条院に連れ帰るまで、そしてそのあとの少納言の心の動き、実際の行動をひとつひとつ追っていくのが面白かった。ダメなところもあるけれど、仕事のできる女だと思います。(ぴ)
次は3月分の感想
・「まことの懸想もをかしかりぬべき」
源氏の君が紫ちゃんのもとを出ると、外の世界は霧に包まれ霜がおりてとても趣深い。筆者が言うその風景に、案の定、「リアルもいってみようかな」という気分になっちゃうのね、この貴公子は。紫ちゃんへの思いが「まことならざる懸想」というのだとしたら、なんか嫌な感じー、と思ってしまったわけです。(ぴ)
第49回ゆかり雲瞬間感想文(2019.3.2)
若紫の「少女との一夜」から「乳母の立場」までを読みました
・若紫が無事に源氏に引き取られるか、父の所に引き取られて北の方にいじめられてしまうのか、ドキドキの場面が続く。(このあと引き取られることは知っていても)昔の人々も読みながらドキドキしていたのでしょう(読者)
・源氏も父君も自分本位で若紫がかわいそう。乳母も含めて自分の立場が一番なのですね!
・少女との一夜を過ごし、翌朝帰りぎわに少女の頭を「かい撫でつつ、かへりみがちに出でたまひぬ」という表現に、源氏のかわいさ、気持ちのやさしさが表れている。(SUZU)
・激しく霰降る夜に御格子まで閉めて真っ暗な所の気配、朝帰りの源氏が、あらしの静まったきれいな朝に2回も女の家の前で歌を詠ませる場面、きれいなことばで表されたその場面を感じることができてうれしかった。(BB)
・源氏の君が、若君(少女)を抱いて一晩過ごしたものの、別の女の家に寄って、振られた様子はおかしかった。父君がやってきたものの夜になると帰ってしまったのは子どもとしては寂しかっただろうと思った。(YOKO)
・形としての若紫と源氏の結婚。実としてはまだ若紫とは結婚していないがゆえ、まことの懸想という言葉が生きてくるわけですね。(みどり)
・えっこれって結婚したことになっちゃうの? えっそうなの? 家に帰ってちょっと勉強します。(e)
・源氏と若紫は形の上では結婚したことになったらしい…。三日続けて通ってこなければいけないのに源氏は来ないと乳母はなげく。そして父宮に源氏と若紫のことがばれてはマズイとも思う。源氏も父宮も乳母も、尼君を失って悲嘆にくれている若紫の気持ちに心からは寄り添ってはくれない。若紫の孤独が伝わってくる。(ムスカリ)
・若宮をめぐっての父宮と源氏の対照的な書きっぷりが面白い。講義のおかげで映像を浮かべながら読むことができました。(Yang yang)
・この時代の人はいつ寝ているんだろう。帰りに別の人の所に行ったけど、大人とくらべて若君がまだ子どもであることを強調させたかったのかと思う。源氏、フラれてダメダメだけど、絵を送ったのは良。(W)
・紫の上との一夜にまつわる源氏の気持ちと進行していく状況は色々と複雑でした。(九十九)
・嵐の夜、源氏が御帳に入るところ「いと馴れ顔に」という言葉がおもしろい。源氏は恋の相手として、兵部卿は娘として若紫を見ているその差が原文からわき立つようによく理解できた。乳母の心の動きもおもしろい。これからの展開が楽しみです。(月影)
2019年2月9日~10日 ゆかり雲有志が葉山相洋閣にて合宿。
2日間で8時間以上田中先生にご指導いただきました。
桐壺
P12揺れる内裏~P57母君、胸中を語る
☆K.Mさん(ゲスト)
桐壺更衣が消えゆく寸前の歌
「限りとて別るる道の悲しきに いかまほしきは命なりけり」
のように、行く、生くが掛詞で見事であるとともに 生きたい、大事な命と、桐壺帝に訴え、
桐壺帝の愛に応えようとしている場面が心に刺さった。
鬱病で桐壺更衣は亡くなったと私自身が勘違いしていたのが恥ずかしい。
☆T.Rさん
桐壺帝がどれだけ桐壺更衣に魅せられていたか、桐壺更衣がどの様なお方だったのか。そしてお互い惹かれあい大切に思っていたのかを理解することが、その二人の御子である若宮の人物像、立場を理解する上で重要なのだと感じました。
源氏とまわりを取り巻く人びとの物語を更に読み進めたいという気持ちが今回の合宿でより強くなりました。
☆K.Eさん
どなたかが「桐壺の更衣は自分がなりたいと思う女性」というようなことをおっしゃっていましたが、私もまさにそうで、いつの時代も理想の女性像というのは変わらないものなのだなと思いました。結局のところ、意地悪をしていた人たちも桐壺の更衣に憧れていたわけですよね。
桐壺の更衣が源氏に接する姿はあまり描かれていませんでしたが、きっと愛情深く優しいお母さんだったんだろうなと想像できます。
☆S.Nさん
桐壺は高校の古文の授業でも読んだし、いろいろな現代語訳で(途中挫折しても)桐壺だけは最初の部分だから必ず読んでいたので、わかったつもりになっていました。
今回、2回めを読み始めて気になったのは、あまたいる女御更衣のなかで、ただ一人帝に熱愛される桐壺の更衣が、どんな女性なのか、容姿も性格もなかなか描かれてこないこと。源氏が生れると源氏についてはすぐに、「きよらなる」だとか「玉のような」と説明されるのに。更衣については、亡くなってからやっと出てくる。何てもったいぶっているのか。この書き方により、更衣に対しての興味がかきたてられ、ストーリーの展開にワクワクさせられるのだと思う。
しかし、紫式部は、「小説の書き方」を参考にしたわけではないし、多くの小説を読んで研究したりしたわけではない。すべて自分ひとりで編み出したもの。天才。
そしてなよなよした頼りない女だと思っていた(先入観もあるだろうが)更衣が意外にも「凛とした」人だったこと。
3回めには、どんなことを思いながら読むのか楽しみになってきました。その前に若紫の続きもありましたね。
☆W.Mさん
記憶にある限り高校までの国語で源氏物語はやったことがなかったので、有名な冒頭部分から学習できて感動しました。
現代訳のマンガや小説と比べると、本当に古文で原文で読まないと
意味無いな、と実感しました。ヘタしたら真逆の解釈もありました。
桐壺前半の感想ですが、今も昔も帝と言うのは本当に因果なお役目だな、と思いました。
どんなものかわかった状態で、それでも帝になるかならないか選べるのならば、なりたくなかった、という人は何人もいたのではないだろうか。
当人以外のほとんどの貴族は、つらさがわからず単にうらやましいと思ってのかも。
それなのに女性である式部が帝の辛さをわかっているなんて、非常に想像力のある頭のいい人だったのだろうということがわかります。
きっと歴代帝の中にも源氏物語を読んで「わかるわかるー」と涙した人もいたと思う。
そんな自由の無い常態で、桐壺帝は更衣に会えて、一生に一度の恋ができてよかったのではないか。
まぁまわりに対する対応はかなり間違ってたけど。
桐壺後半も気になるので、できたらまた補講やって欲しいです。
☆S.Yさん
身分の高くない妃が、帝から抜きん出て手厚くもてなされて、特別扱いされている。
最初は、帝や更衣がどんな人となりか、わからないから、今後の展開は、どういう事になるの? と、気になり、どんどん読みすすめたくなる。
他の妃や、その女房たちから、目障りとおもわれ、妬まれる。いじめられて、きぶせになって亡くなる。
寵愛を受けた人が、亡くなる。物語性として、いい人や、美人が亡くなるという展開は、よくあるけど…‥‥……
帝が、御子(源氏)を特別に目をかけて、更衣亡きあと愛情深く育てていたのを知りました。私は、源氏は、幼少期寂しく過ごしていたのかと思っていたので、本当によかったと、暖かい気持ちになりました。この事を知ることができ、とてもよかったです。
更衣が弱り、里に下がるとき、御子を宮中にとどめておこうとする。皇子としての将来がある。病気にもかかわらず、御子の事を気遣うという人となりが、よくわかる。
更衣亡きあと、帝のつかいで、命婦が、母君に帝のことばを伝えにくる。
『しばしは夢かとのみたどられしを…‥‥……』と伝える。どんどん帝の気持、人間性が立ち上がり、私の中に人物像がとてもイメージできる。
☆O.Yさん
源氏物語の冒頭は高校の時に暗記した思い出があるので、今回勉強させていただき、懐かしく、また、暗記した先も触れることができたので、作者が語ろうとしていることが、良く理解できました。
桐壺の更衣は帝に寵愛され過ぎで、周りの人からいじめられて弱々しく亡くなったような先入観がありました。
しかし、唯一遺した歌をよむと、凛とした人柄で、帝も惹きつけられる程、輝くような知性と美しさを持っていた女性だったのではと思います。
亡くなった後の帝の嘆きや、遺された若君の後々の様子から想像するに、めったにいない素晴らしい人だったのでしょう。
教科書の冒頭部だけではわからないですね。
第48回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2019.1.5)
若紫の「尼君の死」から「少女との一夜」の途中までを読みました。
・源氏の君、強引に行ったなー。これが吉と出るか凶と出るか。(W)
・若君との思いがけない急接近でこれからが大変気になるところですが、「尼君の死」のたった9行であれだけ深い濃い内容を表現できる古文の力に改めて圧倒されました。(ねこおばさん)
・源氏の想いだけの場面に比べ、若紫が登場すると途端に色鮮やかに情景が変る。生き生きとした場面に読む側も心がときめく。(九十九)
・姫君を源氏に託したい。でもまだ早すぎる。父君のもとにはやりたくない。会わせてみたらやっぱりまだ不安…という少納言の乳母の心の動きが手に取るようにわかります。(ぴ)
・上皇の御所への帝の行幸で忙しくしている間に、尼君は亡くなり、少女は京都の古びた屋敷に戻ってきていた。源氏の君は弔うために訪ねる。乳母の少納言の話を聞いて、つられて泣いてしまった様子は若々しい。少女の声を聞いて、思わず御簾越しに髪に触れてしまった場面は、みなドキドキさせられてしまったことだろう。(YOKO)
・1年ぶりの源氏物語の授業ですのに、お話が上手に続いて、ますます魅了されてしまいました。いや楽しい! 今度はどこに行っても「若紫」の本を持ちまわって自分なりにかじり読みします。全く感想文になっておらず御免なさいませ!!! m(_ _)m (海老彰子)
・姫君の可愛さにあらがうことも出来ない源氏の行動が興味深く表現されているように感じました。(うさ子)
・源氏は若紫に初めて言葉をかけることができた。そして御簾の下から手を入れ、若紫の手を取り、御簾の中に入ってしまったではないか! 驚かされる場面であったが、相手は「ねむい」とか「寝たいと言っているのに」と乳母に駄々をこねるおさない若紫であるから、源氏とてどうこうできるわけがない。少納言に「私の気持ちを見届けてほしい」と言った源氏を、私も見守りたいと思う。
(ミル)
・ドラマのような展開でこの続きがたのしみです。3月まで読まずにだいじにとっておきます。(ネギ屋が待ちきれない女)
・尼君の死を伝える僧都の言葉「つひに空しく見たまへなして」が心に沁みました。源氏はどんどん若紫に近づいていく。何と素早いことか! あきれながらも次回の展開が楽しみです。(玉藻)
・「尼君の死」の始めが「十月に朱雀院の行幸あるべし」と一文で状況を伝えているのをはじめ無駄にことばを使わず的確な書きっぷり。少納言のくどくどした言葉に不安感が伝わってきた。(やんやん)
・続きがきになります! ドラマみたいになってきました。(e)
・姫をとりまく人々の心のうち。尼君・僧都そして源氏の。少納言も大役で、源氏に語りかける様、皆いっしょうけんめい。でも姫はいつもの姫。興味が拡がる拡がる。このあとも楽しみ!!(ファジっ子)
・久々に充実した興味深い時間でした。前後がわからず、説明についていくのに必死でしたが、一番のショックは「源氏」の中身より、ノートを取る字が書けないこと。ペンを持って手で字を書くところから練習していこう!と思いました。みなさまのお考えを聞くのがたのしかったです。ありがとうございました。
(Bino Byun)
/
第47回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.11.3)
若紫の「懐妊」の途中から「少女の声」までを読みました。
・藤壺へは思いが通じず悶々としていたところ、病に伏せている尼君を見舞うことができ、少女の将来を任されるようになったのは一筋の光となったことだろう。尼君に呼びかける少女の声はかわいげだ。(YOKO)
・藤壺の存在が遠くなるのを感じながらも、強く思い続けていたかの少女をいよいよ「手に摘みて」というほど近くに感じられる時が来た。過去と未来の交差する時に思いました。(九十九)
・ついに藤壺懐妊!本当に帝は自分の子だと思っているのかな…。怪しい…。
(みろりん)
・「御遊び」での藤壺の様子、惟光の機転をきかせたふるまい、尼君の想い、天真爛漫な少女の様子、慌ててとりつくろうとする女房たち、察して少女のことには触れずに帰る源氏、場面や心の動きが鮮明で細やかで物語に引き込まれました。(Ashi)
・源氏の「一声きかせて」に女房達ドン引き。声聞けてよかったね。(W)
・恋多き源氏は藤壺と若紫のどちらにも心を揺すられていて、二人の女性が対照的に描かれていた。これからの展開に目を離せられない。(まり)
・若紫の後見をしたいという源氏のかねてよりの願いは、臨終の尼君を見舞うことでついに叶えられることになった。源氏が心に秘めている思わくなど知る由もない若紫の言動はただただあどけなく幼い。この二人はこの後どうなっていくのだろうか? 読者の気持ちをぐいとつかんで物語は進められていく。(紫根)
・六条京極辺りへ行こうと思い立ってその途中、荒れた家に目をとめたり、おばちゃんを見舞ったりするのは夕顔の巻でもあったね。六条で待っていた人のことを思うとフクザツです。
紫ちゃんが、無邪気に「おばあちゃまー!」とかけこんでくるところが本当にほほえましくて、その場の空気感を共有していました。(ぴ)
第46回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.9.1)
若紫の密会と懐妊を読みました。
・山寺の少女とは惟光を使者として手紙を持たせたが、尼君からお断りの手紙が来て、進展はなかった。そうこうするうちに藤壺が体調をくずし里帰りしていることを知った源氏の君はついに密会に成功する。何も知らない帝に対し、源氏との間の子どもを妊娠してしまった藤壺はどんなにか恐れおののいたことだろう。源氏物語のクライマックスのひとつの場面を原文で楽しめました。(YOKO)
・すべては源氏の藤壺への深い愛からにしても、まだ子供の若紫にまで心をうばわれるのにはあきれるし、子どもまで作ってしまうという危険を犯すどうしようもない「業」。現在のようにDNA鑑定がなくて良かったです。「もののけ」のせいにできて!!(うさ子)
・今もやっているのかわかりませんが、一時期の昼ドラのような重い話でした。しかし藤壺の宮は本当にかわいそうです。(e)
・紫式部は源氏をひとりの女のところには立ち止まらせない。前回と今回読んだところで、若紫・葵・藤壺が次々と登場。源氏は女性との間に何らかの障壁があってはじめて気持ちが燃え上がるタイプの人なのだなとつくづく思った。葵の上に気持ちが向かないのは彼女の人柄のせいではなく彼女があてがわれた妻だからなのだ。父帝と源氏はなんと違うことだろうか。 源氏に想われた女性は渦中へと巻き込まれていく。(トレニア)
・紫ちゃんを何とか自分のところへと思っている一方、藤壺と2度目の夜を過ごす事が出来て、放心状態の源氏。一方藤壺は懐妊し、今後いかに…。今までの様々な伏線があり、紫式部をストーリーテラーだと感心します。(SUZU)
・高校卒業以来の古文体験でした。自分で読んだだけではまったく理解できない、また解説文を読んでも?になってしまう文章がとてもいきいきと伝わってきて楽しかったです。光源氏にはあまり感情移入できない気がしますが、成育歴、人となりには興味がわきます。紫式部のあからさまに説明するのではない書き方は面白いと思いました。(Yang yang)
・若紫の件は待ちがいつまでなのか不明。源氏は心乱れ不安に。いっぽう藤壺の里帰りを機会と、会うことにシツヨウに…。そして実現するが、二人にとって悲しい思い、つらい思いが一層濃くなってその結果! 今回「し」のひとことで源氏物語の厚みを知った驚きが…私に!!(ふぁじっ子)
・久し振りに藤壺の女御が登場。源氏が成人してからもところどころでその存在を感じさせていたけれど、ついに、本人が生身の女性として現れた。あまりにも衝撃的に。物語が動いていく。もうひとつの衝撃は、直衣などをかき集める王命婦。容赦なく朝が来る。(ぴ)
・こういった話がでるということは、妃が帝の子以外を宿すようなことが当時ありえたのかなーと、下世話な事を思ってしまう。(W)
・「密会」は短い文章の中で重要な内容が描かれていたのですね。一読しただけでは内容が把握できないです。解説していただいて内容が理解できました。(九十九)
第45回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.7.7)
若紫の「めでたき人」から「小さき結び文」までを読みました。
・源氏の君は迎えに来た頭の中将たちと都に帰ってきた。帝とはあれこれ話せたが、義父の左大臣邸に連れてこられ、妻とは話もはずまず。冷たい関係はますます。北山の少女のことが気になって尼君や僧都に手紙を送ったり、惟光を使者として送ったり、思い詰めている様子が印象的だ。(YOKO)
・10歳の子どもに恋心とは!! 素直になれない葵の気持ちもちょっとわかるかも…。(みろりん)
・葵の上とのやりとりと若紫に対する想いの強さとの対比がおもしろかった。今後、若紫へどの様に接近してゆくのか。展開が楽しみです。(九十九)
・源氏は左大臣邸に連れていかれて、葵の上に久しぶりに会ったが、愛想がない妻を前にして「たまには妻らしくしてほしい」とお小言をもらしてしまう。「とざまかうざまこころみきこゆるほど」と源氏は言うが、葵は源氏の心が自分に向いていないことがわかるから、決して打ちとけようとはしないのである。源氏は左大臣邸では凡庸な夫となり果てている。(日日草)
・源氏の君と葵さんのすれ違いは読んでいてなんかとっても切なくなる。葵さんはお高くとまったやな女じゃないはずなのー! 暴走がまた始まりそうです。(ぴ)
・このマメさを少しでも妻の方に振り分けてあげればいいのにと思う。このあたり、内容もおもしろいけれどメンバーの考え方もいろいろ違っておもしろい。(W)
・葵の上と源氏の関係
すれ違ってしまって、残念でしかたがない。ま、だからストーリーが展開→少女の方に行くのでしょうが…。(SUZU)
・やみ上がり(?)の源氏なのに、ほっておいてくれない…。また、帝は源氏にやつれを感じ心配し、左大臣はただ娘のためとあわただしい様。でも妻はいつもと変わらず冷ややかな…。源氏にはまた苦しみが。でも少女のことには一生懸命!!(ふぁじっ子)
・源氏と葵の上の久し振りの邂逅の冷たい雰囲気と源氏と尼君の文のやり取りの内容の対比というか、落差。葵の上があわれ。(まり)
・療養のために山に入ったのに迎えの者たちは宴を始めるし、やっと帰京すれば左大臣に邸に連れて行かれ、正妻には冷たくされる。忙しくふりまわされる源氏を気の毒に思ったが、若紫を得たいとあれこれ画策するなど、やっぱり相変わらずの源氏でした。(adagio)
第44回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.5.12)
若紫の「心中を訴える」から「めでたき人」の途中までを読みました。
・僧都が俗っぽくておもしろかった。ひそかに結構お金持ち。(W)
・尼君に心中を訴えるが、軽くかわされてしまった源氏…。でもいつまでも彼女のことが心に残る。これからどうなるのか…楽しみです。送別の宴が源氏の気持ちとはそぐわないけれど~しかたなく付き合うのか…。(SUZU)
・少女に藤壺の面影を見て、一瞬のうちに恋してしまった源氏だが、尼君に気持ちを訴えたときは「自分と少女は境遇が似ているので類と考えてほしい」と切々と述べたのであった。これも源氏の本心の一部であったのだろう。
僧都の人物像が少しこっけいに描かれていて面白かった。(山法師)
・源氏の君は尼君に、少女について強くアピールしたものの固く断られ、都に帰ることになった。山の描写が、読経の声・山おろし・滝の音と、生き生きとしていて、紫式部が行ったことがある所がモデルなのか気になりました。(YOKO)
・お忍びで療養に行ったはずなのに、帰り際は大宴会になってしまう源氏の立場の大変さを垣間見ました。それにしても僧都のアクションはいちいちおもしろい。今回はとても楽しめる場面だった。(Adagio)
・源氏を取り巻く僧都、尼君、聖との会話の内容、行動の描写からそれぞれの個性が表現されているところを興味深く読みました。(竹原理津子)
第43回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.3.3)
若紫の「少女の素姓」から「眠れぬままに」までを読みました。
・源氏の君は思い切って僧都に少女への気持ちを話すものの、あっさりいなされ、恥ずかしかっただろう。それでもあきらめず、尼君の女房に、歌を伝えてほしいと積極的にアプローチ。尼君も「あな、今めかし」と本音を言ってしまうなんて、源氏の君は人気がありますね。(YOKO)
・源氏が直情的に、つい、僧都に自分の気持ち(本音)を打ち明けてしまったのが、若さゆえか、純粋でかわいい(SUZU)
・これからの源氏と尼君のやりとり、展開が楽しみです。(うさ子)
・少女へのやむにやまれぬ恋心を、なりふり構わずに僧都へ伝えた源氏の姿は真剣そのもの。だけど源氏の描かれ方は少しコミカルになっていて、読者の気持ちはぐいぐいと源氏にひきつけられていく。源氏の恋心にはついていけない私もその一人でした。(雪割草)
・源氏の一途な想いはかなり強引だが、これだけ強引すぎるとかえって叶えてあげたくなってしまう。そこが源氏の魅力なのかも(adagio)
・自分の心のままに行動する源氏を少しうらやましく思ったのでした。(e)
・僧都が意外にもまじめだった。逆に尼君の反応の方が軽かった。はやく少女本人と会うところが読みたい。(W)
・昼間見た少女が「あの方」と同じ血筋であると知って、何がなんでも自分のもとに引き取りたいと、世間の常識まるで無視して僧都に迫る源氏の姿は若くてみずみずしい。その行動の背後にある源氏の苦しい恋がほの見えて切ない。(ぴ)
第42回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2018.1.6)
・源氏の君は少女について詳しい事情が聞けて、さらに気持ちは深まったようだ。かのあこがれ藤壺の姪にあたるとはなんという偶然だったことか…。(YOKO)
・病気を治すのにやってきたはずが、若紫ちゃんのおかげで、すっかり元気になったようでうれしいです。(ねこおばさん)
・生まれて初めて本式に接する源氏物語の内容の深さに驚嘆しています。日本人としてこれは、学ぶ、知って認識すべき素晴らしい日本文化だと、やっと判りました。もっと早くに勉強、知るべきであったと思いますが、このような機会を与えてくださった田中順子先生に深謝です。私の生き方も日本人として、もっと知りたい。そして自分の在り方も学びたいと思いました。ありがとう存じます。
(えびあきこ)
・病気の治療に行ったにもかかわらず、常に女性のことが頭にある源氏。あっという間に元気になったということでしょうか?(うさこ)
・源氏が少女の素姓を知りたくて僧都にかまをかけると、僧都はペラペラと語ってくれたので、源氏は少女の素姓を知るところとなり驚く。「かの人」の面影があるのもゆえなきことではなかったのだ。おしゃべりな二人の男たち、源氏と僧都に対して、尼君(僧都の妹)はしっとりとした方だった。(日本水仙)
・ひと目見た児にひかれる源氏。ひかれる心が流れてゆき、その筋を知り納得する、どきどき感が伝わってきて、何とも言えない運命の糸の存在かと。(ふぁじっこ)
・えっと、確認したいのですが、源氏は病気を治すために北山のなにがし寺に来たのですよね?(adagio)
・ありがたくて寿命がのびる、はこのころからあった言いまわしなのがおかしかった。(W)
・尼君が少女の将来を心配して涙を流しているところにドタドタと入ってきて、「源氏の君がおいでなんだ。あなたたちもご覧になった方がいい。あー、挨拶してくるっ!」という僧都の俗物っぷりがとてもおもしろいところ。でもこの辺りで語られているのは実はストーリーの核だったりする気がするのです。(ぴ)
第41回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2017.11.4)
「若紫」海龍王の后から走り来たる女子まで読みました。
・供の者たちが、明石の元国司の娘のことを話して、源氏の君の気をひこうとしていたが、「海龍王の后」になるしかないとか、面白いことを言う。いずれこの娘に会うとは思っていなかっただろう。そして、運命の女の子を目にすることになる。雀の子を失って涙ぐんでいる可愛い子は、ずっと想いを寄せるある人にそっくりだった。劇的な場面です。(YOKO)
・源氏が若紫を見かけて、将来の成長したさまを想像し、さらに彼の人を思い出す場面はしっとりとしていてよかった。でも小柴垣から惟光と二人でのぞいている姿を想像すると、ちょっとこっけいにも思える。(まり)
・美しさは昔の基準で考えてしまうとちょっと苦しいので、現代風に置き換えてイメージしてみることにする。しかし若紫ちゃん、髪もキレイだなんてうらやましい。(W )
・「雀の子をね、犬君が逃がしちゃったの。伏籠の中に閉じこめておいたのに。ぐずっ。」高校の教科書で出会った女の子は変わらずにかわいらしくそこにいた。尼君よりも年上になった今、垣間見していた源氏の君の心をどう取り扱うかなぁー。(ぴ)
・高校の教科書に載っていた場面がとてもなつかしく楽しかったです。若紫の可愛らしいほのぼのしたシーンという記憶でしたが、最後の源氏にびっくりしました。入道の娘との対比がすばらしい!(ねこおばさん)
・源氏は興味本位から垣間見で女たちを見始めた。尼君や少納言の美しさにもひきつけられるがやはりどうしてもおんなごの方に目が吸いよせられていくのだった。それはなぜなのか。気付いた時の源氏の涙にこちらもホロッとさせられた。(野紺菊)
・のんびりと子供らしく育った若紫と親の立身出世のために教育を受けた明石の君。子供時代の環境の違いが将来どのように影響して行くのか、その後の人生は?(ななしさん)
第40回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2017.9.3)
「若紫」に入り、明石入道まで読みました。
・源氏の君が加持を受けに出かけた北山のなにがしの寺。大雲寺という説が濃厚とか。おつきの人たちが話した播磨の元国司が後の明石の入道というエピソードに驚かされました。紫式部の構想はすごいのです。(YOKO)
・新しい巻に入って、ちょっと今までと違う雰囲気がただよう話が進んでいく。源氏自身のことではない話が面白い。明石入道の話が20年後の伏線となっているのには感服する。(まり)
・北山の聖、源氏の前でウキウキと札つくっていたと思うとかわいい。(W )
・山の上から京の都の景色を見て、まるで絵のようだといたく感動した源氏が少し気の毒に思いました。(なにがしの入道)
・夕暮れ時の忍び歩きからはじまった夕顔を読み終え、続く若紫は暁の出立から始まる。春の北山の風景、僧都の庵の童女たち、山道を下りてのぞきに行く供人。若紫の冒頭は麗らかな春の明るさに満ちている。(ぴ)
・ついに源氏と紫の上の対面! これからが楽しみです。(みろりん)
・宮中という、雅ではあるがある意味とても窮屈な世界で暮らしている源氏が心を奪われたのは山の上から眺めた芽吹きのころの景色だった。「かかる所に住む人、心に思ひ残すことはあらじかし」とつぶやいた源氏を、とてもいとおしく感じてしまった。(秋海棠)
・若紫のことの記述の前に明石入道のことが書かれてあり、今まで気が付かなくて、あっと驚きの伏線で、さすが式部と思う。(SUZU)
第39回「ゆかり雲」 瞬間感想文(第二巻P326「四十九日の法要」~巻末)
◆いろいろな女性と付き合っても、なお女性の心模様がわからないという源氏。
男女の仲は永遠の謎。
もてぬ女子
◆夕顔の巻読破ではあるけれど、最後に描かれた空蝉が切なくも可愛い。
心を解き放った空蝉は清々しくさえある。
源氏はここで空蝉というひとりの人間と向かい合ったんではないだろうか。
ぴ
◆四十九日の法要を源氏は精いっぱいしてあげている気持ちは痛々しい。
空蝉のショックは後日に残るかも~
でも源氏との事は人生のいい思い出として今後を生きると思う。
SUZU
◆空蝉も夕顔も、雨後の品さだめに出てきた「生まれは高貴だけどおちぶれてしまった姫」
という条件にあてはまる。
そんな二人に出あえるとは、さすが源氏というべきか。
しかしやっぱり小袿は返さない方がよかったのではないかと思う。
W
◆夕顔の四十九日の法事は比叡山の阿弥陀堂でしっかりと営まれ、源氏の君の気持ちもだんだ
ん落ち着いてきたのだろうと思う。
よく顔を合わす義兄であり、友人である頭の中将に夕顔の死や子供の行方について語ること
ができなかったのは、さすがに後ろめたかったのだろうと思う。
空蝉が夫と任国へ旅立つ前に例の夜の小袿を源氏から返したら、空蝉から悲しいという返歌
が来た。秘めたる恋の卒業とともに、源氏の君も大人になっていったのですね。
YOKO
◆前回もそうでしたが、夕顔に感情移入しているところに空蝉をからませてくる構成のすばらし
さに改めて「源氏物語」すごい!と思います。
熱い恋心に流されないプライド高き強き空蝉、今までとちょっとイメージが変わりました。
猫おばさん
◆空蝉をいやな女だと思っていました。でも今は印象が変わりました。
状況にしばられ、プライドにしばられたかわいそうな女だと。
最後に感情をぶつけられたのは彼女にとっては良かったのかもしれない・・・
N子
◆初めて出席させて頂きましたが楽しく拝聴させて頂きました。
源氏物語はダイジェスト版のようなものしか読んだ事がなく、又、随分以前に読んだので
もうすっかり忘れてしまっています。
これからもできるだけ出席させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
石井
◆夕顔の法要は事そがず、空蝉へは小袿を返す。
二人共、源氏の元からはゆくから知らずになってしまった。
また次の話が始まっていくのですね。
ふなっしー
◆2011年3月、震災直後、「いずれの御時にか」と始まったゆかり雲。
今回第39回目で2冊目まで読了、六年で一つの節目を迎えました。
夕顔の締めくくり、式部のコメント。
源氏の秘めたる真実の姿を、源氏のために語ったのだと。
詳細に語ってしまった罪まで語るところ、見事でした。
Adagio
第38回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2017.5.13)
それぞれの追慕から軒端の荻の文までを読みました。
・右近と共に夕顔の思い出に浸っていた源氏の君だったが、空蝉から心配する手紙をもらった辺りからだんだん本来の性格に戻ってきたようだ。軒端の荻の返歌にけちをつけたり、それでもかわいいと思ったり、源氏の君らしい。(YOKO)
・夕顔の正体もしだいにわかったが、源氏も右近も憂いの日々を重ねていた。そこへ空蝉からの思い余った手紙が届いて源氏はにわかに復活していく。でも少しは大人になったのだろう。(まり)
・夕顔に対する想い、空蝉に対する感情、表現する手段が歌なので歌を理解できるようになりたいです。(ふなっしー)
・源氏の「女なら誰でも」的なところがある意味うらやましいです。(笑)けど今だったら事件怒っていますよね。(e)
・空蝉、キッパリ断った所がよかったのにちょっとがっかり。それ以上に源氏がダメだったが。(W )
・源氏の夕顔への追慕がしっとりと書かれたあと、源氏のもとに空蝉からの文が届く。そして今度は軒端の荻へと文をかいた源氏。いたずら心がムクムクと頭をもたげてきたところをみると、悲嘆にくれていた最悪の時期はもはや乗り切ったようだ。(キジバト)
・夕顔を失って、砧の音さえ恋しく悲しみに沈んだ源氏を気の毒と思ったが、軒端の荻の一件で、同情の気持ちが消えてしまった。紫式部は男のことをよく理解していらっしゃる。さすがです。(つくつくほうし)
・源氏と右近の様子から、空蝉の文への展開もさることながら、ちょっかいを出す源氏。どうなっているの???どうなっていくの???という感!!(ふぁじっ子)
・女から男へ歌を送ることは緊急事態であると先生がおっしゃった。夕顔の巻では冒頭の「心あてに~」の歌と空蝉の「問はぬをも~」がそれに当たる。今夜眠れるかな…?(ぴ)
・突然の空蝉の文に驚き、文のやりとりで自分の心をおさめられる空蝉にまたちょっとびっくり。文のおかげ(?!)でか、源氏の君もすっかり元に戻ってきた感じがいいです。(ねこおばさん)
第37回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2017.3.4)
「右近と語る」から「女君の身の上」までを読みました。
・一緒に過ごした時にはわからなかった夕顔の人物像が右近との会話の中で浮かび上がってくる。夕顔の亡き後にそれを知る事になる源氏。過ごした時間はあまりに短かった。夕顔の忘れ形見の女の子の存在を早く知りたいです。(ふなっしー)
・昔も今も幸薄い女性の方が物語に欠かせない男性をひきつける対象になるのかと思います。(ガサツ女子)
・相手の立場、自分の境遇を考えて「つれなくのみもてなし」ながらも悩んでいた夕顔の気持ちを源氏も中将も全然わかっていない? いつの世も女性の方が思慮深いのだなあと思ってしまう。(adagio)
・夕顔は源氏が自分から名乗ってくれるのを待っていた。後ろ盾もなく、わびしい家に住んで源氏を待っていた夕顔にとってそれはどれほど切実な願いであったことか。源氏君、これからは自分の想いをとげるときに、愛するひとに悲しい思いをさせないようにしてくださいね! (貝母)
・私も正直なところ夕顔さんは少しぼんやりした人かと思っていました。こんなことを考えていたとは。雨夜の品定めの時から、この展開になると考えて書いていたのだろうか。(w)
・夕顔の素性もわかり、前を読み直すといろいろと発見があって、源氏物語の面白さを体感できました。(まり)
・源氏と右近の会話から、夕顔の性格が明らかになったところ。彼女は自分の感情はさておき、相手には一切心配や不快な思いをさせたくないという控えめな人。だけど強さがなければそれを貫くことってできないことでもあるよね。わたしは、自分のイメージする夕顔ちゃんを破綻なく形にしたいと思っているのでした。(ぴ)
第36回 ゆかり雲 瞬間感想文(2017.1.7)
「鳥辺野の対面(途中)」から「源氏、病に倒れる」までを読みました。
================
・若い17,8の源氏が、そのときの最愛の人を亡くし、自分の気持ちの整理が出来ず
寝込んでしまうのは、人間的で小説だけど、生身の人を感じることが出来て親しみがわく。
(かわいそうだけどね~)(suzu)
・源氏、なさけないと思ったけど、17才だったらしかたない。
トラウマにならなければいいが。これからの右近の話が楽しみ。(W)
・さすがの源氏も、夕顔に突然死なれた心の痛みに病に倒れたが、父帝の嘆きを知り
ようやく治った。そして、脱皮したように一段落成長したのではないか(まり)
・惟光の人間らしい弱さが出てきてよけい惟光に親近感を覚えました。
それ以後の惟光の働きはさすが!右近ちゃんへのサポートも完璧ですネ(ねこおばさん)
・十代で愛する人を亡くすという体験がこの後の源氏にどのような影響を与えるのか
読んでみたいと思いました。(e)
・気持ちに従って行動したものの、この行動から様々なこと、右近を力づけること、
それに反し自らも生きていられないとか、惟光の動揺、彼の動揺から自らをふるいおこして
などなど、今まで経験したことのない様に、それぞれがとまどう。やはり病の床に。
そして、日常に戻るには・・・。これからはどの様なことになるのか・・。(ファジっ子)
・源氏の尻ぬぐいをする惟光はたいへんだなあち思いしました。
それにしても源氏って見た目は美しいかもしれないが、なさけない男だ。
こんな人はあまり近くにいてほしくないかも・・・。(みろりん)
・傷心の源氏も、絵でみると滑稽に見えました。でも右近の心配をしている所は
配慮のある人物にも見えました。(下々の女)
・八月十五夜、「北隣さん、聞いてるかい」なんて声を聞いていたところから、
十七日の月では鳥辺野の対面、この数日間でどれだけ源氏は消耗したんだろう
一ヶ月寝込むほどのショックはあっただろうと思う
回復した源氏を囲っちゃう左大臣がけっこう好き。(ぴ)
・夕顔とすごした美しい時間がまぼろしの様に
過酷な現実が源氏を打ちのめす辛い様子を感じました(ふなっしー)
・鳥辺野まで亡くなった夕顔を一目見たさに出かけた源氏だったが、悲しみとストレスで
病になり三週間位寝込んでしまった。
鳥辺野からの帰り、落馬して混乱している源氏を見て、清水の観音様に手を合わせている
惟光の様子が深刻な場面だけど、ちょっとおかしかったです。(YOKO)
第34回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2016.9.3)
「孤独の一夜」から「惟光の采配」までを読みました。
・夕顔が息絶えてしまった。右近もガタガタ震えるばかりで役に立たない。源氏は惟光が来るまで長く感じたことだろう。ようやくのことで馳せ参じた惟光は、動揺したものの源氏に比べると現実的に対処できるようで頼もしかった。それにしても夕顔が哀れでならない。不幸せな人生だった。(YOKO)
・惟光が来なければどうなっていたことか。今日「みつはくむ」が気になるキーワードになった。(W)
・惟光がいかに頼りになる男かを源氏は実感したことだろう。惟光が来るまでの源氏の心細さと、それに打ち勝とうと気丈にふるまう様がよくわかった。
(まり)
・夕顔の死で不安におののく源氏の様子を、さらに屋外の音、鳴き声が臨場感を高めていると思いました。式部さん上手い。(しほじみぬる どち)
・惟光が「からうして」源氏のもとに駆けつけると、それまで「賢しがり」なんとか持ちこたえようとしていた源氏は、ほっとして思いきり泣いてしまった。源氏の惟光に対する信頼、二人の間の兄弟のような心の通い合いが良く描かれていた。(だるま萩)
・夕顔が動かなくなってから源氏は心もとなく、自分で何を言っているのかもわからないあやふやな状態で、頼りにしている惟光がやっと来て、心がほっとして感情があふれ、よよと泣いてしまうところ、人間的でかわいい。美しい人が泣くところは人を動かすのですね。私も見てみたかったわ~。
(SUZU)
・惟光が来る前後の源氏の心理描写がおもしろかったです。惟光は情に厚いけど、しっかりと物事を考えられる頼れる兄貴なんですネ。右近ちゃん、泣いてばかりいないで、もう少ししっかりしなくては。(三匹の猫おばさん)
・今回は頼もしい惟光の巻でした。源氏もよくがんばりました。(ひぐらし)
・たよる者が不在でどうしてよいかわからないが、また自らに「私はしっかりしている」と言い聞かせたり。千々に乱れる源氏。なんとか惟光が来てくれて、泣いてここでは取り乱す。事が起こって主従の関係、源氏の立場などあらためて学んだかもしれない。(ファジっ子)
・「惟光とく参らなむ」と、とにかく彼に事態をなんとかしてほしかった源氏。
惟光が参上してから、緊張が少し解けて弱気になったり、「素」の源氏が会話から見えるのが面白いところでした。(ぴ)
・初めて参加致しまして、古文に接する機会が得られた事が大変嬉しく思いました。日常の生活の中では体験できないので、とても新鮮な気持ちになりました。今後も頑張ってついていきたいと思います。(T,R)
第33回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2016.7.2)
「枕上の女」から「息絶えた女君」までを読みました。
・せっかく夕顔と親しくなれたのに。「あまの子なれば」と言っていた夕顔がかわいそう。彼女の死に接することになるとは…。源氏も右近もつらいですね。無常感漂う…。(SUZU)
・西洋の古典でも、わけのわからない理由で死んだりする話がある。やっぱりショック死だったのだろうか。AEDがあれば。(W)
・物の怪は本当にいたのだろうか。やはり源氏が部屋を出ていた空白の時間が気になる。右近犯人説をどうしても捨て切れないのであった…(失礼!)。助詞をどうとらえるかで、情景が大きく変わる箇所は、異なる解釈が可能となる点で興味深かった。(平安探偵事務所)
・夕顔のあまりにもかわいそうな最後。古語の淡々とした語り口によけいに背すじが寒くなります。夕顔と右近2人だけの時間、いったい何があったのでしょうか?! (ねこまた)
・源氏、女君、右近と3人だけの時に起こってしまった、おどろおどろしい様。それぞれがとまどう様から、女君の死に気づけない源氏。気づいたら大変なことに。死の表現が深まってゆきました。(ファジッ子)
・夕顔の身に何が起きたのか、源氏にも読者にもよくわからないまま、夕顔は息をひきとり、からだは冷えに冷え入りていった。楽しき一夜は一転して絶望の一夜に。源氏は「ものにけどられぬるなめり」などと言っているが、女君を守りきれなかった自分を、いったいどう思っているのだろうか。(七変化)
・枕上の女人は何だったのか、まだわからない。源氏自身の心が紡いだ幻?
ようやくうちとけて心を許しあった恋人との突然の別れはどれほどのショックだったろう。(ぴ)
・心細さと得体の知れない恐怖を感じていた夕顔は、物の怪のせいかわからないが、それらの感情が昂じて突然死してしまう。医学的にも説明はつけられるだろうが、源氏がもっと夕顔の心に寄り添っていれば、こんなことにはならなかっただろうに。(まり)
・廃院でのアバンチュールがとんでもないことになってしまった!源氏が悪夢かと思って目が覚めたら、夕顔は苦しんで息絶えてしまったのだ。夢にでてきた美しい女の面影がようやくのことで灯をかかげた時にちらりと見えたので、物の怪だったのか、生霊だったのか。何にもできなかった右近が泣きわめいても、夕顔は行き返ることはなかった。なんともミステリアスな終末を迎えてしまった。(YOKO)
第32回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2016.5.7)
夕顔「なにがしの院」から「夕映え」までを読みました。
・荒れ果てた屋敷だけれど、仕事をさぼって夕顔とうちとけた時間を過ごせた源氏は、女が素性を明かしてはくれなかったが、満ち足りたであろう。夕顔も幸せを感じながらも、一抹の不安を感じているのが伏線なのだろう。次回も楽しみ!(まり)
・仲睦まじい若い恋人同士のふんいきがほほえましいですネ。久しぶりに登場した惟光が良い味を出しています。少しずつ不吉な予感が迫っていて先が気になります。
(にゃあぞう)
・源氏が名乗っても「海士の子なれば」とはぐらかし、でも後目に見てかわいい感じが今までの女性と違う感じで源氏の心をとらえてしまうのがこころにくい。(SUZU)
・揚名の介、史実では藤原惟光の名前で申文(もうしぶみ)が出されていたようです。式部さんはこの事実を知っていたのでしょうか?(カマボコ)
・怨みの中にも、恋の怨みがあると知りました。怨むほどの恋をしてみたい(過去形か?)です。(還暦女)
・夕顔と共に「なにがしの院」で過ごした光源氏は、不安はあるもののお互い寄り添って良いムード。本当に恋人同士という感じでした。でも夜が近づいてきて…。次の回が恐いです。(YOKO)
・心のままに動いた、実行した源氏。今までには見られなかった行動力。に反してさびれた館で感じた恐ろしさ。いつも人々に囲まれているにぎやかさから、さびしさをヒシと思う。でも心から打ちとけた人と過ごす時には大満足。ふと気づくと帝や六条のことも…。おとなになってゆく源氏。(ファジッ子)
・源氏は夕顔と、ゆっくり親密に過ごすことができて、幸せに浸っている。夕顔の背景に複雑なものがありそうなことや夕顔の不安に深く思いをいたすことができない源氏は、まだかわいい「ぼくちゃん」である。原文からは等身大の源氏が伝わってくる。(矢車菊)
・六条さんの事をいろいろと言っているが源氏君はもう少し考えて行動しなさいよ、と思う。案外流されるタイプ?(W)
・「よく見ると、ずいぶん興ざめなところだなあ。別棟に管理人が住んでいるらしいけど、ここからは遠いみたいだな」夕顔とふたりきりで過ごしたくてここまで突っ走ってきた源氏がちょっと弱気になって、女の子の手前「けど、鬼だってわたしには手出しはしないよ」と強がってみせるところが若くてかわいらしかったです。(ぴ)
・「なにがしの院」に到着してからしばらく“女”の様子が描かれていなかったが、源氏が顔を見せる場面の歌のやりとりは絶妙で美しい。戸惑いながらも源氏に魅かれている気持が浮かび上がってくるようでした。(なにがしのGW)
第31回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2016.3.5)
夕顔「板屋の物音」から「なにがしの院」までを読みました。
・夕顔の住まいのまわりに住む庶民の暮らしが出てきて、興味深かった。昔の人は日の入とともに寝て、薄暗い夜明け前から起き出して働いていたのを知り驚きました(まり)
・夕顔への一途な恋心で、周りも夕顔の心も見えない源氏。夕顔がお気の毒。若いから行動に出るのも早いですね。(にゃあぞう)
・夕顔の家の周囲の生活者に耐えられなくなった源氏は夕顔を牛車にふわりと乗せて「なにがしの院」へと向かう。草が茂って不気味な様子に恐がる夕顔。二人の時間を楽しみたいと気持ちを高ぶらせる源氏。この気持ちのすれ違いは今後どうなるのか。読者も不安になります。(YOKO)
・源氏の一途さが、身もふたもない、聴く耳ももたないあり様が目に浮かぶようです。今までは一歩引いていたような所も有ったように思えたが今回は…。(ファジッ子)
・とろとろとゆっくりしているようで素早い展開もあり、作者は達人だなーと思い入り乍ら終わりました。次回も楽しみです。(敬子)
・夕顔を「なにがしかの院」へと連れ出した源氏は初めての経験に興奮しており、つい女に「ならひたまへりや」などど聞いてしまう。「たをたをとして、ものうち言ひたるけはひあな心苦し」と自分が見ている彼女にそんなことを聞くなんて、デリカシーがないこと! つい忘れてしまうのだが、源氏もじつはまだうら若い青年なのだった。(マンサク)
・夢見る男と現実を見る女の対比がおもしろい。源氏、最初はおもしろがっていたカルチャーショックに耐えられず、やっぱりおぼっちゃまだ。(W)
・「生まれ変わってもきっと一緒になろうね」「こんな不運な身の上でどうしてこの先の愛が誓えましょう」かみあわない歌。ラブラブではないのか、この二人は? 次回へ続く(ぴ)
・理想と願望を素直に行動に移そうとする源氏。ストレートに攻めてくる源氏に魅かれながら、これまでの人生や現実を冷静に見つめる女とのギャップが二人の行く末を暗示しているようだ。(adagio)
第30回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2016.1.9)
「下の品への冒険」から「いづれか狐」までを読みました。
・惟光の「かくかくしかじか」の奮闘と奔走のおかげで、源氏は夕顔の咲く家の女のところに通うことができるようになった。式部さん、「くだくだしい」と言わず、その段取りを詳しく知りたかったです。(まめジョ)
・「雨夜の品定め」でのことが伏線となっていて、あのときの「下の品」の女のことを聞かなければ、源氏は夕顔に惹かれることもなかったかも。これからも色々と話が絡まっていくのだろう。(まり)
・恋に身をやつしている源氏。身分を感じられなく、むしろ人間を感じさせられる場面はいつの世にもある人を思う姿がヒシヒシと忍び寄ってきました。
(ファジッ子)
・関係ないふりして、源氏を通わせることに成功した惟光はスゴイ。このあたりを詳しく書いてほしかった。(W)
・源氏と夕顔のほのぼのとした語らいからは、夕顔の言う「もの恐ろしくこそあれ」はほとんど感じられない。男の身分や素性はしかとはわからなくても、夕顔は「この人は信じられる」という自分の感覚を信じているのかな。
(冬のナデシコ)
・源氏は惟光の馬に狩衣という姿で夕顔の家に通って行く。お互いに名も語らず、素顔も見えない忍び恋に、ついに「二条院」に住まわせたいと思うほど、気持ちは高まる。源氏も気にはしているが、本当に頭の中将の言っていた「常夏の女」なのか、ミステリーのような怪しい関係である。(YOKO)
・夕顔の家の女に夢中になって片時も離れていたくない、どんな面倒なことになってもこの女と一緒にいたい、そんな気持ちと、この女を失ったらどうなるのかという不安を抱えてどっぷりつかっている源氏の様子が心に浸む感じでした。(ぴ)
・恋愛体質で恋愛上手の男女が出会ったらこうなるのかという感じ。心の動きがよく表現されていると思う。(奥)
・夕顔しかみえない源氏が可愛らしく、身近に感じました。お互いの素性も顔さえもよく分からない相手にそこまでひかれる感覚はちょっと?ですが、分からないからこそ本当に心と心でひかれあっているのかもしれませんね。
(ねこおばさん)
第29回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.11.7)
「六条の女君」から「隣家と頭の中将」までを読みました。
・六条の君と夕顔の家の様子の対比が面白かった。打ちとけぬ六条の君とは正反対の、夕顔のつき人たちの生活が生き生きとしていて、源氏がその女主人とまみえる場面が楽しみです。(まり)
・源氏は、強引に口説き落とした六条の女君に「つらき」怨む気持ちにさせてしまいました。今後の御息所の行く末が気がかりです。(殿下)
・六条の家と夕顔の家の雰囲気の対比が描かれていると思った。高位の暮らしも長屋の暮らしも、各々苦労があるだろうが、今回は長屋のドタバタ感が好ましかった。(長屋育ち)
・源氏の君は六条御息所を恋人として充実した生活を送っているはずだが、夕顔が気になって、相変わらず惟光に様子を探らせていた。惟光の話から、夕顔が頭の中将の話していた常夏の女ではないかとひらめいた。源氏の勘の良さも素晴らしいし、惟光の探偵ぶりも面白い。二人のコンビが楽しい。
(YOKO)
・だんだん当時の生活に興味がわいてきました。(e)
・とりあえず女性はくどいとけ、というのがこの当時の礼儀だったのだろうか。それとも源氏だけ? まさにイタリア男のようだ。(W)
・朝霧の中、六条の女君の庭に立つ源氏の君は、さぞかし美しい姿だったのでしょうね。(紫苑)
・高貴な家の女房と、中の家の女房の世界を対比させた描写が生き生きしていて、面白い。惟光の活躍が楽しみです。(ハート)
・今日、読んだところに、童女が「なにがしくれがしと数えしは」というくだりがあった。今でも「なにくれとなく」とか「なにがしか貸して」とか、「それがし」などと使う。昔からの言い回しが現代まで生き残っているのを新鮮に感じた。(万年青)
・霧の朝、わずかに頭をもたげて源氏の後姿を見送ることしかできない六条の女君。会えなくてつらい、会ってもつらい。読んでいるこちらまでせつない気持ちになる…のに、朝顔を手折りたくなっちゃう源氏がいると思うと、まったくもう!です。スパイ惟光の楽しい「ミッションポッシブル」でした。(ぴ)
・六条の女君(上の品)と、夕顔(下の品)の文章自体も上下の感じになっていて面白いです。惟光、やり手ですね。今後の展開に期待大です。女性に名前が無かったというのには、今更ながらに驚きました。(にゃー蔵)
第28回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.9.5)
夕顔の「惟光、隣家をさぐる」から「伊予の介と対面す」までを読みました。
・惟光は隣家の女性(夕顔)について、こと細かに源氏の君に報告している。その女性の女房たちと親しくなって手紙をやりとりしたり、まめな様子が面白い。源氏の君には是非もててほしいようだ。
一方、任地から戻った空蝉の夫である伊予の介と対面した源氏は、任地に連れていかれる前に空蝉に会いたくても会えず、手紙のやりとりは続けている。プラトニックラブで終わりそうである。(YOKO)
・伊予の介の誠実な人柄が描かれていて、源氏よりも素敵だと思いました。でもいろいろな女性を同時に思えるのは心が広いということかしら?(下々の女)
・源氏の心の動き等、登場人物の心理がよくわかる。話の展開、物語の作り方が見事である。(奥)
・空蝉は源氏を逆に翻弄しているのでは? 惟光が源氏のためにと言いながら喜々として「調査」している様子がほほえましい。それにしても簡潔な文章の中に各人物の心の動きが詳細に表現されている。(adagio)
・惟光の大活躍に見を見はり、伊予の介の帰りにあわてて、と内容盛りだくさんでした。惟光のお兄さん目線がいいなと思いました。空?の女心に伊予の介が少し気の毒になりました。(にゃあ造)
・源氏は空蝉とのことを、まだ何とかしたい様子。あれだけ拒まれたのになぜあきらめがつかないのだろうと、不思議に思っていたら、空蝉は源氏からの恋文に時々お返事を書いていたのだった。「源氏の心がすっかり離れてしまうのは寂しい」なんて言って…。自分が傷つかない範囲で恋を楽しみたいのですね。結構したたかなひとです。(秋海棠)
・惟光が固いタイプだったら、さぞかし源氏の行動に頭を痛めただろうと思う。2人、とてもいいコンビだ。(W)
・今日読んだところの最後のところは、主語がくるくる替わって難解だった。また、源氏が空蝉に対して負けたとくやしがっているのが、結構意外でした。(まり)
・本日は展開のところがおもしろかった。惟光の情報収集の様や、その展開をあたかも身をのり出して聞いている源氏の姿が浮かんだ。その後、伊予の介の出現にドギマギする源氏の姿も見えてきたりして。(ファジッ子)
・【伊予の介と対面したことについて妄想する】
大切な後家さんに何かあったと直感して、帰京してすぐに源氏の君に会いに行ったとしたら?
だからこそ、娘は嫁がせて、妻を連れて任国へ行くと言い出したのだとしたら?
実直な大人の男も、ちょっとかわいそうに思えてしまうのです。(ぴ)
第27回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.7.4)
夕顔の「扇の歌」を読みました。
・惟光の乳母のお見舞いに行ったはずが、隣の家の、夕顔の花を歌とともに扇にのせてくれた謎の女性が気になりながら、六条の貴婦人も訪ねる源氏の君。これからこの恋の行方が気になります。(YOKO)
・非の打ちどころのない気品ある六条と、いやしい小家の五条との対比が興味深い。どちらにもひかれる源氏の心の様子を牽制する筆者がおもしろいと思いました。(adagio)
・夕暮の中の夕顔の白い花に込めた思いが美しいと思いました。「それ」はやはり源氏の君なのでは? (下々の女)
・白露の光をまとった夕顔の花は、もしかしたら源氏の君じゃないかと思ったのだけれどちがうかしら?
ずいぶん積極的だね。夕暮れにぼんやり見えた夕顔の花が“それ”かどうか、もっと近くに来てたしかめてごらんよ。
きれいなことばだけれど、なかみはかるいなあ。 (ぴ)
・和歌のやりとりが気になる。その解決をめぐって今も論争があるらしいが原文のまま味わいたいと思った。(奥)
・源氏は謎の家の住人から夕顔の花と歌を贈られた後、期待をしたり幻滅したり面白いほどコロコロと気持ちが変わっていきます。まったくもって読者を飽きさせない主人公です。打ち解けぬ御ありさまの女君ひとすじとは到底いかないですね!(ヒオウギアヤメ)
・随身のきまじめな感じがよく出ていておもしろかったです。さりげない言葉に階級社会が現われていて、仕える人のつらさを思いました。なぞの小家の女性と源氏との恋のゆくえが楽しみです。
(ねこおばさん)
・「朝明の姿」を色々と想像してみる。このころの一番格調高いお屋敷の様子も想像してみると楽しい。(まり)
・この時代、たぶん昼から夕方ぐらいまでは休んでいたのではないかと。本人はよくても随身の人達が大変そう。(W)
・やっぱり来るものはこばまずというか、常に間口を広くしておくのがモテる秘訣なんですかね。それでいて下品にならない。深いなぁ…。(e)
第26回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.5.9)
・源氏の君は乳母(惟光の母)の家にお見舞いに行った。惟光の兄妹たちが、母と源氏の君との涙ながらの交流を見て、気持ちが変わっていく様子が良くわかりました。隣りの家の夕顔の花にひかれた一瞬のエピソードもこれからの物語のプロローグなのでしょう。(YOKO)
・夕刻の下町、むさくるしい風景の中にふわんと浮びあがる白い花からお話が進むと思いきや、ひたすら恐縮しまくる惟光さんによって、夕顔の花のお話は中断。年老いた尼君をみっともないと思っていた子どもたちが、母親はすごい人だったんだと納得できてよかったなあと思います。(ぴ)
・「夕顔」の花は名前負けしてしまうなんということもない花なのですが、源氏は「白き花ぞおのれひとり笑みの眉ひらけたる」と、この花に惹きつけられました。いろんな女性の持ち味に惹かれ、味わおうとする源氏の感性や好奇心は、花に対してもそうなのではないかと思わされました。源氏のそういうところは好きかな。(ウツギ)
・平安のころの暮しのこまやかさが良くわかる気がしました。荒っぽい世の中に生きているものだと思いました。次が楽しみです。だんだん面白くなります。(福地)
・夕顔の花を手に入れる場面と乳母の見舞いの場面はどちらも当時の習慣や暮らしが語られていた。ゆったりした時間が流れ心地よかった。
・夕顔が咲いていた「小家」を感慨深く見つめる源氏。大弐の乳母を見舞った源氏をおそれ多く感じる子どもたち。やがて高貴な香りで母の偉大さに気付く。今回の部分は身分の差を様々な角度から感じる章でした。(Pasta)
・前に出てきた時も思ったのですが、真秀という名前の友達がいた。親は知っていてつけたとしたらすごい。実際、片秀どころか非常に真秀な人でした。(W)
・乳母を見舞う源氏は今迄の姿とは違っている。まだ17歳の子どもなんだなあと思わされました。(みろりん)
・源氏が乳母を思う気持ちが細やかで、幼い頃の気持ちも素直に述べている所も育ちの良さが…。乳母の家族にも理解が生まれたのは素晴らしい!(ファジっ子)
・恋愛の話よりも乳母とのやりとりの方が身近に感じられるのは自分の年齢のせいだと思いますが、源氏への想いは年齢には関係ないのかもしれないとも思いました。(奥)
第25回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.3.7)
・空蝉に逃げられ、その義理の娘である西の君(軒端の荻)と契りを交わした源氏は、小君の手配で逃げ帰ってきた。空蝉の残した薄衣を蝉の脱け殻に例えた歌を手習いのように書きつづったり、小君にぼやいたり、なんだかかっこのいい様子ではない。小君がその紙を姉に届けるが、怒られて二人の間にはさまれ、かわいそうなありさま。(Y0KO)
・英国には蝉がいないとのこと。源氏物語の空蝉の英訳は大変だったでしょう。(雪の月)
・近づこうとすると逃げていく女性に「空蝉」と名付けた命名の妙を感じました。(老人)
・おろかな源氏といちずに源氏につかえる小君、複雑な想いをかかえる空蝉、何も考えていない西の御方、各人物の描写が生き生きとしていて面白い。特に躍動感があったのは「老いたる御達」の場面でした。少しずつ場面が浮かぶようによめるようになってきて 嬉しいです。(ひぐらし)
・another ladyと小君がかわいそう過ぎる。老人のくだりは下の生活と下をかけたのかと思った。(W)
・今日のお話を読んだ限りでは、源氏は女好きで、グチっぽくて、子どもにやつあたりする変態男子という印象ですが、この後どういう魅力が描かれるのかが楽しみです( e )
・源氏はその歌で女を、脱け殻を残して飛んで行ってしまった蝉に例えた。女を恨めしく思っていたのに、ようやくあきらめがついて、気持ちが浄化されたようだ。今日のところを読んで、高貴な男性であっても、品性というものは磨いていかなければ備わらないではないかと思った。今の源氏の品性は?? (沈丁花)
・源氏の一途な思いが届かず意外な展開(困ったことに!)になり、小君も本人もあわてる様や、知るか知らずか老女房の現われる様などから、美しい歌での終わりが良かった。(ファジッ子)
・言葉にするのとは違う心の中の動きが表現されていることに感動します。人は口にすることばとは違う思いをいだいているものだということだと思います。(奥)
・空蝉の名の由来がさいごの歌でわかり、なぞが解けた。御達の挿入エピソードからはそのころのふつうの人の暮らしが垣間見られて面白かった。(まり)
・空蝉の歌でばっさりとこの帖が終わったことに衝撃を受けました。これが千年も前の言葉で書かれた小説なのかと。歌はリアルな自分が現れるもの、また贈答しあうものでもあり、ここでの歌は完全なモノローグ。ただひとり自分を見つめて、想いを封印する女君がここにいました。次の帖の冒頭とのコントラストも絶妙です。(ぴ)
第24回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2015.1.10)
・小君に協力させて空蝉の寝所に忍び込んだ源氏の君であったが、気づいて空蝉は、生絹の肌着姿で逃げ出してしまった。残された源氏とそこに寝ていた軒端荻はどうなるのか?! 源氏が忘れられないのに逃げ出した空蝉、逃げられてぼう然とする源氏、目が覚めてびっくりするであろう軒端荻。三者の心理描写がすごいですね。(YOKO)
・人々の寝静まった寝殿で、密かに進行する夜這いの描写が上手。源氏は後で小君には何ていいわけするのか、次回が楽しみ。(まり)
・源氏、ストライクゾーンが広いのは悪くないと思うけれど、成行きとは言え、せっかく口説いている女の人に対して「御心とまるべきゆえもなき」はひどいと思う。(W)
・源氏物語の世界を想い浮かべながら原文で読む事ができて楽しいと思いました。(奥富)
・空蝉は奥ゆかしく思慮深い反面、すばやく判断し逃げ出す様子はちょっと意外でした。逃げおおせた空蝉はそのあと何を思ったのだろう。(まろ姫)
・源氏は(男は)勝手ですね! ひどいかも…。(N)
・「すべり出にけり」源氏の君への断ちがたい思いからも空蝉は脱け出たのでしょう。
(竹河の左大臣)
・源氏の君はまたもや空蝉に逃げられてしまった。のぞき見した時、大らかな美人の軒端荻も良いなと思っていたのに、彼女はやはり好みではなかった。一方、空蝉の虚像はいよいよ源氏にとって大きなものとなっていく。空蝉は、源氏のことが「心に離るるをりなき」なのに、自分の気持ちを源氏に見せまいと凝り固まっている。空蝉さんは、これ以上どうしても自分が傷つきたくない(いろんな意味で)のでしょう。(無患子)
・たくさんの人が住む中で、お互い気をつかいながらの生活は大変だったろうなと思いました。見てみぬふりの世界でしょうか。(KT)
・空蝉がいなかったからって軒端荻と…なんて。調子良すぎです!誰でもいいのか源氏!!
(みろりん)
・小君が源氏と接する上手さ(と私はとらえました)、源氏の一途さ、そしてその時におこってしまった「もぬけ」の様、このかっこ悪さから“もちまえのスマート”な態度で乗り切る様、ますます楽しみ…→! (ふぁじっ子)
第23回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2014.11.1)
・源氏の君は小君に頼み込んで、あこがれの空蝉を「かいま見」に行くチャンスを得たけれど、義理の娘である軒端荻の魅力にもひかれてしまったようだ。若い男子にはしかたないことのように思われますね。(Y0K0)
・挑戦は子どもまで巻き込み、源氏の強い思いが…。本命よりも碁の相手の方をしっかり見つめている姿が何ともいえない。千々に迷っている心の様がよく書かれているなーと。 (ファジッ子)
・源氏物語って面白いなーと本日は特に思いました。これからが楽しみです。物語の中に出てくる単語をふざけて日常に使えるようになりたいです。(福地)
・狙った獲物は逃がさない源氏…。現代にいたら恐いかも…と思いました。(みろりん)
・源氏の指示で細々と源氏のためにつくす小君がいじらしい。「夕闇の道たどたどしげなるまぎれに」が、情景が目に浮かぶようで心に残りました。女性たちの描写も楽しめました。(二藍)
・のぞき見をしている源氏の心が移ろっていくのが面白かった。当時の生活の様子が描かれていたのも面白かった。 (まり)
・好みでない女性でも、よく見て、良い所をさがしている源氏。これは生まれながらのものか、育ちの良さなのか。(W)
・西の御方のことを「すこし品おくれたり」などと見ながら、御方の伸びやかさ、朗らかさをいいなと思っている源氏のこころの動きは若々しい感性に満ちていて、とても自然なものであると思った。(あぶらちゃん)
・やせやせちゃんのことをね、目は腫れぼったくて、鼻筋も通ってなく老けて見え、艶やかな美しさは見られない、言ってしまえばブス寄りのルックス…つてあんまりです。でも、つぶつぶちゃんには見られない人間性を見つめる源氏の君がいます。んー、でもこっちの若くてぴちぴちのほうも、これはこれで捨てておけないんだよー。よくばりさんですね。(ぴ)
・雲居雁をイメージさせる軒端荻を登場させるとは、執筆の順を思わず考えさせる物語です。 (成立論)
第22回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2014.9.6)
「帚木」を読み終えました。
・帚木とは遠くから見えるが、近寄ると見えなくなるという信濃国の国原にあったという伝説の木だとか。源氏にとって空蝉は近寄れるかと思ったのに消えてしまった女だと嘆いています。そう簡単につかまらないから想いも深くなるのでしょう。 (YOKO)
・なかなか今の世界に住んでいる者には理解のむずかしい女ですが、手紙くらいは欲しいというのはわかります。(N)
・私達には理解できないが、当時の中流の人達はこれを読んで「わかるわ~」と言っていたと思う。小君もちょっとしたたかかも。 (W)
・空蝉に拒まれて動揺し、「こんなことは初めてだ」と嘆く源氏は、なんだかとても子どもっぽくて、かわいらしく感じられた。大人の男性になる第一歩でした。 (秋海棠)
・中の品の人妻との恋を当時の読み手はどのように感じたのでしょう。(衆道)
・源氏の使いを果たせずにおろおろと邸内をうろついている小君。傷心の源氏になでなでされて、君をなぐさめているつもりだったのに、置いて行かれてさびしい小君。こどものかわいさもいっぱい描かれていました。(ぴ)
・源氏の初めての挫折。振った女君の複雑で屈折した恋心。この先の二人のかけ引きはどうなるのだろう。(まり)
・自分の無力さを自覚して大人になっていく。源氏も同じですね。(さばれオバさん)
・空蝉の心情、わからなくもないけれどプライドにがんじがらめになっているようで、うまく感情移入できませんでした。小君の一途なふるまいが可愛い。(ひぐらし)
第21回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2014.7.6)
「したごころ」から「使者小君」までを読みました。
・源氏の君は空蝉の手紙を渡すために弟の小君を手なずけて、子どものように世話をしたり連れ歩いている。本命の女君との再会を果たせず、悶々としているが、小君のことも可愛く思っている様子が面白いです。 (YOKO)
・幼い小君の純粋さかわいらしさがイキイキと描かれていて「うち笑みて」などかわいい笑顔が思い浮かぶようです。こんな弟が欲しかった…。源氏がかわいがるのが理解できます。それにしても、こういう女はイライラします。でもこういうタイプに男は弱いのでしょうかね。 (N)
・小君がいいように利用されている。しかし源氏も本気でかわいがっているのでよしとしよう。 (W)
・めぐり会う時がこの時でいたずらに二人を悩ませた様がとても美しく示されていると思った。この時代の文の大切な役割!!! (ファジッ子)
・源氏と紀伊の守のやりとりの奥深さ、“霧ふたがりて”“親めきて”などの言葉の美しさなど、原文ならではの魅力を堪能しました。(adagio)
・女君は源氏から重ねて文をもらっても、うちとけた答えを書かない。源氏は恋心をつのらす。女君が源氏のもとに飛び込んでいかないのにイライラするという意見もあったが、私は空蝉さんて普通の女の人だと思った。源氏の「本気」だっていつまで続くかわからないのだから…。小君に冗談をいう源氏がとてもおかしかった。(合歓)
・不自由な身だからこそ、愛が燃えあがり深まるのだと思います。うまくいく恋なら「お話」にならないのでは。(いい君、小君)
・中の品の女が空蝉と呼ばれるようになるのはなぜなのでしょうか(ふせや)
・幼いままに源氏の君に憧れ、盲目的に従う可愛らしい小君をはさんですれ違いまくる源氏と女君。会話パートが多く、テンポが良いところでした。(ぴ)
・年の離れた姉弟の行く末は哀れな結末が予想されそうですが、どうなりますか。(まり)
第20回 ゆかり雲 瞬間感想文 (2014.5.10)
「口説き上手」から「心のこり」までを読みました。
源氏の君に突然、侵入された空蝉の動揺はいかばかりだったでしょうか。拒みながら結局一夜を過ごしてしまった二人。二人の気持ちのかけ引きが興味深かったです。翌朝の現実感あふれる描写に、式部の文才のすごさを感じました。 (YOKO)
一晩限りの逢瀬… 一度経験してみたかったな~。 (TY)
空蝉の心を理解できない源氏のジレンマを感じました。 (小君)
今日はすべて、ひとことひとことが刺激となり想像が拡がるのを気づかされた自分が居ました。ことばを発見する楽しみが加わりました。 (ファジッ子)
空蝉と別れたあと、もの思いにふける源氏の姿を読んで、なんとか源氏に対する信頼がつなぎとめられました。 (みずき)
空蝉さん、一夜だけでもときめきが欲しかったんだと思う。源氏よりもかなり年上だと思っていたけれど、けっこう年が近かったのかも。 (W)
月は有明にて~
光は失っても、くっきりと見える月。源氏の君には女君の、女君には源氏の君の面影なのかな。 (ぴ)
空蝉の心の動きが過不足なく書かれていた。「何ともおぼえず」はぎょっとしました。彼女の心情があわれである。 (まり)
「西面の格子」を「そそきあげる」という表現が気に入りました。また「何心なき空のけしきも、ただ見る人から艶にもすごくも見ゆるなりけり」(見る人によって景色は違ってくる)という言葉は心に残りまし。 (あけぼの)
千年前に「何ともおぼえず」と書いた紫式部はすごい(今のいい意味で)と思う。あまりに強烈で今日一番心に残りました。 (N)
第19回ゆかり雲 瞬間感想文(2014.3.1)
帚木の「姉弟」から「ちさやかなる人」までを読みました。
・紀伊守の邸に方違へで泊まった源氏の君は紀伊守の義母となった空蝉の寝所にこっそり忍び入り、連れ出すことに。いよいよ源氏物語らしいエピソードが始まりました。
(Yoko)
・「源氏のにほひ」とはどんな香りなのか興味深々…。先が楽しみになってきました。
(みろりん)
・現代語訳で読んだときには、一度も出会ったことのない女君のところに忍び込んでいく源氏に全く好感を持てませんでしたが、原文で口説き文句などを読んで雰囲気を味わうことが出来ました。ただし「源氏がただの色男とは違う」という先生の御説にはまだまだ頷くことはできません! (沈丁花)
・空蝉物語には「光源氏」でなく「君」と表現されています。不思議な事と思います。
(帚木三帖)
・源氏物語のすごさがだんだんわかって来た気がして嬉しい一日でした。
(K)
・今回は寝殿の図をいただいたので状況が見えるようでした。「動もなく」という源氏のしぐさが目に浮かぶようで、この言葉は深いと思いました。 (adagio)
・源氏の若者らしい思い切った行動が思いがけず成功したわけであるが、その経緯は原文ならではの味わいがあって、思わず引き込まれる魅力があって面白かった。(まり)
第18回ゆかり雲 瞬間感想文(2014.1.11)
長い「雨夜の品定め」を終えて今日は「源氏と女房たち」から「噂話」までを読みました。
・「品定め」とは違って、源氏の心の動きがよく書かれているところが面白く、前回までとは違った雰囲気が良い。(まり)
・思ひあがるむすめの今後が楽しみな物語の開始です。(輝く日の宮)
・源氏が静かに話を聞いていた今までと全く違い、行動に動き出した様子から今後の展開にわくわくする。ここに来て、今までの話が生きてきたので復習しないといけないか??
(ファジッ子)
・皆で話し合うと、思いがけないことに気がついて楽しい。(福地敬子)
・雨夜の品定めの一夜を過ごした光の君が久しぶりに葵の上を訪ねたものの、相変わらずのクールぶりにがっかり。方違へをいいことに紀伊守の屋敷を訪れます。左馬頭の言っていた中の品の女たちに触れられると内心喜んでいたものの、自分の噂話にまたがっかり。このあとが楽しみです。(YOKO)
・いよいよ空蝉で、とても楽しみにしています。(みろりん)
・「雨夜の品定め」が長々と続いたあと、再び場面が生き生きと動き出してきて面白くなってきた。源氏は周りの人々を魅了するとてもチャーミングな男性になっているようだ。
(水仙)
・紀伊守の苦労話。
おそらく源氏の方がかなり年下だろうに悲しき身分社会。(W)
光:こう宮中にばかり籠っていたら、さすがに左大臣のお爺どのに悪いよなぁ…、きょうあたり、あちらに行っとかなくちゃだよなぁ。
ぴ:いやいや、左大臣への義理じゃなくて、葵さんのところへ行ってよ。
光:女ならみんな私を見てぽぅっとした顔を見せるのに、彼女だけはお高く取り澄まして、取っつきにくいんだよね。あちらのハイクオリティな女房たちにちょっかい出してるほうが楽しいよ。
ぴ:ってか、光君さま、どうぞとあてがわれた妻でなかったら、きっと語っていた甘い言葉があるのでは?姫君の心を溶かす努力ってなさったの?
光:…ん? えっ、きょうは方角が悪い? しかたないなあ(いそいそ)。
(=ぴ=)
第17回ゆかり雲 瞬間感想文(2013.11.2)
「蒜食いの女」を読み終えてやっと第1巻が終わりました。第二巻でまだ帚木は続きます。
・品定めはようやく終わりました。いろいろな女性が出てきて、紫式部の描き出す人物像の多彩さに驚きました。やはり有名な箇所は面白い! (まり)
・最後まで読み通せて嬉しい。少しずつ文章を楽に読めるようになってきました。次が楽しみです。(にんにく女)
・読み終わりました。人生の先輩方の話をじっと聞いていた光の君。次からは君の物語が展開しますでしょうか? 楽しみです。(YOKO)
・蒜食いの女は中将のムチャぶりに見事に答えたと思う。良いオチだった。そう思うのは自分も式部丞と同じく「下の下」の身分だからだろうか。(W)
・やさしい心と弱い心の常夏、実利的と賢さの蒜食いの物語でした。(文のはし)
・上々の人と下々の人との表現がおもしろかった。考えが及ばない格差のある世界。今にも通ずるところも。(ファジッ子)
・式部丞が語ったのは、等身大の女と男の話でとてもユニークでした。現代語訳で読んだときは感じなかった面白さ、おかしさを原文では味わうことができました。式部丞の話を度外れた話だと本気にしない君達の感覚こそが不思議でした。 (つわぶき)
・蒜食いの女は教養もあり現代に生きていれば、女官僚で活躍できると思いました。
(下流女)
・蒜食いさんが蒜を服用したのは、下々のものだったから。目からウロコの瞬間でした。民間療法の方が貴族のやっている加持祈祷よりよっぽど治療効果があがりそう。そして
「ささがに」と「ひるま」の歌のやりとりがこんなにすてきだったとは。ここでも男と女はすれちがっているけれど、蒜食いさんの誠実な人柄に触れました。(ぴ)
・式部の話は下世話でとても楽しかった。又、彼が申し述べることをきいていると、現代人の心のありようが巾がなく深くないと思わせられた。 (福)
・まわりに気をつかい、太鼓持ちのような式部丞に親近感を覚えました。才能があってもそれを活かせていない女性、娘を嫁がせようと懸命な身分の低い博士、生き生きと身近に感じられて楽しかったです。(寝り猫)
・日本人が自分の能力をひけらかしたりせずに、ひかえめにしているのが良いということが、平安時代に既にそうだったことに驚きました。日本人はなぜ他の国々と違うのか、不思議です。(N)
第16回ゆかり雲 瞬間感想文(2013.9.7)
「木枯らしの女」が終わり、「常夏の女」の途中まで読みました。
・主語がめまぐるしく変わるために源氏物語はいつもわからなくなり続きませんでした。今日のように教えて頂いて、天下の源氏がスラスラとわかるようになりたいです。(福地)
・左馬頭が上人のあとに付いていってしまったため、見てしまった光景がまるでまんがの一場面のようで素晴らしかったです。左馬頭にはつらい光景でしたが。(YOKO)
・すきがましきあだ人の行いがどういうものか良くわかる物語でした。(三位中将)
・指喰いの女の一途さとは対照的な木枯らしの女の変わり身の早さにびっくりしましたが、左馬頭の二人の女性の形は違うものの主張の強さとはやはり対照的な、常夏の女の主張しない主張にびっくりしました。色々な女性が登場してくる面白さがあります。(ゆみっち)
・繊細で気遣いのある女性に対し、男は鈍感で自分本位。千年の昔も現代も変わらないんだろうなあ。(adagio)
・常夏とはナデシコのことだと初めて知りました。指喰いの女、木枯らしの女、常夏の女、どの女も違った意味で健気であり、いとおしくなりました。「常夏の女」では中流貴族の女性の生きづらさに衝撃を受けました。(マンテマ)
・左馬頭と中将の性格の描き分けがいい。どちらの場合も男と女の思いのすれ違いは若気の至りとは言え、女の方が哀れを誘う。物語の遠いさきの伏線になっているそうで楽しみはまだまだ続く。(まり)
・左馬頭も中将も、お坊ちゃんだなあと思いました。現代にもこういうお坊ちゃんっていますよね!(みろりん)
・「痴れ者」は中将さん、あなたですヨ。常夏さんのSOSが読み取れなかったうえにとんちんかんなこと言って、結局これっぽっちも彼女の心に寄り添っていなかった。北の方の嫌味もこわかったけれど、あなたの無関心が彼女を「かき消ちて」しまったのです。(ぴ)
・今回の二話は相反することで心がゆさぶられた。左馬頭と中将の人柄の違いもあるが、上人とは全くちがう育ち方をしたのではと思われる。ドン(感)な心も…。(ファジッ子)
・木枯らしの女は後ろの方を読んで、大森さんの説もありかと思いました。結局は自分に合う人を選べと言うことにつきるでしょう。(W)
第15回「ゆかり雲」瞬間感想文 (2013.7.6)
「指喰いの女」を読み終えました。
・「指喰いの女」はいたくできた人だし、自分の意志を死んでまで貫き通せる強い人だと思いますが、なぜその相手が左馬頭だったのかがどうしても不思議です。(ももぱん)
・思いつめた一途な女ごころはすごい! でも品定めしている男たちには理解できない。式部はそのどちらも描きわけているのはすばらしい。(まり)
・軽々しい左馬頭に心底から愛をそそいでいた女性の気持ちが濃く表れている。亡くなってしまうなんてショック! 綱引きのあいだにもどうにもならなかった幼稚さが悲しい。 (ファジッ子)
・「指喰いの女」とはどんな人なのかと思っていましたが、嫌なこと(男の浮気)はイヤと言える、正直で情の深い女性でした。ちょっと女を懲らしめてやったら自分の主張を飲み込むだろうなどと考える左馬頭を恋してしまって、引き返せなくなってしまったのが、返す返すも気の毒でした。(日々草)
・素直にお別れしたくない思いを歌に託すことができれば、命を失うような切ない流れにならずにすんだのでしょう。今も昔も人はそれ程変わることもないのかもしれません。
(ゆみっち)
・頭の中将のすきがましきあだ人振りが、指喰いの女にどの様な結果をもたらしたのでしょうか。
・いつでも自分の心を歌で表さなければいけないとは、平安時代はなかなか大変だったんだなあと思いました。(みろりん)
・雪降る夜はてっきり他の男がいるかと思った。指喰いの女は左馬頭にはもったいない女性だ。(W)
・心から深く愛していても、自分がどうしても曲げられないことをつらぬき通した“指喰いの女”にはとても共感しました。もしかしたらそういう自分にも悩んでいたのだろうと思うとさらに親近感が湧きました。(adagio)
・たしかにわたしはブサイクよ。でも、あなたのためにこんなに努力しているわ。あなたに恥ずかしい思いなんてさせないわ。どうしてわたしだけを愛してくれないの? キィ―ッ! こんなにつくしてもこれっぽっちも通じない。わたしの思いっていったい何だったのかしら。指喰いちゃんのプライドです。(ぴ)
・左馬頭はその女が一生懸命尽くしてくれているのに、理解せずに浮気心を捨てられなかった。その女もプライドが高く嫉妬を抑えることが出来ず、指をかじるという壮絶なケンカの果てに別れ、そのあげく、左馬頭を思いながら亡くなった。現代もありそうな不器用な女と適当な男の物語なのかな~。
第14回「ゆかり雲」2013.5.11 瞬間感想文
帚木「女の心変わり」から「指喰いの女その1」まで読み進めました。
・なかなか勉強になりますが、若い頃に勉強したかった内容ですね。これから話がどう展開するのか楽しみです。(N)
・工芸、美術、書のホンモノの見方は現代にも通じるものだと思いました。(K.I)
・本当に指を喰われてしまったら馬の頭は世の中を渡ってゆけるのでしょうか。次回が楽しみです。(集会所)
・何ごともうわべだけでごまかせない、と左馬頭の例えは、教訓となりました。話はまだまだ面白くなりそうで、また、源氏の打ち明け話も楽しみです。(まり)
・例え話をひき出しているおもしろさ。角度を変えて判じてみると、様々に変わる可能性が。源氏の在り方(聞いているのかいないのか)もおもしろい書き方だと思う。(ファジっ子)
・「帚木」なかなか教科書などでは深く取り上げられないようですが、面白い章かもしれないと思いました。源氏物語、いや紫式部の多才ぶりがのぞいていました。(ノリリン)
・左馬頭は相変わらずいろいろと語っているが、工芸・絵・書の例えを持ち出してきて、妻選びでは、見ばえに惑わされてはいけない、まことの心や実質が大切であると言い切ったあたり、真面目な人なのだなーと良くわかった。 (ユリノキ)
・中将は遊び人かと思ってたけれど、左馬頭の話に食いついているので、実は案外純情なのではと思う。次回、指喰いの女、楽しみです。(W)
・男が言いたい放題、好き勝手に語っているなあと思いつつ、本質を言い当てているなあと感心しました。やはり女性が描いた物語だからでしょうか。紫式部の才能を感じました。(adagio)
・奇抜で目を引くだけのものは本当の工芸や芸術ではない。雰囲気だけ上手そうに見せてもきちんとした下地がなければ薄っぺらなものでしかない。…って芸術論が女性論と一緒になるのか―。失敗をくりかえしてたどりついたのね。左馬頭さん。(ぴ)
・左頭頭の話はますます調子づいてきます。工芸、絵画、書道と話はふくらみますが、言いたいことは女性のことです。どんな女性が自分にとって大切であるかを語りだします。人生経験の深い左馬の頭の話を夢中で聞く頭の中将、半分寝ながらも耳をそば立てる光の君。楽しそうな様子です。 (YOKO)
第13回ゆかり雲(2013.3.9) 瞬間感想文
帚木「妻の条件」の後半から「甘えた妻」までを読み進めました。
・左馬頭の夫婦をめぐる話は現代でも通ずる話ですね。夫婦喧嘩は小出しにやっておかないと、我慢してたのが爆発して出家してしまったという妻の話は今日でもありそうで怖い話です。(YOKO)
・平安の世と現代では、世の中のしくみや男女の立場は大きく異なっていましたが、理想の妻の姿は昔も今もあまり変わらないのですね。(adagio)
・妻を対比させ、かなりきびしい見方を! この時代の複雑なかかわり、仏教の見方など、奥が読み取れる楽しさ…。(ファジッ子)
・馬の頭の女性論総論は、以後の巻々にその人物が書かれてくるのでしょうが、なかなかムズカシイお話です。(竹取翁)
・「すごき言の葉」の内容が気になる。いったいどんな事だったのか。
この時代の女性は出歩かないので、家出はかなりすごいことだと思うけれど男からすると「甘い」になるのだろうか。(W)
・左馬頭の長い語りは、一旦「誠実な、情緒が安定した妻が良い」というノーマルな線に落ち着いた。やれやれと思ったら、まだ続きがあって、今度は夫に未練がありつつも「あはれ進み」て尼になってしまうような妻のおろかしさを、面白おかしく語る。なんともおしゃべりな方。夫選びの観点から言わせていただきますと、このような方は女性からは支持されないタイプでは?! (春黄金花)
・男の言い分や見方を女の紫式部がながながと書き綴っているのには驚く。男の本音をどのような機会に聞き知ったのか興味のあるところです。このあとの展開も楽しみです。(まり)
・ずいぶん都合のいいことを並べているけれど誠実な落ち着いた奥さんが良いんだってね。さてここで私は問いたい。妻にそういう資質を求めるアナタは誠実な頼れる夫君でいらっしゃるのですか、と。自己陶酔で尼にまでなっちゃう女性を左馬頭に語らせているのが、女性の紫式部さん。毎度のことながらすごい。(ぴ)
・人間の心は1000年たっても、大きな変化がないものですね。科学は進歩しても人間の心まで自由にはできない。いつか心まで科学で自由自在にできる日がくるのでしょうか? でもそれはいやだなあ…。 (N)
第12回ゆかり雲(2013.1.12) 瞬間感想文
今日はまず、関弘子さんの朗読で「桐壷」の最初のところを聞いてから、「帚木」の、「家の主人」「妻の条件」の段を読みました。終わってから上野毛の中華料理店「吉華」で新年会をしました。
・もの定めの博士の女性論はとどまる所を知りません (たもたるるもの)
・現代の妻の条件と、あまりかわらない点に驚きました。少しは夫の話を聞いてあげなければと思いました。 (あはつかな妻)
・左馬頭の語りは、女性に対して妻とはこうあるべきという教えのような気がしました。それにしても男女の仲は楽しくもむずかしいなあと、つくづく。(adagi o)
・関さんの朗読は、そのころがほうふつと想像されて、おっとりとした雰囲気がよくわかりました。本文では左馬頭の思い描く理想的な妻像と、実際のすれ違いの夫婦のギャップによるもどかしさが伝わってきました。 (まり)
・貴族の妻はヒマなのかと思ったら割と忙しいらしい。自分はいつも「耳はさみ」だ。(w)
・妻選びの難しさをだらだらと語る左馬頭と、それを聞く男たちの姿は、女の井戸端会議のようだ。日本の現代小説で、このような場面は読んだことがないなーと思った。(南天)
・時代の背景、細かな点にも興味をそそられるものが…。使われていることばにも変化が感じられます。これからはどうなる?? (とし子)
・左馬頭の下世話なとめどない話が面白いです。結婚したばかりの源氏がどんなことを思って聞いているのか気になりますが。紫式部という女の人が、男から見た女性(妻)の理想を書いているのも面白いです。 (ねこおばさん)
・昔の発音の源氏、面白かったです。書いた通りの発音であること、「ハ行」が「F」になること、「チ・ト」が「ティ・トゥ」になること、韓国語のように発音することばなど、興味深く聞きました。
第11回「ゆかり雲」 瞬間感想文 平成24年11月10日
午前中は有志で五島美術館の源氏物語絵巻を鑑賞してきました。
何年もかけて復元した模写により、原画ではわからなかった色彩や構図が
浮かび上がり、興味深かったです。
田中先生の解説を聞きながら、より深く鑑賞できました。
今回の勉強会は「雨夜の品定め」でした。
情景が目に浮かぶようで、楽しい場面でした。
以下、瞬間感想文をお伝えいたします。
今回も、瞬間だからこその素敵な感想をたくさんいただきました。
*****************************
◆ 男が女の品定め。紫式部はよく男心がわかったものだと思います。
K
◆ 頭中将の「すぎがましきあだ人」振りがどう書かれているか、次回以降が楽しみです。
信濃の箒木
◆ 4人の異なる階級の男を登場させ、階級により違う女性観を語らせる。非常に巧みです。おもしろいです。
N
◆時代が違っても男の思うことはあまり変わらないらしい。葎の門に住む人は父兄が居ないのだと思っていましたが、その点は今と価値観が違うらしい。
渡辺
◆ 最高の女性たちに囲まれて育った源氏が「雨夜の品定め」ではほとんど聞き役に徹している。葎の門の女性の考察は、源氏はどんな風に感じたのだろうか?
Adagio
◆源氏物語は「あさきゆめみし」などのマンガで読んだりしていましたが、原文で読んでいくと色々と深いところがわかり、とてもおもしろかったです。
みろりん
◆男性達が、理想の女性というものを得意げに語り合っているのが目に浮かぶようでした。それを聞いている源氏がこの話を参考にして今後女性を選んでいくのでしょうか・・・楽しみです。
一口まんじゅうおかき
◆「葎の門」なかなか趣のある章でした。まだ町中にかつての栄光を感じさせる庭の広い屋敷があります。なにかロマンを感じる私です。この感覚は私の年代位までかしら?
ノリリン
◆「いかではた、かかりけむ」って思わせる意外な一面を持った女性になりたいな。それから「くつろいだときにだらしなくならない」すごくハードルが高いけれど、できたら素敵。
ぴ
◆本日は「とても貴族」な面が学べたと思います。発想、考え方、表現が刺激的でした。対比されていたり、平安時代の最大の賛辞が最後に!!
とし子
◆雨夜の品定めは、光源氏と頭中将のボーイズトークに左馬頭と藤式部も加わり盛り上がってきます。光源氏の、ちゃちゃをいれながらしどけない姿で聞いている様子。イケメンはなんでも似合いますね~
YOKO
◆一回休んだ間に、物語の雰囲気ががらっと変わっていて楽しいです。男4人の恋愛談、恋愛そのものの基準が今とは違っていて面白かったです。男性目線の話を女性が書いている視点も興味深いです。今回は「かたかど」がとても心に残りました。
ねこおばさん
第10回ゆかり雲(9月1日)瞬間感想文
今日は「帚木」第1回目でした。
光源氏も17歳になって、義兄弟の頭の中将と女性談義するようになったのですね。
この二人の親友であり、ライバルである関係性は興味深いです。(YOKO)
初参加ですが、とても楽しかったです。古文は受験以来で、難しい所も多くありましたが、
田中さんの説明がわかりやすかったため、何とか理解できました。次回も楽しみに
しています。 (渡邊)
帚木に入って光源氏という人物の描写が細かく深くなってとても興味深い。
頭中将の源氏をうらやみながらしたっている様子がほほえましく感じた。
好感が持てる人物である。(adagi o)
帚木の始まりは、今ならばガールズトークならぬボーイズトーク。とても楽しそうです。
女性にとっては耳の痛い話や反省させられる点も多くありましたが、初々しさいっぱいの
内容でした。 (裕美子)
他人の恋文みたいなんて、昔の人もゴシップ好きなのね。 (すず虫)
源氏も頭中将も17才にして、女性のことがよくわかっていると思います。
現代の17才の青年にこれだけのことがわかるでしょうか? (ホウキおばさん)
帚木に入り、今回は頭中将が大活躍。左大臣家の父子、大殿と頭中将は
2人ともお人よしで、なんとも愛すべき男たちです。
源氏が頭中将に付きまとわれて、苦笑い(?)したり、
調子を合わせたりしている様子がおかしかったです。 (風船蔓)
頭中将と源氏が一緒に遊んでいる様子(女性への評価)が
描かれているのはなかなか面白かった。
(のりりん)
「帚木」は「桐壷」と打って変わった雰囲気で驚きました。
でも源氏は、かつては帝が庇護者でしたが新たな大殿という保護者を得ました。
母には早くに死なれましたが、父性には恵まれていて、その点では幸せものと言えます。
彼はそれに応えていくのか、これからの展開が楽しみです。 (まり)
「忍びたまひけるかくろへごと」とか「あやにくにて、さるまじき御ふるまひ」とか
なんか怪しい…?
源氏の君と頭の中将の若者らしいおしゃべりがとても楽しい。
頭の中将はなんだか犬がじゃれついてくるところみたいだな、と思ったりして。
(ぴ)
難しい所にさしかかって(文章が)ちょっと退屈。
人の見方へのだんだん深い所へ入ってきた感じ。でもいいこといっているな。 (ぞうのハナ)
「帚木」に入りました。文章が難しい。
でもじっくり読むと今にも通じるイキイキとした内容でおもしろい。 (N)
第9回「ゆかり雲」(7月7日)瞬間感想文
今回は、帝と大臣の後半から、結婚、さまよう魂までで、桐壺を読み終えました。
源氏の時代のことば、今の時代と違うのかしら?
言葉ってどのように変化していったのか知りたいです。
書き言葉と話し言葉の違いがあったのかしら? (さくらんぼ)
みんなから諸説紛々で面白かった(うさぎの耳)
いよいよ桐壺の最後となりました。元服し成人した光源氏は
左大臣の姫君と結婚しますが、なかなか藤壺のことが忘れられません。
少年から青年へどんな物語が待っているのでしょうか?
やっと一帖が終わり、まだまだ長いですが、楽しみです。 (YOKO)
源氏は結婚したにもかかわらず、花嫁に気がなく
更に好きになってはいけない父のお嫁さんの藤壺に恋心を募らせていく。
新婚時代からこんな状態なんて辛いことですね。
かたくなに心を閉ざす新妻の気持がよくわかる気がしました。
(神戸プリン明石焼きせんべい)
元服、結婚という変化のなかでも、源氏のいちずな恋心が
また周りを動かし、さらに変化を生み、それがさらにさらに恋心は深まり、
これからは? (とし子)
桐壺帝もどこか妖しいぞ!
葵の上は可哀想に思います。 (さまよえる高麗人)
桐壺を読み終えて、今後の光君の行く末がとても気になります。
「ゆかり雲」は古語の美しさを味わう楽しさはもちろんですが、
物語の登場人物の心情などを憶測して語り合う雰囲気が楽しいです。
(adajiо)
紫式部の物語の運びのうまさに驚かされました。
1年ぶりのお教室、皆様が思い思いの言葉で自由闊達に話されていて、
とても楽しかったです。 (ノリリン)
源氏と左大臣の姫との寒々しい夫婦関係ですが、「心にもつかず」と
源氏に思われている姫が気の毒でなりません。
藤壺への思いを絶てない源氏、結婚の重みを感じてもいない若すぎる源氏は
「あなたを大切にします」という気持すら、左大臣の姫に対して表していないようです。
それでは、姫だって心の開きようがありません・・・。 (ムクゲ)
今日のところを読むまでは、葵の上の方に非があってという意識だったのが、
180℃変った感じです。
葵の上は一番の被害者なのでは・・・と思えて、可哀想になりました。
帝と左大臣の親ばか加減があわれです。 (猫おばさん)
似げなくはづかし
左大臣の姫君は、源氏の君にひと目ぼれをしました。
そしてその一瞬で、彼の心を占めているのは他のひとであると
直感してしまいました。
大好きになった人の心が、手の届かない所にあるということを
受け入れられない姫君は、殻にこもるしかなかったのです。
お話の中に入り込んで、姫君の相談相手にあってあげたい。
源氏の君にお説教してあげたい。そんな雨の日でした。 (ぴ)
光君と左大臣の姫君の二人の、幼いための心のすれちがいがもどかしく、
もっと世慣れた大人なら、もう少しお互いを思いやることができたのではないか、
それなりに幸せを感じることもできたかもしれないと残念な気がします・・・
・・・と思わせる紫式部が上手です。 (N)
第8回「ゆかり雲」瞬間感想文
5月12日は、「少年源氏の恋」から「帝と大臣」の途中まで読みました。
源氏が元服して、いよいよこれから物語がどんどん進み
おもしろくなりますね。楽しみです。(N)
伊勢の物語、在五の中将とは一段と異なる源氏の初冠です。
源氏が美しく立派に成長していく、
その成長を喜ばしく、一方で淋しく思いながら見守る帝がほほえましい。
帝の心情表現が見事で美しい文章でした。(adagio)
少年となった源氏が義母藤壺に思いを寄せる様子が初々しかったです。
そしていよいよ元服式を迎えることになりました。
亡き桐壷の更衣を思い出しながら、息子の晴れ姿に涙ぐむ帝の
父親らしい様子に心打たれました。(洋子)
元服の儀式の描写がとても好きです。
帝の様々な想いを散りばめながら壮大な絵巻を見るような
あでやかさがあり、映像を越える映像美を見せられた様な
美しさがありました。 (yumi)
まだ源氏の思いはあまり語られてはいないが、
藤壺との初恋の場面は微妙な心の動きが綴られていて面白かった。
また元服の時の帝の心遣いと式の最中の思いも、
数少ない言葉でみごとに表されていて、
式部のストーリーテイラーとしての才能に驚くばかりでした。(まり)
源氏と藤壺の仲はこのあとどのように進展していくのか
今から、ドキドキします。
元服式の場面の見事な描写や、帝が「源氏はおとなの髪型が
似合うだろうか」と女親のように心配するところなどを
味わえたことが今日はとても新鮮でした。(ユリノキ)
一回お休みした間に、ふさぎこんで涙ばかりだった帝が
すっかり父親(母親もかねて)になっていて安心(?!)しました。
藤壺が入内しても、心は源氏を思っている親としての帝が良いですね。
親ばかでも子どもの心を知らず、これからが楽しみです。(にゃー助)
光君と輝く日の宮こそお似合いなのに
ああこの二人はどうなってしまうのかしら・・・と
ぎゅうっと読み手の気持をつかんだところで、元服、そして大人の世界へ。
どうやら結婚の準備もできている様子。
左大臣は「うちの娘もなかなかの器量で・・・」なんてほのめかしていたのでしょうか。
でも藤壺の宮の面影がちらついて、ほかの女性に興味がもてなかったのではないかな。
なんたってまだ12歳のボクちゃんだし。
それにしてもたった一文でみんなが沸く弘き殿さん、すごい存在感ですね。
みんな彼女のことが大好きみたい。 (ぴ)
ゆかり雲 第7回(2012.3.3)
桃の節句のよき日、「若宮の微笑」から「藤壺入内」まで読み進めました。
男性2人が参加してくださいました。
〈瞬間感想文〉
当時の原文を読むときの音の響きが気持ちよかった。
即席に理解できない物語だなァとツクヅク思いました。(ユカリのフリカケ)
いつまでたっても亡くなった更衣のことを忘れることが
できなかった帝。でも、ついについに愛しく思える人が
出現されて良かったと思いました。(ロールケーキ桜もち子)
あれだけ心に想いつめていた桐壺更衣も、藤壺の登場で
忘れ去られていくのですね。時は流れ、戻るすべもないのですね。(桃の花)
物語なのに、現実のように議論させてしまう「源氏物語」は
ただ者ではないですね。男性の参加もあり面白かったです。(トヨ)
帝にいつくしまれて御子は賢く成長されました。御子の処遇も
熟考の末に決められた帝は、今度はご自分の幸せのために
藤壺を迎え入れました。今回は安堵の連続。
物語はいっとき、調和の世界に落ち着いたかのように見えますが
この先いかに? 次回がとても楽しみです。 (春待ち草)
光の君がなぜ源氏として臣下になったのかの理由がよくわかりました。
父の帝は息子の行く末を心配していたのですね。
ところが帝が桐壺の更衣に良く似た藤壺に出会うと
だんだん気持ちが変わっていく様子がわかりました。
現実の美女にはだれもが心動かされるものなのでしょうね。(洋子)
藤壺さん がんばって!!
弘き殿に負けないで、たくさんの身内(親族)の
生活を立てるために。一ファンで~す。
帝の若宮のゆくすえを思う気持ち、悩む気持ちが痛いほど表現されている。
相人が突然に出てくる展開には驚きが・・・。
若宮に対する帝の心が定まり、帝自身の変化が・・・。期待の変化が・・・。
これから多くの楽しみに・・・。(とし子)
子の行く末を案じ、子育てに悩む父親としての帝と、
桐壺の更衣の面影を宿す女性に心を奪われていく男性としての帝の
二面を語る物語を今回は楽しめました。
次回はいよいよ佳境に入り、期待がふくらみます。(まり)
いよいよおもしろくなってきました。
が、源氏ってこういう物語だったのかととても新鮮です。
今まで口語訳を読んでいては全くわからなかったことが
原文を読むことで理解できた気がします。 (N)
帝の桐壺更衣への想いは、藤壺を得ることでやっと続きが
描けるのでしょう。
桐壺更衣が過去の人となり、これから藤壺さんがつないでいく未来。
五十四帖のプロローグも佳境に入りました! (ぴ)
第6回ゆかり雲 2012.1.7
今日は「かたみのかむざし」から「若宮、内裏に住まう」までを読みました。
「かたみのかむざし」に関連して「長恨歌」も少し読みました。
〈瞬間感想文〉
今回から参加させていただきありがとうございます。
源氏物語は一人で読んでいてもなかなか現実ばなれしていて
わからなかったのですが、先生の説明をお聞きして理解できます。
次回も楽しみです。ありがとうございます。(浅野晴美)
長恨歌(楊貴妃)との対比のところおもしろかったです。
長恨歌、楽しみになりました。
源氏の成長の背景が見えてきて、なるほどと思いました。
先生が読むのを聞くにつけ、日本語の音の美しさを感じます。
「最愛の更衣を亡くされて悲しいのはわかりますけれど、帝さん、
あなた様は大事なお立場の方なのですから、しっかりしてくださいネ!」と
私まで言いたくなりました。
けれど後継者問題については冷静な判断をされたとホットしました。(七草がゆ子)
更衣亡き後の帝と弘き殿の女御の関係で、若宮の運命も決まっていくのですね。
若宮がどんな風に育っていくのかが興味深いです。(YOKO)
新年早々、古代の世界に浸ることができて幸せだなあと思いました。
今回は弘き殿の心境がとても興味深く、彼女のいら立ちがわかる気がしました。
若宮の幼少時代は決して華やかではなかったのですね。(Adagio)
衣よりも食、色気よりも食い気。これでは物語は成り立ちませんね。
(トヨ)
更衣亡き後、悲嘆にくれる帝にここのところずっとお付き合いしてきました。
今日の回では、眠ることもままならず、食べ物ものどを通らず、
現実が遠のいてしまっている帝のご様子を知りました。
早く立ち直ってほしいと願うばかりです。(風露草)
何もかもできないほどの帝の姿、更衣に対する気持ちがズッシリとひびきました。
その反面、若宮に対する親心も・・・。弘き殿の深い気持ちも、見逃せない女心・・・。
いろいろと多方面にひろがるイメージ!! (とし子)
これまでの物語と同じく、帝の心情がこと細かく書いてあるのには驚くばかりです。
これからも登場人物の心の動きが語られていくのだと思うと楽しみです。(まり)
あまりにも完璧ですごい人よりも、ちょっとかわいそうという気持ち→好きになる。
源氏がこれから多くの女性に愛されるようになるための伏線か?
かわいくてきれいな男の子をかわいがる宮中の女性、
いつも女性に愛されてきたことから、すべての女性にやさしい源氏、
ますます女性から人気がでる?
次回の展開が楽しみです。 (NAO)
2011年11月5日 第5回「ゆかり雲」
瞬間感想文
帝の人間らしい心情が語り尽くされているのに驚きました。(まり)
今日、初めて参加させていただきました。
ゆっくりじっくり読んでいくのでついていけそうです。
現代と同じ言葉でも意味が全く違ったり、改めて勉強になります。
その場のイメージがわかって古文を読むのは
とても楽しいことだと実感しました。
場面が切り替わるところ、主語が変るところが
なかなか理解できずにいましたが、先生の解説で
ようやくわかったところがいくつかありました。
なげき悲しむだけだった帝が、更衣の母を思いやる場面が
帝の優しさを感じて、感慨深く思いました。(adagio)
心の細かいところまで、主観的に客観的に描いているのが
千年以上前に書かれたものとは思えない。(NAO)
いつまでも愛されている更衣がうらやましくもあり、
しんどさも感じました。月の形、虫の音、草花の
うつろいを気づけたらよいと思います。(トヨ)
恋物語だと思っていた源氏物語に、更衣の母君と帝との間の
しめやかなやりとりが、長々と描かれていたことに驚きました。(風露草)
妻を亡くすと男性はガタガタにくずれ、娘を亡くすと母親は悲しみくれる。
「私の夫、母親はこんなに嘆いてくれるかしら?」(おぜんざい)
感情を直接的に表現するのではなく、自然描写などたくすことで、
よりあざやかな表現になっているように思います。
美しく優雅な世界にひかれました。(ゆみっち)
人の心をとらえた自然描写に加え、帝、母君、命婦それぞれの
心の奥の深いところを読み取ることができたのは
ゆかり雲に居るからこそ・・・と。(とし子)
小萩二首、どちらも同じことを描いていて、合わせ鏡みたい。
父帝もおばあちゃまも、忘れ形見を手許に置きたいよね。
周りの女房さんたちには「宮中に帰りたいでしょ」なんてたきつけられて
三つの坊やはきっとまだ自分の意志なんてなかったろうから、
間でぽかーんとしていたんだろうな。(ぴ)
亡くなった更衣の母君になぐさめの手紙を送り届けた帝。
娘の死にいまだ不安にさいなまれる母君。
いつになったら落ち着いた日々が来るかと思いますが、
知らず知らずに時が流れて、亡くなった方は思い出となっていくのですね。
数年前に亡くなった友人のご主人から娘さんの結婚式の写真を送っていただき、
寂しいながら喜びを家族で分かち合った様子に心打たれました。
若宮の成長が父と祖母の心のよりどころですね。(YOKO)
第4回「ゆかり雲」
2011年9月3日(土)
奥沢地区会館にて
台風模様の中、何とか集まることができました。
「夕月夜の訪問」から「母君、胸中を語る」までを
読みました。
【瞬間感想文】
酷暑の夏からまだ抜けられず、台風にまどわされた今日に、
母君の心の内のはげしいものに触れ、“今日はこういう日”という感。
という思いの反面、久しぶりに雅な世界にタイムスリップ。
気持ちがおさまって帰れる幸せ感! (とし子)
源氏物語に表された式部の幅広い人間観察眼に驚きました。
物語を書くにあたっては、筆の進み具合は速かったのか遅かったのか
知りたいところです。 (まり)
直接的な感情表現を重ねるのではなく、
植物(蓬、葎など)または季節の移ろいを描写することにより、
より鮮明に登場人物の感情や状況を表現する部分に
和歌と類似する部分があるような気がして、今までよりさらに
気持ちが魅かれました。 (ユミッチ)
野分けだちて・・・の情景の描写が見事だと思いました。
荒涼とした風景が心情をも表していて、悲しみが伝わってきます。
自然や季節、気候がとても身近だったことが
現代の私たちに欠けてしまった感性を気付かせてくれた気がしました。
(Adagio)
親にとって孫よりも子どもに関わることの方が、
身を切られる思いをもつことは
今も昔も変らないと思います。 (Toyo)
「源氏」はむずかしい内容の物語という印象が強かったが
(現代語訳を何種類か読んでいるにもかかわらず)人間の感情を
きめ細かく描いているということが原文を読んで強く感じられた。
原文を読んで、それで自分が何を感じるか。
やっぱり原文を読むことが大切ですね。 (NAO)
桐壺の更衣の母上の言葉は本当に現代に通じるものがあります。
子どもが先に亡くなるというのはどんなにつらいものか想像を絶します。
ましてや宮中でいじめられて、病気になって亡くなったのですから。
母上はどこに気持ちをぶつけたらいいのか、後悔と絶望の底にある様子が
理解できました。 (ようこ)
命婦が夕月夜に、桐壺の更衣の母君を訪問する場面、
「月影ばかりぞ、八重葎にもさわらずさし入りたる」という情景の
すごみのある美しさに圧倒されました。
亡くなった娘を思う、母君のやるせない悲しい気持ちの吐露に
胸を打たれました。母君に娘とのありきたりな日常を味わわせて
あげたかった! (風露草)
亡き夫、大納言の遺言とはいえ、
どうして娘を入内させてしまったのだろう。
宮中へ上がり、帝に愛されることが、女の最大の幸福だと思ってきた。
そしてそれを果たしたはずの娘が幸せであったかと問われれば
わたしは答えを持たない。って母君が言ってました。
女の幸せの定義はいつも難しいようです。
(ぴ)
2011年7月2日 「桐壺」を読む その3
今日は「臨終の更衣」から「死の波紋」まででした。坂本さん、伊藤さん、
持田さんが新に加わってくださり、11人の参加。
瞬間感想文
・初めての参加で、ひとことひとことに“思い”があり、感情がゆさぶられました。
学生の時はつまらない思いばかりでしたが、次回が楽しみです。(とし子)
・ゆったりと原文にひたることができました。
読み返す時スラスラと読みあげることができるようになっていた!! (ノリ)
・高校の時、古文はすべて文法的に分解して理解しようとしていたが、
今回文法は気にせず、とにかく読んでみたら、日本語なので
自然に何となくわかることに驚いた。(直子)
・登場人物の気持ちが読む者にひたひたと伝わってくるのには驚きました。(まり)
・桐壷より弘き殿の方が、ハッキリしていていいと思います。
帝はうっとうしい。(Toyo)
・死による男女の別れ、母娘の別れなど、時代を超えて変らない人間の感情の表現に
とてもひきつけられました。 (ゆみっち)
・あまりに愛されすぎることもつらいし・・・。
あまりに愛しすぎることもつらい・・・。
何でもほどほどが良いとも思うけれど、そうなれないところが魅力的!!
(あなたのおそば)
・更衣に先立たれた帝や、更衣の母親が悲しみにくれる様子に
心を打たれました。母親を知らずに御子はどのように
育っていくのでしょうか? (ようこ)
・更衣が「絶えはてて」いく様子、帝の慟哭、北の方の嘆きがとてもリアルに
手に取るように感じられ、少しずつ古語の行間を想像できるようになってきた
気がして嬉しく思いました。(Adagio)
・更衣の臨終の床で、帝との間で、御子のことが語られていないことが気になりました。
愛しあう二人の男女であっても、ここでは父と母ではなかったってことだったのかな?
ちょっと息子がかわいそうに思えました。(ぴ)
・今日読んだ所は、大変にドラマティックな場面で、泣きまどう、泣きこがる、
恋ひしのぶなどの言葉に圧倒されました。大げさな感情表現を抑えたり
慎んだりすることが日本人の昔からの美質なのではないかと思っていましたが、
平安時代の人々はそうではなかったのですね。(織田真紀)
2011年5月14日 「桐壺」を読む その2
冒頭、田中先生より、869年の貞観津波の記事をいただき、
この度の震災・津波災害が決して未曾有のものではなく、
繰り返された地球のサイクルであるということ、
千年前の人々が未来に託した文献や、それらを研究し、3月11日以前に
警鐘を鳴らしていた科学者があるにもかかわらず、
いかに我々は耳を傾けてこなかったかということにもどかしさを覚えました。
わたしたち源氏の読み手は、千年前の女性が書いた物語から何かを受けとり、
伝えていくことができるでしょうか。
瞬間感想文
範囲は御子誕生~病む更衣。
御子誕生のさい、男性の目から父親としての視点に変わる様子をたいへん面白く感じました。
矢作裕美子
今回も古語の奥深さや使われ方の味わいを楽しみました。
桐壺更衣は、御子を産み、帝に愛されて、幸せの絶頂にあったとはいえ、
その幸せが正面からかかれていないのがとても悲しいと思いました。
ミクロシュ
それぞれの登場人物の思いが強く迫ってくる、迫力のある文なのにはびっくりしました。
まり
初めて参加させて頂きました。最初に貞観地震(869)の資料を頂き、平安時代も人々が津波のために
大変な思いをさせられたことを知りました。
源氏物語は、桐壺の更衣の悲しみが深まっていく様子が実感できました。次回も楽しみです。
洋子
古語を一語ずつゆっくり読み進めていくので、少しずつ文章として理解できるようになってきた気がしました。
原文だからこそそのニュアンスが伝わってくるのがわかり、嬉しくなりました。
これからがますます楽しみになってきました。
adagio
いつまで亡くなったひとのこと思ってウジウジしていらっしゃるのです?
帝としてなさらなくてはならないことはたくさんおありでしょうに(たとえば
一の御子をきちんと東宮としてお披露目くださるとかいろいろ)。
妃はあの方ばかりではありませんのよ、わたくしは生きてここにあります(なのに
こちらを向いてくださらないのはさみしいのです)。
いさめちゃん(ぴ)
2011年4月2日 「桐壺」を読む その1
瞬間感想文
・ある方が帝ってどんな方だったのかしらなんていう疑問をなげかけられて・・・。初めて帝という人物のことを考えてみました。(N.O)
・あんなたった数行の文章の中に、イメージをふくらませる色々なことが盛り込まれていたなんて、若き学生の時代には気が付きませんでした。大人になってよかったと思う一時でした。(萌)
・源氏物語の生まれた時代と世界史の対比、文学史の中の位置が興味深かったです。冒頭の書き出しのインパクトにびっくり。いきなり最初から引き込まれる。原文を一語ずつていねいに読み進めていくことで、視覚的なイメージがどんどん広がっていく気がして、これからが本当に楽しみです。日本人だからこそ、原文が理解できる、歴史に参加できるというのはとても嬉しい。(Adagio)
・桐壺帝はイケメンだったに違いない。そして少年のままの心を持ったひと。彼と恋愛してみたいかな、どうかな・・・。魅力的なひとではあるんだけどね。うーん、好きになっちゃうかな きっと。でもいろいろ面倒そうだなあ。 (ぴ)
・今も私たちが使っていることばが、どのような意味合いで使われていたのか、とても関心があります。「めざまし」「まばゆし」などが、あまりいい意味では使われていなかったなんて、面白いと思いました。「思い上がる」は良い意味だったそうです。
今回の部分では、帝の性格をあれこれと考えました。恋に目がくらんだ、少しわがままな思慮深くない方だったのか、それとも真の心の通い合い、うそでないものを求めた方だったのか。今のところ、どちらなのかの判断はつきかねています。 (織田真希)