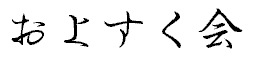住吉詣の絢爛豪華な行列を目の当たりにした明石の君は、圧倒的な身分差に打ちのめされている。住吉詣をあきらめ、お祓いだけでもしてもらおうと難波へと櫓を進めた。源氏との縁は父入道の切望ゆえである。対等の男女関係とは程遠い身分格差を思い知ったいま、源氏とのつかの間の思い出はかえって辛いものになっているかもしれない。父入道が心を込めて用意したに違いない奉納品までも色褪せてみえてしまうのだ。
受講者からは、絶対的な身分差を知った明石の君は娘の将来に不安を膨らませて押しつぶれそうだったろうという指摘がされた。浮かれたところが微塵もない明石の君の気質は入道の教育によって作られた人間性、という意見もあった。出産後の気力の低下もあり、京の都からみれば明石という田舎育ちの娘の行く末は知れている…、恋しい源氏の住吉詣でに出くわした明石の君は意気消沈である。
明石の君の落ち込みようが激しいので、なぜか源典侍が思い出されてしまう。源典侍だったら、こんな場合にどんな反応を示すかなぁ。艶っぽい歌を送らずにはいられないだろうし、滑稽な展開が期待できる…源典侍がなつかしくなった「澪標」です。
惟光の気遣いは相変わらずです。源氏の威光に圧倒されて引き上げてしまった明石の君に気づいて光源氏にそっと知らせました。源氏の女性がらみには必ず付きそってきた乳兄弟の惟光。彼が登場したのですから大きな場面展開が近いのでは、と期待される登場の仕方です。行列を彩っている官吏たちの苞の色なども確かめました。官位による苞の色が行列に華やかな彩を添えていると、残された絵巻以上の華麗さであったろうと想像できます。
一層輝きを増した二十日余りの月が照らしている宮中は、今や右大臣派の権力に覆われ、帝とも遠く隔てられています。中宮は、もう今では春宮を頼みたい帝には会えません。二人の交わした歌は、あの華やかな桐壺帝の時を偲ぶもの。効果的な二十日余りの月。
母は気掛かりで、あれこれ話して聞かせますが、久し振りに母に会えた喜びで、その一つ一つを頭に入れる余裕もなく、別れの時までと、眠たさを我慢している東宮が哀れ。
初時雨が近い木枯らしの頃、右大臣家との関わりも煩わしくて、長い間音信不通にしていた尚侍の君か
ら思いがけず歌が。使いを待たせ、入念に紙を選び、筆を整え、心を込めて返事を書く源氏の【艶なる】
高揚は、女房たちの目に【つきじろふ】程はっきり見えます。源氏の尚侍の君に対する気持ちは、他の
女たちに対してよりもずっと深い。尚侍の君の相変わらず積極的な木枯の歌に、源氏は初時雨で返します。
初時雨の後は大雪。桐壺院の一周忌の法事の後、亡き院を悼む御国忌の日に、源氏は中宮に歌を送りま
す。【ゆきあふ】と【ゆきめぐり】歌の中に秘められた二人の想いを雪が覆い隠す様。でも、今日は、それを打ち消し【雪の雫に濡れ濡れ】涙に濡れながら桐壺院の為に勤行する源氏です。
・ 時の移ろいを【二十日月夜の夜】【初時雨】【木枯】【霜月の朔日】と季節の表現、その折々の源氏の心の動きが美しい古語で綴られる。危険な恋に燃える源氏さまのおかしさ。中宮から院の御法要の歌の美しさ。【あはれなる雪の雫に濡れ濡れに行ひたまふ】
新しい出版された本で、今日も又、五感をゆさぶる豊かな古語に酔う。
・ 藤壺への想いやら、政治的な疎外感やらで、気が滅入る源氏の元に、尚侍の君から歌が届く。
いいねぇ、感情がダイレクトで・・・。
すると、源氏は、ルンルン気分で返事を出すのよね。「あら、まあ、一体誰に?」周りの人達のヒソヒソ声が聞こえるようです。
久し振りに会った弟に色々な話をしたがる、聞きたがる。その人恋しさに、強い権力に囲まれた帝の孤独を感じました。源氏も又孤独です。もっとこのまま一緒に居たい兄。兄弟なのだから・・・。
でも、弟は急いでいます。中宮に会いたい。
春宮を皇子にという桐壺院の遺言を朱雀帝は忘れてはいないけれど・・・彼は右大臣家と弘徽殿の女御の恐ろしさを良く分っています。
退出した源氏に【はなやかなる若者 頭の弁】が、【白虹日を貫けり。太子畏ぢたり】と、聞きかじりの漢詩で嫌味を。多分深い意味は良く解っていない?軽い男。弘徽殿の身内の、こんな蓮っ葉な若造にまで軽んじられる自分の立場を源氏は情けないと思った事でしょう。
そしてやっと中宮のもとに到着します。
・ 【春宮をば今の皇子になしてなど、のたまはせ置きしかば、とりわきて心ざしものすれど、ことにさしわきたるさまにも何ごとをかはとてこそ。・・・】朱雀帝はいきなり春宮の話を始める。胸に重くのしかかっていた桐壺帝の言葉を、源氏と久し振りにしみじみと語った乗りで、源氏に吐き出す。
【ことにさしわきたるさまにも何ごとをかはとてこそ】という二重否定の慌ただしい言葉の響きに、朱雀帝の気持ちが表れている。
・ 絡み合う様な古語を読む程に、ほのぼのとした貴公子二人の会話に、異母兄弟の微妙な立場。これから展開する物語の暗示が織り込まれている。
尚侍の君を巡る恋の想いや、吾が子でもある春宮、母君である中宮への想い。【いとほしう想いたまへられはべる】源氏の胸中は、いかばかり。
今日も平安の【ことのは】が駆け巡りました。
・ 宮中での居心地の悪さを事あるごとに痛感する源氏。兄・朱雀帝とは久々に話し込むけれど、弘徽殿大后側のあてこすりは露骨になっていく。つけ入るスキを見せたら我が身の危機よ、源氏君。
虎視眈々とチャンスを狙う大后の影が怖いです。
・朱雀帝の、人となりがこんなに書かれていたのは初めてです。優しく、自信がなく、意志が弱く、優柔不断で、決して悪い人にはなれない、そんな青年。兄と弟の会話の中に見える優しさは肉親という血の繋がりから来るのでしょう。二人の共通の女性、尚侍の君について、源氏を責められない。
内館牧子さんは【十二単を着た悪魔】の物語をこの場面から考えついた? そんな気がしました。
・弘徽殿の女御が、【大宮】と【后】で表現されていました。こういう所が古語の難しい所です。
・今風の軽薄な男を登場させて、勢力図をはっきりさせていました。
・二十日の月は、源氏の旅の、奈良ホテルで観たあの月だそうです。
朝顔は、本当に覚めた目で源氏を捉えています。高貴な身分と、若さの持つ冷徹な視線なのでしょう。語り手が【恐ろしや】【御癖の見苦しき】【あやしき御心】と、源氏の行為を神への冒涜であると批判し続けます。斎宮は神にお仕えの身なのですから。有り得ない!
紫はそこまできっぱりと源氏を拒めない。
雲林院を去る場面と【若紫】の巻の、山を降りる場面が似ている様に思い読み返しました。【若紫】の別れは、豪華絢爛、華やかに書かれていましたが、送る者達の涙と源氏の美しさは全く同じでした。
・ いとしい春宮にも会いたい。しかし一歩踏み出す事も出来ず、藤壺の君への恋情も断ち切れず、悶々とする源氏の向かった雲林院は、秋たけなわの美しい風景。僧侶の勤行の声に【世の中の常なき】と、思いは宙を舞う。
しかし、いつも源氏の君の支えは掌中の珠の姫君。文を交わしながらお互いへの思いに絆が深まる。
姫君の成長に【けしうはあらず生ほし立てたりかし】この姫君おいて出家願望は、終止。
・ 藤壺との恋に深く傷つき、雲林院に籠るが、二三日したら紫上が気になり、頻繁に手紙を書くのが源氏らしい。ただその返歌が、紫上の妻としての自負と切なさを感じ、素晴らしい。
・ 久々の母と子の対面であろう今回の場面だが、愛くるしく成長した春宮に出家する意志を伝える藤壺の心の内は、【おぼし立つ筋はいとかたけれど】と、切なさが伝わって来る。
【かをりうつくしきは】その光り輝く子は~、罪作りの源氏の君であることよ。
・ 幼い男の子の表情が可愛く、ゆらゆら揺れる髪、虫歯もしっかり書いてあります。既に春宮の自覚を持つ幼い顔に、源氏の幼い頃の気配が、かおり立ちます。それは藤壺の【玉の瑕】であり、世間への恐れです。
・ ここでも桐壺院の藤壺や春宮に対する深い愛情を思い出す。藤壺は、【院のおぼしのたませしさまのなのめならざりしをおぼしいづるにも】【やうやう后の位をさりなむ】と、思い立つ。
・ 院の用意してくれた、心苦しくも捨てる事になってしまった、源氏との恋は、春宮を守る為とはいえ、出家という形を取らざるを得なかった藤壺は、これで良いと思ったのだろうか?ホッとしたのだろうか? 【おぼし立つ】【背く】は、出家だという事を覚えました。
前回の音のない世界と対照的に、源氏が【泣く泣く怨み】話した【よろづのこと】。それに対して藤壺は【いとようのたまひのがれて、今宵も明けゆく】今夜も又源氏を拒み通しました。語り手が【かやうなるなからひは、あはれなることも添ふなるを、まして、たぐひなげなり】禁断の恋と。
自分の発する言葉に興奮し、それを抑えられない源氏の目を覚まさせたのは、藤壺の歌。次々に色々な言葉で自分にからんで来る源氏に対して、こんな事まで言わせてしまったと、ギリギリのところで受け止める藤壺は、愛してはいるけれど、賢い母でなくてはならない。
【二人していみじきことどもを・・】の二人は、源氏と藤壺の様に思ってしまいましたが、王命婦と弁なのですね。夜がすっかり明けてしまった今、彼女たちの焦りが【いみじきことどもを聞こえ】に良く表れていました。
・ 今までの恋と異なり、禁断の恋に燃え、溺れる源氏。母として生きる決断をし、先を考え冷静に対応する藤壺。年下の男と年上の女の激しくドラマチックに展開していくシーンを、息を殺して見た。
- 【夢のようにぞありける】だった源氏は狂気の人となり、藤壺との応酬では、冷静であり賢い藤壺に軍配が挙がったのでは・・・・。
原文からひろがる源氏物語 「賢木上巻」接近 2013年5月1日受講
源氏は、藤壺の姿を久し振りにまじまじと屏風越しに見て、【めづらしくうれしきにも】涙する。そ
の興奮状態が、【心まどひして】、【心やましうつろうて、引き寄せ】、【心にもあらず、御髪の取り添へ】へ。そして、藤壺は【心憂く】宿世を思う。原文で読まなかったら、この、【心】の動きの緊張した流れは、とても捉えられず、つまらない月並みな場面になってしまう。音のない、スローモーションの様に目の前で流れていく想像世界を、ドキドキしながら読み進みました。源氏が放つお香の匂いが、とても効果的です。
成長した若紫が、藤壺に生き写しと、この重い空気の中で、【はるけどころあるここち】する源氏。【はるけどころあるここち】って素敵な表現でした。
読後一言感想
・【・・・心にもあらず、御髪取り添へられたりければいと心憂く、宿世のほどおぼし知られて・・・】
何と源氏の生々しいむき出しの姿か!!今まで「野々宮」でも、涙は流しても、その姿は美しく月に照
らされ、この様にむき出しの源氏は初めてである。この物語は、有り得ない程の理想の恋が底に流れ
ているので、格調高く美しいのでしょうね。
・ 一夜を塗籠に押し込められた君は、女房達の【いかにたばかり出だしたてまつらむ】と、【ささめき
あつかふ】も、ものともせずに、【やをらおしあけ】、【伝ひ入り】目を凝らして叶わぬ想いが募り涙して、宮の美しい姿から【年ごろすこし思ひ忘れたまへりつるを】と対の姫君へと繋ぐ、たおやかな古語の表現。式部の筆の流れは、ついに理性を失い【心にもあらず】、ついに理性を失い「男」に豹変する。藤壺の【むくつけう】ああ・・ここまでも。
・ 罪悪感・・・、でも恋は止められない。私だったら、源氏にこれだけ言い寄られたら、何もかも捨て
てしまいそうだ。それで、失敗するのだけれど・・・。
藤壺の理性は、母ゆえに働くのだろう。しかし、女として揺れ動きもする。その心理の様を描く式部の筆は冴えわたる。
こんな風にハラハラドキドキしながら、日本人は千年の時を読み継いで来たのだろう。
・ 元服の時以来思いつめた人を間近に見た、その姿はあまりにも美しく輝いて見え、理性を失ったかの様な行動に出るところは息を呑んだ、お芝居の様な場面でした。
・源氏の、想い続けた人に会い恋情を爆発させる様子は、緊迫したドラマの様に迫る。
・ あららん、貴公子がこんな行動に出ちゃうの?!桐壺院が亡くなってからの源氏の振る舞いは、タガ
が外れたとしか言い様がない。ま、それだけ藤壺に対する想いが募ったのでしょうが、ちょっと見苦しい気もしないでもない。式部の描く、リアルな恋の顛末。次回も楽しみです。
原文からひろがる源氏物語 「賢木上巻」接近 2013年4月3日受講
【若紫】の巻【密会】で二人が別れの時に交わした歌、
源氏:【見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちに やがてまぎるるわが身ともがな】
二度と会えないと思っていた逢瀬は夢の様で、そのまま夢の中へこの身も紛れ込んでしまいたい
藤壺:【世語りに人や伝へむたぐひなく 憂き身をさめぬ夢になしても】
たとえ貴方様の夢の中に一緒に紛れ込んだとしても、帝を裏切った自分をやがては世間の人々が
伝える事だろう
【男】は変わらぬ夢を持ち続け、【女・宮】は母になり、亡き院への裏切りは永遠に消えず、あの時より更に現実をしっかり捉えていて、【男】の自分に対する気持ちを【憎き御心】とまで思ってしまいます。藤壺は、源氏の【まねぶべきやうなく聞こえ続けたまふ】声に【いとこよなくもて離れきこえたまふ】しかないのです。
式部は、変わる事のない男と女の在り方を、繰り返ししっかり書いていました。
尚侍の君との危うい逢瀬を【かやうのこと】とし、その後源氏は藤壺に接近します。【花宴】でも、朧月夜と初めて会った後、彼女が誰なのかを気に掛けつつも、藤壺の素晴らしさに想いが流れていく源氏が書かれていました。
朧月夜と藤壺は、筋書きの中で連鎖的に繋がって書かれている事に気がつきました。
読後一言感想
・【ともすれば御胸をつぶしたまひつつ、いささかもけしきを御覧じ知らずなりにしを思ふだに】この文で藤壺の桐壺院への想いと、本当は源氏の子である息子を、疑うことなく春宮に立ててくれた感謝の気持ちが分かり、本当に重い文である。
・源氏は、右大臣の世となってから鬱々として楽しめず、息子を守ろうとする藤壺の心も理解出来ない様である。
・執拗に迫る源氏に、藤壺はどう対処するのかドキドキものだったが、やはり自分の気持ちを押し通すところが、源氏より上手かな。男は勝手。
・今回の【接近】の場面、ここまでやるか!と思ったけれど、文中の【男】と【宮】の呼称が、二人の想いのズレ、立場の違いを物語る。源氏の行動は、ま、それだけ藤壺への想いが募っていたのだろうが、ちょっとねえ。源氏のこうした青臭い一面もまた、彼の魅力の一つなのでしょうけどね。
・尚侍の君と逢瀬を重ねるが・・・【もて離れつきなき人の御心を】藤壺への思いはますます募るばかり。
・母として春宮の立場を案じ、後見人として大切な源氏ではあるが、藤壺は、深い罪に苦悩し、祈祷までして頑なに拒否する。
・文中【男】と表現されて虎視眈々と・・・、人騒がせな困ったさん?
・難解な古語だが、式部の表現の巧さに臨場感が伝わった。
・主語が書かれていないまま、文章はどんどん進み、誰の御心?誰の御胸?先生の解説で読み進んで初めて、ああ、これは源氏、これは藤壺と解りました。
・藤壺の心の中の故院への罪の意識は、永遠に消える事はなく。
・守るもの(春宮)がある女と、無い男の心の動きが細やかに書かれていました。
・王命婦と弁の慌てる姿、そして、塗籠へ押入れられる源氏は、芝居を観ている様でした。【若紫】の直衣をかき集める場面を思い出しました。
・ 長い間塗籠へ押入れられて、源氏は何を思っていたのでしょうね。
原文からひろがる源氏物語 「賢木上巻」代わり目 2013年3月6日受講
まず、左大臣の嬉しそうな顔が浮かびました。屋敷を去って行った時の、しおたれた女房達の前に、再び現れ、一人一人を労う優しい源氏。若紫の幸福を噛みしめる少納言とその裏にある、【物語に作りいでたるやうなる】継母物語。気を紛らわす朝顔の姫君への文。帝の(院の)源氏への思いを阻む弘徽殿の女御と右大臣の不気味さ。そして、スリリングな密会の中に、【をかしきもの】を挿入する式部のひょうきんさ。霧の中にぼんやり浮かぶ暁の月の下、源氏の美しさが仇となって・・・ヤバい!
【まぎるることなきままに】流されている源氏が、何故か段々追い詰められている様に感じました。
読後一言感想
左大臣家を訪ねたり、朝顔と文を交わしつつも、源氏の空しさは紛れる事がない。紫の君の存在が世に認められても、継母、継姉のイジメがある。尚侍の君との密会もこれから先の暗雲が予想される。何一つ、源氏の空虚さを埋めるものが無い事で、源氏の暗い運命を暗示している。
際立ったエピソードでは無い場面だが、何とも言えない不安感を醸し出す式部の筆は、秀逸だ。
日頃のうさばらしを、密会という事で、とてもスリルがありました。ドキドキでしたが、案の定気付かれてしまいました。どんなに身をやつした姿をしても、源氏はやっぱり光の君なんです。
今回は、語り手の箇所がとても多かった様です。関係図が難しく、見ないと解らない。
源氏と尚侍の君の綱渡りの様な逢瀬。でも、やましい事は隠しおおせるものではなく、どこかで露見する。二人の密会もそうなのよ。そして源氏は窮地に追い込まれていくのです。
ああ、なんてドラマチックなの!読者もハラハラ、ドキドキで、心キュンで~す。
・御代変わり【見知りたまはぬ世の憂に】籠りがちながら【ありしにかはらず】大将の君は左大臣邸を訪れ、若君や女房たちと【いとのどやかに】
・恋の遍歴も今や【あいのうおはしなりて】 ええ・・・そんな!しかし、大将の君は栄枯盛衰の中で愛の災いは消すこともなく。
・西の対の紫の君への深い愛情。
・親交を重ね、揺るぎない間柄の朝顔の君。その神へかしづく身に【くちをしくと】思いを寄せる。
・もっと危険な尚侍の君とのアバンチュールな恋。
あの時この時、ドラマを織り込みながら、源氏の君の【はかなしことども】の展開を。
平安時代から現在までの長い間、多くの女性達が、この密会を自分の事の様に、ドキドキ、ハラハラしながら読み繋いで来たのでしょうね。源氏物語をエロく翻訳する人達にとって、この密会は、この巻の山場になるのでしょうが、原文は実に冷静に、客観的に書かれていました。
原文からひろがる源氏物語 「賢木上巻」代わり目 2013年1月9日受講
年が改まり、春の除目の候を迎えた。もの憂く籠もりがちに過ごしている源氏。「馬車うすらぎ」た邸内のの風景が桐壺院時代の終焉を雄弁に物語っていた。
朱雀帝の時代である。大后(弘徽殿女御)の政治力によって入内した御匣殿(朧月夜)は、帝の寵愛を得て華やかに時めいていたが、源氏とは文を交しあう仲がつづいている。
院崩御はその後を生きる者たちの欠落を炙り出していた。源氏と大后、左大臣・右大臣両家の権勢の盛衰は世の習いとはいえ、埋められない欠落が死者を欲っして、その距離を縮めたり、遠ざかったりした。死者と対峙すれば、記憶の谺(こだま)にさいなまれるのである。
「なぜあなたはいらっしゃらないか?」「詫びることもできない罪を犯しました」「愛した者の胸へ還っていったのでしょうか?」「愛を知らない者は生き場所がないのか…」
絶望的な空虚感を漂いながら汲み上げてもらえない感情に包まれる源氏と大后。
渇望は大后の方が大きいかもしれない。源氏が・左大臣が憎いという激情は、故院に汲み上げてもらえなかった飢えを顕(あきら)かにしていないだろうか。強引に単純化すれば崩御によって、和解できないままになってしまった傷痕は肥大化したのではないか。後悔や詫びの感情、屈辱までも谺(こだま)して、大后を苛んだのではないのか。
不在者として存在しつづける桐壺院の「不在の存在」。政治力発揮は、大后の失ったものの測りがたい大きさを実感させる。故人を懐かしく思い出すことができず、とっぷり悲しむこともできない喪の欠落が、冷徹な権力者へと育てていくのではないだろうか。
ついに桐壺院という雪の重さに耐え抜いた枝は、解放され、大きく弾んで跳ぶような春を迎えた。朱雀院・右大臣家の時代である。
死者として存在しつづける桐壺院。源氏と大后は故院を抱え直して生き直すしかない。源氏失墜へ向って注がれるエネルギーは、幸せになろうとする希いを奪われてしまった大后の心の闇への挑戦だろう。幸せになろうとする意思を奪われた大后の傷は、誰よりも深いようだ。
読後一言感想
院の崩御と共に左大臣の権勢から右大臣の権勢へと移りゆく様子がこまごまと書かれ、人間関係も遡って思い起こさせてくれて大変勉強になりました。私は、語り手と作者とを混同しがちです。
語り手は、弘徽殿をにくにくしき覚えけれど、どちらの味方にもあらずで文章の流れが楽しい。私は、弘徽殿は性格が良くない方が楽しい。あの時代の位の上下、権力の移動がこまやかに書かれていて、短い文章であるが理解できたような気がした。
代り目――院の崩御によって世の中や人々の日常までも「ものすさまじくなむ」。時代は右大臣家へと権力が流れていく。まして大将殿は「もの憂く籠もりたまへり」とあるが……今をときめく大后の妹君「朧月夜に似るものぞなき」~以来から恋の炎は「いと忍びて通はしたまふ…」。「例の御癖」と恋の行く手を案じても、源氏さまは危うい恋に燃えるのね。短い行間からイメージを拡げようと、今日も平安の「ことのは」が脳を駆け巡った。
大后の政治力によって入内した朧月夜が御匣殿として登場。朱雀帝の寵愛を受けているにもかかわらず、あの四年まえの出会いの夜からずっと源氏と文が交されていたんですねぇ。時めく右大臣家と衰退していく左大臣家、そして源氏の失意。世の無常と大后の冷徹さを際立たせながら、これからもっと源氏を追い詰めていくだろうか。それにしても朱雀帝を裏切る朧月夜といい、冷徹に政治力を振るう弘徽殿女御といい、右大臣家出身の悪女たちはとても魅力的!!
さあー弘徽殿のお出ましです。源氏の存在によって、これまで苦渋を呑んできた恨み、ここに炸裂! 桐壺院の庇護を失った源氏が政権の代わりゆく現実に心がしおれていく。今回の受講の中で、先生が「こういう言葉は現代語に訳したくないのよねぇ」と言われたのが印象的でした。そう、古語はそのまま使った方がニュアンスが伝わる場合が多い、と改めて思いました。
弘徽殿女御の大暗躍がつづられていました。まめ男・源氏は葵の死、御息所との別れの悲しみを語りながら、御匣殿と文を通していた。ヘー!! 源氏物語の語り手はどんな人だろうか? これまでの経緯を全て知り尽くしている古女房、どちらかといえば源氏側ではないかしら。
世の人々の変わり身の速さが「馬車うすらぎて」に感じられました。「見知りたまはぬ」今まで経験したことのない屈辱感、それは源氏がお坊ちゃまだったから。左大臣と右大臣の確執が「そばそばしう」と表現されていたので、トゲトゲして痛かった蕎麦の実を刈り採ったときの手の感触を思い出しました。
院のおわしましつる世こそ憚りたまいつれ、后の御心いちはやくて、……見知りたまはぬ世の憂さに、立ちまふべくもおぼされず。さあ、弘徽殿の仕返しが始まる。政治力のある弘徽殿の動きは速く、それに引きかえ源氏は「立ちまふべくもおぼされず」と、現実に傷ついたまま、迎え撃つ気力が失せている。栄華を失った左大臣も内裏に参上しなくなった。大后の矛先は鈍ることなく政敵を追い詰めるだろう。源氏の君、おっとり構えている場合ではありませんよ。
原文からひろがる源氏物語 「賢木上巻」 院崩御後(後半) 2012年12月19日
人は悲しみと出会いながら生きていく。とはいえ、大切な者からの遺棄は、強烈にならざるを得ない。喪失を知る人々であふれた世間の貌が見えるとき、初めて「誰もが悲しみを抱えて生きている」ことに気づく。それは特別なことではない。だが特別なことのように感じた悲しみは「生きる意味」との出会いなおしになり、時を経て、経験が生き抜く力を養ったことに気づく。
故桐壺院の四十九日は、師走の20日であった。院を偲んで詠みあった歌に、語り手は辛口の評価をした。兵部喞や源氏、王命婦たちの和歌でさえ、悲しみが生のまま投げ出されていて、経験を超える瞬間に共有されていく、深い共感に乏しいようだ。だから他の者の歌などは、評にも値しないと切り捨てた。喪色を共有しただけの歌では、芸がない……(読者は厳しい批評を理解するのが難しい)。「悲しみの一歩先、見極めるところまでも詠め」ということらしいが……語り手に応えるのは、この状況の兵部喞や源氏・王命婦たちばかりでなく、現代の読者にとっても至難である。
恐ろしい秘密を抱えながらの喪・四十九日は、院との臨終の日々を反芻する日々だった。
東宮は久しぶり会う嬉しさを隠さない幼さで、臨終の院を見ていた。院は東宮ではなく、私(藤壺)を見つめていた。東宮の五歳という、幼さ、を見ていた私。源氏の君は…何を見ていただろうか。朱雀帝に東宮の庇護を堅く約束をさせた院の思い悩み。どの妃よりも慈しんでくれた院の眼差し。
「背負うものがあれば、預かって逝こうぞ」、大きな優しさに充ちたダイニングメッセージ。
東宮の補佐役として大后に対峙できる力を与えるために、院は藤壺を中宮の地位につけた。遺された東宮の将来について、考えられる全てを尽くした院は、それでも直、さまざまに思い乱れ悩みながら逝ったのではないだろうか? 堅い約束を交わせば、心穏やかに逝けるものだろうか?
死に赴く院の心の乱れは、藤壺に伝わっていただろう。「おどろおどろしきさまにもおはしまさで、かくれさせたまひぬ」は、「背負うものがあれば、預かって逝こうぞ」という、院からの究極の愛の告白ではないだろうか。
秘密を抱えている藤壺は、亡き院とつながる扉の鍵を、開けかねて逡巡する。院の思い悩みの種は自分にある。大きく包んでくれた翼を失ったこれからは、弘徽殿女御・大后に対抗できる力を持たなければならない。これからは宮廷の表の動向に囚われて裏が読めないようでは、東宮を守れない。
「別れ」を超えながら養っていく中宮の「力」を予感させる。
一言感想
今年最後の「およすく会」は、院の崩御を機に、これから様変わりする宮中のパワーバランスを示唆している。講師が「ここの文が気になる」とおっしゃった部分に、全員で「あーでもないこーでもない」とバトル。これが「およすく会」の面白さですよね。来年も楽しみで~す。
桐壺院が崩御し、安定していた世の中がこれからどうなってゆくのか…。辛口の語り手は、皆がただただ悲しんでいるのを、ただ悲しんでいる場合かと、冷静なするどい眼で見ている……ような気がする。
四月から読み始めた賢木の巻は、あわれの文学といわれる所以が六条御息所、源氏の君、藤壺、そして院、弘徽殿女御、それぞれの心が葛藤が、ため息が出るほど織り込まれている。七七忌の法要の過ぎた院邸は「雪うち散り風はげしゅう」。里下りを決意した中宮の心の中には、これからの世、そして過ぎ去った院との思いが複雑に去来する。思い思いに詠まれた和歌も、悲しみで心ここにあらずと、語り手はそっけなくあしらう。式部はどのように物語を紡いでいくのか。平安の人々も心ときめかして「源氏物語」を読んだことでしょう。平成を生きる私たち同様に。
師走の二十日となり、院の四十九日を迎えた。故人を偲んで妃たちが集まったこの日は、桐壺院の時代の終焉を象徴するように、雪雲を孕んだ暗い空が今にも落ちてきそうだった。そして上皇御所から、それぞれがそれぞれの帰るべき処へ帰っていく。後ろだてを失った藤壺中宮は、これから大后の時代が来るという意味が、それが自分と春宮にとってどれほど生き辛いものになるかが想像できた。ぐずぐずと院邸に留まるべきではないこともわかっている。それでも、今はただただ、喪に服していたい藤壺の、政治的な計算を超えた喪失感。短い文章の中で、大后と中宮の、それぞれの立場を生きなけばならない最高位の女の哀れを記して、興味深い講義だった。
院が崩御して、もう四十九日。これからのそれぞれの身の振り方があり、仕えた者たちは院邸から去っていく。院の人柄が支えた世だったが、これから先は平穏の日々は消えていくのだという落胆と、世の中が変るだろうという不安が、よく書かれている。とは言うものの、読み込みが難しかった。
中宮の心の動きを言葉の端々から読み解く力が必要となる難しい文章でした。大后との今までの緊張関係を書かなくてはならなかった。(おぼすよりも)語り手の和歌に対する辛らつな評価…、下手な歌も書ける式部です。今回は語り手が妙に眼につきました。院の四十九日は、暗く寒く寂しい天候を背景に書かれていて……古語は謎解きです。
2012年11月7日 賢木上巻 遺言・院崩御
「大妃も参りたまはむとするを、中宮のかく添いおはするに御心置かれて、おぼしやすらふほどに、おどろおどろしきさまにもおはしまさで、かくれさせたまひぬ」
すぐにでも見舞いに行かなくてはと思っていたのに、院に付き添っている藤壺の存在に気後れして躊躇していた大妃(弘徽殿女御)。グズグズしているうちに院は崩御してしまった。
大妃という地位と寵愛とが天秤にかけられたとき、弘徽殿女御は再び深く傷いた。右大臣家出身であり、誰よりも早く入内し、一ノ宮まで儲けていたのに、中宮の地位は藤壺へ与えられてしまった。
かつて桐壺帝は、貴族社会のルールを無視して、身分の低い女を徹底的に寵愛した。弘徽殿女御は右大臣家出身の妃として、後宮では筆頭の身分であり、一ノ宮の生母でもある。後宮の秩序を乱した桐壺更衣への寵愛は、弘徽殿女御のプライドを傷つけ、桐壺更衣を死へと追いつめてしまった。
かつて桐壺帝は、一ノ宮を東宮に、二宮(源氏)を臣下にして宮廷内の不均衡を納めた。そしてまた、天皇の地位を一ノ宮に譲り、藤壺の子を春宮に立てた。弘徽殿女御の心を見透かすように「あなたは皇太后になるのだからいいではないか」と言い含めたのだった。
自分という女のどこに不足があるのか? 生涯愛されない妃でいつづけなければならないのか?
愛を得られなくても、実家を外戚の地位へ引き上げる責務は果たさなければならない。怒りを収めて冷静な政治的判断をしなければならない弘徽殿女御は、大妃という位と引き換えに中宮の地位を譲らざるを得なかった。大妃という地位は、女心を酷く引き裂かれた代償である。
弘徽殿女御の女心を踏みにじる形で常に政治バランスを取り戻してきた桐壺院。傷ついたプライドは、癒えないまま心の腫れになっている。大妃の裡に沈殿する苦い記憶が、院の崩御によって和解できないままに暴れ出そうとする。幻肢痛のようによみがえり、感情の圧力を高めながら、眼裏(まなうら)の残像までもよみがえらせる。徹底的に愛されない女の、寵愛と引き換えに得た大妃の地位は、屈辱を超え、身構えて生きることを強いる……「私は大妃なのだから。」
大妃の心中がごく短い文で語られた。行間から寂しさがあふれ出して、読者はひとりの女の心の腫れに触れることになった。周囲を敵に回してでもひたすら寵愛する男・桐壺院の愛は、ついぞ大妃に向けられることはなく、もし臨終の院を訪れていたら、遺言はどのように彼女へ伝えられただろう? 愛に渇望している女へいっそうの惨めさを味あわせないために、「臨終に間に合わせない」という酷い優しさが必要だったのかもしれない。桐壺院は、徹底した政治バランスの中でしか大妃をみない男であり、激しい気性を持った女の屈辱と怒りは、源氏に向わざるを得ないのだろう。
当時の後宮や摂関政治のありかたを示す人物として、「源氏物語」に圧倒的存在感を示す大妃の心の闇は、どこまで深いのだろうか…、式部は大妃に和歌を詠ませていない。徹底して愛されなかった妃への愛おしさが、「和歌を詠ませない」という式部の優しさで、抱きしめられている。
一言感想
桐壺院が亡くなると、世の中も政治バランスも女性たちの力関係も変わっていく。今後の展開が楽しみだ。それにしてもあの弘徽殿女御の久々の登場がキラリと光った今回。出番は少ないけれど、キラキラとみせてしまう「素顔」は、なんか憎めないのよねー。
弘徽殿女御の「人となり」で受講時に盛り上がり、改めて彼女なしで源氏物語は成立しないと思いました。桐壺院との永遠の別れに、気後れがして行かれなかった女心。愛されない女の悲しみが、復讐のエネルギーになっていくのでしょうか。添いぶしの妻のプライドをつぶされても、敢然と生きている彼女を描ける式部に、またもため息です。桐壺の巻の更衣が亡くなったとき、弘徽殿女御のとった態度・「月も入りぬ」の描写を思い出しました。
いつの世も子を思わぬ親はなく、親を思わぬ子もない。子はどこかで親を心の支えにしているものだ。院が亡くなり、平和な世がなくなり、どんな世が来るのか不安に思うのは私だけかしら。源氏もどうなるのか楽しみ。
臨終の院は帝に、源氏を幼い春宮の後見人にするよう遺言した。弘徽殿女御は臨終の院の元へ駆けつけたかったが、機を逸して臨終に間に合わなかった。院の愛を得られなかった大妃の心の傷は深い。右大臣家の娘である自分に何の不足があるのか? 「愛を得られない」という屈辱。政治バランスの為にだけ処遇される女でしかない。桐壺院崩御後の世を迎えて、大妃・弘徽殿女御は絶大な権勢をもってどのように屈辱を解消していくだろうか?
源氏が御息所への未練で悶々とする頃、桐壺院は自分の亡き後の世の中の勢力の推移を案じる。ご病状の悪しき折、院は朱雀帝へ、春宮のこと、とりわけ源氏について「かならず世の中たもつべき相あり人」だからと軽んじることのないよう言い残す。朱雀帝は院の思いを重く受け止めた。父親の愛情の深さがあふれる描写である。遺言、院崩御の物語には、権力の転換に筋道をつける通過点。物語はなお波乱が起こりそう。
2012年10月3日 賢木上巻 別れの櫛
都を去るときが来た。物見車の多さは昔と同じで、「ありさま変りて」参内した御息所の栄華盛衰は衆目を集めた。夢幻のように過ぎた日々、喜怒哀楽までもよみがえる御息所の孤独感は、自らの「決断」を信じることで救われていた。
御息所は「悲しみの先へ」行こうとしていた。流してきた涙が心を耕し、すがすがしく生きる道は伊勢下降にある…そう信じて旅立つのだった。
「別れの櫛の儀」で涙した帝の恋情、女房たちと殿上人たちとのそれぞれの別れ、故東宮との別れが二十歳であったという独白も添えられ、別離が重層的かつ鮮明に描かれて印象深い。源氏は「どうしようもない切なさ」をこの恋から与えられただろう。六条御息所というキャスティングによって、コントロール出来ない恋情の切なさや、別れの喪失感を濃厚に味わうことができた。
俵万智は『愛する源氏物語』冒頭で「和歌は心の結晶。ここぞというときの和歌には登場人物の思いが凝縮しているわけで、それが恋のゆくえを大きく左右したりもする。」と書いている。
未練断ちがたい源氏は詠った。
ふりすてて今日は行くとも鈴鹿川 八十瀬の波に袖はぬれじや
誇りを取り戻した御息所は、きっぱりと返した。
鈴鹿川八十瀬の波にぬれぬれず 伊勢まで誰か思ひおこせむ
野の宮の一夜を持ってしても距離は埋められない。身を投げ出すようにして辛さを訴えた男女を隔てる霧は、すっきり晴れることなどない…、紫式部の声が聴こえてきそうだった。
男女の距離感は人知の及ばない普遍性をもって読者へ迫り、「ただならぬ美しい朝ぼらけ」が再出発を祝す緞帳のように、憮然と眺めるしかない源氏の喪失の深さを浮き上がらせる。「霧の隔て」と「美しい朝ぼらけ」、なんと見事な恋のエンディング装置だろう!
一言感想
輿に乗り、斎宮の「別れの櫛の儀」のために内裏に参上する御息所。かつて同じように乗った輿だが、故宮に嫁いだ華やかさとは打って変わって、今回の輿の乗り心地は針の莚のようなものではなかったか……。それでも心の内は別として、御息所の姿は凛として格好いい! やっぱり御息所、女として最高です。源氏にはもったいないのでした。
取りこぼした恋の喪失感で心乱す源氏と、取り戻した誇りで決断の刻を潔く受け止める御息所。伊勢下降の行列は、去る者と見送る者たちとのさまざまな別れを彩るものでもありました。御世代わりまでは都へ戻れない、まだ稚さを残す斎宮に、帝は涙を流したし、華やかな袖口をみせる出車の女房たちの数だけ、殿上人たちとの恋の別れがあり、それぞれの喪失感を併せた華やかな行列が、伊勢を目指して都を去って行ったのでした。……源氏と御息所の恋が終わりました。野の宮で互いの気持を確かめることが出来ても、鈴鹿川を挟んだ二人の間を隔てる濃い霧が降りました。御息所の再出発を祝すような「ただならぬ美しい朝ぼらけ」を憮然と眺めるしかない源氏の恋の痛手。「あわれなるけをすこし添へたまへらましかばとおぼす」とつぶやく男の、ないものねだり・身勝手、絶滅危惧種的単細胞ぶりは古今変ることがありまへん!
16歳の時は父大臣の限りなき筋におぼし心ざして、女性としては皇后となる最高の栄誉を感じながら内裏に上がったが、20歳の時に東宮を亡くし、そして今、30歳になり、自分で自分の人生を清算すべく都を下る決心をし、九重を見る。この短い文で御息所の人生とそのきっぱりとした人格がよく現れている。すごい!!
とうとう伊勢へ出立してしまった。潔く去って行った御息所といつまでも未練がましい源氏とが対照的。失って初めて知る相手の偉大さ。後悔先に立たず。
先日「およすく会」恒例の旅で訪れたばかりの、平安のたたずまいを残す大覚の風情。十二単衣を纏って楽しんだひと時を思いながら、今日の一節の物語を読みつつ…高貴な家柄に育ちながら栄光の道のりを途(ママ)されて、源氏との恋に狂おしいほど己を責める雅な御息所が等身大に浮かぶ。
きっぱりと過去を断ち切る女。未練断ち難く悶々とする男。短い古語の表現ながら式部の描写力にまたもや脱帽の至りでした。
御息所の今までの人生を振り返る歌に源氏が未練で詠う「袖ぬれじや」に対して、御息所の「ぬれぬれず」に、現実の中に生きている女性がいました。空蝉、夕顔、葵、御息所、それぞれの別れの中に、源氏の成長してきた様子が丁寧に書かれていると思いました。
これで御息所とお別れです。彼女の最後の歌で、心が少し明るくなりました。
2012年9月5日 伊勢出立
あの日の「車争い」が世間へ、通いどころの一人でしかない女だと知らしめた。源氏に捨てられた女…、伊勢下向はその噂を決定的なものにする。現実を変えることができない恋の果てを世間へ暴くのが伊勢下向の行列だった。御息所の生き辛さと、ご褒美のように訪れた野の宮でのひととき…。
泥田を這うような恋の辛さも、世間への恥さらしな事ごとも「若々しきもの思ひをして、つひに憂き名をさへ流し果つべきとこと…(葵巻p129)」と受け止めた御息所。若々しいもの思いの挙句に生魂の噂まで流した苦悩が、源氏との最後の一夜で浄化されていくようだった。
だが一方、並々でない女として遇してきたはずの御息所から捨てられる惨めさを感じる源氏は、納得がいかない。未練がある。世間体が悪く、恥ずかしくもある。世間にも御息所にも、薄情な男と思われたくない。だから過分な餞別は、世間体と未練を繕う源氏のリベンジだろう。しかしそれもこれも恋の残滓でしかないのだった。翳りを帯びて描かれた女の儚かなさの中に横たわる沈潜した時間が、新たな展開・伊勢へ赴いていく。
母を伴う伊勢下向に「うれしとのみおぼしたり」という幼さが語られ、著者は初めて斎宮の人となりを描き、御息所の母としての立場も浮き上がらせた。「普通でないワケアリ」に恋心を引かれる源氏は、御世代わりになれば斎宮に会う機会も訪れるだろうと(現帝に対しても不謹慎!)、と思う。斎宮に関心を持った源氏について、語り手は「…かならず心にかかる御癖にて」といいわけをする。この手の源氏の癖について、俵万智は『愛する源氏物語』の中で、「いみぢうあだめいたる心さまの源典侍」を例に、中村真一郎との対談を引用している。
~若いときに恋愛をするのはごく自然なことだ。ある意味、それは本能でもある。が、「本能の時代」が過ぎた後にも、異性とのやりとりを求める気持ちというのは、これはもう人間だけがもつもの。つまり文化だろう。「文化としての恋愛」は「本能としての恋愛」よりも、ずっと難しく高度なものだ。
(そういえば、「不倫は文化である!」と言って物議を醸したタレントがおりましたなぁ。)
源氏と御息所の世間への体裁の差異を通して、男女間には超えられない「暗くて深い」川があることを顕かにしている。
恋愛の終わらせ方は十人十色である。逡巡の末の、野の宮の熱い一夜で描いた「恋の幕引き」は、御息所にふさわしい。「野の宮の別れ」は視覚と聴覚を存分に刺激して、読者を陶酔させた。
一言感想
未練たらたらの源氏くん。御息所の伊勢下向をくい止めようと、斎宮宛に文を出すなんて、見苦しいですよ。 今回の場面は、御息所と源氏を通して、女と男の心模様の違いがクッキリと描かれている。ウーン、式部女子、あなたはスゴイ!
男と女の違いがきっちり書かれていました。
斎宮の大人っぽい皮肉な歌を、源氏が「ほほゑみて」読んだのはどうして? → 当時の常識として、女は最初にきた和歌に対して、まず否定的な歌を返す。「恋」はその後の和歌のやりとりを通して、互いの教養の程度に応じた展開をしていくからだそうです。斎宮に和歌を送った無神経な男心のあり様は、視点を代えたら、純情で、真剣で、真面目な男心なのですかねー。御息所も源氏も、相手に「捨てられた」と思っているが、捨てたのは源氏です。斎宮に興味を持ったことに関して、デートしている男が美人に視線を流すなんてことは、現代でもあるでしょう、と受講者の一人がいいました。これって男の本性! 紫式部の人間観察の深さを感じます。
二人の思いはいろいろあったが、御息所の別れの決意は固く、とうとうその日が来た。往生際の悪い源氏は、今度は斎宮が気になってきた。事情のある人(斎宮)に心惹かれていく(癖のある)源氏はどうするのでしょうか、先が楽しみ!
伊勢出立が動かせない事実となり、源氏の未練は断ちがたかった。しかしこの期に及んでは、御息所へ執拗に迫るのは、未練がましい。男と女の世間体という壁がリアルに描かれたが、それにしても、斎宮へ女としての関心が芽生えていく源氏という男、ワケアリ好きな「こりない男」ですなぁ。御息所という手中の珠を取りこぼした源氏の無念さと新しい恋への期待が、オヤジ臭くてコッケイです。御息所の恋の幕引きに納得、こうでなくちゃね!
美しい月夜、静寂な夜も明け、場面は展開する。野の宮の別れの余韻も覚めやらぬ源氏は、熱烈な思いを込めて後朝の歌を送る。燃え立つ思いの源氏に対して、御息所はこれまでのことを「起き臥し嘆きたまふ」が「いとかいなし」「何ともおぼされず」と全てのことを冷静に受け止める。語り手の辛口コメントを織り交ぜた源氏の「まめおとこ」ぶり。気の多い ひかる様である。トホホ。
2012年8月1日 野の宮の別れ 文責 染谷久美子
暑いですね!
でも今年は暑さが少し控え目か、朝晩が楽ですね。
さて、八月は一言感想だけを載せます。
☆☆さぁ、二人の別れの場面である。
九月七日の(ながつき なぬか)の月を背景に 思いを重ねるように
二人の心のすき間が埋まっていく。
この場面を月が効果的に盛り上げる。
う~ん、紫式部はすごいなぁ、この演出力。
九月七日の月を「おお!」と頭に描ける当時の人々(昔の日本人)
の感性もすばらしい。
また研究者ってここまで拘って調べるのねえと感心しきり。
☆☆御息所は「やうやう今はと思い離れたまえるに」、波立つ心をおさめ
伊勢下向を決めていたが・・・野の宮を訪れた源氏の熱い思いに
「さらばよ」と心乱れる。
静寂の庭では松虫の鳴き音が一層あわれを催す。
七日の月の一夜の逢瀬。
御息所、源氏、女房達のそれぞれの心に余韻を残して
夜も明けてゆく。
雅な貴婦人御息所についついなおざりに、しかし別離の折には
熱く優しく切なく寄り添って読み手の心を揺さぶるのです。
☆☆*目の前の女が居なくなる事によってしか その女の素晴らしさ
を受けとめられない未熟な源氏の悲しい別れでした。
*野の宮の別れの時の一刻一刻はその夜の月の動きの元にきざまれて
いたことが分かりました。
*空、月、庭そして松虫の音。
最高の美意識を持つ二人の別れにふさわしい舞台装置でした。
*月影の姿、残り香、五感すべてに響いてきた文章でした。
*闇の中だから二人は心からお互いを解放出来たのでしょう。
☆☆野の宮の趣深い風情(月や虫)と二人の別れのシーンと月の鑑賞の
解説はよかったです。
野の宮での月は七日の月でこの場面で月は重要な役目を果たしている
とのことでした。
☆☆紫式部はここまで舞台装置を計算しつくしていたのか!
北の対に入る時は月が源氏の姿を浮かび上がらせ、「まねびやらんかたなし」
というほど寄り添って語りつくすその時は、闇の中。
闇の中では二人は今までかぶってきた鎧を思い切りはずせたことでしょう。
「二人でドアをしめて~二人で~名前消して~♪」という歌があったなぁ。
素のままになったっていうことですね。
月ばかりでなく「をり知り顔なる」松虫の声とか、庭のたたずまいも
「げに艶なるかたにうけばりたまえるありさま」とか今回の舞台装置は
大盛りである。
さてまだまだ暑さも油断できませんが・・・
でも私は御自愛しすぎて体重オーバー (-_-;)
油断ならん・・・
2012年7月4日 榊のしるし
夕月夜である。煌々と降り注ぐ月光が、枯れた景色の夜の顔に映え、源氏の美しさをいっそう輝かせていた。
心のままに会う都合のいい女・御息所との関係が、ずっとつづいていくはずだった。会えばまず無沙汰の弁解を重ねた残忍さに気づいたいま、習い性になっていたその場しのぎの言葉が出てこない。言い訳を積み上げた嵩の丈、その嵩高さこそが、御息所の傷ついた自尊心であると気づいたのだ。もう二度と舫いあうことのないときを迎えて、源氏は失うものの大きさにやっと気いたのだった。
心に言葉が追いつかない源氏は、心弱く泣くしかなかった。さめざめと洗い流すものは、女への愛に気づかずにここまで来てしまった悔いである。ただ泣くことで、悲しんだぶんだけの解放を得て浄化されるとでも言うように、源氏は泣く。すすり泣きは枯れた風景を包んだ闇にとけていき、低音部のトリル(2度高い音と交互に演奏される?)を奏じて、野の宮に吹き渡る静寂を際立たせる。
「人生はときにどこかで誰かの人生と交差する。偶然の一点で交わったあと、それぞれの方向へ遠ざかり、すべてはぼんやりとした全体へ含まれて消える」(龍應台著・台湾海峡1945より)
悲しみは濃くなることはあっても淡くなることはないと思わせる場面展開で、源氏の悲しみが飽和点に達し、滴となってあふれ出た。御息所を癒すものがあるとしたら、飽和点に達した源氏のすすり泣きだけだったに違いない。
御息所との別れの舞台として、野の宮の晩秋の景色は実によく響きあう。神域の静寂は、別れの場面の重要な装置になっており、静寂が響きわたる野の宮の大きな空間を充たすのは、源氏の悲しみだけだった。この刻を御息所は心に秘して持ち歩き、生涯支えられていくに違いない。
悲しみにはさまざまな貌がある。紫式部は一人ひとりの悲しみをひと括りにせずに、源氏物語の中で丁寧に確認してきた。一組の男女を通して、その男女にふさわしい場面が選ばれ、別れが設定され、いま我々は野の宮まで導かれてきた。夕顔や葵との別れの貌とはまた別の、悲しみの棲家がここにある。煌々とした夕月夜の明りは読み手の心へも差し込んで、読者もまた持ち歩いてきた悲しみを照射されるのである。
神域の夕月夜にとけていく静寂の低音部を支えるトリルを聴きながら、なんともいえない緊張に包まれた場面であった。愛するがゆえに深く傷つく淋しさが、晩秋の寂寥に溶けていく。深化する物語の奥ゆき。
一言感想
月ごろのつもりをつきづきしゅう聞こえたまはむも、まばゆきほどになりにければ……。今まで会えば言い訳の言葉を重ねてきたけれど、月のはなやかにさし出でたる夕月夜に御息所に向き合うと、初めて今までの言葉の軽さに気づき、言葉を失う源氏。でも源氏が初めて自分をさらけ出してくれて、御息所はうれしかっただろうな。
御息所をまえにした源氏は、いつものような無沙汰の言いわけ・おざなりの弁解を口にできなかった。ためらいを憶えたのは、御息所と心をつなぐ言葉を、いつの間にか失っていたことに気づいたからだ。だから源氏はただ泣くしかない。会いたいときにはいつでも会えるはずの女と、そう思うようになっていったのは、いつ頃からだったか。源氏は、失ったものの大きさに愕然とし、自分の慢心が御息所を傷つけてきたことに思いいたる。この場面の源氏は、昨日までとは違う成長を見せた。名場面だと思う。講師から、身分を超えた男女の対等な心をつなぐ言葉として和歌がある、と解説があり、和歌が内包する世界への標となった。「人生は大切なものを失いながら、それでも生きていく」若者には気づけないこの言葉の重さがわかる歳に源氏と出会えたことは幸せです。
ハイレベルな歌のやりとりに圧倒された。久々の二人の逢瀬。野の宮の場面は、源氏がこれまで軽く扱ってきた御息所への仕打ちを後悔する涙なみだで、講義は終わる。二人は心通った言葉を重ねあうのだろうが、「なーんかねぇ」と、ちょっと複雑な気分。源氏君、ちょっと身勝手じゃないの?
和歌のやりとりで始まった会話や、気持を伝えることが余りに深くて、講師の解説なしでは理解出来ないことがたくさんあり、有意義な勉強会でした。感激です!
はなやかに出でたる夕月夜。煌々とした月明かりに浮かぶ源氏の姿はまさに光の君であろう。斎垣を越えて一夜の逢瀬に、榊の小枝をもちて古歌をなぞらへ、切々と御息所へ心のさまを伝える。闇の中での男女の得もいわれぬ息づかい。映像では表せない深い場面である。
ここら思ひ集めたまへるつらさも消えぬべし→御息所の苦しみからの解放。言葉で心をつなげない。言葉が出てこない。その時、和歌が二人をつなぐ。だんだんと昔を思い出し、我が身を責め、心弱く泣く源氏。この涙は心からのものだったと思えました。自分の今までの仕打ちが見えてきたのは、彼が歳を重ねて来たから、と感じました。御息所の知的優位を知らされた場面でした。
2012年6月6日 P.4~野の宮へ
受講冒頭に、賢木巻・嵯峨野の描写は源氏物語屈指の名文、と講師からの解説があり、荒涼とした、しかしそれ故に美しい景色の中へ、読者は源氏と伴に導かれていった。美しさとは寂しさと背中合わせなのか……嵯峨野の晩秋が拡がっている。
都から遥けき野辺を分け入った嵯峨野で、他所とは異なる風情と出会う源氏。そこは趣き深い、という一言では括れない、枯れた季節が見せる別れの舞台である。嵯峨野の晩秋の描写、情緒的な美的感覚は、千年の刻を経ても色あせてはいない。むしろ新鮮な感覚を呼び覚ましていく。美的感覚への追憶、培った美意識への恋慕、とさえ言えそうな冴えた筆が紡ぎ出す景色は、決断を迫ったギリギリの心情と重なる。このような景色の点景として包み込まれたら、誰だって胸を締め付けられるに違いない。
源氏はかってのように恋人をかき口説いた。この恋人を得るために熱心に口説いた若い日のように、心を込めて情熱的に口説いたのだった。
「北の対の、さるべきところに立ち隠れたまひて、ご消息聞えたもふに、遊びはみなやめて、心にくきけはひあまたきこゆ。何くれの、人づてのご消息ばかりにて、みづからは対面したもうふべきさまにもあらねば、いとものしとおぼして、『かうやうのありきも、今はつきなきほどになりにてはべるを思ほし知らば、かう注連のほかにはもてなしたまはで、いぶせうはべることをも、あきらめはべりにしがな』と、まめやかに聞えたまへば」という口説きで、女官たちがおち、「いともの憂けれど、情けなうもてなさむにもたけからねば、とかくうち嘆き、やすらひて、ゐざり出でたまへる御けはひ、いと心にくし。」となる。
「六条御息所のあはれさは、自尊心と同時に深い情をあわせて持っていたことでしょう。自尊心の傷つけられ方に対する怒りを伴っていたことは見逃せない。~六条御息所を苦しめたものは、人一倍高い自尊心に密着した、深い愛情とあふれ尽きない熱い情熱であり、自尊心と濃密な情との相克にひき裂かれ、生霊となって宙をとんでいった」と円地文子は解説しています。「源氏は七つ年上の御息所に興ざめたのでもなく、彼女の世に聞こえた才華や美貌・サロンの女主人としての大きさ、それらのすべてに感動もし、理知に統一された貴婦人の底深く沈んでいる鋭い触覚を持った情熱に、本能的な畏怖と崇拝とを(源氏は)感じたに違いない。」とも言っています。賢木の巻きで、御息所の決断はどう描かれていくのでしょうか。
一言感想
野の宮の神域において、源氏も来訪は1つのケガレであろう。特に一大決心をした御息所にとっては……。それを悩みながら、受け入れざるを得ない御息所の揺らぐ女心。「つっぱねちゃえ、つっぱねちゃえ」と思わず御息所に肩入れしてしまうけれど、それにしても源氏の行動は…ねぇ。
いさやここの人目も見苦しう、かのおぼさむことも若々しう、出でいむが今さらにつつましきこととおぼすに……。御息所の揺れる気持がよくわかる。女房の手前やら、源氏の手前やら、場所も神聖な所だし…と迷う。美意識の強い御息所はつらい。それでもいざり出たのは、やっぱり源氏に会いたい気持が勝ったのね。
「賢木巻・野の宮へ」の冒頭文は、源氏物語の中でも名文として有名だそうだ。嵯峨野の荒涼とした晩秋の美しさに筆を尽くした紫式部。季節が彩った装飾が朽ち果てて、裸になっていく風景の趣きが、「これでもか!」と描かれている。季節の変わり目ギリギリの際が見せる枯れた景色は、美しく「艶」であると式部は描写する。暮れていく野の宮辺りと、恋の終焉を迎える男女の心象風景が重なり、遠くに火焼屋の灯りが頼りなくぼんやり揺れるのも、松風に吹き消されてしまいそうな恋の灯火に似て、切ない。とはいえ、今さら男が言葉を尽くしてくれてもねぇ、光の君ちゃん、今さら恋の寸止めはあんまりじゃありませんかぁ?
挿入部――遥けき野辺~「いと艶なり」の部分は情景が本当に美しく目に浮かんできます。ゾッとするほど寂しい目の前の風景に、虫の音の合間あいまに松風が運んでくるかすかな管弦の音。この一文は映像的な世界でした。源氏を目の前にした御息所の心の迷いが彼女の動きにみられました。
野の宮があまりに荒涼としたもの寂し気な処であり、ここに身を置いて過ごしている御息所を思い、すぐにでも会いたいところだったのに、そうあっさりとは会ってもらえない。手前勝手といえば手前勝手と思うが、一歩踏み込んで、この後どうなるか、楽しみです。
「遥けき野辺に分け入りたまふありいとものあはれなり」。究極の恋の決別にふさわしい深まる秋の情景と御息所の葛藤が切なく重なって、今回も魅了されっぱなし。美しい古語に導かれ、先生と皆さんと一緒にイメージを膨らませながら読めることで、物語の楽しさが倍増します。
2012年5月2日 P.1~原文からひろがる源氏物語 賢木上巻 決断
「袖濡るるこひじとかつはしりながらおりたつ田子のみづからぞ憂き」
『原文からひろがる源氏物語ー葵の巻』あとがきで著者・田中順子は言う。この歌には嫉妬・怨恨などのどろどろした心情のひとかけらもなく、心のままにひたすら己を見つめる澄み切った眼差しがあるだけである、と。また、この歌を頂点とする「葵の巻」は状況というものに翻弄される人間の姿を意識の底までも追っていくリアリズムの目で捉えた世界が、見事な構成力をもって映し出されている、と洞察した。
「賢木の巻」ー決断
伊勢へ下ることで、源氏との決別を図る御息所。だが源氏にしてみれば「じゃ、さようなら」と突き放すわけにはいかない。北の方に迎えるのではないか、という世間の眼もある。元東宮妃の、サロンの女主人として人々を魅了する教養と感性には惹かれており、源氏にとっては、末永く通い処にしておきたい女だった。
伊勢へ下る日が迫っていた。御息所のもとへ源氏から文がしきりに届けられる。愛した苦しみから抜け出す鍵は、苦しみそのものの中にあり、だから存分に苦しまなければならないと、紫式部は言いたげで、抜き差しならない存在・源氏への思いと、決断を超えてなお立ち上がってくる恋情で、濁流をいく木の葉のように心が揺れる御息所。
泥田を這い回るような苦しい恋が、女の心を耕してきた。そして伊勢下降という選択を生み、すがすがしく己を生きるための糧になろうとしていた。だが、ひるがえることのない決断であっても、男の泣き落としの責めで崩れそうになる。御息所は「決断」という大きな波を、崩してしまうだろうか。
逡巡し、繰り返し己に言い含めた決意であっても、男にせがまれれば、激しい曲線を描いて崩れそうになる。恋に殉じる揺れは、読者を共感の海へ投げ出し、拡がっていく。
決断は悲しい曲線を崩しながら、……さめざめと悲しく、混乱の刻となる。辛い恋は深く苦しむことでしか、その先へ行けるはずもないのだ。
「不在」という「別れ」への出会い方を、夫との死別で経験していたのに、恋を手離すことにはまだ不慣れな御息所は、向っている方向が前だと信じるしかないのだった。
会えば瞬時、充たされるものがあるだろう。しかし充たされれば、また縛られてしまう。御息所に仮託した恋の表皮を通して、決断してもなお熱く揺らぐ恋情が、読者へ迫る。紫式部は、読者をも翻弄しつつ、恋情の内側を見つめさせていく。
一言感想
人の心はカタがつかないやっかいなもの――斎宮となった娘と伊勢へ下る決心をした御息所の、心は止めどなく揺らいでいる。その身を捩るような想いが、ひしひしと伝わる。「賢木」の巻きの始まり。さて、物語がどう進んでいくのか、楽しみである。
斎宮と伴に伊勢へ向かう御息所の決意に至る……源氏との重い関係に、悩む切なさ、その気持を源氏は「人聞き情けなくやと…」野々宮へ。辛い思いの御息所の心に波紋を投じる……。自己中心に思えるけど。
いよいよ「賢木」に入った。六条御息所の心の動きが微細に描かれる。揺れる女心。賢い女性であるが故に、その女心は切ない。読者(私)は毅然と生きて欲しいと思いつつ、恋に溺れてもいいのではないか、とも思う。次から次へと、紫式部はやはり…スゴイですね。
ひょっとしたらもう最後になってしまうかも知れない。別れへの迷いを断ち切って伊勢へ行こうとしているのに、心をかき乱さないで! という感じです。また気持が揺れ動いてしまうじゃないですか……。微妙な心が動きが素晴しいです。
御息所は、恋心を封印して伊勢へ下る決断をした。とはいえ、理性ではコントロールできない思いもある。恋の、実りの果実を味わうことはないことはわかっている。男の心が離れていることもわかる。だから決断をひるがえすことはないのだが、しかしひと目あいたい。声が聴きたい。あの車争いの屈辱のなかでさえ、遠目に見た源氏の晴れ姿を、見てよかったと、そう思えた恋の熾火(おきび)が、御息所を翻弄する。全てを捨てて恋に殉じることができる女が、世間体へ細かな気配りができる男の口ベッピンに翻弄される残酷。
「賢木」が始まりました。御息所の、抑えても、抑えても、揺れ動く心が愛おしい。「かき絶え」の表現が現実を冷静に伝えます。手紙のやりとりが重なり、ついに会うこととなった御息所の「人知れず待ちきこえたまひけり」のドキドキが聴こえてきました。「葵巻」に続いて、御息所は、私たちの心を躍らせてくれます。
性格の激しい御息所にも、源氏に会いたい気持を世間の体裁を考えて、押さえに押さえ、源氏もよい意味での後くされのない、よい別れをしたかったのでしょうか? 源氏物語に詳しくない私には、源氏の気持と御息所の気持が、現在でも古でも、変らないものと感じました。
2012年4月4日 左大臣家の新年
左大臣家へ新年の挨拶に訪れた源氏。「新年」「正装した源氏」「左大臣家」という輝かしい幸せのイメージをくつがえした葵巻の最終章は、「その後」を生きる悲しみへと傾斜していった。
あまた年今日あらためし色ごろも きては涙ぞふる心地する
新しき年といはずふるものは ふりぬる人の涙なりけり
大君と源氏が元旦に交わした歌は、物語の底流を流れている世界観を垣間見せる。桐壺帝譲位から朱雀帝即位、葵の懐妊そして車争い、生霊、六条御息所の懊悩、若宮誕生と葵の死。若紫との結婚などなど、葵の巻を彩ってきた華麗で寂しく悲しい展開。大切な人を失なってなお生きていく悲哀を、読者は物語の登場人物と伴にのぞき込み、尽きない余韻に包まれた。
葵巻 印象的だった和歌
恋路に苦悩する六条御息所の歌
袖ぬるるこひぢとかつは知りながら おりたつ田子のみづからぞ憂き
生霊の歌
歎きわび空にみだるる我がたまを 結びとどめよしたがひのつま
葵を失った母宮の歌
いまも見てなかなか袖をくたすかな 垣ほ荒れにし大和撫子
葵の死を悲しむ源氏の歌
のぼりぬる煙はそれとわかねども なべて雲井のあはれなるかな
若紫の新枕の朝 源氏の歌
あやなくも隔てけるかな夜を重ね さすがになれし中の衣を
一言感想
亡き娘への深き愛を、父に感じました。
葵の巻が終わりました。何と深い心の世界であったことか。最後は左大臣家の娘を亡くした父と母の悲しみ。そして情の深い・義理の父母への源氏の思いが、あふれていました。早くに親と祖母を亡くした源氏の優しさを感じました。左大臣の目に映る大人びたきよらの源氏と、元服式の日の源氏が重なりました。
例年の新年とは違って、喪の明けていない正月を寂しく過ごしている二人のもとへ源氏が訪ねて来たことで、「おめでとう」はなく、涙で終わるのは並大抵のことではないだろう。葵の巻きは深かったなぁと思った。源氏の典侍や車争い、御息所の怨恨やら葵の上にとりつく生霊、そして死、紫の上との結婚等など。
一年余りかけて葵の巻を読み終わる。父帝桐壷帝から朱雀帝へ。車争いの描写から始まる物語は深く、濃く、重く、悲しく、切なく、物のあわれが緻密に綴られる美しい古語に導かれて、今までになく圧倒された巻であった。次の展開に更なる期待。
元旦、正装で左大臣家を訪れた源氏へいつものように、大宮の心を尽くした装束が用意されていた。ただ例年と異なるのは、源氏の装束に並んで華やかさを放っていた葵の装束が、そこにないことだった。遺児は愛らしく成長しており、機嫌よく笑うのも哀れである。大宮の悲しみに添う源氏。語り手もまた、正月の涙であってもおろかなことではないと、葵へのそれぞれの鎮魂に寄り添う。艶やかで華やか、そして寂しく悲しかった巻は、しみじみとした余韻をいつまでも微かく震わせながら閉じていった。
大きな秘密を抱えた源氏は、成長した若君が春宮に似ているのでは、と疑心暗鬼になる。ま、無理もありませんね。それにしても、左大臣家の新年は痛々しい。大宮の心に春が来るのはいつのことなのか……。それぞれの女性の心のありようを、リアルにえぐってみせた「葵」の巻。五十四帖の中でも圧巻のひと巻でした。
2012年3月7日 P192~ まことのよるべ
ささやかだが、心づくしに充ちた三日夜の餅の祝いが終わった。束の間でも新妻から離れると、落ち着かない源氏。かって経験したことのない、初々しいまでの恋心は、源氏に「我ながらあやしの心」であると思わせるほどであった。源氏はこの期に紫の上の裳着を行い、新妻の父宮へ知らせて、世間への認知をしようと考える。紫の上は、裳着(女性の成人式)のまえに結婚した、父宮にとっては行方知れずの娘だ。父宮へ知らせ、紫の上を世間に認知させたい。
もう少女ではなくなったという現実が、受け容れられない新妻。そんな自分自身と格闘し、拗ねている。新妻と新郎の心が細やかに描き分けられ、結婚におけるの男女の差異は、二人の関係を暗示して興味深い。
紅葉賀以来2年つづいている有明の君との仲を、空席となった源氏の正妻の席へ置いてもいいと考える右大臣と、是が非でも入内させたい弘微殿の確執。この年が暮れていき、新年を迎えた。
「まことのよるべ」は、古語だからこそ描ける世界、デリケートで繊細な性的な感覚に踏み込んでいる。豊かな性的な感覚を、平安時代の人々は的確な表現をもつて描ききっていた。「まことのよるべ(妻」「新手枕(新妻)」「夜をや隔てむ」などなど、現代語では表現できない奥深さであり、古語の魅力を余すことなく現代に伝える。
読後一言感想
これまで付き合ってきた多くの女性たちとは距離をおき、自分の心に正直に生きたい、と思い始める源氏、。女君への想いは募るばかりである。…でもね、女君と「まことのよるべ」をするには、ひとえにこれからの君の行動にかかっているのだよ、とオバサンは思います。
女君を妻にしたことで源氏は満足しているが、女君はどうしても今の自分を受け入れられず、不機嫌な様子が描かれていて、素晴らしいと思いました。男性の思いと女性の思いの違いがいいです。
女君の自己嫌悪を理解できます。新鮮な女への愛おしさいっぱいの男君。二人の間には永遠のテーマ「男と女の深い川」が横たわっています。源氏にぶつける紫の心の葛藤が、ストレートに書かれていました。
「まことのよるべ」として、手塩にかけて育て上げた紫の上はふさわしい、と源氏は思う。花宴で出会った有明の君とは、紅葉賀以来2年間つづいていた。弘微殿は入内まえの妹に近づいた源氏に激しい怒りをもっているが、父・右大臣は北の方を亡くした源氏に乗り換えてもいいじゃん、なんていう。結婚は政治なのだ。源氏には正妻として申し分ない恋人・六条の御息所がいたが、「心置く人」なので、ブッチャケタ話、これまで通りに通い処のひとつにして置きたい。新妻への愛おしさが募るなかで、源氏はあれこれ思いを巡らし、一方「まことのよるべ」となった新妻は、源氏との関係の変化についていけない自分を持て余している。女心の揺れ、そして優しさとしたたかさと気配・計算などなど「できる男」のストレートさが描かれていて、興味深い。
惟光の計らいで三日餅の祝いもすみ、男君は女君を正式の妻にと準備を進める。ひと時も女君の側を離れたくないという源氏の心持は募るばかり。「静心なく…」ひたすら女君を思うが、女君はますます疎ましく「あさましき心なれど」頑なに心を閉ざす。二人の関係は修復できるでしょうか…読み手は気を揉み、式部は次の展開へつなげる。重い関係だが感性豊かな御息所への断ちがたい思慕。そして桜の夜の姫君との危うい逢瀬。あ…あとのことを次の物語に期待!!
2012年2月1日 P183~ 文責 沈 光子
若紫と過ごした特別の一夜は源氏に深い喜びをもたらした。この結びつきは葵を亡くした喪失感を癒し、安息・自信・生きがいともいえる感慨をもたらした。源氏は西の対の女君を、父兵部卿宮と世間に公表しようと思う。
乳兄弟の惟光が久しぶりに登場する。夕顔が急死した際の働きぶりにみるように、彼は常に源氏の恋愛において重要な役割を果たしてきた。
若紫を見いだしたとき、保護者の尼君へ源氏の手紙を持参した惟光。尼君が死去し、父宮に引き取られそうになったことを知らせたのも彼であり、式部卿宮に先んじて若紫を自邸に引き取る切っ掛けを作った。細やかな心づかいで新婚三日目の儀式が仕切られ、過不足なく美しく完成して祝福された結婚。惟光によって完璧になされたと、この祝いの儀式で彼以上の適任者はいないと、読者は納得させられる。紫式部は惟光をこのように登場させて、あらゆる意味で源氏の危機や幸せの場に添わせていく。
読後一言感想
原文に話し言葉が出てくるとその人物たちの姿までも ヤッ! にわかに立ち上がる。匂い立つ、といってもいいほどに。これもまた原文にふれる収穫であり、面白さなんでしょうね。「あーでもない・こーでもない」と言葉が行き交うおよすく会は、やっぱり面白い。
女君の頑な姿にも愛おしさが募る。男君は はて!さて! と思い巡らす……。はた!と一計を思いつく。 久しぶりに惟光さん登場。源氏の救世主である。源氏の気持を一手に引き入れてきびきびと「作りゐたれり」。何だか知らないけど、惟光の指示に従う娘の弁。源氏の深い思いに「いとかうしもや」と感涙する乳母・少納言。
西の対の情景が行間からあふれる。古語の深さに今回も魅了されっぱなし。
源氏と惟光との夕顔以来の深い信頼関係がまた読み取れました。「片端にもあらざりけり」という源氏の若紫に対する愛情の深さよ。少納言の源氏への感謝の涙は心に響きました。
幼い若紫が幸せな女君になるため皆が裏方で頑張りました。
結婚することのしきたりや内密に気をきかせて事を運ぶ惟光は頼もしい腹心であり、頼りになる人です。
若紫と源氏が男女の契りを交わした翌日は亥の日。翌々日の子の日に惟光は源氏から大事な用を仰せつかる。北山で18歳の源氏が若紫を垣間見たときから見守りつづけてきた惟光だ。全てを了解して結婚の膳を整えた。彼の細やかな心づかいで、この結婚を過不足なく、美しく完成して祝福する。女君のために自分達こそしたかった仕事だったのに、と女房たちを羨ましがらせるほどパーフェクトに事を運んだ惟光であった。
源氏は若紫と肉体的に結ばれた喜びを、尋常で無い心境だと 吐露している。これは意味深の一言で、成熟した男でなければ言えない台詞でしょう。源氏も夕顔との出会いの頃より遥かに大人の男になったんですねぇ。
2012年1月18日 葵の巻 p179~
4年もの間、父娘のようにして共寝してきた二人の結婚。その夜も父娘のように添い寝したのだったが……、若紫は男女の契りに衝撃を受けた。ふさぎこみ、口をきかず、汗びっしょりになりながら衾を引きかぶって、源氏を近づけない。だがそんな若々しい依怙地さも源氏には愛おしい。
忌明けで二条院へ戻った源氏は憔悴しきっていただろう。久しぶりに西の対へ渡ると、若紫は少女から女性へと孵化して輝くばかりに美しかった。妻との束の間の和解、六条御息所の生魂、若君誕生、そして妻の死…深い悲しみと苦悩に翻弄されて左大臣邸から戻ったばかりの源氏には、若紫の成長ぶりがまぶしかった。それはまた妻として若紫を迎える期が熟したと思えた瞬間でもあったに違いない。
一言感想で書きそびれてしまったとメールをしてきた受講仲間がいた。若紫の涙は「源氏への信頼が崩れてしまった」という「頼る者を無くしたという悲しみがあったのではないだろうか。みなし児同然の若紫の初夜の衝撃に、自分も涙した」という。読後わずか15分ほどの間に書く一言では、旬が際立つと同時に言い足りなさも残る。ひとりひとりの源氏酔いは帰宅後もつづいて、イメージをいっそう膨らませている。源氏酔いが心を豊かに耕していく!
読後一言感想
若紫の幼さが映画のシーンのように描かれています。性教育の係りは源氏自身であった? 4年間、夫婦の関係を持つことなく大切の育ててきた源氏の優しさ。決して若紫を強奪してきたわけではなかったのだが。「よろづにこしらへ」る源氏の困った様子も目に見えるようです。
それにしても若紫の境遇を思うと、私はもらい泣きしそうでした。源氏を唯一の拠り所にしていたみなし児のような若紫には、裏切られたような絶望感があったのではなかったでしょうか。
幼妻誕生ですか…何も知らなかった女君はさぞびっくりしただろうな、と思いました。
先月、私たちは源氏と若紫の間柄の変化を得も言われぬ表現で描かれていることに圧倒された。さて、男君は思いを込めて「後朝の文」を…。しかし女君はうとましい思いが募る。「いよいよ御衣ひきかづき臥せたまえり」 二人の心のずれが端的な古語で語られる。式部の発想の豊かさに魅せられながら古語を楽しみました。
若紫の若さが際立つシーン。読者はどちらに心寄せるだろう。強情なまでの若さがまぶしく、可愛いらしく見えるのは年寄りの観点だろうか。源氏は決してロリコンの嫌らしい男ではない。懐が深い男だ。
プロローグは最近上映された源氏物語の映画で盛り上がった。今回、4年もの歳月を経て、やっと男と女になった二人の翌日の様子がリアルかつ、微笑ましい。それにしても若紫は幼すぎる。汗グチョングチョンのその姿に手をやく源氏のオロオロさも想像できるなー。
若紫は結婚における「男女の契り」に衝撃を受けた。後朝の和歌へ返歌もしない。というより作法がぶっ飛んでしまうほど平常心を無くしてしまった。衾を顔まで引き上げて汗をかいている新妻を、源氏は持て余しつつも、愛おしく、日がな一日べったりと寄り添ってご機嫌をとる。男女のことにウブな若紫の、何もかもが愛おしいのね。男はウブが好きですもん。
初夜の経験の仕方は、男女ではこのようにまったく異なるものらしい。男側の初体験談も聴いてみたいわねと、ウブな頃など思い出すのも難しい大年増たちは、この日も姦しかった。
2011年12月7日 文責 浜岡はるみ
帰邸 P-168
1) 精進⇒身を清め、心を込めて勤行する 2)け⇒原因、為 3)心苦しげ⇒心の中で痛々しく思う 4)ものを参
る⇒物を食べる 5)とやかくや⇒あれやこれや 6)おぼしあつかひ⇒世話をやく 7)中宮の御方⇒藤壺の女房たち 8)めづらしがり⇒久し振りで、面やつれ新鮮な感じ 9)命婦の君して⇒王命婦を介して 10)常なき世⇒世の無常 11)目に近く見はべりつる⇒身近に体験いたしまして 12)いとはしきこと⇒つらく、嫌な事(御息所の事も含め) 13)今日までも⇒今日まで生きて来られました 14)さらぬおりだにある御けしき取り添へ⇒そうでない他の時でさえ、中宮に会いに行く時は憂い顔なのに、それに添えて 15)無紋⇒無地16)下襲、纓⇒資料P-22,23 17)やつれ姿⇒喪服
18)なまめく⇒未熟、若々しく瑞々しい自然な上品さ 19)春宮⇒藤壺との子ども 20)おぼつかなさ⇒気掛かり
【イメージ】
妻を亡くした悲しみと、喪失感の左大臣邸から、「院が心配している」という口実?で、源氏は、そのまま院に来ました。桐壷院は、あまりに痩せ細った源氏に驚き、「妻の死に、心を籠めて勤行したからだろう」と心の中で痛々しく思い、ものなど持って来させて食べさせ、あれやこれや世話を焼きます。源氏はそれに対して、有難く、嬉しく、かたじけないと思います。父と子の心の交流と、父親の目を通して、やつれきった源氏の姿が表されています。中宮(藤壺)を訪問すると、女房達には、久し振りに会う面やつれした源氏が、とても新鮮な感じに見えました。王命婦を介して藤壺が「人の死を悼む終わりのない悲しみの数々を経験したでしょうに・・・大丈夫だったでしょうか?」と様子を聞きます。源氏は「世の無常はたいてい分かっていましたが、多くの厭わしい事(御息所の事も入っている)を身近に体験いたしまして、心が乱れましたが、貴女様の度々のお便りに慰められ、今日まで生きて来られました」と、中宮に会いに行く時は普段でも憂い顔なのに、それにも増してとても心苦しげなご様子と語り手が。
無地の正装に、灰色の下襲と、纓(被り物に伸びた、たれ)を巻いた源氏の喪服姿は、華やかな装いよりも、自然な品のある瑞々しさが勝っていました。春宮(藤壺と源氏の子ども)にも長い間お会いしていない気掛かり等を話して、夜遅く二条の院に帰られました。
P-171
1) 払ひみがき⇒ピカピカに掃き清め 2)男女⇒上から下までのあらゆる人々 3)上臈ども⇒身分の高い女房達
4)まうのぼり⇒里に下がっていたのが、源氏が帰って来たので、二条の院に参上した 5)装束き⇒着飾って 6)かのゐ並み屈じ⇒別れの時、悲しみに押しつぶされ、居並んで体を折り曲げていた左大臣家の女房達 7)たてまつりかへ⇒普段着に着替えて たてまつる⇒着る、食べる、乗る 8)西の対⇒姫君の住む建物 9)衣がへ⇒冬十月一日、夏四月一日衣服だけでなく調度品も、部屋の作りも替える 10)くもりなくあざやかに⇒左大臣家の喪の色に対して鮮やかに色がある 11)よき⇒最高に美しい あし<わろし<よろし<よし 12)めやすくととのへ⇒見苦しくなく、見て感じが良く整えて 13)心もとなし⇒不安に思う所がなく 14)心にくし⇒奥ゆかしく、行き届いている 15)うつくしう⇒愛らしく可愛いい 16)ひきつくろひ⇒身なりを整えて 17)うちそばみ⇒横を向いて 18)かたはらめ⇒横顔 19)心尽くしきこゆる⇒自分が心慕って止まない 20)見る⇒見られる 結婚する 婚ひ(まぐわひ)⇒目と目を合わせる
【イメージ】
二条の院は、ピカピカに掃き清められ、あらゆる男、女達は、源氏の帰りを、今か今かと待ちわびていました。身分の高い女房達は、里から戻り、我も我もと着飾って化粧しているのを見ると、別れの時に、悲しみに押しつぶされ、居並んでふさぎ込んでいた、左大臣家の女房達を思い出し、胸が締め付けられます。普段着に着替え、姫の住む西の対へ渡って行きました。季節は、冬への衣替えで、部屋の調度品も、喪中の左大臣家の色に比べ鮮やかに見え、若人や童女達の姿、容姿は、見苦しくなく美しく整えられ、少納言の裁量は、心憎い程と思われました。
姫君は、とても愛らしく、可愛く身なりを整えていらっしゃいました。「しばらく会わない内に、すっかり大人らしくなりましたね」と言って、小さい几帳を引き上げて見ると、横を向いて恥じらうその様子に、飽きる所はありません。灯影に浮かぶ横顔、髪の様子は、ただ、何と、自分が慕ってやまない人に、そっくりになっていくと思え、とても嬉しくなる源氏です。
P-173
1) おぼつかな⇒気掛かりな事だ 2)日ごろ⇒留守の間の 3)物語⇒雑談、世間話 4)いまいましう⇒妻が亡く
なったので忌み慎まなければならない 5)異方(ことかた)⇒別室 6)今は⇒これからは 7)とだえなく⇒何時でも 8)見たて⇒お会いする 9)いとはしう⇒煩わしい、うるさい 10)ものから⇒と思うものの 11)やむごとなき⇒社会的に上の身分で重きを置いている 12)忍び所⇒密かに通う所 13)かかづらふ⇒入り組んで関わっている 14)わづらはしきや立ちかはり⇒面倒くさそうな、北の方に代わって(君臨する) 15)憎し⇒見苦しい、気のまわし過ぎ 16)すさび⇒慰みに・・する 17)若君⇒葵との子ども 18)あはれなる御返り⇒左大臣家からの気の毒な返事 19)おぼしも立たれず⇒外出しようという気にもなれなかった
【イメージ】
姫君の近くに寄って、留守の間の気掛かりだった事等を言い、「留守の間の出来事をゆっくり聞きたいけれど、妻が無くなり忌み慎まなければならないので、しばらく別室で休んでから参ります。これからはいつでもお会い出来るでしょうから、煩わしく、うるさいとさえ思いますよ」とお話になる源氏に、少納言は嬉しい思うものの【ものから】、なお危ないと思って聞いていました。源氏は、重きを置いている上の身分で、密かに通うお方が多く、入り組んで関わっているので、北の方に代わってそんなお方が(北の方の様に)君臨するのではないか。と、思うのは少納言の気のまわし過ぎではないのと、語り手が言います。
源氏は、東の対に戻り、中将の君という女房(位の高い召人)に足など揉ませて寝ました。
次の朝、葵との子どもに文を送くられました。左大臣家からの気の毒な返事を見ても、悲しみが尽きない事ばかり。ぼんやりともの思いに耽りがちで、何となく外出するのも憂く思われ、外出したいと思う気にもなりません。
結婚 P-176
1)あらまほし⇒理想的 2)果て⇒しきって 3)いとめでたうのみ⇒ただもうとても美しく 4)似げなからぬ⇒似合わない、幼くなった 5)見なし⇒見てとれば 6)けしきばむ⇒それとなくほのめかす 7)をりをり聞こえこころむ⇒折をみて誘ってみる 8)見もしりたまはぬ⇒何を言いたいのか分からない 9)偏つき⇒漢字のつくりだけ出して、その偏を当てる遊戯 10) 心ばへ⇒気立て 11)らうらうじ⇒優れている 12)愛敬⇒愛らしさ 13)はかなし⇒何という事もない 14)たはぶれごと⇒遊び 15)うつくし⇒可愛いい 16)筋⇒生まれ持っている性分 17)おぼし放つ⇒ほっておく 18)さるかた⇒そういう方面でも 19)人のけぢめ⇒(周りの者は当然夫婦関係があると思っているが)今更ながら見極める 20)とく⇒早く 21)さらに⇒全く、決して
【イメージ】
姫君は、何ごとも理想的に整いきっていて、ただもう美しく見えるので、当然、結婚するのに自分と釣り合わなくないとは言えないと思い、それとなく(結婚を)ほのめかす事など、折を見て誘ってみましたけれど、姫君は、源氏が何を言いたいのかが分からない様子でした。所在なく碁打ちや偏つきの遊びをして日を暮していると、若紫の身に備わった優れた気立てと愛らしさ、何という事もない遊びの中にも、可愛いい、生まれ持っている性分が表れ、子どもと思ってほっておいた年月にも、姫君の才気ある魅力ばかりに心が引かれていて、そういう面でもいとおしいと思っていたと、我慢できなくなって、このままの姫君が何も知らない状態でいたら、心苦しい、全てを求めたいけれど・・・どうしたことでしょう?周りの者は、二人を当然夫婦の関係があると思い、今更ながらそれをはっきりさせる仲でもないのに・・・
【男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり】ある朝、【とく】早く起きた男君と【さらに】起きぬ女君がありました。
【まとめ】
子に対する院の温かい優しさと、院の目を通して、やつれ切った源氏の姿を映し出します。そして、中宮(藤壺)との再会。言葉の裏に隠されたお互いの思いの深さ。源氏の憂い顔が一層曇ります。二人の間に文のやり取りがあった事が書かれていました。やつれ切った喪服姿の源氏の美しさを語り手は伝えます。帰って来た二条の院では、源氏を待っていた人々の明るい華やかさと、源氏との別れの悲しみに、喪服姿でふさぎ込んでいた左大臣家の女房達、色に溢れた家の中の調度と、喪中の左大臣家を対照的に思う源氏の優しさが書かれています。ずっと求めていた人(藤壺)に似て来た、若紫のあまりの美しさに、ドキドキしたのか、早めに東の対に戻る源氏。そして、容姿は大人でも、心は幼い子供の若紫に、父親として接してきた自分が、夫としてどう迫ったら良いのか。北山で覗き見をしてから四年。床を共にしていても本当の夫婦ではなかった。自分に【似げなからぬほど】に成長したと言い聞かせ、若紫を賛美する数々の言葉の中に、人としての戸惑い、悩みが溢れています。しかし、ある朝の事、【男君・女君】【とく・さらに】という言葉で、二人の関係が変わった事を読者に知らせました。読者に想像させる古語の優れた表現に感動、驚愕しました。
読後一言感想
・とうとう二人が実質的な夫婦となった【結婚】。今年の絞め締めくくりに相応しく、来年に気を持たせる内容でした。一同興奮しまくり。【男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ】です。
姫君は、容姿こそ美しく大人びても、まだ心が幼かったのだ。源氏の忍耐強さと姫君の未熟さが際立ちましたね。あー、一月が楽しみ。
・左大臣家を後にして、君は院へ参上。面やつれした君をいとおしむ文章の優しさ。色を抑えた喪服の装束でさえ、君の姿は艶めかしい。二条院の華やかさ、紫の君の成長に戸惑う源氏。式部の才ある表現、そして展開が楽しみです。
・今日は、硬く凍った私の心もさすがに時めきました。【男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり】の一文で、男性と女性の違いと、若紫の若さ、幼さを表し、ほんとにゾクッとする文章でありました。
・源氏と若紫の結婚が、この様に衝撃的に表現されているのを初めて知った。現代語訳では、知る事が出来なかった世界だ。それにしても、逆説的ではあるけれど、源氏の品性、思いやりを感じる場面でもある。次が楽しみで、ワクワクする。
・久々に源氏が帰って来て、院は又華やかになって来たが、姫君との結婚が明らかになった場面は、あからさまな表現ではなく、呼び名が、男君・女君になり、【男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり】は、見事だと思った。
・若紫との結婚が、たった一行ですか!その一行に、背中がゾクゾクしました。そこに至るまでの、源氏の戸惑いや悩みを長々と書いた後の一行は、実に効果的です。初めて北山で少女を覗き見てから四年。二人のそれぞれの気持ちが読者にしっかり伝わって来ました。誰かさんの、「今は、女が起きて来て、男が起きて来ない場合があるんじゃない?」は、みんなに大受けでした。
2011年9月7日 【長恨歌】その2 文責浜岡はるみ
Ⅶ. 都に戻ると、かつての自然は変わらず、でも人々は年老いて、季節の移ろいの中、帝の深い悲しみ
1)太液⇒太液の池の名 2)芙蓉⇒蓮の花 3)未央⇒宮殿の名 4)面⇒顔 5)桃李⇒スモモ 6)梧桐⇒青桐の葉 7)西宮・南内⇒両方とも帝の離宮 8)紅⇒紅葉した葉 9)梨園⇒歌舞団の養成所 10)椒房⇒皇后の居る部屋 11)阿監⇒女官長 12)青蛾⇒若い女の眉 13)孤灯⇒ぽつりと灯っている灯り 14)鐘鼓⇒時刻を知らせる 15) 耿耿星河⇒キラキラと輝く天の川 16)翡翠衾⇒カワセミの羽を縫い付けた掛布団 17)悠悠⇒はるかに限りないさま 18)魂魄⇒死者の魂
【解説】
都に帰って来れば、池も苑も昔のまま
太液の池の蓮の花も、未央宮殿の柳も
蓮の花はあの人の顔、柳はあの人の眉の様
これらを見れば、どうして涙が溢れ出ない訳があろうか
春風にスモモの華が咲く日も
秋雨に青桐の葉が落ちる時も(涙が溢れる)
帝の離宮の西宮も南内も秋草が生い茂り
落葉が吹きだまって階段を紅くしても、それを掃く人もいない
歌舞団養成所の女官たちには、白髪が目立ちはじめ
皇后の部屋の女官長の美しかった眉(顔)は老いてしまった
夜の御殿に飛び交う蛍を見ても、物寂しい思い
● ぽつりと灯っている灯りの灯心をかき立てつくしても、眠りはやって来ない ⇒桐壷P-80
時の流れがとても遅く、時を知らせる鐘や太鼓の音が聞こえてこない、楊貴妃不在の長い夜
明けようとしている曙の空には、天の川がキラキラと輝く
● オシドリの形(恋のシンボル)の瓦に冷たい霜の華が重く咲く ⇒葵P-163
● カワセミの羽を縫い付けた掛布団は寒く、共にする人は居ない ⇒葵P-163
はるかに限りなく遠く離れた生と死で別れてから、年月が経ってしまった
楊貴妃の魂は皇帝の夢にすら現れない
Ⅷ. 皇帝の思慕の情に感動した臨?の道士は、弟子に楊貴妃の魂を探し求めさせ、弟子は仙山にたどり着く。
1)臨?⇒四川省の場所 2)道士⇒道教の修験者 3)鴻都客⇒長安に身を寄せている旅人 4)精誠⇒神通力
5)輾転⇒眠れないで寝返りを打つ 6)慇懃⇒心をこめて 7)排空⇒空を押し開く 8)馭気⇒大気に乗る
9)碧落⇒大空 10)黄泉⇒地の底 11)茫茫⇒はっきりしない 12)忽⇒ふと耳にした 13)仙山⇒仙人の住む山 14)虚無縹渺⇒何もなく広く限りない世界 仙界 15) 楼閣⇒高い建物 16)玲瓏⇒透き通って光輝く 17)綽約⇒
しなやかで美しい 18)仙子⇒仙女 19)参差⇒どうやらその人らしい
【解説】
臨?の修験者が長安に身を寄せていた
彼は神通力を使って、死者の魂を招きよせる事が出来る
君王の楊貴妃を慕って眠れない夜を思い
ついに、弟子の方士に命じて心をこめて楊貴妃の魂を探し求めさせた
方士は、空を押し開き、大気に乗り、稲妻の様に走った
天に昇り、地にもぐり、全てにわたって楊貴妃の魂を求めてまわった
上は大空の果て、下は地の底の果てまで探し回った
どちらも空間が広がっているだけで、何も見えない
海の上に仙人が住む山があると、ふと耳にした
その山は、何も見えない限りなく広い世界にあった
仙山には、高い建物が透き通って光輝き、五色の雲がたなびいていて
その中にはしなやかで美しい仙女が大勢居た
中の一人に太真(楊貴妃が生前用いていた)というあだ名の仙女が
雪の様な膚、花の様な容貌から、どうやら楊貴妃その人らしい
Ⅸ. 弟子は、黄金で飾った宮殿の西の棟に行き、太真に会う事が出来る。
1)金闕西廂⇒黄金造りの宮殿の西の離宮の廂 2)玉?⇒玉で飾った門のかんぬき⇒美しい立派な門 3)転教⇒取り次がせる 4)九華⇒色とりどりの花模様 5)珠箔⇒真珠のすだれ 6)銀屏⇒銀の屏風 7)??⇒幾重にも連なり続く様子 8)雲髻⇒雲の様な髷 9)仙袂⇒仙女の着物のたもと 10)欄干⇒涙がとめどなく流れる様子
【解説】
黄金で飾った宮殿の西の棟に行き、美しい立派な門を叩いた
小玉という童女から、侍女の双成に取り次がせた
漢の天子の使いと聞いて
色とりどりの花模様の帳の裏に寝ていた人が、はっと夢から覚めて驚いた
衣を手に取って、枕をとって起き、取り乱して、意味もなく同じ所を歩き回っている
幾重にも連なり続く、真珠のすだれや銀の屏風が開いて
起き抜けの雲の様な髪が歪んで、今眠りから覚めた風情で
仙女の冠も被らず、取り乱して高い所から下りて来た
風は、仙女の衣の袂を飄々とひる返し
【霓裳羽衣】の舞姿を思わせた
玉の様な美しい顔は寂しそうで、涙をとめどなく流していた
春の雨に梨の花がしっとり濡れている様に
・・・・つづく
一言感想文
●漢詩二回目。八十歳にて読む。朗々とリズム感があって、情景が広がる。
【雪膚花貌参差是】文字から意味が浮かんで来るが、難解です。
●初めての漢詩。楊貴妃の美しさが、手に取る様。これから先が楽しみです。
●読むのに精一杯。漢詩は対句であるという事を知りました。
色々な語句がここから来ていたのかと、改めて知った。
【梨園弟子白髪新】や、【雪膚花貌参差是】等時々聞いたことのある言葉が出てきたりすると、
あーと思った。苦労してるけど、楽しい。
●【排空馭気奔如電】スピード感があり、方士が走り回り探している様子が目に浮かぶ。それとは逆に、
【梨花一枝春帯雨】の一行は、しっとりとした楊貴妃の美しい姿を浮かばせる。
●柳眉とか、青蛾とか・・・そういえば、かつて若かりし頃のメイクにそんな型の眉が流行ったなあ。
あの時、毛抜きで細く眉毛をバッツンバッツン抜いて以来、眉不在で不自由するハメになったのを思い出したのです。美人は、魂になっても美しい容姿なのね。
●国を傾ける程の美女は、殺されても絢爛豪華な世界に有った。俗世で歳を経る人々に比し、天にある人の時は止まったまま。若く美しい楊貴妃は、死して天界を傾ける程の妖艶さでもって、探し尋ね当てた道士の前に現れた。漢文の面白さは、極限まで突き詰めた表現の極みにあるようだ。源氏物語に与えた影響は、現代にまで及んでいる。ため息です。
●・【春風桃李花開日】、春風にスモモの花が咲く日
・【秋雨御梧桐葉落時】秋雨に青桐の葉が落ちる時
・【落葉満階紅不掃】落葉が吹きだまって階段を紅くしても、それを掃く人もいない
・【夕殿蛍飛思悄然】夜の御殿に飛び交う蛍を見ても、物寂しい思い
・【耿耿星河欲曙天】明けようとしている曙の空には、天の川がキラキラと輝く
・【鴛鴦瓦冷霜華重】オシドリの形の瓦に冷たい霜の華が重く咲く
嗚呼、何と美しい自然の描写、そして悲しみ深さでしょう。
2011年8月3日【長恨歌】 受講 文責浜岡はるみ
この百二十句の詩は、唐の第六代皇帝玄宗と楊貴妃の悲劇の約50年後に白楽天が書いたものです。
その物語の内容と平易さで、国内外で大流行しました。日本では、【源氏物語】に深い文学的影響を及ぼしました。
Ⅰ. 物語の始まり、二人の出会い
1)漢皇⇒まだ歴史的に生々しい事件なので漢の時代とした 2)色⇒好色、女好き 3)思傾国⇒国が傾く様な美人を求めていた 4)御宇⇒治世 5)初長成⇒やっと大人になった処女 6)深閨⇒深層 7)麗質⇒美しさ 8)一朝⇒ある日 9)在君主側⇒天皇に謁見した 10)百媚⇒人を驚かす程の魅力 11)六宮⇒内裏、奥御殿 12)粉黛⇒美しく化粧した人 13)無顔色⇒色褪せ負けてしまう 14)春寒⇒春の初め 15)賜浴⇒浴室を作らせた 16)水滑洗⇒水を灌ぐと滑らかに水をはじく 17)凝脂⇒真っ白く固まった油、美人の美しい白い肌 18)侍児⇒腰元 19)嬌⇒色っぽく 20)恩沢⇒結婚の前の儀式
【解説】
漢の天子は、好色で、国が傾く様な美人を求めていた
その治世の間長年探していたが、得られなかった
楊家に娘がいて、やっと大人になったばかりであった
両親に大切にされ、深層に育ったので、人は知らなかった
生まれ持った美しさは、そのまま見捨てられる事なくて
ある日選ばれて、天子に謁見した
瞳を回し動かしてにっこりすると、人を驚かす程の魅力を生じた
内裏の美しく化粧した人達は、色褪せて負けてしまった
春の初め、帝は華清の地に浴室を作らせた
温泉の水は、滑らかに注ぎかかり、真っ白い肌を洗った
腰元が助け起こすと、色っぽくなよなよと、力なかった
こうして結婚前の儀式を終え、これが初めて天子の愛情を受けた時であった
Ⅱ. 帝の寵愛を一身に受ける楊貴妃
1)雲鬢⇒雲の様に盛り上がった髪 2)花顔⇒花の様な顔 3)金歩揺⇒歩くと揺らめく金のかんざし 4)芙蓉⇒蓮の花 5)度春宵⇒春の宵を過ごす 6)承歓⇒楽しみを承り 7)宴侍⇒何を言いたいか読んで 8)無閑暇⇒付きっきりで離れる暇がない 9)夜専夜⇒帝の夜は楊貴妃に独占された 10)佳麗⇒美しい人 11)金屋⇒妃の住む所 12)粧成⇒化粧をこらす 13)嬌侍夜⇒あでやかに夜の奉仕につとめる 14)玉楼⇒美しい二階建ての建物 15)宴罷⇒宴が終わって
【解説】
雲の様に盛り上がった髪、花の様な顔の楊貴妃が歩くと、金のかんざしが揺らめき輝く
蓮の花(愛情の象徴)の几帳は暖かく、春の宵は過ぎて行った
春の宵は短く、天子は起きる事が嫌になり、日が高く昇ってから起きた
楊貴妃と結婚してから、天子は朝の政務をとらなくなった
楊貴妃は、美しいばかりでなく、天子の楽しみが何かを読んで、つきっきりで側を離れる暇がない
春は春の遊び、夜は夜で、天子の時間は楊貴妃に独占された
後宮には三千人もの沢山の美しい女達が居た
今や、その三千の女達への帝の寵愛は、楊貴妃一人の身にあった
妃の住む金屋で、化粧を凝らし、艶やかに夜の奉仕に務めるのだった
美しい二階建て建物での宴が終わり、楊貴妃は、酔って春の気分に溶け込む
Ⅲ. 楊貴妃の一族にまで栄華が及び、管弦と舞の夢の様な日々を、安禄山の変が破る
1)姉妹弟兄⇒楊家の親戚 2)列土⇒諸侯になって領土に名を連ねる 3)可憐⇒何とまあ 4)光彩⇒光が射している 5)門戸⇒邸宅の門 6)驪宮⇒華清宮 7)仙楽⇒仙人の音楽 8)緩歌⇒緩やかな歌 9)慢舞⇒ゆったりとした舞 10)糸⇒弦楽器 11)竹⇒管楽器 12)驚破⇒驚かし夢は破れ 13)?鼓⇒攻めつつみと太鼓 14)霓裳羽衣曲⇒玄宗が作った曲
【解説】
楊貴妃の親戚は、皆諸侯となり、領土に名を連ねた
何とまあ、楊一族の邸宅には光が射している
とうとう世の中の親たちの心は
男ではなく、女を生めと命令するようになった
華清宮の屋根は、雲に突き入らんばかりの高い所にあり
そこから、仙人の音楽の様な楽の音が、風に乗り吹きおろして、色々な所で聞こえた
緩やかな歌、ゆったりとした舞、管弦のすすり泣くような凝った曲想が
一日中流れ、天子は鑑賞するのに飽きる事がなかった
安禄山の変が起こり、攻め鼓や太鼓の音が地面を動かして聞こえて来て
天子が作った、霓裳羽衣の曲の調べを驚かし、その夢を破ってしまった
Ⅳ.乱を逃れ都から落ち延びる途中、軍が帝に楊貴妃を殺す事を迫り、殺される楊貴妃
1)九重城闕⇒天子の城の九つの門 2)千乗⇒千の乗り物 3)万騎⇒万の騎馬武者 4)西南⇒蜀の成都 山の中 今の四川省 5)翠華⇒カワセミの羽根飾りのついた天子の旗印 6)揺揺⇒右往左往 7)六軍⇒近衛兵 8)不発⇒動かなくなった 9)宛転蛾眉⇒青い蛾の羽根の様な長く伸びた眉 10)馬前死⇒自ら首をくくった楊貴妃の遺体がさらされた 11)花鈿⇒螺鈿の花の模様のかんざし 12)委地⇒地に捨てられ 13)無人収⇒拾う人が無い 14)翠翹⇒カワセミの羽根 15)金雀⇒金のクジャク 16)掻頭⇒かんざし 17)凝脂⇒真っ白く固まった油、美人の美しい白い肌 18)侍児⇒腰元 19)嬌⇒色っぽく 20)恩沢⇒結婚の前の儀式
【解説】
天子の九つの門がある城の辺りに煙塵が生じ、(反乱軍が宮中まで入って来た)
千の乗り物と万の騎馬武者は、西南(蜀の成都:山の中)へ落ち延びて行った(実際は、もっと少ない)
カワセミの羽根飾りの天子の旗印は、右往左往して、行ったと思うと又止まる(軍の内部がもめている)
都を出てから百余里(50km位)の所で、軍は止まった(兵士の中の動揺)
六軍(近衛兵)が動かなくなって、帝はどうする力も無かった
青い蛾の羽根の様な長く伸びた眉(楊貴妃)は、自ら首をくくり、皆の前に遺体がさらされた
(死んだ楊貴妃の)螺鈿の美しい花模様のかんざしは、地面に捨てられ、拾う人が無い
カワセミの羽根や、金のクジャクの形のものや、玉の美しい髪飾りも
天子は、見るに絶えず、顔を手で覆って、助けようにも助けられなかった
振り返って見ればその目から血と涙があいまじって流れ落ちる
Ⅴ. 蜀の地で、玄宗は悲しみに沈む
1)黄埃⇒黄色い土埃 2)散漫⇒舞い上がって 3)風蕭索⇒風が物悲しく吹いている 4)雲桟⇒絶壁に架けた道 5)?紆⇒くねくね曲がりくねって 6)剣閣⇒山の名前 7)峨眉山⇒成都市にある名山 8)旌旗⇒天子の旗 9)蜀江⇒蜀を流れる川 10)蜀山⇒蜀の山 11)聖主⇒天子 12)朝朝暮暮⇒朝から晩まで 13)行宮⇒旅先での仮の宮殿 14)断腸⇒(子を失い悲しみのあまり死んだ母猿の腸が細かく千切れていたという故事から)腸が千切れる程悲しい事 15)金雀⇒金のクジャク 16)掻頭⇒かんざし 17)凝脂⇒真っ白く固まった油、美人の美しい白い肌 18)侍児⇒腰元 19)嬌⇒色っぽく 20)恩沢⇒結婚の前の儀式
【解説】
黄色い土埃が舞い上がって、風が物悲しく吹いている
絶壁に架けた道は、くねくね曲がって、剣閣山を登って行く
成都の名山蛾眉山は、人が殆ど通らない
天子の旗も色褪せ、太陽の光さえ薄く見えた
蜀を流れる川の水は青緑色で、山は青い
天子は、朝から晩まで楊貴妃を思い、憂いに沈む
仮の宮殿から月を見れば、その色に悲しみを感じ
夜の雨に桟道を行く馬の鈴の音を聞けば、腸が千切れる程悲しい
Ⅵ. 戦乱が落ち着き、都に戻る途中、玄宗は楊貴妃の死んだ馬嵬で涙する
1)天旋地転⇒戦乱が収まり世の中の情勢が変わったこと 2)廻⇒戻る 3)竜馭⇒天子の馬車 4)至此⇒楊貴妃が死んだ馬嵬の地 5)坡下⇒堤の下 6)君臣⇒君子と部下 7)東望⇒東の方を目指し 8)信馬帰⇒馬の歩くのに任せて帰る
【解説】
戦乱が収まり、世の中の情勢が変わり、天子の馬車が都へ戻ることになった
楊貴妃が死んだ馬嵬の地に到着した時、去りがたく、先に進めなくなった
馬嵬の堤の下、泥の中
玉の様な美しい顔はもう見られず、空しく死んだ所
君子も部下も皆回想し、袖を濡らし
呆然と馬の歩くのに任せて、帰って行った
・・・・つづく
一言感想文
●源氏物語に多大な影響を与えた長恨歌を、声を出して読んだ。漢詩のサイン・意味・七七調子も美しく、楽しい受講だった。国を傾ける程の絶世の美女に生まれなかった幸福と不幸をかみしめた我々でした。
でもねぇ、一度でいいからここまで男を魅了したら、女は死ぬしかないでしょう。何ごとも程々がいいんです…我ら幸福。
●長恨歌まだよく読めないけど、やって良かった。学生時代を思い出しました。
今また新たに勉強します。違ったものに出会えて嬉しいです。
●耳に心地よく響く。【宛転蛾眉馬前死】の一行で、天子が抑える事の出来なくなった、軍の混乱と軍の兵士達の前で処刑されるに到った様子が目に見える様である。
●長恨歌ってこんな艶めかしく始まった詩だったのね。
女学生の頃に理解していたら、私の「女の道」も少し違ったかも。そんな事ないか・・・・!?
●【峨眉山下少人行】【旗旗無光日色薄】【蜀江水碧蜀山青】【聖主朝朝暮暮情】
自然と人間の情が絡み合って文字から浮かび上って来る。
●古語と繋がった、正に五感で読む、素晴らしい世界でした。目の前に、黄色い砂煙、真紅の血、川の青緑、山の青。【仙楽風飄処処聞】風に乗って聞こえる楽の音。そして【朝朝暮暮情】の悲しみ。
原文からひろがる源氏物語 2011年7月6日受講 残された手習い p162~
?源氏が去ったあとの「空蝉のむなしきここちぞしたもふ」部屋をのぞいた左大臣は、源氏が残こした手習いに胸を突かれた。そこに葵と仲睦まじかった日々への追慕が、余すことなく記されていた。不足を感じていても女として充分に愛し、また男して愛されていたと、美しく筆にし、反芻していたからだ。はっきりと思い出せ ないようなことごとも、取り戻すことのできない何もかも、「悲しみ」に浸って幽かに触れられているのだった。
葵を取り巻く遺こされた者たちの悲しみの仕事(悲哀の仕事)は「かくのごとくであった」と、式部は丁寧に描いてきた。大切な人を失ったとき、悲しみをきちんと悲しまないと精神的な支障をきたすらしいことは、現代ではよく知られている。悲しいことをしっかりと悲しみ、さめざめと悲しむことで超えていくしかない「その後」。悲しむまいと思っても止めることができないこの感情は、自分を超えて起きるようだ。そこから抜け出す鍵は、ただ「悲しむ」ことの中にあると言いたげである。
悲しみの感情や涙が心を耕し、他者への理解を深め、すがすがしく明日を生きるエネルギーとなると、柳田邦夫が何かに書いていた。フロイトに先んじて、式部は「生きる糧」としての悲しみを描いてきたように思う。こうした感覚が日本人の美意識を育てきたのだろう。それは悲しみを抱いてこそ知る自然の美しさであったり、おごそかさ・しづかさへとつながっていくようだ。存分に喪の仕事を勤め、そしていつしか飼い馴らされていく悲しみは、人を自由にしていく。
蛇足ながら、3.11以降、三陸の地は深い悲しみを抱えた地となった。だがそこはまた悲しみを抱えながらも、再生の芽を育む地となっている。あの廃墟から被災者が立ち上がっていく姿は、先の見えない時代を生きる私達を力づけている。
読後一言感想
◎ 身近な人を亡くした悲しみはこうやって引きずっていくのね…と痛感する「葵」の巻。生きていればこうもしたかった、ああも言いたかったに違いない。源氏の後悔も伝わってくる。それにしても書き残した手習いの歌の「心ならひに」という部分は「あら、まぁ」の展開でした。式部さん、葵が死んでからコレはないでしょう。
◎ 「…あくがれがたき心ならひに」妻を亡くした喪失感と後悔。いつかはと、それが突然の死に直面したのです。「君なくて塵つもりぬるとこなつの 露うち払ひいく夜寝るらむ」源氏の葵を亡くした悲しみは本当に深い。
「葵」ではP107の急死からp166まで、葵の死の悲しみと別れが長々と書かれていました。それほど死と別れは重いのです。「一日の花なるべし、枯れてまじれり」、映像的な部分でした。
◎ 空蝉のような夫婦の部屋に、喪に伏した源氏が書き汚した歌が残されていた。「なき魂ぞいとど悲しき寝し床の あくがれがたき心ならひに」そんなふうに書いて葵を偲んだ源氏。いつも二人は離れがたかったものだが…という呻きを吐露した。娘と婿の夫婦関係に、左大臣は慰められたのではないだろうか。源氏は葵を女として愛していたの? 他者には知りえない夫婦間の情愛を今頃になって知らされて、改めて源氏の喪失感の深さを知った。大宮は朝夕の光を失ったと、娘婿までも失う寂しさをそんなふうに嘆いた。それにしても式部ちゃん、ここに及んで「あの二人、実は仲がよかったんですー」って言われてもねぇ、後出しジャンケンじゃないの?
◎ 「あくがれがたき心ならひ」から夫婦には夫婦しか分からない深い繋がりがあるのだと思いました。他人にはわからないものですね。長恨歌を知らないと素通りするところでした。
◎ 式部は多くの女性を描いているが、妻を描いているのはこの葵の巻だけではないだろうか? 源氏が葵をどのように思っているか、妻に対して求めることが多過ぎる! 葵を亡くして悲しむ源氏の歌は心情にあふれているが、式部の目は少し皮肉に光っているようにも見える。
◎ 初参加なので、誰の死を悲しんでいるのか解らなくて困りました。始めから読まなくては。皆さん物語を多方面から見ていらっしゃるように思います。なるべくなら物事を簡単に考えたい私…、これからが楽しみです。
原文からひろがる源氏物語 2011年6月14日受講 葵巻・別れ・大宮と左大臣p153~
遺された者たちの悲しみは、順々に質を変えていき、逝ってしまった者との距離は「御しつらひよりはじめ、ありしに変わることもなけれど、空蝉のむなしきここちぞしたもう」と実感される。悲しみと死者は表裏一対であった。だから悲しみを手放したくないと思っていた……。家具調度はそのままに主をなくした夫婦の部屋を覗き、在りし日の残響に翻弄されながらも喪失の悲しみから解放されていく左大臣。遺棄された者は死を受け容れ認めることで、生きていく.
一陣の風に木の葉がそよぎ出し、時節をわきまえているように降り出した時雨の中を、源氏が去っていく。存分に流した涙の分だけ、歳月が幽かに遠くなっていくようだ。
葵の死がもたらしたそれぞれの喪失感が、過不足なく描かれてきた。源氏が鼻をかむという描写があり、我らはずっこけるほど驚いた。源氏が涙と鼻水にまみれた顔をどのように拭たらハッとするほど美しいのか…どのようであれ、雅で美しい源氏。粗ぶれた武家社会とは異なる貴族社会の美意識に導かれて、しっかりと悲しむ男たちの涙もまた珠のように美しいと、我々は「葵」の死で知ることとなった。
読後瞬間一言感想
◎ 左大臣家の人々のと源氏との別れは去る者と残される者の双方が、互いの心情を思いやる言葉にあふれている。 平安の文化は男性が泣き、涙にくれるのを「美しい」と捉えるのだ。大臣の感情も人間的だし……。韓流ドラマですぐに 泣く男たちとは「別モノ!」だね。
◎ いよいよ左大臣家を出て行く源氏。舅を思いやって「心配している院にちょと会ってきます」なんて言い方をする。 式部は葵の喪の刻・喪失感を、深く丁寧に描いてきた。遺棄された人々は、死の衝撃と悲しみの中で、時間の経過とと もに喪失感の質を変化させ、順々と受け入れていった。生きるということは死を受け入れること、という現実が読者の胸 を突く。遺こされてなお生きていく者は、悲しみを受け入れるしかない。源氏が去り、主を失った夫婦の部屋は「空蝉の むなしきここちぞしたもう…」。左大臣の悲しみの余韻は、読者を大臣の喪失感の残響へと投げ出した。
◎ 今回も源氏の泣く姿の美しさが描かれている。どんな場面でも美しさが際立つ源氏がこれでもかと出てくる。美しさと はそういうことなのだろう。葵の死の悲しみから一転して、源氏と左大臣家の人々との別れの悲しみ場面に変わったが、感情は細やかに描かれる。悲しみばかりでなく、女房たちの不安も描かれていて、きめ細かだ。今日の気になった一言は「あからさま」でした。
◎ 源氏が左大臣家を去る時の様子が印象的だった。左大臣は二人の仲がうまく行ってないなかったと薄々感じてはい たが、そのうち仲良くなるだろうと期待していたのに、それもかなわなくなった今、源氏は邸を後にしてしまう。主がいなくなった二人の部屋は蝉の抜け殻のようだ。
◎ 最後の「空蝉のむなしきここちぞしたまふ」で左大臣の悲しみは最高に。その静かさの中に時雨の音が。死の悲しみ は美しく、マイナスではない。今、おしこりて遠くから源氏を送っている女房たちが、時々しかない源氏の来訪を、胸とき めかせて待っていたあの歳月は、もう跡形もなく、なくなってしまうのです。
◎ 源氏は後ろ髪を引かれる思いながらも「かくてのみ」と、桐壺院へ参上の意向を告げて左大臣家との別れを決する。見送りにさぶらう女房たちの涙を一層誘うように「時雨うちそそぎて木の葉をさそう風…」美しい古語の流れで情景が浮か ぶ。悲しみの中にも凛とした源氏の姿の美しさ。最愛の娘を失い、婿の源氏もまた去っていく。大臣と宮の喪失感がひしひしと伝わり、人の気配の絶えた夫婦の部屋。大臣の「空蝉のむなしさ」寂寥が漂う。涙・なみだの物語に、平安の姫君たちも心痛めて、もらい泣きしであったことかと。
「原文からひろがる源氏物語」
2011年5月18日受講 葵の巻「別れ・仕える人々」p148~
忌明けである。鳥部野で有明の月を仰ぎ見た日から49日が過ぎた。あの日、妻を捜して空をながめては、どの雲もどの雲も愛おしかった。源氏は喪失の感情と向き合い、失ったものの大きさに呆然としつつ、悲しみを抱きしめながら追慕の日々を過ごした。
左大臣邸で源氏に仕えてくれた人々との別れ。これでもう「名残なきさまにあくがれ果てさせたまはむほど…」跡形も無く離れ、源氏は遠い人になっていく…… 女房たちは悲しみ、源氏もまた「そんなことはないさ」と慰めてみるものの、この屋敷に脚しげく通う日が来るとも思えないのだった。
葵は生前、親を亡くした女童に目をかけていた。可愛がってくれた主人まで亡くしてしまったこの女児へ、源氏は声をかける。「これからは私を頼りにしなさい」と。
左大臣はさりげなく細やかな心遣いで、それぞれの身分の応じた形見分けをした。
逝くものが残した悲しみを抱きしめることはできる。しかし遺された者たちが「その後」を生きていくには、死を受け容れなければならない。生きるとは「死を受け容れる」こと、そんな切ない真理に気づかされた受講だった。
読後一言感想
◎ 別れの時の悲しみやこれからのこと等、それぞれの立場から思い思いに考えている様子がよく描
かれていると思いました。
◎ 晩夏の有明の月を仰ぎ視た日から、忌明け。左大臣家を去る日がきた。
現在使われている「名残惜しい」という言葉は、古語「波残りおし」、波が引いた跡に去った波
跡が残る、からきた言葉であるという説明があった。美しい古語が、このような形で現代に残って
いることに、感動。
源氏づきの女房たちにも去るべき刻が訪れている。左大臣家に仕える女房たちは、次の就職先に
困らない。だが左大臣は希う。忘れ形見の若宮を育てながら、いつまでも留まって欲しいと。
左大臣は葵の形見分けをした。さりげない心配りで顕かにした本音は「このまま仕えてくれ…」。
この心遣いの意味を講師が指摘したが、私は形見分けで見せた大臣の真意を汲み取れなかった。
娘を亡くし、気に入りの婿を失う寂しさを、細やかに顕す左大臣なのだ。両親を亡くした児を可愛
がっていた葵の人となり、隠されていたこのエピソードを知らされた読者は突然に断たれた一組の
夫婦の無念さ…震えるような余韻に包まれた。
◎ 秋も深まり、北の方の忌が明け、左大臣邸を去らねばならない源氏は、悲しみを共に過ごした女
房たちと灯火のもとで語りあう。(この描写に読み手はイメージを膨らませる)女房たちも主を失
ったつらい日々であった。源氏の存在は大きな光であり、支えであった。別れを惜しむ女房たちに
「見なれ見なれて…恋しからじや」「おさなき人を見捨てずものしたまえ」と言葉を尽くして語る。「いてや待遠にそなりたはむ」とさらりと水をさす(辛口コメント)。秋の情景と別れの」心が織り
合い、物語は展開する。
◎ 女房たちとの別れ。幼い頃から内裏で女性たちに囲まれて育った源氏は、女房たちとの別れの言葉
一つ一つに深くこめた思いが伝わっていました。上手です。
灯りを眺める瞳が濡れる、その美しさが薄暗い光の中に見えました。大殿の源氏付きの女房に対す
る微妙な心遣いが切なく感じられました。
【なごり・名残り】とは、【波残り】という字を書いたそうです。砂浜に寄せた波が引いていく時、
水は砂に少しづつ浸み込み、そしてなくなって、波が寄せなかった元の砂の色に戻る。…細やかな心
のひだを感じさせる字。古語の持つ繊細な表現に感動しました。
◎ 身近な人の死は、残された人たちに「これからどう生きるか」を問いかける。北の方との死別も
然り。左大臣邸を離れていく源氏と別れねばならない女房たちの悲しみ伝わってくる。それにし
ても「名残」という言葉が「波が残す水のあと」という先生の説明に、目から鱗でした。
「原文からひろがる源氏物語」2011年4月6日受講 葵の巻 朝顔の宮と p142~
左大臣邸で喪に伏す源氏は、時雨にもたらされた心象を誰かと分かち合いたいと思う。存分に心を通わせ合えなかった夫婦生活が途切れて……絆の芽生を実感したあの日々が、うたかたのようである。
現在というこの思いを誰かと分かち合いたい。生きなずむ他ないあわれの感情に包まれるとき、寄り添って欲しい相手として思い浮かぶのは、朝顔の姫だった。
桐壺院の弟・式部卿の宮の姫が、登場した。返歌にみるように、源氏に等身大の感慨を摘み取らせる感性豊かな姫である。
朝顔の姫は「箒木」巻に、方違えで泊まった屋敷で聴いた女たちの噂ばなし・朝顔の花に添えた歌の送り主として、登場している。「葵」巻で父帝から御息所をおろそかにしてはいけないと諌められる源氏から恋を仕掛けられていたが、御息所の二の舞にはなるまいと深く心に刻んでいる。御禊の行列を父宮・式部卿と桟敷から見物しながらも、やはり源氏とは距離を保っていかなければと決意を新たにした姫である。
多々の具体的な身分と地位を背負った女性たちと関われば、女たちの事情に関与していかざるを得ない源氏の恋。恋は癒しがたい渇きへの彷徨であり、関わった女を通して世相を映していく。源氏の心の渇望の核心に迫る手段として、式部は様々な女性を登場させるが、この姫は恋にのめりこみそうになる心を抑えて、やんわりかわしつづけている。折々に文を交わし合う関係だけが続いているのは、恋は相手を傷つけ、また自分も深手を負うものだということを、御息所の苦しい恋から学んでいるからだった。これから朝顔の姫はどのように源氏の深層の闇をあぶり出していくだろうか。
読後一言感想
◎ 男心を勝手と言うけれど、こんなものでしょう。読者としては源氏に腹を立てるけれど、六条の御
息所の素敵さは変わりは無いはず。紫式部の書き分けは素晴しい。
◎ 言葉や態度はぶっきらぼうでも、何となく心が通じる人がいる。源氏と朝顔の君との関係もこう
かもしれない。男と女であっても感性が似ており、ほどよい距離、ほどよい温度。これをキープでき
れば長い付き合いが続くことだろう。……源氏物語の場合はどうも自分に置き換えてしまいがち
だなぁ。
◎ 七七忌の頃になる左大臣邸で、心の寂しさが募る日々。源氏の君は朝顔の宮に思いを巡らす。
御禊の行列で式部卿と共に胸ときめかせて源氏に見入っていた姫君「いとど近くて見えむまでほ
おぼしよらず」 姫君の感情の押え方に同感した。そして今回、源氏からの文に更に姫の魅力
を覚えた。
「秋霧に立ちおくれぬ聞きしより しぐるる空もいかがとぞ思ふ」
一歩引きながらも相手を思い包み込める心情に、私も来世に生まれることができたら、このような
女の子でありたいと思う。
◎ 見えない所に御息所が隠れていました。「なほゆゑづきよし過ぎて人目に見ゆばかりなる」人で
あったと。理想的な朝顔に比べて「難も出て来けり」…御息所は難ですか? 対の姫君を「さは生
ぼし立てじ」と御息所を更に否定する。源氏には絶対超えられない・かなわない女であったと、改
めて書かれていました。
◎ 喪失感を分かち合う相手として、朝顔の姫へ文を送ると、「秋霧に立ち遅れてしまったあなたの
嘆きは、しぐるる空もいかがかと思っておりました」 と返事が届いた。この絶妙な添い方で源氏の
心を掴んで離さない朝顔の姫。御息所の文句のつけようのない全に憧れていたはずなのに、源
氏は引け目を感じるようになっていた。優れてかなわない相手なのに、そこがまさに欠点であるか
のような、若紫をそのようには育てないぞ、と思う源氏。憧れの女性がいつしか嵩高い女になって
しまったのは、男と女の心の距離。「足りないところがないのが、足りないところ」だなんて…お調
子者の源氏です。しょせん男なんてそんなもんでしょ!
◎ うつうつとした気持ちを誰かに吐き出したいとの思いが朝顔の登場となりました。付かず離れず
の関係だった宮だが、なぜか思いがかなうような気がしていた。普段は冷たいのだが、つらいとき
に、その気持ちを受け止めてくれ、心が和んだ。「いざ」というときに態度で示してくれる。普段は
どうでもこの「いざ」が大事と思った。御息所のような人は源氏にとって少々重かったのでしょう。二
人の対比が面白い。
沈光子コーナー
当事者は視ることがない(被災地停電で)津波の恐怖映像を、繰り返しテレビ報道で視ました。
この二ヶ月余り、被災と原発のニュースばかり。
大切な家族を喪失したまま、「もしかしたら」と淡い期待を握りしめる人々。
せめてこの手で葬りたいと、捜索の手をいまだ休めない人々。
無策の政治と官僚と天下り原発と、余りに多くのものを一度に見てしまった。
3.11を言葉にして考えることができません。
言葉を超えたところに悲しみや苦しみ・衝撃があるのでした。
みなさんの読後一言感想がなかったら、今月の報告は不可能でした。
何も思い出すことができませんでした。
生きていることに感謝です。
昨日と同じ今日に感謝です。
明日の朝が穏やかに訪れることを祈ります。
はるみさん、脚をいたわって下さい。
みなさまとお会いするのを楽しみに!!
下記 今月の駄句
海凪いで 瓦礫の山に 春の月
陸奥の 山笑ふか 月欠ける
三陸の 海の響(とよみ)に 五月来る
浜岡はるみコーナー
緑が一日一日深まり、
やまぼうし、みずきの花の白さが心を慰めます。
家を失くし、家があっても帰れない人たちに、今年の春はきついでしょう。
百姓にとって、あれもこれもと、しなければならない、でも、春は心躍る時期です。
自分の故郷を遠く離れて、何も出来ない。天気の良い日は、特に心が痛む。
その人たちを思うと、泣けます。
でも、一方で、安くなっているイチゴで、何回もジャムを作っている私です。
足は、殆ど痛みはなくなりましたが、まだ重く、完治には当分掛かりそうです。
皆さんお元気でお会いしましょう。
高見沢公子コーナー
明日の参加があやしくなってきましたので、思い切ってメールしました。
今回の災害によって、様々な問題提起がされたと思います。
この災害は、明治維新、第二次世界大戦終結に次ぎ、その出来事を境に、
3.11以前、以後と呼ばれるような区切りの一節となるべく起こった歴史的大災害でしょうね。
この災害によって、科学主義、技術主義、経済主義に立っていた近代的な価値観の限界をまざまざと見せつけられた。
沈さんがおっしゃるように、アメリカをお手本にした結果が現代の日本であり、現代日本の病が露呈しましたね。
今回は、西洋文明によって作り出された近代という時代と社会の価値観を変える契機であるとも思います。
江戸時代の暮らしに学ぶべきものは多いですよね。何も、横文字で「エコロジー」「グリーンツーリズム」などと提唱しなくとも、昔の日本の良さを取り戻すだけで良いのですよね。
被災者は本当に気の毒だけれど、「がんばれ日本」「日本の力を信じている」「みんな仲良く」
というような言葉も気持ち悪い。今、どんな言葉が求められているのか…。文学者はどうしているのでしょう。
大江健三郎のように「原発は広島、長崎の犠牲者への裏切り」とはっきり言っている人は何人いるのでしょう。
先の見えない時代を生き抜く力や勇気、真の幸福とは何か、違う者同士が思いやり共に暮らすということ、人と人とのかけがえのない絆、無償の善意は存在するか。
私達も考えなくてはいけないことが沢山ある。
この災害をきっかけに、曖昧さや答えの先送りは許されないくなったと思います。
沈さんのおっしゃるように、私達は嫌というほど長生きして、この国の行き先を見届けたいと思います。
「哀」ばかりでは無く、時には「怒」の感情も使いつつ。
「原文からひろがる源氏物語」2011年3月3日受講 葵の巻 貴公子ふたり p133~
葵の上が逝き、49日を迎えるころ。左大臣邸にこもって喪に服す源氏のつれづれを慰めんと、頭中将(三位に昇格)が入り浸っている。世間話の折には源内侍を話の種にしたり、末摘花の姫を話題にしては笑い合う。好きごとばかりでなく、あはれなる世を言い言いして、涙する日々であった。
秋と冬の隙間の移ろいに、時雨がサットおちてあたりを濡らしていく。衣代えもしていない源氏は少し濃い目の夏の直衣をゆったりと着付けて高欄に身体を預けて頬杖をついている。仮に自分が女で、このような男を残して逝かねばならないなら、魂が離れがたいに違いないと、中将は惚れ惚れと源氏を眺める。それにしてもどの雲を妹と見分けたらいいのだろうか、と思う。
雨となりしぐるる空の浮雲を いづれのかたとわきてながむ
「行くえなしや」と妹の魂の行方が案じられ、ひとり言のようにつぶやく頭中将。
見る人の雨となりにし雲居さへ いとど時雨にかきくらすころ
妻の魂が雲になり雨となった。その空も時雨のいまは悲しみを誘うばかり……源氏は妻への思慕をそう詠んだ。中将が帰えっていき、庭の植え込みの中から龍胆・撫子などを折らせて大宮へ使わし、忘れ形身・若宮の寂しさを詠んだ歌。
草枯れのまがきに残るなでしこを 別れし秋のかたみとぞ見る
今も見てなかなか袖を朽すかな 垣ほ荒れにしやまとなでしこ
悲嘆の海に溺れる大宮は、若宮を見るにつけても涙をあふれさせて、袖も朽ちてしまいそうだと詠む。
時雨は訪れる季節の匂いに満ちていただろうか。下枯れた庭木に降り注ぐ雨脚越しに、遠く遠い人を探しあぐねる源氏の魂は、身体を遊離していく。葵を求める心と身体の乖離。
流れる雨脚を縫って、雲に溶け込んでいる鈍色の景色へと魂が彷徨い出ていく……。時雨の向こうへ遊離していく魂を見つめる源氏。高欄にもたれた忘我の姿態は、だから息を呑むほどに美しかったのではなかろうか。
喪失の悲しみは式部の筆によって余すことなく描かれていた。式部の筆が美しければ美しいほど、悲哀が際立つというように。
読後一言感想
◎ 源氏の妻を亡くして悲しむ姿が美しく書かれていますね。時雨と秋の草花を物語の中に取り
入れることが出来るのは、女性である紫式部だからだと思いました。
◎ 忘れた頃に登場する中将、心が和みます。お互いに貴公子であるが上に影響しあい、幼な馴
染みが訪ねて来てくれているようで、ホットします。中将は打ち沈んでいる源氏を思いやり、一緒
の時を過ごしてくれ、沈痛な源氏を見て、妹はそれなりに大事のされていたんだと、改めて思う。
源氏との関係もだんだん薄れてくるのだろうか。
◎ 紫式部の文章の中の天候の表し方の美しさに感服します。49日を迎える頃の喪中の在り方も
「いとあわれなる」さまを見る事が出来ました。
◎ 「時雨うちし」「時雨さとしたる」「しぐる空の」「時雨にかきくらす」と、秋の悲しみは「時雨」抜きに
は表せない様でした。
「なでしこ」が「なで」+「し」+「こ」であったとは! 改めて「箒木」「紅葉賀」を読み返してみます。
妻を亡くした源氏は生活基盤がなくなった。もう左大臣家には居られない。亡くなったのは妻だ
けでなく、暮らしも、とは。高欄によりかかる源氏の直衣の色を確認しました。美しかったです。
◎ 貴公子が2人が葵の49日を目前に逢い、寄り添っている。独り娘を失って「光失せぬここちす
る」左大臣邸。妻を失った源氏は同時に左大臣家という後ろ盾も失うことになった。
妻の実家で喪に服している源氏の美しさは中将をして「女にては見捨てなくならむ魂必ず止まり
なむかし」と思わせるほど美しい。エエ男は何をしても何を着ても何があっても美しいのだ!
「なでしこ」の「し」は過去助動詞・「撫でてかわいがった児」ではないか、と講師が読み解いた。
◎ 源氏の「よろづにつけて光失せぬここち」は妻を失った悲哀だけでなく、自身の生活基盤まで、
全てを失った落胆なんですね。先生の「なでしこ」の解説も新鮮な驚きでした。それにしても源氏
と妹の夫婦仲をよく知る中将の「憂さ」を垣間見るシーンだなぁ、今回は。
◎ 左大臣家でうつうつと過ごす源氏のもとへ訪れた三位の中将。帝の祝賀の宴で青海波の舞を
競い合い、祖母殿(源内侍)と丁々発止と戯れ、友情の絆も強い妻の兄である頭中将。妻・妹を
失った二人の貴公子の雅の装い、見飽きぬほど美しい源氏の姿が豊かな古語から浮かび上がっ
てくる。降る雨も雲の流れにも妻・妹に思いを馳せる二人の歌。
娘を失った母大宮の身を削るほどの悲嘆…諸行無常の切なさが伝わってきました。
◎ 源氏の後悔の深さがこれでもかと語られるが、悲しみの迫り方が浅いような感じがする。また母
君の悲しみの表現からも深さが感じられない。それは高貴な人達のどこか情の薄い感じを出す為
のレトリックとするならば、やはり紫式部の力に感嘆するばかりで、今まで一貫して描かれてきた葵
の上のイメージと一致する。
◎ 悲しみにしずむ源氏の姿はやはり美しい。「やつしの美」だ。頬杖つく美男のポーズは古今東
西共通である。哀愁が無いと美しさに味がない。中将の思いがしみじみと伝わり、男らしい視点が
感じられた。
原文からひろがる源氏物語」2011年2月16日受講 葵の巻 御息所の文 p123~
深まる秋の訪れを風が伝えていた。朝ぼらけの霧に包まれる頃、源氏へ濃き青鈍色の紙に書き付けた文がひっそりと届けられた。御息所からの弔問である。
「さださだとけざやかに見聞きけんとくやしきは」……今もはっきりとと鮮やかに焼きついて離れない生魂への不快感。かといって弔問を無視することもできず、紫のにばめる紙に返事を書き送った。もう私に執着しないでくれ、と。
御息所が優れて美しい女性であればあるほど、葵の枕辺に現れた生霊への嫌悪感を払拭できない源氏は、生霊の素性を知っているとほのめかして、執着しないでくれと伝えたのだった。隠し通すべき秘密を源氏に知られた上に、決定的な一言を突きつけられた御息所は、心の裏側を見透かされたように恥るしかなかった。
御息所は元皇太子妃という高貴な身分であり、教養が深く、奥ゆかしく、すべてに洗練されていた。院にも「後宮に迎えたい」と申し出られたほどの女性だった。嵯峨野(野の宮)では趣ある趣向を凝らした催しを主催して、殿上人を足しげく通わせるほどのサロンの女主人である。その御息所を失うことは、美意識を共有する相手を失う寂しさに耐えることであった。だが生霊への嫌悪がよみがえってしまう自分を、源氏はどうすることもできない。
ここで初めて御息所の人となりが語られた。嫉妬深い怨霊の女として語り継がれる人では決してない、優れて高貴な実像が語られた。式部はこれまで、恋に殉じて身悶えする御息所をこれでもかと描き、苦悩を生霊にまで憑依(ひょうい)させた。源氏から「もうこれっきりに」と言わせてから、御息所の実像を明かした。この構成に引きづられてきた読者は「若々しきもの思い」におちた御息所の恋の果てが、どのようにとも言えないほどの深い闇であることを知らされた。
「若々しきもの思い」、恋に殉じるがゆえの苦悩、愛するがゆえの寂しさ・孤独は、高貴な名の誇りも世間体も、一切の虚飾を捨てた
袖濡るる こひぢとかつは知りながら おりたつ田子の みづからぞ憂き
に詠まれた(p68)。泥田を這い回るほどの苦悩を味わいつくした果てに、恋が彼女を手放さなくても、恋を手放す御息所へと変貌して欲しい。毅然と蘇生して変貌をとげるはずと希う読者は、いつしか御息所の恋の伴走者になっていることに気づかされた。
「若々しきもの思い」に射抜かれた恋は生霊まで産んだ。生魂は恋が昇華していく過程の姿である。おぞましい嫉妬ではない、恋に殉じたがゆえに訪れたものであり、御息所の人となりを語り尽くして、美しく哀れな調和を保っている。 御息所が別れを決意するには、いま少し、心の支度が要るだろう。苦悩から解放されることを、ゆっくりと噛み締めるための支度が……。
失われていこうとしている膨大な闇に耳をすませて、御息所は何を訊くだろうか。
御息所からの弔問の文が届き、源氏は恋の幕引きを告げた。鳥部野で見上げた有明の月(八月二十日過ぎ)からいつのまにか、風が見えるような秋を迎えた。夜の帳を拓いて刻々と変化していく気配が、繊細な日本語で描きわけられ、朝を迎える時間の変化は恋の時間の経緯でもある、と講師から指摘があった。暁→曙→あさぼらけ 暁に男は帰っていき、曙が恋の余韻を包む。そして朝ぼらけに後朝の文が届く……。この朝ぼらけの刻に、源氏から御息所へ弔問の返事が届いたのだった。
読後瞬間一言感想
◎ 深き秋のあはれまさりゆく風の音 時の移ろいに~悶々と日々を過ごす源氏のもとに「今めかし
う」の文がさし置きて去にけり……。場面の情景と物語の展開の美しさ、源氏への思慕が断ち切
れない御息所の文に、亡き北の方の枕辺に現れた生霊と文の主を重ね併せる源氏は、苦悩す
る。理性と感性に揺さぶられ、究極の恋に苦しむ御息所の一途な心情を、式部の冴えた筆力が
伝える。
能「葵上」の御息所は、やりきれない女の悲しみ、寂しい姿を表現している。能の舞台を拝見
したいと思う。高見沢さん、解説をありがとうございました。
◎ 六条御息所のイメージが良くなり、これから先の事が気になります。紫式部が各々違った女性
に心を寄せる源氏を様々に書き綴っていくので、読む楽しみが増えました。
◎ 源氏に生霊を見られてしまったことがこんなことになろうとは……。隠し通せなかったのが悔や
まれる。世間の噂はやがて桐壺の院にも知れることとなるだろう。そんなこんなで心は乱れ、精
神を病むことになってしまった。思い詰めると現代で言う精神病になります。
◎ 御息所の感情は、式部の実生活からあふれ出てくる思いを書き出しているのでは、と思いまし
た。所々にフィクションも入れて……。ステキな納得のいく御息所でした。
◎ 野の宮のサロンの女主人公・御息所の「おほかたの世」、綺麗だけではない、人望を集める風
流人の暮らし。「忍び見たてまひて」源氏の手紙を開けるときの御息所の高鳴る胸のドキドキが
聞こえそうです。
「心よりほかに若々しきもの思ひをして」と自分の恋を振り返っている御息所の心は、やっぱり
50歳を過ぎないと分からない…?
◎ 六条御息所がいかに美しく、教養高く、洗練された女性だったかが、はっきりと述べられてい
る。純粋で可愛いところもある素敵な人だ。だから「若々しきもの思ひ」で恋をしたのだろう。源氏
は御息所の生霊を見てしまったが故に心が離れそうになるが、御息所の魅力を思うとやはり離
れがたい気持になる。恋とは一筋縄ではいかないものだ。
◎ 若い殿上人たちが憧れ、一目を置く御息所。源氏にとっても美意識を同じくするかけがえのな
い女性だ。とはいえ、生霊を垣間見た源氏の心は揺れる。ああ「若々しきもの思ひ」か…。ホント
ため息が出ますよね。源氏は罪な人です。
◎ 「心よりほかにもの思ひ」をしてしまい、身を焦がすこととなり、ついに世間の噂の種に。いづれ
は院の耳にも入る。「ついに憂き名をさへ流し果てて」という嘆き。「とうとうこんな情けないことに
なってしまった」。恋の破局、御息所の絶望感が痛々しい。
破局が御息所を打ちのめしても、しかし彼女は嵯峨野のサロンの女主人。殿上人を足しげ
くサロンへ通わせる人望・センスがあり、美貌も才能も教養も兼ね備える女性。生霊と化した
女は、源氏が美意識・教養を共有する大切な恋人であると明かされた。絶妙な構成によってここ
にきて御息所の人となりが書かれているので、これ以上の効果的構成はないと、式部の天才
ぶりに驚愕した。葵巻の冒頭、または夕顔の巻の六条あたりをうろついていた頃に御息所の
人となりが描かれていたら、印象は違ったものになっただろう。式部のような天才は天才にしか
できないことを為す!!
原文からひろがる源氏物語」2011年1月19日受講 葵の巻 追慕の日々 p116~
鳥部野で送った葵への追慕を抱えながら、それぞれがそれぞれの喪に伏していた。
独り娘を失った母宮の嘆きは言うまでもない。悔い多い結婚生活を振り返る源氏には、形見の若宮がせめてもの慰めであった。
< 能「葵上」の六条御息所 >
高見澤公子
能には「源氏物語」を典拠とする作品が少なくない。
六条御息所が主人公の能には「葵上」「野宮」があり、趣を異にするが、それぞれ名曲、人気曲として上演される機会も多い。六条御息所は「源氏物語」の女君の中でも、ひときわ異彩を放つ存在であり、劇的人物である。世阿弥が手引書の中で次のように述べている。
「あるひは六条御息所の葵の上に付崇り、夕顔の上の物の怪の取られ、浮舟の憑物などとて、見風の便りである幽花の種、逢ひがたき風得也」
「源氏物語」に登場する貴人のうつつない風体を、舞台に適していると世阿弥は考えていたようである。
能「葵上」では、病み臥している葵上は舞台上の装束(出小袖)により象徴されているだけで、一度も登場しない。生々しい人間として出てこないのである。役者同士を対立させず、主人公の心理を際立たせる能の優れた技法だ。能「葵上」には、恨みをより強く、より美しく見せるための演出の工夫があり、舞台展開が際立っている。
ところで、能は鎮魂の芸能と言われるが、六条御息所は成仏し、葵上は癒されたことになるのだろうか。観客は、六条御息所が愛執から解放されたと納得できるのだろうか。
「成仏得脱の身となり行くぞありがたき」という結びの言葉が表すように、台本的には六条御息所は成仏したことになっている。御息所は行者との激しい闘いの中に、孤独ですさまじい愛執をくぐりぬけ、浄化への帰着を見せるのだ。観客がすんなり納得できないとしたら、一様には捉えられない人物造形が能の六条御息所になされているからであろう。
実際に演じる能楽師は御息所の人物造形をどう考えているのだろうか。
その問を何人かの能楽師に投げかけたところ、大変興味深い話が聞けた。
「詞章が『成仏した』で終っていても、すんなり終わるのではなく、『また何かきっかけがあったら、この人(御息所)のドラマは始まってしまうのだろう』というような、モヤモヤとした不穏な空気をそこに残しつつ終わるように、と教えられてきてずっとそう演じてきました」
とは、観世流のある能楽師。
もう一人、観世流の能楽師の話。
「激しい情念を表現するわけですが、乱暴にならないように気をつけます。般若の面をつける曲には他に『道成寺』『安達原』などがありますが、その中で『葵上』のシテが一番身分の高い六条御息所ですので、強さの中にある程度気品を考えます」
「宝生流は、詞章に忠実にやります。気をつけるとしたら、鬼の姿になった自分を『こんな姿になって現れるのが、恥ずかしく悲しい』という気持ちを入れること」
こう言うのは、宝生流の女性能楽師。
同じ宝生流の、私の尊敬する能楽師はこう言っている。
「鬼となった苦しみ、幾重にも蓄積された、やりきれない女の悲しみ、寂しい姿が感じられないといけないように思います」
実際、この能楽師の「葵上」は、少し陰があって寂しいなかに色気があり、素晴らしい舞台であった。
それにつけても、能楽師の様々な話には能という600年続く芸能の奥深さを改めて感じさせられる。能楽師は「源氏物語」をよく読み込んでいる。その上、能「葵上」は観客が「源氏物語」を熟知していることを前提として上演される。これは「源氏物語」が日本文学の中で重きをなし、それ以降の文化全般に影響を及ぼしていることの端的な例であろう。
読後瞬間一言感想
◎ 源氏の葵の上の死の悲しみが非日常的な行動で伝わってきます。また娘の死を悲しむ母大宮
の何に心をぶつけたら良いのか解らない思い悩んでいる姿が、浮かび上がってきます。しばらく
はこのやるせない文が続くのでしょうか?
◎ 人ひとりが亡くなるということは、亡くなった人とのつながりによつて様々な悲しみをもたらす。
残された人達、特に源氏はいろいろな苦しみを味わっています。後悔してもしきれない、今頃気
づいても遅いよ、と言いたい。
鈍色の濃淡があんなに多いとは思わなかった。(色辞典を見て思いました。)
◎ ようやく得た北の方との絆も有明の月空に煙となって昇って……。源氏は「なほざりのすだび
につけても」と心を通じ合わせることもせず過ごした日々を顧みて、嘆き、悔やみ、悩む。ひたす
ら念誦する姿は「いとどなまめかしさまなり」と、語句の響きに情景が広がる。
文中の「なほざり」のことばに私は「?」。過ぎたときを感じた。「なほざり」「をざなり」おこごとや
お詫び、反省などの日常語だった平安からの言葉に驚いた。「おぼし続けらるれど」古語の流
れの美しさはラ行から成り立つのかしら。
◎ なぜ葵があの様な女性となったか? 内親王の母とその女房たちに階級社会の頂点の環境で
育てられた彼女は、男に媚を売ったり、へつらう術は知ろうにも知りえなかったのです。
「なほざりしのすさび」を深く深く後悔し、でも「ほだし」の若君を、そして西の対の姫君のため
に出家できない。悲しみはまだまだ続きます。また、能が回会(えこう)舞であったと知りました。
◎ 母大宮が悲嘆にくれ、源氏が後悔の念にかられる今回は、書けませーん。ただ某女のお能の
話に「おー!」でした。古文の世界から話が広がるのがスバラシイです。合掌!
◎ 葵亡きあとの源氏・母宮のそれぞれの追慕の日々。これから妻との関係を積み上げていける、
はずだったのに、逝かれてしまった。どんなに悔いても悔い足りない。
亡くして初めて知った妻への感情。源氏の読経は艶めき、面やつれ…色男は見苦しくやつれ
たりはせず、ヤッパ美しい!!
「古語は相手との関係語である」という講師の指摘。「うとくはづかし」「かたはらさびしくて」など
など、相手あっての言葉。 ほだし→馬の脚をしばるロープ→つなぎ止めるもの→こども、という
古語の解説が印象的です。(某女子の能の話が面白かったのに、感想が書けないのが残念)
2011年12月15日受講 「原文からひろがる源氏物語」 葵の巻・急死 P107~
男たちが秋の人事のために内裏へ出払った隙をついて、物の怪たちが再び葵に取り付いた。
葵の急逝に衝撃を受ける左大臣邸の人々。男たちは取るものもとりあえず「足を空にて」屋敷に戻ったが、押し寄せる弔問の使者たちに目もくれず、右往左往するばかりであった。もしや生き返るのではないかという希いも虚しく、死者が蘇える奇跡は起きなかった。
病床で握った葵の手の感触、幸せの余韻が源氏を苛む。自分の気質が葵と六条の御息所という二人の女を滅ぼしてしまったのか……。
院から弔問が届き、左大臣は悲しみと名誉あるうれしさに、滂沱と落ちる涙に流されそうであった。鳥部野(火葬場)へ向かう親の嘆きへ、式部は「いみじけなること多かり」と添いつつ、悲嘆であれ晴れがましさであれ、感情を顕わにする左大臣の人柄を、温かな人間味に充ち充ちたものに描く。すでに左大臣へ情の移っている読者は、この逆縁にもらい泣きしそうだった。
脆さの足りない花にしか見えなかった妻とは、久しく疎遠だった。やっと二人の絆が快復したのだったが、……喜びに酔ったぶんだけ、悲しみは深かった。立ち昇っていく煙をぎ見る源氏には、葵との歳月が幽(かすか)に遠のいていくように思える。雲が妻のように思えてならず、あの雲、その雲も妻かと思う。あれもこれもどの雲も妻のように思えて愛おしく、行方を追わずにはいられないのだった。
悔恨と悲愁の感情で過去とつながり、汚点のような記憶まで膨らんだ。それで気持ちを支えられるのなら、悔恨も悲愁も汚点さえも悪くはない。悲しみの感情は、さまざまな物事・他者への想像力を潤す地下水となって、源氏を成長させていくだろう。感傷は、だから涙へと結晶するしかないのだった。
鳥部野に二十日余りの有明の月があがる。月の欠けた部分は葵、いやいや、欠けてしまったのは自分だと、源氏は思っただろうか。欠けていく月が、また順々と快復していく日々、左大臣と源氏が涙の奔流から這い出してほしいと希わずにいられない。
命は、長さよりも深さが大切であることを示すために、式部はこのようにあっけなく、源氏から葵を引き離なしたのだろうか。葵の急逝は、生か死かのいずれしかない人生のシンプルさを際立たせるための、展開なのか。互いの人生に立ち会うべき人として、かけがえのない相手であったと気づかせるための、操作なのか。刻を経れば、別れが傷口だけを残すのではないと、式部はそんなことも言いたいのだろうか。
荼毘の煙を仰ぐ者への慰めなどあるはずもなく、多くのものを喪いつつ人は生きていくしかない。幸福に酔ったぶんだけ悲しみが深いのは、しかたがあるまい。涙の海に遺棄された者が思い出から開放されることはないが、幸福を探す道筋を「幸福」と言うのなら、二人の和解の刹那は到達点だった。それに気づくために、源氏は激しく嘆き悲しむこと受け入れなければいけないだろう。
「冴ゆるとも 、冬のときは冬ばかり、冬の寒さに震えるしかない」、式部はそう言いたげだ。だから悲しみは衝撃的なまでに美しく描くことで示すしかないと。
存分に悲しむがいい。悲しみを避けて通る路などありはしないのだから。
そんな式部の声が聴こえてきそうだ。
………葵急逝の衝撃をかぶった受講者たちは、源氏や左大臣の悲しみに添いつつ、覚えのある死者との対話を蘇らせました。死者と遺された者との対話は、生涯を通してつづけられ、か細く薄れていく記憶は、しかし消えることはありません。より良く生きてもらうために、死者はそうやってこの世へ遺棄した者へ添いつづけてくれるのではないでしょうか。俗に連れ合いを遺す人の「自分など忘れて幸せになれ」という遺言を耳にしますが、死者との対話がつづく先にこそ、胸はって幸せになる日がくると思うのですが……どうでしょう。先に逝った者に恥じない生きかたをするために、対話しつづけることが必要かと。
読後瞬間一言感想
◎ 北の方の急死、やっと穏やかになった水面に、突然石が投げ込まれたように訪れる。
その波紋が広がり、波だった中心は悲しみの底に沈む。「あぁ、どうしてこうなるの…?」
源氏が空「のみ」のなかて詠んだ歌が胸にしみる。
◎ 娘を亡くした左大臣の悲しみを細かく細かく描き、その後、空を見上げて歌う源氏の妻を慕
う深い悲しみの歌。 八月二十余日の有明の月と、空に浮かぶ雲が葵の死を悼む。書割に
はぴったり!!
◎ 突然の葵の死。左大臣家の隙をついたように、葵は逝ってしまった。
野辺送りの雑踏は左大臣の権力の証でもある。娘に先立たれた父親の悲しみを昇華せんと、
荼毘にふした煙が昇っていき、その先に拡がる雲々を仰げば、あの雲が葵だろうか、それとも
…。どれもこれも、あの雲もその雲もみな妻のような気がして愛おしい。
有明の月を見上げながら、妻を失った悲しみにヒタと寄り添う源氏。悲しみは深く、深い悲し
みはあらゆるものを浄化して、透きとおった美しさを放つ。悲しみは飽和状態となり、珠のような
夜露を産む夜陰に似て、美しい。葵を昇華した煙は、別れを惜しんで身をよじるように昇っ
ていっただろう。人はこんな風に逝ってしまうものなのか。こんな風に逝かせていいのか。
悲しみが深いぶん、美しい場面となって読者の心をわしづかみした。
◎ 葵の亡骸が変化していく様が繰り返し述べられ、強調されることによって、近しい者の死に
直面した者があきらめ、受け入れていく心理がリアルによく描かれている。とはいえ死を受け入
れ難いのも人間の心理である。子に先だ立れた老いた親の悲しみが左大臣の姿を通して、読
者の心に沁み入る。
人の死に直面した時に、自然界の美しさに心を奪われることは、よくあることである。この普遍
性こそ、やはり名作の所以であろう。
◎ 葵の死は親からみれば娘の死であり、夫からみれば妻の死であり、それぞれの悲しみが交互
に描かれている。式部により人の心の描写が鮮明に良く現れされていると思います。私も日
常の生活の中で、ここまで細やかな感受性があればと思いますが、もしそんな感受性があった
ら、生きてはいけないだろうとも思います。
◎ 古文の読みにつまづきながらも源氏物語6冊目。いつもことばの流れに魅せられる。
「殿の内人すくなにしめやかなるほど」「いといたうまどいたまふ」 北の方が死に至る左大臣
邸の情景。 「足を空にて」「ものにぞあたる」「ゆすりみちて」、人々の狼狽・動揺・嘆きが短い
語句から伝わってくる。
「いみじげなること多かり」と左大臣の心中は尽くしがたい悲しみに充ちていると、語り手は伝
える。「いみじゅうかなし」と伝わる。源氏はようやく得た妻との思いも束の間、葵の上は昇天
される。
◎ ようやくお互いを解りあえたかな、に見えたのに、突然の妻の死によって深い悲しみと後悔の
念にかられることになってしまった。亡くなって知る悲しみは、味わった人でないと分からないか
な。死は、親と夫婦とでは悲しみの深さが違うらしいが。
平成22年11月17日 報告 沈光子とその仲間たち
「原文からひろがる源氏物語」葵の巻・夫婦の絆 p100~
源氏は内裏にも出仕せず、葵の看病にかかりきりだった。危うい峠を越えたのだろうか、弱々しい葵の返事が返る。もはやよそよそしく良い所だけを見せ合う夫婦ではなかった。臥している御座近くで妻と言葉をかわし、久しぶりに出かけていく源氏。
美しい髪の端麗さはそのままに、北の方はいま病み衰えている。痛々しく、またいじらしくもあり、どうにでもして労わりたいと思うほど可憐だった。かつて感じたことのない妻への思いは、源氏の自尊心のもっとも深い部分をくすぐり愛撫しただろう。「これまで自分はこの人の何が不満であったのだろうか…」、源氏は妻をまぶしいものを見るように見詰めた。
殻から頑なに抜け出すことのなかった妻に疲れていたのだ。しかし病み臥した妻は、何かに寄りかかりたい気持を隠すこともない。こうして思いがけず弛みほどけた枷から押し寄せた夫婦の絆。苦しい夫婦愛への渇望から開放され、潤されていく二人。源氏と葵が並んで初めて同じ方向を向いた瞬間である。
夫婦としての過去の失敗の経験が、修復されて宝になろうとしている。共に病を闘ってすくいとった絆だ。この場面の葵と源氏は、額縁の中の記念写真のように読者に記憶された。幸福が崩れ去ることはたやすいのだから、しっかりと源氏という夫の枠へ、葵を繋ぎ止めて欲しいと思う。
可召ある定めの日に左大臣邸の男たちがこぞって出払ってしまった。物の怪がつけいる隙ができた左大臣邸……。
この日は夫婦関係の回復にホットした読者は、先へ読み進むのが惜しくなりました。「ハイ、ここまで!」と早めに本を閉じたのは、誰もが源氏と葵の関係に心を痛めていたからです。
読後一言感想
- 何故に当時はそれほど髪の美しさにこだわったのか……、五感をゆさぶる暗闇文化。
女の美しさは闇の中から立ち昇る。髪、肌、香、声、けわひ…から。
夫婦関係が自覚されたとき、そして連れ合いを喪おうとするときに、お互いを「らう
たく」感じるのでしょうか。夫が随分大人になったと北の方は思ったでしょうね。
- 病床に臥す葵の上の姿に源氏が目を奪われる気持が、よく伝わる場面だ。夕顔の亡骸
の描写を彷彿とさせる葵の髪の美しさが際立ち、印象的だった。
- 若い源氏が年上の妻をやっといとおしく思えるようになる。「大宮がつと若くもてな
したまえば……」と夫らしい声で語りかける。薬湯を飲ませたり、と源氏は案外まめな
人であるらしい。モテる男はマメである。
- 床に臥した身にやさしい言葉はこたえます。頼りになる夫として互いも意識し、絆に
目ざめ、ホッとさせられる場面に安心した。ギブ・アンド・テイクですね。
- 葵の上の苦しんでいる様子が目にとれるように表現されていますね。他の者を入れな
い夫婦の関係が、危篤状態のとき良くなるなんで。式部の構成力には感心させられまし
た。
- 妻が病み衰え、初めて夫婦の関係が回復するという場面でした。乱れをみせなかった
完成された美に包まれた妻には、とりつく暇がなかった。そのよそよそしさが一転して、
病み臥し、衰えたとき、に初めて心から寄り添うことができた。源氏の優しさと、あり
のままの素直さをみせる葵の弱々しさが、凍てついた互いの関係を溶解した。感動的!
可召ある定めの日、男たちはより高い官位を得ようとして、出払ってしまった。左大
臣邸はカラッポになった。不安をかきたてる含みあるこの場面。またまた読者は、次の
展開へと式部の筆に翻弄されつつ、附いていくしかない。
平成22年10月 「葵」受講 二重写し~芥子の香 P45~ 沈 光子とその仲間たち
若宮が産まれた。災いをもたらそうとやって来た物の怪たちが妬んで騒いだが、膨大な奉納と引き換えに比叡山の座主や高僧たちの祈祷はつづき、後産も無事おわった。緊張の日々から解放された左大臣家は歓喜に包まれ、人々の関心は赤子に集まる。祈祷の手を緩めているわけではなかったが、緊迫していた邸内の空気が緩んでいく。
珠のような若宮を得た喜びに沸く左大臣邸の噂は、六条の邸へも届いた。らしくもないいどみ心がよみがえる御息所は、心穏やかに過ごすことができない。……気づくと、芥子の香が全身を包んでいた。
芥子の香という動かぬ証拠が、わが身を包んだおぞましい現実を突きつけていた。うちかなぐる夢を見はしたが、北の方を苦しめた生霊が自分であったとは。
誇り高く生きてきた御息所は、ありていなみすぼらしい挑み心を憎んでいたはずだった。だが手繰りよせるまでもなく激しく匂う香りが、秘められた闇を照射している。。匂いから逃れようとする姿に、必死さゆえに、あたりを圧する凄みがあった。
「色」「音」かそけき「けはい」に加えた「香り」という小道具が、最大の効果を発揮して、棲んでいた心の闇を浮かび上がらせた。愛がもたらした苦しみの果ての、自意識を追い詰める闇への扉を開く冷徹な場面と言えよう。
若宮を得た左大臣家が「明」なら、御息所の孤独は漆黒の「暗」。左大臣邸の「明」を際立たせるものとして、御息所の心の闇が「暗」が最大効果を持って対比され、人間の光と陰が残酷なまでに迫ってくる場面が、この「芥子の香」部分だろう。香りという感覚を刺激された読者は、御息所と伴に孤独の感覚を味わった。他者と分かち合うことのできない闇のエネルギーが、読者の胸をもまた絞めつけた。
野心に燃えて王を殺害したマクベス婦人をシェクスピアが書いた遥か500年もまえに、式部が「匂い」とう感覚を刺激して「人間の心の闇」を照射してみせたのは驚くべきことだという解説が講師からされた。また「汗おしのごひつつ」急ぎまかでた僧たちが退散する姿は、高僧ゆえに滑稽であり、式部の容赦ない鋭い観察が細部にまで行き届いていることに、改めて驚かされた。
瞬間感想
◎ われにもあらぬ御ここちをおぼし続くるに、御衣などもただ芥子の香にしみ返りにる
あやしさに……。いまで言えばノイローゼ。臭覚は脳の近く、脳がまた香りを作り出す。
御息所をここまで追い詰める紫式部はなんと残酷な人なのでしょう。紫式部は五感すべ
てに訴えかけてくる。
◎ 自分の衣服と髪に芥子の香が深く沁みついているのに気づいた。その瞬間の御息所の
息を呑む表情。古語で読むから見えるのでしょうね。シェクスピアのマクベス婦人が手
を洗うシーンが書かれたのが、紫式部の源氏物語から500年以上あととは!!
式部はどうして、これでもかこれでもかと、御息所を追い詰めるの?
◎ 出産は今でも女性の一大事ですが、平安の昔はとても大変な事だったのですね。葵の
上の出産に周りの夫・父・御息所の不安な心が描写されています。そしてあの延暦寺の
お坊さんの心情までもが、読み取れる様に式部は書いているとのことで、恐れ入りまし
た。これから一児の親として、源氏がどう書かれていくのか、楽しみです。
◎ 怨念って恐ろしい。生霊となり執拗にとりつき、おどろおどろしい芥子の香りが沁み
つくなど怨念の心を掻き立てる。これは生霊となってとりついたものだと動かぬ証拠を
つきつけられた御息所は他言することも出来ず、自己嫌悪に陥り泥沼に沈んでいく。生
霊を信じない源氏もこの光景は驚くべきことだったろう。ともあれ無事に若宮は誕生。
お祝いムードに包まれるが次はどうなるのか? 御息所と源氏との仲は断ち切れてしま
うのか。
◎ 無事出産し、若宮を得た喜びに包まれている左大臣家。対して御息所は自分に芥子の
香りが沁み付いていることに気づく。芥子の香は、葵にとりついて苦しめていた生魂が
自分であった確たる証拠。夢で打ちかなぐる姿を見たがまさか……。芥子の香りから逃
れられることができない御息所。
必死に芥子の香を消そうしている御息所の姿に凄みがあり、哀しさがあり、人間のど
うにもコントロールできない心の闇へ踏み入っていく怖さがあった。出口の見えない
闇はどこまで御息所を追い詰めていくのか。また生魂の正体を知ってしまった源氏は、
御息所とどのようになっていくのか。紫式部の手の内に翻弄される読者である。
◎ 左大臣家では北の方の出産の成就祈願で若君誕生となり「にぎわしくめでたし」と盛
り上がる一方、御息所は御衣にしみ返る芥子の香に「わが身ながらうとましや」と心は
闇に沈む。源氏は若君出産を喜びながらも生霊の「声」「けはい」に苛なまれる日々。左
大臣も北の方の病を案じつつもやっと充たされる思いに「いかでかは」語り手のことば
に、ここまでの道のりを思い巡る。光と陰が相対して展開する。二月から読み解いてき
た「葵の巻」、起状あるストーリーリズミかな古語の表現を堪能。まだまだ続く物語。
平成22年9月15日「葵」受講P40~ 妻のまなざし 沈光子とその仲間たち
斎宮が野の宮へ移る二ヶ月の間に再びの御禊の準備で忙しかったが、六条の御息所は「ただあやしく、ほけほけしゅうて、つくづくとと臥しなやみたもふ」日々だった。ただただ呆けたように過ごしていたのである。源氏からの見舞い、訪問はあったが、男の心ここにあらずだった。紫式部は「まさるかたのいとわづらひたまへば、御心のいとまげなりおう」と妻を案じてお座なりになっている見舞いの様子を筆にのせる。身分社会の序列から滑り堕ちた御息所は、男の愛情さえも最上級ではないことを思い知ったのだ。男の愛に過敏になっている怜悧な女に、追い討ちをかけた源氏のお座なりさ。いっそ見舞いなどない方がいいのか、それでもある方がいいのか……、古今を問わず恋の「生殺し」は罪深い。式部の手にかかると、あらゆる感情が残酷なまでに映しだされるので、読者は苦しくなる。
予定日より早めに産気づいた葵の苦しみようは尋常でなかった。高らかな祈祷の読経がある旋律となって左大臣家邸内を包んでいく。取り付くろうこともかなわない病み臥した葵は、身構えを解き放ち頼りなげで愛らしかった。白い装束と家具調度に調えられた産屋に臥した妊婦の艶々した黒髪が、命を与えられたように白黒のコントラストを際立たせて輝き、読者の瞼の裏に描かれるイメージを射抜く。黒髪だけが、それだけが命を与えられているような、新鮮な感動を現代人にも与える美しい場面である。読経の声が生霊に乞われて鎮められると、いっそうの迫力をもって地から湧き上がるような祈祷の響きが邸内を圧した。
葵と生霊は混然一体であった。まさかそんなことはあるまいと否定した世間の噂。しかし葵を苦しめている生霊は、まぎれもなく御息所であろうと確信した源氏。沈黙を呑み込んで吐き出された恋する女の苦悩が、こうして飛んできたのだと。
瞬間一言感想
- 音を考えました。僧たちの祈祷の大声の中の女房たちのざわめき。それが静まり几
帳の中の二人のヒソヒソした会話、そして「いで、あらずや……」
御息所の人格と生霊の人格は全く別のもの。源氏の涙が生霊の涙を誘い、生霊がや
さしい声で「なつかしげに」言うのでしょうか「いであらずや」と。一般に言われている御息所の「嫉妬」という言葉の薄さを感じました。
- 産室では出産をひかえた葵も、部屋に控える者たちも白装束。臥している葵を載せ
た畳の白いヘリ。白い家具調度。産室は降り積もった雪景色のように、ピーンと張り
詰めた空気が漲っている。その緊張を揺さぶって左大臣邸に響く加持祈祷の読経。真
白な空間を切り裂くように、若々しい生命力に満ちた艶やかな黒髪が臥した葵に寄り
添っている。几帳の中で源氏は葵と混然一体となった生霊と対した。高らかに響き渡
る読経は生霊に請われて鎮まり、低音部となってこの場面の厚みを下支えする。源氏
は葵にヒタと添って離れない生霊が六条の御息所だと確信した。奥ゆかしくまた教養
と誇りに充ちた御息所の、理性では治めきれない苦悩が、こうして葵の元へ飛んでき
た。生霊と御息所とは別人格であるとの講師の指摘に、改めて「いで、あらずや」と
源氏に対した愛らしさを納得した。迫力と臨場感に充ちた場面でした。それにしても
病み苦しんでいる妻を、愛らしくいとおしく見詰めた源氏の眼は、どこまでも品定め
の域にあり、美的感覚に貫かれている。源ちゃんダメだよ、ちょっと泣いたくらいじ
ゃぁ。もっともっと取り乱さなくちゃ。
- 声に出して読みたい日本語「いかがあわれの浅からむ」などまるで浪曲を聴いてる
ようである。スピード感があり、臨場感がある。「生きすだま」もやさしく手をとられ
て話かけられると、なつかしげな声で答える。人の心は相手しだいであるようだ。
- 出産を目前に生霊にとりつかれてしまった北の方は、源氏に対していつもの堅苦し
さはなく、柔和な眼差しと涙に愛らしさを感じた。源氏は少しホットしたようだが、
それにしても生霊ってすごいなと思った。「すごいな」としか言いようがない。
- 御息所の魂に人格を感じることができました。古典は難解な文章だけかと思ってい
ましたが、現代にも通じるSFの世界ですね。現代人の私たちは映像でも物語りを見
て楽しんでいますが、文章で、しかも平安の時代に読者に解るように書いているのだ
から、スゴイですね。
- 斎宮の準備の慌しい中、母君御息所は「ただあやしくほけほけしうて」。古文の表現
は言い得て妙。一方、左大臣家では北の方が出産の兆し。渾身の祈祷の続く中「大将
に聞こゆべきことあり」とのたもう北の方。御几帳の中で我が子を身籠って苦しむ妻
の姿に「らうたげになまめきたるかた……」源氏は初めて妻を身近に感じて泪する。
慰めの言葉を紡ぐ源氏に「いであらずや」「のたもう声、けはひ」「その人にあらず」
と短いフレーズ。やっと北の方と夫婦(メオト)の気分に浸った源氏。場面の展開に
読み手も息を呑む。
- 女二人の苦しむ姿が交互に出てくる今回の場面。苦しみの中身は違うけれど。苦悩
も心の限界を超えると「あくがるる」魂になるのね。そんな想いしてみたいような、
してみたくないような……、オオこわ!!(怖い)
平成22年8月18日 例会報告 沈光子と仲間達の瞬間感想文
源氏物語 こひじぢの田子 p35~ 2010年8月18日
恋の甘露に酔ったぶんだけ、女は傷つかければならないのだろうか。七転八倒している苦悩を横目に、男の心はすれ違って通り過ぎていく。高貴な身分・誇り高くという衣を脱いで悶えるような感情をさらけ出した御息所の歌には、恋に殉じる潔さがあったが、その潔さに源氏はたじろぎ、応えることができなかった。はぐらかされて、いっそう傷ついたにちがいない御息所。
世間では生霊の噂がかしましかった。御息所は屈辱にまみれた御禊の日以来、無念な思いが育てた自分の魂のゆくえに、今更のように思い至る。もの思いが高じてあくがれ、ふらふらと彷徨い出た魂は、感情のままにかの姫君とおぼしき人をうちかなぐったのではないか。これまで他人をあしかれと思ったことなどなかった。自分は心に怨みの根を張るような女ではない。だが裡に塗りこめられていたものに気づいてみれば、そんな通り一遍のうのぼれが霞んでいく。……ただひたむきに恋に殉じただけなのに……、気づいてみれば、なんと遠く異質の境地へ私は辿り着いてしまった。世間からも、そして源氏からも孤立していく怒りにも似た愛憎に包まれる心の裡を覗き見た御息所は顎然とし、醒めていくものがあった。。
もの思えば 沢の蛍も我が身より あくがれいずる魂かとぞ見よ 和泉式部
受講後瞬間感想
- 魂があくがれる。コントロール出来ない自分の分身を、冷静に分析している。「あな憂
しや」。御息所よ、フロイトの世界が1000年前にあったとは。世間がこれほどまでに
恐ろしい時代、ある意味、今も変わらないのでは。和泉式部の蛍の歌。さまよう魂が蛍
とは。素晴らしいです!!こんなに御息所の心の闇が書かれているとは知りませんでし
た。ストーリを追いかけることが目的の第一だったら、今回の箇所は素通りでしょう。
四次元の魂の世界まで描ける式部に改めて、目を見張りました。
- 自分の気持を相手に伝え、真意をわかってもらうことはとても難しいということです
ね。今の日常においてもよくあります。お互い自分の都合の良い様に解釈しますから。
まして歌ではよけいそうです。(ここでは源氏にうまくかわされましたが。)袖のみの「の
み」が強く印象に残りました。こうして御息所は精神的に追い詰められ気持の持って行
く場を失い、とうとう異常をきたす様になってしまった。源氏って罪つくり。
- 今まで思い描いていた御息所とはなんと異なった印象か!! 御息所は自分の源氏へ
の想いが深すぎるため生霊となってあくがるなる魂となってしまったと恐れおののいて
いる。そして何より恐ろしいのは無責任に噂をする世間。闘いようのない理不尽さには
魂も彷徨い出てしまうほど苦しいに違いない。
- 大殿から離れない御霊・生霊は何者ゆえなのかと、口さがない世間がかしましく噂す
る。御息所は車争い以来、身体が不調である。呆けたようになった自分の裡から、生魂
が抜け出て、あくがれ・うちかなぐっていたというのだろうか…と愕然とした。深い内
省が細な筆で緻密に描かれている。式部がヒタと寄り添って細やかな筆使いを行き届か
せているので、御息所という女像を浮き上がらせた。それにしても一夫多妻制度の時代
を生きる男と女。あっちの花もきれいだし、こっちも可憐だ、あれも良い、これも……、
と苦悩を真正面から受け止めようとしない男という生き者に再び打ちのめされる女。男
と女の間の、暗くて深い谷を渡るすべがあるはずもないのだが。
- 御息所は自分が自分でなくなると思う苦悩、心の揺らぎ、情念。「たかが恋、されど恋」
読み手も一緒に沈んでしまいそう。式部は御息所の深層心理を見事に表現。難解な古文
でこそ味わえる葵の巻です。
- 御息所の恋はとても重い。魂も飛んで行ってしまう恋なんですね、ビックリしました。
今年の夏はとても暑いですね。生霊の噂も出たりして、少し涼しくなりました。
- 御息所は苦しい心情を歌にさらけ出したのに、源氏の返歌の何と逃げ腰なこと。言葉
遊びにしかできないなんて。桐壷院に叱ってもらいたいです。それにしても車争いで受
けた屈辱は生霊になるほど心にシミになったんですねぇ。
平成22年7月21日 例会報告 沈光子
大殿のもののけ
車争いのあと、北の方はすっかり病みついてしまった。加持祈祷をさせると、もののけや生霊が現れて名乗りする。だが憑座(よりまし)に移ることもなく、北の方にヒタと張りついて離れない霊があった。
院からも見舞いがひっきりなしに届いた。源氏の後ろ盾である左大臣家の妻を失ってはならないのだ。院の、源氏の、なみなみならない心づかいは、大殿(葵)が大切にあつかわれている証として、波紋のように世間へ拡っていく……愛の天秤にかけられる御息所。
世の中を味方につけた北の方に比べて、御息所は身分社会からすべり落ち、はじかれてしまった現実を思い知るのだった。クサビのように鋭く刺した車争いの屈辱が、今さらのよう疼く。御息所もまた体調を崩した。
源氏が見舞いに訪れ、ギクシャクと打ち解けないときを過ごした。盛りを過ぎた陽ざしでも、瘡蓋を残酷に剥ぎ取った痛みをしばし暖め癒してくれそうだった。だから源氏の、たまの訪れを待つ女でいい……と思う御息所。
後朝の文が夕刻になって届いた。北の方の病状が急変したので今夜は行かれないと言う。ああ、やっぱり……不実な男の、いつものこの手の言いわけに、ごまかされた振りなどもうできなかった。
泥田に投げ出されて這いずりまわるような苦悩が、元東宮妃・御息所から吐露される。極限まで膨れきった恋情をこうして突いて詠ったが、だからと言って小さくしぼむことはない。研ぎ澄まされた知性が男の心を見据え、苦しみもがくしかない自分を見つめた歌一首。
袖濡るるこひぢとかつは知りながら
おりたつ田子のみづからぞ憂き
過ぎた岸辺には帰りつけない。甘やかな恋の装いを剥ぎ取って、もがき苦しむ境地をのぞき込めば、恋の果実を二度と摘みとることはないと、知るだけ。だが、それでもよかった。
張り詰めた言葉の響きが魂の叫びとなって読者に迫る。御息所の歌に読者は圧倒された。恋に身を投じる懊悩、ただ一心に男を見詰め、冷徹に己を見詰める知性。しかし未練の泉は枯れることがない苦しさ。
夜枯れた男の心を再獲得することでしか、穏やかになれまい。これこそが、まぎれもなく源氏との恋から手渡された苦い果実である。
瞬間一言感想
- 「うっ」「うーん」「ううう~ん」。ひとくぎり読むたびに、こんなため息がもれた今回。
御息所の心情は私たち塾女をうならせました。解りすぎて、かわいそう……すぎる!
- 御息所は世間すべてを敵にしたように苦しんでいる。「御いどみ心」からついに自分を
客観的に表す「袖濡るる……」の歌を詠むまでの心の動きの深さ・悲しさに比べて、源
氏の言葉の軽さ。男は嘘をつく時ほど言葉が多くなる。
- 車争いに端を発した二人の女性はそれぞれに変化を来たしてしまった。一人は物の怪
に取り付かれ、一人は深い深い屈辱感を抱き苦しみ、北の方に対して平常でいられなく
なり、自然と憎しみに変わっていった。訪ねてきた源氏に見事な歌で自分の気持を伝え
るところは素晴らしい。源氏って罪深いと思いません?
- 車争いの余韻も覚めやらぬ折、北の方の患いに左大臣家では「誰も誰もおぼし嘆く」。
しっくりしない間柄であるが、妻の存在でゆるぎない立場を得ている源氏は、忍び歩き
もままならない。加持祈祷で現れる物の怪の正体を、口さがない女房たちは詮索する(い
つの世にもあること)。源氏の吐息が聞こえてきそう。北の方、御息所、源氏と巴になっ
て展開する物語は式部の冴えた筆力でさらに続く。御息所さま、重く深くエネルギーを
消耗する一途な恋をなさいましたね。
- 当時は仏を信じ、極楽に死後に行けるようあの世からの仏の来訪を待つ時代。物の怪
のいることを信じて祈祷をし、恐れ、ただただ加持祈祷に頼った時代。御息所のやさし
い心情が後の歌にもでていて、今までの見方と違った感情が湧いてきました。
- 御息所の「おりたつ田子のみづからぞ憂き」で、物の怪のこと、生霊のことも一気に
忘れてしまいました。人生の中で気張らない、湧き出る恋の詩が作れる紫式部はやっぱ
りスゴイと思いました。蛇足ですが、私の父は七月七日に山から竹を切って来て、亡く
なった母へラブレターを出していました。「君子によろしく」と……。
- 「袖濡るるこひぢとかつは知りながら、おりたつ田子のみづからぞ憂き」。
この歌に至る御息所の心の動き。うちとけぬ朝ぼらけ→なほおぼしかへさる。おどろか
さるるここち→御文ばかりぞ→例のことづけとみたまふものから。更につづけて山の井
の水もことわりに、と決め打ち!! 何と冷静すぎて、悲しい女性。
- 大殿の物の怪を憑座(よりまし)に移して病を治そうとする左大臣家の心痛。世間に
圧し潰されまいとする御息所のいどみ心が痛々しい。打ち解けられないままに夜が白々
と明け、源氏は帰っていった。文があったが、今夜は行かれないという。例によって言
い訳に満ちたものだった。それも暮れつかたになって。御息所の透徹した感性が、男の
嘘も己の心も真っすぐに射抜いて詠んだ歌一首。「袖濡るるこひぢとかつは知りながら
おりたつ田子のみづからぞ憂き」。涙なしには読めない……こんなに悲しい恋があるだろ
うか。
男性読者は夕顔に、女たちは御息所に心引かれる所以を、遅まきながら納得。
平成22年6月16 日 例会報告 沈光子
典侍のかざし p24~
物見車がひしめく一条大路で声をかけられた源氏。どんな「すきものか」と思えば、あの典侍だった。
「参ったなぁ、こんなところでボクに声かけないでよ」
内心舌打ちする思いの源氏へ「恋の土俵では歳の差も身分も超えちゃうのよ」とばかりに典侍は歌をしかけてくる。やんわりかわせば、皮肉で切り返した典侍。ラリーはあっけなく終わった。
御簾を下げたままの源氏の車に女が同乗している。いったいどんな女なのか……、祭りに繰り出していた女たちの想像は膨んでいくばかり。張り合う気力がなえていき、結局、源氏に挑んだ女は典侍ただ独りだった。
海人のうけ p24
源氏の脚が遠のき、苦悩を抱きしめる御息所。彼とかかわったことで、味わったことのない日々に囚われている。寄せては返し、また新たな力を得て打ち寄せる懊悩の波は、いっこうに鎮まることがないのだった。波うちぎわで呆然と佇むしかない恋する女は、溺れそうである。
愛は虚しく頼りない、ただそれだけのものなのだろうか。みじめに打ちのめされる慰めに、一目なりと源氏の晴れ姿を……、そう思ってやつし車で出かけた御禊見物だった。そして車争い。屈辱を味わったが、それでも晴れ姿をチラと見ることができた……屈辱にまみれたがしかし、見ない後悔よりは良かった。そう言い聞かせても、誇り高い女を懊悩が捉えて離さない。
御息所の悲しみをわかっていて、源氏は寄り添うことをしない。できないのではなく、若さゆえの残酷さが女の苦悩に寄り添うことをさせないのだろうか。たがこれだけはわかる、男の心がもう自分にはないと。
耐え切れず、思いの丈のほんの一滴をすくって歌い送ると、おざなりの返事が戻った。さらに傷つき、脚をすくう深みのまえで、引くことも進むこともできない。自分を傷つけずにはおかない恋が御息所を追い詰めていく。
瞬間一言感想
- 葵の祭りで源氏は、典侍に会ってちょっとがっかりしたように感じます。式部は読者
のことも考えて、私たちと同世代の女性を登場させて楽しませてくれているように思い
ます。式部様でないと中年女性の思いをこんなに書けないのではないでしょうか。
- またまた登場の典侍は源氏に対して積極的です。これに引き換え御息所は悩み苦しん
でいる。諦めてはいるものの御禊の見物に出かけたときの車争いに遭遇し、心の苦悩・
葛藤は深まるばかり……、どう乗り切って行くのかしら?
- 源氏がうきうきと西の対の姫君たちと出揃って一条大路へ。「もの騒がしけるわたり」
の中、見覚えのある扇の端に歌が。それは源氏と頭中将と丁々発止の恋の火花を散らし
た典侍だった。扇の端に書き留めた典侍の歌に「あふひ」「葵」「逢う日」をかける言葉
の綾。華やかな御禊を軸に、挑発的な典侍と車争いで遭遇した御息所の屈辱で苦悩の日々、
二人の女性の陽陰を三次元で表現した式部の才能に脱帽です。
- エネルギッシュな恋のハンター・典侍のおばちゃまが、あざやかに再登場。あいかわ
らずで、老け込んでなんかおりませんでした。結局この祭りの趣旨を堪能した粋人は、
典侍ただ独りでした。源氏が伴った御簾の中の女をおもんばかって、他の女たちは腰が
引けているのに、おおっぴらに源氏とやりとりしましたねぇ。恋に関しては一歩も引か
ないところ、あっぱれ!!
思い煩う六条御息所の、海士の浮きのように心定まらない日々。源氏は思わせぶりな、
そして通りいっぺんの歌を返しましたね。男の心がもう自分にはないことを知りつつも
懊悩する御息所は、そんな自分が歯がゆくて、いっそう傷ついたにちがいありません。
誇りが彼女を支えていたのに、いつの間にか誇りゆえに苦しみ、恋に殉じる女になって
いた。口べっぴんの源氏の歌が傷口へ塩を塗ったわね。新鮮味を失った女に真っすぐに
向き合おうとしないのは、男の常よ。古今東西、男なんてこんなもんでしょ。男と女の
間には「深くて暗い河」があるです。
- 典侍は正統な祭を楽しんでいたのだと、この歳になったから見える「あふひ」の場面でした。あっぱれ典侍!! 旧りがた人になりましょう、皆さん!!
「御禊河の荒かりし瀬の波」がいかに大きいものであったか、改めて御息所の心の傷の
痛さ深さを表している。優れた表現です。海七の「うけ」と「御ここちも浮きたる」「う
け」と「浮き」が感覚的にわかります。
☆ 典侍の出現はいつも私たち読み手の心をゆるくする。いいキャラクターだなぁ。
「かの典侍なりけり」の「かの」が効いている。それにしても御息所の心の傷は痛々し
くカワイソー。源氏、うらめしやーである。
祭りの日は人間の悲喜こもごも。
源氏の周りには いろいろな思いをかかえた女性がいる。
紫式部はここでも裏表というか陰陽というか、異なる
立場の女性をたくみに描いている。
今回はにぎやかな女車の典侍のたくましいまでの恋心、
それに対して御息所の深い悲しみが強調される。
祭りのにぎやかなお囃子のなかで目が回る。

平成22年5月19日 葵 例会報告・感想文 沈光子
見物の人々 p17-13行~
神に魅入られてしまうのではないかとさえ妖ぶむほどの源氏の美しさだった。御禊の行列をひと目でも見たいと胸をときめかすのは、縁のある女たちだけではない。数ならぬ女たちでさえ源氏の一瞬のまなざしが自分を捕らえるはず、と胸をときめかせていた。
朝顔の君は桟敷から御禊の行列を見た。そして数年に渡って文を送りつづけてくる源氏の情熱を思い、しかし六条御息所のようには決してなるまいと、改めて自分に言い聞かせるのだった。
翌日、源氏は車争いのことを聴いた。葵の上は御息所に気遣いをする情の細やかさに欠けており、御息所は深く傷ついたに違いなかった。慰めようと駆けつけた源氏を、しかし御息所の誇りが遠ざけた。北の方もさることながら、御息所もまた源氏に心の弱さを見せることがない。愛情と、気位が天秤にかけられ、せめぎ合う。そして結局は気丈さが源氏を遠ざけることになる。
「ねぇ、2人ともボクの妻なんだからさぁ、巧くやってよ! 」
つぶやく源氏。泣きたいときは、ボクの胸があるのに…という思いがはぐらかされる。
こんな気鬱の日には、そう、源氏は確かな成長ぶりに慰められたくて、西の対を訪ねる。「紫の上を連れて加茂の祭りを見に行こう」。源氏は陰陽道・暦の博士に調べさせて紫の上の髪を切りそろえた。千尋の御髪という表現は、艶々とした豊かな黒髪を想像させて、紫の上の美しさを際立たせる。
はかりなき千尋の底の海松ふさの 生ひゆくすゑはわれのみぞ見む
(深い海の底に茂る海松のように 豊かに成長していく黒髪は私が見届けよう)
千尋ともいかでか知らむさだめなく 満ち干る潮ののどけからぬに
(満ち干す潮のように定めないあなたに 末長い愛情を誓われてもねぇ…)
堂々たる返歌だった。歌を書き付ける紫の上の、美しくそれでいてまだ幼さを残した愛らしい成長ぶりに、源氏は目を細めた。自ら髪を切り揃えてやり、「千尋に」と髪そぎの祝い言葉を唱えてやった。源氏の愛情は細やに行き届き、くつろぎと喜びが感じられる。
この時代の女性は常に男の愛を奪い合っている。高貴な身分、容貌が優れている、深い教養がある、などと全てを備えているようでも男を独占できるわけではない。気位の高い女性であれば、夫の夜離れは堪えがたかっただろう。この時代の常識とはいえ、一夫多妻制を受け入れらない女性は多くいただろう。葵の上も六条御息所も、時代の寵児・光源氏を夫に持ったために、深く深く傷ついた。だがその気持を直接ぶつけるようなことはしない。まして六条の御息所のような立場であれば、辛さは心の葛藤となって内在化してしていっただろう。この心理的発展が、これからの物語を展開させていく軸になっていくと思われる。
六条御息所は夫である東宮が死去しなければ皇后になったはずである。その女性に源氏は通りいっぺんの扱いをした。七歳年上という年齢の差への引け目、源氏の足が遠のいている屈辱、何ごとも決して世間に知られたくなかった。六条御息所を気安く扱ってはならないと父桐壷院から叱責されていたにもかかわらず……車争いが起きたのだった。六条御息所の懊悩はまた、皇后になり損ねて権力闘争からこぼれ落ちた敗者の姿としても、描かれたのではなかろうか。
瞬間一言感想
- 北の方と御息所の争いに「なぞや、かくかたみにそばそばしからで、おはせかし」男
の立場です。紫の上が登場するのは、いつも重々しい心から逃れたいときですね。源氏
の「かはりなき……われのみじ見む」に対して紫の上の「千尋とも……のどけからぬに」
しっかり育ってきましたね、彼女は!! これからが楽しみです。
- 北の方の心づかいのなさ、六条の御息所の傷つきよう。どちらの女の気質も源氏には
気鬱の種である。こんな気分のときは、必ず西の対へいく源氏。そして美しく利発に成
長している紫の上に心から慰められる。車争いの緊迫した場面から一転して、紫の
上と源氏の交流を式部もまた、ホット一息つくように書き留めていると感じる。
- 車争いの重苦しさから逃れるようにして姫君の元へ。ここでは一転して明るい雰囲気
になり、よかった。ますます美しくなっていくであろう姫君のこれからが楽しみ。源氏
様、頑張ってください。
- 源氏の時代の加茂の祭りは全てが本物であったのだろうと想像することが出来ました。
誰もがワクワクする祭礼だったのですね。私もいつか行って観ようと思います。
- 六条の御息所の辛い内面を際立たせたと思うと、次は紫の上の愛らしさをこれでも
かと書く。話の展開のうまさはさすが紫式部の筆力!
- 御禊の行列の桟敷には、源氏がかねてから文を送り続けている姫君もいる。源氏の美
しさに圧倒されながらも「いとど近く見えむまではおよしよらず」と恋に流されること
なく、また溺れることのない、源氏との関係を冷静に受け止める朝顔の君の存在が短い
文節から読み取れる。
車争いで「いみじゅうねたき限りなし」「心弱しや」の御息所と北の方とのすきすきしい
夫婦の間柄が重い。源氏は「なぞやかくかたみにそばそばしらでおはせし」とつぶやく。
難解な古語の行間から源氏のため息がもれてくる。また西の対で美しく成長した姫君に、
にんまりする源氏の風情が浮かぶ。
平成22年4月21日 葵 例会報告・感想文 沈光子
P12 6行~
御禊の日の一条大路は見物の車や人々でぎっしり。遅れをとった左大臣家の一行は、権力の物言わせて、見物に最良の場所にいる車をどかす。だが場所を譲ろうとしない網代車、しかしそれなりの身分と思われる「やつし車」があった。網代車の供人は「このお車は、さようにさしのけなどしてよいお車ではない」と後に引かない。 振舞酒で酔った供人たちが騒ぎあい、お忍びで来たことを大勢の人の中で露呈されてしまった網代車の女。「六条御息所ここにあり……、それもやつし車で」。
「たかが通いどころじゃないか」と侮辱され、いたたまれずに逃げ出したかったが、大混雑がそれを許さない。それでもなお「ひと目でも」と希う女心。屈辱に苛まれてもなお、源氏を目の端にでも捉えたかった。抑え切れない恋情は、語り手に「心弱しや」とため息をつかせるほどである。亡き皇太子妃であり斎宮の母という身分が、痛ましい。
左大臣家の車の遥か後ろから、それでも一瞬、馬上の源氏の姿を見ることができた。今日の源氏の美しさを知らないでいたら、どんなに口悔しいことだったろうと、女は思う。身をよじるように懊悩する切なさが、読者にも深く深く刻みこまれて共感の橋を架けた。
源氏は心当たりの女性の車を見いだすと、それとなく合図していく。遥かかなたからでも、御息所には一瞬で源氏の振るまいが読み取れる。だが源氏はやつし車に気づくことはなかっただろう。
たとえ相手が自分を見てくれなくても、自分はあの人の姿を一目見たから、やはり来てよかった。男が冷たい分、女の心は渇いていた。渇望し、ただ「あの人を見たい」。その渇きに男の晴れ姿が沁みていく。
噴き上がる恋情は鎮まることがない。現実が心をかき乱し、それでもなお網膜の奥にしっかりと焼き付けた姿は、彼女の懊悩への一点のなぐさめとなった。
読者も辛いですねぇ、恋の苦悩をこれほどあざやかに切り取って描いたものを、私は知りません。
ひときわ目立つ馬上の源氏、「さらぬ顔なれど微笑みつつ後目にとどめたもうもあり」の場面で、威厳をもってゆっくりと進みながら、それとわかる女の車には目だけで「君なんだね」僕には解るよと微笑みながら目の端に捉えつつ通り過ぎていく様を確認しました。後目を流し目と訳すものも多くあるそうですが、媚を含んだ眼差しではないそうです。流し目になると長谷川和夫になっちゃって光源氏ではなくなっちゃうんでしょう。(これって芝居で演じる場合、難しい演技を要求されますよね。美男子の後目って、どんなんかしらねぇ。見られた方はゾクッとするわけでしょう?)
――某受講生、仕事の打合せがあるので、と瞬間感想を置いて早退。受講後に行くいつもの割烹店に入ると、そこのカウンターで仕事の打合せ中の某受講生がいた。「車争い」の余韻は夜遅くまで熱くたぎっておりました。
読後瞬間一言感想
- これが有名な車争いなんですね。御禊の行列見物の場所とりに権勢を誇る左大臣家。
そして御息所は高貴な身分ではあったが、源氏の単なる通い所となっている。正妻と
通い所、両家をとりまく供人達の様子や御息所の無念さやみじめだが、ありありと伝
わって来ました。お忍びで出かけて来た筈なのに、大ぴらにされてしまって……。行
列を迎えた御息所と源氏の様子が印象深い。さらぬ顔(さり気ない顔)なれど微笑み
つつ…、というところが好きです。
- 網代車の下簾の隙間の奥から、見られぬと思っていた源氏の馬上の堂々たる姿を見
た御息所と、気づかぬ振りをして通りすぎて行く源氏はお互いに何かのインスピレー
ションを感じていたと思う! でも何か切ない出会いである。
- 恋する人の姿を遠目に垣間見た御息所の切ない心。泣けてくる。「思い切り泣いて
いいんだよ」御息所へ声かけたくなる場面だ。世に喧伝されているステレオタイプの
御息所には決して無い姿だ。
- 人目を忍んで来たのに、左大臣家の供人と車争いになり、深く傷ついた六条御息所。
でも源氏への思いを断つことができない。その切なさを「心弱しや」と語り手に言わ
せた。見物に集まってきた人々の中には、山から下りてきた世捨て人のはずの尼まで
いて「倒れ転びつつ」輝くばかりの源氏の姿をひと目見ようと駆けつけた。そういう
見物人の様子も、実に生き生きと描かれていた。それにしても御息所の切ない恋情に
式部が寄り添っている。式部も恋に身もだえしたことがあるのよね、きっと。でなき
ゃ、こんなにこんなに切ない恋心を切り取って見せるなんてできないス。
- 正に絵物語の文章です。行列の喧騒の中で、源氏への断ち切れない思い、深く
深く沈んでいく御息所の傷ついた心。
映像として、アップで追う源氏の目線と、その下にあふれる見物人たちの様子が実
にリアルです。
- ものも見で帰らむとしたまえど、通り出でむ隙もなきに「事なりぬ」と言えば、さ
すがに、つらき人の御前わたりの待たるるも、心弱しや……。
今日ほど原文のすばらしさを思ったことはない。御息所の気持に添いつつも「毅然
として欲しい……」と希う紫式部の深いため息が聞こえそうである。
- 行列の人々の動き、雅な衣装の色合い、権力の争いをダイナミックに展開させてい
た。
語り手は源氏の美しさを力説する。物語の焦点は六条御息所に。
「ものおぼし乱るるなぐさめにもや」「ことさらやつし」「忍び出で給うがひとだま
ひの奥に追いやられ」「いみじゅうねたまきこと限りなし」と前皇太子の妃そして斎
宮の母であり、雅で高貴な地位にありながら、屈辱を味わう。語り手は六条御息所の
女心の切なさを「心弱しや」と意味深長なことばで表す。
- 車争いの場面には、源氏の大将を見に色々な職業や身分の女性が来ているようです。
ただ一点、詮ないこととは言え、御息所の悲恋が世間の人に知れ渡っていたことが
痛々しかったです。源氏のファッションも見てみたいですが、車争いで北の方の一行
に負けてしまった御息所が印象に残りました。
平成22年3月17日 葵 例会報告・感想文 沈光子
葵の巻 P7~
葵の上が結婚10年にして懐妊。うちとけることのなかった妻が、子を宿して心細気にそして夫を求めているような頼りなげな様子をみせた。そんな妻がいとおしく、そして懐妊という慶事でありまた命掛けの大事に、心おちつかない源氏だった。妻とは冷え切った関係だったのに、改めて出会い直したような不思議な感覚。源氏は自分の内側に、妻に対するいくつかの未知を探索する新鮮さを感じる。どの女にも恨みを買うような軽んじた扱いをしてはいけない、と帝から叱責されていたが、源氏は妻の懐妊により六条の邸へはますます足が遠のいていく。
斎院交代の御禊(みそぎ)の日、左大臣家の女房たちは母君の忠告で、気乗りしない葵の上を連れ出すことに成功した。女主人は祭り見物などには関心を示さない誇り高い女君である。供奉の者に選ばれた夫の妻という晴れの外出にも、やっぱり気乗りしない。(それって体調不良とか誇り高いとかいうよりは性格なんじゃない?)。
盛大な御禊の行列に参列する源氏を一目見んと集まった人々で大混雑した中へ、左大臣邸の車がくりだした。ぎっしり立ち並んでいる牛車が、左大臣家の威光を笠にした供人たちによって立ち退かされていく。源氏を隠れ見て、つれない仕打ちの慰めにせんとする新斎宮の母・六条の御息所の車は、回りの車が蹴散らかされたことであらわにされた。源氏との噂で注目の人になっている彼女は、お忍びで来ているなどと、誰にも知られたくないのだが。さぁいよいよ名場面・車争いへ……。
読後瞬間一言感想
- 左大臣家の車が身分の高そうな女房達の車をお忍びで来たのであろうか、隠しきれな
い趣味のよい後期な身分の人のものであろう車が二つ、パァートっと現れる。これから
有名な車争いが始まる……。期待でドキドキ。
◎ 下加茂神社の御稜の日に車争いが起こった訳が良く解りました。
以前に下加茂神社から御所の通りを歩いたことがあり、ああそうだったのか、と思いま
した。
- 源氏にとっては降って湧いたように起こった懐妊騒ぎに、気分は落ち着かなくなり、
目の前に起こった出来事に頭がいっぱいで、気持の中では気になっているものの、だん
だん御息所のことが遠のいてゆくのは仕方ないことでした。
一方、御代りということで、伊勢の斎宮と加茂神社の斎院に未婚の内親王・女王らが
選ばれるが、選ばれた姫は名誉なの? 神に仕えて独身を通す特別な身分なんて、考え
てしまうけど、嫌だなんて言えないんですよね。現代の皇室の嫁選びみたいな華やかな
儀式など大変なことです。
- 御代かわりの後、父帝からの戒めで「かしてまかりてさぶろう」の日々。一方、左大
臣家の女房は夫・源氏の浮気沙汰にも「怨じきこえをたまわず」いつも端然ととしてい
た妻が「もの心細げ」の様子に、源氏は「あわれと思いきこえたもう」妻の懐妊に惑い
ながら「子はかすがい」源氏は父親になる。物語は展開して桐壷院の計らいで新斎院の
行列が盛大に行われる折、源氏も供奉として加われる。人々の期待や左大臣家の女房た
ちの浮き立つ様子が文面から溢れる。いつの世も人々は浮かれさわぎ大好き。大宮の口
添えで慌しく混雑の中を場所を求めてクライマックスの車争いに展開する。
◎ 「心苦しきさまの御ここち」が懐妊とは!! 「おぼしたる」相手は御息所なんです
ね。
「日たけゆきて」は、朝の早いこの時代ならではすごーく遅い時間。当然の様に横暴な
左大臣家の供の者に対し、口ごはく車に手を触れさせぬ。供の者の毅然とした態度に高
貴な身分が表れています。混雑の状況が目に浮かびます。
- 源氏の姿を一目見ようとする人々の熱狂ぶりが事細かに語られる。次はどうなるのだ
ろうと読者の期待がふくらんでいく展開の速さで、グングンと引きつけられる場面だ。
「源氏物語」のクライマックスの一つとして有名な「車争い」へ向かう文章運びがすば
らしい。
- 10年目にして葵の上が懐妊。つれない妻へ源氏は夫の務めを果たしていたんですね。
正妻へのこの律儀さが痛々しいけど、でも命を懸けた出産を前に心細くなっている妻を
改めて「君って可愛いところがあったんだぁ」といとおしく思う源氏は、優しく情に充
ちた男ね。帝に叱責されなくても、女たちにはそれなりに誠心誠意を尽くして接してい
たんですね。
六条の御息所は精神的なよりどころをどこに求めていたのでしょう。斎宮となった娘
について伊勢へいこうかしらん、などど悶々とするあたり、不運や悲しみ、世間の噂や
屈辱・寂しさ……、そういうものものに静かに耐えていこうする彼女の強さを感じます。
私だって情が深いぶん、化けてとりついてやりたいと思うことシバシバです。
平成22年2月17日 葵 例会報告・感想文 沈光子
御代かわり
「世の中かはりてのち」。冒頭に式部はこのように「葵の巻」を紐解いた。
花宴から2年の歳月が過ぎている。桐壷帝は桐壷院となり、時は朱雀帝の御代である。桐壷帝は弘徽殿の第一王子を朱雀帝とし、春宮を藤壺の子に定めた。源氏は近衛の大将(従三位)に昇進して、後見人に定められた。皇太后となった弘徽殿の実家、右大臣家の権勢はいやまさっている。父帝の退位は源氏を重苦しい気持にさせていた。「よろずものうい」日々に、忍び歩きも遠のきがちだった。
退位した桐壷院に添う藤壷の心中を、読者は想わずにはいられない。帝を裏切った記憶を生涯抱えた退位後の日々が、平穏であるほど、院の心づかいの深さが、禁断の罪への悔いを煮詰めていっただろう。藤壺は全身を貫く圧倒的な懼(おそれ)に押しつぶされそうになりながら、院の愛情を受け止めていただろう。
院の優しさのまえで愚かな女となって、秘密の封印を破ることができたら、どんなにか楽になるだろうか。重荷を突き崩してしまえば……全てが終わる。封印を切った刃先が、自分を新たな奈落へと引き込んで行くことはわかっている。誇り高く生きてきた藤壺には、世間のそして弘徽殿の高笑いが耳の奥深くで屈辱的に響いていることだろう。逡巡してもしかたないのだ。未来なんて頭の中で想起される幻影に過ぎない。そう腹をくくって、秘密を守り通す藤壷。桐壷院との生活に添うことで、大切なものを守らなければなない。
この巻で桐壷帝の弟の妻だった六条の御息所が紹介された。源氏との関係は桐壷院の耳に入るほど世間の噂になっている。だが6歳年上の彼女は煮え切らない源氏に深く傷ついていた。「相手の名誉をよくよく考えてやり、どの女も公平に愛して、恨みを買わないように」と、棚の上に押し上げた弘徽殿のことはおくびにも出さずに諌める帝は、子を思いやる世間の父親と同じ顔をのぞかせる。
朝顔の君が源氏とつかず離れずの関係を維持している様子も紹介された。(式部卿の宮の姫・朝顔の君のことはすっかり忘れています。エッ! そんな姫がいた? )
朝顔の姫は、六条の御息所のうわさから、守るべきものの輪郭をしっかりつかんでいる。そして源氏との恋に悩まされる愚を犯すまいとしていた。源氏の手紙には時に短い返事を書き、それもだんだんと書かぬようになっていき、かといって冷たくあしらうふうでもない。こんな朝顔の姫を源氏はうれしく思う。こういうボクちゃんに都合のいい姫だから、長いこと忘れることもなく恋しいんだよ、と手前勝手なボンボンぶりは相変わらずだ。(こんな源氏じゃ、まだまだナオちゃんに会ってもらえませんなぁ)
受講後瞬間感想
- 大将の君になり、やっと源氏が大人の社会人として生きて行かねばならない環境に入
ってきた様ですね。時に父君に、女性関係で注意されたり、六条の年上の御息所がでて
きたりして、どんな大人になるのが楽しみです。
- 政権交代は今も昔も大変だったのですね。人間関係が複雑なのでもう一度復習します。
登場人物にそれぞれ個性があります。御息所はどうなるのでしょうか。
- 源氏物語は前にも後にも今日のこの部分も一度も読んだことがないので、知識があり
ません。今日の先生の解説で当時の院政がよくわかり、天皇を退いた後の院の様子や、
帝の地位を争う人達の気持がこの文章でよくわかります。
文章のつながりがどういう風になっていくのか、古文苦手の私には難しいが、楽しみに
なってきました。
- 「葵」が始まりました。父親として、源氏にカツを入れる桐壷院も、かつての(源氏
の母親を亡くした頃の)ふがいなさから比べると大人になりましたね。
二年の空白の時間。たった二年なのに紅葉賀も花宴も遠い昔の様。六条御息所の人と
なりが明らかになりました。短い文章の中に現実がたくさん書き込まれていました。
- 主語がくるくる変わり、3D映画を見ているようであるが、深い意味が込められ、厚
みのあるすばらしい文章である。この章の出だしで院の「女の怨み負いそ」という諌め
が、この先の物語を暗示しているのだろうか。
- 物語の進展がめまぐるしい。源氏ものほほんと恋のアバンチュールを楽しんでばかり
はいられない。今回は頭の中がぐるぐると迷走気味。次回までに整理をしておきます。
- 御代かわりがあり、今後の源氏の立場はどうなるのか。葵の巻も面白くなりそう。人
間関係がグチャグチャで……。それにしても当時、帝の妻は多くいても神さまの妻・斎
宮は一人なんですね。
- 葵の巻が始まった。御代がわり後の展開を暗示するような濃い幕開けである。あの花
宴から2年の間に、帝は院となり藤壺との蜜月を堪能しているように見える。だが藤壺
の心中をを読者たちは俯瞰するようにながめている。穏やかな暮らしで睦まじさが増し
ていくほど、藤壺の心のどこかが薄くやせて行く。代わりに黒く膨れていくものがある。
弘徽殿は息子を天皇にして皇太后の地位を得た。ひきかえに帝との夫婦生活をあきらめ
た。帝と睦まじく暮らしているらしい藤壺を傍観することで、源氏は春宮の後見人の地
位を得た。人間は大切な何かを引き換えにして、別の何かを得て生きていくようだ。
この巻で初めて六条の御息所が紹介された。六条あたりをウロチョロしていたのは、実は帝の耳に届くほど深い関係の女の邸が六条にあったからなんですね。ヤッパねぇ、行き当たりばったりチョロチョロする源氏じゃありませんよねぇ。
源氏は22歳。北の方25歳。御息所27歳。女の実家が男の出世を支えている時代に、年上ということが引け目を感じさせるんですかねぇ。相手が源氏だからなんでしょうかねぇ。珠には少しの傷もあってはならない、てな感じが姫君たちの縛りのきつい人生観なんでしょうか?
平成22年1月20日 例会報告と感想文 沈光子・浜岡はるみ
花宴
藤の宴 P-143
1)かの有明の君⇒今までずっと話してきた 2)はかなかりし夢⇒あのはかなかった夢の様な逢瀬の一時 3)ながむ⇒もの思いにふける 4)春宮には⇒春宮に入内するのは 5)卯月⇒四月 6)いとわりなし⇒どうにもならない 7)男⇒源氏の事 女に対して、恋する男 8)尋ねたまはむ⇒もう一度探し求めて行きたい 9)あとはかなし⇒手掛りがない 10)いづれ⇒四、五、六の女君たちのどちらか 11)ことに⇒わざわざ 12)ゆるしたまわぬあたり⇒弘徽殿の女御一族 13)人わるし⇒体裁が悪い 14)思ひわづらふ⇒思い悩む 15)弓の結⇒弓の競技会 16)やがて⇒そのまま 17)ほかの散りなむ⇒古歌【見る人もなき山里の桜花ほかの散りなむ後ぞ咲かまし】 18)御裳着の日⇒女宮の成人式 19)はなばなと⇒派手好み 20)今めかし⇒今風の流行を取り入れて 21)一日⇒先日 22)聞こえ⇒招待した 23)おはせねば⇒来ない 24) くちをしう⇒残念がる 25)ものの栄なし⇒敵方の親分源氏が来ないと色褪せ物足りない 26)たてまつる⇒向かわせる 27)宿⇒屋敷 28)し⇒強調 29)なべての⇒普通の 30)何かは⇒どうして 31)上に奏す⇒帝に見せた 32)したり顔なりや⇒右大臣は得意そうな顔をしているね 33)わざと⇒わざわざ 34)あめるを⇒来たのだから 35)ものす⇒行く 36)かし⇒自己の判断を相手に強く示す 37)女御子⇒源氏の妹 38)し⇒強調 39)なべてのさま⇒全くの他人扱い 40)ひきつくろふ⇒装束を整える 資料P-22 41)いたう暮るる⇒日も落ちて暗くなってから 42)待たれてぞ⇒待ち抜いている |
【イメージ】女君はそこに居る。行きたくもあり、弘徽殿の女御もそこに居る。行きたくもなし。
今までずっと話してきたあの朧月夜の君は、【いとわりなうおぼし乱れ】ています。忘れられないあの夢の様な一夜の逢瀬!四月には彼女を入内させようとしている父右大臣。どうにもならない焦りの中。一方、【男】源氏も尋ねて行きたい相手が、弘徽殿の女御の一族で、しかもどの姫君?四?五?六?思い悩んでいました。そんな【弥生の二十余日】に右大臣邸で、主だった者達を集めて私的な弓の競技会【弓の結】が開かれ、そのまま藤の花の宴に。桜の盛りは過ぎているのに、遅れて咲いた二本の桜は美しく、派手好みの右大臣が、娘達の成人式のために【みがきしつらはれた】新しい【はなばなとものしたまふ】御殿。全てキラキラしています。でも、何かが足りない!そうです源氏です!源氏には宮中で招待した筈なのに?右大臣は、催促の歌を息子の四位の少将に歌を持たせ内裏に居た源氏に遣わします。【わが宿の花しなべての色ならば何かはさらに君を待たまし】自信たっぷりの歌を見た帝が【したり顔なりや】右大臣は得意そうだねと皮肉な笑み。しかし、わざわざ手紙をよこしたのだから【早うものせよかし】と親が子供に言う表現で、お前の妹達も生まれた所だから、【なべてのさまには思ふまじきを】全くの他人とは扱わない。早く行くように勧めます。装束を【ひきつろひたまひ】整えて、【いたう暮るるほどに】日も落ちて暗くなってから、【待たれてぞ】待ちぬいている右大臣邸に現れた源氏の姿は?
P-145
1)桜の唐の綺⇒表が白、裏が蘇芳色の唐織の錦に似た薄絹 2)葡萄染の下襲⇒赤紫色の裾を後に長く引く 源氏物語の色;吉岡幸雄著参照 上が桃色で下が赤紫色 3)うへのきぬ⇒資料P-23 布袴(ほうこ);準正装 私的な儀式に着用 4)あざる⇒くつろぐ 5)おほきみ姿⇒帝の日常着 直衣(平常服)6)いつかれ⇒かしづかれ 7)異なり⇒予想外 8)なかなか⇒かえって 9)ことざまし⇒興ざめ 10)酔ひなやめるさま⇒ひどく酔って気分が悪い 11)もてなす⇒みせかける12)まぎれ⇒それとなく 13)寄りゐ⇒寄りかかって座った 14)つま⇒端 15)上げわたす⇒上に持ち上げ 15)踏歌⇒宮中の年始行事の一つ足を踏み鳴らして歌い舞うこと 16)袖口⇒資料P-27 打出・出衣 御簾の下から袖口を見せる 17)ことさらめき⇒わざわざ 18)まづ⇒自然に |
【イメージ】
右大臣はじめ皆を、焦らせに焦らして登場した源氏は、こともあろうに【あざれたるおほきみ姿】普段着の直衣姿!【皆人はうへのきぬ】準正装の人々の中を、かしずかれて進むその直衣は桜色。そして赤紫色の長く引いた裾。【げにいと異なり】。花の匂いも負けてしまう美しさ。宴の賑やかな時間は過ぎ、夜も少し更けた頃、【いたく酔ひなやめるさまにもてなし】酔ってしまって気分悪そうな振りをして、それとなく寝殿の女君の居る東の戸口に寄りかかる源氏。目の前に見える女達の【ことさらめきもていでたる】わざわざ派手に御簾から出した袖口を、宮中の行事【踏歌】を真似て、図々しく不快【ふさはしからず】と批判し、【まづ藤壺わたり】またまた、自然に藤壺の上品さを思います。
P-147
1)わびにてはべり⇒困っている 2)かしこ⇒慎むべき事 3)御簾を引き着る⇒御簾を頭にかぶっている 4)よからぬ人⇒身分の低い者 5)やむごとなき⇒高貴な人 6)ゆかり⇒縁 7)かこつ⇒口実に頼って 8)重々し⇒落ち着いて堂々としている 9)あて(貴)⇒家柄が良い 10)そらだきもの⇒来客があった時隣の部屋に匂う様なお香 11)衣の音なひ⇒衣裳の衣擦れの音 12)奥まりたるけはひ⇒深みを思わせる奥ゆかしい感じ 13)たちおくれ⇒乏しい 14)さしもあるまじきこと⇒女御子達の前人も多くまずい状況 15)扇を取られて⇒催馬楽・石川【石川の高麗人に帯をとられてからき悔する いかんなるいかんなる帯ぞ花田の帯の中は絶えたるかやるかあやるか、中は絶えたるか】p-99 はなだの帯 16)おほどく⇒おっとりしている 馬鹿っぽい口調 17)いづれならむ⇒(女君は)何処だろう 18)あずさ弓⇒いるに掛かる枕詞 19)まどふ⇒迷う? 20)月のかげ⇒女 21)おしあて⇒当て推量 21)え忍ばぬなるべし⇒堪え切れなかったのだろう 22)いる⇒弓を射る、心に入る |
【イメージ】
いよいよ挑戦開始!
【なやましきに、いといたう強ひられて・・・】飲みたくないのに飲まされてしまって・・・御簾を頭にかぶって、中の女達に声を掛け様子を探ります。気安く声を掛ける様子は落ち着いてはいないが、若くもない様子。周りに漂う【そらだきもの】も衣擦れの音も奥ゆかしさには程遠い。兎に角、派手!次に【うちおどけたる声】馬鹿っぽい口調で催馬楽・石川の歌を引いて、帯を扇に変えて試みる。最初の女は【あやしくも、さまかへける高麗人かな】と外れ!(この歌はP-99で頭の中将が帯を源氏に返した時も使われた歌です)そんな中、ため息が漏れてきた几帳がありました!思わずその女の手をとらえ【あづさ弓いるさの山に・・・】月が入る方角の山で迷ってしまいました。ちらりと見えた貴女の姿をみたまま。どうして?と当て推量で言いました。その言葉に堪えられなかった女は【心いるかたならませばゆみはりの・・・】私の事を心に深く掛けているならば、月の無い暗闇の夜でも迷う事はないのに、薄情だからですよ。と言う声が返って来ました!!ただそれだけ。【いとうれしきものから】ああうれしい!
【まとめ】
花の宴が【いとうれしきものから】で終わりました。
三島由紀夫が愛したというこの巻は華やかでしたが、紅葉賀の巻程、奥深い心の動きはありませんでした。
あの朧夜に女が返した
【うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ】
・貴方が本気ならば、不幸な私が名乗らずにそのまま死んでしまっても私の墓を探しに会いに来てくれるでしょう?
と、今回の【心いるかたならませばゆみはりの月なき空にまよはましやは】
・私の事を心に深く掛けているならば、月の無い暗闇の夜でも迷う事はないのに、薄情だからですよ。
歌った人は結構強気というか、奥ゆかしさはないですね。右大臣の娘だから仕方ない?
でも、源氏は【いとうれしきものから】なのです。
香田さんが、しばらくお休みします。いつもの旅には参加されますのでご安心下さい。
この巻の終わり方について先生から下記の資料を頂きました。
- 朝日新聞 2009年10月30日 【光源氏に別の顔】「大沢本」に新記述
【かろかろしとてやみにけるとや】軽薄な女性だと判断してそれ以上は動こうとはしなかった
この部分が線を引いて消されていた。
2)大江広道( ~ )
かの扇を取りかへたまひし人と聞きつけたまひて、いとうれしきものから さすがにあたりあたりの人目もあ
り、心知らぬ右大臣家にけふ初めて入りたまふなどの事もあれば、憚(はばか)りたまひて、ただにもえ逢ひ
たまはぬくちをしさなど、千万(ちよろづ)の思ひを含め残してそえられた筆つき、例のめでたしともめでた
き文なり。
- 藤原俊成(1114~1294)平安後期~鎌倉時代の歌人・歌学者
六百番歌合の判の詞に「紫式部は歌よみのほどよりも物書く筆は殊勝の上、花宴はまことに優艶な巻であり、
ことに最後の結句の余韻た嫋々(じょうじょう:余韻)たる趣は朧々(おぼろおぼろ:ぼうっとかすんで)と
して幽玄の趣をたたえる。
【瞬間感想文】
1)いやー、「ものから」という花宴の終わり方には驚きました。作者が男性だったら、まず、こんな思わせぶりな終わり方は出来ないでしょうね。式部に脱帽です。
2)今日は源氏の御直衣が、心を揺さぶりました。源氏なりの有職故事の衣装の整え方、少し外れている処が魅力的です。型にはまった人間でない処が、一番のポイント。
当時は冠位十二階色で身分の分る時代、源氏は自分で衣装を選んだのでしょうか?
もしそうならば、素晴らしい色彩感尚素晴らしい!
3)紅葉賀~花宴も終わりに、
平安貴族の雅な生活を四季折々の背景にして源氏の姿、心情にイメージを膨らませながら、2008年10月から読み進み、次の巻へと流れる様に物語の展開。
ひたすら藤壺に想いを募らせながらも、花宴の朧月夜に出会った姫君にも心ときめきながら、弥生の日右大臣での藤宴へ源氏はおもむろに「待たれてぞわたりたまふ」
帝、左・右大臣のそれぞれの思惑も、夜更け、酒の酔いにかこつけて、姫君の居所へ。さすが恋の達人。歌のやり取りで姫君と邂逅「いとうれしきものから」余韻を残して!
4)源氏の登場で、華やかな宴も花の美しさも負かしてしまう程高貴で品のある姿に、催しもちょっと色褪せた感じだが、源氏には違う目的があり、言い方は悪いが、狙った獲物は何とかして探し出すところがすごい!恋に対する執念みたい。
5)何時も大和絵の世界に入って行く様な気持ちです。源氏の花宴のファッションは、藤の花をバックに美しいですね。寝殿に迷い込んだ源氏は、私達に右大臣家の女性達の世界を観せてくれました。
6)右大臣家のパーティーの待ちわびた人々の前に、沢山の従者にかしずかれて登場する源氏の姿が鮮やかだ。センスの良い色合いの衣裳を、少しだけ崩して着こなすお洒落ぶり。
やはりスターですね。意識して出来る事では無い。存在が花だ。
7)帝に促されるように右大臣家へ行く源氏は、自分では意識してはいないものの、右大臣に敬意を払う事の無い、普段着で行く。従者にかしずかれ、スポットライトを浴びた様に現れる源氏の姿の美しさ。
帝に、愛され大切にされる源氏の今を時めく姿が目に浮かぶ。
8)すっかり暗くなった右大臣邸、灯りの中に浮かぶ従者にかしずかれた普段着の、なまめきたる源氏の姿!!
けばけばしい、品の無い流行物好きの右大臣邸の雰囲気が、これでもか、これでもか、と書かれていました。何時も比較されるのは藤壺。
「ただそれなり。いとうれしきものから。」こんな終わり方ってあるの? 花宴はかくして終りました。
平成19年以前の報告は[こちらから]
平成20年から平成21年までの報告は[こちらから]
TOP ページ
index付きTOPページ