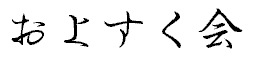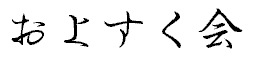

およすく会 紹介
平成14年の4月にスタートしたこの会の名称は、桐壷の巻の【きよらにおよすけたまへれば】から。
古語では「おゆ(老ゆ)=成長する」と、「源氏物語」から教わりました。ネガティヴな面だけで使われる現代語の「老いる」の本来の意味に立ち戻り、私達の会も成長して行こう!と、原文の古語に事寄せました。
ことほど左様に、現代語には失われてしまった日本語の深い味わい、美しさを「源氏物語」の原文に求め、読み込んで、10年経とうとしています。
「源氏物語」の味わい深く、豊かで奥深い世界を読み飛ばしてはもったいなく、じっくり細部にこだわった読みで、10年間で「葵」の巻まで来ました。歩みは遅いかもしれませんが、深い読み方には拘り続けたいと思います。
【蓬生】までは行こう!を合言葉に、毎月一回(主に文京シビック5階会議室で)2時から5時まで、みっちり読み進んでいます。
10年間の実績
・勉強会の記録作成:その時々の登場人物達の様々な心模様や、心を動かされた場面を書き留めて来ました。
・勉強会終了後の一言感想:各人が直後の素直な感想を、その日学んだことからその場で書き下しています。
・源氏物語に関わる場所への旅:京都市内、鞍馬山、比叡山、石山寺、明石、宇治等々へ、計7回行きました。
・夏季合宿:蓼科で、朝から夕方まで【桐壷】【帚木】の再勉強会を計2回強行(?)しました。
・長恨歌を読む:【桐壷】、【葵】の巻への関連と漢詩の素晴らしさを知りました。
・そして、勉強会後のお疲れ様会は、最大の盛り上がりです。
各方面の優れ者(酒飲みも含め)が揃った結果、上の様な事が実現できました。
「およすく会」は既成の型にはめ込まれない、自由な開かれた会です。
私達は、原文でしか味わえないこの「源氏物語」の素晴らしい世界を、自分たち以外の人たちとも語りあってみたいと思っています。現代訳では何か物足りない、原文を一度は読んでみたい、と思っていらっしゃる方の参加をいつでも歓迎しております。
連絡先 09039130841
原文からひろがる源氏物語
澪標
10月澪標受講雑感
源氏は多くの願が叶えられて住吉にお礼参りをする。世間は大騒ぎをして上達部・殿上人たちが我も我もとお供した。そんな折も折、明石の君が姫君出産で例年の参詣を怠ったお詫びをかねて舟で参詣に来あわせた。立派な参詣の行列に「誰がご参詣なさるのですか」と質問したらしい下僕に答えて、「内大臣殿が御願ほどきに参詣なさるのを知らない人が」いると得意げに笑われてしまう。明石は傷つき源氏の参詣を遥かに見ることになってしまったのは彼との身分差ゆえと、遥かに劣る我が身をみじめに思う。明石滞在中に見知った人々が華やかに晴れやかに、何の憂いもなさそうにあちこちに参内の列に連なって、馬や鞍にまで飾りを整え磨き上げて見ごたえがあった。田舎では考えられないない華麗な行列に目を見張らずにはいられない。
絵巻に残されている住吉詣での行列を講義中に回し見たが、式部の筆よりかなり地味にみえた。華麗な行列を式部は筆を尽くして読者の想像力を刺激し届けている。
須磨滞在中に見た源氏のお供たちのこの日のあでやかさ。蟄居した源氏についてきたお供たちの出世を目の当たりにした驚き。しかし「姫君を出産した身ならば、どれほどの出世が待っている…」という期待は彼女には微塵もなくて、ただただ我が身を恥じてただただみじめだった。「もしかして♪もしかして私も出世の階段上る~♪」なんて脳天気な期待をしない。この時代の身分格差の厳しさ故でしょうかね。
官位相当表によって源氏が上り詰めた太政官は太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣の上位であることや、須磨から返り咲いた共人たちの官位などを確認。父帝の親心から皇位争いから外された源氏は、しかし臣下として最高位についたことになる。天皇になってしかるべきだという思いがある源氏は溜飲を下げただろうか。就職先が朝廷しかない時代ですから、官位が上がるということは大変なことらしい。
源氏の官位についての記述、ネット検索で下記フィットしましたので貼り付けました。
「光源氏は、天皇の子であるが、臣籍に落とされたために、「源氏姓」を名乗った。彼の位階の昇進状態を見てみると、十七歳にして既に「近衛中将(従四位下)」になっているが、これは桐壺帝の息がかかあっているからである。以下、次の通りに進んでいく。
「宰相中将」→「近衛大将(従三位)」→「権大納言(正三位)」→「内大臣(従二位)」→「太政大臣(従一位)」?「準太上天皇」
呆れるほどの出世の速さであるが、須磨に流れた時には一切の官位を剥奪(はくだつ)されているが、明石から帰るや、即「権大納言」になっている。このような光源氏の呆れるほどの出世は彼自身の実力であるともに、秘密の子・冷泉帝の息がかかったものでもある。
最後の「準太上天皇」は官位ではなく、名誉職で、おまけ。
2022/11/2
【五十日(いか)の祝い】 P 50~56
京へ戻った源氏29歳の春、明石から女児誕生の吉報がもたらされたのは3月16日。児の五十日の祝いが五月五日になると密かに心待ちしていた源氏。
「帝の父となる、親子3人、帝、后、必ず並びてうまれたもうべし。なかの劣りは太政大臣にて位を極るべし」この予言は現実味をもって源氏を鼓舞する。「明石の君の生んだ姫によって運が拓ける」…必ず拓けるという確信。明石に置いておくわけにいかないと思う。貴族たちによる地方蔑視の考えは、源氏とてその例にもれず、京の都以外の地を蔑視し、田舎暮しは決定的な負い目だ。一刻も早く姫宮を京へ呼び寄せたい。
五十日(いか)の祝いの使いが明石に遣わされ心憎いばかりの祝いが届けられると、入道は感激のあま生きていた甲斐もあったと身を震わせて泣きべそをかく。その喜びようは語り手に「もっともなことだ」とやゆされるほどであった。若紫を見初めた北山でうわさに上がった偏屈な入道は、今や源氏に魅了され骨抜きにされている。都から遣わされた乳母にさえ怠りなく気遣いを見せる源氏の「人たらし」は本領発揮である。
受講者から「源氏物語の世界は常に複層的に語られている」ように感じられるという感想があった。
物語は常に重なり合う複数の事々を含みながら読者に深層を想像させ膨らませる展開をくりかえし
てきた。明石で謹慎することになったのは帝の寵姫・朧月夜との密会を表沙汰にできない弘徽殿が
朝顔を口実に追いやったからであるが…源氏は朝顔との関係を「何事も濁りなき心」を強調して濡れ
ぎぬと胸をはった。藤壺とのことがあからさまにならなければ、朧月夜のことだって…自分の罪は天
皇の外戚に迫害の口実を与えてしまったからだとうそぶくことができた。
「誰のために苦労をしてきたのだ」という自己弁護は、紫の上だけでなく読者をシラケさせた。琴の
引き合わせに誘って紫の上の気持ちを更にさかなでしたが「われはわれ」と開き直る自我をみせた紫
の上は大人の女への成長を見せている。
悟られてはならない源氏の深層は語られることなく読者の創造にゆだねられ、物語は幾重にも補完
されて重層的な世界を織り上げていく。複層的に語りつつも語られない世界は重く黒々と拡げられ作
者の筆は読者の深い読みにゆだねつつ展開されていく。
(参照―源氏物語 物語空間を読む 三田村雅子著)
読後一言感想
・紫の上の味わう失望は昔も今も変わらないものと、しみじみ思います。硬く重く冷たい石つぶてのように、心の奥に沈んでいくのでしょうね。
それでも信じたいし愛はある! 読んでいて切なさが先に立ってしまうのは単純過ぎますかね。
・これだけの登場人物がいて、同じキャラクターがほとんどないという人間観察力と想像力、及び表現力!
やはり、紫式部は凄い。その観察力はメインの人間ばかりでは無く、脇役まで及ぶ。今回は乳母の複雑な心境を描き、光源氏を通して乳母への配慮を見せる。
当時の明石はかなりの田舎だったのだろう。貴族に仕える身としては、都の方が良いに決まっている。だが、源氏からの行き届いた賜物の素晴らしさに感じ入り、心も揺れる。それに、こんなに身近に源氏に仕えることもあるまい。どんな田舎でも付いていっちゃうよね、、、
ありとあらゆる階層、キャラクターを描き分けているので、読者の共感を呼ぶ人物が必ず登場する。そんなところも1000年のベストセラーの所以だろうか。
・何度読み返してみても源氏の女君の態度についての感じ方は不愉快です。この不愉快さは言語化できない。
・入道の腑抜けぶりは娘を思う親心ゆえ。桐壺帝が源氏を臣下にしたのも弘徽殿が朱雀帝を守るために源氏を排斥したのも親心…、古今東西、児に勝てる親はいない。
2022年7月6日受講
【乳母、明石へ】 ?【もの怨じ】P38~47
入道は、乳母の到着を喜び、源氏の居る京の方向に向かって拝み、産まれた児を大切にしようと。児は不吉な程まで可愛らしいく他と比べ様がなく、乳母は、京からこの辺鄙な所に来てしまい、夢でも見ている様な嘆きもその児を見て冷め、とても可愛くいたわしく思い扱いました。子持ちの君(明石の君)も、源氏が去ってから何か月も物思いに沈んでいて、生きたいという気持ちもなくなっていたのに、この源氏の取り計らいで少し物思いを慰められ、床から起きて、使いの者にも最高級の贈り物をし、すぐに京に帰りたいと迷惑そうにしている使者に源氏への歌を託します。
私一人で子供を育てるのは力不足ですから貴方様の大きな庇護をお待ちしています
源氏は不思議な位子供が気にかかり、早く会いたいと思います。
紫の上に明石の君の事を少しも口に出していないのを、外から彼女の耳に入る事もあるかもしれないと源氏は、「明石で女児が誕生したそうだ。変にうまくゆかないものだな。そうなって欲しいと思っている所は待たされるばかりで、意外な所で産まれたのは残念な事だ。女の子なので、本当につまらない話だ。ほっておいてもかまわない事だけれど、無下に見棄てる訳にもいくまいと思っている。呼びにやって貴女にお見せしよう。嫉妬するなよ」と言うと、紫の上は顔を上気させ、「嫌な事、いつもこの様な嫉妬の話を貴方様にさせてしまう自分の心こそ我ながら嫌になります。人を嫉妬する事は何時教わったんでしょうね」と源氏を恨むと、源氏はにこにこ笑い「そうそう、誰が教えているんだろうね。思いも掛けない事を言いますね。私の考えもしない事を勝手に想像して恨み言等言う。そんな貴女を思うと悲しい」と言って最後には涙ぐみました。二人が離れ離れで暮らした年月の間、いつも相手が恋しいと思った色々な心の内を、折に触れた手紙で交し合った事を思い出すと、この度起こった全ての事は源氏の当座の気まぐれに過ぎないと、紫の上は嫉妬の気持ちを打ち消しました。「この人(明石の君)をこうまで心に掛けるのは、やはり考えるところがあるからなのです。貴女に時期早々に話せば、又誤解するでしょうから」と言いかけて、「相手の人柄が魅力的だったのも明石と言う場所柄のせいか、目新しく感じたのでしょう」等と。しみじみと心を動かされた夕方の塩を焼く煙、明石の君の話した事等、はっきりとではないけれどその夜の明石の君の顔をちらっと見た事、琴の音の優美で美しかった事も、源氏が全て自分の心に刻まれて感じた様子を話し出した事につけても、紫の上は、自分は留守の間この上なく悲しいと嘆く日々を送っていたのに、一時の慰みとはいえ他の女と心を分けていたのだと、たまらなく心を乱し続けて、【われはわれ】「私は私」と顔を背けて、「昔は心の通い合う二人の仲だったのに変わってしまいました」と、独り言の様に嘆き、
愛し合う二人の共になびく方角でなくても 煙に先立って死んでしまいたいのは私の方です
読後一言感想
・ 明石の君は、源氏が去った後に児を産み、鬱状態に苦しんだ。しかし、母として変貌する。
作者は、【子持ちの君】として成長した明石の君を描く。
翻って源氏は、紫の上へ児の誕生を明かしつつ、心なくも男の身勝手を顕わにする。
人間への鋭い作者の筆には容赦が無い。
・ 【子持ちの君】、【面うちあかみ】、【いとよくうち笑み】、【われはわれ】等重さのあるキイワードとなる表現の多い所でした。人の、特に女性の心が掘り下げられていて、心が痛みました。
- この【見せたてまつらむ。憎みたまふなよ】源氏の姫君誕生の告白する時の配慮の無さ、いや無神経に驚
きました。不信感や怒り、嫉妬心を内に秘め必死に心を保とうとする紫の上。【われはわれ】は読んでいて
あまりにも切なく哀しい。【年ごろ飽かず恋し】から大人の女性の苦悩が始まるのですね。ここは二人(紫
の上と明石の君)のターニングポイントになるのでは?
- 子供を産めない自分に、子供の母親との日々を隠すことなく喋る源氏。紫の上の嘆きは深く、死んでしま
いたいと詠い、明石の君は、母になり、源氏への庇護を望む歌を詠う。年齢も近い二人を【若紫】の巻から
比べて描いてきた式部の物語の作り方に、又感心してしまいました。
2022年6月1日受講
【若やかななる乳母】から【乳母、明石へ】 P28~37
源氏は、急いで乳母として明石に行く女を探し、母親が故院に仕えていた宣旨(帝の言葉を伝える役の女官)で、父親が宮内卿の宰相で亡くなり、今や母も亡くなり、当てにならない男との間で子供を産んだ女の噂を耳にします。まだ若く、何も考えず、ひっそりとしたあばら家でぼんやり過ごしていた心細さから、女は深くも考えず、源氏からの依頼を素晴らしい事と承諾しました。源氏は、何も知らない女を一方では大層不憫に思いながら明石へ出立させる事に。出立当日、極秘の内に源氏は女の家を訪ねました。承諾の返事をしたものの、思い乱れていた女は、源氏の訪問に大層恐縮し、色々な気持ちを治めて「仰せの様に致します」と。陰陽師に占わせた旅立ちには良い日だったので、出立を急がせて「心配りも無い様な頼みだけれど、特別に訳がある事なのです。思いがけない場所の生活に気が滅入った私の体験を思い出してもらって、しばらく我慢して下さい」等、源氏は諸事情を詳しく話しました。女は、昔見かけた時よりすっかりやつれていて、大きな屋敷もひどく荒れ、手入れされない木々等が薄気味悪く、こんな所でどうやって暮らしていたのかと眺めました。それでも若々しく美しい女に、源氏は目を離す事が出来ず、軽口をたたいて、「明石へやらないで自分の所に来させたいと思うけれど。どうですか」と言うと、女は、本当に同じ事ならおそば近くでお仕え出来たら自分の辛い身も慰められるだろうと、源氏を見つめました。
「以前から親しくしていた仲にはならなかったけれど 貴女との別れは失うに忍びない
貴女を追って行きたい」と源氏が詠うと、女はにっこりして
「突然の別れを惜しむ事を言い訳にして 恋しいお方に慕って行きたいのではないですか」
と歌をすぐに返せるのは見事だと源氏は思いました。
京を離れる迄は車で、信頼のおける家来を共に添えて、この事を決して他言しない様に、固く約束させて遣わし、御佩刀(みはかし)守り刀、必要な物等思いつかない物が無い程持たせ、乳母にも、細やかな心遣いを十分しました。入道が産まれた女の子を大切にいつくしむ様子を想像し微笑み、明石の君への手紙にも、産まれた子供をいい加減に扱ってはいけないと何度も繰り返し注意し、
「一日でも早く私も袖を掛けてみたいものだ 天女が長い年月羽衣の袖で撫でる娘の行く末を祝って」と。
※拾遺集;【君が代は天の羽衣まれに来て撫づとも尽きぬ巌ならなむ】
津の国(摂津の国);今の大阪と兵庫の一部迄は船で、それより向こうは馬で、急いで明石に着きました
読後一言感想
・ 源氏の娘への思いは深い。末は后になる娘である。乳母をあらゆる伝を使って選び抜き、託すに足る確か
な手応えも得た。秘密を内に、急いで明石へ乳母を送る源氏の政治力が発揮される。乳母は源氏の面接に満点合格。口別嬪の源氏を満足させる返歌に、彼女の教養と育ちの良さが表れていた。
(昔の人はスゴイ。昭和生まれの庶民で良かった!)
・ 将来后なると予言された娘の為に源氏は最高の乳母を選びます。
入内させたいと思う親達も娘の誕生と共に英才教育がスタートするのですね。
乳母は親を亡くした後は【かすかなる世に経ける】。ふと六条御息所を思い出しました。未亡人になった後、後ろ盾の人はいたのでしょうか。源氏との辛く哀しく苦悩の恋に目が行きますが、残された六条院の広大な屋敷と娘(斎宮)をしっかり守り、維持していることに、御息所の知性と管理能力の凄さを感じました。
・ この時代の、女の子が産まれるという事がいかに重大な事であり、その後の自らの道がどの様に拓かれて
いくのかが懸かってくる事。源氏にとっては大変な事だったのですね。その女の子の乳母となる女性があり、母として生きる事になる女性があり、女性は駒として生きていく、ちょっと切ない気がします。
・ 源氏が急いで選んだ乳母は、送った歌にすぐに答えられる才能ある【いたしとおぼす】女性でした。
山ほどの荷物と、車、船、馬を使って急がせながら、源氏は、あの入道の孫娘を得た喜びを想像して微笑み、
明石の君には、娘を決しておろかにもてなしてはいけないと戒めます。
源氏にとって女の子の誕生が如何に重要であったかが良く分かる場面でした。
澪標
【女子誕生を占う】 P23~28
源氏は、忘れる事が無かったあの明石の娘の子供がどうなったか、三月初めの頃に産まれるのではないかと、公使の忙しい合間をぬって密かに京から明石に使者を立たせました。帰った使者は、「二月十六日に、女の子が何事も無く無事に産まれました」と告げ、自分にとって初めての女の子でもあったので喜びはひとしおです。どうして、あのような田舎でなく、京に迎えてお産をさせなかったのかと残念に思いました。
宿曜(星の運行等で人の運勢を占う人相見)が自分を、「子供は三人、帝と后になる者が必ず二人揃って生まれ、三人の中の劣った者は、太政大臣になりその地位を極める」と予言した事が、今その様に一つ一つ的中しています。優れた人相見の多くは、源氏が一番上の位に昇り、世を治める相であると口を揃えて告げていて、長い間世間の情勢の変化をはばかって全て諦めていたのを、自分と藤壺の息子が帝に即位した事で、願いが叶ったと嬉しく思います。父桐壷帝は、多くの子供達の中で、自分を特別に可愛がってくれたけれど、あくまでも臣下の身分と決めていたその判断を思うと、自分の運命は帝位とは遠い巡り合わせであり、今の帝がこの様に即位した真相を誰も知らないけれど、人相見の言った事は間違ってはいなかったと、心の中で思いました。今、将来の願い事を考えると、住吉神社の神様のお導きは、本当に明石の君も偏屈者の父親もそのお陰で途方もない野望を抱けたのではないか、そういう事ならば、畏れ多い后の位にもつくべき人が辺鄙な田舎で産まれてしまったのは、気の毒で畏れ多くもあるので、しばらく日を置いてから京へ迎えよう、と思い、自分の住む東の院を急いで改築する様に命令しました。
2022年5月
【女子誕生を占う】 P23~28
源氏は、忘れる事が無かったあの明石の娘の子供がどうなったか、三月初めの頃に産まれるのではないかと、公使の忙しい合間をぬって密かに京から明石に使者を立たせました。帰った使者は、「二月十六日に、女の子が何事も無く無事に産まれました」と告げ、自分にとって初めての女の子でもあったので喜びはひとしおです。どうして、あのような田舎でなく、京に迎えてお産をさせなかったのかと残念に思いました。
宿曜(星の運行等で人の運勢を占う人相見)が自分を、「子供は三人、帝と后になる者が必ず二人揃って生まれ、三人の中の劣った者は、太政大臣になりその地位を極める」と予言した事が、今その様に一つ一つ的中しています。優れた人相見の多くは、源氏が一番上の位に昇り、世を治める相であると口を揃えて告げていて、長い間世間の情勢の変化をはばかって全て諦めていたのを、自分と藤壺の息子が帝に即位した事で、願いが叶ったと嬉しく思います。父桐壷帝は、多くの子供達の中で、自分を特別に可愛がってくれたけれど、あくまでも臣下の身分と決めていたその判断を思うと、自分の運命は帝位とは遠い巡り合わせであり、今の帝がこの様に即位した真相を誰も知らないけれど、人相見の言った事は間違ってはいなかったと、心の中で思いました。今、将来の願い事を考えると、住吉神社の神様のお導きは、本当に明石の君も偏屈者の父親もそのお陰で途方もない野望を抱けたのではないか、そういう事ならば、畏れ多い后の位にもつくべき人が辺鄙な田舎で産まれてしまったのは、気の毒で畏れ多くもあるので、しばらく日を置いてから京へ迎えよう、と思い、自分の住む東の院を急いで改築する様に命令しました。
読後一言感想
・ 女児誕生を知った源氏は、昔三人の顔相見達の予想を思い出した。
父帝が源氏を臣下にした意味の深さ、自分の運命の行く先の目標が明らかになっていく。
源氏は自分の歩み先を、この【澪標】巻ではっきりと見据える。
現代小説に通じる内面の掘り下げが面白い。
・ 源氏が生まれてこの方心の内にあった父への思いが今、少しほぐれたのでしょうか。
自分の宿世を深く思いやり、これからに向けて進み始めた源氏。
宿世という言葉が深い。
・ 宿曜による御子三人のお告げには驚きました。
源氏自身は、帝に就く事は無かったが、子供達がそれぞれ頂点を極める事で、黒幕として国の権力を掌握す
る事が可能?
【宿世遠かりけり】の思いを抱きながら、これから大人としての源氏の活躍を予感しました。
・ 自分と藤壺の子供が帝になり、明石の娘に女の子が誕生した事で、人相見達の予言が現実的になっています。桐壷帝の自分への扱いが納得出来ず、ずっと心の中でくすぶり続けていた世界が変わりました。父の考えは正しかったと今やっと理解出来ました。明石で誕生した女の子は后になる可能性があり、全ては住吉の神のご加護。しまった、あの明石の様な辺鄙な田舎で産まれてはいけない女の子だった!
物語が大きく転回し始めました!
読後一言感想
・ 女児誕生を知った源氏は、昔三人の顔相見達の予想を思い出した。
父帝が源氏を臣下にした意味の深さ、自分の運命の行く先の目標が明らかになっていく。
源氏は自分の歩み先を、この【澪標】巻ではっきりと見据える。
現代小説に通じる内面の掘り下げが面白い。
・ 源氏が生まれてこの方心の内にあった父への思いが今、少しほぐれたのでしょうか。
自分の宿世を深く思いやり、これからに向けて進み始めた源氏。
宿世という言葉が深い。
・ 宿曜による御子三人のお告げには驚きました。
源氏自身は、帝に就く事は無かったが、子供達がそれぞれ頂点を極める事で、黒幕として国の権力を掌握す
る事が可能?
【宿世遠かりけり】の思いを抱きながら、これから大人としての源氏の活躍を予感しました。
・ 自分と藤壺の子供が帝になり、明石の娘に女の子が誕生した事で、人相見達の予言が現実的になっています。桐壷帝の自分への扱いが納得出来ず、ずっと心の中でくすぶり続けていた世界が変わりました。父の考えは正しかったと今やっと理解出来ました。明石で誕生した女の子は后になる可能性があり、全ては住吉の神のご加護。しまった、あの明石の様な辺鄙な田舎で産まれてはいけない女の子だった!
物語が大きく転回し始めました!
2022年4月6日
【政権復活】 P14~22
帰還した翌年の二月に、十一歳になった春宮の元服の儀式があり、源氏とそっくりの美しさに世間の人は称賛しますが、母宮(藤壺)は、はらはら気をもむのでした。同じ月の二十日過ぎに、帝の譲位の儀式があり、大后(弘徽殿の女御)は相談も無かったので驚き度を失いましたが、帝は「帝を退き不甲斐ない身だけれどこれからはいつでもお会い出来ます」と母親を慰めました。皇太子には、承香殿(右大臣の娘で朱雀帝の女御)の息子がなり、世の中が刷新され、執政に当たっていた人々も入れ替わり、色々明るく華やかな事が多く、源氏の大納言は、帝の外戚として内大臣になりました。そのまま源氏が天皇に代わって政治を行うべきでしたが、「そのような多忙な仕事に自分は堪えられない」と、致仕の大臣(隠居した左大臣)が摂政職をする様位を譲りましたが、「病気で左大臣の位をお返ししていたのに、増々年寄りになって、立派な仕事は出来ない」と引き受けませんでした。他国(中国)の例を出して説得した結果、朝廷の会議と個人の意見もあり、左大臣は断り切れず太政大臣に。歳も六十三歳になり、右大臣の前政権が面白くない世の中だったので、元の位に就任して華やかさを取り戻すと、世の中に採用されず不遇を託っていた子供等も皆一斉に出世し活躍の場を得ました。中でも、宰相の中将(元の頭中将)は権中納言になり、十二歳になったあの四の君(右大臣の娘の)の娘を入内させたいと大切に育てていて、あの高砂歌ひし君(【賢木】P190で源氏の演奏に合わせて催馬楽「高砂」を歌った頭中将の次男)も元服させ、思い通りに育っています。奥方達に子供達が次々に生まれ、賑やかで繁栄を誇っているのを、源氏は羨ましがっていました。
大殿腹の若君(葵の息子)は特別可愛く、帝や春宮に仕える殿上童になり、葵が亡くなってしまった事を、葵の母との父は改めて嘆きます。けれども、娘が居なくなった後も、左大臣家は源氏の威光で、長い間不遇に甘んじていた事が嘘の様に栄えました。源氏の気持ちは元と変わらず、その時々につけて訪問しながら、若君の乳母達やその他の女房達も、辞めないで仕えられる様配慮したので、幸せな人が多くなった様です。
二条院でも、同じ様に源氏の帰京を待っていた女房を愛おしいと、自分が不在の長い間の悲しみが【胸あくばかり】晴れる様にと、中将、中務の様な親しい女房達には、身分に応じながら逢瀬の時を設けたので、他の女の所へ通う事もしませんでした。源氏は、故院の遺産で受け継いだ二条院の東の御殿を見違える程素晴らしく改築させ、花散里などの生活が困窮している人達を住まわせようという心づもりで修繕させました。
読後一言感想
・ 藤壺の心の闇は深い。
源氏には、幼い自分を占った輝かしい未来像に支えられている自信がありそうだ。
失脚し、落ちた自分を裏切る事の無かった人々へ、恩返しをしていく等、格好良い源氏が細やかに描かれていた。こういう所、人たらしですよね。
・ やっぱり源氏はマメでした。昔、馴染みのあった女房、女君等にも目を掛け、心遣いを忘れなかった。
これから源氏の第2ラウンド、華やかな御世が始まるのね。
・ 明石から戻ってからの源氏の政治力の骨太さが見える部分でした。
それにも係わらず、自分に縁のある人々に温かい心遣いをするきめ細かさ、広いスケールの人ですね。
・ 朱雀帝が退位し、東宮が即位します。
東宮と源氏の容貌は瓜二つ。母宮は「かたはらいたきこと」と複雑な思いを吐露していますが、源氏の心境は描かれていません。父院への最大の裏切りであり最大の秘密の東宮が天皇に。
源氏は政治手腕を発揮し即位の準備をしていますが、心の奥底にはどんな思いがあるのでしょうか。
・ 【葵】の巻の最後に涙で別れたあの女房達が、【幸ひ人】になって嬉しく思いました。
左大臣家の勢いが戻って来た中で、大后(弘徽殿の女御)の絶望的な叫びが聞こえました。
【須磨】、【明石】の時間の流れの中で、多くを学んだ源氏は随分大人になり、偉くなりました。
2022年1月5日受講
【譲位の涙】 P6~14
須磨で夢に見た桐壷院の事【明石】の巻P-26 をずっと気にかけていた源氏は、都に帰って来たので、【明石】の巻の終わりから準備していた御八講を十月に行い、一度は離れて行った世間の人は昔の様に源氏を支持しました。御八講は、盛大な法会の挙行を通して一族の結束を確認する(特に一族の祖の追善供養)と共に、世間に主催者の権勢を誇示するもので、本来は帝か大后が主催する追善供養を源氏が行った事で、大后(弘徽殿の女御)は、病気が重い身で、結局源氏を消してしまう事が出来なかった【つひにこの人をえ消たずなりなむ】と、悔しく、苦々しく思いましたが、帝は、桐壷院の遺言と罪の報復を恐れ、(母親の意見を聞かず)源氏を都に召還し、元の地位に就け、爽やかな気分になり、悪かった目も治ってきているけれど、心細い事ばかりで、帝の地位も長くないと、源氏をいつも召して、国の政治の事などにも意見を言わせました。世間の人々も、帝と源氏の仲が戻ったと喜びました。
帝が退位しようと思う時が近くなり、尚侍(朧月夜)が心細そうに、この先どうなるのか不安を募らせているのを帝は不憫だと、「右大臣(祖父)が亡くなり、大宮(弘徽殿の女御、母)も病気が重く、私の命も残り少ない気がする今、世の中の何もかもが変わってしまって貴女が残されてしまうのは気の毒です。昔から貴女は、人(源氏)より私を軽く見ているけれど、愛情の比べようもない深さで、ただ貴女の事だけを愛おしく思っています。自分にはとても及ばない人(源氏)が、又貴女へよりを戻して逢瀬を重ねていくようになっても、貴女を想う並々でない愛情だけは比べ物にならないと思う自分が辛い」と、帝は泣き、それを聞いた女君(朧月夜)は、上気して赤くなり、溢れるばかりの愛らしさで泣きます。その姿を見て、帝は、源氏と密会した等の色々な罪を忘れ、愛おしいく可愛いと見ます。「どうして御子だけでも産んでくれなかったのか残念でならない。宿縁深い人(源氏)のためには、近い内に子供を産むだろうと思うのも悔しく無念です。その生まれる子は、臣下として育てるのですよ」等と、将来の分からない先の事まで話すのを、女君はとても恥ずかしく、悲しく思います。帝の顔立ちは、気品に満ちて美しく、年月が経つにつれ、この上ない愛情深まる相手をしてくれました。一方源氏は素晴らしい人だけれど、それ程自分を想ってくれている訳でもない態度、気持ちなど、付き合ってみて段々分かる様になった今、自分の若く幼稚だった情熱に駆られるままに、どうしてあんな危うい恋まで引き起こし、自分の入内が無くなった事は言うまでもなく人(源氏)の都を追われた運命までも変えてしまったのか等と思い出し、とても自己嫌悪です。
読後一言感想
・ 帝(朱雀帝)が朧月夜に想いの丈を吐露する。何だか圧倒された。
ま、それは解らないではないけれど、ちょっと女々しいというか、情けないというか・・・。
返り咲いた源氏を苦々しく思いながら床に臥せる弘徽殿も憐れだなあ。弘徽殿、私、好きです。
・ 【澪標】に入ってからの源氏は、太く逞しく、ダークな影をまとった様に思われる。
これから政治家としての源氏が歩み出すのだろう。
帝の心情が、ここでようやく人間宣言をした様に思われる。
・ 今、典侍は源氏より帝に愛されていることを感じていますが・・・
帝はあまりにも愛情が強く、スキャンダルを過去の恋と割り切れず、典侍を前にすると背後霊の様に源氏が見え、嫉妬に苦悩します。後ろ盾が無くなりそうで【心細げに世を思ひ嘆きたまへる】典侍。
破竹の勢いで権力を握っていく源氏。対照的な二人。
高貴で美しく奔放なお姫様が数年後【いと憂き御身なり】。
あの華やかな典侍が厳しい立場になっていくのは読んでいて切なく哀しさを感じました。
・ 何時もは理性的な帝が、源氏を【人】、【立ちまさる人】等と、今迄の恨みつらみ、嫉妬その他支離滅裂に
思いの丈を朧月夜にぶつける言葉の数々と、改めて帝の深い愛情に気づいた朧月夜の場面は圧巻で、古語に、
こんなリアルな会話があったとは驚きでした。
男はいくつになっても子供で、女は人生を学びながら大人になっていく。
2021年12月1日受講
【帰り咲き】 続き P168~終わり
二条の院に到着し、都の人達とお供の人達は夢の様な再会に感涙。紫の上も諦めていた再会が出来ました。彼女は、成長して美しくなり、豊かだった髪は心労で少し薄くなり、むしろ好ましく、一緒に暮らせると安堵する源氏は、明石の君を思い出し、明石の君のとの事を紫の上に話し、その語る様子から、相手への気持ちが浅くないと、紫の上は、さりげなく【身をば思はず】と(百人一首 右近の歌)を引き、チクリと浮気を咎めますが、源氏はそんな紫の上も魅力的で可愛いと。見飽きない紫の上の姿に、どうして長い間逢わずにいられたのか、世間の仕打ちも思い出し無念な気持ちに。間もなく、源氏は権大納言に。須磨に同行した人達も元の官位に復帰し世の中に許され、枯れた木が春に巡り合った様。帝からのお召しで源氏は参内。帝の見た源氏は成長していて、今は老いて呆けた桐壷院の時からの女房などは、泣き騒いで褒めたたえ。朱雀帝も、源氏に会いたいけれど、ばつが悪く、何日も体調を崩し体力が衰えていましたが、少し良くなり、服装等を特別最高に整えて会いました。二人はしんみりと十五夜の月が煌々と輝く静かな夜迄語り合い、昔を思い出し帝は涙にくれ、「不在の間、管弦の遊び等もせず、その道の名手の演奏の音等も聴かないまま久しい」と言うと、
海辺で心しおれて悲しみに沈む※蛭の児の脚は立たないまま三年が経ってしまいました ※日本書紀のイザナギ、イザナミの二神が生んだ子供で三年経っても歩けなかったので、舟に乗せて海に流した神話 と源氏が詠い、
帝は、神話の※宮柱の様に、再び会えたのだから別れた春の怨みを忘れて欲しい ※イザナギ、イザナミ二神が宮柱を巡って国を生んだ神話から巡り合うにかかる と大層気品ある優美な様子で答えました。
源氏は亡き桐壷院の為の八講行(法華経の追善供養)を急がせ、学問(漢学)が身につき、帝として世を治める事に何の心配も無さそうに成長した春宮に、そして入道の宮(藤壺)にも会いに行きました。又明石の君には、紫の上に隠れて、明石に帰る人に託して、「貴女を想っている」という文を。あの帥の娘の五節(【須磨】P131~135)は、都に帰り皆に騒がれている源氏に興ざめでしたが、誰からと知らせず「須磨の浦に心を寄せた舟の上の私はまだ貴方を想う」という歌を屋敷に置かせ、源氏はそれを五節からだと見抜き、気持ちが残っていたので、「私も忘れていない」という歌を届けましたが、この頃は、思い出のある女を軽々しく訪れる事はすっかりしなくなった様で、花散里にも、ただ手紙などばかりなので、彼女はかえって怨めしそう。
読後一言感想
・ 都へ戻った源氏の輝かしい復活。位が復活しただけではない。やんちゃで強気な源氏は、三年振りに対面した兄帝へ、一パツかましてみせた。源氏根性いや増さっていくのでは? 【明石】巻が終わった。
・ 【明石】が終わった。【明石】を読む迄は、【源氏物語】を読んだと言うな。と聞く。
年明けて【澪標】が始まる。これでいよいよ本格的に【源氏物語】に突入だ。楽しみで仕方ない。
・ 返り咲いた源氏がこれからどうなるのかー。期待が膨らみつつ【明石】の巻が終わった。
とはいえ、再会した朱雀帝との歌のやり取りはきつい。父帝との約束を違えたとしても、あんなに責めなくてもねぇ。マザコン長男が少し可哀そうになりました。
・ いよいよ都に復帰した源氏が、強さを見せつけた場面。これから、増々力を得た源氏の快進撃が始まるの
ですね。
・ 参内した時の源氏の【・・・蛭の児・・・】の歌には驚きました。そもそも原因は「朧月夜」では?
島流しの話が出たとき、先手を取って自ら須磨に蟄居したのでは?なのに、この強気はどこから来るのでしょうか。源氏に対する帝のあまりの弱気と不甲斐なさにも驚きました。読んでいて何かもやもやした気持ちになりました。
・ 源氏と紫の上の再会が、ほんの数行で表される。女君には【かひなきものにおぼしつる命】という程の悲
しみからの再会であり、源氏にとってもこれからはずっと一緒にいられるとの喜びは大きい。しかし、御心が落ち着くと源氏は、【かのあかず別れし人】を思う。女君は【身をば思わず】とチクリと皮肉るが、源氏はその姿を【をかしくろうたく】思い、ほくそ笑み満足する。別れの悲しみも、この再会のため!と思うほど、恋にはまめな男である。
・ 【明石】が終わりました。源氏は復活しました!源氏から【明石の君】の事を話された紫の上はため息。自分を【蛭の児】だと言う、今迄の恨みを込めた反撃の歌。
2021年11月10日受講
【残されし入道一家】 続き・【帰り咲き】 P161-~168
入道は、明石に馴染んだ自分はここから離れられないと歌を詠み、娘を思う親の【心の闇】で、国境までも送る事が出来ない、【すきずきしきさまなれど】出家の身で男女の話をするのも何だけれど、娘を思い出す時があったらと、源氏の気持ちを伺いました。源氏は悲しい親心を思い、目頭を熱くし、所々赤みがさした目元のあたりなど、言い様が無い程美しく見えました。懐妊もあるので、すぐに迎えに来たいと思う気持ちを分かって下さい。ただ住み馴れた明石の地こそ見捨てられませんと、
都を出立した時の春の悲しみに劣らないでしょう 何年か暮らした明石の浦を別れようとしている秋は 源氏は詠い涙を拭い、入道はもう何が何だか分からなくなり号泣。立っているのも危うい程で、よろよろした足取りで屋敷に帰って行きました。
明石の君は、源氏が自分を捨てて行ってしまった悲しみ、嘆き、憎しみ等やり場のない気持ちを静めようと思いましたが、面影ばかりを追って忘れられないので、出来る精一杯の事は泣く事だけでした。母君も慰められず、どうしてこの様な気がもめる結婚を思ってしまったのか、全ては、普通でない父親に従ったのが間違っていたと言うと、「うるさい、黙りなさい。懐妊の事もある様だし、何かお考えになっているところがあるのだろう。見捨てるなど縁起でもない」と入道。乳母、母君等がその偏屈ぶりを皆で非難し合い、出来るだけ早い時期に、何とかして思い通りの所に嫁がせたいと長い間期待して過ごして来て、ようやく願いが叶うと頼もしく思ったのに、結婚早々こんな仕打ちに合うとは、と嘆くのを見るのも入道は辛く、一層呆け、昼は一日中寝て暮らし、夜はすっと起き上がり、そのまま数珠が何処かへいってしまった等と、ただ手をすり合わせて仏を拝む始末。弟子達に軽蔑されて、月夜の晩に読経しながら池の周りを巡り歩く行道をしていて、庭に引いた流れに倒れ込み、その中の岩の出っ張った部分に腰もつき損ねて寝込んでしまい、その間は腰の痛みで悲しみも少し紛れました。
源氏は、難波に渡り、御祓へ(神に祈って災いや罪を取り除く)をし、住吉神社には、無事に帰還が叶ったけれど今回は参拝せず、後日色々な願ほどきに来るという使いを出し、急いで京の二条の院に入りました。
読後一言感想
・ 入道の娘を思う親心にほだされた。こわもての入道の落胆ぶり、悲しみ、不安等々、正に親心は闇に包まれてしまった。源氏が去った後の入道は、昼夜逆転し、遣水に倒れ込んで岩に腰を打つ痛みで、少し悲しみが紛れたとか・・・。(笑い・・)
・ ほぼ一年振りに出席したら、源氏に会うのを拒否していた入道の娘が、何と懐妊した上、源氏と分かれるとか!展開の速さについて行けません。かつては、良い夫を得ないと海に沈めるぞ、と娘に言っていた入道なのに、この子煩悩さ全開には、つい顔が緩むのでした。
・ 源氏、入道、明石の君の心情が、情感豊かに描かれていました。
別れの後の辛さは、深い中にもリズム感良く畳みかけて、入道の様を語る式部の筆の確かさと上手さを痛感しました。
・ 今回は、都へ帰る源氏と入道の別れの場面が面白い。
【すきずきしきさまなれど、おぼし出でさせたまふをりはべらば】と、娘の懐妊を匂わせ、源氏の顔を窺
う入道の様子が、私達の目にもおかしく、でも親心が、特に父親の気持ちがよく描かれている。
一方母親は「あんな頑固者の言うことに従った私が間違っていたわ!」と現代でもこんな場面はよくあり
そうである。
・ 源氏は、京へ出立し、残された入道の【心の闇】の悲しみ、母君や乳母達の後悔、明石の君の【たけきこととはただ涙に沈めり】泣く事しか出来ない悲しみが丁寧に書かれていました。
途中住吉神社に後日改めて願ほどきに参拝するという使いを出しました。物語に重要な事がさり気なく。
【形見の琴】続き・【残されし入道一家】 P-155~161
いよいよ源氏が京へ出立する明け方です。準備で騒がしい中、源氏は明石の君に歌を送ります。
貴女を捨てて京へ出立するこの明石の浦の別れを、貴女はどんなに悲しく嘆いている事かと思っています
その返歌は、
長い年月を経た海辺の粗末な小屋も貴方様が去った後は荒れてしまい、
寄せては返す波に京へ帰る貴方様を追って身を投げてしまいたい と、自分の思ったままの気持ちの歌を見て、涙がほろほろとこぼれました。事情を知らない人々は、何年もと言う程住み馴れた所を今いよいよ最後だと思うと悲しいのだろうと。良清は、源氏があの娘にかなり夢中になっている様だと察し、【若紫】のあの時から事の成り行きでこうなった事をいまいましいと思いました。他の供人達は京へ帰るのは嬉しいけれど、今日を最後にこの海辺を別れる事を感慨深く思いました。
入道は、今日出発する旅装束の準備をいつの間にか大層立派に、お供の者、迎えの者の全て、身分の低い者迄用意していて、源氏の装束の素晴らしさは言うまでもありません。都へのお土産に相応しい多くの贈り物は、立派で趣があり全て神経が行き届いていました。
源氏がこれからの旅路に着る狩衣に明石の君の歌が添えられていて、
寄る波が幾重にも立つ様に、私が布を裁ち重ね合わせて縫い合わせて仕上げた貴方様の旅の衣が、
波と私の涙でびっしょり濡れていると貴方様はお嫌でしょうか
とあるのを見つけて、慌ただしい中でありましたが、
お互いに、今私が着ている衣と貴女が贈ってくれた衣を取り換えましょう
又逢える迄何日も経ってしまう二人の間の衣を
と詠い、着ていた衣を脱いで贈られた衣に着替えました。そして、これまで身に着けていた装束を明石の君に贈りました。これこそ一層想いを募らせる形見の品になるに違いありません。今迄着ていた、言い様も無い素晴らしい衣に香の匂いが移った贈り物は、どんなにか明石の君の心深く沁みこんでいった事でしょう。と語り手。入道は、「もうこれまでと俗世を捨てた身ですが、今日のお見送りに一緒に行けない事が残念でたまりません」等と言って、べそをかくのも気の毒だけれど、若い人は吹き出してしまった様です。
読後一言感想
・ 源氏の出立の時になって、明石の君の歌があまりにも変わってきたのに、私達はびっくり!
特に【しほどけしとや人のいとはむ】というくだりは夫婦感満載で、明石の君のなりふり構わぬ想いの丈に、
源氏は、【心ざしあるをとて】と感激した様だけど、私的にはちょっとタジタジ。
・ いよいよ別れの場面です。
映画ならば、帰途につく源氏一行の姿から、映像は住吉へと早々に移っていくのでしょうが、源氏、明石の君、入道そして周囲の様子までズームアップされ、その心情を味わう事が出来ました。
豊かな思いを頂きました。
・ 源氏が京に出発する日。慌ただしさの中、明石の君の苦悩が鮮やかに描かれています。
懐妊を知って間もなくの別れです。「・・・帰るかたにや身をたぐへまし」今までの聡明で理知的な歌と異なり激しく想いが伝わります。残される身の辛さ、寂しさや哀しみだけでなく、生まれ来る子供の事を思うと不安や絶望が噴き出ているのを感じました。
・ 明石の君が、あの冷静な明石の君が、「貴方を追って死んでしまいたい!」と!
源氏の残り香の衣を毎夜毎夜抱きしめて床に就く姿が浮かびます。形見の演出に語り手も感動。
入道は、京に帰る源氏に恥をかかせてはいけないと、旅支度に今迄の人生の全てをかけました。
明石の浦はこれから寂しくなります。ゆっくり時間を掛けて読む事で色々な部分が見えてきました。
2021ねん7月7日
【帝の召還】続き・【形見の琴】 P-143~154
源氏の都への召還で喜ぶ供人達、京からも迎えが来て悲しむ入道。その間も時は流れ秋に。源氏は、今も昔も思いも掛けない恋路に身を投じてしまう自分に悩み、周りは、「困った事、何時もの癖」と。時々こっそり女の所へ行き、さりげなく振る舞っていたのに、娘の心を傷つけてしまうと供人達は互いに袖を突き合い。昔北山で明石の娘の噂を最初に源氏の耳に入れた少納言良清は、その噂に内心穏やかではありません。
出立が明後日のまだ夜が更けない内に源氏は岡辺の家へ。今迄はっきりと顔を見なかった女は、大層上品で由緒ありげで、思いの外素晴らしく、見捨てがたく、都に呼び妻の一人に迎えると約束して慰めました。何年にもわたる仏への祈りでひどく痩せた源氏の顔は、凛とした気品を添えて美しく、涙ぐみつつ、心を込めて約束しました。ただこの逢瀬を持てただけでも幸せと、女は、身を引こうと思いますが、源氏のあまりの素晴らしさにも、どうしようもない身分の差にも、その魅力に抗しきれない自分を悩みます。波の音が、秋の風に混じり、遠くで塩を焼く煙がかすかにたなびき、この地でなければ味わえない、もの悲しい秋の風情。【このたびは立ち別るとも藻塩焼く煙は同じかたになびかむ】別れてもいずれ都へ迎えるつもりです と源氏が詠うと、【かきつめて海士のたく藻の思ひにも今はかひなきうらみだにせじ】私の物思いは胸一杯にありますが、今は怨みも口にしません と女は、泣きながらも、返歌をする男と女の決まり事。
いつも聞きたがったのに恥ずかしがって聞かせなかった琴を、聞かないのはとても心残りで、「それならば、貴女の形見として思い出す様な一弾きだけでも」と、源氏は京から持ってきた琴で、たとえようも無く澄んだ音色でほんの少しかき鳴らし、夜更けの空気の澄んだ中の琴の調べは、たとえようも無く美しく、入道は、堪えられなくなり娘の筝の琴を御簾の中に差し入れます。女は、源氏の弾く琴の音に掻き立てられたのでしょう、涙を流しながら低い音でひっそりと弾きます。それは貴人の弾く様な音。今風で、華やかで本当に美しいと思った入道の宮(藤壺)の琴の音と、この琴の音を比べると、どこまでも澄んだ、奥ゆかしく優れた音色で惹かれるのに、途中で止めてしまう弾き方は物足りず、もっと聞いていたいと、どうして今迄無理を言ってでも聞かなかったのか残念に思います。源氏は、ひたすら将来の約束をし、「琴は又一緒にかき鳴らす時迄の形見に」置いていくと言います。女は、【なほざりに頼め置くめる一ことを尽きせぬ音にやかけてしのばむ】気休めの残して置く一言(一つの琴)を当てにしていつまでも泣かされていますと、恋歌の定型通り男の言葉を否定して、つぶやく様にさり気ない詠い方。源氏は、【逢ふまでのかたみに契る中の緒の調べはことに変らざらなむ】この琴の糸の調子が狂わない前に必ず逢いますと詠い、色々約束した様ですと、語り手。けれども、女はどうにもならない切なさを思い、むせび泣いたのも当然です。
読後一言感想
・ いよいよ明石の君との別れの場面となる。
いつも聞かせて欲しいと言っていたのに、君は最後まで琴を聞かせてくれず・・と源氏が恨み
【さらば形見に】と源氏が琴をかき鳴らすと、明石の君も涙を抑えられずに弾き始める。その音はどこまでも冴えわたり、【心にくくねたき音】であり、源氏でさえ舌をまくほどの技巧!しかも思わせぶりに、途中で音が止まったりする。一方藤壺の琴は華やかで、又となく美しく、聞く人の心を満たす音だった。
ふーん、明石の君はなかなかのテクニシャンなのね!でも賢いだけで、恋の駆け引きをするほど計算高い人ではない。そうだったら、もっと早く琴の音源氏に聞かせてるわよね!
・ 【すずろなることにて身をはふらかすらむ】、源氏をみて【あな憎、れいの御癖ぞ】と見る供人、周りの人達の目からも源氏がこの様に見えていた事が面白い。これまで【聞かせたてまつらざる琴の音】は、【弾き澄ましこころにくくねたき音】だった。【琴はまた掻き合いするまでの形見に】とのたまふ源氏に、【なおざりに頼め置くめる一こと】と返す女、【ただかばかりを幸ひにても】との文にも表れている諦観を感じる。
・ ひたすらに悲しい明石の君が描かれた。
無理もない、別れて去って行く源氏が、誠意をみせてくれるかどうか、全く分からない現状である。
理知的な女性ではあるが、さすがに悲しみの極みであったのだろう。
・ 出立が明後日の夜に【迎へむとおぼしなりぬ】とはちょっと?
秋風に遠くから聞こえる波の音、そこに二人の琴の音。琴が溢れる程詠われた素晴らしい恋歌でした。
【若紫】で播磨を誇らしげに語った良清は、少納言になっていました!
明石
2021年4月7日受講
【思うは二条の君】続き 【帝の召還】 P-133~143
思った通り捨てられてしまった、今は本当に死んでしまいたいと明石の君は思います。年とった親だけを頼りに結婚するとは思わず、心を悩ます事無く幸福だったのにと、後悔しながらも源氏に逢う時は【なだらかにもてなして】気持ちを隠していました。源氏は明石の君を愛しいと月日が経つにつれて思いましたが、京で不安を抱えて自分を待っている紫の上を悩ませてしまい気の毒だったので、独り寝で過ごしがちでした。絵を色々描き、思う事を様々書き付け、二人は交換絵日記を始めました。
年が変わりました。帝の眼病の事で世の中の人々は色々大騒ぎします。朱雀帝の子供は、右大臣の娘の承香殿の女御を母の男の子で、二歳でとても幼いのです。春宮が譲位を受けるしかない。朝廷の後見をし、春宮が世を治められる人を考えると、源氏がこの様に須磨に行っている事は大変惜しく、あってはならない事と、帝はとうとう弘徽殿の后の忠告迄も背いて、源氏を許すという決定を出しました。昨年より后も物の怪に悩み、都では様々な神仏のお告げがしきりにあって騒がしいのを、帝が厳重な物忌みを何度もさせた為でしょうか良くなってきた目の病気までも、この頃は重くなってきて、いよいよ死が迫っている不吉な予感がしたので、七月二十日過ぎにまた再び源氏に京へ帰る様に帝は命令を下しました。
結局は京へ帰る事になると思っていましたが、どの様に命が尽きるのかと嘆いていた源氏は、帝からの召還がこの様に急だったので、嬉しさと同時に、この明石の浦を離れる事を考えて辛く思い、入道は、いつか源氏が京へ帰る日が来ると思いながら、それを小耳にはさんだ時から胸が一杯になりましたが、源氏が都で思う存分位を上げれば、それこそ自分の思いが叶うと思い直しました。その頃は通わない日が無く、源氏と明石の君は語らいました。明石の君は六月位より懐妊の兆しがあり体の具合が悪くなりました。この様に分かれるべき時だったので、源氏はまずい事になったと思ったのでしょう、前よりも可愛く思って、いつもこの様に見苦しく悩む自分だと動揺します。明石の君は、別れを前に塞ぎ込んでいました。全くもっともな事ですね。自分では思いも掛けない悲しい須磨へ旅立ちでしたが、最後にはきっと都に戻ってくるだろうと、一方では思い心を晴らしてきましたが、この度は嬉しい都への旅立ちで、再び決して此処を訪れる事は無いだろうと思うと源氏は辛いのでした。
読後一言感想
・ ついに源氏に京へ帰る宣旨が下る。
文章の出だしは【年かはりぬ】である。響きからして気分の変わる言葉で始まる。朱雀帝はついに母弘徽殿の女御のいさめに背く。春宮に位を譲るには後見をする人が必要であるからである。弘徽殿さんは、どんなにニガニガしく思っている事か。でも、やっぱり源氏は世の中に必要とされる人らしい。
・ 出ました、弘徽殿大后。弱っていても彼女が登場すると色めき立つ。
源氏の京への帰還が決まった。わざとらしくないエピソードが自然だ。
源氏、明石の君、明石入道、登場人物の冷静さと熱情の間の心情が上手く描かれている。
・ 紫の上のどうしても拭えない不安、明石の君の絶望、その心理を読む事が出来ました。
人の心は深く、深くあるものですね。
紫式部の洞察力は凄い。この時代の文章に、心理がここまで書き込まれているとは!
・ 読んでいると映像が浮かぶ事がよくありました。
今回、物語が急展開し、明石、源氏、帝等多くの人が登場します。映像よりも、何もない舞台の上で各々の状況や想い、哀しみなど心情を語る朗読劇を見ている様でした。感想を話している時、ある方が「紫の上とは同じ境遇(幼き時母亡くす)なので他の女性とは源氏の想いは全く違う」のを聞き、二人を同じ境遇との視点で考えてなかったので新鮮な驚きでした。
・ 【なだらかにもてなして憎からぬさま】の明石の君に魅かれていく源氏は、交換絵日記で紫の上との関係を保とうとします。まだ兄妹の様であった二条院での日々を思い出しました。
朱雀帝は母親も弱った事もあり、源氏の召還を決めます。長い年月にわたる弘徽殿の妃の怨みは、我が孫を春宮にという夢すらまたもや打ち砕かれ、今迄の悔しさを思い心が痛みました。
明石の君の懐妊と明石の浦への愛着が、都へ戻ろうとする源氏の心を重くしています。
2021年3月3日受講
【思うは二条の君】 P-126~133
紫の上への良心の咎めがあるのでしょうか、遅れていた後朝の手紙はやっと今日届きましたが、周囲に知られたくない思う源氏と、それを察した明石の君の方でも手紙を運んだ使いを大歓待出来ず、入道は残念だと思います。その事の後、源氏は人目を避けて岡辺の家へ時々通って来ましたが、途中で地元漁師の子供達に見られ、口さがなく噂話される事を心配します。明石の君は、やっぱりと思い嘆き、入道は、この先どうなるかと、自分の極楽往生する事の祈りもすっかり忘れ、源氏の来訪をただただ待つ、それだけです。風の便りで、明石で妻をめとったと紫の上が耳にしたら、冗談にせよ隠し事をしたと思い、嫌われるのは、辛く気まりが悪いと思うのも、止むに止まれぬ紫の上に対する気持ちだからではないでしょうか。と語り手。紫の上がこの様な源氏の浮気沙汰に怨みをぶつけた、昔のその時々を思い出し、どうして、つまらないしのび歩き等して嫌な思いをさせたのだろうか、昔に戻りたいと。
明石の君の様子を見るにつけても、紫の上がたまらなく恋しく、何時もより長い手紙を書き、我ながらそんな気が無かった浮気沙汰で貴女に嫌われてしまったあの時々を思い出す事さえ胸が痛いのに、又不思議な、はかない夢を見てしまいました。と隠し事のない気持ちを察して欲しい【問はず語り】で明石の君との事を告白します。そして、
貴女を想うと、まず涙がとめどなく流れてしまいます
一時的な明石の女との逢瀬は、なぐさみに過ぎなかったけれど と送りました。
紫の上の返事は、無心に可愛らしく書いてありましたが、最後に、隠しておけないで打ち明けてくれた貴方様の夢の話について、思い当たる事が多いけれど、
【末の松山波越さじとは】の歌の様に、絶対心変わりしない事を、疑いなく信じていますから
と、穏やかにゆったりとしている様に見えながら、尋常でない紫の上の気持ちをほのめかした歌は、重く、しっかり源氏の心に響き、その後長い間岡辺の家にも姿を見せませんでした。
読後一言感想
・ 入道はやっと娘を高貴の人の妻にしましたが、その後は思い描いた様にはならないもどかしさ。「極楽の願ひをば忘れて」以前と異なりどうにも出来ない源氏への想い。娘への切なさ、辛さが伝わってきました。今は入道の野望ではなく娘を思い、心が揺れる父親としての哀しさと人間性を感じました。
・ 源氏の思い、二条の君の思い、入道の思い。思いが読み取りやすい部分でした。
それぞれの想いの深さが読み取れました。
・ 源氏の二条の君への愛は【あながちなる】程深く、明石の君とは忍びの旅寝でしかない。
【あながちなる】を辞書は、止むに止まれぬ、一方的だ、度を越している、一途だ、と解説しています。
この表現に源氏と紫の上の思いとの微妙な違いが書かれている様に感じました。【何心なくらうたげに】書かれた紫の上の文には、裏切られた悲しみが潜んでいました。「ああ、まだ懲りない貴方様。」
誰もが不幸で寂しい回でした。
2021年3月3日受講
【思うは二条の君】 P-126~133
紫の上への良心の咎めがあるのでしょうか、遅れていた後朝の手紙はやっと今日届きましたが、周囲に知られたくない思う源氏と、それを察した明石の君の方でも手紙を運んだ使いを大歓待出来ず、入道は残念だと思います。その事の後、源氏は人目を避けて岡辺の家へ時々通って来ましたが、途中で地元漁師の子供達に見られ、口さがなく噂話される事を心配します。明石の君は、やっぱりと思い嘆き、入道は、この先どうなるかと、自分の極楽往生する事の祈りもすっかり忘れ、源氏の来訪をただただ待つ、それだけです。風の便りで、明石で妻をめとったと紫の上が耳にしたら、冗談にせよ隠し事をしたと思い、嫌われるのは、辛く気まりが悪いと思うのも、止むに止まれぬ紫の上に対する気持ちだからではないでしょうか。と語り手。紫の上がこの様な源氏の浮気沙汰に怨みをぶつけた、昔のその時々を思い出し、どうして、つまらないしのび歩き等して嫌な思いをさせたのだろうか、昔に戻りたいと。
明石の君の様子を見るにつけても、紫の上がたまらなく恋しく、何時もより長い手紙を書き、我ながらそんな気が無かった浮気沙汰で貴女に嫌われてしまったあの時々を思い出す事さえ胸が痛いのに、又不思議な、はかない夢を見てしまいました。と隠し事のない気持ちを察して欲しい【問はず語り】で明石の君との事を告白します。そして、
貴女を想うと、まず涙がとめどなく流れてしまいます
一時的な明石の女との逢瀬は、なぐさみに過ぎなかったけれど と送りました。
紫の上の返事は、無心に可愛らしく書いてありましたが、最後に、隠しておけないで打ち明けてくれた貴方様の夢の話について、思い当たる事が多いけれど、
【末の松山波越さじとは】の歌の様に、絶対心変わりしない事を、疑いなく信じていますから
と、穏やかにゆったりとしている様に見えながら、尋常でない紫の上の気持ちをほのめかした歌は、重く、しっかり源氏の心に響き、その後長い間岡辺の家にも姿を見せませんでした。
読後一言感想
・ 入道はやっと娘を高貴の人の妻にしましたが、その後は思い描いた様にはならないもどかしさ。「極楽の願ひをば忘れて」以前と異なりどうにも出来ない源氏への想い。娘への切なさ、辛さが伝わってきました。今は入道の野望ではなく娘を思い、心が揺れる父親としての哀しさと人間性を感じました。
・ 源氏の思い、二条の君の思い、入道の思い。思いが読み取りやすい部分でした。
それぞれの想いの深さが読み取れました。
・ 源氏の二条の君への愛は【あながちなる】程深く、明石の君とは忍びの旅寝でしかない。
【あながちなる】を辞書は、止むに止まれぬ、一方的だ、度を越している、一途だ、と解説しています。
この表現に源氏と紫の上の思いとの微妙な違いが書かれている様に感じました。【何心なくらうたげに】書かれた紫の上の文には、裏切られた悲しみが潜んでいました。「ああ、まだ懲りない貴方様。」
誰もが不幸で寂しい回でした。
2020年12月2日受講
【もの思い】続き~【岡辺の家へ】 P-110~117
月の光に照らされた岡辺の家は、木が鬱蒼と茂り、物寂しく住んでいる入道をしみじみ感じ、広い庭は、三昧堂の鐘の音が松風に響き物悲しく、庭の前栽からは虫の声が限りなく聞こえている中、源氏は、娘の住処に向かって行きます。そこは念入りにきちんと美しく整えられ、月の光が差し込む真木の戸口はほんの少し開いていました。ためらいながら、色々娘に話しかけますが、源氏がこんなに近くまで来る事はないだろうと思っていた娘は、ただただ驚くばかりで、情けなくて返事もせず、返事をしない娘を、大層な一人前の貴族の女の様だとか、簡単に会えない女でさえこれだけ言い寄れば、気が強い態度で拒まないのが普通なのに、とか更には自分が本当にこんな様にみすぼらしくなっているから、馬鹿にしているのではないか等と癪にさわり悩みました。娘に思いやり無く強い迫るのも、父親の承諾を得て結婚しようとしている状況では違っているし、娘との意地の張り合いに負けるなんてみっともなくて嫌だ等、思い乱れて恨み言を言う姿は、実に、源氏が恋の道に長けていて、物思いなど知らないと思っている人に見せたいものです。と語り手。
その時、源氏の耳に、近くにある几帳の紐が、筝の琴の弦に当たった微かな音が聞こえ、それを突破口に、「いつも入道から聞きている琴を聞かせて欲しい」と源氏は再び話し掛け、歌を詠みました。何と、すぐに娘から歌が返って来ました。その奥ゆかしい歌の様子は、伊勢の御息所を思い出させるものでした。何も考えずくつろいで琴を弾いていた娘は、この突然の源氏の訪問に慌て、どうしようもなく近くの曹司に逃げ込み、しっかり戸を閉めてしまいました。源氏は無理やり開けようとはしないで立ち往生。【されど、さのみもいかでかはあらむ】と語り手。(どうやら部屋に入れた様)明石の君は、とても気品があり、すらりとした体つきで、こちらが気後れする程凛としていました。この様な普通では考えられない強引な結びつきを考えても、源氏は一層愛情が増すのでした。【近まさり】でしょうと、語り手。いつもは嫌いな夜の長さも、すぐに明けてしまい、気がせく源氏は、これからの逢瀬の詳しい約束をして出て行きました。
読後一言感想
・ 明石の君の「うちとけぬ心ざま」に源氏はなす術もなく「乱れ怨みたまふさま」。以前の源氏とは違いすぎます。明るく想いのまま恋に邁進していたことを思うと少し寂しさを感じました。
住まいの様子や源氏と明石の君の恋の駆け引きまでを描き、その後は語り手の「されどさのみも・・・」によってさらりと場面転換をさせてしまう式部の凄さを感じました。
・ 娘の住む処は、源氏の感性に合った趣のある佇まいだった。
今日の場面は、明石の巻のハイライトで、二人が結ばれるシーン。源氏と明石の君とのやり取りが、くるくる入れ変わり、主語が無いので難しいが、中身は濃いのです。
でも、肝心なシーン、式部は、「どうぞ想像して」と読者に投げるのよ。ずるいです。
・ 明石の巻のクライマックスでした。
紫式部の筆の確かさ、力量に圧倒されながら、いよいよ明石の君の女性としての苦難の道が始まるのですね。
・ 【心くらべ】となってしまった、にっちもさっちもいかない場面から、几帳の紐がポロンと琴を鳴らして、源氏の緊張が解け、場面がガラリと変わる。うまいなー。
明石の君の姿は、【いとあてに、そびえて、心はづかしきけはひぞしたる】ずっと、どんな人だろうと心待ちしていたが、こんな短い言葉で姿が見える様なので不思議である。
今日は、古語の、リズム感、想像の膨らむ余地のある面白さをたっぷりと味わった。
- 緊張した場面が、几帳の紐の触れた琴の音で急展開する。和歌を交わすとその気配に好感を覚え、実際
は【心はづかしきけはひ】だった明石の君の少しづつ見えてくる姿に惹かれる源氏が、目に浮かぶ様な文章でした。
- 今回は、舞台作品を鑑賞した様でした。
月の光に照らされた岡辺の家の庭に聞こえる、鐘の音、松風、虫の音、その中に微かに聞こえる源氏の美しい声、声が途切れた時、几帳の紐が琴に触れる微かな音、明石の君が逃げ込み戸を閉める音、源氏がそれを開けようとする音。暗転した後の静寂。語り手が黒子の様に場面場面を説明する。最高の演出の素晴らしい舞台を堪能しました。
2020年11月4日受講
【もの思い】続き~【岡辺の家へ】 P-110~117
都からの噂だけで聞き、いつかはそんな別世界の美しい貴公子の姿をほんの少しでも見てみたいと想像していたそのお方が突然この明石に住み、時には遠くから姿を垣間見た事もあり、その暮らしぶり、風に乗った琴の音も聞こえている、その貴公子が何と自分を一人前の女と認めてくれ、手紙まで届けて来る事など、この様な身分が低い【海士のなかに朽ちぬる身】には身に余る事と、決して身近な男女の間柄になることは考えられない明石の君は同時に、本当に長い間自分の事を住吉神社へ祈ってくれた両親を心配する一人の娘でした。父親は何も考えず無遠慮に娘を源氏に近づけ様としているけれど、たとえ結ばれたとしてもその後捨てられたら、どんなに嘆くだろう、裏切られた時の辛さ悲しさはどんなに大きいだろう、目に見えぬ仏神に頼んで、源氏様の気持ちも私のたどる運命をも知らないで、と繰り返し思い悩みました。一方源氏は、娘の琴の音を聞きたいとなどと、入道にいつも言っていました。
入道が動き出しました。誰にも気づかれずに暦の上で婚礼に良い八月十五夜の二日前の十三日の月夜を選び、妻の心配も聞き入れず、家の者達にまで何も知らせず、自分の胸一つに収めて準備に立ち振る舞い、部屋を輝くばかりに仕立て上げ、当日月が華やかに昇って来た頃、ただ【あたら夜の】(後撰集:【あたら夜の月と花とを同じくは心の知られむ人に見せばや】:惜しむべき今宵の月光と桜の花(娘)を同じ事なら情緒の分かる人にみせたいもの)とだけ書いた文を源氏に届けました。源氏は、【好きのさまや】まあ、風流ぶってと思いましたが、招待を断れず、正式な直衣を着て化粧等おしゃれをして、夜が更けて出掛けました。入道からの素晴らしい迎えの車ではなく、馬に乗って惟光と数人をお供に。道の途中眼下に見える、四方の浦の月を見て、【思ふどち】(古歌:【思ふどちいざ見に行かむ玉津島入江の底に沈む月影】)愛しい人とさあ見に行こう玉津島の入江に映る月を の歌から都の紫の上に逢いたくなり、そのまま馬で都まで駆けてしまいそうだと、都の紫の上への恋しさを独り言で詠いました。
読後一言感想
・ 明石の君は、青く透きとおる石の様な人に思えます。冷え冷えとして澄んだ青色。
そんなイメージの女性に思えます。
・ 明石の君が自分を散々卑下しつくしている間も、父・入道はチャンスとばかり、源氏を月観宴に誘う。
入道の「野望の階段」は、又一歩上へ。いよいよ岡辺の家だね。
・ 源氏、明石の君、入道夫妻のそれぞれの思いや立場が鮮やかに描かれていました。他の女性とは異なり恋に夢中になれず、慎重で自分に起こるうる将来を考えてしまう冷静さ。プライド・教養・知性が複雑に絡み合った明石の君が浮かび上がりました。
・ 途切れなく句読点だけで続ける文章が、明石の君の心の悩みと叫びを素直に表していました。
四方の浦の月を眺め、都の紫の上を想う場面、何故か【夕顔】の鴨川を惟光と二人、馬で亡き夕顔に逢いに行った月夜を思い出しました。あの時の月は遠くて小さかったかも。
明石にある【岡辺の家】への狭く短い道、目の前にすぐ広がる海とその向こうに黒く横たわる淡路島。およすく会の明石の旅は、昔話になってしまいました。
2020年10月7日受講
【そのころ都では】続き P105~110
太政大臣(右大臣)が亡くなり、【つぎつぎにおのづから騒がしきこと】ある都で、大宮(弘徽殿の女御)も、原因不明の病気になり衰弱していくのを心配した帝は、その原因が、父桐壷院との約束を違えて源氏を須磨に追いやったからだと、源氏を元の位に戻さないとその【報い】は更にあるだろうと、再三母大宮に進言しますが、法律にも詳しい弘徽殿は、「罪にびくびく恐れて都を去った人を、三年も経たないのに(当時の法律【獄令】では、流刑は六年後、流刑でなく配流は三年後出仕出来る)許してしまう事は、世間の人から軽率な処置だと非難されるに違いない」等と正論で強く否定します。帝はそれ以上言えないまま、日々が過ぎ、大宮と帝の容体も増々重くなっていきました。
明石にも須磨と同じ様に秋がやって来て、須磨の【いとど心尽くしの秋風】とは違う浜風が吹いています。ここでの独り寝も本当に寂しくてやりきれず、源氏は入道にも時々声を掛けて話をさせ、「何とか人目につかない様に娘をこちらに来させなさい」と、自分から女の家に出向くなんて事は絶対出来ないと思っていました。娘当人は、自分から源氏の屋敷に参上しようなどとは全く思っておらず、田舎女が、一時的に都からやって来た男の甘い言葉につられて、軽率に男女の中になると聞いていて、自分は、身分的に一人前に扱われない女なので、すぐに捨てられてしまうだろうし、娘に及びもつかない高望みをする親達も、もしそんな当てにならない【あいな頼み】が叶ったらかえって悩むことになるだろうと冷静に思います。源氏様がこの明石の浦にとどまっている間だけでも、この様に手紙だけを交換し合う事で彼女は十分幸せなのです。
読後一言感想
・ 身の丈以上の教養を身につけてしまった明石の君。
田舎育ちの彼女にとって、源氏との出逢いは幸なのか不幸なのか。
明石の君のプライドに身もだえする様な今回だった。
・ 私はどうしても、作中の女性の悲しみに心を取られてしまう。
でも、本日の講座の中で、明石の君の様な事は歴史的にはあり得ない事であるが、しかしフィクションがここに入る事により、より豊かな膨らみが増すと知り、源氏物語の読み方をもっと考えなくてはと、反省しました。より豊かに味わいたいと思います。
・ 天変地異や身内の病気や不幸は源氏を追放した結果と悩み【もとの位を】と思う帝。【后かたくいさめたまふ】。情の帝。理の后。優しく穏やかな帝(息子)と一門を背負う強い后(母親)の対比が鮮やかに描かれています。時代を超えて現在でもいそうな親子です。
・ 今まで母親に口答え出来なかった帝が、源氏を都に戻す様【たびたびおぼしのたまふ】程、都の状況は深刻です。弘徽殿の女御の一貫した答えに感動。昔と変わらない彼女を好ましく感じました。
明石の君は、文の交換だけで幸せでした。都の女房達に幼い頃から教えられた自分の歌で、あの源氏様を感動させる事が出来、そしてドキドキする程素敵な歌が返って来る!
源氏学者の男性の多くの理想的な女性が、明石の君だと先生から聞き、へー本当!と思いました。
2020年7月1日受講
【宣旨書き】続き??? 【そのころ都では】 P98~104
明石の姫君との文のやりとりで、京を思い出し、段々惹かれて行く源氏ですが、二三日置きに【つれづれなる夕暮れ】や【ものあはれなる暁】等を意識して文を交換。姫の、思慮深く気位が高く自分が自分である事を失わない【思ひあがりたる】様子に、逢わずにはいられないと思いますが、ふと、良清が長い間心を寄せている姫を、目の前で自分のものにしては可愛そうだ等と考え、姫が自分から進んで仕えて来れば良いのにと思います。しかし、姫は京の高貴な身分の女よりもかえって気位が高く、源氏は面白くなく、姫との意地の張り合いで時間は過ぎて行きました。
そんな中、須磨の関よりまだ遠く離れている京の紫上の事を想い、あまりに辛く冷静さを失いそうで、こっそり此処に迎えたいと思って気が弱くなる時もありましたが、この様にこの地で年を重ねる事は、まさかないだろうし、今更人に非難される体裁の悪い事は出来ないと、源氏は心を落ち着かせました。
時間は遡り、
その年、都では神仏のお告げが度々あり、世間の人々が騒ぐ事が多くありました。三月十三日(入道が源氏を迎えに舟を出し、源氏の夢に故院が現れたP-26,P-35と同じ日)に、都では雷が鳴り光り、雨風が騒々しい夜、帝の夢に故桐壺院が、清涼殿の階段の元にお立ちになり、心の底から怒りを露わにした表情で、帝を睨んで源氏の事を多く話しました。帝はとても恐ろしく、約束を違えた自分をどうしていいか分からず、母后弘徽殿の女御に話すと「雨などが降って、天気が乱れた夜にはそんな夢もみるもの。軽々しい下々の人の様に驚くことではありません」。
故院が睨んだ時に目を合わせたのを夢に見たせいでしょうか、帝は眼病になり失明する程病みました。眼病平癒のための加持祈祷の物忌みを、内裏でも弘徽殿の屋敷でも数多くさせました。
読後一言感想
・ 源氏と明石の君との恋の駆け引きが始まります。
明石の君は、貴族と同等の教養と誇りを身に着けると共に、受領階級のコンプレックスで積極的に動けません。源氏も人目や良清の事を気にして、恋に受動的な思考になっています。
状況は整っているのに・・・
空蝉では人妻だけど恋に猪突猛進。空蝉の時は源氏17才。明石の時は27才。若々しい青年と分別のある大人の差? 明るく怖いもの知らずの源氏が懐かしい。
・ 【人目つつましければ】気を使いながら始めた明石の君との文の交流で、【心深う思ひあがりたるけしき】に心惹かれながらも、良清の事も気になる。
京の事に思いは募るが、今更【人わろきこと】も出来ない。周りの人の評判が気になる。
若い頃とは違う思いが、源氏の行いを規制する。そして都の様子が、次の物語の展開を予感させる。
・ どんな女もすぐ手に入れてしまう源氏が、人目を気にして思い悩む姿が新鮮だ。都を思い、紫上を思い出し懐しがっている場面から、都の様子へと移っていくストーリーの運びが上手い。
やはり、式部は天才だ!!
・ 明石の女は、源氏にとっては大変手強い人であり扱いづらい人。性格も難しそうで、あまり可愛い人とは言えない。女性から見ても賛否の分かれるところだと思う。でも、あくまでも【思ひあがり】の心とコンプレックスからの、自分の身の程を知って振舞う生き方は、知的で、冷静で、こういう女性を書き起こした紫式部の洞察力は、凄いとしか思えない。
・ 源氏の枕元に現れ【内裏に奏すべきことあるによりなむ、急ぎのぼりぬる】と消えた(25~26頁)故院は、入道がお告げに従って源氏を迎えに舟を出した、正に同じ三月十三日の夜、帝の夢に現れたのでした。時間の推移が正確に書かれている事に驚きました。
久し振りの【后】弘徽殿の女御様。相変わらず指導的な帝への物言い、懐かしく。
2020年2月5日受講
【宣旨書き】 P89~98
源氏は、次の日娘の所に手紙を。こんな田舎の片隅に思いがけない美しい人がひっそりと隠れ住んでいるかもしれないと、紙の色、質、筆、墨つき等々に気を使い、高麗の胡桃色の紙を使って仕上げました。
父上様から貴女の事をちらっと聞いて貴女の家宛にお便り致します と。入道は、家族には言わず、源氏の手紙を待っていて、使いの者に、当時は貴重な酒をたら腹飲ませ酔わせました。娘が中々返事を書かないので、早く書くよう催促しましたが、決して書こうとしません。娘にとっては、目がくらむ源氏の手紙に、返事を書こうにも、筆跡も、ただ恥ずかしく遠慮されて、受領の娘のという自分の立場を考えると、結局書けず、使者に何と言ってよいか分からず困った入道が、何と代わりに返事を書きました。
貴方様が眺めていると同じ雲を眺めるのは娘の思いも同じ思いだからでしょう という陳腐な歌でした。陸奥紙に書かれた入道の手紙は、古風に見える様に、書体は、趣があって洒落っぽく書いてあり、源氏は呆れ果てて、僧侶の身で出過ぎた真似をと、苦々しく思い、当てつけの様に、入道の使いに目の覚める程上等な都の女装束の上衣を褒美として与えました。次の日、「代筆の手紙は、今迄もらった事がありません」と、源氏は再び娘に気を引く様な歌を送りました。今回は、若い女がドキドキする様な、とてもしなやかで薄い紙に、文字も美しく見える様に書きました。娘は、美しいとは見ましたが、釣合わない身の上を思い、源氏が自分の存在を知り、恋の相手の一人前の女として尋ねてくれる事に、涙ぐみ、手紙を書かない訳にもいかず、お香を深く染み込ませた紫色の紙に、墨つきを濃く薄く、筆跡の癖を相手に分からなくして、
貴方様の私を思ってくれる心の深さは、さあどうでしょうか
まだ会った事の無い貴方様が、私の噂だけで悩んだりするのでしょうか
筆跡、歌の作り方等は、都の身分の高い女性に劣らない様な、貴人らしく見える歌でした。
読後一言感想
・ 明石の君の姿が段々見えてきてワクワクする。
かなり賢い人らしい。源氏の歌に対してもきっぱりとした歌を返す。かっこいい。
娘に比べて入道は、もう舞い上がってしまい、返事をしぶる娘の代筆をしてしまうが、何と色気のない歌か。久し振りに笑えた。
・ 源氏が初めて出した(恋)文に、明石の君は身がすくみ返事も書けない。
とはいえ、パパが代筆するとは・・・! それも「何じゃ、こりゃ」という歌。面白い。
明石の君は良く出来上がった娘よねぇ。父親の様な野心は無くても、その親心で磨かれた教養が、
源氏の心をちょっと刺激する。返歌が上手過ぎますよ。
・ いよいよ源氏と明石の君との交流が始まる。
身の程を知る明石の君の苦悩はいかに深いものだろうと、気の毒になる。
が、一方明石の君の冷静さと知に勝った気配がそれとなく伝わる一場面だった。
・ 入道は、ようやく自分の思いを打ち明けた事でホッとしているが、まだ初期の段階。これから先が全く分からないが、源氏の方は、こんな田舎にそんな評判な娘がと、気になり手紙を送ったものの、これが一筋縄ではいかなかった。娘にしびれを切らした入道が代筆までしてしまうなんて・・・。
でも田舎に暮らしている人にしては、中々と思いました。
・ 十分ではないが不満ではないという【かつがつかなひぬるここち】の入道が【宣旨書き】を。
源氏の今まで培った美意識全てを投入し【心づかひたまひて】【えならずひきつくろひて】書かれた明石の君への恋文は、高麗の胡桃色の紙に。それを見た明石の君は、何も書けない。書ける訳が無い。入道が娘の代わりに書いた歌を【めざましう見たまふ】源氏は、【宣旨書きは見知らずなむ】と更に、若い女の子の心をわし掴みにする手紙を送りますが、明石の君は、冷静で謙虚な賢い女性で、身分に対する気後れ等微塵も書かぬ、【やむごとなき人】に劣らぬ歌を返しました。
式部は、入道のどうしようもない歌も書けました。【陸奥紙】で、【末摘花】を思い出しました。
2020年1月15日受講
【問はず語り】????? P78~88
明石に住み始めた不安、仏道修行の様子、娘の様子を、ぽつりぽつり話した入道の【問はず語り】は、深夜にまで及び、【ただこの人を高き本意かなへたまへ】と、この十八年間毎年春秋に住吉大社に祈願し続けたので貴方様に会えたと。自分は大臣の子孫で、このままこの様な田舎の民として子孫までもが劣っていく事は許せず、娘は【生まれし時より頼むところ】があり、どうにかして【都の貴き人にたてまつらむ】と、身分相応の縁談を断り続け多くの人から嫉まれた時もあったが、私が先に死んだら、【波のなかにも交じり失せね】と娘には言い置いてあります等々涙をこぼしつつ話し、源氏も涙ぐみながらその話を聞きました。
「身に覚えのない罪でここ明石に流れてきたのは、【先の世の契り】で、貴方の事は、ほんのちょっと聞いていたけれど、落ちぶれた私は縁起が悪いと、遠ざけられていると落ち込んでいました。それでは、娘さんとの仲立ちをしてくれるのですね。心細い一人寝の旅の途中の仮そめの恋の相手に出来るかもしれません」と源氏が言い、入道は限りなく嬉しく思いました。二人は明石の寂しさの歌を交わします。
すっかり打ち解けた源氏の【うち乱れたまへる御さま】はとても魅力的で、何とも言えない姿です。最後に語り手が、入道はあまりに多くの事を話してうるさいです。あえて誇張した様に書いたので、彼の愚かしく、頑固な心の様子も露わにした様ですね。と。
読後一言感想
・ 問われもしないのに、思わず心の有り様を吐露してしまう【問はず語り】。
入道の話は止まらず、娘の存在を源氏に知らしめる大きなチャンスになる。
一方源氏も「じゃあ会ってみようかな、一夜の慰めに」と釘を刺しつつも受け入れる。
いずれにしてもこの二人の距離がぐっと近づいた事は間違いなさそうだ。
・ 今回は、源氏と入道の自分に都合の良いやり取りが面白い。入道は、娘を身分の高い人に【たてまつらむ】と願う。一方源氏は、一人寝の慰めにもと、現代の我々には、ちょっと違うんじゃないと思うけど、入道は限りなく嬉しいと思う。式部は、入道の様子を【さすがにゆえなからず】と言ったり、自分が書きなしたのに、入道を【聞こえ尽くしたれど、うるさしや】と、結構バッサリと切って面白い。
・ 入道は自分の意志を貫こうとするあまり、【問はずがたり】をするが、源氏は源氏で今迄色々の苦難があり、運命の変転はどこか共通するものがあったのであろう。【心細きひとり寝のなぐさめにも】という源氏の言葉に、入道は天にも昇る気持ちになった興奮度は、マックス。
・ 入道の【問はず語り】は、明石に住んでから今までに考えていた思いを全て吐き出したもので、大臣の血を自分の代で途絶えさせる事は、彼にとって涙ながらに語る程重要な事柄でした。
【若紫】の【この思ひおきつる宿世違はば、海に入りね】が【波のなかにも交り失せね】に。
源氏は、必死に防衛線を張りながらも、娘への興味は増しています。
【みづからもをさをさ参らず、もの隔たりたる下の屋にさぶらふ】入道が、何故こんなに親しく源氏と話せたのか考えた時、神仏は勿論、琴と琵琶の演奏、そしてお酒の力だったと思いました。
入道を、当時の貴族社会の中の新しい階級として描いた式部の時代を読む能力の高さを知りました。
原文からひろがる源氏物語 明石
2019年12月4日受講
琵琶行 白楽天
前回の【明石】で、娘が琵琶を弾くと入道が話した、【商人のなかにてだにこそ、ふること聞きはやす人ははべりけれ・・・】P-73は白楽天の【琵琶行】の事。作者四十五歳の時。
そこで今回は【琵琶行】を読みました。
白楽天の【長恨歌】と並び、【琵琶行】は当時の日本において広く読まれていました。
時は秋、左遷された作者は船で帰る客を長江迄送りに。別れの酒に何の音楽も無く、果てしなく広がる川面に登ってきた月は浸される。その時、琵琶の音。音を求め探すと、一人の年増女が乗る舟が現れ、手にまかせて、心の中のありったけを語りたい様に、軽くおさえ、ゆるくひねり、はらうてまたかかぐ。太い弦は急雨の如く、細い弦は男と女が囁く様に、それは、大粒、小粒の真珠が皿の上にこぼれ落ちる様。
女の声は、春の鶯の声が花咲く下を滑らかに流れ、むせび泣く様な泉の流れ、氷の下で渋る様にも聞こえ、
その音がしばらく止むと憂いと悲しみが。この時声無きは声あるにまさる。突然銀の瓶が破れ、水がほとばしり、騎馬武者が飛び出し刀や槍を鳴らし曲は終わる。琵琶の四本の弦を一度にはらうと、絹を裂くような響き。東西に止まっていた船の上の人々はあまりの凄さに言葉なく、見上げると登りきった白い月が長江の真中に。弾き終わった女が、自分は長安の都の生まれで十三歳に琵琶を学び得て成り、一流の演奏家としても容姿の美しさも同僚から妬まれる程で、いなせな若者が争って絹を贈る程。贅沢三昧の日々を呑気に過ごす毎日。しかし、戦争が始まり、弟は軍隊に、母親は死に、年と共に顔色衰え、商人の妻に。商人は利を重んじ別離を軽んじ、茶を買いに行ってしまい、ここで空船を守り、若い頃の華やかな夢を見て涙が流れると。
作者は女の話に、左遷された今の不遇さを切々と語り、この様なホトトギスと猿の声しか聞こえない辺鄙な土地で聴く音楽もなく、今宵貴女の琵琶歌は天上の仙人の音楽の様に清々しく、どうぞもう一曲弾いて下さい。貴女の為に琵琶行の歌に作り替えましょうと。すると女はこれまでとは全く違う鬼気迫る演奏をし、聴いている皆が涙を流し、その中の誰が一番涙を流したかといえば、司馬の地に流され、下級官吏の青い服を着ている私自身でした。という漢詩です。
読後一言感想
・ 本日の源氏は、【明石】の巻にちょこっと出てきた【琵琶行】を読んだ。
この年頃になって、漢詩はいいなぁ、とつくづく思う。
【長恨歌】もいいけれど、さすが白楽天は凄い!
・ 秋の侘しさの中、船上での様子が目に浮かび、琵琶の音が聞こえ、都の華やかな生活から地方へ落ちぶれた心情が切々と伝わってきました。
【茫茫として江月を浸す】【名月江水寒し】等の【江】【月】の描写が印象的で、
【暮去り朝来りて顔色故る】が心に残りました。
・ 入道の娘が琵琶の名手であることから【琵琶行】を勉強することになったが、うまくまとめられない。
作者と自分を重ね合わせた部分もあるのかと思う。
・ 日本の文化には、中国の文化が底流に太く流れている事を実感しました。
流れの様に自然にリズムも情景も心も伝わりました。
漢詩を又読んでみたくなりました。
・ 漢詩の心地よい響き。
しかしその内容は女の深い哀しみ「顔色の衰えと零落」。片や男は、男として最も惨めであろう「左遷と謫居の身」を詠う。琵琶の音が大きく響き、途切れると【此時、声なきは 声あるに勝る】。
う?ん、すごい!
・ 琵琶の音の微妙な違い、女の歌う声、川面の月、人々の吐息や涙が漢字の連なりから、しっかり伝わり、五感で読む源氏物語に繋がっていました。しつしつ、ぼうぼう、そうそう、切々等々の擬音が実に効果的で、漢詩の素晴らしさと、それを日本語で表記した先人の繊細な感性に改めて感動しました。
2019年11月6日受講
【弾きくらべ】続き P68~78
古人、入道は、源氏の琴の演奏と歌に涙が止めらない程感動し、岡部の屋敷から琵琶と十三弦の琴の琵琶を持って来させ、自ら【いとをかしうめづらしき手】で琵琶を弾き、源氏にも箏の琴を勧めます。源氏が少し弾いた音色に又感動。遥か先まで広がる明石の海を前に奏でる楽の音は、春の桜、秋の紅葉の盛りではない、ただ何となく茂っている緑の緑の木の蔭にも風情が感じられ、その音に混じってきた水鶏(水鳥)の鳴き声から源氏は、古歌「誰が門さして」を思い出し心を動かされます。入道の弾き鳴らす琴の音にも心が惹かれ、「その琴は、女が男の為にしっとりとした風に弾いた方が風情あるよ」と一般論として言ったのに対し、入道は、女という言葉で無闇矢鱈変に顔をほころばせて笑い、実は、自分は醍醐天皇からの琴の奏法を伝えており、帝から数えて三代目になる筈で、その自分の奏法を違えず真似をして伝える者が居り、琴の名手の親王に似た弾き方に通じていると。是非貴方様にお聞かせしたいと言いながら入道は身を震わせて涙を落とした様だと、語り手。
源氏は、入道の琴の才能に恐縮し、「昔から箏の琴は女が弾くもので、嵯峨天皇の第五皇女繁子は、有名だったが、それを継ぐ者が居ない今、世の中の名高い人々の演奏は、表面的な気晴らし程度ばかり。ここ明石にこんな風に弾きこなす人が居るとは興味ある事。何とかして聞かなくては」と。入道は、是非娘の琴を聞かせたいと、白楽天の詩【琵琶行】を引き合いに出し、更に娘の琵琶の才能も特別だと。この田舎の荒い波の音に混じる琵琶の音では悲しいだろうと思いながらも、それを聞くと自分の積もる憂いが紛れる時々もあると。源氏は入道の風流な物言いに努力している姿が可笑しいと思いながら、入道に箏の琴を弾かせます。その演奏は素晴らしもので、「清き渚に貝や拾はむ」という催馬楽を声の良い供人に歌わせ、源氏も時々拍子を取り一緒に歌うのを、琴を弾き止め入道は聞き入っています。菓子や人々にしきりに酒を勧め、日頃の嫌な事を忘れる夜の様子です。
読後一言感想
・ 入道は源氏に娘の事を認めて欲しく、何時言い出すか常に考えていたが、遂に言えた時の、かなり興奮した様が面白い。その後も実はと、琵琶の腕前を披露する。
何としても娘に気を止めて欲しいが故に力が入る。
・ 源氏の【これは、女の・・・おかしけれ】で【入道はあいなくうち笑みて】は入道の気持ちがよく表れていると思いました。娘を高貴な人に嫁がすという長年の宿願に命を懸けて疾走。
源氏は何気ない一言で入道の激しい想いに絡められていきます。
ついに【いかでかはきくべき】明石の君の登場が楽しみです。
・ 来ました。待ちに待った入道のチャンスが!
といっても入道の思い込みが強いのだけれど、娘を源氏に引き合わせる事が出来そうだ。
それにしても、入道の娘への思いの深さには驚くばかり。ちょっと微笑ましい。
・ 入道は、源氏の目を何とかして娘に向けさせたいと思う。
更には、娘の事を少しでも上級なものを身につけた、素晴らしい女性であるかを印象付けたい。
これでは源氏は逃げられない。
・ 入道が、優れた琴と琵琶の奏者で、白楽天の【琵琶行】や醍醐、嵯峨の帝まで繋がる話が出来る文化人
である事を知り喜ぶ源氏。娘が琴を【あやしうまねぶもの】だと源氏に打ち明け【うちわななき】感動する姿は、遠い昔の左大臣を思い出させました。源氏も娘への興味が湧いて来て、明石の物語はいよいよ動き始めました。琴と琵琶の音に溢れた場面でした。
2019年10月2日受講
【弾きくらべ】 P62~68
四月の衣更えになり、源氏の衣類、御帳の布などを夏向きの【よしあるさま】に【し出づ】入道を、やり過ぎだと感じながらもその品ある努力を受け入れます。京からも便りが沢山来ます。ある月の美しい晩、目の前の月に照らされ凪いだ海が二条の池の水面を思い出させ、今何処に居るのか一瞬分からなくなりますが、目の前にどっかりと横たわる淡路島が【淡路島なりけり】と源氏を現実に引き戻し、何もかもを照らし出す様な澄んだ淡路島の夜の月を歌います。月に誘われ、久しく触らなかった琴を取り出し、源氏はちょっと弾いてみました。心を込めて広陵という曲を弾くと、入道の娘の館まで届いたその音に若い女房たちはうっとりとし、今迄聞いた事のない美しい調べにあちこちの老人たちは落ち着いていられず、浜を歩き回り風邪を引く程。勤行していた入道も我慢できず源氏の所にやって来て、泣きながらほめたたえました。源氏自身も宮中での時節時節の管弦の遊びの誰々の琴、誰々の笛もしくは声、その時々に自分が世間から受けた賞賛、帝をはじめとする人々が自分を大切に思って敬ってくれた事、他人の姿も自分の姿も思い出され、夢を見ている様な心地のままにかき鳴らす琴の音色も、人々の心にぞっとする様な寂しさを感じさせました。
読後一言感想
・ 今日の一言は、何と言っても気付きの【なりけり】
【淡路島なりけり】この簡潔なセンテンスが、圧倒的な淡路島の存在感を示す。
的確な言葉さえあれば、長々と説明する必要はないのだ。
・ 源氏物語に描き出された色彩が、水墨画の夜の景色であったり、(月は銀色)
琴を弾く源氏が思いを馳せる宮中での雅な遊びの、きらきらとした色彩であったり。
源氏の世界は、奥行深く美しい!
・ 源氏の【はかなく かき鳴らし たまふる琴の音】は【何とも聞きわくまじき このもかのもの しはふる人どもも、すずろはしくて、浜風をひきありく】と源氏の琴の音がどんなに【心すごく】聞こえたかが、面白く描かれている。須磨に居た時は、琴を弾いても、荒涼とした寂しさばかりであったが、入道も急ぎ参るし、耳を傾けてくれる人がいるのは、源氏も慰められるのでは。須磨とは違ってくる予感がする。
・ 望郷の念にかられて琴をかき鳴らす源氏。
だがその一方で、明石に居る今の自分―現実を見つめるのだった。
源氏の奏でる音色に、密教の修行も放り出し駆けつけた入道。源氏と入道の今後のやりとりも楽しみだ。
・ 夏の衣更えが済んで、最近は絶えず手紙を通し気持ちも少し落ち着いていく様子がうかがえるが、
月を見ては宮中の風景、琴を弾いては管弦の催しを思い出したりする。
しかし、此処は京から遥か遠い明石だと現実に引き戻されてしまう。
・ 【淡路島なりけり】で、その後の歌の月の輝きが増しました。
明石の浜に流れる【何とも聞きわくまじき】琴の音に老人達が【浜風をひきありく】式部のユーモア。
【紅葉賀】、【花宴】の源氏、その場の色、光、音、懐かしい人達の顔、香りまでもが短い文章の中に戻って来ました。青海波も。
2019年9月4日受講
【あるじの入道】 P54~61
勤行に励む入道の唯一の悩みは娘の事。それを時々漏れ聞く源氏は、あの【若紫】で良清が話した娘との縁を思いながらも、紫の上への気持ちが嘘だったと思われては恥ずかしいと【けしきだちたまふ】事無く、ただただ勤行に励みます。でも、折に触れ娘の噂が聞こえ、【ゆかしうおぼされぬにしもあらず】です。
そんな入道は、源氏の住む部屋から遠く離れた使用人達の部屋に住み、恐れ多いと滅多にやって来ませんが、どうやって源氏を婿にする事を叶えようかと、仏神に更に心をこめてただただ祈願するのでした。
源氏の目から見た入道は六十歳ばかり。偏屈なところもあるけれど勤行に励み過ぎて痩せて骨ばっていて、生まれの良い上品な男。長年宮中で忙しかった源氏が耳にした事のない、昔彼が勤めていた宮中で見知った話や、風情の趣もあり、ここ明石の様な田舎で会えなかったら【さうざうしくや】と思う程の男。
でも入道は、源氏のあまりの高貴さ立派さに気後れし、一切娘の事など口に出せない自分を妻と嘆いています。そして娘本人も、源氏を【世にはかかる人もおはしけり】と見て自分の受領の娘だという【身のほど知られて】源氏を【いと遥かにぞ】思いますが、彼を全く知らなかった時より物思いが多くなっています。
読後一言感想
・ 今回は入道の「人となり」が描写された部分を読み込んだ。
これまで何となく成金的なイメージのあった入道だが、かなり印象が違ったのだ。
明石の君もここまで卑屈にならなくても・・・と思うが、それだけ源氏が気高いという事ね。
やっぱりこれは『源氏物語』なのだ、と改めて痛感した。
・ 入道像が段々はっきりとしてきて、源氏も明石に来て入道と出会い、須磨とは違った時を得て、心が満たされ惹かれていった。
・ 入道は、娘の婿にと強く望みながら源氏に仕えます。
源氏は、謹慎中の為勤行に励みますが、娘に対し心が微妙に揺れます。
気位の高い娘は、源氏を垣間見て身分違いを実感し、【ただなるよりはものあはれなり】。
三人それぞれの想いや心の動きが浮かび上がってきました。これからの展開が楽しみです。
・ 入道の「人となり」が見えてきました。
【行いさらぼえる】程勤行をしちゃうなんて、何だかヨガをやり過ぎて痩せ細った人を思い出しちゃう。
明石の君は、館の中に源氏が居る事を空気感でビリビリと感じている。でも、【身のほど知られて・・】自分には関係のない人と思う。
末摘花の様な究極のお姫様は、自分の身なり、容姿を考えたりしないのにね。
・ 入道と源氏、二人共自分の心の惑いを仏神に念じていました。
源氏の目を通した入道は、六十歳位で痩せた、昔の宮中を知る品のある、とても面白い人物でした。
二人で語る時間が増えましたが、一介の受領にとって源氏はあまりに高貴で恐れ多い貴族でした。入道の極端な卑屈さは、いかに階級社会が絶対的であったかを表しています。そして今回初めて登場した娘もそれが分かっています。源氏と自分を冷静に考える娘。同じ年頃の紫の上との愛情の形の違いを思いました。
物語が動き出す気配を短い文章のあちこちで読者に感じさせる筆の力に、又ドキドキしました。
2019年8月7日受講
【明石の館】続き P47~53
明石に移り、少し落ち着き、源氏は京へ手紙を書きました。手紙の使いは、まだ須磨に居たあの嵐の日にびしょ濡れで現れた男。手紙の宛先は【むつましき御祈りの師ども】、【さるべき所々】、そして【入道の宮】。【むつましき御祈りの師ども】とは信用できる祈祷師や陰陽師で自分のこれから先を占わせる為、【さるべき所々】とは東宮御所の王命婦、左大臣家等が考えられ、明石への移転を決して右大臣家に知られてはならない。【入道の宮】だけには、死ぬ程恐ろしかった経験を知らせました。そして紫の上には、【うち置きうち置き、おしのごひつつ】、別れ際に紫の上が歌った【鏡を見ても】が自分の【今はと世を思ひ離るる心】出家したい気持ちを押し止めてくれたと、心のままの想いを歌に。源氏の書き乱れた文字を【いと見まほしき側目なるを】、【いとこよなき御心ざしのほど】と供人達。彼らも手紙を言伝ました。
心細かった須磨と違い、晴れ渡った空の下、漁師は誇らしげで、人が多くて嫌だと思った明石に段々心惹かれる事が多く、心が慰められるのでした。
読後一言感想
・ 先生の解説を伺って、サッと一読した時には見えなかった源氏の姿と平安の人々の感性が感じられてきて、古語の面白さをつくづく思った段だった。
源氏の手紙を出す順番は、政治的にも重要な所から、次の入道の宮には全てを聞いてもらう少し甘えが入り、二条の院には、身悶えしながら・・・と、源氏の姿が良く見えた。
・ 短い文章の中にも、源氏物語がいかに骨太い作りになっているかを教えて頂けました。早々に歩くのではなく、一文にも、つまずきながら、目を凝らして読み解いていく素晴らしさを実感する事が出来ました。
本日のこの時間を頂けて、有難うございました。
・ 明石に来て少し気持ちが落ち着いた頃、京に便りを出す事にした。
東宮御所や左大臣家、次に入道の宮に、そして紫の上にも届けたのは、須磨での色々な出来事から明石に来る事になった事等、今はまだ夢の中に居る様で、このはっきりしないモヤモヤの気持ちの中で、出家を考えていたと告白する。ちょっとびっくりしたが、いざ出家となると、それは出来そうもなく、取り敢えずは今、明石に移った事だけは伝える事が出来た。
・ この部分、難しい文体だった。これが今の源氏の複雑な心情を表す為の作者の意図だとするならば、
やはり紫式部は天才作家である。不安から希望へと繋がっていく文脈、ほっとする最後だ。
・ 源氏は明石に慣れ、気持ちが落ち着いてきたので京へ転居したことを知らせます。
先ずは祈祷師(専属祈祷師がいたことを知り驚きました)、左大臣、東宮御所には冷静に【くはしく言ひつかはす】。入道の宮には【めづらかにて・・・】伝える。二条の院は【うち置きうち置きおしのごひつつ】【書き乱りたまへる】
須磨に蟄居してからの緊張、不安が一気にゆるみ恋慕の情が溢れます。心を許す人はこの世でただ一人。
・ 源氏が明石から京へ書いた手紙の順番は、最初に、これからの自分を占わせる為に信頼出来る祈祷師、左大臣、東宮御所(王命婦)、そして入道の宮。最後に感情を丸出しに書いたのは紫の上。その中で見せた自分の弱さ。須磨であれ程強がっていた源氏が初めて書いた【今はと世を思ひ離るる心】に、そんなに頑張っていたんだと、改めて心が揺さぶられました
2019年7月17日受講
【出迎え】続き【明石の館】P37~47
入道の申し出に、今までの神仏のお告げの様な多くの不思議な事に思いを巡らす源氏は、勅勘を被った身で、帝の子供でもある自分が、入道の様な訳の分からない田舎者に騙されて、しかも行ってはいけない機外の明石迄連れて行かれたと世の中の噂になったら、又本当の神の助けだったのに神の意向を断った物笑いの種になったら等々、ああでもないこうでもないと考えた結果、中国の故事、ひどい嵐で死にそうになった事、夢の中の父帝の【住吉の神の導きたまふままに、はや舟出して、この浦を去りね】で、明石行きを決意。
入道に返した返事、【知らぬ世界に、めづらしき愁への限り見つれど、・・・うれしき釣舟をなむ。かの浦に静やかに隠ろふべき隈はべりなむや】身分の低い者にこれ程気を遣う言葉選びをする源氏の品格の高さに驚き感動。【例の風が、飛ぶやうに】連れて来た明石の浜の賑わい、明け方の光の中で源氏を見た時の入道の【老忘れ、齢の延ぶるここち】。【月ごろの御住まひよりは、こよなくあきらかに、なつかし】い、屋敷の庭の景色、家の中の華やかな調度品は、都の高貴な人々が住む所々と比べても引けを取らず趣あるもの。
※【たてまつる】①尊敬⇒乗る、着る、食べる、飲む ②謙譲⇒相手を敬う
読後一言感想
・ 入道の迎えを【人のそしりもやすからざるべき】、又神の助けに背くのであれば【人笑はれなる目をや見む】と 思いを巡らし迷いながらも、【うれしき釣舟をなむ】と明石行きを決める。
明石は、【絵に描かば、心のいたり少なからむ絵師は描き及ぶまじと見ゆ】所だった。ひなびた須磨から、【ゆほびかなる明石】へと【見たてまつる】だけでも、人を【笑みさかえ】さす麗しい源氏の新しい生活が始まるのが楽しみです。
・ いよいよ源氏と明石の入道の出会いだ。入道の満面の笑み!!その喜びが想像以上のものだったと分かる。入道の、ただの田舎者、成金ではない人物像が、家のしつらい等から趣味の良い人だと分かる。
源氏も入道に出会えて嬉しかったであろう。
一人として同じキャラクターが出てこない源氏物語に、又魅力的な人物が登場した。期待大である。
・ 散々暴風雨に悩まされ苦悩している中、入道の迎えの舟が来る。
源氏はあれこれ考慮の上決断する。入道に導かれるまま明石に到着し、須磨との違いと、風情があり美しさに富んでいた入道の館が此処での生活の一歩になるのか。
・ 明石に行く事は源氏にとって大きな決断だ。
あれこれ迷った揚句、父帝の【ここを立ち去れ!】の夢に背を押される様に入道の迎えを受け入れる。
明石の地は、須磨のうら寂しい土地と異なり活気があった。
入道の財力があってこそ成す【艶にまばゆきさま】に源氏はべた誉めです。
・ 良清が伝えた入道への源氏の返しの上品なこと。入道はまずここで限りなく喜ぶ。更に【日やうやうさしあがりて】源氏の顔を【ほのかに見たてまつるより、老忘れ、齢延ぶるここちして、笑みさかえ・・】。入道は今まで財を成す事に一生懸命だったのでしょうが、これからは【月日の光を手に得たてまつりたるここちして】源氏のお世話に励む事でしょう。
・ 須磨は源氏にとって都と違い侘しく辛い場所でその上、天変地異のような暴風雨と落雷で家は悲惨な状況の中、源氏は【そしり】【人笑はれなる目】を気にして明石に移るか否かを非常に悩みます。
明石の入道は源氏の母桐壷更衣の従兄。親戚であっても階級が異なると別の世界の人?
源氏程の人でも自分の噂をとても気にします。
貴族社会の世間の噂について考え方を垣間見た感じがしました。
・ 人生のどん底で入道の誘いをどうするか?階級社会の中では有り得ない筋書きは、夢の中の亡き父帝の強い言葉と神仏への信仰から生まれ、例の風に運ばれ源氏は明石へ。まず、舟上の源氏の目から明石の浜を、その後入道の屋敷の様子を事細かく描き、その財と風情に感動。
明るくなり、源氏の顔を初めて見た入道の感動的な嬉しさの表現に心が温まり、良い人の様だと。
2019年6月5日受講
【父の声】【出迎え】
消えてしまった故院に、「一緒に連れて行って下さい」と打伏し泣く源氏。しばらくして見上げると、月の顔がまるで故院の顔の様に輝いていて、この様な悲しみのどん底の自分を助けに天空を飛んで来てくれた。こんなひどい天変地異のお陰で会えたと、心強く、心が満たされ、又会いたくて寝ますが全く眠れず、夜明けになりました。
渚に小舟を寄せ、二三人位の者が源氏の屋敷に現れ、明石の浦から前播磨の守の入道が、源氏を乗せようと舟を仕立てて来たので、良清に事情を話したいと。入道は、親しい間柄でしたが、私事で気まずい事があり、今は手紙すら交換しないのに、この天変地異の騒ぎの後に、会いたいとはどういう事かと驚く良清。
故院の「早く舟を出してこの浦を去れ」も思い合わせた源氏は、早く会うよう命令し、良清は舟に行き、入道に会いました。あれ程激しかった波風の中をやって来た事が良清には理解出来ません。
入道は、去る弥生一日祓えの日の夢に現れたおかしな者に、十三日に舟を整えて、雨風が止めば須磨の浦に舟を寄せろと言われ、試しに用意して待っていると、猛烈な雨風、雷が鳴り響き、中国にも、夢を信じて国を助けた話があり、この国の高貴な方々は自分の様な受領の夢など信じないでしょうが、お告げの日に舟を出すと、怪しい風が細く吹き、この浦に着いたのは神のお導きに違いないと。こちらでも、もしや思い当たる事がございましたでしょうか。大変恐れ多いけれど、この話を源氏様に申し上げて欲しいと言いました。良清は、その話をこっそり源氏に伝えました。
読後一言感想
・ 須磨の屋敷が混乱を極める中、疲れた源氏の夢に現れた故院。源氏は悲しみに沈むが、父が自分を気に掛けていてくれた事に嬉しさも感じる。【月の顔のみきらきらとして・・・】源氏の心の中と、ふと見上げた風景が重なって、父への想いがひしひしと伝わってくる。
夢は、良くも悪くも「気がかり」の心を映すものかもしれませんね。
・ 夢から覚めると、父の【御けはひとまれるここちして】、月の顔もきらきらとしている。
父が【助けに翔りたまへる】という想いを嬉しく思う源氏の所に、入道の迎えが導かれる様にやって来る。
いよいよ【明石】楽しみです。
・ 源氏の夢に現れた桐壺帝の言葉を成就するかの様に、渚に【小さやかなる舟】が現れる。
前の守新発意の言葉は、【明石の浦より・・・ことの心とり申さむ】と、歯切れが良い。
一方、私事で少し思うところのある良清は、【入道は、・・私にいささかあひ恨むことはべりて・・】
と、歯切れが悪く、これからの関係も面白そうだ。
・ 「夢」がキーワードになる一連のエピソード。源氏の夢と入道の夢が一致し、劇的な出会いが実現する。荒唐無稽に見える出来事も、夢が介在すると妙に納得できる。
小説家紫式部の力は、やはり凄いとしか言えない。
・ 【若紫】の「海龍王の后」の段を読み返してみる。
源氏の関心を引こうと、明石の浦で、前播磨の国守明石の入道が娘を最高位の身分の男に嫁がせようとしているという話をしたのが良清だった。その良清の前に、嵐の去った波打ち際に【小さやかなる舟】が現れ、入道は良清がいたらと、源氏への取り継ぎを頼む。良清の慌てふためく様が可笑しい。これからの明石の入道の娘の話の布石がちゃんとあったとは、式部は何という頭脳をしていたのでしょう。
・ 【月の顔のみきらきら】、【空の雲あはれにたなびけり】の夜、父の余韻が残る中源氏は、子供の様に父院を恋い慕いながらも、生きる力が湧いてきます。月の光の中、源氏の心の動きが鮮やかに浮かび上ってきます。 いよいよ父院のお告げにより、明石の入道の登場。これからが楽しみです。
・ 【須磨】の故院の御陵で雲に隠れた月が、今は【きらきらとして】。父が自分を忘れていなかった喜び。
【あやしき風細う吹き】は、風神の持つ袋の先の風を連想。
内裏から遠く離れた【須磨】と【明石】の天変地異を、当時の女性が、かくもリアルに描いた事は奇跡。
2019年5月8日受講
【父の声】
ようやく空も星が見える程広く晴れわたると、供人たちは源氏を元の寝殿に戻そうとしますが、大勢の人々が避難しにやって来て踏み歩いたので、寝殿の中は御簾等も皆倒れていました。夜が明けたら皆で主人を移そうと。源氏は、経文を唱えて祈りながら色々な事を考えています。月が出て来て、高潮が押し寄せた痕跡もあらわに見え、嵐の名残でまだ寄せ返す波が荒いのを、柴垣の戸を開けて源氏は眺めます。このあたりには占いであれやこれやと説き明かす陰陽師等も居ません。身分の低い漁師達が、源氏が居る所だと集まって来て、聞いても解らない多くの事を庶民の言葉で【さへづりあへ】喋り合うのも、有り得ない事だけれど、追い払う事も出来ません。「この風がもう少し止まなかったら、高潮が押し寄せて来て何も残っていなかっただろう。源氏様が祈り、神が助けてくれたのは大変なものだった」と漁師達が感謝するのを聞いても、とても心細い源氏は、自分も海の神のご加護に感謝する歌を詠みます。
一日中雨風と雷の騒ぎで気を強く対処していた源氏でしたが、ひどく疲れ、つい仮の御座所で物に寄りかかってうとうとしていました。すると、父桐壺院が正しく在位中の時の姿のまま目の前に立ち、「どうして、この様なむさくるしい所に居るのだ」と源氏の手を取って引き立て、「住吉の神がお導きになるままに、さっさと船出してこの浦を去れ」と言いました。源氏はとても嬉しくて「恐れ多いお姿にお別れして以来、様々悲しい事だけ多くございましたので、今はこの渚に命を捨ててしまおうかと思っております」と言うと、「とんでもない。この嵐はほんのちょっと事。大した事ではない。私は、帝であった時、道に外れる事をした事は無かったけれど、自分が知らず知らずの内に犯した罪があったので、その罪の償いを終わらせるのに忙しくて、この世をかえりみる事も出来なかったけれど、貴方がひどい難儀にあい苦しんでいるのを見るに見かねて、遠いあの世から海や渚を超えてここまでやって来てとても疲れてしまったけれど、このついでに帝に申し上げなければならない事があるので、急いで都へ行くつもりだ」と言って桐壺院は立ち去りました。
読後一言感想
・ 天変地異も収まりかけた時、源氏の夢に桐壺院が現れる。住吉の神やら、八百万の神に願をかけても直らなかった、荒れに荒れたこの物語の舞台をどう収めるのかと思ったところ、待っていました桐壺院!
これで源氏の運命も変わるのでしょうか?
運命が変わるとか、政治が動くとか、物語を大きく変えるのには、舞台上で雷の一つも落として、観客を驚かせないとね!式部さん、うまいなぁ!
・ 源氏の孤独は深まるばかり。思いがけず、まどろんでしまった源氏に桐壺院が現れる。
命を捨ててもいい、とまで思いつめた源氏は思いの丈を訴えるのだが、つい甘えてしまう。その気持ちも
分からないではない。とはいえ、故院の言葉には、ちょぴり笑えた。「お前に逢う為に、海に入って、渚に上がって、すっごく疲れたけれど・・・」。やっぱり笑えます。
・ ようやく静かになったかにみえたが、源氏はこれからの事を思うと不安でならなかった。
疲れ切ってウトウトしているところに、まさかの父が夢に現れ、住吉の神のお告げで早くここから去る様に・・・と嬉しいこと。夢とは言え恋焦がれた父に会え、嬉しかった。
・ 亡くなった人は、会いたいと思った時にいつでも会いに来てくれる。いつでも見守ってくれているのだ。そんな思いにさせてくれる、人間味溢れる場面だった、源氏と亡父との語らい。
・ 今回、内容より末端のところが気にかかりました。父院のあの世の様子も興味深かったですが、それ以上に気になったのは「海に入り、渚にのぼり」? 父院はなぜ直接源氏のところに来なかったのか。
古くは熊野の補陀落の話や沖縄では死者の霊を海から呼ぶこともあり、海から来たのではないか。
又、父院は「龍王」に会うため海に入り、住吉神社にお参りしてきたのではないかとの話も出ました。
【いたく極じにたれど】も意外でした。平安人のあの世への思いを少し垣間見た感じがしました。
・ 月の光で見えてきた嵐の爪痕と、澄み切った空に輝く星。
桐壺院の切れ目なくトントン流れ出る言葉に、せっかちな性格が現れ、思わず笑ってしまいました。
突然現れた父親に対し、自分の裏切りは全て忘れ、幼い子供の様にただただ嬉しかった源氏でした。
2019年4月3日受講
【落雷】
【かくしつつ世は尽きぬべきにや】と思う程の1日だったのに、その翌日の夜明け前から更に風は強く吹き、海水は高まり、波の音が荒く、まるで岩も山も崩されてしまいそう。雷が鳴り稲妻が光り、皆うろたえるばかり。供人が「どんな罪を犯してこの様な悲しい目に会うのだ。家族の顔も見ないで死んでしまうに違いない」と嘆くのを聞き、源氏は気持ちを静めて、無実の自分がこの海岸で溺れ死ぬ事など無いと強く自分に言い聞かせるけれど、皆の動揺が治まらないので住吉の神に大願を立てました。それを見た供人一人一人は、自分の命はおいても、有り得ないこの天変地異で源氏が死んでしまう事はとても悲しいと、気持ちを奮い立たせ、源氏の身だけを救わなくてはと皆が揃って仏神に祈願しました。「宮中で養われ、様々な楽しみに思い上がり得意になったお方ですが、深い慈愛で、広く苦しい境遇の人々を助けたのに、今、どうしてこの様な非道な波風に溺れなければならないというのか、天地よ、その訳を説明して下さい。罪なくて罪になり、官、位を取られ、家を離れ、都を去って、この須磨で嘆いていたのに、この様な目迄にあい、命が尽きてしまいそうになるのは、前世の報いか、この世の罪か、神仏がいらっしゃるものならば、この嘆きをなくして穏やかにして欲しい」と、御社の方に向かい、様々な願を立て、海の中の龍王や、沢山の神々にも願を立てさせると、それに呼応するかの様に、雷は鳴りとどろき、源氏が住んでいる所に続く廊に落ち、炎が燃え上がり廊は焼けました。そこに居る皆が動転し、大炊殿(下人が食事を作る場所)に源氏を移し、身分の上下なくごった返し、大声を上げてうるさく泣き騒ぐ声は、雷の音にも劣りません。空は墨をすった様で、日も暮れたのでした。
読後一言感想
・ 本の読みに入る前に、小学6年生の国語の教科書に載っているドナルドキーンのエッセイ
「かなえられた願いー日本人になること」を読みました。
日本人より日本人らしいキーンさんの文を読む小学生が羨ましい。
今回は、天変地異の恐ろしさと神にお願いするシーンはリアルでした。
・ 【かくしつつ世は尽きぬべきにや】と思う程の風雨の中で、惑い祈願する人々の姿が鮮やかに目に浮かぶ、式部の文章の素晴らしさを感じる箇所でした。
【空は墨をすりたるやうにて】の表現も美しく、その色の深さ、その場の雰囲気をも感じさせる。
・ 正に「この世の終わり」を思わせる事態に、泣き叫ぶ供人たち。
トントンと調子のよい文章が小気味よい。それでも落雷で源氏の寝殿は使えなくなる。
これまで立ち入った事もない【大炊殿】に避難した源氏の姿を想像すると、ちょっぴり笑える。
・ 【・・前の世の報いか、この世の犯しか・・・】
と住吉の神やよろづの神に願を立てると余計悪天候となり、遂に落雷により廊が火事になります。
天変地異の様な時、人々の想いや右往左往する様子がリアルに描かれ、叫びや泣き声、祈りの声が聞こえ
てきました。 神は、何にお怒りだったのでしょうか? 源氏に? それとも・・・
・ いよいよ【風いみじう吹き】供人は源氏を守ろうと【仏神を念じたてまつる】
ここからは、はるみさんに祝詞風に読んでもらう。すると確かに神社での祝詞だ。祝詞を上げているうち
に、供人の気持ちがどんどん高まり、【天地ことわりたまへ。罪なくて罪にあたり、宮、位を取られ】と、スピード感が増してゆく。声に出して読みたい場面であった。
・ 雷、風、波の音、雷の音にも劣らない【いとらうがはしく泣きとよむ声】。
白い高波、稲妻、燃え上がる炎、墨をすった様な空の色。臨場感溢れる音と色の世界。
仏神への祈りの言葉は、祝詞の様に源氏の出生から始まり、滑らかに最後の【この愁へやすめたまへ】
落ちた雷で廊が焼け、【心魂なくて、ある限りまどふ】人々に日も暮れ。
原文からひろがる源氏物語
2019年2月6日受講 明石
【都の使者】
相変わらず雨風は止まず、雷鳴が静まらないで何日にもなり、これまでもこれから先も悲しい自分に、今まで気丈に振舞って来たけれどそれももう出来ず、どうにもならない源氏。この様な状況で藤原伊周の様に都へ帰るのも物笑いになる事だろう、これよりも深い山の中を求めて身を隠しそうと思っても、波風が怖くて隠れた等と後の世まで軽率な名を世間に流してしまうと悩みます。夢にも、あの誰とも分からない全く同じ人物だけが何回も出てつきまとうのでした。風雨に明け暮れる日が多くなるにつれて、京の方も心配でたまらなく、【かくながら身をはふらかしつるにや】こうして見捨てられ朽ち果てるしかないのかと心細く思いますが、【頭さし出づべくもあらぬ】自分の頭も外に出せない空の乱れに、やって来る人もありません。
ところが、何と二条の院から、矢鱈に妙な姿で、【そほち】ずぶ濡れの使者がやって来ました。道で会っても人だか何だか分からない、まずは追い払わなければならない身分の低い男を、親しく可哀想だと思うのも我ながら【かたじけなく】もったいなく、卑屈になってしまった自分の気持ちを思い知らされる源氏です。紫の上からの文は、ちょっとの間も雨が止まない空模様に、ますます(私の心だけでなく)空までも閉じ塞がる気がして、どうしようもなく眺めやっていますと、
貴方様のおられる須磨の浦の風がどの様に吹いているか遠くから思うと
涙で袖が濡れ、【波間なき】涙が止まる間がありません
辛く悲しい色々な話が書き集めてあり、手紙を開けると同時に更に【汀まさりぬる】一層涙がとめどなく流れた様で、文字が涙で【かきくらすここち】ぼんやりした様に源氏は思いました。「京でも、この雨風は不吉なたたりだと、仁王会(三月と七月に宮中で国家鎮護・七難即滅の為の帝主催の大規模に行われる祭祀で臨時もある)など行うべきだと聞いております。内裏に参上する上達部なども、全ての【道とぢて】道が役割をなさないので行けず、政治も止まっております」など、使者は、ぼそぼそと、【かたくなしう】不格好にみっともなく話しましたが、源氏は京の方面の事と思うと【いぶかしうて】色々聞きたくて、使者を御前に召し出し聞きました。「京でも同じように雨は降り止まず、風は時々吹いて、何日かの間過ぎたのを、今までに無い事だと驚きました。しかし、こんな風に、【地の底徹るばかり】地面を突き通す位の氷が降り、雷がずっと鳴っている事はありません」など、須磨の大変な天候に驚き怯えている表情が、もっと辛そうなのにも、源氏を含め皆がいよいよ心細くなってくるのでした。
読後一言感想
・ 二条の院から使者が来る。
【あやしき姿にて、そほち参れる】そほち・・濡れそぼって という事は、きっと使者は小柄な貧相な男だったのね! 濡れそぼってって言葉は、もともと、可哀そうな感じのものに使うわよね。子犬とか。
屈強な男だったら、ずぶ濡れって感じ。だから、源氏は使者の姿を見て、思わず【むつましうあはれに】おぼされたのね。
【我ながらかたじけなく】って、遠くから来てくれて申し訳ないって事かと思った。
みんなが平民の今ではピンとこないなぁ。
・ まるで天変地異の様な嵐の中、二条院(紫の上)からの文が届く。
ビチャビチャで濡れ鼠の様な使者から京の様子を聞く源氏。
そりゃ【心細さぞまさりける】よね。
・ 【心細さぞまさりける】の文の文末に敬語がない事が話題となった。
雨風・氷雨(ひょうう)・雷(いかづち)が止まない恐ろしい状況が主語という結論となり、
頭が働く勉強が出来ました。
・ 今日から【明石】に入りました。
【須磨】の巻に引き続き、天候の荒れた、心細い状況から【明石】の巻が始まりました。
物語の展開としては、まだ何も始まっていないので、早く次へ読み進めたいです。
願はくば、もう少し読みに集中して次を読みたいです。もっと、どんどん読みたいです。
・ 【明石】は【なほ雨風やまず】で始まり、【須磨】の続きでした。
【人か何ぞとだに御覧じわくべくもあらず】人間とは思えない賎しい風態の【そほち】ずぶ濡れの使者に同情する自分をわれながら【かたじけなく、屈しにける心】を自覚した源氏。紫の上と繋がれた喜びの涙。
2018年12月5日受講 須磨
【三位中将来訪】
馬を見た中将、飛鳥井(催馬楽の一つ)を朗詠し、泣いたり笑ったりしながら、源氏不在の若君の悲しさ、左大臣の嘆き等都の出来事を語り、源氏は耐え難い。二人の話は尽きず、一晩中漢詩を作り合いました。世間の噂を気にし、中将は急いで帰ろうと。別れが辛く、かえって会わなければ良かったと思います。素焼きの盃を回し飲みながら、白楽天の白氏文集の詩の一節【酔悲灑涙春盃裏】を、声を合わせて朗詠し、源氏のお供の者も、あまりに短い別れを惜しんで皆涙を流します。
ほのぼのと明るくなった朝の空に雁が都のある北の方に渡って行くのを見て源氏、
都をいつかの春に行って見たいものだ 羨ましいのは北へ、都へ帰る雁(貴方)よ それに対し中将、
名残惜しくて、須磨の地を立って別れても、花の都へ行く道が分からなくなるかもしれない と。
中将の土産は都風の物。有難い訪問のお返しに源氏は一頭の立派な黒駒を差し上げ、「勅勘(天皇の命令による勘当)の自分からの品は忌まわしいでしょうが、この馬は、風に当たればいななき勇んで故郷をめざすので迷わず都に行き着きます」と。中将は「私の思い出を懐かしんで下さい」と名のある笛等を。
それ以外、人目に立って疑われる様な事は互いに何もしませんでした。と語り手。
次第に日は高くなり、中将が名残惜しく振り返りながら出発するのを、見送る源氏は悲しくて、かえって会わなければ良かったと。中将が「いつ又お会い出来るでしょう。このまま会えなくなることはありませんよね」と言うと、源氏は、
「宮中の近くにいる貴方も空をご覧なさい 私は一点の曇りのない無実の身ですよ この様な罪をかぶってしまった人は、昔の菅原道真の様な人でさえ、すんなりと宮中に復帰する事は難しかったのに、どうして私が都に又戻りたいと思う事がありましょう」 と強く言い放ちます。 それに対し中将は、
頼りにする貴方様が居ない宮中に一人寝て私は声をあげて泣きます 一緒に翼を並べた友を恋しく思いながら 勿体無くも帝の御子の貴方様と親しくさせて頂いて、それが当たり前だと思った事を後悔しています」と、しっとりとした気持ちもなく帰ってしまい、悲しく源氏は物思いにふけり日を暮らしました。
読後一言感想
・ やっと会えた源氏と宰相であるが、宮中での立場もある宰相であるから、一晩語り明かした後は、
【ものの聞こえをつつみて】急ぎ帰る。やはり常識的またバランスのとれた性格の宰相である。しかし、
二人は何事も競い合い、じゃれ合って育った様なものだから、別れ際には、道真だって帰れなかったのだから、私も【都のさかひをまた見むとなむ思ひはべらぬ】と気持ちをぶつけ、宰相も【かたじけなく馴れきこえはべりて・・・】と、帝の御子と親しくさせて頂いたが、と嫌みを言わせる式部は、男同士の心の機微もよく承知している。
・ 突然の出会いと別れは、嬉しいのに、お互いの立場から別れの際は複雑だった。
盃を回し飲みし、白氏文集の一節を朗詠する等、始終和やかだったのに、突然の帰京を切り出され、その別れの寂しさから口走った売り言葉に買い言葉の様な言い合いになり、中将は立ち去ってしまい、残された源氏の何とも言えない寂しさは、一層深く沈んでいった様だった。
・ いつ都に戻れるか分からない、果たして帰れるものなのかも分からない源氏。一方の中将は、己の立場もあって長居は出来ない。久々に会えた喜びは尽きないが、でも、たった一晩で帰っちゃうの!?
【うらやましきは帰るかりがね】と詠う源氏の気持ち、よく分かるなぁ。それにしても、売り言葉に買い言葉の様な別れ方。互いにちょっとシコリの様な物を抱えつつ、須磨と都で暮らすのね。
・ 【いとなかなかなり】いっそ来なければ良かった、会わなければ良かった という言葉がこの短い文章の中に二回も出てくる。複雑な心情を見事に表している。再会の喜びも束の間、別れの悲しみがやってくる。自分を置いて都へ帰ってしまう中将にスネる源氏。中将も皮肉を投げつける。
友情で結ばれた男同士のやり取りが熱い。胸に沁みる。
・ 久し振りの頭中将との再会で、離れていた時間を取り戻す様に【終夜まどろまず】、翌朝には、互いに離れ難い思いの辛い別れ。親友同士の多少の言葉のすれ違い。【いとなかなかなり】、【いとど悲しうながめ暮らしたまふ】。中将が都に帰った後、須磨に残った源氏の孤独と寂寥感が心に迫って来ます。
・ 中将と源氏との再会。ライバルだった若い二人を思い出しながら、母親みたいに温かく見守れた場面。
2018年11月7日受講
【三位中将来訪】
須磨の侘び住まいも一年。都が恋しくてたまらない源氏の下へ親友の中将が訪ねて来る。
中将も源氏不在の都を味気なく思っていて、罪人になる覚悟で、須磨を訪ねたのだった。読者の目には唯の貧しい住居だった住居が、中将の目には風情あるものに。服装も、田舎風に装っているが、やはり源氏はセンスが良い。源氏は、土地の海産物などで中将をもてなし、折しもやって来た漁師の話を聞き、二人して珍しい体験をする。仲の良い二人が親交を深める、心温まる場面であった。
読後一言感想
・ 須磨に来た時に植えた桜の若木が花ほころばせ、あぁ、一年が経ったのだ・・・と孤独を深める源氏。
七年前の春の日の「花宴」を思い出す。そんな時、中将が訪ねて来る。唐風の簡素な住まい、海士たちと
の交流など、全てが珍しく、興味は尽きない。 こんな処に追われても、源氏らしい美意識は健在だ!
とばかり目を輝かせる中将が微笑ましい。友情は、厚いなぁ。
・ 【桜ほのかに咲きそめる】のを見ると、【いつとなく大宮人の恋しきに桜かざしし今日も来にけり】と
素直に懐かしく、京の人達との交わりを思い出す。そこに同じ様に源氏を恋しく思う中将が【罪にあたるともいかがはせむ】と訪ねて来る。田舎びた住居、調度などを【めづらかにをかし】。そして、源氏の姿を【見るに笑まれてきよらなり】と再会を喜ぶ中将の友情の深さ、優しさが感じられる。
・ 陽気が良くなり、つれづれなる時、桜を見て都の「花の宴」を思い出し、源氏の心は複雑だった。
そんな折、中将が現れた。中将も世間にこの事が分かってしまうと大変な事になることを承知の上、会いに来てくれた。源氏の須磨での生活を見て、それは「郷に入っては郷に従え」の様に映った。都の華やかな生活しか知らない二人は、須磨という地の何もかもが珍しい。
源氏が都から居なくなり、中将の心にポッカリ穴が空いたのだ。この穴は埋められるのだろうか。
・ 須磨にも新しい年が巡って来る。
【植ゑし若木の桜ほのかに咲きそめて】と桜を見て、良かった時代を思い出す。読んでいる私達でさえ、
桐壺の御代は良かったと、文化の花が咲いた明るい内裏を思い出す位だから、源氏はいかばかりか。
そこへ、三位の中将がやって来る。珍しそうに源氏の暮らしを見る。同じ感性を持っている友に会えるのは、嬉しかっただろうね。今は中将も生き難い時代みたいだしね。
・ 今回は、源氏の須磨の侘び住まいに頭中将が訪れる場面を読みました。源氏はもう一年も須磨に。
都に居た時と、まず服装が違う。中将の目から見ると【山がつめき】た格好なのだけれど、それでも同時
に源氏はやはり【きよら】に見える。中将にはそう思える源氏は、やはり本物の美しい人なのだと感じま
した。又、源氏の住まいは【唐めい】ている。前に、平安時代には貴族達は菊の栽培に熱中していて、そ
れは、大正時代に西洋渡りのバラの栽培が流行したのと同じく、とてもハイカラな、モダンな趣味だった
のでは。という本を読んだ事があったのを思い出しました。唐めいた家というのは、大層モダンな感じを
平安時代の人は抱いたのかもしれません。それを、頭中将を登場させて語らせるところに、複数の視点を
用意して、場面を多面化する、紫式部の技量に感心します。一体何故、小説の無い時代にこの様な技術を
得たのでしょう。
・ 源氏は須磨に来て二年目。日々孤独の中、折に触れて都を恋しく思い【うち泣きたまふをり多かり】。
右大臣家を恐れて手紙を送る人もいない時、三位の中将は、源氏を想い【罪あたるとも】と決意をして
須磨を訪れ、涙の再会をします。中将の勇気、心の強さ、温かい人間性を感じました。
二人は、ライバルであり、恋敵であり、無二の親友!!
・ 前回では、良清が【若紫】で明石を語った場面が思い出され、明石入道は【桐壺】の更衣を語り、
そして今回、二月二十日あまりの須磨で、源氏は【花宴】で【紅葉賀】の青海波の舞を覚えていた東宮に求められ、桜をかざして【けしきばかり舞ひたまへる】を、その後舞った中将に桐壺帝が【御衣たまはり】の場面を思い出して歌を詠んだのだと。そしたら中将が須磨にやって来た。【紅葉賀】と【花宴】には、源氏と頭中将の輝かしい青春が詰まっていて懐かしく、あの典侍をめぐる取っ組み合いを読み返すと笑えました。式部の頭の中には、今までの物語の一つ一つの場面が映像化されている様で驚きました。
原文からひろがる源氏物語 須磨
2018年10月3日受講
【明石入道一家】
須磨から明石迄は【ただはひわたるほど】歩いて行ける程。【若紫】で、明石と明石入道を語った播磨
国司の息子良清は、明石の姫に文を出しますが、明石入道から連絡が。それを良清は無視。【世のひがもの】変わり者の明石入道の途方もない志の高い考えでは、娘婿は播磨の国司の息子などでは満足出来ない。妻に「源氏様が須磨に居ると聞き、何とかしてこの機会に娘を差し上げたい」と。妻「とんでもない!京の噂では、身分の高い妻が多く、その上隠れて帝の妻にまで内通し浮名を流している人が、この様な田舎者の娘を心に留めるわけがない」と。入道「考えている事があるからその心づもりで。機会があったら此処にも招きたい」と、ぼそぼそ小さい声で。彼は家の中を目が眩む程に飾り、娘を玉のように大切に育てて。
妻「いくら素晴らしい人でも、わざわざ罪になり流された人を婿には選べないし、冗談でも自分たちの娘などにその様な人が心を留める筈が無い」と。それに対し入道「唐にも我が国朝廷にも抜きん出て、何事にも人と違う格別の人には必ずこの様な事はある。そもそも、源氏様の亡くなった母上は叔父の按察使の大納言の娘。人並み外れて優れて評判高く宮中へお仕えし、帝が、比べ様がない位の特別な愛情を注いだ事で、他の人に嫉妬されて亡くなったけれど、源氏様を残した。私がこの様な田舎者だと言って源氏様が娘を見捨てる事はあるまい」と。娘は、素晴らしい美人ではないが、優しく気品があり、都の身分のある人に劣らず、受領の娘という我が身の境遇を不甲斐ないと悟っていて、身分の高い人は自分を物の数にも入れないだろうが、身分相応な結婚は決してせず、親に先立たれたら、尼にもなり、海の底にも入ろうと。父親は、年に二度大阪の住吉神社に娘を詣でさせ、神のご利益を密かに拠り所に。
※ 明石入道一家については、【若紫】頁14~24に。その後すぐ若紫が登場しています。
読後一言感想
・ 明石入道の家では、源氏に会う以前より縁を結ぼうと画策する入道がその思いを語る。現実的な視点を持つ母君、【ほどにつけたる世をばさらに見じ】と思いながらも【高き人はわれを何の数にもおぼさじ】と、自身の立場を冷静に見ている娘。三人三様の思いから、それぞれの人柄が現れる場面でした。
・ 明石の入道が語る、従妹の【桐壺の更衣】の出世話。正にこの大長編【源氏物語】の冒頭部分である。【すぐれて時めかしたまふこと並びなかりけるほどに・・・】と、表現も殆ど同じだ。
このあたりは、紫式部の天才的な手法であり、物語の始まりのトキメキを思い出させてくれる。
・ 源氏は、須磨で不遇をかこっている、その一方で、場面は明石入道一家の紹介が行われます。
思い込みの激し過ぎる明石入道、冷静で常識をわきまえた入道の妻、娘の明石の君は「父の娘」らしく、
身分相応の男としか結婚出来ないなら、尼になった方がマシ、海に入った方がマシ、と頑なになっています。同時に、高貴な人が自分などに目を止める訳ないでしょ、と、母譲りの常識をちらりと見せている。
はてさて、この先どうなってゆく事か、先が楽しみです。
・ ついに明石の入道の一家が現れる。
入道は、【「女は心高くつかふべきものなり。おのれ、かかる田舎人なりとて、おぼし捨てじ」など言いゐたり】この【言いゐたり】と自信を持って言い切るポジティブな考え方が、今でも昔でもやっぱり運を引き寄せるんだね。娘は、父親が家を【まばゆきまでしつらひ】、娘に【かしづきける】迷いの無い姿を見て育ったせいか、父の思いに添おうとする。けなげだ!!
・ 須磨で源氏がとことん落ち込んでいる頃、一方、お隣の明石では、入道が愛娘に“チャンス到来”とばかり興奮していた。【若紫】で良清が語った明石入道とその娘。
いよいよ待ちに待った登場ですね。
・ 明石の入道一家は、入道の娘の結婚に三者三様の様だったが、本人はさて置き、父親と母親の考え方の
違いがある様な気がした。父の気持ちは、兎に角高貴な志の高い男。母の気持ちは、身分の差を強調。娘
の気持ちは、父の影響を多分に受けているので、高貴な男性以外は問題外なので、父親と同じかな。
だとしたら、源氏はぴったりという事かしら。
・ 明石が畿外であり、今の源氏が行ってはいけない場所であった事。明石入道一家の人柄を各自の言葉で、妻との力関係もリアルに表現。次々に明らかになる物語の筋との繋がり!桐壺の更衣が入道の従妹!
山の中で育った若紫と教養人として育った明石の君とのこれからの振る舞いが楽しみに。
?
2018年9月5日受講
【冬の須磨】
住み始めてから一年近くの須磨の暮らしに源氏は段々耐え切れなくなり、こんな所に二条の院の姫君を連れて来るのは全く無理な事だと改めて思います。都では知る筈もない身分の低い者の暮らしにも馴染めなく、呆れる程に耐えている自分が、恐れ多く勿体無いと、自分を慰めます。歌の中の【海士の塩】を焼く煙だとずっと思っていた煙は、後ろの山に薪という物を燻している煙だと知り、新鮮に感じて歌います。
山人が粗末な家で燃やす柴の煙の様に、都からの度々の便りを私に運んでくれないか里人よ
冬になり、雪が降り天気が荒れた空の様子を眺め、良清に歌を、惟光に横笛を吹かせ、源氏は七弦琴を弾きました。気持ちのままに弾く源氏の琴の音に、歌や笛を止め、それを聴きながら皆涙をぬぐい合いました。
昔、漢の元帝に胡の国(今のモンゴル)の后として遣わされた王昭君を源氏は思い、自分は元帝の切なさには到底及ばないが、今の状況では恋しい二条の女君をその様に手放す事も有るかもしれないと不吉で、王昭君を歌った一節【霜の後の夢】と口ずさみました。月の光は大層明るく屋敷の奥の方まで入り、山の端に入る光は寂しげに見え、菅原道真が詠んだ【唯是西に行く左遷ならじ】月はただ真っ直ぐに動いて行くだけで左遷とは関係ない の【ただこれ西に行くなり】と独り言を言い。そして歌います。
どこの雲の中の路に菅原道真と同じ様に私も迷ったのだろう この姿を月に見られ事も恥ずかしい
何時もの様に、眠れない暁の空に、多くの鳥がしみじみ心を動かされる様に鳴くのを聞き、更に歌います。
群れている多くの鳥が一緒に鳴く暁は 一人で目が覚める寝床も、千鳥が励ましてくれる様で頼もしい 夜更けに手や顔を洗い清め経を唱える源氏も、供人には新鮮で素晴らしく、実家にも帰りませんでした。
読後一言感想
・【めざましうかたじけなう】普段は下々と接する事がない源氏が、須磨の生活で下々の様子を見る。
目障りで、それを見なければいけない自分が、「もったいない」と感じる。その境地が微妙で興味深い。
貴人でもない私達には、すんなりと受け入れられない心境だが、イメージを膨らませて理解したいものだ。
と思う。
・ 春先に須磨に流されて来た源氏が、この地で初めての冬を迎える場面を読みました。
孤独を支えてくれるものは、身に培った教養であると、改めて感じました。
冬の深更から暁まで、ずっと月の進行と対面している事は、実にステキだと思います。
海辺の開かれた部屋で、月の動きをずっと見ながら過ごしてみたくなりました。
・【え念じ過ぐすまじうおぼえ】る 場所にいる源氏は、まどろまれぬ夜を過ごす日々。
孤独とやるせない気持ちを、【ただこれ西に行くなり】の言葉が支えている様に思えた。
いづかたの雲路にわれもまよひなむ 月みるらむこともはづかし の歌が美しい。
・ 下人や山人を見下す訳ではないけれど、高貴な源氏にとってやはり須磨の暮らしは応える。
これまで知る必要すらなかった、下々の暮らしぶりを目にする事のうっとうしさ。煩わしさ。「これが当
たり前の階級意識だった」と先生。その辺をきっぱりと解って読まないと・・・・と改めて思った。
王昭君にしろ、菅原道真にしろ、教養が無いと孤独も語れないのね。
・ 源氏の須磨での生活(侘び住まい)は上人も下人も住んでいる、住み分けの無いものだから、それを実
感している源氏は、【かたじけなう】と思う。又実際にあった史実を折に触れ物語に組み込む事など、
式部ならではと思う。今回、王昭君・菅原道真は特に良かった。
・荒涼とした寂しい須磨の冬。
二条の姫君を思いめぐらせながら王昭君の【霜の後の夢】そして道真の【ただ西に行くなり】を切々とし
た感情で口ずさみます。煌々とした月の光に照らされる心の中。
冬の冷たく澄んだ空気の中、孤独や不安と寂寥感が迫ってきました。
・ 【めざましうかたじけなう】が表す当時の貴族の意識を初めて知り、【夕顔】の五条の家のあの冒険は、
若い源氏にとって、それはそれは物凄い体験だった事を知りました。
秋から冬に移る景色の変化、煙や月で空気の透明さが感じられ、そこに【和漢朗詠集】の王昭君や菅原道真の【菅家後集】を添えて、格調高い夜を表す式部の知識、そして月の美しさに又々ため息。
2018年8月1日受講
【弘徽殿の一言】
都では、日が経つにつれて、帝が先頭になって源氏を恋しく思う機会が多くなりました。春宮(八~九歳)は、言うまでもなく毎日毎日源氏を思い出して、こっそり泣いているのを見る乳母、まして(唯一春宮の出生を知る)王命婦はとても可愛そうだと思っていました。入道の宮(藤壺)は、春宮のこれから先に不吉で嫌な事が起こりそうだと悪い事だけを考えて、源氏もこのように落ちぶれて情けない身となってしまった事を大層嘆いていました。源氏の異母兄弟達で、心を通わせていた上級貴族などは、最初の内は、相手を慰める手紙や贈り物等の交流がありました。当時流行った漢詩作りの手紙の交換をし、その事についても宮中の声が源氏の素晴らしさだけになると、弘徽殿の女御がそれを聞いて、ものすごく変だと言いました。「朝廷から咎めを受けている源氏の様な人は、勝手気ままに貴族が楽しむ音楽や詩の趣を知る事は有り得ないでしょう。須磨に贅沢な屋敷を構え、主流の右大臣一派を非難して、あの司馬遷の【史記】P-143の、鹿を見て馬だと言い追従した者の話の様に、間違っている源氏に皆がおべっかを使っているのです」等、悪い噂が聞こえて来て、上級貴族達は、面倒でいやだと、ぷっつり源氏に文を届ける人が無くなりました。
二条の院の紫の上は、半年過ぎる間に、気持ちが晴れる時はありませんでした。源氏付きの女房たちも、皆西の対に移って来た最初は、紫の上を、どうせ大した者ではないと思っていましたが、世話をし、馴れていくうちに、彼女の優しく美しい容姿や態度、真面目で誠実な心遣いも、気遣い深く愛情豊かだったので、屋敷から去って行く者も居ませんでした。家柄の良い女房たちは、紫の上の姿をちらっと見る事も出来ました。沢山の女君たちの中で、源氏が紫の上にとりわけ深い愛情を持っているのは当然だと、女房たちは納得しました。
読後一言感想
・ 【弘徽殿の一言】は、口調からして【いみじうのたまひけり】(許せないと怒っている)というのが良く分かり面白い。弘徽殿は、鹿を馬と言う様に源氏に追従している人に対して腹を立てているのだが、【史記】の中の趙高は、自分に追従する者を選んだ様だが、きっと企てた乱は失敗した事だろう。
弘徽殿の言葉は、二回目でしょうか。怒っている声が聞こえてきそうである。
・ 久々に登場した弘徽殿。嬉しい!
その一言は、まっとうであり、后の宮の怒りは良く分かる。「須磨の地で反省してるんじゃないの!」と。
右大臣家を牛耳っているのは、やっぱり弘徽殿なのよね。
一方、紫の上は、二条院の女主人として、そつなく日々を送る。須磨の源氏の暮らしの中に、ちょっと顔を見せた二人の女性。読者の気持ちにも応える、今回のちょっと出、上手いんですよね、式部さんは。
・ 源氏の居ない都では母二人が戦っています。
秘密が漏れる事を恐れながら、春宮を次期帝に即位させる為に思い悩む入道の宮。
現体制を強く支える事により、帝を擁護する弘徽殿。
必死に我が子を守ろうとする二人。子を思う母の強引さと共に切なさを感じました。
・ 弘徽殿の面白くない事
自分の価値観に値しない源氏に腹を立てている弘徽殿は、非難攻撃をする。それぞれ源氏と交流のあった人々との間も絶たれてゆく。「謹慎」とは、【この世のあぢはひをだに知ること】が出来ない所に、外との交わりを絶ち反省する日々を送る事であるのに、何たる事。
ここで人々との交流は絶たれてしまった。又寂しい日々が来るのかな。
・ 源氏不在の都の女達の時間は流れ、
春宮の事を【ゆゆしうのみおぼす】入道の宮は変わらず。
久し振りに登場した弘徽殿の、【朝廷の勘事なる人】についての正統な考えにブレは全くない。
紫の上は、前よりも立派な女主人に成長して。
そして、源氏と都との繋がりは再び弘徽殿の一言で絶たれてしまいました。
須磨 2018年7月4日受講
【海路のあいさつ】
その頃、(太宰府の長官の次の地位の)大弐が四年の任期を終え上京中でした。船で浦に添って来ると、他よりも風光明媚な須磨に心が惹かれ、此処に源氏が 住んでいると聞くと、若い娘達は、船の中でさえドキドキします。まして源氏と恋仲だった、【花散里】P-221の筑紫の五節(通説:源氏と恋に落ち、源氏が取立てで父親が大弐に)は、ここで船を停めて欲しいと願い、琴の音が風に乗って遠くから聞こえて来ると、周りの景色、源氏の事、七弦琴の音の心細さが一つになって、風流のある者は皆泣きました。大弐は源氏に、筑紫の国から都に戻り、まず出来るだけ早く貴方様にお伺いして、四年間留守の間の都の出来事も聞けると思っておりました。けれども、今の状況では、お会い出来ません。このまま通り過ぎる事を許して下さい。改めてお会いしたい。と、【はべる】を多用した、とてもとても丁重な手紙を書きました。
大弐の子の筑前の守が、父の代理として手紙を持って源氏の屋敷を訪問しました。筑前の守は源氏の働きで六位の蔵人に抜擢された人なので、本当に悲しいけれど、人目を考えて、すぐに帰ります。源氏は、「都を離れてから後、昔親しかった人々に会うことが難しくなっていたのに、このようにわざわざ立ち寄って頂きました」と答えました。筑前の守は、泣きながら帰り、源氏の様子を話すと、父親をはじめ、都から迎えに来た人々の吠える様に泣く声であたりは満ち溢れました。娘の五節は、こっそりどうにかして源氏に手紙を届けました。
貴方様の琴の音に引き止められた引き船の手綱の様な 思い迷う私の心を貴方は知らないでしょうね
私から手紙を出すのは色好みらしいけれど、大目に見てね。 と書きました。
源氏は、五節を思い出し、【ほほゑみて】その手紙を読みました。その様子は、気後れする位華やいで見えました。と、語り手。
私を思う気持ちがあって、綱を引くのをためらうならば、このまま須磨の浦波を通り過ぎるでしょうかね
一緒に漁をして暮らすとは思いませんか とありました。
菅原道真が大宰府に向かう途中、それを嘆いている明石の駅長に自分の歌を贈り感動させた故事もありますが、五節は感動して、なお一層此処に居残ってしまいたいと思うのでした。
読後一言感想
・ 五節の君が可愛い。【たゆたふ心】・・・可愛い。【人なとがめそ】・・・可愛い。
一方、源氏は品性がある。やっぱりね。人を怨んだり、悪く見たりしない。
ま、品性はなかなか身につくものではないから、生まれが重要。
やっぱりね。
・ 今回の【海路のあいさつ】は、難解だったかな?
父は、都の情報と自分の状況を考えての手紙を、息子を使者にして届け、
娘の五節は、自分の想いを源氏に伝える事で、気持ちは伝わった。
【ほほゑみて見たまふ、いとはづかしげなり】は、難解でした。
・ 任期を終えて京へ帰る大弐の一行が須磨を通る。
恩人である源氏が、この須磨に居る事を知り、訪ねずに通り過ぎる訳にはいかない大弐は、源氏に手紙を送る。言い訳の手紙であるせいか、【所狭さを思ひたまへ憚りはべることどもはべりて・・・】と、歯切れが悪い。でも源氏は、立ち寄ってくれた事を喜ぶ。素直な人だ。
一方娘の五節の君は、素直に自分の気持ちを歌にする。可愛い歌である。
それに対し、源氏のからかう様な変化も、またいい。
・ 前回は須磨から海を、今回は海から須磨を眺める。遠くから琴の音が風に乗って海の上迄届く。
これから都へ帰る大弐の、難しい政治的立場の手紙は滑稽な程丁重。でも、その文章に隠されている大弐の立場を理解出来、手紙に心から感謝する源氏は、人格的な品、人を怨まない心広い大人になりました。
五節からの文を、【ほほゑみて】見た源氏の様子は、【いとはづかしげ】語り手が恥ずかしくなる程の素晴らしい美しさです。
須磨
2018年6月6日受講
【望郷の秋】続き
庭の植え込みの花々が咲き乱れる気持ちの良い秋の夕暮れ。海が見える廊に出て立っている源氏の、恐ろしい程の美しさは、こんな須磨の山の中ではこの世のものには見えない。紫苑色(赤紫系)の指貫に縹色の直衣。帯をゆるく結び、くつろいで「私は釈迦の弟子」とゆるゆる経を誦える声も又、この世では聞いた事がない程。沖から沢山の船。船乗り達が舟歌を大声で歌いながら船を漕いでいく声。その船が遠ざかり、まるで小さい鳥が海に浮かんでいる様に見えるのも心細くなるのに、雁が連なって鳴く声が櫓の軋む音に似ているのを遠く見渡しながら、自然に涙がこぼれます。涙を拭う白いしなやかな源氏の手が、持っている黒い数珠に引き立ち、残して来た女が恋しい男たちの心を慰めました。源氏は、「初雁は恋しい都人の仲間」と。良清は、「雁は昔の友ではないか」と。民部の大輔(惟光)は、「海の彼方の不老不死の世の常世を捨てた雁は、私達と同じだ」と。そして前の右近の尉が、「不老不死の世を出て旅の空にいる雁も仲間に遅れない限りは慰められます」と、各々歌います。前の右近の尉は、親が常陸の国に赴任したけれど、親の思いに従わず、源氏と須磨に来ました。心の中では思い悩んだでしょうが、元気そうに忙しくたち働いています。
月が、煌々と眩しい程の明るさで昇って来ました。ああ、そうだ今宵は十五夜だったと初めて気づき、宮中の月の宴の管弦が恋しく、残した女達が都でこの月を眺めているだろうと、【月の顔】をじっと見つめる源氏。白楽天の【白氏文集】の、左遷された親友を八月十五日の夜、宮中で思う詩の一節【二千里外故人心】を口ずさみ、逆の立場の自分に涙が止められない。藤壺の【九重に霧や隔つる雲の上の月をはるかに思ひやるかな】の月の歌を思い出し、【言はむかたなく】恋しく、長い年月の間の二人の間の色々な事が思い出され、おいおいと声を出して激しく泣く源氏。供人が「夜が更けました」と言っても中に入らず歌います。
月を見ている間はしばし心が慰められます いずれは又お会い出来るだろう 京(月)の都は遠いけれど
その夜、兄の朱雀帝と一緒に親しく昔話をした時、兄が桐壺院によく似ていた事を恋しく思い出し、菅原道真が太宰府で詠んだ歌の中の【恩賜の御衣は今ここにあり】を口ずさみながら部屋の中に入りました。
朱雀帝から賜った御衣は、大切に肌身離さず近くに置いてありました。そして、
自分をこんな目に合わせた帝だが冷淡だとだけは思えないで、恨みでも恋しさでも涙が出ます
と歌います。
読後一言感想
・ 【今宵は十五夜なりけり】月を眺めているうちに宮中の月見の宴を思い出す源氏。去年は華やかの日々、宴の中心にいました。今は侘しく孤独な須磨での生活。【月の顔のみまもられたもう】激しい望郷の想いと寂寥感が伝わってきました。
月は明るく照らすばかりでなく、人の心をざわつかせたり、激しく揺さぶる何かを持っている気がします。
・ 今回は、雁や月等秋一色になり、須磨という土地柄もあり、物悲しい寂しい晩であった。
特に月は、いろいろな事を思い出すもの、感情的になるものの様な気がしました。
白楽天や道真の詩もよく分かって良かった。
・ 今回は、「涙」だ。
落ち込んだ姿を、供人達に見せまいと、我慢に我慢を重ねてきた源氏だが、十五夜の輝く月の光に、心の堰が崩れてしまった。泣きなさい、源氏君。これから楽しい事もある。
・ 前回の、風と波の音の夜の恐ろしい夜と対照的な静かな海の夕暮れは、音、色、光に溢れ。
場違いな源氏の美しい姿と声。目の前の海を、船乗り達の賑やかな歌声が遠ざかり、雁の声も又遠ざかる。
時間が動いている。流れた涙を拭う源氏の白い手は、男たちに恋しい女を思い出させる。
月が昇り今宵は十五夜。ああ何と、十五夜を、あの宮中の月の宴の管弦の楽しさをすっかり忘れていた。
藤壺の詠んだ月の歌。恋しい、会いたい【よよと泣く】。院によく似ていた帝も恋しい。確かに帝は自分の支えだ。ああ、月の中に都があるというが、都が恋しい。
【竹取物語】では、月を眺めるのは不吉な事でしたが、この時代の人々の、月への思いを強く感じました。
2018年5月2日受講
【望郷の秋】
須磨の【心尽くしの秋風】の夜、在原行平の歌の様に、遠くから聞こえる浦波の音は、【夜々】とても近くに聞こえ、源氏は眠れません。皆が寝静まった中一人目を覚まし、【枕をそばたてて】耳を澄ますと、波はここまで寄せてくる様。【涙落つともおぼえぬに、枕浮くばかり】知らぬ間に涙が溢れます。琴をかき鳴らすと、夜更けで気味悪く聞こえたので途中で止め、声を出して都が恋しい歌を歌います。供人たちが目を覚まし、皆が都恋しさに【鼻を忍びやかにかみわたす】のです。そのすすり泣きを聞くと、彼らは、一人親兄弟から遠く離れ、この先都に何時帰れるか分からず彷徨っているのだと思うと可哀想で、自分が落ち込んではいけないと、源氏は、昼は冗談を言い、暇に任せて、継ぎ合せた色々な紙には書を、模様入りの唐の織物に絵を描き屏風の面に。それらはとても見所あるものでした。昔、北山で聞いた明石の海や山の話は遠いものだったのに、目の前の須磨の光景は、想像以上の迫力で、沢山の絵を描きました。今都で評判の(墨で描いた絵に)彩色する絵師を呼びたいと思う位の出来ばえです。源氏の親しみやすく、魅力的な様子に供人たちは現実を忘れ、四五人はいつも源氏にぴったり寄り添って仕えていました。
秋の名文と言われているのも納得で【古今集】【行平の歌】【新古今集】【後撰集】【白氏文集】
【古今六帖】等から引いた表現がこれでもかと続く。【香炉峰の雪】の清少納言もびっくり。
読後一言感想
・ 【望郷の秋】は、音が響いています。都の華やかな生活との落差。寂しさ、孤独や不安。眠れぬ秋の長夜は【枕浮くばかり】寂寥感が、夜の風や波の音と共に伝わって来ます。その中、源氏は【げに、いかに思ふらむ】と供人に気遣い、供人達は【近う馴れつかうまつるをうれしきこと】と源氏を支える。苦しい時に供人への思いやりは、さすが源氏。辺境の地に居ても、優しさと、供人との絆をより強く感じました。
・ 十七歳の源氏が嫌で、「およすく会」を辞めさせて頂きました。
その後十年。年を重ねた源氏の君、やはり貴族のぼんぼんさんやと思ってしまいました。
三十近くなって枕を浮かばせる程、泣くんじゃないと言いたくなってしまいます。
勿論、仕えてくれている人々への思いやり等、大人になっている部分はあるので少しは安心致しました。
・ 【いとど心尽くしの秋風に】とは、何と風情のある言い回しでしょう。
ここは、声に出して読み、暗記し、秋に、一人呟いてみたいものです。式部は、今回の所では、波の音、四方の嵐の音、供人が【うち休みわたれる】静けさ、供人が【鼻を忍びやかにかみわたす】音など、音で深い須磨の秋を表していて面白い。
・ 須磨に来て半年余り。秋が深くなるにつれ、源氏達の望郷の思いは深まる。
「今回は【音】が印象的だよねー」というのが皆の感想。
海鳴りの様に響く波の音は、ホント怖いし、不安感をかき立てるよね。
あぁ、都は遠いんだ・・・。源氏は心底、身にしみたに違いない。
・ 秋は、物悲しく心細いが、ことさら須磨という土地柄ゆえ、心をかき立てられる。まして、夜の波音は、不気味であり、眠れない源氏である。こんな所にどうして私が・・・。でも、自分が悲しんでばかりでは、供人達にも影響する。その供人達の為にも自分が変わらなければ・・・。
・ この先がどうなってゆくのか、次を知りたく思いました。
源氏は、暇に飽かせて絵など描いていますが、絵を描く事も、とても高価な趣味なのだと、改めて感じました絹の布に、モノトーンで描いて、色は専門の職人がする。色が、とても高価な贅沢なものだと思いました。
・ 波の音、風の音、琴の音、自分の歌を読む源氏の声、供人の鼻をかむ音。音で源氏の孤独の凄さを強調。
供人を励まそうと、若い彼らと遊ぶ。書、絵、写生の才能にも優れている源氏は、大人になりました。
【若紫】の北山の場面が懐かしい。
2018年4月4日受講 須磨
【帝と尚侍の君の涙】
源氏との密会を知られ落ち込んでいた尚侍の君。父親と大后(弘徽殿の女御)の口添えで、一般の女御として帝の元に戻って来ました。それを非難する世間に帝は知らない振りを。尚侍の君の心にはまだ源氏の面影が溢れて。それを知りながらも、愛せずにはいられない帝。彼女を【つとさぶらはせたまひて】過ごします。気品がある申し分ない美しさの帝ですが、源氏と比べてしまう尚侍の君です。ある管弦の遊びの日、帝は源氏の居ない【さうざうし】さと、【何事も光なきここち】、そして桐壺院の遺言を実行せずに源氏を須磨に追いやった後悔を尚侍の君に言い涙ぐみます。尚侍の君も涙をこらえきれず。「私がもし死んだら、貴女は源氏との別れ以上に悲しんでくれますか?【生ける世に】という歌を詠んだ人には、目の前の恋する人の心に別の人がいてどうにもならない事が分からないのだ」と、しみじみと話す帝に【ほろほろと】涙を流す尚侍の君。その涙に帝【さりや。いづれに落つるにか】「その涙はどちらの為の涙なのか、源氏か私か」嫉妬に叫ぶ。更に自分の思い通りにいかない政について弱気な本音を尚侍君に話す若い帝です。
読後一言感想
・ 今回の【帝と尚侍の君の涙】はなんと主語がくるくると変わり難解であることか。
しかし何度も読んでみると、まったく無駄がなく、リズミカルでおもしろい。 (帝は)【涙ぐませたまふに】(尚侍の君は)【え念じたまはず】。あっち向いたり、こっち向いたり。そして帝ってこんな人だったのかと、その人となりを初めて知る。とても素直でいい人だ。結婚したら苦労させられるタイプかもしれないけど。しかし尚侍の君の涙はそれこそ誰のため? やっぱり自分のためよね。かたじけなきことである。帝はあの親政を行った桐壷帝の息子なんだから、もう少し強くならなきゃ。でもいつか帝は院との約束を果たし、源氏を呼び戻し、春宮を【院ののたまはせしさま】にするわね。 いい人だから。
・ 尚侍の君の心が源氏にあることを知りつつも許し、【生ける世にとは、げに、よからぬ人の言い置きけむ】とおぼす帝の恋心。【思ひ出づることのみ多かる心のうちぞかたじけなき】と思いながらも、源氏への想いが募る尚侍の君。そして、ライバルである源氏の不在を【光なきここち】と思う帝の気持ち。
人間の感情は、どうしようもないものである事を、つくづくと思わされる所でした。
・ 源氏みたいな男が周りに居たら、
それも何事につけても比較される様な立場にあったら、とても辛いに違いない。朱雀帝、かわいそ!
今回の【帝と尚侍の君の涙】は、あるべきもの(源氏)がなく心が満たされない淋しさ、二人の内なる【さうざうし】が交錯する場面だった。
それにしてもこのシーン、受け取り方もみんな個性的で、そっちの方がおもしろかったなぁ。
・ 帝は源氏に対しては対抗意識がすごくあり、
尚侍君に対してちょっと意地悪っぽく言う処等、自分に対してひがみがある様に感じた。
もっと強くなって! 兄なんだから。
・ 今日は、《事件》を経て後の尚侍の君と帝の関係を描いた場面を読みました。
源氏に会わなければ、入内して后になっていたであろう尚侍の君は、人に笑われる様な立場に立たされる事によって、人生の挫折を知り、人間として少しは深みを得たのでしょうか、【ほろほろ】と涙をこぼしたりします。一方、帝の方は、始終メソメソと泣いて「ボクなんて死んだ方がいいんだ」と口走ったりして、【強きところなき】人物を全身で訴えていました。平安時代の外戚の強い天皇は、生きていても楽しい事は何も無いみたい。それにしても、すぐに「死にたい」なんて言うヤツに限って長生きするのよね。
・ 尚侍の君は離れている源氏への激しい想いを抱きながら参内します。おっとり優しい帝は屈折した想いで尚侍の君を寵愛します。恋には積極的でストレートに突き進む源氏。その上禁断の恋。激しく燃える恋愛の条件がそろっています。理性では割り切れない帝と尚侍の君の想いが伝わってきました。
・ 【ほろほろとこぼれ出づる】尚侍の君の涙は、自分でもどうしようもない涙だったのに【さりや。いづれに落つるにか】帝は源氏に嫉妬する。これは永遠の恋愛小説のテーマ。源氏に会った時少女だった尚侍の君は、女、母となり、案外弘徽殿の女御みたいになったりして。と、久し振りに弘徽殿の女御で盛り上がり。生物的に、女は変態するけれど、男は変わらないと。
2018年3月7日受講 須磨
【伊勢よりの使者】
使いの若者が運んだ伊勢の御息所の手紙は、【言の葉、筆づかい】、【唐の紙、墨つき】で、凝りに凝った言葉を選んだ歌は、「私も辛いけれど、貴方様はすぐ都に戻れますよ」「私の方がずっと辛いのよ」と、優しさと思いやりに溢れた、究極の文化的表現。御息所が、自分を思いやりながら文を書く姿を想像し【いとほしうかたじけなきもの】と恋心が甦る源氏。源氏の姿を直接見る等決して有り得ない使いの若者は、その美しさに涙を落とします。源氏は、「貴女と一緒の小船に辛い思いをしないで乗りたかった」「私は何時まで須磨の浦で涙にくれていればよいのでしょう」など、心を溶かす程の優しさと甘えた歌を返します。
どの女君にも不安を与えない為にこんな手紙を書いたと。語り手。
花散里も、麗景殿と一緒に悲しみを書き集めた手紙を送ってきました。その手紙に今の自分との距離を感じ【目なれぬここち】と。思いやりも優しさもない、ただ二人の困窮状態を表す歌に現実を突きつけられ、二条院に彼女達の屋敷の修理等申し付けます。
御息所の手紙を絶賛した後に花散里の悲惨な現実を描く。式部の冷静な目で描かれていました。
読後一言感想
・ 尚侍の君、紫の上、御息所、花散里と、女君達の手紙が次々と紹介されてゆく場面から、それぞれの女君の性格や生活振り、その違いがよく分かりにました。御息所と花散里は対照的だと感じました。御息所は、女としては憧れます。花散里は、中々世帯じみた、女としてみるとちょっとあなどってしまうタイプの人と感じました。墨と筆で書く手紙は、その人の息遣いや、ここで筆を置いて休んだな、とか、ここは一気に書き進んだのね、とかが伺われる素晴らしい道具だと思いました。御息所の文は、どれ程情緒ある美しい筆使いだったのか、想像するだに、御息所の格の高さに憧れを感じました。
・ 御息所からの返しはやはりスマートである。
そして、【よろづに思ひたまへ乱るる世のありさまも、なほいかになり果つべきにか】など、政治のあり方にも心を砕き、やはり年上のインテリジェンスを感じる。花散里の歌は【かつはもの思ひのもよほしぐさなめり】で、源氏は今の花散里達の生活の困窮振りを感じてしまう。早速麗景殿の修理を手配する源氏。
何だかんだと言っても、やっぱり源氏は優しい。
・ 今迄の何人もの女性からのものよりも御息所からの文は、より高い教養のあるものと思われた。
でも、もう一人いらっしゃったのだ。
こちらも放ってはおけないと、助けに出るが、源氏って何とかしなければという性格?で、何とかしてしまうのだ。
・ 淋しい源氏は、方々に手紙を出す。マメだ。
ここで面白いのは、源氏がこれまで係わってきた様々な女性たちが、返事の歌を通して、その個性が一堂に歌に表現されている事だ。入道の宮、紫の上、尚侍、伊勢の宮そして花散里まで。
ホント、人柄が滲んでおもしろいなぁ。
・ 閑職にあり、田舎の侘び暮らしの中でも、源氏の魅力が描かれる。
六条御息所の使いの若者が、源氏の魅力に感動する場面や、花散里達を思いやる源氏の優しさ。やはり魅力ある男だ。六条御息所は、いつでも上品で、文化度が高く、登場すると匂い立つ様だ。
・ 女性の返歌に対して源氏の想いが気になりました。
前回は須磨に離れても、源氏はそれぞれ女性に深い愛情や激しい恋心を持ち続けていることが描かれていました。今回の御息所と花散る里は対照的。
御息所には【いとほしうかたじけなきもの】。花散る里には実質的な経済的援助を手配します。
激しい恋心ではなく源氏の優しい情愛が伝わってきました。
今回、久しぶりに御息所と花散る里ですが、対照的に描かれています。
・ 伊勢の御息所からの文は、今の味気ない須磨の生活を忘れさせる、白い唐の紙、選んだ言葉、墨の濃淡のある素晴らしい物。源氏の返歌は、相手の心をメロメロにさせ甘え切ったもの。その見え透いた言葉に、御息所は心底喜んだに違いない。一方、花散里の歌は、困窮した状況を伝える現実的なものだった。
2018年2月7日受講 須磨
【都人の返りこと】
源氏が都へ送った手紙の返事が戻り、各人の歌に、三人三様の源氏への想いが溢れていました。
藤壺の歌
二人の秘密を隠し通し、春宮を守った源氏を評価し、彼の想いを受け取れなかった自分を思い返し、源
氏が須磨に行き二人の緊張関係がなくなった今、恋しい想いをとても素直に今までになく【すこしこま
やかに】。
尚侍の君の歌
「隠した恋はまだ胸の中でくすぶっています」【さらなることどもは、えなむ】何も書けないと。
彼女の厳しい状況を中将の君の手紙で知り、源氏は泣きました。
紫の上の歌
「貴方の濡れた袖に比べてみなさいよ、海の彼方の私の一人寝の夜を」一緒に送ってきた見舞いの品々は、
色、仕立て具合全て垢抜けした、源氏が望む美しさ。都の面倒な関係から解放されたこの地で、ゆったりと一緒に暮らしたいと面影が夜昼浮かび、ここにこっそり迎えたいと望んではみるけれど、この身に降りかかった罪を取り除かねばと、源氏は朝夕勤行に励みます。
左大臣家の葵との子供は、後見がしっかりしているから安泰だと思う姿に、親の顔が見えますと語り手。
読後一言感想
・ 女達からの便り、それぞれに個性があり、見事に描き分けられている。
歌がその人物の心情を訴えている事がよく分かる場面だった。
この描き分けられた歌も、一人の作者(紫式部)が書いているのだからやはり、式部はやはり天才だ。
・ 源氏が須磨から出した文の返事。
今回は、入道の宮(藤壺)、尚侍の君(朧月夜)、姫君(紫の上)の歌が並んだ。
それぞれに個性や背景が伝わるもので面白い。でも、あと一人、足りないよね。
次回のお楽しみと、いうことで・・・・。
・ 源氏にとっての重要人物に送った手紙の返事は、それぞれの立場のものだった。
入道の宮や紫の上の歌は、特に心を揺さぶられた。
暇で仕方のない源氏は、勤行にいそしむが、する事はこれだけだったのかしら。
・ 今回は、須磨に落ちた源氏からの文に、それぞれの女君が返した歌の場面を読みました。
入道の宮、尚侍の君、紫の上、それぞれの女君の置かれている立場と、性格の違いが良く分かりました。
紫の上のほかの二人の女君は、源氏との恋は忍ぶ恋。決して人には知られてはいけない関係の為に苦しいのだけれど、都と須磨との距離が、情熱的な歌を詠ませたのだと思います。
それにしても、須磨の源氏は時間だけはたっぷりあるので、勝手な事ばかり考えて、時々お経を読んだりして過ごしています。
・ 源氏が女性達に送った歌の返りが来る。
三者三様であるが、夫婦 男女の想いのあり方を考えると、これは一人の女性の中にある三種の想いの様でもある。別れて初めて自分や子供の事を考えてくれていたと、しみじみ思い、初めて優しい言葉が掛けられる。夫婦となっても、【くゆるけぶり】の様に先は分からぬ。【浦人のしほくむ袖にくらべ見よ】私がこんなに想っているのに・・と。そして源氏はそれぞれの想いに涙を流すが、今までと違うところは、源氏が初めて【かく憂き世に罪をだに失はむ】とする決意があることである。
今日の読んだところでは、三人の女性の歌だけでなく、こういう源氏の罪をあがなおうという気持ちに驚いた。女性達が真実の想いをぶつけてくるからこそ、今の自分がしなければならないことに向き合おうとしている。源氏の生き方変わるかも。
・ 入道の宮、尚侍の君、紫の上の歌に、源氏との関わり方とその人柄がしっかり詠まれていました。
藤壺の源氏に心を開いた、【すこしこまやかな】歌に、今まで源氏に【すくすくし】かった場面を、紫の上の飾り気のない【浦人のしほくむ袖にくらべ見よ】の歌に、今までの彼女の涙を思い出しました。
原文からひろがる源氏物語 須磨
2018年1月10日受講
【それぞれの文】
梅雨の頃になり、須磨の新居が落ち着いて来ると源氏は京が恋しく、人を仕立てて京に手紙を送ります。紫の上と出家した藤壺に書こうとして、胸が一杯になり【くらされたまへり】涙で見えない。でも、藤壺へは、【賢木】P-176の歌【ながめかるあまのすみかと見るからにまづしほたるる松が浦島】から、【松島のあまの苫屋】、【須磨の浦人しほたるるころ】。そして尚侍には、【こりずま】、【塩焼く海士】等須磨の海に関わる言葉選びで、素晴らしい歌に仕上げ、左大臣、若君の乳母にも若君を宜しくと。京では彼の手紙に心を乱した人多く、中でも紫の上は、読んだ後起き上がれない程。使っていた調度品、琴、脱ぎ捨てた着物の匂い、それらを見るとまるで源氏が死んでしまった様に思われ、縁起でもないと、少納言は僧都に夫婦二人の平安を祈らせます。僧都の祈りが通じたか、女君は冷静さを取り戻し、源氏への送り物を整えます。夜具、夜着、絹でない硬めの布で作った直衣、指貫は、以前の華やかな薄い柔らかな絹とは大違いの悲しさ。【去らぬ鏡】と言った姿、出入りしていた口、寄りかかっていた真木柱を見ると胸が一杯に。語り手が、経験を積んだ老人でさえ悲しいのに、慣れ親しみ、父母となり養い育てた源氏なのだから当然で、全く世の中から居なくなってしまえば諦めもついて、忘れていってしまうでしょうが、須磨は聞くと近いが、いつまでと期限が決まっている別れではないので、心が休まる時が無かったでしょうね、と。
読後一言感想
・ 源氏は生活が落ち着いてくると寂しさもつのり、京へ人をやり手紙を届ける。
入道の宮や尚侍には、相手を海士になぞらえ、自分は「浦人しほたるる」 などと、事件の共犯者たちとも言える二人には少し余裕のある歌を送っている。しかし紫の上への手紙は載っていないだけに、私たちの妄想をかき立てるわけだが、それは源氏の叫びだったのではないでしょうか。その叫びをぶつけられる相手はやはり紫の上しかいなかったのね!
・ 須磨から源氏は京へ【人出だし立てたまふ】
入道の宮と尚侍への歌には少し源氏の余裕を感じる。紫の上への歌は書いてないが、きっと源氏の叫びを感じるものだったに違いない。式部は、紫の上への歌を書いてしまうと、言葉の限界を感じさせてしまうが、書かない事によって我々の妄想をかき立てている。
・ やっぱり源氏はマメ男だ。
マメだけれど、京に残された紫の上には気配りが足りませんよね。若さのせい? 男だから?
何にせよ、紫の上が不憫だ。心が折れるよねぇ。
・ 源氏の置いていった物に残る匂い。
匂いはかくも残るものだ。平安時代は、匂いや触覚(?)が重要な感覚。それを効果的に使い、小説として膨らみを持たせた紫式部は、やはり天才的作家である。
・ 須磨に居る源氏の辛さ、寂しさ、孤独と、都に居る二条院の君の辛さ、寂しさ、孤独。
源氏からの文により、二条院の君の耐えていた気持ちが一気に崩れる事になります。
華やかな都に居て、より深い悲しみ、想い、絶望の心に迫ります。
・ 【御文に、御心乱れ】、二条院の君は【そのままに起きもあがりたまはず】さぶらふ人々が心細くなる程の嘆き。紫の上にとっての源氏の存在の大きさを、つくづくと思わされる箇所でした。
【こりずまの歌】は、掛詞の説明を伺ってやっと歌の意味が分かりました。
・ 春先に旅立った源氏ですが、時は移り、梅雨の頃となりました。【長雨】の頃に。
ここで思い出した、小野小町の歌。
【花の色は移りにけりないたずらに 我が身世にふる長雨(ながめ)せしまに】やはり古語は素敵だと
思いました。イメージが重層的に立ち現れて来るので。
今回読んだ所は、和歌が効果的に使われていて良かったです。私は和歌が好きです。
・ 二条の院にもう源氏の琴の音は無く、残された衣服の残り香や、数々の残された【おもかげ】だけ。
今迄耐えてきた紫の上の心が源氏の文で壊れてしまった。丁寧に書かれている彼女の悲しみを読むと、前の二首の歌が軽く思える。源氏にとって藤壺と尚侍は、まだ大切な女達。男と女の感性の違いを感じた。
原文からひろがる源氏物語 須磨
2017年11月22日受講
【須磨の家居】
紫の上の面影を胸に、馬と船を使い源氏は須磨に到着。旅の心細さは今迄知らぬ程、でもこんな旅の風情も又感じています。大江殿という、昔源融の別院で有名だった場所は、松だけが残っていました。
【唐国に名を残しける人】屈原が追放された場所よりも侘しい自分の住まいを思い、渚に波が打ち寄せては帰るのを見て伊勢物語の歌を思う。お供の者達は、そんな先人達に繋がろうとする主人の姿が悲しい。陸地の方を見ると、遠くの山には霞がかかり、白楽天が詠んだ【三千里の外】に居る気がするけれど、古今集の【櫂の雫】の歌の様に涙が抑えられない。そして詠んだ歌は、
都を山の霞は隔てているけれど、都で眺める空の雲はこれと同じものだろうか
これから住む所は、在原行平が【藻塩垂れつつわぶ】と詠んだ家の近くの、ぞっとする程寂しい山の中。
我が家を初めて好奇心で眺めると、屋根を葦でふいて都風に廊を付けた様な屋敷などで風情があり、昔の忍び歩きを思い出しました。近くの荘園の長を呼び、家の改築等色々な事を良清の朝臣に命じ、僅かな時間で、良清はとても見栄えのする住居に改造させました。池や植木に手を加えてやっと落ち着いた気持ちになったのは自分でも信じられない。国守(良清の父親)も目立たない様に好意を寄せて仕え、こんな山の中とは思えない位、人の出入りがあるけれども、対等に物を言え楽しい話が出来る人が居ないので、知らない国に居る様で、全く気が滅入り、どうやってこの先の年月を過ごしたらよいかと源氏は考えるのでした。
読後一言感想
・ さあ、いよいよ須磨へ下る源氏。
旅の景色を眺めては、白楽天の詩や行平の歌を例えて我が身を嘆くが、本当の寂しさは、須磨の住処が整ってからだった。源氏が身に沁みた「落差」は、これまで当たり前に馴染んできた京の文化との隔たりだ。気心の知れた話し相手も居ない。正に【知らぬ国のここち】。これは応えるだろうな。
・ 【渚に寄る波のかつかへる】を見ても、霞を見ても、ただただ望郷の思いに沈む源氏が着いた【おはすべき所】は、【あはれにすごげなる山中】の茅屋だった。【近き所々の司を召して】水遣りや植木などもして、しつらえを整え、落ち着いても、【はかばかしうものをものたまひあはすべき人】の居ない事が一番応える。人・友があってこその生活・人生という事をつくづくと思わされる所でした。
・ 源氏の孤独、ここに際まれり。
現代人の心情にも訴える紫式部の筆の力である。だからこそ、次はどうなってしまうのか、という読者の興味は尽きない。 紫式部は、やはりスゴイ!!
・ 官位を剥奪され、自ら須磨に退く事を決意したとはいえ、あまりにも寂しい山の中の住居は、都からは想像もつかない処だった。覚悟はしていたものの、住まいの環境は整ったが対等に話せる者もおらず、寂しさはひとしおだったと思う。でも、源氏の事だからこれで終わる筈はないだろう。
・ 源氏はついに須磨に着く。
須磨へ向かう途中は、源氏は胸ふたがりながらも、自らを【唐の名を残しける人】(屈原)になぞらえたり、業平の歌の心情に浸ったり、景色が流れればそれなりに何時もの源氏らしく【めづらかなり・・・】と、周りを眺める。しかし、いよいよ須磨に着き、【今はと静まりたまふここち、うつつならず】となると、【はかばかしうものをものたまひあはすべき人】が居ない。初めてこれからどう年月を過ごしていくのだろうと、寂しさをヒシヒシと感じる。話せる人が居ないのは本当に寂しいよね。
・ 行きつ、戻りつを繰り返して、長く続いた別れの場面が終わり、ようやく須磨に到着しました。
須磨への道中は、業平や屈原や、不遇の流人である先人に思いを馳せて、こおいう描写が出て来る所に、短い文章の中で時間と空間をグッと広げる、古典ならではの素敵さを味わいました。良い意味での教養主義だと思いました。そして移動が済み、家を整えて、供廻りの人々も退出してシーンとなった所に、源氏がポツンと一人で居る場面は、本当に孤独で寂しいと思いました。この孤独に終わりが来るのだろうか、と思えば、耐え難い孤独に違いないと感じました。
・ これでもかと行間に隠れていた、驚く程の式部の知識の凄さに驚くとともに、都のその高い知的文化圏から完全に切り離されてしまった源氏の深い孤独は、私達の想像を超えたものだった事でしょう。
2017年10月4日受講
【残されしゆかり草 続き】
王命婦の返事は、春宮の様子が不憫だと。そして、貴方様は必ず帰って来られますという励ましの歌。
【咲きてとく散るは憂けれどゆく春は花の都を立ち帰り見よ】春宮御所では、女房たちから身分の低い者まで全てが源氏の須磨行きを悲しみます。春宮御所の者だけでなく、今回の仕打ちを悔しく思う者は多く、七歳から帝と夜昼一緒に居て、帝に願うと全てが叶う源氏の恩恵を受けた一部の三位以上の上流貴族や太政官や、それより下位の者は数知れず。その恩恵を忘れた訳ではないけれど、右大臣の天下の容赦のない【いちはやき世】を恐れ、源氏の屋敷には近寄らないのでした。陰では源氏の落ちぶれた事を大騒ぎして惜しみ、朝廷を非難しましたが、我が身を考え、何の得になろうかと思う人が多く、源氏は、世の中はどうにもならないものだと色々な時に思うのです。
三月二十日過ぎの出立の日がやって来ました。源氏は一日紫の上と【御物語のどかに】過ごし、夜深く出かけます。旅の装束は身分の低い者が着る狩衣など着て、ひどくやつしました。月が出て、いよいよ出立の時。紫の上は、悲しみの余り部屋から出て来ません。源氏は自分を見送って欲しいと、御簾を巻き上げて外へ誘います。【泣き沈みたまへる】女君が心を静め出て来た、その美しい姿が月の光に照らされ、身寄りのないこの女君を一人残したら【いかなるさまにさすらへたまはむ】と、気がかりと悲しさで胸が一杯になりますが、そんな事は口に出せず、わざとさらっと軽い歌。「生きている内にこんな別れがあるとは知らないで、貴女と命の限り一緒に暮らそうと約束したのに はかない事です」
返した紫の上の、【惜しからぬ命にかへて目の前の別れをしばしとどめてしがな】目の前の別れを暫くとめて欲しいという、絞り出された悲しみの歌。源氏は、そうだ貴女を見捨てられない。
でも、夜がすっかり明けてしまい、源氏一行は急いで出立しました。
読後一言感想
・ ようやく出発を迎えた、このシーンは素敵だった。今迄どれだけの人々と別れの挨拶をしたのだろうか。
世の習わしとはいえ、政権を交替した人々の混乱ぶりも今の世に通じるものがあるのかなあと思った。
・ とうとう紫の上との別れが訪れた。この時源氏二十六歳、紫の上十八歳。
この時代の“旅は死と隣り合わせ”とおっしゃる先生に、となると「別れ」は死別にも等しいのね。と、改めて思った。人の死は、この世を去る当人よりも残された者がどう生きていくか、が問題と常々思っている私だが、源氏も同じだったのね。
・ 桐壺帝の後ろ盾が無くなり源氏は挫折を味わう。権力の中枢にいて【奏したまふことのならぬはなかりし】とあったが、反勢力になった時には、新たな権力側は容赦ない攻撃に合うのは平安時代も現代も同じです。世間も手のひら返す様な冷たさも同じ。人は厳しい試練で大人になるのでしょう。
出立の日、月の光の中の女君の様子は、切な美しい。
返歌は、源氏に対する激しい想い。叫びがストレートに胸に届きました。
・ 今日は、源氏が春宮、王命婦に別れを告げ、紫の上の元を離れて都から落ちてゆく場面を詠みました。
我が世の春を過ごしていた源氏の、漂泊の日々が始まります。
思えば、父帝は、桐壺更衣との子供、光る君を【決してただよはさじ】との強い愛情から、源氏の姓を与えて臣下としたのでした。【決してただよはさじ】・・・しかし、裏切る現実、人間の思惑など所詮は小賢しいもの。源氏の漂う人生が始まります。次回から舞台は須磨に移ります。
・ 春宮、王命婦と最後の別れを済ませ、源氏が去った春宮御所の女房達の悲しみは御所全体に広がって。
【いちはやき世】の恐ろしさが生々しく書かれていました。人心は今の世も変わらない。非情の世界。
いよいよ紫の上との別れ。旅は死と隣り合わせであり、源氏不在で、後見人の居ない紫の上がこれからどうなるか誰にも分からない。本当の別れになってしまうと、二人には分かっていました。
だから紫の上の【惜しからぬ命にかへて目の前の別れをしばしとどめてしがな】は、悲し過ぎる。
2017年9月6日受講
【御陵参拝 続き・残されしゆかり草】
故院の墓参に、供人はたった五・六人。そして数人の下人。それも馬で。昔華やかな時の忍び歩きとは随分異なって。その中に、あの御禊の日(【葵】P-20~P-36)臨時の随身になり源氏の行列に加わった殿上人、右近の尉の蔵人の姿が。源氏の失脚と供に、五位になる事もなく、官位も剥奪され、今や須磨行きのお供の一人に。下賀茂神社を通る時、彼はふとあの最高の一日を思い出し、今の辛さを歌にしました。それを聞いた源氏は、あの様にひときわ人より目立って華やかな青年が、自分のせいでこの様な事になってしまったと、心苦しく、馬から降りて神社の方角を拝み、神に須磨に行く暇乞いと、身の潔白の歌を詠みました。源氏の様子に右近の尉の蔵人は感動し、自分が選んだご主人様を心から素晴らしいと思うのでした。
御陵にお参りし、元気な頃の桐壺院の姿がまるで目の前に居る様に思い出され、死んでしまった人なのだと。色々な事を泣きながら申し上げても、その声を聞かせてはくれない。あれ程心を砕いて伝えてくれた、様々の遺言はどこかに消えてしまったと、言葉も無い程虚しい。(源氏二十三歳の十月に桐壺院は亡くなり)それはたった二年前の事なのに。院の墓へ行く道の草は茂り、分け入るにつれて、一層露に濡れて、月も雲に隠れ、森の木立は深く、気味悪くぞっとします。拝んでいると、桐壺院の生前の姿がはっきり見え、ぞくっとしました。 夜がすっかり明けた頃二条の院に帰り、御所に住む春宮にも手紙を書きました。今藤壺の代わりに仕えている王命婦宛に書いた手紙は、今日都を離れます。又参上する事が出来ないのは、数ある嘆きに勝るように思われます。貴女が(私の気持ちの)全てを推し量って春宮にお話下さい。
何時か又春の都の花を観る時があるでしょう 時勢に見捨てられたみすぼらしい山に住む人として
桜の散り過ぎた枝に文をつけました。王命婦が春宮に「これこれ、こういう訳です」と説明し、歌を見せると、「しばらく会わなくても恋しいのに、遠くなったらどんなに恋しいか、と言え」と。舌足らずの返事に、幼い春宮を王命婦は可哀想に思い、藤壺が、常識外れの源氏との恋に心を砕いていた昔の事、その時々の様子を思い出し続けると、何の苦労もなく、藤壺も源氏も過ごせただろう世を、自分から求めて辛い道を突き進んで嘆いたのを、悔しく、まるで二人の情熱を押し止められなかった自分の判断が、この二人の人生を狂わせてしまった責任を感じている様です。が、そんな事はないですよね、と語り手。
読後一言感想
・ 源氏は出発の前夜、桐壺院の墓を詣でる。
【さばかりおぼしのたまはせしさまざまの御遺言は、何方か消え失せにけむ】と、世の中の流れは右大臣方に流れ、遺言もおざなりになっているのを悲しむ源氏は、自分の処遇だけでなく、桐壺帝の治世が失くなってゆくのを悲しんだ事だろう。又、王命婦が春宮の淋しい今の姿を見て、こうなったのも源氏を手引きした自分のせいでは・・・と思うあたり、女房にも深い人間性を感じる。
・ 今日は、源氏の都落ちの前日、北山の故院の御陵に詣でる場面を読みました。
途中、賀茂の下の御社、糺の森を通ると、まだ華やかだった昔を思い出し、又葵祭の時に行列に従った、同じ右近の尉の蔵人も再び登場させ、明暗のコントラストをはっきりと出している所が感慨深かったです。
父の墓前で別れを告げ、春宮に別れの歌を贈り、いよいよ須磨へ出発。幼い春宮が哀れでした。「少し会えなくても恋しいのに、まして・・・」
・ 故院を思う時は息子の心、春宮を思う時は父の心。
源氏の心象風景がストーリーの流れと背景に重ねられていて、見事だ。
・ 有明の月の中、五・六人の供に【御社のかた拝み】、月が雲隠れの中【御墓】に別れの参拝をする源氏。故院に交錯した思い、深い悲しみ、寂寥感や夜明けの重苦しい空気まで伝わり、舞台を観ている様な感じがしました。
・ 出立する朝迄も、次々と別れの人達の事が出て来て、以前読んだ事が思い出されてきました。
華やかな時を過ごした源氏も寂しくなります。春宮との別れも、幼いが故、源氏に会えなくなる事に不安を
感じる筈です。悲しみに耐える姿はいじらしい
・ 葵祭のみそぎの日の、仮の御随身の美しい姿、王命婦が慌てて二人の衣類を拾ったあの時、物語の懐かしい場
面場面が、くっきり浮かび上がって、まるで映画の回想シーンの様でした。
2017年8月2日受講
【出立準備 続き・御陵参拝】
【わりなくして】届いた源氏の文に【忍びたまへど、御袖よりあまるも所狭う】溢れる涙の尚侍。涙ながらに書いた文の筆跡は【いとをかしげ】と評価。もう一度会いたいけれど、尚侍は【憂しとおぼしなすゆかり多うて】、【おぼろけならず忍び】並大抵でなく謹慎していた様なので、もう手紙も書けない。
出立の前日暗いうちに桐壺院の御陵に行くため北山へ。月が出る迄まず入道の宮(藤壺)を訪問。宮と御簾を通して直接会話するのは何年ぶりか。春宮の事。それが一番大事。【かたみに心深きどちの御物語】は、どんなに辛いものだったことか。宮の上品な美しさは昔と変わらない。私に対する貴女様の冷たかった仕打ちも口にしてみたいけれど、今更そんな事は嫌悪されてしまう。冷静にならねばと、「この様な須磨への追放の罪に問われる事は何も無いけれど、思い当たるのは一点で、人力を超えた何でも見通せる天の目も恐ろしく、自分の身は無いものとしても、東宮が帝になる世だけ無事に作る事が出来れば」とだけ。宮も、右大臣側からの東宮への攻撃を弱める為に源氏が須磨へ行くと全て分かっていたので、【御心のみ動き】言葉にならない。源氏は、二人の間の色々な出来事を思い集め泣く。それは【いと尽きせずなまめきたり】。瞬間二人は愛する者同士に。しかし、源氏の次の言葉「御陵に参りますが、院にご伝言は?」に【とみにものも聞こえず】凍りつく宮。心の乱れで上手くまとめられなかった二人の歌は、尚侍との歌より月並み。
読後一言感想
・ 尚侍と入道の宮。それぞれ禁断の恋ですが対照的に描かれています。
秘密は厳守され、藤壺は天皇の寵愛をうけて中宮になり、源氏との子供は天皇の子として東宮となります。東宮のために仏門に入り、日夜天皇になることを祈り続けます。今まで入道の宮は聡明で理性的な人と思っていましたが【御陵参拝】では「宮の御代」を願う母親の執念の凄さに驚きました。恋が公になり罰を受けても、激しく恋に生きるのもありかなと思います。途轍もなく恐ろしいことを胸の奥底に沈めて冷静に生きていく人の強靭な心に怖さを感じました。
・ 今日は、尚侍(朧月夜)と、出家した藤壺の二人の女との別れの場面を読んだ。
尚侍との別れは何しろ悲しい、辛い、涙、涙の別れであったが、入道の君(藤壺さんの事だったのね!)との別れは、更に深い。入道の君は、身を引いて春宮を守ろうとする源氏に、自分に対する深い愛情を感じて【御心のみ動きて聞こえやりたまはず】でも、【空も恐ろしうはべる】程罪の意識も大きいけれど、【見しはなくあるは・・・】と、藤壺の二人の男性に対する想いも見え、愛情って一筋縄ではいかないのね。
・ 今日は、今回の須磨行の原因ともなった尚侍のところから読みました。
音信不通だったが、文は届きました。ここで、来る筈もないと思っていた相手からの文を目にした尚侍は、文を返すその筆跡の事がすごく気になりました。
字体は相手の人を判断する。字の乱れ具合で、その時の状況等が判断出来る。という事です。
・ 源氏は、やはり罪な男だ。
あのプライドの高い六条御息所に絶唱の様な歌を詠ませるし、今日の尚侍(朧月夜)にも、泣く泣く乱れ書く歌を詠ませる。でも本日、一番面白かったのは、入道の君(藤壺)の歌だ。【見しはなくあるは悲しき世の果てをそむきしかひもなくなくぞ経る】う~ん、藤壺のイメージが少しずつ変わっていく。
・ 今日は、須磨へ落ちて行く源氏の、朧月夜の君と藤壺との別れを同時に読みました。
前後して二人の女君が出てきましたが、並べてみると、何と朧月夜の小さい事か・・・。今上帝を裏切って、源
氏を恋人にしている訳だけど、藤壺のコワサの前ではカワイイもんです。私は今日、藤壺はコワイ女だと思いま
した。弘徽殿の女御よりも、六条御息所よりも、藤壺は余程スゴイです。何しろ帝を謀(たばか)って、帝の
息子と通じて、その間に出来た子供を、表向きは帝の皇子として春宮に立てて、次の天皇になるべく養育してい
るのだから・・・。余程タフな精神でないと、事の重さに耐えられないと思います。(後の女三の宮と正反対で
す。)源氏物語の登場人物の中で、一番強い人かもしれないです。
・ 内侍と藤壺との別れが並べて書かれていた。涙が袖から溢れる程の悲しみを歌う尚侍。その筆跡に【いとをかしげ】と冷静な評価。藤壺と御簾を通しての直接対面には心が乱れる。甘えた事を言いたくなる。でも堪え、二人の【空も恐ろしい】秘密を守り抜き、春宮を間違いなく天皇にする為に画策する二人の政治家としての誓いを。
原文からひろがる源氏物語 須磨
2017年7月5日受講
【月かげやどる花散里】 続き
夜も更け、殆んど源氏の来訪を諦めている花散里に【あはれ添へたる月影】は、【なまめかしうしめやかに】。その月光の下、【うちふるまひたまへるにほひ、似るものなく】源氏は、【いと忍びやかに】登場。花散里の動揺が【すこしゐざり出で】に。そして二人でそのまま月を眺める。絵の様な美しい描写。【またここに御物語】の後、【短の夜のほどや】。時はあっという間に過ぎ別れの時。もっとゆっくり落ち着いて会いたかったと、自分の飾らぬ気持ちを語る源氏。【鶏もしばしば鳴き】、まるで【月の入り果つる】様に急いで帰ろうとする源氏に、花散里は、【とめても見ばやあかぬ光を】貴方様をもっと見ていたいと、心をさらけ出した悲しみの歌。【ゆきめぐりつひにすむべき月影のしばし曇らむ空なながめそ】今の立場は悪いけれど、やがて晴れるのだから心配しては駄目と、彼女を励ます歌を返し、薄暗い内に源氏は帰って行きました。【濡るる顔】は、古今集の伊勢の歌から。【ただ知らぬ涙】は後撰集の源済の歌から。風情は教養がないと醸し出せない!
出立の準備。源氏は、とても冷静に一つ一つを処理。自分不在のこの院をどう維持するか、右大臣側になびかない家来、須磨へついて行きたい家来それぞれの処遇。須磨へ持っていく調度品は最小、質素に。漢学の本と白楽天の白氏文集などの箱。そして琴一つ(七弦:中国からの輸入品)。大きな調度品、きらびやかな衣服などは【さらに】持たない【あやしの山賎めき】の風態。そして、紫の上を頂点とした、二条の院の管理体制の確立。荘園、牧場や色々な権利書は全て紫の上に譲渡。若紫と運命を共にして来たあの少納言は、今や【はかばかしきもの】として倉の管理の中心に。中務や中将など女房の中の恋人たちには、「私の帰りを待つ者は此処に居なさい」と、紫の上が面倒をみる事に。若君の乳母、花散里にも【まめまめしき筋】生活上の援助迄細かく指図します。全て完璧。
読後一言感想
・ 親しき人々との別れ、残される紫の上の立場、細々とした屋敷の運営に至るまで、源氏は気配りを怠らない。須磨に下る迄にやるべき事は沢山あり、まだ出立しないの? まだなの?・・・と、読者は待たされる。
貴方のマメさは分かるけど、早く須磨に行けよ、源氏君。
・ また別れの場面は月が描かれる。歌もまたよろしい。でも今回、源氏物語では初めて事務的な事どもが描かれていて面白い。【世になびかぬ限りの人々、殿のこととり行ふべき上下定め置かせたまふ】新しく、世になびかぬ人々で体制を固めた。また、持って行くのは四書五経、白楽天の詩集、琴。さすが教養溢れる人の持ち物である。そして御荘、御牧など、さるべき所々の券を紫の上に預ける。貴族の生活も初めてよく見えてきた。
・ 源氏が、気になっていた花散里を訪ねたシーンは印象的だった。香りと月の風情が、別れの場面としてはとても良く表現されていた。その後は現実的な旅立ち準備の様子が、源氏の采配を見事に表現していた。意外と出立の事、自分が居なくなった後の事等、あれこれ気を配る人なのだと思いました。
・ 今日は、須磨に落ちて行く前の、花散里との別れの場面と、二条院の今後の面倒をあれこれと源氏が指示をし
て、二条院が困る事なく立ち行く様に気を配る場面を読みました。
花散里との別れは、月の光、源氏の香の香り、古今集を本歌とする和歌のやりとり、涙の袖。これぞ平安絵巻
といった典雅な場面でした。一転して、二条院の運営の指示をする場面は、紫の上に荘園を預け、紫の上が女主
人として振る舞える様人事を固めて、事細かに気を配る描写に、絵空事ではない現実がうかがえました。また、
自分の持ち物としては、いくつかの書物と、琴と、質素な装束のみ。シビレました。本当の金持ちは、物に執着
しないものですね。源氏の人となりが、今回読んだところで少しうかがえた気がしました。全てに行き届いた親
切と、内面の豊かさと。
・ 中々出立しない物語。花散里の影の薄さ、源氏の香、美しい月の光の下、思いのたけを吐き出した歌。
須磨へ選んだ、自分の理想的な美意識の持ち物。そして、残す二条の院を紫の上体制に。あの少納言は、ここでもしっかり頼りになっている。細々指図する源氏は覚めている。二度と帰れないかもしれない。
そして、別れはもう少し続く。月は今回も美しく、人々は月と共に生きていた。
原文からひろがる源氏物語 須磨
2017年6月7日受講
【落魄の二条の院】 続き
右大臣の娘婿二人が二条の院を訪問。(師の宮は三の君、三位の中将は四の君の夫)その正式な訪問に対し、源氏は、【位なき人は】と無紋の直衣を選ぶが、それでも美しい。鬢をとかす為に鏡台に近寄ると、鏡に映る痩せた姿を、自分でもとても高貴な気品があって美しいと確信した後で、「ひどく醜くなってしまった。この姿の様にやつれて見えますか?気の毒なありさまだね」と紫の上におちゃらけると、紫の上は、涙を目に一杯浮かべ、じっとこちらを見ている。明るく振舞っていたけれど、もうとても耐えられず、
この身はこの様にさ迷い歩いても、貴女の傍に居る鏡の中の私の姿は離れる事はありませんよ
と詠み、それに対し紫の上は、
別れてもせめて姿だけでも鏡の中に留まるならば、鏡を見て慰める事も出来るのに、それも出来ません
柱の陰にじっと座って、涙を見せまいとする様子は、やはり沢山見る女達の中では一番大事だと。
師の宮は、何気ないお喋りをして日が暮れる頃に帰りました。
源氏の須磨行きを知った花散里に住む麗景殿は心細く、何通も便りを寄越してくるのも当然だろうし、もう一度会わないで自分が須磨に旅立ったら、花散里も辛いだろうと思えば、その夜また出かけるしかない。と思うものの、とても体が疲れきって動かない。大層夜更けて花散里を訪れると、女御が「このように女君の一人に並ぶ様な扱いをして立ち寄って頂いて」と喜ぶ様子は、書き続けるのも面倒な位。とても並々なく心細い様子は、源氏の経済的援助だけで過ぎて来た年月であったから、自分が居なくなったら一層荒れ果てていくだろうと。屋敷の中は【いとかすか】で、音、光、動き等存在感が感じられない。月がぼんやりと出て、池が広く、山はずっと木が茂っていて、心細げに見えるその景色に、源氏は、遠い須磨の侘び住まいを思います。
鏡に映る姿の相聞歌。何て洒落た、そして悲しい歌でしょう。別れの時は刻々と近づいて来ています。
読後一言感想
・ 源氏の道化も【涙を一目うけて・・・】女君が印象的です。
源氏だけを頼っている女君の悲しみ、孤独、絶望が迫ってきます。
花散里は屋敷名でその主が麗景殿女御であり、源氏に生活の不安を訴えるのも女御であることを知りました。女御といえど、桐壺院が亡くなった後は生きていくのが厳しい状態になるとは思いませんでした。
・ 今日は、身をやつして、そのやつした姿を鏡に映して、若紫におどけて見せる源氏の所を読みました。
身をやつしてみた、でも本当の僕は大丈夫、綺麗のままと確信している描写が面白かったです。それでも
別れが 間近に迫っている。若紫の、目に涙を一杯溜めて、じっと源氏を見つめる様子が哀れでした。
この、須磨へ落ちて行く直前の、本来ならお先真っ暗の只中にありながら、軽口を叩いて見せる。これ
が本当のユーモアだと思います。
・ うちやつれた源氏の姿・・・。地味な無地の直衣で現れても美しいのね。
それにしても、別れの日が近づく中、肉体的にも精神的にも疲れ果てているだろうに、律儀に挨拶に回るのだから、やっぱり元がマジメなのね。これじゃ須磨に出立する前に倒れてしまうわよ。
・ 源氏は、関係のあった女性を最後までみる人。その真面目さが垣間見られる場面だった。
自分自身も辛い時期でもあるのに、男の中の男である。
これから苦労の日々だが、再び都に戻れる日が待たれる。
・ 右大臣の娘婿二人の訪問を受け、源氏が選んだ直衣は無紋。それでも【いとめでたし】。
鏡の中の自分の顔を【われながらいとあてにきよら】と確認し、紫の上を元気にさせたいとおどけてみる。
紫の上の【涙を一目うけて見おこせたまへる】。もう【忍びがたし】の源氏。
疲れ切っていても花散里へは別れを告げに行く。【書き続けむもうるさし】の女御の感動と【殿の内いとさすかなり】屋敷は、存在感が感じられない。出てきた月がぼんやりと目の前を照らす。
原文からひろがる源氏物語 須磨 2017年5月17日受講
【落魄の二条の院】
明け方左大臣邸から帰って来た源氏の目に映る二条の院。女房たちは眠れず、一緒に須磨へ下る家臣たちは【心まうけ】して家族との別れを惜しみに行き、詰所には誰も居ない。右大臣方の非難を恐れるその他の家臣は屋敷に近寄らず、所狭いと感じた乗り物や人の跡形もなく、【世は憂きものなりけりとおぼし知らる】。台盤の上には塵、畳も引き返し、自分が此処を去ったら、どんなに荒れてしまうだろうと。
紫が住む西の対に行くと、皆一睡もしていない様子。小さい女の子たちの可愛いい寝間着姿を見ると、この子たちも何処かへ行ってしまうだろう等、そんな所まで目が留まります。紫の上に、昨夜の事を詳しく話し、何時もの様に【思はずなるさま】の、他の女の所へ行ったと思っているかもしれないけれど、都を去るには色々あって、旅立つ前ずっと貴女と一緒に居たいが、家に籠ってばかりでは、薄情者と【心おかれ果む】嫌われきってしまうと弁解。紫の上からは、こういう目に合う以外の【思はずなることは、何ごとにか】短く強い返事。父兵部卿の宮は、源氏の親族である事を迷惑がり、娘に手紙一本よこさず、見舞いにも来ないのを女房たちに知られてしまうだろう事も恥ずかしく、父親に自分を知られないままにしておきたかった。継母の北の方が、彼女について、不幸な運命から急に幸福になったのに、愛してくれる人が次々別れていってしまう不吉な人だと語ったと漏れ聞き、更に嫌になり、こちらからも一切連絡せず、今の彼女には頼る者が誰もいない。本当に可哀想。源氏は、貴女を連れて行きたいけれど今は無理。でも、ずっと許されなかったら、必ず須磨の巌に迎える。私は罪を犯した訳ではないが、これ以上のひどい事もあるかもしれないから、しっかりしなくてはいけない、この逆風を自分と一緒に受け止めて欲しいと。太陽が昇るまで二人は一緒でした。
※ 先生が選らばれた【落魄】を辞書で調べました。
鬼は魂、白は空白を、魄は、魂、心、、形、隙間を意味しています。正にこの場面にピッタリの語でした。
読後一言感想
・ 右大臣側の謀略とはいえ、自分の軽率な行動が招いてしまった須磨への都落ち。身の周りの人々との別れもさ
る事ながら、自邸の二条院の寂しい様子は、胸を打つ。今回、久し振りに紫の上の生い立ちや心情に触れ、その
【心もとなさ】が、しみじみと伝わってきた。 紫の上、かわいそ~です。いつになく源氏に強く当たっても仕
方ないわよね。
・ 今回は、須磨に落ちて行く源氏の、直前の二条院の様子が描かれている所を読みました。
それまでとは打って変わってガラーンとして、埃が隅に積もっているお屋敷に、紫の上が独り待っている・・・。
他の女の所に行ってた訳じゃないと冗談めかす源氏に対して、紫の上の返事は短く、鋭い。「今の状況より思い
がけない状況なんてありません!」紫の上の置かれている状況は、源氏の境遇より辛いものです。頼りの源氏は
去って行く、父親はお見舞いもくれない、そんな父に見放された娘である事が女房にバレてしまい、軽んじられ
てしまう。継母には、「縁起の悪い娘ねぇー」と陰口を叩かれる始末・・・。
人は不遇に身を置いた時に周囲の人の真実の姿が分かる。これは不変の真実です。
・ 紫の上の境遇が激変。源氏との結びつきは特別深く別離だけでも耐えがたいほど悲しい。実父とは【いとおろ
かに】【御とぶらひにだに・・・」継母の冷たい言葉が漏れ聞こえてきます。【なかなかしらでたてまらで】、【絶えておとづれきこえたまず】と思うほど、味方となるべき実家とは疎遠になり孤独な紫の上。
空蝉や夕顔もそうでしたが、貴族社会は後ろ盾がなくなると女性は致命的でお姫様でなくなるばかりでなく、生きていくことが大変で不安定なものだと感じました。
・【常なき世】を実感させる場面。馬車のかたもなく、塵ばむ台盤、引き返した畳。日常であった筈の物の変化から、現在の自分の状況、これからたどるであろう運命に思いを馳せる。他に頼る者が無く、心細さから嘆く女君にかける言葉、若き童女達などの行く末を心配する様子は、今まで自分の感情、美意識のみに生きて来た様な源氏が、人間として変わっていくであろう今後の姿を想像させる。短い文章の中で、その場の気配、雰囲気、人の驚きや心配が、そこに居ない人々の心の葛藤まで、全てありありと伝わってくる、とても興味深い箇所でした。
・ 源氏の厳しい立場が、二条の院のあらゆる場所に見えていました。紫の上が今までに流した多くの涙を思い出
し、更に今唯一頼りの源氏までもが去って行く、【思はずなることは、何ごとにか】この一言に、彼女の深い
絶望と悲しみが。
原文からひろがる源氏物語 須磨 2017年4月5日受講
【忍びて大殿へ】
三位の中将も加わり別れの酒を酌み交わした後、源氏は夜更けに自分の部屋に懐かしい女房たちを呼び、話をさせました。その中の葵公認の中将の君の、【言へばえに】言うに言えない悲しみが恋しく、皆が寝静まった後、二人でひっそり会いました。だから泊まったのですねと、語り手。人目につくといけないので、暗いうちに部屋を出ました。有明の月の下、(山)桜の花が散ってしまった木の影、散った花が白く地面を覆う庭にうっすら霧がかかり、遠く霞がかかってぼんやりとした情景は、秋の夜の美しさをはるかに超えていました。もう再び会えない悲しみを語る源氏に、中将の君は、言葉も言えず泣きます。
若君の乳母の中で一番偉い乳母が大宮からの言葉を伝えに来ました。「お話ししたいと思っていたのに、グズグズしているうちに、早いお帰りを聞きました。不憫な若君が寝入っている間に帰ってしまわれるのですね」それを聞き源氏は泣きます。
鳥部山で(妻葵を)火葬にした時の煙に似ているかどうか 私は須磨の塩を焼く煙の浦へ怨んで行きますと、返歌ともなく口ずさみ、乳母は、「今朝の別れは、親と子の、比べようがない程の別れ」だと、涙声で深く悲しみます。大宮へは、「話したい事も、沢山ありましたが、ふさぎ込んでいた自分を察して下さい。寝ている若君に会うとかえって都を出にくくなってしまうので、心を鬼にして、急いで帰ります」と。
沈もうとして西に傾いた月が、一層明るく源氏を照らします。その艶かしく優雅な悲しみに満ちた姿は、虎や狼でも泣いただろうと。まして【いはけなくおはせしほどより見たてまつりそめてし】幼い頃から世話をして来た女房たちにとって、見る影もない源氏の姿に悲しみは尽きません。大宮の返歌は、
亡くなった娘と貴方様は一層遠くなるでしょう 須磨は娘が煙となった都ではないので
大宮の悲しみも加わり、源氏が都を出て行く喪失の悲しみに、不吉なほど女房の皆が声を上げて泣いたのでした。
読後一言感想
・ 中納言の君と【とりわきてかたらひたまふ。これによりとまりたまへるなるべし。】
平安貴族の夫と妻。妻付きの女房との関係。今回、召人の話を初めて伺い驚きました。中納言の君との別れは、
二人の深い想いが描かれています。【明けぬれば、・・・】は、本当に素敵。春の幻想的な情景が目に浮かび
ます。娘の死や若宮のことなど、辛く悲しい事の多い大宮。別れの反歌は想いが溢れ、切ないです。
・ 源氏が須磨へ下る。
これは左大臣家の人々にとって底知れぬ悲しみだった。中でも、若君を見守り育てている大宮、そして葵の上に仕えていた女房たちとの別離は胸を打つ。
“都の華”を背負っていた様な源氏が、都から居なくなるという喪失感が、ひしひしと伝わる今回のおよすく会
でした。
・ 源氏が都から離れる別れの場面が、それぞれの立場から描かれていて、せつない。
須磨へ行くという事は、華やかな生活から隔たってしまうんでしょうね。
・ 源氏が左大臣家に別れの挨拶に行く。【三位の中将も参りあひたまひて】語り合う。源氏は、中納言の君とは、
【とりわきてかたらひたまふ】そして【明けぬれば、夜深う出でたまふ】その時の描写が美しい。
桜が散って白く光る庭に、わづかなる木陰が、・・月の光が強調される。
春の夜の美しさが別れの場面を際立たせている。
・ 前回は左大臣との涙の別れの場面を読みましたが、今回読んだ所は、馴れ親しんだ女房達との別れでした。
左大臣もそうでしたが、嘆き悲しんで涙を流す女房達の描かれ方を見ると、この左大臣の屋敷でどれ程光源氏が
大切に思われていたかが良く分かります。別れの風景は、盛りを過ぎて僅かに残る山桜と、有明の月と、たち込
める霧と、美しいイメージを喚起させてくれます。参考に見た【源氏物語】の冊子の絵の桜も、赤い葉の出てい
る山桜でした。東京の桜は何処も染井吉野ばかりで、私は残念です。昔の人が見てきた山桜を見たいです。
・ 桜の季節にぴったりの、春の夜の景色の美しさが別れの悲しみの深さを感じさせました。
周りを覆う霧の中、桜の花びらが庭一面を白くし、その上に残り少ない花びらが、はらり、はらりと散っている。
そして、それらを照らす有明の月。言葉だけでこんな美しい景色が描けるのですね。
原文からひろがる源氏物語 須磨 2017年3月1日受講
【忍びて大殿へ】
須磨へ立つ二三日前に訪れた左大臣邸。この邸を去った日が思い出される場面。あの懐かしい女房達も待っていました。家の誇りであった婿が、夜陰に、うちやつれた網代車でひっそりと、【夢とのみ見ゆ】です。葵との子供が走り来て、膝の上に座ります。【忍びがたげ】な源氏の父親姿。左大臣がやって来て、会いに行けなかった事を侘び、右大臣一派の情け容赦ない今の【いちはやき世】は恐ろしいと本音を語り、涙を流しながら、【天の下をさかさまになしても】源氏の今の状況は信じられないと。それに対し源氏は、【前の世の報い】で【これより大きなる恥】を避け、須磨へ立つ事を親密に話します。左大臣は、桐壺帝の時代や、院の遺言等を話し始め涙が止まらず、源氏も又泣いてしまう。娘葵がこんな源氏の姿を見ないで死んでいて良かったけれど、幼い若君が父親と遠く離れてしまう事は、とりわけ悲しい。何故貴方がこの様な事になったか分からない。左大臣は、これが最後になるかもしれないと、多くを語りました。
何時も、本当に嬉しそうに源氏を迎えた昔の左大臣の様々な姿と対照的な、今回の【しほたれた】姿。彼の悲しみがより深く感じられました。登場人物が生き生きと見えるから、絵巻が沢山描かれたのだと感じました。
読後一言感想
・ 源氏と左大臣家の人々との悲しい悲しい別れ。
理不尽でしかない出来事の為に翻弄される人々。その中でも、無邪気な若君の姿が愛らしい。それが又悲しみを
際立たせてもいる。左大臣の優しさが再確認させられる場面であった。
・ 左大臣の袖も【え引き放ちたまはぬ】嘆きに、【え心強くももてなしたまはぬ】源氏。
【常ならぬ世】でも変わらぬ、若君の美しく何心なき姿が、この場面に一筋の光を与えている。
かかることを、【みづからのおこたり】と考え、【これより大きなる恥にのぞまぬ先に】立ちぬる事は、源氏
の最後のプライドだと思う。
・ 須磨に旅立つ前に、左大臣邸に挨拶に行った源氏。
今回は涙、涙の場面だった。久し振りに会った息子に喜ぶ源氏。となると、これが永遠の別れになるかもしれな
い。女性関係も大事だけど、もっと頻繁に、子供に会っておけば良かったよね、源氏君。
・ 今日は、源氏の君が須磨へ下る前に左大臣家へ別れの挨拶に行く場面を読みました。
かつて源氏の君が華やかに過ごしていた頃と、今の不遇の様子との対比が、くっきりと悲しく描かれていたと思います。左大臣は、泣いてばかりいて、(その割には口数が多い様ですが)袖を絞れば涙が滴り落ちる程嘆いています。泣いてばかりいる昔の人の袖は、さぞ塩っぱかったのだろうと思います。それにしても、上等の絹の袖だったろうに、こんなに濡らしてしまって絹は痛まなかったのでしょうか。
今日の場面では【いちはやき世】という表現が印象に残りました。生き馬の目を抜く、陰謀うごめく時代は、コワイわー と、上品な左大臣は思っちゃったのですね。上品は何時だってやり手には負けます。
・ 左大臣との別れの場面は、難しい言葉が多く難解だった。
源氏は、どうして須磨に行く事になったかを語るが、その場の空気は重く感じた。そこへ現れた若君の無邪気な
様子は重い空気を和ませてくれたが、この先、この若君はどう成長していくのか。
・ いつの時代も人は政治の中枢から離れると状況は激変しますが、源氏と左大臣の対話はしみじみそれを実感し
ます。悲しく重苦しい雰囲気の中に若宮の子供らしい振る舞いは救いです。【膝にすゑたまへる御けしき、忍び
がたげなり】は親子の情景がうかびます。女性との華やかな印象が強いので、源氏に父性(若宮への愛情)が描
かれているのに驚きました。
・ 須磨へ立つ前に久し振りに訪れた左大臣邸。人目を忍ぶその姿を左大臣家の人々は【夢とのみ見ゆ】と。
桐壺帝の時代をあれこれ思い出し、源氏の今の境遇を悲しむ左大臣。誰よりも源氏を愛し、源氏も心から頼りに
していた二人は右大臣一派の【いちはやき世】を本音で語りあう。葵の死後この邸を去った時の【しほたれた】
女房たちも又彼を暖かく迎えた。若君の可愛らしさが物語を明るくしていた。
原文からひろがる源氏物語 須磨 2017年2月1日受講
【須磨退居】
【須磨】が始まりました。物語は【賢木】の続き。
源氏と娘との密会を弘徽殿大后に駆け込み訴えした右大臣。その弘徽殿大后の脳裏に次々に映し出された今までの屈辱の日々。鬱憤は、父親のとりなしの言葉で増幅し、【いとどいみじうめざましく】三連続形容詞でブチ切れ、【構へ出てむに、よきたよりなり】今や源氏の運命は、弘徽殿の女御に委ねられる。という場面で【賢木】は終わりました。そして今、【世の中いとわづらはしく、はしたなきことのみまされ】完全に追い詰められている源氏。※【安和の変】の源高明の様に流罪になる恐れを感じ、畿内の最果て、在原行平が流され、古今集の歌を詠んだ、あの須磨へ行こうと決心します。田舎の須磨への不安と都への思いで心は乱れます。気掛かりなのは紫の上。彼女は、本当に一人ぼっちになってしまう。いっそ連れて行こうか?いやいやそれは叶わぬ事。二人の愛情の深さと繋がりの強さを、先人の和歌を多用し、式部は力を入れて書いています。そして仏門に入った藤壺からの度々の文に、叶わなかった恋を懐かしみながらも【心をのみ尽くすべかりける人の御契り】であったと。源氏にとって、桐壺帝の時代が終わりました。
源高明が流罪になった史実と同じ頃の三月二十日過ぎに、源氏は【いとかすかに】ひっそりと七八人の供人と都を出発しました。出発にあたり、大事な女たちには、彼女たちが自分を哀れと思ってくれる様な、見所の多い手紙を送った様で、悲しみに紛れきちんと聞いておかなかったのは残念です。と、語り手が。
※【安和の変】969年は、源氏と同じ天皇の子供でありながら讒言密告により流罪になった源高明。
首謀者は、藤原兼家(蜻蛉日記974年作者の夫)。源氏物語1010年。(中古文学史年表)
読後一言感想
・ 【賢木】の最終をすっかり忘れ難儀した。
身に迫った危機に追い詰められた源氏は、先人の様に謹慎する事で畿内最果ての須磨を選んだが、都の様に華やかでなく、荒涼した処に住めるか思い悩む。
果たしてどのような暮が待っているか、この先どうなるか。
・ 【須磨】に入りました。
【空蝉】を読んだ後に【須磨】に入ったので、その間の、【賢木】等の部分を私は読んでいないので、あれから
源氏は九歳ばかり年を取った事に、やや戸惑いを感じました。私事ですが、私は海の傍で育ったので、隣に海が
ある事に懐かしさを感じますが、ぐるりと山に囲まれた安全な都に住む貴公子が、波が打ち寄せる、汐風が吹き
すさぶ辺境の地に移り住むのは、どれだけ不安だったかと思います。その移動を、源氏は自分で決断したのです
ね。都の人が親しいウミと言えば琵琶湖。所詮は湖だったはずです。それが本当の「海」の方へ行くのはコワい
だろうな、と思うのです。
・ 本日から【須磨】に入る。
この時、源氏は二十六歳という。これまでに親交のあった多くの女性たちに別れを告げ、消える様に、京を後に
する。源氏物語はフィクションだが、今回の背景にある「安和の変」という史実を知らないと理解出来ない。
先生のそういった解説も面白かった。次回からも楽しみだ。
・ たぐいまれな容姿、深い教養、全て備えた若き源氏。激しく突き進む禁断の恋愛、奔放な恋、青春を謳歌した
時代は終わり、初めての逆境になります。自ら身を引く事により新しい時代に入りますが、これからの源氏が、
どの様に変わるか楽しみです
・ 源氏、初めての挫折。
不幸は物語を面白くする。【須磨】のプロローグは、源氏の状況と女達の心情を簡潔に述べている。
次への期待が高まる構成だ。やはり紫式部は凄いとしか言えない。
・ 【夕顔】の最後から【須磨】へ。【賢木】の最後の弘徽殿女后の呪いの言葉を思い出しました。
紫の上との別れは本当に辛く、繋がりの深さがしっかり書かれていました。入道の宮(藤壺)から度々来る秘密
の文。昔こんな気持ちをもらえたら嬉しかったけれど、二人が苦しむしかない前世からの宿縁であったと改めて
思います。都に多くの女たちの悲しみが溢れる中、源氏はそっと都を後にしました。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 夕顔 2017年1月11日受講
【伊予の介と対面す・空蝉の文・二道の別れ】
【空蝉】は前回終わりましたが、空蝉は【夕顔】の中にも書かれており、今回【夕顔】の中の空蝉を追いました。
源氏が夕顔に逢う前まで女君と源氏の文の交換は続いていた様。その間に伊予の介が伊予から船旅で戻り、真っ先源氏の元へ。愛する女の、年取った夫を十七才の源氏は、細部にわたって観察し、その大人大人さに対し、自分を【なのめならぬかた】と認め、彼の為には女君に拒否されて良かったと。娘は嫁がせ、妻と伊予へ向かうとの話に、もう一度会えないかと思いますが難しい。夕顔の出現で源氏からの手紙は、ぱったり途絶えました。女君の時間は止まったまま。噂で聞く源氏の病気は自分が原因と考え、思い切って手紙を書きました。源氏からの、貴女を忘れていないという小袿を思わせる[空蝉]の文字と、弱々しい【うちわななかるる】筆跡は、更に彼女の恋心を膨らませましたが、それでもまだ理性的な気持ち【いふかひなからずは見えたてまつりてやみなむ】を保てていられました。しかし、伊予への旅立ちに際し、源氏が返してきた小袿と【ひたすら袖の朽ちにけるかな】の歌を目にした時の衝撃は、彼女の恋する女の本性を呼び覚まし、【ねは泣かりけり】の歌を源氏に叩きつけ伊予へ下って行きました。空蝉は【あやしう人に似ぬ心強さ】の女として源氏の中に残りました。【過ぎにしもけふ別るるも二道にゆくかた知らぬ秋の暮かな】何と寂しい歌でしょう。時雨れる空の下、二人の女に一人置いていかれた源氏の悲しさが痛い程感じられます。軒端の荻については、今回時間不足で割愛しましたが、常に空蝉と並行して登場させ、その名前の由来の歌もあり、歌が非常に重要な物語の構成要素でした。
読後一言感想
・ 空蝉は慎み深く貞淑な妻と思っていましたが印象が覆りました。夕顔と空蝉は後ろ盾を失い、上の品から外れましたが全てが対照的な気がします。空蝉は現実を冷静に見つめ、生きていく道を決めたが、心にマグマのように激しい想いがあります。源氏への最後の文には今まで抑えていた想いが一気に爆発し、悲しみ、絶望感が溢れます。素直に感情を出した時、恋は終る。残酷です。空蝉(蝉の抜け殻)とは小袿と思っていましたが、もしかして、女君の恋?女君自身?
「過ぎにしも・・・」それぞれの旅立ちには相応しく、立冬の時雨の寂しさ、しみじみとした情緒と余韻が残りました。
・ 源氏が空蝉を忘れられずに悶々としている間に、源氏が方違へで自分の家に寄ったことを知ったであろう伊予
の介が都へ帰って来たという。【まづ急ぎ参れり】。仕事上の報告とは言え、【まづ急ぎ参れり】というところ
に、源氏の少しあたふたとしたであろう気持ちがよく表われている。「えっ!!来るの!!」って感じ。
源氏は伊予の介をよく観察する。源氏はあらぬことを考えているのに、伊予の介は真面目に国の話をする。伊予
の介は容貌など【ねびたれど きよげにて ただならず ものまめやかな】大人であった。源氏の前で堂々と報
告をする伊予の介は、源氏に【おこがましく うしろめさ】を感じさせる。伊予の介は自信に溢れている。
後ろめたい事をしているから源氏は押され気味なのか。いや、伊予の介は我が妻に自信があるのだ。勿論空蝉に
は後妻となったわが身を嘆く気持ちはあるが、伊予の介は妻としての空蝉を愛おしく、また家の主としての空蝉
を頼もしくも思っているだろう。この自信に源氏は負けている。そして源氏はあの雨夜の品定めの時、左馬頭が
した【ものまめやかな】男と、男に【たもたるる】女、縁があって結ばれた夫婦のあり方の話を思い出していた
に違いない。【なのめならぬはかたは なべかりける】最後に源氏から小袿を返された空蝉が源氏の気持ちにす
がる様なくだりがあるが、大丈夫、伊予の介は妻を守り、賢い空蝉は【たもたるる女】として幸せに生きてゆく
だろう。
・ 【空蝉】は心理的描写がすごく、とても難解だったが、源氏をひたすら拒んでいたのに突然別れを言われ、本
音を言った空蝉。思っていた事を言えて踏ん切りがついたのでは?しかし、唯一の繋がりだった小袿も返され、
もう本当の終止符を迎えました。内容の濃い巻でした。
・ 今回は【夕顔】の中に登場する空蝉をひろった。へえ~、こんなに出てくるんだ、と面白かった。歌で終わっ
た【空蝉】の巻も良かったけれど、【夕顔】の終わり方もしびれる。空蝉というと、あんなパッとしない女と言
われがちだが、私はやっぱり空蝉が好きだ。
・ 【帚木】、【空蝉】、【夕顔】は三部作であったと改めて確認しました。【空蝉】の最後の源氏に届かない歌【うつせみの羽に置く露の木隠れて忍び忍びに濡るる袖かな】、小袿を返した源氏に対して自分をさらけ出した歌【蝉の羽もたちかへてける夏衣かへすを見てもねは泣かれけり】が同じ女性の歌とは思えない。空蝉の自分でも抑えられないどうしようも無い気持ち。袖を濡らす露だった涙。今は声をあげて泣いている。
若さの残酷さ。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 空蝉 2016年12月7日受講
【源氏、御達をまく・しのぶの薄衣・うつせみの心】
暁近い煌々と輝く月の下、緊張続きの物語を、老女房お腹下しのひょうきん話で緩ませる。この女房源氏の香に気づく余裕もなく。無事に屋敷を抜け出し二条の院に帰る。語り手【いよいよおぼし懲りぬべし】とは言うけれど、伊予の介に負けたと、小君を攻めに攻め、【つらきゆかりにこそ、え思ひ果つまじけれ】意地悪な源氏。彼が畳紙に書いた、女君を蝉に例えた未練の歌【うつせみの身をかへてける木のもとになほ人がらのなつかしきかな】を小君は懐に入れる。例の【人香】を残す薄衣を傍らに置きながら、西の御方も心に浮かぶけれど諸事情を考えて、まあいいか。姉は弟を待ち構え、【いみじくのたまふ】相当怒っています。まずは、人の目を恐れ、源氏の仕打ちを攻める。小君は【左右に苦しう】、そして例の畳紙の歌を姉に。【さすがに、取りて】源氏の歌に釘付け。あの薄衣の行方を知り、自分の汗臭い衣が源氏の元にある事に【いとよろづに乱れ】、一方、西の御方は、源氏との夢の様な出来事に【ものはづかしきここち】で、自分の部屋に帰る。手紙もくれない源氏の仕打ちに驚き呆れる考えもなく、唯ぼんやり過ごす若さを、語り手【ものあはれなるべし】。【つれなき人】空蝉は、真面目に自分に迫った源氏に、昔の自分であったらと再び想いを。そして、源氏には決して届かない、自分の本心を源氏の歌の片隅に書いた歌に込める。
【うつせみの羽に置く露の木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな】
読後一言感想
・ 【空蝉】の巻が終わりました。
【雨夜の品定めの】場面で、源氏の君は中の品の女との恋を勧められ、ここで初めて実際に中の品の女との出逢いが語られました。源氏にしてみれば、中の品の女など、自分が仕掛ければ軽々となびいてくるものと思っていたのでは・・・。ところがどっこい、空蝉の君は、身動きの取れない境遇に落ちた事から、深い内面を持つ、手強い女でした。源氏を受け入れる事の出来ない空蝉は可愛想で、同情してしまいますが、ちょろいと思っていた女に、そで にされた源氏には、いい薬だったと思います。
・ 今日の一番の山は何と言っても、源氏と空蝉の歌でしょう!
源氏は畳紙に、手習いの様に書きすさぶ。【うつせみの身をかへてける木のもとに なほ人がらのなつかしきかな】一方空蝉は、小君に渡された源氏の歌を見て、【いとよろづに乱れて】この畳紙の片つ方に、【うつせみの羽に置く露の木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな】としたためる。二人は、相手に届くとも思わずに歌を詠むが、とてもしっとりと、いい歌である。源氏の、後妻に来た若い女に対する興味から始まった恋であるが、空蝉の人柄がやはり優れていたのでしょう。
【空蝉】の最後は中々しっとりと終わりました。
・ 空蝉にソデにされた源氏は、小君に怨み言をこぼす。「他人でもいいから優しい返事をして欲しい」なんてね。源氏が「友だちでもいい」なんて、そんな事無理でしょ。
小君も源氏の為に一生懸命なだけに、ちょっと可哀想ですよね。
・ 源氏の深い気持ちを頑に拒んだ事を、二度と再び戻らぬであろうと胸に収めるも、小君が渡した源氏の歌の畳紙の隅に書いた自分の恋心は、源氏は知らずに過ぎてゆく。何とも切ない【空蝉】の最後でした。
・ 御達は【一昨日より腹を病みて】【たけ高き人の常に笑はるる】など下世話な話をし、道化として登場します。女房生活の様子を垣間見た気がします。「空蝉」に御達の話があることを初めて知りました。
突然事故に会った西の御方は【人知れずうちながめて】【胸のみふたがれど御消息もなし】源氏は無視し切り捨てます。受領階級の恋の駆け引きも知らない、若く無邪気な女性。空蝉の身代りをさせられ、その上対照的な酷い扱いは、切なく哀れを感じます。
・ 歌で、それも相聞ではない、相手に届かぬ片想いの歌で巻を終わらせ、女の悲しみを深く伝える上手
さ。登場人物達のままならない気持ちを表す多くの言葉。【あはむ】【うらむ】【憎む】【憂し】【心づきなし】【わびし】【左右に苦し】【あさまし】【忍びがたし】等々。古語の表現世界の奥深さ。登場人物皆がモヤモヤしたままの終わり。読み直し、改めて空蝉の揺れに揺れた女心が理解出来ました。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 空蝉 2016年11月2日受講
【もぬけ・人違へ・西の御方と】
小君、今度は妻戸を叩いて部屋に。皆寝静まるまで【空寝】。二度の【やをら】で、二人がいかにそーっと動いているか。その静寂の中【御衣のけはひ、いとしるく】。源氏との突然の出会いを思い出し【心解けたる寝だに寝られず】の女君、その微かな衣擦れの音に気づく。隣には一緒に碁打ちした義理の娘がスヤスヤと。香の香りが漂い始め、頭をもたげた女君には、近づいて来るあのお方が誰かはっきり分かった。【あさましく】驚き呆れ、何が何だか【思ひ分かれず】【やおら】起き出て下着姿で部屋から【すべり出で】た。
部屋に入った源氏。一人だけ寝ていて安心して近寄るけれど、おや?何かが違う!寝ている山が【ものものしく】、【いぎたなく】寝ている女。この前とは【あやしくかはり】人違いだ!逃げられた!これ程嫌なら仕方がない。あの碁打の相手なら、まあいいか。と思う源氏を、語り手が【わろき御心浅さ】と。
若い女は目覚めが遅い。目覚め、現状に驚き、呆れ、呆然と。それを眺めながら、女を評価する源氏。ここをどう乗り切るかを冷静に考える。女君が関わっている事を知られてはならない。思い通りにならない女君への想いは更に募る。【なま心なく若やかなる】女と【情々しく】契った後、決して人に知られてはならぬと、「人目をはばかる事がある訳でもないけれど、我ながら自由にはならない身の上、貴女のご両親も許さないだろう、私を忘れないで待っていて下さい」等々、【なほなほしくかたらふ】ありきたりの口説き文句。
若い女、【うらもなく】無邪気に便りはしないと言う。「小君を通じて便りをしますから、何も無かった様に過ごして下さい」この事は二人だけの秘密と確約を。帰りがけに逃げた女君が【脱ぎすべしたる】と思われる薄衣を取って出て行く。
読後一言感想
・ 碁打ち後、源氏を、源氏を想って寝られぬ夜を過ごしていると、何やら香しい香りと衣擦れの音。源氏と気付いた女君は素早い反応に出る。【あさましくおぼえて、ともかくも思ひ分かれず、やをら起き出でて、生絹なる単を一つ着て、すべり出でにけり】好きな場面です。
気付いた時、それはもう一人の女だった。この事が周りの人に知られてはまずいと考え、上手く言い聞かせ、その場を去った。お芝居に出て来そうな場面でした。
・ 人違へをしてしまった源氏が、【情々しく契り】【人知りたることよりも、・・あはれも添ふこと】等と言いくるめたり、【忘れで待ちたまへよ】と約束を交わしたりと、女性の扱いに慣れたプレイボーイの常套句を使うおかしさと、【やおら生絹なる単を一つ着て、すべり出でた】空蝉の様子や、その【脱ぎすべしたる】薄衣を取って出て行く源氏の様子が、映像として鮮明に浮かんで来る、とても印象的な所でした。
・ 今日、読んだ所は空蝉の巻のクライマックス場面でした。
夏の夜、蝉が殻を脱いで飛び立つ様に、空蝉の君も薄衣を残して闇の中に滑り出てしまいました。空蝉は素敵に姿を消して、余韻だけを感じさせて、一枚上手な女を演出出来たけれど、残された源氏の君と軒端の荻はどうすればいいのでしょう。(空蝉は軒端の荻に対して何の思い入れもない。一緒に碁を打ったりおしゃべりしたりしても、軒端の荻なんて歯牙にもかけていない事が分かる)その後の源氏の歯の浮くような荻に対する口説きは、私は嫌い。私が荻になって源氏のムジュン点を突いて、源氏を傷つけてやりたくなりました。この場面で源氏は、【情々しく】契りを荻と結ぶ訳ですが、荻の事なんてちっとも好きではないけれど、これはこれで、まあ良しとしよう、と荻に対して形式的には心を尽くして振舞ってみせる、プレイボーイのプレイボーイたる所以の場面を読む事が出来ました。
【情をかける】という言葉の本来の意味を知りました。
・ 空蝉は【昼はながめ】、【夜は寝覚めがち】で恋に悩んでいますが、源氏の気配がすると【すべり出でにけり】と、とっさに対応してしまいます。源氏はその為に心ならずも西の方を口説く事になりますが、空蝉は何処に隠れ、どう思ったのでしょうか。その後、聡明で理性的な空蝉と、義理の娘の軒端の荻との関係は・・・。
・ 源氏⇒女君⇒源氏と、まるで脚本の様に物語は進む。闇の中の衣擦れの音、うっすら見える人影と香の香り。正に五感で読む世界。【情々しく】契った若い女の【うらもない】無邪気さが哀れ。
女君を【本意の人・つらき人・うれたき人・執念き人】と書き、源氏の無念さを強調していた。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 空蝉 2016年10月5日受講
【碁打ち・かたちくらべ・小君、たばかる】
御簾の隙間から、碁打ちする女の、衣装、衣装の色、髪、額、口元と舐めるように観察する源氏。
胸を肌け【つぶつぶと肥えて】いる若い女は、【にほひ多く見え】、少し品はないけれど、【おぼし放つまじ】。一方、自分が求める女は、【鼻などもあざやかなるところなうねびれ】【わろきによれる容貌を、いといたうもてつけ】これでもかと魅力の無さを書き連ねた後、それが彼にとっては【心あらむ】【目とどめつべきさま】? 今まで見た事のない女たちの打ち解けた姿。ずっとずっと見ていたい。
人々が寝静まり、いよいよその時。源氏は、幼い小君を信じています。でも、【たわむところなくまめだちたる】姉の性格を良く分かっている小君は、姉に源氏が来ていると言えない。人目が少なくなったら源氏を姉の部屋に入れてしまおう。やっぱり子共です。源氏は【紀伊の守の妹・・かいま見させよ】って、ちょっと前にもう見ているのに・・・。
そうして夜は刻々と更けていきます。
読後一言感想
・ 全く対照的な二人。
軒端の荻は、【つぶつぶと肥えて】【はなやかなる容貌】【品おくれたり】、一方空蝉は、【痩せ痩せにて】【わろきによれる容貌】【心あらむと、目とどめつべきさま】。
若き源氏が恋焦がれたのは、若く美しい人より、聡明で上品な女性。暗く灯火が揺らぐ中、二人で碁を打ち、華やかで明るい笑い声や打ち解けた様子は、まるで舞台を観ている感じがしました。
・ 源氏は、簾と簾の間に身を潜めて母屋を覗く。
【つぶつぶと肥えた】【愛敬づきたる】女が居る。【親の世になくは思ふらめと、をかしく見たまふ】が、【碁打ち果てて、『十、二十、三十、四十』などかぞふるさま、伊予の湯桁もたどたどしかるまじう見ゆ】。当時の男性は、あまり数にも強く、テキパキした女性は、【品おくれたり】と思うのですね。
都知事の小池さんの、「一兆、二兆、三兆なんて、豆腐屋じゃあるまいし!」なんて、歯切れよく言う人はダメなんですね。
・ 対照的な二人を、面白く比較していると思います。
物静かであまり美人ではない女と、【すこし品おくれたり】と思わせる女。
だが、源氏は外見よりも、奥ゆかしさに惹かれた様な気がします。
・ 【空蝉】の巻は、源氏物語の中でも[会話]が多い巻と言う。そして、源氏が今で言う[覗き魔]の如く、中の品の女たちの、打ち解けたやり取りを目の当たりにするのだ。碁打ちの場面では、軒端の荻と空蝉の容姿を対比させていて、源氏の[女性感]が良く伝わってくる。
女は若けりゃいいってもんじゃないのよ。
・ 今日、読んだ所は、空蝉と軒端の荻が碁を打っている姿を、源氏が盗み見する場面でした。当時の人達、それも貴族の連中と、現代を生きる私の美意識は全然違うものとは思いますが、ここに描写されている軒端の荻は、むしろ生き生きした素敵な女の子に思えました。【つぶつぶ】なんて言葉も、とても印象に残ります。ふっと、十代の頃の溌剌とした、女優の小池栄子さんが念頭に浮かびました。もしかしたら、空蝉も、軒端の荻に圧倒されるところもあったかもしれない?それとも、開けっ広げな荻に、「やっぱり生まれながらの中流の女は騒々しいわー」とか思っていたのでしょうか?
・ 灯火に浮かぶ、若く【つぶつぶと肥えて、そぞろかなる】女を、舐める様に観察する源氏。とても魅力的だけど、見栄えは今ひとつでも、やっぱり求めるのは、元は上の品のあの人。覗き見なんて、全くもう初めてで、源氏の瞳孔は開いたまま?正に未知との遭遇。古語がそのドキドキ感を増幅し、灯火が、目の前の景色を効果的に浮かび上がらせる。今はもう小君を信じるしかない源氏と、【たわむところなくまめだちて】いる姉の心を知る小君。さあ、どうなる、どうなる。 ―続き―。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 空蝉 2016年9月7日受講
【それぞれの夜・三度挑戦・碁打ち】
生まれて初めて女に振られ、落ち込んだ源氏は、可哀想だと涙を流す小君を抱きしめる。【あながちにかかづらひたどり寄らむも、人わるかろべく】等色々考え、眠らないまま深夜、小君に声も掛けず屋敷を後にする。女も源氏を想い【かたはらいたし】の眠れない夜を。その後源氏からの文は、ぷっつり途絶え、揺れる、揺れる女心。でも、源氏は諦めてはいなかった。面目丸つぶれのままではいられない。「もう一度機会を与えよ」と小君に迫る。そして、三度目の挑戦。小君の車に隠れ、夕闇に紛れ紀伊の守邸に潜入。小君緊張の中、源氏は主不在の無用心な屋敷の中に入り込み、暑さで布が上にめくられた几帳の隙間から女を垣間見る。灯火に自分が心を掛けている女が浮かぶ。【頭つきほそやか】、【ものげなき姿】、【手つき痩せ痩せにて、いたうひき隠しためり】これが私を振った女? えー?
小君が大活躍。本当に源氏が好きになったのですね。読者をドキドキさせてくれました。
読後一言感想
・ 十七歳の男性ホルモンに乗っ取られた源氏は、小君の車に忍び込んでまで空蝉に会おうとする。
【さのみもえおぼしのどむまじかりければ】という所に源氏のはやる心が良く出ている。
一方、空蝉は、【やがてつれなくて止みたまひなましかば憂からまし・・】と断りながらも、源氏との関わりが絶えてしまう事を恐れる。
一途な男と、自分の立場をわきまえ過ぎた女の違いが、こんなにも上手く書かれているとは!!
・ 初めて振られ、驚き、動揺し、傷つきながらも、逃げる女を追う源氏。
自から心を決めて源氏を拒むが、文が断えると心が乱れ、より強く源氏を想い惹かれる空蝉。
情報や知恵を集め、芝居がかった行動で源氏を手引きする小君。源氏の為に必死で画策する小君は、子供から急に大人になった気がします。小君の源氏への尽くし方は、いじらしく、切ない感じがしました。
・ 【空蝉】今日から空蝉の巻に入りました。
空蝉の君の、あれこれと思い悩んで、心が千々に乱れる様子と、源氏の君のプライドを傷つけられて、何とか想いを遂げたいと、じたばたする様子が対照的で少し可笑しかったです。きっと質素な服装(なり)で、小君の車なんかに乗せられて、これが最後のチャンス!とばかりに出掛けていく様が目に浮かぶ様でした。それにしても、小君の様な子供に手引きさせて女君に逢いに行くなんて・・・源氏の君のなり振り構わない直情に、空蝉も小君も、「こおいう所はちょっと困るのよねー」とか。ちらりと思われてしまう所に、源氏の君の【絶世の美男】に納まり切らない面白さを感じました。
・ 初めて知った中の品の女に魅了され、「恋こそ命」の源氏。女の頑なの心に、【われはかく人に憎まれてもならはぬを】【はじめて憂しと世を思ひ知りぬれば】悶々とした思いを小君に投げかける。幼い小君は心を悩ます。涙して臥している小君の寝姿に気持ちが昂ぶり、あの夜の逢瀬の女への想いは募るばかり。古語ならではのニュアンスを読み手は受け止める。
源氏の愛と、我が身の立場に揺れる女【なみなみならずかたはらいたし】空蝉の巻、想い入れた女を執拗に求める源氏の姿に、平安の人々もさぞかし心ときめきて・・・。
・ 空蝉が拒んだ事によって、源氏も眠れぬ夜を過ごし、拒んではみたものの、相手に恥をかかせた事に申し訳なかったと、こちらも悩み、どっちもどっちかな、気になる存在なんです。でも、源氏はここで引き下がりません。挑戦して、とうとう女を目撃するのです。まずそれは成功?したのですが・・・。
次が楽しみです。
・ 男と女のそれぞれの夜。男【ながらふまじく】までのショック。女【かたはらいたしと思ふに】、【閉ぢてむ、と思ふものから】短い文の中に【思ふ】が三度も。心の迷いが、これでもかと書かれる。
源氏への想いで【涙さへこぼし】、手引きまでして、必死で愛されたい小君が哀しい。
【夕闇の道たどたどしげなる・・】が万葉集からとは、深い!
源氏が垣間見た空蝉の姿は、【頭つきほそやか】、【ものげなき】、【手つき痩せ痩せ】あまり美しくないもの。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき) 2016年8月3日受講
【手引き・帚木の心】
小君を使った逢瀬は失敗。【とてもかくても今はいふかひなき宿世】【無心に心づきなくて止みなむ】と【思ひ果てたり】。源氏への想いが強いからこそ、この恋を諦める強い心が必要な女君。一度も女から拒まれた事のない源氏に【あさましくめづらかなりける心】の女の仕打ちはあまりに酷い。二人の心境を素直に表した【帚木】の歌。夜が明けようとしても源氏は、女君を【すずろにすざまじくおぼし続け】【めざましくつらい】諦められない。小君の必死さが、物語に動きを与え、愛おしかった。
【とぞ】という言葉で【帚木】が終わり、次回から【空蝉】に。新しい人物が登場すると、巻が変る。
読後一言感想
・ 【帚木】とは遠くから見ると在るから、近づいていくと、あら?無い! という不思議な伝説の木。
当時は周知の歌枕だったのでしょう。【帚木の心を知らでそのはらの道にあやなくまどひぬるかな】と源氏が詠む時、【帚木】は【空蝉の君】を指している。空蝉の返歌にも、【・・あるにもあらず消ゆる帚木】と、私(空蝉)=【帚木】としている。私は生きていても、もう死んだも同然の女なんです。と言っている。そして【帚木】とは【空蝉】であると同時に、空蝉の心の中に生えている幻の木だと思った。つまり、本来なら上の品であった私、両親が生きてさえいたら宮仕えさえしていたかもしれない私・・・。そしてその頃に源氏に逢えていたら、たまの逢瀬も叶ったかもしれない私。今在る中の品に落ちた私ではなく、本来あるべきだった幻の私。
空蝉がどれだけの悲しみの中にいたかと思うと、泣きたくなりました。そして空蝉の深さに比べて、源氏は、こどもっぽいと思いました。 空蝉の毅然 ⇔ 源氏の呆然
・ これまで抱いていた空蝉のイメージが変わった。
何となくハッキリしない、ぼやけた感じで薄い印象だったのが、「あら、まあ」です。ハッキリしないどころか、彼女の心の底には「白か黒か」という、揺るぎのない芯の様な物が通っていたのね。
「ま・じ・め」なんですね。 空蝉の心理描写が凄い!
・ 【方違へ】の方法をとってまで女君への想いは、凄まじい。
源氏の君の想いを姉君に伝えたいと所在を懸命に捜す小君。やっと逢えた姉君に【いかにかひなしとおぼさむ】と泣きそうに言うと、姉君からは【かくけしからぬ心ばへは・・いみじく忌むなるものを】。
弟を可哀想と思いつつも、今の立場を守り抜く女君の切なさ。【帚木】になぞらえた、二人の切々とした歌。式部の筆致の極み。小君を【あはれ】と思う源氏の心情も語り手は添える。
難解な平安の言の葉から三人の心情が熱く伝わって来ました。
・ 源氏は、女君に拒まれて相当のショックを受けたが、女君は女君としての切ない気持ちがあったと思う。女君は、中の品の女の、自分を持っている人、自分を主張する人を貫き通している。
橋渡しの小君が間に入って痛ましかったが、最後に源氏の【あこだに、な捨てそ】にホッとした。
・ 源氏を頑なに拒んでいますが、心の中は、【品定まりぬる身】【親の御けはひ・・ふるさと】と、昔の事を想像する女君が切なく、哀しい。元上の品として、意志の強さで理性的に対応する女君。
中の品になった今、【宿世】と思い込もうとしていますが、断ち切っても、文章から源氏への想いが切々と伝わって来ます。
・ 前回では、空蝉に女性って現実的ね・・と思ったが、もう少し読み進めると、上の品から身を落とした女性の悲しさをしみじみ感じた。後妻という立場、自分の魅力の無さを、良くわきまえている。
源氏は、空蝉の立場を理解していない。相手の立場を理解しなきゃ、恋は発展しないよね。源氏は、一生懸命に源氏の気持ちに寄り添おうとする小君を【いとほし】と思う。【つれなき人よりは、なかなかあはれにおぼさる】と、【御かたはらに臥せたまへり】若い男の子って可愛いよね。
・ 前回読んだ時は、女君のプライド、美意識なんて理解出来ず、ただ面倒臭い女だと思いました。でも、今回浮かんで来たのは、中の品に落ちてしまった自分を憐れむ哀しい女。そして、ただただ女を追い求める源氏の気持ちとのギャップでした。十七歳で初めて求める女に拒絶された源氏が、小君を思わず抱きしめたとしたら・・・。心が安らかになった事でしょう。源氏もまだ子共ですもの。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき) 2016年7月6日受講
【使者小君・手引き】
首を長くして女君の手紙を待っていた源氏の前に、小君は何も持たないで現れ、落胆させます。更に新しい手紙を小君に託した後で、【あこは知らじな】自分は姉上を【伊予の翁】よりも【先に見し人】。でも私が【たのもしげなく、頸細し】だから姉上は私を馬鹿にして、あの爺さんを【ふつつかなる後見】にした。でも、お前は私の子、【たのもし人(伊予の介)はゆくさき短かりなむ】。若い源氏の年寄り伊予の介に対する挑戦的な言葉の数々。【さもやありけむ、いみじかりけることかな】と感心し自分を信じ込む小君を【をかしと】思う。今や小君は源氏にべったり。女君に源氏からの文は常に届けられたけれど、源氏の様な身分の高い人から想われる事をとても似つかわしくないと思うと、この素晴しい事も、今の自分は受領の後妻の立場なのだからと、心を許した返事も書けません。源氏の微かに見えた様子、有様は、実際普通ではなかったと思い出さない訳ではないけれど、自分の心のときめきを源氏に見られても、【何にかはなるべき】一体何になるというのか等と女君は思い返すのでした。源氏は、ずっと女君を気の毒にも恋しくも思い出し、思い悩む様子などの不憫さも思い続けるのです。こっそりと紛れて、紀伊の守の家に立ち寄りたくても、人目が多いだろう所に、自分の振る舞いが人に知られてしまうだろうし、女君の為にも気の毒だと悩んで動きが取れないのです。
内裏に何日も逗留していた源氏についに【かたの忌み】が。左大臣邸に帰る振りをして、突然紀伊の守の屋敷に現れる。紀伊の守驚き、感動。小君とは打ち合わせ済み。女君にも前もって訪問を手紙で知らせます。女君は、はかりごとを考えるまでして逢う程浅くは思っていないけれど、だからといって心を許し、卑しい自分が会ったとしても、どうにもならなく、夢の様に過ぎたあの嘆きを又加えるだけ。と、思い乱れて、やはりその様な形で待ち受ける事は相手が立派過ぎて恥ずかしいと、中将という女房が部屋を持っているちょっとした隠れ所に移りました。
読後一言感想
・ 源氏は小君を恋文の使者にと~
【君、召し寄せて・・~まことに親めきてあつかひたまふ。】 の九行の原文のユーモラスな表現。源氏の言いたい放題の言葉に、小君【さもやありけむ】と納得し、まめまめしく姉の元へと。女君は、源氏の【心苦しくも恋しくもおぼしいづ】熱い想いに宿世を顧み、困惑し【つきなかるべく】思う。
源氏は再度の【方違へ】に、紀伊の守の館へ計画実行。そして、源氏の思いは・・・。女君のとった行動は・・・。 原文からひろがるイメージで読む物語の世界である。
・ 小君は尊敬する源氏の為に恋の使者として働く。姉の気持ちを理解するには幼すぎますが、一生懸命さは初々しく可愛い。【いとつきなし】と覚悟を決めても源氏の面影を追う女君。覚悟とは裏腹の心の葛藤、切ない思い。【心苦しくも恋しくも】恋の成就の為には小君を巻き込みながら突き進む源氏。
次の幕が紀伊の守邸を舞台に始まる感じがしました。
・ 源氏の【ほのかなりし御けはひありさま】と【夢のやうにて過ぎにし】時を深く思いながらも、【何にかはなるべき】と、自分の立場を考えると身動きがとれず【思ひ乱れて】いる女君の姿、【おぼしおこたる時の間もなく、心苦しくも恋しくもおぼしいづ】源氏の姿、素直に源氏に従う小君の姿、それぞれの心情が生き生きと、女君の想いが切なく伝わる所でした。
・ 源氏が小君に話す【伊予の翁】やら【ふつつかなる後見】、【このたのもし人は、ゆくさき短かりなむ】やら、又、自分を【たのもしげなく、頸細し】。式部は、書いていて、思わず笑ってしまった?
【ほのかなりし御けはひありさまは、思いできこえぬにはあらねど】、【何にかはなるべき】、【あぢきなく、夢のやうに過ぎにし嘆きをまたや加へむ】女君(空蝉)の心中がかくも深く、丁寧に書かれていた事を改めて知りました。読み直して良かった!
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき) 2016年6月1日受講
心のこり・したごころ・にわかの文】
女君と別れの朝、有明の月がうっすらと。もう会えないと思うと空の景色さえ違って見える。中の品の女に初めて接し、左馬頭の話を実感。もう一度会いたい思いで紀伊の守を呼び、女君の弟を身近で使いたいと。【姉なる人】でもう【胸つぶれ】、子供の有無、夫との関係、容姿までも問う。紀伊の守答えるが、【離れてうとうとしく】【むつみはべらず】と源氏の下心を察する。目の前の小君は【こまやかにをかし】ではないが【なまめきたるさま】の、賢い、でも子供。姉宛の手紙を持たされる。女君【あさましきに涙も出で来ぬ】。【いと多くて】に長々と綴った源氏の言葉が。人に見られても良い様に作った、さりげない歌は【目も及ばぬ】筆跡。夢見た頂点の人からの手紙に【霧ふたがりて】【心得ぬ宿世うち添へりける身】を思い続ける女君。次の日源氏に召された小君、姉に源氏への返事を迫る。突っぱねるものの、弟は二人の関係を既に知っている!【つらきこと限りなし】。厳しい言葉【な参りたまひそ】。小君は結局返事を持たず参上。紀伊の守は継母への下心から小君を【もてかしづき】連れて歩く。 ※ 紀伊の守の【姉なる人にのたまひみむ】は敬語。舞い上がった彼の心情が表れている様。
読後一言感想
・ 【何心なき空のけしきも、ただ見る人から、艶にもすごくも見ゆるなりけり】源氏の初々しい恋心のまえには、どの様に見えたのだろうか。【帰りたまひても、とみにもまどろまれたまはず】、【姉なる人】という言葉に胸つぶれる思いをする源氏が、紀伊の守や弟を巻き込んでも、女君の様子を探ろうと
する勢いに源氏の若さを感じます。
・ 恋は一夜限りと決めた空蝉と恋の成就に賭ける源氏。空蝉は小君から手渡された手紙により胸の奥にしまっていた恋情を呼び戻され乱れる心と共に弟が源氏の元に呼ばれた理由を知り、二重の辛さ切なさ悲しみがあった気がします。
・ 源氏は女君の情報を得たくて【その姉君は、朝臣の弟や持たる】等と巧みに紀伊の守をくすぐる。紀伊の守は【さもはべらず・・・】と応ずるが、そのうちに源氏にうまく乗せられて喋り過ぎたのに気づき【もて離れてうとうとしくはべれば、世のたとひにてむつびはべらず】と、だんまりを決める。
源氏の会話の巧みさが面白い。
・ 互いの下心を感じつつ、知らぬ振りして言葉を交わし合う源氏と紀伊の守。若者らしい〈軽さ〉があり、千年前もおんなじだわね、と思う。それにしても源氏君、恋の為ならあの手、この手やるねぇ。結局は、空蝉の立場よりも、小君を手なづけてまでも、自分の気持ちを貫く。若さ故の一途さと言うべきか・・。 如何なものでしょうか。
・ 恋の一夜が明けて、源氏と空蝉の心のあり方がくっきりとコントラストを持って違っている、と思いました。まず源氏の方は、後朝の別れ、有明の月、美しい風景の中で名残りを惜しんでいる様子は、悲しみに暮れながらも美しくもあります。一方、空蝉にしてみれば、源氏とは背負っているものの重さ、身の境遇のどうにもならなさが、際立っている様に思えました。「どうして今になって、私にこんな事が起こるの?」運命にいたぶられている空蝉のやりきれない気持ちが哀れと思いました。
今日の前半、源氏に対しては、【嘆けとて月やはものを思はする かこち顔なる我が涙かな】という西行の歌を思い出しました。一方、空蝉には【ただこれ運命にして我が身のつたなきを泣け】という芭蕉の言葉を思い出しました。
・ まさかと思っていた源氏からの手紙に女君の今迄巡って来た境遇が【宿世】という言葉によく表されていると思う。また、源氏と姉と紀伊の守に振り回される様子も何だか切ない。小君が純粋だけに。
・ 【あさましき涙】と【霧ふたがる涙】女君の悲しみ、心の葛藤を深く感じさせる表現。
【月は有明にて光をさまれるものからかほけざやかに】自然描写の美しさ。
短い文章の中に、源氏、姉と弟、紀伊の守の心の動きが明確に書かれていました。【なまめきたるさま】は未熟な若々しい美しさで、小君を表すぴったりの言葉。まだ【なまめきたるさま】が残る源氏。
中の品の女を長々と話し続けた左馬頭を思い出しました
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき) 2016年5月11日受講
【口説き上手・夫の面影】
源氏の【例のいづこより取う出たまふ言の葉】の口説き文句に対して、汗だくの女君、【いとかやうなる際は、際とこそはべなれ】と【心はづかしき】程の迫力で拒否。軽い女ではないと、源氏【まめだちて】本気で迫る。比べ様のない美しさで自分に迫る源氏は、不釣り合いだと、切なく辛く、わざと無愛想で強情な女の振りをする女君。そんな女君を、源氏はなよ竹に例え、目の前で泣くこの女に会わなかったらどんなに心残りだったろうと。二人は段々本音で話し始め、「この出会いは宿縁なのに、どうして心を開かないのだ」と恨み言を言う源氏に、「もし私がこんな後妻でなく、娘の頃に貴方様に出会っていたら・・、この【仮なる浮寝】一夜の、はかない逢瀬を思うと心が乱れます。でも【よし、今は見きそなかけそ】」女君は決心します。源氏はいい加減な心でなく契り、慰めた様。鶏も鳴き、別れの時が刻々と。恨みと未練で、泣きながら離そうとしない源氏、夫への発覚を恐れ【何ともおぼえず】女君。でも、自分の身を嘆き彼女も叉泣きました。
読後一言感想
・ いやー 驚いた!! 空蝉って今まで凛とした女性というイメージしかもっていなかったが、式部はなんと空蝉を生身の女性として生き生きと描いていることか!確かに【数ならぬ身ながらも】【いとかやうなる際は、際とこそはべなれ】と強い言葉を吐くが、式部は男女の恋を倫理感などというもので縛る気は無い様である。空蝉は現実的な女性である様だ。次の朝空蝉は【伊予のかたの思ひやられて、夢にや見ゆらむ、と、そら恐ろしくつつまし】と感じるが、これもそれだけ自分が源氏に惹かれてしまったということで、自分のその強い思いが、伊予の方へ飛んで行ってしまい、バレることを恐れただけ。どうやら空蝉は自分の気持ちに実に正直な女性らしい。
・ 「歌は心の表現」。源氏と空蝉の一夜の逢瀬で交わした後朝の歌には、唸った。
揺れる女心が痛い程伝わるのよね。でも空蝉の立場や複雑な心模様は、深読みすべきですよね。
およすくにピッタリ。う~ん、空蝉ってこんな女性だったのね。
・ 「口説き天下一」と自負する男に圧倒されながらも【死ぬばかりわりなきに・・・】女は今の立場を守るため【つれなくのみもてなしたり】健気に対応する。女に【あはれなり】と思いつつも、気持ちは更に昂ぶり、【なさけなさけしくのたまひつくし】強引に迫る。女はこの場を収めるしか・・【仮なる浮寝】と応じる。何と罪作りな・・。しかし、二人の一夜は許されぬ恋となって炎になる。
式部の物語の展開に、今日も と き め い て。 今時の草食系男子は光さまをどう思うでしょうカナ。
・ 自分を持ってる女、主張する女として自分の前に現れた中の品の女は、源氏に対して拒み続けてはみたものの、【よし、今は見きとなかけそ】なんて、この場面ドラマですよね。
一夜は長かった?短かった?どっち? 短いのよね。
・ 今回、読んだ所は、感想を言うのが難しいです。空蝉の心の中の深い部分に感動しました。
空蝉は、自分の身を取り巻く環境の変化を嘆いていても仕方なく、どうにも身動きが取れなくなった時に、よりにもよって源氏と出逢ってしまうとは・・・。運命と言ってしまってはミもフタも無く、ただどうにもならない空蝉が哀れです。それにしても、「娘」だった頃の空蝉に源氏が逢っていたら、これ程源氏は空蝉に魅了される事は無かったのではないでしょうか。
・ 突然の侵入に恐怖におののき、必死に抵抗しますが、次第に源氏に傾いていく心の動きが鮮やかです。
今まで空蝉は源氏を拒み、この物語では珍しい貞淑な妻だと思っていましたが、地位があっても後ろ盾を失った女性の厳しさ、切なさを垣間見る思いがしました。源氏への思いは胸の奥にしまい、弟と共に夫の元で生きる道を選んだ空蝉。どんなことがあっても中の品(女)としての自覚と覚悟。
内面はか弱い女ではなく、現実を冷静に判断できる強さと潔さを感じました。
・ 刻々変わっていく二人の気持ちを、古語は生々しく伝える。鶏が鳴き、別れの時【ゆるしたまひても、また引きとどめたまひつ】泣く源氏に、女は【何ともおぼえず】。ただ夫を思い【そら恐ろしくつつまし】。初めて会った女との別れに際し、泣くほどまで自分をさらけ出したのは、自分になびかない女への恨み? 悔しさ?女は、今は気が張っているけれど、これから段々男が恋しくなっていく。それ程源氏は【なまめいて】いた。たった一夜の話なのに、何だかとても長く感じられました。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき) 2016年4月6日受講
【しのび込み・ちひさやかなる人】
暗闇の中、眠たくて自分への興味が薄い女君を源氏は【ねたう】【あじきなく】思う。女房の中将の君は不在。皆が寝静まった頃、しのび込む。【ば】の連続多用で、暗闇の中手探りで女君を求める源氏の動きが読者に生々しく伝わる。【中将召しつればなむ】と、おどける余裕がこの若さで?【や】と怯える女君は声が出ない。【年ごろ思ひわたる心のうち】?初めて会ったのに?源氏の【いとやはらかな】声は【鬼神もあらだつまじきけはひ】。女君は【はしたなく】叫ぶ事も出来ず【わびしく】でも【人違へにこそ】と弱々しい声で抵抗。それを【心苦しくらうたげ】で【をかし】と源氏。掻き口説く言葉の後【いとちいさやかなる】女君をかき抱き出ようとするその時、【求めつる中将】登場。【やや】と言う源氏。暗闇の中【探り寄る】中将の君。【いみじくにほひみちて、顔にもくゆりかかるここち】。【なみなみの人】ではない、【人のあまた知らむ】は大変。仕方なく源氏の後に。彼女の動揺に反して源氏は【動もなく】奥に部屋に入ってしまう。暗闇の中、声、香、衣擦れ、顔に掛かる衣。やっぱり五感で読む物語。
読後一言感想
・ 闇の文化を感じる場面だった。音、匂いが際立ち、五感をくすぐる。
現代は、何という光の洪水だろうか!!
・ 今の私は、あまりにも視覚にばかり頼って日々を過ごしている事が残念でなりません。夜の闇や、その中にあって、様々な違う種類の音を聴き分けたり、香りを聞き分けて物事を察したり出来る昔は、何て豊かな、広がりを持った世界が展開されていたことかと、思います。それにしても中将の君、貴女が湯なんかに行かずにちゃんと空蝉の傍に居て、内側から障子に鍵さえ掛けていたら、そんなに慌てふためく事はなかったのにねー。
・ 源氏は、興味津々だった伊予の介の後妻のもとへ忍び込んで行く。【いとささやか】に【ちひさやかなる人】が臥せている。源氏は、【いとやはらかに】口説き始めるが、【ちひさやかなる人】は、【はしたなく「ここに人」とも】ののしる事も出来ず、【消えまどへるけしき】であるが、【「人違へにこそはべるめれ」】と抵抗する。その様子が【らうたげなれば】源氏は【をかしと見たまふ】。
源氏は唯好奇心から忍び込んでみたが、思いがけず中の品の女の、自分をきちんと保とうとする様子に引かれてゆく。
・ 夜の暗い中【かれたる声】の小君と【ねぶたげな声】の女君の何気ない会話を、外から聞いている源氏。それから場面が変わって源氏が女君を突然口説く場面。暗い中での源氏と女君の動きばかりでなく、その表情やお香の香りまでが感じられ、さすが紫式部です。
・ 【や】。空蝉との出会いはこんなだったっけ~?
古語の一つ一つがイメージを掻き立てて、今日は香りまで想像を巡らす事に。
中の品の女達でさえ知る源氏の香とは・・・さて、さて。
・ 源氏に踏み込まれながらも、自分の意志をはっきり示す女性に引き寄せられるが、空蝉も源氏の魅力に心が萎えて来る。皆さんが言ってた様に、舞台の一場面を観ているような、騒と動がありました。
・ 【しのび込み】流れる様な平安の【言の葉】が連なる。
源氏は、かの女への思いが高ぶるばかり・・・。すると、微かな人の気配。【いづくにおはしますぞ】【ここにぞ臥したる】二人の会話で女の存在を知る。源氏は好機到来と行動開始。思いも掛けない出来事に、女のおののく様子がリアルに伝わって来る。女の求める【中将の君】と近衛中将源氏が【中将召しつればなむ】の絡みは絶妙。平安の人々も胸をときめかして読み手に引き込まれる。
[ジュクジョと読む源氏物語]という記事を目にした。熟女ならではの「およすく会」である。
・ 暗闇で、耳元に源氏の囁く声、覆いかぶさる高貴な香り、私だったら体が固まり、胸がドキドキ動けない。そんな状況で【人違へにこそはべるめれ】と抵抗する女君に【思ひあがる女】が見えた。女房【中将の君】の、動揺にもかかわらず声を上げない賢さの裏に、階級制や女君の置かれた難しい立場が隠されていた。子供の声、眠たげな女の声、香の匂い、衣擦れの音。見えない場面が浮かび上がる。
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき)
2016年3月2日受講
【中の品の家・噂話・姉弟】
隣から漏れてくる中の品の若い女房達の噂話に、もし藤壺との密会が漏れてしまったらと【まづ胸つぶれ】る。朝顔の姫君とのやりとり迄噂に。【とばり帳もいかにぞは】と、今宵の女を求める源氏に、紀伊の守はさらりと受け流す。屋敷の大勢の童の中に【いとけはひあてやかにて十二三】の子供。故衛門の督が【いとかなしくし】とても可愛がった末の子。紀伊の守の若い義理の母親の弟。桐壺帝に娘の入内を内密に話していた亡き父親は、従四位下の殿上人。源氏は【世こそ定めなきものなれ】と【およすけのたまふ】。紀伊の守は義理の母親に同情しつつも、若い女に従者の様にかしずく父親の姿を子供達は【うけひきはべらず】と。その若い女を若い息子たちに【おろしたてむやは】譲ったら良いのに、でも伊予の介は年取っているけれど絶対しないね。と源氏。【いづかたにぞ】女たちは何処に?紀伊の守の微妙な返事【えやまかりおりあへざらむ】。二度の【しづまりぬ】で寝静まった屋敷の静寂さが強調されています。
読後一言感想
・ 紀伊の守邸でのそれぞれの人物の気分や仕草がリズミカルに、やんわりした古語から浮かび上がって来る。先生の解説があってこそイメージが広がり、式部の巧みな表現力に引き込まれる。
やはりここでの焦点は、【不意にかくてものしはべるなり】。父親(伊予の介)の若い後妻。紀伊の守の心を見抜く問いかけ・・・。密やかに男二人が交わす会話の意味深さ。
この女に源氏も興味津々【いづかたにぞ】と探りを入れる。【いとおよすけたまふ】源氏の恋愛観。
五十才過ぎてからの【源氏物語】、【およすく会】十二年余、ようやく古語の読みも馴れて来ました。
・ 今日、読んだ部分で空蝉の状況が良く分かり、人物として浮き上がってきた気がします。世が世なら、宮中にあって、帝の寵愛を受けていたかもしれない女が、(源氏の母親の桐壺の更衣の様に)弟の後ろ楯を得る為に、年の離れた男に(泣く泣く?と源氏は思ったかも・・・)嫁いで、それでも、年の離れた男にしてみれば、宮中に上がっていてもおかしくない程、位の高い授かりものの姫君なので、つい骨抜きになって、下男の様にかしずいてしまう・・・。そしてそれを年の離れた男の息子は、苦々しく思って目も当てられない様子。空蝉は、かしずかれて安定は得ても、針のむしろに居る様な状態だろうと源氏は感じて、俄然空蝉に興味をかき立てられたのだろうと思いました。色々な角度から空蝉を捉えて、空蝉が人物として立体的に立ち上がってくる様です。
・ 「あ~、そうだったのか・・・」。
紀伊の守の屋敷に方違えに訪れた源氏。上の品と中の品では仕える女房たちの品(ひん)も違うのね。
源氏と紀伊の守の生々しいやりとりにも、改めてビックリでした。
文章は短いのに奥が深くて、「すご~いですね」っきり言えませんです。
・ 源氏は、西面に【人のけはひ】がするので、耳をそば立てる。【若き声どもにくからず】思うが、自分が朝顔の君に渡した歌を、【すこしほほゆがめて】、【くつろぎがましく】、【歌誦じがちに】噂している。それを聞いた源氏は【おぼすことのみ心にかかりたまへば】もし、自分と藤壺の事が噂にでもなれば・・・と【胸つぶれる】思いがする。あら?もう既に藤壺とやっちゃってたの?
【胸つぶれる】だから会っただけじゃなくて、やっちゃったんだよね。
・ 源氏が来た事で、伊予の守邸はテンヤワンヤ。女房達も浮き足立っている様子が良く描かれている。そして話は、どうして若い妻が来たのかも核心に触れていて、源氏は、この邸の何処かに居るであろう女に益々興味を示す。
・ 紀伊の守邸、舞台の様に物語は進む。
若い女房たちの自分の噂話に【まづ胸つぶれ】、【おぼすこと】は藤壺との密通の発覚!
朝顔の君との歌の交換までもが噂に。源氏は、どの品の女房にとっても、それ程の注目人物。
従四位であった故衛門の督の子供という空蝉と小君の素性。その若い【思ひあがれるけしきの】空蝉を、自分の主人の様に扱う、老人伊予の介。それを眺める息子紀伊の守の心中。
暗転した静寂の中、源氏は息を潜めその時を待っている。ドキドキの凄い舞台演出!
イメージで読む源氏物語 Ⅱ 帚木(つづき)
2016年2月3日受講
【源氏と女房たち・方違へ・中の品の家】
【御心いとほしい】と訪れた左大臣家。昨夜話した理想の妻像を思い出しながら、改めて女君を眺め、妻としては【さうざうしい】と思う。挨拶にやって来た左大臣に【暑きに】とおどけ、女房たちを笑わせ、急な方違えで帰るのも告げない。京の夏の暑さ、寝不足で疲れていた、若い源氏は、左大臣に甘えている。
【方違へ】だの【方塞ぎ】だの、今から考えたら本当に面倒な風習。突然高貴な人に訪問された主人の困惑を【人も聞き入れず】。兎に角ご馳走しなくては【枕草子】の【すざまじき】ものになってしまう主人。中の品の家の、庭、水、風、虫の声、蛍の乱舞は、絵の様。いよいよ冒険の始まり。
読後一言感想
・ 今日から再読に入った。【イメージで読む源氏物語Ⅱ】1回目は2004年の1月だったから、何と、12年振りに再び!ということだ。前回と違って、場面の1つひとつが目に浮かぶ。
かつては文章を追うのもやっとだったのに、ね。
10年一つの事を続ける、ということはこういうことか・・・と痛感。
これも「原文だから」なのだが、個々のキャラクターが浮かび上がって、とても面白いシーンですよね。
・ 【からうして、今日は日のけしきもなほれり】やんわりと場面が展開する。心引かれる内裏だが、向かった左大臣家の【けざやか】、北の方の【あまりうるはし御ありさまの、とけがたくはづかしげに思ひしづまる】に、源氏は【さうざうし】。古語の意味は重く深い。気折れる心で女房たちと戯れる源氏の【いとやすらかなる御ふるまひなりや】。女房たちの【見るかひあり】式部の筆は止まらない。
更に【方違へ】次のストーリー。突然の申し出に困惑する伊予之介。
【人近からむなむ、うれしかるべき】と源氏の好奇心!中の品の邸のさまに【このなみならむかし】と。
それぞれの動きが浮き出て、楽しい話でした。
・ せっかく左大臣邸に行ったものの、【方違へ】をしなければならないという事になり、紀伊の守の家に行くことになる。紀伊の守は【狭き所にはべれば・・・】と嘆くが、源氏は【その人近からむなむ、うれしかるべき】と興味津々。【・・・ただその几帳のうしろに】女房たちの寝ている傍がいい!!と言えば、左大臣邸の女房たちも【げによろしき御座所にも】と即座に答える。気心の知れた仲の軽妙なやりとりが面白い。
・ 左大臣家と葵の上の、上の品の様子を【雨夜の品定め】の締めとして短く描いています。
各階級はあっても、男女の心、すれ違い、思いなどが鮮やかに感じられます。
【方違へ】により紀伊の守の慌てぶりがコミカルで、一息出来ました。
次の、中の品の空蝉が楽しみです。
・ 久々に訪れた左大臣家では、少し満たされない様だったが、紀伊の守家への【方違へ】は、上の品しか知らない源氏が、中の品を実感した瞬間だったのか。
・ 1回お休みしたので、久し振りの感がありました。【雨夜の品定め】が終わり、一夜明けて、雨も上がり、場面がガラリと変わった印象を受けました。【雨夜の・・】の頃は、光源氏の描写が少ない様でしたが、今回読んだ所は、光源氏が初々しく、若々しく、坊ちゃん坊ちゃんしていて面白かったです。
「暑いのに~」とか「寝むいよ~」とか、軽く不満顔の貴公子が思い浮かびました。年上の女房たちが、光源氏の周りを取り巻いて「ウチの殿様って可愛い」と思いながら眺めている感じがしました。上下関係ではあっても、そこは、やはり男と女なのだと思いました。
・ 場面転換の素晴らしさ!天気もそうですが、藤壺を語った後、打ち解けない葵の様子を克明に描く。
同じ部屋に居る、葵、若い女房たち、左大臣、それぞれの人物を包んでいる空気の違いが見えました。
家の佇まいや目の前の水音、虫の声、蛍の乱舞が、寝不足だった目を覚ませてくれ、【このなみならむかし】と、中の品を実感する。夏の京都の昼の耐えられない暑さ、自然を生かした夜の涼が感じられました。
イメージで読む源氏物語 帚木
2016年1月6日受講
【女性論の果てに】
女性論の結論は、漢詩や歌作りで、【才がる】知ったか振る女は最低。【よしばみ情立たざらむ】女が【目やすかるべき】でした。源氏は【足らずまたさし過ぎたること】のない女性藤壺一人を想い、【胸ふたがる】のです。そして男達の話は、【あやしきことどもになりて】夜が明けるまで続きました。
資料【紫式部日記】の中で、式部は上臈の一人、清少納言を【さかしだち、真名書き散らす】とこっぴどく批判。「自分は才があり【日本紀】も読んでいるし、漢籍も兄より理解が速かった。けれども、その様な素振りは人には決してひけらかさず、一の字さえ上手く書けない振りをしましたよ。でも中宮様には漢籍を人に隠れてお教えしたの」裏返すと自慢ばかり。中宮に仕える女房達の激しい派閥争いが垣間見られ、女房達から嫌われる才女式部だからこそ、男の考えをここまでまとめられたのだと思いました。
読後一言感想
・ 夜はしんしんと更けてゆく。左馬頭が口火を切る。
自他共に「すき者」と、内裏の女房達に興味津々。才をひけらかす女に対しては手厳しい。
【心に知れらむことをも、知らず顔にもてなし・・・】男の目線(実は式部の持論?)
あれこれ御託を並べる。
灯火ほのかに揺らぐ・・・物憂げな光の君の姿が浮かぶ。
【君は人ひとりの御ありさまを、心のうちに思ひつづけたまふ】様々な女の在り方を聞き流しながら【足らずまたさし過ぎたることない】藤壺の君への秘めたる想いは更に募り【いとど胸ふたがる】
満たされない恋。これからの道筋へのプロローグ。
・ 女性の理想像の果てが、源氏が想っている藤壺に繋がっていたという事は驚き。
前回迄何をやって来たのかしら。源氏は思いを遂げる事が出来るのかな。
・ ひとしきり女性談義が終わると、左馬頭がまとめに乗り出すが、これは紫式部が常日頃自分の教養をひた隠しにして生きて来た姿を、女の在り方として左馬頭に言わせているのか・・・?でも、教養を隠さなければならないなんて、何と窮屈な!!式部程の人なら【蒜食いの女】の可愛さを本当は分かると思うけど・・・。やはり式部の本当の考えではなく、あくまでも男の代表としての左馬頭の女性論だと思うな。
・ 平安時代、女は【真名】を使ってはいけないと思っていました。左馬頭が【上臈のなかにも多かる】と言っている。上級の女房達が日常生活で【真名】を使っていると知り、驚きました。
上臈の中に【蒜食いの女】の様に【才の際なまなまの博士】の人がいて、殿上人と漢籍や漢詩等を対等に話す事が出来た人がいたのでは?式部が左馬頭に【上臈のなかにも多かる】と語らせているので、色々想像してしまいました。
紀貫之が【土佐日記】を仮名文字で書いています。当時、男は【真名】女は【仮名】と云われていますが、使い方は案外自由なところもあったのでしょうか?
・ 紫式部VS. 清少納言。先生が配られた【紫式部日記】のプリントを読み、平安の宮中での権力争いまで見え隠れする「生々しさ」に圧倒されました。
これでもか~!と、悪口や謙遜を並べる式部さん。貴女は色々な意味で(頭が切れたり、上からの覚えがめでたかったり・・・)周りの女性達から、かなり嫌われていたのね。
・ 女性論の果てに左馬頭。
女は【たをやか】に【仮名】を書き、漢籍を物知り顔で【真名】の文を書くなど【あなうたて】。
男の状況も考えず、歌詠んで来る、知ったか振り女は【心後れて見ゆ】。女は、【知らず顔にてもてなし、言はまほしからむことをも、一つ二つのふしは、過ぐすべくなむ・・・】それが結論。
聞きながら、源氏は理想的な藤壺を想い、【胸ふたがる】。
【紫式部日記】の辛辣さにびっくり。ここまで書く?本当の知ったか振りは、貴女ではないの?
千年前の悪口が現在まで残ってしまうと、式部は思いもしなかった事でしょう。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年12月2日受講
【蒜食いの女 その二】
久し振りに訪れた男に女は屏風越しにしか会わない。さてはすねているのか?分かれるには潮時か。しかし、この【さかし人】そう軽々しく嫉妬などしない筈。女【はやりか】な声、漢詩調「蒜が臭いのでお会いできぬ」と。【答へに何とかは】。【うけたまはりぬ】と立ち去ろうとする男に、女【高やかに】「臭わなくなったら又来て欲しい」と。【聞き過ぐさむもいとほし】躊躇する男。女の気持ちが分かる。そこへ蒜の匂い【はなやかに】。逃げようとする男の歌に、即返した、男を責める女の歌。スピード感溢れる場面。全て聞き終わった君達は、この話は虚言だと。【さかし女】は【鬼】より珍しい存在!
読後一言感想
・ 【雨夜の品定め】終盤へと。
階級・年齢の異なった四人の男達は、ちょっと得意げに口惜しい気やら混じえて語る。
再度のレクチャーで、一層式部の巧さに引き込まれた。思い込んだら命懸けの女、圧力に屈しないでさらりと身をかわす女、色事は華やかに自分本位で楽しむ。才たけているが人情味の表現の乏しい女。四人の女達の、生活から心の動きまでの描写・古今集・漢学に至るまでの式部の教養の高さならではの筆致・古文の表現こその味わいと思いました。
余談ですが、毎回講読の時、月日を記入していて、243頁【蒜食いの女】に2003年12月17日とありました。えっ・・・! 干支を一巡り! 小学生が高校卒業するその月日! を思うと、過ぎ去った歳月の重さを感じました。
・ ニンニク臭くても、一目会いたい・・・。漢学に通じた賢い女は、貴公子の間ではバケモノ扱いだが、現代人から見るとちょっと可愛い。源氏物語には、個性的な女性達が登場するが、蒜食いの女は末摘花と共にかなり印象的ですよね。
・ 【蒜食いの女】は、【さかし女】で、漢文調の話し方で、行動も普通の女性とは違いますが、どこかに、一途さの中の可愛さを感じます。蒜の話等ひどい逸話ですが、【才】の女性には、紫式部の冷たい目を少し感じてしまいました。
・ 藤式部丞は、中将達にけしかけられて、漢学で頭の硬い、硬すぎてユーモラスでさえある女の話をする。男達はこの漢学女のおかしさを分からない様である。式部丞は、この漢学女の可笑しさ、不器用な可愛さを理解していたかは分からないが、でも、身分の高い君達に【しづしづ】と話し終え、自分では満足して、【「これよりめづらしきことはさぶらひなむや」とて、をり】。この【をり】で式部丞の人格も見える様で面白い。少し小太りで、正直で、いい人そうである。
・ 源氏物語の中に【蒜食いの女】の様なエピソードがある事を知り、この物語の奥深さを感じました。
ユーモアがあるじゃないか、と。とかく日本の真面目な文学の中にはユーモアが無い、と言われがちですが、源氏物語の中には、ちゃんとあると思いました。しかし同時に、「サブカル in 源氏物語」というタイトルが頭に浮かびました。【蒜食いの女】のエピソードは、あくまでもバラエティーの一つで、やっぱり主流ではないですよね。それでも夕顔みたいに優雅で、はかなげな女の人が早く死んでしまう、可哀想な場面(主流)に対して、こおいう面白い女の話題が挟まれる事で、ホッと息がつけるのだと思いました。私はこの女の人結構好きですけど、日本の主流を成す男達(上流貴族)が、こおいう女の人を楽しんでくれないのは、昔も今も同じだと思います。
※サブカル⇒サブカルチャー:若者文化、都市文化等、社会の主流ではない一部の独特な文化
・ 【蒜食いの女】の【食い】は【喰い】ではなかった事に気がつきました。
藤式部丞は、この【かしこき女】を理解する唯一の男で女は彼を深く愛していた。【はやりかな】な、【高やかな】声で引き留め様とする女の必死さ。それを分かっていながらも、女を鬼とまで言う君達に、面白話として、話をした藤式部丞は【これよりめづらしきことはさぶらひなむや】と言い切る。そこに女に対する申し訳なさと、自分の情けなさを感じた。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年11月4日受講
【蒜喰いの女 その一】
新たな語り手、藤式部丞登場。彼は地下人。この中で階級的に一番低い身分。言葉に階級がはっきり現れています。【下が下】の男の面白い話。それは【かしこき女】の話。自分が通う学者の娘で相当な優れ者。付き合い始めると、女は男を恥ずかしくない朝廷人に仕立てようと決心。床の中の語らいも勉強の事、手紙も漢字だけで男を教育。結果、男は、そこそこ学問を取得出来た。でも女を【なつかしい妻子】にするには、女が賢すぎ、【無才】な自分が【はずかしい】。【宿世の引くかた】で女との縁は切らず過ごしていましたと。話し終えた藤式部丞に、中将は満足げ。それを見て得意げに【鼻のわたりをこづき】藤式部丞は話を進めます。
【まいて君達の御ため、はかばかしく、したたかなる御後見は何にかせさせたまはむ】に、上の階級の三人に対するお世辞と、藤式部丞の、自分の階級、学問の低さを恥じる微妙な心を感じました。
一般に博士の階級は低く、女の家が男の優れた後見人にはなり得なかった厳しい現実を式部は書きました。
読後一言感想
・ 最近ちょっと面白かったテレビドラマに「デート」というのがあった。
文学の香りが散りばめられていて、文学好きには興味深いものがあった。藤式部丞の話す「賢女」はこのドラマのヒロインに似ている。知識はたっぷりだが、ガチガチで面白みが無く、行動も極端だ。極端過ぎて滑稽ですらある。女としては、どうかなあ思うところがあるが、どこか憎めないのは、周りも見えない程一生懸命だからだろう。千年前も今も、人間は変わらないのだ。
・ 源氏物語には、色々なタイプの女が登場するが、【雨夜の品定め】では、四人の、位も性格も違う男子がつるんで語らっている。色々なタイプの男たちが一堂に揃うのは面白いが、階級社会が当たり前の世の中の現実が透けて見えて、何か、ちょっと切ないなあ。
・ 【蒜食いの女】は、少し極端な例なのかもしれませんが、平安時代には、漢文、漢詩の【才ざえ】ある女はそれ程少なくはなく存在していたのかなー。と思いました。今でいうと科学者になる女の人、理系女子の様な感覚でしょうか?紫式部だって、「日本紀の局」(?)なんていう悪口(なのか?)を言われて、たとえ【才】があっても、それを見せてはならない世の中の雰囲気があったのでしょうか。あるいは、見せ方にセンスを要求されたとか? 清少納言が仕えていた中宮定子にも【才】があって、【香炉峰の雪は如何あらん】と言われ、清少納言が御簾をくるくると巻上げた。という有名な場面があるけれど、これなどは、漢詩を遊びにしてセンス良く楽しんでいる、ステキなサロンねー。という感じがします。やはり、定子を取り巻く環境と、文学博士の家との落差は大きく、文化は、上流貴族のものなのですね。 【才】ある女に対して、同様に【才】の無い男は、また辛かったろうと思います。
・ 式部丞の話は、今までにない変わった女として登場するが、【かしこき女】は男にとって煙ったいのかしら。女の人の学があるというのは、嫁の貰い手が無いという事か。
中将の、上から目線が何か気になった。下が下、上が上の格差は一生?
・ 下の女として彼女は【博士はづかし】と思う位才媛ですが、式部丞に良く尽くす世話女房ではないでしょうか。夫は自分を【無才の人】と思っているので、優秀な妻に育てられている事に「圧迫感」を感じていたのでしょう。もう少し式部丞がおおらかだったら・・・
・ 会話表現の下に流れている階級制は、確固たるもので、式部丞の焦りや安堵が見えました。
床の中でも、夫を教育し、役に立ちたい懸命さに【指喰いの女】と共通する気持ちがあります。男女均等の今でも、男達は心の隅に【かしこき女】を【をかしかりける女】としたい気持ちを持っている様に思います。当時の世の中の価値観に、式部は挑戦しようとした?
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年10月7日受講
【常夏の女 その一~二】
女の現実が何も見えていない中将は、久しぶりに訪れた女の荒れた家を眺め、昔物語の様だと。絶望した女の【うち払ふ・・秋も来にけり】の歌が悲しい。式部はここでも、歌で男と女の心のズレをはっきり表わしています。【あともなくこそかき消ちて失せにしか】に女の強い意思が。自分を捨てて消えた女を未練がましく語る中将は、女がまだ自分を想い【えしも思ひ離れず】【胸こがるる夕もあらむ】と強気。そして、【えたもつまじくたのもしげなき】頼りない女の例だと言い切る。
さて、理想的な女とは?【指喰い】【木枯】【常夏】すべて【思ひ定めず】が結論。【吉祥天女】では抹香臭いしね。と、皆でどっと笑ったのでした。
読後一言感想
・ 常夏の女が、かき消えた。
様々な感情を内に秘め、中将の訪れを、ただただ待ち続けていた女だが、子供の事もあり腹をくくったのだ。ざまあみろ、中将! さて、【痴者】はどっちでしょうね。
歌が多く登場する部分は、それだけ感情のやりとりがあるという事。
歌に詠み込まれた心の機微に思いを馳せる。 源氏物語は、やっぱり面白いでーす。
・ 中将の元へ撫子の花を添えて送られた文・・・
中将は、荒れ果てた家を訪れたが、女の心情を汲み取れない。切々とした女の歌が重い。
中将の、感念を超えた女の行動に思い巡らし揺れる心・・・。だが自分よがりに決め込む。
式部の筆は、軽やかに運ぶ。
私達は、難解な古語に惑いながら、【常夏の女】の選択、私ならどっちかな?
男達の女選び・・・永遠の課題、今は女性優位ですね。
・ 男と女は、どこまでも平行線で交わる事はない、という作者の信念の表現でしょうか。
【常夏の女】がどれだけの思いを抱えて、同時に自分を惨めな女に貶めない様に振舞っても、そんな事、男には通じない。儚い世渡りを強いられている女が、かくも矜持(自信と誇り)を持って生きているのに、女に比べて安全な所に身を置いている男は、かくも鈍感なものですね。その男達が集まって、理想の女って居ないよねー、やりきれないよなーって笑うなー ?。
やりきれないのは女の方です。男は何時だって気付くのが遅いし、全て終わった後で、自分勝手な解釈を付けて・・・女を舐めてますね。
・ 中将は、女の気持ちを察する事が出来ず、突然姿を消すと何時までも面影を追う。
【親もなく】【いと心細げ】な【常夏の女】は、強く主張をしないので、気持ちが伝わらず、辛く悲しみ深い。が、いざ覚悟を決めると、全て捨ててしまう。
女性の強さと潔さを感じます。【常夏の女】の文章の深さに感動しました。
・ 女のサインに気付かず、消えてしまってからでは後悔先に立たずだが、自分に都合良く解釈してしまう
中将もお調子者かな?
さて、自分の事はさて置き【指喰いの女:さがなもの】、【木枯の女:すきたる罪】、も男にとっては・・等と言ってる内に、自分の女もその辺りに居る様な頼りない女に思えてしまっていた。
男って勝手ですね。自分中心で。
・ 二つの歌を並べ、間に【大和撫子をばさしおきて、まず、塵をだに、など親の心をとる】と入れ、女と男の心の中のすれ違いを、より大きく読者に感じさせました。
中将の衝撃が【あともなくこそ、かき消ちて失せにしか】にリアルに表現されていました。
【痴者】とは、男友達と話す勢いで、中将が自身をそう言う事も有りうるのでは?という意見に納得。
理想的な女はこの世には居ないという結論に、皆笑い、【常夏の女】が終わりました。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年9月2日受講
【常夏の女 その一】
今度は、中将が【痴者の話】を始めます。【常夏の女】の登場です。
中将の話から連想される女の様子と、夕顔の仕草を思い出しながら読みました。自分を主張せず、頼りなさそうで、支えたくなる女。【のどけき】女は、男に安らぎを与える。普通、女から男に手紙を送る事はあり得なかった時代、【のどけき】彼女の、母親としての強さが、撫子の歌に現れています。涙ぐんだ後で、
※【いさや、ことなることもなかりきや】と照れる中将に、母からの頼みは届いてはいなかった様に思う。
【撫子】が撫でた子で、【露】が涙。何と美しい表現でしょう!そして、中将は女の家に行く。
江戸時代の源氏物語注釈書※【細流抄】に、涙ぐんだ中将の※【いさや、ことなることもなかりきや】の
表現は、とても優雅な言葉で、中将の品格が表れていると記されているそうです。
※【細流抄】;青表紙本系統の本文による最新の注釈書。1510~13年に成立。
読後一言感想
・ 常夏の女、後の夕顔の君の初登場でした。(それだけで感動的)
この頃は、後に夕顔として再登場する何年位前なのか?まだ若くて、幼い娘を抱えて、その置かれた立場を思うと、随分と苦しかったろうに、【あはれはかけよ撫子の露】の歌は、前面に朝露の降りた撫子が、スッと咲いている様子が浮かんで、その向こうに幼い少女(娘)が悲しんでいる姿が見えて、表現が奥ゆかしく美しいです。手紙で何か伝える時に、和歌を詠んで寄越す当時の習慣は、文化として卓越していると思いました。
最初の中将の発言【痴者の物語をせむ】の【痴者】が、中将なのか、常夏の女の事なのか、まだ判断がつきません。どっちの事なのか?
・ 【常夏の女】の読みは深い。いとしさを感じる女です。
中将は、【馴れゆくままに】女の寛容と健気さに浸っていた。やがて女へ北の方の圧力が迫る。苦境の中で女は悩み、撫子の花を添えて、子を思う切々な文を・・中将のもとへ。しかし、のほほんと受け流した若き日の愚かさに涙する。【さてその文のことばは】と源氏の問いに、再度のレクチャーで、この文節が次の物語へと。古語の味わいと式部の筆致の巧みさを楽しみました。
冒頭の【痴者】は、中将ですね。
・ 【らうたげ】で【のどけき】女は、【頼めわたる人】と中将を思っていたが、あまりに呑気で鈍感。
【常夏の女】と【指喰いの女】の性格は、全く対照的に思いますが、底に流れているものは同じ様に感じられます。夕顔のイメージが、今回少し変わりました。
・ この時、読者は中将が語る【常夏の女】が、後に登場する【夕顔】とは知らない。
源氏物語、ホント良く出来てますよね。勿論、紫式部の構成力も。
それにしても、若き中将の鈍さには呆れるばかりです。
・ 常夏の女
【かうのどけきにおだしくて】中将から見た女の、のどかな様子と、それに安心しきった中将の様子を、この一言で見事に表わしている。
古語のリズム感と言葉の広さを楽しんだ。
・ 頼れる親のいない【常夏の女】は、中将を頼みに思っているのに、恨む様子もなく健気につくす。
北の方の嫌がらせにも気付かず、後になって知るなんて。中将は愚か者だ。
・ 【痴者】は中将か女か?前の講義を思いだし、最初中将だと思ったけれど、今では常夏の女では?
【山がつの垣ほ荒るともをりをりに あはれはかけよ撫子の露】に母の悲しみを思い、うるっと。
【のどけきにおだしくて】の文の中に主語が二つ!
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年8月5日受講
【木枯の女 その一~その二】
目の前の、かっこつけ男が自分の女に迫って行く様子をコマ送りで詳細に語る左馬頭。
女を意識して【簾のもとに歩み】古今集の引き歌で女を【ねたます】。菊を折り(御簾に投げ入れ)、
琴の腕前と月を誉め、でも貴女は男を引き留められないという歌を詠んだ後で、琴を催促する馴れ馴れしさ。【女、いたう声つくろひて】歌を返し【なまめきかはす】二人。左馬頭が【憎くなるをも知らで】派手に十三弦の琴を掻き鳴らす女に【まばゆきここち】する。そういえば、内裏でこういう【さればみすぎる】女を【をかし】と思っていた頃もあったけれど、【忘れるよすが】とは思えず。結局その夜の出来事を口実に、木枯の女とはすっぱり手を切ったと。
【指喰いの女】と【木枯の女】の長い話の結論は、今の若い貴方達が心を動かすであろう【折らば落ちぬべき萩の露】【拾はば消えなむと見ゆる玉笹の霰】の様な【艶にあえかなるすきずきしさ】で、男に【すきたわめらむ】女にご注意という事に。
うなずく中将。皮肉な笑いで、「体裁の悪い身の上話」と、皆の笑いをとる源氏。
※【菊を折りて】の後の歌の中に【菊】が入る事が歌作りの定石。なのに、【琴の音も月も・・・】と【月】が入るのは【青表紙本】で、【河内本】では【菊】になっているとの事。
源氏物語は、本当に長い時間研究されてきているんですね。
読後一言感想
・ まろやかな古語で、秋の夜の逢い引きのさまが浮かび上がる。「五七五七七」の言の葉で、女の情を押したりひいたり。この好き男、恋の達人、中々のテクニシャン。言い寄る男に女は【なまめきかはす】。左馬頭は見た!!女の主体に【たのもしげなくさし過ぐいたり】。そして、若き頃の苦い恋心のいきさつ【すきたわめらむ】女に用心をと皆に【いましむ】。それに【例のうなずく】中将。しかし、源氏の反応は【君、すこしかた笑みて】と、絶妙な表現。
居合わせた好き心ある男達、笑いの中に何を感じたでしょう。深読みの面白さを味わいました。
・ 木枯の女
左馬頭は、自分が通っていた女と男との【さればみすきたる】場面を見てしまう。
男はキザで、ポマードの匂いプンプン。女は少し厚化粧。男が【いたくあざれかかれば】女は【いたう声つくろひて】・・・ 若さを少し失いつつある二人の駆け引きがうまく描かれている。
・ ま、左馬頭には、無理でしょうが、同僚と木枯らしの女は「恋のかけひき」を楽しんでいるのよね。
気障で芝居がかっていて、とてもついていけないけど、今で言う所のゲーム感覚かな。
こういう男、私の近くにもおりました。うへ。
・ 美人で趣味豊かな【すきたわめらむ女】より、不器用ですが誠実な【指喰いの女】を【忘れぬよすが】としている左馬頭の思いが伝わってきます。
【指喰いの女】と【木枯の女】はそれぞれ情景が浮かび、その対比が素晴らしく感じました。
・ 体験談が終わり、最後に説教めいた事を語る左馬頭の、常識の人、正直者の人物像をみた気がした。
・ 簾に迫る男の【歩む】歩き方、女を【ねたます】歌、菊を御簾に投げ入れ、【つれなき人】の歌を詠み、【わろかめり】と女の弱味をつきつつ琴を催促し【あざれかかる】男に、【いたう声つくらひ】歌を返し、改めて十三弦の琴を【今めかしく掻い弾く】女。左馬頭の前で繰り広げられる【なまめきかはす】男と女の動き一つ一つが、芝居の一場面の様に詳細に描かれていました。
【指喰いの女】を愛する左馬頭には【さればみすぎ】て【まばゆきここち】して到底出来ない芸当。
彼にとってそんな女は【忘れぬよすが】ではなかった。だから、【すきたわめらむ女に心おかせたまへ】と若者達に注意喚起。
次から次へと出てくる、古語の深い表現力に又驚かされました。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年7月1日受講
【木枯の女 その一】
続いて、左馬頭は【指喰いの女】と同時進行で付き合っていた【木枯の女】の話を。【指喰いの女】女が生きている間は【このさがなもの】に比べると完璧に近いこの女の多才さと、そこそこの美しさに心がとまっていました。でも、【このさがなもの】に死なれてからは、【しばしばまかり馴るるには、すこしまばゆく】段々かれがれになるうち、女には【忍びて心かはせる人】が出来た様だと。
【神無月のころほひ】偶然乗り合わせた上人が、何とその相手。輝く月の夜、崩れた築地の間から見える池に映る月、霜枯れの菊、風に散り乱れる紅葉。この完璧な舞台装置のもと【とばかり月を見る】上人。そして、やおら笛を懐から取り出し吹き始める。何と、女は既に調弦してあった和琴ですぐにそれに応える。怒らなくてはいけない目の前の情景に、左馬頭は【けしうはあらずかし】そして【清く澄める月にをりつきなし】とその場面に感動してしまいます。風情ある静かな場面でした。
※【過ぐ】には死ぬという意味もあり、自然や時の流れと同じ様に人の死がありました。
読後一言感想
・ 左馬頭は、失った女を【あはれながらも過ぎぬるはかひなくて】満たされない心を紛らわせるように、以前からの通い所へ。この女は、【指喰いの女】よりも【立ちまさり、心ばせまことにゆゑあり】、男のすき心を揺さぶる。その美しさに惹かれていたが、左馬頭には【すこしまばゆく】、段々と女の心情に不信が募り、【かれがれにのみ】に。古語の解釈は難しいけれど、知る事で言葉の深みを感じる。
或る夜の出来事・【人待つらむ宿なむ】心ウキウキの上人あり。相乗りした車の向かった先は~
かの女の邸・やっぱり!!【過ぎむもさすがにて】左馬頭と同様、読み手も引き込まれる。
【月おもしろかりし夜】【月だにやどる住処】【清く澄める月】秋の夜の舞台。
男女の仕草、笛と事の音、秋風、草木。
こっそりと息を潜めて覗き見した左馬頭・【けしうはあらずかし】。
柔らかな古語、巧みな描写で平安の雅な場面が浮かび上がりました。
・ 「ないものねだり」
【木枯らしの女】は、左馬頭のないものねだりだったのね。【指喰いの女】が甲斐甲斐しく左馬頭の面倒をみてくれるからこそ、浮気も出来るのだろう。
「安定しているから、不安定になりたいのよ」。「これこそ浮気の本質!」と先生。
へぇ~、そうなんですね。
・ 左馬頭は、【指喰いの女】が亡くなってから【木枯の女】のもとへ、しかし、【しばしばまかり馴るるには、すこしまばゆく】、【うち頼むべくは見えず】という気持ちになる。この左馬頭の気持ちの移り変わりが短い言葉で、リズム感良く語られる。現代の言葉にすると、長い説明文となるところが、左馬頭の裏の心をも匂わせつつ、何と見事に表わしている、古語の素晴らしさか!!
・ 左馬頭は、昔の事を思い出して語っている割には、微に入り、細に入り良く憶えているもんだなー、と関心してしまいます。ただ、それは絵に描いた様な型どおりの恋愛の導入場面だったからでしょうか。
【木枯の女】の居る風景は、月の光、池に映る月、終りの菊、風に舞う紅葉、笛と琴の音、あまりにも風流の道具立てが揃い過ぎていて、ちょっと恥ずかしい程です。美し過ぎて、気恥ずかしいです。これが色好みの文化の洗練の極みでしょうか。この場面は、やっぱり絵に描かれているのですね。絵描きなら描きたい場面だと、つくづく思います。
・ 【木枯の女】には【指喰いの女】には見られなかった風情のある場面が出て来て、少しホッとした。
今迄の話は、小難しくて気が抜けなかったから。
・ 【木枯の女】を語る左馬頭の表現の裏には、【指喰いの女】が隠れていました。まるで語りながら【指喰いの女】を懐かしむ様に。
笛と琴の音に聞き惚れて【清く澄める月にをりつきなからず】と思う左馬頭って、平和な男です。
これでもかと、風流を満載したこの場面は、絵になりましたが、【指喰いの女】は、やっぱり絵にはなりませんね。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年6月3日受講
【指喰いの女 その三】指を喰われた左馬頭の後日談
霙から雪へ時間の変化と、天気の様に一刻一刻変わる男の心の中をドキュメンタリー風に。
最初【なま人わろく爪くはるれど】の恥じらい⇒歓迎されている様子に【さればよ】の【心おごり】⇒
女の【ひたやごもり】⇒【あへなきここち】⇒【我をうとみね】女に猜疑心⇒【着るべきもの】が【あらまほしく】⇒再び女への情愛が湧いてくる。やっぱり男は単純?
一方、女は【ありしながらは、え見過ぐすまじき】は譲れない。【いたく綱引きて見せた】男に絶望し【はかなくなり】亡くなってしまった。深く悲しむ左馬頭は、女を龍田姫や織姫に例える。
中将が、「たなばたの織物は控えて、長い契りが出来たら良かったのにね」には笑えました。
【かたき世とは、定めかねたるぞや】でこの話はおしまい。理想的な男と女の仲なんて決められない。
読後一言感想
・ 【指ひとつ引き・・・】その後の展開は男女の深層心理を、難解ながら、豊かな古語の表現で読み手を引き付ける。男は、居場所を求める様に【なま人わろく】、【爪くはる】。はにかみ、照れながら期待感をもちつつ向かった女の家は、【火のほのかに壁にそむけ・・】美しく整って、人を待つかの様に(臨場感が溢れる描写)。しかし、【心おごり】した男の受けた衝撃は深かった。男が思っていた以上に女は【いといたく思ひ嘆き】切々と悲哀が伝わる。男の思い上がりは破局の道と・・・。
【かたき世とは定めたるぞや】いつの世も、男と女の絆は不可思議です。
・ 左馬頭は、みぞれ降る夜【なほ家路と思はむかた】と思う女の所へ。けれど、歌の一つも残さず、女は親の家に【ひたやごもり】。衣は温めてあるし、帷は上げてあるし・・でも、【正身はなし】。
この時代にも、自分の意志をはっきりと示す強い女が居たのですね。少し不器用で真っ直ぐな女性。
私は好きだな。
・ 左馬頭、気が付くのが遅かったですね。自分にピッタリの女はもう死んでしまって、今頃後悔しても、もう遅いのに・・・。人はいつも遅れて気付くものなのか?社会の習慣で、一夫多妻がまかり通っていても、社会の在り方とは別に、女の人個人は、制度としての一夫多妻や男の浮気に苦しんでいたのですね。しかし、この点(一夫多妻か、一夫一妻か)においては、何時の時代、何処の地域でも、男と女は平行線ではないかと思います。【指喰いの女】は、あはれです。ただ思い悩んで、死ぬこたぁないんじゃないか、と。しかし、死んだからこそ、左馬頭は、【龍田姫】やら【たなばた】やらに例えて偲んでくれたとも言えそう。生きていたら、こんなに「しみじみ」はしてくれなかったでしょう。
左馬頭、反省して下さい。
・ 【指喰いの女】が終わりました。
この様に自分の命を失ってしまう程悩んだ女の人がいたのに対して、軽く考え生きて来た男もいたという事で、ここはすごく興味深かった。
【ひたやごもり】の深~い意味。妻を選ぶのは今も昔も大変なんですね。
・ 【雪をうち払ひつつ】京都の寒い雪の夜です。
来るか来ないか分からない男を迎える、愛情溢れた準備。それをしながら親の家に【ひたやごもり】、
妥協出来ない、譲れない女の気持ち。女に対する気まずい男の【なま人わるく爪くはる】の心情。
二人の思いが、夫々生々しく伝わりました。
通い婚の時代には珍しい、主張する女。それ程真剣に男を愛していたのです。
そんなに真剣に男に関わらなくても大丈夫なのに・・・。
男って女よりもお気楽な生き物ですから。と、私は思っています。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年5月6日受講
【指喰いの女 その一・その二】若い頃の左馬頭の経験談。
女の【憎きかた一つ】の【もの怨じ】を直そうと画策した男が、女に指を噛まれたお話。
別れたくないのに別れてしまった、【若きほど】の男と女の微妙な心のズレが書かれていました。
読後一言感想
・ 今日の読書会は、本文の内容の面白さもさることながら、場外の、読書会参加者の話がとても盛り上がった。尽くす女に嫌悪を示す人、偉いなあと感心する人、それぞれの経験に照らし合わせて様々に読めるのが、優れた小説なのであろう。
それにしても、指を喰ってしまう女ってスゴイ!! カワイイ!! (この感想が違うのだ)
・ 「こんなに尽くして我慢してきたのに? 」ついにやっちゃったね。
どうせ別れるなら指くらい噛みついてもしょうがない。左馬頭は【われたけく言ひそしはべるに】、女に逆襲されると、【かかる疵さへつきぬれば、いよいよまじらひをすべきにもあらず・・・】などと、まるで駄々っ子の様な言葉を吐く。 やっぱり男はガキだね。
・ もう情けないやら、悔しいやら。こんな薄情な男の為に身を粉にして尽くしてきた私ってバカね・・
思わず自虐的に笑いがこみ上げてしまったわ。
いゃあ、【指喰いの女】って面白い。
男女のいさかいって、エスカレートするとこうなる。1200年前も同じなのよね。
・ 左馬頭は、【あながちに従ひおぢたる人】と思い込み、【もの怨じ】を直そうと一芝居するが、妻からの逆襲。身勝手で妻の心を思い計れない夫。離婚する時の修羅場を見ている様です。
指を【くひて】に、妻の深い怒りや悲しみが伝わって来ます。
・ 【もの怨じ】とは古今東西を貫いて、文学の主題になり得るパワーを持つ感情だろうか?
私はふと、シェイクスピアの『オセロ』を思い出してしまいました。そして、もうずっと昔に、私が恋
愛の師と仰いでいた友人に、「男が浮気をしても、決して責め立ててはいけない」という様な意味の事
を忠告された事も思い出しておりました。たとえ疑わしくとも、「信じているわ」と言っておけ、と。
嫉妬の事を大和言葉で【もの怨じ】と言うと知った事も良かったです。漢語ではなく大和言葉、和語を
もっと学びたいです。
・ 十年余り前の【指喰い女】の印象は薄かった。
古語を読みこなすのに精一杯だったと思う。再度のレクチャーで、式部の想定外の展開に引き込まれた。
男(左馬頭)は、【あはれと思う人】がありながら【すき心】発散したいが、女【もの怨じはべりし】。
男、女の【とかくなびきてなよびゆき】に図に乗り【ことさら情なくつれなきさま】を。この波紋は、
丁々発止、遂に【指ひとつ引き】仰天の事態に。
伊勢物語から引用して、修羅場でも歌を詠ずる式部の文学的才能の冴え。
・ 【指喰いの女 その一から二】まで
左馬頭の女改造案は、思わぬ事態に・・・。夫婦喧嘩へと発展し、指まで噛みつかれ、別れの言葉を言ってしまう所等、とても滑稽で面白かった。
が、この後がどうなってしまうかが楽しみだ。
・ 【すこしうち笑ひて】、貴方は【あいな頼み】のつまらない男だったと、男の指を噛んだ女。逆上し、【まじらひをすべきにもあらず・・世をそむきぬべき身になめり】こんな怪我をしたら、もう働けない、出家するしかない!と突然の事にびっくりした男の、子供みたいな悪態。「狂言」に出てくる話の様。
女に別れを告げ【この指をかがめて】出て行く男が詠う歌【手を折りて・・・】女が【手をわかるべきをり】と返す。こんな喧嘩別れでも歌を詠む余裕があるんだ!?
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年4月15日受講
夫婦の行き違いは、女が【恨むばからむふしをも、にくからずかすめなさば】恨み言を言う時も可愛くそれとなく言い、お互いが【のどやかに見忍ぶよりほかに、ますことあるまじかりけり】穏やかに、のんびり眺めて忍ぶより他に勝る事はない。女は【なだらかに、のどやかに、見忍ぶ】が理想で【けしきばみ、そむく】のはいけない。平和な明るい家庭は、こうすれば築けると誰もが分かってはいるのですが・・・。
中将は、【見忍んでいる】葵を分ってもらいたいのに、源氏にはうたた寝。
【つながぬ舟の浮たるためしも、げにあやなし】女に繋がれないでいる男は生きる張り合いがない。
通い婚が、女性優位に成り立っていたとは思いも掛けませんでした。
左馬頭の話は、更に指物、絵画、書にまで発展し、彼の年で理解したのは、
【見る目の情をば、え頼むまじく思うたまへ得て】見た目に惑わされない事!
式部の芸術、特に絵画の唐絵と大和絵に対する知識に驚かされました。奈良時代、多くの仏寺が建立され、絵師は唐絵を描きましたが、平安時代には仏寺の建立が極端に減り、絵師も少なくなり、貴族の邸宅の襖絵が主な仕事で、一条帝の頃、大和絵は革新的な絵画だった様です。(田中先生談)
いよいよ次回から、様々な女性が登場です!
読後一言感想
・ 左馬頭は結婚観にも及ぶ。
妻は【頼み所】であり、夫は【つながぬ舟の浮きたるためし】。(意味ありな古語)
中将は、妹(葵の上)と源氏とのあり方に【違ふべきふしあらむ】・・・と。
【もの博士になりてひひらきゐる】工芸、絵画、書と例えながら左馬頭は熱く語る。
難解な古語から式部の見識、美意識の深さ。要するに、選択の目を持ちなさい・・・と。
・ 【つながぬ舟の浮きたるためしもげにあやなし】
一夫一婦制であれば、たとえ妻が不機嫌な顔をしようと堂々と家に帰るが、通い婚のこの時代
【むげにうちゆるべ見放ちたる】奥さんでは通いにくかったのね。
男性にも【よるべ】の大切さは身に沁みていたのね。
・ 左馬頭の妻論は続く。
あーでもない、こーでもないと、ま、好き勝手な事をのたまわっていますけど、
「例えば」で、書画の優劣が例に挙げられたのは分かりやすい。
でも、これって全て、式部の「美意識」なのよね。いいですねぇ。
・ どういう女を妻にするかの例え話を、指物師、絵師、書についてそれぞれ妻を選ぶ際の例えは、左馬頭の話の妻論の結びかな。
妻は【よるべ】(頼み所)であり、夫は【つながぬ舟】でありたくない。
・ 今回読んだところでは、視点が近寄ったり離れたりするところが感じられました。
式部が左馬頭に語らせながらも、ふっと下がって、中将に、コクンとうなずかせるようなところが、
「オオー」と思いました。現代の私達は、映画や映像を観ているから、小説の中の一つの場面を読む時
に、距離を置いて、俯瞰(鳥の目)する手法に慣れているけれど、この時代、式部のこの目の配り方は、
天才的なのではないかと思いました。絵画についても語られているし、上っ面だけ取り繕ってもダメな
んだよ。というメッセージに加えて、その例に絵や木工、書を取り上げて、教養が本当に深いのだと思
いました。式部はこんなに色々気付き過ぎてさぞかし腹の立つ事も多かったのではないか、と。
(回りが鈍感過ぎて)
・ 【つながぬ舟の浮きたる】通い婚の男達の危うい生活が浮かび上がり、話が盛り上がりました。
通い婚は、女に愛され続けられなくてはならない、男にとって厳しい制度だった。
年取って女に捨てられる男の悲哀を思いました。
馬頭の妻選びの結論が、地味で保守的になるのは仕方がない事なのです。
左馬頭が【ひひらきゐたる】表現は笑え、匠の世界の例を書ける式部の教養深さに驚きました。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年3月4日受講
左馬頭の妻選びは【定めかねて、いたくうち嘆く】結論を決められず、ふっとため息をつく結果となり、
消去法での最終的【よるべ】は、
【いとくちをしく、ねぢけがましきおぼえだになくは、ただひとへにものまめやかに、静かなる心のおもむき】
と、なりました。続いて、【甘えた妻】の事例を話し、
【やがてあひ添ひて、・・見過ぐしたらむ仲こそ、契り深くあはれならめ】を結論としました。
「蜉蝣日記」の主人公の【甘える女】に対する全否定の文章に、当時の女性達の反応はどうだったのでしょう?
式部の挑戦状の様な文章でした。
会話表現の【かし】が多用され、「そうなんだよ!」という左馬頭の唾が飛ぶのが見える様。
【雨夜の品定め】は、女という生き物の生態を詳細に観察し書かれている、辞典の様です。
読後一言感想
・ 左馬頭は、話せば解るいい奴だと思った。
あれこれ女を思い浮かべて、考えてみたけれど、結局、最後は何だか解らなくなっちゃって、もう出自も顔もどうでもよくて、性格が良くて、情緒が安定していればいい・・・それが結論。
世の多くの男は、その結論に辿り着いて欲しいものです。
紫式部は、甘ったれたお騒がせ女を、心の底から憎んでいたのね・・・。不満を爆発させて、極端から極端に走る女は、【やがて尼になりぬかし】、あーあ、悲劇のヒロインか?
そのまんま尼になっちゃったよ。そおいう【なまうかび】の女は地獄に落ちろよ!
言葉が刺激的でステキです。同時代の読者も、さぞや溜飲を下げた事だと思います。
・ 妻たるもの、こうであって欲しい・・・。
まぁ、勝手な理想を語る左馬頭だが、最終的に行き着いた結論は、「心穏やかな女性であれば良し」という事なのね。
それにしても、人間観察が鋭いよね、紫式部は。
・ 甘えた妻について語る男。
その言葉を書くのは、女性の紫式部である。式部は同性として、いい加減な甘えた女に対しては特に厳しい。男を振り向かせる為に、信心も充分ではないのに出家の振りなどする女など最低だ。
【なまうかび】にならない様に生きなければ、と思う。
・ 左馬頭の話はまだまだ続き、
理想の妻像とは、情緒の安定した誠実さという事かな。そしてそれが出来ずに尼になった妻の話の、【なまうかび】は、強烈でした。
理想の妻の最低限必要なものの話は、今の世も同じかも。
・ 式部は、女性にも厳しかったのですね。
【かからむきざみをも、見過ぐしたらむ仲こそ、契り深くあはれならめ・・】とは、手厳しい。
静かなる心の趣が一番大切だというのは、千年経った今でも変わらない。
・ 左馬頭は、求める妻の理想論を熱く語る・・・。
【隅なきもの言ひも、定めかねて、いたくうち嘆く】理想と現実の隔離!!
その通りと、式部はあれこれ例を挙げて。
描写の巧みさげに、読み手も引き込まれる。上手ね!!
左馬頭は、結局妻は、【ただひとへにものまめやかに、静かなる心のおもむきならむ】【よるべ】で、【つひの頼み所】と。
いつの世も、夫婦は、「持ちつ持たれつ」で繋がっていくものでしょうね。
・ 甘えた妻は、「蜉蝣日記」を思い出させました。
結論は、消去法で【ゆゑよし心ばせ】はどうでもよくて、【うしろやすく、のどけき所】が良いと。
【仏も・・心きたなしと】とか、【なまうかび】とか、女性に厳しい式部の表現に驚くばかりでした。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年2月4日受講
当時の男にとって理想的な家の主人は、自分をしっかり後見出来る女。
すなわち、賢く、信頼出来る家事をこなし、自分の話を理解出来る教養を備え、更に美しく、優しく!
若い娘の【塵もつかじ】【おほどかに言選り】【息の下にひき入れ、言少な】な、思わせぶりに騙されるのを【はじめの難】とし、【もののあはれ知り過ぐし】ている女には、そんな情けは【なくてもよかるべし】。
一方、家事と格闘して【耳ばさみがちに、びさうなき家刀自】を色々難癖つけた後で、彼女が【何ごとぞ】と言うのに【いかがはくちをしからぬ】ですと?よくもこれ程の要求が出来るものだと、式部の男目線に感心しながら、男がみんな我慢している? 結婚している殆どの女は、【たもたるる女】?
えー、これって現代の女と男の生態と全く変わっていない!
結局、左馬頭は【わが力いりをし、なほしひきつくろふべき所なく、心にかなふやうにもやと、選りそめつる人の、定まりがたきなるべし】と。彼は分かっています。求める女はこの世では見つけられないと。
源氏より階級が下の左馬頭は【君達】に面白おかしく話をしようと随分頑張りました。
そしてまだ彼の話は続いていきます。
【上は下に、下は上に】の考え、男尊女卑と思われた夫婦の力関係は、もっと現代風であった事を知りました。【あやなきおほやけ腹立たしく、心ひとつに思ひあまることなど多かる】は現代サラリーマンの愚痴そのもの。
もっと古語を勉強したら、話し言葉のニュアンスが、生々しく伝わるだろうと思いました。
読後一言感想
・ 紫式部は、やはり「凄い」の一言しかない。
男が語るという形をとって、見事に女の様々な醜態を描いている。現代にも通じる永遠のテーマだ。同性なのに笑えるところが、ユーモアの質が高いのだろう。近代化とか言っても、人間の本質はちっとも進化していないのだと感じた。
・ 年配格の左馬頭は自らの経験を語る。【わがものとうち頼むべきを選らむに・・・】
妻を選ぶに当たっては、【えなむ思ひ定むまじかりける】妻との関係も【朝廷につかうまつり】と、「世の習わしの様に上下双方が助け合わねば」と例えて、妻の条件論に発展する。
古今東西、いつの世にも有り得る事だが、夫婦の在り方を細やかにユーモラスに描写。
古文の表現は難解。式部の冴えた表現!!
・ 千年経っても夫婦って変わらないんですね。
「爪も染めず、びさうなき家刀自」でいてくれと言っておきながら、【何ごとぞ】と言えば、味きなしと言われ、やってられないね!!
でも、【たもたるる】事に意味があるなら我慢するか。
「なーんか勝手な事言ってるわねぇ、若い男どもは・・・」だけれど、雨夜の品定めはやはり面白い。
これから色々な女が出てくる。「あーでもない、こーでもない」と。
次回も楽しみだ。それにしても「容貌きたなげなく」は、凄い表現よね。ドッキリです。
・ 文章に省略されている部分が多く、言葉や状況を判断するのが難しかったが、滔々と話す左馬頭の、
妻選びの話は面白かった。
・ 家の主人は女性だったんですね。 力いりをして女を選ぶ男達が面白可笑しく書かれていました。
ぶりっ子の【塵もつかじと身をもてなし】姿、【耳はさみがちに、びさうなき家刀自】姿は、今でも
見かける女の姿。声を【息の下にひき入れ言少ななる】が【何ごとぞ】に変貌していく。
式部の深い人間観察!
いつの世も男達は女房に対して不満ばかり。永遠のテーマです。
イメージで読む源氏物語 帚木
2015年1月7日受講
源氏より七歳年上の左馬頭が、品の違いをどうやって分けるのか?という源氏の問いかけに答え、滔々と話し始めます。成り上がり者に厳しく、落ちぶれた貴族に優しく。中の品の新興階層の受領は、階級が細かく分かれているが、中々良い様だ。貴族の中では、中途半端な三位までの上達部よりも、元の家柄の良い家の、参議でない四位の者達の、経済的にゆったり育て、難癖をつけがたく成長している娘達も大勢いて、宮仕えに出て、帝の子供を産むなど、引き合いに出す例も多い。等と。それを聞いた源氏が「女を選ぶ全ては、経済力なんだな」と茶化すと、中将は、左馬頭の話を中断させた源氏をたしなめます。左馬頭は話を続け、上の品に良い女が居るのは当たり前だけれど、そうでない場合もある。上の品は自分の及ぶ世界ではないので置いて、【さて世にありと人に知られず・・・】と【葎の門】の【いといたく思ひあがる】精神的に気高い、意外な女の話を、皆の興味を引く様に話し始めます。語り手は、源氏様は「上の品と思う人でも疵のない女など滅多にない」と思っているでしょうと。そして、【白き御衣どものなよよかなるに、直衣ばかりを、しどけなく着る】灯影に、【女にて見たてまつらまほし】女にして見ていたい。この方の為には、上の中の上の女を選び出してもまだ不十分だと見えます。と。語り手のドキドキ感が伝わる文章でした。
本物の上の品の男達は成り上がり者に手厳しい。そして意外性のロマンが好きです。
【思ひあがる】の意味が、精神的に気高いという意味には、驚きました。
※当時の受領が赴任した国は、60数か国あり、大国、上国、中国、下国に分類されていました。
・大国:大和・常陸・陸奥・肥後他9国
・上国:山城・三河・安芸・筑前他31国
・中国:安房・丹後・土佐・薩摩他7国
・下国:和泉・伊賀・伊豆・対馬他5国
紫式部の父は受領で、七十歳の時越前(福井)へ、明石の入道も受領で、物語の中心人物として登場。
読後一言感想
・ 貴公子の女性論が始まる。
まず左馬頭は、道筋をたてながら理論を展開する。【今時の中の品・・・】何時の世でも価値観の相違はつきまとうが、【心は心としてこと足らず】短い文節だが意味深い、難しい。
中の品にも【きざみきざみ】古語の表現の面白さ。年上の左馬頭はこれぞと熱弁をふるう。
難解な古語の連続ながら、私なりのイメージを膨らませられる、式部の洞察力、表現力の凄さ!!
光さまの火影に浮き出た姿にうっとりと~、今日は終わる。
・ 雨夜の品定め、2回目の受講です。
上の品よりも中の品の方が面白い云々・・。
2回目の良さは、様々に登場した女性達に当てはめる事が出来るからだろうか。
1回目は、文章を追うだけで精一杯でしたもんね。
・ 左馬頭の知ったかぶりは、とてもリアルだったが、あの手この手で弁舌を振るうのも面白い。
階級制度の話は難しい。
・ 【末摘花】を勉強した時、【葎の門】の話が出た記憶がありました。
年上の左馬頭は、若者達を前に、とうとうと、自信ありげに喋ります。
【直衣ばかりを、しどけなく着なしたまひて・・添ひ臥したまへる御灯影】の源氏に、皆でため息をついた事も懐かしく思い出しました。
受領が治めた国が、大・上・中・下国に分れていた事は、大きい会社の沢山ある支店を連想しました。
イメージで読む源氏物語 帚木
2014年12月3日受講
【すきがましきあだ人】中将の体験的女性論が始まりました。
開口一番【難つくまじきはかたくもあるかな】「ケチをつけられない女はいないと分かってきた」と。そして、事細かに女達の難点を話す彼は【かたかど】ではない、自分の話し相手として教養ある女を求めている様です。親、女房達が女の本当の姿を隠し、偽っていると。結局【見劣りせぬやうはなくなむあるべき】「見劣りしする女ばかりなのですよ」と呻く。これは難しい表現ですが、会話表現の微妙なニュアンスが伝わりました。それに対して源氏は苦笑しながら【かたかどもなき人はあらむや】「何の取り柄もない女っているのかね?」火に油の一言。中将【三つの品】論への突入です。上の品のお嬢様は、優れた女房達がその欠点を覆い隠し、個性等は見つけられない。これは葵タイプ?
【中の品なむ、人の心々、おのがじしの・・】中の品の女にこそ個性ある、それぞれ思い思いに主張する心模様がにじみ出ていると。下の階級は【耳たたずかし】聞く気も起きない。それに対し源氏はもっと奥深い観点で、高貴な家が落ちぶれた場合、並みの人間が上流貴族に登った場合、これらをどう区別するのか?と問い掛けたその時、【世のすきもの】で【ものよく言ひ通れる】左の馬の頭、籐式部の丞が、帝の物忌で内裏に籠ろうと登場。二人が入って話は【いと聞きにくきこと多く】色っぽい話も交えて展開して行きます。
読後一言感想
・ 雨夜の品さだめの展開~
しめやかに降る雨の宵に、恋文をめぐって二人の貴公子のやりとり。源氏の恋人を射止めむ・・と、【すきがましきあだ人】中将は理想と現実の狭間で並々ならぬ情報と想像力を駆り立てるが、さて現実となるとうらさみしい結果・・と。【うめきたるけしきもはづかしげなれば】源氏は、中将の女性像に興味津々。これから三つの品に登場する女性像を、式部の描写力を楽しみに。
・ 三つの品の分け方が面白い。一旦【花散里】迄読んだ私達にとって、それまで登場して来た女性達を、「この人は上の品だね」、「あの人は中の品か・・」と、当てはめるのだ。【中の品】はそれぞれに個性を持つ環境なのね。納得です。
・ 中将の話をちょっとからかって、源氏が【そのかたかどもなき人はあらむや】から始まった【三つの
品】は、なるほどと思った。
これから色々出てくる女の人達は、どの品に当てはまるか、考えるのも面白いかな、と思います。
【上の品】:隠す(女房たちが多勢いて隠される)
【中の品】:個性が表に出る。
【下の品】:【耳かたずかし】聞く気も起きない
・ 【三の品】の女性論に、これまでの登場人物をあれこれ挙げ、盛り上がりました。そして、「お嬢様には個性が育たない」に、お嬢様達を思い浮かべましたが、私は本当のお嬢様に会った事がない!
同じ【中の品】の清少納言の【随筆】と比較して、式部はこの様な【ドキュメンタリー的物語】が同じ時代にどうして書けたのか?今更に、凄い事だと語り合いました。
【上達部などまでなりのぼった】者の【我は顔にて家のうちを飾り、・・】は、今の成金の有り様と同
じでした。
イメージで読む源氏物語 帚木 2014年11月5日受講
【帚木】とは
信濃の園原にあり、遠くからは箒の様な梢が見えるが、近寄ると見えなくなるという伝説の木の名。
情がある様で無い様子を例えている。(旺文社:全訳古語辞典)
【源氏十七歳】の見出しで始まる【帚木】に戻ってきました!
【桐壷】の巻の最後で、自分の里に【思ふやうならむ人をすゑて住まばやとのみ】思った源氏はもう十七歳。
式部は【帚木】の冒頭で、改めてこの物語の主人公・光源氏がどの様な人物かを、【交野の少将】の様な好色でないと書きます。中将の頃の源氏は、内裏にばかり居て、相変わらず左大臣邸への訪問は稀です。左大臣は【しのぶの乱れや:新古今集:伊勢物語】と、月並みな恋をする男ではないかと疑いますが、源氏は【いといたく世を憚り、まめだちたまひけるほど、なよびかにをかしきことはなくて】:大層世間体を気にして、真面目くさっている様子に、艶っぽい、人々が楽しめる恋愛の話等はない。【まれには、あながちに引き違へ心尽くしなることを御心におぼしとどむる癖】:まれには度を越して予想に反して気をもむ事を心に思う癖があり、【あやにくにて、さるまじき御ふるまひもうちまじりける】都合が悪い、あってはならない振る舞いも混じっています。と、語り手が。そして物語が始まります。
帝の物忌で、長いあいだ内裏に逗留している源氏に、左大臣は気を使い、彼の衣服を新調させ、子息たちを仕えさせます。息子の頭中将は、【すきがましきあだ人】好色めいた浮気者で、右大臣の婿としての暮らしよりも、源氏と共に管弦の遊びや漢学の勉強、その他の遊びに夢中です。
【つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵の雨】何と素敵な情景でしょう。そんな夕刻、宿直所で、中将は、女達から源氏に届いた文を見たがり、勝手に手紙を厨子から引き出します。困り顔の源氏に、中将は面白がって迫ります。若者二人のじゃれ合いに合間に【言すくなにて、とかくまぎらはしつつ、とり隠したまひつ】と、源氏の焦る気持ちが書かれ、決して明かしてはいけない恋文がある事を感じさせます。 そして、そんな流れの中から中将が話し始め、【雨夜の品定め】は始まります。
※二人の会話に【きこえ】:謙譲と 【たまふ】⇒尊敬が、多々使われ、二人が対等ではない事を表していました。
※十一年前には、何故此処に源氏の人柄が突然書かれているのか、全く理解出来ませんでした。再読して良かった。
読後一言感想
・ およすく会は、月毎に源氏さまの歩みと共に十年余。
亡き母の面影と慕う藤壺の君との禁断の恋。少年期から青年期に至る恋物語に引かれながら・・・
そして今日、十年経過した感覚で【帚木】の巻をひもとく。
若き日の源氏と心安い間柄の頭中将とのからみ。
意味深い古語で楽しい場面の展開でした。
・ 【桐壺】の後、五年の空白があって始まる【帚木】の巻。
十七歳になった源氏と仲良しの頭中将のやりとりが眩しい。二人共若くて初々しいですよね。
こうして【雨夜の品定め】に入っていくのね。
それにしても、五年をすっ飛ばしてしまう式部さん。
ぐだぐだ書かない事で読者を魅きつける・・・うまいなぁ。
・ 忘れてしまった処や難しいと思った処等数々あったが、進んで行くうちに段々思い出して来ました。
いよいよ【雨夜の品定め】に入って行くので、期待してます!
・ 平成十五年の三月に学んだという【帚木】をもう一度読み始めました。あの当時、ぼんやりと存在感も何も感じなかった登場人物達が、今ではその姿までも文字の下から浮かんできました。
源氏と頭中将との微妙な上下関係が、尊敬語と謙譲語にはっきり書かれていたことも知りました。
書き出しはとても難しく、【交野の少将】や【しのぶの乱れや】の表現の中に、これから書く物語
は今までの物語とは違うという、式部の自信と意気込みが表わされているなんて事、十一年前は、何のこっちゃ?でした。当時は、言葉一つ一つを追いかけていただけで、その先のイメージを捉えるには十年以上掛かったと知りました。再読する楽しさは、自転車に乗れるようになった子供みたいに、どんどん読み進みたい衝動に駆られました。
原文からひろがる源氏物語 花散里 2014年10月1日受講
二十日の月の光が麗景殿の女御の荒れた庭の小高い木の影を映し出し、そこに橘の香り。年取った女御の変わらぬ人柄の可愛らしさに、桐壺院の昔を偲び、涙する源氏。そしてまた郭公の鳴き声。【いにしへのこと語らへば郭公いかに知りてか古声する】の【いかに知りてか】と口ずさみます。元歌【橘の花散里の郭公片恋しつつ鳴く日しぞ多き】から、【橘の香をなつかしみ郭公花散里をたづねてぞとふ】「昔を思い出させる橘の香が懐かしくて郭公は花散里を探してやって来たのです」と歌います。麗景殿の女御は桐壺院なき今、自分の弱みをさらけ出せる大切な一人でした。源氏は彼女の孤独な辛い日々を慰めます。それに返して、女御は【人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ】「荒れ果てて訪れる人がいない住まいは、橘の花だけが軒端に咲いて香り、彼方様を導く手がかりになったのでしょう」この歌だけを詠いましたが、心の奥行きの深い、温かい人柄を感じさせました。
三の君(花散里)の住まう西面をさりげなく訪れ、ひょいと覗いた源氏の久し振りの訪問に加え、その美しさに、彼女は今までの辛さも忘れたことでしょうと、語り手。二人は何やかや懐かしく、変わらない心で【情をかわしつつ】語らい過ごします。それを【あいなし】つまらない事だと、人の心が変わるのは世の習らわしだと思う人は、途中で立ち寄った女も同じだと。ここに【ありつる垣根】が出てきました。
花散里はあっという間に終わりました。
何故途中で違う女の屋敷を訪れるの? 何故そこで郭公が鳴いたの? 最後に全てが繋がりました!
橘、花散里、郭公はセットだった!
最初この短い巻が何故必要か分かりませんでした。でも、今の落ち目の源氏を見捨てる女と、傷心の源氏を受け止めてくれる誰かがまだ居るよ!という大切な巻でした。
怒涛の【賢木】の話をそのまま続けない式部の素晴らしい物語作りに感動しました。
※【情をかわす】は、相手を思いやる男と女の関係。先生が【軒端の荻】と源氏の関係を話されました。
古語の深さにまたも痺れました。
読後一言感想
・ 花散里登場は短かったけれど、麗景殿を訪ねるところは、源氏の心を落ち着かせ考えさせる場面が多かった様に思う。麗景殿のひっそりと静かに暮らす姿がとても良いです。こんな場面があってホッとしています。【情けをかわす】は、ちょっと難しかった。
・ 賢木の巻は、何と源氏さまの恋のいきさつの重かったこと。大将の君は、八方塞がりの中で心の安らぎを求める様に、内裏で院にたずさわれた麗景殿女御へと心を馳せる。
行きすがら昔懐かしい恋の香りにつられて・・・
けんもほろろのつれない返歌に、惟光の粋な計らいで道草もせずに、
人目なく静かな佇まいの邸、気品ある女御との語らいで【むかしのことかきつらねおぼされて、うち泣きたまふ】女御の凛とした奥ゆかしさ。心癒された源氏の君は、西面に【わざとなく忍びやかにうちふるまひたまひてのぞきたまへる】姫君は、【ほのめきたまひし名残】密かに長年憧れを抱く三の君(花散里)二人は懐かしい語らい・・。緑変わらぬ橘の香・・・花散里。
恋の遍歴を重ねた源氏は、人の絆の深さをしみじみと思ったことでしょう。
・ 気弱になった時、ふと思い出して会いたくなる様な人・・・。源氏にとって花散里はそんな女性だったのね。それにしても、古語って本当に奥深い。【われも人も情をかわしつつ】の解釈がすご~い。一口に男女の関係といっても、こういう大人のケースもあるのよね。
紫式部さん、あんたは何者?!
・ 二十日の月が映し出す深い黒々とした木の陰。近くから橘の香。そこに又郭公が効果的に鳴く。
麗景殿の返した歌のさっぱりした上品さ。
【情をかわす】の意味は深く。【世に目なれぬ御さま】は源氏の美しさを表す。
【ありつる垣根】への寄り道がどうして書かれなければならなかったか、郭公がそれを繋いで物語を面白く、重厚にしていました。
この短い【花散里】の巻の必要・重要性が、良く分かり感動しました。
原文からひろがる源氏物語 花散里 2014年9月3日受講
【花散里】の花は橘の花だそうです。この巻は【賢木】と【須磨】の間の短い物語。
怒涛の【賢木】が終わり、さてこの続きは?ドキドキしながら読み進むと、全く違う展開が始まりました。
源氏にとって【かくおほかたの世】周りの状況は【わづらはしうおぼし乱るることのみ】【もの心細く】出家してしまいたい程厳しいけれど、そうする事も出来ない。
そんな折、ふと桐壺院の女御の妹三の君(花散里)を思い出します。麗景殿に子供はなく、院亡き後は落ちぶれて、源氏が陰で経済的に支えています。内裏あたりで源氏は三の君にはそれとなく気持ちを伝えてあり、全く忘れてはいないけれど、あえて手紙を書く事はありませんでしたが、三の君は、源氏に心を尽くしていた様です。
華やかな時には思い出さない、落ちぶれて思い出す女性。五月雨の晴れ間に会いに出かけます。
忍びの姿で向かう途中、由緒有りげな家から上手に【にぎははしく】華やかに琴の音が。よくよく眺めると、一度来た事がある家と知ります。【ただならず】普通ではいられない。長い時が経っていて、女は覚えていないだろうと、気が引け通り過ぎかねていると、その時郭公の声が【もよほしきこえ顔】そそのかしている様に聞こえ、車をおし返させて、惟光に歌を託して女に届けます。【郭公の私は、恋しさに耐えかねて、昔に戻って引き返して来ました。ちょっとお話した宿の垣根に】それに対する女からの歌は【昔の郭公の声の様ですが、嗚呼良く分かりませんわ、五月雨の曇った空なので】とつれない返事。惟光は【よろしい、それならば私が家を間違えたのでしょう】と、引歌の言葉を残し去って行きました。女は、心の中で密かに、残念でだと、しみじみと心が動きます。源氏は、女に男が出来ていれば遠慮するのはもっともな事と諦め、この様な中の品として、筑紫の五節の舞姫が可愛かった事を思い出します。
語り手が、どんな女に対しても気遣いして苦しそうで、年月を経ても、なおこの様に一度会った女に対して知らん顔が出来ないのは、かえって多くの女達の物思いの種になるのですね。と。
思い立った女の所を訪ねる途中、違う昔の女に【ただならず】普通ではいられなくなって恋の歌を贈る。
こんな事の出来る男の【御心の暇なく苦しげ】を同情する語り手は、変です。現在では。絶対。
※郭公は、カッコウ科の鳥で鶯等の巣に托卵し、声は鋭く「テッペンカケタカ」と聞こえるそうです。少し
下手くそな鶯の声に似ています。
読後一言感想
・ これでもか、とドラマチックな展開が続いた【賢木】が、思わせ振りに終わり、さて、源氏が須磨に・・と思いきや。間にそっと書きつらねられた【花散里】。すごく短いけど、何か気になる巻ですね。それにしても、源氏は恋多き・・・すぎる。悩めて当たり前よね。
・ 自分が落ち込んだ時や自分の居場所が無い時には、あまり上の人間とは付き合いたくないものだ。現代にも通じる人間の心情が、源氏の気持ちを通して伝わる、【源氏物語】らしくない、面白い場面だ。
・ 久々に出て来た惟光は、ずーっと源氏に寄り添って相変わらず気転のきく最良と思った。
中川の女や筑紫の五節は、あまり【源氏物語】の中では華々しくないので、知らなかった。
・ 落ち目の源氏は恋に逃げる。落ちぶれて思い出した、桐壺帝の女御の妹花散里に会いたくなる。
その道すがら、昔一度だけ訪れた女の家の前を通り、思い出して歌をおくるが、歌で拒否される。腹いせに五節の舞姫を思い出す。
私は、講義の最後まで拒否した女が花散里だと、思っていました。そんな余裕は今の源氏にはないと。
郭公はどんな声で鳴くのでしょう?
秋に桂の黄葉は香り、葉の形は葵と類似しているそうです。
イメージで読む源氏物語 夕顔 2014年8月6日受講
高見沢さんは、最近お能の制作に関わっておられ、八月三十一日に国立能楽堂で、源氏物語【夕顔】を元にした【半蔀】の公演をすると言います。
【賢木】が終わり、彼女の提案もあり、今月は急遽【夕顔】のおさらいをする事となりました。
【イメージで読む源氏物語Ⅱ】の本と先生がお持ち下さった【半蔀】の謡本を資料に勉強しました。
まず、【夕顔】の【なにがしの院】辺りまで先生が解説して下さり、懐かしく、愛おしく、正に言の葉を拾う様?に読み返しました。
私達が【夕顔】を読んだのは、九年前と知りました。源氏は十七歳でした。私達はまだ・・才!
次に【半蔀】の謡本の最初から最後まで解説して頂きました。
その中に多くの原文からの抜粋を発見し、胸を躍らせ、各人が叫びました!
謡本の写し
【白き花乃おのれひとり笑乃眉を開けたるハ如何なる花を立てけるぞ】
【黄昏時の折なるに。などかハそれと御覧ぜざる】
【これハ夕顔の花にて候、げにげにさぞと夕顔乃。花乃主ハ如何なる人ぞ】
【何某の院にも】
【山の端乃。心も知らで行く月ハ。上の空にて絶え絶え跡の】
そして、【帚木】の頭の中将に常夏の女が残したあの歌、
【山賎の。垣ほ荒るともをりをりハあはれをかけよ撫子乃】
【夕顔】の御嶽精進の声【南無。當来導師】
扇の場面は最後に、
【あの花折れとのたまへば。白き扇の端いたう焦したりしにこの花を降りて参らする】
【遠方人問ふとても】
【折りてこそ。それかとも見め。たそかれに ほのぼの見えし。花の夕顔】
本の最後は、
【また半蔀の内に入りてそのまま夢とぞ。なりにける】で終わっていました。
夕顔は五条の宿が一番安心出来たのでしょうか?
高見沢さんが持って来て下さった資料と共に、能【半蔀】を深く鑑賞したいと思います。
原文からひろがる源氏物語 賢木 右大臣と大后 2014年7月2日受講
右大臣の、娘の大后(弘徽殿の女御)への駆け込み訴えの一部始終。【かうかうのことなむはべる】と、早口でまくし立てた父は、娘のあまりの剣幕に、我に返りますが、時既に遅し。
【いとどしき御心】の宮、弘徽殿の女御の脳裏に次々に映し出された今までの屈辱の日々。鬱憤は、父親のとりなしの言葉で増幅し、【いとどいみじうめざましく】三連続形容詞でブチ切れました。【構へ出てむに、よきたよりなり】 今や源氏の運命は、弘徽殿の女御に委ねられました。
源氏の元服式の場面【桐壺】P-108~116に弘徽殿の女御は登場していません。その華々しい儀式の、場面場面を彼女の視線で追うと、その悔しさが生々しく蘇りました。
そして、それからどうなるの?という読者を置き去りに、【賢木】は、本当に突然終わりました。
読後一言感想
・ 源氏と尚侍の君は密かに逢瀬を重ねる。と、ある日激しい雷雨が轟く中、おとど突然の出現。
ついに、うたかたの恋が露見。
おとどは、あるまじき情況に狼狽と怒り、【籠たるところおはせぬ本性】大后のもとへ突進。
口角泡を飛ばす勢いも【天下をなびかしたるさま・・・】天下の源氏様だもん!!と。
大后は、おとどの甘い認識に、長い年月の悔しさ、恨み【いとどいみじゅうめざましく】更に怒りの炎は燃え上がる。
大后の胸の内には【さるべきことども】源氏失脚を【おぼしめぐらすべし】式部の迫真の描写、古語の深みを存分に味わいました。
・ 大后の憎々しさが際立つ場面。父右大臣もたじたじだ。
大后が毒を吐いた激しいシーンで、この巻は終わり、大后にこの先の運命を握られた源氏の行く末が案じられる。処罰も想像される。次の巻が待ち遠しくなる、小説としては、とても面白い終わり方だ。紫式部は、やはり天才だ!!
・ この度の源氏の振る舞いは、大后のたまりにたまった怒りに火をつけてしまう。
ま、当然と言えば当然よね。この怒りの炎の色は、きっと「青白い」のでは・・・と思う。
大后の瞳の中にメラメラと復讐の炎が燃え盛る。おお、こわ。
と、こんな思わせぶりで、【賢木】は終わる。うまいねぇ。
・ 右大臣と大后の人物像がとても良く描かれていると思いました。
最後の【構へ出でむ】は、何か恐ろしい事の予感です。
大后は、今迄ずっと溜め込んでいた事を爆発させるのでしょうか。
・ この事件での右大臣家の人々の心模様。
大后の、常に源氏の陰になっていた今迄の、辛さ、切なさ、恨みが一気に吹き出し、その勢いに圧倒されてしまう。
・ 【賢木】が、えっという?感じで終わりました。
右大臣と大后の会話の中に、大后・弘徽殿の源氏に対する今までの、恨みつらみが。帝に愛され、皆にちやほやされた源氏と、今一つ歯がゆい自分の息子。その憎き源氏が妹と関係し、その事で帝の后としてではない立場でも仕方がないと、やっと入内させたのに又!事もあろうにこの屋敷の中で! 私達を【軽め弄ぜ】ていた! もう許さない! 復讐の時がやって来ました。
輝いていた源氏の多くの姿を、弘徽殿の視点で、改めて眺め直すと、彼女も切なかった。
右大臣は、娘の剣幕にとりつく隙もない。
直ぐに続きが読みたくなる終わり方でした。
原文からひろがる源氏物語 賢木 発覚 2014年6月4日受講
右大臣の突然の登場。彼の一挙一動で場面が流れて行きます。緊急事態の中、源氏は右大臣の早口と左大臣の喋り方を比較して【ほほゑむ】余裕すらあります。尚侍の君の赤くなった顔、絡みついた薄二藍色の男物の帯。カラー映像の様。畳紙を見つけられ、振り返った尚侍の君と、几帳の中に横たわっている源氏を【男もあり】と見た右大臣の大きく開いた瞳は、劇画の様。
この密会を【あさましう、めざましう心やましい】右大臣は、源氏に面と向かって文句も言えず、【目もくるるここち】もするはずです。入内した娘を傷モノにしたくはなく、帝のスキャンダルにしてはいけないのです。大目に見る寛容の余裕があるはずもありません。
几帳の中に厚かましく添い臥しながら、源氏は【つひに用なきふるまひのつもりて・・・】退廃的で、やけっぱちになり、落ちていく自分が良く分かっています。【死ぬべくおぼさる】尚侍の君は、そんな源氏に惚れたのです。退廃的な男をどうしようもなく好きになる娘心。
語り手は、右大臣の行為に対して、【げに入りはててものしたまへかしな】とか【・・・さばかりの人はおぼし憚るべきぞかし】とか意地悪でした。
さて、弘徽殿はどう出ますか?次回のお楽しみ。
読後一言感想
・ やんぬるかな!!
難解な古語の行間から浮かび上がる、滑稽とも読み取れる大臣(おとど)、女君、源氏との情況に引き込まれる。
突然の右大臣(おとど)の出現【かれは誰がぞ】【つつましからず添ひ臥したる男もあり】【われかのここち・・・】おろおろする内侍の君。【つひに用なきふるまひのつもりて・・・】女君の心情を思いやる源氏さんだが・・・、恋は命・・・自身の振る舞いで何人もの姫君が涙したことか。
怒り心頭のおとど、右大臣の渦中での内侍の君との恋の結末は・・・如何に!
・ とうとう発覚してしまいましたね。それも現行犯。
右大臣の狼狽ぶり、頭の中真っ白の内侍の君の姿が目に浮かぶ様です。
それにしても、事態をこと細かに聞いた弘徽殿大后。
ああ、次回はその怒りが炸裂するのね・・うふっ、楽しみ。
源氏危うし!
・ 朧月夜との出会いは、桜を愛でる夜。密会が露呈するのは、今回の天気の急変、雷によるもので、右大臣にバレる場面はスリルがあった。
いつかは分かってしまうという行為そのものに刺激を求めたのかしら?
やっぱり内侍の君は魅力的だったのかな?
・ 神鳴りやみ、右大臣が娘を案じて早口でまくし立てながら入って来るのを、源氏は、左大臣の物腰とくらべて、
【たとしへなうぞ ほほゑみたもふ】笑っている場合か?大臣が几帳より【見入れたまへる】と、【いといたうてなよびたる】男が、【つつましからず添ひ臥し】ているではないか。すると、【今ぞ やをら顔ひき隠して】と、見つかってしまった今になって顔を隠す。源氏に慌てた様子が全くない。大臣をなめとんのか?
しかし、源氏も【つひに用なきふるまひのつもりて、人のもどきを負はむとすることとおぼせど・・・】と、自暴自棄となっている自分の事は分かっていた様である。
・ 帯、畳紙そして【添ひ臥したる男も】に右大臣の驚き、怒り不快感が【目もくるる】程に!
右大臣の動きが、動画の大写し場面の様に目の前に浮びました。
右大臣の動に対し【いといたうなよびて、つつますからず添ひ臥したる】源氏は静。
悲劇と喜劇は紙一重。源氏はこの密会を【用なきふるまひ】と言う。その人が女君を慰めている。
デカダンスで、やけっぱちな源氏がそこにありました。
原文からひろがる源氏物語 賢木 憂さ晴らし~発覚 2014年5月7日受講
中将邸の【まけわざの宴】は、いよいよ酒宴に。中将は、源氏を薔薇の初花に例え賛美する歌を詠みますが、源氏が返した歌は、今朝咲いた花(自分は)早く咲きすぎて夏の雨にしおれていると自虐的に、はしゃぎ、酒を飲み続けます。参加した各人が酔っ払った勢いで源氏讃歌の和歌や漢詩を詠む中、【おぼしおごりて】源氏は、自分が【史記】の中の【文王の子武王の弟:桐壺院の子で朱雀帝の弟】であり、優れた政治を行い聖人として尊ばれた周公であると名乗りを上げます。右大臣ではなく自分こそが帝を補佐する血筋の者だと。人々は、それを又褒めたたえ喜びました。それでは、自分は【成王:春宮】の何だと言うのでしょうね。そればかりは又頼りなく不安ではないでしょうかね。と、語り手が冷静にピシャリ。
マラリアの様な病気で、尚侍の君は実家の右大臣邸に帰っています。加持祈祷で病状が快復し、家の者達は安心したの【に】、この【めずらしき隙】千載一遇の機会を恋する二人は見逃しません。どんな方便を使ったか【夜な夜な対面】です。明るく華やかで賑やかな彼女は、女盛りでもありますが、病んで痩せ細り美しくなっていました。でも、ここは右大臣邸。弘徽殿の女御も里に帰って来ていました。その気配はとても恐ろしいけれど、源氏の【かかることしもまさる御癖】はもう止まらない。右大臣にとって思いも掛けない事なのに、ある暁、急な豪雨と雷が皆をたたき起こし、邸内はものすごい騒ぎになりました。尚侍の君と一緒に居る御帳の周りには、怖がり、うろたえて座り込む女房達が集まって来て、外には出られないまま夜はすっかり明けてしまいました。【いと胸つぶらはしくおぼさる】源氏。 さあ、どうしましょう!
※源氏物語は、政治について書かれていないという説は、今回の酒宴での源氏の【御名のり】で否定されました。右大臣から疎まれた、自分と漢学の専門家達の憂さを晴らす【史記】の【文王の子武王の弟】宣言は、今の彼の置かれている政治的な立場からは、あまりに危険な発言。
更にそんな中での右大臣の娘との密会ですって! 源氏さん、何を考えているの?
読後一言感想
・ 内侍の君との右大臣邸での逢瀬は大胆不敵、あまりにも危険でスリリング。
突然の雷雨で、御帳台の廻りに人々が集まって、源氏はピンチ。
人々の動きを思い浮かべる事が出来、ハラハラドキドキさせられてしまった。
・ 右大臣に傾く時世・・・中将、博士など源氏と古歌を諳んじながら【やるせなさ】を紛らわせる。
折しも内侍の君は病の療養で里帰り。千載一遇の機会と手引きをつけて、夜な夜なの逢瀬を。
危うい恋ほど湧き立つ恋心。内侍の君の病み上がりの【をかしげなる】風情にアバンチュールの炎は燃え上がる。天の諌めか、突然轟く雷鳴と大雨。
【いと胸つぶらはしくおぼさる】源氏さま危機、いかなるや。
・ 『かかることしもまさる御癖なれば』と式部にピシャリと片づけられてしまう源氏は、ついに尚侍の君との逢瀬が「発覚」しそうに!
源氏は中将が招いた『まけわざ』で『うちそうどきて、ろうがはしく聞こしめしなす』源氏のこんなお酒の飲み方の表現は初めてだよ! やばいよ!
源氏が自分を『文王の子武王の弟』と 自らを励ますように口ずさんだのを、『げにめでたき』と称える人々。「右大臣のこの時代では日の当たらない人々」が源氏をあまりに持ち上げるのもいけないよ!
源氏の逢瀬が発覚に至るあやうい状況が上手に描かれている。
・ 文王の子武王の弟
中国の史記は、説明を聞いても良く分らないけれど、文王は、故桐壷帝で武王は朱雀帝、周公は源氏を指す事は分かった。
内侍の君(朧月夜)との密会の場面は、この先どうなるか楽しみ。ハラハラドキドキです。
・ 初花を自分に例えた源氏は、へこたれ、酔っ払います。史記の【文王の子武王の弟】の周公を自分に例え名乗ります。皆へべれけの宴会は、貫之が耳を塞ぐ歌の数々。
その後、突然激しい恋の物語に場面転換し、読者を離さない式部の筆の冴え。
弘徽殿の気配が感じられる右大臣邸内での内侍の君との危険な逢瀬に、天まで怒る。【雨にはかにおどろおどろしう】【神いたう鳴りさわぐ暁】御帳の中、大勢の人々に取り囲まれた二人の運命は!
息をひそめて、来月を待ちましょう。
原文からひろがる源氏物語 賢木 司召の仕打ち~憂さ晴らし 2014年4月2日受講
左大臣家の子供達にも右大臣側の司召の仕打ちは及び、人柄も良く快活だった彼らに今勢いはありません。右大臣の四の君との関係が冷たくなっている三位の中将も同じで【思ひ知れとにや】とばかり、右大臣家の信頼出来る婿としても認めてもらえず、ふさぎ込んでいます。そんな中、中将は源氏と腹をくくって、学び遊びます。【帚木】、【末摘花】、【紅葉賀】、【花宴】そして源の内侍を巡る戦い?二人の友情を懐かしく思い出しつつ、それでもまだ源氏に挑む彼の姿は微笑ましい。
仏事をはじめ、漢詩の韻塞や管弦の遊び。閑になった文化人達の救済。憂さ晴らしにしては高尚過ぎ。
ここでも源氏はスーパーヒーロー! 素晴らしい学才と、単の直衣姿は年老いた博士達を泣かせる位。
中将の子供で、八才か九才の次郎は、誰からも大切に育てられ、利発で性格も良く、美しい声と容姿、そして難しい笙までも吹ける才能。【うつくしびもてあそぶ】源氏の顔は喜びで高揚しています!美しいものが大好きだから!この孫に対する左大臣の誇らしげな顔が浮かびました。彼も美しい源氏が大好きでした。
源氏が【御衣ぬぎてかづけたまふ】場面をどこかで見た記憶がありました。そうです!中将が、【花宴】の中で急に指名されたにも関わらず、帝の前で立派に舞った【柳花苑】に対し帝から御衣を賜った場面でした。物語は繋がっていました。
季節は夏。中将の屋敷の階に薔薇(そうび)が【けしきばかり】咲いていました!
驚きました。中国から入って来た、野ばらとの事。白?赤?どちらの色でしょう?
この【憂さ晴らし】で物語は面白くなって行くのだろうけれど、世間に対しあまりに目立ち過ぎです。
読後一言感想
・ 源氏は籠ってもさすが優雅。気ままに学問や遊びにと日々過ごし、同じ境遇の三位の中将との韻塞
ゲームに興じて楽しんでいる様に感じます。
官位をはなれても雅で平穏な生活に見えますが、その心の中は・・・
・ 本人に目立つ気はなくても、どうしても滲み出てしまう源氏の学識の深さや姿かたち。
あ~あ、そんな御仁が傍に居たら、うっとりみとれるか、うっとうしく思うか・・・。
品格が問われたりして。
・ 時世の変化は、容赦なく大将の君、左大臣家の子息達に及ぶ。
【世ははかなきものと見えぬるを】中将は大将の君の邸を訪れて【学問も遊びをももろともになしたもう】かねがね親交の厚い二人の様々な場面が浮かぶ。
逆境の中で、貴公子、博士等と打ち興ずる雅な趣。秀でた才能で、真摯に対応する源氏。
【いとこよなき御才のほど】と【人々めできこゆ】
式部の知識の深さ、平安の流れる様な物語の描写。充分堪能しました。
・ 【年老いたる博士どもなど、遠く見たてまつりて涙落しつつゐたり】。この年老いたる博士達は、【花宴】で内裏の白砂の庭で朗々と声を張り上げ詩を詠った博士達である。桐壺帝の治世は、文化の華が咲いた、良い時代であった。博士達は、源氏の美しい【単を着たまへる】姿を見て、あの良い時代を懐かしみ、涙を落としたのでしょうか。
・ バラの花が平安時代に中国から入って来ていたなんて、驚きです。
憂さ晴らしに、漢詩で競ってみたいものです。
・ 久々に登場した中将とは、相変わらず競争心があって微笑ましい。負けわざの催しでは、華やかではな
いが、久々の宴会場面を見た様な気がした。
良き時代を思い出しました。
・ 中将との友好が戻って来ました!
御読経、漢詩、管弦の遊び、司召の後の暗い日々を忘れられそうです。でも、目立たない訳がありませ
ん。心配しつつも、源氏の相変わらずの【御才】に、そうだよね・・・。
【薔薇(さうび)けしきばかり】咲いていました! 小さく、白い色?
原文からひろがる源氏物語 賢木 青鈍の人~司召の仕打ち 2014年3月5日受講
時の流れが、解けた薄氷、岸の柳、中宮の返歌に【涙ほろほろ】する源氏を眺める老いた女房達の涙に、静かに描かれていました。あの輝く光る君であった彼の今の悲しみが、彼女たちには痛い位解ります。出家した中宮と源氏に対する右大臣側の仕打ちが、【司召】にあからさまに現れ、中宮は、周りの人々の苦境を目にし、自分の出家に【御心動くをりをり】もあります。でも、決して知られてはならない【人知れずあやふくゆゆしう】の罪を思い、ただただ春宮の平穏無事を【わが身をなきになしても】と仏に祈ります。源氏もあまりに露骨な仕打ちを【はしたなく】思い、籠ってしまいます。左大臣は、こんな世に嫌気がさして、辞意を表し、自宅に籠ってしまいました。帝は優しい人です。
【今はいとど一族のみ】の世に変わってしまった時の流れです。
読後一言感想
・ 新しい年を迎え、三条の宮邸も新春の風情が漂う。源氏は中宮との贈答歌に和やかな心持ちを【むべも心ある】感慨に浸る。その雅な佇む姿に【ねびまさりたまふかな】と【老いしらへる】人々の感無量が、美しい古語で伝わる。
出家し、落ち着いた心持も、世に流れ【からきことのみあれば】世の流れのはかなさ・・・
・ いよいよ始まった右大臣家の仕打ち。まずは、経済面での差し止め。これによって中宮の生活は困窮するが、黙って受け入れ、唯ひたすら春宮を守る事を祈る。
一方、源氏も真意を汲み取り籠ってしまう。抵抗は沈黙かな。
・ 遂に右大臣の世となった。登り坂の一族と下り坂の一族。どの時代どの社会も、主流から下ると同じで厳しく辛い状況になる。現代そのままを実感する。
・ 今も昔も、会社勤めの明暗は変わらないと思いますが、高貴な人は引き籠る手があったのだと分かり、勉強になりました。
・ 【涙ほろほろと】こぼれる源氏を、【老いしらへる】女房達は【ねびまさりたまふかな】ご立派になられて・・・と、昔を思い涙します。
右大臣側の仕打ちは、あからさま。
中宮は、自分の罪が春宮にかからぬ様、唯々仏に祈る。源氏は【世の中はしたなくおぼされ】籠る。
そして、あの明るかった左大臣までも辞表を提出し、籠ってしまう。
【今はいとど一族のみ、かへすがへす栄えたまふことかぎりなし】です。
原文からひろがる源氏物語 賢木 御八講果ての日・青鈍の人 2014年2月5日受講
【月のすむ雲居をかけてしたふとも この世の闇になほやまどはむ】は、言いたいことが何も言えない
【いぶせし】心境源氏の、中宮藤壺の出家に対するせめての抵抗。返した歌の最後【かつ濁りつつ】が中宮の心の迷いを良く伝えていました。
二条の院に戻り、今までの事、これからの春宮を考え、眠れぬ幾夜を過ごし。そうだ!正月前に彼女の為の仏具を! 王命婦も出家しました。その後の【くはしう言ひ続けむに・・・さうざうしや】時々出てくる語り手を通した式部の本音。【をかしき歌】を省いたのは手抜き?
中宮の【つつましさ薄らぎて、御みづから聞こえたまふ】姿に、苦しみから解放された安堵感が伺えます。【思ひしめてしことは、さらに御心に離れぬ】源氏に、その想いを遂げることは【ましてあるまじきことなりかし】絶対有り得ないですよね。と語り手。
院の喪も明けた新しい年。中宮は【後の世のことをのみ・・たのもしく】新年の特別な勤行を。そんな三条の院に源氏が登場。その後、外の賑やかさと対照的な院の、のどかな静けさ、人少なく、うなだれている様に見える宮司達、例年通りの白馬を見物する女房達、去年は此処に、所狭く来ていた上達部達が道を避けて向いの右大臣邸に次々過ぎて行く姿が書かれます。
女房達を涙ぐませた【千人にもかへつべき御さま】華麗な正装姿の源氏は、目の前の【いとものあはれなる】変わってしまった景色に言葉も出ません。そんな中、彼の目は、青い鈍色の御簾の端、几帳、隙間から微かに見える女房達の薄鈍色、梔子の袖口に吸い寄せられ、慕わしいと思います。
読後一言感想
・ 中宮が出家するしかない、とまで思いつめた【世の憂さ】。原因の一つは源氏の抑えの切れない行動にもあったのに、羨ましく思うなんて・・・。とは言え、宮の【つつましさ薄らぎて】にちょっと救われるなぁ。これまでピーンと張り詰めていた緊張感が少し緩み、その分源氏との関係も少し薄まっていくのではないだろうか。出家は、最良の選択でしたね。
・ 中宮も源氏も様々な苦悩を超えて、それぞれの境地へ。
鈍色の衣の宮は、ひたすら勤行。吾が子春宮の為源氏の力を【たのもし】と念ずる。
新しい年、ひっそりとした三条の宮邸へ【大将参りたまへり】源氏の来訪に、【千人にもかへつべき御さま】源氏の優雅な姿を数字の千で表現。宮の人々の喜びと興奮。
青鈍の色彩に、薄鈍、くちなし色(黄色味)、式部の表現力の豊かさが行間から湧いてくる。
・ 桐壺院は、【母宮をだにおほやけがたざまにとおぼしおきてしを・・・】と、春宮の後々を心配して逝った様子がここでも描かれる。桐壺院って本当に優しい人だったのね。
中宮(藤壺)は、出家して少しほっとしたのか、【今はつつましさ薄らぎて、御みづから聞こえたまふをりもありけり】これから二人の関係も変わるのかな。
・ 政権が移ってしまい、中宮は出家した中での正月を迎えた様子が良く描かれていると思います。
色々な色の勉強は、とても楽しいです。色の名前も現代的な、赤、青、黄色ではなく、いいなと思いました。
・ 中宮の突然の出家で、激しく動揺する源氏。二人の心の思いがそれぞれ異なる、その違いを強く感じる。
・ 心の叫びを声に出して言えない【いぶせし】源氏。これからどうしよう。春宮を守らねば。でもまずは、仏の調度品の調達。さぞかし素晴らしい仏具を揃えた事でしょう。
今の中宮を【つつましさ薄らぎて】と感じる源氏に、彼女の出家の原因が自分にあるかもしれないという考えは全くない。【ましてあるまじきことなりかし】本当に遠い人になってしまった中宮藤壺。
女主人の出家で、権力圏外になった三条の院の寂しい正月の様子を、次々に視点を変えて描いている。
その暗さを、千人力の美しさで源氏が明るくする!ヒーローに拍手!
原文からひろがる源氏物語 賢木 新本 御八講果ての日 2014年1月8日受講
中宮の御八講への深い、深い思いが、用意された品の全てに込められ、【よになきさま】の【極楽思ひやる】最高の品々。そして、何時もの様に、源氏様は、【いかがはせむ】最高!
厳かに、静かに御八講は進行します。
最終日の突然の結願【世を背きたまふ】宣言。何時も覚めている兵部卿の宮の驚きと動揺。止める兄に強く自分の意思を貫く妹。授戒の後、髪をおろす。それは【宮のうちゆする】、【ゆゆしう泣きみちる】騒ぎに。周りの女房たちにも寝耳に水の、あまりに突然の事。中宮と桐壺帝との安らかな日々を知る人々の戸惑い、同情と悲しみ。源氏は立ち尽くしています。【くれまどい】何も言えない。
源氏が中宮に会えたのは、人々が帰り静かになり、月が庭の雪を明るく輝かせている頃。【いとやうおぼししづめ】御簾の中に話しかける源氏の緊張。中宮は冷静にそれに答えるけれども、皆の反応に【心乱れぬべく】。
外からは見えない御簾の中から、大勢の女房達の【鼻うちかむ】【しめやかにふるまいなす衣の音なひ】抑えたすすり泣きと慟哭が漏れて。風が激しく吹きすさび、御簾の内の薫物の香に仏前の香もほのかに漂い、それに源氏の衣の香までが香り合う【めでたく、極楽思ひやる】すばらしい夜。
東宮の使いに、心が弱くなり返事が出来ない母中宮。【大将ぞ】源氏は代わりに言葉を加え、使いの者に返事をし、しっかり中宮を支えます。泣いてはいられない。
女房達は、何故中宮が御八講に最高の準備をしたか、今になって分かりました。最高の地位の女性が今までに得た美意識の集大成をしたのだと。悲しみと、これから先を思う女房たちの不安は相当なもの。
雪を輝かせる隈なき月。御簾から漏れる抑えた悲しみの音。風に交じり合う三種の香。
正に、凍れる美の世界!
読後一言感想
・ 波乱が展開する賢木の巻
中宮は、御八講(追善供養)を催す。お供養の品々、経典に携わる僧に至るまで、中宮の人となりが表され、【まこと極楽の思ひやらる】人々の感嘆の極み。
いよいよ御八講の果ての日、中宮の結願【世を背きたまふよし】仏に出家を願う。
思わぬ事態に、人々の驚き、悲しみ、嘆き。中宮の強い決意と苦悩が胸に突き刺さる。
御八講の明暗を語り手は、微に入り細をうがつ。
式部の筆致に今日も又感嘆!!
・ 厳しい雪景色の御八講
厳かで、きらびやかな法要は絵巻を観ている様だ。
最後の日、中宮の出家を告げる事により静から動に移る。その場の人々の驚き、嘆き。
中宮の強い決心の裏の心の動き。母としての切なさと悲しみ。
香を用いる事により、雅な悲しみの雰囲気がより伝わる、すごい場面だ。
・ 賢明な藤壺の意志の強さと行動の慎重さが際立つ場面だ。
そのきっぱりとした態度故か、珍しく源氏もいつになく冷静だ。
冬のさえざえとした場面の描写が素晴らしく、悲しみさえも美しく感じる。
心理描写と背景描写が見事に溶け合い、紫式部は、やはりすごい!!
・ 出家するという決意を潔く実行に移すが、春宮からの使いには、さすがに意志がくじけそうになる。
いつの世も母と子は変わらぬ情があるものです。
ここの場面は素敵です。
・ 御八講の為に中宮が準備した、最高の品々の説明、法要の一部始終が冷静に描かれた後、突然の中宮の結願。その後の【宮の内ゆする】人々の動揺と驚きが目の前に見える様。
人々が去り【月は隈なきに、雪の光りあひたる庭】、【衣の音なひ、しめやかにふるまひなす】御簾の中の中宮の女房たちから漏れてくる抑えた嗚咽を聞く源氏。
その頬に強い風が。その風に漂って来る御簾の中の薫物と、仏に供えた香、更に源氏の香が絡み合う。
また、五感が激しく揺さぶられ、深い溜息。溜息しかない、この式部の世界!!
平成19年以前の報告は[こちらから]
平成20年から平成21年までの報告は[こちらから]
平成22年(2010年)から平成25年(2013年)までの報告は[こちらから]
TOP ページ
index付きTOPページ
|